2022年01月01日
まなびの「場」の人類学的アプローチ
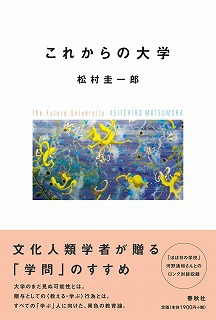
「これからの大学」(松村圭一郎 春秋社)
一ノ関駅近くの北上書房で購入。旅先の新刊書店での本との出会いはうれしい。
昨年末の仙台「火星の庭」での「はみだしの人類学」に続いて、松村圭一郎さんがタイムリーに来ました。
どんな場をつくりたいのか?という問いに対して、昨日の時点では、「ともにつくる場」だったのだけど、それをもう少しマクロで見させてくれたのがこの本でした。
~~~以下本書より引用
世界最古の大学は、いまの大学とはまったく違う場所でした。偏差値のためでも、いい就職をするためでもない。研究者が研究に没頭するための場所でもない。もっと学びたいという学生たちによる、学生たちのための大学だったのです。
テストの問題は、正解と不正解が明確にわかるものに限定されます。言い換えれば、点数化するのに適した「問い」だけが出題されます。複数の解答が可能な設問や議論のわかれている問題は出題のときに避けられるのです。
でも、世の中に正しい答えがひとつだけの問いなど、ほとんどありません。むしろ正解がないような問いを考える能力のほうが大切だったりします。テストの成績は「仮のもの」に過ぎません。まずは、それを認識しておく必要があります。社会の中には、そんな「仮のもの」があふれています。東日本大震災のとき、私たちは原発の安全基準が想定されたリスクの範囲内での仮の基準に過ぎなかったことを思い知らされました。
「答え」のようにみえるのは、あくまでも前提とされる要素の範囲内での暫定的なものにすぎません。誰もが、人生において意思決定を下すときには、つねにこうした限界のなかで判断を迫られるのです。
判断が間違っていたとき、これまで考慮してこなかった要素はなんなのか、どんなことを次の判断のために加えて考えるべきか、いつも問える状態にしていることが必要です。自分はわかっている、正しい判断をしている、これが唯一の答えだ、と居直るような態度が、学問的な態度からはもっとも遠いですし、「正しい判断」からも遠いのです。
学生が世の中に出て、どんな現場に立っても必要となるのは、自分で情報を集め、それらを検証しながら、あらたに知識をつくりだせる力でしょう。その学問にとっての基本的な方法論こそが重要なのです。大学は、何かを知っている人がそれをたんに教える場ではありません。教員も、学生も、まだわかっていない何かをわかりたいと思っている人が集まり、みんなでその問いについて考え、追究していく場なのです。
研究者とは、つねにあらたな問いを発する人間です。もうすでに誰かが取り組んできた問いへのあらたな答えを模索するだけでなく、問いそのものを根本から考え直そうといている人たちです。「専門家」とは何かを「よく知っている人」のことではありません。むしろ、自分が「知っていること」は限定的だと知っている人のことです。「わからない」から「わかる」に向かうプロセスこそが、学問なのです。
~~~
まなぶとは何か?どんな姿勢が必要なのか?プロセスこそが学問。
そして、大学とは「場」であること。それは教員も学生も、ゴールのない「知」に向かうベクトルとして存在を許される「場」であるということを知った。
そして、この本の僕にとってのハイライトは、第5章 文化人類学者の教育論でした。
~~~
イギリスの人類学者、ティム・インゴルドは、「教育」を私たちの「生」を変容させることだと考えています。インゴルドは、客観的でも中立的でもない人間どうしの直接的な出会いのなかに、人類学という変わった学問の独自の可能性があると考えているのだと思います。
そこで避けがたく生じてしまう出会いや対話をとおして、人びととともに考えるプロセスが進んでいくからです。そして人びとも人類学者もともに変容を経験する。そこで起こるお互いの「変容」が教育的でありうるためには、人類学者が人びとを研究対象として突き放して扱うのではなく、彼らから学ぼうとする姿勢がなくてはいけない、と言います。
~~~
なるほど。
これ、ハーベストの山崎さんが言う、「中動態的学び」ってことですかね。トークフォークダンスの「場」で起こること。自分から切り離された「まなび」などありえず、自分が「座」として学びが起こる。
そして、インゴルドの「迷宮」と「迷路」のたとえ話につながっていきます。
~~~
わかりやすい「迷宮」のイメージとして、インゴルドは、登下校の子どもたちの歩みを例にあがています。子どもたちは通学路を俯瞰的にみて目的地に最短ルートを進むのではなく、驚きと発見に満ちた曲がりくねりとしてとらえた歩いているはずだ、と。
一方、都市で働いている大人たちは、ある地点から目的地に向けて、ナビに従って最短ルートを進むように歩きます。そこであらわれる道が「迷路」です。目的地に速やかに到達することしか頭になく、誰かに話しかけられて足が止まったり、ルートとは違う道に入り込んでしまったりすると、いずれもがある種の「失敗」として経験されます。
迷路を進むとき、私たちはゴールにたどり着くという意図をもって進みます。意図が先にあって、行動はその結果に過ぎません。本来は最短ルート以外にもいろんな道の選び方があるわけですが、その複数の選択肢は、いずれも目的地にたどり着くという目的から逸れるというお意味で、迷路の「行き止まり」と考えらえてしまいます。
「迷宮」の道をたどる子どもたちは、たとえば道に不思議な虫がいれば、足を止め、じっとそれを観察するでしょう。そうやってその虫を追いかけているうちに、脇道に入り込むかもしれません。その瞬間、子どもたちにとって目的地である「学校」や「家」にたどり着くことは頭から消えています。迷路を進む大人たちが目的地に向かうこと以外に関心を払わず、行先以外は視界にも入らなくなるのとは対照的です。
インゴルドは、そういう意味で、迷宮が世界に対して開かれているのに対して、迷路は閉じている。そして、迷宮の歩みは、目的地にたどり着こうといった「意図(インテンション)」にもとづくのではなく、たえまない周囲の世界への「注意(アテンション)」にもとづいている、と書いています。
学校教育が意図をもってあらかじめ用意された「知識」を教え込むことだとしたら、どうやって生きていくか、その歩みのなかでそれぞれが自分や周囲のことに目を向け、その観察と対話ととおして、生き抜く方法を見いだしていくことが「知恵」なのです。
~~~
おお~。迷路と迷宮、これですね。
コロナ禍は、世の中を「迷路」から「迷宮」に変えてしまったのではないか。
「迷宮」を進むように生きていく必要があるのではないか。
そして、クライマックス。
人類学の「参与観察」が出てきます。ここがシビれた。
~~~ここから引用
人類学のフィールドワークでは、客観的な第三者として観察するのではなく、人びとの実践のなかに参加して身体を動かして巻き込まれながら考える参与観察を重視しています。インゴルドも、この観察者であると同時に参与者であるという状態が大切なのだと言います。
参与観察は、対象から距離をとって客観化するのではなく、人や物に注意を払い、そのなかにまじって内側から学ぶ方法です。インゴルドはそれを「調和の実践」だと言います。
理論家は頭で考えて、その思考を物質的な世界にあてはめる。職人は、それとは対照的に、周囲の人やモノとの実践や観察をとおした関わり合いのなかから考えを深めていく(そのプロセスが「知恵」に相当します)。インゴルドはそれを「探求の技術」と言います。
この探究の技術でも、迷宮での歩みと同じく、「調和」が重要になってきます。
一般的に、この木がこういう性質だという「知識」だけでなく、じっくり感覚を研ぎすましながら、木材そのものを観察し、手を動かしながら、その材料との関係を調整していくことが大切になります。それが「調和」を目指す探求の技術です。
この実践的なプロセスは、人類学者や職人だけでなく、あらゆるアーティストにとっても同じだとインゴルドは書いています。いずれも、ある種の調和の道を探りつつ、何かを表現として生み出しながら、世界を少しずつ変えていく。
~~~
そうだったのか、って。僕の高校魅力化のアプローチ方法は、「人類学」的な「参与観察」の実践なのだなあと。「高校」や「役所」や「地域」に入り込み、ともに生活しながら、「調和」をはかっていく、というアプローチ。「コンサル」ではなく「参与観察」。それが僕の性に合っていたんだなあと。「学校」とか「学校化社会」に対して、人類学的で参与観察的アプローチをしたかったんだ、と。
そしてそれは、あらゆるアーティストにとっても同じだ、と。ああ、俺のことや、と。(笑)
でもさ、まなびとか、探究とか、もっと言えば、これからの観光とかエンターテイメントって、そっちに行くんじゃないか、って僕は思ってる。
最後に、これからの時代について。
~~~
インゴルドが言うように、目標に向かって脇目もふらず突き進んでいるあいだ、私たちは世界に対して存在しないかのようになります。おもしろいことはすべて道の途中で起きる。インゴルドはそう書いています。
ふらふらと寄り道もせず、文字通り「死んだように」、何も考えず、周囲のことにも他者にも注意を払わない人が、自分自身を変容させ、社会をよりより場所に変容させていくような、創造的な仕事ができるとは思えません。
そもそも社会も、人の人生も揺れ動き、変化し続けています。歩みを進めるうちに、どんな地平線があらわれてくるのか、きちんと注意を払いながら進み、いち早くその変化と調和の道を探る能力こそが求められているはずです。
かつて役にたったかもしれない「知識」を詰め込んで、それを一方的に現実にあてはめるように導くことに、どんな教育的な意味もないのです。
人生を切り開く「知恵」につながる学びは最初から予測可能な状況では生まれにくいものです。もともと考えもしなかった自分になることが、「成長」であるにもかかわらず、いまだにシステムに「乗る」ことを評価しようとする方向性が強調されています。
でも、そのシステムにうまく乗る能力は、システムそのものを刷新したり、あらたなものに創り変えたりする力とはまったく別物です。
システムの中で効率的に上手にふるまえることよりも、予測不可能で予定調和的ではない自然のなかで遊び回る経験のほうが、あらたに物事を創造するときの力になるようです。
重要なのは、既存のシステムに「乗る」だけではなく、そこからあえてはずれて、自分の足で一歩一歩、確かめながら歩くことなのだと思います。自分がどうやって生きていけばいいのか、どんな人間なのか、そんな答えのない問いにきちんと向き合う。それを大学で経験してもらえたら、という思いがあります。
~~~
これこそが「探究的学び」の目指すところなのではないか、と。
!!と思ったのはこの一節
「目標に向かって脇目もふらず突き進んでいるあいだ、私たちは世界に対して存在しないかのようになります」
うわあ「存在」しないのか、と。たしかに、目標に向かって脇目もふらずに進むということは、周りに影響され、自らも影響し、みたいなことを最小限にする、ということだもんなあと。
ここにも「存在」の喪失の原因があったのか、と。
あらためて、僕が取り戻したいのは、「存在」なんだなと。
この前言ってきた山形・朝日町の佐藤恒平さんと構想しているマイプロスピンオフ(自分と大人のための振り返り会)はこんな感じでどうかなあとぼんやり考えてみた。
メインテーマ:「発見」と「変容」(これは目標・目的ではなく、結果だ)
サブテーマ(ふりかえり項目)
「越境性:どのくらい越境したか」
「固有性:あなただからこそのプロジェクトか」
「対話性:他者や自分と対話し、違和感を発見したか」
みたいな感じかな。
その観点からプロジェクトを振り返る会っていうのをやってみたいな、と。
まなびの「場」、それはこれからの観光、これからのエンターテイメントのあり方とも重なってくるのだけど、あらためて。
~~~
一般的に、この木がこういう性質だという「知識」だけでなく、じっくり感覚を研ぎすましながら、木材そのものを観察し、手を動かしながら、その材料との関係を調整していくことが大切になります。それが「調和」を目指す探求の技術です。
この実践的なプロセスは、人類学者や職人だけでなく、あらゆるアーティストにとっても同じだとインゴルドは書いています。いずれも、ある種の調和の道を探りつつ、何かを表現として生み出しながら、世界を少しずつ変えていく。
~~~
「世界に入り込み、調和の道を探りつつ、何かを表現として生み出しながら、世界を少しずつ変えていく」
そんなアプローチを始めていく2022年にしていきたいと思います。




