2022年12月31日
つくるためのギャップ
4年前の就職活動のときにフッと降りてきたキーワード
フラットな関係をつくるコミュニケーションのデザイン。
http://hero.niiblo.jp/e488624.html
(参考:未来に対して「フラット」であること 18.12.28)
つくりたいのは、
・新しいことが生まれる
・ひとりひとりがケアされる
そんな「場」だ。
と4年前に書いている。たぶんそれは今でも変わらない。
いまのキーワードは「つくるためのギャップ」
つくるためにはギャップ(差異や隙間、違和感)が必要で、ギャップを受け止めるためにコミュニケーションが必要になる。4年前に降りてきた「フラットな関係をつくるコミュニケーションのデザイン」は、「新しいものをつくるため」と「ひとりひとりがケアされるため」の方法だった。
いま、高校魅力化という舞台で、文科省用語でいえば「社会に開かれた教育課程」をつくるのはなぜなのだろうか?高校生にはどんな学びが期待されるのか?地域にとってはどんなメリットがあるのか?高校生はなぜ探究しなければいけないのか?そして温泉と高校生の寮とブックカフェを併設する意味は何か?
アマチュアリズムとブリコラージュとコ・クリエーション。
わたしの好きなこと
・新しいものが生まれること。結果というよりは生まれる瞬間や「場」
・代わりに売ってあげること。いいものを違った角度でアピールすること。
・問いを投げかけること。みんなが当たり前だと思っていることを揺さぶること
「ともにつくる」の「ともに」部分には、コミュニケーションという意味なのかもしれない。
「つくる」ためにはフラットなコミュニケーションが必要でありフラットなコミュニケーションには「つくる」というベクトル感が必要である。
その双方が「共創する場」には必要なのだ
ひとりひとりがケアされる創造。
それは差異を、隙間を、違和感を大切にするということだ。
http://hero.niiblo.jp/e492799.html
参考:「学校外の」とは「学校ではない」ではなく「学校まわりの」(22.12.13)
ビジョン(ベクトル)を持つ中心と「コンセプト」を持つ周辺。参加のデザイン。
中心はビジョンと目標達成が至上命令だ。周辺はコンセプトと実験することが大切だ。
実験のために仮説が必要で、そのためにギャップを必要としている。
「みんなちがって、みんないい」みたいな道徳の話ではなくて、そのギャップが必要なのだと。
むしろそのギャップを貸してくれと、そんな風に言える組織や学校や地域をつくりたいなと。
「余白デザイナー」っていうのはきっとそういう意味もあるのだろうな。
「つくるためのギャップ」
このキーワードの解読から2023年は始まりそうです。
フラットな関係をつくるコミュニケーションのデザイン。
http://hero.niiblo.jp/e488624.html
(参考:未来に対して「フラット」であること 18.12.28)
つくりたいのは、
・新しいことが生まれる
・ひとりひとりがケアされる
そんな「場」だ。
と4年前に書いている。たぶんそれは今でも変わらない。
いまのキーワードは「つくるためのギャップ」
つくるためにはギャップ(差異や隙間、違和感)が必要で、ギャップを受け止めるためにコミュニケーションが必要になる。4年前に降りてきた「フラットな関係をつくるコミュニケーションのデザイン」は、「新しいものをつくるため」と「ひとりひとりがケアされるため」の方法だった。
いま、高校魅力化という舞台で、文科省用語でいえば「社会に開かれた教育課程」をつくるのはなぜなのだろうか?高校生にはどんな学びが期待されるのか?地域にとってはどんなメリットがあるのか?高校生はなぜ探究しなければいけないのか?そして温泉と高校生の寮とブックカフェを併設する意味は何か?
アマチュアリズムとブリコラージュとコ・クリエーション。
わたしの好きなこと
・新しいものが生まれること。結果というよりは生まれる瞬間や「場」
・代わりに売ってあげること。いいものを違った角度でアピールすること。
・問いを投げかけること。みんなが当たり前だと思っていることを揺さぶること
「ともにつくる」の「ともに」部分には、コミュニケーションという意味なのかもしれない。
「つくる」ためにはフラットなコミュニケーションが必要でありフラットなコミュニケーションには「つくる」というベクトル感が必要である。
その双方が「共創する場」には必要なのだ
ひとりひとりがケアされる創造。
それは差異を、隙間を、違和感を大切にするということだ。
http://hero.niiblo.jp/e492799.html
参考:「学校外の」とは「学校ではない」ではなく「学校まわりの」(22.12.13)
ビジョン(ベクトル)を持つ中心と「コンセプト」を持つ周辺。参加のデザイン。
中心はビジョンと目標達成が至上命令だ。周辺はコンセプトと実験することが大切だ。
実験のために仮説が必要で、そのためにギャップを必要としている。
「みんなちがって、みんないい」みたいな道徳の話ではなくて、そのギャップが必要なのだと。
むしろそのギャップを貸してくれと、そんな風に言える組織や学校や地域をつくりたいなと。
「余白デザイナー」っていうのはきっとそういう意味もあるのだろうな。
「つくるためのギャップ」
このキーワードの解読から2023年は始まりそうです。
2022年12月14日
「偶然」は内部と外部のあいだに
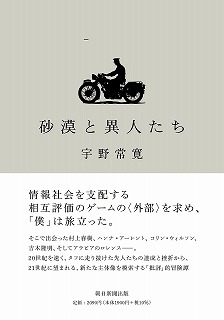
「砂漠と異人たち」(宇野常寛 朝日新聞出版)
読み始めました。
宇野さん、さすが、スルドいなあって。
~~~
いつの間にか人々は問題を解決するためではなく不安を解消するために、考えるためではなく考えないために情報を検索し、受信し、そして発信するようになっていった。
プレイヤーの目的は問題の解決や再設定ではなく問題についての応答による評価の獲得だ。
この十年のあいだSNSによって動員されたそこは本当に外部だったのか。偶然目に映り、耳に入るものに溢れた出会いの場だったのだろうか。
~~~
それは本当に「偶然」だったのか。
いい問いだなあと。
facebookはネットとリアルをイコールにしてしまった。
そこでの情報は必然的にフィルタリング後になる。
「twitterで見ました。」と言ってイベントに来る人により「偶然」はもたらされるのだろうか。
ツルハシブックスの最大の価値であった「偶然」は何によって引き起こされたのだろうか?
その偶然は風舟では起こらないのだろうか。
そのカギを説くヒントが、同時に読み進めていた(日本人)(かっこにっぽんじん 橘玲 幻冬舎)にあった。
人は内側から「愛情空間」「政治空間」「貨幣空間」を生きていて、関係人数としては順に多くなっていくが、関わりは薄くなっていく。
政治空間は「統治の倫理」でできていて貨幣空間は「市場の倫理」が覆っている。
この「統治の倫理」と「市場の倫理」のダブルバインドが生きづらさのひとつでもあるし、
このような内部から外部へという考え方こそが、ヒントになっているように思う。
昨日のブログ
http://hero.niiblo.jp/e492799.html
それをまとめたツイート
「教育を変える」のではなくて、「教育の余白を増やす」ってことなのかもね。学校だけじゃなくて地域も。学校と地域のあいだの地域と協働した授業とかね。その余白は予測不可能であり、目的・目標に向かっておらず、だからこそ地域の大人もフラットに学べるんだ。
「偶然」とは、予測不可能なことであり、目的・目標に向かわない「余白」に発生する。
それなら、風舟でもできるんじゃないか。
「風」を感じ、旅立つ
「自由」へ向け委ねる
もうひとつ小川さんにもらったキーワードは「あたらしいつよさ」。ひとりで強くなるのではなく、ひとりの単位としてはむしろ弱くなっているかもしれないけど、広く見れば(精神的・全体的に)つよくなっているという状態。
アマチュアリズムとブリコラージュとコクリエーション
それを関係性的に言えば
プロとアマチュアの関係性
マイナスもプラスに変える関係性
部分的に差し出して創造をつくる関係性
なんだろうけど。
場にひとまず出して、機会提供する部分とそこに来る人々(外部)とここはしっかりと押さえないととちゃんとする部分と店員(内部)
そのあいだにある「余白」
それは、店員サムライや一箱本棚オーナー外部から内部へ人を変化させる仕組みなのかもしれないし、空間やイベントを一緒に作り上げていく仲間なのかもしれない。
その「余白」を楽しみ、時にキャッチし、参加し、委ねる人になること。
その行き来が多くなることで「偶然」は生まれるし、
それを行き来することで人は委ねられる人になり、
「あたらしいつよさ」を身に付け、新たな旅に出ていくことができるようになる。
そんな空間づくりをするための本棚が必要なんだなあと。
「あたらしいつよさ」を身に付ける旅に誘うやさしい本棚をつくること
・疑問・好奇心を持つ
・俯瞰してみる(世界、歴史)
・美学を持つ(アート)
・「自分」「人間」を知る(哲学・心理)
・師匠を持つ
・自分を表現する(西村さんの本とか)
・社会・共同体を知る
・働き方を知る
・関係性をデザインする
・アイデアを出す
・マーケティングする
・文章を書く
・プレゼンする
・食べる
・農業する
・散歩する
まだ途中ですけど、ひとまず記録。
2022年12月13日
「学校外の」とは「学校ではない」ではなく「学校まわりの」
「教育実習に行ったら、学校じゃないな、って直感した」
大学生や20代のそんな話をよく聞くのだけど、実は僕もそうだ。
32歳になって行った中学校の教育実習。
女子生徒のガッカリ感がハンパなくてキツかったけど。
僕のポジションは、学校じゃないな、って思った。
結局30歳で編入した大学は、単位を満たせずに中退となった。
10年ほど前まで「教育に携わる仕事」というのは、基本的に学校の先生のことだった。
ところが「高校魅力化」の流れがそれを多様化することとなった。
「地域おこし協力隊」としての
・学校と地域をつなぐコーディネーター
・学習指導を行う公営塾の講師
・生活支援をする寮のハウスマスター
そのように学校の先生以外の「教育に関わる」仕事の選択肢が増え、それを志向する若者も増えている。
「学校外で」教育に関わる仕事。
僕自身は、
20代の時に自宅で学習塾+小さな本屋+もぐりのゲストハウスをやりながら
農作業サークルとかやぶきの家での釜炊きの朝ごはんを主宰した。
30代で大学生の地域企業でのインターンシップをプログラムし、
プラットフォームとしての本屋さんを運営した。
40代は大学に潜入して地域とのコーディネートを行い、
後半は高校魅力化プロジェクトを舞台としている。
大学生のキャリア支援やアイデンティティ問題に関心があり、たくさんの本を読んだ。
今でも感じるのが「教育」という言葉そのものへの違和感だ。目的・目標を決め、評価基準を決め、そこに向かっていくという手法を教育と呼ぶとしたら、予測不可能な時代を迎えた今、教育はどうなっていくのか。
今回。
ハウスマスターの募集の取材を受けて、気づいたこと。
「教育」という言葉そのものへのアレルギー。
それは僕が持つバイアス(偏見)だった。
「学校外の教育の場」と言ったときに、「学校ではない」(≒アンチ学校)というニュアンスを含んでしまっていたこと。
そうじゃないんだ。
「学校外の」っていうのは、文字通り「内側」と「外側」の話で、文部科学省が「地域学校協働本部」というように、役割(≒ポジショニング)の違いであるだけだ。
こう書いてみれば当たり前のことなのだけど、人間のバイアスって恐ろしいなと思った。
「手段としての学び」と「機会としての学び」
その両方が必要なのであって、特に後者の「機会としての学び」は、地域と協働してつくる必要があるし、それによって地域の大人自身の学びの場にもなる。
「学校外の」というより、地域における学校と地域の関わりを広くデザインしていくこと。
小学校、中学校、高校があり。
公営塾があり、寮があり、温泉や本屋がある。
地域の商店があり、事業者さんがいる。
学校内と学校外、そして授業内での協働。
そんなのをひとつひとつ整理し、自分のポジションを知ること。
持ち場を、ミッションをていねいに果たしていくこと。
この冬にやっていくのはきっとそういうこと。
大学生や20代のそんな話をよく聞くのだけど、実は僕もそうだ。
32歳になって行った中学校の教育実習。
女子生徒のガッカリ感がハンパなくてキツかったけど。
僕のポジションは、学校じゃないな、って思った。
結局30歳で編入した大学は、単位を満たせずに中退となった。
10年ほど前まで「教育に携わる仕事」というのは、基本的に学校の先生のことだった。
ところが「高校魅力化」の流れがそれを多様化することとなった。
「地域おこし協力隊」としての
・学校と地域をつなぐコーディネーター
・学習指導を行う公営塾の講師
・生活支援をする寮のハウスマスター
そのように学校の先生以外の「教育に関わる」仕事の選択肢が増え、それを志向する若者も増えている。
「学校外で」教育に関わる仕事。
僕自身は、
20代の時に自宅で学習塾+小さな本屋+もぐりのゲストハウスをやりながら
農作業サークルとかやぶきの家での釜炊きの朝ごはんを主宰した。
30代で大学生の地域企業でのインターンシップをプログラムし、
プラットフォームとしての本屋さんを運営した。
40代は大学に潜入して地域とのコーディネートを行い、
後半は高校魅力化プロジェクトを舞台としている。
大学生のキャリア支援やアイデンティティ問題に関心があり、たくさんの本を読んだ。
今でも感じるのが「教育」という言葉そのものへの違和感だ。目的・目標を決め、評価基準を決め、そこに向かっていくという手法を教育と呼ぶとしたら、予測不可能な時代を迎えた今、教育はどうなっていくのか。
今回。
ハウスマスターの募集の取材を受けて、気づいたこと。
「教育」という言葉そのものへのアレルギー。
それは僕が持つバイアス(偏見)だった。
「学校外の教育の場」と言ったときに、「学校ではない」(≒アンチ学校)というニュアンスを含んでしまっていたこと。
そうじゃないんだ。
「学校外の」っていうのは、文字通り「内側」と「外側」の話で、文部科学省が「地域学校協働本部」というように、役割(≒ポジショニング)の違いであるだけだ。
こう書いてみれば当たり前のことなのだけど、人間のバイアスって恐ろしいなと思った。
「手段としての学び」と「機会としての学び」
その両方が必要なのであって、特に後者の「機会としての学び」は、地域と協働してつくる必要があるし、それによって地域の大人自身の学びの場にもなる。
「学校外の」というより、地域における学校と地域の関わりを広くデザインしていくこと。
小学校、中学校、高校があり。
公営塾があり、寮があり、温泉や本屋がある。
地域の商店があり、事業者さんがいる。
学校内と学校外、そして授業内での協働。
そんなのをひとつひとつ整理し、自分のポジションを知ること。
持ち場を、ミッションをていねいに果たしていくこと。
この冬にやっていくのはきっとそういうこと。




