2015年06月30日
「お手伝い」で仕事サーファーになる

「僕たちは就職しなくてもいいのかもしれない」(岡田斗司夫 PHP新書)

「いいひと戦略」(岡田斗司夫 マガジンハウス)
おもしろいですね。
岡田さん。
いいひと戦略。
「消費者の味方」は「国民の敵」かもしれない。
とAmazonを例に出して言っています。
本を注文したら即日か翌日に
自宅に届くサービス。
すごく便利です。
このサービスが隆盛を極めることによって、
町の本屋さんはすごい勢いで無くなっていっています。
消費者はそんなに困っていません。
本は買いやすくなり、選択肢が増えるということで、
便利になりました。
何万冊という在庫から自由に選べます。
1999年に22,000店あった本屋さんは
2014年に14,000店。
実に15年で8,000もの店が消えました。
年間500ということは毎日1店舗以上の本屋が
なくなっているということです。
そのぶん本屋さんで働く人たちは
失業しているのです。
このように「便利」=消費者の味方は
ときとして、人の職を奪うことがあります。
ダイエーが主導した流通革命、
いわゆる「中抜き」が多くの失業を生んだのと同じです。
そしてこれから、
「ワークデザイン」の長沼さんの言うように、
「成長する会社は雇用を生まない」が現実化してきます。
つまり、成長している企業は、
そもそも人を介さないシステムを作り上げているので
競争力があるのです。
そこにはわずかの人手しか必要ではないのです。
では、どうしたらいいのか?
岡田さんは
「単職から多職へ」と提唱します。
これは、
「ナリワイをつくる」(伊藤洋志)や
「月3万円ビジネス」(藤村靖之)でも提唱されていましたが
岡田さんの面白いところは、それをどのように作るか?
です。
「お手伝いのサーフィン」をしろ。
しかも50個。と言います。
「仕事サーファーになれ」、と岡田さんは言います。
いいなあ、これ。
大学生にこそオススメしたい戦略ですね。
全員が同じ日本語を使い、教育水準がとても高く、国家のモラルが高い
(本文より)
というすごい資産を持った国民、それが日本人です。
こんなにも一緒に仕事をしやすい民族は世界になかなかない。
したがって、次から次へとお手伝いのニーズが生まれてくると言います。
まずは「お手伝い」できることを見つけ、手伝ってみる、
そこからすべては始まります。
それをやっていくと、さまざまな能力が高まっていきます。
岡田さんは人間の値打ちは3つのCで決まる、と言います。
「コンテンツ(能力)」「コミュニティ(仲間関係)」「キャラクター(人柄)」
だそうです。
なるほどなあ。
まずはコンテンツ。
とりあえずさまざま経験して技を磨く。
次にコミュニティ。
これは仕事を頼んでくれる人たちのこと。
このときに、
「お手伝い」をどのような形でやっているか?
がすごく問われます。
なんてこともない「お手伝い」でも
ていねいにやったりだとか、ちょっと才能が見えたりだとか、
そういったことで、「キャラクター=人柄」が確立されていきます。
キャラクターが確立されたら、
仕事はどんどん回ってきます。
スキルのない仕事でも、「そんなら俺が教えてやる」と
言ってくれます。
そうなると3つのCがどんどんまわり出します。
能力も仲間関係が増え、キャラクターの信用が増す。
その先に、仕事があるのではないか?
と僕は思います。
ここでのポイントは
「たくさんのお手伝いをすること」だと岡田さんは言います。
仕事ではありません。お手伝いです。
相手が求めていることを理解して、
喜ばせるためにお手伝いをしたこと。
言い換えるとそれは「いい人になること」
これが「いい人戦略」なんですね。
なるほどな~。
面白いなあと。
人を幸せにするのはスキル、つまり「コンテンツ(能力)」だけではないのだなあと。
人に負けないように、と勉強してきたのだけど、
「コミュニティ」と「キャラクター」も大切だよなあと。
むしろ、会社に頼れない時代に継続して仕事をしていくためには、
「コンテンツ(能力)「コミュニティ(仲間関係)」と「キャラクター(人柄)」
という3つのCをぐるぐる回していくことなのだなあと実感する。
大学生のいまこそ。
「いいひと戦略」を選択し、「無数のお手伝い」を経験していくこと。
次々に来るお手伝いの波に乗り、「仕事サーファー」になっていくこと。
そうして「コンテンツ」だけではなく「コミュニティ」と「キャラクター」を磨いていくこと。
この繰り返しが
人生を拓いていくのではないか?
と思いました。
仕事サーファー、はじめませんか?
2015年06月29日
ハックツ改装工事中
27日、28日と
練馬区上石神井のブックスタマ上石神井店で
ハックツの改装工事を行いました。

ブックスタマ加藤社長も駆けつけました。

サンクチュアリ金子さんはトラックも運転!似合ってる!

初日は床張り。

二日目は壁張りしました。

初日の集合写真

二日目の集合写真
いい笑顔ですね。
次回は7月4日5日です。
スポットでの参加も受け付けています。
本を寄贈したい!
など、ハックツへの参加はこちらから。
http://www.tsuruhashibooks.com/hakkutsu.html
練馬区上石神井のブックスタマ上石神井店で
ハックツの改装工事を行いました。

ブックスタマ加藤社長も駆けつけました。

サンクチュアリ金子さんはトラックも運転!似合ってる!

初日は床張り。

二日目は壁張りしました。

初日の集合写真

二日目の集合写真
いい笑顔ですね。
次回は7月4日5日です。
スポットでの参加も受け付けています。
本を寄贈したい!
など、ハックツへの参加はこちらから。
http://www.tsuruhashibooks.com/hakkutsu.html
2015年06月26日
価値観の多様化とは、明確な価値が失われたのと同義語である

「教育の力」(苫野一徳 講談社現代新書)
伊那市のオルタナティブスクール
「伊那谷 まあるい学校」
の濱ちゃんに強くおススメされた1冊。
読むほどにうなります。
ただ熱いだけじゃなくて
冷静な社会分析、教育分析、
そして提案まで新書1冊に詰め込みました。
まずはそもそも教育とは何のためにあるか?
の原則を問います。
~~~ここから引用
公教育はすべての子ども(人)が「自由」な
存在たりうるよう、そのために必要な力
(わたしはこれを教養=力能と呼んでいます)を育むことで、
各人の自由を実質的に保障するものなのです。
そのことで同時に
社会における「自由の相互承認」の原理を
より十全に実質化するためにあるのです。
~~~ここまで引用
そうですね。
その通りだなあと思います。
著者はこの原則を考えない
教育論議は不毛であると言います。
しかし、わが国では多くの教育論議が
「ゆとり教育、是か非か」というような
二者択一になってしまっています。
著者はこの原則を踏まえたうえで、
学力とは何かを定義し、
そしてそのためには
学びの「個別化」「協同化」「プロジェクト化」
が必要だと言います。
なるほど、これはまさにいま
大学教育が直面している課題ですね。
まだじっくり読みたいと思います。
この本で注目したのは、
第六章 学校空間の再構築です。
これ、昨日のブログの題材である
「桐島、部活やめるってよ」の学校観の
見事な解説になっています。
ビックリしました、このシンクロニシティ。
キーワードはここです。~~~ここから一部引用
「価値観の多様化に伴って、
かえって露わになった同質性への過剰要請」
かつて、学業成績によって、
明確に序列化されていた個々人が
その序列から解放されたことで、
かえって個々人を個々人たらしめる指標が失われ、
集団の中における位置づけが、きわめてあいまいな
「空気」に支配されることになったのです。
分かりやすい指標をが失われてしまったからこそ、
ノリがよく空気を読める「能力」がこれまで以上に求められるようになり、
そしてその「能力」にしたがって、新たな序列が顕在化するようになったのです。
うわっ!!と思った。
これ、「桐島、部活やめるってよ」に描かれている世界そのものじゃん!って。
近代以前は個々人の価値観は家や共同体に縛られ、
今と比べれば圧倒的に自由ではありませんでした。
お上に忠誠を尽くし、親の決めた相手と結婚し、代々同じ職業を続けてきました。
近代以降、わたしたちは「自由」を手に入れました。
他者をひどく傷つけるのではない限り、
どのような価値観をもっても自由であるという「自由」を
手に入れました。
現代においては、
企業が短命化し、終身雇用が機能せず、
明確な「成功コース」みたいなものが崩壊しました。
だから、「多様な価値観」に対して、
誰も異論を唱える人はいないでしょう。
しかし、この価値観の多様化の進展によって、
私たちは「明確な価値」を失い、
何を確固たる目標として生きていけばいいのか?
をわかりづらくなり、
価値の拠り所を失ってしまった集団の中で、
空気を読み合う人間を多かれ少なかれ送らなければならなくなっているのです。
これが中学生高校生の息苦しさの「社会構造上」の要因です。
そして、もうひとつ、「学校構造上」の問題は逃げ場のない教室空間です。
かつて、
学校は「自由の相互承認」の感度を高めるため、
子どもたちそれぞれの土着的閉鎖的習俗から離れるために
学校に集められました。
しかし今は
学校がむしろひとつの習俗になってしまいました。
「価値観の多様化」が進展している一方で
学校空間はその多様性を許さない「空気」を持った
あらたな習俗になってしまっていると著者は指摘します。
しかも子どもたちは、
「地域」や「家庭」が機能していない中で
「ここにしか居場所がない」場所だと考えます。
これを解決するには、人間関係を流動的にすることです。
その方法のひとつが
学びの「個別化」「協同化」「プロジェクト化」です。
総合学習はもしかしたら、それに対する一つの方法だったのでしょう。
~~~ここまで一部引用
「桐島、部活やめるってよ」の息苦しさを
ここまで表現されているとは、本当にビックリしました。
そして、苫野さんは次の章で
教員にもっとも必要な資質として
「信頼と承認」「ケア」だと挙げています。
子どもを信頼し、承認してあげること。
裏切られたとしても、信頼し、承認し続けること。
そして子どもが自分の自己肯定感を高め続けられるように
ケアしつづけること。
「信頼と承認」「ケア」に包まれた空間づくり、
それが教員にとってもっとも大切であり、
そのことが「自由の相互承認」を得られる空間を
作っていくということにつながるというのです。
学校がそんな場所であったらいいと思いました。
そして、同時に、学校だけがその責任を
負うべきではないとも思いました。
私たちはひとりの地域住民として、
子どもたちに、「心の安全基地」(本書より)
と呼べるような場を提供していかなくてはいけないのではないか?
「信頼と承認」「ケア」に包まれた居場所から
始まっていく小さなチャレンジが応援するような、
そんな地域空間を創っていきたいと心から思いました。
素敵な時間をありがとうございました。
2015年06月25日
それぞれの人生、それぞれの青春

「桐嶋、部活やめるってよ」(朝井リョウ 集英社文庫)
今さらながら読みました。
誰かが書評で、
今の高校生のリアルがもっともよく表現されている
と言っていたので。
いや、ホント、胸が苦しい。
こんなにも生きづらい世の中を
みんな生きているのだなあ。
~~~ここから引用
見たこともない表情だった。
僕はあのふたりが、教室の片隅で
肩身狭そうに雑誌を読んでいる姿しか、
見たことがなかった。
できるだけ目立たないように、
誰の目にも留まらないように、
雑誌を広げてあいつらにしかわからないような
話をしている姿しか、見たことがなかった。
~~~ここまで引用
あ、これ。
僕にも経験がある、って思った。
解説にはここの部分の前の部分に
クライマックスを置いているので、
気になる方はぜひ読んでほしい。
僕には見覚えがある。
2007年5月。
32歳だった僕は、中学校に3週間の教育実習に行った。
玉川大学教育学部の教員免許課程に籍があった。
なんと、3年生のクラスだった。
女子からの「誰このオッサン」的な視線が痛い。
そこで僕が見たもの。
それは、音楽部と美術部。
教室にいる彼女たちと部活動している彼女たちの
表情がまったく違うことに気がついた。
教室での彼女たちは仮の姿なのだろうか。
それを決定づける出来事があった。
6月、新潟県の各地域では
中学校の総合体育大会が行われる。
その時に、学校から運動部はいなくなる。
「西田先生はどうされますか?」
僕は一応、卓球部の顧問という位置づけだったのだけど、
学校に残ることにした。
学校には、音楽部や美術部の子達しかいなくなる。
そこで僕は衝撃の光景を目にすることになる。
教室での彼女たちが、
部活動をしているときと同じ、
生き生きと輝いた顔で教室内を躍動しているのだ。
ああ。
普段、教室にいるときだけが、彼女たちの顔ではないのだ。
当たり前。
ごく当たり前の真実を、僕は見せつけられた。
でも、あの一瞬で僕は教育実習をした意義を見つけた。
誰もが、いや、特に若者は、
教室内にいるときだけが若者の姿ではない。
多様な顔を持っているし、
また多様な顔を持てることで、
自分が自分であり続けることができるのだろう。
ツルハシブックスはそんな多様な顔を見せられる、
そんな空間のひとつになりたいなあ、
と強く思った。
2015年06月24日
ビール屋がそば屋をやる理由
木内酒造。
新潟にいたときから
木内梅酒の醸造元として知っていた。
ビールで仕込んだ梅酒が日本一になった。
http://www.kodawari.cc/
昨日の「茨城学」で
登壇された木内さんの話に
心を打ち抜かれた。
木内さんが家業である木内酒造に
もどってきた20年前の1995年。
世の中は地ビールブームに沸いていた。
「真似しない」
木内さんを貫く哲学がある。
学ぶけど、真似しない。否定もしない。
第3の道を歩んでいくということ。
こうして木内酒造の地ビールづくりが始まる。
茨城県はかつて、
日本の麦の20%以上を栽培していた。
それをビール麦栽培へと移行していく。
戦略は「世界に売る」ということ。
コイツで世界に出てやろうと考えた木内酒造のビールは、
ラベルにはフクロウ、そして英語表記がされている。
現在、アメリカではすでにサントリービールの輸出額を超えている。
アメリカで売れて、日本で話題になる。
よくある話だ。
つまり、木内酒造は、茨城ブランドではなく、
日本ブランドで勝負してきた。
そんな木内酒造のものづくりキーワードは、
・全国・世界に通用するローカル
・自主自立・創意工夫があるもの
・きちんとした人づくりをする。
これは1980年に大分県で始まった一村一品運動をモデルにしている。
ビールづくりを始める前、
3人だった社員が10人となり、
いまや120人を抱える企業となった。
地域貢献活動も活発に行っている。
山奥での古民家を改装したレストランなどを経営している。
東日本大震災時には、
1週間、水をビール瓶に詰めてひたすらに配った。
木内さんのお話を聞いていて思ったのは、
「本業を通じた社会貢献」という言葉だ。
企業CSRが叫ばれているが、
地域の中小企業にとって、
本業を継続することこそが社会貢献であるということだ。
それは、学生のひとりが最後に質問していた
地域貢献か、利益か?
という二者択一ではない。
両方があるから、地域に愛され、継続していくのだ。
地域に愛されることは、信用そのものだ。
最後には愛される会社が残る。
銀行も支援する。
最後にタイトルになったそば屋について。
木内酒造は、な嘉屋という蕎麦屋を経営している。
http://nakaya.cc/

それはなぜか?
茨城県では、日本の麦の20%を生産していた。
そのときに、裏作で蕎麦を育てていたという。
いわゆる二毛作だ。
だから、木内さんがビール麦を作るように地元農家に
お願いしたら、農家はそのあいだに蕎麦を育てる。
そうしたらその蕎麦も買い取って、お店で出そう。
そんなわけでビール屋がそば屋をやっているのだ。
蕎麦⇔日本酒ではなく、蕎麦⇔ビール麦なのだ。
農学部出身の僕としては、非常にシビれる話でした。
かっこいい経営者ってやっぱり素敵だなあ。
水戸に来て、地ビール飲んで、日本酒も飲んで、そばで〆る。
そんな飲み会、やりませんか?
新潟にいたときから
木内梅酒の醸造元として知っていた。
ビールで仕込んだ梅酒が日本一になった。
http://www.kodawari.cc/
昨日の「茨城学」で
登壇された木内さんの話に
心を打ち抜かれた。
木内さんが家業である木内酒造に
もどってきた20年前の1995年。
世の中は地ビールブームに沸いていた。
「真似しない」
木内さんを貫く哲学がある。
学ぶけど、真似しない。否定もしない。
第3の道を歩んでいくということ。
こうして木内酒造の地ビールづくりが始まる。
茨城県はかつて、
日本の麦の20%以上を栽培していた。
それをビール麦栽培へと移行していく。
戦略は「世界に売る」ということ。
コイツで世界に出てやろうと考えた木内酒造のビールは、
ラベルにはフクロウ、そして英語表記がされている。
現在、アメリカではすでにサントリービールの輸出額を超えている。
アメリカで売れて、日本で話題になる。
よくある話だ。
つまり、木内酒造は、茨城ブランドではなく、
日本ブランドで勝負してきた。
そんな木内酒造のものづくりキーワードは、
・全国・世界に通用するローカル
・自主自立・創意工夫があるもの
・きちんとした人づくりをする。
これは1980年に大分県で始まった一村一品運動をモデルにしている。
ビールづくりを始める前、
3人だった社員が10人となり、
いまや120人を抱える企業となった。
地域貢献活動も活発に行っている。
山奥での古民家を改装したレストランなどを経営している。
東日本大震災時には、
1週間、水をビール瓶に詰めてひたすらに配った。
木内さんのお話を聞いていて思ったのは、
「本業を通じた社会貢献」という言葉だ。
企業CSRが叫ばれているが、
地域の中小企業にとって、
本業を継続することこそが社会貢献であるということだ。
それは、学生のひとりが最後に質問していた
地域貢献か、利益か?
という二者択一ではない。
両方があるから、地域に愛され、継続していくのだ。
地域に愛されることは、信用そのものだ。
最後には愛される会社が残る。
銀行も支援する。
最後にタイトルになったそば屋について。
木内酒造は、な嘉屋という蕎麦屋を経営している。
http://nakaya.cc/

それはなぜか?
茨城県では、日本の麦の20%を生産していた。
そのときに、裏作で蕎麦を育てていたという。
いわゆる二毛作だ。
だから、木内さんがビール麦を作るように地元農家に
お願いしたら、農家はそのあいだに蕎麦を育てる。
そうしたらその蕎麦も買い取って、お店で出そう。
そんなわけでビール屋がそば屋をやっているのだ。
蕎麦⇔日本酒ではなく、蕎麦⇔ビール麦なのだ。
農学部出身の僕としては、非常にシビれる話でした。
かっこいい経営者ってやっぱり素敵だなあ。
水戸に来て、地ビール飲んで、日本酒も飲んで、そばで〆る。
そんな飲み会、やりませんか?
2015年06月23日
「富国強兵」「殖産興業」という一神教
江戸時代、士農工商それぞれの身分で
教育制度があった。
武士は儒教、躾。
農民は農事暦、内発的動機付け
職人は「覚える」「盗む」
商人は家訓に基づいた教育
それぞれが違うことを教えた。
特に職人の「覚える」というのは、
非常に個人的体験的学びに依存していた。
つまり、均一化された人材が生まれてこなかった。
明治時代になり、
国の方針が「富国強兵」「殖産興業」
となった。
そこでひとつの教育制度が生まれた。
それが学校(近代学校)である。
学校の思想は「平準化」である。
「土佐人」や「長州人」ではなく、
「日本人」を作らなければならなかった。
産業労働者であり、かつ戦争を担う人を
育てる必要があった。
そこで日本人の「能力」の基準を一元化し、
かつ、日本人としての「意識」を統一する必要があった。
学校と軍隊は双子の兄弟であると言われることがある。
学校教育の本当の狙いは、
学力をつけることではなく、
挨拶ができるようになるであったり、
先生の言うことをきちんときくことであったり、
一定時間の授業をおとなしく聞いていることだったりするのだという。
つまり、
軍隊に入った時に、組織を乱さずに行動できる人を
育てたかったのだという。
おそらく。
この試みは成功した。
日清戦争、日露戦争、第1次世界大戦という結果。
しかしながら、この150年。
常に統一された「学力」という考え方は
それ以外の力も大事だ、という考え方と
せめぎ合ってきた。
大正デモクラシー。
民主主義教育のはしりがここで生まれた。
しかし。
ふたたび1931年。
日本は15年戦争に突入していく。
そして1945年、終戦。
ふたたび日本が混乱した中で、
アメリカの民主主義社会をモデルを
つくろうと、各地域で取組が始まる。
これがコアカリキュラム運動に代表されるものだ。
しかし、1950年の朝鮮戦争を境に
高度経済成長にひたすらに突き進むなかで
ふたたび「学力」重視の方向に向かう。
学校は荒れた。
それを管理教育で押さえつけようとして
さらに学校は荒れた。
「スクール・ウォーズ」の時代だ。
その後2000年。
当時文部省の寺脇研さんが提唱した「生きる力」
総合学習が始まる。
しかしながら2007年。
ふたたび「学力」重視の教育へと転換される。
こうして、「学力」とそれ以外の力はせめぎあいを続けてきた。
そして、もちろん、スクールウォーズのモデル、山口先生をはじめ、
何人もの優れた教師たちが輩出され、子どもたちを救ってきた。
しかしながら、構造的に、システム的に、
「学校」というのは「学力」をつけるところであり、
その「学力」の根本は
軍隊、あるいは企業社会で戦力になる、
悪い言い方をすれば文句を言わずに働けるようになること、である。
それでもまだ、
30年前まで、日本には「地域」が存在した。
「家庭」も存在した。
お祭りがあり、家族団らんの機会があった。
それを失ってまでも
日本は産業(企業)優先社会へとシフトしていった。
しかし。
突如、というか必然というか、
時代や社会のほうが変わってしまった。
学校で真面目に学んでいても就職できなくなった。
「言われたことをやっているだけの人材は要らない」
「自分で考えて高付加価値を生める人材がほしい」
と言い出した。
「富国強兵」「殖産興業」という一神教を
システム化した「学校」は、
就職できる人を生むシステムではなくなってしまった。
宙に浮いた若者たち
(いや、これは我々世代にも当てはまる)
が頼るべき地域や家庭はもはやない。
いまの若者たち(や我々世代)の漠然とした不安は、
一神教を失ったことに起因しているのではないか。
信じていた宗教と社会システムが
自分にとって機能しなくなったという不安。
これはすごく大きいのだろう。
しかし、それでも、私たちは生きていかなければならない。
希望を生んでいかなくてはならない。
だから、自ら希望を生み出す仕組みを構築する必要がある。
「本」、そして「人」、さらに「地域」
小さな入り口から始まる希望を生み出す仕組みを
創っていきたいと思う。
教育制度があった。
武士は儒教、躾。
農民は農事暦、内発的動機付け
職人は「覚える」「盗む」
商人は家訓に基づいた教育
それぞれが違うことを教えた。
特に職人の「覚える」というのは、
非常に個人的体験的学びに依存していた。
つまり、均一化された人材が生まれてこなかった。
明治時代になり、
国の方針が「富国強兵」「殖産興業」
となった。
そこでひとつの教育制度が生まれた。
それが学校(近代学校)である。
学校の思想は「平準化」である。
「土佐人」や「長州人」ではなく、
「日本人」を作らなければならなかった。
産業労働者であり、かつ戦争を担う人を
育てる必要があった。
そこで日本人の「能力」の基準を一元化し、
かつ、日本人としての「意識」を統一する必要があった。
学校と軍隊は双子の兄弟であると言われることがある。
学校教育の本当の狙いは、
学力をつけることではなく、
挨拶ができるようになるであったり、
先生の言うことをきちんときくことであったり、
一定時間の授業をおとなしく聞いていることだったりするのだという。
つまり、
軍隊に入った時に、組織を乱さずに行動できる人を
育てたかったのだという。
おそらく。
この試みは成功した。
日清戦争、日露戦争、第1次世界大戦という結果。
しかしながら、この150年。
常に統一された「学力」という考え方は
それ以外の力も大事だ、という考え方と
せめぎ合ってきた。
大正デモクラシー。
民主主義教育のはしりがここで生まれた。
しかし。
ふたたび1931年。
日本は15年戦争に突入していく。
そして1945年、終戦。
ふたたび日本が混乱した中で、
アメリカの民主主義社会をモデルを
つくろうと、各地域で取組が始まる。
これがコアカリキュラム運動に代表されるものだ。
しかし、1950年の朝鮮戦争を境に
高度経済成長にひたすらに突き進むなかで
ふたたび「学力」重視の方向に向かう。
学校は荒れた。
それを管理教育で押さえつけようとして
さらに学校は荒れた。
「スクール・ウォーズ」の時代だ。
その後2000年。
当時文部省の寺脇研さんが提唱した「生きる力」
総合学習が始まる。
しかしながら2007年。
ふたたび「学力」重視の教育へと転換される。
こうして、「学力」とそれ以外の力はせめぎあいを続けてきた。
そして、もちろん、スクールウォーズのモデル、山口先生をはじめ、
何人もの優れた教師たちが輩出され、子どもたちを救ってきた。
しかしながら、構造的に、システム的に、
「学校」というのは「学力」をつけるところであり、
その「学力」の根本は
軍隊、あるいは企業社会で戦力になる、
悪い言い方をすれば文句を言わずに働けるようになること、である。
それでもまだ、
30年前まで、日本には「地域」が存在した。
「家庭」も存在した。
お祭りがあり、家族団らんの機会があった。
それを失ってまでも
日本は産業(企業)優先社会へとシフトしていった。
しかし。
突如、というか必然というか、
時代や社会のほうが変わってしまった。
学校で真面目に学んでいても就職できなくなった。
「言われたことをやっているだけの人材は要らない」
「自分で考えて高付加価値を生める人材がほしい」
と言い出した。
「富国強兵」「殖産興業」という一神教を
システム化した「学校」は、
就職できる人を生むシステムではなくなってしまった。
宙に浮いた若者たち
(いや、これは我々世代にも当てはまる)
が頼るべき地域や家庭はもはやない。
いまの若者たち(や我々世代)の漠然とした不安は、
一神教を失ったことに起因しているのではないか。
信じていた宗教と社会システムが
自分にとって機能しなくなったという不安。
これはすごく大きいのだろう。
しかし、それでも、私たちは生きていかなければならない。
希望を生んでいかなくてはならない。
だから、自ら希望を生み出す仕組みを構築する必要がある。
「本」、そして「人」、さらに「地域」
小さな入り口から始まる希望を生み出す仕組みを
創っていきたいと思う。
2015年06月22日
学校という自信喪失装置
「自信のない若者」問題において、
学校が果たしてきた役割は大きい。
かつて、学校、地域、家庭は
子どもを社会化する(大人に育てる)ために
それぞれの役割があった。
学校:学力をつける。比べられても負けない力をつける
地域:価値観が多様であると伝える。社会力をつける。
家庭:自分がかけがえのない一人であると知る。自己肯定力を育む。
この中で
地域と家庭が急速に力を失っていく。
そして「学校」だけに子どもの教育が依存されていく。
学校は、その構造的な性質上、
「単一の価値観」「他者評価」「他者との比較」
から逃れられない。
A先生とB先生が
「個人の好き嫌い」で子どもを評価してはいけないからだ。
文部科学省の方針にのっとり、
教育を実践しなければならない。
この単一の価値観による評価は、
他者との比較を生む。
勉強ができる、できない。
運動ができる、できない。
できるにしても自分はクラスの中でどのくらいなのか?
ということになる。
一部の勝ち組と
その他大勢の負け組を生む。
しかしこの場合の「負け」は
「学校という価値観」における「学校空間」における「相対的な」負けであって、
それで人生がどうのこうのなる問題では本来はない。
しかしいま、子どもたちは多様な価値観を与えてくれる「地域」を失い、
かけがえのない自分として「親和的承認」を与えてくれた
おじいちゃんやおばあちゃんのいる「家庭」を失った。
言わば、
学校という単一の価値観の宗教に入信せざるを得ない状況となった。
NHK朝ドラ「まれ」でこんなセリフがあった。
「祭りにも帰してもらわれん会社、やめてもえ」
このセリフの主は、
あきらかに、会社よりも地域の祭りが大切だと言っている。
ところが。
もはやそんな地域は稀有な存在となってしまった。
日付に意味があったはずの
春祭り、秋祭りは土日開催へと固定された。
学校優先・会社優先の社会が作り上げられた。
その試みはある意味では成功した。
世界2位の経済大国(現在は中国に抜かれて3位)
へと躍り出た。
その一方で、
学校という単一の価値観に染められた空間で
育つ子どもたちは、そこに適合しながら、
徐々に自信を失っていく。
他者評価(先生からの評価)が気になり、
他者比較(同級生との比較)をするようになる。
こうして、自信のない若者が完成していく。
しかしながら、
もはや「地域」と「家庭」に頼ることはできない。
答えはひとつではないという「多様な価値観」
そして
かけがえのない存在であるという「自己肯定力」を
つけるために、
おそらくは地域とのコミュニケーション・デザイン
プログラム・デザインが必要になってくるのだろう。
新潟・ツルハシブックスや練馬・暗やみ本屋ハックツはおそらく、
これまで「地域」が果たしてきた機能である
「多様な価値観」と伝えるということと、
「家庭」が果たしてきた
「自己肯定力」を育むということを
商店街の中の本屋が果たしていけるのではないか?
という仮説ではないだろうか。
「多様な価値観」「自己肯定力」
この2つをベースにして初めて、
学校での学びが生きてくる、
学びへのモチベーションが上がってくる、
と僕は思っている。
そんな場と、そんな学びをつくりたいなあと心から思う。
学校が果たしてきた役割は大きい。
かつて、学校、地域、家庭は
子どもを社会化する(大人に育てる)ために
それぞれの役割があった。
学校:学力をつける。比べられても負けない力をつける
地域:価値観が多様であると伝える。社会力をつける。
家庭:自分がかけがえのない一人であると知る。自己肯定力を育む。
この中で
地域と家庭が急速に力を失っていく。
そして「学校」だけに子どもの教育が依存されていく。
学校は、その構造的な性質上、
「単一の価値観」「他者評価」「他者との比較」
から逃れられない。
A先生とB先生が
「個人の好き嫌い」で子どもを評価してはいけないからだ。
文部科学省の方針にのっとり、
教育を実践しなければならない。
この単一の価値観による評価は、
他者との比較を生む。
勉強ができる、できない。
運動ができる、できない。
できるにしても自分はクラスの中でどのくらいなのか?
ということになる。
一部の勝ち組と
その他大勢の負け組を生む。
しかしこの場合の「負け」は
「学校という価値観」における「学校空間」における「相対的な」負けであって、
それで人生がどうのこうのなる問題では本来はない。
しかしいま、子どもたちは多様な価値観を与えてくれる「地域」を失い、
かけがえのない自分として「親和的承認」を与えてくれた
おじいちゃんやおばあちゃんのいる「家庭」を失った。
言わば、
学校という単一の価値観の宗教に入信せざるを得ない状況となった。
NHK朝ドラ「まれ」でこんなセリフがあった。
「祭りにも帰してもらわれん会社、やめてもえ」
このセリフの主は、
あきらかに、会社よりも地域の祭りが大切だと言っている。
ところが。
もはやそんな地域は稀有な存在となってしまった。
日付に意味があったはずの
春祭り、秋祭りは土日開催へと固定された。
学校優先・会社優先の社会が作り上げられた。
その試みはある意味では成功した。
世界2位の経済大国(現在は中国に抜かれて3位)
へと躍り出た。
その一方で、
学校という単一の価値観に染められた空間で
育つ子どもたちは、そこに適合しながら、
徐々に自信を失っていく。
他者評価(先生からの評価)が気になり、
他者比較(同級生との比較)をするようになる。
こうして、自信のない若者が完成していく。
しかしながら、
もはや「地域」と「家庭」に頼ることはできない。
答えはひとつではないという「多様な価値観」
そして
かけがえのない存在であるという「自己肯定力」を
つけるために、
おそらくは地域とのコミュニケーション・デザイン
プログラム・デザインが必要になってくるのだろう。
新潟・ツルハシブックスや練馬・暗やみ本屋ハックツはおそらく、
これまで「地域」が果たしてきた機能である
「多様な価値観」と伝えるということと、
「家庭」が果たしてきた
「自己肯定力」を育むということを
商店街の中の本屋が果たしていけるのではないか?
という仮説ではないだろうか。
「多様な価値観」「自己肯定力」
この2つをベースにして初めて、
学校での学びが生きてくる、
学びへのモチベーションが上がってくる、
と僕は思っている。
そんな場と、そんな学びをつくりたいなあと心から思う。
2015年06月21日
親和的承認装置としての本屋
「自信のない若者」問題。
高校、大学、あるいは既卒者の
キャリア教育上の大きな課題。
機能しない「チャレンジ理論」。
※チャレンジ理論とは、
小さなチャレンジ⇒小さな成功体験の
繰り返しによって自信がつくという理論。
しかし、自信がなければ、
その最初のチャレンジが始まらないので、
永遠にそのドミノは倒れない。
もっと、その根本原因にアプローチを
する必要があると思う。
「自信がない」若者問題の根本原因は
僕の仮説では、以下の3つだ。
1つ目が
核家族化・地域のつながりの喪失による
「親和的承認」機会の不足。
※「親和的承認」とは承認欲求の第一段階の
「ありのままの自分を認める」ということ。
2つ目が学校での他者評価・他者比較による
「成長思考」(やればできるかもしれない)から
「才能思考」(自分の能力はこんなもん)の上書きが起こること。
3つ目が「継続は力なり」あるいは「安定志向」
という戦後に続いてきた安定型社会、
もっと言えば稲作時代から続く呪縛だ。
特にもっとも大きいのが、1の親和的承認機会の不足であろう。
人間は本来、比べることのできないかけがえのない存在である。
にもかかわらず、
「学校」や「経済社会」はそれを単一の尺度で比べることを
余儀なくさせる。
あるいは「産業社会」は、
人々を「交換可能な部品」にしてしまう。
課長が突然退職しても、
ほどなく係長の誰かが課長に昇格して会社は回っていく。
「地域」や「家庭」では
そんなことはない。
地域の消防団や祭りの担い手、
家庭における祖父母にとっての孫というのは、
かけがえのない存在である。
その「地域」と「家庭」が与えてきた
親和的承認がだんだんと与えられなくなる。
「学校」「産業」に世の中がシフトしたからだ。
地域のつながりは失われ、
家庭では、「勉強できたら褒めてあげる」
というような「条件付き承認」が
与えられるようになる。
親和的承認の不足は、
個人の自信にとって、もっとも大きな影響を与えていると私は思う。
先日、

「すごい弁当力」(佐藤剛史 五月書房)
を読んで、弁当の日という実践に、心が震えた。
弁当の力で社会は変えられる、そんなふうに僕も実感した。
小学校で、あるいは大学で行われる弁当の日。
子どもたちは自分ひとりの力で弁当をつくる。
大学生たちは、自ら作った弁当のおかず一品を
みんなに食べてもらう。
ああ。
これぞ「親和的承認」の機会の創出だと思った。
子どもたちは自分たちがどんなに愛されているか知るだろう。
大学生たちは、自分の個性がたくさんの仲間に受け入れられている
と実感できるだろう。
親和的承認。
人が生きていく上でもっとも基本となる機会が
弁当の日にはあると思った。
ではそれを地域の現場で再現できないだろうか。
そう、それが本屋ではないか、と僕は考える。
本屋の本という圧倒的な多様性。
本屋に来る大人たちという、利害関係のない第3の大人。
同じように人生に悩んでいる大学生たち。
それらが織りなす場のチカラが、
お客さんにとっての小さな「親和的承認」の
機会を与えるのではないだろうか。
ありのままの中学生高校生大学生を受け入れる力が
本屋にはあるのではないか?
商店街にもあるのではないか?
商店街の中にある本屋という空間のチカラで、
若者の自信を取り戻していくことはできないだろうか。
ツルハシブックスという取り組みは
きっとそういうことなのかもしれないと思った。
高校、大学、あるいは既卒者の
キャリア教育上の大きな課題。
機能しない「チャレンジ理論」。
※チャレンジ理論とは、
小さなチャレンジ⇒小さな成功体験の
繰り返しによって自信がつくという理論。
しかし、自信がなければ、
その最初のチャレンジが始まらないので、
永遠にそのドミノは倒れない。
もっと、その根本原因にアプローチを
する必要があると思う。
「自信がない」若者問題の根本原因は
僕の仮説では、以下の3つだ。
1つ目が
核家族化・地域のつながりの喪失による
「親和的承認」機会の不足。
※「親和的承認」とは承認欲求の第一段階の
「ありのままの自分を認める」ということ。
2つ目が学校での他者評価・他者比較による
「成長思考」(やればできるかもしれない)から
「才能思考」(自分の能力はこんなもん)の上書きが起こること。
3つ目が「継続は力なり」あるいは「安定志向」
という戦後に続いてきた安定型社会、
もっと言えば稲作時代から続く呪縛だ。
特にもっとも大きいのが、1の親和的承認機会の不足であろう。
人間は本来、比べることのできないかけがえのない存在である。
にもかかわらず、
「学校」や「経済社会」はそれを単一の尺度で比べることを
余儀なくさせる。
あるいは「産業社会」は、
人々を「交換可能な部品」にしてしまう。
課長が突然退職しても、
ほどなく係長の誰かが課長に昇格して会社は回っていく。
「地域」や「家庭」では
そんなことはない。
地域の消防団や祭りの担い手、
家庭における祖父母にとっての孫というのは、
かけがえのない存在である。
その「地域」と「家庭」が与えてきた
親和的承認がだんだんと与えられなくなる。
「学校」「産業」に世の中がシフトしたからだ。
地域のつながりは失われ、
家庭では、「勉強できたら褒めてあげる」
というような「条件付き承認」が
与えられるようになる。
親和的承認の不足は、
個人の自信にとって、もっとも大きな影響を与えていると私は思う。
先日、

「すごい弁当力」(佐藤剛史 五月書房)
を読んで、弁当の日という実践に、心が震えた。
弁当の力で社会は変えられる、そんなふうに僕も実感した。
小学校で、あるいは大学で行われる弁当の日。
子どもたちは自分ひとりの力で弁当をつくる。
大学生たちは、自ら作った弁当のおかず一品を
みんなに食べてもらう。
ああ。
これぞ「親和的承認」の機会の創出だと思った。
子どもたちは自分たちがどんなに愛されているか知るだろう。
大学生たちは、自分の個性がたくさんの仲間に受け入れられている
と実感できるだろう。
親和的承認。
人が生きていく上でもっとも基本となる機会が
弁当の日にはあると思った。
ではそれを地域の現場で再現できないだろうか。
そう、それが本屋ではないか、と僕は考える。
本屋の本という圧倒的な多様性。
本屋に来る大人たちという、利害関係のない第3の大人。
同じように人生に悩んでいる大学生たち。
それらが織りなす場のチカラが、
お客さんにとっての小さな「親和的承認」の
機会を与えるのではないだろうか。
ありのままの中学生高校生大学生を受け入れる力が
本屋にはあるのではないか?
商店街にもあるのではないか?
商店街の中にある本屋という空間のチカラで、
若者の自信を取り戻していくことはできないだろうか。
ツルハシブックスという取り組みは
きっとそういうことなのかもしれないと思った。
2015年06月20日
コッソリ世界を変える方法
1週間前も同じようなことを書いていたけど。
気づかれないうちに、コッソリと世界を変える方法。
それは、「哲学する」こと。
「哲学する」とは、
価値観と感性を揺さぶるということ。
価値観とは、何を大切にするか?
大切なものはなんですか?という問い。
感性とは、何をもって美しいとするか?
美しいってなんですか?という問い。
このふたつを
気づかれずに問うこと。
これがコッソリ世界を変える方法だと思う。
「名作」と呼ばれる絵本や児童文学は
きっとそれができる本だ。
そんな本をこっそりと手渡していくこと。
それが図書館や本屋の役割だ。
その次に実践の手法。
美しいとは何か?
を実践すること。
これはきっと小売業が向いている。
小阪裕司さんの本に出てくるお店は、
すごく美しい。
生き方と働き方が一致している。
哲学と志がある。
本屋と米屋。
コッソリ世界を変えるには、
このふたつが最前線にあると僕は思っている。
気づかれないうちに、コッソリと世界を変える方法。
それは、「哲学する」こと。
「哲学する」とは、
価値観と感性を揺さぶるということ。
価値観とは、何を大切にするか?
大切なものはなんですか?という問い。
感性とは、何をもって美しいとするか?
美しいってなんですか?という問い。
このふたつを
気づかれずに問うこと。
これがコッソリ世界を変える方法だと思う。
「名作」と呼ばれる絵本や児童文学は
きっとそれができる本だ。
そんな本をこっそりと手渡していくこと。
それが図書館や本屋の役割だ。
その次に実践の手法。
美しいとは何か?
を実践すること。
これはきっと小売業が向いている。
小阪裕司さんの本に出てくるお店は、
すごく美しい。
生き方と働き方が一致している。
哲学と志がある。
本屋と米屋。
コッソリ世界を変えるには、
このふたつが最前線にあると僕は思っている。
2015年06月19日
「役」を取り戻すコミュニティデザイン
公開講座の最終回でした。
高齢社会にシニアはどう生きていくのか?
という問いかけ。
非常に面白い時間となりました。
~~~ここから講義メモ
5 家族との別れ
多世代世帯⇒後継ぎがいる
核家族⇒最後は一人になる
老いる⇒「血縁」「地縁」「職縁」「友縁」が変化する
1980年⇒2002年調査「あなたにとって家族とは?」(神栖市)
3世代同居家族の中でも祖父母が家族と認識されなくなった。
幼稚園児に
「ままごとするとき、どんな役がいるのか?」たずねる。
1 お母さん
2 友だち
3 お父さん
4 ペット
5 おばあちゃん
6 おじいちゃん
※祖父母の役割が消えてきたことを示している
かつて、大切なことは祖父母から伝えられた。
「隔世遺伝」
昔話がなぜ「むかしむかしあるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。」
と始まるのか?
読み手がおじいちゃんおばあちゃんだったから。
大切なこと=人間としての基本は祖父母から孫へ伝えられた。
・お金がすべてじゃない
・人には親切にしないといけない
・うそをついてはいけない
※学校がなかったから。
かつては役割であふれていた年寄りたち。
現在は家族の中に役割がない。
⇒地域のおじいちゃんおばあちゃんとして役割を持つ。
6 健康との別れ
・西洋の健康観:アトミズム(分節的)、臓器的に見る。
・東洋の健康観:場=ネットワーク、悪いところとバランスを取りながら生きていく。
「風水」=地理学であり、病理学。
「風」=呼吸、「水」=血流
東洋:生気が流れている。気脈⇒病気⇔元気
3つの健康
1 身体
2 精神
3 縁
縁が切れていく⇒キレる子どもたちを生む。
7 情報との別れ
宮崎県のとあるNPO法人の言葉
「お年寄りが一人亡くなるということは、
小さな図書館がなくなるのと同じだ」
聞き取る⇒次世代に渡す。
☆2つの世界をどう生きるか。
「職の世界」⇔「役の世界」
お金とモノ⇔愛と縁
※ボランティアの世界
1 無償性:お金の機能を限定する
お金:比べる道具
ボランティア⇒お金を否定するのではなく、
「比べる」ことを否定する。
人間は比べられない
2 公共性:みんな
人は一人では生きられない。
コモンズの掟=サバンナの木陰
共有・総有
3 自主性・自発性
組織⇔個人
組織があって個人があるのか
個人があって組織があるのか
会社人間として生きる=自分を無くすこと
組織の中に入るのではなく、
ひとりひとりの個がネットワークをつくる
大豆食品組織論
豆腐:1粒1粒すりつぶして真っ白になる⇒すぐつぶれる
がんもどき:大豆以外が生かされている。変わったヤツが役割を果たす:つぶれない
納豆:1粒1粒が生きている。活動すると糸を引く⇒虹色納豆ワーク(ネット)
ボランティアの意味
・福祉ボランティア:人は一人では生きられない
・学習ボランティア:人は本能だけでは生きられない。学ばないと生きられない
・環境ボランティア:食物連鎖の頂点に立つ人間としての責任。地球上で生き残れない
・国際交流ボランティア:人類として連帯しないと生きられない
「職の世界」と「役の世界」のあいだにNPO・ソーシャルビジネスという世界がある
そこに商品をつくっていくこと。
~~~ここまで講義メモ
なるほど。
核家族化は経済の要請だったと思うが、
それによって、年寄りは「高齢者」と区分され、
被支援者となった。
しかし。
本当の支援とは、介護予防の運動をさせるようにするのではなく、
ひとりひとりの「役」を復活させていくことではないだろうか。
それは高齢者ばかりではなく、
「東北オープンアカデミー」のときにも感じたことだが、
働く全世代に必要なことではないだろうか。
ツルハシブックスや暗やみ本屋ハックツ。
そして、これから始まっていく米屋のプロジェクトは、
地域の中でひとりひとりが「役」を取り戻していくという
コミュニティデザインの実験場になっていくのだろうと
強く予感した講座であった。
高齢社会にシニアはどう生きていくのか?
という問いかけ。
非常に面白い時間となりました。
~~~ここから講義メモ
5 家族との別れ
多世代世帯⇒後継ぎがいる
核家族⇒最後は一人になる
老いる⇒「血縁」「地縁」「職縁」「友縁」が変化する
1980年⇒2002年調査「あなたにとって家族とは?」(神栖市)
3世代同居家族の中でも祖父母が家族と認識されなくなった。
幼稚園児に
「ままごとするとき、どんな役がいるのか?」たずねる。
1 お母さん
2 友だち
3 お父さん
4 ペット
5 おばあちゃん
6 おじいちゃん
※祖父母の役割が消えてきたことを示している
かつて、大切なことは祖父母から伝えられた。
「隔世遺伝」
昔話がなぜ「むかしむかしあるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。」
と始まるのか?
読み手がおじいちゃんおばあちゃんだったから。
大切なこと=人間としての基本は祖父母から孫へ伝えられた。
・お金がすべてじゃない
・人には親切にしないといけない
・うそをついてはいけない
※学校がなかったから。
かつては役割であふれていた年寄りたち。
現在は家族の中に役割がない。
⇒地域のおじいちゃんおばあちゃんとして役割を持つ。
6 健康との別れ
・西洋の健康観:アトミズム(分節的)、臓器的に見る。
・東洋の健康観:場=ネットワーク、悪いところとバランスを取りながら生きていく。
「風水」=地理学であり、病理学。
「風」=呼吸、「水」=血流
東洋:生気が流れている。気脈⇒病気⇔元気
3つの健康
1 身体
2 精神
3 縁
縁が切れていく⇒キレる子どもたちを生む。
7 情報との別れ
宮崎県のとあるNPO法人の言葉
「お年寄りが一人亡くなるということは、
小さな図書館がなくなるのと同じだ」
聞き取る⇒次世代に渡す。
☆2つの世界をどう生きるか。
「職の世界」⇔「役の世界」
お金とモノ⇔愛と縁
※ボランティアの世界
1 無償性:お金の機能を限定する
お金:比べる道具
ボランティア⇒お金を否定するのではなく、
「比べる」ことを否定する。
人間は比べられない
2 公共性:みんな
人は一人では生きられない。
コモンズの掟=サバンナの木陰
共有・総有
3 自主性・自発性
組織⇔個人
組織があって個人があるのか
個人があって組織があるのか
会社人間として生きる=自分を無くすこと
組織の中に入るのではなく、
ひとりひとりの個がネットワークをつくる
大豆食品組織論
豆腐:1粒1粒すりつぶして真っ白になる⇒すぐつぶれる
がんもどき:大豆以外が生かされている。変わったヤツが役割を果たす:つぶれない
納豆:1粒1粒が生きている。活動すると糸を引く⇒虹色納豆ワーク(ネット)
ボランティアの意味
・福祉ボランティア:人は一人では生きられない
・学習ボランティア:人は本能だけでは生きられない。学ばないと生きられない
・環境ボランティア:食物連鎖の頂点に立つ人間としての責任。地球上で生き残れない
・国際交流ボランティア:人類として連帯しないと生きられない
「職の世界」と「役の世界」のあいだにNPO・ソーシャルビジネスという世界がある
そこに商品をつくっていくこと。
~~~ここまで講義メモ
なるほど。
核家族化は経済の要請だったと思うが、
それによって、年寄りは「高齢者」と区分され、
被支援者となった。
しかし。
本当の支援とは、介護予防の運動をさせるようにするのではなく、
ひとりひとりの「役」を復活させていくことではないだろうか。
それは高齢者ばかりではなく、
「東北オープンアカデミー」のときにも感じたことだが、
働く全世代に必要なことではないだろうか。
ツルハシブックスや暗やみ本屋ハックツ。
そして、これから始まっていく米屋のプロジェクトは、
地域の中でひとりひとりが「役」を取り戻していくという
コミュニティデザインの実験場になっていくのだろうと
強く予感した講座であった。
2015年06月18日
「課題解決」の前に「課題共感」
「課題解決」
高齢社会。
少子化。
消滅可能性都市。
課題先進国ニッポンの中で、
盛んに「課題解決」が叫ばれている。
課題解決の手法もたくさんある。
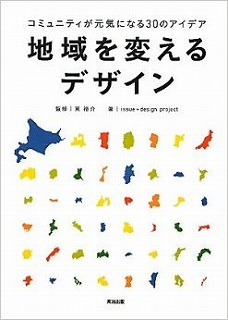
「地域を変えるデザイン」(筧裕介 英治出版)
僕が主に学んできたのは
コミュニティデザインやソーシャルデザイン
という手法。
つまり、「デザイン」の力で解決するという手法だ。
たとえば、高齢者のひとり暮らしの課題がある。
彼らの安否確認を、民生委員が一軒ずつ家を訪問してやるには限界がある。
そして孤独の中でテレビを見ていると、どうしたって、足腰も脳も衰えていく。
それを何とかしようと思った時に、
他の課題、たとえば、子どもの教育課題である「地域の教育力」という観点から
それらをミックスするのだ。
地域の居場所、あるいは学校に子どもと年寄りを集め、昔の遊びを楽しむ。
このように「組み合わせることで2つの課題が同時に解決できる」
という手法を考えていかなければならない。
もちろん、目の前に見えている課題は
表面上の課題なのであって、
それの本質を突き詰めていかなければならないのは言うまでもない。
僕がこの10年取り組んだ課題は、
「やりたいことがわからない若者」問題であった。
「自信がなくて動けない若者」問題でもあった。
あるいは、「よくわからないけどなんとなく不安である中高生」問題であった。
それらの原因は、
突き詰めていくと、
「夢至上主義という経済社会の要請」
「学校教育という自信を失われるシステム」
「中高のキャリア教育のキャリアデザイン志向」
ではないか?と思っている。
そのひとつひとつに対し、
これから対策を練って実行していくステージにいる。
ツルハシブックスや暗やみ本屋ハックツは、その方法論のひとつだ。
大切なことは、「課題解決」の前に
「課題共感」があることだと思う。
自分ごとになる、と言い換えてもいいかもしれない。
27歳の時、不登校の中学3年生に出会い、
地域の大人との接点が必要だと思った。
本屋をやっている中で、
「やりたいことがわからない」という悩みをもった
就活生に何人も出会った。そしてかなり深刻そうであった。
「行動しなければ自信はつかない。しかし、自信がないから行動できない」
という矛盾の中で、苦しんでいる若者を見てきた。
なんとかしたい。
そう思った。
これが「課題共感」である。
地域課題でも同じだ。
地域に入り込み、対話をし、その課題に共感をする。
そこからしか始まらない。
共感するからこそ、モチベーションが上がり、
課題解決へのエネルギーが湧き、その分、学びが多くなる。
表面上こういう課題を抱えています。
じゃあどう解決しますか?
という手法が大切なのではない。
いや、もちろん解決するのはいいことなのだけど、
大学生がアイデアを出して、単に課題を解決することは
大学生にとってどんな価値があるのだろうか?
地域の課題は、「この場所でどう生き続けていくか?」ということ。
大学生にとっての課題は、「これからどう生きていくか?」ということ。
これらをうまくデザインすることがコーディネーターには求められる。
地域の課題に共感し、寄り添うだけではなく、
大学生の人生の課題、
「自分はこれからどう学び、どう生きていくか?」
「自分は世界とどう対話していくのか?」
「自分はどこからきて、どこへいくのか?」
そんな課題に共感し、寄り添い、プロジェクトをつくっていくこと。
先の見えないこの時代。
誰もが先頭を走っているかもしれないこの時代。
そんな時代に生まれた。
そのことに大学生も僕も
感謝できるようなプロジェクトを生んでいこうと思っています。
高齢社会。
少子化。
消滅可能性都市。
課題先進国ニッポンの中で、
盛んに「課題解決」が叫ばれている。
課題解決の手法もたくさんある。
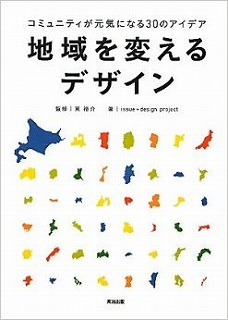
「地域を変えるデザイン」(筧裕介 英治出版)
僕が主に学んできたのは
コミュニティデザインやソーシャルデザイン
という手法。
つまり、「デザイン」の力で解決するという手法だ。
たとえば、高齢者のひとり暮らしの課題がある。
彼らの安否確認を、民生委員が一軒ずつ家を訪問してやるには限界がある。
そして孤独の中でテレビを見ていると、どうしたって、足腰も脳も衰えていく。
それを何とかしようと思った時に、
他の課題、たとえば、子どもの教育課題である「地域の教育力」という観点から
それらをミックスするのだ。
地域の居場所、あるいは学校に子どもと年寄りを集め、昔の遊びを楽しむ。
このように「組み合わせることで2つの課題が同時に解決できる」
という手法を考えていかなければならない。
もちろん、目の前に見えている課題は
表面上の課題なのであって、
それの本質を突き詰めていかなければならないのは言うまでもない。
僕がこの10年取り組んだ課題は、
「やりたいことがわからない若者」問題であった。
「自信がなくて動けない若者」問題でもあった。
あるいは、「よくわからないけどなんとなく不安である中高生」問題であった。
それらの原因は、
突き詰めていくと、
「夢至上主義という経済社会の要請」
「学校教育という自信を失われるシステム」
「中高のキャリア教育のキャリアデザイン志向」
ではないか?と思っている。
そのひとつひとつに対し、
これから対策を練って実行していくステージにいる。
ツルハシブックスや暗やみ本屋ハックツは、その方法論のひとつだ。
大切なことは、「課題解決」の前に
「課題共感」があることだと思う。
自分ごとになる、と言い換えてもいいかもしれない。
27歳の時、不登校の中学3年生に出会い、
地域の大人との接点が必要だと思った。
本屋をやっている中で、
「やりたいことがわからない」という悩みをもった
就活生に何人も出会った。そしてかなり深刻そうであった。
「行動しなければ自信はつかない。しかし、自信がないから行動できない」
という矛盾の中で、苦しんでいる若者を見てきた。
なんとかしたい。
そう思った。
これが「課題共感」である。
地域課題でも同じだ。
地域に入り込み、対話をし、その課題に共感をする。
そこからしか始まらない。
共感するからこそ、モチベーションが上がり、
課題解決へのエネルギーが湧き、その分、学びが多くなる。
表面上こういう課題を抱えています。
じゃあどう解決しますか?
という手法が大切なのではない。
いや、もちろん解決するのはいいことなのだけど、
大学生がアイデアを出して、単に課題を解決することは
大学生にとってどんな価値があるのだろうか?
地域の課題は、「この場所でどう生き続けていくか?」ということ。
大学生にとっての課題は、「これからどう生きていくか?」ということ。
これらをうまくデザインすることがコーディネーターには求められる。
地域の課題に共感し、寄り添うだけではなく、
大学生の人生の課題、
「自分はこれからどう学び、どう生きていくか?」
「自分は世界とどう対話していくのか?」
「自分はどこからきて、どこへいくのか?」
そんな課題に共感し、寄り添い、プロジェクトをつくっていくこと。
先の見えないこの時代。
誰もが先頭を走っているかもしれないこの時代。
そんな時代に生まれた。
そのことに大学生も僕も
感謝できるようなプロジェクトを生んでいこうと思っています。
2015年06月17日
「学力」への反発という本能
公開講座第3回目。
今回も気づきがたくさん。
「富国強兵」「殖産興業」
の名の下で「日本人」をつくる教育、
それが学校教育だった。
そして、何度も繰り返される
一元化された「学力」と「多様な力(生きる力)」
のせめぎあい。
いやあ。
教育学部必修なんじゃないかな、これ。
と思いました。
~~~以下講義メモ
〇分節型階層社会=士農工商
・江戸時代は4つの身分に明確に区分されていた。
⇒それぞれがそれぞれの「子育てのカタチ」を持っていた。
1 武士社会=儒教
「知行合一」「致良知」「一期一会」を大切にする
・通過儀式(イニシュエーション)を持つ(元服など)
・「恥」の子育て(モラルに反する⇒恥 ⇔ ルールに反する⇒罰)
・「恥」=「卑怯」:誰も見ていなくても自分が見ている。
2 農村社会=農事暦=作物の照応
・育つ=背立つ(稲穂が成長する)⇒内発的動機型
・しつける=田植えを決まった場所にする。
・「育」という字は子の反対に肉付き
⇒悪い子を(外発的に)トレーニングするという文字
・そだつ=農耕的子育て⇔育つ=武士的子育て
3 工=職人社会
・「親方」→「奉公」→「覚える」→「自立」:流動社会
・技を盗む=マイスター
・ゲマインシャフト:共同社会 結・講:お金を介さない社会
・ゲゼルシャフト:職人社会 お金が動く社会
・「覚える」:個人的・体験的学び:大量に均質に教育できない
4 商人社会
・訓育・鍛育⇒商家の家訓を守る:江戸しぐさ、繁盛しぐさ
〇明治維新:1~4を国民教育として一本化する必要があった。
・日本人の子どもの能力を一元化する⇒平準化
・「平準化」:地域性を除外、一斉授業・黒板
・シャドウカリキュラム:学力よりも「遅刻しない」「1時間ガマンして聞いている」ことが軍隊・工場に入った時に重要。
・日本人の意識を統一する。
・学校をつくる:地域みんなでお金を出し合ってやった。
・手に入れたもの:学問知(知識)⇔日常知(知恵)
・科学:学問知が日常知とつながらなくなった:現代
明治時代「富国強兵」「殖産興業」
産業労働者であり、かつ戦争を担う人を育てる。
「皇民教育」
1894年 日清戦争
1904年 日露戦争
1914年 第1次世界大戦
10年ごとの戦争のあいだ。
1925年に大正デモクラシーが起こる。
「民主主義教育」:窓際のトットちゃん「自由の森学園」
など、新しい教育のカタチが生まれる。
しかし、
1931年 満州事変
から
1945年 終戦
までの15年戦争で再び「皇民教育」へ。
終戦後アメリカ型の戦後社会をつくる
アメリカ型:民主主義社会
1 民主主義
2 平和主義
⇒やったことがないので1946年~1950年
新しい教育のカタチの模索が始まる。
全国でさまざまな実践モデルが出てくる。
「コアカリキュラム運動」
⇒地域の力を反映した自発的な学校運営
⇒作文教育などの実践
※「コアカリキュラム運動」で学力が上がったのか?問われる
1950年 朝鮮戦争
1955年 高度経済成長
大量生産・大量消費型の経済モデルを選択し、
それを担う労働者を生むことがが重要になる。
1967年 学力テスト
学力テストを上げた人がよい先生
「学力」重視⇔地域の行事:学力の足しにならない:悪い
「学力」一辺倒⇒学校は荒れる。校内暴力・対教師暴力
⇒管理主義教育:子どもは悪⇒学校がトレーニングする。校則で縛る。
⇒子どもが社会悪に触れないようにする。
⇒体罰・いじめ:学校と父母が対立する
〇2000年「生きる力」:感情喚起型概念⇔定義型概念(それとそれ以外を分ける)
2007年に再び「学力」論争が起こり、
「ゆとり教育」の撤回
〇コミュニティスクール
地域⇔学校
・学校の中に地域の課題を入れていく
・先生を評価する権利がある
~~~ここまで講義メモ
なるほど。
「学力」という単一の尺度で、
子どもが比べられるようになったのは
わずかこの150年、ごく最近なんですね。
それは、校内暴力も起こるよなあと。
比べられないはずの人が比べられるのだから
そのストレスはハンパない。
そして150年の間に何度も
一元化された「学力」と
多様な「生きる力」とのせめぎあいが起こっているのだなあと。
いまいちど問いかけたいのは、
「富国強兵」「殖産興業」の時代なのか?
ってこと。
アイデア・付加価値・イノベーション・デザインの
時代なのではないか?
そのために、教育はどうあるべきか?
子どもはどのように育てたらよいのか?
真剣に考え直さないといけない。
何よりも、
いま、この瞬間を生きている子どもたちが
輝けるような空間を作っていかないといけないなと思った。
今回も気づきがたくさん。
「富国強兵」「殖産興業」
の名の下で「日本人」をつくる教育、
それが学校教育だった。
そして、何度も繰り返される
一元化された「学力」と「多様な力(生きる力)」
のせめぎあい。
いやあ。
教育学部必修なんじゃないかな、これ。
と思いました。
~~~以下講義メモ
〇分節型階層社会=士農工商
・江戸時代は4つの身分に明確に区分されていた。
⇒それぞれがそれぞれの「子育てのカタチ」を持っていた。
1 武士社会=儒教
「知行合一」「致良知」「一期一会」を大切にする
・通過儀式(イニシュエーション)を持つ(元服など)
・「恥」の子育て(モラルに反する⇒恥 ⇔ ルールに反する⇒罰)
・「恥」=「卑怯」:誰も見ていなくても自分が見ている。
2 農村社会=農事暦=作物の照応
・育つ=背立つ(稲穂が成長する)⇒内発的動機型
・しつける=田植えを決まった場所にする。
・「育」という字は子の反対に肉付き
⇒悪い子を(外発的に)トレーニングするという文字
・そだつ=農耕的子育て⇔育つ=武士的子育て
3 工=職人社会
・「親方」→「奉公」→「覚える」→「自立」:流動社会
・技を盗む=マイスター
・ゲマインシャフト:共同社会 結・講:お金を介さない社会
・ゲゼルシャフト:職人社会 お金が動く社会
・「覚える」:個人的・体験的学び:大量に均質に教育できない
4 商人社会
・訓育・鍛育⇒商家の家訓を守る:江戸しぐさ、繁盛しぐさ
〇明治維新:1~4を国民教育として一本化する必要があった。
・日本人の子どもの能力を一元化する⇒平準化
・「平準化」:地域性を除外、一斉授業・黒板
・シャドウカリキュラム:学力よりも「遅刻しない」「1時間ガマンして聞いている」ことが軍隊・工場に入った時に重要。
・日本人の意識を統一する。
・学校をつくる:地域みんなでお金を出し合ってやった。
・手に入れたもの:学問知(知識)⇔日常知(知恵)
・科学:学問知が日常知とつながらなくなった:現代
明治時代「富国強兵」「殖産興業」
産業労働者であり、かつ戦争を担う人を育てる。
「皇民教育」
1894年 日清戦争
1904年 日露戦争
1914年 第1次世界大戦
10年ごとの戦争のあいだ。
1925年に大正デモクラシーが起こる。
「民主主義教育」:窓際のトットちゃん「自由の森学園」
など、新しい教育のカタチが生まれる。
しかし、
1931年 満州事変
から
1945年 終戦
までの15年戦争で再び「皇民教育」へ。
終戦後アメリカ型の戦後社会をつくる
アメリカ型:民主主義社会
1 民主主義
2 平和主義
⇒やったことがないので1946年~1950年
新しい教育のカタチの模索が始まる。
全国でさまざまな実践モデルが出てくる。
「コアカリキュラム運動」
⇒地域の力を反映した自発的な学校運営
⇒作文教育などの実践
※「コアカリキュラム運動」で学力が上がったのか?問われる
1950年 朝鮮戦争
1955年 高度経済成長
大量生産・大量消費型の経済モデルを選択し、
それを担う労働者を生むことがが重要になる。
1967年 学力テスト
学力テストを上げた人がよい先生
「学力」重視⇔地域の行事:学力の足しにならない:悪い
「学力」一辺倒⇒学校は荒れる。校内暴力・対教師暴力
⇒管理主義教育:子どもは悪⇒学校がトレーニングする。校則で縛る。
⇒子どもが社会悪に触れないようにする。
⇒体罰・いじめ:学校と父母が対立する
〇2000年「生きる力」:感情喚起型概念⇔定義型概念(それとそれ以外を分ける)
2007年に再び「学力」論争が起こり、
「ゆとり教育」の撤回
〇コミュニティスクール
地域⇔学校
・学校の中に地域の課題を入れていく
・先生を評価する権利がある
~~~ここまで講義メモ
なるほど。
「学力」という単一の尺度で、
子どもが比べられるようになったのは
わずかこの150年、ごく最近なんですね。
それは、校内暴力も起こるよなあと。
比べられないはずの人が比べられるのだから
そのストレスはハンパない。
そして150年の間に何度も
一元化された「学力」と
多様な「生きる力」とのせめぎあいが起こっているのだなあと。
いまいちど問いかけたいのは、
「富国強兵」「殖産興業」の時代なのか?
ってこと。
アイデア・付加価値・イノベーション・デザインの
時代なのではないか?
そのために、教育はどうあるべきか?
子どもはどのように育てたらよいのか?
真剣に考え直さないといけない。
何よりも、
いま、この瞬間を生きている子どもたちが
輝けるような空間を作っていかないといけないなと思った。
2015年06月16日
機会を提供し、同じ方向を見つめること
天職という職業・職種があるのではない。
天職だと思える瞬間があるだけだ。
昨日もそんな時間がありました。
「プレゼンなんてやってことがない」
という学生にアドバイスする先生。
真剣な眼差し。
その瞬間。
僕は天職に出会いました。
「機会提供」という天職
それはコーディネーターという仕事で
得られる一瞬なのかもしれない。
あるいは、
「本の処方箋」で悩みを聞いて、
そこに本を処方していくプロセスにあるのかもしれない。
この一瞬の機会を
活かしたいと思うこと。
それが僕の天職だなあと思います。
あの瞬間。
僕の脳にはベータエンドルフィンが流れます。

「お客様の感動を設計するハッピーエンドのつくり方」(平野秀典 ダイヤモンド社)
「お客様は共演者」
って僕がやっとたどり着いたものに、
平野さんは10年前に発表していたんですね。
参りました。
愛する、それはお互いに見つめ合うことではなく、
一緒に同じ方向を見つめることである。
(サン・テグジュペリ)
やっぱりこれですね。
愛するということ。
これを大学生と接しているときも
本屋で接客をしているときも、
意識するということ。
そこに僕の悦びがあるのだなあと。
「本の処方箋」っていうのは、
まさにそんなツールなのかもしれませんね。
そして「同じ方向を見つめる」
さらに「小さな一歩を踏み出す」
その瞬間を共有することが僕の天職なのかもしれません。
本屋も米屋もコーディネーターも
もしかしたらそういう仕事なのかもしれませんね。
天職だと思える瞬間があるだけだ。
昨日もそんな時間がありました。
「プレゼンなんてやってことがない」
という学生にアドバイスする先生。
真剣な眼差し。
その瞬間。
僕は天職に出会いました。
「機会提供」という天職
それはコーディネーターという仕事で
得られる一瞬なのかもしれない。
あるいは、
「本の処方箋」で悩みを聞いて、
そこに本を処方していくプロセスにあるのかもしれない。
この一瞬の機会を
活かしたいと思うこと。
それが僕の天職だなあと思います。
あの瞬間。
僕の脳にはベータエンドルフィンが流れます。

「お客様の感動を設計するハッピーエンドのつくり方」(平野秀典 ダイヤモンド社)
「お客様は共演者」
って僕がやっとたどり着いたものに、
平野さんは10年前に発表していたんですね。
参りました。
愛する、それはお互いに見つめ合うことではなく、
一緒に同じ方向を見つめることである。
(サン・テグジュペリ)
やっぱりこれですね。
愛するということ。
これを大学生と接しているときも
本屋で接客をしているときも、
意識するということ。
そこに僕の悦びがあるのだなあと。
「本の処方箋」っていうのは、
まさにそんなツールなのかもしれませんね。
そして「同じ方向を見つめる」
さらに「小さな一歩を踏み出す」
その瞬間を共有することが僕の天職なのかもしれません。
本屋も米屋もコーディネーターも
もしかしたらそういう仕事なのかもしれませんね。
2015年06月15日
哲学と志とそれをつなぐ生き方
かっこいい人。
それは、哲学がある人。
それは、芯のある人。
そして志がある人。
使命感を感じられる何かを持っている人。
そして、
哲学と志をつなぐ「生き方」をしている人。
哲学とは、
大切にしたいもの=価値観と
美しいと思う心=感性
価値観と感性を携えて、世界と対話し、
志に向かって、日々、自分を生きること。
きっとそんな生き方が
かっこいいのだなあと思った。
それは、哲学がある人。
それは、芯のある人。
そして志がある人。
使命感を感じられる何かを持っている人。
そして、
哲学と志をつなぐ「生き方」をしている人。
哲学とは、
大切にしたいもの=価値観と
美しいと思う心=感性
価値観と感性を携えて、世界と対話し、
志に向かって、日々、自分を生きること。
きっとそんな生き方が
かっこいいのだなあと思った。
2015年06月13日
哲学のある人
哲学のある人。
大げさだけど、それが
魅力的な人の条件なのかもしれないな。
それは、
年齢に関わらないと思う。
経験、
とりわけ、精神的経験、
「長さ」ではなく、「深さ」
によるのだろう。
「哲学」を形成するのは容易ではない。
いくつもの精神的苦悩を超えて、
人は哲学を形成していく。
それが内面からにじみ出ることで、
魅力的なオーラとなるのではないか。
20代の魅力的な人にたくさん出会って、
そんなことが分かった。
大げさだけど、それが
魅力的な人の条件なのかもしれないな。
それは、
年齢に関わらないと思う。
経験、
とりわけ、精神的経験、
「長さ」ではなく、「深さ」
によるのだろう。
「哲学」を形成するのは容易ではない。
いくつもの精神的苦悩を超えて、
人は哲学を形成していく。
それが内面からにじみ出ることで、
魅力的なオーラとなるのではないか。
20代の魅力的な人にたくさん出会って、
そんなことが分かった。
2015年06月11日
気づかれずに世界を変えよう
気づかれずに世界を変えよう。
そんなふうに思う。
僕にとって「世界」とは、「ひとりひとり」のこと。
「世界を変える」とは、「ひとりひとり」を変える、ということ。
しかし、人は変えることができない。
自分が変わることならできる。
「変わろう」とする自覚なく、
気が付いたら変わっていた。
そういう変わり方が美しいと思う。
絵本で言えば、
「せかいでいちばんつよい国」(デビッドマッキー なかがわちひろ 光村教育図書)
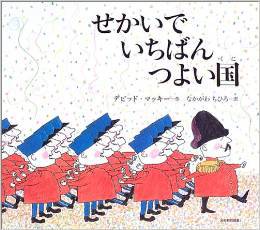
世界を征服した王様と小さな国の話。
気づかれないうちに「文化」の力で、
その国を変えていってしまっている。
これからの社会活動というか、
NPOというかまちづくりというか、
いや、経済活動であっても、
そういう方法論は必要なことなのかもしれない。
昔のように
CMをバンバン流して、キャンペーンを張って、
渇望感を持たせて、モノを買わせるなんて通用しないのだから。
東京都練馬区上石神井(かみしゃくじい)で
準備中の10代のための古本屋「暗やみ本屋ハックツ」は、今週末の13日
お出かけサイト「Holiday」とコラボしてまちあるきイベントを開催する。
「Holiday」
https://haveagood.holiday/
ゲストに来ていただく谷さんにお話を伺い、
「ハックツ」のコンセプトに近い、と感じた。
お出かけサイトと古本屋、何が近いのか?
「気づかれずに世界を変えよう」としているところ。
Holidayは簡単な近所のお出かけプランを個人が
ウェブ上にアップし、小さな散歩提案ができるサイト。
クックパッドが各個人のレシピをアップロードできるように、
たとえば、上石神井を降り立ったら、目の前の「だんごのつくし屋」で
団子を買い(いそべがおすすめ)、食べ歩きながら、喫茶ベルに行き、
マスターと野球談議、その後、ブックスタマに立ち寄って本を買い、
となりの一圓でジャンボ餃子を食べながらビールを飲む。
みたいな(完全のオッサンコースだな、これ)
そんなおでかけプランを個人が投稿できる。
「それ、おもしろそう」と思った人がまちをあるきたくなって
そうするとだんだんとそのまちが好きになって、
気が付いたら、そのまちでたくさん買い物をしている。
結果、地元はもっと元気になって、住みやすくなる。
「それって、世界変わっているよね。」
って思った。
お出かけする前と後で、その人にとっては、
まちが変わっている、人生が変わっている。
その繰り返しと人の広がりで、
まちは作られ、また誰かの人生が変わっていく。
それ、世界変えてるよ、って思った。
だから、「Holiday」はカッコイイ。
暗やみ本屋ハックツもそうありたいと思った。
地域の本屋で中高生に本を届ける。
中高生と一緒に街を歩く。
だんだんと地域の人が参画してくる。
もっとこんなこともあんなこともやったほうがいいんじゃないか。
中高生と一緒に何かが始まっていく。
気がついたら、地域の人たちは仲良くなっていた。
そうそう、そういうの。
「種をまく人」(ポールフライシュマン)の世界もそう。
気が付いたら、世界が変わっているんだ。
僕たちにとって「世界」ってのは、政治とはちょっと違っていて、
人だったり、その関係性だったりする。
特に中高生のとってはそうだ。
地域の人と出会い、話をして
一緒に何かをやってみて、その関係性が変わっていく。
それを「世界が広がる」と言うのではないか。
暗やみ本屋ハックツは、そういう場所でありたい。
昨日。
新潟で、もうひとつのプロジェクトが産声を上げた。
「つながる米屋 コメタク」のウェブショップ「と、くらす」
http://kometaku.net/wp/
最近米を炊いたのはいつですか?
と問いかけ、
ツルハシブックスと同じ商店街にある
飯塚商店の新潟産コシヒカリブランド「収穫物語」をまずは売る。
今年中には、「ご飯のある暮らし」をテーマに、
さまざまなものを売っていく予定だ。
気づかれずに世界を変える。
そんなプロジェクトって楽しいね。
そんなふうに思う。
僕にとって「世界」とは、「ひとりひとり」のこと。
「世界を変える」とは、「ひとりひとり」を変える、ということ。
しかし、人は変えることができない。
自分が変わることならできる。
「変わろう」とする自覚なく、
気が付いたら変わっていた。
そういう変わり方が美しいと思う。
絵本で言えば、
「せかいでいちばんつよい国」(デビッドマッキー なかがわちひろ 光村教育図書)
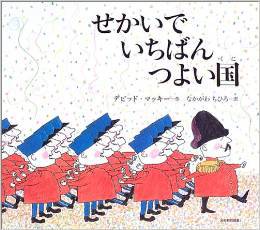
世界を征服した王様と小さな国の話。
気づかれないうちに「文化」の力で、
その国を変えていってしまっている。
これからの社会活動というか、
NPOというかまちづくりというか、
いや、経済活動であっても、
そういう方法論は必要なことなのかもしれない。
昔のように
CMをバンバン流して、キャンペーンを張って、
渇望感を持たせて、モノを買わせるなんて通用しないのだから。
東京都練馬区上石神井(かみしゃくじい)で
準備中の10代のための古本屋「暗やみ本屋ハックツ」は、今週末の13日
お出かけサイト「Holiday」とコラボしてまちあるきイベントを開催する。
「Holiday」
https://haveagood.holiday/
ゲストに来ていただく谷さんにお話を伺い、
「ハックツ」のコンセプトに近い、と感じた。
お出かけサイトと古本屋、何が近いのか?
「気づかれずに世界を変えよう」としているところ。
Holidayは簡単な近所のお出かけプランを個人が
ウェブ上にアップし、小さな散歩提案ができるサイト。
クックパッドが各個人のレシピをアップロードできるように、
たとえば、上石神井を降り立ったら、目の前の「だんごのつくし屋」で
団子を買い(いそべがおすすめ)、食べ歩きながら、喫茶ベルに行き、
マスターと野球談議、その後、ブックスタマに立ち寄って本を買い、
となりの一圓でジャンボ餃子を食べながらビールを飲む。
みたいな(完全のオッサンコースだな、これ)
そんなおでかけプランを個人が投稿できる。
「それ、おもしろそう」と思った人がまちをあるきたくなって
そうするとだんだんとそのまちが好きになって、
気が付いたら、そのまちでたくさん買い物をしている。
結果、地元はもっと元気になって、住みやすくなる。
「それって、世界変わっているよね。」
って思った。
お出かけする前と後で、その人にとっては、
まちが変わっている、人生が変わっている。
その繰り返しと人の広がりで、
まちは作られ、また誰かの人生が変わっていく。
それ、世界変えてるよ、って思った。
だから、「Holiday」はカッコイイ。
暗やみ本屋ハックツもそうありたいと思った。
地域の本屋で中高生に本を届ける。
中高生と一緒に街を歩く。
だんだんと地域の人が参画してくる。
もっとこんなこともあんなこともやったほうがいいんじゃないか。
中高生と一緒に何かが始まっていく。
気がついたら、地域の人たちは仲良くなっていた。
そうそう、そういうの。
「種をまく人」(ポールフライシュマン)の世界もそう。
気が付いたら、世界が変わっているんだ。
僕たちにとって「世界」ってのは、政治とはちょっと違っていて、
人だったり、その関係性だったりする。
特に中高生のとってはそうだ。
地域の人と出会い、話をして
一緒に何かをやってみて、その関係性が変わっていく。
それを「世界が広がる」と言うのではないか。
暗やみ本屋ハックツは、そういう場所でありたい。
昨日。
新潟で、もうひとつのプロジェクトが産声を上げた。
「つながる米屋 コメタク」のウェブショップ「と、くらす」
http://kometaku.net/wp/
最近米を炊いたのはいつですか?
と問いかけ、
ツルハシブックスと同じ商店街にある
飯塚商店の新潟産コシヒカリブランド「収穫物語」をまずは売る。
今年中には、「ご飯のある暮らし」をテーマに、
さまざまなものを売っていく予定だ。
気づかれずに世界を変える。
そんなプロジェクトって楽しいね。
2015年06月10日
「日本人」をつくった「学校カリキュラム」
江戸時代に「日本人」はいなかった。
日本に住んでいる人たちはいた。
それぞれの人は藩に属していた。
脱藩した坂本竜馬はそういう意味では日本人だったかもしれないが。
富国強兵。
明治政府はその名のもと、
「軍隊」、そして「学校」を整備した。
昨日は公開講座でした。
子どもの発達(社会化)の「3つの場」と「3つの間」
3つの場というのは「学校」「地域」「家庭」
3つの間というのは「時間」「空間」「人間(じんかん)」
です。
~~~以下講義メモ
・「職の世界」(会社・学校)と「役の世界」(地域・家庭)
・「職の世界」の価値観は「お金とモノ」=比べる世界、代わりがきく。
・「役の世界」の価値観は「愛と心」=比べられない世界、代わりがきかない。
・人は「役の世界」から「職」という仮面をかぶって会社に行き、赤提灯で仮面をはがして帰ってくる
・「お金」は比べるための道具
1 時間
・「職の世界」で流れる時間と「役の世界」で流れる時間は違う
・学校時間(産業時間)=カチカチ時間(平等・うしろから追いかけてくる・量で測る)
・地域・家庭時間(民俗時間)=サラサラ時間(不平等・深さがある・伸び縮みする)
・学校と軍隊は双子の兄弟
・学校はよき「日本人」=兵隊あるいは企業戦士になるために設計された。
・休んじゃダメ=いい企業人になるためのプログラム
・学校にいると比べられないもの(ヒト)を比べられるように錯覚する
・比べられても負けない力を身につけるのが学校
・学校=管理時間・平面時間
・地域には民俗時間が流れていた。「どんどん焼き」「節分」「七五三」
・これらの「行事」は時間の区切り=通過儀式として行われた。
・お祭りでも役割がだんだん上がっていった。
・比べられない時間がそこには流れていた。
・地域の行事を、学校が奪っていく。「学芸会」「運動会」「音楽祭」
・通過儀式さえも学校が奪っていったのが現在。例:「2分の1成人式」
・カチカチ時間だけではゆったりと生きられない。
⇒サードプレイスっていうのはサラサラ時間が流れる場所
2 空間
・学校=機能空間、管理空間、監獄空間、平面図空間
・管理しやすいためには、効率よく見えることが大切
・日本の家庭空間:プライバシーという概念がなかった。
・ふすまを開けると、大広間になり部屋がつながった。
・縁側という、人がつながる場をつくった。
・聞こえていても聞こえていないふりをしているあいだに本当に聞こえなくなる
(選択的注意・選択的不注意)
・子どもは空間を絵巻物のように見ていた⇒小3くらいで平面空間を認知する。
・子どもが存在するのが学校空間だけになっていく
⇒タブーをつくる「あんたのため」(国親思想):川や海に近づいては危ないからダメ。
3 人間(じんかん)
・学校は日本人を作らなければいけなかった⇒基準(言葉・行動)をつくる
・言葉を合わせる、ルールを守る。
・制服:すべて軍服。学ラン=日露戦争の軍服、セーラー服=イギリス水兵隊
~~~ここまで講演メモ。
なるほどな~。
「学校化」社会って今までも聞いたことがあったのだけど、
そういうことか~。
地域コミュニティとか
駄菓子屋とか
サードプレイスとか
本屋とか
そういうのがなぜ必要なのかっていうことが
説明できるようになるって楽しい。
そういえば僕は、
20歳になる年に大学に入り、
30歳で玉川大学に入り、
40歳で茨城大学で学んでいるなあ。
学べるってありがたい。
なぜ本屋なのか?
を説明できるようにならないといけないね。
今週もめちゃめちゃ面白かったのです・・・
ありがとうございました。
日本に住んでいる人たちはいた。
それぞれの人は藩に属していた。
脱藩した坂本竜馬はそういう意味では日本人だったかもしれないが。
富国強兵。
明治政府はその名のもと、
「軍隊」、そして「学校」を整備した。
昨日は公開講座でした。
子どもの発達(社会化)の「3つの場」と「3つの間」
3つの場というのは「学校」「地域」「家庭」
3つの間というのは「時間」「空間」「人間(じんかん)」
です。
~~~以下講義メモ
・「職の世界」(会社・学校)と「役の世界」(地域・家庭)
・「職の世界」の価値観は「お金とモノ」=比べる世界、代わりがきく。
・「役の世界」の価値観は「愛と心」=比べられない世界、代わりがきかない。
・人は「役の世界」から「職」という仮面をかぶって会社に行き、赤提灯で仮面をはがして帰ってくる
・「お金」は比べるための道具
1 時間
・「職の世界」で流れる時間と「役の世界」で流れる時間は違う
・学校時間(産業時間)=カチカチ時間(平等・うしろから追いかけてくる・量で測る)
・地域・家庭時間(民俗時間)=サラサラ時間(不平等・深さがある・伸び縮みする)
・学校と軍隊は双子の兄弟
・学校はよき「日本人」=兵隊あるいは企業戦士になるために設計された。
・休んじゃダメ=いい企業人になるためのプログラム
・学校にいると比べられないもの(ヒト)を比べられるように錯覚する
・比べられても負けない力を身につけるのが学校
・学校=管理時間・平面時間
・地域には民俗時間が流れていた。「どんどん焼き」「節分」「七五三」
・これらの「行事」は時間の区切り=通過儀式として行われた。
・お祭りでも役割がだんだん上がっていった。
・比べられない時間がそこには流れていた。
・地域の行事を、学校が奪っていく。「学芸会」「運動会」「音楽祭」
・通過儀式さえも学校が奪っていったのが現在。例:「2分の1成人式」
・カチカチ時間だけではゆったりと生きられない。
⇒サードプレイスっていうのはサラサラ時間が流れる場所
2 空間
・学校=機能空間、管理空間、監獄空間、平面図空間
・管理しやすいためには、効率よく見えることが大切
・日本の家庭空間:プライバシーという概念がなかった。
・ふすまを開けると、大広間になり部屋がつながった。
・縁側という、人がつながる場をつくった。
・聞こえていても聞こえていないふりをしているあいだに本当に聞こえなくなる
(選択的注意・選択的不注意)
・子どもは空間を絵巻物のように見ていた⇒小3くらいで平面空間を認知する。
・子どもが存在するのが学校空間だけになっていく
⇒タブーをつくる「あんたのため」(国親思想):川や海に近づいては危ないからダメ。
3 人間(じんかん)
・学校は日本人を作らなければいけなかった⇒基準(言葉・行動)をつくる
・言葉を合わせる、ルールを守る。
・制服:すべて軍服。学ラン=日露戦争の軍服、セーラー服=イギリス水兵隊
~~~ここまで講演メモ。
なるほどな~。
「学校化」社会って今までも聞いたことがあったのだけど、
そういうことか~。
地域コミュニティとか
駄菓子屋とか
サードプレイスとか
本屋とか
そういうのがなぜ必要なのかっていうことが
説明できるようになるって楽しい。
そういえば僕は、
20歳になる年に大学に入り、
30歳で玉川大学に入り、
40歳で茨城大学で学んでいるなあ。
学べるってありがたい。
なぜ本屋なのか?
を説明できるようにならないといけないね。
今週もめちゃめちゃ面白かったのです・・・
ありがとうございました。
2015年06月09日
私が時代の先頭に立つ、と決める
「成功者は想いを5分ごとに確認する。」
福島正伸さんの本のメッセージ。
目にしたのは新潟の紀伊國屋書店。
1998年6月発売だから、大学4年生になったばかり。
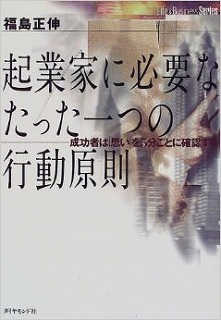
あの日、僕の読書人生が始まった。
「5分ごとに確認するんだ!」
という衝撃。
その一言で「この本、買わなきゃ」と思った。
一言に1500円の価値があると思う。
昨日も、そんな本を見つけた。
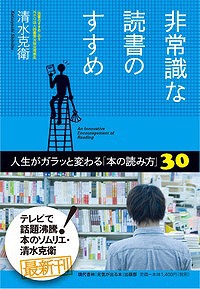
「非常識な読書のすすめ」(清水克衛 現代書林)
あの業界では有名な「読書のすすめ」の清水さんの本。
開いた瞬間。
飛び込んでくる。
「私が時代の先頭に立つ、と決める。」
いいですね。
清水さんの志は
「日本一の本屋になる!」でした。
それを言い続けて、
いまや日本一の本屋になってます。
「日本一」というのはいろいろあると思いますが、
「読書のすすめ」が日本一の本屋だと言って、
うなずく人はめちゃめちゃたくさんいると思います。
まあ。
「日本一の本屋」ってたくさんあると思うんですけどね。
僕の中でも
日本一の本屋って聞かれたら、
10個くらい出てきますからね。
ブックスキューブリック箱崎店(福岡)
井戸書店(神戸)
スタンダードブックストア心斎橋店(大阪)
・・・などなど
と続きますね。
たぶん新潟の北書店とかも日本一だと言う人多いんじゃないかな。
ということで。
今回のフレーズは、
「日本一になると決める」ではなく、
「時代の先頭に立つと決める」というところがポイントなのではないか、
と思います。
未来がどうなるかわからないこの時代。
誰もが時代の先頭を走っている可能性がある。
だから。
自分が時代の先頭に立つと決める。
これが大切なのだと思います。
その上で、
「目的」と「手段」を考える。
⇒戦略を立てることが大切なのだなあと。
「目的は何か」を考え抜くこと(2014年3月28日)
http://hero.niiblo.jp/e390417.html
より抜粋。
「よい戦略」とは
「目的と手段」が現状分析に基づいて
それぞれ適切に「選択」され「集中」されているもの
僕にとって、
「目的」は
「夢・目標を持て」的な
キャリアデザイン一辺倒から脱し、
「とりあえずやってみる」的な
キャリアドリフト思想を入れていく。
その中での
「とりあえずやってみる」へのハードルを下げる。
それは、
才能思考から成長思考への変化。
やれば、できるかもしれない。
というマインド。
それには、過去を見つめることも大切なのかもしれない。
あるいは友人たちとともに取り組むことが大切なのかもしれない。
場の力が重要なのかもしれない。
年寄りからの愛が大切なのかもしれない。
そこをもうちょっと考えていかなきゃね。
とにかく。
私が時代の先頭に立つと決めようか。
福島正伸さんの本のメッセージ。
目にしたのは新潟の紀伊國屋書店。
1998年6月発売だから、大学4年生になったばかり。
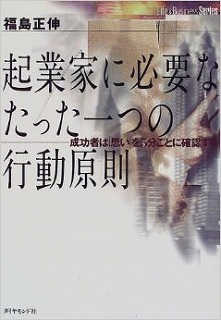
あの日、僕の読書人生が始まった。
「5分ごとに確認するんだ!」
という衝撃。
その一言で「この本、買わなきゃ」と思った。
一言に1500円の価値があると思う。
昨日も、そんな本を見つけた。
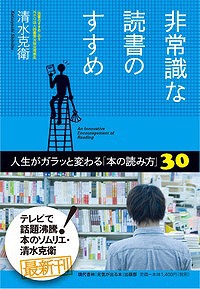
「非常識な読書のすすめ」(清水克衛 現代書林)
あの業界では有名な「読書のすすめ」の清水さんの本。
開いた瞬間。
飛び込んでくる。
「私が時代の先頭に立つ、と決める。」
いいですね。
清水さんの志は
「日本一の本屋になる!」でした。
それを言い続けて、
いまや日本一の本屋になってます。
「日本一」というのはいろいろあると思いますが、
「読書のすすめ」が日本一の本屋だと言って、
うなずく人はめちゃめちゃたくさんいると思います。
まあ。
「日本一の本屋」ってたくさんあると思うんですけどね。
僕の中でも
日本一の本屋って聞かれたら、
10個くらい出てきますからね。
ブックスキューブリック箱崎店(福岡)
井戸書店(神戸)
スタンダードブックストア心斎橋店(大阪)
・・・などなど
と続きますね。
たぶん新潟の北書店とかも日本一だと言う人多いんじゃないかな。
ということで。
今回のフレーズは、
「日本一になると決める」ではなく、
「時代の先頭に立つと決める」というところがポイントなのではないか、
と思います。
未来がどうなるかわからないこの時代。
誰もが時代の先頭を走っている可能性がある。
だから。
自分が時代の先頭に立つと決める。
これが大切なのだと思います。
その上で、
「目的」と「手段」を考える。
⇒戦略を立てることが大切なのだなあと。
「目的は何か」を考え抜くこと(2014年3月28日)
http://hero.niiblo.jp/e390417.html
より抜粋。
「よい戦略」とは
「目的と手段」が現状分析に基づいて
それぞれ適切に「選択」され「集中」されているもの
僕にとって、
「目的」は
「夢・目標を持て」的な
キャリアデザイン一辺倒から脱し、
「とりあえずやってみる」的な
キャリアドリフト思想を入れていく。
その中での
「とりあえずやってみる」へのハードルを下げる。
それは、
才能思考から成長思考への変化。
やれば、できるかもしれない。
というマインド。
それには、過去を見つめることも大切なのかもしれない。
あるいは友人たちとともに取り組むことが大切なのかもしれない。
場の力が重要なのかもしれない。
年寄りからの愛が大切なのかもしれない。
そこをもうちょっと考えていかなきゃね。
とにかく。
私が時代の先頭に立つと決めようか。
2015年06月08日
学校教育では「正解」と「不正解」しか教えられない

「新しい道徳」(藤原和博 ちくまプリマー新書)
やっぱり藤原さんの
教育を切る視点には非常に共感するところが
多いなあと感じる。
日本は「テレビが神様」であると断じる。
テレビでもっとも大切なのは「わかりやすさ」である。
「正義の味方か悪の手先か」
「勝ち組か負け組か」
「金持ちか貧乏人か」
実際にはこの「間」の人たちが多いのに、
その多様性を無視して極論が支配する。
ニュースも、討論番組も、バラエティーでも、ドラマでさえも
短い間で子供からお年寄りまで様々な層にアピールするには
「二項対立」が有効なのだ。
したがって、
テレビの過剰視聴は、
頭の中身まで「二項対立」
にしてしまう。
「味方か敵か」
「好きか嫌いか」
「自分に合うか合わないか」
「役に立つか立たないか」
で物事を見てしまう。
そしてテレビは
その二項対立をより強化する役割を果たす。
かくしてテレビは神様になった。
そしてその「テレビ教」を
学校の正解主義が支えているのだと藤原さんは言う。
受験勉強でパターン認識応力を鍛えられた子供は
「正解」に弱い。
「正解」を無自覚に受け入れてしまう特性を持ってしまうからだ。
そしてそのテレビの教えをケータイが強化する。
こうして、
テレビ、ケータイ、学校のいわゆる「テレビ教」が成立している。
なるほど。
本当は正解と不正解のあいだに
無限の多様な解が広がっているのだよなあ。
それをどう実感していくか。
やはり、地域の力だな。
多様な大人、多様な地域に出会うこと、感じること。
正解がひとつではないこと。
自分で考えるしかないということ。
「自然農」との出会いは僕にとって、
ゴールであり、出発点だった。
僕自身が「自分がやるべき農業のスタイルは何か?」
という問いへの正解を探し続けていた。
「正解などない。畑に立てば自然とわかるようになる」
徳島の沖津さんからそう学んだ夏。
あれからすでに17年の時が過ぎた。
2015年06月06日
「融合」という第3の道
今週の「茨城学」で取り上げられた
日本近代美術の父、岡倉天心に心を奪われた。
授業中のメモと、
「茨城学」の担当教員である清水先生が書かれた
「五浦の岡倉天心と日本美術院」(茨城大学五浦美術文化研究所)
を読みながら、いまこそ岡倉天心なのではないか、と感じた。
横浜で育った幼少時代から異国の文化に触れ、
東京美術学校(現:東京芸術大学)の
設立のために美術取調委員としてヨーロッパを視察。
その時に
西洋の美術は、表現の違いこそあれ、
同じ愛と共感で訴えてくる、といい、
東洋の美術と西洋の美術は融合することができると説いた。
つまり
「東洋」と「西洋」は「共感」によって
両文化の間に横たわる溝を飛び越え
「融合する」このと可能性を実感した。
しかしながら、東京芸術学校は、
西洋美術にシフトしていったため、
岡倉は校長を辞し、日本美術院を創設する。
しかしながら、すぐに財政苦境に陥り、
挫折を味わった。
そんなときに岡倉はインドを旅し、
素晴らしい出会いを果たすのである。
ひとりはインドの僧ヴィヴェーカーナンダであり、
もうひとりは詩人のタゴールである。
ヴィヴェーカーナンダは、
宗教は多様性と二元性を経て
究極の単一性に到達することだと説いた。
これに感銘を受けた岡倉の中に、
美術だけではなく、「芸術」と「宗教」も
融合していくという思想が生まれた。
日本美術のベースを維持しながらも、
西洋美術を取り入れ、新しいものを
つくっていこうとしていた岡倉の大きな出来事であった。
詩人タゴールとの出会いも、
その思いを強くさせた。
西洋と東洋のそれぞれに「普遍的要素」がある
それを生かしあいながら新しいものをつくっていくこと。
岡倉は「茶の本」でそれを茶に託した。
~~~ここから引用
東西両大陸が、互いに悪口を言い合うのはやめにしましょう
互いが、両半球から得ることによって、
もっと賢くなるとはいかないまでも、
もっと憐みの心を持とうではありませんか。
私たちは異なる道筋をたどって発展してきましたが、
互いに足りないところを補いあってはいけない理由はありません。
あなたがたは、安息という代償を払って膨張してきました。
私たちは侵略に対しては非力ですが、調和というものを生み出してきました。
あなたたちは信じられますか。
東洋はある点で西洋よりもすぐれているということを!
実に不思議なことですが、人間性(ヒューマニティー)は、
これまで茶碗の中で出会っていたのです。
それは、万人が尊敬を払う唯一のアジアの儀式です。
白人は、私たちの宗教や道徳を嘲笑してきましたが、
この褐色の飲み物は、躊躇せず受け入れてきました。
今日、アフタヌーン・ティーは、
西洋社会で重要な役割を果たしています。
盆や茶托が微かに触れあう音、
もてなす夫人の柔らかな衣ずれの音、
クリームや砂糖についてのよくある問答の中に、
私たちは、疑いなく「茶の崇拝」が確立されていることを知るのです。
(『茶の本』第一章)
~~~ここまで引用
岡倉天心は、「茶」の中に西洋と東洋の融合・調和を見た。
茶は中国に始まり、インドを経て、ヨーロッパに渡った。
同時に日本にも茶道として確立されてきた。
そこに「融合」を見たことで、
岡倉の五浦での六角堂建設へとつながっていく。
五浦で見ていたものは、
日本・中国・インド・そして西洋の融合だった。
いやあ。
熱いね、熱い。
茨城で学ぶものはまずここからですね。
「Think globally Act locally」ということだけではなく。
岡倉は常に世界を見ていた。
そして世界と対話していた。
1900年代初頭。
アジア諸国が欧米列強に次々と植民地化されていく中で、
岡倉が世界に伝えたかったことはなんだろう?
東洋と西洋は融合できる。
白か黒か。
右か左か。
東か西か。
ではなく第3の道、融合がそこにはあったはずだ。
いやあ、五浦、行かなきゃだな。
日本近代美術の父、岡倉天心に心を奪われた。
授業中のメモと、
「茨城学」の担当教員である清水先生が書かれた
「五浦の岡倉天心と日本美術院」(茨城大学五浦美術文化研究所)
を読みながら、いまこそ岡倉天心なのではないか、と感じた。
横浜で育った幼少時代から異国の文化に触れ、
東京美術学校(現:東京芸術大学)の
設立のために美術取調委員としてヨーロッパを視察。
その時に
西洋の美術は、表現の違いこそあれ、
同じ愛と共感で訴えてくる、といい、
東洋の美術と西洋の美術は融合することができると説いた。
つまり
「東洋」と「西洋」は「共感」によって
両文化の間に横たわる溝を飛び越え
「融合する」このと可能性を実感した。
しかしながら、東京芸術学校は、
西洋美術にシフトしていったため、
岡倉は校長を辞し、日本美術院を創設する。
しかしながら、すぐに財政苦境に陥り、
挫折を味わった。
そんなときに岡倉はインドを旅し、
素晴らしい出会いを果たすのである。
ひとりはインドの僧ヴィヴェーカーナンダであり、
もうひとりは詩人のタゴールである。
ヴィヴェーカーナンダは、
宗教は多様性と二元性を経て
究極の単一性に到達することだと説いた。
これに感銘を受けた岡倉の中に、
美術だけではなく、「芸術」と「宗教」も
融合していくという思想が生まれた。
日本美術のベースを維持しながらも、
西洋美術を取り入れ、新しいものを
つくっていこうとしていた岡倉の大きな出来事であった。
詩人タゴールとの出会いも、
その思いを強くさせた。
西洋と東洋のそれぞれに「普遍的要素」がある
それを生かしあいながら新しいものをつくっていくこと。
岡倉は「茶の本」でそれを茶に託した。
~~~ここから引用
東西両大陸が、互いに悪口を言い合うのはやめにしましょう
互いが、両半球から得ることによって、
もっと賢くなるとはいかないまでも、
もっと憐みの心を持とうではありませんか。
私たちは異なる道筋をたどって発展してきましたが、
互いに足りないところを補いあってはいけない理由はありません。
あなたがたは、安息という代償を払って膨張してきました。
私たちは侵略に対しては非力ですが、調和というものを生み出してきました。
あなたたちは信じられますか。
東洋はある点で西洋よりもすぐれているということを!
実に不思議なことですが、人間性(ヒューマニティー)は、
これまで茶碗の中で出会っていたのです。
それは、万人が尊敬を払う唯一のアジアの儀式です。
白人は、私たちの宗教や道徳を嘲笑してきましたが、
この褐色の飲み物は、躊躇せず受け入れてきました。
今日、アフタヌーン・ティーは、
西洋社会で重要な役割を果たしています。
盆や茶托が微かに触れあう音、
もてなす夫人の柔らかな衣ずれの音、
クリームや砂糖についてのよくある問答の中に、
私たちは、疑いなく「茶の崇拝」が確立されていることを知るのです。
(『茶の本』第一章)
~~~ここまで引用
岡倉天心は、「茶」の中に西洋と東洋の融合・調和を見た。
茶は中国に始まり、インドを経て、ヨーロッパに渡った。
同時に日本にも茶道として確立されてきた。
そこに「融合」を見たことで、
岡倉の五浦での六角堂建設へとつながっていく。
五浦で見ていたものは、
日本・中国・インド・そして西洋の融合だった。
いやあ。
熱いね、熱い。
茨城で学ぶものはまずここからですね。
「Think globally Act locally」ということだけではなく。
岡倉は常に世界を見ていた。
そして世界と対話していた。
1900年代初頭。
アジア諸国が欧米列強に次々と植民地化されていく中で、
岡倉が世界に伝えたかったことはなんだろう?
東洋と西洋は融合できる。
白か黒か。
右か左か。
東か西か。
ではなく第3の道、融合がそこにはあったはずだ。
いやあ、五浦、行かなきゃだな。





