2018年02月28日
「サードプレイス」から「アナザー・バリュー・スペース」へ
「サードプレイス」とは、本当は何なのか?
「サードプレイス」は、本当に必要なのか?
昨日の「有縁」「無縁」の話を受けて、
考えたこと。
「無縁」社会とは、「有縁」社会のように、
一人ひとりが縁を結ばず、金だけが支配している社会で、
だからこそ、そこには中央権力が定める法律も及ばないし、
世俗のしきたりも希薄である。
しかし、それが
「有縁」社会のセーフティネットになっている。
つまり、有縁社会からはじき出されても、
行く場所があるということ。死ななくてもよいということ。
有縁社会は無縁社会を必要とし、
無縁社会はまた有縁社会を必要としている。
これを、現代に当てはめるとなんだろうか。
「非日常空間」が必要だと言われる。
あるいは、「非日常体験」が観光にとって重要だと言われる。
たとえば、家族と温泉に行く。
たとえば、デートでテーマパークに行く。
あれは「非日常空間」だろうか。
たとえば、ひとりでカフェに行く。
たとえば、仲間と行きつけの居酒屋に行く。
それは、近すぎて「日常空間」だろうか。
川崎・新城劇場のミーティングで、
「居心地のいい場所」というテーマで話した時、
「カフェにいる時間」だと答えたメンバーに、
どうして?と聞いたら、
カフェに入って、飲み物を目の前にしたとき、
その瞬間、「目的・目標」から解放された、と
感じるからだという。
メモをとったり、手紙を書いたりするらしいのだけど。
あの話を思い出した。
非日常空間、あるいは、サードプレイスとは、
日常とは異なる価値観が支配する空間であり、
その場に身をおくことは、根源的に大切なことなのではないか。
上記の彼女がカフェに行くのは、
「目的・目標から解放された空間」に身を置きたいからではないか。
そういう意味では、ストレス解消のため1泊2日で温泉に行く、とか
乗り物による刺激やスリル、大量の消費をするために行くテーマパークは、
「日常の価値観(効率化や消費第一主義)」のまま、
時間を過ごしていることにならないだろうか。
もちろん、コンセプトのあるホテルや、歴史ある温泉旅館、
思いや祈りのこもったテーマパークでは、ある程度の非日常を味わえるだろう。
そうか。
「日常」と「非日常」を決めるのは、
場所そのものではなくて、
場所に込められた思いや歴史などの
「価値観」なのではないかと。
休みの日に、
団体スポーツを楽しんだり、
ひとりで山に登ったり、
酒を飲みに行ったり、
もしくはギャンブルをしたりするのは、
そこが、違う価値観が支配する空間だからじゃないのか。
本当に必要なのは、
「サードプレイス」という場所ではなく、
「アナザー・バリュー・スペース(タイム)」
とでもいうのか、
日常とは異なる価値観に
支配される場や空間、時間ではないか。
そして、その価値観は、必ずしも
明確に言語化される必要はなくて、
それをなんとなく感じられればいいのだと思う。
福島県白河市のカフェ・エマノンには、
言語化されない「ベクトル感」があり、
それを感じたくて高校生は集うのだろうと思う。
次は「ベクトル感」について書こうかな。
「サードプレイス」は、本当に必要なのか?
昨日の「有縁」「無縁」の話を受けて、
考えたこと。
「無縁」社会とは、「有縁」社会のように、
一人ひとりが縁を結ばず、金だけが支配している社会で、
だからこそ、そこには中央権力が定める法律も及ばないし、
世俗のしきたりも希薄である。
しかし、それが
「有縁」社会のセーフティネットになっている。
つまり、有縁社会からはじき出されても、
行く場所があるということ。死ななくてもよいということ。
有縁社会は無縁社会を必要とし、
無縁社会はまた有縁社会を必要としている。
これを、現代に当てはめるとなんだろうか。
「非日常空間」が必要だと言われる。
あるいは、「非日常体験」が観光にとって重要だと言われる。
たとえば、家族と温泉に行く。
たとえば、デートでテーマパークに行く。
あれは「非日常空間」だろうか。
たとえば、ひとりでカフェに行く。
たとえば、仲間と行きつけの居酒屋に行く。
それは、近すぎて「日常空間」だろうか。
川崎・新城劇場のミーティングで、
「居心地のいい場所」というテーマで話した時、
「カフェにいる時間」だと答えたメンバーに、
どうして?と聞いたら、
カフェに入って、飲み物を目の前にしたとき、
その瞬間、「目的・目標」から解放された、と
感じるからだという。
メモをとったり、手紙を書いたりするらしいのだけど。
あの話を思い出した。
非日常空間、あるいは、サードプレイスとは、
日常とは異なる価値観が支配する空間であり、
その場に身をおくことは、根源的に大切なことなのではないか。
上記の彼女がカフェに行くのは、
「目的・目標から解放された空間」に身を置きたいからではないか。
そういう意味では、ストレス解消のため1泊2日で温泉に行く、とか
乗り物による刺激やスリル、大量の消費をするために行くテーマパークは、
「日常の価値観(効率化や消費第一主義)」のまま、
時間を過ごしていることにならないだろうか。
もちろん、コンセプトのあるホテルや、歴史ある温泉旅館、
思いや祈りのこもったテーマパークでは、ある程度の非日常を味わえるだろう。
そうか。
「日常」と「非日常」を決めるのは、
場所そのものではなくて、
場所に込められた思いや歴史などの
「価値観」なのではないかと。
休みの日に、
団体スポーツを楽しんだり、
ひとりで山に登ったり、
酒を飲みに行ったり、
もしくはギャンブルをしたりするのは、
そこが、違う価値観が支配する空間だからじゃないのか。
本当に必要なのは、
「サードプレイス」という場所ではなく、
「アナザー・バリュー・スペース(タイム)」
とでもいうのか、
日常とは異なる価値観に
支配される場や空間、時間ではないか。
そして、その価値観は、必ずしも
明確に言語化される必要はなくて、
それをなんとなく感じられればいいのだと思う。
福島県白河市のカフェ・エマノンには、
言語化されない「ベクトル感」があり、
それを感じたくて高校生は集うのだろうと思う。
次は「ベクトル感」について書こうかな。
2018年02月27日
「負債感」と「当事者意識」

「21世紀の楕円幻想論」(平川克美 ミシマ社)
第4章まで来ました。
「有縁」社会と「無縁」社会。
第3章の途中から、
さらに面白くなってきました。
場、近代、縁などなど、
僕のキーワードにピッタリです。
いちばんハッとさせられたのは、
この章の冒頭にある「賭場の論理、世俗の論理」。
カジノ法案、是か非か、みたいな。
まあ、政治っていうのは決めることだからいいのだけど、
1つの価値観でもって、それをどちらか決めるのはどうなんだと。
平川さんが言うように、
~~~以下引用
酒やたばこ、あるいはギャンブルを楽しむという社会と、
酒やたばこは身体に良くない、
ギャンブルは依存症をつくりからダメだという社会と、
比較してどちらに同意するんだと迫るのは、
思考停止だといわざるを得ないのです。
こうした、思考停止による二者択一は、
文化的なふるまいから逸脱した、
生活の強制へと向かってしまいます。
そもそも、相反する二つの事項、
異なった原理を有する二つの事項について
考えるときに、どちらか一方だけに
収斂させれば問題は解決すると考えるのは、
成熟した大人がやるべきことではない。
~~~以上引用
なるほど。
僕もそう思います。
そして、賭場の原理を以下のように説明します。
~~~以下引用
賭場の原理というのは、
人情無縁の「無縁」の原理なんです。
一人ひとりが縁を結ばず、金だけが支配している社会です。
だからこそそこには中央権力が定める法律も及ばないし、
世俗のしきたりも希薄である。
そういう逃げ場がないと、
世俗の社会をはじきだされたものは、
死ぬしかなくなってしまいます。
共同体が存続していくために必要なことは、
脱落者を出さないことです。
(中略)
だから、「無縁」の原理を必要としているのは、
「有縁」の場なのであり、「有縁」の原理もまた
「無縁」の場が必要としているともいえるだろうと思います。
~~~以上引用
「駆け込み寺」っていうのは、
中央権力、幕府の権力が及ばないところでした。
そうやって、
「有縁」と「無縁」がうまくかみ合って、
世の中は存在していたのではないかと。
平川さんの言葉を借りれば、
宗教的な場は「許し」の場であり、
世俗の場は、「贖罪」と「許し」がせめぎあう場であり、
ビジネスは厳格な等価交換の場だということです。
なるほどね。
世の中が「ビジネスの場」で一元化されちゃうと
それはつらいですね。
「相互扶助では儲からない」
これはたしかにそうなんでしょう。
友達から本を借りて読むより、
古本屋で安く本買うより、
新刊書店で定価で買ってもらったほうが儲かるもんね。
そうやって、だんだんと「無縁社会」へとシフトしていった。
でも、そこに惹かれた若者たちって
なんだったのだろう。
「東京には夢がある」って思って、
田舎から出てきて、高いアパート家賃を払って、
家賃を払うためにアルバイトして、
J-POPを聞きながら、途方に暮れる、みたいな暮らし。
ホントにしたかったのかな、って。
挙句に、「自己責任」とか言われちゃって。
「無縁社会」を象徴するような言葉です。
「自己責任」。
平川さんが指摘しているように、
起こった結果に対して、当事者として、
自分の身に引き受けるという本来の意味ではなく、
自分には無関係であるということの言明にすぎないのです。
つまり、「俺には関係ないよ」ってことです。
~~~以下三たび引用
「責任」は、英語ではresponsibilityと言いますね。
これは、respond(応答する)と同じ語源を持つ言葉だと
いうことがわかります。
日本語なら、まさにこれは「縁」ですね。
(中略)
「縁」の世界で起きたことは、
どんなことも、どこかでつながっており、
呼びかけがあれば応答しなければならない。
すべての人間は、
程度の差はあっても当事者性から
逃れることができないということです。
まあ、面倒くさいといえば面倒ですね。
しかし、当事者性を意識するところから責任をとるという
モラルが出てくる
しかし、他者に対して「自己責任だ」と言うのは、
自分とはまったく関係がないという責任転嫁の
言明でしかありません。
~~~以上三たび引用
ここから、平川さんは、
「無縁」を否定しない「有縁」社会を提案します。
江戸時代の厳しい身分社会の中でも成立していた、
共同体の内側では、相互扶助的なものが
息づいているような社会。
たぶん。
いま、若者がシェアハウスをしたり、
メルカリでものをやり取りするのも、
あまりにも世の中が「無縁社会」なので、
なんとか生き延びていく方法論なのだろうなと思います。
なんか、いろいろ深いところで考えさせられるなと。
「縁」って「負債感」を負わせる。
「借りがある」と思わせる。
等価交換じゃない何か。
たぶんそういうのが大切なので、
当事者意識の源泉なのではないかなと思う。
中村くん星野くんと2008年に立ち上げた
「起業家留学」(byヒーローズファーム)の
キーコンセプトは「当事者意識」と「価値創造力」だった。
中小企業経営者のもとで、
「当事者意識」を育みながら、
価値について考え、価値を生み出していく
人材を育成していくこと。
なかなかいいコンセプトだったなと改めて思う。
「志」とは、
社会や先輩方に対しての「負債感」と
責任を勝手に引き受ける「当事者意識」
からも生まれてくるのだろうなと思った。
そしてもうひとつ。
僕がいつも「顧客はだれか?」「顧客は過去にいる」
と問いかけているのは、
過去に出会った具体的な人や
過去の自分自身を顧客とすることが
もっとも当事者意識を感じることができるからではないか。
なんか、いろいろ過去が解読される感じでよいですね。
ありがとうございます。
2018年02月26日
「お金」とは、関係を「断ち切る」ためのツール

「21世紀の楕円幻想論」(平川克美 ミシマ社)
くまざわ書店南千住店の阿久津店長
のご紹介により購入。
いま100ページくらいまで読み進めましたが、
心の深いところをえぐるように来ますね。
第3章 見え隠れする贈与‐消費社会の中のコミュニズム
より、ひとまずキーワード抜粋
~~~以下抜粋
モラルとは、生き延びるための共同規範
「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」は、
マルクス主義の基本ですが、(中略)
小さな相互扶助はほとんど無意識に行われている。
皆が「自己責任」だとか言い出したら、
その社会はもはや共同体としては、崩壊している
ということだと思うのです。
社会全体が崩れるというのは、
社会の秩序を支えているモラルが
崩壊し始めているということなんです。
言葉は、他者の共生を前提にして交換されるものです。
言葉に対する相互の信頼があって初めて、
人間同士の交通が可能になります。
その意味では、言葉は貨幣に似ているのですが、
決定的に違うのは、貨幣は商品交換のための
道具であるのにたいして、言葉は、
もともと贈与のための道具だったということです。
貨幣は、それが偽札でない限りは、
それが偽札でない限りは、
それが流通している地域においては、
誰に対しても同じ価値基準を表現します。
同じ交換価値として機能しています。
一方、言葉はそれが嘘であるか、
本当であるか、傍からは、見分けがつきません。
相互に信頼し、相互に扶助し合う共同体の
内部においてのみ力を発揮するものであり、
異なった共同体や異人種とのあいだでは、
言葉はときに敵対のための道具になってしまうことが
あるのだろうと思いますね。
「自己責任」とは、まさに、
ひとつの共同体の内部が、分断され、
敵と味方に分別されたときに発声される敵対的な言葉なのです。
~~~ここまで抜粋
言葉と貨幣。
おもしろい。
つづいて、貨幣(お金)の交換性と関係性について。
「お金」とはつまり、「等価交換」のための道具である。
という前提で。
▽▽▽以下引用
贈与と返礼という
交換関係もまた、それが等価交換ではない限り、
どちらかが負債を負った状態のまま、
贈与返礼を繰り返しているということになります。
関係を続けていくためには、
返礼は等価ではいけないのです。
お金とは、関係を断ち切るための道具として
登場したということなのです。
お金:
・交換を促進する道具
・関係を断ち切る道具
交換を促進するためには、
関係を絶えず断ち切る必要があったのです。
お金を払うことによって負債関係が断ち切られる。
負いつ負われつという関係の無限連鎖を
終了するためには、等価物を返さなければならない。
等価物を返すことで、相対の関係が終了する。
じゃあ終了しない関係は何かというと、その逆です。
お金が介在しない贈与関係なんですよ。
贈与関係:
・交換を禁止すること
・関係を継続させること。
△△△ここまで引用
このあと、本では、
「消費者」の登場によって、
「近代化」という名のコミュニティの崩壊が起こる、
と続いていく。
これも書きたいけど、今日はここまで。
面白いです。
「ゆっくりいそげ」(影山知明 大和書房)と
合わせて読みたいですね。
あ、西野彰廣さんの「革命のファンファーレ」に書いてある
「お土産理論」にも近いものがあるかも。
「健全な負債感」とは何か?
そんなことが書いてあるような気がします。
楽しいね、読書。
2018年02月25日
未来を見ながら問いと共に生きる
「向き合わない」
っていうのがテーマになるのかもしれない。
うまく付き合っていく。
そんな感じ。
違和感が問いになり、
問いが仮説をつくり、
仮説を繰り返すことで志にたどりつく。
「問いがわからない。」
それなら、誰かの仮説に身を委ねてみる。
それが「インターン」の意味なのかもしれない。
経営者、特に創業した経営者は、
世の中とのコミュニケーションツールとして、
その会社を運営している。
つまり、仕事は、言語だ。
自分の中の問いに出会うための
もうひとつのパワフルな方法は、
「お客に出会う」ことだ。
この人のために何かしたい。
何ができるか?
という人に出会うこと。
僕にとっては
2002年に出会った15歳のシンタロウくんだったわけだけど。
「15歳が自分と住んでいる地域を好きになり、
自分と社会の未来創造へ向けて歩き出している
地域社会を実現します。」
ツイッターの自己紹介文。
その原点は彼との出会いにある。
これはもうミッションでもあるのだけど、
それはそのまま問いでもある。
その方法はめちゃめちゃあるわけだから。
15歳が自分を好きになるには?
好きになれないのはなぜか?
みたいなところから始まって、
未来創造ってどういうこと?
地域社会ってどのくらいの広さの範囲?
と、いろいろと広がっていく。
僕がツルハシブックス時代に感じていた
「違和感」というか、なぜ?は、
「やりたいことがわからない」
「自分に自信がない」
という相談に来る大学生が多かったこと。
僕が感じていたのは、
現在の夢至上主義的なキャリア教育のあり方という
社会側からのアプローチと、
社会構造の変化に伴う
個人のアイデンティティと承認欲求という
個人側からのアプローチだった。
中越地震ボランティアで感じたのは、
承認欲求が東京から無職の若者を
ボランティアに惹きつけているのではないか、ということ。
山竹伸二さんのいう
「一般的承認」(世の中でよいとされていることをすることで認められる)
がそこにはあったから。
しかし、大切なのは、
かつて家庭で育まれていたはずの
「親和的承認」(ありのままの自分を受け入れてもらうこと)
ではないか。
そしてそれは、地域でカバーできないだろうか?
そんな思いもあって、ツルハシブックスはできている。
新潟市と連携した若者支援のプロジェクトでは、
「ほめる」ことに対する強烈な違和感を感じた。
「リスペクト」とは、「フラットな関係」とは、なんだろうか?
と問いかけた。
大学生の「やりたいことがわからない」「自信がない」問題も、
「学校化社会」などさまざまな要因による
アイデンティティと承認欲求の問題にいきあたる。
それをどうクリアしていくか。
そうやって、
問いに向き合うというよりは、
問いを抱きながら生きるというか、
問いと共に生きてきた。
いまの問いは、おそらく、
この前から出ている「サードプレイス」ではないかな。
「サードプレイス」は本当に必要なのか?
そもそも、「サードプレイス」の機能は何か?
なぜ必要なのか?
そんな問い。
僕としては、これも、承認欲求とアイデンティティの問題に
近くなると思う。
人は誰でも承認されたい。
話を聞いてもらいたい。
そうやって、アイデンティティを形成していく。
http://hero.niiblo.jp/e249757.html
「貢献できるコミュニティがあるという幸せ」(13.3.28)
たぶん、居場所を欲するというのは、
承認される場所を欲しているということ。
親和的承認(前出)ではなく、
集団的承認(役割を果たすことで認められる)
しか学校や職場では得られないので、
親和的承認を満たす場所として、
第3の場所が必要なのではないか。
僕が32歳で教育実習した中学校の生徒たちも
美術部や音楽部が居場所になっているように見えた。
いま、サードプレイスというお題をもらい、
その問いと共に生きている。
それを共にするのがチームであり、
http://hero.niiblo.jp/e485003.html
「チームとは問いを共有すること」(17.6.8)
そんな風にして生きていくことで、
志につながるかもしれない。
なんか、とりとめなく書いてしまった。
また整理します。
っていうのがテーマになるのかもしれない。
うまく付き合っていく。
そんな感じ。
違和感が問いになり、
問いが仮説をつくり、
仮説を繰り返すことで志にたどりつく。
「問いがわからない。」
それなら、誰かの仮説に身を委ねてみる。
それが「インターン」の意味なのかもしれない。
経営者、特に創業した経営者は、
世の中とのコミュニケーションツールとして、
その会社を運営している。
つまり、仕事は、言語だ。
自分の中の問いに出会うための
もうひとつのパワフルな方法は、
「お客に出会う」ことだ。
この人のために何かしたい。
何ができるか?
という人に出会うこと。
僕にとっては
2002年に出会った15歳のシンタロウくんだったわけだけど。
「15歳が自分と住んでいる地域を好きになり、
自分と社会の未来創造へ向けて歩き出している
地域社会を実現します。」
ツイッターの自己紹介文。
その原点は彼との出会いにある。
これはもうミッションでもあるのだけど、
それはそのまま問いでもある。
その方法はめちゃめちゃあるわけだから。
15歳が自分を好きになるには?
好きになれないのはなぜか?
みたいなところから始まって、
未来創造ってどういうこと?
地域社会ってどのくらいの広さの範囲?
と、いろいろと広がっていく。
僕がツルハシブックス時代に感じていた
「違和感」というか、なぜ?は、
「やりたいことがわからない」
「自分に自信がない」
という相談に来る大学生が多かったこと。
僕が感じていたのは、
現在の夢至上主義的なキャリア教育のあり方という
社会側からのアプローチと、
社会構造の変化に伴う
個人のアイデンティティと承認欲求という
個人側からのアプローチだった。
中越地震ボランティアで感じたのは、
承認欲求が東京から無職の若者を
ボランティアに惹きつけているのではないか、ということ。
山竹伸二さんのいう
「一般的承認」(世の中でよいとされていることをすることで認められる)
がそこにはあったから。
しかし、大切なのは、
かつて家庭で育まれていたはずの
「親和的承認」(ありのままの自分を受け入れてもらうこと)
ではないか。
そしてそれは、地域でカバーできないだろうか?
そんな思いもあって、ツルハシブックスはできている。
新潟市と連携した若者支援のプロジェクトでは、
「ほめる」ことに対する強烈な違和感を感じた。
「リスペクト」とは、「フラットな関係」とは、なんだろうか?
と問いかけた。
大学生の「やりたいことがわからない」「自信がない」問題も、
「学校化社会」などさまざまな要因による
アイデンティティと承認欲求の問題にいきあたる。
それをどうクリアしていくか。
そうやって、
問いに向き合うというよりは、
問いを抱きながら生きるというか、
問いと共に生きてきた。
いまの問いは、おそらく、
この前から出ている「サードプレイス」ではないかな。
「サードプレイス」は本当に必要なのか?
そもそも、「サードプレイス」の機能は何か?
なぜ必要なのか?
そんな問い。
僕としては、これも、承認欲求とアイデンティティの問題に
近くなると思う。
人は誰でも承認されたい。
話を聞いてもらいたい。
そうやって、アイデンティティを形成していく。
http://hero.niiblo.jp/e249757.html
「貢献できるコミュニティがあるという幸せ」(13.3.28)
たぶん、居場所を欲するというのは、
承認される場所を欲しているということ。
親和的承認(前出)ではなく、
集団的承認(役割を果たすことで認められる)
しか学校や職場では得られないので、
親和的承認を満たす場所として、
第3の場所が必要なのではないか。
僕が32歳で教育実習した中学校の生徒たちも
美術部や音楽部が居場所になっているように見えた。
いま、サードプレイスというお題をもらい、
その問いと共に生きている。
それを共にするのがチームであり、
http://hero.niiblo.jp/e485003.html
「チームとは問いを共有すること」(17.6.8)
そんな風にして生きていくことで、
志につながるかもしれない。
なんか、とりとめなく書いてしまった。
また整理します。
2018年02月23日
違和感から問いへ。問いから仮説へ。仮説と志のあいだ。
なんのためにうまれて
なにをしていきるのか。
こたえられないなんて
そんなのはいやだ
なにがきみのしあわせ
なにをしてよろこぶ
わからないままおわる
そんなのはいやだ
(アンパンマンのマーチより)
これって、ドラッカーでいうところの
「ミッションは何か?」
「顧客にとって価値は何か?」
っていう問いですよね。
問いがあるね、アンパンマン。
きっと、この問いには根源的なものがあって、
きっと思春期の若者は、問いかけているのだろうと思う。
いや、40のおっさんになっても、
同じように問いはあるのだけどね。
みんな、考えないようにしているのかな。
それとも、思考停止という価値に染められてしまったのだろうか。
みんな「ミッションは何か?」
つまり、「志」を求めて
あてもなく旅をしているように思う。
しかしながら、いきなりぼんやりと、
「自分のミッションとはなんだろう?」って
考えても、何から考えていいかわからないだろうし、
私たちは、宗教の開祖ではないから、
天命というものが空から降ってくるわけでもない。
一発で見つけようとせずに、
「志」はこれなんじゃないか?
という仮説を立てて、実行すること、
そして振り返ること、この繰り返しでしかないと思う。
僕は高校1年の時、クラス最下位を取るくらいに劣等生だったのだけど、
3年の時に市立図書館で「沙漠緑化に生命を賭けて」という本に出会い、
著者である遠山正英先生のいる、鳥取大学農学部が第一志望となって、
そこから受験勉強を開始した。
僕のミッションは砂漠の緑化だと、本気で思っていた。
まあ、結果は、新潟大学農学部に入ったのだけど。
2002年1月には、不登校の中学3年生に出会って、
最初はぜんぜんしゃべらなかった彼が、
だんだんと心を開いてきて、話をするようになった。
そのとき感じが強烈な違和感。
「なんでだ?」って思った。
当時、僕はプータローだった。
勤めていた地ビール屋さんを9か月で退職して、ブラブラしていた。
もっと立派な大人がたくさんいるだろう。
それなのになぜ?
「違和感」が「問い」に変わる。
「問い」から仮説を立てる。
僕がプータローであることに価値があった場合。
・学校と家庭以外の地域で多様な大人に出会うことが必要なのではないか?
と考え、山形を中心に行われていた「だがしや楽校」をモデルに、
遊びと学びの寺子屋「虹のひろば」を実施した。(2005~2010)
・本を通じて、中高生と地域の大人が出会う仕組みとして、
地域の大人から寄贈してもらった本を、若者が暗やみで発掘する
地下古本コーナー「HAKKUTSU」を開始した(2011~2015)
その動きが、現在、
東京都練馬区で行っている「暗やみ本屋ハックツ」(2015~)や、
大阪市旭区の千林で行われている「こめつぶ本屋」(2017~)や
川崎市中原区の武蔵新城駅前の「新城劇場」(2017)にも設置された。
しかし、この問いに対する仮説は、これだけではなかった。
それに気づいたのは、僕が「本の処方箋」をやるようになったからだ。
「本の処方箋」は、
問診票にお気に入りの書店、最近読んでいる本や、
悩んでいることを書いてもらいながら、それに基づいて対話をし、
3冊程度の本を提案するものなのだけど。
特に大学生や20代に好評である。

本の処方箋@nabo(長野県上田市)
それをやっていて気づいたこと。
友人に、「西田さんは本を通じて人と向き合いたいんですね。」
って言われたときに、「あれっ」て思った。
向き合いたくない。
僕は話や悩みを聞くのは好きだけど、
向き合いたくはないのだ。
だから、本棚のほうを向いて、話をしているのだ。
話を聞いているフリをして、(いや、聞いてるとは思うんですが)
意識の何%かは、どんな本がいいかなって、思っている。
あとは、僕自身が、
その悩みを解決しようとするわけではなくて、
「共に悩みたい」っていう願望があるんだなと。
だから、
「向き合って、悩みを解決する」のではなく、
「向き合わずに、共に悩む」という価値を提供しているのが
「本の処方箋」なのかもしれない。
それってさ、もしかしたら
2002年の時の違和感からの問いへのひとつの仮説になっているんだ。
彼が心を開いたのは、
僕がテキトーな大人で、彼に真剣に向き合わなかったことや、
「共に悩みたい」という欲求が僕の中にもあったからではないかと。
実は中高生にとって、必要なのは、
喫茶店のマスターのような、話を聞いているようで
真剣には向き合わず、意外性のある一言をくれる大人なのではないかと。
これが第2の仮説だ。
そしてもうひとつ。
今年1月に福島県白河のカフェ「EMANON」に行って思ったこと。
http://hero.niiblo.jp/e486769.html
(「ベクトル感」を感じる 18.1.15)
高校生が集まってくるこのカフェに、何があるのか?
僕がインタビューをして、思ったのは、「ベクトル感」だった。
「ベクトル感」とは、
この人は、この方向に向かっているんだな
と感じること。
エマノンとは、そういう「名もなき」若者が、
それぞれの方向へのベクトルを持ちながら、
実験的に何かをやってみる、という場所だった。
だから、高校生が集まったのだ。
つまり、高校生は「ベクトル感」を必要としているのではないか?
これが第3の仮説だ。
2002年1月、僕は無職だった。
でも、畑をやっていた。
どうやって食っていくか?
っていうビジョンは無かったけど、
僕にはきっと、27歳ならではの「ベクトル感」があった。
以上3つの仮説は、
2002年の時に感じた「違和感」から始まった「問い」に対するものだ。
この「仮説」を実行してみる。
それを繰り返すと、
人は「志」を手に入れられるのではないだろうか。
僕だったらこの3つを総合した場をつくるのだ。
・地域の多様な大人に出会える場
・悩みに対しては「共に悩む」という姿勢で臨む
・「ベクトル感」のある大人を呼んでイベントをする
などなど。
そういう場を中高生は必要としている。
たぶんね。
仮説だから、わからないけど。
仮説と志って、同じようなものではないかな。
志を持てば、人生は学問になる、ですよね、深谷さん?
なにをしていきるのか。
こたえられないなんて
そんなのはいやだ
なにがきみのしあわせ
なにをしてよろこぶ
わからないままおわる
そんなのはいやだ
(アンパンマンのマーチより)
これって、ドラッカーでいうところの
「ミッションは何か?」
「顧客にとって価値は何か?」
っていう問いですよね。
問いがあるね、アンパンマン。
きっと、この問いには根源的なものがあって、
きっと思春期の若者は、問いかけているのだろうと思う。
いや、40のおっさんになっても、
同じように問いはあるのだけどね。
みんな、考えないようにしているのかな。
それとも、思考停止という価値に染められてしまったのだろうか。
みんな「ミッションは何か?」
つまり、「志」を求めて
あてもなく旅をしているように思う。
しかしながら、いきなりぼんやりと、
「自分のミッションとはなんだろう?」って
考えても、何から考えていいかわからないだろうし、
私たちは、宗教の開祖ではないから、
天命というものが空から降ってくるわけでもない。
一発で見つけようとせずに、
「志」はこれなんじゃないか?
という仮説を立てて、実行すること、
そして振り返ること、この繰り返しでしかないと思う。
僕は高校1年の時、クラス最下位を取るくらいに劣等生だったのだけど、
3年の時に市立図書館で「沙漠緑化に生命を賭けて」という本に出会い、
著者である遠山正英先生のいる、鳥取大学農学部が第一志望となって、
そこから受験勉強を開始した。
僕のミッションは砂漠の緑化だと、本気で思っていた。
まあ、結果は、新潟大学農学部に入ったのだけど。
2002年1月には、不登校の中学3年生に出会って、
最初はぜんぜんしゃべらなかった彼が、
だんだんと心を開いてきて、話をするようになった。
そのとき感じが強烈な違和感。
「なんでだ?」って思った。
当時、僕はプータローだった。
勤めていた地ビール屋さんを9か月で退職して、ブラブラしていた。
もっと立派な大人がたくさんいるだろう。
それなのになぜ?
「違和感」が「問い」に変わる。
「問い」から仮説を立てる。
僕がプータローであることに価値があった場合。
・学校と家庭以外の地域で多様な大人に出会うことが必要なのではないか?
と考え、山形を中心に行われていた「だがしや楽校」をモデルに、
遊びと学びの寺子屋「虹のひろば」を実施した。(2005~2010)
・本を通じて、中高生と地域の大人が出会う仕組みとして、
地域の大人から寄贈してもらった本を、若者が暗やみで発掘する
地下古本コーナー「HAKKUTSU」を開始した(2011~2015)
その動きが、現在、
東京都練馬区で行っている「暗やみ本屋ハックツ」(2015~)や、
大阪市旭区の千林で行われている「こめつぶ本屋」(2017~)や
川崎市中原区の武蔵新城駅前の「新城劇場」(2017)にも設置された。
しかし、この問いに対する仮説は、これだけではなかった。
それに気づいたのは、僕が「本の処方箋」をやるようになったからだ。
「本の処方箋」は、
問診票にお気に入りの書店、最近読んでいる本や、
悩んでいることを書いてもらいながら、それに基づいて対話をし、
3冊程度の本を提案するものなのだけど。
特に大学生や20代に好評である。

本の処方箋@nabo(長野県上田市)
それをやっていて気づいたこと。
友人に、「西田さんは本を通じて人と向き合いたいんですね。」
って言われたときに、「あれっ」て思った。
向き合いたくない。
僕は話や悩みを聞くのは好きだけど、
向き合いたくはないのだ。
だから、本棚のほうを向いて、話をしているのだ。
話を聞いているフリをして、(いや、聞いてるとは思うんですが)
意識の何%かは、どんな本がいいかなって、思っている。
あとは、僕自身が、
その悩みを解決しようとするわけではなくて、
「共に悩みたい」っていう願望があるんだなと。
だから、
「向き合って、悩みを解決する」のではなく、
「向き合わずに、共に悩む」という価値を提供しているのが
「本の処方箋」なのかもしれない。
それってさ、もしかしたら
2002年の時の違和感からの問いへのひとつの仮説になっているんだ。
彼が心を開いたのは、
僕がテキトーな大人で、彼に真剣に向き合わなかったことや、
「共に悩みたい」という欲求が僕の中にもあったからではないかと。
実は中高生にとって、必要なのは、
喫茶店のマスターのような、話を聞いているようで
真剣には向き合わず、意外性のある一言をくれる大人なのではないかと。
これが第2の仮説だ。
そしてもうひとつ。
今年1月に福島県白河のカフェ「EMANON」に行って思ったこと。
http://hero.niiblo.jp/e486769.html
(「ベクトル感」を感じる 18.1.15)
高校生が集まってくるこのカフェに、何があるのか?
僕がインタビューをして、思ったのは、「ベクトル感」だった。
「ベクトル感」とは、
この人は、この方向に向かっているんだな
と感じること。
エマノンとは、そういう「名もなき」若者が、
それぞれの方向へのベクトルを持ちながら、
実験的に何かをやってみる、という場所だった。
だから、高校生が集まったのだ。
つまり、高校生は「ベクトル感」を必要としているのではないか?
これが第3の仮説だ。
2002年1月、僕は無職だった。
でも、畑をやっていた。
どうやって食っていくか?
っていうビジョンは無かったけど、
僕にはきっと、27歳ならではの「ベクトル感」があった。
以上3つの仮説は、
2002年の時に感じた「違和感」から始まった「問い」に対するものだ。
この「仮説」を実行してみる。
それを繰り返すと、
人は「志」を手に入れられるのではないだろうか。
僕だったらこの3つを総合した場をつくるのだ。
・地域の多様な大人に出会える場
・悩みに対しては「共に悩む」という姿勢で臨む
・「ベクトル感」のある大人を呼んでイベントをする
などなど。
そういう場を中高生は必要としている。
たぶんね。
仮説だから、わからないけど。
仮説と志って、同じようなものではないかな。
志を持てば、人生は学問になる、ですよね、深谷さん?
2018年02月21日
「顧客」は「過去」にいる
多治見でのワークショップふりかえり第2弾。
あらためて確認したこと。
「顧客」は「過去」にいる、ということ。
http://hero.niiblo.jp/e463169.html
(キャリアドリフトのゴールは、顧客に出会うこと 15.2.15)
http://hero.niiblo.jp/e476591.html
(キャリアドリフトのゴールは、「お客に出会う」ということ 16.1.28)
ぼぼ同じタイトルのブログ書いてる。笑

「経営者に贈る5つの質問」(P.F.ドラッカー ダイヤモンド社)
経営の神様、ドラッカーは問う。
1 ミッションは何か
2 顧客はだれか
3 顧客にとって価値は何か
4 成果は何か
5 計画は何か
この5つの質問に答えることが
「経営」にとって不可欠である、と。
僕は知らないうちに、
顧客はだれか、っていうワークショップを
やっていたように思う。
過去を振り返り、未来を語る。
そうやって、「顧客」を探していく。
そういうワークショップをやることで、
チーム作りも同時にできていくんじゃないか、と思いました。
つづきます。
あらためて確認したこと。
「顧客」は「過去」にいる、ということ。
http://hero.niiblo.jp/e463169.html
(キャリアドリフトのゴールは、顧客に出会うこと 15.2.15)
http://hero.niiblo.jp/e476591.html
(キャリアドリフトのゴールは、「お客に出会う」ということ 16.1.28)
ぼぼ同じタイトルのブログ書いてる。笑

「経営者に贈る5つの質問」(P.F.ドラッカー ダイヤモンド社)
経営の神様、ドラッカーは問う。
1 ミッションは何か
2 顧客はだれか
3 顧客にとって価値は何か
4 成果は何か
5 計画は何か
この5つの質問に答えることが
「経営」にとって不可欠である、と。
僕は知らないうちに、
顧客はだれか、っていうワークショップを
やっていたように思う。
過去を振り返り、未来を語る。
そうやって、「顧客」を探していく。
そういうワークショップをやることで、
チーム作りも同時にできていくんじゃないか、と思いました。
つづきます。
2018年02月20日
本のある空間という祈り
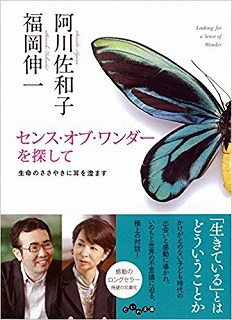
「センスオブワンダーを探して」(福岡伸一 阿川佐和子 だいわ文庫)
名古屋のちくさ正文館本店で購入。
いついってもほしい本だらけです。
今回は泣く泣く3冊に絞りました。
そのうちの1冊。
「生物と無生物のあいだ」の福岡さんと
「聞く力」の阿川さん。
対談本ってあんまり得意じゃないのだけど
この本はするする来ます。
序盤のハイライトを紹介します。
阿川さんは、石井桃子さんが始めた私設図書室「かつら文庫」
に子どものころ通っていたが、
ほかの子どもが次々と大作を読破する中で、
さんざん外で遊んだあとに、文字の少なくて絵が多い、
「せいめいのれきし」や「ちいさいおうち」などを読んでいたという。
「かつら文庫50周年の集い」で
石井さんのお弟子さんで、児童文学者の
松岡享子さんの講演で
「子どもの感受性は大人になってからでは取り返しがつかない」
と聞いて、「今から読んでも無駄なんだ」と悲しくなったのだという。
そしてトークショーで松岡さんと一緒になったとき、
思わず言ったという。
~~~以下本文より引用
「私は本当にダメな子でした。
かつら文庫に通っていたほかの子どもたちと違って、
あんまり本を読まなかったし」とお話したら、
「大丈夫よ、佐和子ちゃんはたくさん本のオーラを
浴びて育ったから、それがちゃんと残ってる」
というような言葉で励ましてくださったんです。
~~~ここまで本文より引用
そっか!
本のオーラを浴びるだけでいいんだ。
そのあとに紹介される石井桃子さんの言葉も素敵です。
「子どもたちよ。子ども時代をしっかりと楽しんでください。
大人になってから、老人になってから、
あなたを支えてくれるのは子ども時代の『あなた』です」
うわ~。
そうなんだよね。
子ども時代はちゃんと遊ばないとね。
って。
かつら文庫には、そんな「祈り」が詰まっていたのだろうな。
「本」というものが、著者の「祈り」を形にしたものだとしたら、
「本棚」っていうのは、本棚のつくりての「祈り」そのものだ。
そこからは、
「本のオーラ」が確実に出ていて、
それを感じるだけで、何かが動いていく。
「暗やみ本屋ハックツ」で
暗やみの中にあるのは、
本を寄贈してくれたひとりひとりの「手紙」であり、「祈り」だ。
それを感じることだけでも、何かになるような気がした。
3月4日まで、
東京都練馬区関町図書館(最寄駅:西武新宿線・武蔵関駅)で
「暗やみ本屋ハックツが関町図書館にやってくる!」
を開催中です。
https://www.lib.nerima.tokyo.jp/event/detail/2202
3月4日には僕も行きます。
本のオーラ、感じに来てください。
2018年02月19日
無目的性と多目的性のあいだ

「世界時計」がシンボルだった、
多治見駅の近く、旧ワタナベ時計店の
リノベーションプロジェクト。
まちの中心に本屋さんがなっていくような、
そんなプロジェクト。
今日もミーティングが楽しかった。
ちょっと振り返り。
13:00 ワタナベ時計店前に集合
名前、所属、最近食べたおいしかったもので自己紹介
13:05 まち歩き~多治見市立図書館
図書館に人が集まっている様子を見る
13:25ころ 企画会議第1ターム@まちづくり会社会議室
いきなり本題。
「あなたはなぜ、ここにいるのか?」
今日の参加動機、あるいは未来に作りたいもの、で自己紹介。
14:10ころ 第2ターム
「もし、それが本屋であるとしたら、それはなぜか?そしてどういう場所か?」
みんなが思う、「本屋」や「場」への思いを語る。
14:55ころ 休憩
15:00ころ 今後のスケジュール、ネクストステップ確認
旅に出る大学生は、「特派員」名刺を渡し、レポートしてもらう。
教育系の大学生は、3月中旬に「マーケティング合宿」を行い、
高校生のサードプレイスについてリサーチする。
16:00 多治見発の快速に乗る。
っていう感じの3時間。
めちゃ楽しいミーティングでした。
「チューニング」するミーティングでした。
「あなたはなぜ、ここにいるのか?」で過去といまの関心を語り、
「それが本屋であるとしたら、なぜか?どういう場所か?」
っていうことで、未来とミッションを語るというセットになっていた。
特に2つ目のそれが本屋である理由の
ワークは聞いていて、トリハダが立つほど面白かった。
昨日出てきた本屋のコンセプトは、
「何かを探している人が集まる本屋」
これをプロジェクト名に仮で入れておく。
そうそう。
本屋ってそういう場所だよ。
工藤直子さんの「あいたくて」を思い出す。
あいたくて 工藤直子
だれかに あいたくて
なにかに あいたくて
生まれてきたー
そんな気がするのだけれど
それが だれなのか なになのか
あえるのは いつなのかー
おつかいの とちゅうで
迷ってしまった子どもみたい
とほうに くれている
それでも 手のなかに
みえないことづけを
にぎりしめているような気がするから
それを手わたさなくちゃ
だから
あいたくて
(工藤直子詩集『あ・い・た・く・て』 より)
何かを探している人たち。
そんな人たちが本屋に集まる。
本屋に「何か」(それは本ではないかもしれない)
を探しに来て、
そしてまた、「何か」を探しに、まちに出ていく。
次の人生へ出ていく。
きっと本屋っていうのはそういう場所なんだろうな。
ふたたび
「サードプレイス」について考えさせられた。
多くの人にとって、「サードプレイス」とは、
「無目的に」行ける場所のことだった。
たぶんそれがすごく大切なのだろうと思う。
僕は九州の武雄市図書館に行った時の、
上から図書館を眺めたあの光景や、
ツルハシブックスがにぎわっているときに、
2Fの階段から1Fを覗き込むのが好きだった。
「いろんな目的の人が同じ空間を共有している」
ことが僕にとっては心地よいのだ。
そんな、無目的性と多目的性のあいだ。
それは決して、「単一の目的」ではない、
そういうあいまいな空間。
そこにこそ、
探している「何か」があるような気がする。
まあ、あくまで「気がする」だけなんですけどね。
2018年02月18日
ソフトとしての本屋
「ツルハシブックスは、ハードとしての本屋ではなく、
ソフトとしての本屋になっていくんじゃないか?」
たしか、ツルハシブックスの閉店が決まった会議の時に
山田さんが言っていた言葉だったような。
そんな山田さんは、
「古本詩人ゆよん堂」をつくった。
ツルハシブックスとはなんだったのか。
そして、ツルハシブックスを立ち上げた自分はなんだったのか。
そもそも、偶然に導かれたことから始まった。
・インターン事業が軌道に乗りつつあり、
・学生を集めるのがたいへんになって、
・事務所を構えたいと思って、内野に来たら、
・その事務所が激しく欠陥物件で、半年で移動せざるを得ず、
・駅前で物件を探していたら、駅前一等地に「貸」が出ていて、
・新潟市の中心市街地活性化の施策もあったり、
・カフェをやりたいという宮澤くんの存在もあり、
・1階どうしよう?って話で人を集める場をつくらなきゃって思って
・人が集まると言えば駄菓子屋、で、そうなりかけたんだけど、
・そういえば、俺、ヴィレッジヴァンガード郡山アティ店で
・まちを創れる本屋に憧れていて
・本屋で人が集まる場を作れたら面白いな
って思って、
ツルハシブックスになったんだな。
すごい偶然。
あそこの正式名所は、
「ウチノ・コラボレーション・ラボラトリー」
内野地域で、協働を生む、実験場。
これがコンセプトだった。
地下古本コーナー「HAKKUTSU」が話題になって、
全国から人が集まってきていたけど、
本来の価値は、本を売ることではなく、
コラボレーションの実験が起こること、としていた。
実際にツルハシブックスから始まったものは、
・野菜ソムリエランチ
・にしかん・農家マップ制作
・フリーペーパー「内野日和」の作成
・うちのまち なじみのおみせ ものがたり(商店街でのミニゼミ)
・社長10人×新潟の学生50人「夜景企画会議」
などなど。
もっとあると思うのだけど、
そう考えるといろんなことが起こっているよな。
実際に、それは本屋じゃないくてもできるんじゃないか?
って言われたし、
ツルハシブックスに来て、本を買わないお客さんは
多かったし、本の売り上げは上がらなかったし。
なんで本屋なんですか?
本屋である必要があったのか?
って聞かれたけど。
僕は本屋だから、しかもそれが新刊書店だから
できたようなところはあると思っている。
本のある空間のチカラがあるのだ。
人と人のコミュニケーションのツール。
そして、多様性の許容。
さらに、空気感の入れ替え。
たぶんこの3つが
「場」にとってプラスの影響をもたらす本の効能だと思う。
ツルハシブックスがハードからソフトになる。
それはつまり、ツルハシブックスの実態から出てきた学びを
ほかの場に応用していくことだろう。
そういう意味では、
以上3つのポイントをどう具体的につくっていくか。
それがポイントなのだろうと思う。
本屋の先に、何を見るか。
それを語りながらつくっていきたい。
今日は多治見で本屋づくりプロジェクトのキックオフです。

ソフトとしての本屋になっていくんじゃないか?」
たしか、ツルハシブックスの閉店が決まった会議の時に
山田さんが言っていた言葉だったような。
そんな山田さんは、
「古本詩人ゆよん堂」をつくった。
ツルハシブックスとはなんだったのか。
そして、ツルハシブックスを立ち上げた自分はなんだったのか。
そもそも、偶然に導かれたことから始まった。
・インターン事業が軌道に乗りつつあり、
・学生を集めるのがたいへんになって、
・事務所を構えたいと思って、内野に来たら、
・その事務所が激しく欠陥物件で、半年で移動せざるを得ず、
・駅前で物件を探していたら、駅前一等地に「貸」が出ていて、
・新潟市の中心市街地活性化の施策もあったり、
・カフェをやりたいという宮澤くんの存在もあり、
・1階どうしよう?って話で人を集める場をつくらなきゃって思って
・人が集まると言えば駄菓子屋、で、そうなりかけたんだけど、
・そういえば、俺、ヴィレッジヴァンガード郡山アティ店で
・まちを創れる本屋に憧れていて
・本屋で人が集まる場を作れたら面白いな
って思って、
ツルハシブックスになったんだな。
すごい偶然。
あそこの正式名所は、
「ウチノ・コラボレーション・ラボラトリー」
内野地域で、協働を生む、実験場。
これがコンセプトだった。
地下古本コーナー「HAKKUTSU」が話題になって、
全国から人が集まってきていたけど、
本来の価値は、本を売ることではなく、
コラボレーションの実験が起こること、としていた。
実際にツルハシブックスから始まったものは、
・野菜ソムリエランチ
・にしかん・農家マップ制作
・フリーペーパー「内野日和」の作成
・うちのまち なじみのおみせ ものがたり(商店街でのミニゼミ)
・社長10人×新潟の学生50人「夜景企画会議」
などなど。
もっとあると思うのだけど、
そう考えるといろんなことが起こっているよな。
実際に、それは本屋じゃないくてもできるんじゃないか?
って言われたし、
ツルハシブックスに来て、本を買わないお客さんは
多かったし、本の売り上げは上がらなかったし。
なんで本屋なんですか?
本屋である必要があったのか?
って聞かれたけど。
僕は本屋だから、しかもそれが新刊書店だから
できたようなところはあると思っている。
本のある空間のチカラがあるのだ。
人と人のコミュニケーションのツール。
そして、多様性の許容。
さらに、空気感の入れ替え。
たぶんこの3つが
「場」にとってプラスの影響をもたらす本の効能だと思う。
ツルハシブックスがハードからソフトになる。
それはつまり、ツルハシブックスの実態から出てきた学びを
ほかの場に応用していくことだろう。
そういう意味では、
以上3つのポイントをどう具体的につくっていくか。
それがポイントなのだろうと思う。
本屋の先に、何を見るか。
それを語りながらつくっていきたい。
今日は多治見で本屋づくりプロジェクトのキックオフです。

2018年02月16日
「違和感」をリスペクトすること
気になる異性に対して思う「違和感」をギャップ萌えという、
と言ったのは、現代美術家の
ニシダタクジ(1974‐)だったけど。(笑)
すべては「違和感」から始まってるんじゃないか。
「違和感」というか、「好奇心」というか、そういうやつ。
そんなことを思っていたら、
そういえば、積ん読にこんな本があったなと。
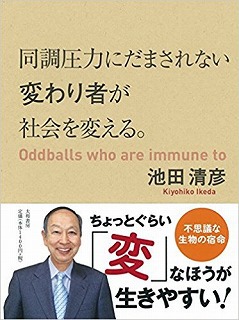
「同調圧力にだまされない変わり者が社会を変える」(池田清彦 大和書房)
タイムリーヒット。(笑)
まだ前半だけど、
生物学者が書く、同調圧力について。
~~~ここから引用
民主主義は多数決を宗とする政治制度であるため、
マジョリティに属していたほうが、
法律上の優遇措置を受け易く、マイノリティよりはるかに有利である。
タバコバッシングがこれほどきつくなったのは、
もちろん喫煙者がマイノリティになったからだ。
残念なことに民主主義はマイノリティを抑圧する制度としても機能するのだ。
マイノリティの人たちを擁護するのは、自分のためなのだ。
人は、常にマジョリティでいることはできないのだから。
群れで生活している動物にとって、
仲間に同調するのは身を守るための大切な本能だ。
人類は野生動物から身を守ったり、野生動物を捕獲するために、
集団で生活するようになったことは間違いなく、その習性は今に引き継がれている。
現代社会を見ても、ビジネスや新しい技術で社会に驚くような
イノベーションを起こすことができるのは「変な人」である。
人類は経験的にそのことを知っていた。
そのためどの文明でも、社会構造の中に「変な人」を一定数取り入れ、
彼らを排除しないようにしてきたのであろう。
「世の中で流行しているものが好き」というタイプの人もいる。
いや、むしろそちらのほうがずっと数が多い。
彼らは「同調するのが好き」なので、他の人と同じ行動をするのにためらいがない。
それは生物学的にも、同調を好む人のほうが社会の中で生存する確率が高いからである。
~~~ここまで引用
なるほどね~。
説得力あるね、「生物学的に」って言われると。
人がマジョリティーになるのは、習性なんだね。
まあ、それはそれとして。
僕が思うのは、「同調圧力」によって、
自らの感性を発動させない、ということが
起こっていないだろうか?
ということ。
数学とは何か?
数学は何から始まったか?
っていうのは、
僕としては今年のマイブームな問いなのだけど
解き明かしたい自然現象や
違和感みたいなのがあって、
わかった!ってなって、
それを数式で表現したっていうことなんだよね。たぶん。
そういう、違和感に対するリスペクトみたいのが
始まりなんだったと思うんだよね。
違和感という感性の発動を大切にすること。
それ、すごい大事だと思う。
みんなと一緒に絶滅しないために。
と言ったのは、現代美術家の
ニシダタクジ(1974‐)だったけど。(笑)
すべては「違和感」から始まってるんじゃないか。
「違和感」というか、「好奇心」というか、そういうやつ。
そんなことを思っていたら、
そういえば、積ん読にこんな本があったなと。
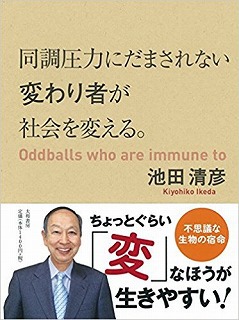
「同調圧力にだまされない変わり者が社会を変える」(池田清彦 大和書房)
タイムリーヒット。(笑)
まだ前半だけど、
生物学者が書く、同調圧力について。
~~~ここから引用
民主主義は多数決を宗とする政治制度であるため、
マジョリティに属していたほうが、
法律上の優遇措置を受け易く、マイノリティよりはるかに有利である。
タバコバッシングがこれほどきつくなったのは、
もちろん喫煙者がマイノリティになったからだ。
残念なことに民主主義はマイノリティを抑圧する制度としても機能するのだ。
マイノリティの人たちを擁護するのは、自分のためなのだ。
人は、常にマジョリティでいることはできないのだから。
群れで生活している動物にとって、
仲間に同調するのは身を守るための大切な本能だ。
人類は野生動物から身を守ったり、野生動物を捕獲するために、
集団で生活するようになったことは間違いなく、その習性は今に引き継がれている。
現代社会を見ても、ビジネスや新しい技術で社会に驚くような
イノベーションを起こすことができるのは「変な人」である。
人類は経験的にそのことを知っていた。
そのためどの文明でも、社会構造の中に「変な人」を一定数取り入れ、
彼らを排除しないようにしてきたのであろう。
「世の中で流行しているものが好き」というタイプの人もいる。
いや、むしろそちらのほうがずっと数が多い。
彼らは「同調するのが好き」なので、他の人と同じ行動をするのにためらいがない。
それは生物学的にも、同調を好む人のほうが社会の中で生存する確率が高いからである。
~~~ここまで引用
なるほどね~。
説得力あるね、「生物学的に」って言われると。
人がマジョリティーになるのは、習性なんだね。
まあ、それはそれとして。
僕が思うのは、「同調圧力」によって、
自らの感性を発動させない、ということが
起こっていないだろうか?
ということ。
数学とは何か?
数学は何から始まったか?
っていうのは、
僕としては今年のマイブームな問いなのだけど
解き明かしたい自然現象や
違和感みたいなのがあって、
わかった!ってなって、
それを数式で表現したっていうことなんだよね。たぶん。
そういう、違和感に対するリスペクトみたいのが
始まりなんだったと思うんだよね。
違和感という感性の発動を大切にすること。
それ、すごい大事だと思う。
みんなと一緒に絶滅しないために。
2018年02月15日
百姓=農民ではなかった
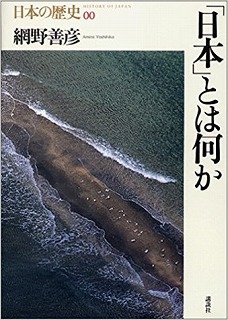
「日本」とは何か 網野善彦 講談社
某古本屋さんで購入。
なかなか面白い。
「日本」が誕生したのは、7世紀末。
壬申の乱に勝利した天武天皇が
「倭国」から「日本」へと国号を変えた。
対外的に初めて用いられたのは、
702年、中国大陸に到着した
ヤマトの使者が、唐の国号を
周と改めていた則天武后に対してであった。
にもかかわらず、
明治以降の国家的教育によって、
記紀神話の描く日本の「建国」が
そのまま史実として、徹底的に
国民に刷り込まれた。
なるほど。
「建国記念日」っていうのは
神話に基づいているんだな。
それはそれで面白い。
「物語の力」ってすごいなと。
そして、この本の目玉としては、
第四章の「瑞穂国日本」の虚像
江戸時代まで我が国の農村部は
稲作を中心とした自給自足が基本であった、というもの。
年貢だって米で納めていたし。みたいな。
しかしそれは、
為政者たちが描いた「こうなったらいいな」
というストーリーに過ぎなかったのだ。
しかもそれは701年の大宝律令までさかのぼる。
「班田収授法」だ。(なつかしい)
簡単に言えば、
田んぼから全国一律に税を徴収するという制度。
政治をするほうとすれば画期的だ。
ところが、これは、
理想先行で、うまく機能しなくなってのだという。
そこで政治は、
「三世一身法」を723年に、
「墾田永年私財法」を743年に制定。
田んぼつくっていいから、税を納めろよっていうやつだ。
ここから「荘園」時代が始まっていく。
しかしながら、
実際のところ、海や山の幸が豊かだった地域では、
海産物を獲ったり、絹織物を生産したりして、
貨幣経済、市場経済で生きてきたのではないかという。
たしかにそう考えるほうが自然な気がする。
著者は、能登輪島の海産物の豪商が、
明治時代の壬申戸籍によると、
いわゆる土地を持っていない水呑(=小作農)にカウント
されているのだという。
つまり、教科書に記載されている
士農工商の「農」は、
漁民や、養蚕⇒織物、地方での商業などを
全部、「農」にくくったのだ。
つまり、データ上は、
自作農が少なく、小作農が多い「貧しい農村」は、
「農業以外の仕事で食べていた」という可能性があるというのだ。
なるほど。
百姓っていうのは農民とはイコールではなくて、
田んぼもやってたかもしれないけど、
さまざまな仕事を並行してやっている人たちと
考えたほうがよさそうだということ。
それを明治政府は
「四民平等」という名のもとに、
「農民」に一元化したのだ。
つまり、あとづけで「農民」という
カテゴリーがつくられているのだ。
なるほどね~。
そうやって、「専業思想」が生まれていったのかも
終身雇用、年功序列による「専業」システムに
国家を、国民を無理やり適用させていったのだろう。
壮大なストーリーだなと思う。
歴史はこういうふうに見ると、めっちゃ楽しいかも。
いろいろ問いがある。
2018年02月14日
サードプレイスは、見つけ出す場所
昨日のブログ
「サードプレイスは本当に必要なのか?」
の反応にインスパイアされた。
中高生にとっての「サードプレイス」は、
与えられた場ではなく、探し出す場ではないのか?
という問い。
そこから考えた。
そもそも、「サードプレイス」は、
一般化された概念ではあるけれど、
ひとりひとりにとっての「サードプレイス」とは、
あくまで、その人にとってのパーソナルな「サードプレイス」であり、
みんなにとっての「サードプレイス」、
しかも場所として認知されうる「サードプレイス」
というのはあり得ないのではないか。
それは、「居場所」問題や
「アイデンティティ」問題とも関わってくるのだけど、
静的な「居場所」と動的な「場」
「プレイス」と「プロジェクト」
たぶん、その両方が必要なのではないかな。
いずれにしても、
みんなが「サードプレイス」だと思う
「サードプレイス」というのは存在しないので、
ひとりひとりが、自ら
「サードプレイス」も「サードプロジェクト」
も見つけ出していかなければならない。
「プロジェクト」にしても、
成果にフォーカスし過ぎるのではなく、
ひとりひとりにフォーカスしたミーティングを行っていくこと。
つまり、チューニングを行うこと。
ミーティングとは感性をチューニングすること(17.4.23)
http://hero.niiblo.jp/e484576.html
そうやって、プロジェクトが
その人にとって「サードプレイス」化してくるのかもね。
なるほどなるほど。
だんだんつながってきますね。
サードプレイスは、提供される場ではなく、
見つけ出す場、勝ち取る場、創り出す場
なのだと思います。
たぶん、
その見つけ方、勝ち取り方、創り出し方、
そんなのを一緒に考えていけたらいいなと思います。
「サードプレイスは本当に必要なのか?」
の反応にインスパイアされた。
中高生にとっての「サードプレイス」は、
与えられた場ではなく、探し出す場ではないのか?
という問い。
そこから考えた。
そもそも、「サードプレイス」は、
一般化された概念ではあるけれど、
ひとりひとりにとっての「サードプレイス」とは、
あくまで、その人にとってのパーソナルな「サードプレイス」であり、
みんなにとっての「サードプレイス」、
しかも場所として認知されうる「サードプレイス」
というのはあり得ないのではないか。
それは、「居場所」問題や
「アイデンティティ」問題とも関わってくるのだけど、
静的な「居場所」と動的な「場」
「プレイス」と「プロジェクト」
たぶん、その両方が必要なのではないかな。
いずれにしても、
みんなが「サードプレイス」だと思う
「サードプレイス」というのは存在しないので、
ひとりひとりが、自ら
「サードプレイス」も「サードプロジェクト」
も見つけ出していかなければならない。
「プロジェクト」にしても、
成果にフォーカスし過ぎるのではなく、
ひとりひとりにフォーカスしたミーティングを行っていくこと。
つまり、チューニングを行うこと。
ミーティングとは感性をチューニングすること(17.4.23)
http://hero.niiblo.jp/e484576.html
そうやって、プロジェクトが
その人にとって「サードプレイス」化してくるのかもね。
なるほどなるほど。
だんだんつながってきますね。
サードプレイスは、提供される場ではなく、
見つけ出す場、勝ち取る場、創り出す場
なのだと思います。
たぶん、
その見つけ方、勝ち取り方、創り出し方、
そんなのを一緒に考えていけたらいいなと思います。
2018年02月13日
サードプレイスは本当に必要なのか?
問いが近い人と話をするのは楽しいなと。
昨日の大テーマは、
「サードプレイスは本当に必要なのか?」
暗やみ本屋ハックツ
http://www.hakkutsu.info/
で出会った人たちの何人かは、
「自分が中学生の時にこんな場所があったら。」
っていう。
でもさ、それって、
中学生の時は自覚していないんじゃないか、って思う。
「サードプレイス」っていう概念がないからね。
学校と家庭しか「世界」がない。
っていうのは本当にそうなんだろうけど。
そして、
ツルハシブックス閉店で僕が学んだこと。
それは、「居場所のジレンマ」とでも
いうべきものだった。
居心地のいい場所は、たくさんの人の「居場所」になり、
その場にいる人の一定数以上がそこを「居場所」化すると、
それは一見さんやほかの人にとって
居心地の悪い場所になるというものだ。
ここから脱することができず、
ツルハシブックスは閉店した。
そこで思ったことは、
「集まる場」は同時に「始まる場」で
なければならないのではないか、というのと、
言語コミュニケーションだけではなく
非言語コミュニケーションの要素が必要なのではないか、と
本を置いているのならば、
その本を随時入れ替え、「空気」を一新する
ことを定期的にやらなければならないのではないか、ということ。
まあ、それを前提として、
昨日の話へ。
「サードプレイス」は、
米国の社会学者レイ・オルデンバーグが提唱し、
スターバックスコーヒーがキーコンセプトとして
世界に広まっていったのだけど。
第1の場所(自宅)、第2の場所(職場・学校)でもない
個人としてくつろぐことのできる「第3の場所」という意味。
これを、社会教育系の人たち(つまり学校教育ではないNPOとか)は、
非常に重要視しているように思う。
しかし、
「サードプレイスは本当に(中高生に)必要なのか?」
という問いを立ててみると、
サードプレイスというプレイス(場所)が
必要なのではないのではないか?と思う。
たとえば、
体育会系の部活動や生徒会や、高校の文化祭
みたいなやつは、サードプレイスではないのか?
そう言われると、
「サードプレイス」というのは、特に高校生にとっては、
特段に重要な概念ではないのではないか?
というふうに思えてくる。
ここで、このブログに何度も登場している
川喜田二郎氏(KJ法生みの親)の言葉を。
http://hero.niiblo.jp/e468419.html
(帰る場所、ふるさとをつくる 15.5.14)
「ふるさととは、子どもながらに全力傾注して
創造的行為を行った場所のこと。」
(「創造性とは何か」川喜田二郎 洋伝社新書より)
そっか。
体育会系部活も、生徒会も、文化祭も
それが「全力傾注した創造的行為」ならば、
そこは「ふるさと」になりうる。
そしてそれこそが、
高校生にとっての「サードプレイス」の実態なのではないか。
つまり、大切なのは、
「プレイス」ではなく、「プロジェクト」なのではないか。
というのが昨日の仮説だ。
「サードプレイス」から「サードプロジェクト」へ。
そんなことが重要なのではないか。
だからこそ、「屋台のある図書館」に価値があるのではないか。
http://hero.niiblo.jp/e474463.html
(誰のための図書館? 15.11.14)
僕はそれが、
「本のある空間」を起点に起こっていくと思っている。
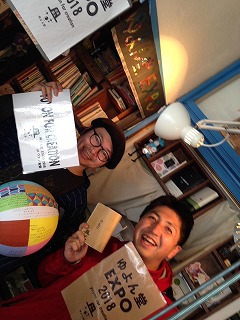
2月10日、古本詩人「ゆよん堂」EXPO@ウチノ食堂「藤蔵」で
山田正史が言っていた。
「1つ1つの本がドアだ。どのドアを開けるか。それが本屋なんだ」
って言っていた。
そうそう。
それだよね。
本を売っているんじゃなくて、
ドアを売っているんだよね。
そんな空間で、その日に出会って人に誘われて、
うっかりプロジェクトに関わってしまうような、
そんな空間をつくること。
昨日のハイライトは、
「数学の前では子どもも大人もない」
もちろん、この「数学」には、
「本」とか「プロジェクト」とかも入るのだけど、
つまり、「学び」の前では、大人も子どももない。
それこそ、吉田松陰先生が野山獄で実践したことではないか。
学びの前では、罪人も聖人もないのだ。
そんな空間、そんなプロジェクト。
そんなのが無数に生まれていくような、「場」。
たぶんそれが僕が
「本のある空間」で実現したいことなのだろうと思った。
「サードプレイス」から「サードプロジェクト」の生まれる「場」へ
その「場」は制的な場所ではなく、動的な「場」であるような気がしている。
なんだか、楽しくなってきました。
いい対話をありがとうございました。
昨日の大テーマは、
「サードプレイスは本当に必要なのか?」
暗やみ本屋ハックツ
http://www.hakkutsu.info/
で出会った人たちの何人かは、
「自分が中学生の時にこんな場所があったら。」
っていう。
でもさ、それって、
中学生の時は自覚していないんじゃないか、って思う。
「サードプレイス」っていう概念がないからね。
学校と家庭しか「世界」がない。
っていうのは本当にそうなんだろうけど。
そして、
ツルハシブックス閉店で僕が学んだこと。
それは、「居場所のジレンマ」とでも
いうべきものだった。
居心地のいい場所は、たくさんの人の「居場所」になり、
その場にいる人の一定数以上がそこを「居場所」化すると、
それは一見さんやほかの人にとって
居心地の悪い場所になるというものだ。
ここから脱することができず、
ツルハシブックスは閉店した。
そこで思ったことは、
「集まる場」は同時に「始まる場」で
なければならないのではないか、というのと、
言語コミュニケーションだけではなく
非言語コミュニケーションの要素が必要なのではないか、と
本を置いているのならば、
その本を随時入れ替え、「空気」を一新する
ことを定期的にやらなければならないのではないか、ということ。
まあ、それを前提として、
昨日の話へ。
「サードプレイス」は、
米国の社会学者レイ・オルデンバーグが提唱し、
スターバックスコーヒーがキーコンセプトとして
世界に広まっていったのだけど。
第1の場所(自宅)、第2の場所(職場・学校)でもない
個人としてくつろぐことのできる「第3の場所」という意味。
これを、社会教育系の人たち(つまり学校教育ではないNPOとか)は、
非常に重要視しているように思う。
しかし、
「サードプレイスは本当に(中高生に)必要なのか?」
という問いを立ててみると、
サードプレイスというプレイス(場所)が
必要なのではないのではないか?と思う。
たとえば、
体育会系の部活動や生徒会や、高校の文化祭
みたいなやつは、サードプレイスではないのか?
そう言われると、
「サードプレイス」というのは、特に高校生にとっては、
特段に重要な概念ではないのではないか?
というふうに思えてくる。
ここで、このブログに何度も登場している
川喜田二郎氏(KJ法生みの親)の言葉を。
http://hero.niiblo.jp/e468419.html
(帰る場所、ふるさとをつくる 15.5.14)
「ふるさととは、子どもながらに全力傾注して
創造的行為を行った場所のこと。」
(「創造性とは何か」川喜田二郎 洋伝社新書より)
そっか。
体育会系部活も、生徒会も、文化祭も
それが「全力傾注した創造的行為」ならば、
そこは「ふるさと」になりうる。
そしてそれこそが、
高校生にとっての「サードプレイス」の実態なのではないか。
つまり、大切なのは、
「プレイス」ではなく、「プロジェクト」なのではないか。
というのが昨日の仮説だ。
「サードプレイス」から「サードプロジェクト」へ。
そんなことが重要なのではないか。
だからこそ、「屋台のある図書館」に価値があるのではないか。
http://hero.niiblo.jp/e474463.html
(誰のための図書館? 15.11.14)
僕はそれが、
「本のある空間」を起点に起こっていくと思っている。
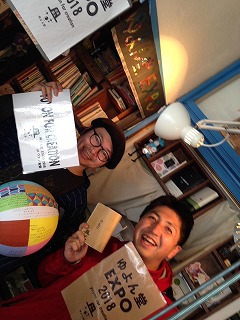
2月10日、古本詩人「ゆよん堂」EXPO@ウチノ食堂「藤蔵」で
山田正史が言っていた。
「1つ1つの本がドアだ。どのドアを開けるか。それが本屋なんだ」
って言っていた。
そうそう。
それだよね。
本を売っているんじゃなくて、
ドアを売っているんだよね。
そんな空間で、その日に出会って人に誘われて、
うっかりプロジェクトに関わってしまうような、
そんな空間をつくること。
昨日のハイライトは、
「数学の前では子どもも大人もない」
もちろん、この「数学」には、
「本」とか「プロジェクト」とかも入るのだけど、
つまり、「学び」の前では、大人も子どももない。
それこそ、吉田松陰先生が野山獄で実践したことではないか。
学びの前では、罪人も聖人もないのだ。
そんな空間、そんなプロジェクト。
そんなのが無数に生まれていくような、「場」。
たぶんそれが僕が
「本のある空間」で実現したいことなのだろうと思った。
「サードプレイス」から「サードプロジェクト」の生まれる「場」へ
その「場」は制的な場所ではなく、動的な「場」であるような気がしている。
なんだか、楽しくなってきました。
いい対話をありがとうございました。
2018年02月09日
「向き合わない」で「パラレル」につくる
ついつい、「多数派」とか「権威のあるもの」とかに挑んでしまう。
「経済至上主義社会」とか「学校」とか。
「本の処方箋」の価値は、
「人の悩み」に対して「向き合わない」ということだと思う。
話を聞いているとき、
僕の意識の半分は、本棚のほうを向いている。
どんな本がいいのかなあと
感性が発動している感じだ。
そして
1 ストレートで悩みに直結する本
2 変化球で悩みにアプローチする本
3 話と全然関係ないけど思いついた本
を提案する。
そっか。
「向き合わない」「対抗しない」って大事かも、と。
僕がいま大学生に一番伝えたいことは、
「就職」も「インターン」も
「旅をする」のも、「本を読む」のも、
「学びの場の選択」に過ぎないっていうこと。
個人戦か、団体戦かの違いはあるけど。
そしてそのひとつひとつのプロジェクトは、
「小さな船」のようなもので、
その船のコンパス(価値観・バリュー)を共有して、
行き先(ビジョン)を決めて、
乗組員と顧客の幸せ(ミッション)を果たしながら進んでいく。
そんな小さな船の航海のようなものだと思う。
だとすると、
挑まなくてもいいのかもしれないなって思った。
批判はしない。
パラレル(並行)に走る船を作ればいいのだ。
正確に言うと、その海は3次元空間(もしかしたら4次元)
を漂っているので、並行していないかもしれないが。
いよいよ。
2002年から、というか
たぶん大学時代に、教育学部の自主ゼミに
出た時からの思い。
思考停止こそが不幸の源泉であり、
考え続けることこそが希望である。
そして、「学校」というシステムは、
「効率化」のために
「思考停止」することを良しとするシステムなんだって。
まあ。
それは、それとして。
江戸時代にも、
藩校に対して、私塾があったように。
公立学校や仕組化された「学校」に挑む、
就活のシステムや形骸化されたインターンに挑む、
のではなくて、
パラレルにつくるんだ。
もうひとつの選択肢を。
たとえばそれは、本屋さんの形をしている、
パラレルでオルタナティブな学びの場
をたくさん作っていったらいいんじゃないかなって。
向き合わないし、挑まない。
「職場」も「学校」も、
そのひとつに過ぎないのだから。
そんな船旅に、たくさんの自分の分身を
載せていくような、
そんな感覚になれたら楽しいかもなと
いろいろ妄想してみた。
「経済至上主義社会」とか「学校」とか。
「本の処方箋」の価値は、
「人の悩み」に対して「向き合わない」ということだと思う。
話を聞いているとき、
僕の意識の半分は、本棚のほうを向いている。
どんな本がいいのかなあと
感性が発動している感じだ。
そして
1 ストレートで悩みに直結する本
2 変化球で悩みにアプローチする本
3 話と全然関係ないけど思いついた本
を提案する。
そっか。
「向き合わない」「対抗しない」って大事かも、と。
僕がいま大学生に一番伝えたいことは、
「就職」も「インターン」も
「旅をする」のも、「本を読む」のも、
「学びの場の選択」に過ぎないっていうこと。
個人戦か、団体戦かの違いはあるけど。
そしてそのひとつひとつのプロジェクトは、
「小さな船」のようなもので、
その船のコンパス(価値観・バリュー)を共有して、
行き先(ビジョン)を決めて、
乗組員と顧客の幸せ(ミッション)を果たしながら進んでいく。
そんな小さな船の航海のようなものだと思う。
だとすると、
挑まなくてもいいのかもしれないなって思った。
批判はしない。
パラレル(並行)に走る船を作ればいいのだ。
正確に言うと、その海は3次元空間(もしかしたら4次元)
を漂っているので、並行していないかもしれないが。
いよいよ。
2002年から、というか
たぶん大学時代に、教育学部の自主ゼミに
出た時からの思い。
思考停止こそが不幸の源泉であり、
考え続けることこそが希望である。
そして、「学校」というシステムは、
「効率化」のために
「思考停止」することを良しとするシステムなんだって。
まあ。
それは、それとして。
江戸時代にも、
藩校に対して、私塾があったように。
公立学校や仕組化された「学校」に挑む、
就活のシステムや形骸化されたインターンに挑む、
のではなくて、
パラレルにつくるんだ。
もうひとつの選択肢を。
たとえばそれは、本屋さんの形をしている、
パラレルでオルタナティブな学びの場
をたくさん作っていったらいいんじゃないかなって。
向き合わないし、挑まない。
「職場」も「学校」も、
そのひとつに過ぎないのだから。
そんな船旅に、たくさんの自分の分身を
載せていくような、
そんな感覚になれたら楽しいかもなと
いろいろ妄想してみた。
2018年02月08日
「古本屋セット」始めようかな
結局、本売りたいんだよね。
届けたいんだよね。
他者評価の呪縛から、解放したいんだよね。
それには本がいいと思うんですよ。
世の中を俯瞰して見ることが
必要だと思うんですよ。
そんな声に賛同する人に、
「古本屋セット」を始めようかなと思ってます。
タイトルは、
「19歳のための本棚」
主に大学の前の
カフェとかお店とかNPOとか、
そういう場所に、
本棚を設置してもらって、
僕が選んだ本(古本)を
たとえば、150冊⇒30000円とかで送りつけるんです。
売る人は300円・500円とかで値段をつけて売る。
こっちで値段を付けてもいいけど。
そしたら30000円で本屋スタートできるじゃん。
他の本で自分が並べたい本があったら、
それも並べたり、某古本屋で仕入れてきたり。
それって結構楽しいよ。
本棚のない人は、「こっそりー」を
そのまま展開したいんだけどね。
やっぱ、それやりたいかも。
ストライクゾーンである
15歳~25歳にフォーカスした本を、
セレクトするのをはじめようっと。
カテゴリは
「じぶん」
「まなび」
「しごと」
「こらぼ」
「れきし」
「くらし」
「ものがたり」
こんな7カテゴリかな。
「じぶん」は、
・孤独と不安のレッスン(鴻上尚史・だいわ文庫)
・非属の才能(山田玲司・光文社新書)
「まなび」は、
・先生はえらい(内田樹・ちくまプリマー新書)
・すべての教育は洗脳である(堀江貴文・光文社新書)
「しごと」は、
・ナリワイをつくる(伊藤洋志・ちくま文庫)
・計画と無計画のあいだ(三島邦弘・河出文庫)
「こらぼ」は、
・かかわり方の学び方(西村佳哲・ちくま文庫)
とかとか。
ちょっと考えてみます。
ツルハシブックス常備本(16.5.12)
http://hero.niiblo.jp/e479203.html
こちらも参考にしてみようと。
これで150冊のラインナップができたら、
新刊も交えていけるかもな。
ちょっと構想してみます。
届けたいんだよね。
他者評価の呪縛から、解放したいんだよね。
それには本がいいと思うんですよ。
世の中を俯瞰して見ることが
必要だと思うんですよ。
そんな声に賛同する人に、
「古本屋セット」を始めようかなと思ってます。
タイトルは、
「19歳のための本棚」
主に大学の前の
カフェとかお店とかNPOとか、
そういう場所に、
本棚を設置してもらって、
僕が選んだ本(古本)を
たとえば、150冊⇒30000円とかで送りつけるんです。
売る人は300円・500円とかで値段をつけて売る。
こっちで値段を付けてもいいけど。
そしたら30000円で本屋スタートできるじゃん。
他の本で自分が並べたい本があったら、
それも並べたり、某古本屋で仕入れてきたり。
それって結構楽しいよ。
本棚のない人は、「こっそりー」を
そのまま展開したいんだけどね。
やっぱ、それやりたいかも。
ストライクゾーンである
15歳~25歳にフォーカスした本を、
セレクトするのをはじめようっと。
カテゴリは
「じぶん」
「まなび」
「しごと」
「こらぼ」
「れきし」
「くらし」
「ものがたり」
こんな7カテゴリかな。
「じぶん」は、
・孤独と不安のレッスン(鴻上尚史・だいわ文庫)
・非属の才能(山田玲司・光文社新書)
「まなび」は、
・先生はえらい(内田樹・ちくまプリマー新書)
・すべての教育は洗脳である(堀江貴文・光文社新書)
「しごと」は、
・ナリワイをつくる(伊藤洋志・ちくま文庫)
・計画と無計画のあいだ(三島邦弘・河出文庫)
「こらぼ」は、
・かかわり方の学び方(西村佳哲・ちくま文庫)
とかとか。
ちょっと考えてみます。
ツルハシブックス常備本(16.5.12)
http://hero.niiblo.jp/e479203.html
こちらも参考にしてみようと。
これで150冊のラインナップができたら、
新刊も交えていけるかもな。
ちょっと構想してみます。
2018年02月07日
ミライ会議のつくり方
2月4日「若松ミライ会議」@常陸多賀をやりました。
ミライ会議は、
「過去」の振り返りから始まります。
なぜなら、
「顧客」は過去にしかいない、からです。
経営に必要な5つの質問。
1 ミッションは何か
2 顧客は誰か
3 顧客にとって価値は何か
4 成果は何か
5 計画は何か
今まで(今も)、「未来会議」「作戦会議」と言いながら、
成果と計画だけを話し合ってきました。
でも、経営に大切なのは、
それよりももっと、
なぜやるか?
誰に向けてやるか?
生み出す価値は何か?
ということです。
だからこそ、まずは過去を掘っていくことが必須です。
15分の人生モチベーショングラフ記入。
3分のプレゼンテーション。
これを全員繰り返します。
そこが出発点になるからです。
次に、未来を描きます。
自分たちが考える「価値」は何か?を考えます。
未来日記を書くのもいいでしょう。
大切なのは、そこに「お客」が登場しているということです。
「過去」の振り返りで見つけた「お客」。
それをどのように幸せにしていくか?
お客にとって価値はなんだろうか?
これが、通常の「ペルソナ設定」と違って、
よりリアルになります。
実際に出会った人なのですから。
もし、過去を振り返っても、
そういう人が思い浮かばなかったら、
ひとえに経験が足りないか、
日々、感性を発動させていないということではないでしょうか。
「違和感」「危機感」「使命感」
っていう3つの勘違い(昨日のブログ参照)
を発動させていくこと。
そして、価値を問うこと。
一つは社会(地域)ベースで。
もう一つは、個人ベースで。
たとえば、
大学生が企業に数か月コミットする「インターン」ではなくて、
大学生に限らず、社会人も参加できる「プロジェクト」をつくっていく。
そうすれば、企業は、即戦力的なチームができるし、スピード感がある。
地域にとっても、若者がネットワーク化して、新しいことが起こる環境ができる。
個人にとっては、プロジェクトメンバーとしての経験というか、
0から1をつくる経験ができる。
大学生にとっては、社会人と一緒にチームを組んで、
何かに取り組むことができる。
そして何より、そこに、志向性の近い「仲間」というか
ウォンテッドリー仲さんの言葉を借りれば、
「トライブ」が手に入る。
http://hero.niiblo.jp/e485916.html
(就活を再定義する 17.9.29)
たぶん、そういうこと。
本屋も、「コミュニティ」ではなくて、
「プロジェクト」をベースにした「トライブ」をつくっていくこと。
そんなことが可能になるのではないかと思った。
そして、そこで集まったメンバーを
チームにするために、ミライ会議をしっかりとやる
っていうことなのかもしれないね。
そんな文化をつくっていきたいかも。
僕自身も、
過去を振り返って、考えてみると、
根源的欲求の中に、現代美術家的な
「問いを投げかけたい」っていうのがあるんだよな、って。
「まきどき村」のネーミングは
種の袋に書いてあるカレンダーの
種を蒔くタイミングを表記した
「まきどき」(たとえば4月中旬~5月上旬)
なのだけど。
あの時は完全な勘違いで、
「今、種を蒔かないと、
このまきどき村という種は花を咲かせたり、
実をつけたりしないんだ」っていうことだった。
しかし、本質的には、
まきどき村は「豊かさとは何か?」
っていう問いをカタチにしたものではないかと思った。
ツルハシブックスは、
「偶然」という価値について、
(いわゆるキャリアドリフトなど)
本屋という形態を通して、
問いかけているものだし、
コメタクは、
「米を炊く暮らし」を通じて、
好きな米屋で米を買うこと、
余白の大切さについて問いかけているし。
そう考えると、
次は、本丸である、「学校」(大学も含む)
を問うことなのかもしれないな、と。
2002年に不登校の中学3年生の家庭教師を
したときからの問いを
今こそ、表現する瞬間を迎えているのではないか。
そんなことを僕自身は考えた
ミライ会議でした。
ミライ会議は、
「過去」の振り返りから始まります。
なぜなら、
「顧客」は過去にしかいない、からです。
経営に必要な5つの質問。
1 ミッションは何か
2 顧客は誰か
3 顧客にとって価値は何か
4 成果は何か
5 計画は何か
今まで(今も)、「未来会議」「作戦会議」と言いながら、
成果と計画だけを話し合ってきました。
でも、経営に大切なのは、
それよりももっと、
なぜやるか?
誰に向けてやるか?
生み出す価値は何か?
ということです。
だからこそ、まずは過去を掘っていくことが必須です。
15分の人生モチベーショングラフ記入。
3分のプレゼンテーション。
これを全員繰り返します。
そこが出発点になるからです。
次に、未来を描きます。
自分たちが考える「価値」は何か?を考えます。
未来日記を書くのもいいでしょう。
大切なのは、そこに「お客」が登場しているということです。
「過去」の振り返りで見つけた「お客」。
それをどのように幸せにしていくか?
お客にとって価値はなんだろうか?
これが、通常の「ペルソナ設定」と違って、
よりリアルになります。
実際に出会った人なのですから。
もし、過去を振り返っても、
そういう人が思い浮かばなかったら、
ひとえに経験が足りないか、
日々、感性を発動させていないということではないでしょうか。
「違和感」「危機感」「使命感」
っていう3つの勘違い(昨日のブログ参照)
を発動させていくこと。
そして、価値を問うこと。
一つは社会(地域)ベースで。
もう一つは、個人ベースで。
たとえば、
大学生が企業に数か月コミットする「インターン」ではなくて、
大学生に限らず、社会人も参加できる「プロジェクト」をつくっていく。
そうすれば、企業は、即戦力的なチームができるし、スピード感がある。
地域にとっても、若者がネットワーク化して、新しいことが起こる環境ができる。
個人にとっては、プロジェクトメンバーとしての経験というか、
0から1をつくる経験ができる。
大学生にとっては、社会人と一緒にチームを組んで、
何かに取り組むことができる。
そして何より、そこに、志向性の近い「仲間」というか
ウォンテッドリー仲さんの言葉を借りれば、
「トライブ」が手に入る。
http://hero.niiblo.jp/e485916.html
(就活を再定義する 17.9.29)
たぶん、そういうこと。
本屋も、「コミュニティ」ではなくて、
「プロジェクト」をベースにした「トライブ」をつくっていくこと。
そんなことが可能になるのではないかと思った。
そして、そこで集まったメンバーを
チームにするために、ミライ会議をしっかりとやる
っていうことなのかもしれないね。
そんな文化をつくっていきたいかも。
僕自身も、
過去を振り返って、考えてみると、
根源的欲求の中に、現代美術家的な
「問いを投げかけたい」っていうのがあるんだよな、って。
「まきどき村」のネーミングは
種の袋に書いてあるカレンダーの
種を蒔くタイミングを表記した
「まきどき」(たとえば4月中旬~5月上旬)
なのだけど。
あの時は完全な勘違いで、
「今、種を蒔かないと、
このまきどき村という種は花を咲かせたり、
実をつけたりしないんだ」っていうことだった。
しかし、本質的には、
まきどき村は「豊かさとは何か?」
っていう問いをカタチにしたものではないかと思った。
ツルハシブックスは、
「偶然」という価値について、
(いわゆるキャリアドリフトなど)
本屋という形態を通して、
問いかけているものだし、
コメタクは、
「米を炊く暮らし」を通じて、
好きな米屋で米を買うこと、
余白の大切さについて問いかけているし。
そう考えると、
次は、本丸である、「学校」(大学も含む)
を問うことなのかもしれないな、と。
2002年に不登校の中学3年生の家庭教師を
したときからの問いを
今こそ、表現する瞬間を迎えているのではないか。
そんなことを僕自身は考えた
ミライ会議でした。
2018年02月06日
勘違いから始まる「物語」のチカラ

2日金曜日はセンジュ出版@千住
3日土曜日はきっさこ@神保町
で本屋をつくった「とっくん」こと
むらまつくんと一緒に語った。
なんか、感覚的に近い感じ。
感性というか、
つくろうとしている社会が近いような気がする。
金曜日のキーワードは、
「違和感」と「危機感」と「使命感」
そうそう。
それだわ。
「違和感」から学びが始まり、
「危機感」から何かを考え、
「使命感」から行動する。
この〇〇感って全部勘違いだよね。
フィクションなんだよね。
仮説なんです。
でも、人を動かすのは、「物語の力」
なのだから、それでいいんだって。
土曜日のキーワードは、
「居場所」と「場」
「場」の空気をいかに作り、入れ替えていくか。
そのときの本の持つチカラとか、非言語コミュニケーションとか。
そんな話。
「場」のチカラを失わないようにするには、
常に新しい人が入ってくる仕組みをつくる。
たとえば、ゲストハウスであったりとか。
新刊書店であったりとか。
ライブラリーの危険は、
本が入れ替わらないこと=空気が入れ替わらないこと。
あとは、イベントとかやるときに、
facebookで告知するリスクについて、とか。
http://hero.niiblo.jp/e486514.html
(facebookの告知が「顧客」に届かない理由17.12.13)
そのソリューションとして、
「年齢制限」っていう方法があったなと。
ベントを、29歳以下に制限する。
っていうもの。
そうすれば、フェイスブック界隈にいる暇なおじさん
は来れないからね、物理的に。
それはありかもしれないなと。
イベントだからといって、
広く全員を対象にしなくてもいいな、というか。
対象をもっと明確にしたほうがいいなと。
昔はさ、イベントやるには、
チラシ(あるいはメール告知分)
つくんなきゃいけなかったから、
それを目に留めるために
「こんなあなたにオススメです」って
ちゃんと書いていたように思う。
それがフェイスブックになってから、
あいまいでもイベント立てられるようになったりとか。
そういうことってあるかもしれないな。
あとは、「場」について。
「居場所」になるのを防ぎ、
「場」が力を保つためには、
そこは、「集まる場所」だけではなくて、
「始まる場所」でなければならないのではないか。
っていうこと。
「始まる」っていうのは、
単なるアクションではなくて、
プロジェクトが始まる場所だったりするといいのだろうな、と。
だからさ、やっぱり
「屋台のある本屋 新城劇場」とか
塩尻図書館で企画していた「屋台のある図書館」
とかってそれを端的に言い切っているのがいいなと
思うんだよね。
それ、やっぱりやりたくなってくるわ。
もう一度、駄菓子屋楽校、読み直そうかな。
http://hero.niiblo.jp/e484598.html
(「学校」という輸入されたプラント 17.4.26)
僕がやりたいのは、
「プロジェクトが始まる場」で、
それは本屋だったり、図書館だったり、小さなライブラリーだったり
するのだろうね。
2018年02月02日
100冊、お願いします。
「本屋じゃない何か」の話を今日はセンジュ出版でします。
僕には、売りたい本があります。
たまに、「売らなければいけない本」に出会います。
そう言えば、
僕の業界人(?)としての出発点は、
サンクチュアリ出版の本に出会ったことでした。
1998年11月。
設立者の高橋歩さんが、社長を引退し、
世界一周新婚旅行に出るというタイミング。
僕は夜に東京都北区王子のバー「狐の木」で行われた
農学部系の学生・社会人の集まりに行ったのでした。
たしか旅の途中だった僕は、
午後早めにお店についていて、
地下にある「王子小劇場」で
お芝居を見ることになっていました。
その時の情報源は、
「20代サミットメーリングリスト」
PCを持ち歩いて、
公衆電話のダイアルアップ回線で、
メールを受信して、
みたいな旅をしていた僕に、熱いメールが飛び込んできてました。
「20代、熱くなって時代を駆け抜けろ」
ストレートだな。(笑)
当時、坂本龍馬的な生き方にあこがれていて、
その夏には桂浜での野宿も敢行した僕にとっては
どストライクなイベント。
これだ!と直感して、イベントに参加しました。
その主催がサンクチュアリ出版で、
高橋歩さんを含む5人のゲストが
お芝居の後にトークをする、という企画でした。
僕の会は、
のちに映画監督になる軌保博光(てんつくマン)さん
あの時に配られた小冊子
「クロスロードジェネレーションブック」
(サンクチュアリ出版が名言集「クロスロード」刊行に合わせて発行した小冊子)
僕は帰りの新幹線でこの冊子を読んで、
涙が出るほど衝撃を受けて、
「この本を新潟で配らなきゃ」と思って、
サンクチュアリ出版に電話した。
「この本を100冊、送ってほしいんですけど、いくらですか?」
「えっ。100冊ですか?」
「はい。100冊、お願いします」
「ホントは300円なんですが、200円でいいですよ。」
という会話を経て、
僕は20000円を振り込み、
クロスロードジェネレーションブック100冊を手に入れた。
もう20年も前の話。
でも、この時の「配らなきゃいけない」
っていう謎の使命感というか、おせっかいな気持ちって
今もあるよなあと思った。
結局本屋ってそういう衝動の積み重ねを
カタチにすることなのかもしれないですね。
僕には、売りたい本があります。
たまに、「売らなければいけない本」に出会います。
そう言えば、
僕の業界人(?)としての出発点は、
サンクチュアリ出版の本に出会ったことでした。
1998年11月。
設立者の高橋歩さんが、社長を引退し、
世界一周新婚旅行に出るというタイミング。
僕は夜に東京都北区王子のバー「狐の木」で行われた
農学部系の学生・社会人の集まりに行ったのでした。
たしか旅の途中だった僕は、
午後早めにお店についていて、
地下にある「王子小劇場」で
お芝居を見ることになっていました。
その時の情報源は、
「20代サミットメーリングリスト」
PCを持ち歩いて、
公衆電話のダイアルアップ回線で、
メールを受信して、
みたいな旅をしていた僕に、熱いメールが飛び込んできてました。
「20代、熱くなって時代を駆け抜けろ」
ストレートだな。(笑)
当時、坂本龍馬的な生き方にあこがれていて、
その夏には桂浜での野宿も敢行した僕にとっては
どストライクなイベント。
これだ!と直感して、イベントに参加しました。
その主催がサンクチュアリ出版で、
高橋歩さんを含む5人のゲストが
お芝居の後にトークをする、という企画でした。
僕の会は、
のちに映画監督になる軌保博光(てんつくマン)さん
あの時に配られた小冊子
「クロスロードジェネレーションブック」
(サンクチュアリ出版が名言集「クロスロード」刊行に合わせて発行した小冊子)
僕は帰りの新幹線でこの冊子を読んで、
涙が出るほど衝撃を受けて、
「この本を新潟で配らなきゃ」と思って、
サンクチュアリ出版に電話した。
「この本を100冊、送ってほしいんですけど、いくらですか?」
「えっ。100冊ですか?」
「はい。100冊、お願いします」
「ホントは300円なんですが、200円でいいですよ。」
という会話を経て、
僕は20000円を振り込み、
クロスロードジェネレーションブック100冊を手に入れた。
もう20年も前の話。
でも、この時の「配らなきゃいけない」
っていう謎の使命感というか、おせっかいな気持ちって
今もあるよなあと思った。
結局本屋ってそういう衝動の積み重ねを
カタチにすることなのかもしれないですね。
2018年02月01日
「差異」こそが価値
人と違うこと。
人とというか、多数と違うこと。
差異こそが利益の源泉である。
均質なものの供給こそが価値だった
時代があった。
歴史を見ないと、いま起きている現状が、
当たり前のように思ってしまう。
「終身雇用、年功序列」
は日本が高度成長していた時に大いに機能した。
なぜ、機能したか。
求めるスペックが近かったし、
そして何より、転職というエネルギーは、
本人にとっても、社会にとっても、大きなコストだったから。
供給システムとして
機能したのが学校であるし、「学歴社会」だった。
均質な人を「輪切り」にして、管理者と非管理者に分ける。
それはもっとも効率的な生産システムだった。
学びの場の歴史的スタンダードは、
日本でも例外ではなく、
「寺子屋スタイル」であると言われる。
「場」に人が集まって、各自が学んでいる。
そこに分からないことが出てきたとき、
師匠の出番がやってくる。
いま、web上にも良質なコンテンツがあふれている。
そんなときに、「学校」という「場」が果たすべき役割とはなんだろうか?
各教科の勉強なのだろうか?
それとも集団生活なのだろうか?
それは何の役に立つのだろうか?
いや、そもそも、「それは何の役に立つのだろう?」
という問い自体が学びのお買い物化を体現しているのではないか。
「学び」というのが、一人前の「社会人」を育てるものだと仮定して、
学ぶべきものとはなんだろうか?

「公教育をイチから考えよう」(リヒテルズ直子×苫野一徳 日本評論社)
この中で、苫野さんは、
学びの「個別化」「協同化」「プロジェクト化」
を繰り返し説く。
学校という「場」は、
特にその協同化・プロジェクト化の拠点になる役割があると。
僕はこれは、
学校ではなくて、図書館や本屋、ブックカフェの
役割なのではないかと思う。
学校という均質集団では、プロジェクトに幅が出ない。
「地域」という不確定要素があることで、
おもしろいプロジェクトができていく。
そして、そこには、ビジネスというか、商売、
「小商い」と呼べるようなものがあると、
さらに面白いと思う。
商いには、ゴール(目標)があり、
それがそのプロジェクトに目的地を
与えてくれるから。
そして、その際にも、
「このプロジェクトは何が違うのか?」
という問いが必須となってくる。
差異こそが価値の源泉である。
そんなことを子どもたちに伝えられる
プロジェクト基地のような本屋や図書館をつくっていくこと。
それ、やってみたいわ。
人とというか、多数と違うこと。
差異こそが利益の源泉である。
均質なものの供給こそが価値だった
時代があった。
歴史を見ないと、いま起きている現状が、
当たり前のように思ってしまう。
「終身雇用、年功序列」
は日本が高度成長していた時に大いに機能した。
なぜ、機能したか。
求めるスペックが近かったし、
そして何より、転職というエネルギーは、
本人にとっても、社会にとっても、大きなコストだったから。
供給システムとして
機能したのが学校であるし、「学歴社会」だった。
均質な人を「輪切り」にして、管理者と非管理者に分ける。
それはもっとも効率的な生産システムだった。
学びの場の歴史的スタンダードは、
日本でも例外ではなく、
「寺子屋スタイル」であると言われる。
「場」に人が集まって、各自が学んでいる。
そこに分からないことが出てきたとき、
師匠の出番がやってくる。
いま、web上にも良質なコンテンツがあふれている。
そんなときに、「学校」という「場」が果たすべき役割とはなんだろうか?
各教科の勉強なのだろうか?
それとも集団生活なのだろうか?
それは何の役に立つのだろうか?
いや、そもそも、「それは何の役に立つのだろう?」
という問い自体が学びのお買い物化を体現しているのではないか。
「学び」というのが、一人前の「社会人」を育てるものだと仮定して、
学ぶべきものとはなんだろうか?

「公教育をイチから考えよう」(リヒテルズ直子×苫野一徳 日本評論社)
この中で、苫野さんは、
学びの「個別化」「協同化」「プロジェクト化」
を繰り返し説く。
学校という「場」は、
特にその協同化・プロジェクト化の拠点になる役割があると。
僕はこれは、
学校ではなくて、図書館や本屋、ブックカフェの
役割なのではないかと思う。
学校という均質集団では、プロジェクトに幅が出ない。
「地域」という不確定要素があることで、
おもしろいプロジェクトができていく。
そして、そこには、ビジネスというか、商売、
「小商い」と呼べるようなものがあると、
さらに面白いと思う。
商いには、ゴール(目標)があり、
それがそのプロジェクトに目的地を
与えてくれるから。
そして、その際にも、
「このプロジェクトは何が違うのか?」
という問いが必須となってくる。
差異こそが価値の源泉である。
そんなことを子どもたちに伝えられる
プロジェクト基地のような本屋や図書館をつくっていくこと。
それ、やってみたいわ。




