2023年11月28日
その「連携」は不可能を可能にしているか
昨日は地域学Aの発表会でした。
もっと現場での振り返りでリアルな言葉を
拾えてたら、プレゼンは面白かったなと、
地域と協働した授業について、振り返りました。
盛んに聞かれる学校と地域の「連携」。
そして「コーディネート」もしくは「コーディネーター」
その意味をあらためて考えないといけない。
ここで参考になるのが、茨城の株式会社えぽっくの若松さんの言葉
参考:目的地を決めないこと、地図とコンパスを持たないこと
http://hero.niiblo.jp/e492190.html
~~~
えぽっくにとって、コーディネートするとは、
・無理でしょ、と思えることをできるようにつなぐ
・面白がる(リフレーミング)
・リソースを拡張する
ことだと。たしかに、コーディネートの価値は、ここにある。
・不可能(だと感じること)を可能にするために「場をつくること(立ち位置を知ることとイメージの共有)」
・新しいアイデア、発想、具体先を出すために「面白がる(⇒リフレーミング)すること」
・それらの実行によって、自分の手持ちだでなく「資源(リソース)を拡張すること」
・仮説を実行した後にふりかえることによって「検証すること」
~~~
なるほど。
学校と地域の「連携」とよく言われるけど、非常に定義が曖昧で、
たとえば、中学校と高校の「連携授業」といえば、
1 どちらかの授業への「参加」(あるいは共通授業の構築)
2 発表会(プレゼン)の共有
だろうか。
学校と地域の「連携」と言えば
1 地域の人が学校に入ってくる授業
2 児童生徒が地域に出ていく「職場体験」「校外学習」
だろうか。
その時にコーディネーターの意味や価値とは、なんだろうか。
問いとなってくるのは若松さんの3つの言葉だ。
1 その「連携」は不可能を可能にしているか?(価値を生み出しているか?)
2 その「連携」は既存の枠組みを超えているか?(面白がっているか?)
3 その「連携」はどんなリソースを拡張しているか?
わかりやすいのは「リソースの拡張」でしょうね。
中学生の授業に高校生が高校生の授業に地域の大人が
入り込み、授業のコンテンツとして機能している。
あるいは教科書だけではない現場での体験・体感を引き出している。
問われるのは1と2。
不可能を可能にしているのか、そして既存の枠組みを超えているか?
「1 不可能を可能にする」とは、高校生だけではできないという意味ではなく、「高校生でなければできないこと」「高校生×地域によって初めて生まれるもの」なのだと思う。
「2 既存の枠組みを超えているか?」についても、その連携が未来のあるべき姿に近づいているか?という問いが生まれる。
この二つを問いかけていくこと。
形だけの「連携」にとどまらないためには考えておきたい問いである。
もっと現場での振り返りでリアルな言葉を
拾えてたら、プレゼンは面白かったなと、
地域と協働した授業について、振り返りました。
盛んに聞かれる学校と地域の「連携」。
そして「コーディネート」もしくは「コーディネーター」
その意味をあらためて考えないといけない。
ここで参考になるのが、茨城の株式会社えぽっくの若松さんの言葉
参考:目的地を決めないこと、地図とコンパスを持たないこと
http://hero.niiblo.jp/e492190.html
~~~
えぽっくにとって、コーディネートするとは、
・無理でしょ、と思えることをできるようにつなぐ
・面白がる(リフレーミング)
・リソースを拡張する
ことだと。たしかに、コーディネートの価値は、ここにある。
・不可能(だと感じること)を可能にするために「場をつくること(立ち位置を知ることとイメージの共有)」
・新しいアイデア、発想、具体先を出すために「面白がる(⇒リフレーミング)すること」
・それらの実行によって、自分の手持ちだでなく「資源(リソース)を拡張すること」
・仮説を実行した後にふりかえることによって「検証すること」
~~~
なるほど。
学校と地域の「連携」とよく言われるけど、非常に定義が曖昧で、
たとえば、中学校と高校の「連携授業」といえば、
1 どちらかの授業への「参加」(あるいは共通授業の構築)
2 発表会(プレゼン)の共有
だろうか。
学校と地域の「連携」と言えば
1 地域の人が学校に入ってくる授業
2 児童生徒が地域に出ていく「職場体験」「校外学習」
だろうか。
その時にコーディネーターの意味や価値とは、なんだろうか。
問いとなってくるのは若松さんの3つの言葉だ。
1 その「連携」は不可能を可能にしているか?(価値を生み出しているか?)
2 その「連携」は既存の枠組みを超えているか?(面白がっているか?)
3 その「連携」はどんなリソースを拡張しているか?
わかりやすいのは「リソースの拡張」でしょうね。
中学生の授業に高校生が高校生の授業に地域の大人が
入り込み、授業のコンテンツとして機能している。
あるいは教科書だけではない現場での体験・体感を引き出している。
問われるのは1と2。
不可能を可能にしているのか、そして既存の枠組みを超えているか?
「1 不可能を可能にする」とは、高校生だけではできないという意味ではなく、「高校生でなければできないこと」「高校生×地域によって初めて生まれるもの」なのだと思う。
「2 既存の枠組みを超えているか?」についても、その連携が未来のあるべき姿に近づいているか?という問いが生まれる。
この二つを問いかけていくこと。
形だけの「連携」にとどまらないためには考えておきたい問いである。
2023年11月22日
関係人口は「一緒にやる」「場と余白」がつくる
「名所じゃない観光」Day1でした。
ゲストは香川県三豊市の石井さんと鳥取県南部町の井上さん。
メモ:石井さん(香川県三豊市 Cafe季)
洋菓子店⇒古民家でお店がしたい
Cafe季(とき)を開設
テーマ「地域のアップデート」
カフェ季(とき):地産地消:消費者と共に生産者を応援できる拠点
⇔シェアハウスNAE:移住支援:ヨソ者と地域、人と人をつなぐHUB拠点
おためしカフェ
ジュージュー会:毎月10日に行う焼肉会
三日月の夜会:ウチの町にないものをひとつ実現するには?というテーマでディスカッションする
地域の人と未来に向けての話がしたい、マッチングのミスを減らしたい。
ヨソ者のアツい思いをどのように地域の人が受けとめるか。
やり方。
模造紙、町内のマップ:町内にあるもの、景色が綺麗とか、魅力の洗い出し
この町に住むとしたら何が必要か?ハード、ソフトでないものをひとつだけ企画する
サイコロで予算を決めて、実現するための妄想アイデア出しをする。
⇒こうやったらできるよ、っていうところまでやっていく話し合い。
⇒マップが成長していく
⇒空き家ができたら、これやります、みたいな。
「一緒にやる」っていうのが大事。
シミュレーションゲームを行う。
カルチャー:大人の部活動:草木染、キャリアカウンセリング
メモ:井上さん
「食べて泊まれる寄り合いの場 てま里」でゲストハウスと子ども向け英会話教室を運営して5年目
好きなもの「旅×子ども」⇒ゲストハウス×英会話教室⇒いろんな価値観や職業の大人に出会える機会。
親でも先生でもないけど子どもと大人をつなぎたい。
てま里は、里山のくらしと、人のあたたかみを分かち合える場所。
宿やカフェは手段で、目的は、鳥取県南部町の手と手、自然の間に込められたあたたかみを世代、住む場所、性別を超えて分かち合うことです。
ゲストハウス+カフェ+交流スペース
土日になると小学生が何かつくってる
親子ワーケーション(農泊・てま里宿泊)を実施
全校17人の小学校に体験入学
ちょっとのんびり滞在⇒日常~非日常が溶ける感覚
子どもにとって特別な「何か」が見つかる旅
★お互いを知る時間:オンラインでつなぐ
★五感を感じる体験
★偶然の出会いとあたたかさ
トークセッション
★移住したきっかけ
石井さん:古民家でお店をしたい。
地域でビジネスをする:ハードルが高い
⇒地域おこし協力隊でコミュニケーションを図りながら起業する。
パティシエ+子どもの食育⇒カフェ
井上さん:ゲストハウスで英会話ができるところ
絵(画)ファーストの移住
つながりから場所が見つかった!⇒地域おこし協力隊の枠に入れてくれた。
「地域の人」「地元」の定義が違う。
家具をつくるイベントをやり続ける。
「この人にまた会いたい」
⇒お互いが一参加者ではなくて、余白のある場でコミュニケーションを取っているか。
⇒プログラムに余裕を持っていた方がいい:偶然的な機会
⇒一方通行じゃないで一緒につくる場
町の小学生限定で、外国人とかキャンプとか農家さんと料理をしたいとか。
⇒「料理をする」っていうコミュニケーションはありかもしれない。
イベントを月に1度くらいやっていた。
芝生で朝ごはんを食べようとか
食材を活かしたカフェメニューづくり
地域の人にイベントやってもらう:絵本メニュー作りとか
どんなカフェが必要ですか?
⇒カフェをやるという前提になる。
⇒どんなものが必要か?できたときに来てくれる(確認したくなる)
フィールドワークで「人目が気になる」⇒カフェの配置で目線が合わないように設計
話を聞いていくこと。他人事をいかに自分事にするか?感情論を汲み取って、反映していく。
話をただ聞くのではなく、「農家の手伝いをする」などの双方にメリットがあるような
「観光」じゃなくて地元の人が楽しんでいるイベントに外の人も呼べる
地域の人が一緒に何かをつくってる、これからの話をしている、その場に参加してもらう。
それを余白のある場にできたらまた会いたくなる人になる。
名所じゃない観光=ホームステイ
探究カードで行き先を決めるとか
~~~
関係人口ってつくるものではなくて、「一緒にやる」「場と余白」によって、つくられるものなのだなと。
関係人口って、厳密には数値化されないと思うのだけど、やっぱりそれを「個人」としてカウントするのではないほうがいいような気がしますね。
場というか、環境によって、いつのまにか、なっていた、みたいなものなのだろうな。
いつのまにか、「一緒にやる=ともにつくる」仲間になっている、そんな場をつくりたいなあと。
まずは三日月の夜会の阿賀町バージョンでもやりましょうか。
ゲストは香川県三豊市の石井さんと鳥取県南部町の井上さん。
メモ:石井さん(香川県三豊市 Cafe季)
洋菓子店⇒古民家でお店がしたい
Cafe季(とき)を開設
テーマ「地域のアップデート」
カフェ季(とき):地産地消:消費者と共に生産者を応援できる拠点
⇔シェアハウスNAE:移住支援:ヨソ者と地域、人と人をつなぐHUB拠点
おためしカフェ
ジュージュー会:毎月10日に行う焼肉会
三日月の夜会:ウチの町にないものをひとつ実現するには?というテーマでディスカッションする
地域の人と未来に向けての話がしたい、マッチングのミスを減らしたい。
ヨソ者のアツい思いをどのように地域の人が受けとめるか。
やり方。
模造紙、町内のマップ:町内にあるもの、景色が綺麗とか、魅力の洗い出し
この町に住むとしたら何が必要か?ハード、ソフトでないものをひとつだけ企画する
サイコロで予算を決めて、実現するための妄想アイデア出しをする。
⇒こうやったらできるよ、っていうところまでやっていく話し合い。
⇒マップが成長していく
⇒空き家ができたら、これやります、みたいな。
「一緒にやる」っていうのが大事。
シミュレーションゲームを行う。
カルチャー:大人の部活動:草木染、キャリアカウンセリング
メモ:井上さん
「食べて泊まれる寄り合いの場 てま里」でゲストハウスと子ども向け英会話教室を運営して5年目
好きなもの「旅×子ども」⇒ゲストハウス×英会話教室⇒いろんな価値観や職業の大人に出会える機会。
親でも先生でもないけど子どもと大人をつなぎたい。
てま里は、里山のくらしと、人のあたたかみを分かち合える場所。
宿やカフェは手段で、目的は、鳥取県南部町の手と手、自然の間に込められたあたたかみを世代、住む場所、性別を超えて分かち合うことです。
ゲストハウス+カフェ+交流スペース
土日になると小学生が何かつくってる
親子ワーケーション(農泊・てま里宿泊)を実施
全校17人の小学校に体験入学
ちょっとのんびり滞在⇒日常~非日常が溶ける感覚
子どもにとって特別な「何か」が見つかる旅
★お互いを知る時間:オンラインでつなぐ
★五感を感じる体験
★偶然の出会いとあたたかさ
トークセッション
★移住したきっかけ
石井さん:古民家でお店をしたい。
地域でビジネスをする:ハードルが高い
⇒地域おこし協力隊でコミュニケーションを図りながら起業する。
パティシエ+子どもの食育⇒カフェ
井上さん:ゲストハウスで英会話ができるところ
絵(画)ファーストの移住
つながりから場所が見つかった!⇒地域おこし協力隊の枠に入れてくれた。
「地域の人」「地元」の定義が違う。
家具をつくるイベントをやり続ける。
「この人にまた会いたい」
⇒お互いが一参加者ではなくて、余白のある場でコミュニケーションを取っているか。
⇒プログラムに余裕を持っていた方がいい:偶然的な機会
⇒一方通行じゃないで一緒につくる場
町の小学生限定で、外国人とかキャンプとか農家さんと料理をしたいとか。
⇒「料理をする」っていうコミュニケーションはありかもしれない。
イベントを月に1度くらいやっていた。
芝生で朝ごはんを食べようとか
食材を活かしたカフェメニューづくり
地域の人にイベントやってもらう:絵本メニュー作りとか
どんなカフェが必要ですか?
⇒カフェをやるという前提になる。
⇒どんなものが必要か?できたときに来てくれる(確認したくなる)
フィールドワークで「人目が気になる」⇒カフェの配置で目線が合わないように設計
話を聞いていくこと。他人事をいかに自分事にするか?感情論を汲み取って、反映していく。
話をただ聞くのではなく、「農家の手伝いをする」などの双方にメリットがあるような
「観光」じゃなくて地元の人が楽しんでいるイベントに外の人も呼べる
地域の人が一緒に何かをつくってる、これからの話をしている、その場に参加してもらう。
それを余白のある場にできたらまた会いたくなる人になる。
名所じゃない観光=ホームステイ
探究カードで行き先を決めるとか
~~~
関係人口ってつくるものではなくて、「一緒にやる」「場と余白」によって、つくられるものなのだなと。
関係人口って、厳密には数値化されないと思うのだけど、やっぱりそれを「個人」としてカウントするのではないほうがいいような気がしますね。
場というか、環境によって、いつのまにか、なっていた、みたいなものなのだろうな。
いつのまにか、「一緒にやる=ともにつくる」仲間になっている、そんな場をつくりたいなあと。
まずは三日月の夜会の阿賀町バージョンでもやりましょうか。
2023年11月19日
「見立て」「評価」というコミュニケーション・ツール
マイプロ研修でした。
講師はウィルドアの竹田さん。
マイプロの究極的な目標は、僕としては先日書きましたが、
「世界観」という自転車で漕ぎ出す(23.11.16)
http://hero.niiblo.jp/e493342.html
なのかなあと。
その時に危ういのが「主体性」という言葉です。
参考:「主体性」という監獄(23.11.18)
http://hero.niiblo.jp/e493347.html
学校というフレームで求められる学力をつけてきたのと同じように
探究(マイプロ)というフレームで求められる「主体性」を身につけているのではないか?
果たしてそれは、「自由」な学びなのか?
そんな問いかけ。
リベラルアーツという言葉にあるように、
学びが「自由」への道ならば、その伴走ってどうやるの?
っていう意味で、すごくタイムリーな研修となりました。
~~~以下メモ
みんなの学びの主語を変えること
マイプロの違和感
「プロジェクトはすごく良いけど、よく聞くと先生が生み出したい価値を生み出している」
「高校の3年間でやりきることが求められ、興味がないけどとりあえず行っている」
「学校・地域の資源を使うことは応援されるが、そこからはみ出すことを許されない」
⇒
それは関わる大人の持つ「理想」が共有されていないから「いつの間にか」「やり方がわからないから」
改めて、生徒が主語の学びという理想をみんなで共有するとともに、「関わる周囲の人」の在り方やノウハウを言語化し、共有していきたい。
⇒
・伴走する目的は、「一人ひとりが自走・自燃し、豊かな自分の人生・社会を創っていけるようになること
・自走できるようになるためには「目的意識」「選択肢」「学びを自ら創る」の3つが鍵となる。
・それらの獲得に伴走する上では、「見立て」と、それに応じた「関わり方の使い分け」が大事
★何を目指して僕たちは伴走・関わるのか。僕たちが理想とする「学び」とはどのようなものか
◆応援したい理想の学びの姿
一人ひとりが自分と社会のwell-beingの実現へとつながる自身に合った/自身の望む学びを自走し続けている状態
1 わたしが主語:自分の興味関心や内発的動機に基づく、学習者自身が主語の目的に向かっている
2 自己決定:自らの意思で選択をしている/学習者自身が主導権を持っている
3 カリキュラムなき行動:与えられた環境だけじゃなく枠を超えた機会や資源を活用している
4 わたしと社会をつなげる学び:わたしと社会の関係性の変化や変化へとつながる学びを獲得し、変化をし続けている
★学びとはどのようなものか
学び観:学びは楽しいもの。「辛く我慢するもの」ではない。特に学習者が主語の学びは、楽しく、人生を豊かにする
こども観:子ども自身に誰もが「学びたいこと」がある。無いから植え付けるのではなく、あるものを引き出せば自然に学びはじめる。
時間軸:今のwell-beingが未来につながる。未来のために今苦しむより、今をいかに楽しむかが大事
理想の学びへの伴走の形=ナビゲート
ポイント:大切なのは「自走・自燃していく」ために今何が壁になっているのか。
プロジェクトが進む/成功する
発表がうまい/うまく伝わる
それが本当に大事?という問いをもって関わるのが大事
★どうすれば「自走」できるのか
タテ:自分の理想が明確⇔不明確
ヨコ:カリキュラム泣き学びアクションの選択肢 複数ある⇔ない/少ない
左下1:理想不明確・選択肢 無
・「何をしたいのか」「何を得たいのか」わからない、言葉にできない。
・やらなくてはいけないこと以外をやっていいという発想がない。
・自分にはできないと思っている
右下2:理想不明確・選択肢 多数
・「(いろいろできるのはわかるけど)やりたいことはない」
・「何かやりたいけど、どれもピンとこない」
左上3:理想明確 選択肢 無
・「〇〇ができるようになりたいのだけど、何をしていいかわからない」
・「〇〇したいけけど、自分にはできない」
・「これをやって意味があるのか不安」
右上4:理想明確 選択肢 多数
・「本当にこれでいいのか不安」
・「やったらいいのはわかるけど勇気がでない、踏み出せない」
全体上5:
・「やってみたけど、次に何を考えたらいいかわからない」
・経験から得たことを言語化したり、次に行うべきことのヒントとなるような変化を一人で自覚するのが難しい
⇒「人との関わり」なくして、いきなり自走はできるようにならない
これらの「壁」を共に解決する「補助輪」となる伴走者に必要なのが「ナビゲート」
ナビゲートにおける関わり方
1 エンパワメント系:個人の自己決定することを強化し、自己効力感を高めることを目指す行動
「面白がり」「意見交換」「同意・承認」「意義付け」
2 リフレクション・試行整理系:これまでのっ経験や思考を共に整理し、次の行動の発見や納得感を高めることを目指す行動。
「理想の言語化」「思考の可視化・言語化」「気づきを生む問いかけ」
3 情報・選択肢提供系:相手が理想に向かって歩む上でより良い「選択肢」となりうる情報を提供することを目指す行動。
「イベント・プログラム・協力者等機会の紹介」「行動手段・やり方の紹介」「視野を広げる話
1 「マイプロでやること、何も思いつかなくて・・・」「みんなすごいことやってるけど、ああいうのはちょっと自分には無理かなって」
(エンパワメント系)
⇒「(相手の興味とかこだわり聞いて)それ面白いよね!俺も好き!特に〇〇好きで。わかってるねえ」(面白がり)
⇒「(興味のあること聞いてみて、)それ、すごい大切な視点だね。俺は〇〇と思うけど、どう思う?(意見交換・同意承認)
(リフレクション・思考整理系)
⇒「〇〇さんは、なにか将来こうなりたいとか?逆にこうはなりたくないってイメージある?」(理想の言語化)
⇒「何が自分には難しいと思った?それはなぜ?」(思考の可視化・言語化)
(情報・選択肢提供系)
⇒「〇〇、△△、✕✕、この3つだったら強いて言えばどれが面白そう?」(イベント・プログラム・協力者等機会の紹介)
⇒「別にすごいことじゃなくても、例えばまずはボランティアするとか、動画を色々見てみるのもありだよ。」(行動手段・やり方の紹介)
2 「マイプロでやること、ピンとくるものがなくて・・・」「色々面白そうと思うことやものはあるけど、踏み出せない」
(エンパワメント系)
⇒「(相手の興味とかこだわり聞いて)それ面白いよね!俺も好き!特に〇〇好きで。わかってるねえ」(面白がり)
⇒「(気になる選択肢を聞いて)合宿良いよね。楽しいし、知らない人と話すと世界広がりそうだし」(同意承認、意義付け)
(リフレクション・思考整理系)
⇒「例えば最近、なんでこうなんだろって思ったことなにか無い?」(理想の可視化)
⇒「面白いと思ったものってどんなもの?なにか共通点ある?」(思考の可視化・言語化)
(情報・選択肢提供系)
⇒「(色々話を引き出した上で)少しでも現場を見たいって気持ちがあるなら、まずは〇〇ってイベントおススメだよ。」(イベント・プログラム・協力者等機会の紹介)
⇒「(踏み出せない理由を聞いた上で)だったら、〇〇さんに話聞いてみるところから始めて見ると良いかも。」(イベント・プログラム・協力者等機会の紹介)
3 「街をもっと元気にしたいんだけど、何から始めていいかわからなくて。」「地域のボランティアとかもしたいけど不安だし何かそれで生まれるのかわからない」
(エンパワメント系)
⇒「その視点なかったなあー、たしかに!まち元気になったら良いよね。」(面白がり)
⇒「良いアクションイメージだね。俺もボランティアしたことあるけど、その場に行かないとわからないことが多いってことがすごくわかったことあるよ。」(同意承認 意義付け)
(リフレクション・思考整理系)
⇒「街を元気にするアクションを通じて、自分はどうなりたいとかってある?」(気づきを生む問いかけ)
⇒「そもそもななんで街は元気じゃないんだろう}「そもそもなぜそれをしたいって思ったの?」(思考の可視化・言語化)
(情報・選択肢提供系)
⇒「街をもっと元気にする上では、〇〇って検索してみるといいかも」(行動手段・やり方の紹介)
⇒「(目的を聞いた上で)自分だったら〇〇とかやるかも。もしくは✕✕とか。こんな事例もあるし。こういうのも楽しいかもね」(視野を広げる話)
4 「自分のプロジェクトのフィードバックのために教授にメールしてみようと思ったのだけど勇気が出ない」「農家を救うためのイベントアイデアは考えたし、色々な人から評価もらったけど、これでいいのかな。」
(エンパワメント系)
⇒「なかなか怖いよね。でも僕が〇〇でもそれはやろうって思うかも。有識者に聞くのが一番だよ」(同意承認 意義づけ)
⇒すごいオモシロイと思ったよ。特に〇〇が。なんで〇〇にしたの?△△という手もありそうだけど。」(面白がり 意見交換)
(リフレクション・思考整理系)
⇒「何が怖いの?何を恐れているんだろうね・・・(言葉にして見せて)意外に怖いことないんじゃない?」(思考の可視化・言語化)
⇒「何に納得してないと思う?何があるとスッキリしそうかな?」「アイデアを考える中で自分の中のモチベーションとか関心に変化したことってある?」(気づきを生む問いかけ)
(情報・選択肢提供系)
⇒「メールもいいし、手紙書いてみるとかも良いかもよ」(行動手段・やり方の紹介)
⇒「〇〇という助成金とかも使えるかもよ。高校生でも使ってる事例あるよ(視野を広げる話)
⇒「〇〇さんに話聞いてみたら?」(イベント・プログラム・協力者等機会の紹介)
★ナビゲートは一人で行うものではなく、様々な人が連携し合って行うのが望ましい。
★高校生のコンフォートゾーン(安心安全な場所)と外部をつないだり、紹介する存在
「きっかけとなる存在(機会・人・情報)」と「一緒に学ぶ仲間」:自分の興味関心をより深め、行動するための資源や機会をくれる存在。
情報提供ナビゲート:自分の出来ること、挑戦できることを共に見つけてくれる繋いでくれる
リフレクション型ナビゲート:何に興味があるのか、何をしたいのかを言語化してくれる存在
マッチング型ナビゲート:外部ナビゲーターとつなぐ・紹介してくれる存在
専門家ナビゲート:より専門的な領域で自身の問いや進む方を共に考える存在
★ナビゲートの極意は「見立て(自分/相手)」「関わり方の使い分け」にある
ナビゲート:一人ひとりが自分と社会のwell-beingへと近づく学習者主体の学びの【自走】を支える伴走の形
・信頼できる/相談したくなる関係性の構築へつながる振る舞い
・自走に向けた成長プロセスへの理解とその手段・選択肢に関する理解
・相手の状態の見立てとそれに応じた関わり方・バランスの調整
★「見立て」における観点
【観点⇒目指す状態】
・主語が「あの人=先生・教育者」か「わたし=学習者」か
⇒学習者が自身の内発的動機・興味関心にもとづく意思決定をしている。
・目的が「プロジェクト」か「人生」か
⇒わたしと社会の関係性の進化・深化につながる学びを獲得し、次の行動を検討している
・時間軸が「高校生活/総探等の範囲内での行動」か「高校卒業以降、より長期間での行動」か
⇒高校時代に閉じず、自らの時間軸/ペースでやりたいこと・目指したいことを語っている。
・アクションが「カリキュラム・授業の内側/設定した地域やテーマ」か「カリキュラム・授業の外側/制限のないもの」か
⇒与えられた環境だけでなく、枠を超えた機会や資源の選択肢を認識し、活用している
★「見立て」の要素
相手の状況:
「何につまずいている/何が壁となっているのだろうか?」
「何を必要としている/何があれば前に進めるのだろうか?」
自分の状況:
「どんな関わり方が得意なのだろうか?」
「何を渡すことができるのだろうか?」
★まとめ
プロジェクトの伴走ではなく人生の伴走
・伴走する目的は、「一人ひとりが自走・自燃し、豊かな自分の人生・社会を創っていけるようになること
・自走できるようになるためには「目的意識」「選択肢」「学びを自ら創る」の3つが鍵となる。
・それらの獲得に伴走する上では、「見立て」と、それに応じた「関わり方の使い分け」が大事
~~~
こういうの地域の人たちとやっていきたいなと。生徒と地域の大人との関係で言えば、大人自身もプレイヤーであるってこと。ナビゲートを経て、ジェネレートする、されるみたいな関係へと育っていければいい。
教育的文脈だけではなく、まちづくり的文脈で、関わり続ける大人としての関わりは考えたいなと
その時に、「見立て」や「評価(たとえばルーブリック評価)」はどんな意味になるのか?と考えると、「コミュニケーション・ツール」として役立てることかなあと思った。
評価される、もっと端的に言えば、ルーブリック評価の2を3に、4に、5にするために行動するのではなく、「評価」を通じて、自分自身の自転車を見つけ、漕ぎ出していくこと。
つまり「評価」を手段にすること。そしてそれは、生徒と地域の大人とのコミュニケーションだけじゃなく、大人同士のコミュニケーション機会を生んでいく。それは町の大人の価値観や方向性のチューニングにもつながり、新しい価値を生み出す行動に変わるのかもしれない。
ひたすらに「機会」から学ぶ。やったことを振り返り、疑問や次のステップを見つけ、次のステージへと行く。その機会のひとつとして「評価」があるのだと思う。
そんなコミュニケーション・デザインをつくり上げたいなと。
講師はウィルドアの竹田さん。
マイプロの究極的な目標は、僕としては先日書きましたが、
「世界観」という自転車で漕ぎ出す(23.11.16)
http://hero.niiblo.jp/e493342.html
なのかなあと。
その時に危ういのが「主体性」という言葉です。
参考:「主体性」という監獄(23.11.18)
http://hero.niiblo.jp/e493347.html
学校というフレームで求められる学力をつけてきたのと同じように
探究(マイプロ)というフレームで求められる「主体性」を身につけているのではないか?
果たしてそれは、「自由」な学びなのか?
そんな問いかけ。
リベラルアーツという言葉にあるように、
学びが「自由」への道ならば、その伴走ってどうやるの?
っていう意味で、すごくタイムリーな研修となりました。
~~~以下メモ
みんなの学びの主語を変えること
マイプロの違和感
「プロジェクトはすごく良いけど、よく聞くと先生が生み出したい価値を生み出している」
「高校の3年間でやりきることが求められ、興味がないけどとりあえず行っている」
「学校・地域の資源を使うことは応援されるが、そこからはみ出すことを許されない」
⇒
それは関わる大人の持つ「理想」が共有されていないから「いつの間にか」「やり方がわからないから」
改めて、生徒が主語の学びという理想をみんなで共有するとともに、「関わる周囲の人」の在り方やノウハウを言語化し、共有していきたい。
⇒
・伴走する目的は、「一人ひとりが自走・自燃し、豊かな自分の人生・社会を創っていけるようになること
・自走できるようになるためには「目的意識」「選択肢」「学びを自ら創る」の3つが鍵となる。
・それらの獲得に伴走する上では、「見立て」と、それに応じた「関わり方の使い分け」が大事
★何を目指して僕たちは伴走・関わるのか。僕たちが理想とする「学び」とはどのようなものか
◆応援したい理想の学びの姿
一人ひとりが自分と社会のwell-beingの実現へとつながる自身に合った/自身の望む学びを自走し続けている状態
1 わたしが主語:自分の興味関心や内発的動機に基づく、学習者自身が主語の目的に向かっている
2 自己決定:自らの意思で選択をしている/学習者自身が主導権を持っている
3 カリキュラムなき行動:与えられた環境だけじゃなく枠を超えた機会や資源を活用している
4 わたしと社会をつなげる学び:わたしと社会の関係性の変化や変化へとつながる学びを獲得し、変化をし続けている
★学びとはどのようなものか
学び観:学びは楽しいもの。「辛く我慢するもの」ではない。特に学習者が主語の学びは、楽しく、人生を豊かにする
こども観:子ども自身に誰もが「学びたいこと」がある。無いから植え付けるのではなく、あるものを引き出せば自然に学びはじめる。
時間軸:今のwell-beingが未来につながる。未来のために今苦しむより、今をいかに楽しむかが大事
理想の学びへの伴走の形=ナビゲート
ポイント:大切なのは「自走・自燃していく」ために今何が壁になっているのか。
プロジェクトが進む/成功する
発表がうまい/うまく伝わる
それが本当に大事?という問いをもって関わるのが大事
★どうすれば「自走」できるのか
タテ:自分の理想が明確⇔不明確
ヨコ:カリキュラム泣き学びアクションの選択肢 複数ある⇔ない/少ない
左下1:理想不明確・選択肢 無
・「何をしたいのか」「何を得たいのか」わからない、言葉にできない。
・やらなくてはいけないこと以外をやっていいという発想がない。
・自分にはできないと思っている
右下2:理想不明確・選択肢 多数
・「(いろいろできるのはわかるけど)やりたいことはない」
・「何かやりたいけど、どれもピンとこない」
左上3:理想明確 選択肢 無
・「〇〇ができるようになりたいのだけど、何をしていいかわからない」
・「〇〇したいけけど、自分にはできない」
・「これをやって意味があるのか不安」
右上4:理想明確 選択肢 多数
・「本当にこれでいいのか不安」
・「やったらいいのはわかるけど勇気がでない、踏み出せない」
全体上5:
・「やってみたけど、次に何を考えたらいいかわからない」
・経験から得たことを言語化したり、次に行うべきことのヒントとなるような変化を一人で自覚するのが難しい
⇒「人との関わり」なくして、いきなり自走はできるようにならない
これらの「壁」を共に解決する「補助輪」となる伴走者に必要なのが「ナビゲート」
ナビゲートにおける関わり方
1 エンパワメント系:個人の自己決定することを強化し、自己効力感を高めることを目指す行動
「面白がり」「意見交換」「同意・承認」「意義付け」
2 リフレクション・試行整理系:これまでのっ経験や思考を共に整理し、次の行動の発見や納得感を高めることを目指す行動。
「理想の言語化」「思考の可視化・言語化」「気づきを生む問いかけ」
3 情報・選択肢提供系:相手が理想に向かって歩む上でより良い「選択肢」となりうる情報を提供することを目指す行動。
「イベント・プログラム・協力者等機会の紹介」「行動手段・やり方の紹介」「視野を広げる話
1 「マイプロでやること、何も思いつかなくて・・・」「みんなすごいことやってるけど、ああいうのはちょっと自分には無理かなって」
(エンパワメント系)
⇒「(相手の興味とかこだわり聞いて)それ面白いよね!俺も好き!特に〇〇好きで。わかってるねえ」(面白がり)
⇒「(興味のあること聞いてみて、)それ、すごい大切な視点だね。俺は〇〇と思うけど、どう思う?(意見交換・同意承認)
(リフレクション・思考整理系)
⇒「〇〇さんは、なにか将来こうなりたいとか?逆にこうはなりたくないってイメージある?」(理想の言語化)
⇒「何が自分には難しいと思った?それはなぜ?」(思考の可視化・言語化)
(情報・選択肢提供系)
⇒「〇〇、△△、✕✕、この3つだったら強いて言えばどれが面白そう?」(イベント・プログラム・協力者等機会の紹介)
⇒「別にすごいことじゃなくても、例えばまずはボランティアするとか、動画を色々見てみるのもありだよ。」(行動手段・やり方の紹介)
2 「マイプロでやること、ピンとくるものがなくて・・・」「色々面白そうと思うことやものはあるけど、踏み出せない」
(エンパワメント系)
⇒「(相手の興味とかこだわり聞いて)それ面白いよね!俺も好き!特に〇〇好きで。わかってるねえ」(面白がり)
⇒「(気になる選択肢を聞いて)合宿良いよね。楽しいし、知らない人と話すと世界広がりそうだし」(同意承認、意義付け)
(リフレクション・思考整理系)
⇒「例えば最近、なんでこうなんだろって思ったことなにか無い?」(理想の可視化)
⇒「面白いと思ったものってどんなもの?なにか共通点ある?」(思考の可視化・言語化)
(情報・選択肢提供系)
⇒「(色々話を引き出した上で)少しでも現場を見たいって気持ちがあるなら、まずは〇〇ってイベントおススメだよ。」(イベント・プログラム・協力者等機会の紹介)
⇒「(踏み出せない理由を聞いた上で)だったら、〇〇さんに話聞いてみるところから始めて見ると良いかも。」(イベント・プログラム・協力者等機会の紹介)
3 「街をもっと元気にしたいんだけど、何から始めていいかわからなくて。」「地域のボランティアとかもしたいけど不安だし何かそれで生まれるのかわからない」
(エンパワメント系)
⇒「その視点なかったなあー、たしかに!まち元気になったら良いよね。」(面白がり)
⇒「良いアクションイメージだね。俺もボランティアしたことあるけど、その場に行かないとわからないことが多いってことがすごくわかったことあるよ。」(同意承認 意義付け)
(リフレクション・思考整理系)
⇒「街を元気にするアクションを通じて、自分はどうなりたいとかってある?」(気づきを生む問いかけ)
⇒「そもそもななんで街は元気じゃないんだろう}「そもそもなぜそれをしたいって思ったの?」(思考の可視化・言語化)
(情報・選択肢提供系)
⇒「街をもっと元気にする上では、〇〇って検索してみるといいかも」(行動手段・やり方の紹介)
⇒「(目的を聞いた上で)自分だったら〇〇とかやるかも。もしくは✕✕とか。こんな事例もあるし。こういうのも楽しいかもね」(視野を広げる話)
4 「自分のプロジェクトのフィードバックのために教授にメールしてみようと思ったのだけど勇気が出ない」「農家を救うためのイベントアイデアは考えたし、色々な人から評価もらったけど、これでいいのかな。」
(エンパワメント系)
⇒「なかなか怖いよね。でも僕が〇〇でもそれはやろうって思うかも。有識者に聞くのが一番だよ」(同意承認 意義づけ)
⇒すごいオモシロイと思ったよ。特に〇〇が。なんで〇〇にしたの?△△という手もありそうだけど。」(面白がり 意見交換)
(リフレクション・思考整理系)
⇒「何が怖いの?何を恐れているんだろうね・・・(言葉にして見せて)意外に怖いことないんじゃない?」(思考の可視化・言語化)
⇒「何に納得してないと思う?何があるとスッキリしそうかな?」「アイデアを考える中で自分の中のモチベーションとか関心に変化したことってある?」(気づきを生む問いかけ)
(情報・選択肢提供系)
⇒「メールもいいし、手紙書いてみるとかも良いかもよ」(行動手段・やり方の紹介)
⇒「〇〇という助成金とかも使えるかもよ。高校生でも使ってる事例あるよ(視野を広げる話)
⇒「〇〇さんに話聞いてみたら?」(イベント・プログラム・協力者等機会の紹介)
★ナビゲートは一人で行うものではなく、様々な人が連携し合って行うのが望ましい。
★高校生のコンフォートゾーン(安心安全な場所)と外部をつないだり、紹介する存在
「きっかけとなる存在(機会・人・情報)」と「一緒に学ぶ仲間」:自分の興味関心をより深め、行動するための資源や機会をくれる存在。
情報提供ナビゲート:自分の出来ること、挑戦できることを共に見つけてくれる繋いでくれる
リフレクション型ナビゲート:何に興味があるのか、何をしたいのかを言語化してくれる存在
マッチング型ナビゲート:外部ナビゲーターとつなぐ・紹介してくれる存在
専門家ナビゲート:より専門的な領域で自身の問いや進む方を共に考える存在
★ナビゲートの極意は「見立て(自分/相手)」「関わり方の使い分け」にある
ナビゲート:一人ひとりが自分と社会のwell-beingへと近づく学習者主体の学びの【自走】を支える伴走の形
・信頼できる/相談したくなる関係性の構築へつながる振る舞い
・自走に向けた成長プロセスへの理解とその手段・選択肢に関する理解
・相手の状態の見立てとそれに応じた関わり方・バランスの調整
★「見立て」における観点
【観点⇒目指す状態】
・主語が「あの人=先生・教育者」か「わたし=学習者」か
⇒学習者が自身の内発的動機・興味関心にもとづく意思決定をしている。
・目的が「プロジェクト」か「人生」か
⇒わたしと社会の関係性の進化・深化につながる学びを獲得し、次の行動を検討している
・時間軸が「高校生活/総探等の範囲内での行動」か「高校卒業以降、より長期間での行動」か
⇒高校時代に閉じず、自らの時間軸/ペースでやりたいこと・目指したいことを語っている。
・アクションが「カリキュラム・授業の内側/設定した地域やテーマ」か「カリキュラム・授業の外側/制限のないもの」か
⇒与えられた環境だけでなく、枠を超えた機会や資源の選択肢を認識し、活用している
★「見立て」の要素
相手の状況:
「何につまずいている/何が壁となっているのだろうか?」
「何を必要としている/何があれば前に進めるのだろうか?」
自分の状況:
「どんな関わり方が得意なのだろうか?」
「何を渡すことができるのだろうか?」
★まとめ
プロジェクトの伴走ではなく人生の伴走
・伴走する目的は、「一人ひとりが自走・自燃し、豊かな自分の人生・社会を創っていけるようになること
・自走できるようになるためには「目的意識」「選択肢」「学びを自ら創る」の3つが鍵となる。
・それらの獲得に伴走する上では、「見立て」と、それに応じた「関わり方の使い分け」が大事
~~~
こういうの地域の人たちとやっていきたいなと。生徒と地域の大人との関係で言えば、大人自身もプレイヤーであるってこと。ナビゲートを経て、ジェネレートする、されるみたいな関係へと育っていければいい。
教育的文脈だけではなく、まちづくり的文脈で、関わり続ける大人としての関わりは考えたいなと
その時に、「見立て」や「評価(たとえばルーブリック評価)」はどんな意味になるのか?と考えると、「コミュニケーション・ツール」として役立てることかなあと思った。
評価される、もっと端的に言えば、ルーブリック評価の2を3に、4に、5にするために行動するのではなく、「評価」を通じて、自分自身の自転車を見つけ、漕ぎ出していくこと。
つまり「評価」を手段にすること。そしてそれは、生徒と地域の大人とのコミュニケーションだけじゃなく、大人同士のコミュニケーション機会を生んでいく。それは町の大人の価値観や方向性のチューニングにもつながり、新しい価値を生み出す行動に変わるのかもしれない。
ひたすらに「機会」から学ぶ。やったことを振り返り、疑問や次のステップを見つけ、次のステージへと行く。その機会のひとつとして「評価」があるのだと思う。
そんなコミュニケーション・デザインをつくり上げたいなと。
2023年11月18日
「主体性」という監獄
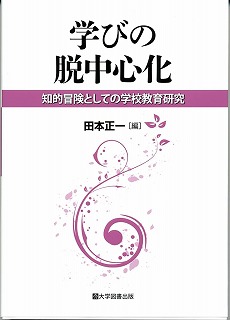
『学びの脱中心化~知的冒険としての学校教育研究』(田本正一編 大学図書出版)
読み直し
以前の読書日記はこちら
http://hero.niiblo.jp/e491788.html
(21.6.7 二人称的アプローチとアイデンティティ)
結局アイデンティティの問題に関心があるのだなあと。
今日は最終章(第12章):主体的な学びについての実存論的検討~本来的自己への変容としての学び より
11.14シンポジウムのつづきで、「主体性」について考えてみましょう。
~~~
そもそも「主体的・対話的で深い学び」や「主体的な学び」を行うに先立ち「主体」について明らかにしなければならないはずである。このことを欠いたままに、学習者が学校教育において振舞ったり、活動したりすることを自明視し、その学習活動を主体的な学びとして実践している場合が多い。主体をどのように捉えるかにより、学校教育の主体的な学びの目標や内容、及び方法は異なってくるはずである。
すなわち、主体的な学びの基礎付けが必要となってくるであろう。現状を鑑みると、主体は自明視され、学校的状況の中でよりよく振る舞うことがよいという常識に従い、主体的な学びが論じられ、授業実践されている。
~~~
いやあ、いいですね。こういうそもそも論。疑問を持つって大事だ。
ということで、まずは第1節:近代的主体の形成から
~~~
「『近代性』という特徴を持つすべての思考には、『個人を単位として、世界あるいは人間社会を見る』という共通の発想がある。
「自立した個」を構成単位とすることが、近代であるということが示されている。
近代は、普遍性、合理性を掲げる。つまり、一般的で超時間的な存在を認めるのである。さらに近代はその考え方を人間にも当てはめようとする。すると、人間は普遍的で超時間的な行為が可能であると考えられる。そのことで、状況や環境に埋め込まれた存在ではなく、それから超越した個人が誕生するのである。
このような「自立した個人」を想定すれば、様々な近代社会のシステムを統一的に説明することが可能になる。
「自立」:近代における構成単位
「自律」:自らの行為等をコントロールできること
学校教育の場合は、まさしく自立した個人が自律的に行為することが求められているのである。それを「主体的な学び」と考えてきたのである。
近代は普遍性、及び合理性に強く依存する。さらに、それらを原理として自律した主体を成立させる。その主体は、常に適切な判断や自由な選択が可能となる存在であると考えられているのである。
澤井陽介によれば「主体的な学び」とは
1 興味や関心を持っていること
2 見通しを持っていること
3 粘り強く取り組んでいること
4 自分の学びの振り返りができること
となるが、これらは自律した主体が前提となっており、それは、客体である対象を操作し、支配することができる主体を自明視する近代的な人間観である。
学校という場で自由に学ぶ姿こそが主体的な学びであるということができるのである。
学校教育は近代の本質を貫徹しているといえよう。それはまるで学習者が学校で主体的に振る舞っているように思える。しかしそれらが主体的な学びであろうか。学校教育の実際からすれば、教師の指示通り、あるいは指示の範囲内で活動することも多々あろう。そこから逸脱して自由に活動しようとするならば、不適切であるとみなされ、許されない行為であるとみなされることもあろう。
ここでの疑問は、果たして近代に依拠した学校教育は、主体的な学びであるといえるのかということである。
~~~
いいですね。この問い。まさにまさに、です。
著者はフーコー『監獄の誕生-監視と処罰』から、「生の権力」について説明する。
~~~
フーコーは中世から近代へと移る際「死の権力」が「生の権力」へ移行し、その理由を規律・訓練に求める。その特徴は
1 配分の技術:特定の空間への各個人の配分
2 活動の取り締まり:時間割等を作成し、行為を方向づけていく
3 段階的形成の編成:些末な活動から始まり、次第に高度な活動を行えるように内容を編成していく
こうした一連のシステムは、軍隊、学校、病院などで認めることができる。例えば学校ではクラスという空間に配分される。さらにそこでは毎日の時間割が決められ、それに従って活動していく。また、授業規律などが決められる。ノートの書き方、姿勢、発言の仕方などがその例である。また、1年間で不十分な成果であると課題を与え、一定の水準に達することができるように指導していく。そうすることで、より高い次元へ移行できるようにするのである。つまり、規律・訓練が当然となり、学習者の規格化が成立していく。そのような場所の1つが監獄なのである。
生の権力は、死の権力のように恐怖心を与えていくものではない。むしろ、メンバーに共通の思考様式を身につけさせ、規格化させることで社会秩序を維持するという考え方なのである。いわば思考停止の状態を無意識に作られているとも考えられよう。
~~~
著者は学校でもまさに「生の権力」が蔓延している場所ととらえる。そしてその構造は「パノプティコン」(一望監視施設)だと説明する。
~~~
この施設における管理人は不可視の状態で、囚人は常に見られている状況が続いていると思い込む。すると、囚人たちはいつみられても困らないように自らの行為をよりよくしていくのである。すなわち、規律が効率よく徹底されていくのである。
こうして自らは好ましくない状況であっても、本人の意思とは異なり、受け入れていくこととなる。つまり行為の制御の内面化である。このような独房において可視化された個人がまさに近代の主体であろう。
以上のパノプティコンから次のような結論を導くことができる。それは主体化が服従化を招くという矛盾した結論である。主体の存立根拠は、前述した理性ある自律した人間観である。しかし、フーコーからすれば、それは疑うべき対象となる。すなわち、服従化によって初めて主体化が可能となることである。
それは近代が目指していた主体が虚構でしかないことを意味するのである。そうであれば、学校教育で実施されている「主体的な学び」も再考すべきであろう。フーコーの論から明らかとなる主体的な学びは、服従化においてのみ成立するものだからである。
~~~
「主体」とは何か、鋭く問いかけてくる著者。
このあとにハイデガーの「実存」について言及される。
~~~
現存在は各状況において「どうすべきか」という問いを立てざるを得ない。またその問いは自己についても向けられ、言及される。つまり、現存在は問う存在である。
<わたし>が存在するということは、<わたし>という自律した実体があるのではない。自己と状況とがアド・ホック(ad hoç)に構成されていることを意味しているのである。その意味では現存在は、1回限りのその都度的なものと考えることができよう。一般的に考えられている「いつでもどこでも誰でも」という学習者でないことは確かである。
我々は世界との関係によって構成されている。つまり、我々は世界を作り替えようと行為する。すると、世界が変わると同時に自己が変容するのである。すなわち、自己が世界を形成し、一方で世界が自己を形成するという相互構成的な関係となる。
~~~
「わたし」とは何か?
そんな出発点から考えていきたい人にはとても刺激的な一節ですね。
つづいて、レイヴ/ウェンガーの「状況に埋め込まれた学習」から
~~~
このことは、学習は知識技能の習得ではないことを意味する。すなわち、学習は状況との相互作用によって成立することを意味する。状況が学習者を作り、学習者が状況を作る。さらには学習活動が世界や学習者を作り出すような相互作用のことである。
学校における教師や学習者と、市民社会におけるあらゆる学習資源(ひと・もの・こと)の相互作用によって学習が成立するとみなすのである。すると、教師、学習者、学校、市民社会あるいはそれに関わる学習資源が1つでも欠けると学習は成立しないのである。この関係性を作り上げていくことで教師、学習者はともに変容していくことが期待できるのである。
レイヴらによると、学習は全人格(whole person)を取り込んだ社会的実践であり、その社会的実践への参加としてアイデンティティを形成していくことである。社会的実践の場は、目的が共通している共同体となる。したがって、学習は社会的実践の共同体でなされ、共同体における人々から意味や価値が与えられる実践となる。社会的な実践によって、学習者は共同体の一員としてのアイデンティティを形成する。一方で、共同体は有能な参加者を得てその維持、発展が可能となる。すると学習者は共同体へ参加するには正統的に、かつ周辺的なところからはじめる必要が出てくるのである。すなわち、正統的周辺参加である。
参加とは周辺から十全へと移行する軌跡を描く。つまり、参加は本物であり、周辺的なことから十全へ進む必要がある。
学習の生起は、何かしらの共同体への参加が可能にしている。したがって参加していないということはありえない。
正統的周辺参加からすれば、学習者は社会的実践の共同体に参加することによって、共同体の一員となるための学習が可能となる。参加によって社会的実践の共同体におけるメンバーとして変容していくのである。このような過程を学習と視れば、学習とは共同体への参加となるのである。
~~~
「探究」のキーワードとしての「正統的周辺参加」。まさにこれだなあと思っています。
著者がまとめます
~~~
正統的周辺参加によれば、学習を共同体への参加と捉える。したがって、学習を個人の内面に見る学習論とは決定的に異なるといえよう。さらに「学習はいわば参加という過程であり、個人の頭の中にはないのである。このことは、とりもなおさず、共同体参加者での間での異なった見え方の違いによって学習が媒介されるということである。この定義では『学ぶ』のは共同体である。あるいは少なくとも、学習の流れ(Context)に参加している人たち、といえよう。学習はいわば、共同体参加者にわかち持たれているのであり、一人の人間の行為ではない」
「正統的周辺性は、関連する共同体の結節点だともいえる。こういう意味で正統的周辺参加は権力のものであると同時に無力さのものであり、実践共同体での結合と相互交流を喚起するとともに阻止もする、というところなのである。
つまり周辺性は特定の共同体において熟達していないため、柔軟で他の共同体との交流を可能にすることを意味している。さらに「正統的周辺性のこのあいまいな潜在力こそが、この概念が通常は関係していると認められないような諸関係の結び目に近づくためのかなめになる役割を反映している。」と述べる。つまり、周辺的参加はある特定の共同体だけではなく、複数の共同体への参加を可能にしていく概念だと考えられる。
これらから周辺的参加は、初期状態に戻ることではない。ある共同体への参加によって形成されたアイデンティティを絶対的なものとせず、それ自体を批判の対象とし、柔軟に新たな世界を作りだそうとするのである。周辺的な参加への移行を志向すれば、1つの共同体にとどまらず、1つの共同体にとどまらず、複数の共同体を横断的に移行する可能性が開かれる。すなわち、共同体間を越境するのである。
ここでの越境とは、異なる共同体を自由に横断するのではない。それは複数のそれらをまとめたり、結びつけたりするものである。
過去の学びをリソースとして新たな共同体において変形させたり、結び付けたりして位置づけ直すことを意味するのである。そうすることで新たな自己へと変容するのである。
~~~
著者は「周辺性への回帰」と言っているが、これって「コミュニティ難民のススメ」とか「アンラーニング」とかの文脈でも説明できそうです。
参考:まるでCDのコンピレーションアルバムのように(16.10.24)
http://hero.niiblo.jp/e482541.html
参考:「自分」を揺さぶり「価値」を揺さぶれ(22.2.2)
http://hero.niiblo.jp/e492293.html
「越境」ってなんだっけ?って改めて考えてみる。
「主体性」という言葉を近代(もしくは「学校」)という枠内で捉えないこと。
それは本書によれば、学校という監獄モデルの服従化を前提とした主体性だし、長岡先生的に言えば、目的-手段の世界だし、そこだけが世界のすべてではないのだから、越境しなければならないのだと。その共同体(価値観・方向感を共有した場)を渡り歩き、周辺参加してみること。
「主体性」という監獄を抜け出すこと。
そんなことを考えていたら、1冊の本を思い出した。
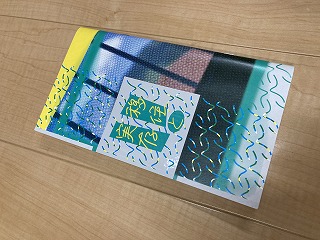
『移住と実存』(瀬下翔太 企画編集)
この鈴木元太さんのところを読み直した。
『地域活動と高校生の〈主体性〉-生活・活動・進路の語りから』
衝撃的な言葉が躍る
~~~
僕は高校3年間を通して主体性・内発性を持った語りを身につけた。主体的にやりたいことを見つけ、内発的な動機のもと自身の生活、学び、キャリア選択を一貫して語ることができるようになった。これは良し悪しで判断できるものではなく、自分が無意識に引き受けたものだった。
「なぜあなたが主体性を持ってこの活動に取り組んでいるのか」を問われ続け、そして自ら問い直す作業を重ねることによって、僕は活動している理由を自らの内発的関心に由来する主体性と結びつけて語れるようになった。同じコミュニティの人とは文脈が共有された状態なのでそのまま固有名詞でしゃべればよいが、発表の場では前提となる文脈や個人的な関係性を一般化した言葉で話す必要が出てくる。その翻訳を行うことに成功した。
東京では、自分がやっていることが自分と社会の全体を作り上げているような感覚を保ち続けることが困難だからだ。津和野のような小さなまちだと、生活の延長でやっている趣味のような活動がもつ意味に、レバレッジがかかる。今までの語りが通用していたのは、地域社会のスケールが小さいからだったのだろう。僕は社会的な自己と主観的な自己とのあいだに乖離を感じるようになった。もっと言えば、自らの語りによって、自分自身が枠にはめられてしまうような窮屈さを感じるようになっていった。
津和野に行って良かったことは何かと聞かれれば、主体性がなくても生活できたことだと答える気がする。自ら主体性を持っていなくとも地域の集まりに誘われたり、偶発的に集まったり、なにかしらイベントが発生するのだ。主体性の有無を問わずに受け入れてくれたコミュニティはとても居心地がよかった。
では主体性を求めていたのは誰なのだろうか。ひとつは地方創生文脈だ。「あなたは何をしたいのですか?」という問いは「あなたはこのまちで何をしたいのですか?という意味合いを含んでいる。
もうひとつは教育文脈だ。近年は自ら問いを立てて、その解決のために情報収集したり、他者と協働したりするという学びのあり方が重視されるようになってきた。自ら問いを立てるために「あなたは何をしたいのですか?」「あなたが関心のある(社会)問題はなんですか?」といった問いが明に暗に投げかけられ、その問いに答えようとし続けてきた。
~~~
いやあ、怖いですね。
「主体性」という「価値」に適応する、適応できてしまう自分への問いかけ。
鈴木さんは、本文の中で、「主体性を削がないこと」と「主体性を問うこと」のあいだには大きな違いがあると説明する。
~~~
主体性を削がないことと、主体性を問うことのあいだには大きな違いがある。津和野の素晴らしい点は、主体性を削がない環境が整っていたところだと思う。けれども、自分の活動を積極的に意味づけして町外の発表会で話したり、地域おこし協力隊と同じ土俵に立ちたくて自分自身をまちづくりの文脈にのせて考えたりすると、主体性を問うばかりの環境がつくられてしまう。
主体性を問われる場なんて、社会に出ればいくらでもあるだろう、しかし、それは多くの場合、社会人として問われる主体性のことを指しているはずだ。いくつかの教育界隈では、社会人がキャリア選択で用いる自己分析の考え方を高校の探究文脈に流用しているケースがあり、僕もその教育を学校外で受けた。例えば、自分のやりたいことをプロジェクトにするためのワークショップとして、will,can,needの重ね合わせを探すフレームワークを使ったことがある。
このようなフレームワークに適応できる高校生もいれば、適応できない高校生もいる。それは言語化能力が足りないとか、主体性が足りないとかいうことではないだろう。高校生は大学生と異なるアイデンティティ形成の時期である。主体性を問うにしても高校生には別の方法論が求められるのではないか。
高校生と社会人の大きな違いは、高校生にはプライベートと仕事の区別がないことだろう。多くの高校生にとって仕事で求められるような主体性はないから、それを問われたら、自分の身の回りのものや生活から考えていくしかない。先ほどのフレームワークで言えば、willやcanは生活の中に見出すことになる。他方で、needについては、一足飛びに社会課題のような大きなトピックになってしまう。
その結果、コミュニティやまちづくりのような、小さなところからコツコツと進め、最終的には社会全体にその取り組みが波及するようなストーリーに辿り着く。本来、プライベートな生活に主体性なんて求められなくても良いはずだし、それを社会的な文脈にのせて語る必要もなければ、社会から共感を得る必要もないはずだ。
~~~
そして「主体性」を問い続ける現在の教育現場に警鐘を鳴らす。
~~~
ひたすら問い続けていくということは、一貫した自我の存在を前提に、自らの自由意志に自信がなければできない。高校時代の僕は、自ら問いを立てたり、他者に問いを投げかけたりすることを無批判に善と捉えてきたけれども、それは負荷の高いことだと今は感じている。
高校生が自らの「主体性」に依拠した行動を続けると、自分の生活を延長させたり、身の回りの出来事への感度を上げたりして、それらに対する意味づけばかりするようになる。そうすると、未知の選択肢を好奇心で選ぶことをしなくなる。
自分自身、自らの主体性を問うことを重視した結果、選ばなかった選択肢がいくつもある。例えば、とりあえず面白そうだからプログラミングを勉強してみようかな、と考えるようなことはなかった。
他方で地方において主体性を重視することは、その社会における生存戦略として真っ当だったようにも思う。どうしても刺激の少ない環境だから、問い、問われるなかで無理矢理にでも周りの出来事に意味を見いださなければ、なににも興味をもたなかったかもしれないからだ。
これは進学校において、学歴至上主義的な価値観をインストールして受験勉強するのと同じようなもので、社会の一要素のようなものだ。結果的に、それなりに今でも興味のある対象を見出すことができた点で、自分にはこの環境がたまたま向いていたのかもしれない。
~~~
「探究」や「マイプロジェクト」でひたすらに主体性を問う、問われることによって、すべての出来事を意味づけようとして結果として、多様な経験ができなくなるという矛盾。
学力、学力と言わなくなった代わりに、こんどは主体性、主体性と言い、目標達成のパラダイムの中でそれが語られていること。
主体性という監獄から高校生たちはいつ、脱出できるのだろうか。
2023年11月16日
「世界観」という自転車を創り、漕ぎ出す
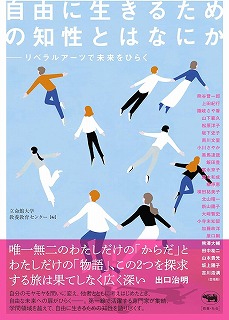
『自由に生きるための知性とはなにか』(立命館大学教養教育センター 晶文社)
なぜ人はあいまいさを嫌うのかP162より
~~~
私たちの社会は、いつの間にか数値による評価経済にどっぷり浸かっていますよね。「商売の業者は信頼できるべきだ」という考えに基づき、信頼できない人をマイナス評価にして排除していく仕組みをつくってきた。
他方、タンザニアの人たちは、業者は信頼できるときもあるし、できないときもあると考えています。羽振りがよいときは信頼できると思ったり、他者にやさしくしていたら「この人は心に余裕があるな」と考えたりする。反対に、「不運が続いているようだから今回は注文をやめておこう」とも、「ちょっと助けてやるか」とも考える。裏切られても、「うまくいってなかったんだな」くらいの感じで、状況が変わったと分かれば、また取引をする。そこにあるのは「人は常に変わりゆくものだ」という前提です。
~~~
いいですね。まさにまさに。
これを高校生に落とし込んでいくときに、坂口恭平さんのエッセンスを借りたいな、と。

『独立国家のつくり方』(坂口恭平 講談社現代新書)
キーワードは、「態度経済」「放課後社会」「交易」このあたりか。
~~~
態度経済は貨幣経済と決別するわけではない。ただそれは匿名化されたシステムとはまったく別のレイヤーにあるものだ。もっと抽象度の高い、かつ具体的な経済感覚である。
態度経済というのは、通貨というような物質によって何かを交換する経済ではない。交換ではなく「交易」するものだ。交易。つまり、そこに人間の感情や知性などの「態度」が交じっていることが重要だ。ただの交換ではないのだ。
「頭の中に都市をつくる」⇒思考都市
自分の様々な思考、志向、嗜好、試行をもとに、都市計画家のように自分の頭の中で実際に都市をつくっていく。そして、人と交易しているときには、その思考都市に招き入れて、対話を行うのである。
~~~
これ、面白いな。本屋さんって、現場で「思考都市」的な対話をしているんじゃないかと思います。
そして本題。
10年前にインパクトを受けた「放課後社会」のキーワードが今よみがえります。
~~~
この社会にはどうやら二つの世界があるらしいということだった。みんなが同じことをやらされる「学校社会」と土井くんが本領を発揮する「放課後社会」。その二つが学校の中で織りまざっているように感じた。
放課後社会は、単一の学校社会と違って、おのおの違う社会の在り方がある。土井くんと僕は同じ放課後社会の仲間だが、目指している社会は違う。でも共存し合える。一方、学校社会は単純でつまらなかった。
学校社会は何度も言うように無意識の世界である。匿名化したレイヤー。これが社会システムのことだ。都市に張り巡らされたインフラのようなものだと言ってもいい。
~~~
大切なのは価値観の形成というより、世界観の醸成でしょ、って感じ。
小規模校の魅力としてよく語られるのは「きめ細かい指導」だが、それを若者のアイデンティティ側面から見たら、ひとりひとりが匿名化されないということなのではないか。学校というシステムが大きくなればなるほど、1人の個人は匿名化され、数値化される。
坂口恭平さんの言う「放課後社会」の形成、それこそが匿名化された社会を生き延びるために高校時代にやってみることなのではないのか。自分自身の放課後社会を見つけること。それは「遊び」を見つけるという意味なのかもしれない。
マイプロジェクトの「マイ」という意味が、マイ放課後社会のようなプロジェクトを一緒につくりたいのよ。「釣りってなんだ?」だよ。
学校社会レイヤーからではない情報。そこに自分独自のレイヤーへの道がある。だから図書館が大切なんですよ。
さらにつづく
~~~
カントは「知る勇気を持て」と言っている。そして、知ったらその自動的な匿名化したレール上の電車から降り、自転車に乗り換えなくてはならない。その自転車は初めて乗るので当然ながらコケる。乗り方を覚える必要がある。
自転車で三回コケても凹んではいけない。今、ほとんどの人が自転車に乗ることができる。コケたから乗れるのだ。しかし、どうやって乗れるようになったのか、もしくは乗れなかった時のことを思い出せる人がいるだろうか。そんなのとっくに忘れている。慣れれば、できなかった自分ですら忘れてしまうのである。もちろんこのレイヤーには「考える」という行為が必要だ。
ただ、何度も言うように、学校社会、つまり無意識の匿名化したレイヤー、つまり社会システムは絶対に忘れてはいけない。このレイヤーから逃れたいと希求する人もいるけれど、それはとんでもない話だ。これがあるから社会は成り立っている。つまり、これは地面のようなものだ。アスファルトです。アスファルトになってしまっているので、息苦しいのだが、本当は社会システムもアスファルトを壊して、ぼこぼこの土のようになればいいのだと思うが、なかなかそうなるのは難しいだろう。
~~~
「探究的な学び」の目的とは、坂口恭平さん的に言えば、この「自転車」づくりということになるのだろうな。「学校社会」という地面(匿名化されたシステム)の上を行き来し、他者(他の自転車)に出会い、交易すること。
匿名化されたシステム(≒学校社会)においては、数値が個性を表す(実際は表さず、交換可能になるだけ)指標になるのだけど、それだけではない「個性」を身につけること、しかもそれは(数値的に)システムから評価されるような「個性」ではなく、自分自身の「世界観」と呼ぶべき何か(≒放課後社会)を必要としているのだと思う。
アスファルトも、自転車が動くには必要な要素である。しかし、アスファルトの地平だけに立っていては、大切なものは見えず、「交易する主体」になることができない。
学校の(勉強の)成績、あるいは他者からの評価だけを気にし続けて、これからずっと生きていくのか?
自らの世界観(≒放課後社会)という自転車を創り出し、徒歩圏内では見えなかった何かや知らなかった誰かに出会う。
「世界観」という自転車で漕ぎ出す、そんな機会をたくさん作って、たくさんコケてほしい。それを人は、世間は「失敗」と呼ぶかもしれない。それは漕ぎ出して者にしか見えない、アスファルトを離れた世界(レイヤー)での機会だ。
機会をさらなる自転車づくりの道具として生かし、次へ向かっていく。その繰り返しによって、アスファルトを見下ろし、風を切っていく視点を手に入れることができるのだ。
僕が高校生に伝えたいのは、この自転車づくりの重要性です。
あなたオリジナルのチャリで、世界へと漕ぎ出さないか。
2023年11月15日
生徒に「学び」を委ねているか

「新潟の未来をSaGaSuプロジェクト」最終事業報告会でした。
午前中の基調講演は、「堀川高校の奇跡」の荒瀬克己先生でした。
いやあ、こんなアツい方が上にいるなんて、日本の教育も悪くないんじゃないかって思える講演でした。ありがとうございました。
文字だけのパワーポイントの行間から伝わる熱意に、心震えました。
まずは、2023年8月31日の「高等学校教育の在り方ワーキンググループの中間まとめ」より
~~~
「『令和の日本型教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」(令和3年1月中教審答申)においては、これからの高等学校教育の目指すべき姿として、社会の形成に主体的に参画するために必要な資質・能力を身に付けられるよう、初等中等教育段階最後の教育機関として
・高等教育機関や実社会との接続機能を果たしていること
・生徒が自立した学習者として自己の将来のイメージを持ち、高い学習意欲を持って学びに向かっていること
・多様な生徒一人一人に応じた探究的な学びが実現されるとともに、STEAM教育などの実社会での課題解決に生かしていくための教科等横断的な学びが提供されていること
などが掲げられ、スクールミッションの再定義やスクールポリシーの策定等が提言された。
・産業構造や社会システムの「非連続的」とも言えるほどの急激な変化
・高等学校教育の在り方を「多様性」と「共通性」の観点から検討
・少子化が加速する地域における高等学校教育の在り方
・社会に開かれた教育課程の実現、探究・文理横断・実践的な学びの推進
~~~
このうちの「多様性」と「共通性」の順番について、荒瀬さんが言及していたのは、これまでは「共通性」と「多様性」の順序で書かれていたのだけど、それが「多様性」⇒「共通性」という順番に変わった。
さらに、締めくくられる言葉がアツい。
~~~
すべての生徒について、その可能性を引き出し、生徒の高等学校生活の満足度と充実度の向上、卒業後の豊かな人生や、生徒個人と社会全体の幸福度の高い状態(well-being)を実現していくべきである。
全ての関係者が連携・協働しながら「生徒を主語にした」高等学校教育の真の実現に向けた取組が進められていくことが期待される。
~~~
「生徒を主語にした」ってホントにその通りだと思うのだけど、「探究」以前のデザインっていうのが大切だと思うんですよね。昨日のパネルディスカッションでうまく答えられなかったのだけど、このあとに出てくる「自立した学習者」っていうのともリンクしてくる。
地域との連携・協働の意味はそこにあるのかもしれない。
学校側にとっての意味:「生徒を主語にした」高等学校教育の実現のためのひとりひとりに最適化された学び
地域側にとっての意味:「生徒を主語にした」高等学校教育のための、探究以前の「場」づくりのプロセスによって地域自身が育つ
学校にとって「地域」は「生徒を主語にした」学びのパートナーであり、地域にとって「学校」は住民主体の参加・参画型まちづくりのパートナーではないか。
だからこそ。
荒瀬先生も言っていた「探究=地域のこと」を学ぶのではないこと。
「市役所にいって、各課に町の課題について聞いてこい」とか
「商店街にいって、各商店に、何か商品開発しませんか?」とか
そういう話ではなくて、生徒自らがその問いを発しているかどうか?
課題意識を持つような状況をつくれるか?というのがポイントなのだと。
探究=世界の広さと深さと遠さを知っていくプロセスなのだと。
次に、どんな学び手に?のところから。
キーワードは「自立した学習者」
~~~
・多様な子供一人一人が自立した学習者として学び続けていけるようになっているか
・多様な機関と連携・協働することによって地域・社会の抱える課題の解決に向けた学びが学校内外で行われ、生徒が自立した学習者として自己の将来イメージを持ち、高い学習意欲を持って学びに向かっている。
「自立した学習者」
・自分で考えて、判断して、行動できる、しようとする能力・意思を持つ
・・・自己決定ができる
・・・他者と協働できる
・「個別最適な学び」と「協働的な学び」とを一体的に充実する
・「指導の個別化」と「学習の個性化」の両方が必要
★学習の個性化
基礎的・基本的な知識・技能等や、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力等を土台として、幼児期からの様々な場を通じての体験活動から得た子供の興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じ、探究において課題の設定、情報の収集、整理分析、まとめ・表現を行う等、教師が子供ひとりひとりに応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで、子供自身が学習が最適となるよう調整する「学習の個性化」も必要である。
「主体的・対話的で深い学び」:アクティブラーニング
1 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連づけながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って、次につなげる「主体的な学び」が実現できているかという視点
2 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているかという視点
3 習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して、考えを形成したり、問題を見出して解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実現できているかという視点
「主体的・対話的で深い学び」
学び方を身に付け、自ら学び続けることのできる人に。
自ら考え、判断して、行動できる人に。
「自立した学習者」に。
~~~
この冒頭の「学ぶことに興味や関心を持ち」っていうところが一番むずかしいし、そこにアプローチしたいなと思うのです。そのためには「まなぶこと」そのもののアンラーニングと新しいOSの再インストールが必要になると思います。まなびの再定義ですね。
キーワードは「遊び」ではないかと僕は思っています。
「探究的な学び」を遊びから始めていくこと。
そしてその主語を「場」にしていくことなのかな、と。
「個別最適化」の説明としての「学習の個性化」というキーワードも大きいな、と。
荒瀬先生が言っていた
1人1人がどのような学びをつくっていくのか?
⇒自分の学びをどのように構築しているのか?
⇒これからどう生きていくのか?と同義だと。
「学ぶ」=「学校に行く」ではない時代・社会において、1人1人に応じた探究的な学びが必要で、1人1人は「自立した学習者」として学びの場に立っていること。それが「多様性」なのだと。
ではその時に、「学校」は、「(一斉)授業」は、どんな意味があるのだろう?と思った。
特に上に出てくる主体的な学び、において。
そんな時にヒントとなったのは荒瀬先生が紹介した
愛知県春日井市立高森台中学校の例
参考:https://www.mext.go.jp/studxstyle/special/46.html
参考:http://swa.kasugai.ed.jp/weblog/index.php?id=kasugai10&type=2&date=20191209&category_id=298&no=3
「真似していい。」これも衝撃的だった。
主体的とは、関係性によって育まれるのではないか、と。
そういう意味では、学校と地域というのは、関係性の広がりをもたらす。
自分と他者、自分と地域。
地域や地域の大人に出会ったときのフィードバック。
そのひとつひとつの「機会」に、学びの意欲は眠っていると思った。
昨日書いた「能力は場に宿る」
参考:http://hero.niiblo.jp/e493332.html
のようなことが起こっていくのではないか。
そのあとに振り返ること。「場」と「個」を往還すること。
僕は心を揺さぶる感情は、「レスポンシビリティ」だと思う。
社会に貢献する第1歩として反応があり、反応する能力=責任が芽生える。
地域・社会における実践で具体的に何を感じたか?
そこから存在が立ち上がってくるのだと思った。
シンポジウム午後の部の遠隔事業の書道の小川先生の実践に、胸が熱くなった。
ひとりひとりの文字から見える個性を、ひとつひとつていねいに指摘していく。
ササっと書いて文字がかすれている生徒も、慎重に慎重に一筆ずつ書いた生徒にも
その芸術的な意味を指摘していく。
ああ、芸術の授業は、遠隔事業でも可能なのか、と思った。芸術には正解がないから、むしろいいのかもしれない。
むしろ、遠隔事業だからこそ、みんなが聞いている中で自分の書をほめられる。なんだか、照れくさい。
でも、対面授業だったら、もっと恥ずかしくて、教室から出ていってしまいたくなる。
素直に聞けない。これまでに何かをほめられたことなんてほとんどないから。
そんな風にお互いに「反応」し、それを表現することから「存在」の承認は始まっていくのだと思うし、それは「学びの意欲」の前提にあるものだろうと思う。
荒瀬先生のラスト「おわりに」はさらに熱くなった。
~~~
高等学校学習指導要領の前文では、これからの学校について「一人一人の生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。」とある。
各高等学校が、教育活動を通じてこの理念を体現していくことができるよう、今後どのような取り組みを進めていくべきか、引きつづき議論を進めていくことが必要である。
・生徒の多様な学習ニーズに応えるための遠隔授業配信センターの体制等の在り方について
・いずれの高等学校においても、全ての生徒の可能性を引き出し、生徒が、社会の一員となるための多様な資質・能力を身に付けた上で次のステップに移行することが可能となる教育システムを一層構築するために、必要な取組とその支援の在り方について
・「総合的な探究の時間」を教育課程の基軸に据えながら各教科等における学びを充実させるとともに、文理横断的な学びや実践的な学びを一層進める上で必要な体制・環境について
・次期高等学校学習指導要領に関して、内容をおおむね堅持しながら学校現場への浸透に時間をかけていくべきとの意見や、「総合的な探究の時間」を教育課程の基軸に据えながら、各教科・科目等の相互の関連を図る中で、高等学校生活全体での学びの充実を図ることを徹底していくべきとの意見、一人一人の「よさを徹底して伸ばす」在り方としていくべきとの意見、全ての通信制の高等学校において人間関係を構築しながら、自分のよさや可能性を認識し、多様な人々と協働する上で望ましい在り方としていくべきとの意見等も踏まえた、今後の望ましい在り方について
・高等学校がやるべきことの整理・明確化、学校における働き方改革の推進や、教職員の配置を含む高等学校の指導体制の充実のための方策について
その際、国、高等学校、教育委員会・学校法人等の高等学校の設置者、家庭、地元自治体、産業界、生徒への各種支援機関など、それぞれの関係機関が実施すべきことを明確化するとともに必要となるリソースの確保を含め、施策の実現に向けた見通しを立てることに留意しながら、検討を進めるべきである、
また、一つの学校の中だけで教育活動や期待される機能、役割のすべてを果たそうとする閉ざされた考え方からの脱却を図るととともに、各高等学校において展開可能な教育活動には、学校長の判断の下に多くの可能性があるとの認識を持ち、今後、高等学校教育を真に社会に開かれたものにしていくことが期待される。
~~~
さて。めっちゃ写経。笑
なんか素晴らしいですね。理念は。
これをどのように実装・実践していくかっていうこと。
パネルディスカッションでもありましたけど、どのように「学び」を委ねていくかっていうのがキーポイントのような気がします。
必要なのは、僕は「場」の力だと思っていて、生徒に「学び」を委ねるのではなく、生徒も地域も含む「場に学びを委ねる」ということが大切なのではないか。その場(環境)づくりにこそ、学校と地域が連携・協働する意味があるのではないか、と。
学びの意欲は、他者や地域、社会との関係性の中に生まれてくる。
だからまずはその関係性をつくる機会を提供する。
あるいはジェネレーター的な地域の大人が巻き込んでいくこと。
「場」を主語にして、いろいろとやってみること。
そこで「ふりかえる」こと
「個」として感じたことを言語化すること。
まわりの生徒や地域の大人からフィードバックをもらうこと。
「発見」すること。
「発見」を「問い」へと変換すること。
「プロジェクト」をつくること。
「役」を演じること
変わっていく周り(環境)を体感すること。
景色が変わること。
その繰り返しで、切実な「問い」に出会うこと。
これを解かなければ生きられないという問いに出会うこと。
そこから、ようやく「探究」は始まっていくのかもしれません。
探究の入り口に立つこと。
僕自身はそこに立っているのだろうか、と問われたシンポジウムとなりました。
関係者の皆様、素敵な機会をありがとうございました。
2023年11月14日
能力ば「場」に宿る
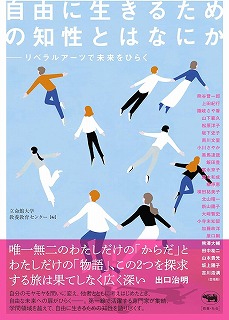
『自由に生きるための知性とはなにか』(立命館大学教養教育センター 晶文社)
高円寺の蟹ブックスさんのオープン当初に購入。
積読になっていました。
まずは「はじめに」から
東京大学教養学部の1993年のカリキュラム改変に際して開設された新規文系科目の教科書から。(『知の技法』より)
~~~
高校までの教育はあくまで、知る者が知らない者に知識とその獲得の方法を与えるという、関係の不均衡と能力の落差が前提でした。しかし大学での教育は、教師と学生が同等に立つことを目標とし、同時に最初からそれが実現されているとの仮説の枠組みで「教育」を行うため、その二者のあいだで、また大学を超えた社会に対して、知の行為者としての倫理が要求されるのです。
その根底にあった理念は、「知は知識ではなく行為である」ということである。知は、まずみずからを、そして世界を更新する革命的行為である!「教養」とは知識の集積ではない、日々あらたに世界を学ぼうとする君自身の「態度」のことだ!
教師と学生が同等に立ち、各々の言は常に反証することが可能なように他者に開かれ、落差のない地平で、対等で平等な相互応酬の議論空間が立ち現れる-これこそが大学、という場です。そして、そうした空間を成立させるために必要なのが教養、すなわちリベラルアーツです。
~~~
いいですね。アツいです。
知は知識ではなく行為であり、教養は知識の集積ではなく世界に対する態度なのだ、と。
そして次に熊谷普一郎さんの「わたし」について
~~~
わたしを形づくる要素には、最低でも二つあるのではないかと考えていて、一つは、わたしだけが持っているこの「からだ」。もう一つはこれまで歩んできた歴史や自分だけの「物語」です。
当事者研究では多くの場合、このからだと物語の二つを、「わたし」を形づくる要素と見なし、それぞれを探求するスタイルをとります。
~~
なるほど。「からだ」と「物語」ね。
これは高校生であってもそうですね。
今日は文科省事業のSaGaSuプロジェクトのシンポジウムなのですが、「自律的な」学習者を「育てる」についての一節を抜粋。
~~~
「自律的な」学習者を「育てる」ということ自体、考えようによっては、形容矛盾に思われるかもしれません。それは学習者を個としてのみ捉え、学ぶ意欲をただ個の内側から出てくるものとしか見ないからです。
実際には学習者は、己を取り巻く様々な人やモノとの関係の網の目の中で、学びの機会に開かれ、学びに関心を見出し、学びの意欲に駆り立てられます。自律的な学習者としての強度は、むしろ学習者を学習者たらしめている関係の束の厚みと豊かさに支えられているのです。
関係の網の目がより包摂的で力動的であれば、「変容する自己」というものを経験することができる。逆に関係の網の目が固定的であれば、「変容する自己」を実現することができない。だから、多様な背景を持ち、多様な条件におかれているあらゆる学び手をエンパワーメントしていかなくてはならない。
~~~
いやあ、まさにまさに。
これが学校における「地域連携」の意味なんだと思います。
自律的な学習者は個として存在するのではなく、あくまで場の構成員として立ち現れるのだと。
そしてP100の発言にあるような
能力というのは「個」に宿るのではなく「場」に宿る、「関係」に宿るという原則です。
これです。たぶんこれ。
人が共同体や組織を生きているのは、場や関係のなかで自分が活かされるから。
大人も子どもも関係なく
学びの機会に開かれ、
学びに関心を見出し、
学びに意欲に駆り立てられる。
そんな地域をつくっていくことがこれからの物語のような気がしています。
2023年11月12日
「問い」を生み出すレイヤーライフ
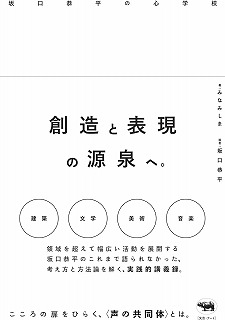
『坂口恭平の心学校』(みなみしま 晶文社)
第1章 建築
を読んでいたら、無性に復習したくなった10年前の本を再読。
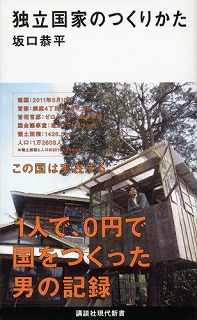
『独立国家のつくり方』(坂口恭平 講談社現代新書)
これ、大学生にもっともおススメしたい新書です。
たぶん某大手古本チェーン店で110円で買えるので探してみてください。
僕はこの本の「放課後社会」というキーワードにビビっと来て、その日以来、そんな場づくりを心掛けているのですけども。
参考:自由とはタテの世界を行き来すること(13.1.19)
http://hero.niiblo.jp/e229119.html
問いが詰まりまくってます。
今日はこの本の根幹をなす「レイヤーライフ」について。
P31 思考が空間を生み出す より
~~~
これまで、人間はこの一つの地球という空間の中で領土を拡げようと試みてきた。あらゆる戦争、いがみ合いの原因はここにある。日本という国の中でも、お金を獲得して自らの土地を増やす、所有を増やすという行為がすべての経済活動、生活のもとにあった。しかし、路上生活者たちは違った。
僕がいた建築の世界もそうだ。私的所有することができた土地を、建築物で囲っていく。そうすることが空間をつくり上げることだとしていた。しかし、それは本当なのか。僕はそうは思わない。なぜなら、どんなに壁をつくって自らの領土に建築物をつくったとしても、空間は増えないからだ。むしろ減る。
それに対して、路上生活者たちの空間の捉え方は違った。もともと自分の土地というような私的所有を断念せざるをえない状況で生きているので、実際に買うことができない。そこで、彼らは自分たちのレイヤーをつくることにしたのだ。日本に住むみんなが当たり前と思い込んでしまっている「匿名化」した社会システムと別のレイヤーを。
建築では空間を生み出せないけど、思考では生み出すことができる。
レイヤーライフが創造にも転化することを教えてくれたのは、鈴木さんの家の玄関だった。この玄関はドアを閉め、ブルーシートを閉じて、沸かしたお湯をプラスチックのケースに入れるとお風呂になる。さらにドアを開くと、裏側には包丁が入っており、台所に早変わり。玄関のどこに自分が立つかによって、一つの空間の用途が変幻する。
つまり、レイヤーを使うことによって、空間がどんどん増えていくのである。これまでの建築の「一つの空間をどうやって壁で埋めていくか」という考え方とはまったく正反対の方法だ。壁など必要ない。人間には見えない空間を次々とつくり出す能力がもともと備わっているのだ。
僕が言うレイヤーとは新しい技術ではない。それは太古からの力だ。
~~~
昔の家でいうところの縁側とか、土間とか、そういう感じの場所、立ち位置や構成員によって変化する場所、なのかもしれませんね。
さらにP41には
~~~
何かを変えようとする行動は、もうすでに自分が匿名化されたレイヤーに取り込まれていることを意味する。そうではなく、既存のモノに含まれている多層なレイヤーを認識し、拡げるのだ。チェンジじゃなくてエクスバンド。それがレイヤー革命だ。
~~~
いや、まさにこれなんですよ。
それが「放課後社会」というキーワードにたどりついた当時の僕のレイヤーに対する認識。
高校生や大学生にとって、本当に大切なのは、「やりたいことが見るかる」ではなくて、「一生かけても答えを出したい問い」が見つかることなのだろうと思う。
!「驚く」ことと?「疑問を持つ」ことを出発点にして、自分の中の共感と違和感に気づいていく。そこから問いを生み出していくこと。
それをもっとも生み出しやすいのは「越境」なのだと思うけど、その「越境」とは、物理的な距離の遠さというよりも、坂口さんの言う、「レイヤーを変えて観る」ということなのかもしれない。
たとえば旅人の目線(視点)から自分の町を見てみること。
そんなレイヤーライフの方法のひとつが「放課後社会」から見る、ということになるのかもしれない。
P123 匿名で交易はできない より
~~~
学校社会から放課後社会へはジャンプできない。学校社会は人間が集まって暮らすには必要な要素である。それに対して、放課後社会は完全に個人の領域だからだ。でも、放課後社会どうしはジャンプすることができる。これが僕の考える交易だ。学校社会上では交易することができない。交易は匿名下では不可能なのである。
今の状況を見ていると、どうにかして学校社会自体をぶっつぶして新しい社会を形成しようと試みている人が多いように感じる。しかし、それは不可能なことだ。なぜなら学校社会は個人の領域ではないからである。それは無意識だから。他人の見る夢なんて改変できっこない。
学校社会は変わらない。変えられるのは放課後社会とのバランスだけだ。
学校社会は消せないけど、認識を変化させることはできる。それが「考える」という行為。学校社会が無数の中のひとつのレイヤーであり、唯一の無意識領域のレイヤーであることがわかれば、もっとうまくバランスが取れる。そのためには自分の放課後社会の風景を拡げる必要がある。
~~~
いやー。これ伝わりますかね。
「放課後社会:おのおのにとって違う社会の在り方」から世界を見つめてみること。
あるいは放課後社会を形成している一人のオーナーとして、違う放課後社会オーナーと、「交易」すること。
それこそがいわゆる「越境」であり、「対話」の意味なのではないか、と。
そこから!や?と共感や違和感をキャッチして、問いが生まれてくる。
まずはこの「放課後社会」っていう概念をいかに伝えていけるか(できれば図解したい)
そんなことを考えていきたいな、と。
「自由」とはタテの世界、つまりレイヤーライフを行き来し、いくつかのレイヤーのオーナーになること。
そこから「探究」的な人生が始まっていく。
2023年11月10日
「想像力/創造力」の育て方

『才能をひらく編集工学』(安藤昭子 ディスカバートゥエンティワン)
「遊び」について、もっと考察した方がいいなと思って、P74 より引用
その前提として、「編集工学」に必要な3Aをおさらい(P115)
1 関係発見の原動力となる「アナロジー」
2 思い切った仮説にジャンプする「アブダクション」
3 世界と自分の関係を柔らかく捉え直す「アフォーダンス」
この中の「アナロジー」について。「遊び」の要素があったのでメモ。
~~~
ロジェ・カイヨウは著書『遊びと人間』の中で遊びの四分類を以下のように提示しています。
1 アゴン(競い)
2 アレア(運)
3 ミミクリー(模倣)
4 イリンクス(目眩)
その前提として
1 パイディア:即興と歓喜の間にある、規則から自由になろうとする原初的な力⇒遊戯
2 ルドゥス:恣意的だが強制的で窮屈な規則に従わせる力⇒競技
というふたつの特徴を遊びの本質としてあげています。
パイディア(遊戯)⇒騒ぎ・はしゃぎ・ばか笑い⇒胴上げ・穴送りゲーム・トランプの1人占い・クロスワード⇒ルドゥス
アゴン(競い)⇒競争・取っ組み合いなど(規則なし)⇒運動競技・ボクシング・玉突き⇒フェンシング・サッカー・チェス・スポーツ競技全般
アレア(運)⇒鬼を決めるジャンケン⇒裏か表か・賭け・ルーレット⇒富くじ
ミミクリー(模倣)⇒子供の物真似・空想の遊び・人形・仮面・仮装・演劇
イリンクス(目眩)⇒子供の「ぐるぐるめまい」・メリーゴーランド・スキー・登山・サーカス
スイカ割りや「ケイドロ」はこの四つのすべてが入っている。
~~~
著者は、この遊びの中での「ミミクリー(模倣)」こそが編集工学にとって重要な「アナロジー」の原郷だと説明します。
~~~
ミミクリー(模擬)と思われる遊びを思い浮かべてください。おままごとやごっこ遊びの他にも、積み木の家や秘密基地、変身レンジャーや折り紙やあやとり。何かを何かに見立てたり、そのつもりになってみたりした遊びも結構あるでしょう。それが「あなた」の中にあるアナロジーの原郷です。
カイヨウは、ひときわ「ミミクリー(模擬)」を重視します。
「人間の最大の誘惑は類似のものを見つけ出すということにあった。」として、人間に備わった「似たもの探し」の本能を、遊びを通して示しました。
何かと何かが似ているということは、それだけで人間のイマジネーションの根っこをくすぐるちょっとした魔術です。目前の問題解決にとどまらず、人間に潜在する想像力の可能性を最大限に引き出すフックとして、アナロジーが重要です。
松岡正剛は、「『似ている』とは、そこにひとつの遊星的郷愁を蝕知する信号だと言いました。それはどこか遠いところにあるものではなく、いまも自分の中で息を潜めている性質なのです。
胸の中のおもちゃ箱の蓋を開けるように、子どものころに慣れ親しんだアナロジカル・シンキングを今一度手の中に取り戻してみてください。
まずは「これは何と似ているかな?」と思ってみる。そこでピンときたものに自信を持つ。自分のイマジネーションの底力を信じる
やがて「アナロジー」という名の眠れる獅子が、ゴソゴソと目をさますはずです。
~~~
最近のキーワードとしての遊び。
1 アゴン(競い)
2 アレア(運)
3 ミミクリー(模倣)
4 イリンクス(目眩)
「遊び」と「学び」が原初的には分かれていないとしたら、このような要素が入っていくことで「学び」は楽しくなるはずだ。そして、自分がまずはどの「遊び」に楽しくなるのか、その自覚から始めてもいいと思った。
そしてさらに「ミミクリー(模倣)」という原動力について、もっと僕たちは注意を払ってもいいのかもしれない。
小学生でも高校生でも、先生の「ものまね」はウケる。いや、大人になってからも、それはエンターテイメントとして人気がある。(だからテレビで視聴率がとれる)
「ものまね」とは観察と表現が問われる遊びである。
以前に、「好奇心は育てられる」として、読書会のやり方を紹介したけど
http://hero.niiblo.jp/e491170.html
参考:それは「本屋」かもしれない(20.11.4)
アナロジーは、ミミクリー(模倣)という遊びによって育まれるし、それこそが「想像力/創造力」の源になっていくと思う。
そしてさらに言えば、「正統的周辺参加」アプローチは、模倣的で「遊び」要素があるんだなと思った。
http://hero.niiblo.jp/e491788.html
参考:二人称的アプローチとアイデンティティ(21.6.7)
「ミミクリー(模倣)」と「表現」を行き来しながら、「面白がる」と「疑問を持つ」を繰り返していくこと。
それによって、楽しく(遊びながら)「想像力/創造力」が育まれるのではないか、という仮説。
2023年11月03日
一立方センチメートルのチャンス
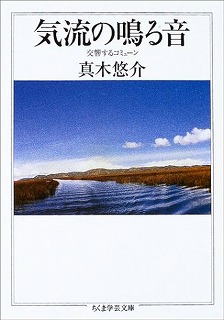
『気流の鳴る音』(真木悠介 ちくま学芸文庫)
友人に勧められた1冊。なんとタイムリー。
『才能をひらく編集工学』とリンクしていてビックリします。
『編集工学』のP215~の「地」と「図」に分けて考えるのところ、ちょうど読んでいたので。
紹介するのはⅡ「世界を止める」-〈明晰の罠〉からの解放(P73~)より「見る」についての考察を
~~~以下メモ
「心の明晰さ、それは得にくく、恐怖を追い払う。しかし同時に自分を盲目にしてしまう。それは自分自身を疑うことをけっしてさせなくしてしまう」
「明晰」とはひとつの盲信である。それは自分の現在もっている特定の説明体系(近代合理主義等々)の普遍性への盲信である。特定の歴史的・文化的世界像への自己呪縛である。人間は、〈統合された意味づけ、位置づけの体系への要求〉という固有の欲求につきうごかされて、この「明晰」の罠にとらえられる。
コヨーテがしゃべるということをあたまから信じないのが、ふつうの人の「明晰」である。これにたいして、コヨーテがしゃべるということを信じてしまうことが呪術者の「明晰」である。しかし両方の「世界」がともにカッコに入ったものであり、どちらも「現実」であるということ、「現実」とはもともとカッコに入ったものであること、このことを〈見る〉力が真の〈明晰〉である。
「明晰」を克服したものがゆくべきところは、「不明晰」ではなく、「世界を止め」て見る力をもった真の〈明晰〉である。
〈明晰〉は自己の「明晰」が、「目の前の一点にすぎないこと」を明晰に自覚している。
~~~
むずかしいけど、まさに、って感じです。
「恐怖」とは知らないことである。
それを逃れようと人は知りたい、理解したいと思う。
「知り、理解する」ということは、「特定の説明体系」で物事をとらえるということであり、それこそが「明晰の罠」だとドンファンは言う。
だから、真の〈明晰〉を手に入れ、「世界を止め」て見ることが必要なのだと
~~~
目の世界が唯一の「客観的な」世界であるという偏見が、われわれの世界にあるからだ。われわれの文明はまずなによりも目の文明、目に依存する文明だ。
〈目の独裁〉からすべての感覚を解き放つこと。世界をきく。世界をかぐ。世界を味わう。世界にふれる。これだけのことによっても世界の奥行きはまるでかわってくるはずだ。
仏教では五根を眼⇒耳⇒鼻⇒舌⇒身と並べるように、視覚⇒聴覚⇒嗅覚⇒味覚⇒触覚はこのような配列が自然なように思われる。それはおそらく、対象を知覚するにあたって、主体自身が変わることの最も少なくてよい順であろう。
「身」による認識は文字どおり「身をもって」せねばならない。熱ければ火傷、冷たければ凍傷、その他対象による捕捉等々の危険を賭することなしに「知る」ことはできない。ここでは「知ること」と「生きること」はほとんど未分化である。
視覚は、遠く身をかくしたままで細大もらさず観察するように、主体自身の身を賭すること最小にして対象をこまかに知覚することができる。それはわれわれの〈世界〉からの自立を最も容易にするとともに、〈生きること〉と〈知ること〉の乖離を最大限にする
~~~
「五感で感じる」ことを大切にしよう、と言っているけど、まさにそれには順序があって、「身」には自己変容の【危険】と隣り合わせであるから、なかなかハードルが高いのだろう。
しかし、視覚に頼りきった近代文明(しかも昨今はPCやスマホ画面上での視覚の使用でしかない)こそが、われわれを「生きる」ことから遠ざけているのかもしれない。
さらに、『才能をひらく編集工学』とリンクしてくる「図」と「地」の話へ。
~~~
われわれがふだんおこなっている〈焦点をあわせる見方〉は、全体から引き出され抽象された個物に関心を集中する。ルビンやゲシュタルト心理学の用語で言えば〈図〉と〈地〉の明確な分化をその前提とする。
〈焦点をあわせない見方〉とはぎゃくに、個別にのめりこまないように全体のバランスをみる見方であり、〈図〉と〈地〉の分化以前にたもつということである。
われわれは無意識に、いつも焦点を合わせているので、〈地〉となった部分を無視しているからだ。〈焦点を合わせる見方〉においては、あらかじめ手持ちの枠組みにあるものだけが見える。「自分の知っていること」だけが見える。〈焦点をあわせない見方〉とは、予期せぬものへの自由な構えだそれは世界の〈地〉の部分に関心を配って「世界」を豊饒化する。
~~~
うーん、深い。
プロジェクト学習において、テーマや目的・目標を「明確に」定めることへの違和感はこういうところにあるのだろう。
さらに、ドン・ファンが語る
~~~
「わしはそいつを一立方センチメートルのチャンスと言っておるんだ」ドン・ファンが言う。「戦士であろうがなかろうが、わしらはみんな目の前に飛び出す一立方センチメートルのチャンスをもっておるんだ。ふつうの人間と戦士のちがいは、戦士はこれに気づいておって、自分の一立方センチメートルが飛び出してきたときにそいつをつかまえるだけのスピードと勇敢さをもてるように、いつもじっくり油断なく待っておるのさ。
チャンスとか、幸運とか、個人的な力とか、とにかくなんと呼んでもいいが、そいつは独特のものなんだ。わしらのまえに出てきて、摘むように招くひどく小さな小枝のようなものさ。ふつうだと、わしらはいそがしくしすぎたり、他のことに気を奪われていたり、でなければただおろかで不精すぎたりして、それが自分の一立方センチメートルだってことに気づかないんだ。
~~~
そう。
誰もの目の前に飛び出す一立方センチメートルのチャンスがある。
それに気づけるかどうか、そしてそれつ掴めるかどうか。
「そいつをつかまえるだけのスピードと勇敢さ」をもてるように、待っていること。
それが、人生を動かすコツなのだろうと思う。
目的・目標を決めすぎず、常に一立方センチメートルのチャンスに応えられる、そんな「生きる」を歩きたいものですね。
2023年11月02日
「自分らしさ」のつくられ方

『才能をひらく編集工学』(安藤昭子 ディスカバートゥエンティワン)
佳境に入ってきました。
今日のテーマは「らしさ」について。
その前に、「コード(code)」と「モード(mode)」について
情報:コードとモードに分けて考えることができる
コード:情報の構造やルールやスペックのこと⇒明記できて、言語化や数値化可能で、管理しやすい
モード:必ずしも言葉や数字で表現できない印象、様相・様式のこと。目に見えない雰囲気やニュアンスとして現れる。
流行や文化やブランド:何かしらのコードの組み合わせの上に表出してきたモードやスタイルが流通しているもの
ということで、「らしさ」について
「らしさ」は、基本的にこの「モード」に宿っています。だからわかりにくいし、取り出しにくい。そのため「そのものらしい」というのは本来大きな価値を持っているのですが、「らしさ」を資産として自覚的に扱うことがなかなか難しいのです。
「らしさ」とは、「アイデンティティ(自己同一性)」というほど窮屈ではなく、「〜的」「〜風」というほどには客観的でもない、そのものをそのものたらしめている何か」です。
~~~
まさに、この「らしさ」を求めて、高校生大学生20代はさまよっているのでしょうね。
メモをつづけます。
~~~
コードや要素の組み合わせだけでは現れてこないという点に着目すると、「らしさ」は「生命」とも似ています。
日本の非線形科学の第一人者である蔵本由紀さんは、生命現象のような複線でダイナミックな世界像を解く視点として、非線形科学「主語」としての科学ではなく「述語」が結びつける科学というふうに捉えました。
モノに着目し普遍性に基づいて世界を見る科学、言い換えれば「What(何)」が主体となる科学を「主語的統一」と呼び、それに対して「How(どのように)」を基軸に世界を見る見方を「述語的統一」と呼びます。
バラや夕日や郵便ポストといったばらばらなモノを「赤い色をしている」というコトの視点でつなぐことで、新しい関係性を探る世界像です。「赤い」という述語(性質/コト)がひとつの場所をつくっていて、そこに夕日などの主語(物質/モノ)が包み込まれるイメージであるとも言います。
哲学者の西田幾多郎さんが言う。
「普通には我という如きものも物と同じく、種々なる性質を有つ主語的統一と考えるが、我とは主語的統一ではなくして、述語的統一でなければならぬ、一つの点ではなくして一つの円でなければならぬ、物ではなく場所でなければならぬ。我が我を知ることができないのは、述語が主語になることができないのである。」(西田幾多郎キーワード論集 2007 書肆心水)
主語的統一ではなく述語的統一、点ではなく円、物ではなく場所。「自分らしさとは何か」を問うほどに、「自分らしさ」は正面から逸れていく。「我」とは結局どこまでいっても主語(what/何)になりえない存在なのだ、と言っています。そして、意識が捉える「直観」についてこう説明します。「直観というのは主語面が述語面の中に没入することに外ならない」
「自然について正しく推測する本能的能力」である直観は、「自分をとりまく自然の諸法則との絶え間ない相互作用の中で有機的に形成されてきたもの」であると、パースは言います。直観は必ずしも、「わたし」という主体が制御しているものではない、ということです。
科学はずっと「不変なもの」を通して変転する世界を語ろうとしてきました。蔵本由紀さんはこの見方を反転させて「変わっていくもの」を通して「不変なもの」を見る見方を非線形科学を通して提示しています。
思いがけない述語的統一が導入されると、個物間の関係が一新され、新しい世界像が現れます。そこでは、モノとして新しい何かが見出される必要はありません。関係の発見こそが、世界を新しくするのです。
「らしさ」のような見えない価値を捉えるには、複雑なものを複雑なままに包み込める述語性が必要なのです。
~~~
「述語的統一」。
これ、重要なキーワードだと思います。就職活動とか自己分析とかする上でも、自分を仕事の内容(営業とか事務)で理解するのではなく、「人と話す」「手を動かす」といったような動詞的に理解するほうが、仕事環境が変化し続ける中で有効だなと思います。
そしてそれは日本人のメンタリティにチャンスがあるかもしれないとこの本は説明します。
~~~
西洋文明においては「主語的統一」が優位であるのに対して、日本は伝統的に「術語的統一」が優位な文化を発達させてきました。
たとえば「寒い」と言う時、西洋の言語では「空気が冷たい」のか「体が冷えている」のかが主語によって明示されます。日本語では、寒さは大気中にもそれを感じる人間の中にも同時にあり、その主体は情景全体に溶け込んでいて分けることができない。日本人からしてみれば、わざわざ考えるのに苦労するくらいに当然のことですが、ベルクによれば「西欧人はこの事態に面食らう」そうなのです。「何を」や「何が」よりも「どのように」「どうなっている」を中心にコミュニケーションを図る。日本が「述語的統一」が優位な文化であるというのは、わたしたちが日々使いこなしている日本語にもあらわれています。
現代の自然科学は、主語的統一を文化の基調とする西欧世界に起源を持つことから、世界全体が主語を基軸とする自然理解を前提とするようになったと考えられます。しかし、その優位を決定づけたコペルニクスからニュートンにいたる近代科学革命の時代は人類の文明史全体から見たら一瞬です。
「人間の問いには、科学的な事実記述によって答えられる問いと、そうでない問いがある。後者には答えがないゆえに問う意味もない、と根拠なく錯覚されているような現代は、ある意味で文化の貧困な時代といわざるをえない。事実的な知のみが知であるはずがない。物語的な知によって適切に答えられるべき問いが、不当に抑圧されている時代は豊かな時代とは言い難い。本書の最大のテーマである、現代の『知のアンバランス』の究極の姿をここに見る」(『新しい自然学』蔵本由紀 ちくま学芸文庫)
~~~
「述語的統一」
主語から述語へ。
「らしさ」を考える上で大きな一歩になりそうです。
「中動態の世界」にも通じてきますね。
まだまだ書きたいところではありますが、今日は「余白」に言及して締めたいと思います。
~~~
真の美はただ「不完全」を心の中に完成するひとによってのみ見いだされる。(『茶の本』岡倉天心 岩波文庫)
茶室においては、心の中に全効果を完成することが客人の側それぞれに任されているとして、招かれる側の想像力こそが美の完成に必要なことを説いたのです。
能が演じられるときの「間」や空間的な「床の間」や「枯山水」、利休の茶室など「余白」「引き算」の発想は、まさに日本のクリエイティビティそのものだと言えるでしょう。
日本人がことさら「余白」や「不完全」を重視してきたのは、「何が」という実体への理解よりも、「どのように」の中に立ち現れる「生き生きとした面影」を交換することに、人間のコミュニケーションの本来があると見てきたからかもしれません。
~~~
「何が」ではなく「どのように」
主語ではなく、述語、そして「空間」というか「余白」。
それを他者や自然との関係性の中で位置づけること。
それが「自分らしさ」のつくり方というよりも「つくられ方」なのではないかとこの本を読んで思いました。




