2014年12月31日
青臭い問いに向き合う

「新世代努力論」(イケダハヤト 朝日新聞出版)
ハチロク世代の価値観。
面白かったです。
「努力すれば報われる」は
高度成長期の世代だけが持っている妄想であり、
それを若者世代に強いることはできないということ。
努力信奉と自己責任を
痛烈に批判する著者の
言い分はもっともだと思う。
その中でこそ、
ひとりひとりは、
青臭い問いに向き合うことが必要なのだと言う。
成功とは何か?
幸せとは何か?
豊かさとは何か?
そんな青臭い問いを考えてみること。
大学生活という膨大な時間の中で、
まずは問いを立ててみるということ。
やっぱりそこからだよなあ。
2014年12月30日
高齢者地域は親和的承認の機会を得る場として魅力的
昨日のつづき。
「自信がない」はあとから獲得された資質である。
それは社会システム側から見た見方であり、
もうひとつ、若者自身の側から見ると、
ひとつの原因は、
「親和的承認の機会の不足」である。
参考:
「承認欲求を超えるには」(2014年6月21日)
http://hero.niiblo.jp/e433586.html
山竹伸二さんの著書
「認められたいの正体」によると、
人間の承認欲求は、
「親和的承認:ありのままの自分を受け入れてもらう」
「集団的承認:集団の中で役割を果たすことで承認してもらう」
「一般的承認:社会一般でいいとされることをすることで承認してもらう」
3段階があるという。
そして、本来であれば、
親和的承認から徐々にステップアップをしていくのだという。
僕はここに、
大学生たちが「社会貢献」というキーワードに惹かれる
理由があると思う。
実は彼らに足りないのは、
ベースとなる「親和的承認」の機会だ。
そして、地域コミュニティの崩壊と共に、
地域は、若者への「親和的承認」の機会を失ったのである。
たとえば、道行く小学生が暗い顔して歩いていたら、
魚屋のおっちゃんが、
「ぼうず、どうした?何か嫌なことでもあったか?」
と声をかけるということ。
お菓子屋さんが、
おい、大判焼きでも食べていくか?
と声をかけること。
「あなたを見ていますよ。」
「あなたに関心がありますよ。」
というメッセージを伝えていくこと。
実はこれがすごく大切だったんじゃないか?
かつて、3世帯が同居して住んでいた時。
あるいは今でも地域のつながりが強すぎる場所に行くと、
監視と同調圧力はともかく、
そこには「親和的承認」の機会があった。
いつのまにか、核家族になり、
地域コミュニティのつながりが希薄になり、
子どもたちの多くは、
「条件付きの愛」を受けるようになった。
「勉強をがんばったら」
「いい子にしていたら」
褒められるのである。
つまり、もっともベースにある承認欲求を満たされない状態にあると思う。
大学生が日本海に浮かぶ離島、粟島に行くと、
何が起こるか?
まさにさっきの魚屋現象が起こるのである。
(特に夏ではないシーズンオフに行くと顕著だ)
歩いているだけで、
「どっから来た?」
「どこへ行くんだ?」
「この島には何もないがいいところだ」
と声をかけてくれる。
そう。
親和的承認の機会が得られるのだ。
実はそれが、
上書きされた「自信のない自分」
をリセットするためのリハビリの第一歩になると思う。
離島や中山間地、そして商店街といった
高齢化した地域は、
若者のリハビリの場としての
第一歩を踏み出すところになり得ると僕は思っている。
粟島にひとり旅に行きませんか?
民宿に2泊すれば、その家はもはや、あなたの実家のようになります。
「自信がない」はあとから獲得された資質である。
それは社会システム側から見た見方であり、
もうひとつ、若者自身の側から見ると、
ひとつの原因は、
「親和的承認の機会の不足」である。
参考:
「承認欲求を超えるには」(2014年6月21日)
http://hero.niiblo.jp/e433586.html
山竹伸二さんの著書
「認められたいの正体」によると、
人間の承認欲求は、
「親和的承認:ありのままの自分を受け入れてもらう」
「集団的承認:集団の中で役割を果たすことで承認してもらう」
「一般的承認:社会一般でいいとされることをすることで承認してもらう」
3段階があるという。
そして、本来であれば、
親和的承認から徐々にステップアップをしていくのだという。
僕はここに、
大学生たちが「社会貢献」というキーワードに惹かれる
理由があると思う。
実は彼らに足りないのは、
ベースとなる「親和的承認」の機会だ。
そして、地域コミュニティの崩壊と共に、
地域は、若者への「親和的承認」の機会を失ったのである。
たとえば、道行く小学生が暗い顔して歩いていたら、
魚屋のおっちゃんが、
「ぼうず、どうした?何か嫌なことでもあったか?」
と声をかけるということ。
お菓子屋さんが、
おい、大判焼きでも食べていくか?
と声をかけること。
「あなたを見ていますよ。」
「あなたに関心がありますよ。」
というメッセージを伝えていくこと。
実はこれがすごく大切だったんじゃないか?
かつて、3世帯が同居して住んでいた時。
あるいは今でも地域のつながりが強すぎる場所に行くと、
監視と同調圧力はともかく、
そこには「親和的承認」の機会があった。
いつのまにか、核家族になり、
地域コミュニティのつながりが希薄になり、
子どもたちの多くは、
「条件付きの愛」を受けるようになった。
「勉強をがんばったら」
「いい子にしていたら」
褒められるのである。
つまり、もっともベースにある承認欲求を満たされない状態にあると思う。
大学生が日本海に浮かぶ離島、粟島に行くと、
何が起こるか?
まさにさっきの魚屋現象が起こるのである。
(特に夏ではないシーズンオフに行くと顕著だ)
歩いているだけで、
「どっから来た?」
「どこへ行くんだ?」
「この島には何もないがいいところだ」
と声をかけてくれる。
そう。
親和的承認の機会が得られるのだ。
実はそれが、
上書きされた「自信のない自分」
をリセットするためのリハビリの第一歩になると思う。
離島や中山間地、そして商店街といった
高齢化した地域は、
若者のリハビリの場としての
第一歩を踏み出すところになり得ると僕は思っている。
粟島にひとり旅に行きませんか?
民宿に2泊すれば、その家はもはや、あなたの実家のようになります。
2014年12月29日
「自信がない」は後天的に獲得した資質である
大学で行うキャリア教育の壁。
それは、「自信がない」ということ。
現在の世の中的には、
「自信がない」のは「成功体験がない」からであり、
「成功体験を積む」ことが、自信をつけるための近道であるという。
しかし。
「成功体験」のためには、「挑戦体験」、
つまりチャレンジをしなければならない。
しかし。
この仮説の最大の矛盾がやってくる。
「自信がない」子はチャレンジする自信もないのである。
だから、チャレンジできない。
すると成功体験を積めない。
だから、自信がつかない。
つまり。
大学4年間のあいだ、その子に自信がつくことはない。
そもそも。
「自信がない」とはどういう状態だろうか?
いつから、その子は自信を失っていったのか。
幼稚園や小学校低学年の頃の文集に、
将来の夢としてなんと書いただろうか?
男の子ならJリーガー。(僕らの時代はプロ野球選手)
女の子ならお菓子屋さんとかお花屋さん。
と書いただろう。
そのとき。
「まあ、こんなこと書いたってどうせなれるわけじゃねーし。」
みたいな冷めた気持ちで書いた子どもってどのくらいいるのだろうか?
おそらくはほとんどいないはずだ。
みんな書いたものに本当になれると当時は思っている。
子どもは全能感(なんでもできる)のカタマリだ。
ほとんどの大学生は自転車に乗ることができる。
ということは、子どものころに自転車に乗る練習をしたということだ。
そして、覚えていないかもしれないけど、
最初はうまく乗ることができなかった。
何度か転んで、あるいは怖い思いをして、
乗れるようになったはずである。
その何度か転んだとき、
自分の能力を疑っただろうか?
「もしかして、僕は自転車に乗る才能がないのかもしれない。」
「自転車は難しそうだから、とりあえずあきらめて、自動車免許とれる18歳まで、歩きで過ごすか。」
などと考える子どもは、ほとんどいないはずだ。
そう。
「なんでもできる」(かもしれない)
という状態がデフォルト(パソコン用語でいう初期設定)
だったはずだ。
いつのまにか。
人は大きくなる。
自我が目覚める。
自分がほかの人と違う人間だと気づく。
小学校高学年、
中学校、そして高校
いつのまにか18歳で、
「自信のない自分」が完成している。
そして自分は自信のない子だと思っていて、
それを克服したいと思っている。
その自信を失っていくプロセスと
目標設定・達成型の「キャリアデザイン」型キャリア教育が
不幸にも同時期に起こることが、
僕は中学校高校の最大の闇(闇というくらい大袈裟な話)だと思う
自信を失えば、
目標を低く設定せざるを得ない。
他者との比較も起こる。
自分は本当は能力がないのではないか?
と勝手に思い込んでしまう。
しかし。
いわゆるお勉強で測られる能力は、
世の中で必要とされる能力のうち、
暗記力と情報処理力だけである。
それは実は社会に出てからは、
概ね、パソコンが代行してくれる。
だから、その評価が低いことは、
そんなに人生に影響を与えない。
そもそも。
「自信がない」という状態は、
後天的に獲得された資質であって、
本当は、みな、
「やればできる」(かもしれない)
のである。
さらに、現在学校などで主流である、
目標設定・達成型のキャリアデザイン型キャリア形成がマッチする職業は、
イチローや本田のようなプロスポーツや将棋の棋士のような専門的世界か、
学校の先生や医者といった資格系の仕事か、
旧財閥系や超がつく一流大企業に入社する場合に限られるのではないか。
わずか数年で激変する現代の世の中においては、
キャリアデザインだけではなく、
「偶然」や「弱いつながり」をつかんで、なんでもやってみる
キャリアドリフト型キャリア形成を並行してやっていかなければならない。
その「やってみる」のネックとなるのが、
「自信がない」という思い込みだ。
そうじゃない。脳科学者の研究によると、
人間はもっとも使っている人でも脳の3%しか使っていないという。
脳が全開したら原子力発電所が必要なくらいの
エネルギーを要するのだという。
だから。
まだあなたの能力は眠っているだけだ。
その開花のチャンスを、あなたは自分の体を使って、
試してみなければならない。
「やればできる」わけではないが、
「やればできる」かもしれない、のだ。
そしてもうひとつ。
「キャリアドリフト」ができるようになっても、
まだもやもやしている人がいる。
これは、アクティブな大学生によく見られるのだけど、
自分自身もそうだったのだが、
いろいろ活動しているけど、なんか不安。
「やりたいことやっていていいね。」と
周りの友達にも言われるけど、
本人はずっと不安を抱えている状態のこと。
「どこに自分の本当にやりたいことがあるのか?」
とずっと迷っている。
これは意外にツラい。
これは僕は
「キャリアデザインの呪縛」だと思っている。
どこかに自分のやりたいこと(目標や夢)が存在して、
それを見つけて、
そのゴールに対して、今自分はここにいるんだ、
と思いたいのだ。
そうではない。
「キャリアデザイン」と「キャリアドリフト」は
まったく別次元の理論である。
キャリアデザインという体系の中の方法論として、
キャリアドリフトがあるわけではない。
だから、それを見つける必要はない。
僕の仮説によると、(笑)
キャリアドリフトの目的は、「お客に出会う」ということ。
自分が仕事として、本当に幸せにしたい人に
出会えるということ。
この人たちのためだったら、
自分はちょっとくらい無理してもいいかな、と思える人に
出会うこと。
これは、数を打たなければ出会えない。
だから、ドリフトが必要なのだ。
「偶然」をつかみながら、いろんなことをやってみるのだ。
自分が幸せにしたいと思えるお客に出会ったとき、
(もちろんお客も経験を重ねることによって変化するかもしれない)
やるべき職業の種類は無限に広がっていく。
その人を幸せにする方法は、
100万通りあるからだ。
そんなキャリア教育を作っていけたらいいと思う。
昨日のツルハシブックスは
そんな思いを確認させてくれるいい対話がありました。
ありがとうございました。
それは、「自信がない」ということ。
現在の世の中的には、
「自信がない」のは「成功体験がない」からであり、
「成功体験を積む」ことが、自信をつけるための近道であるという。
しかし。
「成功体験」のためには、「挑戦体験」、
つまりチャレンジをしなければならない。
しかし。
この仮説の最大の矛盾がやってくる。
「自信がない」子はチャレンジする自信もないのである。
だから、チャレンジできない。
すると成功体験を積めない。
だから、自信がつかない。
つまり。
大学4年間のあいだ、その子に自信がつくことはない。
そもそも。
「自信がない」とはどういう状態だろうか?
いつから、その子は自信を失っていったのか。
幼稚園や小学校低学年の頃の文集に、
将来の夢としてなんと書いただろうか?
男の子ならJリーガー。(僕らの時代はプロ野球選手)
女の子ならお菓子屋さんとかお花屋さん。
と書いただろう。
そのとき。
「まあ、こんなこと書いたってどうせなれるわけじゃねーし。」
みたいな冷めた気持ちで書いた子どもってどのくらいいるのだろうか?
おそらくはほとんどいないはずだ。
みんな書いたものに本当になれると当時は思っている。
子どもは全能感(なんでもできる)のカタマリだ。
ほとんどの大学生は自転車に乗ることができる。
ということは、子どものころに自転車に乗る練習をしたということだ。
そして、覚えていないかもしれないけど、
最初はうまく乗ることができなかった。
何度か転んで、あるいは怖い思いをして、
乗れるようになったはずである。
その何度か転んだとき、
自分の能力を疑っただろうか?
「もしかして、僕は自転車に乗る才能がないのかもしれない。」
「自転車は難しそうだから、とりあえずあきらめて、自動車免許とれる18歳まで、歩きで過ごすか。」
などと考える子どもは、ほとんどいないはずだ。
そう。
「なんでもできる」(かもしれない)
という状態がデフォルト(パソコン用語でいう初期設定)
だったはずだ。
いつのまにか。
人は大きくなる。
自我が目覚める。
自分がほかの人と違う人間だと気づく。
小学校高学年、
中学校、そして高校
いつのまにか18歳で、
「自信のない自分」が完成している。
そして自分は自信のない子だと思っていて、
それを克服したいと思っている。
その自信を失っていくプロセスと
目標設定・達成型の「キャリアデザイン」型キャリア教育が
不幸にも同時期に起こることが、
僕は中学校高校の最大の闇(闇というくらい大袈裟な話)だと思う
自信を失えば、
目標を低く設定せざるを得ない。
他者との比較も起こる。
自分は本当は能力がないのではないか?
と勝手に思い込んでしまう。
しかし。
いわゆるお勉強で測られる能力は、
世の中で必要とされる能力のうち、
暗記力と情報処理力だけである。
それは実は社会に出てからは、
概ね、パソコンが代行してくれる。
だから、その評価が低いことは、
そんなに人生に影響を与えない。
そもそも。
「自信がない」という状態は、
後天的に獲得された資質であって、
本当は、みな、
「やればできる」(かもしれない)
のである。
さらに、現在学校などで主流である、
目標設定・達成型のキャリアデザイン型キャリア形成がマッチする職業は、
イチローや本田のようなプロスポーツや将棋の棋士のような専門的世界か、
学校の先生や医者といった資格系の仕事か、
旧財閥系や超がつく一流大企業に入社する場合に限られるのではないか。
わずか数年で激変する現代の世の中においては、
キャリアデザインだけではなく、
「偶然」や「弱いつながり」をつかんで、なんでもやってみる
キャリアドリフト型キャリア形成を並行してやっていかなければならない。
その「やってみる」のネックとなるのが、
「自信がない」という思い込みだ。
そうじゃない。脳科学者の研究によると、
人間はもっとも使っている人でも脳の3%しか使っていないという。
脳が全開したら原子力発電所が必要なくらいの
エネルギーを要するのだという。
だから。
まだあなたの能力は眠っているだけだ。
その開花のチャンスを、あなたは自分の体を使って、
試してみなければならない。
「やればできる」わけではないが、
「やればできる」かもしれない、のだ。
そしてもうひとつ。
「キャリアドリフト」ができるようになっても、
まだもやもやしている人がいる。
これは、アクティブな大学生によく見られるのだけど、
自分自身もそうだったのだが、
いろいろ活動しているけど、なんか不安。
「やりたいことやっていていいね。」と
周りの友達にも言われるけど、
本人はずっと不安を抱えている状態のこと。
「どこに自分の本当にやりたいことがあるのか?」
とずっと迷っている。
これは意外にツラい。
これは僕は
「キャリアデザインの呪縛」だと思っている。
どこかに自分のやりたいこと(目標や夢)が存在して、
それを見つけて、
そのゴールに対して、今自分はここにいるんだ、
と思いたいのだ。
そうではない。
「キャリアデザイン」と「キャリアドリフト」は
まったく別次元の理論である。
キャリアデザインという体系の中の方法論として、
キャリアドリフトがあるわけではない。
だから、それを見つける必要はない。
僕の仮説によると、(笑)
キャリアドリフトの目的は、「お客に出会う」ということ。
自分が仕事として、本当に幸せにしたい人に
出会えるということ。
この人たちのためだったら、
自分はちょっとくらい無理してもいいかな、と思える人に
出会うこと。
これは、数を打たなければ出会えない。
だから、ドリフトが必要なのだ。
「偶然」をつかみながら、いろんなことをやってみるのだ。
自分が幸せにしたいと思えるお客に出会ったとき、
(もちろんお客も経験を重ねることによって変化するかもしれない)
やるべき職業の種類は無限に広がっていく。
その人を幸せにする方法は、
100万通りあるからだ。
そんなキャリア教育を作っていけたらいいと思う。
昨日のツルハシブックスは
そんな思いを確認させてくれるいい対話がありました。
ありがとうございました。
2014年12月28日
テーマの上に道ができる。
「夢を持つ」よりも「テーマを持つ」ほうが
大切なのではないか、と思う。
テーマというのは、研究対象ということ。
テーマがあれば、人生は楽しくなる。
たとえば、
「居場所」というテーマを持つとする。
そうすると、
休みの日にお茶を飲みに行ったカフェだったり、
見に行った美術館だったり。
そうしたところが「研究対象」となっていくのだ。
「半農半X」というコンセプトを生み出した
塩見直紀さんは、
ひとり一研究所の時代が到来していると言っていたが
まさにその通りだろうと思う。
ひとりひとりが
知りたい学びたい深めたいテーマを持って、
暮らしているような社会は楽しそうだなあと思う。
そう考えると、
僕が通ってきた道、これから進む道は、
これまで研究してきた
テーマの延長線上にあるのだろうと思う。
そう。
「テーマの上に道ができる。」のだ。
道ができれば、
あとはそれを進めばいい。
道を作りたいなら、
まずテーマを持つことから始めることだ。
山頂があるから山に登れるという人も
いるかもしれないけど。
テーマを積み重ねていれば、
ちゃんと道はできるし、そのうち山頂のようなものも見えてくるのではないかと思う。
これがキャリア・ドリフト時代の
キャリアの作り方なのではないか。
振り返ると、
人生はテーマの連続だった。
テーマというと難しいかもしれないので、
キーワードと言い換えてもいい。
高校~大学時代
「砂漠緑化」「持続可能な農業」「自然農」
「豊かさとは何か?」
大学卒業~20代
「農を活用したコミュニティづくり」「地域の力」
「世代間交流」「若者のネットワークづくり」
30代
「コミュニティデザイン」「コミュニケーションデザイン」
「若者のための地域プラットフォーム」「大学生のキャリア形成」
というような感じだろうか。
やはり、テーマの上に道ができている。
40代は何をテーマに研究していこうかな。
あなたの研究テーマを教えてください。
大切なのではないか、と思う。
テーマというのは、研究対象ということ。
テーマがあれば、人生は楽しくなる。
たとえば、
「居場所」というテーマを持つとする。
そうすると、
休みの日にお茶を飲みに行ったカフェだったり、
見に行った美術館だったり。
そうしたところが「研究対象」となっていくのだ。
「半農半X」というコンセプトを生み出した
塩見直紀さんは、
ひとり一研究所の時代が到来していると言っていたが
まさにその通りだろうと思う。
ひとりひとりが
知りたい学びたい深めたいテーマを持って、
暮らしているような社会は楽しそうだなあと思う。
そう考えると、
僕が通ってきた道、これから進む道は、
これまで研究してきた
テーマの延長線上にあるのだろうと思う。
そう。
「テーマの上に道ができる。」のだ。
道ができれば、
あとはそれを進めばいい。
道を作りたいなら、
まずテーマを持つことから始めることだ。
山頂があるから山に登れるという人も
いるかもしれないけど。
テーマを積み重ねていれば、
ちゃんと道はできるし、そのうち山頂のようなものも見えてくるのではないかと思う。
これがキャリア・ドリフト時代の
キャリアの作り方なのではないか。
振り返ると、
人生はテーマの連続だった。
テーマというと難しいかもしれないので、
キーワードと言い換えてもいい。
高校~大学時代
「砂漠緑化」「持続可能な農業」「自然農」
「豊かさとは何か?」
大学卒業~20代
「農を活用したコミュニティづくり」「地域の力」
「世代間交流」「若者のネットワークづくり」
30代
「コミュニティデザイン」「コミュニケーションデザイン」
「若者のための地域プラットフォーム」「大学生のキャリア形成」
というような感じだろうか。
やはり、テーマの上に道ができている。
40代は何をテーマに研究していこうかな。
あなたの研究テーマを教えてください。
2014年12月27日
「企画」というコミュニケーション・ツール
昨日は、
夜景企画会議の続編を考える大学生たちと
「働き方研究所@新潟中央自動車学校」で
話をする。

3年生4名
2年生1名
1年生3名
が集まった。
話のテーマは夜景企画会議の感想と
これからの展開について。
僕がメモしていたのは、
「より広い学生に来てほしい」
「合説とは違う、業種を選ぶとかではない就活」
「後につながっていくイベント」
などなど。
僕は、
「夜景企画会議」がなぜ誕生したのか?
という誕生秘話を語る。
もともとは、
ツルハシブックスで店番をしていたとき、
就活中の大学3年生が相談してくれた。
それは、
「就活というシステムに乗れない」
エントリーして、書類選考を通り、
何重もの面接を突破し、やっと内定。
そんなシステムが耐えられないのだという。
それは、同時期に3人の女子大学生から
聞いたので、結構な人が思っているのかもしれない。
そして新潟には小さな会社ももっとあるのかもしれないけど、
それを知る手段がない。とも言っていた。
このとき。
「新しい就活」というキーワードができた。
それは、
学生が手作りする合同企業説明会。
つまり、学生が人事部長になったつもりで、
会社にヒアリングして、会社のことをプレゼンする、
そのうえで社長と面談する、というような
就活ができたら面白いなあと話をしていた。
しかし。
年度末から年度替わりの時期で、
なかなかパワーがなくて断念。
すると、神様が見ていたのか、
今回の企画がやってきた。
オーダーは
「新潟の中小企業を知るために
学生と経営者の座談会の実施」
「座談会」ってなんだかつまんなそうだし、
しかも、社長に対してする質問は、
「どうして社長になったのですか?」
「大学生のときに頑張っていたほうがいいことってありますか?」
「オススメの本があったら教えてください。」
とかいうどうでもいい(文章でアンケートすればいい)
ことばかりになることは明らかだった。
そこで、考えたのが、
その昔ときめいとで中小起業家同友会さんと一緒にやった
「社会事業創造ワークショップ」
大学生と企業の社長がフラットな立場で
事業構想をするというワークショップ。
そういえば僕はあそこでエブリィの渡部さんと
意気投合したのだった。
そう。
「企画」をコミュニケーションの手段とすること。
そうすれば、学生と社長の垣根は消えていく。
それのほうが本来の目的である
「中小企業を知る」ということにつながるだろう。
あとは、
2月3月に構想した「新しい就活」の
学生人事部長のアイデアを拝借。
社長の人柄を語る紙芝居を作成することで
心理的バリアが解消されるのではないか?
こうして「夜景企画会議」が誕生。
社長の人生の紙芝居を見てから、
一緒に企画を考えるという企画。
非常に満足度の高いイベントとなった。
しかし。
当然ながらイベントは1日で終わる。
せっかく考えた企画は実行に移されない。
それでは、あまり意味がないよね、と学生たちも考えていた。
昨日、話したことで気が付いたのは、
働き方研究所の原点。
みんな、「就職」とか「将来」とか「働き方」を
真剣に語りたいと実は思っている。
(思っていない人もいるかもしれないけど)
しかし学校や仲間内では、恥ずかしくて語れないのだ。
だから、「第3の場所」が必要なのだと思う。
そして、
そのやり方も「働き方」について語ります、
というような、朝活みたいなのをやるのではなく、
継続して活動できるようなもの、
つまり、夜景企画会議のような
「企画を考える」ということが
継続的にできるようなものが必要なのではないか。
つまり、「企画」というコミュニケーション・ツールを使って、
「就職」や「将来」や「働き方」を考える場が
必要なのではないか。
ということで、
新潟中央自動車学校内の「働き方研究所」では、
夜景企画会議の続編として、社長を招いた
「プチ企画会議はじめました」
さらには、働き方を語る仲間を集めるための
ポスターや新聞、名刺など様々な企画を考える
「自動車学校かってに広報部かってに企画課(仮)」
を2015年からスタートする予定です。
大学生ならどなたでも参加できます。
(市外、県外の大学生もOKです)
連絡交換のやりとりには、
「ジョブウェブプロフィール」
http://www.jobweb.jp/
を使ってやりたいと思います。
「企画」というコミュニケーション・ツールを使って、
なんとなく抱えている不安。
「就職」「将来」「働き方」について一緒に考えませんか?
夜景企画会議の続編を考える大学生たちと
「働き方研究所@新潟中央自動車学校」で
話をする。

3年生4名
2年生1名
1年生3名
が集まった。
話のテーマは夜景企画会議の感想と
これからの展開について。
僕がメモしていたのは、
「より広い学生に来てほしい」
「合説とは違う、業種を選ぶとかではない就活」
「後につながっていくイベント」
などなど。
僕は、
「夜景企画会議」がなぜ誕生したのか?
という誕生秘話を語る。
もともとは、
ツルハシブックスで店番をしていたとき、
就活中の大学3年生が相談してくれた。
それは、
「就活というシステムに乗れない」
エントリーして、書類選考を通り、
何重もの面接を突破し、やっと内定。
そんなシステムが耐えられないのだという。
それは、同時期に3人の女子大学生から
聞いたので、結構な人が思っているのかもしれない。
そして新潟には小さな会社ももっとあるのかもしれないけど、
それを知る手段がない。とも言っていた。
このとき。
「新しい就活」というキーワードができた。
それは、
学生が手作りする合同企業説明会。
つまり、学生が人事部長になったつもりで、
会社にヒアリングして、会社のことをプレゼンする、
そのうえで社長と面談する、というような
就活ができたら面白いなあと話をしていた。
しかし。
年度末から年度替わりの時期で、
なかなかパワーがなくて断念。
すると、神様が見ていたのか、
今回の企画がやってきた。
オーダーは
「新潟の中小企業を知るために
学生と経営者の座談会の実施」
「座談会」ってなんだかつまんなそうだし、
しかも、社長に対してする質問は、
「どうして社長になったのですか?」
「大学生のときに頑張っていたほうがいいことってありますか?」
「オススメの本があったら教えてください。」
とかいうどうでもいい(文章でアンケートすればいい)
ことばかりになることは明らかだった。
そこで、考えたのが、
その昔ときめいとで中小起業家同友会さんと一緒にやった
「社会事業創造ワークショップ」
大学生と企業の社長がフラットな立場で
事業構想をするというワークショップ。
そういえば僕はあそこでエブリィの渡部さんと
意気投合したのだった。
そう。
「企画」をコミュニケーションの手段とすること。
そうすれば、学生と社長の垣根は消えていく。
それのほうが本来の目的である
「中小企業を知る」ということにつながるだろう。
あとは、
2月3月に構想した「新しい就活」の
学生人事部長のアイデアを拝借。
社長の人柄を語る紙芝居を作成することで
心理的バリアが解消されるのではないか?
こうして「夜景企画会議」が誕生。
社長の人生の紙芝居を見てから、
一緒に企画を考えるという企画。
非常に満足度の高いイベントとなった。
しかし。
当然ながらイベントは1日で終わる。
せっかく考えた企画は実行に移されない。
それでは、あまり意味がないよね、と学生たちも考えていた。
昨日、話したことで気が付いたのは、
働き方研究所の原点。
みんな、「就職」とか「将来」とか「働き方」を
真剣に語りたいと実は思っている。
(思っていない人もいるかもしれないけど)
しかし学校や仲間内では、恥ずかしくて語れないのだ。
だから、「第3の場所」が必要なのだと思う。
そして、
そのやり方も「働き方」について語ります、
というような、朝活みたいなのをやるのではなく、
継続して活動できるようなもの、
つまり、夜景企画会議のような
「企画を考える」ということが
継続的にできるようなものが必要なのではないか。
つまり、「企画」というコミュニケーション・ツールを使って、
「就職」や「将来」や「働き方」を考える場が
必要なのではないか。
ということで、
新潟中央自動車学校内の「働き方研究所」では、
夜景企画会議の続編として、社長を招いた
「プチ企画会議はじめました」
さらには、働き方を語る仲間を集めるための
ポスターや新聞、名刺など様々な企画を考える
「自動車学校かってに広報部かってに企画課(仮)」
を2015年からスタートする予定です。
大学生ならどなたでも参加できます。
(市外、県外の大学生もOKです)
連絡交換のやりとりには、
「ジョブウェブプロフィール」
http://www.jobweb.jp/
を使ってやりたいと思います。
「企画」というコミュニケーション・ツールを使って、
なんとなく抱えている不安。
「就職」「将来」「働き方」について一緒に考えませんか?
2014年12月26日
大学時代に手に入れるべきたったひとつのもの。
ありがちなタイトル。
まあ、いろんなことを言う人がいると思うのだけど。
大学時代に手に入れるべき
たったひとつのもの。
それは、
「自分の感性への自信」、つまり
「自分の感性に自信を持つ」ということ。
いろんな人に会って、
いろんな活動をして、
気づくことがたくさんある。
それを大切にしていくこと。
最初の「ワクワク」というか、そういう感情を信じられるようになること。
それはもう、場数しかない。
「やってみる」しかない。
こういう空気感のときは進むべきじゃないとか。
やってみるべきではないとか。
こういう人は信じられるし、
こういう人は信じてはいけない。
それはもう、マニュアルではなくて、
自分の感性で判断するしかない。
「本物だ」と思えるかどうか。
そこにかかっている。
僕が大学時代に出会った本物の中で、
もっとも大きいインパクトがあったのは、
自然農実践農家の沖津一陽さんだった。
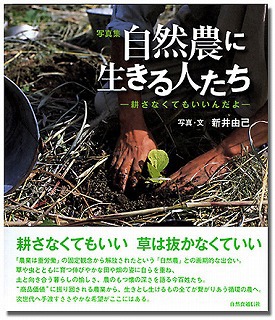
「自然農に生きる人たち」(新井由己 自然食通信社)
に掲載されている。
この人に出会い、僕は農家めぐりの旅を終えた。
「その草を残すべきか、刈るべきか、畑に立つと自然と分かるようになる。」
自然、自由、本気、全力の農、
それが自然農だった。
夏の四国で出会った沖津さんに、僕は秋にまた稲刈りをしに行った。
自分の感性に自信を持つ、ということ。
それは自分の判断を信じられるようになるということ。
2つに道が分かれていたとき、
ひとつに決められるということ。
やるかやらないか決められるということ。
大学時代に手に入れておくべき、
たったひとつのもの。
まずは、感性を磨くため、やってみること、
初めての人に会うということを始めてみませんか?
まあ、いろんなことを言う人がいると思うのだけど。
大学時代に手に入れるべき
たったひとつのもの。
それは、
「自分の感性への自信」、つまり
「自分の感性に自信を持つ」ということ。
いろんな人に会って、
いろんな活動をして、
気づくことがたくさんある。
それを大切にしていくこと。
最初の「ワクワク」というか、そういう感情を信じられるようになること。
それはもう、場数しかない。
「やってみる」しかない。
こういう空気感のときは進むべきじゃないとか。
やってみるべきではないとか。
こういう人は信じられるし、
こういう人は信じてはいけない。
それはもう、マニュアルではなくて、
自分の感性で判断するしかない。
「本物だ」と思えるかどうか。
そこにかかっている。
僕が大学時代に出会った本物の中で、
もっとも大きいインパクトがあったのは、
自然農実践農家の沖津一陽さんだった。
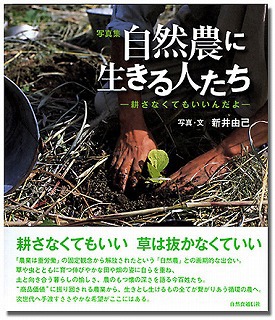
「自然農に生きる人たち」(新井由己 自然食通信社)
に掲載されている。
この人に出会い、僕は農家めぐりの旅を終えた。
「その草を残すべきか、刈るべきか、畑に立つと自然と分かるようになる。」
自然、自由、本気、全力の農、
それが自然農だった。
夏の四国で出会った沖津さんに、僕は秋にまた稲刈りをしに行った。
自分の感性に自信を持つ、ということ。
それは自分の判断を信じられるようになるということ。
2つに道が分かれていたとき、
ひとつに決められるということ。
やるかやらないか決められるということ。
大学時代に手に入れておくべき、
たったひとつのもの。
まずは、感性を磨くため、やってみること、
初めての人に会うということを始めてみませんか?
2014年12月25日
「コミュニティ」を買う時代
モノが売れなくなった。
いや。
実は最近の話ではない。
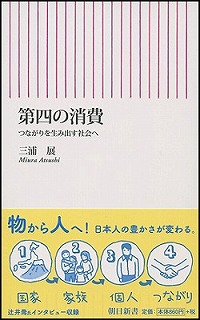
「第四の消費」(三浦展 朝日新書)
を読むと、30年~40年も前にそれは始まっていたという。
※参考 1月30日のブログ「家電を売るために夢を持て」
http://hero.niiblo.jp/e346221.html
冷蔵庫も洗濯機もテレビも家にあった。
冷蔵庫2個あったほうがいいよね、
という人はケーキか漬物の販売業を個人的にしている人くらいだ。
ここで、急速に需要がしぼんでいく、
はずだった。
しかし、そうなるわけにはいかなかった。
家電メーカーにはたくさんの人々が勤めていた。
その多くが団塊の世代で、
彼らは、大都市に出て、マイホームをすでに買っているか、
これから買おうとしていた。
大家族から核家族へ。
これで、冷蔵庫と洗濯機とテレビの需要は2倍になる。
その後、始まったのが、
「夢を持て。」キャンペーンではなかったか。
四人の核家族から一人暮らしへ。
これで家電の需要は四倍になる。
人口増以上のミラクル需要を作りながら、
日本の経済力は高まってきた。
それと引き換えにいろいろなものを置いてきた気がしているいま。
三浦さんは
「第四の消費」として、
「シェア」とか「つながり」などのキーワードがあげられるという。
モノを売る時代、
経済成長とは、「分断すること」だった。
四人暮らしから一人暮らしへ。
業務をアウトソーシングして効率化する。
時代は変わる。
モノが売れなくなった。
「分断された社会」が不安になってきた。
大学生の時、畑サークルで野菜を育てたとき、
豊かさとは、幸せとは、つながっていることだと体感した。
人は何かにつながっていないと生きられないと思った。
「コミュニティ」を売る。
自覚はなくとも、
これはどんどん現実化している。
たとえば、公民館でやっているお茶のサークル。
高齢のおばあちゃんたちが、あそこで欲しいものはなんだろう?
「正しい、もしくは美しいお茶の作法を学びたい」
という動機づけだろうか。
そうではないだろう。
毎週、同じ曜日の決まった時間に趣味を通じて集まってくる
仲間たちに会い、たわいもない話をして、お茶を飲んで帰ってくる。
それが人生にとって必要なのだ。
それは「コミュニティを買っている」ということではないだろうか?
団体スポーツもそうだ。
大人になってからやる趣味のスポーツは、
大会で勝つことが目的ではなく、
体を動かすこと、それよりもそこで出会う仲間たちが価値なのだ
これからは、
「コミュニティ」を買う時代になっている。
ツルハシブックスの「寄付侍」も同じように、
共感した人たちが、自分もその仲間に入りたいと
寄付をすることになる。
それを発展させたのが劇団員の仕組み。
「劇団員」には、それだけではなく、
熱い思想が入っているのだけどね。
自分の周りを劇場のように変えていける人。
それが「劇団員」だと思う。
世の中という大きな劇場の、
日常という小さな劇場のワンシーンを
僕たちは今日も演じている。
共演者たちと、どんなシーンを演じてみようか?
と今日も考える。
年末年始。
周りの人に声をかけて、
不要な古本を集めてみませんか?
1
とても売ることができない大切な古本
⇒メッセージを付けて、ツルハシブックスへ送付
(地下古本コーナーHAKKUTSUに行きます)
2
メッセージをつけるほど大切ではないけど、
誰かの手に届くといいなあという本
⇒段ボールに詰めて、下の申込書に記入し、バリューブックスに電話。
(クロネコヤマトが回収に来てくれます。送料無料)
本でツルハシブックスを応援しよう。
3月までに100件達成を目標にしています。
みなさまの参加をお待ちしています。

いや。
実は最近の話ではない。
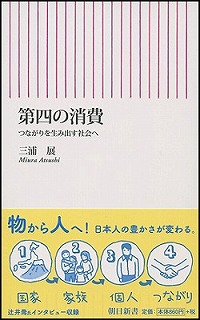
「第四の消費」(三浦展 朝日新書)
を読むと、30年~40年も前にそれは始まっていたという。
※参考 1月30日のブログ「家電を売るために夢を持て」
http://hero.niiblo.jp/e346221.html
冷蔵庫も洗濯機もテレビも家にあった。
冷蔵庫2個あったほうがいいよね、
という人はケーキか漬物の販売業を個人的にしている人くらいだ。
ここで、急速に需要がしぼんでいく、
はずだった。
しかし、そうなるわけにはいかなかった。
家電メーカーにはたくさんの人々が勤めていた。
その多くが団塊の世代で、
彼らは、大都市に出て、マイホームをすでに買っているか、
これから買おうとしていた。
大家族から核家族へ。
これで、冷蔵庫と洗濯機とテレビの需要は2倍になる。
その後、始まったのが、
「夢を持て。」キャンペーンではなかったか。
四人の核家族から一人暮らしへ。
これで家電の需要は四倍になる。
人口増以上のミラクル需要を作りながら、
日本の経済力は高まってきた。
それと引き換えにいろいろなものを置いてきた気がしているいま。
三浦さんは
「第四の消費」として、
「シェア」とか「つながり」などのキーワードがあげられるという。
モノを売る時代、
経済成長とは、「分断すること」だった。
四人暮らしから一人暮らしへ。
業務をアウトソーシングして効率化する。
時代は変わる。
モノが売れなくなった。
「分断された社会」が不安になってきた。
大学生の時、畑サークルで野菜を育てたとき、
豊かさとは、幸せとは、つながっていることだと体感した。
人は何かにつながっていないと生きられないと思った。
「コミュニティ」を売る。
自覚はなくとも、
これはどんどん現実化している。
たとえば、公民館でやっているお茶のサークル。
高齢のおばあちゃんたちが、あそこで欲しいものはなんだろう?
「正しい、もしくは美しいお茶の作法を学びたい」
という動機づけだろうか。
そうではないだろう。
毎週、同じ曜日の決まった時間に趣味を通じて集まってくる
仲間たちに会い、たわいもない話をして、お茶を飲んで帰ってくる。
それが人生にとって必要なのだ。
それは「コミュニティを買っている」ということではないだろうか?
団体スポーツもそうだ。
大人になってからやる趣味のスポーツは、
大会で勝つことが目的ではなく、
体を動かすこと、それよりもそこで出会う仲間たちが価値なのだ
これからは、
「コミュニティ」を買う時代になっている。
ツルハシブックスの「寄付侍」も同じように、
共感した人たちが、自分もその仲間に入りたいと
寄付をすることになる。
それを発展させたのが劇団員の仕組み。
「劇団員」には、それだけではなく、
熱い思想が入っているのだけどね。
自分の周りを劇場のように変えていける人。
それが「劇団員」だと思う。
世の中という大きな劇場の、
日常という小さな劇場のワンシーンを
僕たちは今日も演じている。
共演者たちと、どんなシーンを演じてみようか?
と今日も考える。
年末年始。
周りの人に声をかけて、
不要な古本を集めてみませんか?
1
とても売ることができない大切な古本
⇒メッセージを付けて、ツルハシブックスへ送付
(地下古本コーナーHAKKUTSUに行きます)
2
メッセージをつけるほど大切ではないけど、
誰かの手に届くといいなあという本
⇒段ボールに詰めて、下の申込書に記入し、バリューブックスに電話。
(クロネコヤマトが回収に来てくれます。送料無料)
本でツルハシブックスを応援しよう。
3月までに100件達成を目標にしています。
みなさまの参加をお待ちしています。

2014年12月24日
サンクチュアリ出版と僕 5 第4走者になる
2009年4月。
「ホスピタルクラウン」の著者、大棟耕介さんの
講演会が新潟で開催された。
主催者の今井さんから電話がかかる。
「本を売ってくれませんか?」
しかし、引き受けてくれる書店がなかった。
そこでサンクチュアリ出版に電話。
営業部長の市川さんに相談。
「クラウン売りたいんですけど、書店には断られちゃって。」
「じゃあ西田くん、自分で売る?」
「ええ!いいんですか。売りたいです。」
「何冊にする?それで、委託にする?買い切りにする?」
当日の入場者は250名程度だと言われていた。
大棟さんの講演を聞けば、
きっとみんな本を買いたくなるだろう。
半分くらいの100冊くらいはいけるんじゃないか?
「100冊、買い切りでお願いします。」
代金を振り込み、
僕は100冊のホスピタルクラウンを手に入れた。
当日。
大棟さんの講演会。
本は、売れに売れた。
はずだった。
38冊の売れだった。
やってしまった。
僕は62冊の「ホスピタルクラウン」の在庫を
抱えることになった。
2009年8月。
僕は小さな本屋さんになった。
その頃知り合った新潟活版所の渋谷さんに頼んで名刺を作った。
屋号は、「本屋には小さな人生が転がっている」
オフハウスで1575円の小さなトランクを買った。
名刺交換の時、その名刺を出した。
「本屋さん始めたんです。」
「ええ?どこにお店あるんですか?」
「ココです。」
と後部座席から小さなトランクを出して、
パカっと開けた。
そこには8冊の「ホスピタルクラウン」と
直筆のPOPが貼ってあった。
「天職とは選ぶものではなくたどり着くものだと教えてくれる。」
「その本、そんなにオススメなんですか?」
「もちろんですよ。人生にインパクトあります。
もし面白くなかったら返金しますので。」
と言っていたら、意外に売れた。
笑顔写真家のかとうゆういちくんも
買ってくれたひとりだ。
もしかしたら、
「本屋はじめました。」と言い続けていたことが、
僕を本当に本屋さんにしてしまったのかもしれない。
もうひとつは、福島県郡山駅前にあった
ヴィレッジヴァンガード郡山アティ店の
店長さんとの出会い。
カフェ開業したい人のためのコーナー
のキレイなディスプレイを見て、
何気なく「このコーナー、いいっすね。」
と営業トークをしたことがきっかけだった。
「郡山にカフェをつくろうと思っているんです。」
「えっ?」
「僕がこのコーナーをキレイにつくることによって、
カフェを始める人がいるんじゃないか、と思って。
僕異動して来たんですけど、行きたいカフェがないんですよね~。」
「そんなことできるんですか!?」
衝撃。
郡山にカフェをつくりたいと思って、
カフェコーナーを作る本屋さんなんて。
半年後。
ふたたび営業で行ったとき、
店長さんは笑顔で言った。
「西田さん、カフェできましたよ。」
実際、2件のカフェが新規オープンしたと言うのだ。
衝撃だった。
本屋さんは、人の未来を創るだけじゃなくて、
まちの未来も創るんだって。
いつか自分もそんな本屋をやろうと心から思った。
「人の未来と、まちの未来を創る本屋さん。」
きっとその延長上に、
いまのツルハシブックスがあるのだろうと思う。
出版社の営業という
駅伝の第3走者だった僕は、
書店員(本屋さん)という第4走者になった。
「地域と人生の小田原中継所」という
肩書は辞めてしまったけど、
今日も本屋さんでタスキを渡したいと思っている。
1冊の本で、人生は変わる。
本屋には新しい人生が転がっている。
そのひとつひとつの人生が、そして本が、
本屋という空間をつくる。
出版は素晴らしい仕事だと心から思う。
スポンサー企業の意向を受けることなく、
著者が自分の思いをストレートに紙に綴り、
編集者がそれを伝わりやすくように編集し、
営業が書店員にその思いを伝え、
書店員がそれを目立つところに置く。
「ああ、こんな本あったんだ」
と手に取ったお客さんに何かが伝わったとき、
1冊の本が売れる。
そして今日も、本屋さんでは、
誰かの人生がちょっとずつ動いている。
やっぱり出版は最高です。
日本一ていねいに作り、日本一ていねいに売る。
サンクチュアリ出版の営業として名刺を出せていたことを
僕は心から誇りに思います。
14年間、ありがとうございました。
「ホスピタルクラウン」の著者、大棟耕介さんの
講演会が新潟で開催された。
主催者の今井さんから電話がかかる。
「本を売ってくれませんか?」
しかし、引き受けてくれる書店がなかった。
そこでサンクチュアリ出版に電話。
営業部長の市川さんに相談。
「クラウン売りたいんですけど、書店には断られちゃって。」
「じゃあ西田くん、自分で売る?」
「ええ!いいんですか。売りたいです。」
「何冊にする?それで、委託にする?買い切りにする?」
当日の入場者は250名程度だと言われていた。
大棟さんの講演を聞けば、
きっとみんな本を買いたくなるだろう。
半分くらいの100冊くらいはいけるんじゃないか?
「100冊、買い切りでお願いします。」
代金を振り込み、
僕は100冊のホスピタルクラウンを手に入れた。
当日。
大棟さんの講演会。
本は、売れに売れた。
はずだった。
38冊の売れだった。
やってしまった。
僕は62冊の「ホスピタルクラウン」の在庫を
抱えることになった。
2009年8月。
僕は小さな本屋さんになった。
その頃知り合った新潟活版所の渋谷さんに頼んで名刺を作った。
屋号は、「本屋には小さな人生が転がっている」
オフハウスで1575円の小さなトランクを買った。
名刺交換の時、その名刺を出した。
「本屋さん始めたんです。」
「ええ?どこにお店あるんですか?」
「ココです。」
と後部座席から小さなトランクを出して、
パカっと開けた。
そこには8冊の「ホスピタルクラウン」と
直筆のPOPが貼ってあった。
「天職とは選ぶものではなくたどり着くものだと教えてくれる。」
「その本、そんなにオススメなんですか?」
「もちろんですよ。人生にインパクトあります。
もし面白くなかったら返金しますので。」
と言っていたら、意外に売れた。
笑顔写真家のかとうゆういちくんも
買ってくれたひとりだ。
もしかしたら、
「本屋はじめました。」と言い続けていたことが、
僕を本当に本屋さんにしてしまったのかもしれない。
もうひとつは、福島県郡山駅前にあった
ヴィレッジヴァンガード郡山アティ店の
店長さんとの出会い。
カフェ開業したい人のためのコーナー
のキレイなディスプレイを見て、
何気なく「このコーナー、いいっすね。」
と営業トークをしたことがきっかけだった。
「郡山にカフェをつくろうと思っているんです。」
「えっ?」
「僕がこのコーナーをキレイにつくることによって、
カフェを始める人がいるんじゃないか、と思って。
僕異動して来たんですけど、行きたいカフェがないんですよね~。」
「そんなことできるんですか!?」
衝撃。
郡山にカフェをつくりたいと思って、
カフェコーナーを作る本屋さんなんて。
半年後。
ふたたび営業で行ったとき、
店長さんは笑顔で言った。
「西田さん、カフェできましたよ。」
実際、2件のカフェが新規オープンしたと言うのだ。
衝撃だった。
本屋さんは、人の未来を創るだけじゃなくて、
まちの未来も創るんだって。
いつか自分もそんな本屋をやろうと心から思った。
「人の未来と、まちの未来を創る本屋さん。」
きっとその延長上に、
いまのツルハシブックスがあるのだろうと思う。
出版社の営業という
駅伝の第3走者だった僕は、
書店員(本屋さん)という第4走者になった。
「地域と人生の小田原中継所」という
肩書は辞めてしまったけど、
今日も本屋さんでタスキを渡したいと思っている。
1冊の本で、人生は変わる。
本屋には新しい人生が転がっている。
そのひとつひとつの人生が、そして本が、
本屋という空間をつくる。
出版は素晴らしい仕事だと心から思う。
スポンサー企業の意向を受けることなく、
著者が自分の思いをストレートに紙に綴り、
編集者がそれを伝わりやすくように編集し、
営業が書店員にその思いを伝え、
書店員がそれを目立つところに置く。
「ああ、こんな本あったんだ」
と手に取ったお客さんに何かが伝わったとき、
1冊の本が売れる。
そして今日も、本屋さんでは、
誰かの人生がちょっとずつ動いている。
やっぱり出版は最高です。
日本一ていねいに作り、日本一ていねいに売る。
サンクチュアリ出版の営業として名刺を出せていたことを
僕は心から誇りに思います。
14年間、ありがとうございました。
2014年12月24日
サンクチュアリ出版と僕 4 クラウンとの出会い
もっとも印象に残っている本は、
大棟耕介さんの「ホスピタルクラウン」。
2007年2月発売。
最初の入り方がいい。
病院での笑顔の写真。
「どんなふうに笑ってもいい。」
この最初の数ページだけで、
生きていく希望が湧いてくるような1冊。
2007年5月。
32歳の僕は、玉川大学教育学部(通信)の
教員免許(中学社会)取得コースに在籍していて
北魚沼郡川口町(現在は長岡市)の
川口中学校で教育実習をやらせてもらった。
中学校3年生の担任だったので、
女子からは「だれ?このオッサン?」
みたいなリアクションでつらかったのだけど、
3週間の教育実習をなんとか越えた。
そのとき。
「道徳」の時間を実習することになり、
僕が選んだテキストは「ホスピタルクラウン」だった。
クラウンの中から数ページを抜粋し、
そのシーンで何を感じたか、どんな気持ちだったのか?
を考える授業。
どんな授業の実習よりも、楽しく準備し、熱く語った。
さあ、この夏で集中してラスト20単位を取ろう。
と思っていた矢先の7月16日。
中越沖地震が発生。
「西田さん、刈羽村に入ってくれないか?」
と阿部くんから依頼。
刈羽村ボランティアセンターの
子ども部門のボランティアコーディネーターを
やることになる。
連日の猛暑の中、
弥彦村を出発して往復2時間かけて通う。
避難所となっていた体育館で、
子どもたちの遊び相手をする。
僕はコーディネーターなので、
実際に遊ぶことは少なかったのだけど、
高校生や大学生のボランティアと一緒に、
会えば必ず「野球しようよ」と言ってくる通称、野球少年
の誘いで、35℃の灼熱の太陽の下で野球をしていた。
8月。
急ピッチで仮設住宅が完成。
その集会所をコミュニティの拠点にするにはどうしたらいいのか?
というのがボランティアセンターのミーティングのテーマとなったとき、
クラウンを思い出した。
サンクチュアリの鶴巻社長に電話した。
大棟さんを刈羽村に呼べないだろうか?
数週間後、
大棟さんは刈羽村にやってきてくれた。
集会所には、子どもからお年寄りまで、たくさんの人が集まった。
NHKも取材に来てくれた。
大棟さんたちの芸はどこまでも優しかった。
ちょっぴり涙が出た。
(大棟さんは翌年2008年にも集会所でクラウンをやってくれた。)
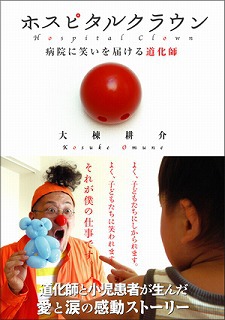
「ホスピタルクラウン」 (大棟耕介 サンクチュアリ出版)
僕の中での思い出の1冊。
そして、ちょうど2007年ころは、
僕が大学生のキャリア支援への
シフトしていくタイミングだった。
「ホスピタルクラウン」は、
医療関係者だけではなく、
働き方生き方を考える全ての若者に
強くオススメする1冊。
天職とは、
選ぶものではなく、たどり着くものだと伝えてくれる。
「病院で芸をして、子どもたちを笑わせたい。」
そんな夢を小さい頃から持つことができる人はほとんどいないはずだ。
もし仮にいるとすれば、長い闘病生活で入院中にクラウンに実際に出会った人だけだ。
そう。
天職とは、出会うものではないのだ。
天職とは、
目の前のことを積み重ねていくうちに
たどり着く瞬間のこと。
来年はもう会えないかもしれない。
(重病の子は亡くなっている可能性があるのです。)
そんな中で、目の前の子どもたちを笑顔にすることに
全力を尽くす。
それこそが働くこと、生きることなのではないか、
と僕は思う。
これからもずっと売っていきたい本、「ホスピタルクラウン」。
大棟耕介さんの「ホスピタルクラウン」。
2007年2月発売。
最初の入り方がいい。
病院での笑顔の写真。
「どんなふうに笑ってもいい。」
この最初の数ページだけで、
生きていく希望が湧いてくるような1冊。
2007年5月。
32歳の僕は、玉川大学教育学部(通信)の
教員免許(中学社会)取得コースに在籍していて
北魚沼郡川口町(現在は長岡市)の
川口中学校で教育実習をやらせてもらった。
中学校3年生の担任だったので、
女子からは「だれ?このオッサン?」
みたいなリアクションでつらかったのだけど、
3週間の教育実習をなんとか越えた。
そのとき。
「道徳」の時間を実習することになり、
僕が選んだテキストは「ホスピタルクラウン」だった。
クラウンの中から数ページを抜粋し、
そのシーンで何を感じたか、どんな気持ちだったのか?
を考える授業。
どんな授業の実習よりも、楽しく準備し、熱く語った。
さあ、この夏で集中してラスト20単位を取ろう。
と思っていた矢先の7月16日。
中越沖地震が発生。
「西田さん、刈羽村に入ってくれないか?」
と阿部くんから依頼。
刈羽村ボランティアセンターの
子ども部門のボランティアコーディネーターを
やることになる。
連日の猛暑の中、
弥彦村を出発して往復2時間かけて通う。
避難所となっていた体育館で、
子どもたちの遊び相手をする。
僕はコーディネーターなので、
実際に遊ぶことは少なかったのだけど、
高校生や大学生のボランティアと一緒に、
会えば必ず「野球しようよ」と言ってくる通称、野球少年
の誘いで、35℃の灼熱の太陽の下で野球をしていた。
8月。
急ピッチで仮設住宅が完成。
その集会所をコミュニティの拠点にするにはどうしたらいいのか?
というのがボランティアセンターのミーティングのテーマとなったとき、
クラウンを思い出した。
サンクチュアリの鶴巻社長に電話した。
大棟さんを刈羽村に呼べないだろうか?
数週間後、
大棟さんは刈羽村にやってきてくれた。
集会所には、子どもからお年寄りまで、たくさんの人が集まった。
NHKも取材に来てくれた。
大棟さんたちの芸はどこまでも優しかった。
ちょっぴり涙が出た。
(大棟さんは翌年2008年にも集会所でクラウンをやってくれた。)
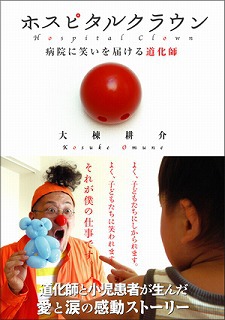
「ホスピタルクラウン」 (大棟耕介 サンクチュアリ出版)
僕の中での思い出の1冊。
そして、ちょうど2007年ころは、
僕が大学生のキャリア支援への
シフトしていくタイミングだった。
「ホスピタルクラウン」は、
医療関係者だけではなく、
働き方生き方を考える全ての若者に
強くオススメする1冊。
天職とは、
選ぶものではなく、たどり着くものだと伝えてくれる。
「病院で芸をして、子どもたちを笑わせたい。」
そんな夢を小さい頃から持つことができる人はほとんどいないはずだ。
もし仮にいるとすれば、長い闘病生活で入院中にクラウンに実際に出会った人だけだ。
そう。
天職とは、出会うものではないのだ。
天職とは、
目の前のことを積み重ねていくうちに
たどり着く瞬間のこと。
来年はもう会えないかもしれない。
(重病の子は亡くなっている可能性があるのです。)
そんな中で、目の前の子どもたちを笑顔にすることに
全力を尽くす。
それこそが働くこと、生きることなのではないか、
と僕は思う。
これからもずっと売っていきたい本、「ホスピタルクラウン」。
2014年12月23日
サンクチュアリ出版と僕 3 タスキをつなぐ
出版社の営業は、駅伝のようだ。
著者から編集者へ。
編集者から営業へ。
営業から書店員へ。
書店員からお客さんへ。
最後の想いのタスキをお客さんが
受け取り、未来へ駆けていく。
第3走者。
出版社営業。
それを自覚したのは、
高橋歩著「イツモイツマデモ」(A-works)
の新刊営業ミーティング。
編集を担当した滝本洋平が
この本への思いを語った。
今でも、耳に焼きついている。
「凛とした感じを出すために、このフォントにしました。」
そうか。
そんなにも編集者は、思いをひとつひとつに込めているんだなと。
God is in the details「神は細部に宿る」
をあれほど感じたことはなかった。
そう。
「ていねいに作られている」すべての本は
著者の思いを編集者が受け取り、
お客さんに届けるために細部まで編集されている。
だから、営業は、その思いを受け取り、
書店員さんに渡さなければならない。
それが「出版社営業」という仕事だと思う。
「売れる本より売りたい本を持ってきてください」
と言ってくれる書店員さんはあまりいないけど、
僕も、
「売れる本じゃなくて、売りたい本を売りましょう。」
といつも営業していたなあ。
本という駅伝の第3走者、出版社の営業。
こんな最高な仕事はなかなかない。
著者から編集者へ。
編集者から営業へ。
営業から書店員へ。
書店員からお客さんへ。
最後の想いのタスキをお客さんが
受け取り、未来へ駆けていく。
第3走者。
出版社営業。
それを自覚したのは、
高橋歩著「イツモイツマデモ」(A-works)
の新刊営業ミーティング。
編集を担当した滝本洋平が
この本への思いを語った。
今でも、耳に焼きついている。
「凛とした感じを出すために、このフォントにしました。」
そうか。
そんなにも編集者は、思いをひとつひとつに込めているんだなと。
God is in the details「神は細部に宿る」
をあれほど感じたことはなかった。
そう。
「ていねいに作られている」すべての本は
著者の思いを編集者が受け取り、
お客さんに届けるために細部まで編集されている。
だから、営業は、その思いを受け取り、
書店員さんに渡さなければならない。
それが「出版社営業」という仕事だと思う。
「売れる本より売りたい本を持ってきてください」
と言ってくれる書店員さんはあまりいないけど、
僕も、
「売れる本じゃなくて、売りたい本を売りましょう。」
といつも営業していたなあ。
本という駅伝の第3走者、出版社の営業。
こんな最高な仕事はなかなかない。
2014年12月23日
サンクチュアリ出版と僕 2 本を並べるの、楽しいんですよね
2001年1月。
僕はサンクチュアリ出版の営業になった。
基本給なしの完全出来高払い。
(いわゆる営業委託契約なのだが)
最初に営業した新刊は
高橋歩さんの「LOVE&FREE」
とりあえず右も左もわからないので、
本屋さんに片っ端から訪問して、名刺を差し出す。
「こんにちは。サンクチュアリ出版です。」
「ああ、営業さんね。」
「新刊のご紹介に参りました。」
「どんなの?」
「高橋歩さんの写真とエッセイがついた本です。」
「旅エッセイ?うちそんなに売れないんだよね。」
ほとんどの書店員さんがそういうリアクションだった。
そこで、僕は既刊本を見せながらシャウトする。
「こういう熱い本が新潟に必要なんすよ!」
熱苦しい営業。
内心、
「必要なのかもしれないけど、大事なのは売れるか売れないかなんだよ」
ときっと思われていたと思う。
「で、指定なの?」
(し、指定ってなんだ?)
※指定とは指定配本のことで、販売前に書店が冊数を指定すること
そこでケースケさんに習った、あれだ。
「フリー入帳です。」
とまあ、噛み合わない会話をして、営業ライフが始まった。
※ちなみにフリー入帳とは、いつでも返本ができる、という意味の業界用語。
最初の共感者は、
蔦屋書店南万代フォーラム店の大森さんだった。
「ええ。サンクチュアリ出版ですか!僕高橋歩さん、好きなんですよ」
「おお!!そうなんですよ。ガツンとやりましょうよ!」
ということでフェア決定。
サンクチュアリ出版の本がドーンと並んだ。
どこの本屋に行っても、
「サンクチュアリ出版?聞いたことないなあ」
と言われながら、本を見せて、ああ、見たことはある、
みたいな感じなリアクションだった。
それを本を1冊1冊説明しながら、
こういう本が新潟の若者を元気にしていくんだと
悩める若者に本を届けたいと営業をしていた。
いつの日か、本屋さんの状況をよく見るようになったし、
本屋さんの話をよく聞くようになった。
どういう本が並んでいて、
どういう本が売れているのか、
どんな人が買っていくのか、
を見るようになった。
「高校が近くにある」と言われると、がぜん燃えた。
サンクチュアリの本を高校生に届けたい、と心から思った。
フェア注文をもらえるようになった。
「この場所で、こういう人たち向けに、こういうラインナップでいきましょう。」
と本屋さんと共感できるようになった。
いま。
思うと、出版営業の仕事は、
「本屋さんと共演者になる。」ことだと思う。
「共犯者」と言ってもいい。
たとえば、
冬のプレゼント本のフェアをやるとき。
こんな人にこんな本が届いたら、うれしいなあと思えるかどうか。
その思いを共有できるかどうか。
それができたとき、出版営業の仕事は楽しくなる。
代官山蔦屋の渡部さんが、
「売れる本じゃなくて、売りたい本を持ってきてください。」
と語っていたけど、(カッコイイ)
書店員さんと一緒に、「売りたい」と思える本、思えるフェアを
並べられるかどうか。
そこに、実は仕事の楽しさも売り上げもかかっているのだ。
え、売り上げは関係ないでしょう。
と思ったあなた。
実は関係があるんです。
新潟にある蔦屋書店の大部分はトップカルチャーという会社が
運営している本屋だ。
その寺尾店に伝説の店員、Yさんがいた。(当時)
いつものように盛り上がって、
「フェアやりましょう。」ということになった。
平台で16点のフェアが並んだ。
売れた。
ビックリするほど売れた。
その半年後、Yさんは南笹口店に異動になる。
「またサンクチュアリのフェアやりましょうよ。」
とふたたびフェアをやることになった。
売れた。
また売れた。
ヤゴマジック炸裂。(あ、名前が・・・)
そのさらに1年後か2年後か、
今度は南万代店に異動になった。
南万代は大森さん時代から、けっこう大きく展開してくれているところなので、
さらにガツンとやってくれた。
そこで、僕はある異変が起きていることに気がついた。
寺尾店と南笹口店に置いてある
サンクチュアリの本がピタリと売れなくなってきていた。
いや、フェアがなくなったわけではない。
Yさんがいなくなっても、フェアは残っていた。
いい場所で大きく展開されていた。
しかし、追加注文が入らない、つまり、売れなくなったのである。
不思議なことがある、とずっと思っていた。
なぜ、Yさんがいる店だと売れて、いなくなると
売れなくなるのか。
そして驚いたことに、
Yさんはサンクチュアリの本をほとんど読んだことがないのだという。
彼女が新潟中央インター店に異動になったときに、
やっと謎が解けた。
サンクチュアリ出版の冬のフェアを、平台にきれいに円形に並べていた。
「これ、展開写真でアップしたいので撮らせてもらってもいいですか?」
と写真を撮ろうとすると、Yさんが言った。
「本を並べるの、楽しいんですよね。」
「それだーーーーー!!!」
と僕は心の中で叫んでいた。
本が入荷されたとき、楽しんで並べているかどうか。
「また本部のヤツら、フェア送ってきやがって。」
と思うのではなく、(笑)
この本の隣はこの本のほうが色的にきれいだな、とか
判型が違うのはこうやってアクセントをつけよう、とか。
そう思っているかどうか。
これは決して精神論ではない。
売れが、まったく違うのだ。
それくらい本屋さんに来るお客さんの感性は鋭くなっているのだ。
店員さんがその本を楽しんで並べているかどうか、
を感じとることができるほどの感性をもっているのだ。
だから、出版社の営業は、
届いた本を楽しく並べたくなるような営業をしないといけない。
そうやって作られた棚やフェアは、
本屋と出版社営業の共同作品であり、
それがたとえ売れなかったとしても、
きっとまた本屋さんはその出版社の本を注文してくれるだろう。
売れない責任を、自分(書店員)も負う。
それが共演者、共犯者になるということだ。
僕はサンクチュアリ出版の営業になった。
基本給なしの完全出来高払い。
(いわゆる営業委託契約なのだが)
最初に営業した新刊は
高橋歩さんの「LOVE&FREE」
とりあえず右も左もわからないので、
本屋さんに片っ端から訪問して、名刺を差し出す。
「こんにちは。サンクチュアリ出版です。」
「ああ、営業さんね。」
「新刊のご紹介に参りました。」
「どんなの?」
「高橋歩さんの写真とエッセイがついた本です。」
「旅エッセイ?うちそんなに売れないんだよね。」
ほとんどの書店員さんがそういうリアクションだった。
そこで、僕は既刊本を見せながらシャウトする。
「こういう熱い本が新潟に必要なんすよ!」
熱苦しい営業。
内心、
「必要なのかもしれないけど、大事なのは売れるか売れないかなんだよ」
ときっと思われていたと思う。
「で、指定なの?」
(し、指定ってなんだ?)
※指定とは指定配本のことで、販売前に書店が冊数を指定すること
そこでケースケさんに習った、あれだ。
「フリー入帳です。」
とまあ、噛み合わない会話をして、営業ライフが始まった。
※ちなみにフリー入帳とは、いつでも返本ができる、という意味の業界用語。
最初の共感者は、
蔦屋書店南万代フォーラム店の大森さんだった。
「ええ。サンクチュアリ出版ですか!僕高橋歩さん、好きなんですよ」
「おお!!そうなんですよ。ガツンとやりましょうよ!」
ということでフェア決定。
サンクチュアリ出版の本がドーンと並んだ。
どこの本屋に行っても、
「サンクチュアリ出版?聞いたことないなあ」
と言われながら、本を見せて、ああ、見たことはある、
みたいな感じなリアクションだった。
それを本を1冊1冊説明しながら、
こういう本が新潟の若者を元気にしていくんだと
悩める若者に本を届けたいと営業をしていた。
いつの日か、本屋さんの状況をよく見るようになったし、
本屋さんの話をよく聞くようになった。
どういう本が並んでいて、
どういう本が売れているのか、
どんな人が買っていくのか、
を見るようになった。
「高校が近くにある」と言われると、がぜん燃えた。
サンクチュアリの本を高校生に届けたい、と心から思った。
フェア注文をもらえるようになった。
「この場所で、こういう人たち向けに、こういうラインナップでいきましょう。」
と本屋さんと共感できるようになった。
いま。
思うと、出版営業の仕事は、
「本屋さんと共演者になる。」ことだと思う。
「共犯者」と言ってもいい。
たとえば、
冬のプレゼント本のフェアをやるとき。
こんな人にこんな本が届いたら、うれしいなあと思えるかどうか。
その思いを共有できるかどうか。
それができたとき、出版営業の仕事は楽しくなる。
代官山蔦屋の渡部さんが、
「売れる本じゃなくて、売りたい本を持ってきてください。」
と語っていたけど、(カッコイイ)
書店員さんと一緒に、「売りたい」と思える本、思えるフェアを
並べられるかどうか。
そこに、実は仕事の楽しさも売り上げもかかっているのだ。
え、売り上げは関係ないでしょう。
と思ったあなた。
実は関係があるんです。
新潟にある蔦屋書店の大部分はトップカルチャーという会社が
運営している本屋だ。
その寺尾店に伝説の店員、Yさんがいた。(当時)
いつものように盛り上がって、
「フェアやりましょう。」ということになった。
平台で16点のフェアが並んだ。
売れた。
ビックリするほど売れた。
その半年後、Yさんは南笹口店に異動になる。
「またサンクチュアリのフェアやりましょうよ。」
とふたたびフェアをやることになった。
売れた。
また売れた。
ヤゴマジック炸裂。(あ、名前が・・・)
そのさらに1年後か2年後か、
今度は南万代店に異動になった。
南万代は大森さん時代から、けっこう大きく展開してくれているところなので、
さらにガツンとやってくれた。
そこで、僕はある異変が起きていることに気がついた。
寺尾店と南笹口店に置いてある
サンクチュアリの本がピタリと売れなくなってきていた。
いや、フェアがなくなったわけではない。
Yさんがいなくなっても、フェアは残っていた。
いい場所で大きく展開されていた。
しかし、追加注文が入らない、つまり、売れなくなったのである。
不思議なことがある、とずっと思っていた。
なぜ、Yさんがいる店だと売れて、いなくなると
売れなくなるのか。
そして驚いたことに、
Yさんはサンクチュアリの本をほとんど読んだことがないのだという。
彼女が新潟中央インター店に異動になったときに、
やっと謎が解けた。
サンクチュアリ出版の冬のフェアを、平台にきれいに円形に並べていた。
「これ、展開写真でアップしたいので撮らせてもらってもいいですか?」
と写真を撮ろうとすると、Yさんが言った。
「本を並べるの、楽しいんですよね。」
「それだーーーーー!!!」
と僕は心の中で叫んでいた。
本が入荷されたとき、楽しんで並べているかどうか。
「また本部のヤツら、フェア送ってきやがって。」
と思うのではなく、(笑)
この本の隣はこの本のほうが色的にきれいだな、とか
判型が違うのはこうやってアクセントをつけよう、とか。
そう思っているかどうか。
これは決して精神論ではない。
売れが、まったく違うのだ。
それくらい本屋さんに来るお客さんの感性は鋭くなっているのだ。
店員さんがその本を楽しんで並べているかどうか、
を感じとることができるほどの感性をもっているのだ。
だから、出版社の営業は、
届いた本を楽しく並べたくなるような営業をしないといけない。
そうやって作られた棚やフェアは、
本屋と出版社営業の共同作品であり、
それがたとえ売れなかったとしても、
きっとまた本屋さんはその出版社の本を注文してくれるだろう。
売れない責任を、自分(書店員)も負う。
それが共演者、共犯者になるということだ。
2014年12月23日
サンクチュアリ出版と僕 1 入社
サンクチュアリ出版新潟営業部。
2001年に鶴巻さんが作ってくれた
ひとりだけの部署。
サンクチュアリ出版。
カリスマ自由人、高橋歩が立ち上げた出版社。
1998年11月、鶴巻謙介さんに引き継がれる。
そのタイミングで僕はサンクチュアリ出版に出会う。
東京都北区王子「物語バー狐の木」の地下に
「王子小劇場」があった。
「20代熱くなって時代を駆け抜けろ」
という恥ずかしくなってしまうような
熱いタイトルのお芝居と、
鶴巻さんと軌保博光(てんつくマン)のトークライブがあった。
シビれた。
今、この瞬間を燃焼して生きようと思った。
そして帰りに渡された特典、
「クロスロードジェネレーションブック」が人生を動かした。
尾崎豊や大リーガー野茂英雄らの熱い名言を集めた
書籍「クロスロード」のサブ本。
日本の各地で熱く輝く20代の姿がそこにあった。
負けられない。
そして僕も新潟を熱くしよう。
そう誓った。
そして、サンクチュアリ出版に電話。
「すみません。クロスロードジェネレーションブックを100冊買いたいんですけど」
「えっ。ひゃ、100冊ですか??」
「はい。新潟で配りますんで。いくらですか?」
「1冊300円なんで、30000円です。でも、特別に20000円でいいですよ。」
「ありがとうございます!振り込みます。」
ということで即20000円を振り込んだ僕のアパートに、
100冊のクロスロードジェネレーションブックが届いた。
それ以来、僕はサンクチュアリ出版の熱心な読者になった。
大学生協の本屋さんで
サンクチュアリ出版の刊行物をすべて(すべてですよ)客注した。
そして東京に行くたびに、
(王子の「狐の木」の飲み会に通っていた)
三田の慶応大学前のサンクチュアリ出版の
入っているビルに遊びに行った。
2000年11月。
僕はとある団体立ち上げのイベントを企画。
新潟を熱くしよう、ということで、
サンクチュアリ出版 鶴巻社長
松本・金子両副社長、そしてverbの梅中くん
を呼んでトークセッションを企画した。
(ノーギャラ、交通費なしという条件で来てくれたみんなに大感謝)
駅前でツルさんを送っていく車の中で、
プッチモニの「ちょこっとLOVE」を聞きながら、
「給料いらないので新潟でサンクチュアリの本の営業、やりたいっす。」
と頼み込んだ。
その2か月後。
2001年1月に、三田のビルで、
僕はケースケさん(現在編集長)
から営業の仕方を習っていた。
「これが注文書で、ココに番線印ってハンコもらえばいいから。」
「そうすると取次ってところから本が届くから。」
「何か聞かれたら、フリー入帳です、って言っとけばいいから。」
ということで、僕はサンクチュアリ出版の営業になりました。
2001年に鶴巻さんが作ってくれた
ひとりだけの部署。
サンクチュアリ出版。
カリスマ自由人、高橋歩が立ち上げた出版社。
1998年11月、鶴巻謙介さんに引き継がれる。
そのタイミングで僕はサンクチュアリ出版に出会う。
東京都北区王子「物語バー狐の木」の地下に
「王子小劇場」があった。
「20代熱くなって時代を駆け抜けろ」
という恥ずかしくなってしまうような
熱いタイトルのお芝居と、
鶴巻さんと軌保博光(てんつくマン)のトークライブがあった。
シビれた。
今、この瞬間を燃焼して生きようと思った。
そして帰りに渡された特典、
「クロスロードジェネレーションブック」が人生を動かした。
尾崎豊や大リーガー野茂英雄らの熱い名言を集めた
書籍「クロスロード」のサブ本。
日本の各地で熱く輝く20代の姿がそこにあった。
負けられない。
そして僕も新潟を熱くしよう。
そう誓った。
そして、サンクチュアリ出版に電話。
「すみません。クロスロードジェネレーションブックを100冊買いたいんですけど」
「えっ。ひゃ、100冊ですか??」
「はい。新潟で配りますんで。いくらですか?」
「1冊300円なんで、30000円です。でも、特別に20000円でいいですよ。」
「ありがとうございます!振り込みます。」
ということで即20000円を振り込んだ僕のアパートに、
100冊のクロスロードジェネレーションブックが届いた。
それ以来、僕はサンクチュアリ出版の熱心な読者になった。
大学生協の本屋さんで
サンクチュアリ出版の刊行物をすべて(すべてですよ)客注した。
そして東京に行くたびに、
(王子の「狐の木」の飲み会に通っていた)
三田の慶応大学前のサンクチュアリ出版の
入っているビルに遊びに行った。
2000年11月。
僕はとある団体立ち上げのイベントを企画。
新潟を熱くしよう、ということで、
サンクチュアリ出版 鶴巻社長
松本・金子両副社長、そしてverbの梅中くん
を呼んでトークセッションを企画した。
(ノーギャラ、交通費なしという条件で来てくれたみんなに大感謝)
駅前でツルさんを送っていく車の中で、
プッチモニの「ちょこっとLOVE」を聞きながら、
「給料いらないので新潟でサンクチュアリの本の営業、やりたいっす。」
と頼み込んだ。
その2か月後。
2001年1月に、三田のビルで、
僕はケースケさん(現在編集長)
から営業の仕方を習っていた。
「これが注文書で、ココに番線印ってハンコもらえばいいから。」
「そうすると取次ってところから本が届くから。」
「何か聞かれたら、フリー入帳です、って言っとけばいいから。」
ということで、僕はサンクチュアリ出版の営業になりました。
2014年12月22日
入口と出口
ツルハシブックスという空間。
それは、
「今まで見てきた世界だけが唯一の世界じゃない」
ということを体感できるということ。
「学校」「部活」「会社」「効率化された社会」
これらは決して、
唯一の世界ではないということ。
いじめや不登校を「ツラい」と思うのは、
「学校」だけが唯一の世界で、
その世界から弾き出された自分に
行く場所がない、ということ。
その解決策は、
「いじめやめよう」とキャンペーンを張ることではなく、
「不登校をなんとが学校にいけるようにしよう」と
努力することではなく、
「学校だけが唯一の世界ではない」
ことを伝えてあげること。
そして、世の中に存在するたくさんの世界(世界観)
を見せてあげること。
それには、地域の力が必要で、
そのような場をたくさんつくっていくことが必要だ。
会社も同じだ。
ひとつの会社に自分が勤められなかったらから、
あるいは就職活動にいまいち乗り切れない、
だったとしても、それはひとつの世界に過ぎないのだから、
世界を広げることで、悩みを解消すればいい。
しかし。
そこに安住することができる人は少ない。
世界の広さを知った上で、
ふたたび、学校や会社といった世の中という舞台に
仮面をかぶって入っていかなくてはならない。
世の中に適応した人を「演じる」ことを始めなければならない。
ツルハシブックスは世界の広さを知るための入口であり、
だとすると、出口を作る必要がある。
中学生高校生にとっての出口は、進学。
大学生にとっての出口は、就職。
社会人にとっての出口は、再就職またはナリワイをつくる。
その部分の強化をしていく時が
来ているのではないだろうか。
ツルハシブックスは、
新潟中央自動車学校内に、
小さなライブラリー「働き方研究所」を設置し、
おもに大学生が働き方について考える機会を提供しています。
11月5日12日に行った、
大学生と地域企業の経営者による
「夜景企画会議」の続きを、
働き方研究所内でスタートしようと思います。
先日話を聞いてきた
「ジョブウェブプロフィール」
http://www.jobweb.jp/
とも連動しながら、
「新しい就活」を作っていけたらと思います。
社会人向けには、
ツルハシブックス「夜のオフィス」
というのをスタートして、
ナリワイづくりをしていこうと思います。
入口と出口。
いろんな関係機関と連携していけたら、
面白いことになるかと思います。
それは、
「今まで見てきた世界だけが唯一の世界じゃない」
ということを体感できるということ。
「学校」「部活」「会社」「効率化された社会」
これらは決して、
唯一の世界ではないということ。
いじめや不登校を「ツラい」と思うのは、
「学校」だけが唯一の世界で、
その世界から弾き出された自分に
行く場所がない、ということ。
その解決策は、
「いじめやめよう」とキャンペーンを張ることではなく、
「不登校をなんとが学校にいけるようにしよう」と
努力することではなく、
「学校だけが唯一の世界ではない」
ことを伝えてあげること。
そして、世の中に存在するたくさんの世界(世界観)
を見せてあげること。
それには、地域の力が必要で、
そのような場をたくさんつくっていくことが必要だ。
会社も同じだ。
ひとつの会社に自分が勤められなかったらから、
あるいは就職活動にいまいち乗り切れない、
だったとしても、それはひとつの世界に過ぎないのだから、
世界を広げることで、悩みを解消すればいい。
しかし。
そこに安住することができる人は少ない。
世界の広さを知った上で、
ふたたび、学校や会社といった世の中という舞台に
仮面をかぶって入っていかなくてはならない。
世の中に適応した人を「演じる」ことを始めなければならない。
ツルハシブックスは世界の広さを知るための入口であり、
だとすると、出口を作る必要がある。
中学生高校生にとっての出口は、進学。
大学生にとっての出口は、就職。
社会人にとっての出口は、再就職またはナリワイをつくる。
その部分の強化をしていく時が
来ているのではないだろうか。
ツルハシブックスは、
新潟中央自動車学校内に、
小さなライブラリー「働き方研究所」を設置し、
おもに大学生が働き方について考える機会を提供しています。
11月5日12日に行った、
大学生と地域企業の経営者による
「夜景企画会議」の続きを、
働き方研究所内でスタートしようと思います。
先日話を聞いてきた
「ジョブウェブプロフィール」
http://www.jobweb.jp/
とも連動しながら、
「新しい就活」を作っていけたらと思います。
社会人向けには、
ツルハシブックス「夜のオフィス」
というのをスタートして、
ナリワイづくりをしていこうと思います。
入口と出口。
いろんな関係機関と連携していけたら、
面白いことになるかと思います。
2014年12月21日
ツルハシブックスの「ファンドレイザー」になります
「ファンドレイジング」とは、
民間非営利団体が活動のための資金を
個人、法人、政府などから集める行為の総称であり、
それを行う人のことを「ファンドレイザー」と呼ぶ。
「ツルハシブックス」の運営団体である
NPO法人ヒーローズファームは、
2002年にNPO法人虹のおととして設立された。
きっかけは、
何度もこのブログに登場している
不登校の中学3年生との出会い。
1月に彼に出会い、元気になっていく彼の姿を見て、
「学校外に、地域の大人との出会いの場がある」
ということがすごく大切であると思い、
そんな場をつくりたいとNPOを設立した。
しかし、設立したのはいいけど、
僕には仮説がなかった。
どうやったら、学校外にそのような「場」を
作れるのかわからなかった。
拠点は巻町(現在の新潟市西蒲区)
祭りでの「昔の遊び屋台」から始まって、
2004年の中越地震のときには川口町で
ホールアース自然学校のコーディネートの元で
子どもと遊ぶボランティアをした。
その翌年から巻の神社でも
定期的に子どもの遊び場づくりを行い、
2007年の中越沖地震のときは刈羽村で
子ども支援部門のコーディネーターを行った。
そのころ、もうひとつの流れがある。
2006年、東京のNPO法人ETIC.が主催する
「NEC社会起業塾」に応募。
たしか、地域の大人とつながれる学習塾みたいなコンセプト
だったと思う。
あえなく2次審査で落ちる。
しかし、それを見ていたETIC.内部では
「チャレンジコミュニティプロジェクト(チャレコミ)」のほうが
向いているのではないか?と思われて、
ETIC.のフェロー、広石さんと面談し、チャレコミのギャザリングに参加する。
ビックリした。
大学生のあまりの眩しさに。
ステージ上に立つ大学生の輝きに。
僕はまぶしすぎて思わず目を覆った。
それ以来、チャレコミが目指している、
大学生が地域企業での長期のインターンシップを
することによる「チャレンジが連鎖するコミュニティ」
を新潟でも実現させようと準備をし始める。
新潟大学経済学部2年(当時)の星野くんと
二人三脚で事業化へ向けてスタートしていった。
2007年秋には、大阪から中村憲和を招致。
2008年2月に長期インターンシップ「起業家留学」がスタートした。
それに伴って2008年10月1日に法人名称を「ヒーローズファーム」に変更した。
3年半に渡って行ったインターンシップ事業は、
試行錯誤の連続だった。
そして、僕には新たな問いが生まれた。
半年間にわたる長期のインターンシップに参加し、やり遂げることができるのは、
いわゆる「優秀な学生」に限られる。
そして企業も当然、戦力になりうる「優秀な学生」を求める。
では果たして、彼らは僕のお客なのだろうか?
もちろん、お客ではない、わけではなかった。
彼らは彼らなりの悩みを抱え、
もやもやした気持ちで大学生活を送っていた。
しかし。
僕が相手にしたいのは、もっと普通の学生だった。
将来になんとなく不安で、夢や目標もなくて、
何をしたらよいかわからない。
2010年から取り組んだ
ソーシャルビジネス人材育成インターンシップは
大学と連携した30日間のプロジェクトだった。
舞台は商店街のお店やNPOだった。
大学1年生が30日間で劇的に変わった。
商店街という舞台に魅力を持った。
大学生は商店街を拠点とした活動で
普通の子も元気になっていくのではないか?
2011年3月。
東日本大震災による自粛ムードが日本を覆っている中で
内野駅前にツルハシブックスがオープン。
あれから3年半が過ぎ、ツルハシブックスは
大学生や若手社会人が集まって話し、
地域の大人たちがたまに顔を出し、
中学生高校生が屋台でモノを売る空間となった。
気がついたら、
2002年の虹のおとを設立したときに探していた
中学生高校生と地域の大人が出会える場
が実現していていた。
ツルハシブックスは民間非営利団体だ。
「本屋」という場が地域のプラットフォームとして
もっとも魅力的だから、その方法論をとっているのだ。
そして、その「場」は
参加者、参画者が増えることで、
魅力を増していく。
だから僕はツルハシブックスのファンドレイザーになることにした。
個人、法人、政府から資金を集めることだ。
団体の魅力を伝え、寄付を募ることだ。

子どもが熱を出したときに会社を休みがちだったこと理由に会社を解雇された
知人の出来事に憤り、病児保育を仕組化したNPO法人フローレンスの駒崎さんは
著書「社会を変えるお金の使い方」(英治出版)の中で
「寄付は投票だ」と言っている。
共感を得て、投票してもらう。
その投票がたまたまお金という「価値」を通して行われるということ。
寄付は目的ではなく、始まりだ。
寄付することで、人は応援者になる。
寄付することで、人は参画者になる。
寄付することで、人は当事者になる。
そんな物語の始まりが寄付なのではないか。
世の中をよくしていく方法は、唯一、当事者を増やすことだと思う。
寄付を募ることは、当事者を増やすこと。
僕は、これからツルハシブックスのファンドレイザーになります。
あなたも、中学生・高校生を含む若者のための
地域プラットフォーム「ツルハシブックス」の
当事者になりませんか?
ツルハシブックスでは、以下の募集をしています。
1 劇団員(月額1,000円 半年または1年一括払い)
劇団員証とハンコがもらえ、劇団員同士がつながれる仕組みです。
※次回(第2期)の劇団員募集受付は2015年3月1日からスタートします。
2 ヒーローズ(月額10,000円)
ツルハシブックスの一口オーナー制度です。1日店長ができます。
3 寄付侍(一口3,000円)
オリジナルの寄付侍名刺100枚をお渡しします。
そして、今回。
株式会社バリューブックスさんとの連携により
「チャリボン」プロジェクトに参加が決まりました。
http://www.charibon.jp/
不要になった本をバリューブックスに送ると、
その買取金額が、ツルハシブックスに寄付されるという仕組みです。
リリースまであと1週間程度かかりますが、
年末大掃除をお考えのご家庭、事業所の皆様には、
不要になった本をキープしていただき、「チャリボン」の
スタートダッシュにご協力をお願いしたいと思います。
3月までに、100名(事業所)の方からの寄付本を
お待ちしています。
そこで、
4 寄付本侍
をスタートしようと思います。
「チャリボン」の仕組みを通じて、本を寄付頂いた方には、
寄付本侍の証として、「寄付本侍バッチ」をお送りしたいと思います。
あとはご協力いただけるお店や事業所には、
「寄付本侍箱」設置のための何かしらのグッズを
お送りしたいと思います。
今井さんのデザインするバッチやグッズがどんなふうになるか楽しみです。
詳細はまだ、決まりませんが、
ご家庭や職場にある本を、捨てずにキープしておいて頂けるとうれしいです。
あなたも、本でツルハシブックスに参加しませんか?
民間非営利団体が活動のための資金を
個人、法人、政府などから集める行為の総称であり、
それを行う人のことを「ファンドレイザー」と呼ぶ。
「ツルハシブックス」の運営団体である
NPO法人ヒーローズファームは、
2002年にNPO法人虹のおととして設立された。
きっかけは、
何度もこのブログに登場している
不登校の中学3年生との出会い。
1月に彼に出会い、元気になっていく彼の姿を見て、
「学校外に、地域の大人との出会いの場がある」
ということがすごく大切であると思い、
そんな場をつくりたいとNPOを設立した。
しかし、設立したのはいいけど、
僕には仮説がなかった。
どうやったら、学校外にそのような「場」を
作れるのかわからなかった。
拠点は巻町(現在の新潟市西蒲区)
祭りでの「昔の遊び屋台」から始まって、
2004年の中越地震のときには川口町で
ホールアース自然学校のコーディネートの元で
子どもと遊ぶボランティアをした。
その翌年から巻の神社でも
定期的に子どもの遊び場づくりを行い、
2007年の中越沖地震のときは刈羽村で
子ども支援部門のコーディネーターを行った。
そのころ、もうひとつの流れがある。
2006年、東京のNPO法人ETIC.が主催する
「NEC社会起業塾」に応募。
たしか、地域の大人とつながれる学習塾みたいなコンセプト
だったと思う。
あえなく2次審査で落ちる。
しかし、それを見ていたETIC.内部では
「チャレンジコミュニティプロジェクト(チャレコミ)」のほうが
向いているのではないか?と思われて、
ETIC.のフェロー、広石さんと面談し、チャレコミのギャザリングに参加する。
ビックリした。
大学生のあまりの眩しさに。
ステージ上に立つ大学生の輝きに。
僕はまぶしすぎて思わず目を覆った。
それ以来、チャレコミが目指している、
大学生が地域企業での長期のインターンシップを
することによる「チャレンジが連鎖するコミュニティ」
を新潟でも実現させようと準備をし始める。
新潟大学経済学部2年(当時)の星野くんと
二人三脚で事業化へ向けてスタートしていった。
2007年秋には、大阪から中村憲和を招致。
2008年2月に長期インターンシップ「起業家留学」がスタートした。
それに伴って2008年10月1日に法人名称を「ヒーローズファーム」に変更した。
3年半に渡って行ったインターンシップ事業は、
試行錯誤の連続だった。
そして、僕には新たな問いが生まれた。
半年間にわたる長期のインターンシップに参加し、やり遂げることができるのは、
いわゆる「優秀な学生」に限られる。
そして企業も当然、戦力になりうる「優秀な学生」を求める。
では果たして、彼らは僕のお客なのだろうか?
もちろん、お客ではない、わけではなかった。
彼らは彼らなりの悩みを抱え、
もやもやした気持ちで大学生活を送っていた。
しかし。
僕が相手にしたいのは、もっと普通の学生だった。
将来になんとなく不安で、夢や目標もなくて、
何をしたらよいかわからない。
2010年から取り組んだ
ソーシャルビジネス人材育成インターンシップは
大学と連携した30日間のプロジェクトだった。
舞台は商店街のお店やNPOだった。
大学1年生が30日間で劇的に変わった。
商店街という舞台に魅力を持った。
大学生は商店街を拠点とした活動で
普通の子も元気になっていくのではないか?
2011年3月。
東日本大震災による自粛ムードが日本を覆っている中で
内野駅前にツルハシブックスがオープン。
あれから3年半が過ぎ、ツルハシブックスは
大学生や若手社会人が集まって話し、
地域の大人たちがたまに顔を出し、
中学生高校生が屋台でモノを売る空間となった。
気がついたら、
2002年の虹のおとを設立したときに探していた
中学生高校生と地域の大人が出会える場
が実現していていた。
ツルハシブックスは民間非営利団体だ。
「本屋」という場が地域のプラットフォームとして
もっとも魅力的だから、その方法論をとっているのだ。
そして、その「場」は
参加者、参画者が増えることで、
魅力を増していく。
だから僕はツルハシブックスのファンドレイザーになることにした。
個人、法人、政府から資金を集めることだ。
団体の魅力を伝え、寄付を募ることだ。

子どもが熱を出したときに会社を休みがちだったこと理由に会社を解雇された
知人の出来事に憤り、病児保育を仕組化したNPO法人フローレンスの駒崎さんは
著書「社会を変えるお金の使い方」(英治出版)の中で
「寄付は投票だ」と言っている。
共感を得て、投票してもらう。
その投票がたまたまお金という「価値」を通して行われるということ。
寄付は目的ではなく、始まりだ。
寄付することで、人は応援者になる。
寄付することで、人は参画者になる。
寄付することで、人は当事者になる。
そんな物語の始まりが寄付なのではないか。
世の中をよくしていく方法は、唯一、当事者を増やすことだと思う。
寄付を募ることは、当事者を増やすこと。
僕は、これからツルハシブックスのファンドレイザーになります。
あなたも、中学生・高校生を含む若者のための
地域プラットフォーム「ツルハシブックス」の
当事者になりませんか?
ツルハシブックスでは、以下の募集をしています。
1 劇団員(月額1,000円 半年または1年一括払い)
劇団員証とハンコがもらえ、劇団員同士がつながれる仕組みです。
※次回(第2期)の劇団員募集受付は2015年3月1日からスタートします。
2 ヒーローズ(月額10,000円)
ツルハシブックスの一口オーナー制度です。1日店長ができます。
3 寄付侍(一口3,000円)
オリジナルの寄付侍名刺100枚をお渡しします。
そして、今回。
株式会社バリューブックスさんとの連携により
「チャリボン」プロジェクトに参加が決まりました。
http://www.charibon.jp/
不要になった本をバリューブックスに送ると、
その買取金額が、ツルハシブックスに寄付されるという仕組みです。
リリースまであと1週間程度かかりますが、
年末大掃除をお考えのご家庭、事業所の皆様には、
不要になった本をキープしていただき、「チャリボン」の
スタートダッシュにご協力をお願いしたいと思います。
3月までに、100名(事業所)の方からの寄付本を
お待ちしています。
そこで、
4 寄付本侍
をスタートしようと思います。
「チャリボン」の仕組みを通じて、本を寄付頂いた方には、
寄付本侍の証として、「寄付本侍バッチ」をお送りしたいと思います。
あとはご協力いただけるお店や事業所には、
「寄付本侍箱」設置のための何かしらのグッズを
お送りしたいと思います。
今井さんのデザインするバッチやグッズがどんなふうになるか楽しみです。
詳細はまだ、決まりませんが、
ご家庭や職場にある本を、捨てずにキープしておいて頂けるとうれしいです。
あなたも、本でツルハシブックスに参加しませんか?
2014年12月20日
【お知らせ】1月から茨城に転居します。
お世話になっている関係者の皆様へ
日ごろからたいへんお世話になり、ありがとうございます。
このたび、私は平成27年1月より、
茨城大学社会連携センターのコーディネーターとして、勤務することとなりました。
非常勤職員という形になりますが、茨城県水戸市近郊に転居する予定です。
ツルハシブックスは、法人名称をヒーローズファームから
「NPO法人 ツルハシブックス」として再出発し、
スタッフ体制を一新し、継続して運営していきます。
法人の代表は今まで通り務めながら、
三連休を中心に本屋の運営に、また東京近郊を中心とした
ファンドレイジングや新たな展開に携わりたいと思っております。
ツルハシブックス運営母体であるNPO法人ヒーローズファームは、
2002年から若者×地域というテーマで、小学生の遊び場づくり、
大学生の企業インターンシップ、商店街や
中山間地、離島などでの若者向けの研修プログラムづくりなどを行ってきました。
2011年3月には内野駅前にツルハシブックスをオープンし、
本屋をベースにした地域拠点づくりに取り組み、
現在では中学生・高校生を含めて、たくさんの若者が訪れる場所となり、
屋台やイベントなどを通じた地域との接点づくりを行っています。
私自身はこの8月で40歳となりました。
今年初めから、ドラッカーの経営者のための5つの質問に答えていく日々を送っておりました。
「顧客は誰か?」「顧客にとって価値は何か?」その2つの質問から、
改めて自分のミッションが浮かび上がってくると思っていたからです。
私にとって、顧客とは、人生と将来に悩む中学生・高校生・大学生・20代社会人です。
顧客にとっての価値は、学校や家庭とは異なる、第3の場所、第3の大人と知り合い、
価値観を揺さぶられ、何か行動を起こすことです。
そのためには、自分自身がもっと彼らのことをよく知り、
なぜ彼らにとって地域が重要なのかを説明できることが必要だと思い、
大学というフィールドで再び学ぶことを決意いたしました。
ツルハシブックスは、私のお店ではありません。
店を設計・施工した今井さんをはじめ、現在支えている店員侍と一口オーナー「ヒーローズ」、
そして新しくスタートした「劇団員」、そして多数のユーザーの皆様の共演作です。
私自身も「劇団員」の一人として、演じ続けていきたいと思います。
今後とも、ツルハシブックスをよろしくお願い申し上げます。
平成26年12月20日 西田卓司
日ごろからたいへんお世話になり、ありがとうございます。
このたび、私は平成27年1月より、
茨城大学社会連携センターのコーディネーターとして、勤務することとなりました。
非常勤職員という形になりますが、茨城県水戸市近郊に転居する予定です。
ツルハシブックスは、法人名称をヒーローズファームから
「NPO法人 ツルハシブックス」として再出発し、
スタッフ体制を一新し、継続して運営していきます。
法人の代表は今まで通り務めながら、
三連休を中心に本屋の運営に、また東京近郊を中心とした
ファンドレイジングや新たな展開に携わりたいと思っております。
ツルハシブックス運営母体であるNPO法人ヒーローズファームは、
2002年から若者×地域というテーマで、小学生の遊び場づくり、
大学生の企業インターンシップ、商店街や
中山間地、離島などでの若者向けの研修プログラムづくりなどを行ってきました。
2011年3月には内野駅前にツルハシブックスをオープンし、
本屋をベースにした地域拠点づくりに取り組み、
現在では中学生・高校生を含めて、たくさんの若者が訪れる場所となり、
屋台やイベントなどを通じた地域との接点づくりを行っています。
私自身はこの8月で40歳となりました。
今年初めから、ドラッカーの経営者のための5つの質問に答えていく日々を送っておりました。
「顧客は誰か?」「顧客にとって価値は何か?」その2つの質問から、
改めて自分のミッションが浮かび上がってくると思っていたからです。
私にとって、顧客とは、人生と将来に悩む中学生・高校生・大学生・20代社会人です。
顧客にとっての価値は、学校や家庭とは異なる、第3の場所、第3の大人と知り合い、
価値観を揺さぶられ、何か行動を起こすことです。
そのためには、自分自身がもっと彼らのことをよく知り、
なぜ彼らにとって地域が重要なのかを説明できることが必要だと思い、
大学というフィールドで再び学ぶことを決意いたしました。
ツルハシブックスは、私のお店ではありません。
店を設計・施工した今井さんをはじめ、現在支えている店員侍と一口オーナー「ヒーローズ」、
そして新しくスタートした「劇団員」、そして多数のユーザーの皆様の共演作です。
私自身も「劇団員」の一人として、演じ続けていきたいと思います。
今後とも、ツルハシブックスをよろしくお願い申し上げます。
平成26年12月20日 西田卓司
2014年12月19日
ワークライフ統合の時代とキャリア教育
「ワークライフバランス」
が叫ばれるようになって久しい。

「キャリアをつくる9つの習慣」(高橋俊介 プレジデント社)
おとといに引き続き、高橋俊介さん。
6年前の著作であるが、
普遍的なテーマを取り扱っているので、
まったく色褪せることがない。
「まず、自分の顧客を明確にする」
「次に、その顧客にどんな価値を提供しているのかを確認するといい」
わお。
僕が8年かかってたどり着いた
キャリア形成の極意を、
6年前に言っちゃってるなあ。
いやあ。
やっぱり本との出会いっていうのは、
目の前に来た時がベストタイミングですね。
「ブランディングとは提供価値の約束である」
自分は何が提供できるか?
を磨いていると、ほかの会社からもオファーがくる。
最終章は「ワークライフ統合の時代」
これからはフリーエージェントな働き方が
主流になってくると言われている。
そのときに
ワークとライフはセパレーション(分離)するものではなく、
インテグレイト(統合)するものと考えることが必要なのだ言う。
ひとつはライフを充実させて、
社会関係資本を持っていたほうが仕事でも活かせるし、
ライフを軽視してワークばかりしていると、
その仕事でしか通用しない狭い能力しか磨かれないので
予期せぬキャリアチェンジが起こった時に耐えられない危険性が大きい。
キャリアチェンジが起こらなかったとしても、
仕事を取り巻く環境はどんどん変化しているから
それに応じて仕事の内容や必要な能力が変わるのは当然だ。
皮肉なことに現代は仕事しかしていないと、
かえって仕事の能力が身につかない時代なのだ。
この上で高橋さんは
長期的視点でキャリアを考える必要があると説く。
今の日本のキャリア教育は
22歳、あるいは18歳、20歳の一時点における
「就職」という瞬間しか見ていないような気がする。
将来どんな仕事が生まれ、
どんな能力が必要となるか、など
今の時点ではわかるはずがない。
だから早くから選択肢を絞り、
狭い世界しか見なければ、
今後必ず必要となる変化に対応する能力が
磨かれないということだ。
人生は想像以上に複雑なメカニズムで
出来上がっている。
22歳の一時点ではなく、
80年の人生にわたってどのようなキャリアをつくっていくのか?
そんな問いをしなければならないと思う。
が叫ばれるようになって久しい。

「キャリアをつくる9つの習慣」(高橋俊介 プレジデント社)
おとといに引き続き、高橋俊介さん。
6年前の著作であるが、
普遍的なテーマを取り扱っているので、
まったく色褪せることがない。
「まず、自分の顧客を明確にする」
「次に、その顧客にどんな価値を提供しているのかを確認するといい」
わお。
僕が8年かかってたどり着いた
キャリア形成の極意を、
6年前に言っちゃってるなあ。
いやあ。
やっぱり本との出会いっていうのは、
目の前に来た時がベストタイミングですね。
「ブランディングとは提供価値の約束である」
自分は何が提供できるか?
を磨いていると、ほかの会社からもオファーがくる。
最終章は「ワークライフ統合の時代」
これからはフリーエージェントな働き方が
主流になってくると言われている。
そのときに
ワークとライフはセパレーション(分離)するものではなく、
インテグレイト(統合)するものと考えることが必要なのだ言う。
ひとつはライフを充実させて、
社会関係資本を持っていたほうが仕事でも活かせるし、
ライフを軽視してワークばかりしていると、
その仕事でしか通用しない狭い能力しか磨かれないので
予期せぬキャリアチェンジが起こった時に耐えられない危険性が大きい。
キャリアチェンジが起こらなかったとしても、
仕事を取り巻く環境はどんどん変化しているから
それに応じて仕事の内容や必要な能力が変わるのは当然だ。
皮肉なことに現代は仕事しかしていないと、
かえって仕事の能力が身につかない時代なのだ。
この上で高橋さんは
長期的視点でキャリアを考える必要があると説く。
今の日本のキャリア教育は
22歳、あるいは18歳、20歳の一時点における
「就職」という瞬間しか見ていないような気がする。
将来どんな仕事が生まれ、
どんな能力が必要となるか、など
今の時点ではわかるはずがない。
だから早くから選択肢を絞り、
狭い世界しか見なければ、
今後必ず必要となる変化に対応する能力が
磨かれないということだ。
人生は想像以上に複雑なメカニズムで
出来上がっている。
22歳の一時点ではなく、
80年の人生にわたってどのようなキャリアをつくっていくのか?
そんな問いをしなければならないと思う。
2014年12月18日
偶然をつかむ就職活動
偶然を計画せよ。
アメリカ・スタンフォード大学・クランボルツ博士が
たどり着いた望ましいキャリアのつくり方。
「計画された偶発性」理論だ。

昨日はjobwebの佐藤孝治さんに
久しぶりにお会いしてきた。
あんまり久しぶりな感じもしないのだけど。
15年前の王子の朝活を思い出し
いい空気感。
でも今度は20代半ばの無謀な自信ではなくて、
根拠のある自信。
http://www.jobweb.jp/
jobwebは、1996年。
就職活動のためのメーリングリストサービスから始まった。
ウインドウズ95の時代。
当然、SNSなどは存在せず、ダイヤルアップで接続ごとに
通話料がとられるネット環境の中で、
大学生のインフラは、メールだけだった。
jobwebは
就活生同士の情報交換をするための
業界別のメーリングリストサービスを開始し、
情報交換をしながら、孤独な就職活動を戦っていた。
あれから18年の時が過ぎ、
「jobwebプロフィール」がサービスイン。
http://www.jobweb.jp/
↑大学生はコチラから登録を。
一言でいえば、
「1年生から就職を真剣に考える大学生のためのSNS」だ。
プロフィール・実績を登録しておくと、
企業からオファーが突然来ることがあると言う。
そして、就活をしている人同士がプロフィールを見て、
同じ関心、興味を持っていると判断すると、
そこでフォローして、情報交換が始まる。
そこには「偶然」があるのではないか。
1か月ほど前のブログに、
東浩紀さんの「弱いつながり」を紹介したが、
http://hero.niiblo.jp/e457179.html
この本で指摘されているように、
ネットは広く浅いつながりをつくると思われているけれど、
本当は強い絆をどんどん強くするメディアとなっている。
フェイスブックやミクシーでは、
既存の友人関係を維持するために、
さまざまな「作業」(いいね!を押す、オフ会を開くなど)
が発生していて、狭い絆をどんどん強化してしまう。
これを打破していくのが、
「就活」といった幅広いけど、
年齢層を絞ったテーマコミュニティなのかもしれない。
言うなれば、
facebook以上、twitter未満の
オープン度を持ったSNSが必要なのではないか。
jobwebプロフィールは、
「就職活動」という時限的であるが
密度の濃いコミュニケーションをすることによって、
「弱いつながり」でありながら、濃い人間関係と人間的成長を
もたらしてくれるSNSであるのではないか。
そして、もうひとつの特徴は、
就活で重要視される「大学外での活動」を記入する欄が
たくさん設けられていることだ。
1年生から地域の活動に参加し、
学んだことを1000字で要約して、記入しておく。
一部の大学が取り組んでいる
「ポートフォリオ」がオープンな情報として開示されていくのだ。
就活に何が効くのか?
そこに答えはない。
採用担当者次第であると言えるだろう。
もしかしたら、
高齢者向けのサービス業を志向している会社であれば、
地域のお祭りを2年間ガチで手伝っていた、
のようなプロフィールがヒットするかもしれない。
そして、何よりも、
そんな切磋琢磨する学生同士が、
地理的条件を超えて、つながることができるのだ。
たとえば新潟に住んでいても、
同じ業界を目指していたり、
かつて同じ団体でボランティアをしていた、
というような「弱いつながり」を活かし、つながることができるからだ。
これは、jobwebのサービス開始当初の
メーリングリストの精神につながっている。
ひとりで戦うのではなく、
学生が横のつながりを生かして、
就活というシステムに挑む。

「就活廃止論」(PHP新書)を書いた
佐藤孝治さんだからこそ、たどり着いたシステムだと思う。
というわけで、
jobwebプロフィールの
新潟営業部長を拝命いたしました。
http://www.jobweb.jp/
大学1年生から真剣に就職を考えているあなたへ
(もちろん2年生、3年生もOKです。)
このサイトを届けます。
アメリカ・スタンフォード大学・クランボルツ博士が
たどり着いた望ましいキャリアのつくり方。
「計画された偶発性」理論だ。

昨日はjobwebの佐藤孝治さんに
久しぶりにお会いしてきた。
あんまり久しぶりな感じもしないのだけど。
15年前の王子の朝活を思い出し
いい空気感。
でも今度は20代半ばの無謀な自信ではなくて、
根拠のある自信。
http://www.jobweb.jp/
jobwebは、1996年。
就職活動のためのメーリングリストサービスから始まった。
ウインドウズ95の時代。
当然、SNSなどは存在せず、ダイヤルアップで接続ごとに
通話料がとられるネット環境の中で、
大学生のインフラは、メールだけだった。
jobwebは
就活生同士の情報交換をするための
業界別のメーリングリストサービスを開始し、
情報交換をしながら、孤独な就職活動を戦っていた。
あれから18年の時が過ぎ、
「jobwebプロフィール」がサービスイン。
http://www.jobweb.jp/
↑大学生はコチラから登録を。
一言でいえば、
「1年生から就職を真剣に考える大学生のためのSNS」だ。
プロフィール・実績を登録しておくと、
企業からオファーが突然来ることがあると言う。
そして、就活をしている人同士がプロフィールを見て、
同じ関心、興味を持っていると判断すると、
そこでフォローして、情報交換が始まる。
そこには「偶然」があるのではないか。
1か月ほど前のブログに、
東浩紀さんの「弱いつながり」を紹介したが、
http://hero.niiblo.jp/e457179.html
この本で指摘されているように、
ネットは広く浅いつながりをつくると思われているけれど、
本当は強い絆をどんどん強くするメディアとなっている。
フェイスブックやミクシーでは、
既存の友人関係を維持するために、
さまざまな「作業」(いいね!を押す、オフ会を開くなど)
が発生していて、狭い絆をどんどん強化してしまう。
これを打破していくのが、
「就活」といった幅広いけど、
年齢層を絞ったテーマコミュニティなのかもしれない。
言うなれば、
facebook以上、twitter未満の
オープン度を持ったSNSが必要なのではないか。
jobwebプロフィールは、
「就職活動」という時限的であるが
密度の濃いコミュニケーションをすることによって、
「弱いつながり」でありながら、濃い人間関係と人間的成長を
もたらしてくれるSNSであるのではないか。
そして、もうひとつの特徴は、
就活で重要視される「大学外での活動」を記入する欄が
たくさん設けられていることだ。
1年生から地域の活動に参加し、
学んだことを1000字で要約して、記入しておく。
一部の大学が取り組んでいる
「ポートフォリオ」がオープンな情報として開示されていくのだ。
就活に何が効くのか?
そこに答えはない。
採用担当者次第であると言えるだろう。
もしかしたら、
高齢者向けのサービス業を志向している会社であれば、
地域のお祭りを2年間ガチで手伝っていた、
のようなプロフィールがヒットするかもしれない。
そして、何よりも、
そんな切磋琢磨する学生同士が、
地理的条件を超えて、つながることができるのだ。
たとえば新潟に住んでいても、
同じ業界を目指していたり、
かつて同じ団体でボランティアをしていた、
というような「弱いつながり」を活かし、つながることができるからだ。
これは、jobwebのサービス開始当初の
メーリングリストの精神につながっている。
ひとりで戦うのではなく、
学生が横のつながりを生かして、
就活というシステムに挑む。

「就活廃止論」(PHP新書)を書いた
佐藤孝治さんだからこそ、たどり着いたシステムだと思う。
というわけで、
jobwebプロフィールの
新潟営業部長を拝命いたしました。
http://www.jobweb.jp/
大学1年生から真剣に就職を考えているあなたへ
(もちろん2年生、3年生もOKです。)
このサイトを届けます。
2014年12月17日
キャリアという“偶然”には「目標」より「習慣」が必要

「Think!43」(東洋経済)
2012年の雑誌を今更買う。
高橋俊介さん。
シンポジウムで1度聞いただけだったけど
やっぱり面白いなあと。
高橋さんは
キャリアは「積み重ねる」ものから「つなぐ」ものへ
変わっているという。
それは世の中が「想定外の変化」をすることが
当たり前になっていて、
キャリア予想図が根底から崩れることが珍しく
なくなっている。
またもうひとつは、
「専門性の深化・細分化」が進んでいることだという。
技術者ばかりではなく、文系の学生にも、
専門性が求められるようになっている。
「想定外の変化」に対応できる
ジェネラリスト(万能型)の人材でありながら、
スペシャリスト(専門型)としての能力が求められるのが
現代の社会だと高橋さんは言う。
だからキャリアは「積み重ねる」のではなく「つなぐ」のだ。
新しい仕事で今までやってきた個性をどう生かすか。
そのように考える必要がある。
一方で高橋さんは、
現在の大学で行われているキャリア教育に警鐘を鳴らす。
現在の若い層に顕著なのは、
将来のキャリアゴールを決めて、
そこにいかに効率的に到達するかに
エネルギーを注ぐ傾向が見られる。
教員を目指しているので、
教員採用試験一本で学んでいます。
メディア業界を目指しているので
テレビ局でアルバイトをしています。
みたいな。
これは、大学で
「自分の内的な分析をして将来やりたいことを考えろ」
「明確なキャリアゴールを描いてそこを目指せ」
ということがなされているからではないか。
しかし、社会に出て仕事をしたことがない
人間に自分がどういう仕事に向いているかを
決めろというのは無理がある。
それに対して、
大学の担当者は、
「それはそうだが、企業で『あなたのキャリアゴールは何?』
と問われて、答えられないと落とされてしまう。
だから無理があるとわかっていても答えられるようにするのが
われわれの仕事だ」と。
キャリア教育は本来のキャリア教育から離れ、
就活視点になってしまっている現状を、高橋さんは面白く比喩する。
これではまるで、
一度もデートしたことがない若者に向かって、
「将来どういう人と結婚したいのかのスペックを全部先に出せ」
「それにマッチするタイプ以外の人とは、付き合っても時間の無駄だからやめろ」
と教育しているようなものだ。
「効率的なキャリア」というのは、
何に対して効率的なのかと言えば、
「明確で具体的な目標」に対してだ。
しかし、想定外の事態が起こる現代においては、
そのゴールにたどりつけなかったり、
そのゴールそのものがなくなってしまう可能性も大きい。
もしそうなった場合、そのゴールを目指して最短距離で
走ってきたキャリアは、無駄のない分、最も脆弱なキャリアになってしまう。
クランボルツ博士の
「計画された偶発性理論」によれば、
「より良い偶然がたくさん起きている人と
そうでない人がいて、その違いは普段の行いにある」
という。
重要なのは、「目標」より「習慣」であり、
大まかな方向性だけ決めておいて、
あとはその場その場で正しいと思うことをやり続ける。
これからのキャリアでは、そのほうが実は戦略的なのである。
と続く。
この後は、実際にどうやっていったらいいのか?
という高橋さんの記事がつづく。
印象に残ったのは、
「背骨になる専門性を生涯かけて掘り続ける」
ということ。
目先のビジネスとはたとえ無関係でも、
これを生涯かけて掘り続けることは、
キャリアにおいて重要な意味を持つ。
なるほどなあ。
自分自身も、抽象度をひとつ上げて言えば、
2002年からは地域資源を活用した教育力
というテーマで活動をしてきたのかもしれないなあ。
まだまだ、掘り下げなきゃね。
2014年12月16日
「情報編集力」を高める

「ビミョーな未来」をどう生きるか 藤原和博 ちくまプリマー新書
8年前に書かれた中高生向けの本。
でも、大人が読んでも面白いなあ。
藤原和博さん
民間人校長として、東京都杉並区の中学校で
よのなか科をはじめとして、
新しい「総合学習」の文化をつくった元リクルート営業マン。
民間校長時代の奮闘ぶり
がたくさんの本になっているので
そちらもお読みください。
「成長社会」から「成熟社会」へと移行している今、
「万人にとっての正解」がなくなり、「ひとりひとりの納得解」
を目指さなければならないと藤原さんは言います。
そして、
大切なのは、「クレジット(信用)・レベル」を上げること。
そのためにはロールプレイングゲームをやるように経験値を
ためていくこと。
成長社会で必要なのは、
「情報処理力」
いわば、ジグソーパズルを早くやり遂げるチカラ。
全体の図柄は決められていて、それをいかに完成させるか?
それに対して成熟社会では、
「情報編集力」が求められる。
いわば、レゴをやるときに要求されるチカラ。
1つ1つの部品はシンプルだけど、
組み合わせることで宇宙にも家にも動物にも人にもなる。
まち全体、世界全体を作り出すチカラだ。
では、「情報編集力」はどのように磨けばいいのか?
藤原さんは以下の5つの技術の大切さを説く。
1 コミュニケーションする技術
2 ロジカルに考える技術
3 シュミレーションする技術
4 役割を演じる技術
5 自分の考えや感情を表現する技術
それぞれの細かい説明は本を読んでいただければと思うけど、
これってやっぱり学校でなかなかできないよなあと。
ツルハシブックスで屋台をやってほうが
1~5のチカラがめちゃめちゃ身に付くと思う。
学校では、最低限の情報処理力を学び、
地域をフィールドにして、情報編集力を高めること。
これが必要なのが
「成熟社会」というものなのだなあと。
やっぱりツルハシブックス屋台、そして野山塾は
時代にマッチしていると思いました。
2014年12月15日
マンガで伝える
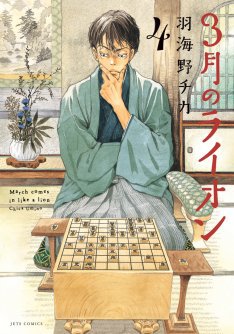
「3月のライオン」(羽海野チカ 白泉社)
坂場さんが貸してくれたので
土日の店番の合間に
一気に読みました。
いやあ。
グッとくる台詞ばかりですね。
感動しました。
将棋を舞台にしたマンガなんですけど、
将棋って人生そのものなんだなあって。
登場人物の身に起こることが
リアル過ぎてドキドキします。
小学校中学校高校のときって
こういうマンガに心を震わせて、
大人になっていくんだろうなあ。
大人になってからも
こういうマンガに出会って、
生きていく力をもらうのだろうなあ。
やっぱりマンガをつないでいくことを
始めていきたいなあ。
ツルハシ号にマンガを詰め込んで、
旅をするって素敵じゃないかなあ。





