2020年06月27日
「主体的である」の反対は、「やらされる」なのか?
昨日、とある会議のあと、とある取材を受けていて感じたことのまとめ。
いちばんの気づきは、
「自律的主体的に学ぶ子」にとって、この町の環境は最高だと思ってた。
資源も課題もたくさんあって、学び放題だと。
でも。
「やりたいことがわからなくて立ち止まっている子」にとっても、
学校内外で、多様で多数の「機会」を提供できるっていうことだ。
「機会」を振り返って、感情から自分を知る。
環境の豊かさっていうのは
・資源の豊かさ:くるみやの農作物などの自然資源
・課題の豊かさ:高齢化・猿による農作物被害などの課題
そしてもうひとつ
・関係性の豊かさ:地域の人たちが重層的に学びにかかわる。
それはそのまま
「機会の豊かさ」であり、「学びの豊かさ」につながっていく。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの阿部さんの論文の「学びの土壌」
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2019/11/seiken_191122_3.pdf
挑戦の連鎖を生む「安心・安全の土壌」←大人の主体性
協働を生む「多様性の土壌」←大人の協働性
問う・問われる「対話の土壌」←大人の探究性
地域や社会に「開かれた土壌」←大人の社会性
これは地域から、というかマクロな目線で書かれたものだけど、
これを高校生目線に落とし込むと。
やりたいことがある、あるいはやりたいことを自ら見つけ、自ら学んでいける高校生にとっては、自らつかんでいく「学びの機会」にあふれていて、反対に「やりたいことがわからない。自分に自信がない。何をしたらいいかわからない」高校生にとっては、周りから与えられる「学びの機会」があるのだと。
これまで僕は思っていたのは
「主体的である」と「やらされる(主体的でない)」の二項対立。
じゃあ、「機会提供」は「やらされる」なのかと言えば、そうでもないと思うし。
「最初は先生に言われたので始めました」っていうのは、高校生のマイプロ発表聞いててもよく出てくる言葉だし。
高校生側の感じ方だったり、
ひとりひとりに話を聞いているか、ひとりひとりに話しかけているか、だし。
もっと大切なのは「ふりかえりをしているか」だったりかもしれないし。
こちらが「機会提供」しているつもりでも、高校生は「やらされている」と思っているかもしれないし。
その前提となる信頼関係があるかないか、にもよると思うし。
つまり。
「主体的である」は「やらされる」と二項対立で考えるものではなく、
高校生目線で言えば、「主体的である」と「機会提供」のあいだにグラデーションが広がっているのだと。
やりたいことがないと悩んでいる子の隣に座って、機会を提供する。
その提供の仕方もあるよね。
ただネタを提供してこちらは見ているだけっていうのは、やらされ感が出る。
一緒にやってみる。考えてみる。悩んでみる。
それが大切なのだろうなと。
地域の自然も資源も課題も地域の大人も、自らも独自の楽器をもって学びという音楽づくりに参加する
高校生にとっての「学びの伴奏者」であること。学びという営みのプレイヤーとして参加すること。
まあ、言うは易し、行うは難しってやつですけどね。
まさにいま、その課題に直面しています。
いちばんの気づきは、
「自律的主体的に学ぶ子」にとって、この町の環境は最高だと思ってた。
資源も課題もたくさんあって、学び放題だと。
でも。
「やりたいことがわからなくて立ち止まっている子」にとっても、
学校内外で、多様で多数の「機会」を提供できるっていうことだ。
「機会」を振り返って、感情から自分を知る。
環境の豊かさっていうのは
・資源の豊かさ:くるみやの農作物などの自然資源
・課題の豊かさ:高齢化・猿による農作物被害などの課題
そしてもうひとつ
・関係性の豊かさ:地域の人たちが重層的に学びにかかわる。
それはそのまま
「機会の豊かさ」であり、「学びの豊かさ」につながっていく。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの阿部さんの論文の「学びの土壌」
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2019/11/seiken_191122_3.pdf
挑戦の連鎖を生む「安心・安全の土壌」←大人の主体性
協働を生む「多様性の土壌」←大人の協働性
問う・問われる「対話の土壌」←大人の探究性
地域や社会に「開かれた土壌」←大人の社会性
これは地域から、というかマクロな目線で書かれたものだけど、
これを高校生目線に落とし込むと。
やりたいことがある、あるいはやりたいことを自ら見つけ、自ら学んでいける高校生にとっては、自らつかんでいく「学びの機会」にあふれていて、反対に「やりたいことがわからない。自分に自信がない。何をしたらいいかわからない」高校生にとっては、周りから与えられる「学びの機会」があるのだと。
これまで僕は思っていたのは
「主体的である」と「やらされる(主体的でない)」の二項対立。
じゃあ、「機会提供」は「やらされる」なのかと言えば、そうでもないと思うし。
「最初は先生に言われたので始めました」っていうのは、高校生のマイプロ発表聞いててもよく出てくる言葉だし。
高校生側の感じ方だったり、
ひとりひとりに話を聞いているか、ひとりひとりに話しかけているか、だし。
もっと大切なのは「ふりかえりをしているか」だったりかもしれないし。
こちらが「機会提供」しているつもりでも、高校生は「やらされている」と思っているかもしれないし。
その前提となる信頼関係があるかないか、にもよると思うし。
つまり。
「主体的である」は「やらされる」と二項対立で考えるものではなく、
高校生目線で言えば、「主体的である」と「機会提供」のあいだにグラデーションが広がっているのだと。
やりたいことがないと悩んでいる子の隣に座って、機会を提供する。
その提供の仕方もあるよね。
ただネタを提供してこちらは見ているだけっていうのは、やらされ感が出る。
一緒にやってみる。考えてみる。悩んでみる。
それが大切なのだろうなと。
地域の自然も資源も課題も地域の大人も、自らも独自の楽器をもって学びという音楽づくりに参加する
高校生にとっての「学びの伴奏者」であること。学びという営みのプレイヤーとして参加すること。
まあ、言うは易し、行うは難しってやつですけどね。
まさにいま、その課題に直面しています。
2020年06月25日
世の中も、自分自身も、前提を疑うこと。
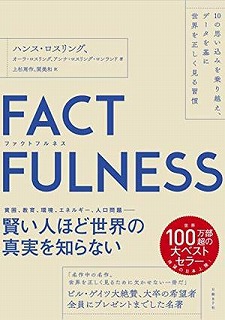
「FACT FULNESS」(ハンス・ロスリング 日経BP)
サブタイトルは、10の思い込みを乗り越え、データを基に、世界を正しく見る習慣。
いつか読もうと思っていたら、高校図書館にあったので借りました。
うれしい。
SDGsとセットで学ぶべき1冊ですね。
目標を立てる前にまず、事実を数字で把握することって大切だなと。
世界は変わっているし、本能は間違えるし、
その間違える本能がビジネスに有効となれば、
メディアはそれを使ってくるし。
具体的に言えば、
この本に出てくる「分断本能」「恐怖本能」「過大視本能」なんかを巧みについてくる。
今回のコロナの報道でも当てはまることが多いなと感じた。
フラットに世の中を見る目を失わなずにアップデートしていくことが大切なのだと思った。
「前提を疑え」っていうのはよく言われるし、心がけてもいるのだけど、
その「前提」は自分自身の中にある「思い込み」にも当てはまるのだと
この本を通じて思った。
特に教育の文脈では、「単純化」して「犯人捜し」をしている場合ではない。
データと、目の前にいる子どもたちと、わたしたちのいまを感じながら、考えながら進んでいくこと。

昨日は阿賀黎明探究パートナーズのミーティングでした。
昼の部10名、夜の部4名が参加。
地域みらい留学フェスタに合わせて、オープンスクール開催と、
そこでやる企画などが話し合われました。
川辺でBBQとか、釣りたての鮎の塩焼きとか、
お祭り感を出していってもいいのではないか、って。
まさにそうですね!
楽しそうな雰囲気、一緒につくろうって雰囲気もめちゃ大切。
湘南のみやじ豚に学んだ
バーベキュー・マーケティングを実現するときが来たようです。
企画詳細決定までもう少しお待ちください。
2020年06月22日
帰ることができる場所をともにつくる
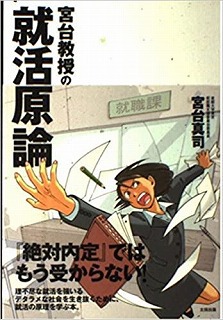
「就活原論」(宮台真司 太田出版)
「就活への違和感」とか言っている人、
社会学的に就活をとらえ直したい人にとって面白い1冊。
ただ、入門編としては
「14歳からの社会学」をお勧めします。
「就活原論」は用語がちょっと難しいです。
参考:「自由」と「承認」と「尊厳」(16.11.18)
http://hero.niiblo.jp/e482857.html
参考:「生きがい」と「仕事」の逆転(16.11.21)
http://hero.niiblo.jp/e482895.html
エッセンスは上記の本に書かれているのだけど、この「就活原論」では、「就活」にテーマを絞って書かれている。
この本のハイライトというか、刺さるところは、やはりこの一節。
仕事での自己実現機会は希少ですが、これを煽ることで、低成長時代の高付加価値化市場に相応しい人材の「動機付けと選別」を行います。そして「仕事での自己実現」競争に敗れた大半の成員には、代わりに「消費での自己実現」を提案するわけです。
うわ。これが欠乏時代から消費社会にシフトした後のシステムなんだなあと。これと「承認」(欲求)が絡んでくるから大変なことになるのではないかと。
~~~以下読書メモ1
前近代 ⇒近代
属性主義 ⇒業績主義
生得的地位で評価⇒能力と努力の結果で評価
大卒者さえ必要なスペシャルな能力を試験で試されることなく採用されるのは、「小⇒中⇒高⇒大」という学校教育のシリーズにおいて「学歴競争に勝ち上がってきた」という事実が保証する、ある種の事務能力だけが評価されたから。
企業も、企業文化も、企業存続のために変わるかもしれない、だから「適応」ではなく「適応力」を求めざるを得ないのです。
社会システム理論では「区別」と「観察」を分けます。「区別」とは差異の線を引くことです。「観察」とは差異の線を引いた上で線の両側のどちらか一方を「指示」することです。適切な「区別」が極めて重要だということです。
70年代には、「成長の限界=環境の限界+資源の限界」が露わになる動きがあり、他方で「福祉の限界=財政破綻+共同体空洞化」が露わになる動きがありました。これに対応して80年代、先進各国で共同体自立化運動が同時多発します。北イタリア発で欧州に拡がったスローフード運動ないしスローライフ運動然り。カナダ発で大英帝国圏に拡がったメディアリテラシーないしメディアエデュケーション運動然り、米国に拡がったアンチ巨大マーケット運動然り。日本は・・・全くありませんでした。
(中略)
これらの運動の共通性は、共同体が、市場に依存しすぎても、国家(行政官僚制)に依存しすぎても危ないとして、市場や国家からの、共同体の相対的な自立を目指すところにありました。ところが、それを理解していなかった日本国民が、90年代に経済がうまく回らなくなって、ふと見回してみると、感情的安全を確保してくれるがゆえに帰還場所にもなれば出撃基地にもなるような家族親族ユニットや地域ユニットはすでに消滅していたというわけです。
要は「仕事での自己実現」などにかまけている暇があったら、市場や国家(行政官僚制)への過剰依存によって風前の灯となった共同体の、自己決定を通じた自立へ向けて、力を振り絞っていなければならないはずなのです。でも日本にはそれがありませんでした。そして気がついてみると、帰還場所も出撃基地も失っている。つまり本拠地を失っている。これを失った状態で「仕事での自己実現」に向けたリスキーなチャレンジができるはずもない。
帰還場所があれば君は言葉通りに振舞えるだろうが、帰還場所がなければ、口で何を言おうが、君には頑張りが利かない。
追い込まれた末の自発性を、内発性と取り違える愚を避けてほしい。
必要なのは、仲間の存在と、あとは泡盛とつまみを買うためのわずかなカネだけ。これといって消費しているモノもサービスもないので、「消費を通じた自己実現」じゃない。強いて言えば、コミュニケーションだけを消費している。それで十分ではないですか。共同体の空洞化ゆえに、こうした「コミュニケーションの消費」が難しくなったから、「仕事での自己実現」や「消費での自己実現」が、埋め合わせとして要求されているのではありませんか。とすれば、それは内発性というより、追い込まれた末の自発性です。
古来、人は、昨日あるように今日あり、今日あるように明日もある、というような生活をしてきました。
「任せて文句垂れる社会」から「引き受けて考える社会」へ
「空気に縛られる社会」から「知識を尊重する社会」へ
「行政に従って褒美をもらう社会」から「善いことをすると儲かる社会」へ
「国家と市場に依存する社会」から「共同体自治で自立する社会」へ
「便利と快適を追求する社会」から「幸福と尊厳を追求する社会」へ
「社会」を「個人」に置き換えてみる。
ホームベースが昔ながらの家族や地域でなければならないということは決してありません。ホームベースは今後、さまざまな形を取るしかないと予想しています。ただ、人間は、埋め込まれ、背負い、貢献し、帰還できる「我々」なくして、雨にも負けず風にも負けず前へは進めません。その「我々」は「長らく近しくあり続ける」近接的な範囲です。
この近接性は、血縁の結びつきで与えられる場合もあれば(血縁共同体)、宗教の結びつきで与えられる場合もあれば(信仰共同体)、日本のように労働集約的な共同作業を通じて物理的にトゥギャザであり続けることで与えられる場合もあります(職場共同体)
絆を与える共同体は、多かれ少なかれ、何かをシェアしているという感覚に支えられます。シェアされるものは、血縁的儀礼だったり、宗教的戒律だったり、職場の時間と空間だったりします。シェアしているという感覚が情緒的アタッチメントを与えます。
何かをシェアしているという感覚なくして「お先にどうぞ」とは言えないのです。
一見したところ典型家族とかけ離れていても、長らく近しくあり続ける近接共同体のうち、とりわけ「成人の感情的回復」機能と「子供の一次的社会化」機能を担うユニットなら、家族と見做すことが大切です。今後は変形家族こそが大切になります。
~~~ここまで読書メモ1
いやあ、すごい。そういうことか、と。
シェアハウスで子育てするとか、山倉さんのやってる拡張家族「Cift」の実験とか。
そして、これからの阿賀町の暮らしにも魅力化にもエッセンスを投入できるような気がします。
高校生を核にして、ふたたび自立的な「共同体」を構築していくこと。
ということで、次に「就職」とか「就活」についていきます。
▼▼▼ここから読書メモ2
「適職幻想」の定義:「自分はこういう人間だから、こういう仕事が向き、別の仕事には向かない」という思い込み。
選択肢が多すぎるという未規定性が人を混乱させて選択不能に陥らせる。
「ニーズに応じて選択肢が提示されるから、学生の適職幻想が煽られる」
最終目的&優先順位を巡る試行錯誤は、「スゴイ奴」と出会って感染(ミメーシス)しては卒業する経験が、最も効果的です。
「仕事の中身」より「周囲の承認」
趣味の時間や家族の時間を楽しむための食い扶持だと割り切っていれば、安全牌狙いの大企業への就職で良いでしょう。でも「仕事での自己実現」を目指している場合は、こうした「全体性からの疎外」は良くありません。全体性が見える中小企業がお勧めです。
その「社会的正しさ」は古くてダサい、これからのこの「社会的正しさ」がカッコイイという訴求を、マーケティング戦略として利用できるはずなのです。
自分にコレが向いてるとかアレがやりたいとか言わず、自分はなんでもやれます、という構えであること。次に、実際自分はなんでもやってきました、という実績を示せるということ。
内定する「他者性」
1 ビビらずに限界ギリギリまで挑戦でき、
2 限界を知るがゆえに高望みせず、
3 様々な社会的手順に通暁し、
4 コミュニケーションにおいて相手が何を求めているかを的確に把握して動ける。
内定が出ない
1 限界を試したことがないのでビビりがち
2 同じ理由でお門違いの自己実現欲求を抱いていたり、
3 どんなボタンを押すとどんな社会過程が動くのか知らなかったり
4 他者の構えに鈍感
「教育意図の失敗」による有効な社会化をいかに設計するか、という「計算不可能性の設計」の可能性が問われています。
共同体の存在が自明だった頃は、グループワーク能力の欠落は珍しいことでした。郊外化に従って共同体が空洞化してくると、グループワーク能力の欠落が珍しくなくなります。
▲▲▲ここまで読書メモ2
「適職幻想」まさにそれだなあと。
そして、この本のあとがきの書き出しが、この本からのメッセージになっている。
デタラメな社会を放置したまま、個人を癒して適応させるだけでいいのか。
就職がどうなろうと揺るぎない帰還場所=出撃基地(ホームベース)を作り、不安ベースより内発性ベースで進むほうが良いです。そうすれば、本文の言葉で言えば「適応」よりも「適応力」ということで、過剰適応せずに相手の要求に応じて「仮の姿」を適当に演じることが可能になります。
「依存」せずに「自立」するための帰還場所=出撃基地が必要です。
そういうホームベースを自らも一緒になってつくること。
これが地域(共同体)にとっても、若者自身にとっても必要なことなのだろうなあと思った。
何かをシェアする(感覚を持つ)共同体をつくっていくこと。
それこそがいまを生きるために必要なことなのだろうと考えさせられる1冊となりました。
2020年06月19日
時計の奴隷

https://www.katariba.or.jp/event/23138/
6月17日(水)の「ゆるいエデュケーション・ラボ」オンライン・ゼミに参加。
若新雄純さんの言う「ゆるい」が好きなので。
「創造的脱力」(若新雄純 光文社新書)は僕にとって思い出の1冊。
参考:「ラボ」というゆるさと強さ(18.11.26)
http://hero.niiblo.jp/e488462.html
ということで、イベントメモ
~~~ここからメモ
・学び合うことをとらえ直していく
・学ぶ場のありかたをゆるめてつくりなおす
・「ゆるい」:答えを出さないといけない⇒答えがすぐに出なくてもいい
⇒成果・結論・まとめ・気づき・学び・いいアイデア・答えを求めない。
⇒つまり、ゴールに向かわないってことか。
「対話」によって「そういう見方もある」という「発見」があるはず。
「正解」から「発見」へ
ソクラテスの時代から「対話」だった。
不知の自覚:無知の知
「哲学」:テーブルに乗せて丸裸にするという営み。
「哲学の本質」:本質洞察に基づく原理の提示。
「公教育」:社会における自由と自由の相互承認の実質化
正当性の原理は「一般福祉」。
150年かわらない学校システム⇒ベルトコンベアシステム⇒同質性の高い集団に最適化したシステム。
学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合。
アダプティ・ラーニング:キュビナ
個別に今学ぶべきことを最適に与える:テクノロジーのほうが優れている⇒テクノロジーに任せることは任せる。
モチベーションを上げることは人にしかできないから人がやる。
主体的対話的学びもテクノロジーでフォローできる。
「学びの個別化」:自分が学びのコントローラーを握っていること。
「学び(のコントローラー)」を子どもの手に返す。
高校生自身に学びの主導権を渡す。
ログが残る⇒リアルタイムのフィードバックができる⇒ゲーミフィケーション。
モチベーションをどうやって上げるのか?
ゲームの攻略:いいゲームは「チュートリアル」がしっかりしている。
麹町中学校のキュビナ導入から
1 ティーチングプロセス⇒ラーニングプロセス
2 助け合える学習空間をつくれるか?
3 先生も探究的に学ぶ
プログラムの提供⇒場を提供して待つ、一緒に学ぶ
自己成長力を信じられないと待てない。
言われたことを言われたとおりにやらせる。
⇒信頼して まかせて 待って 支える
それができないのなら、「時計の奴隷」になっている。
時間割とか、この時間までにここまで、とか。全部そうだな。
幼小中高大をつなげる「ラーニングセンター」として空間を再結成する。
「大きくはみ出せない」「多様であれない」のは、不安だから。
人と違っていてもいいという安心感をどうつくるか。
異年齢の人が出入りしていると同調圧力は軽減される。
「多様性」を目指さない。
結果であり、前提としての多様性。
僕たちはすでに多様。
これまでの学校:スーツケース
長い棒は折らないと入らない。ボールみたいな丸いやつは押し込めないといけない。
⇒ふろしきみたいな学校はつくれないか?
まあ、いろんなふろしきが学校の周りにもたくさんあったらいいなと。
「評価」(≒数値化)の呪縛をアンラーンする。
大切なのは一緒にプロジェクトをやりたいか?っていうこと。
評価が正確・公正であるというウソ。
「こういう人と一緒に学んでいきたい」
”あなたと一緒に学びたい”と思えるか。
「序列」:クラスの中で何番目か
⇒自分(たち)の目指しているものに対して何合目か?
ピアノやギター:やってるからできる
学年とかがない。誰も評価しない。
~~~
とまあこんな感じ。
高校魅力化の文脈に落とし込んでいくと、キーワードは
・「ゆるい」:答えを求めない。ゴールに向かわない。
・モチベーションとゲーミフィケーション、チュートリアル
・ラーニングセンター、異年齢の多様な人の出入りと心理的安全性
・ギターやピアノのようなやってるからできる、っていう感覚。
そんな感じかな。
いちばん響いたキーワードは「評価の呪縛」ですかね。
構造的に見れば。
「目標達成」という大きな仕組みの中で、授業の達成目標があって、
そこに対して限られた時間数で到達させることが重要で、
その到達度をテスト(高校なら中間・期末試験)によって測定するという仕組み。
ところが、キュビナのようなAI教材で学びを個別化したとすれば、
その時点(たとえば、2年生の7月時点)でのテストの結果は、どんな意味があるのだろうか?
そもそも。
目標⇒到達度評価⇒テストみたいな枠組みにどれほどの意味があるのか?
それって、サピエンス全史にも書いてあった、
「時計の奴隷」ってやつだよなあと。
工場は効率化のため、「時計」を発明した。
いや、時計はあったのだけど、イギリス各地域で異なっていた。
「時計」とか「始業時間」とか「時間割」とか
そういう概念そのものがわずか150年しか経っていないのだ。
そうそう。
人は、目標の奴隷である前に、時計の奴隷だ。
島に行くと誰も時間守らないっていうのは、時計から自由だって言うことなのかもしれない。
「学び」と「評価」と「目標」と「時計」
この構造に、何かヒントがあるよ。
「時計」から解放された学びをつくりたいね。
その「学び」はきっと、「遊び」に近づいていく。
2020年06月18日
ビジョンづくり⇒企画書づくり
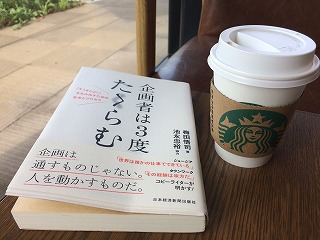
久しぶりのスターバックスひとり朝活。
ソーシャルディスタンスがすごい。
ソファー席もひとつずつ空いてる。
「言葉にできる」は武器になる
の梅田さんの「企画者は3度たくらむ」
企画書づくりの本をこれまでも読んできたけど
そもそも企画ってなんだっけ?という問いに、
スパっと答えてくれていて、いいなあと。
ビジョンづくりは企画書づくりだと思ってやったほうがいいなと。
そこに課題発見があるのか?と。
そういう意味では「探究的学び」と構造上は同じだなあと。
まだ第1章しか読んでいないのですが、
「あたりまえ」の大切なことがたくさん書いてある。
~~~以下メモ
全てのビジネスは、例外なく、誰かの課題を解決することで対価としての報酬を受け取るようにできている。
全ての根源にあるのは「課題に気付く力」であり、そこから解決方法を紐解いていく一連の流れこそが企画なのである。
問題を解消するのではなく、課題を解決することこそが、企画者の仕事なのである。
発生している問題は、あくまでも課題が存在することによってもたらされている結果に過ぎず、解決すべき課題そのものではない。
問題ではなく、課題へ。課題ではなく、現在の課題へ。
企画力=発想力+実現力
課題解決力=企画力=(課題発見力+発想力)×チーム力
提案先が求めているのは、企画書ではない。企画である。
より正確に言えば、企画に辿り着いたプロセスが正確に記されている企画書である。
~~~以上メモ
うーん、すごい。
第1章だけでエッセンスが詰まっている。
いちばん思ったのは、
「ビジョンづくり」って「企画書づくり」だなあと。
ビジョンだけ示しても、現状認識と課題設定からくるプロセスの提示が必要なのだよね。
そのすべてに共感というか少なくとも同意がないと、ビジョンで終わってしまう。
まずその1点。
二つ目は、
そもそも「キャリア教育」ってなんだっけ?
みたいな。
「全てのビジネスは、例外なく、誰かの課題を解決することで対価としての報酬を受け取るようにできている。」この原則から始めないといけないのではないだろうか。
だとしたら「やりたいことは何か?」よりもはるかに大切な問いは、困っている人はいないか?不便を感じていることはないか?それを解決するには?なのではないか。
三つ目の気づきは、アイデンティティの危機という課題に対してのアプローチのこと。僕が思うに、その筆頭は属するコミュニティを多様化・多層化してその掛け算として生きる、で、その階層1つ下に「地域の個性の構成員になること」があり、その場合、地域の個性は「編集」によって生み出すことができるし、周りの人たちと一緒に創ることもできる。
つまり、この本で言うところの「企画書づくり」(課題発見からの一連のプロセス)を通して、チーム(会社・地域)の個性を生み出すこともできるし、その構成員になることもできる。
ビジョンづくりは、企画書づくりへ。
そしてそれは個人のアイデンティティをも創っていく。
いや、仮説ですけどね。
課題とビジョンと、仮説と、打ち手。
そのくりかえし。
2020年06月17日
バンド選びのように、企業を選ぶ

「13の未来地図~フレームなき時代の羅針盤」(角田陽一郎 ぴあ)
withコロナ時代を予言していたかのような2018年3月発刊の1冊。
いまだからこそ読むべき1冊だと思います。
タイトルにもあるように、この本のテーマは、フレーム(枠組み)
本書の中で著者はなんども、フレームそのものがなくなっていくのだ、と説明します。
わかりやすいところで言えば、第1章「モノ⇒情報」の「スマホは携帯電話の進化系ではない」でしょうか。
スマホはそのモノ自体にはたいして価値はなく、購入したあとにオーナーが好きな情報サービスを自由にプラスできることに価値があるわけです。その点で、スマホは携帯電話とはまったく概念が違うもの。
そのうえで著者は、「情報革命」の本質について次のように述べます。
~~~ここから引用
「農業革命」とは、人類が生きていくために「モノを生み出す進化」でした。では「産業革命」とは何だったかというと、機械の力によって「モノを生み出す進化」をより効率的に進める効率革命でした。素晴らしい効率化ですが、モノに価値があるという意味では、あくまで農業革命の延長上にしかなかったのです。
一方、今起こっている情報革命とは、モノから情報という「目に見えないコト」に価値を置く社会への転換です。それは価値の機軸の転換であり「概念革命」なのです。だからこそ、情報革命は産業革命の時よりも、はるかに大きなインパクトを世界にもたらすはずです。
~~~ここまで引用
大きく言うとこういう感じ。
いやあ、メタ認知できる人ってすごいなあと。
ということで、今日紹介するのは2つのシフト
(全部面白かったので、買ったほうがいいです)
4 組織⇒バンド
あれ、聞いたことあるな。
そうです。2019年の1月にやっていた「かえるライブラリー」の
クラウドファンディング「バンドやろうぜ、みたいに本屋やろうぜ」です。
うわー、あれパクリだったのか。って。
角田さんすみません。
これからの仕事における個人と組織の形態はバンドなのではないか?
バンドメンバーは基本的に全員でステージに立ち「替えが効かない」のです。
ここで、素敵な一節を
「ロックバンドが気の合う仲間とともに音楽を奏でるように、あなたがやりたいプロジェクトのための自分のバンドを作るべきだと言っているわけです。」
いいっすね。
かえるライブラリーで目指したのはまさにそれです。
いま、オンライン劇場でやってますけど。
その続きで書いてあるのは、そういう「プロジェクトバンド」経験が就職に効くって言ってます。
ああ、それはあるなって。ボーカルだけじゃなくて、相手によってはギターもベースもドラムもできます。みたいなこともできるし。バンド名を考えたし、作曲も作詞もやったことあります、みたいなのは重宝されそうですよね。でもいちばん自分が好きなのはベースです、みたいな就活。
でも、そもそも、企業ってバンドなのか?みたいなところもあります。特に大企業では難しいかもしれません。「替わりがいること」が最優先されます。やりたい曲もなかなかやらせてもらえないかもしれません。それって、音楽性の違い、なんじゃないか?みたいな気もします。
取材型インターン「ひきだし」のオンラインミーティングで若松さんが「人を通して会社を知る」って言っていたけど、それってまさにバンド選びのようなものだなあと。
ただ、もちろん、大オーケストラでしか奏でられない音楽もあって。そういう音楽を目指したい人は大企業にいったほうがいいかもしれない。
でも、音楽性の合う仲間と、バンド組みたいんだよ、みたいな人は、その音楽性を頼りに、会社を選んだらいいなと。
じゃあ、音楽性って何?みたいなときに、それって、ベクトル感だと思うんだよね。メンバーひとりひとりや全体から感じるベクトル感。そういうのを感じられる「就活」ってできないかなあと。
もうひとう、キーワード
5 イデオロギー⇒ユーモア
これはガツンときました。
「農業革命」によって生まれた2つの概念、国(国家)と「宗教」(あるいは「思想」)その後、産業革命によってまた2つの概念が生まれます。「会社」と「イデオロギー」です。
イデオロギーとは日本語で言えば「〇〇主義」であり、資本主義と社会主義など様々な対立を生み出しました。
そこで、角田さんが言うのは「ユーモア」です。全然違うじゃんって、僕も思いました。
~~~ここから引用
ユーモアは単におもしろいことを言ったりすることではありません。本来の意味は、ある事実や現象を多視点で見る、つまり次元を変えてとらえ直すことによって、同じ事実や事象もまったく違ったものに見えるようになり、そこに”おかしみ“が発生する、という感覚のことです。
新しいフレームを作るには、既存のフレームを超える別次元の視点が必要です。
~~~ここまで引用
おもしろいなあ、と。
「創造的脱力」(若新雄純 光文社新書)を思い出しました。
参考:「ラボ」というゆるさと強さ(18.11.26)
http://hero.niiblo.jp/e488462.html
僕の茨城での失敗は、まさにここにありました。
「創造的破壊」を志向してしまったこと。
「創造的脱力」を発揮できなかったこと。
そのためには「ユーモア」こそが(僕にも組織にも)必要なのです。
「ユーモア」は、遊びではなく、思考の次元を超えていくことだと思います。
フレームを超えるときに必要なもの。
取材型インターンは、そういうものを大切にしていきたいなと思います。
なので、取材型インターンあらため、
ミステリーツアー型企業取材編集ドキュメンタリー「ひきだし」
にするというのはどうでしょうか。(笑)
参加したい大学生はお問い合わせください。
「就活はフレームワークだ」と、大学生さとしが断言していた。
参考:「就活」というフレームワーク(18.12.19)
http://hero.niiblo.jp/e488581.html
その通りだと思う。
そして違和感の正体(正体ってたくさんあるな。笑)も
そこにあるようにも思う。
「学歴社会」っていうのは、フレームワーク至上主義社会のことであると思う。偏差値の高い大学というのは、(学力)入試というフレームワークが得意かどうか?という視点において、一定のクリアをしていることを示している。
本書によれば、その「フレーム」そのものが溶け出しているのだ。「会社」というフレームも、「事業」というフレームも、もしかすると「都市」や「資本主義」というフレームさえ溶け出している。「withコロナ」とは、そういう時代だと思う。
フレームなき時代へのシフトは、すでに起こっていて、新型コロナウイルスがそれにトドメを刺した、と言えるのかもしれない。
フレームを超えて、何を創造できるか?
そんな問いに真っただ中にいる、と僕は思っている。
フレームを超えて「ひきだし」が生み出すものを見てみたい。
2020年06月14日
動的な屋号と空白のある地図
オンライン劇場ツルハシブックス2回目。
ゲストは、ZINE「とまれみよ」を発行した吉野さくらさん。
https://www.tomaremiyo.com/
自らの祖父を題材としたZINE
テーマは散歩と聞き書き。
散歩しながらじいちゃんの話を聞く。
気になったのは、
「とまれみよ」という屋号の由来。
踏切によく書いてある「とまれみよ」
これを見た時にハッとしたのだという。
「とまれみよ」は、自分の在り方としてしっくりくる。
コメタクの活動も、「とまれみよ」だ。
朝ごはんのご飯を炊くこと。
炊きあがるまでの時間(隙)をつくること。
さんぽ×聞き書き
散歩:偶然に出会える、思いつく
聞き書き:アウトプットすること(成果物)が唯一のゴールではない
日常と非日常
言葉と身体性
情報と感情
~~~こんな感じ
いちばん来たのは、屋号の話かな。
「とまれみよ」は、まさにさくらさんの在り方を示している。
いいなあ、在り方を示す屋号。
そういう意味では「ツルハシブックス」もいい線言ってますけどね。
次は「機会として学ぶ」の屋号化だな。
その後、つくばのじゅりさんと今は東京のみのりんと3人で茨城県人会(誰も茨城出身じゃない)
ただの雑談。最近読んだ本とか感じていることとかはひたすら話す、みたいな。
なんか、楽しい時間だった。
お茶とスイーツ、もしくはお酒とおつまみ(手でつまめるもの)をご用意ください。
って書いておけばいいかもしれない。
スイーツ紹介から始まる本の処方箋っぽい雑談、楽しいかも。
そして、第3部は、オンライン・ゼミ
「やりたいことがわからない」の社会学でした。
まず、「やりたことがわからないの社会学」を聞いて、キーワードだし。
そこからひとつずつ拾っていく。
まずは大学生が話した
「ライフヒストリー(チャート)」への違和感。
これ、僕も感じていたので、いいお題だった。
ライフヒストリー(チャート)は、
自分の人生を振り返ってその時のプラスマイナスを折れ線グラフ化するもので、
就活の自己分析に使われたり、チームビルディング研修などでも使われるやつ。
ここ数年、僕もライフヒストリーには違和感があって、
人を理解する方法としては使ってこなかったのだけど、
最近思うのは、「自己開示」のツールとしては使えるのだけど
「自己分析」や「他者理解」のツールとして使うのは危ういなということ。
言ってみれば「人生の編集」だもんね。
その瞬間のその人はあぶりだされない。
次のキーワードは「アイデンティティ」。
まあ、これ言っちゃったら、ゼミが終わっちゃうんだけどね。笑
アイデンティティを分散させる
って誰かが言っていたけど、
コミュニティを多層化、複層化するっていうのはありだなと思う。
そういう意味でも第1部のさくらさんの話に戻るけど、
あり方としての屋号っていうのは面白いなと。
「とまれみよ」は言葉だけど、動的であり。
「言葉」と「身体」、「考える」と「感じる」のあいだにあり、動きを表している。
スピノザ的に言えば、「コナトゥス」(こうありたいと働く力)のことだろう。
動的な(動きを感じられる)屋号だということ。
そういう意味では、僕の次の本屋のイメージは「風の通り道」なのだけど。
そういう感じ。
ライフヒストリー(チャート)の違和感のひとつもそこにあるのかも。
過去の出来事を静的な点として観る。
でも、その時、その点はたしかに動いていたし、
今現時点ではその点(出来事)はマイナスに感じられるのかもしれないけど
5年後にはプラスに感じられるかもしれないので、現実には今も動いているかもしれない。
だからこそ、動的な屋号とか、コンセプトが必要なんだなと。
そしてそれは一人でなくても、二人でも、チームでも、いいのかもしれない。
この船はどこに向かっているんだっけ?っていうのに答えられるような名前を必要としている。
~~~
っていう感じ。
オンライン劇場の未来がまた一つ見えた。

「サピエンス全史 下」(ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社)
を読んでいて出会ったシビれるキーワード
「空白のある地図」
~~~ここから一部引用
15世紀から16世紀にかけて、ヨーロッパ人は空白の多い世界地図を描き始めた。それ以前には地図には空白はなかった。だからそれらは世界の隅々まで熟知しているという印象を与えた。
コロンブスは、1492年に中南米のバハマ諸島に到達した時、東アジア沖にある小島にたどり着いたと信じていた。だからこそ、そこに住む人を「インディアン」と呼んだ。コロンブスは死ぬまでそう誤解していた。
その10年後、1502年~04年にイタリア人航海者アメリゴ・ヴェスプッチらは何度かアメリカ探検をした。これらの探検について書かれた書簡の中で、彼は、コロンブスが到達したのは東インド諸島ではなく、まったく無知の大陸だとした。
1507年、定評のある地図製作者マルティン・ヴァルトゼーミュラーが発行した改訂した世界地図にはそれが独立した大陸であると初めて書かれ、その大陸を発見したのがアメリゴだと誤解したヴァルトぜーミューラーは、その大陸に名前を付けるとき、アメリゴの栄誉をたたえて「アメリカ」と名付けた。
この地図は非常な人気を博し、他の多くの地図製作者に複写されたので、彼が新大陸につけた名前が広まっていった。
世界の陸地面積の四分の一強を占める、七大陸のうちの二つが、ほとんど無名のイタリア人にちなんで名づけられたというのは、粋なめぐりあわせではないか。彼は「私たちにはわからない」と言う勇気があったというだけで、その栄誉を手にしたのだから。
(中略)
これ以降、ヨーロッパでは地理学者だけでなく、他のほぼすべての分野の学者が後から埋めるべき余白を残した地図を描き始めた。自らの理論は完全ではなく、自分たちの知らない重要なことがあると認め始めたのだ。
~~~ここまで一部引用
いいですね、「空白のある地図」。
まさに、僕がオンライン劇場に感じているのはこれのことだなあと。
インターネット黎明期の90年代後半にその世界の人が感じていたものらしき何かを感じている。
オンラインだからこそ、たどり着ける地平があると。
そしてそれは、ひとりではなたどり着けないくらい遠くにありそうで、まだ見えていない。
そこへの旅を進めるために、ひとりひとりの動的な屋号を、ベクトル感を共有したい。
それは「言葉」と「身体」のあいだ。
「考える」と「感じる」のあいだにある何か、なのかもしれない。
ゲストは、ZINE「とまれみよ」を発行した吉野さくらさん。
https://www.tomaremiyo.com/
自らの祖父を題材としたZINE
テーマは散歩と聞き書き。
散歩しながらじいちゃんの話を聞く。
気になったのは、
「とまれみよ」という屋号の由来。
踏切によく書いてある「とまれみよ」
これを見た時にハッとしたのだという。
「とまれみよ」は、自分の在り方としてしっくりくる。
コメタクの活動も、「とまれみよ」だ。
朝ごはんのご飯を炊くこと。
炊きあがるまでの時間(隙)をつくること。
さんぽ×聞き書き
散歩:偶然に出会える、思いつく
聞き書き:アウトプットすること(成果物)が唯一のゴールではない
日常と非日常
言葉と身体性
情報と感情
~~~こんな感じ
いちばん来たのは、屋号の話かな。
「とまれみよ」は、まさにさくらさんの在り方を示している。
いいなあ、在り方を示す屋号。
そういう意味では「ツルハシブックス」もいい線言ってますけどね。
次は「機会として学ぶ」の屋号化だな。
その後、つくばのじゅりさんと今は東京のみのりんと3人で茨城県人会(誰も茨城出身じゃない)
ただの雑談。最近読んだ本とか感じていることとかはひたすら話す、みたいな。
なんか、楽しい時間だった。
お茶とスイーツ、もしくはお酒とおつまみ(手でつまめるもの)をご用意ください。
って書いておけばいいかもしれない。
スイーツ紹介から始まる本の処方箋っぽい雑談、楽しいかも。
そして、第3部は、オンライン・ゼミ
「やりたいことがわからない」の社会学でした。
まず、「やりたことがわからないの社会学」を聞いて、キーワードだし。
そこからひとつずつ拾っていく。
まずは大学生が話した
「ライフヒストリー(チャート)」への違和感。
これ、僕も感じていたので、いいお題だった。
ライフヒストリー(チャート)は、
自分の人生を振り返ってその時のプラスマイナスを折れ線グラフ化するもので、
就活の自己分析に使われたり、チームビルディング研修などでも使われるやつ。
ここ数年、僕もライフヒストリーには違和感があって、
人を理解する方法としては使ってこなかったのだけど、
最近思うのは、「自己開示」のツールとしては使えるのだけど
「自己分析」や「他者理解」のツールとして使うのは危ういなということ。
言ってみれば「人生の編集」だもんね。
その瞬間のその人はあぶりだされない。
次のキーワードは「アイデンティティ」。
まあ、これ言っちゃったら、ゼミが終わっちゃうんだけどね。笑
アイデンティティを分散させる
って誰かが言っていたけど、
コミュニティを多層化、複層化するっていうのはありだなと思う。
そういう意味でも第1部のさくらさんの話に戻るけど、
あり方としての屋号っていうのは面白いなと。
「とまれみよ」は言葉だけど、動的であり。
「言葉」と「身体」、「考える」と「感じる」のあいだにあり、動きを表している。
スピノザ的に言えば、「コナトゥス」(こうありたいと働く力)のことだろう。
動的な(動きを感じられる)屋号だということ。
そういう意味では、僕の次の本屋のイメージは「風の通り道」なのだけど。
そういう感じ。
ライフヒストリー(チャート)の違和感のひとつもそこにあるのかも。
過去の出来事を静的な点として観る。
でも、その時、その点はたしかに動いていたし、
今現時点ではその点(出来事)はマイナスに感じられるのかもしれないけど
5年後にはプラスに感じられるかもしれないので、現実には今も動いているかもしれない。
だからこそ、動的な屋号とか、コンセプトが必要なんだなと。
そしてそれは一人でなくても、二人でも、チームでも、いいのかもしれない。
この船はどこに向かっているんだっけ?っていうのに答えられるような名前を必要としている。
~~~
っていう感じ。
オンライン劇場の未来がまた一つ見えた。

「サピエンス全史 下」(ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社)
を読んでいて出会ったシビれるキーワード
「空白のある地図」
~~~ここから一部引用
15世紀から16世紀にかけて、ヨーロッパ人は空白の多い世界地図を描き始めた。それ以前には地図には空白はなかった。だからそれらは世界の隅々まで熟知しているという印象を与えた。
コロンブスは、1492年に中南米のバハマ諸島に到達した時、東アジア沖にある小島にたどり着いたと信じていた。だからこそ、そこに住む人を「インディアン」と呼んだ。コロンブスは死ぬまでそう誤解していた。
その10年後、1502年~04年にイタリア人航海者アメリゴ・ヴェスプッチらは何度かアメリカ探検をした。これらの探検について書かれた書簡の中で、彼は、コロンブスが到達したのは東インド諸島ではなく、まったく無知の大陸だとした。
1507年、定評のある地図製作者マルティン・ヴァルトゼーミュラーが発行した改訂した世界地図にはそれが独立した大陸であると初めて書かれ、その大陸を発見したのがアメリゴだと誤解したヴァルトぜーミューラーは、その大陸に名前を付けるとき、アメリゴの栄誉をたたえて「アメリカ」と名付けた。
この地図は非常な人気を博し、他の多くの地図製作者に複写されたので、彼が新大陸につけた名前が広まっていった。
世界の陸地面積の四分の一強を占める、七大陸のうちの二つが、ほとんど無名のイタリア人にちなんで名づけられたというのは、粋なめぐりあわせではないか。彼は「私たちにはわからない」と言う勇気があったというだけで、その栄誉を手にしたのだから。
(中略)
これ以降、ヨーロッパでは地理学者だけでなく、他のほぼすべての分野の学者が後から埋めるべき余白を残した地図を描き始めた。自らの理論は完全ではなく、自分たちの知らない重要なことがあると認め始めたのだ。
~~~ここまで一部引用
いいですね、「空白のある地図」。
まさに、僕がオンライン劇場に感じているのはこれのことだなあと。
インターネット黎明期の90年代後半にその世界の人が感じていたものらしき何かを感じている。
オンラインだからこそ、たどり着ける地平があると。
そしてそれは、ひとりではなたどり着けないくらい遠くにありそうで、まだ見えていない。
そこへの旅を進めるために、ひとりひとりの動的な屋号を、ベクトル感を共有したい。
それは「言葉」と「身体」のあいだ。
「考える」と「感じる」のあいだにある何か、なのかもしれない。
2020年06月11日
「大学」という乗り物に乗る。
公営塾対象のAO・推薦入試(総合型選抜)研修(オンライン)でした。
いつも藤岡さんの話は本質的だなあと。
ということで、ひたすらメモします。
~~~ここからメモ
コロナ過で様々な大会、コンクール、部活動、学校外の活動などが停止。
⇒AO・推薦を受験できないのではないか?という不安
⇒(実績)要件は緩和されている
しかし、問うべきは
「そもそも、大学側は、大会、生徒会などで、何を、なぜ、見たいのでしょうか?」
「三ポリ」
・ディプロマ・ポリシー(DP):大学卒業時に身につけておくべき学力の3要素
・カリキュラムポリシー:DPを体系的に身に付けるための授業の配置方針と教育方針
・アドミッション・ポリシー:カリキュラムを受けるために入学者に求めたい学力の3要素
例:北陸大学
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
DPルーブリック(学年別到達目標・評価基準)とカリキュラムツリーがある。
AP:求める学生像が書いてある:例
・自分の考えや意見を述べることができる人
・経験を振り返り、自分の言葉で表現できる人
⇒APから求められる力を導き、ルーブリックを作ってみる
・「表現力」4 聞き手に対して熱意を持って、効果的に語り掛けることができている。⇒1 聞き手を意識せず原稿を読み上げているだけである。
アドミッションポリシー(AP)の例:慶応SFC総合政策学部
総合政策学部は「実践知」を理念とし、「問題発見・解決」に拘る学生を求めます。問題を発見・分析し、解決の処方箋を作り実行するプロセスを主体的に体験し、社会で現実問題の解決に活躍する事を期待します。
従って入学試験の重要な判定基準は、自主的な思考力、発想力、構想力、実行力の有無です。「SFCでこんな事に取り組み学びたい」という問題意識に基づいて、自らの手で未来を拓く力を磨く意欲ある学生を求めます。
~~~ここまで第1部
DP⇒CP⇒APの流れって、高校でも意識してもいいような気がした。
いわゆる「教育目標」って、DPにあたると思うし、
「カリキュラムマネジメント」って言われているのは、CPをベースになっているし、
APも、普通科であればだれでも歓迎なのだろうけど、高校魅力化の観点からは、
そのあたりを明確に、「こういう人に来てほしい」っていうメッセージが必要かなと思う。
あとは、推薦やAOに関わらず、高校でも公営塾でもルーブリック評価みたいな軸を
作っておくことも、自らを確認する上では重要だと思う。
~~~僕の中で切っているだけですが第2部
・大学は「教育研究機関」であり、「研究」の側面を持つ。
・「研究」とは、「まだわかってないことの答えをみつける」こと
⇒講義を受けて知識を得るだけではなく、課題を設定して研究すること「自ら物事をつきつめて明らかにする」ことが求められる
⇒そのために必要な教授や授業、研究会を選び、意見を交換し、アドバイスをもらい、自分の意見を考え続け、まとめていく
・「学生」(≠生徒)とは「自ら物事を突き詰めて明らかにする」自分で学ぶべき課題やテーマを発見・決定、その課題を解決するために自分で動ける人
⇒「学生」として求められるチカラ
基本的な学習能力⇒基礎学力
自ら課題・テーマを発見できる⇒問題発見能力
自ら教授や授業、研究会・ゼミを選ぶ⇒主体性
研究会・ゼミを活性化する力⇒周囲を巻き込む力
推薦・AO入試(総合型選抜)とは
「学生として求められる力」と持つ高校生を多面的観点から選ぶ入学試験。
★大学の裏事情として、大学入試改革が文科省から迫られていることもある。
・大学が見たい高校生のコンピテンシー
⇒大会やコンクールなど、いわゆる「実績」がなくても合格可能
⇒大学は「結果」だけでなく、そこに至るプロセス、プロセスにおけるコンビテンシー(思考特性・行動特性)を見ている。
⇒コンピテンシーとは「思考特性・行動特性」であり、思考と行動、その背後にある価値観や信念を含めて大学側が見たい「人となり」です。
★「個性」とは
「理念・価値観・世界観」⇒「思考」⇒「行動」の集合体
これ、西村モデルの高校生版だなと。

こちらより引用
https://note.com/yuumitakano/n/n767c1516fc65
・なぜ目覚ましい実績・成績があると合格しやすいと言われていたり、出願要件に入っているのか?
実績・成績はあくまで人となりが結果として表出化され出てきたもの。
⇒二次面接者にとって、高校生のわかりやすい人となり:コミュニケーション・ツールになる。
★実績の言語化が必要
・あくまで志望校のアドミッションポリシーに合うかどうかがポイント
・実績があればOKではない
・実績を相手に伝わるように言語化
・活動において実績を出すに至った価値観・思考・行動の言語化が必要。
経験学習サイクル(デイビット・コルブ)
行動(具体的経験)⇒振り返り(自分の経験を言葉でふりかえる)⇒本質の気づき(教訓や持論・自論を引き出す)⇒将来の目標設定(次の経験の際に自分が取る行動の目標を立てる)⇒行動に戻る
★具体から抽象へ。なぜうまくいったか、を再現できる。うまくいかなかったことを再現せず、失敗しない。
「人はおよそ70%を経験から学び、20%は観察学習や他者からのアドバイスによって学び、残りの10%は研修や書籍などから学ぶ。
経験を言語化できる人はパフォーマンスが高くなる傾向がある。
~~~ここまで第2部
今回の研修で、多くの人がヒットしたのは、ここだった。
経験の言語化、ふりかえりの重要性はわかるのだけど、
そもそも高校生が言語化に慣れていない。
藤岡さんは
・言語化するメリットと手法
・言語化できる自信と期待感⇒話したら共感が得られた(うまくいった)みたいな
を高めていく必要を語っていたし、
その前提となるような心理的安全性(安心空間)
をつくっていかないといけないと言った。
多くの高校生は、話すことそのものが不安というか
自分のことを話すのはイタイやつみたいな習慣があるので、
それを打破していかないといけない。
黎明学舎でやっているような、
雑談の時間や、毎日やるお題自己紹介などは
非常に有効なのかもしれない。
「ふりかえり」を反省(特に目標に対する結果の)の場にしないこと
「印象に残ったこと」など、心をまずふりかえること。
~~~ここから第3部メモ(テクニック編)
・プレスタ法
PREP法とSTAR法
PREP法(説明の順番)
1 Point:伝えたい結論・メッセージ
2 Reason:理由・経緯・Pointの詳しい説明
3 Episode:具体的エピソード
4 Point:伝えたい結論・メッセージ
STAR法(言語化の順番)
1 Situation:状況
2 Target&Task:目標・障害・壁・課題
3 Action:解決に向けた意志・行動・姿勢など
4 Result:結果・好転した状況・気づいたこと・得た意見
TAE(Think at the Edge)
https://taetokyo.jimdofree.com/
http://gen.taejapan.org/index.html
志望理由書と7つの観点
1 経緯:過去(高校時代まで)に頑張ったこと、印象に残ったこと、自分に大きい影響を与えた出来事、など
2 気づき・価値観:1を通して、気づいたことや学んだことから得た考え方・大切に思うこと
3 問題意識・テーマ(実現したい野望):2に照らしたとき、問題だと感じること、考えること、このままではいけない、解決したいと思うこと。
4 社会的意義:3の、社会における重要性。それに取り組むべき社会的必然性と、その先にある利益(メリット)
5 解決すべき課題・解決策:3の原因を解決(解消)するためのアイデア、具体的な方法
6 志望大学が最適である理由:5を実現するために、その大学(・学部)に進学したいという根拠。大学の理念・ゼミ・研究内容など。
7 将来の夢・志:その大学での学びをとおして、社会に出て何をしたいか、どのように社会貢献したいか、など。
AO・推薦入試で評価されること⇒総合的な評価が得られれば合格できる。
A 基礎学力
B 人物像(主体性)
C 大学で学ぶときに必要な力(周囲を巻き込む力・リーダーシップ・プレゼン力・コミュニケーション能力など)
D 明確な目的意識(問題発見能力)
AO推薦入試がおすすめな理由
1 一般入試より学力レベルの少し高い大学へ合格できる
2 一般入試(学力)にも相乗効果がある
3 AO入試に挑戦することで就活・社会人など、将来に渡り役に立つスキルが身に付く
~~~ここまで第3部メモ
いや、これって、構造的には大学生の就活とまったく変わらないなあと。
あときっと、中学生が高校を選ぶときにだって、こういう選択プロセスを踏んでいるはずだ。
これを入学志願者を集めるほうの視点で考えることはできるよね。
◎◎な課題を解決したい人にとっては、
ウチの高校のこういう活動、ウチの地域のこういう人、ウチの町のこういう環境は、
とても魅力がありますよ、っていうこと。
それを言語化していくことだ。
「言語化」の課題。
それは高校生ばかりではなく、一生モノの課題。
あとは、全体として思ったことは、
大学に入るのも、企業に入社するのも、
「乗り物に乗る」ようなものだなあと。
もしかすると、ワークショップのような一回性の高い「場」も、
「乗り物に乗る」ようなもの、かもしれませんね。
試験は、乗り物に乗るチケットを手に入れるためのもの。
あるいは、この人たちと一緒に乗ったら楽しいか?成長できるか?
みたいなことを確かめるもの。
そんな感覚で、大学入試にも就職活動にも向かっていけたらいいなと。
いつも藤岡さんの話は本質的だなあと。
ということで、ひたすらメモします。
~~~ここからメモ
コロナ過で様々な大会、コンクール、部活動、学校外の活動などが停止。
⇒AO・推薦を受験できないのではないか?という不安
⇒(実績)要件は緩和されている
しかし、問うべきは
「そもそも、大学側は、大会、生徒会などで、何を、なぜ、見たいのでしょうか?」
「三ポリ」
・ディプロマ・ポリシー(DP):大学卒業時に身につけておくべき学力の3要素
・カリキュラムポリシー:DPを体系的に身に付けるための授業の配置方針と教育方針
・アドミッション・ポリシー:カリキュラムを受けるために入学者に求めたい学力の3要素
例:北陸大学
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
DPルーブリック(学年別到達目標・評価基準)とカリキュラムツリーがある。
AP:求める学生像が書いてある:例
・自分の考えや意見を述べることができる人
・経験を振り返り、自分の言葉で表現できる人
⇒APから求められる力を導き、ルーブリックを作ってみる
・「表現力」4 聞き手に対して熱意を持って、効果的に語り掛けることができている。⇒1 聞き手を意識せず原稿を読み上げているだけである。
アドミッションポリシー(AP)の例:慶応SFC総合政策学部
総合政策学部は「実践知」を理念とし、「問題発見・解決」に拘る学生を求めます。問題を発見・分析し、解決の処方箋を作り実行するプロセスを主体的に体験し、社会で現実問題の解決に活躍する事を期待します。
従って入学試験の重要な判定基準は、自主的な思考力、発想力、構想力、実行力の有無です。「SFCでこんな事に取り組み学びたい」という問題意識に基づいて、自らの手で未来を拓く力を磨く意欲ある学生を求めます。
~~~ここまで第1部
DP⇒CP⇒APの流れって、高校でも意識してもいいような気がした。
いわゆる「教育目標」って、DPにあたると思うし、
「カリキュラムマネジメント」って言われているのは、CPをベースになっているし、
APも、普通科であればだれでも歓迎なのだろうけど、高校魅力化の観点からは、
そのあたりを明確に、「こういう人に来てほしい」っていうメッセージが必要かなと思う。
あとは、推薦やAOに関わらず、高校でも公営塾でもルーブリック評価みたいな軸を
作っておくことも、自らを確認する上では重要だと思う。
~~~僕の中で切っているだけですが第2部
・大学は「教育研究機関」であり、「研究」の側面を持つ。
・「研究」とは、「まだわかってないことの答えをみつける」こと
⇒講義を受けて知識を得るだけではなく、課題を設定して研究すること「自ら物事をつきつめて明らかにする」ことが求められる
⇒そのために必要な教授や授業、研究会を選び、意見を交換し、アドバイスをもらい、自分の意見を考え続け、まとめていく
・「学生」(≠生徒)とは「自ら物事を突き詰めて明らかにする」自分で学ぶべき課題やテーマを発見・決定、その課題を解決するために自分で動ける人
⇒「学生」として求められるチカラ
基本的な学習能力⇒基礎学力
自ら課題・テーマを発見できる⇒問題発見能力
自ら教授や授業、研究会・ゼミを選ぶ⇒主体性
研究会・ゼミを活性化する力⇒周囲を巻き込む力
推薦・AO入試(総合型選抜)とは
「学生として求められる力」と持つ高校生を多面的観点から選ぶ入学試験。
★大学の裏事情として、大学入試改革が文科省から迫られていることもある。
・大学が見たい高校生のコンピテンシー
⇒大会やコンクールなど、いわゆる「実績」がなくても合格可能
⇒大学は「結果」だけでなく、そこに至るプロセス、プロセスにおけるコンビテンシー(思考特性・行動特性)を見ている。
⇒コンピテンシーとは「思考特性・行動特性」であり、思考と行動、その背後にある価値観や信念を含めて大学側が見たい「人となり」です。
★「個性」とは
「理念・価値観・世界観」⇒「思考」⇒「行動」の集合体
これ、西村モデルの高校生版だなと。

こちらより引用
https://note.com/yuumitakano/n/n767c1516fc65
・なぜ目覚ましい実績・成績があると合格しやすいと言われていたり、出願要件に入っているのか?
実績・成績はあくまで人となりが結果として表出化され出てきたもの。
⇒二次面接者にとって、高校生のわかりやすい人となり:コミュニケーション・ツールになる。
★実績の言語化が必要
・あくまで志望校のアドミッションポリシーに合うかどうかがポイント
・実績があればOKではない
・実績を相手に伝わるように言語化
・活動において実績を出すに至った価値観・思考・行動の言語化が必要。
経験学習サイクル(デイビット・コルブ)
行動(具体的経験)⇒振り返り(自分の経験を言葉でふりかえる)⇒本質の気づき(教訓や持論・自論を引き出す)⇒将来の目標設定(次の経験の際に自分が取る行動の目標を立てる)⇒行動に戻る
★具体から抽象へ。なぜうまくいったか、を再現できる。うまくいかなかったことを再現せず、失敗しない。
「人はおよそ70%を経験から学び、20%は観察学習や他者からのアドバイスによって学び、残りの10%は研修や書籍などから学ぶ。
経験を言語化できる人はパフォーマンスが高くなる傾向がある。
~~~ここまで第2部
今回の研修で、多くの人がヒットしたのは、ここだった。
経験の言語化、ふりかえりの重要性はわかるのだけど、
そもそも高校生が言語化に慣れていない。
藤岡さんは
・言語化するメリットと手法
・言語化できる自信と期待感⇒話したら共感が得られた(うまくいった)みたいな
を高めていく必要を語っていたし、
その前提となるような心理的安全性(安心空間)
をつくっていかないといけないと言った。
多くの高校生は、話すことそのものが不安というか
自分のことを話すのはイタイやつみたいな習慣があるので、
それを打破していかないといけない。
黎明学舎でやっているような、
雑談の時間や、毎日やるお題自己紹介などは
非常に有効なのかもしれない。
「ふりかえり」を反省(特に目標に対する結果の)の場にしないこと
「印象に残ったこと」など、心をまずふりかえること。
~~~ここから第3部メモ(テクニック編)
・プレスタ法
PREP法とSTAR法
PREP法(説明の順番)
1 Point:伝えたい結論・メッセージ
2 Reason:理由・経緯・Pointの詳しい説明
3 Episode:具体的エピソード
4 Point:伝えたい結論・メッセージ
STAR法(言語化の順番)
1 Situation:状況
2 Target&Task:目標・障害・壁・課題
3 Action:解決に向けた意志・行動・姿勢など
4 Result:結果・好転した状況・気づいたこと・得た意見
TAE(Think at the Edge)
https://taetokyo.jimdofree.com/
http://gen.taejapan.org/index.html
志望理由書と7つの観点
1 経緯:過去(高校時代まで)に頑張ったこと、印象に残ったこと、自分に大きい影響を与えた出来事、など
2 気づき・価値観:1を通して、気づいたことや学んだことから得た考え方・大切に思うこと
3 問題意識・テーマ(実現したい野望):2に照らしたとき、問題だと感じること、考えること、このままではいけない、解決したいと思うこと。
4 社会的意義:3の、社会における重要性。それに取り組むべき社会的必然性と、その先にある利益(メリット)
5 解決すべき課題・解決策:3の原因を解決(解消)するためのアイデア、具体的な方法
6 志望大学が最適である理由:5を実現するために、その大学(・学部)に進学したいという根拠。大学の理念・ゼミ・研究内容など。
7 将来の夢・志:その大学での学びをとおして、社会に出て何をしたいか、どのように社会貢献したいか、など。
AO・推薦入試で評価されること⇒総合的な評価が得られれば合格できる。
A 基礎学力
B 人物像(主体性)
C 大学で学ぶときに必要な力(周囲を巻き込む力・リーダーシップ・プレゼン力・コミュニケーション能力など)
D 明確な目的意識(問題発見能力)
AO推薦入試がおすすめな理由
1 一般入試より学力レベルの少し高い大学へ合格できる
2 一般入試(学力)にも相乗効果がある
3 AO入試に挑戦することで就活・社会人など、将来に渡り役に立つスキルが身に付く
~~~ここまで第3部メモ
いや、これって、構造的には大学生の就活とまったく変わらないなあと。
あときっと、中学生が高校を選ぶときにだって、こういう選択プロセスを踏んでいるはずだ。
これを入学志願者を集めるほうの視点で考えることはできるよね。
◎◎な課題を解決したい人にとっては、
ウチの高校のこういう活動、ウチの地域のこういう人、ウチの町のこういう環境は、
とても魅力がありますよ、っていうこと。
それを言語化していくことだ。
「言語化」の課題。
それは高校生ばかりではなく、一生モノの課題。
あとは、全体として思ったことは、
大学に入るのも、企業に入社するのも、
「乗り物に乗る」ようなものだなあと。
もしかすると、ワークショップのような一回性の高い「場」も、
「乗り物に乗る」ようなもの、かもしれませんね。
試験は、乗り物に乗るチケットを手に入れるためのもの。
あるいは、この人たちと一緒に乗ったら楽しいか?成長できるか?
みたいなことを確かめるもの。
そんな感覚で、大学入試にも就職活動にも向かっていけたらいいなと。
2020年06月10日
ひきだしミライカイギ
昨日は、取材型インターンひきだしミライカイギ~オンライン「ひきだし」はできるのか~
でした。
参加してくださった企業の方、OBOGの方ありがとうございました。
「ひきだし」の本質的な価値はどこにあったのか?を
改めて考えていく中で、その価値をオンラインである程度再現しつつ、
オンラインでしかたどり着けない場所にいくというミッション。
結論からいけば、始まる前には、完全オンラインは難しくって、
一部オンライン(現地に何名かは行くパターン)
を考えていたけど、実際に話してみたら完全オンラインもいけるような気がしてきました。
さて。
昨日の話を整理してみます。
取材型インターン「ひきだし」の価値(特徴)について
1 学生側と企業側のフラットな関係性
・ミステリーツアー方式(選んでないし、選ばれていない)
・「目的多様性」と「身体性」を持つ「場」づくり
2 会社を「人」から知る
・雑談、雰囲気などから会社のリアルを知る。
3 共同生活がある
・合宿形式で、家事分担などから身体感覚を共有している(オフの時間がある)
4 企業を含め全員が参加者(当事者)である。
・同じ空間(場)を共有すること、問いに向かっていくことで、全員が当事者になっている。
・会社の魅力を引き出して冊子をつくる、とぃうゴールがある。
と、かけば書くほど、やっぱオンラインなんて無理じゃんってなるのだけど、
昨日は後半で、いろいろ大学生や企業の担当者の話を聞いていると、
いや、やっぱいけるかも、と思った。
【オンラインの課題】
・大学のオンライン授業の場合:そもそも主導権が学生側にあるし、自由度が高いので、当事者意識が下がる。
⇒それはかけてるコストが少ないから。
⇒有料化することでそれは変わるのか?
・「人」から会社を知る、という意味では、リアルならでは「雑談」「雰囲気」が大切
⇒オンラインだとフラットなだけにさらに「人」にフォーカスできる可能性がある。(プログラム次第)
・身体性をベクトル性で補えるのか?
⇒ベクトルを合わせることはそもそも難しいし、場のチカラと矛盾するのではないか。
⇒ベクトルを合わせるのではなく、ベクトル性を共有(お互いに知る)ことでできないか。
⇒キーワード・トークなどを会社側も交えてやるとか。
・トランプやサイコロなどの「ギャンブル性」を入れる
⇒これってリアルでもそうだけど、オンラインだからこそのドキドキが必要なのかも。
⇒ブレイクアウトセッションも、ランダムで決めればくじ引きだもんね。
【オンラインひきだしの案】
・各人の「問い」(ベクトル)をていねいにチューニングする。
⇒企業の担当者も含めてやる。
⇒キーワード・カフェとか。
⇒いままでよりさらに「人間性」で勝負する。
⇒会社を「人」で知る
・ブレイクアウトセッションでの対話、雑談の時間を増やす。
⇒経営者や社員とのトークの合間や振り返りで、ブレイクアウトセッションを増やし、1対1の場をランダムにつくる。
⇒雑談の場の設計。ごはんや飲み会、飲みながらの振り返りなども入れる。
・学生の当事者意識を上げるには?
⇒参加費を取る☆コロナ後に使える企業訪問ツアーを付けるなどの特典
⇒参加課題を出す、面接する(ベクトル性の異なる人を集める)
~~~
っと現時点ではこういう感じかな。
来週また話しましょう。
僕としてはあらためて、
「機会として学ぶ」っていう原点に返った気がします。
新型コロナウイルスによって、
現地型のインターンがすべてNGになっていく中で、ひきだしは、どこへ向かっていくのか。
「オンライン化」でなく、オンラインだからこそたどり着ける学びの機会をつくれるのではないか。
キーワードは、向き合わないことだと思った。
人は人と出会うべきなのか(斎藤環)
https://note.com/tamakisaito/n/n23fc9a4fefec
の中で、
~~~
あらゆる関係性は非対称である。これが前提だ。言い換えるなら、非対称性が想定されない場所には関係性も生まれない。そう、「対等な関係性」などは、誰かの政治的夢想の中にしか存在しない。どんな関係性にも上下関係、支配関係が埋め込まれている。
~~~
と出てくる。そしてそれには臨場性が必要だと。
人間関係の非対称性は身体からくるのだと。
まあ、そうなのかもしれないけど。
僕がひきだしに込めた思いは、
「機会としての学び」の中で、人と人はフラットになる、ということだった。
そしてその「場」にこそ、生まれる未来がある、と。
ひきだしがオンラインになったとしても、
機会としての学びに向かって、
企業も、学生も向き合わずに未来を生み出していくような
場をつくっていけるし、
むしろ、オンラインひきだしじゃないと、たどりつけない「場」があるのではないか、と予感した。
まあ、予感しただけなのですが。
それにしても、イベントラストに撮ったこの写真が楽しそうすぎる。
やっぱ身体性大事だわ。
それでは、ご唱和ください。「ヒキダシ、ヒキダシ」

でした。
参加してくださった企業の方、OBOGの方ありがとうございました。
「ひきだし」の本質的な価値はどこにあったのか?を
改めて考えていく中で、その価値をオンラインである程度再現しつつ、
オンラインでしかたどり着けない場所にいくというミッション。
結論からいけば、始まる前には、完全オンラインは難しくって、
一部オンライン(現地に何名かは行くパターン)
を考えていたけど、実際に話してみたら完全オンラインもいけるような気がしてきました。
さて。
昨日の話を整理してみます。
取材型インターン「ひきだし」の価値(特徴)について
1 学生側と企業側のフラットな関係性
・ミステリーツアー方式(選んでないし、選ばれていない)
・「目的多様性」と「身体性」を持つ「場」づくり
2 会社を「人」から知る
・雑談、雰囲気などから会社のリアルを知る。
3 共同生活がある
・合宿形式で、家事分担などから身体感覚を共有している(オフの時間がある)
4 企業を含め全員が参加者(当事者)である。
・同じ空間(場)を共有すること、問いに向かっていくことで、全員が当事者になっている。
・会社の魅力を引き出して冊子をつくる、とぃうゴールがある。
と、かけば書くほど、やっぱオンラインなんて無理じゃんってなるのだけど、
昨日は後半で、いろいろ大学生や企業の担当者の話を聞いていると、
いや、やっぱいけるかも、と思った。
【オンラインの課題】
・大学のオンライン授業の場合:そもそも主導権が学生側にあるし、自由度が高いので、当事者意識が下がる。
⇒それはかけてるコストが少ないから。
⇒有料化することでそれは変わるのか?
・「人」から会社を知る、という意味では、リアルならでは「雑談」「雰囲気」が大切
⇒オンラインだとフラットなだけにさらに「人」にフォーカスできる可能性がある。(プログラム次第)
・身体性をベクトル性で補えるのか?
⇒ベクトルを合わせることはそもそも難しいし、場のチカラと矛盾するのではないか。
⇒ベクトルを合わせるのではなく、ベクトル性を共有(お互いに知る)ことでできないか。
⇒キーワード・トークなどを会社側も交えてやるとか。
・トランプやサイコロなどの「ギャンブル性」を入れる
⇒これってリアルでもそうだけど、オンラインだからこそのドキドキが必要なのかも。
⇒ブレイクアウトセッションも、ランダムで決めればくじ引きだもんね。
【オンラインひきだしの案】
・各人の「問い」(ベクトル)をていねいにチューニングする。
⇒企業の担当者も含めてやる。
⇒キーワード・カフェとか。
⇒いままでよりさらに「人間性」で勝負する。
⇒会社を「人」で知る
・ブレイクアウトセッションでの対話、雑談の時間を増やす。
⇒経営者や社員とのトークの合間や振り返りで、ブレイクアウトセッションを増やし、1対1の場をランダムにつくる。
⇒雑談の場の設計。ごはんや飲み会、飲みながらの振り返りなども入れる。
・学生の当事者意識を上げるには?
⇒参加費を取る☆コロナ後に使える企業訪問ツアーを付けるなどの特典
⇒参加課題を出す、面接する(ベクトル性の異なる人を集める)
~~~
っと現時点ではこういう感じかな。
来週また話しましょう。
僕としてはあらためて、
「機会として学ぶ」っていう原点に返った気がします。
新型コロナウイルスによって、
現地型のインターンがすべてNGになっていく中で、ひきだしは、どこへ向かっていくのか。
「オンライン化」でなく、オンラインだからこそたどり着ける学びの機会をつくれるのではないか。
キーワードは、向き合わないことだと思った。
人は人と出会うべきなのか(斎藤環)
https://note.com/tamakisaito/n/n23fc9a4fefec
の中で、
~~~
あらゆる関係性は非対称である。これが前提だ。言い換えるなら、非対称性が想定されない場所には関係性も生まれない。そう、「対等な関係性」などは、誰かの政治的夢想の中にしか存在しない。どんな関係性にも上下関係、支配関係が埋め込まれている。
~~~
と出てくる。そしてそれには臨場性が必要だと。
人間関係の非対称性は身体からくるのだと。
まあ、そうなのかもしれないけど。
僕がひきだしに込めた思いは、
「機会としての学び」の中で、人と人はフラットになる、ということだった。
そしてその「場」にこそ、生まれる未来がある、と。
ひきだしがオンラインになったとしても、
機会としての学びに向かって、
企業も、学生も向き合わずに未来を生み出していくような
場をつくっていけるし、
むしろ、オンラインひきだしじゃないと、たどりつけない「場」があるのではないか、と予感した。
まあ、予感しただけなのですが。
それにしても、イベントラストに撮ったこの写真が楽しそうすぎる。
やっぱ身体性大事だわ。
それでは、ご唱和ください。「ヒキダシ、ヒキダシ」

2020年06月05日
「機会」を「問い」に換え、Whyに立ち返る。
今週のweekly ochiaiでの一コマ。
テーマは、アフターコロナのリアル「飲食・小売」編
代々木上原のsioの鳥羽周作さんのお店でやってきたことが衝撃で。
sio
http://sio-yoyogiuehara.com/
レシピを無料公開していたツイッター
https://mobile.twitter.com/pirlo05050505
お店ってなんだっけ?
っていう問いに詰まっていたので、メモしておく。
まだ途中までしかみていないのだけど。
~~~以下メモ(他・出演者のもの含む)
コロナ期間中にやったこと。
・ツイッターでのレシピ公開
・1,000円のお弁当
・10,000円/13,500円(2名分)のお弁当
・お店の営業
⇒コロナ前以上の売り上げ
レシピ公開:
お客様しかコロナの答えはもっていない。⇒何を求めているか?
ステイホーム:料理する人が増える。包丁を握ったことがない人もいる
⇒再現性の高いレシピを。
家でつくってみて、弁当にして再現できるか?妻に食べてもらって判定
⇒お客さんの立場(包丁もったことがない)まで想像できているか?
1000円の弁当:
レストランクオリティ(価値体験)を1000円であっても提供するんだという意志。
⇒ぜいたく弁当(10,000円~/2名)へ
※通常のコースは1名10,000円~
トップシェフが弁当で新しい価値を提供する
⇒今まで向き合ってなかった層に価値を提供すること
⇒まず3weekお弁当を研究した。
⇒レストランに求めている価値をどうやって自宅にお弁当として届けるか?
「エンゲージメント」
もともとのお客さんにちゃんと届けているか。
HowやWhatではなく、Whyがあるかどうか?
レシピ公開:売るものさえ変えている。「価値」を届けること
基準は:これをやって幸せな人が増えるのか?増える:やる 減る:やらない
⇒意思決定を最高速に。
レストラン価値を届ける方法として、弁当という方法もある。
10,000円のコースも、1,000円の弁当も、同じ熱量で作りこむ。
誇りをもって1,000円で新しい体験価値を届ける。ナポリタンでもからあげでも。
視点は常に「お客様は何を求めているか?」
⇒予想を上回るものを出し続けることがエンゲージメントにつながる。
エンゲージメント:ファンをつくること。
地域のおばあちゃんが1,000円の弁当やめないでね、と言ってくれる。
~~~ここまでメモ
いやあ、すごい。
「機会」を「問い」に変換し、お客様を見ながら、Whyに立ち返り、
「価値」を提供することに集中する。
お客様が欲しいのは、
「価値」であって、「弁当」や「食事」そのものではない。
だからレシピは公開するし、
(お客さんのレシピを見て料理をつくっても1円の売り上げにもならないが価値は提供できる)
1000円の弁当も本気で作る。
かっこいいなと。
そんな本屋をつくりたいなと。
僕がつくるのではなくて、劇団員と呼ばれる人たちと、ね。
テーマは、アフターコロナのリアル「飲食・小売」編
代々木上原のsioの鳥羽周作さんのお店でやってきたことが衝撃で。
sio
http://sio-yoyogiuehara.com/
レシピを無料公開していたツイッター
https://mobile.twitter.com/pirlo05050505
お店ってなんだっけ?
っていう問いに詰まっていたので、メモしておく。
まだ途中までしかみていないのだけど。
~~~以下メモ(他・出演者のもの含む)
コロナ期間中にやったこと。
・ツイッターでのレシピ公開
・1,000円のお弁当
・10,000円/13,500円(2名分)のお弁当
・お店の営業
⇒コロナ前以上の売り上げ
レシピ公開:
お客様しかコロナの答えはもっていない。⇒何を求めているか?
ステイホーム:料理する人が増える。包丁を握ったことがない人もいる
⇒再現性の高いレシピを。
家でつくってみて、弁当にして再現できるか?妻に食べてもらって判定
⇒お客さんの立場(包丁もったことがない)まで想像できているか?
1000円の弁当:
レストランクオリティ(価値体験)を1000円であっても提供するんだという意志。
⇒ぜいたく弁当(10,000円~/2名)へ
※通常のコースは1名10,000円~
トップシェフが弁当で新しい価値を提供する
⇒今まで向き合ってなかった層に価値を提供すること
⇒まず3weekお弁当を研究した。
⇒レストランに求めている価値をどうやって自宅にお弁当として届けるか?
「エンゲージメント」
もともとのお客さんにちゃんと届けているか。
HowやWhatではなく、Whyがあるかどうか?
レシピ公開:売るものさえ変えている。「価値」を届けること
基準は:これをやって幸せな人が増えるのか?増える:やる 減る:やらない
⇒意思決定を最高速に。
レストラン価値を届ける方法として、弁当という方法もある。
10,000円のコースも、1,000円の弁当も、同じ熱量で作りこむ。
誇りをもって1,000円で新しい体験価値を届ける。ナポリタンでもからあげでも。
視点は常に「お客様は何を求めているか?」
⇒予想を上回るものを出し続けることがエンゲージメントにつながる。
エンゲージメント:ファンをつくること。
地域のおばあちゃんが1,000円の弁当やめないでね、と言ってくれる。
~~~ここまでメモ
いやあ、すごい。
「機会」を「問い」に変換し、お客様を見ながら、Whyに立ち返り、
「価値」を提供することに集中する。
お客様が欲しいのは、
「価値」であって、「弁当」や「食事」そのものではない。
だからレシピは公開するし、
(お客さんのレシピを見て料理をつくっても1円の売り上げにもならないが価値は提供できる)
1000円の弁当も本気で作る。
かっこいいなと。
そんな本屋をつくりたいなと。
僕がつくるのではなくて、劇団員と呼ばれる人たちと、ね。
2020年06月03日
学校はあるものではなく、つくるもの
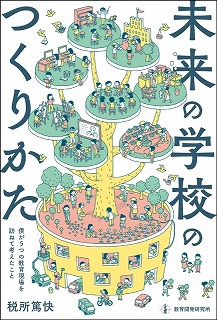
「未来の学校のつくりかた」(税所篤快 教育開発研究所)
久しぶりに、やべえ本に出会ってしまった。
「ありのままがあるところ」以来の衝撃。
https://note.com/tsuruhashi/n/nae7ec266333e?magazine_key=m21a04cf91a68
「学校」「地域」「コーディネーター」「学び」とか
キーワードの方には読んでいただきたい1冊。
さっそく注文しました。オンライン劇場に間に合うといいなあ。
第1章の大阪市住吉区の大空小学校の話だけで2000円の元はとれます。
それくらいの衝撃というか、くやしさというか、実践者っているんやなあって。
映画っていうメディアが苦手なので、まだ見れてないのですが、この本読んだら見たくなりますね。
映画「みんなの学校」上映会+対話の会したいなあ。
6万円だから2000円×30人で見れるのか。
考えてみよう。
この章の締めくくりで書いてあるけど、
大空小学校の初代校長の木村さんの言葉は重い。
学校を「木」だとするならば、地域が「土」、教職員は「風」。
「木が最もよりどころにするのは、常にそこにある土。いい土があって、木がそこにしっかりと根を張っていれば、少々乱暴な風が吹いても倒れません。風は外から、木と土にとって必要なものを運んでこられればいい。」
税所さんは、木村さんを、手段ではなく目的を見ている人だと、
刻みつけるべきは、彼女のしてきたことではなく、彼女の視座だと語る。
ホント、そうだなあと。
キーワードだけ、メモします。
本文をぜひ読んでほしい。
・「教員」ではなく「教職員」
・学校はあるものではなくてつくるもの
・「保護者」になるな、「サポーター」であれ
・学校と地域に上下関係はない
・手段と目的を混同しないこと
いやあ、すごい。
一言一言がグサグサと刺さる。
ひとつ、ヒントになったのは、
ふれあい科の「ようこそ大空の先生たち」という
1~6年の教員(校長も含む)をシャッフルして、
くじ引きで授業をするクラスを選ぶというもの。
子どもたちはとても楽しみにしているのだという。
ああ、こんなふうに、学校現場での
「予測不可能性」ってつくれるんだなあと。
先日のサイコロをつかった探究テーマづくり
https://hen-ai-topic.jimdosite.com/junior/?fbclid=IwAR0P71ofHglQO0cHW5_1oKZYXhTEYPygG-VxjhujgGxhr22TzloayFZFDdI
とか。
そういう小さな部分にいれていくことで予測不可能性は高まるなあと。
ゴールに向かっていかない学びってパラダイムシフトだから、
予測不可能性の面白さを取り入れていく、ってことから始まるのかもしれないなと思いました。
ひとまず、この本、仕入れますので、買ってください。
2020年06月02日
「法人」という神話

「サピエンス全史(上)」(ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社)
読み始めました。
手ごたえがありまくるので少しずつ読みますね。
今日は第2章まで。
~~~ここから読書メモ
地球に君臨する捕食者の大半は、堂々たる生き物だ。何百万年にも及ぶ支配のおかげで、彼らは自信に満ちている。それに比べると、サピエンスはむしろ、政情不安定な弱小国の独裁者のようなものだ。
私たちはつい最近までサバンナの負け組の一員だったため、自分の位置についての恐れと不安でいっぱいで、そのためなおさら残忍で危険な存在となっている。
激しい議論は今なお尽きないが、最も有力な答えは、その議論を可能にしているものにほかならない。すなわち、ホモ・サピエンスが世界を征服できたのは、何よりも、その比類なき言語のおかげではなかろうか。
集団の限界値である「150人」を超えるための虚構の登場、か。
「膨大な数の見知らぬ人どうしも、共通の神話を信じることによって、首尾よく協力できるのだ。」
近代国家にせよ、中世の教会組織にせよ、古代の都市にせよ、太古の部族にせよ、人間の大規模な協力体制は何であれ、人々の集合的想像の中にのみ存在する共通の神話に根差している。
宇宙には神は一人もおらず、人類の共通の想像の中以外には、国民も、お金も、人権も、法律も、正義も存在しない。
言葉を使って想像上の現実を生み出す能力のおかげで、大勢の見知らぬ人どうしが効果的に協力できるようになった。
~~~ここまでメモ
ホモ・サピエンスを世界の覇者にしたのは、言語の力である。
最近は、「言葉」の大切さを実感しつつあったところなので、めちゃタイムリー。
そもそも人は言葉によって、世界を作ってきた。
しかし、ここまで言い切られるとすっきりしますね。
「人が神や宗教を必要としている」のではなく、
協力したり、連帯感をもったりするための「虚構」「神話」「物語」を必要としているのだと。
会社における、ビジョンとかミッションもその話ですね。
この本では老舗自動車メーカー「プジョー」を例に、
「法人」という神話を説明していますがその通りだなあと。
言葉の大切さを語る前に、言葉とは何か?
なぜ、言葉なのか?
を考えさせられる1冊。
これと、最近テーマになっているのが「身体性」なのだけど、
それに関して、友人がシェアしたnoteが面白かったので
人は人と出会うべきなのか(斎藤環)
https://note.com/tamakisaito/n/n23fc9a4fefec
ここでは、「臨場性」と説明されているがまさに
その身体性のようなもの。
「やさしさも暴力である」とか刺激的な内容もあるけれど、ここでは一部を引用する。
オンラインでは完結できない領域とは何だろうか。少なくとも「関係性」が重要な意味を持つあらゆる領域は、今後も臨場性が必須となるだろう。性関係はもとより、治療関係、師弟関係、家族関係、などがそれにあたる。言い換えるなら、関係性よりもコミュニケーションが意味を持つ領域では、臨場性を捨象するほうが効率化されるため、オンラインで完結できるだろう。おわかりの通り、関係性とコミュニケーション(情報の伝達)はまったくの別物であり、私からみれば、ほとんど対義語ですらある。
関係性とコミュニケーションは別物で、関係性には臨場性は必須である、と。
まさに、ここに「オンライン本屋」のカギがあるように思う。
言葉と臨場性(身体性)。
このクロスする領域というか、
無限のグラデーションの中に、「場」を構築できるか、それがカギになる。
ちょっと何言ってるか分からない。byサンドウィッチマン富澤
2020年06月01日
何がどうシフトするのか?
5月29日金曜日に、2つのオンライン勉強会に出たのでキーワードまとめ。
~~~ここからメモ
昼の部:尼崎市職員向け研修(ゲスト:ディスカバ・今村亮さん)
オンラインになると先生中心の「教育」から生徒中心の「学習(学び)」へシフトせざるを得ない。
従来型の学びで得たものを今仕事で使っているとしたら、従来型の学びを提供しようとする。
「問いの立て方、問いの作り方」っていう問いは違うのではないか。
感じたことを、言葉にするプロセスの中で5W1Hを組み合わせれば、問いは生まれる。
サイコロ探究
https://hen-ai-topic.jimdosite.com/junior/?fbclid=IwAR3K7FTaN5iGjStcY-T4h7Xnj9JOAsLTBVMRM_a0yG4wetPkVG5l04Fskfc
浦崎先生の言う「感じること」「問いを立てること」「意味を味わうこと」
の「感じること」と「問いを立てること」のあいだに、深い深い「言語化の谷」が広がっている。
ディスカバ!オンライン(PBLをオンライン上で再現)
https://discova.jp/online/
「教育」つまり、「教える」のは先生だが、「学ぶ」のは子ども。
主語、主導権の大転換が起こっている。
言いたいことが言えない関係。タテの関係は「評価」というプレッシャーが、ヨコの関係は「同調圧力」がかかる。
「評価」も「同調圧力」もない「ナナメの関係」、それがカタリバの関係。ようやく「ナナメの関係」が腑に落ちた。
「学び」の主導権の移行。
それは経済では「企業」から「消費者」へと30年前に起こっていたこと。
ここ30年の経済史をふりかえることで、何か見えるのかもしれない。
戦後最大・明治以来と言われる教育改革としての「探究」
正解を教わるの教育ではなく自ら主導権を持つ探究へ。
本来は「学校」「家庭」「地域」の3つで構成される子育て。しかし、「ステイホーム」は子どもの居場所を「家庭」だけに制限した。
→オンライン上に居場所をつくる必要があった。
→たとえば、「カタリバオンライン」とか「朝の会」とか。
→異年齢の子が接する時間になった。
わかりやすい勉強コンテンツはウェブ上にいくらでもあった。
必要なのは対話・コミュニケーション。
→オンライン朝礼をした
→不登校傾向の子どもたちにとってはむしろプラスに働くこともあった。
夜の部:マイプロ勉強会・事例紹介(ふたば未来学園高校・鈴木先生)
福島県立ふたば未来学園高校の「未来創造探究」
地域社会のneedと自分について理解するWillの真ん中にテーマ設定すること。
「調査のためのアクション」と「解決のためのワーク」を行き来する。
「知らないことを知る」ワーク
自分は何を知っていて、何を知らないのか?
聞いたことがある≠知っている
を再認識する。
情報の種類を知る:「事実」「意見」「仮定」
聞いたことがあって、自分でも使っているのに実はよく知らないこと
→友人に説明できるようになるまでインプットする。
知らなかったワードを自分自身で定義しなおすこと。
「ヒューマン・ライブラリー」
近隣地域で活動する人々を8名を呼び、うち2名に話を聞ける時間にする。
「会いにいけるゲスト」
テーマ「私のマイプロ(探究)」で話してもらう。
そこで新たな問い、観点、ロールモデルを得て、実際に現場に会いに行ってみる。
→問いと調査のためのアクション。
~~~とこんな感じ。
たまたま5月30日に、本屋さんで目に留まったこの本を買いまして、今朝、一気に読みました。

「2020年6月30日にまたここで会おう~瀧本哲史伝説の東大講義」(瀧本哲史 星海者新書)
昨年急逝された瀧本さんの講演録。
久しぶりに奥底に響くような内容。
~~~以下本からメモ
「教養の役割とは、他の見方、考え方があり得ることを示すことである。」アラン・ブルーム
学問や学びというのは、答えを知ることではけっしてなくて、先人たちの思考や研究を通して、「新しい視点」を手に入れることです。
なるほど、学校で学ぶことは守破離の守の、さらに基礎なのか。
バイブルとカリスマの否定。
明治維新というのは近代革命の中でも、際立って言葉を武器にして行われた革命だったと言える。
教養の1歩目は言語。
右手にロジック、左手にレトリックを。
だから「瀧本先生、僕に進むべき道を教えてください」じゃないんです。ぜんぜん違うんです。君が自分の仮説を出して、それを試してみるしかないんですよ。
「弱いつながり」とはSNSでつながることではなくて、バックグラウンドが違う人とつながっているということ。
アイデアがどうかなんてことより、「あなただからその事業をやる意味がある」ということが、やはりきわめて重要です。
~~~ここまでメモ。
なんだかタイムリー。
金曜日の今村さんの一言。
オンラインは先生が主導権を握る「教育」から生徒が主導権を握る「学び」へと変えてしまった。
パラダイムシフト。
夜の部のとある学校の先生が言っていた一言。
「探究活動を積極的にやった子が有名大学にAO・推薦で受かっているので、うちの学校では今年から探究の授業を検討するところと進路指導部が一緒になったんです。」
えっ。
それって・・・
強烈な違和感。
有名大学にAO・推薦で合格するというのは、
探究の「結果」であって、探究の「目的」ではないはずなんです。
そもそも探究とは、
個人の関心と社会の課題の重なるところにできていって、
その題材は、ひとりひとりに委ねられている。
個人の興味関心というエネルギーを注ぎ込まないと成立しないもの。
パラダイムシフト。
が起こっているはずだ。
「探究型学び」へのパラダイム・シフトが。
今村さんが言うように、
教育(≒学び)の主導権が「教師」から「生徒」自身へシフトする。
そして、僕が以前から言っている「機会としての学び」
http://hero.niiblo.jp/e489763.html
学びの構造が「(目的・目標を設定し)手段として学ぶ」から「(展開・振り返り重視で)機会として学ぶ」へシフトする。
教育だけではなく、近代のパラダイム(価値観)のキーワードは「効率化」だった。
「目的・目標を設定して、そこに最高速で行く」に価値があった。
それは工業を中心とした社会だったからだ。
ところが、そのゴールを失い、しかも「効率化」が価値を生まないことがわかってきた今。
当然教育の現場のパラダイムもシフトせざるを得ない。
ところが「AO・推薦入試のために、探究を」って、まったく目的・目標設定のパラダイムではないか。
そのほかにもシフトしているように思うこと。
「個人として学び」から「場としての学び」へのシフト。
方法(メソッド)から場へのシフト。
挑戦から実験へのシフト
達成感から予測不可能性へのシフト。
伝説のカリスマ教師から歌われざる英雄へのシフト。
明確なゴールから方向感・ベクトル感へのシフト。
そんなシフトが始まっている。
いや、コロナ休校期間中にもうシフトは終わっていて、気づいていないだけかもしれない。
瀧本さんに言葉を借りれば、
あなたが今だからこそやらなければいけない探究テーマが、きっとあるはずだ。
~~~ここからメモ
昼の部:尼崎市職員向け研修(ゲスト:ディスカバ・今村亮さん)
オンラインになると先生中心の「教育」から生徒中心の「学習(学び)」へシフトせざるを得ない。
従来型の学びで得たものを今仕事で使っているとしたら、従来型の学びを提供しようとする。
「問いの立て方、問いの作り方」っていう問いは違うのではないか。
感じたことを、言葉にするプロセスの中で5W1Hを組み合わせれば、問いは生まれる。
サイコロ探究
https://hen-ai-topic.jimdosite.com/junior/?fbclid=IwAR3K7FTaN5iGjStcY-T4h7Xnj9JOAsLTBVMRM_a0yG4wetPkVG5l04Fskfc
浦崎先生の言う「感じること」「問いを立てること」「意味を味わうこと」
の「感じること」と「問いを立てること」のあいだに、深い深い「言語化の谷」が広がっている。
ディスカバ!オンライン(PBLをオンライン上で再現)
https://discova.jp/online/
「教育」つまり、「教える」のは先生だが、「学ぶ」のは子ども。
主語、主導権の大転換が起こっている。
言いたいことが言えない関係。タテの関係は「評価」というプレッシャーが、ヨコの関係は「同調圧力」がかかる。
「評価」も「同調圧力」もない「ナナメの関係」、それがカタリバの関係。ようやく「ナナメの関係」が腑に落ちた。
「学び」の主導権の移行。
それは経済では「企業」から「消費者」へと30年前に起こっていたこと。
ここ30年の経済史をふりかえることで、何か見えるのかもしれない。
戦後最大・明治以来と言われる教育改革としての「探究」
正解を教わるの教育ではなく自ら主導権を持つ探究へ。
本来は「学校」「家庭」「地域」の3つで構成される子育て。しかし、「ステイホーム」は子どもの居場所を「家庭」だけに制限した。
→オンライン上に居場所をつくる必要があった。
→たとえば、「カタリバオンライン」とか「朝の会」とか。
→異年齢の子が接する時間になった。
わかりやすい勉強コンテンツはウェブ上にいくらでもあった。
必要なのは対話・コミュニケーション。
→オンライン朝礼をした
→不登校傾向の子どもたちにとってはむしろプラスに働くこともあった。
夜の部:マイプロ勉強会・事例紹介(ふたば未来学園高校・鈴木先生)
福島県立ふたば未来学園高校の「未来創造探究」
地域社会のneedと自分について理解するWillの真ん中にテーマ設定すること。
「調査のためのアクション」と「解決のためのワーク」を行き来する。
「知らないことを知る」ワーク
自分は何を知っていて、何を知らないのか?
聞いたことがある≠知っている
を再認識する。
情報の種類を知る:「事実」「意見」「仮定」
聞いたことがあって、自分でも使っているのに実はよく知らないこと
→友人に説明できるようになるまでインプットする。
知らなかったワードを自分自身で定義しなおすこと。
「ヒューマン・ライブラリー」
近隣地域で活動する人々を8名を呼び、うち2名に話を聞ける時間にする。
「会いにいけるゲスト」
テーマ「私のマイプロ(探究)」で話してもらう。
そこで新たな問い、観点、ロールモデルを得て、実際に現場に会いに行ってみる。
→問いと調査のためのアクション。
~~~とこんな感じ。
たまたま5月30日に、本屋さんで目に留まったこの本を買いまして、今朝、一気に読みました。

「2020年6月30日にまたここで会おう~瀧本哲史伝説の東大講義」(瀧本哲史 星海者新書)
昨年急逝された瀧本さんの講演録。
久しぶりに奥底に響くような内容。
~~~以下本からメモ
「教養の役割とは、他の見方、考え方があり得ることを示すことである。」アラン・ブルーム
学問や学びというのは、答えを知ることではけっしてなくて、先人たちの思考や研究を通して、「新しい視点」を手に入れることです。
なるほど、学校で学ぶことは守破離の守の、さらに基礎なのか。
バイブルとカリスマの否定。
明治維新というのは近代革命の中でも、際立って言葉を武器にして行われた革命だったと言える。
教養の1歩目は言語。
右手にロジック、左手にレトリックを。
だから「瀧本先生、僕に進むべき道を教えてください」じゃないんです。ぜんぜん違うんです。君が自分の仮説を出して、それを試してみるしかないんですよ。
「弱いつながり」とはSNSでつながることではなくて、バックグラウンドが違う人とつながっているということ。
アイデアがどうかなんてことより、「あなただからその事業をやる意味がある」ということが、やはりきわめて重要です。
~~~ここまでメモ。
なんだかタイムリー。
金曜日の今村さんの一言。
オンラインは先生が主導権を握る「教育」から生徒が主導権を握る「学び」へと変えてしまった。
パラダイムシフト。
夜の部のとある学校の先生が言っていた一言。
「探究活動を積極的にやった子が有名大学にAO・推薦で受かっているので、うちの学校では今年から探究の授業を検討するところと進路指導部が一緒になったんです。」
えっ。
それって・・・
強烈な違和感。
有名大学にAO・推薦で合格するというのは、
探究の「結果」であって、探究の「目的」ではないはずなんです。
そもそも探究とは、
個人の関心と社会の課題の重なるところにできていって、
その題材は、ひとりひとりに委ねられている。
個人の興味関心というエネルギーを注ぎ込まないと成立しないもの。
パラダイムシフト。
が起こっているはずだ。
「探究型学び」へのパラダイム・シフトが。
今村さんが言うように、
教育(≒学び)の主導権が「教師」から「生徒」自身へシフトする。
そして、僕が以前から言っている「機会としての学び」
http://hero.niiblo.jp/e489763.html
学びの構造が「(目的・目標を設定し)手段として学ぶ」から「(展開・振り返り重視で)機会として学ぶ」へシフトする。
教育だけではなく、近代のパラダイム(価値観)のキーワードは「効率化」だった。
「目的・目標を設定して、そこに最高速で行く」に価値があった。
それは工業を中心とした社会だったからだ。
ところが、そのゴールを失い、しかも「効率化」が価値を生まないことがわかってきた今。
当然教育の現場のパラダイムもシフトせざるを得ない。
ところが「AO・推薦入試のために、探究を」って、まったく目的・目標設定のパラダイムではないか。
そのほかにもシフトしているように思うこと。
「個人として学び」から「場としての学び」へのシフト。
方法(メソッド)から場へのシフト。
挑戦から実験へのシフト
達成感から予測不可能性へのシフト。
伝説のカリスマ教師から歌われざる英雄へのシフト。
明確なゴールから方向感・ベクトル感へのシフト。
そんなシフトが始まっている。
いや、コロナ休校期間中にもうシフトは終わっていて、気づいていないだけかもしれない。
瀧本さんに言葉を借りれば、
あなたが今だからこそやらなければいけない探究テーマが、きっとあるはずだ。




