2020年04月30日
自由は「問い」の向こうに。
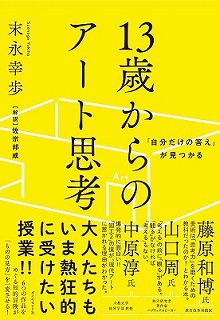
「13歳からのアート思考」(末永幸歩 ダイヤモンド社)
ニュースピックスと晶文社とダイヤモンド社の本ばかり読んでいるなあ。
偏ってる。大丈夫か、おれ。
後半を一気に読み進めて読了。
熱い。
宮澤賢治先生の墓参りしたくなった。
「芸術家たれ」
っていう世界がいままさに目の前にあるなと。
この本は、20世紀のカメラの普及とともに、
アート界に投げ込まれた問いである
「アートにしかできないことは何か?」
を自分なりに問い続けアウトプットしたアーティストが紹介されている。
WEEKLY OCHIAIで宮台真司さんが言っていたけど
https://newspicks.com/news/3689270/
相手の外を設計する、指し示すのがアートだと。
内側に閉じて最適化するのはワクワクしないと。
そういう意味では、「つくる」っていうのは外側にあるなあと。
オンラインの話とかでカギになるのは、
「セミオープン」っていうことなのかもしれないなと。
半分開く。
半分というより、場によって、その比率を変化させていくことなのかもしれない。
そしてもうひとつ。
問わないと、生まれない。
問わないと、つくれない。
オンラインに必要なのは、「問い」なのかもなと。
動画見て、とか話聞いて、の後に問いをひたすら考える時間があってもいいのかも。
問いを生むのは共感ではなく、圧倒的に違和感。
違和感をキャッチするのは脳や視覚ではなく、それ以外の感覚。
オンライン上でその「感覚」を研ぐことができるか。
答えを求めてさまよっていた。
でも、そもそも1つの問いに唯一の答えなど存在しなかったのだとしたら。
答えを探す練習ではなく、問いを生む練習をしなければならない。
個性は、問いによって磨かれ、問いの持つベクトル感が、人と人をつなぐ。
「違和感」を「問い」に言語化し、問いで「ベクトル感」を「共有」することかな。
それを「共感」と呼びたい。文字や同調圧力から強制される共感ではなく。
そんな感覚。
休学してイナカレッジ界隈で1か月の旅をした熊谷くんの冊子のタイトルは「五感再生日記」だった。
まさにそれが必要なのだなあと。
そして、高校生のやる「探究」もまさにそれだもんね。
「13歳からのアート思考」の表現を借りれば、
「表現の花」にとらわれるのではなく、
興味のタネを蒔き、探究の根を伸ばし、アートという植物を
育てていくこと。
その植物は、作品でもあり、高校生自身、つまりアイデンティティでもあるんだと。
そんな場づくり。そして地域の環境づくり。
アートって自由だと思った。
いつのまにか収容されていた(あるいは自ら築いてきた)檻をぶっ壊すのは「問い」というベクトルだった。
自由とは「自ら定義すること」だと思った。
誰かの設定した枠組みで誰かの設定した答えに向かっていくことは不自由だと思った。
宮澤賢治先生は「農民芸術概論綱要」でこう語りかけた。
職業芸術家は一度亡びねばならぬ
誰人もみな芸術家たる感受をなせ
個性の優れる方面に於て各々止むなき表現をなせ
然もめいめいそのときどきの芸術家である
誰もがみな芸術家たれ、と。
茨城で「アーティストとは問いを投げかける人」のことだと知った。
その問いに乗って、という方法だけが
僕たちがこの壁の向こうへ運んでくれるのかもしれない。
だから、芸術家たれ、と。
2020年04月29日
共同体としての学びをつくる

「共感資本社会を生きる」(新井和宏・高橋博之 ダイヤモンド社)
流れがよい。
「共同体の基礎理論」
→「しょぼい生活革命」
→「共感資本社会を生きる」
この順番に読んで未来を展望したい。
鎌倉投信と東北食べる通信の
お二人の次なるステップのその先に見ているもの。
どきどきしながら読み終わりました。
~~~ここから引用とメモ
都会の人って、僕を含めて消費者でしかなくて、みんな割と「点」で生きている。自分の得になることしか考えていない。でも生産者ってすごいんです。亡くなったじいちゃん、ばあちゃんの話はするし、先祖の話、未来の孫子の話、そして動植物、森、海、山、川などの自然の話も。だから「面」なんですよ、あの人たち。あの人たちは面における自分っていうのをすごく意識していて、そこが個でしか生きられない都会の人と全然違うなと思っています。
⇒
「まきどき村」の「営み」っていうのもきっとそうだなと。地域には、「面」っていうのと、時間的な流れである「タテ軸」が流れている、つまり自らが3次元的な空間の中にある1つの点であることが感じられるのではないかな。
生きてる実感から遠ざかるっていうことが起こるのは、もはやいまを犠牲にする正当な理由がないにもかかわらず、なにかの目的や意味のために、いまを使えって言われているからです。
⇒
それって「学び」も同じだよな、と。
「志望校合格」や「将来のなりたい職業に就く」という目的のために今がまんして学べっていうのは、もう無理なんだよね。
そもそもその先の未来みたいなやつは失われちゃっているのだから。
なぜ「予定調和」、つまり「こうすればああなる」っていう考え方の中にいると安心で、自分のいまを犠牲にすることをいとわなくなるのか。この問いに、都会的な問題の本質があると思うんです。いわば人工物というのは人間がコントロールするために設計しているもの。
人間がコントロールできないものがあれば効率も落ちてよくないというので、徹底的に自然を排除してつくられているのが都会。その中で生きていれば、すごく予定調和な思考、「こうすればああなる」という考え方に染まってしまうのは当然です。
対して地方はどうか。都市に比べて、はるかに自然の残る田舎に帰ると、コントロールできないことが一気に増える。自然っていうのはやっぱり思い通りにはならないし、都会より地方のほうが予期せぬことは起きやすい。
「こうすればああなる」っていうことじゃなくて、生き物として、言葉の世界にない感覚的なもので、突如異質なものに遭遇したときにどう対応するかっていうときに必要になるのは、もはや意識的な思考じゃないと思うんですよ。
不確実なものはないほうがいいって、どんどん自然なものから自然でないものに切り替えていくことによって、効率を上げて、不確実性というものを排除する。
⇒
「複雑系」を生きていかなきゃいけない時代に、都市の図書館やスタバで大学受験勉強だけをする3年間という投資にどれほど価値があるのか?
「身体性」とか「感性」を磨かないとヤバいんじゃないの、って思う。
「間」っていう概念も大事ですよね。どっちかを取るってことではない。西洋って「間」がないので、あなたか私か、自然か人間か、みたいなどっちかを取るってなりがちです。だけど日本の面白いところは、間があるんですね。どっちかを取るということをしない。
間にフォーカスすれば、基本的に対立構造っていうのは生まれないんですよ。なぜかと言ったら、そこの間に存在しているのはあなたでもなく自分でもないものだから。でも、自分とあなたってなった瞬間に、壁をつくり対立が生まれるんですよ。
これからは共同体感覚の時代なので、お互いが交わる場所があって、お互いが当事者になれる場所が必要になる。その場所が、僕は「間」だと思っていて、あなたもこの間の当事者だし、自分も当事者であるっていう、お互いが当事者になったときには争いなんて起こらないんです。
この間にフォーカスするっていうことがすごく重要で、これが関係性の再構築なのかなと思っています。
「間」にできあがるものってお互いでつくるものだから、自分自身じゃない部分がある。そうしたときに自分という器の中ではできないことが、この「間」ではできるし、存在しうるわけですよ。
「間」を育むための必要な時間とか環境とかって、僕は地域にすごく存在していると見ている。
働きかけ、働きかけられる、動き、動かされるっていう、この相互作用の複雑系がまるっと「生きる」っていうことだとしたら、地域にはこれを感じやすい環境がありますよね。
人と人との関係性だけじゃなくて、人と自然との関係性もそこには存在していて、その「間」には対話があるじゃないですか。
~~~ここまで引用とメモ
キーワードでまくり。
そして、アイデンティティ問題への視点もありましたね。
「点」で生きてるのがつらいのではないか、ってね。
田舎に行くと、「面」で生きている人がたくさんいて、
もっと大きな時間軸での3次元空間の構成員としてそこに存在できることが
ある意味、幸せだったりする。
一方で、田舎にある関係性っていうのは
いわゆる「しがらみ」的なものでもあって、
そのあたりをどのようにデザインしていくのか?ってことなのだと思う。
昨日、いい問いをもらって、
「これからコーディネーターの役割は変わっていくのではないか?」
っていうのについて考えていたら、まさにここ1週間で読んできた3冊の本に
方向性へのヒントがあるなあと。
うまく説明するのが難しいのだけど、
「学びの共同体」と「共同体としての学び」をつくる。
っていうことなのかもしれない。
ここでいう「共同体」は、
内山さんの「共同体の基礎理論」で書いてあったような、
ヨーロッパ由来の人と人の共同体の意味ではなく、明治以前の日本的な共同体を意味する。
人と自然、人と宗教、都市と農村。それぞれが学びあうこと。感じあうこと。
3次元の、あるいは「シン・ニホン」的に言えば、複素数平面的な学びをつくっていくためには「身体性」は必須で。
さらに、コーディネーターがコーディネートするものは学校とまち、や、生徒と地域の人、とかではなくて、
自然や歴史や宗教や風土や、そういうあらゆる資源や課題なのだろうと思った。
そうやって、「学びの共同体」をつくること。
それにともなって「共同体としての学び」をつくっていくこと。
上に引用した「共感資本社会を生きる」にも書いてあったけど、
(目的に対する)「手段としての学び」は、ひたすら効率化されてしまう。
だから、探究学習に代表されるように「機会としての学び」にシフトしていくこと。
それこそが予測不可能性を高め、学びを面白くするって思う。
その「機会としての学び」を
地域全体から見れば、自然、歴史、宗教を含めた
「共同体としての学び」になっていくのではないか。
まだ、仮説の段階なのだけど、うっすら見えてきた気がします。
いい問いをありがとうございました。
2020年04月28日
「風の通り道」のような本屋
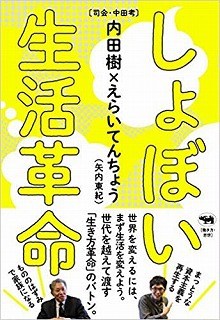
「しょぼい生活革命」(内田樹×えらいてんちょう 晶文社)
いやあ。
いい本読んだなあって。
僕にとって文句なくいい本っていうのは、
「やっぱ俺が本屋やらなきゃいけないんじゃないか?」
って思い出させてくれる1冊。
そんな1冊になりました。
「共同体の基礎理論」の直後に読んだという奇跡も
本文中に見受けられて読書運の強さを感じました。
さて。
大学生のみなさんにお届けしたい部分は
「第4章 教育、福祉制度を考える」より。
~~~ここから引用
学校教育は戦後のある時点から「工業製品を作る」という産業形態に準じて、制度設計されるようになりました。それは適切に管理された工程をたどって、仕様書どおりの「製品」ができていくプロセスを教育についても理想とする考え方です。
その前の時代、学校教育は農業のメタファーで語られていました。種子を蒔き、肥料や水をやって、あとは太陽と土壌に任せておくと収穫期になると「何か」が採れる。
「工場での工業製品を製造する」というのは第二次産業が支配的な業態だった前期産業社会に固有のメタファーです。「教育の質管理」とか「PDCAサイクルを回す」とか「シラバスによる工程管理」とか、そういうのは全部「工場でものを作る」ための作業なんです。
「私はこれこれこういう人間ですと自己規定して、それを言葉にしてずっと維持してゆく」というアイデンティティ圧力というのは、工業製品に固有のものなんです。缶詰や乾電池だったら、規格化しないと使えない。だから、つよい同質化圧が学校教育で働く。
一度仕様書に組成や使途を定められた製品は、途中で仕様を変更することが許されない。いまの日本社会では、その「仕様変更の禁止」のことを「アイデンティティー」と呼んでいるんです。
~~~ここまで引用
うわー。
学校教育(のキャリア教育的文脈)で語られるアイデンティティってそういうことだわ。
それだよね、違和感の正体。
工業中心の社会・時代は終わったんです。
だいぶ前に。
~~~ここからさらに引用
もし、現代において支配的な産業構造のメタファーを適用するとしたら、「離散的なネットワークの中で、さまざまなアクターが自由に出会うことでそのつど一回的に価値物が創造される」というイメージになるはずなんです。
だから、教育も遠からず、工業製品だけではなく、機能とか情報とか生命力とか、そういう「かたちのないもの」を原イメージとして組織化されるようになります。
だとしたら、これからの教育は学校で斉一的に教育されるのではなく、むしろ自己教育というものになると思います。自分のための教育環境を自分で手作りして、自己教育する。そういうかたちのものになると思います。必ず、なる。
その場合の自己教育の目標は一言で言えば、複雑化ということです、教育環境を選ぶ場合に、子どもたちは「自分がそのプロセスを経由することで、どれだけ複雑になれるか」、それを問う。
いまのこの社会の犯している最大の誤謬は「単純であるのはいいことだ」という信憑です。どんな場合でも、同じように考え、同じようなことを言い、同じようにふるまう首尾一貫したアイデンティティを持った人間でなければならないという強い自己同一化圧がかけられている。
~~~ここまでさらに引用
なっていきます。
そういうのを創りたいと願ってもいます。
あと、
「共同体の基礎理論」(内山節 農文協)で読んだばかりの宗教の話からも一節だけ。
「明治政府は宗教の近代化、宗教の国家統制をめざしたわけですけれど、そのときまず標的にされたのが、神仏習合という数理、もう一つは遊行の宗教者という生き方でした。神仏習合のという数理と、宗教者は旅をするという生活形態は実際には不即不離のもので、それこそが日本人にとって一番ベーシックな宗教生活だった。それを支えていた人たちが最初に弾圧されて、神道と仏教という体系化されたものだけが残り、次に仏教が弾圧されて、さらに神道のなかで国家管理になじまないものが廃された。」
これもすごいね。
「効率化」のために、「暮らし」と「宗教」をまず分離したのだと。
そして、「工業化」のために均一化された製品を生み出すための「教育」
が始まったのだ。
でも、世の中はすでに変わっていて。
ただ、「効率化」によって金銭的価値を生み出せる会社というか仕組みは
まだ残っているから、そのハザマで学ぶ大学生にとっては非常にもやもやしたものがあるのだろうと。
「にいがたイナカレッジ」が取り組んでいる地域の集落に入り込んで1か月生活する、
みたいなのは、そういう「身体性」を伴う何かを必要としているからなのではないか?
言語化できない何かをつかみたいからなのではないか?
そうやって自らの「アイデンティティ」そのものを複雑化していく実践なのではないか?
と思った。
あとがきでこの本の対談の司会を務めた中田考さんが引用している内田さんのブログの文面にシビれた。
師弟関係における「外部への回路」は、「師の師への欲望」を「パスする」ことによって担保される。
真の師弟関係には必ず外部へ吹き抜ける「風の通り道」が確保されている。あらゆる欲望はその「通り道」を吹き抜けて、外へ、未知なるものへ、終わりなく、滔々と流れていく。
師弟関係とはなによりこの「風の通り道」を穿つことである。この「欲望の流れ」を方向付けるのが師の仕事である。
師はまず先に「贈り物」をする。
その贈り物とは「師の師への欲望」である。
うわー。
それです。
僕が実現したい本屋はそういう本屋です。
「風の通り道」的な本屋を、ぼくは創ります。
2020年04月26日
豊臣秀吉はなぜ検地、刀狩りを行ったのか?

「共同体の基礎理論」(内山節 農文協)
WEEKLY OCHIAIの2019.12.19
https://newspicks.com/movie-series/25?movieId=428
「未来のコモンズとコミュニティ」を考える。
で紹介されていたので買いました。
100ページ、第3章まで来ましたが、これは深い!
ドキドキしながら読んでます。
イナカレッジとかにも通じるなあと。
さてさて。
いつもながらメモ。
~~~ここからメモ
わずか半世紀の間に、共同体は克服すべき前近代から未来への可能性へとその位置を変えたのである。
「近代化」とは何であったのだろうか。第一に、国民国家の形成があった。国民国家とはそれまでの地域の連合体としての国家を否定し、人々を国民という個人に変え、この個人を国家システムのもとに統合管理する国家システムのことである。
第二に市民社会の形成がある。個人を基礎とする社会の創造である。第三に資本主義的な市場経済の形成があった。
さらにこれらの動きを促進するためには、科学的であることや合理的であることに依存する精神を確立する必要があったし、歴史は進歩し続けているのだという「共同幻想」を定着させる必要もあった。
外来語の「共同体」は人間の共同体を指していて、自然と人間の共同体を意味する日本の地域社会観とは違う概念である。
たとえば村とか集落とかいうとき、日本の村や集落は伝統的には自然と人間の里を意味している。自然もまた社会の構成者なのである。
「私」をもっているとは、仏教的にいえば「煩悩」をもっていることと同義である。ヨーロッパの思想では人間は自己をもち、欲望を抱くからこそ文明が発展するというように、「私」があることを肯定的にとらえる。
テンニュスによる「ゲマインシャフトとゲゼルシャフト」・
ゲマインシャフト:地縁、血縁などで結ばれた有機体
ゲゼルシャフト:利害関係や目的意識などでつくられた人間の社会
ゲマインシャフトからゲゼルシャフトへの移行が
歴史の発展としてとらえられていた。
それは近代形成過程の理論だといってもよい。
マッキーヴァーのコミュニティとアソシエーション
コミュニティ:共同的な生活が営まれている場であり、社会のあり方や文化などが共有されている結合体
アソシエーション:コミュニティの内部にある、ある目的を達成するための組織
「コミュニティは、社会生活の、つまり社会的存在の共同生活の焦点であるが、アソシエーションは、ある共同の関心または諸関心の追求のために明確に設立された社会生活の組織体である。アソシエーションは部分的であり、コミュニティは統合的である。」(「コミュニティ」(中久郎・松本通晴監訳 ミネルヴァ書房)
真理は1つではなく、多層的である。なぜなら真理はある磁場のなかに成立しているのだから、磁場が異なれば真理も異なる。
真理はそれを切り取った断面のなかにあるのであり、切り取られた断面が異なれば真理も異なってくる。
それは共同体を生きた人々が自然とともに存在していたからであろう。
共同体とは共有された世界をもっている結合であり、存在のあり方だと思っている。共有されたものをもっているから理由を問うことなく守ろうとする。あるいは持続させようとする。こういう理由があるから持続させるのではなく、当然のように持続の意志が働くのである。
この共同体のなかにいると、自分の存在に納得できる。諒解できるからである。自分の存在と共同体が一体になっているから、共同体への諒解と自己の存在への諒解が同じこととして感じられる。共同体とはそういうものである。
とすれば共同体の中にいくつもの共同体があっても何の問題もない。自己の存在を小さな共同体の中で諒解し、同時に大きな共同体の中で諒解する。さらにはそれらが組み合わさって、自己の存在が諒解されるのである。しかもその共同体はひとつだけでは成り立たない。いくつもの共同体があるからこそ、ひとつひとつも共同体の性格をもち、全体としても共同体でありうるからである。
故に共同体は多層的共同体なのである。おそらく「アソシエーション」を積み上げても共同体は生まれないだろう。理由のある組織を積み上げても、理由がある社会がつくられるだけだ。それはそれでよいかもしれないが、私はそれを共同体とは呼ばない。
トクヴィルにとって健全な社会とはさまざまな精神の習慣が併存している社会だった。逆に述べれば、ひとつの精神の習慣が覆っているような社会を、トクヴィルは危険な社会とみなした。ひとつの理念が支配するような社会をよい社会だと考えてはいなかったのである。なぜならひとつの理念が支配すれば、その理念だけが正義になり、それとは異なる精神の習慣を圧迫する抑圧的な社会が生まれてしまうからである。
いくら制度が民主的でも、圧倒的な多数派が同一の精神の習慣をもっていれば、それが当たり前のように正義になり、それと異なる意見をもっている人は葬り去られる。ここに制度は民主的でも、実態は強権的、抑圧的、全体主義的な社会が生まれる。それがトクヴィルのみたアメリカだった。
では多様な精神の習慣はどうしたら生まれるのか。小さな集団が多様に存在することだと彼は考える。人間の精神の習慣は自分でつくっているように見えるかもしれないがじつはそうではない。そのグループに加わっていることによって、そのグループの精神を身につけるのだと。
いくつかの精神の習慣を1人の人間が身につけるようになると、どれかひとつの精神の習慣に絶対的な真理があるわけではないことに、人々は気づくようになる。
日本の共同体にはどのような前提基盤があったのだろうか。そのひとつは自然である。
日本の共同体の特徴のひとつはその自治力の高さである。
豊臣秀吉が検地、刀狩りを実行しようとしたのも、武装した自治する共同体が統一国家を形成するうえで壁になっていたからである。
江戸期の社会は、武士が城下町に住み、農村から都市に移動したことが大きな意味を持っている。幕府は武士を農村から引き上げさせることによって、武士と農民のつながりを断ち、検地、刀狩りを実現することによって、自治する共同体を支配する共同体に変えようとしたのである。
中世後期以降のヨーロッパの農村のように、死後のことはキリスト教の神が受けもち、共同体も人間だけの共同体としてつくられていれば、共同体の管理、維持の仕方はわかりやすいかたちが可能になる。ところが自然や死後の世界を含めて共同体をもとうとすれば、人間同士の取り決めだけでは十分ではなく、自治の方法のなかに祭りや年中行事が大きな意味を持つものとして入ってくる。
村人が守ろうとしたのはこういう世界である。だから、それが守れれば、ときには案外簡単に妥協する。武士が強い命令をだせば、とりあえずしたがってみせたりする。壊してはいけない世界を守るためには、そこに手を突っ込まれない限り、平気で「服従」もするのである。それは村人たちの自身である。どうせ武士は農村の直接支配はできないのである。
~~~ここまでメモ
このあと、印象的な一言が出てくる。
「村人は自分の一生だけがすべてだとは思っていない」
うーむ。
「共同体」、奥が深いぞ。
2020年04月20日
「異人」の時代へ
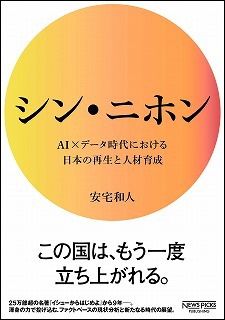
「シン・ニホン」(安宅和人 ニュースピックスパブリッシング)
最初、難しくて流し読みしてしまいましたが、
「WEEKLY OCHIAI」の安宅さんの回を見て、
読み直したら、グイグイ来ます。
今日は第3章からの写経。
~~~ここからメモ
マネジメントとは
0 あるべき姿を見極め、設定する
1 いい仕事をする(顧客を生み出す、価値を提供する、低廉に回す、リスクを回避する他)
2 いい人を採って、いい人を育て、維持する
3 以上の実現のためにリソースを適切に配分し運用する
価値創出の3つの型
1 N倍化(大量生産)
2 刷新(A→B)
3 創造(0→1)
複素数平面的なゲームに入る前の実数空間ゲームのときは、ご存知のとおりとにもかくにも「N倍化」、大量生産でボリュームを生み出すことが何よりも大きな価値の源泉だった。トップに立つことはトップシェアをとることと同義だった。
次の強かったのが「刷新」だ。なんらかの分野に知恵を絞ってアップデートすることである。この実数軸の時代、日の目を見なかったのが今風に言えば0to1の「創造」だ。
ところが今はどうか。「N倍化」はすでにシェアを握りスケール(規模)をとってしまった大企業にとっては、長期的な人口調整局面については先細りのトレンドだ。一方の「刷新」は今や「N倍化」よりも遥かに価値を生む力がある。0to1の聖地のように言われるシリコンバレーで行われている大半の取り組みも実際にはこの刷新モデルが中心だ。
そして、今の時代において明らかにもっとも力強いのは0to1「創造」だ。妄想を形に変える力を持つコミュニティ、人、企業が、もっとも影響力が強く、その結果、富も握る。
Tesla が生み出したのは電気自動車ではなく「人が乗る走るスマホ」
Appleが生み出したのは「人間とインターネット、そして計算機がリアルタイムでつながる世界」
価値創造において、これまでとは真逆の世界が来ていることを直視しよう。
量的拡大のハードワークができるスケール型人材を生み出すことだけに注力してきた
日本の人材育成モデルは、根底から刷新が求められている。
そもそも生み出そうとしている人材の像、ゴール設定が間違っていたのだ。
結果、現在、この日本の教育システムが生み出す最高の人材は、テレビ番組でクイズ王になる、教育評論家や予備校講師になるぐらいしかないという残念なことになってしまう。世界の同世代の若手リーダーが刻一刻と未来を変えていっているそのときに、だ。
★ここからめちゃ重要★
「創造」「刷新」こそが大切な時代にどのような人が未来を作るカギとなる人材なのか。
これまでのゲームでは、とにかくみんなが走る競争で強い人が大切だった。また個別領域での専門家がとても大切だった。なんでも万遍なくできるスーパーマン的な人が期待されてもきた。
しかし、このような世界ではカギとなる人材像も本質的に変容する。これからは誰もが目指すことで一番になる人よりも、あまり多くの人が目指さない領域、あるいはアイデアで何かを仕掛ける人が、圧倒的に重要になる。
1つの領域の専門家というよりも夢を描き(=ビジョンを描き)、複数の領域をつないで形にしていく力を持っている人が遥かに大切になる。
一言で言えば、これからの未来のカギになるのは普通の人と明らかに違う「異人」だ。

図3-2(シン・ニホンより)
当然「異人」は少ない。しかし、異人が大切だと思う社会でなければ、こういう人の多くは異物として排除されるか、秩序を乱す人として潰されてしまう。だから価値観の変容と彼らが生き延びることができる空間が必要なのだ。またこういう人たちを尊重する価値観の人がある程度以上いて、閾値を超えないと変化は起きない。
「起爆人種」
「参画人種」
「応援人種」
「無関心人種」
「批判人種」
「狭き門より、入れ。滅びにいたる門は大きく、その道は広い。そして、そこから入っていくものが多い。命にいたる門は狭く、その道は細い。そして、それを見出すものは少ない」(マタイによる福音書第7章)
つまり、人が群がって流れていくような方向へは行くな、必ずしも人が気づいていないような自分の道に進め、という教えだ。異人化の教えは実は2000年前から存在していたのだ。
これは実に真実を突いている。人生設計、就職、仕事探しにおいて、とりわけ正しい。人が群がるところに行くということは、コモディティへの道、部品化の道を歩むということだ。人がすでに歩いた道を行くのだから、当然、先行者利益などない。その人の価値は「何者であるか」ではなく、「どの組織に属しているか」でほとんど判断されることになる。
少なくとも他人の判断に流されるのを避け、自分の目で見て肌で感じた判断を信じ、逆を張るべきだ。独自性、つまり同列の競争での優秀さではなく質的な違いこそが価値になる時代において、交換可能な部品になると実に厳しい道を歩むことになるからだ。
人生でもビジネスでも直接的な競争はできるだけ避けるのが正しい。実質的な無競争空間を生み出せるかどうかが、幸せへのカギだ。競争から解き放たれたとき、人も事業も自由になれる。そもそも同じ軸で勝負している段階で「異人」ではないことは明らかだ。それは単なる同じ軸上のズレにすぎないからだ。他の人の判断軸に乗らない、ねじれの位置にあるような軸に飛び移るべきだ。
「好きなことをやれ」は正しいけれど、ある意味では正しくないということだ。熱狂的にやるものは、あくまで自分らしくではあるが、他人と自分を異質化できるものであるべきだ。
仕事とは他の人に評価される価値を生むことであり、その人の存在意義の視点で見れば、価値が生み出せることは好きか嫌いかよりも遥かに大切だからだ。たとえば、ゲームが好きだからただやるのは中毒に過ぎない。造り手の作った罠にかかっただけだ。人が作った問いに対して、すでに用意されている答えを出しているだけとも言える。ひたすら探求して、自ら新しく問いを生み出せるかという視点で領域を見たほうがいいだろう。
~~~ここまでメモ
「異人」の時代。
柏崎風に言えば、「変態」の時代。
これはまさしく生存戦略の問題だと思う。
何に張るか?(賭けるか?)っていう問題だ。
ひとつ、書いていて思ったのは、
他者からの「評価」は本来楽しいことなのではないか?
ということ。
それを単一の軸で序列化されてしまう学校教育システムが
つらいのではないか。
自分なりの分野で突き抜けて、異人となり、
それが評価されるのであれば、それは楽しいことなのかもしれない。
まだまだ噛み砕いていく必要があるけど、今日はこのへんで。
2020年04月16日
「文明なるもの」への挑戦
「WEEKLY OCHIAI」
https://newspicks.com/user/2250/
の4月8日放送分
「Withコロナ時代の日本再生ロードマップ」を見ました。
「コロナショック」とはいったい何なのか?
についての皆さんの話が面白く、また可能性を感じて、
メモに残しておきます。
いちばんおもしろかったのは、「シン・ニホン」の著者、
安宅さんの開疎化の話。
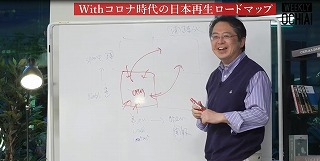
詳しくは以下の「そろそろ全体を見た話が聞きたい2」に載ってますが。
https://kaz-ataka.hatenablog.com/entry/2020/04/04/190643
コロナショックで起こっていることは、
クローズで密な空間からオープンで疎な空間へと
距離をとるところが標準になる。
それっていうのは、
City(都市)への挑戦、つまり「文明なるもの」への挑戦なのだと。
都市に人が集まり、交わることで人類は文明をつくってきた。
2000年以上続いた転換点にいるのだという。
そういう意味では、
いま、多くの人が当たり前のように使っているzoomのようなテレビ電話システムを使えば、
開疎化されても、価値を生むことができるような世の中にはなっている。
つまりデジタルテクノロジーやネットワークが
それを可能にしている。
「都市」「高密度」「効率性」「弱者切り捨て」といった
社会モデルそのものが変わらなければいけないのだと。
鳥取・島根・岩手が最後まで感染者が出なかったように、
もっとも開疎な場所がコロナウイルスの感染が遅かった。
都市化でいい思いをするのは高学歴のインテリだけなんだと。
開疎化された世界では
・土地が余っている
・職住隣接
・食べものがおいしくて安い
また、起業家、ベンチャー企業にとっても
東京のイベントがぜんぶzoomでオンライン配信となったことで、
地方にいても東京と同じ情報が手に入る。
ベンチャー企業にとっては大きなビジネスチャンスが生まれているかもしれない。
建築やオフィスのリノベーションなど。
と同時に地方も企業誘致のチャンスがきている。
zoomによって経営のスピードが上がる。
おじさんたちのゴルフや会食で決めてきた「昭和」の終わり。
「食」や「イベント」:GDPで見れば、トータルで自動車と同じくらいの産業になっている。
⇒もはや基幹産業であり、基幹産業とは多くの平均的な人が働く場所。
~~~
「開疎化」は大きなキーワードだ。
5Gが整い、オンライン会議が標準的になれば、
もはや、東京にいることはプラスというよりもリスクでしかない。
コロナショック後の世界、コロナウイルスと共存しながら未来に向かっているいま、、
本当の価値。
幸せってなんだっけ?
っていう哲学的な問いも、ひとりひとりには課せられているのだなと。
この町でもその問いに対して、1つの旗を立てられないか?と思う。
https://newspicks.com/user/2250/
の4月8日放送分
「Withコロナ時代の日本再生ロードマップ」を見ました。
「コロナショック」とはいったい何なのか?
についての皆さんの話が面白く、また可能性を感じて、
メモに残しておきます。
いちばんおもしろかったのは、「シン・ニホン」の著者、
安宅さんの開疎化の話。
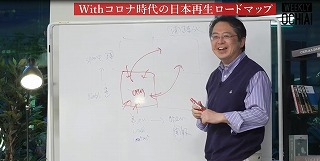
詳しくは以下の「そろそろ全体を見た話が聞きたい2」に載ってますが。
https://kaz-ataka.hatenablog.com/entry/2020/04/04/190643
コロナショックで起こっていることは、
クローズで密な空間からオープンで疎な空間へと
距離をとるところが標準になる。
それっていうのは、
City(都市)への挑戦、つまり「文明なるもの」への挑戦なのだと。
都市に人が集まり、交わることで人類は文明をつくってきた。
2000年以上続いた転換点にいるのだという。
そういう意味では、
いま、多くの人が当たり前のように使っているzoomのようなテレビ電話システムを使えば、
開疎化されても、価値を生むことができるような世の中にはなっている。
つまりデジタルテクノロジーやネットワークが
それを可能にしている。
「都市」「高密度」「効率性」「弱者切り捨て」といった
社会モデルそのものが変わらなければいけないのだと。
鳥取・島根・岩手が最後まで感染者が出なかったように、
もっとも開疎な場所がコロナウイルスの感染が遅かった。
都市化でいい思いをするのは高学歴のインテリだけなんだと。
開疎化された世界では
・土地が余っている
・職住隣接
・食べものがおいしくて安い
また、起業家、ベンチャー企業にとっても
東京のイベントがぜんぶzoomでオンライン配信となったことで、
地方にいても東京と同じ情報が手に入る。
ベンチャー企業にとっては大きなビジネスチャンスが生まれているかもしれない。
建築やオフィスのリノベーションなど。
と同時に地方も企業誘致のチャンスがきている。
zoomによって経営のスピードが上がる。
おじさんたちのゴルフや会食で決めてきた「昭和」の終わり。
「食」や「イベント」:GDPで見れば、トータルで自動車と同じくらいの産業になっている。
⇒もはや基幹産業であり、基幹産業とは多くの平均的な人が働く場所。
~~~
「開疎化」は大きなキーワードだ。
5Gが整い、オンライン会議が標準的になれば、
もはや、東京にいることはプラスというよりもリスクでしかない。
コロナショック後の世界、コロナウイルスと共存しながら未来に向かっているいま、、
本当の価値。
幸せってなんだっけ?
っていう哲学的な問いも、ひとりひとりには課せられているのだなと。
この町でもその問いに対して、1つの旗を立てられないか?と思う。
2020年04月09日
「何を学ぶか」から「誰と学ぶか」へ

22世紀を見る君たちへ~これからを生きるための「練習問題」(平田オリザ 講談社現代新書)
読み始めました。
第2章 未来の大学入試(二)まできました。
いちばん刺さったのはこれ。
「何を学ぶか」から「誰と学ぶか」へ
~~~以下一部引用
現在、ハーバード大学やMITあるいは日本でも京都大学などが、講義内容のインターネットでの公開を始めている。これは一見、不思議な事象だ。学生は厳しい受験戦争を勝ち抜き、また高い授業料を払っているのに、そこでの授業はインターネットでも見られるのだ。
インターネットの時代には、単純な知識や情報は世界共有の財産となる。ネット社会は情報を囲い込むシステムではない。情報をできるだけオープンにして、そこに集まってきた人たちに広告を見せることで、ほとんどのネット産業は成り立っている。
もはや情報を囲い込むことはできない。知識や情報を得るコストは、時間的にも経済的にも急速に低減した。そのようなネット時代を前提にして、ハーバードで一緒に議論することに意義がある。MITで、ともに学ぶことに意義がある。いや、もはや、そこにしか大学の意義はないと、世界のトップエリート校ほど考えている。
だからそこでは、「何を学ぶか?」よりも「誰と学ぶか?」が重要になる。それは学生の質の問題だけではない。教職員を含めて、どのような「学びの共同体」を創るかが、大学側に問われているのだ。
反改革派の方々は口々に「受験勉強にもいい点がある」と言う。それらはいろいろと理由はつけても結局のところ、「達成感が得られる」「根性がつく」「集中力が養われる」といった、「それは部活でも、他の場所でも養えるんじゃないかな?」と思えるものが多い。
たしかに従来型の受験勉強で救われる人もいるのだろう。だがそれは改革自体を阻む理由にはならない。
「努力」や「根性」「従順さ」も大事なのだろうが、それそのものが、もはや人生の中で優先順位が低くなってしまっている。先に掲げた「主体性」「多様性」「協働性」などの方が、21世紀の日本社会と国際社会を生きる上では、少なくとも同等か、それ以上に必要なものとなっている。人生にとって必要な能力自体が変化しているのに、受験がそのままでいいわけがない。
~~~ここまで一部引用
大学入試は近いうちに変わる。
求められる能力も変わっていくる。
いや、そもそも。
新型コロナウイルス感染防止のための一斉休校を受け、
オンライン上での授業が行われたり、
ウェブで学べる様々な学習コンテンツを、
ほとんどが無料で利用できることがわかった。
この本に書いてあるように、
「コンテンツ」(知識や情報)そのものは共有物となって、いつでも誰でも取り出せるものとなっている。
学びが「コンテンツ(知識や情報)の移転」である時代は終わりつつあるのだ。
大学だけではない。高校もそうだ。
「何を学ぶか」から「誰と学ぶか」へ、さらには「どこで学ぶか?」
がとても大切になっていく。
キーワードはこの本で言えば、「学びの共同体」だ。
SCHシンポジウム的に言えば、「学びの土壌」だ。
「誰と」
「どこで」
「何を」
学ぶのか。
「何を」のところ入るのは、単にコンテンツではない。
地域にある題材・課題を探究し、創造する学びになる。
その学びが、この町でしかできない理由。
ここにある「学びの共同体」「学びの土壌」でしかできない理由。
この状況の中で、その問いに答えていくこと。
僕だけでなく、共同体として答えていくこと。
そんな学びの場をつくっていく。
2020年04月07日
エラー求む
note更新のメモ。
41機目「武器になる哲学」
https://note.com/tsuruhashi/n/nfc2122c0e84c
その前に紹介するのは
19機目「心の時代にモノを売る方法」
https://note.com/tsuruhashi/n/na4785b978c95
42機目「社交する人間」
https://note.com/tsuruhashi/n/ne561845849ba
~~~以下引用
「経済の第一の系統は生産と分配の経済であって、これは同質的で均一的な集団を形成しながら、それによって生産物の効率的な増産を目標としてきた。
これに対して第二の系統をつくるのが贈与と交換の経済であって、言葉を換えれば社交と商業の経済だといえる。
生産と分配の経済がよりどころにした「共通の需要、必需品の観念」という絆は崩れた。今の消費者にとって、必需品の観念は共通ではない。誰もが自家用車を欲しがり、マイホームを欲しがった時代は終わったからだ。
(中略)
「心の豊かさと毎日の精神的充足感」への希求が主流をなしてくると共に、長らく―おそらく産業革命以来200年以上も―「生産と分配の経済」の陰に隠れていたもうひとつの系統、「贈与と交換」そして「社交と商業」の経済が、再び表舞台に出てきたのである。
(中略)
もうひとつの経済(贈与と交換の経済)の決定的な原則は
1 1回ごとの試みによって(お客さんに喜ばれるかどうか)が模索される
2 常に需要のないところに新しく需要を作り出す
3 あらかじめ需要は予測され得ない
じっさい、伝統的な商人はつねに遠く旅をする人間であり、異文化の世界から珍しい宝を運ぶ人間であった。彼は旅先でそれが必要とされるかどうかを予期することはできず、かりに必要とされてもどんな対価を求められるかを予測することはできなかった。
商人はめぐりあった消費者に商品の物語を説き、その心を魅惑する会話の成功とともに需要を創造したのであった。
この交易が反復されて市場が形成され、次第に需要の大半が予測可能となっても、一回ごとの個別の商品の取引においては、同じ冒険が繰り返されたはずである。
~~~ここまで引用
商売っていうのは冒険なんだと。
「需要」は創造されるものなのだと。
進学する高校の選択というのは、3年間という「時間」を対価として、「学ぶ環境」を購入する行為だと言えるだろう。
そこに「需要」を「創造」する行為が高校魅力化プロジェクトのだろうと思う。
そしてその需要というか「価値」は、異質な他者によってもたらされる。
そこで「武器になる哲学」だ。
~~~以下メモ
「自然淘汰」とは?
1 生物の個体には、同じ種に属していても、様々な変異が見られる。(突然変異)
2 そのような変異の中には、親から子へ伝えられるものがある。(遺伝)
3 変異の中には、自身の生存や繁殖に有利な差を与えるものがある(自然選択)
ポイントはむしろ「自然選択」よりも「突然変異」にあります。突然変異によって獲得される形質は、当たり前のことですが、予定調和しません。変異の方向性は極めて多様で、確率的には生存や繁殖に有利な差を与えるものと、不利な差を与えるものが、中央値を挟んで正規分布していたはずです。
おそらく、これまでの歴史を振り返れば、突然変異によってオレンジ色のトカゲもグリーンのトカゲも生まれてきたはずです。しかし、そういった形質はむしろ、自身の生存や繁殖に不利な差となります。砂漠地帯において、オレンジやグリーンという色はたいへん目立つわけですから、天敵に狙われやすい。そのような形質を突然変異によって獲得してしまった個体は、天敵に捕食される確率が相対的に高く、結果としてその形質は次世代へと遺伝されません。
どのような形質がより有利なのかを事前に知ることはできません。自然淘汰という仕組みは、いわばサイコロを振るようにして起きた様々な形質の突然変異のうち、「たまたま」より有利な形質を持った個体が、遺伝によってその形質を次世代に残し、より不利な形質を持った個体は淘汰されていくという、膨大な時間を必要とする過程であるということです。
「私たちは一般に、エラー(突然変異)というものをネガティブなものとして排除しようとします。しかし、自然淘汰のメカニズムには「エラー」が必須の条件として組み込まれている。なんらかのポイティブなエラーが発生することによって、システムのパフォーマンスが向上するからです。」
「偶発的なエラーによって進化が駆動される。」
「自然界において、適応能力の差分は計画や意図によるものではなく、一種の偶然によって生まれているのだということを知れば、組織運営や社会運営においても、私たちはそれを計画的・意図的により良いものに変えていけるのだという傲慢な考えを改め、自分の意図よりもむしろポジティブな偶然を生み出す仕組みを作ることに注力したほうがいいのかもしれません。」
~~~以上メモ
かつて。
もっとも強い者が生き残るのではなく
もっとも賢い者が生き延びるのではもない。
唯一生き残るのは、変化できる者である。
って、僕も言ってました。だから、変化しなきゃいけないんだよ、お前(オレ)って。
誤解していました。僕は、ダーウィンを誤解していました。この本を読んで、突然変異は「意志」ではなく「偶然」に起こり、生き延びるのは、「個人」ではなく「集団」なのだ、と。
この町が生き延びるために、異質な他者(エラー)を組み込んでいくことが必要なのだと。
そのエラーを得るために「学ぶ環境」を売り込むキリギリスになろうじゃないか。
エラー求む、だよ。
41機目「武器になる哲学」
https://note.com/tsuruhashi/n/nfc2122c0e84c
その前に紹介するのは
19機目「心の時代にモノを売る方法」
https://note.com/tsuruhashi/n/na4785b978c95
42機目「社交する人間」
https://note.com/tsuruhashi/n/ne561845849ba
~~~以下引用
「経済の第一の系統は生産と分配の経済であって、これは同質的で均一的な集団を形成しながら、それによって生産物の効率的な増産を目標としてきた。
これに対して第二の系統をつくるのが贈与と交換の経済であって、言葉を換えれば社交と商業の経済だといえる。
生産と分配の経済がよりどころにした「共通の需要、必需品の観念」という絆は崩れた。今の消費者にとって、必需品の観念は共通ではない。誰もが自家用車を欲しがり、マイホームを欲しがった時代は終わったからだ。
(中略)
「心の豊かさと毎日の精神的充足感」への希求が主流をなしてくると共に、長らく―おそらく産業革命以来200年以上も―「生産と分配の経済」の陰に隠れていたもうひとつの系統、「贈与と交換」そして「社交と商業」の経済が、再び表舞台に出てきたのである。
(中略)
もうひとつの経済(贈与と交換の経済)の決定的な原則は
1 1回ごとの試みによって(お客さんに喜ばれるかどうか)が模索される
2 常に需要のないところに新しく需要を作り出す
3 あらかじめ需要は予測され得ない
じっさい、伝統的な商人はつねに遠く旅をする人間であり、異文化の世界から珍しい宝を運ぶ人間であった。彼は旅先でそれが必要とされるかどうかを予期することはできず、かりに必要とされてもどんな対価を求められるかを予測することはできなかった。
商人はめぐりあった消費者に商品の物語を説き、その心を魅惑する会話の成功とともに需要を創造したのであった。
この交易が反復されて市場が形成され、次第に需要の大半が予測可能となっても、一回ごとの個別の商品の取引においては、同じ冒険が繰り返されたはずである。
~~~ここまで引用
商売っていうのは冒険なんだと。
「需要」は創造されるものなのだと。
進学する高校の選択というのは、3年間という「時間」を対価として、「学ぶ環境」を購入する行為だと言えるだろう。
そこに「需要」を「創造」する行為が高校魅力化プロジェクトのだろうと思う。
そしてその需要というか「価値」は、異質な他者によってもたらされる。
そこで「武器になる哲学」だ。
~~~以下メモ
「自然淘汰」とは?
1 生物の個体には、同じ種に属していても、様々な変異が見られる。(突然変異)
2 そのような変異の中には、親から子へ伝えられるものがある。(遺伝)
3 変異の中には、自身の生存や繁殖に有利な差を与えるものがある(自然選択)
ポイントはむしろ「自然選択」よりも「突然変異」にあります。突然変異によって獲得される形質は、当たり前のことですが、予定調和しません。変異の方向性は極めて多様で、確率的には生存や繁殖に有利な差を与えるものと、不利な差を与えるものが、中央値を挟んで正規分布していたはずです。
おそらく、これまでの歴史を振り返れば、突然変異によってオレンジ色のトカゲもグリーンのトカゲも生まれてきたはずです。しかし、そういった形質はむしろ、自身の生存や繁殖に不利な差となります。砂漠地帯において、オレンジやグリーンという色はたいへん目立つわけですから、天敵に狙われやすい。そのような形質を突然変異によって獲得してしまった個体は、天敵に捕食される確率が相対的に高く、結果としてその形質は次世代へと遺伝されません。
どのような形質がより有利なのかを事前に知ることはできません。自然淘汰という仕組みは、いわばサイコロを振るようにして起きた様々な形質の突然変異のうち、「たまたま」より有利な形質を持った個体が、遺伝によってその形質を次世代に残し、より不利な形質を持った個体は淘汰されていくという、膨大な時間を必要とする過程であるということです。
「私たちは一般に、エラー(突然変異)というものをネガティブなものとして排除しようとします。しかし、自然淘汰のメカニズムには「エラー」が必須の条件として組み込まれている。なんらかのポイティブなエラーが発生することによって、システムのパフォーマンスが向上するからです。」
「偶発的なエラーによって進化が駆動される。」
「自然界において、適応能力の差分は計画や意図によるものではなく、一種の偶然によって生まれているのだということを知れば、組織運営や社会運営においても、私たちはそれを計画的・意図的により良いものに変えていけるのだという傲慢な考えを改め、自分の意図よりもむしろポジティブな偶然を生み出す仕組みを作ることに注力したほうがいいのかもしれません。」
~~~以上メモ
かつて。
もっとも強い者が生き残るのではなく
もっとも賢い者が生き延びるのではもない。
唯一生き残るのは、変化できる者である。
って、僕も言ってました。だから、変化しなきゃいけないんだよ、お前(オレ)って。
誤解していました。僕は、ダーウィンを誤解していました。この本を読んで、突然変異は「意志」ではなく「偶然」に起こり、生き延びるのは、「個人」ではなく「集団」なのだ、と。
この町が生き延びるために、異質な他者(エラー)を組み込んでいくことが必要なのだと。
そのエラーを得るために「学ぶ環境」を売り込むキリギリスになろうじゃないか。
エラー求む、だよ。
2020年04月03日
未来に素手で触れている、というフロンティア

「遅いインターネット」(宇野常寛 幻冬舎)
これ、面白いです。
まだ読み途中ですが。
「平成」とはなんだったのか?
「グローバル経済社会」になるとどうなるのか?
どうして「民主主義」は危機に陥っているのか?
宇野さんはそうやって社会を斬るのか。
スルドいなあ、って。
東京オリンピックのその先が見えない。
それは、平成という失敗したプロジェクトの先に未来がないのと一緒だ。
グローバルな経済とローカルな政治という関係が成立する前は、
インターナショナルな政治にローカルな経済が従属していた。
ところがグローバル経済が世界を覆うと、
世の中はanywhereな人々(境界のない世界の住人≒どこでも生きていける人)
とsomewhereな人々(境界のある世界の住人≒どこかに属して生きていく人)
に分断された。
これが、ふたたび壁をつくろう、とするのだと。
少し前にアメリカやイギリスで起こったことだ。
かつて民主主義がもたらしてくれた「世界に素手で触れている」という感覚。
もはや1部の経済強者のみがその感覚を得ることができる。
「素手で触れている」という感覚。
これは間違いなく勘違いなのだけど、
多くの人のモチベーションはそうやって駆動されている。
企業や組織だってそうだ。
企業や組織の未来に素手で触れている。
つまり「経営に参画している」という感覚こそが大切なんだと思う。
今回、紹介したいのは、
P98「仮想現実から拡張現実へ」のところ。
前段で、Googleなるものについての説明がある。
~~~ここから引用
かつてGoogleは、本来無秩序なインターネットを検索可能にし、疑似的な秩序をもたらした。その意味において、Google検索とは、本来は分散的なインターネットを「擬似的に」「中央集権化して」「見せる」装置だったとも言える。
今世紀初頭のある時期にGoogleによって成立していたネットサーフィンという行為は、いま過去のものになろうとしている。SEOの手法とインターネット広告産業の発展は、Googleの検索機能を大きく汚染した。
その行き着いた先として、Googleの検索結果の上位に表示されるのは広告収入目的のWikipediaを引き写したような事実上無内容なブログと、扇情的な見出しをつけてクリックを誘うフェイクニュースまじりのニュースサイトばかりになった。
そして気がつけば、僕たちはGoogleをWikipediaと食べログのインデックスにしか使っていない。
~~~ここまで引用
うわー。
バレましたか。笑
言葉を調べたいときとお店を知りたいときにしか
Google使ってないってまさにそれ。
それを「汚染した」と書く宇野さん鋭い。
まさにGoogleの思想が汚染されたのだ。
Google元副社長のジョン・ハンケは、グーグルマップ、
ストリートビューなど地図サービスの責任者を経て、
あの「ポケモンGO」をつくった社内ベンチャーの
「ナイアンティック・ラボ」を設立する。
ポケモンGOの前に開発されたゲーム「Ingress」をプレイし、まちを歩き回ることで
人々は自動的に自然や歴史に触れ、学習するとハンケは考えた。
宇野さんは次のように説明する。
~~~
言い換えればそれは、人間の地理と歴史への感度、世界を見る目を鍛える行為でもあるだろう。自分たちが生きているここ=「この世界」の深さを、多層性を把握しうる世界を見る目なくしては、「ここではない、どこか」=世界の果てまで旅しても何も見えてこない。―そんな確信が「Ingress」のゲームデザインの根底にある。
~~~
そして、今日のハイライト。
「仮想現実から拡張現実へ」
情報技術が目指すものが変わってきたのだと。
~~~ここから引用
かつて、インターネットが代表する情報技術が人類に与えていた「夢」とは、「ここではない、どこか」を仮構することだった。この世界とは異なるもうひとつの世界を構築すること。それが前世紀の末にコンピューターが担った最大の気体であり、そして当時の若者たちが虚構に求めたものだった。
だからこそ僕たちはそこで本名ではなくハンドルを用い、もうひとつの自分を演出した。そしてそこには現実とは切り離されたもうひとつの世界を作り上げ、そこでもうひとつのルール、もうひとつの秩序、もうひとつの社会を築き上げようとした。まだインターネットがソーシャルネットワークに飲み込まれる前の話だ。
だが、現在は違う。僕たちは情報技術を「ここ」を、この場所を、この世界を豊かにするために、多重化するために用いている。多くの人たちが実社会の人間関係の効率化とメンテナンスのためにfacebookを使い、夜の会食の店を食べログで検索して予約し、移動中はApple musicでヒットチャートをチェックする。退屈な会議中は、海外出張中の友人にメッセンジャーで愚痴をこぼす。
21世紀の今日、僕たちは情報技術を「ここではない、どこか」つまり仮想現実を作り上げるためではなく「ここ」を豊かにするために、つまり拡張現実的に使用している。
(中略)
20世紀の最後の四半世紀のあいだ、虚構とは、革命の可能性を失った消費社会において、「ここではない、どこか」を仮構することが役割だった。これが仮想現実的な虚構だ。しかし、超国家的に拡大した市場を通じて世界を変える回路が常態化した今日において、外部を失ったグローバル化以降の世界において虚構が果たすべき役割は「ここ」を重層化し、世界変革のビジョンをこの現実において示すことなのだ。拡張現実(AR)的な虚構がいま、求められているのだ。
~~~ここまで引用
「虚構が果たすべき役割」って言葉いいですね。
この先に未来があるなあ。
このまちのフロンティアはきっと、そこにあるのだろうと。
「ここ」を重層化する。
「この町」を重層化する。
東京というローカルの重層化には限界があると思う。
また、「この町」だけの重層化も難しいと思う。
「ここ」「この町」の暮らしの重層化のために、
観光を強化し、外国人観光客を呼び、テレワーク拠点をつくり、IT企業と連携し、
まちをつくっていくこと。それがこの町で暮らす意味になると思う。
十数年前、「課題先進地」というフロンティアを求め、
海士町に、西粟倉村に、神山町へと志ある若者が移住した。
それはきっと、
アメリカ西海岸でインターネット産業を興した若者たちの
「世界に素手で触れている」という感覚に似たようなもの。
「未来に素手で触れている」というような感覚なのではないか。
それがフロンティアなのではないか。
きっと「高校魅力化」で伝えるべきはそこなのだろう。
このまちの未来に素手で触れられる高校。
そして、この町の未来が世界の未来につながっているという感覚。
それこそが自らの人間関係と人生を多重化・多層化し、豊かにしていくこと。
仲間求む。
みたいな広報をしようじゃないか。




