2018年08月31日
「自分に自信がない」の「自分」って何だ?
明日は茨城県日立市で「若松ミライ会議」の拡大版。
復習しようと。
「顧客」と「価値」の視点から過去を見つめなおす(18.7.12)
http://hero.niiblo.jp/e487733.html
「私」を外す、という美学(17.3.28)
http://hero.niiblo.jp/e484378.html
あらためて。
「日本人は何を考えて生きてきたのか(斎藤孝 洋伝社)より
西田幾多郎の言葉。
「主客があるかのように思うのは、私たちの思い込みにすぎない。実は主客未分のほうが本来の姿であり、純粋な経験である。経験の大もとを純粋な経験だとすると、純粋経験は主客未分でおこっているはずだ。本質を捉えようとするならば、私というものを前提として考えるのではなく、むしろ主客を分けることができない純粋経験こそを追求するべきだと考えたのです。」
そして、鈴木大拙もつづく。
「禅は科学、または科学の名によって行われる一切の事物とは反対である。禅は体験的であり、科学は非体験的である。非体験的なるものは抽象的であり、個人的経験に対してはあまり関心を持たぬ。体験的なるものはまったく個人に属し、その体験を背景としなくては意義を持たぬ。科学は系統化(システマゼーション)を意味し、禅はまさにその反対である。言葉は科学と哲学には要るが、禅の場合には妨げとなる。なぜであるか。言葉は代表するものであって、実体そのものではない。実体こそ、禅においてもっとも高く評価されるものなのである。」
これ、中動態を学んだ今、めっちゃよくわかるね。
自分の過去に、「顧客」と「価値」があって、
それはすごく体験的で、個人的なもので、
そもそも「自分に自信がない」というときの
「自分」ってなんだろう?
と、「やりたいことがわからない」
ことが苦しいから、「やりたいこと」を探してしまうけど、
「自分に自信がない」
ことが苦しいから、自分に自信をつけようとしてしまうけど。
そもそも、やりたいことって何か?
とか
自分に自信がない場合の「自分」って何か?
みたいなことって問わないもんね。
僕はかつて、
「自分に自信がない」と言ってきた若者に対して、
「自信がなくても始められたらいい」
と思っていた。
だから、上田信行先生に出会って、
キャロル・ドゥエック先生の本を読み、
固定的知能観と成長的知能観について学んだ。
「自信がない」は後天的に獲得した資質である(14.12.29)
http://hero.niiblo.jp/e459844.html
やればできる(かもしれない)、
つまり自信がある状態が通常で、
自信がない(からやれない)
というのは後から獲得している。
だから、始めたらいい。
と言っていたけど。
自信がどうの、っていうよりはまず「自分」というか
アイデンティティについて取り組んでいく必要がある。
そのためには、自分の過去を知ること。
過去の結果としての自分を受け入れること。
状況に身を委ねること。
「自分」を知ること
「社会」を知ること
そこから「自分」を見つめなおすこと。
明日の「ミライ会議」がそんな場になったらいい。
これから明日の予習をこの本で。

「We are lonely,but not alone」(佐渡島庸平 幻冬舎)
復習しようと。
「顧客」と「価値」の視点から過去を見つめなおす(18.7.12)
http://hero.niiblo.jp/e487733.html
「私」を外す、という美学(17.3.28)
http://hero.niiblo.jp/e484378.html
あらためて。
「日本人は何を考えて生きてきたのか(斎藤孝 洋伝社)より
西田幾多郎の言葉。
「主客があるかのように思うのは、私たちの思い込みにすぎない。実は主客未分のほうが本来の姿であり、純粋な経験である。経験の大もとを純粋な経験だとすると、純粋経験は主客未分でおこっているはずだ。本質を捉えようとするならば、私というものを前提として考えるのではなく、むしろ主客を分けることができない純粋経験こそを追求するべきだと考えたのです。」
そして、鈴木大拙もつづく。
「禅は科学、または科学の名によって行われる一切の事物とは反対である。禅は体験的であり、科学は非体験的である。非体験的なるものは抽象的であり、個人的経験に対してはあまり関心を持たぬ。体験的なるものはまったく個人に属し、その体験を背景としなくては意義を持たぬ。科学は系統化(システマゼーション)を意味し、禅はまさにその反対である。言葉は科学と哲学には要るが、禅の場合には妨げとなる。なぜであるか。言葉は代表するものであって、実体そのものではない。実体こそ、禅においてもっとも高く評価されるものなのである。」
これ、中動態を学んだ今、めっちゃよくわかるね。
自分の過去に、「顧客」と「価値」があって、
それはすごく体験的で、個人的なもので、
そもそも「自分に自信がない」というときの
「自分」ってなんだろう?
と、「やりたいことがわからない」
ことが苦しいから、「やりたいこと」を探してしまうけど、
「自分に自信がない」
ことが苦しいから、自分に自信をつけようとしてしまうけど。
そもそも、やりたいことって何か?
とか
自分に自信がない場合の「自分」って何か?
みたいなことって問わないもんね。
僕はかつて、
「自分に自信がない」と言ってきた若者に対して、
「自信がなくても始められたらいい」
と思っていた。
だから、上田信行先生に出会って、
キャロル・ドゥエック先生の本を読み、
固定的知能観と成長的知能観について学んだ。
「自信がない」は後天的に獲得した資質である(14.12.29)
http://hero.niiblo.jp/e459844.html
やればできる(かもしれない)、
つまり自信がある状態が通常で、
自信がない(からやれない)
というのは後から獲得している。
だから、始めたらいい。
と言っていたけど。
自信がどうの、っていうよりはまず「自分」というか
アイデンティティについて取り組んでいく必要がある。
そのためには、自分の過去を知ること。
過去の結果としての自分を受け入れること。
状況に身を委ねること。
「自分」を知ること
「社会」を知ること
そこから「自分」を見つめなおすこと。
明日の「ミライ会議」がそんな場になったらいい。
これから明日の予習をこの本で。

「We are lonely,but not alone」(佐渡島庸平 幻冬舎)
2018年08月30日
やりたいことを決めることは価値を固定化すること

「やりたいことがわからない」の社会学&本の処方箋セミナー
と題して、仙台・ファイブブリッジ会議室で
ワカツクの渡辺一馬さんとトークしてきました。
この場所に初めてきた、
あるいはこういうイベントに初めてきた、っていう人がたくさん。
いやあ、これは、タイトルの勝利ですよ、一馬さん。
シナリオは特になかったのだけど、
最初に「本屋の青空」の話をして、
(予想しなかった本に出会えることが本屋の価値ではないか)
それはまちに通じるし、
この場所につくるライブラリーにも通じるよねえという話からスタート。
参加者は、「やりたいことはなんだろう?」と問いかけている大学生と
目標設定、達成だけの会社人生だとつらいといっている
社会人の人など、
まさにそういう人に来てほしい、みたいなのが来てくれた時間だった。
そしてそれは、
本人たちにとってみれば切実な課題なのだとということもあらためてわかった。
そして、学校というシステムが設定する(固定する)「価値」に対して、
それを信じているからこそつらいのだということが分かった。
昨日も話したけど、
「やりたいこと」や「将来の夢」を決めるのは激動の時代にナンセンスだと思うし、
それはもっと言えば、目標とか意志とかを設定し、そこに向かって全力で進むみたいな価値観が
揺らいできているのだと思うのだけど、
それはもっと機能的に説明すると、
「やりたいこと」とか「将来の夢」、「目標」とか「意志」の前には、
「価値」の固定化がある。
一定のもの(売上とか)に「価値」があると設定して、
そこに向かっていくこと。
そうだとすると、明治時代に学校ができて以来、
もっとも大きなコンセプトは「効率化」であっただろうと思う。
富国強兵、追いつけ、追い越せという
スローガンのもとに、急速な「近代化」を遂げた日本、
それを支えた教育。
そのベースには「効率化」がある。
学校では夢(目標)を設定し、
その目標に向かって効率化せよ、と求められる。
あなたはどこに行きたいんだ?
と問われ、そこに早く行くために、
どうしたらいいのだ?と問い詰められる。
ところが。
冒頭の話に戻るけど、それって楽しいのか?
っていうこと。
「本屋の青空」があるような本屋。
目的の本を忘れ、思ってもいなかった本を買ってしまうような、
街を歩いていて、
古めかしいおばちゃんがやっている定食屋で
おにぎりを買う、みたいな、
そんな「たまたま」を人は、人生は求めているのではないか。
「効率化」と「予測不可能性」は対立する。
「やりたいことがわからない」
素晴らしいじゃないかと思う。
とはいえ、
何かに打ち込んでないと不安になる、
それもひとつだろう。
昨日一馬さんとの結論は、
「小さなプロジェクトをやってみる」だった。
「価値」と「お客」を設定して、
小さなプロジェクトをやってみること。
そして振り返ること。
流動する「価値」をいったん固定し、やってみること。
そんな中から自分の「やりたいこと」の仮説ができて、
それを検証し続けること、なのかもしれない。
藤原奈央子ちゃんにも沖縄・糸満ぶりの再会だったけど、
彼女の人生がまさにそんな感じで楽しかった。
さて、仙台にもそんなことを伝えるライブラリーが
できたらいいなと思う。
また来ます。
2018年08月29日
システムを俯瞰して見ること
今月23日に発売された教員志望者向け雑誌「教職課程」の
巻頭メッセージ「そうか、きみは教員を目指すのか?」に掲載されています。
なんとリニューアルされたので第1回の#1です!

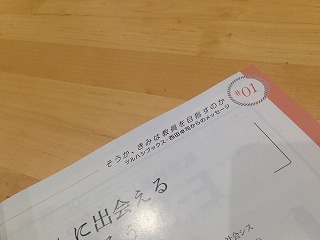
書店や大学生協、大学図書館などで見つけてください!
報告お待ちしてます!
テーマは「価値出会う」ことについて、書きました。
現代の若者の生きづらさの大きな原因のひとつが、
「価値」そのものが流動化していることだと僕は思います。
学校で教えられてきた(今も教えられている)「価値」が
価値を持たなくなっている。
それはインターネットが、とか、AIが、とか
いろいろ原因はあるのでしょうけど、
そもそも「価値」というのは常に
流動しているものなのではないかと僕は考えます。
だから、都度、「価値」を確認しなければならない。
今日、僕は夜、仙台で
「やりたいことがわからない」の社会学というテーマで
話しますけど、
「あなたの夢は何か?」
「将来、つきたい職業は?」
という問い。
親戚のおじさんが聞いてくる「将来、何になりたいんだ?」
とか、親戚のおばさんが聞いてくる
「あなた、いい人いないの?」(これは若干違うか)
みたいな問いにおける
「価値」はなんだろうか?
と問いかけてみる。
5年後10年後の世界がまったく予想できないのに、
自らの10年後のビジョンを描けと小学生に問いかける学校システムは
どう考えてもナンセンスだと思う。
じゃあ、何のために、(何の「価値」があり)
それを問いかけるのか。
それは管理上の理由なのではないか。
あるいは、「評価」のためである。
進路指導(あるいはキャリア教育)をする上で、
目標を定めなければ、指導は難しい。
目標を決めて、その達成を指導・支援することが
学校的な「価値」であるからではないか。
そもそも、
「目標を決める」ことに価値はあるのだろうか?
価値はないわけではないけど、
「価値がある場合がある」が答えだろうと思う。
あるいは、
かつて、そういう時代があった、かもしれない。
たしかに、工業社会においては、
目標を決めて、達成すること。
均質な製品を早く、大量に生み出すことは
絶対的な価値があった。
ところが、それは産業革命以降の限定された時代にのみ
通用する価値だったのではないか。
そしてその時代と
「学校」というシステムが成立していったのとは
同時期に起こっている。
いま、社会は大きく変わりつつある。
少なくともかつての工業システム(大量生産・大量消費)で
「価値」=経済的価値を生むことはできなくなった。
「価値」が流動している時代、
都度、価値は変化していて、
その価値は、自らが判断・決定するしかない。
だから、教員志望者に限らず、
大学時代にやっておいたほうがいいと僕が思うのは、
「価値に出会う」こと。
学校システムが設定する「価値」とは別の「価値」
が世の中にたくさんあって、
それを自分なりに見つけ、そこを目指していくことが必要だ。
学校システムを否定するわけでは決してない。
しかし、学校システムが設定する「価値」は
「価値」のひとつに過ぎないのだ。
じゃあ。
それ以外の価値に出会うにはどうしたらいいのか。
人に会う
本を読む
旅に出る
多くの人が言ってるけど、僕もこれだろうと思う。
陸奥賢さん流に言えば、「他者に出会う」ことだ。
そうやって、「価値」に出会うことで、
自分がいるシステムを俯瞰し、相対化できる。
そこから、自らが生み出したい「価値」を考え、
その価値の実現に向けて動いていくこと。
たぶんそれ。
さて。
僕は「かえるライブラリー」を実現していきますね。
では、今夜、仙台にてお会いしましょう。
巻頭メッセージ「そうか、きみは教員を目指すのか?」に掲載されています。
なんとリニューアルされたので第1回の#1です!

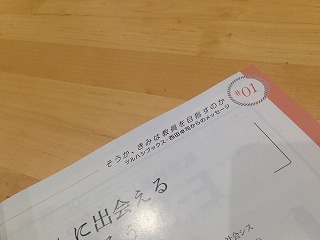
書店や大学生協、大学図書館などで見つけてください!
報告お待ちしてます!
テーマは「価値出会う」ことについて、書きました。
現代の若者の生きづらさの大きな原因のひとつが、
「価値」そのものが流動化していることだと僕は思います。
学校で教えられてきた(今も教えられている)「価値」が
価値を持たなくなっている。
それはインターネットが、とか、AIが、とか
いろいろ原因はあるのでしょうけど、
そもそも「価値」というのは常に
流動しているものなのではないかと僕は考えます。
だから、都度、「価値」を確認しなければならない。
今日、僕は夜、仙台で
「やりたいことがわからない」の社会学というテーマで
話しますけど、
「あなたの夢は何か?」
「将来、つきたい職業は?」
という問い。
親戚のおじさんが聞いてくる「将来、何になりたいんだ?」
とか、親戚のおばさんが聞いてくる
「あなた、いい人いないの?」(これは若干違うか)
みたいな問いにおける
「価値」はなんだろうか?
と問いかけてみる。
5年後10年後の世界がまったく予想できないのに、
自らの10年後のビジョンを描けと小学生に問いかける学校システムは
どう考えてもナンセンスだと思う。
じゃあ、何のために、(何の「価値」があり)
それを問いかけるのか。
それは管理上の理由なのではないか。
あるいは、「評価」のためである。
進路指導(あるいはキャリア教育)をする上で、
目標を定めなければ、指導は難しい。
目標を決めて、その達成を指導・支援することが
学校的な「価値」であるからではないか。
そもそも、
「目標を決める」ことに価値はあるのだろうか?
価値はないわけではないけど、
「価値がある場合がある」が答えだろうと思う。
あるいは、
かつて、そういう時代があった、かもしれない。
たしかに、工業社会においては、
目標を決めて、達成すること。
均質な製品を早く、大量に生み出すことは
絶対的な価値があった。
ところが、それは産業革命以降の限定された時代にのみ
通用する価値だったのではないか。
そしてその時代と
「学校」というシステムが成立していったのとは
同時期に起こっている。
いま、社会は大きく変わりつつある。
少なくともかつての工業システム(大量生産・大量消費)で
「価値」=経済的価値を生むことはできなくなった。
「価値」が流動している時代、
都度、価値は変化していて、
その価値は、自らが判断・決定するしかない。
だから、教員志望者に限らず、
大学時代にやっておいたほうがいいと僕が思うのは、
「価値に出会う」こと。
学校システムが設定する「価値」とは別の「価値」
が世の中にたくさんあって、
それを自分なりに見つけ、そこを目指していくことが必要だ。
学校システムを否定するわけでは決してない。
しかし、学校システムが設定する「価値」は
「価値」のひとつに過ぎないのだ。
じゃあ。
それ以外の価値に出会うにはどうしたらいいのか。
人に会う
本を読む
旅に出る
多くの人が言ってるけど、僕もこれだろうと思う。
陸奥賢さん流に言えば、「他者に出会う」ことだ。
そうやって、「価値」に出会うことで、
自分がいるシステムを俯瞰し、相対化できる。
そこから、自らが生み出したい「価値」を考え、
その価値の実現に向けて動いていくこと。
たぶんそれ。
さて。
僕は「かえるライブラリー」を実現していきますね。
では、今夜、仙台にてお会いしましょう。
2018年08月27日
未知なるものとしての「他者」

陸奥賢さんの「まわしよみ新聞をつくろう」(創元社)発売記念!
まわしよみ新聞&トークライブ新潟ツアー3DAYS。
長岡・コモンリビングで最終日。

まわしよみ新聞をやったあとで、
池戸と陸奥さんとトーク。
「コモンズデザイン」とは、「他者と出会う」こと。
「コミュニティ」は同一性集団であり、だんだんと閉じていく。
自分たちが優先されるから、「ふるさと納税」など、取り合いが起こり、
他のコミュニティは「敵」となる。
インターネットは、
マイノリティがつながりやすくなった半面、
そこに「閉じていく」ことが可能になった。
自分とは主張が違う人たちと
接することなく、あるいは否定するだけで、
過ごせるようになった。
(少なくともネット上では)
それではどんどん世界が狭くなってしまうのではないか。
生きていく、には「他者」との出会いが必要なのでないか。
僕もそう思う。

「まわしよみ新聞をつくろう」(陸奥賢 創元社 2,160円)
には、そのエッセンスが余すところなく、書かれている。
しかも、参考文献はない。
陸奥さんがまわしよみ新聞実践の中で
感じ取って、考えてきたことがすべてだ。
これはすごいなと。
「まわしよみ新聞」の魅力を知るには、
第2章「まわしよみ新聞10のいいね!」を読むのがいいだろう。
この10個の中から、
僕がビビッときた3つを紹介する。
2 司会がいなくてもみんな平等に参加できる
「ノーテーマ」「ノーファシリテーション」だと陸奥さんは言う。
実際やってみると、まさにそんな感じだ。
陸奥さんはみんなが新聞を読み始めた瞬間に、
ソファに寝転んでいたりする。
ひとりひとりが3枚程度「おもしろい」と思う記事を切り抜き、
発表していく。
テーマは様々。ジャンルもいろいろ。
新聞広告を切り抜いてもいい。
これは、「ワークショップ」や「ファシリテーション」
を学んできた僕としては、非常にビックリしたことだ。
司会やテーマがなくても、
自己紹介さえなくても、
みんな楽しそうに新聞切り抜きを発表している。
7 世間を語りながら自分を語り、他者を知る。
まわしよみ新聞は、新聞を通して、
「自分語り」でありながら「世間語り」ができる。
新聞は世間のことが書かれていて、
「誰かに読ませようとして」書かれているメディアなので、
それを元にして話をすると共感が得られやすい。
そして、2枚、3枚と発表していくと、
「あ、この人はこういうことに興味があるんだ」
「こういう考え方するんだ」と他者を知ることになる。
「新聞」という記事を通して、
人を知る、ということだ。
8 「小さい共感」が「話す力」に繋がる。
昨日、長岡でやったまわしよみ新聞は、
1 新聞を読む→切り抜き 15分~20分
2 切り抜いた記事を発表 30分
3 壁新聞を作成 30分
ということでだいたい80分くらいで
「まわしよみ新聞」ができる。
意外に短いのが新聞を読む時間だ。
実はこれには理由があって、
「自分の興味関心にぴったり」な記事というのは、
なかなかない。
だから「強いていうなら関心がある」程度の記事を発表する。
その「好きの度合いが低い」からこそ、小さな共感が生まれるのだ。
怪獣映画好きな人が怪獣映画の記事を
発見して熱く語られても引いてしまって、むしろ共感度は低い。
でも、「こんなのも面白いですよね」
ってさし出されると、「へぇ、おもしろいね」と小さな共感が生まれる。
「他者」と話をするときは「小さな共感」がとても大切である。
これ、まさにそうだなと。
僕が、ミーティング進行の時に
「チューニング」をやっているけど、
それってまさに「小さな共感」のデザインをしているのだなと。
そして、「オープンマインド」をつくる
もっとも大切なことは、
「思ったことを言う」ってことだと思っているので、
「まわしよみ新聞」はそれが見事にデザインされているんだなと思った。
まあ、こんな感じで
エッセンスが詰まりまくっている「まわしよみ新聞をつくろう!」。
場づくりとか、ファシリテーションとか
そういうキーワードを持っている人には
特にオススメの1冊。
あと2冊、僕の手元にありますので、気になる方はお声がけください。
昨日のトークの僕なりの感想は、
僕は、「予測不可能性」こそがエンターテイメントの本質だと思っていて、
それをいかに楽しめるかが人生を楽しむことだと思っている。
では、その「予測不可能性」を誰が(何が)もたらすのか?
といったとき、それは「他者」であるのではないか、と思った。
「他者」とは、「未知なるもの(人)」の総称ではないか。
新聞とは、「新しく聞く」というメディア。
この本の中にも書いてあるけど、
ページを「めくる」ことでどんどん新しい世界、新しい価値観
と出会うことができる。
予測不可能なメディアであり、
かつ、「まわしよみ新聞」はそこに集まっている
「他者」が「おもしろい」と感じた記事が切り出されているので、
それによってもまた「未知なるもの」との出会いがある。
そんな「他者との出会い」
をつくる活動が「まわしよみ新聞」なんだなあと。
そして、陸奥さんは実践の後にこう繰り返す。
「誰か外の人に向けて、貼り出す前提でつくってください。そして貼り出してください」
新たなる他者との出会いを生むための
まわしよみ新聞をつくる、というのだ。
「まわしよみ新聞」3DAYS。
「まわしよみ新聞」というメディアは、「予測不可能性」と「小さな共感の機会」
と「小さな自己表現」を伴った、「他者」との出会いのデザインなのだなあと思った。
ちなみにこの本のタイトルは、
「まわしよみ新聞をつくろう!」であり、徹底した実践ガイトとなっている。
つまり、「やってみよう」っていうこと。
そして、陸奥さんが言うには、「ガイドブック」であって「ルールブック」ではないのだと。
オープンソースであるまわしよみ新聞を実践者が実践し、
そこの場から新たに気づき、新たに出会い、
自分たちなりの「まわしよみ新聞」を展開していくこと、だ。
陸奥さんが昨日の帰り際に言っていた。
「僕は中卒ですから、アクティビストでしかない」
大学の先生のような「アカデミスト」ではないし、
昨今の人文書ブームのような、
「読んだら少し頭がよくなった気がする」という本を書いたのでない。
あくまで実践者(アクティビスト)として、アクションを起こし、
他者と出会い、他者と小さな共感をし、新たな何かを生んでいくこと。
きっとそれが「まわしよみ新聞」から始まった、
陸奥さんのコモンズデザインなのだなあと思った。
さて、僕も実践はじめますか、ね。
「まわしよみ新聞」、一緒にやる人、求む。
★「まわしよみ新聞をつくろう」(陸奥賢 創元社 2,160円)は
僕の手元にあと2冊あります。希望される方はご一報ください
2018年08月25日
「他者」に出会うコモンズ・デザイン
まわしよみ新聞開発者の陸奥賢さん、
内野に来ていただきました!
内野町の「又蔵ベース」で開催。
参加者は12名でした。

まずは直観読みブックマーカー。
これは、本の神様にワンフレーズを聞く、
本占いみたいなものです。
僕がやったのは、

6月に発売された陸奥さんの
「まわしよみ新聞をつくろう」(創元社)です。
愛とは何か。
「1回やれば誰でも簡単にできる」
うーん。
深い。(笑)
ブックマーカーで遊んだあとは、
まったく関係ない本にこっそり挟んでおき、
その本をうっかり手に取った人が
違う世界に興味を持てるきっかけになるような、
そんなデザイン。
そんなブックマーカーの実践をしてからのトーク。
陸奥さんのやっている
「まわしよみ新聞」などのコモンズデザイン。
「まわしよみ新聞をつくろう」には、
2012年からの6年間の実践を通して気づいた
エッセンスがたくさん詰まっている。
特に第4章の「もっと知りたい、まわしよみ新聞」では、
フロー型のテレビやインターネットとは違う、
ストック型メディアである新聞を使うことによる
さまざまな効果が書かれています。
この中にもある「他者に出会う」
というキーワードが、昨日のトークを通しても、
陸奥さんがやっていることの
大きな要素となっているように感じました。
本書では
「共同作業に慣れる」
「会話でもなく対話でもない共話のデザイン」
「ノンバーバルな共同体験」
など、まわしよみ新聞のエッセンスが書かれていて、
それによって、いかに「他者と出会う」ことが大切かと語ります。
大切なのは「他者に出会う」こと。
それを、「まわしよみ新聞」や「直観読みブックマーカー」や
「当事者研究すごろく」などを通じて実践しているのが
陸奥さんの強みだなあと思いました。
それは、僕がいう
「本、本屋をきっかけとした機会提供」
に近いものなのかもしれません。
昨日トークしていて思ったのは、
陸奥さんは
「機会提供」の対象者が、広くて深いんだなあと。
僕は冷たいんだなあというか、
対象者が狭いんだなあと。
僕はおそらく、対象者を限定している。
対象者というのは「お客」と同じことだ。
それは、僕の出発点が
15歳の不登校中学生、シンタロウに出会ったことだったから。
僕は「お客」から出発しているから。
だから、僕にとっては、
「コモンズデザイン」で出会う「他者」であり、その「出会い」を、
顧客である中学生高校生大学生にとって提供したいと思っている。
一方で、「対象者」を設定することは、
「他者」を限定することにつながるのかもしれないと昨日は思った。
陸奥さん的には、
他者っていうのは、想定していない人との出会いであり、
それを生み出すのがまわしよみ新聞などのツール。
だから、まわしよみ新聞をつくったら、
人が見えるところに張り出して、
そこからまた出会いにつなげていくこと。
そういうのを繰り返して行った先にあるもの。
それを見てみたいのだなあと思った。
さて、今日はいよいよまわしよみ新聞の実践と
お笑い集団NAMARAの江口歩代表とのトークです。
トークテーマは、
「越境~コミュニティデザインとコモンズデザイン」
今日もいろいろ学んできます。
参加者まだまだ募集しています。
直接会場へお越しください。
内野に来ていただきました!
内野町の「又蔵ベース」で開催。
参加者は12名でした。

まずは直観読みブックマーカー。
これは、本の神様にワンフレーズを聞く、
本占いみたいなものです。
僕がやったのは、

6月に発売された陸奥さんの
「まわしよみ新聞をつくろう」(創元社)です。
愛とは何か。
「1回やれば誰でも簡単にできる」
うーん。
深い。(笑)
ブックマーカーで遊んだあとは、
まったく関係ない本にこっそり挟んでおき、
その本をうっかり手に取った人が
違う世界に興味を持てるきっかけになるような、
そんなデザイン。
そんなブックマーカーの実践をしてからのトーク。
陸奥さんのやっている
「まわしよみ新聞」などのコモンズデザイン。
「まわしよみ新聞をつくろう」には、
2012年からの6年間の実践を通して気づいた
エッセンスがたくさん詰まっている。
特に第4章の「もっと知りたい、まわしよみ新聞」では、
フロー型のテレビやインターネットとは違う、
ストック型メディアである新聞を使うことによる
さまざまな効果が書かれています。
この中にもある「他者に出会う」
というキーワードが、昨日のトークを通しても、
陸奥さんがやっていることの
大きな要素となっているように感じました。
本書では
「共同作業に慣れる」
「会話でもなく対話でもない共話のデザイン」
「ノンバーバルな共同体験」
など、まわしよみ新聞のエッセンスが書かれていて、
それによって、いかに「他者と出会う」ことが大切かと語ります。
大切なのは「他者に出会う」こと。
それを、「まわしよみ新聞」や「直観読みブックマーカー」や
「当事者研究すごろく」などを通じて実践しているのが
陸奥さんの強みだなあと思いました。
それは、僕がいう
「本、本屋をきっかけとした機会提供」
に近いものなのかもしれません。
昨日トークしていて思ったのは、
陸奥さんは
「機会提供」の対象者が、広くて深いんだなあと。
僕は冷たいんだなあというか、
対象者が狭いんだなあと。
僕はおそらく、対象者を限定している。
対象者というのは「お客」と同じことだ。
それは、僕の出発点が
15歳の不登校中学生、シンタロウに出会ったことだったから。
僕は「お客」から出発しているから。
だから、僕にとっては、
「コモンズデザイン」で出会う「他者」であり、その「出会い」を、
顧客である中学生高校生大学生にとって提供したいと思っている。
一方で、「対象者」を設定することは、
「他者」を限定することにつながるのかもしれないと昨日は思った。
陸奥さん的には、
他者っていうのは、想定していない人との出会いであり、
それを生み出すのがまわしよみ新聞などのツール。
だから、まわしよみ新聞をつくったら、
人が見えるところに張り出して、
そこからまた出会いにつなげていくこと。
そういうのを繰り返して行った先にあるもの。
それを見てみたいのだなあと思った。
さて、今日はいよいよまわしよみ新聞の実践と
お笑い集団NAMARAの江口歩代表とのトークです。
トークテーマは、
「越境~コミュニティデザインとコモンズデザイン」
今日もいろいろ学んできます。
参加者まだまだ募集しています。
直接会場へお越しください。
2018年08月24日
なぜ本なのか、なぜ本屋なのか?
とあるケーブルテレビのインタビューを受ける前の
事前打ち合わせ。
最後に、「なぜ本なのか?」と問われた。
これまで幾度となく聞かれ、
なんて答えたのか覚えていない質問。
気がついたら、本屋だった。
そして、本屋で目指していたのも
「劇場のような本屋、本屋のような劇場」だった。
キャッチコピーは
「気がついたら私も、本屋という舞台の共演者になっていました」
だ。(キャッチコピーとしては長い)
本屋をやる一方で(多方で、か)、
僕はまきどき村で畑と朝ごはんをやり、
ヒーローズファームで大学生の実践型インターンシップ「起業家留学」をプログラムし、
大学生向けの地域プログラムを書き、また大学のコーディネーターとして、
地域活動の立ち上げ支援を行った。
それはなぜなのか?
そもそも本とは、本屋とはなんなのか?
昨日、「かえるライブラリー」の説明をしていて、
「本屋の機能」について説明していた。
僕が考える本屋(あるいは古本屋)におけるもっとも重要な機能は、
「何か面白いものないかなあと」という気持ちだ。
つまり、予測不可能な面白い本(情報)がある、ということだ。
そこに新刊書店であれば、「最近の世の中はどうなっているんだろう」というのが付加される。
ツルハシブックスであれば、そこに集まる人(ほかのお客さん)との出会いも付加される。
野島さんがソトコトに語った「ツルハシブックスにいけば誰かに会えるから」と言ったあれだ。
東京でやっている「暗やみ本屋ハックツ」は、
メッセージで本を選ぶことで普段手にしない本を手に入れたり、
あるいは誰か(寄贈者)の思いを受け取る。といったような機能があるだろう。
僕が現代美術家であるとするならば(この前提。笑)、
すべてのプロジェクトに「問いかけたい(表現したい)」何かがある、はずである。
まきどき村は「豊かさ」の表現だった。
ツルハシブックスは「偶然」という価値の演出だった。
じゃあ、かえるライブラリーは?
そんなことに思いを馳せていると、
1冊の本に出会った。

「中動態の世界」(國分功一郎 医学書院)
僕が本を読む動機の中でもっとも強いのは、
自らの現在や過去の「違和感」や「感動」を解読したいからだ。
そういう意味では、
この「中動態の世界」が僕に拓いてくれたものは
とてつもなく大きい。
僕が何を大切にしているのか、
なぜ本なのか、なぜ本屋なのか。
それは、僕たちが中動態の世界を生きているから、
あるいは僕が生きたいから、なのかもしれない。
「意志」も「未来」も存在しない。
能動と受動が対立するのではなく、
それは中動態から始まっているのだ。
「やりたいことは何か」「将来何になりたいのか?」という問いは
問いが間違っているのではないか、とずっと思っていた。
「意志」と「未来」が存在しないとしたら、
その問いは大きく間違っているのだろう。というか、意味をなさないだろう。
西村佳哲さんがいう、仕事の根っこにある
「あり方、存在」の大切さもここにある。
「場」のチカラって、
それぞれの人が「変状する」のが
それぞれの人の本質に沿っている、
つまり自由が発揮されている状態にあること、だなあと。
「挑戦」とか「目標」とかじゃなくて、
ただ、「結果」が目の前にあって、
他者からの影響も受け続けていて、
そこに対して自分がどのように影響を受け、
またどのように変状していくか。
たぶんそんなのを本屋でやりたいんだ。
なぜ本なのか?
それは、本がもっとも不確実に人に影響を及ぼすからだ。
意図しない変化をもたらすからだ。
なぜ本屋なのか?
それは、本屋空間という場のチカラによって、予測不可能性が高まり、
それによって相互の影響しあうからだ。
目の前の状況から、
いまいるメンバーで何かが起こっていくこと。
それを見届けること。
あるいはそこに自分も参画すること。
そんな「あり方」を僕が望んでいるのかもしれない。
事前打ち合わせ。
最後に、「なぜ本なのか?」と問われた。
これまで幾度となく聞かれ、
なんて答えたのか覚えていない質問。
気がついたら、本屋だった。
そして、本屋で目指していたのも
「劇場のような本屋、本屋のような劇場」だった。
キャッチコピーは
「気がついたら私も、本屋という舞台の共演者になっていました」
だ。(キャッチコピーとしては長い)
本屋をやる一方で(多方で、か)、
僕はまきどき村で畑と朝ごはんをやり、
ヒーローズファームで大学生の実践型インターンシップ「起業家留学」をプログラムし、
大学生向けの地域プログラムを書き、また大学のコーディネーターとして、
地域活動の立ち上げ支援を行った。
それはなぜなのか?
そもそも本とは、本屋とはなんなのか?
昨日、「かえるライブラリー」の説明をしていて、
「本屋の機能」について説明していた。
僕が考える本屋(あるいは古本屋)におけるもっとも重要な機能は、
「何か面白いものないかなあと」という気持ちだ。
つまり、予測不可能な面白い本(情報)がある、ということだ。
そこに新刊書店であれば、「最近の世の中はどうなっているんだろう」というのが付加される。
ツルハシブックスであれば、そこに集まる人(ほかのお客さん)との出会いも付加される。
野島さんがソトコトに語った「ツルハシブックスにいけば誰かに会えるから」と言ったあれだ。
東京でやっている「暗やみ本屋ハックツ」は、
メッセージで本を選ぶことで普段手にしない本を手に入れたり、
あるいは誰か(寄贈者)の思いを受け取る。といったような機能があるだろう。
僕が現代美術家であるとするならば(この前提。笑)、
すべてのプロジェクトに「問いかけたい(表現したい)」何かがある、はずである。
まきどき村は「豊かさ」の表現だった。
ツルハシブックスは「偶然」という価値の演出だった。
じゃあ、かえるライブラリーは?
そんなことに思いを馳せていると、
1冊の本に出会った。

「中動態の世界」(國分功一郎 医学書院)
僕が本を読む動機の中でもっとも強いのは、
自らの現在や過去の「違和感」や「感動」を解読したいからだ。
そういう意味では、
この「中動態の世界」が僕に拓いてくれたものは
とてつもなく大きい。
僕が何を大切にしているのか、
なぜ本なのか、なぜ本屋なのか。
それは、僕たちが中動態の世界を生きているから、
あるいは僕が生きたいから、なのかもしれない。
「意志」も「未来」も存在しない。
能動と受動が対立するのではなく、
それは中動態から始まっているのだ。
「やりたいことは何か」「将来何になりたいのか?」という問いは
問いが間違っているのではないか、とずっと思っていた。
「意志」と「未来」が存在しないとしたら、
その問いは大きく間違っているのだろう。というか、意味をなさないだろう。
西村佳哲さんがいう、仕事の根っこにある
「あり方、存在」の大切さもここにある。
「場」のチカラって、
それぞれの人が「変状する」のが
それぞれの人の本質に沿っている、
つまり自由が発揮されている状態にあること、だなあと。
「挑戦」とか「目標」とかじゃなくて、
ただ、「結果」が目の前にあって、
他者からの影響も受け続けていて、
そこに対して自分がどのように影響を受け、
またどのように変状していくか。
たぶんそんなのを本屋でやりたいんだ。
なぜ本なのか?
それは、本がもっとも不確実に人に影響を及ぼすからだ。
意図しない変化をもたらすからだ。
なぜ本屋なのか?
それは、本屋空間という場のチカラによって、予測不可能性が高まり、
それによって相互の影響しあうからだ。
目の前の状況から、
いまいるメンバーで何かが起こっていくこと。
それを見届けること。
あるいはそこに自分も参画すること。
そんな「あり方」を僕が望んでいるのかもしれない。
2018年08月20日
「やりたいことは何か?」「何になりたいのか?」への違和感

「中動態の世界」(國分功一郎 医学書院)
3月に西村佳哲さんに聞き、
4月にブックスキューブリック箱崎店で購入し、
4か月寝かせておりましたが、
お盆に読んだ「日本文化の論点」(宇野常寛 ちくま新書)
でも言及されていたので、読み始めました。
こんどの週末に行われる
陸奥賢さん、江口歩さんとのコラボに向けて、
この本は読んでおいたほうがいいのではないかと。
この本は、中動態(いま、単語登録しました)
をめぐる旅。
考古学的言語学?人類学的言語学?
とでも言うのだろうか。
國分さんの語り口が、まるで名探偵のように
的を射ていて、とてもワクワクしながら読める。
この週末で第6章まで読みました。
ここらで少しまとめておこうかなと。
まずこの本は
「能動態」(する)と「受動態」(される)という現在の区分のほかに
「中動態」があったとするところから始まる。
~~~以下シビれたところを本書より引用(自分のメモ含む)
実は多くの言語が能動態と受動態という区別を知らない。
責任を負うためには人は能動的でなければならない。
責任を負わせてよいと判断された瞬間に、意志の概念が突如出現する。
完了は、時制であるにもかかわらず、態の区分に干渉する、ということである。
能動と受動の対立においては、するかされるかが問題だった。それに対し、能動と中動の対立においては、主語が過程の外にあるか内にあるかが問題になる。
アリストテレスは意志の実在を認識する必要がなかった。つまりギリシア人は、われわれが「行動の原動力」だと考えているものについての「言葉さえもっていない」のだ。
ギリシア世界には「意志」はなかった。能動態が中動態に対立している世界に「意志」はない。
おそらく、いまに至るまでわれわれを支配している思考、ギリシアに始まった西洋の哲学によってある種の仕方で規定されてきたこの思考は、中動態の抑圧のもとに成立している。
実在する一切のものには、その原因の一つとしての可能態が先行しているはずだという見解は、暗々裏に、未来を真正な時制とすることを否定している。
アレントによれば、未来が未来として認められるためには、未来は過去からの帰結であってはならない。未来は過去からの切断された絶対的な始まりでなければならない。そのような真正な時制としての未来が認められたとき、はじめて、意志に場所が与えられる。始まりを司る能力の存在が認められる。
選択は過去の帰結としてあるが、意志は、過去を断ち切るものとして責任に付随している。
選択は無数の要素の影響を受けざるをえず、意識はそうした要素の一つに過ぎないとしたら、意識は決して万能ではない。しかし、それは無力でもない。
能動と受動を対立させる言語は、行為にかかわる複数の要素にとっての共有財産とでも言うべきこの過程を、もっぱら私の行為として、すなわち、私に帰属させるものとして記述する。出来事を私有化すると言ってもよい。
「する」か「される」かで考える言語、能動態と受動態を対立させる言語は、ただ、「この行為は誰のものか」と問う。
出来事を描写する言語から、行為を行為者へと帰属させる言語への移行。
意志とは行動や技術をある主体に所属させるのを可能にしている装置。
私は姿を現す。つまり、私は現れ、私の姿が現される。そのことについて現在の言語は、「お前の意志は?」と尋問してくるのだ。それは言わば、尋問する言語である。
~~~ここまで引用
どんどん先を読み進めたいところなのだけど。
ギリシア世界には、「意志」は存在しないし、
それに伴って「未来」も存在しない。
過去からつづく流れの中で、状態(状況)としての今がある。
能動態‐受動態という言語体系は、
「この行為は誰のものか?」と問うが、
その問いはそんなに大切なのか?
大切だとしたら、それが大切とされるようになったのはいつからなのか?
そんな問いが浮かぶ。
そこで。
僕の興味ジャンルに、このことを
応用しようとすると、
小学生~大学生が向き合っている(向き合わざるを得ない、強制的に向き合わされている)
次のふたつの問いが浮かんでくる。
「やりたいことは何か?」
「何になりたいのか?」
この二つはまさに「意志」と「未来」を問う
質問なのではないか。
あたりまえだけど、
「言葉」と「世界」は相互に作用している。
「言葉」が「世界」を規定し、
「世界」が「言葉」を規定している。
だから、「やりたいことは何か?」
と問われれば、「やりたいことは何だろう?」
と考え、それに答えようとしてしまう。
でもさ、
そもそも、「意志」や「未来」が存在しないとしたら。
能動態と受動態の対立の世界に生きていなかったとしたら。
もしかしたら、そんなところに
これらふたつの問いの
違和感の正体があるような、ないような気がする本です。
いやあ、これだから本は面白いなあと思いました。
で、この本がどう週末のイベントに関係しているかというと、
陸奥さんのテーマは「コモンズ(共有地)デザイン」
江口さんのテーマは「越境」
大きな意味でふたりは、
「分ける」ということに対して、
チャレンジしているのではないかなと思った。
僕は、そのヒントが「能動態」と「受動態」の対立、
「行為者」や「意志」を確定させようとする言語というか
言語の変遷にあるような気がして、
まあ、たぶん水曜日までに読み終わります。
お楽しみに。
2018年08月16日
「人」にフォーカスする本屋

「日本文化の論点」(宇野常寛 ちくま新書)
お盆読書。
宇野さんの本。
スラスラ読めた。
「メディア」屋の人は必読だと思った。
本屋もそう。
インターネットとはなんだったのか?
AKB現象とは何なのか?
「文化」の役割とは何か?
そんな問いを持っている人に読んでほしい1冊。
キーワードは「想像力」かなあ。
~~~以下一部引用
かつては、宗教がこの想像力の増幅器として機能して、「個」と「公」、「一」と「多」を結びつけていました(祭政一致)。しかし時代が下り、人々が精神の自由を求めるようになると宗教という装置は機能しなくなった。
その代わりに台頭したのが物語(イデオロギー)です。民族や国家の歴史を、個人の人生を意味づける「物語」として機能させることで国民統合を計る、という社会的回路がやがてヨーロッパを中心に標準的になります(国民国家)。
「自分は~民族である/~国民である/~党員である」という物語で、個人の人生の価値を保証することで、「個」と「公」、「一」と「多」を結ぶわけです。このとき大きな役割を果たしたのが新聞やラジオといったマスメディアの存在です。
とくに、すべての国民が同時に同じ番組に耳を傾けることのできるラジオの登場は決定的でした。20世紀前半はこのラジオの威力を用いて、国民の熱狂的な支持を集めることで急進的な独裁政権がいくつか生まれています。ナチス・ドイツやイタリアのファシズム政権がその代表です。
言ってみれば20世紀前半はマスメディアの進化が災いして、それが政治利用されファシズムが台頭し、世界大戦が二度も起こって危うく人生が滅びかけた時代です。
その反省から、20世紀後半の西側諸国では、マスメディアがいかに政治から距離を取るか、政治からの独立性を保つか、が大きな課題になりました。しかしその結果、今度はマスメディアの力が大きくなりすぎて国によっては民主主義が立ち行かなくなっています。
ではどうするか。答えは明白です。
マスメディア「ではない」装置によって「個」と「公」、「一」と「多」を結ぶ以外にありません。ソーシャルメディアがその役割を果たすのです。
これまでのメディアについての議論では、情報化の進行は主に誰もが発信者にも受信者にもなれること、つまり双方向性に力点が置かれていた。
たとえば映画というのは、実際には非常に能動的な観客を対象にしているメディアです。(中略)それに対して、テレビはかなり受動的な視聴者を想定したメディアと言える。より正確に言えば、ダラダラ見たいと考えている視聴者に対応できる番組構成が要求されている。
では、能動性/受動性という観点から考えたとき、インターネットはいかなるメディアだと言えるのか。いや、いかなるユーザーを想定したメディアだといえるのか。それはずばり、その中間です。より正確には、インターネットは映画よりも能動的に扱えるし、テレビよりも受動的に消費できる。
「ここで重要なのは、人間というのはそもそも映画が想定するほど能動的でもなければ、テレビが想定するほど受動的な生き物でもないという点です。」
仮に映画が想定している人間の能動性を100、テレビが想定している能動性を0として考えた場合、人間は0から100のあいだを常に揺れ動いている(あるいは100以上や0以下にもなる)存在です。僕の考えでは、ここにインターネットというメディアの本質があります。
これまで(20世紀)のあいだは情報技術が未発達だったために、人間本来の姿、つまり常にその能動性が変化する主体としての性質に対応することができずに、(能動的な)「観客」や(受動的な)「視聴者」といった固定的な人間像を「想定するしかなかった」と考えるべきでしょう。
人間を二元論的に捉えることが困難になっている。20世紀後半の人間観というのは「能動的かつ理性的な主体=市民」と「受動的かつ感情的な主体=動物」というふたつの側面から人間を捉えようとするもので、前者に対しては規律訓練によって、後者に対しては環境管理によって対応しようとしてきた。
これまでは技術の問題で、人間を中動態として考えることが非常に困難だった。しかし、テクノロジーの発展によってインターネットが登場したことで、僕たちは中動態としての(本来の)人間を可視化することができるようになったわけです。
だからこそ、インターネットについて考えるということは、単にメディアの変化を考えるということに留まらず、「人間という存在をどのようなものとしてイメージしていくことが可能か」という非常に巨大な問いにつながっていくのです。
「若者の街」渋谷から「埼玉の首都」池袋、「サブカルの聖地」下北沢、「オタクの聖地」秋葉原、など特定の都市が若者文化を代表することがなくなり、それぞれのトライブごとに街々がすみ分けるようになってきた。
「秋葉原」という街は若者たちが自分たちの力でー「~が好き」という気持ちで、そこを自分たちの場所に変えていく空間として機能していたからです。
アニメの「聖地」。普通の人にはなんでもない場所が、そのアニメのファンにとっては特別な場所になる。ここではオタクたちがその想像力でなんでもない場所を「意味」と「歴史」を与えている。
かつては「地理」が「文化」を生んでいた。「この町には~な産業が発達した歴史があって、そのために・・・系な施設や商店が多い」云々、といった形式で地理が文化を規定していた。しかし、現代は逆です。文化が地理を規定している、と言えます。
今もオタクたちは郊外のショッピングモールや、ありふれた田舎の駅前の「風景」を自分たちの力で着々と「聖地」に変えていっているのです。
サブカルチャーの歴史とは、半ば創作者であり、半ば消費者である人簿とのコミュニティーたとえばインディーズ作家たちとそのファンたちのコミュニティから文化運動が発生していく、という現象の反復です。
情報化が進行するとコンテンツ(情報)自体でなく、それを媒介としたコミュニケーションこそが価値を帯びる。これはコンテンツビジネスのあり方を根本から書き換えかねない、極めて大きく本質的な変化ななずです。
ゲームというのは、究極的には手段と目的のバランスに介入して、イコールに近づけることで快楽を生むものです。つまり、ゲームを攻略することは手段であると同時に目的でもある。RPGをプレイするとき、レベル上げやアイテムの探索自体が面白くなければならない。
すべてが自己決定=実力で決定されてしまうゲームは攻略の方法が明確に存在するため、人はすぐ飽きてしまう。対してすべてが運で決定されてしまうゲームもまた、人は攻略(介入)の余地がなくおもしろみを感じないのです。
徹底してフェアでオープンな自己決定と、徹底して偶然性に左右される運命。このともに現代社会において信頼を失って久しいもの(そして一見相容れないもの)を奇跡的に両立させている。それが、AKB48の本質なのだと思います。
AKB48も若手芸人たちのM-1グランプリなどの番組も「ゲーミフィケーション」(ゲーム化)の流れの中で、「大きなゲーム」として機能している。
1 個性的なシステムを持つ番組(ゲーム)をプレイすることで魅力が引き出される
2 ゲームの中にいる複数のプレイヤーのうち誰を応援するかは自由
「政治と文学」つまり、「社会と文化」「世界と個人」「システムと内面」がうまく結びついていない。
近代的な(大きな)「物語」が機能しなくなったときの、その代替物としての大きな「ゲーム」の可能性。
<昼の世界>からは見向きもされない<夜の世界>で培われた思想と技術ーここにこの国を変えていく可能性が詰まっている。
<昼の世界>と<夜の世界>のパワーバランスは圧倒的に<昼の世界>。
<夜の世界>が勝っているのは、目に見えない力、つまり「想像力」。<昼の世界>の住人達が思いつかないアイデアやビジョンを見せることで彼らを魅惑して、ワクワクさせて、味方になってもらう、「推して」もらうしかない。
~~~ここまで一部引用
と、またしても引用しすぎ。
ホント、買ってください。笑
AKBとアマゾンが「ロングテール戦略」を取っているという点で
似ていること。
変革を起こすときは、
平氏的アプローチじゃなくて、源氏的アプローチで。
みたいな。
エッセンスの詰まった1冊でした。
序章を読むだけでも、
メディアの変化と歴史について、
なかなか大きな示唆があります。
僕が感じたのは、
「本屋」という「場」、
あるいは小売業という「場」がこれから
どうなっていくのか、っていうこと。
お店が「メディア」であるとすれば、
(僕はそう思っているのだけど)
「ここで重要なのは、人間というのはそもそも映画が想定するほど能動的でもなければ、テレビが想定するほど受動的な生き物でもないという点です。」
たぶんココ。
ここに対応できるツールがインターネットであると
宇野さんは言う。
だから、たぶん、ここの部分を
SNSなどのツールを使って、
本屋というか「お店」がデザインできればいいのだろうと。
おそらくはこれが
今流行っている「ファンクラブ」的なビジネス
になっていくのだ。
ツルハシブックスの「サムライ」制度は、
まさにそのあたりをついていたのだなあと。
この本を読んで、
AKB48的なビジネスの「仕組み」が
やっと読み解けた。
そう読めばいいのか、って思った。
だから、AKBを「総選挙」だと思って、
その手法だけ真似する「総選挙」的なものが世の中にあふれているのだけど。
それは、消費者という主体としてのあなた(の1票)に
フォーカスしているという点では同じだ。
AKBの神髄は、「会いに行けるアイドル」、つまり、
秋葉原の専用劇場に行けば、毎日公演をやっていて、
そこで見れるばかりか、CDについている「握手会参加権」を
行使すれば推しメンと握手ができることだ。
それは、AKBというゲームに自分自身が
「参加」「登場」し、かつゲームの行方に
影響を与えられる、ということである。
そこの意味を理解せず、
「総選挙」という手法だけを真似しても、
AKBほどのビジネスにはならない。
僕は、これからの小さな小売業は
「参加」だけではなく、「ケア」が必要になると思っている。
たとえば、古本屋さんにいて、
「この本はあの人が必要としそうだ」
と思い、購入して店頭に並べる、とか。
この商品は仕事で疲れて
1人暮らしの部屋に帰ってきたときの
こういうシーンで飲んでほしいとか。
それを参加者と一緒に考えていくような、
そんなビジネスになっていく。
そもそも「本屋」っていうのは
そういうビジネスだったのではないか。
本を見ていて、誰かの顔が浮かぶ。
誰かの生活シーンが浮かぶ。
その先の未来を想像する。
宇野さんが最後に
<夜の世界>が勝っているのは、目に見えない力、つまり「想像力」。<昼の世界>の住人達が思いつかないアイデアやビジョンを見せることで彼らを魅惑して、ワクワクさせて、味方になってもらう、「推して」もらうしかない。
こう書いているように、
キーワードは「想像力」だ。目に見えないものに思いを馳せること。
これからの本屋は、そんな想像力を持って、
「人」にフォーカスして、本を並べていくこと。
お客さんが「参加」できる仕組みをつくること。
たぶんそんな感じ。
サムライ制度とか
暗やみ本屋ハックツとか
いい線いってるわ、と改めて思った読書でした。
宇野さん、素敵な本をありがとうございます。
2018年08月13日
17歳に贈りたいマンガ
茨城県日立市の高校で
「ジブンハックツ」という企画が進んでいる。
高校生自ら商店街を訪ねて、
高校生に贈りたい本を集めてくる。
この「高校生に贈りたい本を1冊」というテーマは、なかなか深い。
双方の想像力が問われる。
自らが高校生の時に読んで感銘を受けた本を
オススメする場合もあるし、
「もっと早く読んでおけばよかった」
という本もあるし、
いま、よく売れていて、
高校生に読んでほしいなあと思う本もあると思う。
昨日、
「覇王伝説タケル」というマンガを読み直していた。
久しぶりに読んだら感動しちゃったよ。
ストーリーはいたってワンパターン。(笑)
裏切り続けて、恐怖政治を敷く
人を人とも思わない悪役と戦い、
信と義によって、仲間を増やし、
最終的には天下を取るというストーリー。
当時週刊少年マガジンで連載。
毎週それが楽しみで、コンビニで立ち読みした。
今回読んでみてのハイライトは
19巻の葵四迷が、
自分はニセモノのインチキ軍師
だと告白するところ。
それに対して、タケルは言い放つ。
ニセモノか本物かはどうだっていいと。
おれ自身がニセモノかもしれない、と。
「目の前にやらなきゃいけないことがあった時、
それが王の子であろうとなかろうと関係ねえじゃんか」
と。
いい。
これいい。
17歳に送りたいマンガだわ。
僕は当時きっと、
このマンガを読んで、
「使命」とか「志」とかを学んだ気がする。
他にも
「SHOGUN」と「沈黙の艦隊」
はまさにそんな本だったなあ。
17歳に贈りたいマンガ展、やってみようかなと思った。
それぞれの世代に、それぞれの人生を動かしたマンガがある。
それを集めるのっていいかもしれない。
「ジブンハックツ」という企画が進んでいる。
高校生自ら商店街を訪ねて、
高校生に贈りたい本を集めてくる。
この「高校生に贈りたい本を1冊」というテーマは、なかなか深い。
双方の想像力が問われる。
自らが高校生の時に読んで感銘を受けた本を
オススメする場合もあるし、
「もっと早く読んでおけばよかった」
という本もあるし、
いま、よく売れていて、
高校生に読んでほしいなあと思う本もあると思う。
昨日、
「覇王伝説タケル」というマンガを読み直していた。
久しぶりに読んだら感動しちゃったよ。
ストーリーはいたってワンパターン。(笑)
裏切り続けて、恐怖政治を敷く
人を人とも思わない悪役と戦い、
信と義によって、仲間を増やし、
最終的には天下を取るというストーリー。
当時週刊少年マガジンで連載。
毎週それが楽しみで、コンビニで立ち読みした。
今回読んでみてのハイライトは
19巻の葵四迷が、
自分はニセモノのインチキ軍師
だと告白するところ。
それに対して、タケルは言い放つ。
ニセモノか本物かはどうだっていいと。
おれ自身がニセモノかもしれない、と。
「目の前にやらなきゃいけないことがあった時、
それが王の子であろうとなかろうと関係ねえじゃんか」
と。
いい。
これいい。
17歳に送りたいマンガだわ。
僕は当時きっと、
このマンガを読んで、
「使命」とか「志」とかを学んだ気がする。
他にも
「SHOGUN」と「沈黙の艦隊」
はまさにそんな本だったなあ。
17歳に贈りたいマンガ展、やってみようかなと思った。
それぞれの世代に、それぞれの人生を動かしたマンガがある。
それを集めるのっていいかもしれない。
2018年08月10日
「若さ」という機能
「今の大学生っていろいろ考えててすごいなあと。
僕が大学生の時なんて、ただ遊んでいただけで何も考えてなかった。」
トークイベントなどをしていて、最近違和感を感じる発言。
そんなの当たり前じゃんって。
そして、その発言をした人は、
その大学生と同じ地平に降りてないっていうか、
安全地帯から発言してるっていうか、
僕と君は違うから、って予防線を張っているっていうか、そういう感じ。
昔の大学生よりも今の大学生のほうが優れている。
それは、携帯電話と同じだ。
今の大学1年生は、携帯で言えば、
iphone7みたいなもんだ。
最新の機能(顔認識とか)がついている。
そう考えれば、
今の20代半ばの人たちなんて、
iphone3みたいなもんだよ。
もはや化石だよ。笑。
40代な僕らなんて、
大学時代は携帯電話すらなかった時代
(その頃広末涼子がポケベル宣伝してた)
だから、
僕は、若いというだけでむしろリスペクトというか、
その話を注意深く聞いたほうがいいと思う。
今の最新の感性は何にヒットしているのか、
学んだほうがいいと思う。
高校生に至っては、iphone10みたいなもんだから
より鋭くなっているはずだ。
少し年下の世代を見つけて、
説教したくなるとおじさんになったというらしいのだけど、
(それは大学生でもなってしまうらしい)
「若さ」という機能(つまり感性)に
もっと耳を澄ませてみることが大切なのではないかと思う。
僕が大学生の時なんて、ただ遊んでいただけで何も考えてなかった。」
トークイベントなどをしていて、最近違和感を感じる発言。
そんなの当たり前じゃんって。
そして、その発言をした人は、
その大学生と同じ地平に降りてないっていうか、
安全地帯から発言してるっていうか、
僕と君は違うから、って予防線を張っているっていうか、そういう感じ。
昔の大学生よりも今の大学生のほうが優れている。
それは、携帯電話と同じだ。
今の大学1年生は、携帯で言えば、
iphone7みたいなもんだ。
最新の機能(顔認識とか)がついている。
そう考えれば、
今の20代半ばの人たちなんて、
iphone3みたいなもんだよ。
もはや化石だよ。笑。
40代な僕らなんて、
大学時代は携帯電話すらなかった時代
(その頃広末涼子がポケベル宣伝してた)
だから、
僕は、若いというだけでむしろリスペクトというか、
その話を注意深く聞いたほうがいいと思う。
今の最新の感性は何にヒットしているのか、
学んだほうがいいと思う。
高校生に至っては、iphone10みたいなもんだから
より鋭くなっているはずだ。
少し年下の世代を見つけて、
説教したくなるとおじさんになったというらしいのだけど、
(それは大学生でもなってしまうらしい)
「若さ」という機能(つまり感性)に
もっと耳を澄ませてみることが大切なのではないかと思う。
2018年08月07日
創造力の翼
電車旅。
3冊同時読書。

「一緒に冒険をする」(西村佳哲 弘文堂)
つくばの江本珠理が絶賛していたので積ん読だったのを呼び出してきた。
(大阪・スタンダードブックストアで4月に購入)

「市場って何だろう」(松井彰彦 ちくまプリマー新書)
(甲府・春光堂書店で7月に購入)

「芸術論」(宮島達男 アートダイバー)
(先週、金沢21世紀美術館で購入)
の3冊を同時並行読み。
ちなみに、坂口恭平「隅田川のエジソン」(幻冬舎文庫)
もなぜかカバンに入ってたので読んだ
素敵なタイミングで、
素敵な本に会うなあと思った。
西村さんの本では、
本城慎之介さんの話が響いた。
楽天副社長から、
学校づくりへとシフトする中で
軽井沢の森のようちえんにたどり着き、
そのスタッフをしながら、学校を構想している。
「森のようちえん ぴっぴ」のエピソードがすごい。
子どもはみんな、知っているんだって。
どうやって決めていったらいいのか。
ケンカになったとき、
誰かが泣いているとき、どうしたらいいのか。
答えのない問いへの対応を知っているのだ。
まず、輪になって語る。
ひとりひとりの顔が見えるように。
ひとりひとりが当事者であり、
ひとりひとりが大切である、っていうこと。
そういうのって子どもは知っているんだなと。
いつの間に忘れちゃったのだろうか。
最後に登場する内野加奈子さんが言っている。
~~~ここから引用
私は日本の教育のネガティブな恩恵を直に受けていたなと思います。
「答えがある」という教育。正しい答えがあって、
ちゃんと調べて勉強してゆけばそこに辿り着ける、
という教育をずっと受けてきたと思うんです。
そこから離れるのに少し時間がかかった。
航海術を教わっていたとき、ナイノアに
「僕は君に情報は与えれるけど、知恵はあげることはできない。
機会はあげられるけど経験はあげることはできない。」
と何度も言われた。
「それは自分でやらなきゃいけない作業なんだよ」
ということを教えてもらった。
自分が知ったことを人に伝えることはできる。
けど「体験する」には、本人が自分で動いていかないと。
やっぱり身体を使って感じることが、すごく大切だと思います。
~~~ここまで引用
そうそう。
本当は「答え」などなくて、
「機会」のみが差し出すことができる。
そういうこと。
その機会を生み出すのが「市場」だ。
「市場はヒトとモノ、ヒトとヒトをつなげる場である。
作品(アート)にも市場が必要だ。
市場がなければ僕たちは素晴らしい作品(アート)に出会えない。
それまでお互いに知らなかった人同士が市場を介して
突然結びつく。そのこと自体が市場の力だ。」(「市場ってなんだろう」本文より)
そして、重要なのが自立と依存についての記述
依存先が十分に確保されて、特定の何か、誰かに依存している気がしない状態が自立だ。
たしかにそうだなあと。
特定の何かに依存していると不自由だもんね。
そして最後に、「芸術論」。
これには、シビれるフレーズがたくさん掲載されている。
~~~ここから引用
はっきり言って、「絵で飯は食えない」。誰もがわかっていることだが、
「プロのアーティスト=絵で飯を食う人」という幻想を持ち続ける者は意外に多い。
元来、アートは職業になじまない。職業とは誰かのニーズがあり、
それに応えて初めて成立するものだ。ところが、
アートには他者のニーズがなく、
自らの思いをカタチにするだけだから、そもそも職業とはなり得ない。
ピカソのように絵で食える人は、全体の1パーセントにも満たず、
宝くじを当てるより難しい。したがって、食える/食えないは、
まったくの偶然であると言っても過言ではないのだ。
アーティストはそんなギャンブルのような賭けに、
自分の人生やアートを翻弄されてもいいのだろうか。
私は、アーティストは自分の生活を自分で支え、
なお、自らの思いを納得するまでカタチにし、他者に伝える人間だと考えている。
こう考えていけば、アーティストとは職業ではなく、むしろ生き方になってくる。
アーティストという生き方を選べば、じつはもっと自由になる。
アーティストという「名詞」を目指すのではなく、
アーティストという「形容詞」の生き方を目指してほしい。
~~~ここまで引用
「アート」を「本棚」に「アーティスト」を「本屋」に替えても、同じだろうな、と。
本屋という「形容詞」の生き方を目指す。
たぶんそういうことだ。
この3冊は、まったく別々なようで、
僕が編集すると、
すべて、ひとつのところに向かっているように思う。
「答え」はないということ。
「場」をつくるということ。
「表現」するということ。
「問い」があるということ。
そして、「本屋」である、ということ。
そういうものとして、この3冊を読んだ。
本って素敵だ。
機会しかない。
ヒントしかない。
それをどう学びに変えるか、
力に変えるか、は読んだ人次第だ。
そんな、目的のあいまいな読書をしてしまうような、
興味関心の罠がたくさん仕掛けられているような、
次の世界への扉が無数に存在するような、
そんな本屋になりたいなあ。
最後に「芸術論」から一言。
絵が描けなくても、モノが作れなくても、創造力の翼で芸術家になれるのだ。
3冊同時読書。

「一緒に冒険をする」(西村佳哲 弘文堂)
つくばの江本珠理が絶賛していたので積ん読だったのを呼び出してきた。
(大阪・スタンダードブックストアで4月に購入)

「市場って何だろう」(松井彰彦 ちくまプリマー新書)
(甲府・春光堂書店で7月に購入)

「芸術論」(宮島達男 アートダイバー)
(先週、金沢21世紀美術館で購入)
の3冊を同時並行読み。
ちなみに、坂口恭平「隅田川のエジソン」(幻冬舎文庫)
もなぜかカバンに入ってたので読んだ
素敵なタイミングで、
素敵な本に会うなあと思った。
西村さんの本では、
本城慎之介さんの話が響いた。
楽天副社長から、
学校づくりへとシフトする中で
軽井沢の森のようちえんにたどり着き、
そのスタッフをしながら、学校を構想している。
「森のようちえん ぴっぴ」のエピソードがすごい。
子どもはみんな、知っているんだって。
どうやって決めていったらいいのか。
ケンカになったとき、
誰かが泣いているとき、どうしたらいいのか。
答えのない問いへの対応を知っているのだ。
まず、輪になって語る。
ひとりひとりの顔が見えるように。
ひとりひとりが当事者であり、
ひとりひとりが大切である、っていうこと。
そういうのって子どもは知っているんだなと。
いつの間に忘れちゃったのだろうか。
最後に登場する内野加奈子さんが言っている。
~~~ここから引用
私は日本の教育のネガティブな恩恵を直に受けていたなと思います。
「答えがある」という教育。正しい答えがあって、
ちゃんと調べて勉強してゆけばそこに辿り着ける、
という教育をずっと受けてきたと思うんです。
そこから離れるのに少し時間がかかった。
航海術を教わっていたとき、ナイノアに
「僕は君に情報は与えれるけど、知恵はあげることはできない。
機会はあげられるけど経験はあげることはできない。」
と何度も言われた。
「それは自分でやらなきゃいけない作業なんだよ」
ということを教えてもらった。
自分が知ったことを人に伝えることはできる。
けど「体験する」には、本人が自分で動いていかないと。
やっぱり身体を使って感じることが、すごく大切だと思います。
~~~ここまで引用
そうそう。
本当は「答え」などなくて、
「機会」のみが差し出すことができる。
そういうこと。
その機会を生み出すのが「市場」だ。
「市場はヒトとモノ、ヒトとヒトをつなげる場である。
作品(アート)にも市場が必要だ。
市場がなければ僕たちは素晴らしい作品(アート)に出会えない。
それまでお互いに知らなかった人同士が市場を介して
突然結びつく。そのこと自体が市場の力だ。」(「市場ってなんだろう」本文より)
そして、重要なのが自立と依存についての記述
依存先が十分に確保されて、特定の何か、誰かに依存している気がしない状態が自立だ。
たしかにそうだなあと。
特定の何かに依存していると不自由だもんね。
そして最後に、「芸術論」。
これには、シビれるフレーズがたくさん掲載されている。
~~~ここから引用
はっきり言って、「絵で飯は食えない」。誰もがわかっていることだが、
「プロのアーティスト=絵で飯を食う人」という幻想を持ち続ける者は意外に多い。
元来、アートは職業になじまない。職業とは誰かのニーズがあり、
それに応えて初めて成立するものだ。ところが、
アートには他者のニーズがなく、
自らの思いをカタチにするだけだから、そもそも職業とはなり得ない。
ピカソのように絵で食える人は、全体の1パーセントにも満たず、
宝くじを当てるより難しい。したがって、食える/食えないは、
まったくの偶然であると言っても過言ではないのだ。
アーティストはそんなギャンブルのような賭けに、
自分の人生やアートを翻弄されてもいいのだろうか。
私は、アーティストは自分の生活を自分で支え、
なお、自らの思いを納得するまでカタチにし、他者に伝える人間だと考えている。
こう考えていけば、アーティストとは職業ではなく、むしろ生き方になってくる。
アーティストという生き方を選べば、じつはもっと自由になる。
アーティストという「名詞」を目指すのではなく、
アーティストという「形容詞」の生き方を目指してほしい。
~~~ここまで引用
「アート」を「本棚」に「アーティスト」を「本屋」に替えても、同じだろうな、と。
本屋という「形容詞」の生き方を目指す。
たぶんそういうことだ。
この3冊は、まったく別々なようで、
僕が編集すると、
すべて、ひとつのところに向かっているように思う。
「答え」はないということ。
「場」をつくるということ。
「表現」するということ。
「問い」があるということ。
そして、「本屋」である、ということ。
そういうものとして、この3冊を読んだ。
本って素敵だ。
機会しかない。
ヒントしかない。
それをどう学びに変えるか、
力に変えるか、は読んだ人次第だ。
そんな、目的のあいまいな読書をしてしまうような、
興味関心の罠がたくさん仕掛けられているような、
次の世界への扉が無数に存在するような、
そんな本屋になりたいなあ。
最後に「芸術論」から一言。
絵が描けなくても、モノが作れなくても、創造力の翼で芸術家になれるのだ。
2018年08月06日
「消費財化」という思考停止の罠
「働き方」から「暮らし方」へのシフトが起こっている。
大げさに言えば、「あり方」へのシフトが始まっている。
西村佳哲さんは著書「自分をいかして生きる」の中で
こう語っている。
以下参考ブログ
http://hero.niiblo.jp/e484009.html
(17.2.13東洋的キャリアのつくり方)
http://hero.niiblo.jp/e484019.html
(17.2.14対話型キャリア形成)
http://hero.niiblo.jp/e484047.html
(17.2.17発酵しながら生きる)
~~~あらためて引用
でも本人の実感以外のところから、まるで倫理や徳や常識のように語られる
「働くことは喜びである」といった言い切りには同意しきれない。
それが〈自分の仕事〉ならむろん働くことは喜びになると思うが、
そう思い込まされるようなファシリテーションが社会に施されているとしたら?
そもそもこの、働くことはよいことであるという考え方は、
人類史の途中から姿をあらわしたものだ。
その時々の為政者や権力によって人々に与えられてきた痕跡も見受けられる。
これは労働文化史の領域では決して斬新な視点ではない。
働くことをよしとする価値観は、近世のヨーロッパで生まれ、
キリスト教と産業革命を足がかりに世界へ広がった。
労働や働くことをよしとする考え方は、
共産主義においても資本主義においても機能した。
それは都市化・数量化・産業化の流れに沿って広がった
近代以降の価値観であって、それ以前の社会には、実はあまり見られないという。
人は、より生きているという実感に喜びをおぼえる。
仕事はその感覚を得やすい媒体のひとつである、というだけのことだ。
ただ働くことだけが、わたしたちの生を充足させるわけじゃない。
価値観の形成過程に誘導性も感じられるので、
このことについては、むしろ慎重でいたい。
~~~ここまで引用
そう。
仕事はその感覚を得やすい媒体のひとつである、
ということだけなのだ。
その上で西村さんは
目に見えている仕事を島にたとえ、
そこの目に見えない部分には、
それを支える知識・技術
さらにその下の考え方、価値観
さらにその下にあり方、存在があると説明した。
そう。
西村さんが言っていた「働き方」は
「あり方、存在」を問いかけるようなものだった。
今や、「働き方」が消費財となってしまった感がある。
というか、この社会は、
あらゆるものを消費財としてしまう。
ノマドワーカー。
コワーキング。
パラレルキャリア。
いまや、「働き方」そのものがビジネスとなっている。
そんな中。
イナカレッジインターンが問いかけるもの。
それは「暮らし」であり、「暮らし方」だ。
まあ、「暮らし方」に関しても、
うっかりしていると、「ていねいな暮らし」みたいな
キーワードで消費財化してしまう。
消費財化が別に悪いわけではないのだけど、
その答えを自分の中に求めずに、
他者の考えを取り入れたり、何かを購入することによって
達成できると思うような思考になってしまうことは、
長期的に見れば、本質的には不安なままである。
http://hero.niiblo.jp/e487798.html
「働き方」と「暮らし方」(18.7.23)
イナカレッジの説明会に来た大学生に響いた
キーワードは「暮らし方」だった。
そう、「働き方」は「暮らし方」に包括されている。
そして、暮らしをまず見つめたいということだった。
そういえば、「イナカレッジ」は、2004年10月
新潟県中越地震の復興を目的とした団体が母体だ。
団体がやってきたことは、
よそ者がデザインした計画を押し付けるのではなく、
中山間地の暮らしに寄り添いながら、
「復興」そして「地域の未来」そのものを共に考え、
共に汗を流すことだった。
そこに共通するような「答え」は存在しない。
対話を通して、活動実践を通して、
仮説をつくり、実践して、検証を行い、
また新たな仮説を立てる。
その繰り返ししかない。
たぶん「暮らし」ってそういうものだ。
そもそも不確定要素が多すぎるし。
おそらくは
「働き方」っていうのも同じなんだよね。
ところが、これまで、
というか西村さんも上に書いてあるように
「働くことは美徳である」的な価値観を、
教育によって植えつけられている自分たちは、
「働き方」にさえ「答え」があるような気がして、
「正解」を探してしまう。
それはたぶん思考停止の罠だ。
「暮らし」には正解がない。
「仮説」を立てるには、「感性」を発動させて、
自然の声、住民の声を聴かなければならない。
考え続けて、仮説を検証し続けなきゃならない。
それは終わりのない道だ。
でも、たぶん終わりなんてないんだ。
「価値」とは何か?を問い、
それを「誰に」届けるべきか?
それが仕事であり、
暮らしは「価値」を自分や家族にとどけることだ。
そんな答えのない旅への第1歩となるのが
「暮らし方」インターンなのかもしれない。
なんか、いいネーミングないかなあ。
http://hero.niiblo.jp/e487730.html
これまでの「物語」をつなぎ、これからの「物語」を始めていく(18.7.11)
「保田小魂」に匹敵するような
キーコンセプトを必要としている。
大げさに言えば、「あり方」へのシフトが始まっている。
西村佳哲さんは著書「自分をいかして生きる」の中で
こう語っている。
以下参考ブログ
http://hero.niiblo.jp/e484009.html
(17.2.13東洋的キャリアのつくり方)
http://hero.niiblo.jp/e484019.html
(17.2.14対話型キャリア形成)
http://hero.niiblo.jp/e484047.html
(17.2.17発酵しながら生きる)
~~~あらためて引用
でも本人の実感以外のところから、まるで倫理や徳や常識のように語られる
「働くことは喜びである」といった言い切りには同意しきれない。
それが〈自分の仕事〉ならむろん働くことは喜びになると思うが、
そう思い込まされるようなファシリテーションが社会に施されているとしたら?
そもそもこの、働くことはよいことであるという考え方は、
人類史の途中から姿をあらわしたものだ。
その時々の為政者や権力によって人々に与えられてきた痕跡も見受けられる。
これは労働文化史の領域では決して斬新な視点ではない。
働くことをよしとする価値観は、近世のヨーロッパで生まれ、
キリスト教と産業革命を足がかりに世界へ広がった。
労働や働くことをよしとする考え方は、
共産主義においても資本主義においても機能した。
それは都市化・数量化・産業化の流れに沿って広がった
近代以降の価値観であって、それ以前の社会には、実はあまり見られないという。
人は、より生きているという実感に喜びをおぼえる。
仕事はその感覚を得やすい媒体のひとつである、というだけのことだ。
ただ働くことだけが、わたしたちの生を充足させるわけじゃない。
価値観の形成過程に誘導性も感じられるので、
このことについては、むしろ慎重でいたい。
~~~ここまで引用
そう。
仕事はその感覚を得やすい媒体のひとつである、
ということだけなのだ。
その上で西村さんは
目に見えている仕事を島にたとえ、
そこの目に見えない部分には、
それを支える知識・技術
さらにその下の考え方、価値観
さらにその下にあり方、存在があると説明した。
そう。
西村さんが言っていた「働き方」は
「あり方、存在」を問いかけるようなものだった。
今や、「働き方」が消費財となってしまった感がある。
というか、この社会は、
あらゆるものを消費財としてしまう。
ノマドワーカー。
コワーキング。
パラレルキャリア。
いまや、「働き方」そのものがビジネスとなっている。
そんな中。
イナカレッジインターンが問いかけるもの。
それは「暮らし」であり、「暮らし方」だ。
まあ、「暮らし方」に関しても、
うっかりしていると、「ていねいな暮らし」みたいな
キーワードで消費財化してしまう。
消費財化が別に悪いわけではないのだけど、
その答えを自分の中に求めずに、
他者の考えを取り入れたり、何かを購入することによって
達成できると思うような思考になってしまうことは、
長期的に見れば、本質的には不安なままである。
http://hero.niiblo.jp/e487798.html
「働き方」と「暮らし方」(18.7.23)
イナカレッジの説明会に来た大学生に響いた
キーワードは「暮らし方」だった。
そう、「働き方」は「暮らし方」に包括されている。
そして、暮らしをまず見つめたいということだった。
そういえば、「イナカレッジ」は、2004年10月
新潟県中越地震の復興を目的とした団体が母体だ。
団体がやってきたことは、
よそ者がデザインした計画を押し付けるのではなく、
中山間地の暮らしに寄り添いながら、
「復興」そして「地域の未来」そのものを共に考え、
共に汗を流すことだった。
そこに共通するような「答え」は存在しない。
対話を通して、活動実践を通して、
仮説をつくり、実践して、検証を行い、
また新たな仮説を立てる。
その繰り返ししかない。
たぶん「暮らし」ってそういうものだ。
そもそも不確定要素が多すぎるし。
おそらくは
「働き方」っていうのも同じなんだよね。
ところが、これまで、
というか西村さんも上に書いてあるように
「働くことは美徳である」的な価値観を、
教育によって植えつけられている自分たちは、
「働き方」にさえ「答え」があるような気がして、
「正解」を探してしまう。
それはたぶん思考停止の罠だ。
「暮らし」には正解がない。
「仮説」を立てるには、「感性」を発動させて、
自然の声、住民の声を聴かなければならない。
考え続けて、仮説を検証し続けなきゃならない。
それは終わりのない道だ。
でも、たぶん終わりなんてないんだ。
「価値」とは何か?を問い、
それを「誰に」届けるべきか?
それが仕事であり、
暮らしは「価値」を自分や家族にとどけることだ。
そんな答えのない旅への第1歩となるのが
「暮らし方」インターンなのかもしれない。
なんか、いいネーミングないかなあ。
http://hero.niiblo.jp/e487730.html
これまでの「物語」をつなぎ、これからの「物語」を始めていく(18.7.11)
「保田小魂」に匹敵するような
キーコンセプトを必要としている。
2018年08月03日
「少数派である」ということ
少数派であるということ。
それは多数派ではないということ。
その意味でしかない。
少数派は、異常ではない。
多数派が正常ではないように。
でも、不安になるんだよ、少数派は。
多数派はなぜか自分たちが正しいと思っちゃうんだよ。
「学校」っていうシステムは、
「多数派」を作ってきたのではないか。
「少数派」もしくは「ひとり」にとっては
生きづらいシステムを作ってきたのではないか。
「社会」の中においていつも人は、
「アイデンティティ」(自分らしさ)不安にさらされている。
それを、
「多数派」が支配する社会は、
マズローの欲求5段階説が説明するように、
生理的欲求⇒安全欲求⇒所属と愛の欲求⇒承認欲求⇒自己実現欲求
「所属と愛」を会社と家庭で満たし、
(満たすようなシステムをつくり)
人を「多数派」にしてきた。
しかし、いま、その前提が崩れているのだ。
人口が増え続けること。
地方や他国から搾取し続けること。
そのような条件下にのみ、
そのシステムの維持は可能であったのではないか。
だから、
会社や地域といったコミュニティは溶解した今。
承認不安と同時に、所属の不安を感じている。
つまり、マズローの3段階目以降が溶け出している、
とも言えるだろう。
自己実現と、承認と所属が
それぞれを前提とせずに絡み合っている。
この春から自由の身となって、
自分とは何か?という問いを
大学生並みに問いかけている。
過去を振り返ったりしている。
昨日も金沢で20年ぶりに再会した谷内くんと
地域のプラットフォームについて話していて
なんか、1週間ぶりにあったかのような会話で
なんだかうれしかった。

僕は「畑は人と人をつなぐ」と直感して畑をやり、
不登校の中学生シンタロウに出会って問いをもらい、
小学生と神社で遊んだり、大学生の挑戦の舞台をつくったり、
試行錯誤の結果、本屋になった。
やってくる大学生の悩みを聞いて、
また問いをもらい、
その問いを解き明かしたいと大学職員をやってみた。
「やりたいことがわからない」の社会学
がテーマだ。
思想的には、
大学時代に出会った宮澤賢治先生の「芸術家であれ」
というメッセージと
自然農実践家の沖津一陽さんの
「ダイコンがダイコンを全うするように私は私を全うする」と
「小説吉田松陰」に書かれていた野山獄のエピソードでの
「学びあいで希望が生まれる」
が僕の中で大きい。


今回の旅は、
七尾で行われた高校生と大学生の座談会的なものの見学でした。
振り返りの時間も担当させてもらいました。
「予想できた」「予想できなかった」
「よかったこと」「わるかったこと」
マトリクスの振り返りをした。
大切なのは
「予想できなかったよかったこと」で
その人しか知らない(気づかない)具体的なエピソードが
出るということ。
参加者のこの人に、こんなことを言われた。
とか
あの時間にあの子、いい顔してた。
とか
そういうことが出てくること。
それこそがイベントの「価値」なのだ。
そしてそれを出すためには、
ひとりひとりの「顧客」にもっとフォーカスしなければならない。
僕は本屋(本を売っている)であり、
現代美術家として、「本屋のような劇場」をつくっていて、
高校生、大学生、20代社会人といったキーワードでの
場の設計者であったりファシリテーターであったりする。
キーワードは、
「少数派」であり、「ひとり」かもしれないと思った。
多くの人が「ひとり」であり、「少数派」である。
しかし社会システム、学校システムは「多数派」を要求してくる。
そのほうが効率的だからだ。
でもそれって、
「効率的」が価値を持つ時代、社会にのみ有効なのではないのか。
所属の欲求、承認の欲求、自己実現の欲求が溶け出しているいま、
僕は本屋として、現代美術家として、場の設計者・ファシリテーターとして、
「機会提供」を続けていこうと思った。
ある人に、「機会提供」の結果に責任を持たないのことは無責任じゃないのか?
という問われた。
それは少数派だから、そう言われるのではないか。
多数派な学校教育であれ、その機会提供の責任は同程度にある、つまりいずれも責任はあまりないのではないか。
と僕は思っている。
そんな誕生日の朝です。
新しい1年もよろしくお願いします。
それは多数派ではないということ。
その意味でしかない。
少数派は、異常ではない。
多数派が正常ではないように。
でも、不安になるんだよ、少数派は。
多数派はなぜか自分たちが正しいと思っちゃうんだよ。
「学校」っていうシステムは、
「多数派」を作ってきたのではないか。
「少数派」もしくは「ひとり」にとっては
生きづらいシステムを作ってきたのではないか。
「社会」の中においていつも人は、
「アイデンティティ」(自分らしさ)不安にさらされている。
それを、
「多数派」が支配する社会は、
マズローの欲求5段階説が説明するように、
生理的欲求⇒安全欲求⇒所属と愛の欲求⇒承認欲求⇒自己実現欲求
「所属と愛」を会社と家庭で満たし、
(満たすようなシステムをつくり)
人を「多数派」にしてきた。
しかし、いま、その前提が崩れているのだ。
人口が増え続けること。
地方や他国から搾取し続けること。
そのような条件下にのみ、
そのシステムの維持は可能であったのではないか。
だから、
会社や地域といったコミュニティは溶解した今。
承認不安と同時に、所属の不安を感じている。
つまり、マズローの3段階目以降が溶け出している、
とも言えるだろう。
自己実現と、承認と所属が
それぞれを前提とせずに絡み合っている。
この春から自由の身となって、
自分とは何か?という問いを
大学生並みに問いかけている。
過去を振り返ったりしている。
昨日も金沢で20年ぶりに再会した谷内くんと
地域のプラットフォームについて話していて
なんか、1週間ぶりにあったかのような会話で
なんだかうれしかった。

僕は「畑は人と人をつなぐ」と直感して畑をやり、
不登校の中学生シンタロウに出会って問いをもらい、
小学生と神社で遊んだり、大学生の挑戦の舞台をつくったり、
試行錯誤の結果、本屋になった。
やってくる大学生の悩みを聞いて、
また問いをもらい、
その問いを解き明かしたいと大学職員をやってみた。
「やりたいことがわからない」の社会学
がテーマだ。
思想的には、
大学時代に出会った宮澤賢治先生の「芸術家であれ」
というメッセージと
自然農実践家の沖津一陽さんの
「ダイコンがダイコンを全うするように私は私を全うする」と
「小説吉田松陰」に書かれていた野山獄のエピソードでの
「学びあいで希望が生まれる」
が僕の中で大きい。


今回の旅は、
七尾で行われた高校生と大学生の座談会的なものの見学でした。
振り返りの時間も担当させてもらいました。
「予想できた」「予想できなかった」
「よかったこと」「わるかったこと」
マトリクスの振り返りをした。
大切なのは
「予想できなかったよかったこと」で
その人しか知らない(気づかない)具体的なエピソードが
出るということ。
参加者のこの人に、こんなことを言われた。
とか
あの時間にあの子、いい顔してた。
とか
そういうことが出てくること。
それこそがイベントの「価値」なのだ。
そしてそれを出すためには、
ひとりひとりの「顧客」にもっとフォーカスしなければならない。
僕は本屋(本を売っている)であり、
現代美術家として、「本屋のような劇場」をつくっていて、
高校生、大学生、20代社会人といったキーワードでの
場の設計者であったりファシリテーターであったりする。
キーワードは、
「少数派」であり、「ひとり」かもしれないと思った。
多くの人が「ひとり」であり、「少数派」である。
しかし社会システム、学校システムは「多数派」を要求してくる。
そのほうが効率的だからだ。
でもそれって、
「効率的」が価値を持つ時代、社会にのみ有効なのではないのか。
所属の欲求、承認の欲求、自己実現の欲求が溶け出しているいま、
僕は本屋として、現代美術家として、場の設計者・ファシリテーターとして、
「機会提供」を続けていこうと思った。
ある人に、「機会提供」の結果に責任を持たないのことは無責任じゃないのか?
という問われた。
それは少数派だから、そう言われるのではないか。
多数派な学校教育であれ、その機会提供の責任は同程度にある、つまりいずれも責任はあまりないのではないか。
と僕は思っている。
そんな誕生日の朝です。
新しい1年もよろしくお願いします。




