2021年05月25日
プレイスでもコミュニティでもなく

「イドコロをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)
オンライン劇場ツルハシブックス1周年記念のゲストにも来ていただいた
伊藤さんの新刊。
いまこそ、読む本。
って感じです。
サブタイトルが「乱世で正気を失わないための暮らし方」なのですが、これ、まさに。
「思考の免疫系」という切り口で、現代社会の様々な罠・誘惑に対処していく必要性を語ります。
まずは「イドコロ」の定義から。
イドコロはコミュニティでもなく、あくまで人がいる「淀み」であることも重要な認識である。たまたま居合わせた人が適当な範囲で交流することが正気を保ち、元気でいることにつながる。そういう人が居合わせる淀みが、アクセスしやすいところに複数あるのが暮らしやすい世の中であると思う。
小さな広場たる「イドコロ」をつくること。自分の意識だけに頼らず正気を失いにくい環境について考え、それぞれを身の回りに整備することで全体として心の健康を保ちやすい条件を整えていく作戦だ。
井戸端会議は井戸という共有している家事インフラを起点にしたイドコロである。
ハードと、アプリと、研修。3つがそろって初めてイドコロになる。
正気を失わないために、必要なのは1つの「コミュニティ」ではなく複数の「イドコロ」。そしてそれはひとりでも創ることができる。
正気を失わせる精神的な病原菌が世の中に溢れていて、それに対処するには身体的な免疫と同じ構造が必要。それは複雑系であり意図して設計する必要がある。
自分が元気になる「場」を複数個持つこと。それは必ずしも他者とのコミュニケーションを必要としない。
~~~ここまで。
そうそう。
「イドコロ」は「コミュニティ」ではないのです。
コミュニティはひとりでは作れず、外部があり、メンバーシップがあり、もしかしたら目的・目標があり、その場合は役割と責任が発生する。「イドコロ」はひとりでも成立し、境界があいまいである。
オンラインツルハシで一番印象に残った一言は、「イドコロ」を通して思考の余白をつくる、でした。
あー、なるほど。
正気を失わないってそういうことかと。
生活の余白だけじゃなく、思考の余白が無くなっていくと、人は正気を失ってしまうんだ。
イドコロを意識して持って(作って)いくことがとても大切になっていくんだなと。
オンラインツルハシの第3部は新潟市の畑サークル「まきどき村」のトークだったのだけど。
※現在屋根葺き替えのクラウドファンディング中です。
https://camp-fire.jp/projects/view/410826
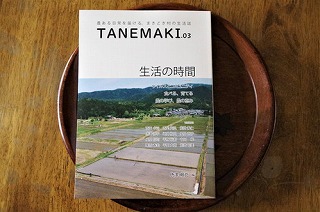
https://karasawa.thebase.in/
こちらの冊子TANEMAKI3にも紹介されているけど、
まきどき村ってみんなにとっての「イドコロ」なんだなあと。
この冊子の終わりに紹介されている「システム」と「生活世界」っていう対比も、まさにそれで。
いつのまにか「システム」が肥大化して、生活世界がそれに取り込まれて、僕たちは「イドコロ」を失った。
「社会人になる」とは、「システムに適応する」とほぼ同義語となっている。
しかし。多くの人たちが実感しているように、「システムに適応する」だけでは「生きられない」のだ。(「社会人」にはなれるけど)
「イドコロをつくる」には、「自然系イドコロ」(仕事や生活に関わる、継続性が高いもの)と「獲得系イドコロ」(強い趣味の集まりや、お店や公園など
の場を活用した比較的インスタントなもの)という分類というように表現されているけど、「まきどき村」という活動は、「獲得系イドコロ」でありながらも、その背景に農や地域といった時間的な長さ(まきどき村的に言えば「営み」)があるので、「イドコロ」として魅力的なのではないか、と思った。
また、まきどき村を取材した大学生に衝撃を与えた、「目的がない」ということも、イドコロにとってとても重要なのだと、伊藤さんも言っている。
~~~
何か明確な目的がある集団は、プレッシャーがある。目的がなければそもそも利害関係も生じない。そういう集まりは、生産性がないと無駄扱いされるが、正気を保つには欠かせないものだと思う。
会話と共同作業によって友情は維持される。
人と人が直接会話・対話するのではなくて、何かを介してコミュニケーションするということ。
~~~
僕たちは「イドコロ」を必要としている。そしてそれは、「システム」(仕事場、経済社会)にも、「生活世界」(暮らし、地域社会)にも複数個あることが必要である。
そんな意識を持つこと。
働く暮らす場所として魅力ある地域とは、そんな「イドコロ」をつくる場(可能性)がたくさんある地域のことなのだろうなと思った。
単なる場(プレイス)でも、役割を果たさなければならないコミュニティでもなく、無数の「イドコロ」をつくっていくこと。そしてそれを意識していくこと。
「イドコロ」というコンセプトは、この町をさらに魅力的にすると感じている。
2021年05月02日
そうして「人生」は創造される

「顧客消滅」時代のマーケティング(小阪裕司 PHPビジネス新書)
ひさしぶりの小阪さんの1冊。
相変わらずシビれる本を書いてくれる。
この本で特に重要なのは「フロー」と「ストック」
「フロー」
・流れていくもの
・新規客、一見客
・人通りの多い場所、目立つ場所への立地が重要
・広告、SEOなどで集客。1日当たりの利用者数や売り上げを重視
・景気変動の影響大
「ストック」
・貯蓄されたもの
・常連客、リピーター、会員、ファン
・立地はあまり関係なく、継続的なコミュニケーションが重要
・「顧客数」や顧客リストを重視
・景気変動の影響少
コロナ禍において伸びた店のうちの多くが
顧客リストなどのストックのお客さんへのアプローチをかけて、成果を上げた。
「フロー」と「ストック」という視点、切り口、面白いなと。
「関係人口」的に言えば、地域おこし協力隊とか、地域みらい留学への参加生徒は、
彼らはフローとストックのあいだ、「期間限定ストック」とでも呼ぼうかを行き来している。
この本の僕的なハイライトは以下のところ
~~~ここから引用
そうして「市場」は創造される。「市場」とは、まるで元からあったもののようによく語られるが、その本質は、こういうものだ。誰かが「価値」を具現化し、世に送り出す。受け手の感性と響きあって「買う」という行動が生まれる。そこに生み出されたものが「市場」だ。
ビジネスとは、「自分のミッションとは何か」という創造活動と、日々の商売によって売り上げを上げていくという問題解決行動を同時並行で進めていくべきものである。
そしてミッションとは、自分が顧客に価値を提供しているうちに、「あ、自分はこういう部分が評価されるのか」と気づいていく中で見つかっていくものだ。それはどんな小さなサービスでも、何億円、何百億円のビジネスでも同じだ。
さらに言えば、そうして決まったミッションも不変というわけではない。ミッションは毎日変わってもいい。
アートとしてのビジネスでは、判断基準は「儲かるか/儲からないか」ではない。「好きか/好きじゃないか」、「楽しいか/楽しくないか」、「美しいか/美しくないか」、そういう基準である。
~~~ここまで引用
そうそう!それそれ!
みたいな。
ツルハシブックス閉店の最大の理由もまさにこれ。常連さん的な人が店を占有する姿を見て、美しくないと感じてしまったからだもんなあ。
逆にスタッフで企画して不用品のバザーまでやった「家賃フェス」や「To you(灯油)フェス」は、僕的には創造的な美しい活動だった。
「美しいか/美しくないか」、それが一番大事だと思う。
そしてこの一節、
ビジネスとは、「自分のミッションとは何か」という創造活動と、日々の商売によって売り上げを上げていくという問題解決行動を同時並行で進めていくべきものである。
これさ、まさに「探究的学び」と同じじゃないか。
「自分のミッションとは何か?」という創造活動と、「出された課題をどう解決するか?」という問題解決行動を同時並行で進めていくもの、ではないのか?
そしてこれ。
そしてミッションとは、自分が顧客に価値を提供しているうちに、「あ、自分はこういう部分が評価されるのか」と気づいていく中で見つかっていくものだ。それはどんな小さなサービスでも、何億円、何百億円のビジネスでも同じだ。
これはまさに、イベントなどの「場」に巻き込まれて、場やチームに溶け込んでいく中で、「あ、自分はこういう部分が評価されるのか」と気づいていく中で見つかっていく、ということなのではないか?
そしてその「ミッション」こそが高校生大学生が抱えている最大の悩みである「やりたいことは何か?」に対応するものなのではないか?
「ミッション」も「やりたいこと」も毎日変わってもいい。とっとと行動を始めることだ。
さらにこれ。
アートとしてのビジネスでは、判断基準は「儲かるか/儲からないか」ではない。「好きか/好きじゃないか」、「楽しいか/楽しくないか」、「美しいか/美しくないか」、そういう基準である。
これを「人生」に置き換える。
「アートとしての人生」では、判断基準は「効率的に稼げるか/稼げないか」ではない。「好きか/好きじゃないか」、「楽しいか/楽しくないか」、「美しいか/美しくないか」、そういう基準である。
これだよ、これ。探究的学びも同じだ。「美しいか/美しくないか」を基準に、やってみて、ふりかえり、進んでいくこと。そういうことなんじゃないかと。
ラストはこれ。
そうして「市場」は創造される。「市場」とは、まるで元からあったもののようによく語られるが、その本質は、こういうものだ。誰かが「価値」を具現化し、世に送り出す。受け手の感性と響きあって「買う」という行動が生まれる。そこに生み出されたものが「市場」だ。
これだ。
そうして「人生」は創造される。「人生」とは、まるで元からそれがあったもののように語られるが、その本質は、こういうものだ。自分が感じた「価値」を具現化し、世に送り出す。受け手の感性と響き合って、「共創」という場が生まれる。そこから生み出されたものが「人生」だ。
僕がつくりたいのは、そういう活動であり、「場」なんだなと、あらためて思い出させてくれた1冊でした。




