2016年12月31日
「学校」から「市場」へ
「学校」という仕組みは、
近代社会の成立とともに成立した。
一斉授業
集団行動
上意下達
それは、おそらく、
工場や軍隊で機能する人々を養成するためであった。
富国強兵。
それがないと、諸外国に侵略されてしまう。
そんな危機感の中、
明治維新後、我が国は急速に近代化した。
そしてそれは、一時期成功し、また失敗したかに見えた。
しかし、第二次世界大戦後。
第二次産業革命の中でふたたび花を開く。
工業社会。
人口が増え続け(人口ボーナス)
それに伴った家電製品が売れ続け、
かつ、安価な労働力が提供され続ける。
それがかみ合った結果、
空前の経済成長が起こった。
そこに「学校」あるいは「教育」は大きく機能した。
2016年11月21日 20代の宿題
http://hero.niiblo.jp/e482895.html
ところが。
時代のほうが変わってしまった。
もう、家電は売れない。
全世帯に行き渡ってしまったから。
人口は増え続けてはいないから。
日本の人件費は上昇し、
海外との価格競争に勝てない企業は、
工場を海外に移転して生き残りを図る。
売るのも当然海外の市場だ。
もう、前提が変わってしまっているのだ。
それなのに、「学校」「教育」は
構造的にはあまり変わっていない。
多くの場合、高校まで、
一斉授業、集団行動、上意下達
を叩き込まれる。
そこで、「人と違っていること」を
悪いことだと思い、個性を抑え込むことも多い。
不登校であること、マイノリティであることで、
「世間」に対して負い目を感じてしまう。
ところが大学に入った瞬間に
個性は武器となり、就職活動ではそれが問われる。
もう、「学校」ではないのかもしれない。
いや、今でも、
大きな組織に入って、働こうと思うのならば、
集団行動、上意下達は必須の条件だろう。
しかし、もし、
自分の個性を生かした
スモールビジネスを興していくことを
将来としてイメージするならば、
そのチカラは「学校」だけでは、
磨かれないのかもしれない。
いや、「学校」ではむしろ、
そのチカラが削がれていくかもしれない。
そのチカラとは、
「感性」であり、「想像力」であり、「創造力」だ。
だから、
「学校」ではなく、「市場」なのかもしれないと思った。
「店」の語源は「見世」、つまり、
誰かに見せるためのものだった。
現金をやりとりするかしないかにかかわらず、
何かを「見世」る、
そんな場をつくることが、
これからの「学び」の場になっていくのではないか、
かつてはそれを学びの場として、
人は考え、試行錯誤し、自分なりの生き方を
探していったのではないか。
「学校」から「市場」へ。
未来がそこにあるような気がした、12月29日のミーティングだった。
近代社会の成立とともに成立した。
一斉授業
集団行動
上意下達
それは、おそらく、
工場や軍隊で機能する人々を養成するためであった。
富国強兵。
それがないと、諸外国に侵略されてしまう。
そんな危機感の中、
明治維新後、我が国は急速に近代化した。
そしてそれは、一時期成功し、また失敗したかに見えた。
しかし、第二次世界大戦後。
第二次産業革命の中でふたたび花を開く。
工業社会。
人口が増え続け(人口ボーナス)
それに伴った家電製品が売れ続け、
かつ、安価な労働力が提供され続ける。
それがかみ合った結果、
空前の経済成長が起こった。
そこに「学校」あるいは「教育」は大きく機能した。
2016年11月21日 20代の宿題
http://hero.niiblo.jp/e482895.html
ところが。
時代のほうが変わってしまった。
もう、家電は売れない。
全世帯に行き渡ってしまったから。
人口は増え続けてはいないから。
日本の人件費は上昇し、
海外との価格競争に勝てない企業は、
工場を海外に移転して生き残りを図る。
売るのも当然海外の市場だ。
もう、前提が変わってしまっているのだ。
それなのに、「学校」「教育」は
構造的にはあまり変わっていない。
多くの場合、高校まで、
一斉授業、集団行動、上意下達
を叩き込まれる。
そこで、「人と違っていること」を
悪いことだと思い、個性を抑え込むことも多い。
不登校であること、マイノリティであることで、
「世間」に対して負い目を感じてしまう。
ところが大学に入った瞬間に
個性は武器となり、就職活動ではそれが問われる。
もう、「学校」ではないのかもしれない。
いや、今でも、
大きな組織に入って、働こうと思うのならば、
集団行動、上意下達は必須の条件だろう。
しかし、もし、
自分の個性を生かした
スモールビジネスを興していくことを
将来としてイメージするならば、
そのチカラは「学校」だけでは、
磨かれないのかもしれない。
いや、「学校」ではむしろ、
そのチカラが削がれていくかもしれない。
そのチカラとは、
「感性」であり、「想像力」であり、「創造力」だ。
だから、
「学校」ではなく、「市場」なのかもしれないと思った。
「店」の語源は「見世」、つまり、
誰かに見せるためのものだった。
現金をやりとりするかしないかにかかわらず、
何かを「見世」る、
そんな場をつくることが、
これからの「学び」の場になっていくのではないか、
かつてはそれを学びの場として、
人は考え、試行錯誤し、自分なりの生き方を
探していったのではないか。
「学校」から「市場」へ。
未来がそこにあるような気がした、12月29日のミーティングだった。
2016年12月29日
「自分」を超えて
19歳に贈りたい本。
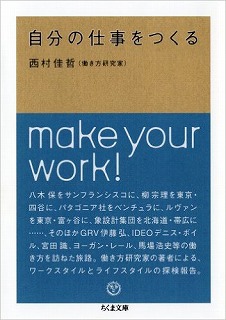
僕が選んだのは、
「自分の仕事をつくる」(西村佳哲 晶文社&ちくま文庫)
いま、水戸市の成人式のウラで、
19歳。本で感じる「これから」展が準備中。
19歳に贈りたい本を集めている。
公式Twitterはこちら
https://twitter.com/meets_for19
僕が1冊を選ぶとしたら、
いっぱいあるのだけど、
「隅田川のエジソン」とかも素敵だなあと思うのだけど。
最近あらためて読んでタイムリーだったので、
この本にします。
26日に、まだ読み途中だった本を、
「これから」展の共同代表に渡して、
27日に、高田馬場で買い戻して、
28日に、読み終わりました。
いやあ、熱い。
ラスト、シビれます。
「働き方研究家」西村さんの原点。
仕事とは何か?
働くとは?
ビシバシ、問いかけられます。
少しだけ紹介
「たったひとつの言葉も、人の口を割って出てくるまでには、
その内面で、時には何年間にも渡る旅をしている。
デザインもモノづくりも同様だ。
その人が感じた世界、経験した出来事がそこに結晶化する。」
「個人を掘り下げることで、ある種の普遍性に到達すること。
自分の底の方の壁を抜けて、他の人にも価値のある何かを伝えることは、
表現に関わる人すべての課題だ。」
「仕事を通じて、自分を証明する必要はない。
というか、それはしてはいけないことだ。最大の敵は常に自意識である。
個性的であろうとするよりも、ただ無我夢中でやるほうが、結果として個性的な仕事が生まれる。」
「その人が欲しているけれど誰にも明かさずにいる、
あるいは本人自身まだ気づいていない何かを、
これ?といって差し出すことが出来たら、それは最高のギフトになる。」
「デザインという仕事はまさにそうありたいものだし、デザインに限らず、
この世界のあらゆる仕事がそのようにして成されたら、どんなにいいだろう。
その時、仕事に対して戻される言葉はありがとうになる。」
素敵だ、素敵。
仕事ってそういうギフトなんだよね。
この前読んだ、マーケティング4.0って根本的には、
自分を掘って掘って、掘った後に、
他者とつながれる地中深くのマグマに到達して、
それをサービスや商品としてアウトプットすることなのだろうなと。
「自分」という存在を超えて、
深く深く掘っていたったときに現れる何か。
それを提供していくことなのだろうと思う。
人生に、将来に悩める19歳に、
僕はこの本を贈ります。
すべての仕事は、「自分の仕事」になっていく。
そしてそれは「自分」を超えたところにある。
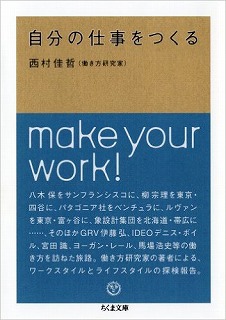
僕が選んだのは、
「自分の仕事をつくる」(西村佳哲 晶文社&ちくま文庫)
いま、水戸市の成人式のウラで、
19歳。本で感じる「これから」展が準備中。
19歳に贈りたい本を集めている。
公式Twitterはこちら
https://twitter.com/meets_for19
僕が1冊を選ぶとしたら、
いっぱいあるのだけど、
「隅田川のエジソン」とかも素敵だなあと思うのだけど。
最近あらためて読んでタイムリーだったので、
この本にします。
26日に、まだ読み途中だった本を、
「これから」展の共同代表に渡して、
27日に、高田馬場で買い戻して、
28日に、読み終わりました。
いやあ、熱い。
ラスト、シビれます。
「働き方研究家」西村さんの原点。
仕事とは何か?
働くとは?
ビシバシ、問いかけられます。
少しだけ紹介
「たったひとつの言葉も、人の口を割って出てくるまでには、
その内面で、時には何年間にも渡る旅をしている。
デザインもモノづくりも同様だ。
その人が感じた世界、経験した出来事がそこに結晶化する。」
「個人を掘り下げることで、ある種の普遍性に到達すること。
自分の底の方の壁を抜けて、他の人にも価値のある何かを伝えることは、
表現に関わる人すべての課題だ。」
「仕事を通じて、自分を証明する必要はない。
というか、それはしてはいけないことだ。最大の敵は常に自意識である。
個性的であろうとするよりも、ただ無我夢中でやるほうが、結果として個性的な仕事が生まれる。」
「その人が欲しているけれど誰にも明かさずにいる、
あるいは本人自身まだ気づいていない何かを、
これ?といって差し出すことが出来たら、それは最高のギフトになる。」
「デザインという仕事はまさにそうありたいものだし、デザインに限らず、
この世界のあらゆる仕事がそのようにして成されたら、どんなにいいだろう。
その時、仕事に対して戻される言葉はありがとうになる。」
素敵だ、素敵。
仕事ってそういうギフトなんだよね。
この前読んだ、マーケティング4.0って根本的には、
自分を掘って掘って、掘った後に、
他者とつながれる地中深くのマグマに到達して、
それをサービスや商品としてアウトプットすることなのだろうなと。
「自分」という存在を超えて、
深く深く掘っていたったときに現れる何か。
それを提供していくことなのだろうと思う。
人生に、将来に悩める19歳に、
僕はこの本を贈ります。
すべての仕事は、「自分の仕事」になっていく。
そしてそれは「自分」を超えたところにある。
2016年12月27日
お店をやるということは世界に問いを投げかけるということ
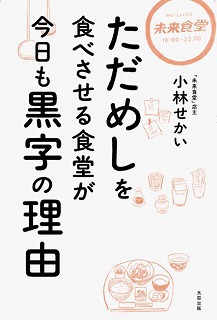
「ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由」(小林せかい 太田出版)
神保町の「未来食堂」の小林さんの本。
http://miraishokudo.com/
衝撃。
この衝撃は、タルマーリーの
田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」以来。
お店をやるっていうのは、
世界に問いを投げかけるということなんだなと
思った。
資本主義経済を内側から突破していく、
突き抜ける何かがある。
まかない、ただめし、あつらえ
など、いろいろ衝撃。
あまりに衝撃過ぎてまだ、ブログには書けません。
ツルハシブックスサムライ必読の1冊です。
2016年12月26日
好きだけど理由のわからないもの

「自分の仕事をつくる」(西村佳哲 ちくま文庫)
読む本がなくなったので、古本屋さんに行き、
処方箋用に「見つけたら買う」ことにしている
「自分の仕事をつくる」を購入。
帰りの電車の中で読み進める。
改めて読み直すと、
キーワードがいっぱいで、
つぶやきたくなるけど、
トンネルがいっぱいで、電波が届かない。
特に
第2章他人事の仕事と「自分の仕事」
の冒頭からシビれまくる。
やっぱ、この本ですよ。
「○○歳のハローワーク」読んでる場合じゃないっす。(笑)
19歳に贈りたい本、
僕はやっぱりこれにしようかな。
日本を代表するクリエイターの佐藤雅彦さんの話。
とっても素敵だった。
佐藤さんは、最初はクリエイティブ(制作)部門ではなく、
31歳までは販促部門で、スケジュールや見積り管理と
いった一般職の仕事に従事していたという。
思うところあって社内試験を受け、合格。
クリエイティブ部門に転配属されたが、
年齢が高いわりに実績も経験もない佐藤さんには
なかなか仕事の声がかからなかった。
そこで。
佐藤さんは何をしたか。
社内の資料室に通い、世界中のCMに目を通して、
その中から自分が面白いと思うものをビデオテープに
まとめはじめる。
じきに、自分が魅力を感じたCMには、
共通するいくつかの規則(ルール)が
あると気づくようになった。
この作業は3か月ほど続けられ、
結果として佐藤さんは、面白くて
印象に残るCMに共通する23種類の
ルールをまとめるに至ったという。
その後のヒットCMのほとんどすべてが、
この時にまとめたルールから作り出された
ものだと本人は語る。
「スコーン、スコーン、湖池屋スコーン」や「バザールでござーる」
は、その一例だという。
そして、佐藤さんは慶応大学の講義で、
次のように説明している。
魅力的な物事に共通するなんらかの法則を見出そうとするとき、
「好きだけど理由がわからないものを、いくつか並べてみる」
という方法をとるのだ。
~~~ここから一部引用
自分が感じた、言葉にできない魅力や違和感について、
「これはいったい何だろう?」と掘り下げる。
きっかけはあくまで、個人的な気づきに過ぎない。
だが、そこを掘って掘って掘って、
掘り下げていくと、深いところで
ほかの多くの人々の無意識とつながる層に達する。
人々に支持される表現は、多数の無意識を代弁している。
しかしその入り口は、あくまで個人的な気づきにある。
深度を極端に深めていくと、
自分という個性を通り越して、
人間は何が欲しいのか、
何を快く思い、何に喜びを見出す生き物なのか
といった本質に辿りつかざるを得ない。
歴代の芸術家や表現者が行ってきた創作活動は、
まさにこのくり返しだ。
~~~ここまで一部引用
いいなあ。
自分の「感性」を発動させ、
それを掘って掘って掘って、
深いところまで行くと、
素敵な仕事ができる。
それを「自分の仕事」
と呼ぶのだなあと。
職業名で「自分の仕事」を選ぶなんて、
こっけいに思えてきます。
まず、感性を発動させていくこと。
たとえば、好きだけど理由のわからないものを
いくつかピックアップすること。
それを深く掘っていくこと。
そこからしか「自分の仕事」は始まらない。
進路に悩む大学生のお正月休みに
ぴったりの1冊です。
2016年12月24日
ツルハシブックスが劇団になった日
2016年12月23日。
ツルハシブックスが劇団になった日。
ツルハシブックス恒例のサムライ合宿。
今回は電車移動で村上に動きながらのミーティング。
しかし、今回は何かが違う。
ツルハシブックス閉店を経て、
次の半年を考える。
いつも大切にしてきたのは、
「顧客は誰か?」
「顧客にとって価値は何か?」
で、だいたい中学生とか高校生になるのだけど、ね。
第1ターム@ベリーデイズカフェで、過去を掘り下げる。
そのあとの第2ターム@新発田イオンスタバが
風間さんプレゼンツの「うれしい瞬間」ワークショップ
これで過去からあぶりだされる個人の理想の状態が
見えてくる。
僕がうれしい瞬間は、
・動から静に場が移る瞬間。
・自分の過去が言語化された瞬間。
・同じ空間を異なる目的の人が分け合っている瞬間
と3つがすぐに思い浮かんだ。
ほかのメンバーからも、
なんというかキーワードが出てきた、出てきた。
特に、
ゆきもんの「違っていることを面白く感じる」と
さくらもんの「無関心である空間」
あいりもんの「なんか、よかった」
の3つが印象に残った。
その後チームに分かれて
第3タームのペアランチ(3人組あり)になった。
今回の僕のランチペアは
のんちゃん(大学2年)だったのだけど、
いろいろとキーワードが出てくる。
いちばんは、「違い」ということ。
「違っていること」は、
中学高校にあっては、デメリットであり、価値がない。
だから、友達と同じようにふるまってきたのだという。
「違いを楽しめる」
お客が高校生だとしたら、
そこに向かっていきたい。
そのためには、
まずは感性を発動させる環境をつくり、
他人と違っている自分を受け入れる。
そして、違いの面白さを体感する。
そこには、「本」のアシストが必要なのかもしれない。
ツルハシブックスは、「劇場」を目指していた。
「劇場」は、多様性と普遍性を同時に実現する。
「本のある空間」は、劇場よりも劇場になれるのではないか。
その一瞬一瞬のキャストが、
自分を演じているとすれば、
非日常と日常のあいだを、
自由自在に揺れ動くことができる。
それを、ナカムラクニオさんは
「一期一会の空間」と呼んだのではないか。
アサダワタルさんは、
「居場所という瞬間」と呼んだのではないか。
異なる目的の人が同じ空間を分け合っている。
それこそが僕の考える心地の良い空間だ。
ツルハシブックスは、
「偶然」という名の作品だと思ったことがある。
でも、次のステージのテーマは、
「偶然」から「劇場」へ。
そして、夜。
もうひとつの問いが投げ込まれた。
「中心は必要なのか?」
僕も感じていた違和感。
「顧客は誰か?」
「顧客にとっての価値は何か?」
という問いに全員で答え、それを言語化するということは、
そこに「中心」を生むことを意味する。
しかし、
「中心」は「ウチ」と「ソト」を生み出し、
そこに疎外感を感じる人を生んでしまうのではないか。
ひとりひとりの中に、
「顧客」と「顧客にとっての価値」を追求することは必要だけど、
きっとそれを「経営」と呼ぶのだろうけど。
「場」はもっと流動的で、
中心がないほうが魅力的なのではないか。
そうそう。
たぶんそうだ。
場の構成員によって、
「顧客」も「顧客の価値」も変わる、
そんな流動的な場をつくっていくこと、
かもしれないなあと思った。
2016年12月23日、ツルハシブックスが劇団になった日。
まだもう少し言語化にはかかりそうです。
ツルハシブックスが劇団になった日。
ツルハシブックス恒例のサムライ合宿。
今回は電車移動で村上に動きながらのミーティング。
しかし、今回は何かが違う。
ツルハシブックス閉店を経て、
次の半年を考える。
いつも大切にしてきたのは、
「顧客は誰か?」
「顧客にとって価値は何か?」
で、だいたい中学生とか高校生になるのだけど、ね。
第1ターム@ベリーデイズカフェで、過去を掘り下げる。
そのあとの第2ターム@新発田イオンスタバが
風間さんプレゼンツの「うれしい瞬間」ワークショップ
これで過去からあぶりだされる個人の理想の状態が
見えてくる。
僕がうれしい瞬間は、
・動から静に場が移る瞬間。
・自分の過去が言語化された瞬間。
・同じ空間を異なる目的の人が分け合っている瞬間
と3つがすぐに思い浮かんだ。
ほかのメンバーからも、
なんというかキーワードが出てきた、出てきた。
特に、
ゆきもんの「違っていることを面白く感じる」と
さくらもんの「無関心である空間」
あいりもんの「なんか、よかった」
の3つが印象に残った。
その後チームに分かれて
第3タームのペアランチ(3人組あり)になった。
今回の僕のランチペアは
のんちゃん(大学2年)だったのだけど、
いろいろとキーワードが出てくる。
いちばんは、「違い」ということ。
「違っていること」は、
中学高校にあっては、デメリットであり、価値がない。
だから、友達と同じようにふるまってきたのだという。
「違いを楽しめる」
お客が高校生だとしたら、
そこに向かっていきたい。
そのためには、
まずは感性を発動させる環境をつくり、
他人と違っている自分を受け入れる。
そして、違いの面白さを体感する。
そこには、「本」のアシストが必要なのかもしれない。
ツルハシブックスは、「劇場」を目指していた。
「劇場」は、多様性と普遍性を同時に実現する。
「本のある空間」は、劇場よりも劇場になれるのではないか。
その一瞬一瞬のキャストが、
自分を演じているとすれば、
非日常と日常のあいだを、
自由自在に揺れ動くことができる。
それを、ナカムラクニオさんは
「一期一会の空間」と呼んだのではないか。
アサダワタルさんは、
「居場所という瞬間」と呼んだのではないか。
異なる目的の人が同じ空間を分け合っている。
それこそが僕の考える心地の良い空間だ。
ツルハシブックスは、
「偶然」という名の作品だと思ったことがある。
でも、次のステージのテーマは、
「偶然」から「劇場」へ。
そして、夜。
もうひとつの問いが投げ込まれた。
「中心は必要なのか?」
僕も感じていた違和感。
「顧客は誰か?」
「顧客にとっての価値は何か?」
という問いに全員で答え、それを言語化するということは、
そこに「中心」を生むことを意味する。
しかし、
「中心」は「ウチ」と「ソト」を生み出し、
そこに疎外感を感じる人を生んでしまうのではないか。
ひとりひとりの中に、
「顧客」と「顧客にとっての価値」を追求することは必要だけど、
きっとそれを「経営」と呼ぶのだろうけど。
「場」はもっと流動的で、
中心がないほうが魅力的なのではないか。
そうそう。
たぶんそうだ。
場の構成員によって、
「顧客」も「顧客の価値」も変わる、
そんな流動的な場をつくっていくこと、
かもしれないなあと思った。
2016年12月23日、ツルハシブックスが劇団になった日。
まだもう少し言語化にはかかりそうです。
2016年12月21日
漂泊する個人の時代

「21世紀の自由論~優しいリアリズムの時代へ」(佐々木俊尚 NHK出版新書)
先週、今週は佐々木俊尚ウィーク。
先週の講演で引用されていた2冊を読む。
最初はリベラリズムとは何か?とか政治の話ばっかりで、
どうしようかなと、思っていたけれど、
やっぱり前フリとして重要で、
最後には希望ある終わりになるところがいいなあ。
この本の(とりあえず今の)ハイライトはこちら
~~~ここから引用
通常の共同体はどんなに小規模にしても、
一時的なものだったとしても、
赤の他人が集まったものであっても、
そこに内外の壁がある限り、
必ず外部を排除し、内部では同調圧力を
高めてしまうことが起きる。
わずか三人の共同体でも、
内部で二人が一人を仲間はずれにし、
外部は排除するというのはふつうにあることだ。
そのような排除・抑圧を防ぐ共同体は
本当に可能なのだろうか。
そのような内外の壁をつくらず、
結果として排除を生まない共同体を、
私は可能だと考えている。
中心がなく、開放され、内と外が
つねに入れ替え可能な共同体である。
~~~ここまで引用
そして、佐々木氏は、
それがテクノロジーによって
生まれたSNSなどのメディア空間によって可能になる
と説明する。
フェイスブックやツイッターには
「中心」が存在しない。
情報はあくまでも参加者同士のつながり
という「線」の上だけで流れている。
なるほど。
リベラリズムの「普遍的なもの」の世界では、
高位にある理想に向かい、人々は高みを目指して
登ることを義務づけられた。
そのような上下で移動する世界だった。
しかし、リベラリズムが終焉した後のネットワーク共同体では、
高位に理想はない。
その代わりに縦横の平面が無数に広がり、
その中を人は流動する。
そうして人は「入れ替え可能」である状態に置かれる。
それは、全員がマイノリティになるということだ。
そうして人は漂泊していく。
それを恐れるべきだはないのだろうと思う。
そしてこの本を読んで、
やはり個人としては、
アイデンティティや居場所は不要なのではないか
という思いであり、
ゆるやかにつながる空間としての
本のある空間であり、
さらにツルハシブックスとしては、
次のステージは「畑のある本屋」なのだろうなという思いが強まった。
漂泊する個人の時代をどうい生きるのか?
そんなことを一緒に悩んでいきたい。
2016年12月20日
自分を「多層化」して生きる

「レイヤー化する世界~テクノロジーとの共犯関係が始まる」(佐々木俊尚 NHK出版新書)
おもしろかったです。
レイヤー(層)化しているのですね。
ソーシャルネットワークのような
プラットフォームによって、
多層化した人を、生きられるというか、生きていかざるを得ない
そういう時代に突入しているのだそうです。
なるほど、と思ったのは、
国民国家というシステムに関する記述。
「国民国家」というシステムが
生まれたのは、ヨーロッパでした。
それまでのヨーロッパは辺境の地で、
世界の中心はユーラシア大陸でした。
「帝国」が東西の交易路を築き、栄えていました。
「陸の時代」です。
そこでは、多民族が、共存していました。
ヨーロッパは、
天候も温暖ではなく、農作物も取れず、
その仲間にさえいれてもらえませんでした。
それが、コロンブスによる「新大陸の発見」で
事態は急変します。
まずは大量の銀を得て、交易に参加し、
そこで「産業革命」が起こり、
原料の調達と販売のために
大量の植民地を必要としました。
その頃は、教会の力も衰え、
人々が「よりどころ」を無くしていった時代と重なり、
そんな中で「国民国家」は発明されました。
「国民国家」は戦争を生み出しやすいシステムでした。
常に境界について争っていました。
佐々木さんは、
国民国家の神髄は、「ウチとソトを分ける」
というところにあると言っています。
自国と他国を分ける。
その中で、「最大多数の最大幸福」を目指す。
これは今も行われているような
途上国での過酷な商品(換金)作物の栽培
なども含まれます。
しかし、
そんな時代も22世紀まではもたないだろうと
佐々木さんは言います。
テクノロジーと
それを基盤にした超国家企業が、
プラットフォームという<場>をつくることによって、
国家のように「上から」支配するのではなく、
超国家企業は「下から」ひとりひとりを支え、また支配するのです。
もはや国家には税金を納めません。
レイヤー化された世の中。
それは、さまざまなレイヤー(居住地、出身校、趣味・・・)
における要素を持つ個人と個人の時代です。
この本の一番の希望は、そこにありました。
「場は、マジョリティとマイノリティを逆転させる。」
そうなんです。
マイノリティのほうが<場>では、
(特にSNSのような場)
価値を持ちます。
強くつながることができるからです。
なるほどなあ、と。
国民国家が終わり、レイヤー化された世界がやってくる、
というか、すでにやってきている。
そんな中で、個人はどう生きていけばいいのか。
佐々木さんは、このように言います。
第一に、レイヤーを重ねたプリズムの光の帯として自分をとらえること。
第二に、<場>と共犯しながらいきていくということ。
たとえば、グーグルやフェイスブックを利用しながら、
私たちは日々、情報を提供しています。
それがビッグデータとなって、彼らのビジネスを
より儲けさせます。
一方で、そのようなテクノロジーは
複数のレイヤーにまたがる私たちをつなげてくれます。
そのように、
多数の層の集合体として自分をとらえ、
そのそれぞれの集合体として生きていくということです。
これは、平野啓一郎さんの「私とはなにか?」
「本当の自分」という幻想
http://hero.niiblo.jp/e405109.html
(2014.4.5 20代の宿題)
の分人主義と合わせて読むと、
なんか、とらえやすくなるように思います。
自分を多層化して生きる。
きっとそういう時代に突入しているのだろうなあと実感できる1冊でした。
2016年12月19日
中高生に必要なのは「居場所」ではなく「劇場」
「居場所」という場所があるのではなく、
居場所という「瞬間」がある。
アサダワタルさんの
「コミュニティ難民のすすめ」の表現によれば、
自分にとって居場所とは、場所ではなく、
「今この瞬間」という「時間」そのものだった。
そしてそれは当然のように常に変化し、転がってゆくものだ。
その感覚ってすごく大切だと思う。
「場」が「居場所」になった瞬間、
そこへのある種の「安定」というか、
変わらないでほしい、というか、保ちたい
というか、そういうのが始まってしまう。
ツルハシブックスは本屋のような劇場
を目指してきた。
では「劇場」とは、なんだろうか。
「劇場」とは、たとえば、中高生にとっては、
「居場所はそこ(学校)だけじゃない」と自ら気づけるところである。
そこでなぜ、本なのか?と、問われたら、
本のある空間こそが多様性を表現している、
と僕思っていたのだけど、
早稲田大学の松永さんが言っていた、
「特異性」と「普遍性」というキーワードが
思い出された。
これは芸術・文化のキーワード。
芸術は特異性と普遍性の表現であるという。
本のある空間において、
本は1冊1冊は特異、個性的でありながら、
自分たちは同じ人間である、ということを
風景以上に伝えてくるのではないか。
「サードプレイスを支配しているのは常連客」
http://hero.niiblo.jp/e209391.html
なるほどな。
本をもっと入れ替えていくこと。
新規の「本を買うことが目的」のお客をきっちりと入れていくこと。
そういうことが必要だったのだろうな。
「居場所」になってはいけなかったのだ。
サードプレイス=第3の場所は
第3の「居場所」になってはいけないのだ。
(多くの場合、学校や家庭を上回り第1の居場所になる)
だとすると、
本屋のような劇場は、
実際の固定された場である必要がないのかもしれない。
カフェの心地よさは、
1 そこに居合わせた人の目的がそれぞれ異なること
2 そもそも構成メンバーが変わること
そこから来るのではないか、と
武雄市図書館にいったときに感じた
分断から共存へ
http://hero.niiblo.jp/e302022.html
に書いてある
いろんな想いを持った人が、場を共有していて、
それがステキな一体感というか、アート作品のような
空気感を出している。
そういう空間。
福島の下枝さんがこの前言っていた
「地域づくりはジャズセッションだ」
ジャズのセッションは
メンバーと方向性だけが決まっていて
そこから演奏が始まっていく。
そういう一期一会感が必要なのだ。
だから、
そんな一期一会のある「劇場」をつくっていくこと。
場が適度な緊張感を持ちながら、
新しくそのセッションに入ってくる人を受け入れていくような、
そんなジャズのセッションのような劇場を
つくっていくこと、かなあ。
「居場所」という場所は不要で、
「劇場」をたくさんつくり、
「居場所という瞬間」をつくっていくこと、なのかもしれない。
居場所という「瞬間」がある。
アサダワタルさんの
「コミュニティ難民のすすめ」の表現によれば、
自分にとって居場所とは、場所ではなく、
「今この瞬間」という「時間」そのものだった。
そしてそれは当然のように常に変化し、転がってゆくものだ。
その感覚ってすごく大切だと思う。
「場」が「居場所」になった瞬間、
そこへのある種の「安定」というか、
変わらないでほしい、というか、保ちたい
というか、そういうのが始まってしまう。
ツルハシブックスは本屋のような劇場
を目指してきた。
では「劇場」とは、なんだろうか。
「劇場」とは、たとえば、中高生にとっては、
「居場所はそこ(学校)だけじゃない」と自ら気づけるところである。
そこでなぜ、本なのか?と、問われたら、
本のある空間こそが多様性を表現している、
と僕思っていたのだけど、
早稲田大学の松永さんが言っていた、
「特異性」と「普遍性」というキーワードが
思い出された。
これは芸術・文化のキーワード。
芸術は特異性と普遍性の表現であるという。
本のある空間において、
本は1冊1冊は特異、個性的でありながら、
自分たちは同じ人間である、ということを
風景以上に伝えてくるのではないか。
「サードプレイスを支配しているのは常連客」
http://hero.niiblo.jp/e209391.html
なるほどな。
本をもっと入れ替えていくこと。
新規の「本を買うことが目的」のお客をきっちりと入れていくこと。
そういうことが必要だったのだろうな。
「居場所」になってはいけなかったのだ。
サードプレイス=第3の場所は
第3の「居場所」になってはいけないのだ。
(多くの場合、学校や家庭を上回り第1の居場所になる)
だとすると、
本屋のような劇場は、
実際の固定された場である必要がないのかもしれない。
カフェの心地よさは、
1 そこに居合わせた人の目的がそれぞれ異なること
2 そもそも構成メンバーが変わること
そこから来るのではないか、と
武雄市図書館にいったときに感じた
分断から共存へ
http://hero.niiblo.jp/e302022.html
に書いてある
いろんな想いを持った人が、場を共有していて、
それがステキな一体感というか、アート作品のような
空気感を出している。
そういう空間。
福島の下枝さんがこの前言っていた
「地域づくりはジャズセッションだ」
ジャズのセッションは
メンバーと方向性だけが決まっていて
そこから演奏が始まっていく。
そういう一期一会感が必要なのだ。
だから、
そんな一期一会のある「劇場」をつくっていくこと。
場が適度な緊張感を持ちながら、
新しくそのセッションに入ってくる人を受け入れていくような、
そんなジャズのセッションのような劇場を
つくっていくこと、かなあ。
「居場所」という場所は不要で、
「劇場」をたくさんつくり、
「居場所という瞬間」をつくっていくこと、なのかもしれない。
2016年12月16日
本棚に向かって、ともに悩む
「本の処方箋」@センジュプレイスやりました。
みんな、話したいことってあるんだなあって。
あらためて、本の処方箋のパワーを感じました。
本を紹介する。
ただそれだけなのに、
本当に直面している悩みを話してくれる。
それは、本の力なのか、空間の力なのか。
とにかくそこには、本との一期一会が生まれている。
話を聞いて、浮かび上がる本がある。
僕は、北海道の「1万円選書」みたいなのはできない。
読書の絶対量やジャンルの幅が足りないからだ。
でも、大学生や20代の将来不安に対する
「視野を広げたり」
「不安をやわらげたり」
「なんとかなりそうだと思えたり」
「世の中ってそうなってたんだと気づきがあったり」
そんな本を処方する「本の処方箋」
この前京都でも話したけど、
「本棚に向かってともに悩む」が僕の本職(=提供価値)なのかもしれません。
井上有紀さん、吉満明子さん、たいへんお世話になりました。
ありがとうございました。
みんな、話したいことってあるんだなあって。
あらためて、本の処方箋のパワーを感じました。
本を紹介する。
ただそれだけなのに、
本当に直面している悩みを話してくれる。
それは、本の力なのか、空間の力なのか。
とにかくそこには、本との一期一会が生まれている。
話を聞いて、浮かび上がる本がある。
僕は、北海道の「1万円選書」みたいなのはできない。
読書の絶対量やジャンルの幅が足りないからだ。
でも、大学生や20代の将来不安に対する
「視野を広げたり」
「不安をやわらげたり」
「なんとかなりそうだと思えたり」
「世の中ってそうなってたんだと気づきがあったり」
そんな本を処方する「本の処方箋」
この前京都でも話したけど、
「本棚に向かってともに悩む」が僕の本職(=提供価値)なのかもしれません。
井上有紀さん、吉満明子さん、たいへんお世話になりました。
ありがとうございました。
2016年12月15日
0.3から始まるまち暮らし
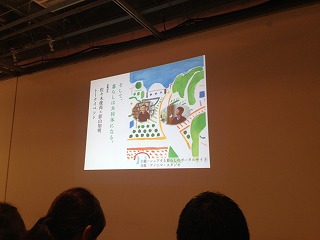
シェアする暮らしのポータルサイト主催
そして暮らしは共同体になる出版記念イベント
佐々木俊尚×影山知明@汐留ホール
に行ってきました。
いってよかったです。
本もすごくよかったので、
話聞きたいなあと思っていたところで
タイミングよかったなあ。
シェアする暮らしのポータルサイト
のシェアって「持ち寄る」」って意味だったんですね。
素敵だなあ。
昨日の話のテーマは
「まちで暮らす。」だったように思う。
コメタクとか、
3号室プロジェクトとか、
きっとそういう話。
~~~以下キーワード
ミニマルな衣食住
ミニマルだからこそ外に開かれる。
ゆるゆるつながって暮らす。
リビングはカフェ。まちを間取りとして考える
豆腐屋やビストロ、まち全体がチーム稲垣
大衆居酒屋のように
居心地の良さが大切になってきた。
アンチ六本木・渋谷とかではなく、
赤羽や西荻窪が愛されるようになってきた。
マンションが発明されたのは近代以降
古代ギリシャでは、
家の前のほうを男の空間(パブリック)
後ろのほうを女の空間(プライベート)とした
日本では、上り框(かまち)=閾というのがあった。
パブリックとプライベートのあいだ。
まちの中心ってどこ?
人が集まる場、広場がまちの中心
Iターンした人が
カフェやゲストハウスをつくるのはなぜか?
人が集まる場がまちの中心だから。
開かれた共同体であることが必要。
ヒッピーコミューンは閉じたことで消滅した。
熊本・サイハテは自給自足しない、開かれている。
ネットというテクノロジーが可能にしている。
共同体の感覚が変わってきた。
不自由さとともにある共生関係ではない。
総中流という幻想
自らを多層化していくこと
まちは自動車なのか、植物なのか。
植物を育てるようにまちをつくる。
設計図はないが状況がある。
芽が出るような状況にしていくこと。
機械・ロボットに置き換わらない仕事
CMH
クリエイティブ、マネジメント、ホスピタリティ
自主性は不要。ついていく人を見つけられればいい。
そして、ついていく。
変化の時代。
その変化を受け入れて楽しもうとすること。
~~~ここまでメモ
写真を交えながら、
そして時代は共同体になるの
エッセンスを受け取りました。
なんか、楽しかった。
「ミニマルな暮らし」を望む人たちは
まち全体でシェアする暮らし、
「まちで暮らす。」の心地よさに気づく。
そんなことができるまちを
求めているのだろうと思った。
そんな人たちをつないでいく、
パブリックとプライベートのあいだ
が必要なのだろう。
あるいは、
ヨソモノと暮らす人のあいだ
が必要なのだろう。
だから人は住み開きをし、カフェをつくり、ゲストハウスを
つくっていくのだろうなと思った。
「そして、暮らしは共同体になる」
っていうのはそういうことなのだろうなあと思った。
コメタク、やっぱりいい線いっているなあと感じた。
その共同体は、開かれていて、演じられていて、
なんていうか、風が吹き抜ける感じになるのだろうなあと。
印象に残ったのは、
影山さんが対談の中で言っていた
「これまで工学的にまちづくりをしてきたけど
まちは自動車なのか、植物なのか?」
って。
自動車であれば、工場を建てて
部品をそろえればできるけど、
植物は、そうじゃない。
おかれている「状況」がある。
自然条件、土、日光、ほかの植物
などなど。
そんな状況のなかで、
ど芽を出し、花を開き、実をつける。
そんなものを育てていくことが
まちづくりなのだろうなあと。
そういった意味では、
ツルハシブックスはもう一度やりなおしなのかもしれないね。
自然条件と、土と、光の具合と相談しながら、
まちにすでにあるお店や人とコラボしながら、
つくっていく。
ゼロからではなく、
0.3くらいから始まるまち暮らし。
そんなのが始まっていく気がする。
コメタク、やっぱり最先端だなあと実感しました。
2016年12月13日
自分に向かって吹いてくる風
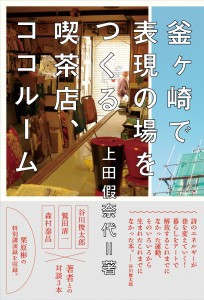
「釜ヶ崎で表現の場をつくる喫茶店、ココルーム」(上田假奈代 フィルムアート社)
読み始めました。
第2章のQ&A、面白い!
まずQ1がいいです。
「何かやりたいけど、何をやったらいいかわかりません。」
いいですね。
あります。
そういうの。
よくあります。
答えるのは臨床哲学者の西川勝さん。
~~~ここから一部引用
今まで、人の言うことばかり聞いていたのに、
自分というものを頼りにしろと迫られても困ってしまうのです。
他人から褒められることで満足しているあいだはよかったけど、
どうも自分自身で満足しないといけないらしい。
でも、自分がほんとうに何をやりたいのか、よくわからない。
大変に困ったことだ、というわけです。
つまりは、自分を頼りにすることが、この問題の原因なのです。
問題の原因がわかれば、対処についても浮かびます。
症状の原因である「自分」をできるだけ小さく、軽く、弱くしてみれば
どうでしょうか。
大きな、重々しい、強い自分を持った「大人」になることを
止めてみるのです。
一人の人間が思いつくことなどたかが知れています。
世界は果てしなく広いのですから、
自分のやりたいことで視野を狭めるのはやめてみましょう。
自分が行くと決めた方向にひたすらまっすぐ歩んでいけば、
自分の背後にある世界は見えません。
たんぽぽの綿毛のように、
吹く風に身を任せてみれば、
世界を360度、味わうことができるのです。
「この仕事は、自分に向いていないのでは」
と考え込むときがあります。
あるとき、「自分に向いている、向いていない」
ということばが不思議に思えて、ちょっと考えたのです。
そして、気づきました。
自分に向かって吹いてくる風に乗っているかどうかが大切なんだ。
よくわからない自分自身の気持ちや考えよりも、
自分に向かってやってくる仕事を大切にしよう。
「いや」と言わずに、自分を乗せてくれる風に乗って
知らない世界へ旅立とう。
その方が、人生は楽しくわくわくするでしょう。
~~~ここまで一部引用
そうそう。
そういう感じでいいのではないかなあ。
「アイデンティティ」や「自分らしさ」という言葉に、
惑わされないように。
目標や目指すものがある人ってカッコよく見えるけどね。
20代は特に、確固たる自分である必要などないんじゃないかなあと。
それよりも、
「自分に向かって吹いてくる風」を感じられるか?
そしてその風に乗る度胸を持てるか?のほうが大切だと思う。
感性と度胸を磨いて、
自分に向かって吹いてくる風に乗っていくような
人生が僕も楽しいなあと思います。
たんぽぽの綿毛のように、
軽やかに生きるのも悪くない。
素敵な本です。
読み進めます。
2016年12月12日
伴走者であり、伴奏者であるような店づくり

「そして、暮らしは共同体になる。」(佐々木俊尚 アノニマ・スタジオ)
ラスト、シビれるほどの感動があった1冊になりました。
「文化をつくる」企業っていうのは、どういうことなのか?
に関して、たくさんの問いをもらいました。
この本では、
野菜の通販会社「オイシックス」
都心立地型スーパー「成城石井」
セレクト通販「北欧暮らしの道具店」
などを取り上げ、説明されています。
オイシックスのオムニチャネルを
担当する奥谷さんの一言。
「ここにきて思うようになったのは、
企業が価値を提供するのではなく、
企業とお客さんが価値をともに創る時代になるということです」
なるほど。
佐々木さんは、これからの企業は
「ネットか、リアルか」ではなく、
「文化なのか、大規模インフラ」か
というように分かれていくと言います。
文化に大切なのは「らしさ」であり、
そこは大規模インフラにはできないこと。
そうして、企業とお客さんの関係も変わりつつあります。
~~~ここから引用
「文化である」ということこそが、
お客さんを受動的な存在におとしめず、
ともに文化をつくり、共感できる仲間としての
能動的なつながりへと高めていくカギなのだと思います。
だからこれからの消費は、
わたしは単に個人のお客さんを相手に商売する、
モノを売るというだけではない。
そのお客さんと仲間となり、さらにお客さんの周囲にいる
家族や恋人、友人たちとのあいだでつくられる
文化の空間を支えていくものでなければなりません。
なにかを売るという行為は、
あるひとりの人に向けてではなく、
文化全体に向けて届けられるのです。
その人の向こう側にいるたくさんの人たちに向けても
伝えられるのです。
(中略)
企業は見えないところで人々を支え、
文化空間が維持されるように心砕いていく。
そういう「伴走者」になっていくのです。
~~~ここまで引用
ツルハシブックスが
「劇団員」という仕組みで目指したかったのは
きっとそういうことなのだろう。
暗やみ本屋ハックツをやって、
ハックツとは、「手紙」だと思ったし、
仕事の本質は手紙にあると思った。
誰かのために書く「手紙」。
それが商品だとしたら、
お店というのは、
文化、地域、その向こう側にあるものに向けての
手紙なのだろう、祈りなのだろう。
その手紙を携えて、
歩くお客さんと伴走し、
お客さんの歌う歌を伴奏する、
そんな存在がこれからのお店になっていくのだという予感がした、
素敵な1冊でした。
2016年12月10日
外でも上でもない、第3の道

「そして、暮らしは共同体になる。」(佐々木俊尚 アノニマ・スタジオ)
アノニマ・スタジオ、いい本出すなあ。
最後に書いてある
「アノニマ・スタジオは」
っていう文章が素敵すぎた。
遠くに住む友人から届いた手紙のように、
何度も手に取って読み返したくなるような本。
いいなあ。
そういう本。
この本も新しい時代への変化のエッセンスが詰まった1冊でした。
いま、第3章を終えたところですが、
これは面白いなあと。
戦後、というか明治維新以来の劇的な変化が
起こっているように感じる現在。
人と人の「関係性」も大きく変化している。
この本を象徴するようなことが第3章の終わりに書いてあったので引用します。
~~~ここから引用
カウンターカルチャーでは、
たがいにつながることよりも、
反逆し、アウトサイドへ逃げることのほうがクールだと
考えられてきました。「外へ、外へ」
そういう願望が多くの人々のこころをくすぐったのです。
それはマスカルチャーの「お金持ちになりたい」「成功したい」
という「上へ、上へ」という願望とセットになって、
われわれの戦後社会を構成してきたといえるでしょう。
中央へ向かう中央集権的な引力と、
外部に向かう反逆クール的な引力があって、
社会はそこにとどまっていたのです。
しかし、近代が終わったいまとなっては、
「上へ、上へ」はほとんど実現不可能な幻想の
アメリカンドリームとなってきている。
もはや可用性は低いのです。
「内部の堅固さ」が崩壊していけば、
「外へ、外へ」の有効性も失われていきます。
つまりは、
「上へ、上へ」という中央集権志向と、
「外へ、外へ」という反逆クール志向は、
一見して真逆の方向に見えながら、
実は戦後社会という安定的なシステムに基づいていた
表裏一体の存在だったといえるでしょう。
しかし、これらはいずれももう有効ではありません。
新しい21世紀の時代状況の中で、
新しいネットワークの重要性が増し、
いってみれば「横へ、横へ」と
網の目のように人間関係を広げていく方向性が
求められているのだと思います。
これからの街や家には、
ふたたび共同体感覚が戻ってくる。
家というものが拡張子、街へとつながっていく。
そしてそこに、内と外を隔てないオープンな共同体が立ち上がってこようとしている。
私たちの社会は、そういうとば口に立っているのかもしれません。
~~~ここまで引用
なるほどな~、って。
これまで感じてきた「違和感」を言語化してくる本。
オーガニック原理主義とかそういうやつ。
「でなければならない」
とする人たちが苦手でした。
それは、「外へ」と向かうベクトルだったからなのかもしれません。
既存のシステムに
NOというのはいいのだけど、
いつの間にか、手段と目的が逆転して
NOと言うことが目的化してしまう危険。
これからは外へ、でも上へ、でもない
第3の道があるのだと思う。
それを佐々木さんは、
「横へ」と表現しているけど、
いろいろな方法があるのだろうな。
それこそ、無数に方法があるのだと思う。
コメタクも、
畑のある本屋も、
きっとそういうところに、向かっているのだなあと
ぼんやりとした自信が湧いてくる1冊でした。
12月24日(土)のツルハシブックスin飯塚商店にはこの本を売ります。
予約を受け付けています。
2016年12月08日
ライト兄弟は東大に行っていません。
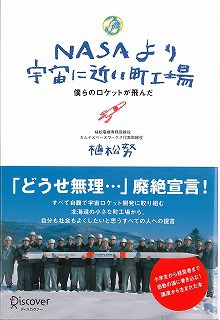
「NASAより宇宙に近い町工場」(植松努 ディスカバー)
すみません。
今ごろ読んでました。
植松さんと言えば、
サンクチュアリ出版からの「空想教室」も素敵な本です。
http://hero.niiblo.jp/e475845.html
(2016.1.1 20代の宿題 やったことがないことをやりたがる人)
ということで。
~~~本文より一部引用
中学校の進路相談の時間に、
先生から「おまえは将来どうするんだ?」
と聞かれたので、
「飛行機、ロボットの仕事がしたいです」と
胸を張って答えたら、
「芦別に生まれた段階で無理だ」と言われてしまいました。
理由は、そのためには東大に入らないといけない。
芦別から東大に入った人間は一人もいない。
ということでした。
「おまえ、将来どうするんだ?」
って聞いておきながら、
「おまえの行き先はこの一校しかない」
と宣言するんです。
これは、進路指導ではありませn。
憶測による進路「評論」です。
どんな挑戦も、夢もアイデアも、
新しい提案も、すべて誰かに憶測の評論をされ、
「それは無理だわ」と言われてしまうことがあります。
このようなくだらない憶測をする人には2つのパターンがあります。
ひとつは、知らないことが恥ずかしいことだと思っている人たち。
もうひとつは、間違えることが恥ずかしいことだと思っている人たちです。
けれども、
大人だって、経営者だって、学校の先生だって、
自分が経験したことしか知らないんです。
世界のすべてを経験することは不可能であり、
経験していないことは全部憶測です。
また、間違えることは誰にでもあります。
だから、間違えたらやり直せばいいんです。
そして、知らなかったら、調べればいいんです。
素直にこれをやればいいだけです。
本当の未来というものは、
やってみたいことをどうやったらできるかなと考えて、
やり始めることです。
ただこれだけで、未来に到達することができます。
僕は、飛行機やロケットの仕事をするためには東大に行かなきゃダメなのかな、
ってちょっと考えました。
でも、考えてみたら、ライト兄弟は東大に行っていません。
だから、関係ないやと思って、その後も自分で飛行機の勉強をしようと思いました。
世界で有名なパティシエというものは、
誰も教えてくれないものをつくるから有名なのです。
そして、それに至るまでは、
「こんなもん食えるか」というものをたくさんつくっているはずです。
~~~ここまで一部引用
なんか、いいですね。
スカッとします。
「進路指導」の名を借りた
進路「評論」に付き合ってはいけない。
ライト兄弟は東大に行っていない。
それいいな。
物理的に行けないと思うけど。(笑)
こうして、植松さんは、
ロケットをつくり、無重力実験装置をつくりました。
間違えたら、やり直せばいい。
知らなかったら、調べればいい。
そんな当たり前のことを繰り返していくだけですね。
ホントそうだな、と。
「やりたいことがわからない」と
悩んでいる暇があったら、
「ナリワイをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)と
「月3万円ビジネス」(藤村靖之 晶文社)を読んで、
とりあえず、月1万円稼ぐ、を目標に
自分でビジネスを始めてみればいいと思うなあ。
やってみる、から始まる
ビジネスの試作品をたくさん作ってみよう。
2016年12月04日
逢着(ほうちゃく)
ツルハシブックスは、
「偶然」という名のアートプロジェクトだった。
そしてそれは、
「居場所」になることによって、
急速に「偶然」機能を失っていく。
「居場所」は日常であるからだ。
そして「常連」は、コミュニティであるからだ。
昨日は千林商店街を
陸奥賢さんと一緒に歩いた。




寄贈本読書会の中で、
陸奥さんが放つ一言一言にちょっとドキドキした。
かつて、わが国には「歌垣」というものがあり、
そこで、男女が歌を歌いあって、求愛したという。
歌垣は、世間から離れた場であり、
そこでは、人は、この世のものではなくなった。
匿名性のある人になり、
歌を歌いあい、愛を求めた。
そんな歌垣を現代に復活させる
「歌垣風呂」という活動を陸奥さんは行っている。
銭湯で男女が
男湯女湯に分かれて歌を歌いあう。
そのフィーリングで、カップルが成立するという
「感性合コン」だ。
顔が見えない相手を、
声と雰囲気で判断し、この人よさそうだな、と決める。
そんな企画。
ああ。
もう一度、「考える」から「感じる」への
シフトが始まっているんだなと。
いや、そもそも、現在のお見合いのシステムのように、
年収いくらとか職業はなにか、とか年齢条件とか、
そんな言語化できる情報で、結婚相手を決めるなんて、
そんな「効率的」な方法で本当にいいのだろうか?
それって、この150年の「近代国民国家」、
つまり、「富国強兵」的な、効率を重視した
システムの中だけの常識なんじゃないか。
もっと人は、感性を発動させていいと思う。
いや、そのほうが圧倒的に自然というか、普通だろうと思う。
陸奥さんのやっている活動は、
「歌垣風呂」だけでなく、
「まわしよみ新聞」にしても、
「直観読みブックマーカー」にしても、
「偶然」と「必然」のあいだ
を行き来しているように思う。
そして人間の持つ「感性」をより研ぎ澄ます
ような活動であるように思う。
時代の最先端。
これからは「感じる」時代なのだ、きっと。
もしかしたら、暗やみ本屋ハックツも、
そんな場所なのかもしれない。
そんな陸奥さんに、
偶然と必然のあいだってなんていうんですか?
って聞いてみたら、
逢着(ほうちゃく)っていう言葉が返ってきた。
逢着(ほうちゃく)
[名](スル)出あうこと。出くわすこと。行きあたること。「難問に―する」
(コトバンクより)
なるほど。
意図しているのか意図していないのか、
のぎりぎりのところで出会うこと。
アクシデントではなく、
予定通りでもなく、逢着する。
同じ出来事が人によって、
偶然とも必然ともとれるのだけど、
そうそう。
それって逢着なんだね。
そういうのに出会える場所のことを
第3の場所と呼ぶのかもしれないなと思った。
僕がツルハシブックスを
「偶然」が起こる「本屋のような劇場」と名乗っていたのは、
おそらくは、その「逢着」を生みたかったのだ。
少しだけ意図しているけど、
たまたま出会う何か。
それを感じ取る感性。
それが本屋さんであるということなのかもしれない。
本屋さんが第3の場所であることなのかもしれない。
場としての緊張感、一期一会が
必要なのかもしれない。
偶然と必然のあいだ。
そこに、ひとりひとりの感性を発動させ、
つかみとり、そこから未来が始まっていくのだ、きっと。
「偶然」という名のアートプロジェクトだった。
そしてそれは、
「居場所」になることによって、
急速に「偶然」機能を失っていく。
「居場所」は日常であるからだ。
そして「常連」は、コミュニティであるからだ。
昨日は千林商店街を
陸奥賢さんと一緒に歩いた。




寄贈本読書会の中で、
陸奥さんが放つ一言一言にちょっとドキドキした。
かつて、わが国には「歌垣」というものがあり、
そこで、男女が歌を歌いあって、求愛したという。
歌垣は、世間から離れた場であり、
そこでは、人は、この世のものではなくなった。
匿名性のある人になり、
歌を歌いあい、愛を求めた。
そんな歌垣を現代に復活させる
「歌垣風呂」という活動を陸奥さんは行っている。
銭湯で男女が
男湯女湯に分かれて歌を歌いあう。
そのフィーリングで、カップルが成立するという
「感性合コン」だ。
顔が見えない相手を、
声と雰囲気で判断し、この人よさそうだな、と決める。
そんな企画。
ああ。
もう一度、「考える」から「感じる」への
シフトが始まっているんだなと。
いや、そもそも、現在のお見合いのシステムのように、
年収いくらとか職業はなにか、とか年齢条件とか、
そんな言語化できる情報で、結婚相手を決めるなんて、
そんな「効率的」な方法で本当にいいのだろうか?
それって、この150年の「近代国民国家」、
つまり、「富国強兵」的な、効率を重視した
システムの中だけの常識なんじゃないか。
もっと人は、感性を発動させていいと思う。
いや、そのほうが圧倒的に自然というか、普通だろうと思う。
陸奥さんのやっている活動は、
「歌垣風呂」だけでなく、
「まわしよみ新聞」にしても、
「直観読みブックマーカー」にしても、
「偶然」と「必然」のあいだ
を行き来しているように思う。
そして人間の持つ「感性」をより研ぎ澄ます
ような活動であるように思う。
時代の最先端。
これからは「感じる」時代なのだ、きっと。
もしかしたら、暗やみ本屋ハックツも、
そんな場所なのかもしれない。
そんな陸奥さんに、
偶然と必然のあいだってなんていうんですか?
って聞いてみたら、
逢着(ほうちゃく)っていう言葉が返ってきた。
逢着(ほうちゃく)
[名](スル)出あうこと。出くわすこと。行きあたること。「難問に―する」
(コトバンクより)
なるほど。
意図しているのか意図していないのか、
のぎりぎりのところで出会うこと。
アクシデントではなく、
予定通りでもなく、逢着する。
同じ出来事が人によって、
偶然とも必然ともとれるのだけど、
そうそう。
それって逢着なんだね。
そういうのに出会える場所のことを
第3の場所と呼ぶのかもしれないなと思った。
僕がツルハシブックスを
「偶然」が起こる「本屋のような劇場」と名乗っていたのは、
おそらくは、その「逢着」を生みたかったのだ。
少しだけ意図しているけど、
たまたま出会う何か。
それを感じ取る感性。
それが本屋さんであるということなのかもしれない。
本屋さんが第3の場所であることなのかもしれない。
場としての緊張感、一期一会が
必要なのかもしれない。
偶然と必然のあいだ。
そこに、ひとりひとりの感性を発動させ、
つかみとり、そこから未来が始まっていくのだ、きっと。
2016年12月02日
「居場所」と「環境」と「コミュニケーション」
「西田さんにとって本とは、なんですか?」
おおお。
「プロフェッショナル~仕事の流儀」だ!
と興奮した。
11月30日の井上有紀卒論応援イベントでの
とある大学生からの質問。
出てきた「キーワード」
畑のある本屋
本屋+米屋+農+福祉
居場所のジレンマ
「居場所」をつくりたかったわけではなかった。
なぜ本、本屋なのか?
ツルハシブックスのラスト1年。
2016年は、居場所のジレンマとの戦いだった。
そして、その戦いに、おそらくは敗北した。
勝てなかった、居場所のジレンマ。
居場所のジレンマとは、
居心地のいい場所は、
誰かにとっての「居場所」になりやすく、
その絶対数が増えてくると、「常連」と呼ばれる人が
その場所を占拠するようになり、
それは初めて来る人にとっては、「居心地の悪い」場所になってしまう
というものだ。
それは越えられたのか?
それとも、空間の力の限界だったのか。
それは、これから問いかけていくことなのかもしれない。
朝6時に集まり、
畑に立ち、農作業をして、おかずを調理し
囲炉裏を囲んで朝ごはんを食べる。

そこには、だれもが「存在を許される」場がある。
そんな「まきどき村」の包容力はどこからくるのか?
なぜ、まきどき村で許容できて、
ツルハシブックスでは許容できないのか。
そんなことを思索していたら、
「コミュニケーション」というキーワードが降りてくる。
人と人は「コミュニケーション」している。
それは、言語で、もしくは非言語で。
冒頭の、なぜ本なのか?本屋なのか?
という質問に対して、とっさに出た答えは、
「本が多様性を表現しているから」
そうそう。
本がそもそも「多様性」だから。
ツルハシブックスは、「偶然」という名のアートだった。
「偶然」を生むには「多様性」が必要だった。
多様性が偶然性をはぐくみ、
偶然性が可能性をはぐくむ。
かっこよく言えばそういう場所だった。
しかし。
まきどき村とツルハシブックスの最大の違いは、
ツルハシブックスには、
言語によるコミュニケーションに圧倒的に依存しているということだ。
これは環境のせいだ。
駅前にある「オシャレなブックカフェ」では、
コミュニケーションの主な方法は、言語によるコミュニケーションだ。
そもそも本だって、言語によって多様性を表現しているのだ。
ところが、まきどき村は、そうではない。
体を動かす、草を取る、火を炊く、ご飯をつくる
そうしているあいだに、
非言語のコミュニケーションがはかられていく。
それなんじゃないか。
世の中には、言語によるコミュニケーションが苦手な人が一定の割合存在する。
おそらく、まきどき村に通っていた
不登校だったTちゃんは、そのひとりだろう。
しかし、あの場所、あの空間、あの時間では、
別に言語によるコミュニケーションを行わなくても、
人と非言語コミュニケーションができる。
それが「居場所」という瞬間をつくっていたのではないか。
「畑のある本屋」っていうのは、
そういう非言語コミュニケーションの機会をつくる、
ということなのかもしれない。
なんか、もう少しだ。
見えてきつつある気がする。
おおお。
「プロフェッショナル~仕事の流儀」だ!
と興奮した。
11月30日の井上有紀卒論応援イベントでの
とある大学生からの質問。
出てきた「キーワード」
畑のある本屋
本屋+米屋+農+福祉
居場所のジレンマ
「居場所」をつくりたかったわけではなかった。
なぜ本、本屋なのか?
ツルハシブックスのラスト1年。
2016年は、居場所のジレンマとの戦いだった。
そして、その戦いに、おそらくは敗北した。
勝てなかった、居場所のジレンマ。
居場所のジレンマとは、
居心地のいい場所は、
誰かにとっての「居場所」になりやすく、
その絶対数が増えてくると、「常連」と呼ばれる人が
その場所を占拠するようになり、
それは初めて来る人にとっては、「居心地の悪い」場所になってしまう
というものだ。
それは越えられたのか?
それとも、空間の力の限界だったのか。
それは、これから問いかけていくことなのかもしれない。
朝6時に集まり、
畑に立ち、農作業をして、おかずを調理し
囲炉裏を囲んで朝ごはんを食べる。

そこには、だれもが「存在を許される」場がある。
そんな「まきどき村」の包容力はどこからくるのか?
なぜ、まきどき村で許容できて、
ツルハシブックスでは許容できないのか。
そんなことを思索していたら、
「コミュニケーション」というキーワードが降りてくる。
人と人は「コミュニケーション」している。
それは、言語で、もしくは非言語で。
冒頭の、なぜ本なのか?本屋なのか?
という質問に対して、とっさに出た答えは、
「本が多様性を表現しているから」
そうそう。
本がそもそも「多様性」だから。
ツルハシブックスは、「偶然」という名のアートだった。
「偶然」を生むには「多様性」が必要だった。
多様性が偶然性をはぐくみ、
偶然性が可能性をはぐくむ。
かっこよく言えばそういう場所だった。
しかし。
まきどき村とツルハシブックスの最大の違いは、
ツルハシブックスには、
言語によるコミュニケーションに圧倒的に依存しているということだ。
これは環境のせいだ。
駅前にある「オシャレなブックカフェ」では、
コミュニケーションの主な方法は、言語によるコミュニケーションだ。
そもそも本だって、言語によって多様性を表現しているのだ。
ところが、まきどき村は、そうではない。
体を動かす、草を取る、火を炊く、ご飯をつくる
そうしているあいだに、
非言語のコミュニケーションがはかられていく。
それなんじゃないか。
世の中には、言語によるコミュニケーションが苦手な人が一定の割合存在する。
おそらく、まきどき村に通っていた
不登校だったTちゃんは、そのひとりだろう。
しかし、あの場所、あの空間、あの時間では、
別に言語によるコミュニケーションを行わなくても、
人と非言語コミュニケーションができる。
それが「居場所」という瞬間をつくっていたのではないか。
「畑のある本屋」っていうのは、
そういう非言語コミュニケーションの機会をつくる、
ということなのかもしれない。
なんか、もう少しだ。
見えてきつつある気がする。




