2012年09月30日
未来は僕らの手の中
昨日は、玉城ちはるさんのミニライブ、
ちはるさんに財津正人さんと僕を加え
3人でのトークセッションでした。
超おもしろかった。
ライブは胸にしみこむような歌声で、
こころを洗い流してくれました。
そしてトークライブ
やっぱり財津さんの時代観、社会観と
僕は非常に近いなあと思いました。
そういう人と話すと面白いなあって。
財津さんの
「本を救うのは俺しかいない」って
すごくよかったなあと思いました。
そういう勘違いで熱く生きれる人ってやっぱ楽しいよね。
先行きの見えない時代。
不安でいっぱいになる。
でも。
こんな時代だからこそ、
自分で未来をつかめる時代だと思う。
国全体が高度経済成長の真っただ中にあった時代。
夢のような未来が約束されていた時代よりも、
今のような先行きの見えない時代は、
個人がつかみたい未来へ向けて歩き始めるときだ。
この時代に生まれて、生きてよかったと思う。
そう。
未来は僕らの手の中。
玉城さん、財津さん、甲本ヒロトさん、ありがとう。
ちはるさんに財津正人さんと僕を加え
3人でのトークセッションでした。
超おもしろかった。
ライブは胸にしみこむような歌声で、
こころを洗い流してくれました。
そしてトークライブ
やっぱり財津さんの時代観、社会観と
僕は非常に近いなあと思いました。
そういう人と話すと面白いなあって。
財津さんの
「本を救うのは俺しかいない」って
すごくよかったなあと思いました。
そういう勘違いで熱く生きれる人ってやっぱ楽しいよね。
先行きの見えない時代。
不安でいっぱいになる。
でも。
こんな時代だからこそ、
自分で未来をつかめる時代だと思う。
国全体が高度経済成長の真っただ中にあった時代。
夢のような未来が約束されていた時代よりも、
今のような先行きの見えない時代は、
個人がつかみたい未来へ向けて歩き始めるときだ。
この時代に生まれて、生きてよかったと思う。
そう。
未来は僕らの手の中。
玉城さん、財津さん、甲本ヒロトさん、ありがとう。
2012年09月28日
なぜ、ヨソモノ、ワカモノ、バカモノなのか?
森田英一さんの
「こんなに働いているのになぜ会社は良くならないのか?」
読みました。
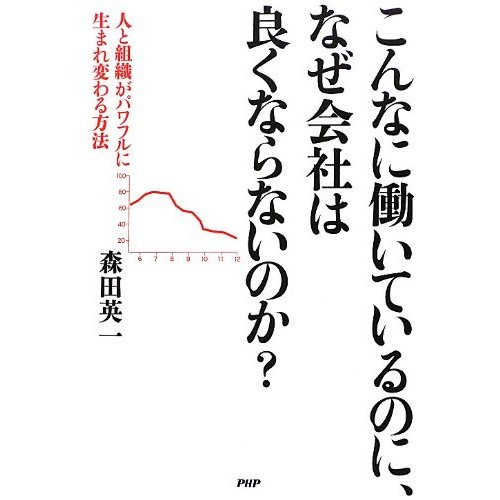
最後の物語はシビれますよ。
熱いです。
カミナリが落ちるような衝撃を受けたのは、
いま、世の中で全盛となっている、
「コミュニケーション力」とは、
いったい何のためにつけなければいけないのか。
そんな問いへのアプローチが
この本だった。
会話でも議論でもない
対話(ダイアログ)の重要性。
どのように場を作っていくか。
そしてどのようにチームは変わっていくのか。
そんなことが希望ある未来として
描かれている。
会社組織だけではなく、
地域社会においてもまったく当てはまる話だと思った。
地域社会の変革に必要なのは、
ヨソモノ、ワカモノ、バカモノだという。
このうち、
ヨソモノとワカモノの役割とは何か?
そう。
重要な役割は
コミュニケーションの媒体となること。
ムラの人が普段、オフィシャルな場では
言えないことを吸い上げ、まとめていくこと。
ヒアリングによって、
まちの当事者をつくっていくこと。
なんでもやってみようとアクションし、
失敗したことを、そこから学びにつなげ、それを活かすこと。
そして何より、
本書で触れられているように
「感じる力」、感性の重要性だ。
相手の考えを理解する。
そこから始まっていく組織の変革。
僕はこの本を読んで、
大げさだけど、「世界は変えられる」って思った。
コミュニケーションが組織を、そして世界を変えていくのだと。
だから、コミュニケーション力が必要なんですね、森田さん。
コミュニケーション力は個人のスキルではなく、
組織変革、社会変革の原動力なのだとこの本を読んで実感しました。
僕もファシリテーターになりたくなりました。
新しい夢をありがとう。
「こんなに働いているのになぜ会社は良くならないのか?」
読みました。
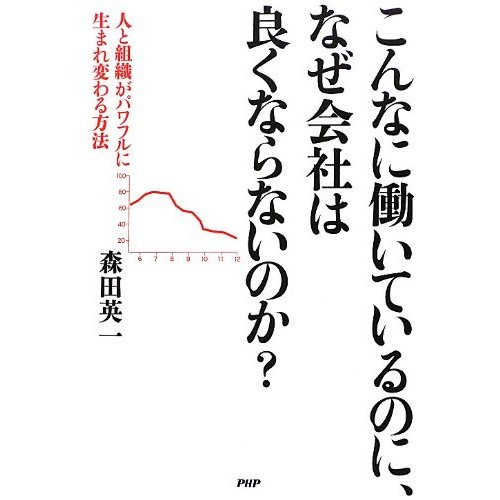
最後の物語はシビれますよ。
熱いです。
カミナリが落ちるような衝撃を受けたのは、
いま、世の中で全盛となっている、
「コミュニケーション力」とは、
いったい何のためにつけなければいけないのか。
そんな問いへのアプローチが
この本だった。
会話でも議論でもない
対話(ダイアログ)の重要性。
どのように場を作っていくか。
そしてどのようにチームは変わっていくのか。
そんなことが希望ある未来として
描かれている。
会社組織だけではなく、
地域社会においてもまったく当てはまる話だと思った。
地域社会の変革に必要なのは、
ヨソモノ、ワカモノ、バカモノだという。
このうち、
ヨソモノとワカモノの役割とは何か?
そう。
重要な役割は
コミュニケーションの媒体となること。
ムラの人が普段、オフィシャルな場では
言えないことを吸い上げ、まとめていくこと。
ヒアリングによって、
まちの当事者をつくっていくこと。
なんでもやってみようとアクションし、
失敗したことを、そこから学びにつなげ、それを活かすこと。
そして何より、
本書で触れられているように
「感じる力」、感性の重要性だ。
相手の考えを理解する。
そこから始まっていく組織の変革。
僕はこの本を読んで、
大げさだけど、「世界は変えられる」って思った。
コミュニケーションが組織を、そして世界を変えていくのだと。
だから、コミュニケーション力が必要なんですね、森田さん。
コミュニケーション力は個人のスキルではなく、
組織変革、社会変革の原動力なのだとこの本を読んで実感しました。
僕もファシリテーターになりたくなりました。
新しい夢をありがとう。
2012年09月27日
NHK新潟のニュースで取り上げられました
昨日放送の
NHK新潟ローカルで
ツルハシブックスの地下古本コーナーHAKKUTSUが
取り上げられました。
http://www.youtube.com/watch?v=fRuF8roBJvc&feature=player_embedded
みなさまからの
熱い本の寄贈、お待ちしています。
NHK新潟ローカルで
ツルハシブックスの地下古本コーナーHAKKUTSUが
取り上げられました。
http://www.youtube.com/watch?v=fRuF8roBJvc&feature=player_embedded
みなさまからの
熱い本の寄贈、お待ちしています。
2012年09月26日
本というコミュニケーションツール
面と向かって人と話すのは、
すごくストレスがかかることだ。
相手がどう思っているのか、
自分はどんな表情をすればいいのか。
うまく話せているか、伝わっているか。
だから、
流れのいいコミュニケーションには媒体が必要だ。
たとえば、
大学生男子が思いを寄せる誰かと食事に行くとする。
そのとき、ついついトークが空回りしてしまいがちになる。
そんなときに、うまく話すためにはどうしたらいいか?
そんなテクニックがいろんな雑誌や本で紹介されていると思う。
僕のソリューション(解決策)は、
どこに食事に行くか?を考えることだ。
イタリアンとか、釜飯とか、
提供までに時間がかかるものは、話を続けるのが相当たいへんだ。
かといって、牛丼を食べるわけにはいかないし。
おすすめはお好み焼き、もんじゃ焼き。
注文するとすぐにテーブルに運ばれてくる。
さっそく夫婦最初の(?)共同作業の始まりだ。
混ぜて、焼いて、焼けたかな。
自分たちの話意外に話のネタが豊富にある。
これで話が盛り上がったような気分になるはずだ。
一方。
僕は、学生時代、ずっと学習塾でアルバイトをしていた。
個別指導の学習塾でかなりの熱血ぶりでやっていた。
そのころから、感じていたこと。
中学生(特に女子)の学校でのストレスはハンパない
だから、学校以外の居場所(今でいう第3の場所)が必要だ
と思っていた。
そして、2002年に運命を変えた中学校3年生との出会い。
不登校だった彼と出会い、人生は決まった。
いろんな世代や、いろんな生き方をしている大人と
人生に迷う中学生・高校生が出会うにはどうしたらいいのか?
そんな座右の問いに出会えた。
まずは学習塾を自分で立ち上げた
最大4名の子どもたちと、騒がしい塾をやっていた。
あれは楽しかったが、
自分ひとりしか出会っていないことが残念だった。
次に取り組んだのは巻町のまちなか拠点づくり。
そこでも不登校の中学生に出会う。
おにぎりやのおばちゃんと語らう彼らを見て、
第3の大人の存在の大きさを実感。
小学生の時から地域と関わるようにと
取り組んだ子どもの遊び場づくりは、
現在も「遊びの屋台村、だがしや楽校」として、
まちづくり協議会に受け継がれ、
今年も10月7日に巻の商店街で開催される。
その後大学生のインターンシップ事業を開始したが、
中学生・高校生にアプローチできないことがもやもやしていた。
2011年3月。
東日本大震災の最中、
念願だった本屋さんを開く機会に恵まれた。
6月、一箱古本市でひらめいた。
若者のための古本屋さんをやろう、と。
地域の大人と中学生・高校生がつながれる
古本屋さんがあったらいい。
そこは彼らにとって学校、家庭以外の第3の場所であり、
地域の大人に出会う場所。
「本」を通じて、コミュニケーションができる場なのだ。
「本」はまだ、その可能性を活かしきれてない。
マンガ「スラムダンク」で仙道が流川になげかけたセリフが
なんども胸を通り抜ける。
本も、人も、まちも、
まだその可能性を活かしきれてない。
だからそれをつなぐのだ。
それがコミュニティデザインなのではないのかな。
地下古本コーナー「HAKKUTSU~発掘」が
27日(木)の夕方の新潟ニュース610で放映される予定です。
お楽しみに。
また「本の可能性を探る」という意味では
同志であり、心のアニキである
財津正人さんとのコラボイベント
玉城ちはる「風になれば」出版記念
ミニライブ&3人のトークライブが
9月29日(土)15:00~
カフェコポコポで開催されます。
参加費は1,000円。
ここにも魂を込めていきたいと思います。
http://tsuruhashi.niiblo.jp/e191822.html
僕たちはまだ、可能性を活かしきれてない。
すごくストレスがかかることだ。
相手がどう思っているのか、
自分はどんな表情をすればいいのか。
うまく話せているか、伝わっているか。
だから、
流れのいいコミュニケーションには媒体が必要だ。
たとえば、
大学生男子が思いを寄せる誰かと食事に行くとする。
そのとき、ついついトークが空回りしてしまいがちになる。
そんなときに、うまく話すためにはどうしたらいいか?
そんなテクニックがいろんな雑誌や本で紹介されていると思う。
僕のソリューション(解決策)は、
どこに食事に行くか?を考えることだ。
イタリアンとか、釜飯とか、
提供までに時間がかかるものは、話を続けるのが相当たいへんだ。
かといって、牛丼を食べるわけにはいかないし。
おすすめはお好み焼き、もんじゃ焼き。
注文するとすぐにテーブルに運ばれてくる。
さっそく夫婦最初の(?)共同作業の始まりだ。
混ぜて、焼いて、焼けたかな。
自分たちの話意外に話のネタが豊富にある。
これで話が盛り上がったような気分になるはずだ。
一方。
僕は、学生時代、ずっと学習塾でアルバイトをしていた。
個別指導の学習塾でかなりの熱血ぶりでやっていた。
そのころから、感じていたこと。
中学生(特に女子)の学校でのストレスはハンパない
だから、学校以外の居場所(今でいう第3の場所)が必要だ
と思っていた。
そして、2002年に運命を変えた中学校3年生との出会い。
不登校だった彼と出会い、人生は決まった。
いろんな世代や、いろんな生き方をしている大人と
人生に迷う中学生・高校生が出会うにはどうしたらいいのか?
そんな座右の問いに出会えた。
まずは学習塾を自分で立ち上げた
最大4名の子どもたちと、騒がしい塾をやっていた。
あれは楽しかったが、
自分ひとりしか出会っていないことが残念だった。
次に取り組んだのは巻町のまちなか拠点づくり。
そこでも不登校の中学生に出会う。
おにぎりやのおばちゃんと語らう彼らを見て、
第3の大人の存在の大きさを実感。
小学生の時から地域と関わるようにと
取り組んだ子どもの遊び場づくりは、
現在も「遊びの屋台村、だがしや楽校」として、
まちづくり協議会に受け継がれ、
今年も10月7日に巻の商店街で開催される。
その後大学生のインターンシップ事業を開始したが、
中学生・高校生にアプローチできないことがもやもやしていた。
2011年3月。
東日本大震災の最中、
念願だった本屋さんを開く機会に恵まれた。
6月、一箱古本市でひらめいた。
若者のための古本屋さんをやろう、と。
地域の大人と中学生・高校生がつながれる
古本屋さんがあったらいい。
そこは彼らにとって学校、家庭以外の第3の場所であり、
地域の大人に出会う場所。
「本」を通じて、コミュニケーションができる場なのだ。
「本」はまだ、その可能性を活かしきれてない。
マンガ「スラムダンク」で仙道が流川になげかけたセリフが
なんども胸を通り抜ける。
本も、人も、まちも、
まだその可能性を活かしきれてない。
だからそれをつなぐのだ。
それがコミュニティデザインなのではないのかな。
地下古本コーナー「HAKKUTSU~発掘」が
27日(木)の夕方の新潟ニュース610で放映される予定です。
お楽しみに。
また「本の可能性を探る」という意味では
同志であり、心のアニキである
財津正人さんとのコラボイベント
玉城ちはる「風になれば」出版記念
ミニライブ&3人のトークライブが
9月29日(土)15:00~
カフェコポコポで開催されます。
参加費は1,000円。
ここにも魂を込めていきたいと思います。
http://tsuruhashi.niiblo.jp/e191822.html
僕たちはまだ、可能性を活かしきれてない。
2012年09月22日
研究会というキラーコンテンツ
あまり知られていないけど、
ツルハシブックスを含むビルの正式名称は
「ウチノ・コラボレーション・ラボラトリー」。
キャッチコピーは
「明日の実験室」
月に1,2度行われている
コミュニティデザイン研究会が
すごい盛況で
フェイスブックで次回日程をアップした
その日に定員が埋まるという事態になっている。
木曜日は遠く、
加茂、十日町からも参加。
ビックリしました。
すごいなあ。
ひとえに
主催のなっぱさんの人柄だなあ。
って思います。
あとは「研究会」っていうのが人を惹きつける
のではないかなと思います。
知的好奇心。
共に学びたい。
そして、何か、世の中をよりよくしたい。
そんな研究会がたくさんあふれると、
まちは活気を取り戻すのかもしれないと思いました。
半農半X研究所を主宰する塩見直紀さんが
言っていました
「1人1研究所の時代」
世の中のために、ひとりひとりが、
何か研究所を作る時代になってきている、
10年前の塩見さんの言葉が
いままさに現実になりつつあります。
僕は、この10年。
「中学生とまちの大人がナチュラルに出会える空間」研究所
をやっていたのだと思います。
研究会から研究所へ。
ウチノ・コラボレーション・ラボラトリーは、
みなさんと共に、探求し続ける実験室で
ありたいと思います。
あなたの研究したいこと、追究したいことはなんですか?
研究会の開催は、
ぜひ、カフェコポコポ、ツルハシブックスを
ご利用下さい。
笹川さん、ボードゲーム研究会、いかがですか?
ツルハシブックスを含むビルの正式名称は
「ウチノ・コラボレーション・ラボラトリー」。
キャッチコピーは
「明日の実験室」
月に1,2度行われている
コミュニティデザイン研究会が
すごい盛況で
フェイスブックで次回日程をアップした
その日に定員が埋まるという事態になっている。
木曜日は遠く、
加茂、十日町からも参加。
ビックリしました。
すごいなあ。
ひとえに
主催のなっぱさんの人柄だなあ。
って思います。
あとは「研究会」っていうのが人を惹きつける
のではないかなと思います。
知的好奇心。
共に学びたい。
そして、何か、世の中をよりよくしたい。
そんな研究会がたくさんあふれると、
まちは活気を取り戻すのかもしれないと思いました。
半農半X研究所を主宰する塩見直紀さんが
言っていました
「1人1研究所の時代」
世の中のために、ひとりひとりが、
何か研究所を作る時代になってきている、
10年前の塩見さんの言葉が
いままさに現実になりつつあります。
僕は、この10年。
「中学生とまちの大人がナチュラルに出会える空間」研究所
をやっていたのだと思います。
研究会から研究所へ。
ウチノ・コラボレーション・ラボラトリーは、
みなさんと共に、探求し続ける実験室で
ありたいと思います。
あなたの研究したいこと、追究したいことはなんですか?
研究会の開催は、
ぜひ、カフェコポコポ、ツルハシブックスを
ご利用下さい。
笹川さん、ボードゲーム研究会、いかがですか?
2012年09月21日
機会提供というゴール
本を読んだ人にどうなってもらいたいか。
ここで人と出会った人がどうなってもらいたいか。
夢を持って前向きに生きていってほしい。
行動しなかった誰かが行動するようになってほしい。
つらさを抱えていた子どものつらさがやわらぐように。
それは、そうなんだけど、そこがゴールではない。
達成目標ではない。
その人の人生にとって、
少しのきっかけとなれば、それでよい。
そのきっかけを提供したこと。
それだけで、価値があると思う。
つまり、機会提供の時点でひとつのゴールを迎えている。
目的最適化。
これが苦しさを生んでいるとすると、
その苦しさを和らげるような1冊や1人の人に出会う。
それだけで十分なのではないかと思う。
価値観の画一化こそ不幸への入り口だ。
そこに一石を投じる場所。
それがツルハシブックスなのかもしれない。
今日も、明日も
ツルハシブックスは機会であふれています。
ここで人と出会った人がどうなってもらいたいか。
夢を持って前向きに生きていってほしい。
行動しなかった誰かが行動するようになってほしい。
つらさを抱えていた子どものつらさがやわらぐように。
それは、そうなんだけど、そこがゴールではない。
達成目標ではない。
その人の人生にとって、
少しのきっかけとなれば、それでよい。
そのきっかけを提供したこと。
それだけで、価値があると思う。
つまり、機会提供の時点でひとつのゴールを迎えている。
目的最適化。
これが苦しさを生んでいるとすると、
その苦しさを和らげるような1冊や1人の人に出会う。
それだけで十分なのではないかと思う。
価値観の画一化こそ不幸への入り口だ。
そこに一石を投じる場所。
それがツルハシブックスなのかもしれない。
今日も、明日も
ツルハシブックスは機会であふれています。
2012年09月20日
もっとちゃんと誘えばよかった
「思い立ったが吉日」人生を生きている僕は、
「後悔」ってあまりすることないのだけど、
いつも、後悔する瞬間がある。
自分が主催したイベントで
いい空間ができていたとき。
「ああ、もっとちゃんと告知すればよかったな」
「あの人に、この空間にいてほしかったな」
「ここにあの人がいたら、人生に影響を与えただろうな」
って後悔する。
ニイダヤ水産復活をかけた
NPO法人素材広場のインターンシップ。
ニイダヤ水産の賀沢さん素材広場の横田さんに出会い、業務を共にできるということで、
人生に大きな変化が訪れるだろうと僕は思うし、
今やっている大学生たちはきっとそれを実感していることと思う。
いや、もしかしたら、
それが発現するのは3年、いや5年かかるのかもしれないが
きっと糧になるのだろうと思う。
いや、僕がそう信じているだけでもしかしたらそうではないのかもしれない。
でも。
それでいいのだと思う。
「影響力のある大人と接すると、大学生の人生がそっちに流されるので危険だ」
と聞いたことがある。
その大人が魅力的であればあるほど、
流される大学生もいるだろうと思う。
「大学生は経験が少ないから、その道がそれでいいのか、判断できない」
それもおそらくその通りだろう。
だから、大学に入って宗教に誘われ、ハマってしまう人たちもいる。
それでは、入学早々、楽しそうなサークルに入って、
毎日カラオケや飲み会をやっている大学生は
自分の意思があって素晴らしいのだろうか。
彼らは、大学3年生の秋になって立ち止まり、
人生の意味を問わないのだろうか。
内田樹さんは
著書「街場のメディア論」の中で、
メディアが凋落したのは、メディアが発する言葉に、
自分の人生を賭けなくなったからだと言った。
「世論はこのように言っている」
というような締めで語るニュースキャスター
「道徳的にいかがなものか」
と語る新聞記者
誰も、自分の人生を賭けて、メッセージを発していない。
当たり前のことだが、誰かが人生を賭けたメッセージだけが、
人を変えることができる。
その責任をひたすら放棄しているのが
現在の地域社会ではないだろうか。
「子どもの意思を尊重して」
という言葉は、自らの責任の放棄と同意語だと思う。
いや。
もちろん、最終的にはそれぞれの人の意思で決めるのだが、
そこになんらかの価値観、人生を賭けたメッセージを入れていくことは
していくべきだと思う。
大学生、20代に贈る次のイベントは
シンガーソングライター玉城ちはるさん。
1980年広島県生まれ。
女優として数多くのCM、テレビ番組出演を経て、
シンガーソングライターへ。
2011年にアルバム「ここにいること」をリリース
2012年には最新アルバム「ひだまり」をリリース
音楽活動と並行し「自身にできる社会貢献・平和活動」という
観点からこれまでに24名のアジア地域留学生をホストマザーとして
共に生活し、送り出している。
9月29日(土)15:00~
カフェ・コポコポで開催。
入場 1,000円
(17:30~の懇親会は別途2,000円)
昨年9月に来店した財津正人さんと
共に登場します。
僕は財津さんの空気感が大好きで、
一緒にいるだけでとてもワクワクした気持ちになります。
その財津さんが出版社を立ち上げた
第1作目が玉城ちはるさんの「風になれば」です。
その発売を記念しての新潟来県となります。
僕自身がとてもわくわくしています。
後悔しないように、ちゃんと告知したいと思います。
「後悔」ってあまりすることないのだけど、
いつも、後悔する瞬間がある。
自分が主催したイベントで
いい空間ができていたとき。
「ああ、もっとちゃんと告知すればよかったな」
「あの人に、この空間にいてほしかったな」
「ここにあの人がいたら、人生に影響を与えただろうな」
って後悔する。
ニイダヤ水産復活をかけた
NPO法人素材広場のインターンシップ。
ニイダヤ水産の賀沢さん素材広場の横田さんに出会い、業務を共にできるということで、
人生に大きな変化が訪れるだろうと僕は思うし、
今やっている大学生たちはきっとそれを実感していることと思う。
いや、もしかしたら、
それが発現するのは3年、いや5年かかるのかもしれないが
きっと糧になるのだろうと思う。
いや、僕がそう信じているだけでもしかしたらそうではないのかもしれない。
でも。
それでいいのだと思う。
「影響力のある大人と接すると、大学生の人生がそっちに流されるので危険だ」
と聞いたことがある。
その大人が魅力的であればあるほど、
流される大学生もいるだろうと思う。
「大学生は経験が少ないから、その道がそれでいいのか、判断できない」
それもおそらくその通りだろう。
だから、大学に入って宗教に誘われ、ハマってしまう人たちもいる。
それでは、入学早々、楽しそうなサークルに入って、
毎日カラオケや飲み会をやっている大学生は
自分の意思があって素晴らしいのだろうか。
彼らは、大学3年生の秋になって立ち止まり、
人生の意味を問わないのだろうか。
内田樹さんは
著書「街場のメディア論」の中で、
メディアが凋落したのは、メディアが発する言葉に、
自分の人生を賭けなくなったからだと言った。
「世論はこのように言っている」
というような締めで語るニュースキャスター
「道徳的にいかがなものか」
と語る新聞記者
誰も、自分の人生を賭けて、メッセージを発していない。
当たり前のことだが、誰かが人生を賭けたメッセージだけが、
人を変えることができる。
その責任をひたすら放棄しているのが
現在の地域社会ではないだろうか。
「子どもの意思を尊重して」
という言葉は、自らの責任の放棄と同意語だと思う。
いや。
もちろん、最終的にはそれぞれの人の意思で決めるのだが、
そこになんらかの価値観、人生を賭けたメッセージを入れていくことは
していくべきだと思う。
大学生、20代に贈る次のイベントは
シンガーソングライター玉城ちはるさん。
1980年広島県生まれ。
女優として数多くのCM、テレビ番組出演を経て、
シンガーソングライターへ。
2011年にアルバム「ここにいること」をリリース
2012年には最新アルバム「ひだまり」をリリース
音楽活動と並行し「自身にできる社会貢献・平和活動」という
観点からこれまでに24名のアジア地域留学生をホストマザーとして
共に生活し、送り出している。
9月29日(土)15:00~
カフェ・コポコポで開催。
入場 1,000円
(17:30~の懇親会は別途2,000円)
昨年9月に来店した財津正人さんと
共に登場します。
僕は財津さんの空気感が大好きで、
一緒にいるだけでとてもワクワクした気持ちになります。
その財津さんが出版社を立ち上げた
第1作目が玉城ちはるさんの「風になれば」です。
その発売を記念しての新潟来県となります。
僕自身がとてもわくわくしています。
後悔しないように、ちゃんと告知したいと思います。
2012年09月19日
目的最適化が唯一の答えではない
中学生・高校生に、「もっとも伝えたいこと」は何か?
と問われたら、何と答えるだろう?
いい問いだなあって思う。
夢を持って前向きに生きてれば、きっとなんとかなる
なんて、言えない。
いや、本当になんとかなるんだけど、
当事者にしてみたら、そんな道徳を聞いたって、
何の心の支えにもならない。
アンジェラ・アキの「手紙」
をテレビの中やi-podから聞いたって、
「自分とは何でどこへ向かうべきか、問い続ければきっと見えてくる」
と言われても、それはそうなんだろうけど、そうはいってもねえ、今おれたちは大変なんだよ。
っていう声が聞こえてくる。
僕が伝えたいことは
「目的最適化が唯一の答えではない」ってことかな。
第3の道。
計画と無計画のあいだ。
効率と非効率のあいだに、大切なものがあるのではないか、ということ。
世の中は工業社会からサービス業社会へと変化し、
仕事が猛烈なスピードで生まれ、そして無くなっていく時代に、
ゴールを決めて、そこに向かっていくだけでは、不十分だという時代背景。
森田英一さんの
「こんなに働いているのになぜ会社は良くならないのか?」(PHP)に
書かれているように、
世の中のビジネスは大きく変わった。
1 加速するスピード
2 高まる時間的・空間的複雑性
3 高まる社会的複雑性
4 誰も答えを知らない
この変化に、キャリア教育は無縁ではいられない。
なりたい職業
という唯一の答えにたいして向かっていくだけが
正しいわけでは決してない。
第3の道を視野に入れた上で
夢や目標を設定し、そこに進んでいくこと。
それが必要なのではないか。
目的最適化の考え方は
生きづらさしか生んでいない。
もし、不登校になったら、
もし、就活に失敗したら、
もし、会社を1年で辞めたら。
目的最適化からもっとも遠い自分がそこにいる。
そのつらさ。
まずはそこから解放しよう。
まちの本屋さんの役割は
まさにその第3の道を提示すること。
大型書店やネット書店が
「目的にあった本をいち早く検索して購入できる」
ことを目指しているのなら、
まちの本屋さんは、
「人生の寄り道を促す、心に余裕を持たせる本や人に出会うヒントを提示する」ことなのかもしれない。
今こそ、まちの本屋さんの出番なのです。
と問われたら、何と答えるだろう?
いい問いだなあって思う。
夢を持って前向きに生きてれば、きっとなんとかなる
なんて、言えない。
いや、本当になんとかなるんだけど、
当事者にしてみたら、そんな道徳を聞いたって、
何の心の支えにもならない。
アンジェラ・アキの「手紙」
をテレビの中やi-podから聞いたって、
「自分とは何でどこへ向かうべきか、問い続ければきっと見えてくる」
と言われても、それはそうなんだろうけど、そうはいってもねえ、今おれたちは大変なんだよ。
っていう声が聞こえてくる。
僕が伝えたいことは
「目的最適化が唯一の答えではない」ってことかな。
第3の道。
計画と無計画のあいだ。
効率と非効率のあいだに、大切なものがあるのではないか、ということ。
世の中は工業社会からサービス業社会へと変化し、
仕事が猛烈なスピードで生まれ、そして無くなっていく時代に、
ゴールを決めて、そこに向かっていくだけでは、不十分だという時代背景。
森田英一さんの
「こんなに働いているのになぜ会社は良くならないのか?」(PHP)に
書かれているように、
世の中のビジネスは大きく変わった。
1 加速するスピード
2 高まる時間的・空間的複雑性
3 高まる社会的複雑性
4 誰も答えを知らない
この変化に、キャリア教育は無縁ではいられない。
なりたい職業
という唯一の答えにたいして向かっていくだけが
正しいわけでは決してない。
第3の道を視野に入れた上で
夢や目標を設定し、そこに進んでいくこと。
それが必要なのではないか。
目的最適化の考え方は
生きづらさしか生んでいない。
もし、不登校になったら、
もし、就活に失敗したら、
もし、会社を1年で辞めたら。
目的最適化からもっとも遠い自分がそこにいる。
そのつらさ。
まずはそこから解放しよう。
まちの本屋さんの役割は
まさにその第3の道を提示すること。
大型書店やネット書店が
「目的にあった本をいち早く検索して購入できる」
ことを目指しているのなら、
まちの本屋さんは、
「人生の寄り道を促す、心に余裕を持たせる本や人に出会うヒントを提示する」ことなのかもしれない。
今こそ、まちの本屋さんの出番なのです。
2012年09月18日
「好き」という感性を信じる
人は「好き」という感性を持っている。
粟島で取材を受けた。
なぜ、ニイダヤ水産を応援しているのか?
福島と新潟、いわきと粟島、震災復興・・・
そんなカッコよく言えるような理由などなかった。
理由はひとつ。
会津若松・素材広場の横田さんが応援しているから。
素材広場の横田さんが
震災前に知り合い、活動と思いを聞く上で、
「好き」という感性が生まれてくる。
震災後、新潟大学の菊地さんの被災地復興に何かしたい
という思いを受けて、横田さんに相談。
そこで、ニイダヤ水産のことを知る。
そのとき、僕はニイダヤ水産・賀沢社長には会ったことがなかった。
でも。
プロジェクトは決定した。
横田さんが応援している、なんとしてもつぶしたくない、
そんなニイダヤ水産は僕も好きに違いない、と思った。
キュレーションの時代、だと言われる。
マスメディアで広告されたものよりも
知り合いがフェイスブックでオススメしていた商品に魅力を感じ、
購買につながる。
そう。
僕は横田さんというキュレーターを信じた。
だから、今のプロジェクトがあるのだろうと思う。
もうひとり。
僕の大好きな人がいる。
財津正人さん。
昨年6月の一箱古本市で知り合い、
9月にはイベントをやった。
財津さんは今年、アツイ出版社、本分社を立ち上げ。
その第1号書籍が玉城ちはる「風になれば」だ。
読むと心にさわやかな風が吹き抜ける1冊。
風のように生きたいと思った。
しかし、何より、
僕の大好きな財津さんが、
本を出したい、伝えたいと思った玉城ちはるさんの歌は
素晴らしいに違いないと思っている。
http://tsuruhashi.niiblo.jp/e191822.html
9月29日(土)
15:00~17:00
カフェコポコポで待ってます。
「好き」という感性を信じてみる。
誰かの「好き」にアプローチする。
そこから始まる世界がある。
29日はそんな話をしようと思います。
玉城さんのお話、ミニライブは
20代女性にとって、人生を動かす
インパクトがあると思います。
ツルハシブックスが贈る、
この秋のビックイベント、参加をお待ちしています。
粟島で取材を受けた。
なぜ、ニイダヤ水産を応援しているのか?
福島と新潟、いわきと粟島、震災復興・・・
そんなカッコよく言えるような理由などなかった。
理由はひとつ。
会津若松・素材広場の横田さんが応援しているから。
素材広場の横田さんが
震災前に知り合い、活動と思いを聞く上で、
「好き」という感性が生まれてくる。
震災後、新潟大学の菊地さんの被災地復興に何かしたい
という思いを受けて、横田さんに相談。
そこで、ニイダヤ水産のことを知る。
そのとき、僕はニイダヤ水産・賀沢社長には会ったことがなかった。
でも。
プロジェクトは決定した。
横田さんが応援している、なんとしてもつぶしたくない、
そんなニイダヤ水産は僕も好きに違いない、と思った。
キュレーションの時代、だと言われる。
マスメディアで広告されたものよりも
知り合いがフェイスブックでオススメしていた商品に魅力を感じ、
購買につながる。
そう。
僕は横田さんというキュレーターを信じた。
だから、今のプロジェクトがあるのだろうと思う。
もうひとり。
僕の大好きな人がいる。
財津正人さん。
昨年6月の一箱古本市で知り合い、
9月にはイベントをやった。
財津さんは今年、アツイ出版社、本分社を立ち上げ。
その第1号書籍が玉城ちはる「風になれば」だ。
読むと心にさわやかな風が吹き抜ける1冊。
風のように生きたいと思った。
しかし、何より、
僕の大好きな財津さんが、
本を出したい、伝えたいと思った玉城ちはるさんの歌は
素晴らしいに違いないと思っている。
http://tsuruhashi.niiblo.jp/e191822.html
9月29日(土)
15:00~17:00
カフェコポコポで待ってます。
「好き」という感性を信じてみる。
誰かの「好き」にアプローチする。
そこから始まる世界がある。
29日はそんな話をしようと思います。
玉城さんのお話、ミニライブは
20代女性にとって、人生を動かす
インパクトがあると思います。
ツルハシブックスが贈る、
この秋のビックイベント、参加をお待ちしています。
2012年09月16日
ないよりはあったほうが少しだけいい
夢がある。
目標がある。
なりたい職業がある。
これを過大に評価しすぎだと思う。
夢がある友達はいいなあって思う。
夢がない自分はダメだなあって思う。
その差は
あまりにも大きいように感じる。
天と地の隔たりを感じる。
ここを、何とかしなきゃいかないのではないか。
大げさに言うと、
「夢がない自分は人にあらず」
それくらい、追い詰められている。
たいしたことない。
夢がなくても生きていける。
夢はないよりもあったほうが少しだけ楽しい、
そんくらいだ。
大人たちに、
「将来何になりたいんだ?」と聞かれたら、
「あなたは何になりたいですか?」
「あなたの目標はなんですか?」
「あなたの生涯を賭けて成し遂げたい夢はなんですか?」
と聞き返すことだ。
それが、20代の宿題、いや人生の宿題なのだ。きっと。
その宿題を解いている同志、それが中学生だろう。
同志に掛ける言葉はいったいなんだろうか?
高橋歩さんの言葉を、僕は贈ります。
~夢があろうとなかろうと、楽しく生きてる奴が最強~
高橋歩
目標がある。
なりたい職業がある。
これを過大に評価しすぎだと思う。
夢がある友達はいいなあって思う。
夢がない自分はダメだなあって思う。
その差は
あまりにも大きいように感じる。
天と地の隔たりを感じる。
ここを、何とかしなきゃいかないのではないか。
大げさに言うと、
「夢がない自分は人にあらず」
それくらい、追い詰められている。
たいしたことない。
夢がなくても生きていける。
夢はないよりもあったほうが少しだけ楽しい、
そんくらいだ。
大人たちに、
「将来何になりたいんだ?」と聞かれたら、
「あなたは何になりたいですか?」
「あなたの目標はなんですか?」
「あなたの生涯を賭けて成し遂げたい夢はなんですか?」
と聞き返すことだ。
それが、20代の宿題、いや人生の宿題なのだ。きっと。
その宿題を解いている同志、それが中学生だろう。
同志に掛ける言葉はいったいなんだろうか?
高橋歩さんの言葉を、僕は贈ります。
~夢があろうとなかろうと、楽しく生きてる奴が最強~
高橋歩
2012年09月14日
真実は現場にある
粟島3泊4日。
村の課題を知り、それを踏まえて、
自分たちの課題と重ね合わせ、
その解決をはかるツアープランを立案する。
ヒアリングを重ねるに連れて、
真実が見えてくる。
役場では、
「現状をなんとかしたい」
と言われるが、
現場の人たちは「このままでいい」
って言われる。
無医村である現状を、改善したいとは思っていない。
観光客がもっと多くなることを望んではいない。
この現実を目の前にする。
それでも、プランを立案しなければならない。
それはどんなプランか?
誰をどのように幸せにするのか。
どんな課題を解決するのか。
そんな問いをひたすらぶつけていく。
そこから、生み出されるものに
僕は期待している。
自分の五感を総動員して、
感じたことを、プランに落とし込んで欲しい。
本日、合宿最終日。
中学生の前で発表します。
村の課題を知り、それを踏まえて、
自分たちの課題と重ね合わせ、
その解決をはかるツアープランを立案する。
ヒアリングを重ねるに連れて、
真実が見えてくる。
役場では、
「現状をなんとかしたい」
と言われるが、
現場の人たちは「このままでいい」
って言われる。
無医村である現状を、改善したいとは思っていない。
観光客がもっと多くなることを望んではいない。
この現実を目の前にする。
それでも、プランを立案しなければならない。
それはどんなプランか?
誰をどのように幸せにするのか。
どんな課題を解決するのか。
そんな問いをひたすらぶつけていく。
そこから、生み出されるものに
僕は期待している。
自分の五感を総動員して、
感じたことを、プランに落とし込んで欲しい。
本日、合宿最終日。
中学生の前で発表します。
2012年09月10日
課題共感と行動すること
地域仕事づくりチャレンジ大賞に
いってきました。
新潟・北信越ブロック代表の
「小さな八百屋が結ぶ地域の役割再生」
は残念ながらグランプリとはなりませんでしたが、
プレゼン終了後、交流会のときに、参加者から
たくさんのコメント、問い合わせを頂きました。
発表がたくさんの人の心に届いたのではないかと思います。
星田くん、長嶋社長、中村さん、高澤さん
プレゼン準備からおつかれさまでした。
僕は朝のリハーサルですでに泣いていました。
素晴らしいプレゼンテーションでした。
チャレンジ大賞グランプリに輝いたのは
山形県朝日町の「ウサヒ」プロジェクト。

ウサギの着ぐるみをきた
佐藤恒平くんの物語。
ウサヒは朝日町を歩き回り、
町民と接していく仲で、
「何か、ウサヒにやらせたいことはあるか?」
と聞きまわる。
スキーを滑ったり、
いろんな観光地に出かけていったり、
ときには無茶なことをする。
それをみんなが楽しそうに見守っている。
衝撃。
このプロジェクトのプレゼンははっきりいって衝撃だった。
「当事者をつくる」
これがまちづくりの最大要因であり、必須要因だと僕も思っている。
当事者とは何か?
「課題に共感し、行動すること」
これに尽きる。
僕たちヒーローズファームはつねづね、
「課題共感」を大切にしてきた。
課題共感がなければ、行動は起こらないと思っていたからだ。
しかし。
ウサヒは違った。
ゆるーいキャラクターで
気さくに町民に話しかけ、巻き込み、
自然と彼らは企画をつくり、自ら実行する。
そう。
行動するようになるのである。
行動すれば、課題が見えてきて、
さらに行動するようになる。
ウサヒは、当事者意識の媒介となっている。
課題共感と行動すること。
この2つの繰り返しが当事者をつくる。
その順番はどちらが先でもいい。
ウサヒはまず行動することから、
人々の心に小さな灯を灯す。
課題共感だけが出発点ではない。
そんな衝撃を受けた東北ブロック代表
の発表、そしてグランプリでした。
紹介団体のハーバランス舟田さん、
恒平を育てた明天貝沼さん。
素晴らしい事例をありがとうございました。
いってきました。
新潟・北信越ブロック代表の
「小さな八百屋が結ぶ地域の役割再生」
は残念ながらグランプリとはなりませんでしたが、
プレゼン終了後、交流会のときに、参加者から
たくさんのコメント、問い合わせを頂きました。
発表がたくさんの人の心に届いたのではないかと思います。
星田くん、長嶋社長、中村さん、高澤さん
プレゼン準備からおつかれさまでした。
僕は朝のリハーサルですでに泣いていました。
素晴らしいプレゼンテーションでした。
チャレンジ大賞グランプリに輝いたのは
山形県朝日町の「ウサヒ」プロジェクト。

ウサギの着ぐるみをきた
佐藤恒平くんの物語。
ウサヒは朝日町を歩き回り、
町民と接していく仲で、
「何か、ウサヒにやらせたいことはあるか?」
と聞きまわる。
スキーを滑ったり、
いろんな観光地に出かけていったり、
ときには無茶なことをする。
それをみんなが楽しそうに見守っている。
衝撃。
このプロジェクトのプレゼンははっきりいって衝撃だった。
「当事者をつくる」
これがまちづくりの最大要因であり、必須要因だと僕も思っている。
当事者とは何か?
「課題に共感し、行動すること」
これに尽きる。
僕たちヒーローズファームはつねづね、
「課題共感」を大切にしてきた。
課題共感がなければ、行動は起こらないと思っていたからだ。
しかし。
ウサヒは違った。
ゆるーいキャラクターで
気さくに町民に話しかけ、巻き込み、
自然と彼らは企画をつくり、自ら実行する。
そう。
行動するようになるのである。
行動すれば、課題が見えてきて、
さらに行動するようになる。
ウサヒは、当事者意識の媒介となっている。
課題共感と行動すること。
この2つの繰り返しが当事者をつくる。
その順番はどちらが先でもいい。
ウサヒはまず行動することから、
人々の心に小さな灯を灯す。
課題共感だけが出発点ではない。
そんな衝撃を受けた東北ブロック代表
の発表、そしてグランプリでした。
紹介団体のハーバランス舟田さん、
恒平を育てた明天貝沼さん。
素晴らしい事例をありがとうございました。
2012年09月09日
大学は地域貢献を余力でやるのではない
昨日。
ETIC.の大学関係者向けの分科会。
「大学は地域にとってどういう存在であるべきか。」
というテーマ。
シンクタンクからドゥータンクへ。
地域と共に行動する大学へ。
特に地方都市では、
業を起こす力を身につけなければいけない。
地元に就職口がないのなら、
自分で作っていける人材を輩出しなければならない。
いちばん印象に残った一言は
「大学は地域貢献を余力でやるのではない。」
そういう時代になったようだ。
地域に必要とされる大学とは何か?
あらためて問い直す必要がある。
そして、地域団体として、大学とどう連携していくか、
そのゴールは何か?
目指したい卒業生像とはなにか?
その問いを共有していく必要がある。
高知大学、上田先生が最後に言った。
「風が吹いてきたんじゃないか。」
未来から吹いてくる風、未来に向かっていく風。
いまこそ、変革者たちの出番だ。
大学も、地域も、学生も、地域団体も、
変わっていくときがきているのではないか。
ETIC.の大学関係者向けの分科会。
「大学は地域にとってどういう存在であるべきか。」
というテーマ。
シンクタンクからドゥータンクへ。
地域と共に行動する大学へ。
特に地方都市では、
業を起こす力を身につけなければいけない。
地元に就職口がないのなら、
自分で作っていける人材を輩出しなければならない。
いちばん印象に残った一言は
「大学は地域貢献を余力でやるのではない。」
そういう時代になったようだ。
地域に必要とされる大学とは何か?
あらためて問い直す必要がある。
そして、地域団体として、大学とどう連携していくか、
そのゴールは何か?
目指したい卒業生像とはなにか?
その問いを共有していく必要がある。
高知大学、上田先生が最後に言った。
「風が吹いてきたんじゃないか。」
未来から吹いてくる風、未来に向かっていく風。
いまこそ、変革者たちの出番だ。
大学も、地域も、学生も、地域団体も、
変わっていくときがきているのではないか。
2012年09月08日
ただ、それを感じればいい
分かろうとしなくていいんだ。
ただ、それを感じればいい。
感じたことを分かろうとしたり理由をつけないと
感じたことにならないと思ってる。
これは、感じたフリをしているだけだよ。
理由づけはいらないの。
(セアロ108の言葉より)
昨日。
「PASS the book~本の卒業式」というイベントで
ブラストビート代表、松浦さんからいただきました。

ブラストビートは、「音楽×起業×社会貢献」というコンセプトで
高校生がイベントを次々と実行していくNPO法人。
支援する「大人」は20代から60代まで
まさにプラットフォームだ。
http://blastbeat.jp/
そんな松浦さんの座右の1冊。
悩んだときに常に横にあった1冊。
それが「セアロ108の言葉」
この本に込められたエピソードに
泣きそうになった。
そして松浦さんが好きになった。
読んでみたいと思った。
そしたら、メッセージを書いた人から選ばれ、
僕がもらいことになった。
そして真っ先に開いたページに書いてあったのが
冒頭のメッセージだ。
昨日は、たくさんの人たちと再会。
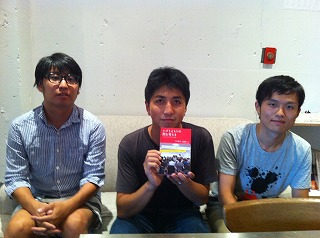
日本仕事百貨の中村さん、大越さん
greenzの兼松さん
イマココミライの森田英一さん
そして。
僕を育てた王子・狐の木の
コージ・エイジこと
佐藤孝治さんと渡辺栄治さん。
3人でバスペールエールを飲んだら、
14年前に飛んだ。

そうだ。
ただ、それを感じればいいんだ。
あの日。
自分が信じた感性。
そうそう、そういう感じ。
もう一度、感性を全開にして、一緒にやってみたい。
元気が湧いてくる1日でした。ありがとう。
ただ、それを感じればいい。
感じたことを分かろうとしたり理由をつけないと
感じたことにならないと思ってる。
これは、感じたフリをしているだけだよ。
理由づけはいらないの。
(セアロ108の言葉より)
昨日。
「PASS the book~本の卒業式」というイベントで
ブラストビート代表、松浦さんからいただきました。

ブラストビートは、「音楽×起業×社会貢献」というコンセプトで
高校生がイベントを次々と実行していくNPO法人。
支援する「大人」は20代から60代まで
まさにプラットフォームだ。
http://blastbeat.jp/
そんな松浦さんの座右の1冊。
悩んだときに常に横にあった1冊。
それが「セアロ108の言葉」
この本に込められたエピソードに
泣きそうになった。
そして松浦さんが好きになった。
読んでみたいと思った。
そしたら、メッセージを書いた人から選ばれ、
僕がもらいことになった。
そして真っ先に開いたページに書いてあったのが
冒頭のメッセージだ。
昨日は、たくさんの人たちと再会。
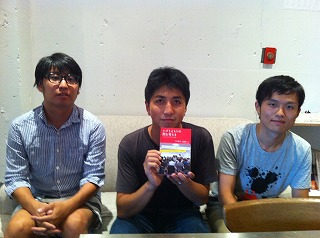
日本仕事百貨の中村さん、大越さん
greenzの兼松さん
イマココミライの森田英一さん
そして。
僕を育てた王子・狐の木の
コージ・エイジこと
佐藤孝治さんと渡辺栄治さん。
3人でバスペールエールを飲んだら、
14年前に飛んだ。

そうだ。
ただ、それを感じればいいんだ。
あの日。
自分が信じた感性。
そうそう、そういう感じ。
もう一度、感性を全開にして、一緒にやってみたい。
元気が湧いてくる1日でした。ありがとう。
2012年09月06日
風のように生きる【ツルハシブックス9月イベント情報】
カッコイイな、と思う20代、30代がいる。
彼らの多くが、「風のように生きているなあ」って思う。
そんなふうに感じたのは以下の3冊。
「計画と無計画のあいだ」(三島邦弘)
「シゴトとヒトの間を考える」(中村健太・友廣裕一)
そして、
玉城ちはる「風になれば」(本分社)

特に20代女子にオススメの1冊。
風のように生きる
ってこういうことか、って思います。
胸にさわやかな風が吹き抜ける。
http://www.youtube.com/watch?v=dRWzIQwpc-Y
この出版を記念して、
ミニライブ&トークイベントを開催します。
●日 程:2012年9月29日(土)
●会 場:「ツルハシブックス」 http://tsuruhashi.niiblo.jp/
新潟市西区内野町431-2
ウチノ・コラボレーション・ラボラトリー1F (Pなし)
TEL 025-261-3188
●時 間:START 15:00-END 17:00
●チケット:1,000円(当日受付にてお支払い下さい)
●出 演:玉城ちはる 財津正人、西田卓司
※当日は玉城ちはるミニライブ、
本分社代表・財津正人とのトーク、
そしてツルハシブックスの西田卓司さんを迎え、
3人でトーク「今の時代にあらゆるものを発掘するエネルギーについて」&質疑応答を行います。
●お申し込み、お問い合わせは、
ツルハシブックスまで、下記をご記入の上、メールにてお申し込みください。
tsuruhashibooks@gmail.com
-----------------------------
件名:玉城ちはる出版記念ミニライブ&トーク申込
本文:
①お名前(フリガナ)
②当日連絡の取れる電話番号
③メールアドレス
④参加人数
⑤ライブ&トーク終了後の懇親会(別途費用2,000円が必要です)参加希望者はお知らせください。
------------------------------
また翌日30日には屋台イベントうちのマルシェが行われます。
そちらで開催される一箱古本市の出店者も募集しています。
(11:00~17:00)
参加費は1,000円で最大残り9ブースです。
こちらは先着順になりますので、よろしくお願いします。
ツルハシブックスまでお問い合わせ下さい。
当日は野菜ソムリエ山岸さんの野菜ブースも
出店されますので、こちらも合わせてお楽しみ下さい。
以下9月・10月のイベント情報です。
9月29日(土)玉城ちはるミニライブ&トーク 15:00~17:00 (懇親会17:30~20:00)
9月30日(日)うちのマルシェにて一箱古本市11:00~17:00
10月7日(日)巻鯛車商店街で遊びのフリーマーケット「だがしや楽校」9:00~15:00
(※大学生のボランティアを募集しています)
10月20日21日(土日)カフェCopoCopoでファン待望のカレープロジェクト 11:00~16:00
彼らの多くが、「風のように生きているなあ」って思う。
そんなふうに感じたのは以下の3冊。
「計画と無計画のあいだ」(三島邦弘)
「シゴトとヒトの間を考える」(中村健太・友廣裕一)
そして、
玉城ちはる「風になれば」(本分社)

特に20代女子にオススメの1冊。
風のように生きる
ってこういうことか、って思います。
胸にさわやかな風が吹き抜ける。
http://www.youtube.com/watch?v=dRWzIQwpc-Y
この出版を記念して、
ミニライブ&トークイベントを開催します。
●日 程:2012年9月29日(土)
●会 場:「ツルハシブックス」 http://tsuruhashi.niiblo.jp/
新潟市西区内野町431-2
ウチノ・コラボレーション・ラボラトリー1F (Pなし)
TEL 025-261-3188
●時 間:START 15:00-END 17:00
●チケット:1,000円(当日受付にてお支払い下さい)
●出 演:玉城ちはる 財津正人、西田卓司
※当日は玉城ちはるミニライブ、
本分社代表・財津正人とのトーク、
そしてツルハシブックスの西田卓司さんを迎え、
3人でトーク「今の時代にあらゆるものを発掘するエネルギーについて」&質疑応答を行います。
●お申し込み、お問い合わせは、
ツルハシブックスまで、下記をご記入の上、メールにてお申し込みください。
tsuruhashibooks@gmail.com
-----------------------------
件名:玉城ちはる出版記念ミニライブ&トーク申込
本文:
①お名前(フリガナ)
②当日連絡の取れる電話番号
③メールアドレス
④参加人数
⑤ライブ&トーク終了後の懇親会(別途費用2,000円が必要です)参加希望者はお知らせください。
------------------------------
また翌日30日には屋台イベントうちのマルシェが行われます。
そちらで開催される一箱古本市の出店者も募集しています。
(11:00~17:00)
参加費は1,000円で最大残り9ブースです。
こちらは先着順になりますので、よろしくお願いします。
ツルハシブックスまでお問い合わせ下さい。
当日は野菜ソムリエ山岸さんの野菜ブースも
出店されますので、こちらも合わせてお楽しみ下さい。
以下9月・10月のイベント情報です。
9月29日(土)玉城ちはるミニライブ&トーク 15:00~17:00 (懇親会17:30~20:00)
9月30日(日)うちのマルシェにて一箱古本市11:00~17:00
10月7日(日)巻鯛車商店街で遊びのフリーマーケット「だがしや楽校」9:00~15:00
(※大学生のボランティアを募集しています)
10月20日21日(土日)カフェCopoCopoでファン待望のカレープロジェクト 11:00~16:00
2012年09月05日
ニイダヤ水産、復活しました
2012年9月1日。
工場の稼動再開。
連日、お客さんでにぎわっています。
みんなが待ち望んだ
ニイダヤ水産復活。

UX小林さんにロングドライブで連れてきてもらいました。
夜はブルーピクトにて干物で大宴会。
ブルーピクトは建設業のはずなのに、
ニイダヤ水産のチラシのDMが山になっていました。
なんか、いい。
ニイダヤ水産復活にみんなの力が重なっています。
青木社長の心意気に胸が熱くなります。
また来ます。
そして、僕も干物売ります。
ニイダヤTシャツも扱いたい。
豊かな時間をありがとうございました。
※ニイダヤ水産復活ファンドにご協力頂いた方、
今月中に、干物セットが到着します。
お楽しみにお待ち下さい。
ご協力、本当にありがとうございました。
工場の稼動再開。
連日、お客さんでにぎわっています。
みんなが待ち望んだ
ニイダヤ水産復活。

UX小林さんにロングドライブで連れてきてもらいました。
夜はブルーピクトにて干物で大宴会。
ブルーピクトは建設業のはずなのに、
ニイダヤ水産のチラシのDMが山になっていました。
なんか、いい。
ニイダヤ水産復活にみんなの力が重なっています。
青木社長の心意気に胸が熱くなります。
また来ます。
そして、僕も干物売ります。
ニイダヤTシャツも扱いたい。
豊かな時間をありがとうございました。
※ニイダヤ水産復活ファンドにご協力頂いた方、
今月中に、干物セットが到着します。
お楽しみにお待ち下さい。
ご協力、本当にありがとうございました。
2012年09月04日
僕がなぜいま、コミュニティ・デザインなのか?
昨日。
世の中から見たコミュニティ・デザイン
の重要性を考えてみた。
コミュニティ・デザイン研究会のときに、
もうひとつ用意していたネタ。
それは
僕がいまなぜコミュニティ・デザインなのか。
ということ。
物語は1998年。
小説「種をまく人」から始まった。
畑をしたい。
と思っていた僕にとって、
塩見直紀さんから贈られた本は
人生を大きく動かした。
そのうちの1つが「種をまく人」だった。
ゴミ捨て場となっていた空き地に
ひとりの女の子がマメの種をまいた。
すると、近所の人たちが気にするようになり、
いつの間にかゴミ捨て場は菜園になり、
人種を超えて人々は笑い、語らうようになった。
「畑ってそんなことができるんだ!」
素直な24歳の胸にその小説が突き刺さる。
これが思えば、コミュニティ・デザインとの出会いだったのかもしれない。
その後2002年に不登校の中学校3年生と出会い、
「中学生高校生と共に将来を見つめ、共に悩み、共に語る場はどうやったら作れるだろうか?」
という座右の問いに出会い、
さらに、佐藤家保存会のかや刈りに出て、
地域に生きる人たちの誇りに触れた。
これだ!って思った。
コミュニティの復活、そして役割再生。
これが、中学生高校生にとって
必要なんだろうと思う。
その場はどうやったら作れるのか?
中高生×地域という場をどうやってつくるのか?
そんな問いの中で
ツルハシブックスに地下古本コーナーが誕生。
10年越しの問いに、
ようやく第1歩を踏み出したのだ。
まだまだ、始まったばかりだ。
~~~追伸
そんな拠点という意味では、
沼垂よりどころ、やさい村・よろずや
の取り組みは、非常に興味深い。
高齢者地域に八百屋という
コミュニティ拠点をつくったこと。
これが地域にとってどんな意味があるのか。
地域に住む高齢者の人生にとってどんな意味があるのか。
そんな問いを置いてこようと思います。
【事前投票にご協力をお願いします】(紹介団体・新潟市ヒーローズファーム)
地域仕事づくりチャレンジ大賞
http://challenge-community.jp/award2012/youth/288
「小さな八百屋から始まる地域の役割再生」
小さな八百屋から始まった、
地域のひとりひとりの役割再生の物語。
おばあちゃんの笑顔の秘密とは?
9月9日(日)東京・渋谷に熱い思い、置いてきます。
世の中から見たコミュニティ・デザイン
の重要性を考えてみた。
コミュニティ・デザイン研究会のときに、
もうひとつ用意していたネタ。
それは
僕がいまなぜコミュニティ・デザインなのか。
ということ。
物語は1998年。
小説「種をまく人」から始まった。
畑をしたい。
と思っていた僕にとって、
塩見直紀さんから贈られた本は
人生を大きく動かした。
そのうちの1つが「種をまく人」だった。
ゴミ捨て場となっていた空き地に
ひとりの女の子がマメの種をまいた。
すると、近所の人たちが気にするようになり、
いつの間にかゴミ捨て場は菜園になり、
人種を超えて人々は笑い、語らうようになった。
「畑ってそんなことができるんだ!」
素直な24歳の胸にその小説が突き刺さる。
これが思えば、コミュニティ・デザインとの出会いだったのかもしれない。
その後2002年に不登校の中学校3年生と出会い、
「中学生高校生と共に将来を見つめ、共に悩み、共に語る場はどうやったら作れるだろうか?」
という座右の問いに出会い、
さらに、佐藤家保存会のかや刈りに出て、
地域に生きる人たちの誇りに触れた。
これだ!って思った。
コミュニティの復活、そして役割再生。
これが、中学生高校生にとって
必要なんだろうと思う。
その場はどうやったら作れるのか?
中高生×地域という場をどうやってつくるのか?
そんな問いの中で
ツルハシブックスに地下古本コーナーが誕生。
10年越しの問いに、
ようやく第1歩を踏み出したのだ。
まだまだ、始まったばかりだ。
~~~追伸
そんな拠点という意味では、
沼垂よりどころ、やさい村・よろずや
の取り組みは、非常に興味深い。
高齢者地域に八百屋という
コミュニティ拠点をつくったこと。
これが地域にとってどんな意味があるのか。
地域に住む高齢者の人生にとってどんな意味があるのか。
そんな問いを置いてこようと思います。
【事前投票にご協力をお願いします】(紹介団体・新潟市ヒーローズファーム)
地域仕事づくりチャレンジ大賞
http://challenge-community.jp/award2012/youth/288
「小さな八百屋から始まる地域の役割再生」
小さな八百屋から始まった、
地域のひとりひとりの役割再生の物語。
おばあちゃんの笑顔の秘密とは?
9月9日(日)東京・渋谷に熱い思い、置いてきます。
2012年09月03日
いまなぜコミュニティ・デザインか?
先週の木曜日
コミュニティ・デザイン研究会の第2回。
いまなぜ、コミュニティデザインなのか、を考える。
マクロで言えば、
1 少子高齢化による行政依存システムの限界
2 課題は組み合わせれば資源になる
3 役割の復活による生き甲斐の創造、再生
この3つではないかと思う。
税収減によって、
まちの課題は、行政に言えばなんとかしてくれる、
という時代は終わりを告げた。
だから、まちの課題は住民ひとりひとりが
解決していかなくてはならない。
そのとき。
デザイン思考が必要だ。
栃尾のNPO法人UNEが取り組んでいる
高齢者と障がい者の農業分野での連携。
これは、双方が抱える課題を
組み合わせによって、解決しようという取り組み、
かつ、限界集落に限りなく近い中山間地の活性化を図っていくというものでもある。
このようにして、課題を組み合わせて、
資源に変えていくという取り組みは、
地域社会に「役割」を復活させる。
農業社会、農的生活の中で育まれてきた「役割」はすでに風前の灯となった。
工業社会からサービス業社会への産業構造の変化の中で、
いや、経済合理性を最大の価値とする社会によって、
人々は分断され、「役割」は失われた。
「役割」を失うことは、大げさに言えば、
生きる意味を失うことにつながっていく。
だから。
コミュニティデザインが必要なんだと思う。
コミュニティデザインが生んでいくのは
人と人のつながり、そしてひとりひとりの役割。
それこそが、いま、若者が欲しているもの
そのものなのではないだろうか。
「誰かの役に立ちたい」
「人のためになる仕事がしたい」
そんな純粋な思いが、発現する場所と仕組みを
つくっていくこと。
それがコミュニティデザインの本質なのではないだろうか。
コミュニティ・デザイン研究会の第2回。
いまなぜ、コミュニティデザインなのか、を考える。
マクロで言えば、
1 少子高齢化による行政依存システムの限界
2 課題は組み合わせれば資源になる
3 役割の復活による生き甲斐の創造、再生
この3つではないかと思う。
税収減によって、
まちの課題は、行政に言えばなんとかしてくれる、
という時代は終わりを告げた。
だから、まちの課題は住民ひとりひとりが
解決していかなくてはならない。
そのとき。
デザイン思考が必要だ。
栃尾のNPO法人UNEが取り組んでいる
高齢者と障がい者の農業分野での連携。
これは、双方が抱える課題を
組み合わせによって、解決しようという取り組み、
かつ、限界集落に限りなく近い中山間地の活性化を図っていくというものでもある。
このようにして、課題を組み合わせて、
資源に変えていくという取り組みは、
地域社会に「役割」を復活させる。
農業社会、農的生活の中で育まれてきた「役割」はすでに風前の灯となった。
工業社会からサービス業社会への産業構造の変化の中で、
いや、経済合理性を最大の価値とする社会によって、
人々は分断され、「役割」は失われた。
「役割」を失うことは、大げさに言えば、
生きる意味を失うことにつながっていく。
だから。
コミュニティデザインが必要なんだと思う。
コミュニティデザインが生んでいくのは
人と人のつながり、そしてひとりひとりの役割。
それこそが、いま、若者が欲しているもの
そのものなのではないだろうか。
「誰かの役に立ちたい」
「人のためになる仕事がしたい」
そんな純粋な思いが、発現する場所と仕組みを
つくっていくこと。
それがコミュニティデザインの本質なのではないだろうか。




