2011年04月30日
死生観
田坂広志さんは言う。
死生観
世界観
歴史観
この3つを持って
世の中に対峙していけと。
いま。
東日本大震災で
多くの人が死と向き合っている。
死生観。
生きるとは、
死ぬとは、
いったいなんだろう?
そんな根本的な問いかけ。
昨日、地域若者チャレンジ大賞の新潟地区予選。
ひとりひとりが「働く」ことに向き合い
自分なりにこたえていった半年間だった。
働くとは?
生きるとは?
そんな問いこそが一番の価値なのだろうと思う。
死生観
世界観
歴史観
この3つを持って
世の中に対峙していけと。
いま。
東日本大震災で
多くの人が死と向き合っている。
死生観。
生きるとは、
死ぬとは、
いったいなんだろう?
そんな根本的な問いかけ。
昨日、地域若者チャレンジ大賞の新潟地区予選。
ひとりひとりが「働く」ことに向き合い
自分なりにこたえていった半年間だった。
働くとは?
生きるとは?
そんな問いこそが一番の価値なのだろうと思う。
2011年04月29日
ダイアログ
ディスカッション(討論)ではなく、
ダイアログ(対話)が必要だ。
相手のことを理解しようとする気持ち。
そこから始まるコミュニケーション。
コミュニケーション力とは
ダイアログする力なのかもしれない。
ダイアログ(対話)が必要だ。
相手のことを理解しようとする気持ち。
そこから始まるコミュニケーション。
コミュニケーション力とは
ダイアログする力なのかもしれない。
2011年04月28日
成功の循環
森田英一さんに教えてもらった、
MITのダニエル・キム教授の
「成功の循環」。
関係の質を高めると
思考の質が上がり、
行動の質が向上し、
結果の質が上がる。
まずは、関係の質を高めていくこと。
ところが、
世の中の組織では、
「結果」を出そうとするあまり、
「行動」を強要する。
そうすると、
「思考」が低下し、
結果、関係の質が悪化する。
そして結果がさらに下がる、という悪循環に落ちる。
まず高めるべきは関係の質だ。
MITのダニエル・キム教授の
「成功の循環」。
関係の質を高めると
思考の質が上がり、
行動の質が向上し、
結果の質が上がる。
まずは、関係の質を高めていくこと。
ところが、
世の中の組織では、
「結果」を出そうとするあまり、
「行動」を強要する。
そうすると、
「思考」が低下し、
結果、関係の質が悪化する。
そして結果がさらに下がる、という悪循環に落ちる。
まず高めるべきは関係の質だ。
2011年04月27日
代理体験と共感
バンデューラが
提唱した「自己効力感」=(自信)
~~~~~~~~~~~~~~~
自己効力感の高め方
自己効力感は、主に4つの源泉によって形成されるといわれている。
1.達成体験
自分自身で行動して、達成できたという体験のこと。
これが最も自己効力感を定着させるといわれている。
2.代理経験
他者が達成している様子を観察することによって、「自分にもできそうだ」と予期すること。
自らが体験できる範囲は限られているため、
この代理経験で得られる自己効力感の影響は大きいと考えられる。
3.言語的説得
達成可能性を、言語で繰り返し説得すること。
しかし、言語的説得のみによる自己効力感は、容易に消失しやすいといわれている。
4.生理的情緒的高揚
苦手だと感じていた場面で、落ち着いていられたり、
赤面や発汗がなかったりすることで、自己効力感が強められること。
進路指導講演会
などはこのうちの2を狙ったものであろうと思う。
先輩社会人から就活の話を聞いて
「自分にもできそうだ」
と感じることで少し自信がつく。
だとすれば。
有効なのは、「共感」をより高める仕掛けだ。
その手段は
ていねいなアイスブレイクかもしれないし、
カタリバのような少人数の紙芝居のワークショップ。
共感度を高める仕掛けによって、
「代理体験」が可能となり、
自信がつく。
なるほど。
カタリバがカタリバである理由が少しだけ分かったような気がした。
代理体験からスタートし、達成体験を積み重ねていくことが
必要なのだろう。
提唱した「自己効力感」=(自信)
~~~~~~~~~~~~~~~
自己効力感の高め方
自己効力感は、主に4つの源泉によって形成されるといわれている。
1.達成体験
自分自身で行動して、達成できたという体験のこと。
これが最も自己効力感を定着させるといわれている。
2.代理経験
他者が達成している様子を観察することによって、「自分にもできそうだ」と予期すること。
自らが体験できる範囲は限られているため、
この代理経験で得られる自己効力感の影響は大きいと考えられる。
3.言語的説得
達成可能性を、言語で繰り返し説得すること。
しかし、言語的説得のみによる自己効力感は、容易に消失しやすいといわれている。
4.生理的情緒的高揚
苦手だと感じていた場面で、落ち着いていられたり、
赤面や発汗がなかったりすることで、自己効力感が強められること。
進路指導講演会
などはこのうちの2を狙ったものであろうと思う。
先輩社会人から就活の話を聞いて
「自分にもできそうだ」
と感じることで少し自信がつく。
だとすれば。
有効なのは、「共感」をより高める仕掛けだ。
その手段は
ていねいなアイスブレイクかもしれないし、
カタリバのような少人数の紙芝居のワークショップ。
共感度を高める仕掛けによって、
「代理体験」が可能となり、
自信がつく。
なるほど。
カタリバがカタリバである理由が少しだけ分かったような気がした。
代理体験からスタートし、達成体験を積み重ねていくことが
必要なのだろう。
2011年04月25日
2011年04月23日
誕生日の本
京葉線の車内。
「電車で読むと、泣いちゃいますよ」
と言われていた本、
「この世でいちばん大切な日」
(十川ゆかり サンクチュアリ出版)

を読んでいた。
泣けた。
これはすごい本。
誕生日にまつわる心温まる
ストーリーが31編。
あんまり泣けるので
もったいなくって、
途中で読むのをやめておいた。
雨の中、全力疾走で追いかけ、忘れ物を
届けてくれたタクシーの運転手さん。
ずっと昔にプレゼントした
肩たたき券を大事にもっていたおばあちゃん。
ひとつひとつが
超泣けるエピソードに詰まっています。
生きるっていいな、と思える本。
2011年、必読の1冊です。
ツルハシブックスにて、昨日から発売中。
「電車で読むと、泣いちゃいますよ」
と言われていた本、
「この世でいちばん大切な日」
(十川ゆかり サンクチュアリ出版)

を読んでいた。
泣けた。
これはすごい本。
誕生日にまつわる心温まる
ストーリーが31編。
あんまり泣けるので
もったいなくって、
途中で読むのをやめておいた。
雨の中、全力疾走で追いかけ、忘れ物を
届けてくれたタクシーの運転手さん。
ずっと昔にプレゼントした
肩たたき券を大事にもっていたおばあちゃん。
ひとつひとつが
超泣けるエピソードに詰まっています。
生きるっていいな、と思える本。
2011年、必読の1冊です。
ツルハシブックスにて、昨日から発売中。
2011年04月21日
ゼロをイチにする
昨日付の日経MJ最終面に
糸井重里さんが載っていた。
100を110にするのではなく、
ゼロをイチにする。
そんな仕事が必要とされている。
糸井重里さんの
メッセージには力がある。
自分がやりたいのは、
不特定多数の人を相手にした広告ではなく、
価値観を共有しあえる人たちとの
親しいコミュニケーション。
そうして生まれたのが
35万部を超えるヒットとなった
ほぼ日手帳。
手に届く範囲の人に届ける商品づくり。
これがヒットの秘密なのか。
糸井重里さんの言葉が
フェイスブック時代の到来を
物語る。
糸井重里さんが載っていた。
100を110にするのではなく、
ゼロをイチにする。
そんな仕事が必要とされている。
糸井重里さんの
メッセージには力がある。
自分がやりたいのは、
不特定多数の人を相手にした広告ではなく、
価値観を共有しあえる人たちとの
親しいコミュニケーション。
そうして生まれたのが
35万部を超えるヒットとなった
ほぼ日手帳。
手に届く範囲の人に届ける商品づくり。
これがヒットの秘密なのか。
糸井重里さんの言葉が
フェイスブック時代の到来を
物語る。
2011年04月20日
主客一体
佐々木俊尚「キュレーションの時代~つながりの情報革命が始まる」
は必読の1冊。
なぜ、フェイスブックなのか。
に対してのアンサーがここにある。
時代が変わった。
一方的な情報の流れは通用せず、
ひとりひとりが、情報を編集し、物語や新たな意味を加える
「キュレーター」を通して、情報を取捨選択する。
震災のときの
ツイッターを見ていても
1つ1つの情報の真偽を確かめるというのが
ものすごく難しいということが分かる。
だから人は、
信頼できる人が発する情報なら、
友人が発するなら、
ということで信頼するしかない。
そしてその意味付けが
新たな付加価値を生み出していく。
フェイスブックによって
生み出される無数のリンクが、
人と人をつなぎ、
行動を起こさせる。
それを著者は「視座を手に入れる」という。
ある人が世の中を見る、
その見方、考え方を通して、
自分も世の中を見るということ。
本の中で著者は
「主客一体」という言葉を紹介している。
外国のパーティーでは、
「ホスト」(受け入れ側)と
「ゲスト」(お客さん)に分かれる。
日本の茶道などの
もてなしの場では、
その区別があいまいである。
本書では千利休と津田宗及のエピソードが紹介されている。
千利休が水を換えに
水汲みに行っているとき、
宗及は、まずは起こされた炭の見事さに感激し、
利休がお茶を入れるために
炭を足しておく。
その行為を利休は褒めるのだ。
主客一体。
これからの情報も、まさに主客一体の時代が来る。
おもしろいことになってきた。
は必読の1冊。
なぜ、フェイスブックなのか。
に対してのアンサーがここにある。
時代が変わった。
一方的な情報の流れは通用せず、
ひとりひとりが、情報を編集し、物語や新たな意味を加える
「キュレーター」を通して、情報を取捨選択する。
震災のときの
ツイッターを見ていても
1つ1つの情報の真偽を確かめるというのが
ものすごく難しいということが分かる。
だから人は、
信頼できる人が発する情報なら、
友人が発するなら、
ということで信頼するしかない。
そしてその意味付けが
新たな付加価値を生み出していく。
フェイスブックによって
生み出される無数のリンクが、
人と人をつなぎ、
行動を起こさせる。
それを著者は「視座を手に入れる」という。
ある人が世の中を見る、
その見方、考え方を通して、
自分も世の中を見るということ。
本の中で著者は
「主客一体」という言葉を紹介している。
外国のパーティーでは、
「ホスト」(受け入れ側)と
「ゲスト」(お客さん)に分かれる。
日本の茶道などの
もてなしの場では、
その区別があいまいである。
本書では千利休と津田宗及のエピソードが紹介されている。
千利休が水を換えに
水汲みに行っているとき、
宗及は、まずは起こされた炭の見事さに感激し、
利休がお茶を入れるために
炭を足しておく。
その行為を利休は褒めるのだ。
主客一体。
これからの情報も、まさに主客一体の時代が来る。
おもしろいことになってきた。
2011年04月19日
本屋さんであって本屋さんではない空間
本との出会いは人生を変える。
僕はたくさんの本に出会い、
人生を動かしてきた。
本屋さんに新しい人生が転がっている。
本当にそう思う。
でも。
いま思うのは、
人を幸せにするのは、
本そのものだけではないだろう。
「本から始まる関係性」
これこそが人を幸せにするのではないか、
と僕は思う。
価値観が多様化しているいま。
本を通じて、人と人がつながる。
そこから始まるたくさんの物語。
そんなものを生み出せる空間を創りたいのだ。
僕はたくさんの本に出会い、
人生を動かしてきた。
本屋さんに新しい人生が転がっている。
本当にそう思う。
でも。
いま思うのは、
人を幸せにするのは、
本そのものだけではないだろう。
「本から始まる関係性」
これこそが人を幸せにするのではないか、
と僕は思う。
価値観が多様化しているいま。
本を通じて、人と人がつながる。
そこから始まるたくさんの物語。
そんなものを生み出せる空間を創りたいのだ。
2011年04月18日
ワクワク51%
プラス思考とか
マイナス思考とか、
0か100かってことではなく。
全ての出来事に
プラスもマイナスもない。
そう思う自分がいるだけだ。
と小林正観先生に教えてもらったが、
すべてのものが
プラスだと思える人は
なかなかいないだろう。
ものごとにはマイナス要素も当然ある。
それでもやるのは、
ワクワクが51%を超えているから。
不安でいっぱいだ。
だけど、
ワクワクがそれを割合的に超えていること。
ワクワクの種をいっぱい見つけ、
それを加算していく。
こんなことができたら、
こんないいことがある。
実現したら、こんなにも楽しい。
そんなワクワクを積み重ねて、
51%を超え、アクションにつなげていこう。
マイナス思考とか、
0か100かってことではなく。
全ての出来事に
プラスもマイナスもない。
そう思う自分がいるだけだ。
と小林正観先生に教えてもらったが、
すべてのものが
プラスだと思える人は
なかなかいないだろう。
ものごとにはマイナス要素も当然ある。
それでもやるのは、
ワクワクが51%を超えているから。
不安でいっぱいだ。
だけど、
ワクワクがそれを割合的に超えていること。
ワクワクの種をいっぱい見つけ、
それを加算していく。
こんなことができたら、
こんないいことがある。
実現したら、こんなにも楽しい。
そんなワクワクを積み重ねて、
51%を超え、アクションにつなげていこう。
2011年04月16日
自分はどんな価値を生めるのか?
どんな仕事だとしても、
プロジェクトだとしても
ボランティアスタッフだとしても
必要な問い。
「自分はどんな価値を生めるのか?」
この問いを常に胸においておくこと。
ホスピタルクラウン
大棟耕介さんはいつも言う。
「まだ自分を世の中に使い切ってもらっていない」
自分を使い切ってもらうのは
どうしたらいいのか?
その問いを胸に、今日も歩き出そう。
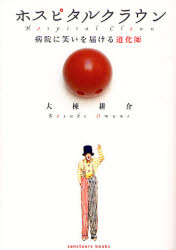
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031841526&Action_id=121&Sza_id=GG
プロジェクトだとしても
ボランティアスタッフだとしても
必要な問い。
「自分はどんな価値を生めるのか?」
この問いを常に胸においておくこと。
ホスピタルクラウン
大棟耕介さんはいつも言う。
「まだ自分を世の中に使い切ってもらっていない」
自分を使い切ってもらうのは
どうしたらいいのか?
その問いを胸に、今日も歩き出そう。
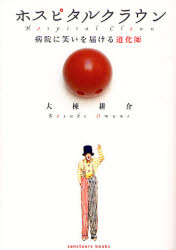
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031841526&Action_id=121&Sza_id=GG
2011年04月14日
テレビ生中継
テレビ生中継。
そんな機会なんてなかなかない。
非常に落ち着いていたのは
宮澤くん。
いつもどおりの笑顔で安定感がある。
本番に強かったのは、今井さん。
自然な感じでステキな店長さんでした。
そして料理を作ってくれた森絵美さん。
すげー美味かったです。
テレビの生中継に出るなんて、
なかなかないチャンスです。
ここから一気に登っていきましょう。
ありがとうございます。

そんな機会なんてなかなかない。
非常に落ち着いていたのは
宮澤くん。
いつもどおりの笑顔で安定感がある。
本番に強かったのは、今井さん。
自然な感じでステキな店長さんでした。
そして料理を作ってくれた森絵美さん。
すげー美味かったです。
テレビの生中継に出るなんて、
なかなかないチャンスです。
ここから一気に登っていきましょう。
ありがとうございます。

2011年04月13日
イベントを学びに落とし込む
人生はプロジェクトだ。
ひとつひとつの小さなプロジェクトの積み重ねだ。
だから、充実した人生のためには、
充実したプロジェクトを作ることだ。
「おもしろそうだから」
とあちらこちらにイベントスタッフを
やっているだけでは、身にならない。
僕はそれを
温泉理論と名づけた。
イベントに少しだけ関わるのは、
温泉で言えば、足湯めぐりをしているようなものだ。
足だけ入っても、少しは効果があると思うが、
基本的には効能はわからない。
温泉に入るのなら、
頭までどっぷりと漬かることだ。
それで効能があるかどうか、
はっきりと自覚し、自分に合った温泉かどうか、
判断することだ。
イベントに参加するだけではなく、
スタッフになるのなら、
そのイベントの目的は何か?
成果として目指す指標は何か?
それはどの程度達成したのか?
その要因は何か?
次回イベントを作るとしたら
注意ポイントはどこか?
そんなことを考えながら、
イベントに参加することが大切だ。
学びに落とし込む。
これをやっていくことが学生サークルにも
必要だと思う。
ひとつひとつの小さなプロジェクトの積み重ねだ。
だから、充実した人生のためには、
充実したプロジェクトを作ることだ。
「おもしろそうだから」
とあちらこちらにイベントスタッフを
やっているだけでは、身にならない。
僕はそれを
温泉理論と名づけた。
イベントに少しだけ関わるのは、
温泉で言えば、足湯めぐりをしているようなものだ。
足だけ入っても、少しは効果があると思うが、
基本的には効能はわからない。
温泉に入るのなら、
頭までどっぷりと漬かることだ。
それで効能があるかどうか、
はっきりと自覚し、自分に合った温泉かどうか、
判断することだ。
イベントに参加するだけではなく、
スタッフになるのなら、
そのイベントの目的は何か?
成果として目指す指標は何か?
それはどの程度達成したのか?
その要因は何か?
次回イベントを作るとしたら
注意ポイントはどこか?
そんなことを考えながら、
イベントに参加することが大切だ。
学びに落とし込む。
これをやっていくことが学生サークルにも
必要だと思う。
2011年04月12日
文化として、何を残したいか?
「鍋茶屋は高橋のものではない。新潟の文化なんだから」
古町の老舗料亭、鍋茶屋の
経営が傾いたときに、
支援者が言った言葉。
「会社は公器」とは、
あの松下幸之助さんが放った言葉だが、
まさにいま、そんな会社、
そんな経営者が求められている。
自分たちの会社は何のために存在しているのか?
そんな問いに向き合い、
社会と共に生きることで、
冒頭の言葉がかけられる存在になる。
我々は文化として、
何を残したいのか?
いや。
残したい。
と思われるような「文化」とは何か?
そんな問いからスタートしたい。
古町の老舗料亭、鍋茶屋の
経営が傾いたときに、
支援者が言った言葉。
「会社は公器」とは、
あの松下幸之助さんが放った言葉だが、
まさにいま、そんな会社、
そんな経営者が求められている。
自分たちの会社は何のために存在しているのか?
そんな問いに向き合い、
社会と共に生きることで、
冒頭の言葉がかけられる存在になる。
我々は文化として、
何を残したいのか?
いや。
残したい。
と思われるような「文化」とは何か?
そんな問いからスタートしたい。
2011年04月11日
佐藤家かや刈り
「地域愛」に触れる。
25歳のとき。
僕は初めてその世界を知った。
旧庄屋佐藤家保存会。
地元の人たちが集まって、
かやぶきの家を保存しようという集まり。
昨日はそのかや刈りボランティアの日。

休耕となっている田んぼで
かやを刈って、それを集める。
ひたすらその繰り返し。
そしてお昼。
12時半だというのに、宴会開始。
これがいいんだな。
地域の人からにじみでる地域愛に
美味しいお酒の時間となりました。

これこそ、20代の宿題でしょう。
25歳のとき。
僕は初めてその世界を知った。
旧庄屋佐藤家保存会。
地元の人たちが集まって、
かやぶきの家を保存しようという集まり。
昨日はそのかや刈りボランティアの日。

休耕となっている田んぼで
かやを刈って、それを集める。
ひたすらその繰り返し。
そしてお昼。
12時半だというのに、宴会開始。
これがいいんだな。
地域の人からにじみでる地域愛に
美味しいお酒の時間となりました。

これこそ、20代の宿題でしょう。
2011年04月10日
裸でも生きる
山口絵里子「裸でも生きる。」(講談社)
は名著。
何度でも読み返したくなる
起業の物語。
「起業したい」
と言っている大学生や社会人必読の一冊。
「覚悟」とは何か?を教えてくれます。
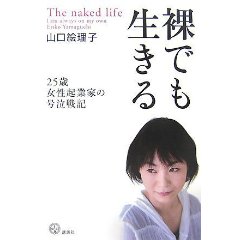
ツルハシブックスでは現在品切れ中。
入荷までしばしお待ちを。
は名著。
何度でも読み返したくなる
起業の物語。
「起業したい」
と言っている大学生や社会人必読の一冊。
「覚悟」とは何か?を教えてくれます。
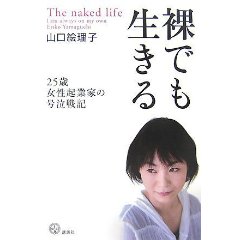
ツルハシブックスでは現在品切れ中。
入荷までしばしお待ちを。
2011年04月09日
火を見て語る
「人生の岐路」ワークショップ兼飲み会を開催。
まきどき村の本拠地
旧庄屋佐藤家にて、開催されました。
自分がどこから来て、
どこへ行くのか?
何のために、
誰のために人生を使いたいのか?
そんな問いが満載でした。
火を見ながら語る。
そんな空間の雰囲気がよかったです。
まきどき村の本拠地
旧庄屋佐藤家にて、開催されました。
自分がどこから来て、
どこへ行くのか?
何のために、
誰のために人生を使いたいのか?
そんな問いが満載でした。
火を見ながら語る。
そんな空間の雰囲気がよかったです。
2011年04月08日
社会事業創造ワークショップ
自分あってる働き方って。。。
誰かの役に立つ仕事って。。。
自分を分析しないで、
「誰のために働きたいか?」
「何を解決したいのか?」
そんな想い、ミッションからスタートする
社会事業創造ワークショップ。
1月に続いて、今年度第2回目の開催です。
今回も限定15名募集します。
第1次締め切りは4月18日(月)
第2次締め切りは4月25日(月)です。
迷っているけど・・・
という人はとりあえずのエントリーを
お願いします。
前回参加学生の声
学生同士のみの語りでは気づけなかった、社会の実態というものを学ぶことができました。
実際に事業をするにあたって、人・もの・お金はこのように動くといった経営のノウハウや、
自分が“これは必要だ”という気持ちから
新しいことは生み出されるということを知ることができました。(新潟大学4年)
新事業や新商品ということで「アイデア力」というものが非常に重要になってくると気づいた。
学生側と企業側で発想や考え方など、やはり異なることが多くあったので
学生側の自分としては企業の方と一緒にワークショップをするということ、
それだけでものすごいインスピレーションを得ることができた。
いかに日頃「考える」ということをしていない、あるいは足りていないと感じた。(新潟県立大学2年)
あ~こういう方法もあるのか~ということを一番思いました。
根本にある解決したいことはみんな同じだったのに、
解決策がどんどん出てきて、結局まとまらず…(笑)
自分が考えていた方法以外のことをたくさん知ることができたのが一番大きかったです。(新潟大学3年)
前回参加経営者・社会人の声
若い人の目線。わかっていた内容でもその中でまた新しい問題点が見つかったような気がします。
“コレ”が気づけたという明確化された型はないですが、
自分の中でインプットしたものをアウトプットすることで自身の中で落としこめると思います。
「みんなの共感+ビジネスとして続けていける+他の誰も実現していない」3つが重なるアイデアを
生み出す苦しさと楽しさを感じました。やはり、困っている人・巻き込みたい人をより
具体的に考えていったほうがアイデアが具体的に出やすいと思いました。
人の行動を変えるための仕掛けを本気で考えるのは、ビジネスのシーンでも非常に有効だと思います。
ここから告知文~~~~~~~~~~~~~
★人のためになる仕事がしたい★
★仕事で「社会貢献」したい★
★困っている人を助けたい★
★新潟のために何かしたい★
そんな大学生に贈る
「社会事業創造ワークショップ」
2011年1月に続き第2回目の開催です。
5月18日(水)、25日(水)18:30~21:00
@新潟駅南口ときめいと(新潟駅直結PLAKA1)
2週連続で行われるワークショップです。
主催:新潟県中小企業家同友会
共催:NPO法人ヒーローズファーム
参加無料。
テーマは
●地域活性化
●教育・福祉
●食と農業
●環境
●国際貢献
など。
これらをテーマに、新潟の企業経営者とガチンコトークをすることで、
新しい事業アイデアを生んでいくこと、
それが企業にとっての新しい事業展開につながります。
お困りごとを解決し、新潟を元気にする新しい事業を
本気で実現させてみませんか?
5月18日(水)
18:30 開始
18:45 お困りごと発見ワークショップ
20:30 資源発掘シートの発表
5月25日(水)
18:30 開始
19:00 課題発表
19:30 ブラッシュアップ
20:15 プラン発表
※1週間の間に各チームでアイデア出しの日を設けます。
申し込みは
info@herosfarm.net
に氏名、大学名、学部、学年、TEL、メールアドレス、
関心のあるテーマを書いて送って下さい。
「新潟を面白くしたい」そんな熱い友人がいたら、ぜひ誘ってみてください。
誰かの役に立つ仕事って。。。
自分を分析しないで、
「誰のために働きたいか?」
「何を解決したいのか?」
そんな想い、ミッションからスタートする
社会事業創造ワークショップ。
1月に続いて、今年度第2回目の開催です。
今回も限定15名募集します。
第1次締め切りは4月18日(月)
第2次締め切りは4月25日(月)です。
迷っているけど・・・
という人はとりあえずのエントリーを
お願いします。
前回参加学生の声
学生同士のみの語りでは気づけなかった、社会の実態というものを学ぶことができました。
実際に事業をするにあたって、人・もの・お金はこのように動くといった経営のノウハウや、
自分が“これは必要だ”という気持ちから
新しいことは生み出されるということを知ることができました。(新潟大学4年)
新事業や新商品ということで「アイデア力」というものが非常に重要になってくると気づいた。
学生側と企業側で発想や考え方など、やはり異なることが多くあったので
学生側の自分としては企業の方と一緒にワークショップをするということ、
それだけでものすごいインスピレーションを得ることができた。
いかに日頃「考える」ということをしていない、あるいは足りていないと感じた。(新潟県立大学2年)
あ~こういう方法もあるのか~ということを一番思いました。
根本にある解決したいことはみんな同じだったのに、
解決策がどんどん出てきて、結局まとまらず…(笑)
自分が考えていた方法以外のことをたくさん知ることができたのが一番大きかったです。(新潟大学3年)
前回参加経営者・社会人の声
若い人の目線。わかっていた内容でもその中でまた新しい問題点が見つかったような気がします。
“コレ”が気づけたという明確化された型はないですが、
自分の中でインプットしたものをアウトプットすることで自身の中で落としこめると思います。
「みんなの共感+ビジネスとして続けていける+他の誰も実現していない」3つが重なるアイデアを
生み出す苦しさと楽しさを感じました。やはり、困っている人・巻き込みたい人をより
具体的に考えていったほうがアイデアが具体的に出やすいと思いました。
人の行動を変えるための仕掛けを本気で考えるのは、ビジネスのシーンでも非常に有効だと思います。
ここから告知文~~~~~~~~~~~~~
★人のためになる仕事がしたい★
★仕事で「社会貢献」したい★
★困っている人を助けたい★
★新潟のために何かしたい★
そんな大学生に贈る
「社会事業創造ワークショップ」
2011年1月に続き第2回目の開催です。
5月18日(水)、25日(水)18:30~21:00
@新潟駅南口ときめいと(新潟駅直結PLAKA1)
2週連続で行われるワークショップです。
主催:新潟県中小企業家同友会
共催:NPO法人ヒーローズファーム
参加無料。
テーマは
●地域活性化
●教育・福祉
●食と農業
●環境
●国際貢献
など。
これらをテーマに、新潟の企業経営者とガチンコトークをすることで、
新しい事業アイデアを生んでいくこと、
それが企業にとっての新しい事業展開につながります。
お困りごとを解決し、新潟を元気にする新しい事業を
本気で実現させてみませんか?
5月18日(水)
18:30 開始
18:45 お困りごと発見ワークショップ
20:30 資源発掘シートの発表
5月25日(水)
18:30 開始
19:00 課題発表
19:30 ブラッシュアップ
20:15 プラン発表
※1週間の間に各チームでアイデア出しの日を設けます。
申し込みは
info@herosfarm.net
に氏名、大学名、学部、学年、TEL、メールアドレス、
関心のあるテーマを書いて送って下さい。
「新潟を面白くしたい」そんな熱い友人がいたら、ぜひ誘ってみてください。
2011年04月07日
ピア万代インターンシップ

ピア万代での
経営企画室インターンシップ。
最大の目標である
4月5日のイベントが開催。
新大の入学式中止になる
というハプニングがありながらも実施。
僕が行った12時前後は人もにぎわっていた。
永井くんを始めとする
3人のメンバーの実感はどうだっただろうか。
振り返りをきっちりして次につなげていきたい。
2011年04月06日
2つのソウゾウ力
大学生のときに書いた
育英会の懸賞論文のタイトル。
2つのソウゾウ力。
想像力
創造力
この2つが
環境を考える上でキーワードとなるはずだと説いた。
あれから10年以上がたち。
時代が、本当に2つのソウゾウ力を求めている。
人生をより豊かに、充実して生きるために。
想像力と創造力をひとりひとりが必要としている。
育英会の懸賞論文のタイトル。
2つのソウゾウ力。
想像力
創造力
この2つが
環境を考える上でキーワードとなるはずだと説いた。
あれから10年以上がたち。
時代が、本当に2つのソウゾウ力を求めている。
人生をより豊かに、充実して生きるために。
想像力と創造力をひとりひとりが必要としている。





