2015年03月31日
15歳に「手紙」を届ける本屋、はじめます
2008年、NHKの合唱コンクールのために
書き下ろされたアンジェラ・アキの「手紙~拝啓 十五の君へ」
2年連続で
NHK紅白歌合戦にも出場し、
大きな反響を呼んだ。
中学生の悩む心、将来への不安を
見事に表現した1曲だった。
テレビやネットでは、
歌いながら涙を流す中学生の姿が
何度も流れた。
苦しい。
なんという違和感。
いまでも僕は、
この歌を聴いて、共感はするけど、
僕は何とも言えない無力感に襲われる。
「十五の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。」
という十五歳の自分に対して、
「自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。」
って。
そんな道徳的なことを言って、
果たして15歳は救われるのだろうか?
「誰にも話せない」のはなぜなのか?
そもそも「誰にも」の「誰」が
親と友達、学校の先生しかいないのではないか?
だから15歳はネット上に救いを求めているのではないか?
そんな地域社会に誰がしたのか?
そう思うと、僕はなんとも言えず悲しくなる。
2002年1月、前年に会社を辞めてプータローだった27歳の僕は、
あるお母さんに中学校3年生の家庭教師を頼まれる。
彼は学校に行っていなかった。
高校受験をしたいので勉強したいのだという。
最初、ほとんど口を開かなかった彼が1か月ほどで
だんだんと笑顔になり、よく話をするようになった。
不思議だった。
もっと立派な大人が周りにいるだろう、と思った。
そのとき。
学校や家庭以外の第3の場所で第3の大人に
出会える場所が必要なのではないか、と強く思った。
しかし。
僕にはその方法がわからなかった。
9年後、2011年。
僕は本屋になった。
ツルハシブックス開業から4か月後。
地下古本コーナー「HAKKUTSU」が誕生。
ただ、地下があいていたのでドラクエのダンジョンのような
古本屋さんをつくろうと思っただけだった。
置かれている本はすべて寄贈された本。
なぜか、入場できるのは29歳までとした。
「なぜ、年齢制限をしようと思ったのですか?」
取材されたメディアにそれを聞かれた。
そういえば、10年ほど前に、
中学生がどうやったら地域の大人と出会えるのか?
という問いを立てていたことを思い出した。
学校だけが世界のすべてではないことを
いま見えている世界だけが世の中のすべてではないことを
メッセージを付けた本を通じて届ける。
その本は15歳に向けて書かれた「手紙」
のようなもの。
この秋、東京・練馬で
スタートに向けて動いている「暗やみ本屋 ハックツ」は
入場者をさらに絞り10代限定とする予定だ。
先日の3月14日のキックオフでは、
10代に贈りたい本として、1冊本を持参してもらったら、
非常にクオリティの高い、思いの詰まった本が集まった。
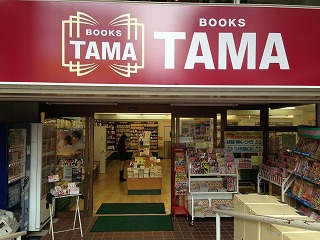

20代までとするのと違い、
新入社員のときに読んだビジネス書などは贈れなくなるからだ。
15歳に本を通じて「手紙」を届ける。
そんな本屋さんをつくろうと思います。
この秋、オープンに向けて
クラウドファウンディングをスタートします。
みなさまの参加・参画をお待ちしています。
https://readyfor.jp/projects/hakkutsu
書き下ろされたアンジェラ・アキの「手紙~拝啓 十五の君へ」
2年連続で
NHK紅白歌合戦にも出場し、
大きな反響を呼んだ。
中学生の悩む心、将来への不安を
見事に表現した1曲だった。
テレビやネットでは、
歌いながら涙を流す中学生の姿が
何度も流れた。
苦しい。
なんという違和感。
いまでも僕は、
この歌を聴いて、共感はするけど、
僕は何とも言えない無力感に襲われる。
「十五の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。」
という十五歳の自分に対して、
「自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。」
って。
そんな道徳的なことを言って、
果たして15歳は救われるのだろうか?
「誰にも話せない」のはなぜなのか?
そもそも「誰にも」の「誰」が
親と友達、学校の先生しかいないのではないか?
だから15歳はネット上に救いを求めているのではないか?
そんな地域社会に誰がしたのか?
そう思うと、僕はなんとも言えず悲しくなる。
2002年1月、前年に会社を辞めてプータローだった27歳の僕は、
あるお母さんに中学校3年生の家庭教師を頼まれる。
彼は学校に行っていなかった。
高校受験をしたいので勉強したいのだという。
最初、ほとんど口を開かなかった彼が1か月ほどで
だんだんと笑顔になり、よく話をするようになった。
不思議だった。
もっと立派な大人が周りにいるだろう、と思った。
そのとき。
学校や家庭以外の第3の場所で第3の大人に
出会える場所が必要なのではないか、と強く思った。
しかし。
僕にはその方法がわからなかった。
9年後、2011年。
僕は本屋になった。
ツルハシブックス開業から4か月後。
地下古本コーナー「HAKKUTSU」が誕生。
ただ、地下があいていたのでドラクエのダンジョンのような
古本屋さんをつくろうと思っただけだった。
置かれている本はすべて寄贈された本。
なぜか、入場できるのは29歳までとした。
「なぜ、年齢制限をしようと思ったのですか?」
取材されたメディアにそれを聞かれた。
そういえば、10年ほど前に、
中学生がどうやったら地域の大人と出会えるのか?
という問いを立てていたことを思い出した。
学校だけが世界のすべてではないことを
いま見えている世界だけが世の中のすべてではないことを
メッセージを付けた本を通じて届ける。
その本は15歳に向けて書かれた「手紙」
のようなもの。
この秋、東京・練馬で
スタートに向けて動いている「暗やみ本屋 ハックツ」は
入場者をさらに絞り10代限定とする予定だ。
先日の3月14日のキックオフでは、
10代に贈りたい本として、1冊本を持参してもらったら、
非常にクオリティの高い、思いの詰まった本が集まった。
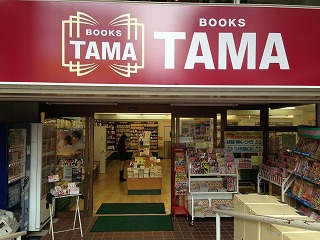

20代までとするのと違い、
新入社員のときに読んだビジネス書などは贈れなくなるからだ。
15歳に本を通じて「手紙」を届ける。
そんな本屋さんをつくろうと思います。
この秋、オープンに向けて
クラウドファウンディングをスタートします。
みなさまの参加・参画をお待ちしています。
https://readyfor.jp/projects/hakkutsu
2015年03月30日
「社会実験」だと言えばいい
陸奥賢さんに
教えてもらったキーワード。
「社会実験」
いい日本語。
社会実験っていい響きだ。
失敗しても許される感がある。
ツルハシブックスのある内野駅から吉田駅間の
越後線の増便をしていた社会実験の期間が
3年過ぎてあえなく終了して、
40分に1本あった電車が再び60分に1本になった。
なってみるとなんとも不便だ。
乗り過ごしたら40分後なのか1時間後なのかによって
ダメージはだいぶ違う。
こういうときに本屋があるといいのだけど。
あ、あるじゃん、内野駅前には。(笑)
「なんのためにやるのか?」
「どんなメリットがあるのか?」
とすぐ聞かれてしまう日本社会において、
「社会実験です」と言い切れることが
大切だと思う。
大学生のうちのやるべきこと。
それが「社会実験」なのだと思う。
悪く言えば、「イタズラ」だ。
企みを実行する。
そこには「誰かを幸せにする」という仮説がある。
小山薫堂さんが仕事を始める時の条件
1 それは誰かがやっていないか?
2 それは誰を幸せにするか?
3 それが自分にとって面白いか?
これらを満たしていれば、
あるいは、2,3だけ満たしていれば、
「やってみる」ことが大切だ。
それが「うまくいく」とか
「お金が儲かる」とかよりも、
「やってみる」ことが大切だ。
うまくいっていても、いなくても
「社会実験です」と言いながら、
サラッと、それでいて熱く何かに取り組めたらいいと思う。
あなたは社会実験してますか?
教えてもらったキーワード。
「社会実験」
いい日本語。
社会実験っていい響きだ。
失敗しても許される感がある。
ツルハシブックスのある内野駅から吉田駅間の
越後線の増便をしていた社会実験の期間が
3年過ぎてあえなく終了して、
40分に1本あった電車が再び60分に1本になった。
なってみるとなんとも不便だ。
乗り過ごしたら40分後なのか1時間後なのかによって
ダメージはだいぶ違う。
こういうときに本屋があるといいのだけど。
あ、あるじゃん、内野駅前には。(笑)
「なんのためにやるのか?」
「どんなメリットがあるのか?」
とすぐ聞かれてしまう日本社会において、
「社会実験です」と言い切れることが
大切だと思う。
大学生のうちのやるべきこと。
それが「社会実験」なのだと思う。
悪く言えば、「イタズラ」だ。
企みを実行する。
そこには「誰かを幸せにする」という仮説がある。
小山薫堂さんが仕事を始める時の条件
1 それは誰かがやっていないか?
2 それは誰を幸せにするか?
3 それが自分にとって面白いか?
これらを満たしていれば、
あるいは、2,3だけ満たしていれば、
「やってみる」ことが大切だ。
それが「うまくいく」とか
「お金が儲かる」とかよりも、
「やってみる」ことが大切だ。
うまくいっていても、いなくても
「社会実験です」と言いながら、
サラッと、それでいて熱く何かに取り組めたらいいと思う。
あなたは社会実験してますか?
2015年03月29日
偶然を楽しみ、即興で演じる。

「自由になるのは大変なのだ」(今井純 論創社)
移動車中で読みながら、
出会ってしまったのは
陸奥賢さん。


観光家として
活躍する陸奥さんにお会いした。
いやあ、面白かった。
本はもっともっと遊べるのだなあと。
昨日チャレンジしたのは、直観読み。
あれをインプロの導入にしたら
面白いんじゃないかと今朝思いました。
偶然を楽しみ、即興で演じる。
本はそんなツールになりうるのかもしれません。
いやあ、わくわくしてきたなあ。
陸奥さんの名言。
「社会実験ですから」は
また明日かきます。
2015年03月28日
会議とインプロ

「自由になるのは大変なのだ」(今井純 論創社)
読み始め。
インプロ(即興演劇)のマニュアル本。
インプロっていうのは
台本のない即興演劇だから
それにマニュアルっていうのも面白い話だけど。
「劇団員」を名乗るからには、
インプロを知らなきゃいけないよなあと思って。
これが読み進めると面白い。
インプロで重要なイエスアンド、
とかがわかりやすく解説されている。
これは、これからの社会を生きていくには
すごく大切なことが含まれているように思う。
企業の人材育成の手法として、
インプロを取り入れるところも出てきているという。
企業が重視するヒューマン・スキル
1 コミュニケーション能力
2 チームワーク
3 自己表現力
などなど。
これって、大学の授業とか
インターンシップにも重要な
要素になっていくのだろうと想像できる。
ツルハシブックスは劇場で、
劇団員を養成するとすれば、
これらの要素がすごく重要になってくる。
いいタイミングでいい本に出会っているなあと思う。
2015年03月27日
「働くこと」=「自己実現」ではない

「キャリアポルノは人生の無駄だ」(谷本真由美 朝日新書)
いわゆる「自己啓発本」ブームについて
断じた1冊。
この中で著者は
日本人は集団内競争や
集団間競争が好きな人種であり、
そのため自己啓発本がよく売れるのだという。
特にそれは
「働くこと」=「自己実現」と考えてしまうから、
苦しくなるのだという。
2004年の調査によると、
仕事に生きがいを求める高校生は
男子41.9%女子43.1%なのだが
同じ調査で高校生の保護者にとったアンケートだと
62.3%が「生きがい」を仕事に求めてほしいと
答えており、「将来の安定」や「収入」を
上回ったのだという。
親は、「仕事は生きがいでなければならない」
と言っているのです。
本来は自己実現は
仕事に限らず幅広い生活活動
(子育てや趣味を含む)によって
実現されていくのが当たり前です。
しかし、それを「仕事」に限定してしまうと、
仕事=生きがい
働くこと=自己実現
ではない場合は
満たされない気持ちになってしまいます。
この思想こそが、
高い離職率やニートと呼ばれる働かない若者の
引き金となっているのではないかと思います。
働くことで自己実現しなくてもいい。
お金のために働くことでいい。
そんな感覚がもっと広まれば
若者はもっと楽になるのではないかと思います。
2015年03月26日
肩書きではなく、感性で把握する
イタリア勤務となった日本人は
最初の数か月は、パーティーの席の
自己紹介で場を凍りつかせるという。
「ワタクシは日本から来た〇〇と申します。
〇〇という会社でITを担当しております。
日本ではネットメディア関連の部署に勤めておりました。」
と自己紹介すると、みんなが固まっている。
少しの沈黙の後、イタリア人から
「そう。で、あなたはどういう人なのかしら?」
と質問されるという。
イタリアに限らずヨーロッパでは、
まずはこの前の休日にどこにいったとか、
趣味はなにで、弟がなにしてるとか、
そいうプライベートなことを話すのが普通だ。
「肩書きから入る」のは
日本サラリーマン社会特有の文化だという。
これはどういうことなのだろうか?
なぜ、肩書を聞いて、それで安心してしまうのだろうか。
「どこの組織に属しているか?」
ということがそんなにも重要なのはなぜだろうか。
系列とかいろいろあるから?
(ビールはキリンじゃないとダメだとか?)
それにしても、
これからの時代には通用しない戦略だろうと思う。
一生同じ会社に勤める人は少なくなっている。
しかも同じ会社だからと言って、
やっている仕事は多角化しているだろうから、
それによって、その人を判断することはまったくできないだろう。
だとしたら、
自分の感性で目の前の人を判断するしかない。
感性を磨くこと。
目の前の人が信用できるのかできないのか。
一緒に仕事をして楽しいのかそうではないのか。
そんな感性を磨くために
大学時代と20代はある。
1 本を読む
2 人に会う
3 旅をする
感性を磨く三大活動を今日からはじめよう。
最初の数か月は、パーティーの席の
自己紹介で場を凍りつかせるという。
「ワタクシは日本から来た〇〇と申します。
〇〇という会社でITを担当しております。
日本ではネットメディア関連の部署に勤めておりました。」
と自己紹介すると、みんなが固まっている。
少しの沈黙の後、イタリア人から
「そう。で、あなたはどういう人なのかしら?」
と質問されるという。
イタリアに限らずヨーロッパでは、
まずはこの前の休日にどこにいったとか、
趣味はなにで、弟がなにしてるとか、
そいうプライベートなことを話すのが普通だ。
「肩書きから入る」のは
日本サラリーマン社会特有の文化だという。
これはどういうことなのだろうか?
なぜ、肩書を聞いて、それで安心してしまうのだろうか。
「どこの組織に属しているか?」
ということがそんなにも重要なのはなぜだろうか。
系列とかいろいろあるから?
(ビールはキリンじゃないとダメだとか?)
それにしても、
これからの時代には通用しない戦略だろうと思う。
一生同じ会社に勤める人は少なくなっている。
しかも同じ会社だからと言って、
やっている仕事は多角化しているだろうから、
それによって、その人を判断することはまったくできないだろう。
だとしたら、
自分の感性で目の前の人を判断するしかない。
感性を磨くこと。
目の前の人が信用できるのかできないのか。
一緒に仕事をして楽しいのかそうではないのか。
そんな感性を磨くために
大学時代と20代はある。
1 本を読む
2 人に会う
3 旅をする
感性を磨く三大活動を今日からはじめよう。
2015年03月25日
「商店街」は100年前に発明された

「商店街はなぜ滅びるのか~社会・政治・経済史から探る再生の道」(新雅史 光文社新書)
「伝統的な商店街」だから
残していくべき、という論を打ち破る、
商店街の起源に迫った1冊。
これは面白い。
だからこそ商店街は衰退するし、
だからこそ商店街には希望があるのだと実感できる。
第一次世界大戦後くらいから、
近代雇用の仕組みが
親方請負制から企業での直接雇用に切り替わっていった。
いわゆる「新卒一括採用」のはしりである。
しかも当時は学校を卒業してすぐには就職はできないという制度があり、
そのような社会背景から、
農村部から大量の人が都市部に流入し、
そこで手っ取り早く始められる
食品などの小売業を始めることになる。
都市部で小売業が急増し、
もちろん、人口も急増しているので
生活必需品の需給が不安定となり、
物価は乱高下した。
それを都市住民は
小売業の増加のせいだととらえ、
米騒動などが起こる。
消費者側がそれに対処する形で生まれたのが
「協同組合」である。
みんなで仕入れてみんなで買うことで
物価の安定をはかった。
自治体側がそれに対応したのが「公設市場」であり、
場所を決めて決まった業者がものを売れることで、
物価の安定をはかった。
その頃同時期に都市部にできたのが
「百貨店」である。
それまでの「呉服店」のようなところは、
座売り方式といって、富裕層を相手に、
カタログを見せて、それを奥から小僧が持ってくる、
というような商売をしていた。
三井呉服店(いまの三越)は
1900年に座売り方式をあらかじめ商品を見せる陳列方式に変え、
食堂や休憩所などを設け、催し物を開催するようになった。
1923年の関東大震災後には、一般大衆向けに、
日用品の販売をして一定の成功を収めたことで、
店舗面積を拡大し、サービスを多角化していった。
「協同組合」「公設市場」は零細小売商の反発を生んだ。
さらに「百貨店」の登場により、
零細小売商は、自分たちの「テリトリー」を
奪われることとなり、各地で百貨店に対する
不買運動・投石運動などを起こしていった。
このまま零細小売商の危機を見過ごすと、
大きな社会不安を引き起こすことになる。
そこで考え出されたのが
「商店街」だった。
「商店街」のコンセプトは、3つ。
1 百貨店における近代的な消費空間と娯楽性
2 協同組合における協同主義
3 公設市場における小売の公共性
つまり。
当時の最先端の要素が取り入れられたものが
「商店街」だったのだ。
かくして商店街は「組織」化し、
協同して計画的に事業に取り組むことになり、
また専門店が集積し並んでいる
「横の百貨店」として機能し、
それは地域間格差をつくらないという公共性を持っていた。
なるほど。
この本には、ほかにも
家族の近代化と商店街など興味深いトピックが並んでいる。
「商店街」とは100年ほど前に発明された仕組みだった。
ということは、
「これからの商店街」は、
まだまだ発明できるということなのではないか。
僕としては
協同機能と公共性を
NPO等の組織が補いながら、
消費空間としての娯楽性をアップさせる。
その際には、
「ふるさと」としての商店街
「学びの空間」としての商店街を
取り戻していくことがこれからの(というか内野町の)
商店街を作っていくのではないか?
という仮説を持っている。
商店街を学びの場、人にスポットを当てた観光の場として
再構築していくこと。
それがこれからの商店街のつくり方に
なっていくのではないだろうか。
2015年03月24日
あきらめない理由と売れ続ける理由
新規事業立ち上げミーティングの
お手伝いをしてきた。
カタルタでアイスブレイクした後に、
チームビルディングの手法である
人生モチベーショングラフ。
「ぶっちゃける」っていうのが大切なんだと、
森田英一さんに教わった。
人生モチベーショングラフ。
違うものがクローズアップされて
何度やっても面白い。
あきらめない理由と売れ続ける理由。
それらは自分自身の過去にしかない。
過去に出会って衝撃を受けた人、
過去に激しく憤りを感じたこと。
社会起業家に限らず、
事業継続している人には
過去にそんな経験をしている。
ホントは誰もがかつて、
お客に出会っている。
それを思い出していないだけだ。
過去の自分自身か、
過去に「なんとかしたい」と心から思った人たち
こそがお客だ。
そこを出発点にするから、
あきらめない理由になる。
そこにお客さんが共感するから、
売れ続ける理由になる。
まずは過去を振り返り、それを共有すること。
そこから新しいプロジェクトが始まっていく。
お手伝いをしてきた。
カタルタでアイスブレイクした後に、
チームビルディングの手法である
人生モチベーショングラフ。
「ぶっちゃける」っていうのが大切なんだと、
森田英一さんに教わった。
人生モチベーショングラフ。
違うものがクローズアップされて
何度やっても面白い。
あきらめない理由と売れ続ける理由。
それらは自分自身の過去にしかない。
過去に出会って衝撃を受けた人、
過去に激しく憤りを感じたこと。
社会起業家に限らず、
事業継続している人には
過去にそんな経験をしている。
ホントは誰もがかつて、
お客に出会っている。
それを思い出していないだけだ。
過去の自分自身か、
過去に「なんとかしたい」と心から思った人たち
こそがお客だ。
そこを出発点にするから、
あきらめない理由になる。
そこにお客さんが共感するから、
売れ続ける理由になる。
まずは過去を振り返り、それを共有すること。
そこから新しいプロジェクトが始まっていく。
2015年03月23日
思いがけず、たどり着いた駅

ツルハシブックス4周年記念イベント
「これからのツルハシブックスのつくりかた」
山田店長とのトークセッション。
ツルハシブックスとは何か?
これからどうなっていくのか?
ここでも大活躍した店員サムライのみほてぃーに
1年間でいろんなものをもらった気がする。
彼女が最後に言った一言が
印象的だった。
みんなが集い、そして旅立っていく
「プラットホーム」としての本屋を
別の言い方で表現するとどうなるか?
「思いがけず、たどり着いた駅」
だと彼女は言った。
誰もが人生という旅の途中で、
どこかに向かっている。
まっすぐに新幹線で向かっている人は
そんなに多くなくて、
ゆっくりと各駅停車で乗り換えながら
自分でもよくわかっていない目的地を目指す。
ある人は、電車の心地よさに、うっかり寝てしまい、
乗り過ごしてしまった。
ある人は、車窓の景色に惹かれ、
降りてみようと思った。
ある人は、終点で乗り換えようと思った駅に
次の電車までのあいだ、ちょっと降り立ってみた。
そんな人たちが偶然にも出会う、小さな本屋。
「気がついたら私も、
本屋という舞台の
共演者になっていました。」
後から振り返ると、
そんなふうにしか回想できない、不思議な場所。
ある人は、
本棚からピンと来た1冊を選び、
イロハニ堂でゆっくりと読んでから、次の旅に出る。
ある人は、
地下古本コーナーで誰かからの手紙のついた本を受け取り、
初めて出会ったはずの店員さんや他のお客さんとなぜか仲良くなって、
また会おうと約束して学校生活に戻っていく。
ある人は、そこに残り、店員サムライとして、
後から来る共演者たちのために、
場を一緒につくることにする。
そうして、旅立つ人は旅立ち、残る人は残る。
旅立つ人たちにとっては、帰ってくる場所である。
そんな空間を一緒に作ってきた
3人の卒業生。
21日は彼らの卒業式だった。
よこおくんとのじまさんとはばっち。
3人は3年以上も関わり、
ツルハシブックスの礎を作ってくれた。
それぞれ、山形、東京、福島への旅立っていく。
「思いがけず、たどり着いた駅」からの出発。
次はどんな色の、どんな速さの電車に乗るのだろう?
どんな人と一緒に旅をするのだろう?
ツルハシブックスを卒業してからも、
どこの現場にいっても、
みなさんが「ツルハシブックス劇団員」として
演じ続けることを心から願っています。
卒業おめでとうございます。
よい旅を。


※素敵な卒業式を企画してくれた今井さんと店員侍のみなさん、本当にありがとうございました。
※ツルハシブックスという「思いがけずたどり着いた駅」を
一緒につくっていく「劇団員」を募集しています。
http://tsuruhashi.skr.jp/boshu
※「思いがけずたどり着いた駅」というコンセプトからは
本当に演劇がひとつできそうだなあと思っています。
ツルハシブックスを舞台に演劇をやる日は近い。
2015年03月21日
やってみる、とは機会を得るということ
「教育」ではなく、「機会提供」
こそが僕の目的なのだ。
そして、「機会提供」は同時に、
自分にとっては、「機会を得ること」
になる。
その「機会」は
一方向ではなく、双方向だからだ。
2014年11月に
文部科学省がフリースクールフォーラムを開催し、
フリースクールに対しての支援検討に入っている。
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/209083.html
僕の周りでは、いわゆる「サドベリースクール」の
設立ラッシュを迎えている。
見学にいってきた
伊那の「まあるい学校」もその一つ。
きっとこれから、
「機会提供」「双方向」がキーワードになってくる。
そしてそれは、
地域のお年寄りの出番を作ることにも
直結している。
それは決して、
「お年寄りから先人の知恵を学ぼう」
というものではない。
そこに参加するお年寄りの基本姿勢は、
「自分たちが子どもから学ぼう」
であり、
「機会提供」と「機会を得る」
が同時に起こっているのだという自覚。
そんな「場」がこれからは学校と呼ぶのだろう。
これからの教育に携わる人の条件は、
「子どもたちと接することで自分が学ぼう」と思っている人。
反対に言えば、
「子どもたちと接することで自分が学ぼう」と思っている人が
集まれば、「学校」は成立することになる。
そんな学校がこれから、どんどんできていく。
松下村塾がどんどんできていく。
こそが僕の目的なのだ。
そして、「機会提供」は同時に、
自分にとっては、「機会を得ること」
になる。
その「機会」は
一方向ではなく、双方向だからだ。
2014年11月に
文部科学省がフリースクールフォーラムを開催し、
フリースクールに対しての支援検討に入っている。
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/209083.html
僕の周りでは、いわゆる「サドベリースクール」の
設立ラッシュを迎えている。
見学にいってきた
伊那の「まあるい学校」もその一つ。
きっとこれから、
「機会提供」「双方向」がキーワードになってくる。
そしてそれは、
地域のお年寄りの出番を作ることにも
直結している。
それは決して、
「お年寄りから先人の知恵を学ぼう」
というものではない。
そこに参加するお年寄りの基本姿勢は、
「自分たちが子どもから学ぼう」
であり、
「機会提供」と「機会を得る」
が同時に起こっているのだという自覚。
そんな「場」がこれからは学校と呼ぶのだろう。
これからの教育に携わる人の条件は、
「子どもたちと接することで自分が学ぼう」と思っている人。
反対に言えば、
「子どもたちと接することで自分が学ぼう」と思っている人が
集まれば、「学校」は成立することになる。
そんな学校がこれから、どんどんできていく。
松下村塾がどんどんできていく。
2015年03月20日
儲かるビジネスと世界観
儲かるビジネスと世界観のジレンマ。
スティーブ・ジョブズの例を出すまでもなく、
継続して儲かるビジネスには、世界観がある。
その世界観が支持されるからだ。
それはもはや合理性というよりは
宗教性に近いものがあると思う。
みな、iphoneというマシーンが欲しいのではなく、
極端な話をすれば、
「iphoneユーザーであるという誇り」がほしいのだ。
きっとこれからのビジネスは
そんな風になっていく。
ビジネスと宗教のあいだ。
では、これから若くして(若くなくても)
ビジネスを始める人はどうしたらいいのか?
「世界観」をつくる。
ということ。
どんな世界をつくりたいのか?
お客さんにどんな世界を見せたいのか?
そこがもっとも大切になってくる。
なんとかして稼がなければならない。
しかし、そこで「世界観」とビジネスのバランスが
重要になってくる。

「ナリワイをつくる」の伊藤洋志さんによる衝撃の一言。
「本業ではないほうが本質的なことができる」
つまり、世界観を構築するような本質的なことは、
本業ではなかなか生み出すことが難しいということだ。
だから、はじまりは、本業じゃないビジネスのほうが
世界観を生み出すのには向いているのではないか、
ということだ。
しかし、継続して儲かるビジネスには、世界観が必要である、
これがいまの世の中だ。
しかしそれには時間がかかる。
これが儲かるビジネスと世界観のジレンマ。
ツルハシブックスは、いよいよ
「世界観」を語る時がきているのではないか。
そうなると、
やはり原点に返るしかない。
小説「吉田松陰」
野山獄と松下村塾のエピソードに胸が熱くなった。
・学びあうことで獄中でも希望が生まれるのだということ。
・教えるのではなく、ともに学ぼうとすることで人が育つということ。
これらをツルハシブックスで実現することができないだろうか?
ツルハシブックスは
現代の松下村塾に成り得るのではないか。
本屋という入り口で
コミュニケーション・デザインをし、その入り口をつくり、
入ってきた人たちが
年齢や職業の枠を超えて、ともに学ぶ。
そんな舞台をつくることが可能なのではないか?
ツルハシブックスは、
現代の松下村塾を目指します。
「ともに学ぼう」
そんな人たちと一緒にこれからの本屋を、ビジネスを、世界観をつくっていきたい。
ツルハシブックス第2期劇団員募集(4月30日まで)
http://tsuruhashi.skr.jp/boshu
本日、ツルハシブックスは4周年です。
スティーブ・ジョブズの例を出すまでもなく、
継続して儲かるビジネスには、世界観がある。
その世界観が支持されるからだ。
それはもはや合理性というよりは
宗教性に近いものがあると思う。
みな、iphoneというマシーンが欲しいのではなく、
極端な話をすれば、
「iphoneユーザーであるという誇り」がほしいのだ。
きっとこれからのビジネスは
そんな風になっていく。
ビジネスと宗教のあいだ。
では、これから若くして(若くなくても)
ビジネスを始める人はどうしたらいいのか?
「世界観」をつくる。
ということ。
どんな世界をつくりたいのか?
お客さんにどんな世界を見せたいのか?
そこがもっとも大切になってくる。
なんとかして稼がなければならない。
しかし、そこで「世界観」とビジネスのバランスが
重要になってくる。

「ナリワイをつくる」の伊藤洋志さんによる衝撃の一言。
「本業ではないほうが本質的なことができる」
つまり、世界観を構築するような本質的なことは、
本業ではなかなか生み出すことが難しいということだ。
だから、はじまりは、本業じゃないビジネスのほうが
世界観を生み出すのには向いているのではないか、
ということだ。
しかし、継続して儲かるビジネスには、世界観が必要である、
これがいまの世の中だ。
しかしそれには時間がかかる。
これが儲かるビジネスと世界観のジレンマ。
ツルハシブックスは、いよいよ
「世界観」を語る時がきているのではないか。
そうなると、
やはり原点に返るしかない。
小説「吉田松陰」
野山獄と松下村塾のエピソードに胸が熱くなった。
・学びあうことで獄中でも希望が生まれるのだということ。
・教えるのではなく、ともに学ぼうとすることで人が育つということ。
これらをツルハシブックスで実現することができないだろうか?
ツルハシブックスは
現代の松下村塾に成り得るのではないか。
本屋という入り口で
コミュニケーション・デザインをし、その入り口をつくり、
入ってきた人たちが
年齢や職業の枠を超えて、ともに学ぶ。
そんな舞台をつくることが可能なのではないか?
ツルハシブックスは、
現代の松下村塾を目指します。
「ともに学ぼう」
そんな人たちと一緒にこれからの本屋を、ビジネスを、世界観をつくっていきたい。
ツルハシブックス第2期劇団員募集(4月30日まで)
http://tsuruhashi.skr.jp/boshu
本日、ツルハシブックスは4周年です。
2015年03月19日
共感されるプロジェクト
共感されるプロジェクトとは、
出発点は非常に個人的事柄でありながら、
世界観を持ったプロジェクト。
世界観とは、
世界をどう観るか?
課題は何か?
未来はどうなっているといいのか?
どのような手法でそれを達成するのか?
そこに共感できなければならない。
本屋やカフェ、米屋は
それを表現するためのツール。
その世界観を持てなければ、
事業一つ一つの芯がなくなり、瓦解する。
世界観が定まれば、
次は多様な人たちを集め、それを実行していく。
ひとりひとりがもっているツールボックスが違うから
多様な人を集めることが必要になる。
幼稚園児からおじいちゃんまで、
あらゆる人たちのツールを活かし、
新しい仕事やまちのカタチをつくっていこう。
出発点は非常に個人的事柄でありながら、
世界観を持ったプロジェクト。
世界観とは、
世界をどう観るか?
課題は何か?
未来はどうなっているといいのか?
どのような手法でそれを達成するのか?
そこに共感できなければならない。
本屋やカフェ、米屋は
それを表現するためのツール。
その世界観を持てなければ、
事業一つ一つの芯がなくなり、瓦解する。
世界観が定まれば、
次は多様な人たちを集め、それを実行していく。
ひとりひとりがもっているツールボックスが違うから
多様な人を集めることが必要になる。
幼稚園児からおじいちゃんまで、
あらゆる人たちのツールを活かし、
新しい仕事やまちのカタチをつくっていこう。
2015年03月18日
「効率化」という仮説

(ビジネス寓話50選 博報堂ブランドデザイン アスキー新書)
軽快、そして痛快。
電車で読むならこんな本。
ちょっと面白かったので、
ひとつ紹介
~~~ここから引用
「第18話 教授と助手のゲーム」
教授と助手が飛行機に乗っていた。
目的地まではまだしばらくある。
退屈しのぎに教授は隣の席の助手に
ゲームをしようと提案した。
「どんなゲームですか?」と助手が言った。
「そうだな。交代で質問を出し合って、
答えられなければ相手に罰金を払うことにしよう。
君の罰金は5ドル。私の罰金は、まぁ、ハンデをつけて50ドルでどうかね?」
「いいですよ、受けて立ちます。先生からどうぞ」
「では、地球から太陽までの距離はいかほどか?」
助手は黙って5ドル払った。
「ふむ、勉強が足りんな。約1億5000万キロメートルだ。
『1天文単位』でも正解だったんだがね。さあ、君の番だ。」
「では先生、丘に上がるときは3本脚で、降りるときは4本脚のものをご存知ですか?」
教授は必死に考えたが答えが思いつかず、とうとう目的地についていまった。
教授はしぶしぶ50ドルを払って訊ねた。
「私の負けだ・・・。正解はなんだったんだ?」
助手は黙って5ドル払った。
~~~ここまで引用
クイズの問題を出す人は、
その答えを知っていなきゃいけない。
これは私たちが疑うことすら忘れてしまっている問題です。
助手はその前提にとらわれず、教授との罰金の額という条件を見て、
まんまと40ドルを手に入れます。
既存のフレームを疑うこと。
いや、そもそも
資本主義そのものがフィクション(仮説)なのかもしれないのです。
(平川克美 「路地裏の資本主義」より)
世の中のほどんどのものは
実は仮説に過ぎません。
検証が終わっていて絶対の真実であるものは、
ほとんどないと言えるでしょう。
会社に雇用された給与所得者(=サラリーマン)が
メジャーな働き方になったのは、ごく最近の話です。
世界史的には、1920年代ではないかと言われています。
まだ100年経っていません。
そして、学校は言い方を変えれば、
「サラリーマン製造装置」として機能してきました。
一定のクオリティの人材を
低コスト高パフォーマンスで生み出し続けるシステム、
それが学校でした。
その根本には「分業」、
さらに根本には「効率化」という思想があったことは
容易に想像できます。
効率的に一定の人材を輩出し続ける。
地域の影響を受けずに、均質な人材を輩出すること。
これは日本の工業を軸にした
経済発展に大きく貢献してきました。
しかしながら、
効率化ではもはや価値を生むことができなくなりました。
「資本論」的な考え方をすれば、利益を生み出すためには、
効率化し、人材を低コストで極限まで能力を発揮させる体制をつくることが大切でした。
しかし、それは同時に、
人件費の安い国へ生産拠点が移動することを意味します。
これから価値を生むのは、
イノベーションを生む「創造力」です。
しかし、
「創造力」は「効率化」からは生まれないと
私は思っています。
「効率化」という仮説が崩れた時代を
僕たちはいま、生きています。
だとすると、
学校は?
企業は?
そしてひとりひとりのライフスタイルは?
小さい時から夢を定めて、そこに向かって効率的に努力する。
かえって、リスクの高い生き方なのではないかなと思います。
「効率化」という前提を
仮説にすぎないと見ることで、
では、何をすればいいのか?を考えるきっかけになるのではと思います。
2015年03月17日
ビジネスとアートと宗教のあいだ
暗やみ本屋ハックツ企画会議。


23人の人が参加。
ブックスタマ上石神井店の
会議室は人でいっぱいになった。

1月に寄付侍になった高橋さんと村山さんも初めまして、で名刺交換。

打ち上げ会場はすぐ近くの餃子屋「一圓」
こちらにも16名が参加。
すごい盛り上がりました。
これから半年かけて、
「暗やみ本屋 ハックツ」を形作っていきましょう。
これは、みんなで作る本屋です。
寄贈本を集めるのと同時に
企画を語り合う「ハックツ企画会議」は
毎月1回開催予定。
次回は4月18日(土)14:00予定です。
今回のイベントで出たのは、
・本を寄贈したい人・工事をしたい人・寄付をしたい人・劇団員として運営したい人
さまざまなメニューを用意したほうが参加しやすいということ。
最後に川上徹也さんからのご指摘で
・店内との一体感をどう作っていくか?
ここはこれから半年かけてつくっていかなければなりません。
今回、いちばんすごいと思ったのは、
寄贈本のクオリティの高さ。
これは「10代に向けて」と
テーマを設定したことによって、
より相手のことを考えた選書に
なっていると思いました。
10代から20代だと、
社会人の初めのときに読んだ、
ちょっとしたビジネス書を
寄贈してしまうのだけど、
今回は、
わざわざ本を新たに買いなおして
持ってきてくれた人も多く、
非常に思いが詰まっていました。
だからこそ、前半での本の紹介にも熱が入りました。
昨日は劇団員チームで振り返りと今後の展望をしました。



※ツルハシブックスでは劇団員を募集しています。
http://tsuruhashi.skr.jp/boshu
僕は、アートとしては中学生高校生に
メッセージを届ける手段としての本を
洗練させていきたいと思っています。
そして、オトナのアート(ビジネス)としては、
ブックスタマ上石神井店に好影響(売り上げが上がる)
をもたらしていきたいと思っています。
そして、宗教としては、
「劇団員」という生き方を
広めていく最前線にしていきたいと思ってます。
中学生高校生が来た時に、
「共演者が来た」と感じて、
彼らの話を引き出し、
その瞬間を演じる劇団員。
そんな人たちと一緒に
これからの本屋の仮説をつくり、
検証していきたいと思っています。
ブックスタマ×ツルハシブックス
「暗やみ本屋 ハックツ」
ようやくスタートしました。
ビジネスとアートと宗教のあいだに
「暗やみ本屋 ハックツ」という
リレーショナル・アートを
形作っていきたいと心から思います。
東京近郊の方、全国の方、
あなたも10代に本を届けませんか?
「劇団員募集」はこちらから。
http://tsuruhashi.skr.jp/boshu


23人の人が参加。
ブックスタマ上石神井店の
会議室は人でいっぱいになった。

1月に寄付侍になった高橋さんと村山さんも初めまして、で名刺交換。

打ち上げ会場はすぐ近くの餃子屋「一圓」
こちらにも16名が参加。
すごい盛り上がりました。
これから半年かけて、
「暗やみ本屋 ハックツ」を形作っていきましょう。
これは、みんなで作る本屋です。
寄贈本を集めるのと同時に
企画を語り合う「ハックツ企画会議」は
毎月1回開催予定。
次回は4月18日(土)14:00予定です。
今回のイベントで出たのは、
・本を寄贈したい人・工事をしたい人・寄付をしたい人・劇団員として運営したい人
さまざまなメニューを用意したほうが参加しやすいということ。
最後に川上徹也さんからのご指摘で
・店内との一体感をどう作っていくか?
ここはこれから半年かけてつくっていかなければなりません。
今回、いちばんすごいと思ったのは、
寄贈本のクオリティの高さ。
これは「10代に向けて」と
テーマを設定したことによって、
より相手のことを考えた選書に
なっていると思いました。
10代から20代だと、
社会人の初めのときに読んだ、
ちょっとしたビジネス書を
寄贈してしまうのだけど、
今回は、
わざわざ本を新たに買いなおして
持ってきてくれた人も多く、
非常に思いが詰まっていました。
だからこそ、前半での本の紹介にも熱が入りました。
昨日は劇団員チームで振り返りと今後の展望をしました。



※ツルハシブックスでは劇団員を募集しています。
http://tsuruhashi.skr.jp/boshu
僕は、アートとしては中学生高校生に
メッセージを届ける手段としての本を
洗練させていきたいと思っています。
そして、オトナのアート(ビジネス)としては、
ブックスタマ上石神井店に好影響(売り上げが上がる)
をもたらしていきたいと思っています。
そして、宗教としては、
「劇団員」という生き方を
広めていく最前線にしていきたいと思ってます。
中学生高校生が来た時に、
「共演者が来た」と感じて、
彼らの話を引き出し、
その瞬間を演じる劇団員。
そんな人たちと一緒に
これからの本屋の仮説をつくり、
検証していきたいと思っています。
ブックスタマ×ツルハシブックス
「暗やみ本屋 ハックツ」
ようやくスタートしました。
ビジネスとアートと宗教のあいだに
「暗やみ本屋 ハックツ」という
リレーショナル・アートを
形作っていきたいと心から思います。
東京近郊の方、全国の方、
あなたも10代に本を届けませんか?
「劇団員募集」はこちらから。
http://tsuruhashi.skr.jp/boshu
2015年03月16日
生きる、ということ、それは書をかくということ
書展「HAKU」@栃木県総合文化センターに
お邪魔してきました。
新潟大学の書道科卒業生4人の展示会。
卒業して学校現場に入り、書道を教えている人。
自分で書道教室を開き、さまざまな制作物を作っている人。
いろいろな立場の人が
今の自分を表現した書展でした。


書道というのは、
「道」なんだ、って初めて体感した機会となりました。
、
4人のプロフィールを見ると、
四者四様の意気込みが書かれています。
「書道とともに生きていく決意表明」
「現在地の確認」
「書と向き合い続けるということは、すなわち自分と向きあい続けるということです。」
(福田さん)
「純粋に無意味な世界への欲望」とやらを
皆様と一緒に考えて、共有していけたらいいなと思います。
(白石さん)
果たして自分はこのままでいいのか?
今までの生活態度も書道に対する姿勢も改める必要があったように思います。
(近藤さん)
鑑賞者との間に共有できるものを3つ用意し、
鑑賞者に対して、書と3つのものとが互いにどのような影響を及ぼすのか、
試案として書きました。
(徳田さん)
ひとりひとりが
生きる、とは何かを問い、
生きる、ことと向き合い、
そしてそれを筆に載せて、紙に落としていく。
答えのない、終わりのない、ゴールのない旅。
それを「道」というのだろうなあと思いました。
その「道」を歩いていこうとする
人たちの書は、胸に迫るものがありました。
帰りの電車で僕の脳裏に浮かんだのは、
子どものころに歌った「若者たち」と
一休和尚の「道」でした。
君のゆく道は果てしなく遠い。
だのになぜ、歯を食いしばり
君はゆくのか、そんなにしてまで。
(若者たち)
この道を行けばどうなるものか
危ぶむなかれ 危ぶめば道はなし
踏み出せばその一足が道となり その一足が道となる
迷わず行けよ 行けばわかるさ
(一休和尚「道」)
「書」という道を
歩み続ける彼らの書に、
心震えました。
生きる、ということ。
それは、問うということ。
生きる、ということ。
それは、向き合うということ。
生きる、ということ。
それは、書をかくということ。
生きる、それは磨き続ける、ということ。
素晴らしい機会を、ありがとうございました。
お邪魔してきました。
新潟大学の書道科卒業生4人の展示会。
卒業して学校現場に入り、書道を教えている人。
自分で書道教室を開き、さまざまな制作物を作っている人。
いろいろな立場の人が
今の自分を表現した書展でした。


書道というのは、
「道」なんだ、って初めて体感した機会となりました。
、
4人のプロフィールを見ると、
四者四様の意気込みが書かれています。
「書道とともに生きていく決意表明」
「現在地の確認」
「書と向き合い続けるということは、すなわち自分と向きあい続けるということです。」
(福田さん)
「純粋に無意味な世界への欲望」とやらを
皆様と一緒に考えて、共有していけたらいいなと思います。
(白石さん)
果たして自分はこのままでいいのか?
今までの生活態度も書道に対する姿勢も改める必要があったように思います。
(近藤さん)
鑑賞者との間に共有できるものを3つ用意し、
鑑賞者に対して、書と3つのものとが互いにどのような影響を及ぼすのか、
試案として書きました。
(徳田さん)
ひとりひとりが
生きる、とは何かを問い、
生きる、ことと向き合い、
そしてそれを筆に載せて、紙に落としていく。
答えのない、終わりのない、ゴールのない旅。
それを「道」というのだろうなあと思いました。
その「道」を歩いていこうとする
人たちの書は、胸に迫るものがありました。
帰りの電車で僕の脳裏に浮かんだのは、
子どものころに歌った「若者たち」と
一休和尚の「道」でした。
君のゆく道は果てしなく遠い。
だのになぜ、歯を食いしばり
君はゆくのか、そんなにしてまで。
(若者たち)
この道を行けばどうなるものか
危ぶむなかれ 危ぶめば道はなし
踏み出せばその一足が道となり その一足が道となる
迷わず行けよ 行けばわかるさ
(一休和尚「道」)
「書」という道を
歩み続ける彼らの書に、
心震えました。
生きる、ということ。
それは、問うということ。
生きる、ということ。
それは、向き合うということ。
生きる、ということ。
それは、書をかくということ。
生きる、それは磨き続ける、ということ。
素晴らしい機会を、ありがとうございました。
2015年03月15日
キャリア教育は科学なのか?
科学的根拠は?
と問われる世の中を生きてきた、
と僕は思っていた。
ところが、キャリア教育はそうではないようだ。
13歳のハローワーク。
村上龍さんが自分の経験に基づき、
「僕にも小説家という天職があった。だからあなたにも天職がある。」
それって事例1人じゃないですか!
ってツッコミたくもなる。
そして、
スポーツ選手の小学校6年生のときの
作文がクローズアップされ、
だから小さいころに夢を持とう、と説かれる。
サッカー日本代表の本田圭佑も
そのひとりだ。
小学校6年生のときに
「Jリーガーになりたい」
「日本代表に選ばれてワールドカップ」
「欧州リーグで活躍する」
みたいな作文を書いた小学生が
日本に何十万人いるのだろうか?
おそらくは相当な数だ。
しかし実際にサッカー日本代表に登録されるのは
23人に過ぎない。
ベンチ入りとなると18人ともっと少なくなる。
それは割合的にどのくらいなのか?
と問いたい。
小さいころに夢・目標を立てたほうがいい。
まあ、立てないよりは立てたほうがいい。
そのくらいではないか?
スタンフォード大のクランボルツ博士の
調べた「計画された偶発性理論」では、
18歳のときに描いた将来の夢と同じ職についていたのは
わずか2%だったという。
それのほうがよっぽど科学的ではないだろうか?
キャリア教育は手段と目的が逆転していると僕は思う。
幸せに生きる
毎日を充実して生きるための
手段だったはずの夢が
いつのまにか夢を持つこと自体が目的化してしまっている。
早急にキャリア教育を科学する必要があるだろう。
夢を強制される世の中は、学校社会はだいぶ窮屈だと僕は思う。
と問われる世の中を生きてきた、
と僕は思っていた。
ところが、キャリア教育はそうではないようだ。
13歳のハローワーク。
村上龍さんが自分の経験に基づき、
「僕にも小説家という天職があった。だからあなたにも天職がある。」
それって事例1人じゃないですか!
ってツッコミたくもなる。
そして、
スポーツ選手の小学校6年生のときの
作文がクローズアップされ、
だから小さいころに夢を持とう、と説かれる。
サッカー日本代表の本田圭佑も
そのひとりだ。
小学校6年生のときに
「Jリーガーになりたい」
「日本代表に選ばれてワールドカップ」
「欧州リーグで活躍する」
みたいな作文を書いた小学生が
日本に何十万人いるのだろうか?
おそらくは相当な数だ。
しかし実際にサッカー日本代表に登録されるのは
23人に過ぎない。
ベンチ入りとなると18人ともっと少なくなる。
それは割合的にどのくらいなのか?
と問いたい。
小さいころに夢・目標を立てたほうがいい。
まあ、立てないよりは立てたほうがいい。
そのくらいではないか?
スタンフォード大のクランボルツ博士の
調べた「計画された偶発性理論」では、
18歳のときに描いた将来の夢と同じ職についていたのは
わずか2%だったという。
それのほうがよっぽど科学的ではないだろうか?
キャリア教育は手段と目的が逆転していると僕は思う。
幸せに生きる
毎日を充実して生きるための
手段だったはずの夢が
いつのまにか夢を持つこと自体が目的化してしまっている。
早急にキャリア教育を科学する必要があるだろう。
夢を強制される世の中は、学校社会はだいぶ窮屈だと僕は思う。
2015年03月14日
支縁(四縁)のあいだ
長谷川先生の話を伺った。
人間は動物である。
哺乳類は、恐竜時代に生まれた。
ほとんどの哺乳類は、
生存戦略として、
「生まれたら、立ち上がり、逃げられる」
というのを選択した。
そのためには、
人間は、本来21か月の妊娠期間が必要だった。
ところが10月10日で生まれてくる。
つまり、未熟な状態で生まれてくるのだ。
のこり11か月を、母親の助けを受けながら育つ。
それは大脳を発達させたため、
頭蓋骨が大きくならざるを得ない。
だから、産道を通るために、
頭蓋骨が柔らかい状態で生むしかないのだ。
この未熟な状態をフォローするための
幸せ装置として「社会」をつくった。
「社会とは」
1 つながる
2 環境を変える
本能は肉体的本能=反射だけではなく
心の反射=共感や好奇がある。
これが1 つながるである。
そして2 環境を変えるとは、
いままで自然に合わせて適応してきたのが、
開発とは、人間の住みやすいように環境を変えること。
を行ってきた。
それを「第二の自然」という。
そして第2の自然のひとつとして、
社会をつくった。
それは、
血縁(家族)、地縁(農耕)、友縁、職縁
の4つの縁によってなりたっていた。
それはそれぞれ網のようになっていて、
人が網から落ちないように、
(つまりこれセフティネットという)
人を支えていた。
ところが、現在、そのそれぞれの縁が小さくなっている。
そこで現れているのが無縁社会だ。
NPOとは、友縁と職縁をつなぐもの。
地縁と友縁をつなぐのが
テーマコミュニティだ。
その間を埋めていくもので
人は社会的動物たろうとする。
時間と空間と人間で
その隙間を埋めようとする行為、
それを社会教育と呼ぶ。
共感することばかり。
素晴らしい時間となりました。
ありがとうございました。
人間は動物である。
哺乳類は、恐竜時代に生まれた。
ほとんどの哺乳類は、
生存戦略として、
「生まれたら、立ち上がり、逃げられる」
というのを選択した。
そのためには、
人間は、本来21か月の妊娠期間が必要だった。
ところが10月10日で生まれてくる。
つまり、未熟な状態で生まれてくるのだ。
のこり11か月を、母親の助けを受けながら育つ。
それは大脳を発達させたため、
頭蓋骨が大きくならざるを得ない。
だから、産道を通るために、
頭蓋骨が柔らかい状態で生むしかないのだ。
この未熟な状態をフォローするための
幸せ装置として「社会」をつくった。
「社会とは」
1 つながる
2 環境を変える
本能は肉体的本能=反射だけではなく
心の反射=共感や好奇がある。
これが1 つながるである。
そして2 環境を変えるとは、
いままで自然に合わせて適応してきたのが、
開発とは、人間の住みやすいように環境を変えること。
を行ってきた。
それを「第二の自然」という。
そして第2の自然のひとつとして、
社会をつくった。
それは、
血縁(家族)、地縁(農耕)、友縁、職縁
の4つの縁によってなりたっていた。
それはそれぞれ網のようになっていて、
人が網から落ちないように、
(つまりこれセフティネットという)
人を支えていた。
ところが、現在、そのそれぞれの縁が小さくなっている。
そこで現れているのが無縁社会だ。
NPOとは、友縁と職縁をつなぐもの。
地縁と友縁をつなぐのが
テーマコミュニティだ。
その間を埋めていくもので
人は社会的動物たろうとする。
時間と空間と人間で
その隙間を埋めようとする行為、
それを社会教育と呼ぶ。
共感することばかり。
素晴らしい時間となりました。
ありがとうございました。
2015年03月13日
「地域ではたらく」を意識すること
金沢大学佐川先生が来訪。
ふつう、こういうのって1時間くらいで
終わるのだけど、2時間オーバー。
本質的な話があふれている素敵な時間となった。
「地域に貢献できる大学」として、
教員がいかに地域に目を向けるか?
正課と課外のあいだの「準正課」と
呼べるような場所に学びの場をつくっていくことで
学生の主体性を引き出せるのではないか?
「悩みを相談する相談室」ではなく、
「こんなことがしたいんだ」というような
ポジティブな相談窓口として機能させることができないか?
地域活動しているサークルなどと連動して、そんな窓口がつくれないか?
山形大学のエリアキャンパスもがみは
職員研修が出発点だったそうだ。
職員が地域のヒアリングをしていて、
「最上地域には大学がない。しかし、地域の課題解決に力を貸してほしい」
というところが出発点で、
いまや全国から注目される取組となっている。
「エリアキャンパスもがみ」
http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/yam/index.html
こうやって、
「地域」をベースに「教育」を作り上げていくことで
「教育」「研究」「社会貢献」がぐるぐる回っていくのではないかと
佐川先生は言う。
素敵なビジョンだなあと思った。
これはおそらく企業でも同じだ。
地域企業の中に入り込み、
「地域企業は本当は何を求めているのか?」を
きっちりヒアリングすることで、
「社会人基礎力」ではない「人材育成目標」が決まるだろう。
たとえば、工学部で学ぶべきは、
「ものづくり」の技術だけではなくて、
「経営」としてどうするか?
どう売っていくか?どんなコンセプトでものをつくっていくか?
を考える機会が必要であるとなるかもしれない。
そうして編み出された絵(人材育成目標)に
企業が賛同してくると、
地域企業50社が応援する取り組みが見えてくる。
そんな企業とも直接やりあえる場を
大学の中につくっていくこと。
それが大学の大きな役割なのだと感じた。
金沢大学では1年次に
「地域概論」という必修科目がある。
これは3学域16学類(金沢大学は学部制から学域・学類制に移行している)
それぞれの担当教員が
「専門科目と地域とのかかわり」という視点から
1年自向けに授業を作りこんでいく科目である。
これは、地域創造学類とかであれば
簡単に授業はつくれるし、学生自身も
学ぶ意欲をもって入ってくるだろう
では、数学・物理を学びたいと思って入ってくる学生に
数学・物理の教員が何を教えるか?
地域と数学・物理はどうかかわるか?
という問いに向き合って授業を作っていかなければならない。
いいなあ。
教員自身がまず問われる授業。素敵です。
ここで行われるのは、
「学生は地域に出てはたらく」というのを
念頭においた授業だ。
誰もが卒業して、「地域ではたらく」を経験する。
それを見据えて、どんな学びをしていったらいいのか?
そういう意味では、すべての学部は
地域とかかわっていると実感することが大切である。
さらにその先に
「キャリアデザイン」や「授業外での学び」
を作っていくことで、学生の伸びしろをつくる。
教育をベースに、
「研究」「社会貢献」をぐるぐる回していく。
「研究」「社会貢献」が出発点でも
3つに横断していくことを行っていく。
これが
地域に必要とされる大学の進む道なのではないか?
という素敵な問いを、佐川先生にはいただいた。
いいタイミングで佐川先生に再会することできた。ありがたい。
コーディネーターとしてやるべきことが山ほどあると
実感した佐川先生の来訪だった。
ありがとうございました。
ふつう、こういうのって1時間くらいで
終わるのだけど、2時間オーバー。
本質的な話があふれている素敵な時間となった。
「地域に貢献できる大学」として、
教員がいかに地域に目を向けるか?
正課と課外のあいだの「準正課」と
呼べるような場所に学びの場をつくっていくことで
学生の主体性を引き出せるのではないか?
「悩みを相談する相談室」ではなく、
「こんなことがしたいんだ」というような
ポジティブな相談窓口として機能させることができないか?
地域活動しているサークルなどと連動して、そんな窓口がつくれないか?
山形大学のエリアキャンパスもがみは
職員研修が出発点だったそうだ。
職員が地域のヒアリングをしていて、
「最上地域には大学がない。しかし、地域の課題解決に力を貸してほしい」
というところが出発点で、
いまや全国から注目される取組となっている。
「エリアキャンパスもがみ」
http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/yam/index.html
こうやって、
「地域」をベースに「教育」を作り上げていくことで
「教育」「研究」「社会貢献」がぐるぐる回っていくのではないかと
佐川先生は言う。
素敵なビジョンだなあと思った。
これはおそらく企業でも同じだ。
地域企業の中に入り込み、
「地域企業は本当は何を求めているのか?」を
きっちりヒアリングすることで、
「社会人基礎力」ではない「人材育成目標」が決まるだろう。
たとえば、工学部で学ぶべきは、
「ものづくり」の技術だけではなくて、
「経営」としてどうするか?
どう売っていくか?どんなコンセプトでものをつくっていくか?
を考える機会が必要であるとなるかもしれない。
そうして編み出された絵(人材育成目標)に
企業が賛同してくると、
地域企業50社が応援する取り組みが見えてくる。
そんな企業とも直接やりあえる場を
大学の中につくっていくこと。
それが大学の大きな役割なのだと感じた。
金沢大学では1年次に
「地域概論」という必修科目がある。
これは3学域16学類(金沢大学は学部制から学域・学類制に移行している)
それぞれの担当教員が
「専門科目と地域とのかかわり」という視点から
1年自向けに授業を作りこんでいく科目である。
これは、地域創造学類とかであれば
簡単に授業はつくれるし、学生自身も
学ぶ意欲をもって入ってくるだろう
では、数学・物理を学びたいと思って入ってくる学生に
数学・物理の教員が何を教えるか?
地域と数学・物理はどうかかわるか?
という問いに向き合って授業を作っていかなければならない。
いいなあ。
教員自身がまず問われる授業。素敵です。
ここで行われるのは、
「学生は地域に出てはたらく」というのを
念頭においた授業だ。
誰もが卒業して、「地域ではたらく」を経験する。
それを見据えて、どんな学びをしていったらいいのか?
そういう意味では、すべての学部は
地域とかかわっていると実感することが大切である。
さらにその先に
「キャリアデザイン」や「授業外での学び」
を作っていくことで、学生の伸びしろをつくる。
教育をベースに、
「研究」「社会貢献」をぐるぐる回していく。
「研究」「社会貢献」が出発点でも
3つに横断していくことを行っていく。
これが
地域に必要とされる大学の進む道なのではないか?
という素敵な問いを、佐川先生にはいただいた。
いいタイミングで佐川先生に再会することできた。ありがたい。
コーディネーターとしてやるべきことが山ほどあると
実感した佐川先生の来訪だった。
ありがとうございました。
2015年03月12日
アクティブシニアが欲しいモノ
笠間市の
地域おこし協力隊の報告会に
行ってきました。
3人の隊員とも、すごいヒアリングをしっかりしていて、
やはり、地域おこし協力隊は、
受け入れ担当者が仮説を持って取り組めば、
何かいい事業のきっかけとしては、
すごくいいなあと思った。
ひとつ気になったのは、
お客の不在。
誰のために
空き店舗を開いて店にするのか?
「地域活性化」という旗では、
残念ながら賛同者は増えないと思う。
お客は誰か?
という問い。
一般的には、これからのビジネスマーケットは
「アクティブシニア」層に向けて
打っていくのがいいと言われている。
比較的人口が多く、しかもお金を持っているからだ。
JRの大人の休日倶楽部に代表されるように、
アクティブシニアを取り込んでいく(言い方が悪いが)ことが
必要だ。
では、国全体のような大きなマーケットではなく、
地域のような小さいマーケットではどうか?
いや、そもそも、
アクティブシニアが欲しいモノなどあるのだろうか?
僕の仮説だけれど、
彼らがほしいのは「コミュニケーション」と「出番」だ
若い人とコミュニケーションしたい、あるいは教えたい、
あるいは若い人を応援したい、力になりたい。
この欲求をどのように満たしていくか?
がカギになっていく。
だから、逆説的だが、
お客を若い人に設定すべきだと僕は思う。
そして、アクティブシニア層を
「第二の顧客」として、機能させるのだ。
つまり、「あなたも若い人たちの役に立つことができる。」
というのを商品にして、販売していく必要がある。
次に必要となってくるのは
若い人でも、どんな若い人か?
ということだ。
まきどき村では、
「ふるさとを持たない若い人」を
ツルハシブックスは
「将来に不安を抱える中学生高校生大学生」を
そしてこれから始まる米屋さんは
「ていねいに生きたい20代女子」を
それぞれお客に設定している。
あとはシニア層とのコミュニケーションを図っていく
デザインをどのように作っていくか?
40代はそのつなぎ役になれるのかもしれない。
地域おこし協力隊の報告会に
行ってきました。
3人の隊員とも、すごいヒアリングをしっかりしていて、
やはり、地域おこし協力隊は、
受け入れ担当者が仮説を持って取り組めば、
何かいい事業のきっかけとしては、
すごくいいなあと思った。
ひとつ気になったのは、
お客の不在。
誰のために
空き店舗を開いて店にするのか?
「地域活性化」という旗では、
残念ながら賛同者は増えないと思う。
お客は誰か?
という問い。
一般的には、これからのビジネスマーケットは
「アクティブシニア」層に向けて
打っていくのがいいと言われている。
比較的人口が多く、しかもお金を持っているからだ。
JRの大人の休日倶楽部に代表されるように、
アクティブシニアを取り込んでいく(言い方が悪いが)ことが
必要だ。
では、国全体のような大きなマーケットではなく、
地域のような小さいマーケットではどうか?
いや、そもそも、
アクティブシニアが欲しいモノなどあるのだろうか?
僕の仮説だけれど、
彼らがほしいのは「コミュニケーション」と「出番」だ
若い人とコミュニケーションしたい、あるいは教えたい、
あるいは若い人を応援したい、力になりたい。
この欲求をどのように満たしていくか?
がカギになっていく。
だから、逆説的だが、
お客を若い人に設定すべきだと僕は思う。
そして、アクティブシニア層を
「第二の顧客」として、機能させるのだ。
つまり、「あなたも若い人たちの役に立つことができる。」
というのを商品にして、販売していく必要がある。
次に必要となってくるのは
若い人でも、どんな若い人か?
ということだ。
まきどき村では、
「ふるさとを持たない若い人」を
ツルハシブックスは
「将来に不安を抱える中学生高校生大学生」を
そしてこれから始まる米屋さんは
「ていねいに生きたい20代女子」を
それぞれお客に設定している。
あとはシニア層とのコミュニケーションを図っていく
デザインをどのように作っていくか?
40代はそのつなぎ役になれるのかもしれない。
2015年03月11日
やればやるほど、開花のチャンスに出会える
「やってみる」を科学する。
それが僕の研究テーマになってくるだろうと思う。
今、とあるメルマガの原稿を構想中。
締切が近づいている。
3部作を書いてます。
1 子どもが夢を持たなくてもいい3つの理由
2 なぜ、学校は「夢至上主義」一色なのか?
3 「やってみる」を取り戻す~劇団員として生きる。
時代が変わってしまった。
「努力すること」で報われるということは
ほとんどなくなった。
急速に進む時代の流れの中で
企業が継続することは難しくなった。
にも関わらず。
夢を持て。
目標に向かって努力しろ。
というのはなぜなんだろう?
その成功モデルとはなんだろうか?
「サッカー日本代表になりたい」と
小学生のときに書いた夢を
実現する確率はどのくらいだろうか?
しかもその確率は努力によって劇的に向上するのだろうか?
もちろん、
実現した人たちは、
血のにじむような努力をしたことは間違いない。
イチローだって小学校高学年から
友達と遊ばずに1年のうち360日は
厳しい練習をしていたと卒業文集に書いている。
だから「実現した人は、夢を描き、その達成に向け努力をしている」
ことは確かである。
しかし。
「努力をしたから夢が叶う」というのは、そうではないだろう。
人には「向き不向き」がある。
きっとこの前提を共有したほうがいい。
そしてそのさらに前提として、
「やればやるほど、開花のチャンスに出会える」
ということが大切だ。
努力をすれば、叶う、
のではなく、
やればやるほど、開花のチャンスに出会えるのだ。
もちろんそれは「開花のチャンス」に過ぎないから、
開花しないことも多数ある。
ひとつのことに打ち込んで、集中するのも
「開花のチャンスをつかみに行っているプロセス」
に過ぎない。
開花しないこともある。
それは「向き不向き」があるからだ。
学校の夢至上主義と正解主義とのコンボは、
この前提を覆してしまう。
努力をすれば夢は叶う
=夢が叶わなかったのは努力・能力が足りないから
この思想が
いわゆる「大二病」と言われる、
「おれ、まだ本気だしてない」症候群を生んでいるのだろうと思う。
「能力がない」とラベルを貼られるのを恐れ、
「まだ本気だしてない」アピールをする。
幼いころは「やればできるかもしれない」という成長思考だったはずが
小学中学高校を経て「自分の才能には限界がある」という才能思考に上書きされてしまったのだ。
こうしてどんどん「やってみる」を失っていく。
「やってみる」がなければ、失敗はないが、
その代わり、自分で考える機会もない。
これが工業による経済成長期で、
「効率化」だけが価値を生む方法論で
企業が成長した時代は、うまく機能した。
誰か位が上の人やコンサルタントが
現場から上がってきた意見などを参考に
「こうしたほうが効率的だ」
と考え、判断をし、社員はそれに従っていればいいという時代があった。
しかしいま。
工業製品だってアイデアの時代だ。
「イノベーション」を起こさなければならない。
それには「やってみる」が必要だ。
「やってみる」から何かが起こり、
何かを考え、それが失敗に終わったとしても、
アイデアの種になる。
「アイデアとは既存の要素の組み合わせに過ぎない」
のだから、自分の中にその要素を蓄えておく必要がある。
個人ベースでいけば、
「やってみる」ことで、開花のチャンスに出会えるということ。
「やればできる」わけではないけど、
「やればできるかもしれない」のだ。
だから、「やってみる」こと。
僕のミッションは、「やってみる」を増やすこと。
上書きされた才能思考を取り払い、
やってみる状態にすること。
それをきっちり科学していくことをしていかないといけない。
そういう意味でツルハシブックスという第3の場所は、
ぶらっと来た小学生中学生が「屋台、やってみる?」
と言える、素敵な空間なのかもしれないと思った。
これもきっちり言語化していかないといけないなと。
さあ、こんな組み立てでメルマガ書いてみます。
それが僕の研究テーマになってくるだろうと思う。
今、とあるメルマガの原稿を構想中。
締切が近づいている。
3部作を書いてます。
1 子どもが夢を持たなくてもいい3つの理由
2 なぜ、学校は「夢至上主義」一色なのか?
3 「やってみる」を取り戻す~劇団員として生きる。
時代が変わってしまった。
「努力すること」で報われるということは
ほとんどなくなった。
急速に進む時代の流れの中で
企業が継続することは難しくなった。
にも関わらず。
夢を持て。
目標に向かって努力しろ。
というのはなぜなんだろう?
その成功モデルとはなんだろうか?
「サッカー日本代表になりたい」と
小学生のときに書いた夢を
実現する確率はどのくらいだろうか?
しかもその確率は努力によって劇的に向上するのだろうか?
もちろん、
実現した人たちは、
血のにじむような努力をしたことは間違いない。
イチローだって小学校高学年から
友達と遊ばずに1年のうち360日は
厳しい練習をしていたと卒業文集に書いている。
だから「実現した人は、夢を描き、その達成に向け努力をしている」
ことは確かである。
しかし。
「努力をしたから夢が叶う」というのは、そうではないだろう。
人には「向き不向き」がある。
きっとこの前提を共有したほうがいい。
そしてそのさらに前提として、
「やればやるほど、開花のチャンスに出会える」
ということが大切だ。
努力をすれば、叶う、
のではなく、
やればやるほど、開花のチャンスに出会えるのだ。
もちろんそれは「開花のチャンス」に過ぎないから、
開花しないことも多数ある。
ひとつのことに打ち込んで、集中するのも
「開花のチャンスをつかみに行っているプロセス」
に過ぎない。
開花しないこともある。
それは「向き不向き」があるからだ。
学校の夢至上主義と正解主義とのコンボは、
この前提を覆してしまう。
努力をすれば夢は叶う
=夢が叶わなかったのは努力・能力が足りないから
この思想が
いわゆる「大二病」と言われる、
「おれ、まだ本気だしてない」症候群を生んでいるのだろうと思う。
「能力がない」とラベルを貼られるのを恐れ、
「まだ本気だしてない」アピールをする。
幼いころは「やればできるかもしれない」という成長思考だったはずが
小学中学高校を経て「自分の才能には限界がある」という才能思考に上書きされてしまったのだ。
こうしてどんどん「やってみる」を失っていく。
「やってみる」がなければ、失敗はないが、
その代わり、自分で考える機会もない。
これが工業による経済成長期で、
「効率化」だけが価値を生む方法論で
企業が成長した時代は、うまく機能した。
誰か位が上の人やコンサルタントが
現場から上がってきた意見などを参考に
「こうしたほうが効率的だ」
と考え、判断をし、社員はそれに従っていればいいという時代があった。
しかしいま。
工業製品だってアイデアの時代だ。
「イノベーション」を起こさなければならない。
それには「やってみる」が必要だ。
「やってみる」から何かが起こり、
何かを考え、それが失敗に終わったとしても、
アイデアの種になる。
「アイデアとは既存の要素の組み合わせに過ぎない」
のだから、自分の中にその要素を蓄えておく必要がある。
個人ベースでいけば、
「やってみる」ことで、開花のチャンスに出会えるということ。
「やればできる」わけではないけど、
「やればできるかもしれない」のだ。
だから、「やってみる」こと。
僕のミッションは、「やってみる」を増やすこと。
上書きされた才能思考を取り払い、
やってみる状態にすること。
それをきっちり科学していくことをしていかないといけない。
そういう意味でツルハシブックスという第3の場所は、
ぶらっと来た小学生中学生が「屋台、やってみる?」
と言える、素敵な空間なのかもしれないと思った。
これもきっちり言語化していかないといけないなと。
さあ、こんな組み立てでメルマガ書いてみます。





