2022年05月31日
2つのソウゾウリョクと本を読むこと

「クリエイティブ・ラーニング~創造社会の学びと教育」(井庭崇 編著 慶応義塾大学出版会)
完全に自習モード。
今回も大量のメモを。
東京での田口幹人さんとの再会でNPO法人読書の時間設立の話を聞けたのもよかった。
僕はなぜ、本屋なのか?そういうのって後付けについてくるんだよね。
ということで、本書より
今日はヴィゴツキーの「想像力」と「創造性」(P96)より
~~~ここからメモ
ヴィゴツキーは、人間は想像する能力をもっており、それは創造性の重要な要因であるとして、想像力についても研究した。人間は、実際には見たことがない過去や未来のこと、現実とは異なる世界の情景を想像することができる。「脳は私たちの過去経験を保持し再生する器官であるばかりではなく、その過去経験の要素から新しい状況や新しい行動を複合化し、創造的につくりかえ、新たに生み出す器官でもある」のである。この力が人間を、未来をつくり出し、現状から変えていく存在にしている。
想像や空想(ファンタジー)というと、私たちは日頃、非現実的で単なる遊びや趣味の世界であり、実際には重要ではないものと捉えがちだが、ヴィゴツキーはそれこそが、芸術的な創造や科学的な創造、技術的な創造を可能にすると、その重要性を強調した。
「私たちの回りにあるもの、人間の手によって作られたものはすべて例外なく、つまり自然の世界とはちがう文化の世界すべては、人間の想像力の産物であり、人間の想像力による創造の産物なのです。」
そして、そのような力は一部の天才のみにあるのではなく、すべての人に備わっているのであり、「名もない発明者たちの協同的な創造」によって世界はつくられてきたという。
心理学的に見るならば、想像は無から生み出されるのではなく、いつも現実から得た素材によって成り立っている。過去の経験が空想を構成する素材を提供するのである。その人のこれまでの経験が豊かであるほど、想像で用いられる素材も多くなることを意味している。このとき、過去のある経験がまるごとそのまま再生されるのではなく、分解されて保持されるものであり、忘れられる。そして、それらは、想像を生み出すときに、変形や新しい結びつきを伴って、新しい印象や意味をもって、構成される。
(中略)
ヴィゴツキーは、想像と経験は相互に関わりあっているという。一方で、いま述べてきたように、経験に基づいて想像がつくられ、他方で、想像が経験に影響するということである。
想像が経験に影響するということは、まず、想像が現実的な感情を生み出すことに関係する。想像されたことがたとえ架空のことであっても、そこから引き起こされる感情は現実のものである。恐ろしい情景を想像して身震いするとか、楽しい場面を想像して気持ちがウキウキすることは、日常的にもよくあるだろう。また作家が生み出された空想が表現された作品によって、感情が大きく揺さぶられることもある。物語は空想上の虚構であったとしても、読者は本当に興奮したり不安を感じたりする。このように想像は、本物の感情を伴って体験されるのである。
(中略)
ヴィゴツキーは、「子どものあらゆる教育において想像力を形成することは、個々の機能の訓練とか発達促進という部分的な意味だけでなく、人間の行動全般に反映する全体的な意義を持っています」として、想像力と創造性の形成を促す教育のあり方についても論じている。
結論にあたって、学齢期に創造性を培うことの重要性を指摘しなければなりません。人間は未来のことはみな創造的な想像の助けをかりて理解します。すなわち未来を見定め、その未来に依拠し、そして未来から発する行動は、想像の最も重要な機能です。ですから、教育者の指導の基本的な教育姿勢が、児童生徒を未来に向かって準備する路線で彼らの行動を方向づけることであるかぎり、この想像力を発達させ、練習することは、その目的の実現過程にとって、基本的な力の一つなのです。未来を志向する創造的な人格は、具象化される創造的な想像の準備教育で今つくられるのです。
この問題は次の二つの部分から成り立っています。一方からすれば、創造的な想像を豊かにしなければならないし、また他方では、創造によってつくりだされるイメージを具体化するには特別な技芸が必要なのです。その両者の面が十分に発達しているところでのみ、子どもの創造力は正しい発達をすることができ、子どもから当然に期待されているものを与えることができるのです。
この後、本書では、伝統的な教育(学校)は、創造性な可能性が芸術的創造に限られているかのように捉えているがそうではなく、技術の分野でも発揮できるとし、教育者も実生活の創造者となっていく必要があると説きます。「教育を創造的にする」には教育者自らが生活を創造的なものにしていくのだと。
~~~
消費社会⇒情報社会⇒創造社会への移行。
「創造性」が求められる時代。
ヴィゴツキーによれば、
「創造」のためには「想像力」が不可欠であり、想像と経験は相互に関わりあっている。
おそらくその「想像」の一歩目が、「感情」の振り返りなのではないかと。
「体験学習」の意味もそこにあるのではないか。
校内ではなく、校外の現場に行って学ぶ。その道のプロに話を聞く。
そのとき、心が動く。それをキャッチし、表現する。
他者の表現を見て、他者を認識するとともに自分を認識する。
体験にベースにした「問い」を考え、仮説と立てる。
感じたことの違いを活かし、創造する。
そのときに「想像力」の出番だ。
かつての経験から未来を展望するんだ。
その「経験」の中には読書経験も含まれるだろう。
本書の中で引用されているがミヒャエル・エンデや村上春樹は、
自分の経験が断片的に無意識の中に埋もれていて、
とつぜんアイデアとして浮かび上がる、あるいは染み出してくる。
だから、経験が必要で、そのひとつの方法が「読書」なんだなと思った。
「創造力」のために「想像力」が必要で、「想像力」のために経験(体験)と読書が有効なんだと。
しかしそれは、目的最適化することはできず、無意識の中のストックを増やすだけだと。
しかしそのストックこそが「想像力」と「創造力」の礎となるのだ、と。
2つのソウゾウリョク、そして本を読むこと。
教育と本屋、やっとつながってきました。
2022年05月29日
「発達の最近接領域」をともにつくる

「クリエイティブ・ラーニング~創造社会の学びと教育」(井庭崇 編著 慶応義塾大学出版会)
まだ序章なのですけど、内容が濃すぎて。
ひとまず、ヴィゴツキーの「発達の最近接領域」についてメモ
~~~
ヴィゴツキーは、これまで、知能の評価では、すでに成熟した能力のみが評価されてきたが、いま成熟しつつある能力にも目を向けるべきだと主張した。なぜなら、そのいま成熟しつつある領域こそが、教授‐学習が可能で、効果を発揮する領域だからである。教育において重要なのは、その人がすでに知っている‐できることだけでなく、何を学ぶことができるのかを知ることだというわけである。
ヴィゴツキーは、これまで知能や発達の段階としては、現在の発達水準、つまり、すでに発達のサイクルが完了し、成熟した能力のみがその評価の対象となってきたと指摘する。このことは試験の場面に端的に表れている。試験とは「もっぱら一人で行う問題解決に基づくもの」だと考えられてきたのである。
これに対してヴィゴツキーは、この現在の発達水準だけでなく、いま成熟しつつあるが、まだ十分に発達していないという水準も見るべきだという。
ヴィゴツキーは、自分一人で自力で解ける水準(現在の発達水準)と、他者の助けを借りて解ける水準(いま成熟しつつある水準)の間の領域を「発達の最近接領域」と名付けた。現在の発達水準に「最も近接」する「発達」の「領域」という意味である。
「発達の最近接領域は、まだ成熟してはいないが、成熟中の過程にある機能、今はまだ萌芽状態にあるけれども明日には成熟するような機能を規定します。つまり発達の果実ではなくて、発達のつぼみ、発達の花とよびうるような機能、やっと成熟しつつある機能です。」
「模倣は、それが子どもにおおよそ可能な領域にあるときにのみ可能なのです。それゆえ、子どもがひそかに助言を得てなしうることは、子どもの発達状態の十分な指標となります。」
~~~
ここで、中断。ロシア語の「obuchenie」について解説。ヴィゴツキーが使っていた「obuchenie」という言葉は、「教授」という意味と「学習」という意味を併せ持っており、その相互作用を表す言葉である。そのどちらか一方の訳語で訳してしまうと、本来持っている意味・ニュアンスが損なわれてしまう。実は、かつては日本でも欧米でもこの言葉は「教授」か「学習」のどちらか一方で翻訳されていたため、ヴィゴツキーの考えに対する混乱・曲解が生まれたと言われている。
いや、言葉は大切。「教育心理学者たちの世紀」でジョナサン・タッジとシュリル・スクリムシャーは、次のように指摘している。
「obuchenie」の用語のもっとも適切な訳は「指導」に含まれるよりも双方向性の流れを意味している。その訳によって私たちは、「教授/学習」が、子どもたちが学校に行くずっと前に生じるというヴィゴツキーの見方をよく理解できるのだ。優れた翻訳は読者に、発達の最近接領域が教師と子どもの間、あるいは二人以上の仲間の間の相互作用の過程で作り出されるとき、あらゆる参加者は、創造の過程と生じてくる次の発達の過程との両方に参加していることも理解させる
これ、すごいですよね。「発達の最近接領域」は相互作用の中で作り出せる。僕が「創造のエッジ」って言ってたやつはこれなんじゃないかな。
http://hero.niiblo.jp/e491178.html
存在は創造のエッジにある(20.11.10)
学校にとって重要なのは、子どもがすでに何を学んだかではなくて、むしろ何を学ぶことができるかであり、発達の最近接領域こそ、子どもがまだできないことを、指導や援助を受けたり、指示にしたがったり、協同のなかで習得するという意味で、子どもの可能性とはどのようなものであるかを近似的に明らかにするものです。
教授‐学習は、発達の最近接領域でのみ可能であり、効果をもつ。すでに発達している領域で教授‐学習をしても意味がなく、また、発達の最近接領域を超えて、未成熟な領域で行うことは難しく、効果を持たない。遅すぎる教授‐学習も、早すぎる教授‐学習も、効果がないのである。学習の最盛期には下限と上限が存在する。その意味において、ヴィゴツキーは、教授‐学習は発達の最近接領域に対して行われるべきであり、それゆえ、いわば教授‐学習に先回りするもののみが効果を持つと唱えた。
そして、ヴィゴツキーは一方的な教授に対しての厳しい批判をしている。
「生徒は自分自身で学ぶのです。教師によってなされる講義は多くのことを教え込むことができますが、それは自分で何もせず、何も確かめることをしないで、他人に頼る能力や願望を育てるだけです。今日の教育では、知識の一定量を教えることはそれほど重要ではなく、その知識を獲得し、利用する能力を育てることの方が重要です。それは(生活ほかのすべてと同様)活動の過程でのみ獲得されるものです。」
教師は、生徒に教えるのではなく、生徒が自分で学ぶことができるように環境を組織化する役割を担うのである。ヴィゴツキーに言わせれば、教師は、社会環境の組織者であり、生徒と環境の相互作用の調整者であるべきなのである。
「園芸家が、植物の成長に影響を与えようとして、手でそれを土から直接引っ張り出すとしたら、狂人と言われるように、教育者が子どもに直接影響を及ぼそうとするのは、教育の本質に反することになるでしょう。しかし、園芸家は、温度を高め、湿度を調整し、隣の植物の配置を変え、土や肥料を選んだり混ぜ合わせることによって、すなわち、またしても間接的に、環境を適切に変化させることによって、花の発芽に影響を及ぼすのです。それと同じように、教育者も環境を変えることで子どもを教育するのです。」
教育においては、生徒による刺激の知覚、それらの加工、応答的行為という三つの要素がすべて揃う過程がなければならないと、ヴィゴツキーは言う。
~~~
今日はこの辺で。次回は「想像力」と「創造力」について書きます。
「ともにつくる」場っていうのは、ヴィゴツキーの言うところの「発達の最近接領域」なのではないか、と。
ヴィゴツキーを解説したこの部分が、今日のハイライトかな。
発達の最近接領域が教師と子どもの間、あるいは二人以上の仲間の間の相互作用の過程で作り出されるとき、あらゆる参加者は、創造の過程と生じてくる次の発達の過程との両方に参加している
http://hero.niiblo.jp/e491411.html
「過程」としての学びと「手段」としての学び(21.2.9)
「発達の最近接領域」が相互作用で作り出されるとき、あらゆる参加者は創造の過程に参加している。
これです。場のチカラって。
「地域学」でパートナーズと生徒が生み出す学びの「場」って、こういうやつじゃないかなと。
2022年05月24日
「つくる」こと、発見と変容
昨年から取り組んでいる探究学習では、
・個の力、チームの力⇒場のチカラ
・「達成と成長」⇒「発見と変容」モデル
・心理的安全性を高める探究ネーム
を大切にしてきた。
そして語ってきたのは、「まなぶ」から「つくる」へのシフトだった。
「つくる」を前にすると人と人はフラットになるし、(学校社会的)能力差が無効化される。
そんなタイミングで「ジェネレーター」を読み、そしてその1つ前の
「クリエイティブ・ラーニング」にたどり着いた

「クリエイティブ・ラーニング~創造社会の学びと教育」(井庭崇 編著 慶応義塾大学出版会)
今日、読み始めたばかりですが、プロローグでもうすでに、すごいことになっているのでアウトプットせずにはいられません。
~~~以下メモ
「6Cs(シックスシーズ)」 P5
1 コラボレーション collaboration
2 コミュニケーション communication
3 コンテンツ content
4 クリティカル・シンキング critical thinking
5 クリエイティブ・イノベーション creative innovation
6 コンフィデンス confidence
コラボレーションとコミュニケーションがコンテンツ、クリティカルシンキングより先に来ている点。
⇒人間は生まれながらにして社会的存在でありその中で交流し、協働し、学んでいく。
ここ100年とこれからの社会の変化と豊かさ指標
1 Consumption(コンサンプション:消費)を中心とした消費社会⇒どれだけ商品やサービスを享受しているか
2 Communication(コミュニケーション:)を中心とした情報社会⇒どれだけよい関係やコミュニケーションをしているか
3 Creation(クリエイション:創造)を中心とした創造社会⇒どれだけ生み出しているか、どれだけ創造的でいるか
「つくる」ことが前提の社会になっていく。
30年後の人が今の時代を振り返るときに、「信じられないことに、自分が使う道具や身につけているものを、自分ではいっさいつくらず、すべてを買っていた時代」として、驚きをもって語られることになるだろう。
創造社会では、生活のあり方が変わり、ビジネスのあり方が変わり、教育のあり方が変わるのである。ありとあらゆるものが「つくる」対象になることは、すなわち、自分たちの未来を自分たちでつくるということを意味している。
創造的であることを一部の職種や天才に任せるのではなく、誰もが創造的に「つくる」ことに参加する社会。これが、本書が見据えている未来である。
~~~
いいなあ。そうそう。そうなんですよ。
「まなぶ」から「つくる」へのシフトが起こっているんです。
そして、それを裏付けるような一流たちからのコメントが熱い。
~~~
村上春樹は、自分が書いている小説が「どんな物語になるかは僕自身にもわかりません」と断言し、次のように語る。
主人公が体験する冒険は、同時に、作家としての僕自身が体験する冒険でもあります。書いているときには、主要な人物が感じていることを僕自身も感じますし、同じ試練をくぐりぬけるんです。言い換えるなら、本を書き終えたあとの僕は、本を書きはじめたときの僕とは、別人になっているんです。
ミヒャエル・エンデもこのように言う。
わたしはよく言うのですが、わたしが書く行為は冒険のようなものだって。その冒険がわたしをどこかへ連れていき、終わりがどうなるのか、わたし自身さえ知らない冒険です。だから、どの本を書いた後も私自身がちがう人間になりました。私の人生は実際、わたしが書いた本を節として区切ることができる。本を執筆することがわたしを変えるからです。
さらに「冒険」について、エンデは語る。
本当の冒険は、そんな力が自分のなかにあるとはそれまでまるで知らなかった、そのような力を投入しなければならない状況に人を運んでゆくものです。そうして、そんなふうにして自分を知ることになる。真の冒険者は実はそれを求めているのだと思います。そして、わたしは、いわば書くことを通じてそれを行っているのです。書きながら、わたしはわたし自身について何かを体験する、そのなかには、それがわたしのなかにあることも、わたしがそれをできることも、それまでまったく知らなかったことです。考えるだけでは、それはわからないことなのです。
さらに、KJ法の川喜田二郎氏の言葉「主体」と「客体」について
創造的行為は、まずその対象となるもの、つまり「客体」を創造するが、同時に、その創造を行うことによって自らをも脱皮変容させる。つまり「主体」も創造されるのであって、一方的に対象を作り出すだけというのは、本当の創造的行為ではないのである。そして、創造的であればあるほど、その主体である人間の脱皮変容には目を瞠るものがある。
参考:最初にあるのは、「我」ではなく「混沌」である(19.12.10)
http://hero.niiblo.jp/e490086.html
これらの人たちが示していることは、小説を書くこと(つくること)は、新しい発見が生じるプロセスであり、何かを「つくる」ことはつくり始める時点ですでに自分のなかにある何かを外に出すということではなく、つくることで新たな発見が生じ、学びが深まり、成長につながるという「構造的」なものである。
「つくる」という冒険に出る。
探究的な学びとはきっと、こういうことなのだろうな、と。
この後、本書はそのかかわり方として「ジェネレーター」を提唱している。
知識を教えたりスキルを身につける機会をつくるティーチャーやインストラクターではなく話し合いの流れを促すファシリテーターでもなく、一緒につくることに参加するジェネレーターという関わりが必要になるのだと。
~~~
なるほど。「つくる」という冒険を生成するジェネレーター的なかかわりが重要なのだ、と。
さらに、もうひとつ。「自己表現」についても言及されている。
村上春樹が次のように述べる
~~~
今、世界の人がどうしてこんなに苦しむかというと、自己表現をしなくてはいけないという脅迫観念があるからですよ。だからみんな苦しむんです。・・・日本というか世界の近代文明というのは自己表現が人間存在にとって不可欠であることを押しつけているわけです。教育だってそういうものを前提条件として成り立っていますよね。まず自らを知りなさい。自分のアイデンティティーを確立しなさい。他者との差異を認識しなさい。そして自分の考えていることを少しだも正確に、体系的に、客観的に表現しなさいと。これは本当に呪いだと思う。だって自分がここにいる存在意味なんて、ほとんどどこにもないわけだから。タマネギの皮むきと同じことです。一貫した自己なんてどこにもないんです。
~~~
「創造」「つくる」とは、自分の主張や自分らしさを表現するという「自己表現」をしようと呼び掛けているのではないと井庭さんは言う。
たんに自分を表現しているのでは、そこに学びや成長は見込めない。そうではなく、自分がつくっているもの(つくられつつあるもの)が「あるべきかたち」になるようにつくることによって、自分を超えたものに出会い、気づきがあり、成長が可能となる。村上春樹はつくるものの論理に身を委ね、それについていくことで自己表現の罠から抜け出せると言う。
~~~
物語という文脈を取れば、自己表現しなくてもいいんですよ。物語がかわって表現するから。僕が小説を書く意味は、それなんです。僕も、自分を表現しようと思っていない。自分の考えていること、たとえば自我の在り方のようなものを表現しようとは思っていなくて、自分の自我がもしあれば、それを物語に沈めるんですよ。僕の自我がそこに沈んだときに物語がどういう言葉を発するかというのが大事なんです。物語というのは常に動いていくものであって、その動くという特性の中にもっとも大きな意味があるんです。だからスタティックな枠みたいなのをどんどん取り払っていくことができます。それによって僕らは「自己表現」の罠を脱することができる
~~~
これさ、「物語」とか「小説を書く」を「プロジェクト」に換えても同じだろうな。同じというか、プロジェクトという場に溶け出してこそ、いいアウトプットが出るのだと思う。そしてそれこそが「自己表現の罠」、つまりアイデンティティの呪縛を解くカギになっていくのだと。
いやあ、今日、僕確信しました。これでいいんだ、って。
プロローグは次のように締めくくられる。
このように、本格的な創造とは、つくっているものの「あるべきかたち」になるようにすることであり、その過程で、つくる対象やその世界を内側から体験することを伴う。それは自我の表出や作為というものを手放し、対象と一体になるという意味で「無我の創造」と呼びうるような創造である。そのような意味での創造の経験の機会を、教育の場では提供していくことがこれからますます重要になってくる。
~~~
・「つくる」という冒険に出る。
・その物語(プロジェクト)を走らせる。
・その物語(プロジェクト)に自我を沈める。
この繰り返しこそが「自己表現せよ」という呪いを解くカギなのだろう。
「つくりこと」から始め、発見と変容を繰り返す「場」を持つプロジェクトを設計すること。たぶん、そういうことだ。
・個の力、チームの力⇒場のチカラ
・「達成と成長」⇒「発見と変容」モデル
・心理的安全性を高める探究ネーム
を大切にしてきた。
そして語ってきたのは、「まなぶ」から「つくる」へのシフトだった。
「つくる」を前にすると人と人はフラットになるし、(学校社会的)能力差が無効化される。
そんなタイミングで「ジェネレーター」を読み、そしてその1つ前の
「クリエイティブ・ラーニング」にたどり着いた

「クリエイティブ・ラーニング~創造社会の学びと教育」(井庭崇 編著 慶応義塾大学出版会)
今日、読み始めたばかりですが、プロローグでもうすでに、すごいことになっているのでアウトプットせずにはいられません。
~~~以下メモ
「6Cs(シックスシーズ)」 P5
1 コラボレーション collaboration
2 コミュニケーション communication
3 コンテンツ content
4 クリティカル・シンキング critical thinking
5 クリエイティブ・イノベーション creative innovation
6 コンフィデンス confidence
コラボレーションとコミュニケーションがコンテンツ、クリティカルシンキングより先に来ている点。
⇒人間は生まれながらにして社会的存在でありその中で交流し、協働し、学んでいく。
ここ100年とこれからの社会の変化と豊かさ指標
1 Consumption(コンサンプション:消費)を中心とした消費社会⇒どれだけ商品やサービスを享受しているか
2 Communication(コミュニケーション:)を中心とした情報社会⇒どれだけよい関係やコミュニケーションをしているか
3 Creation(クリエイション:創造)を中心とした創造社会⇒どれだけ生み出しているか、どれだけ創造的でいるか
「つくる」ことが前提の社会になっていく。
30年後の人が今の時代を振り返るときに、「信じられないことに、自分が使う道具や身につけているものを、自分ではいっさいつくらず、すべてを買っていた時代」として、驚きをもって語られることになるだろう。
創造社会では、生活のあり方が変わり、ビジネスのあり方が変わり、教育のあり方が変わるのである。ありとあらゆるものが「つくる」対象になることは、すなわち、自分たちの未来を自分たちでつくるということを意味している。
創造的であることを一部の職種や天才に任せるのではなく、誰もが創造的に「つくる」ことに参加する社会。これが、本書が見据えている未来である。
~~~
いいなあ。そうそう。そうなんですよ。
「まなぶ」から「つくる」へのシフトが起こっているんです。
そして、それを裏付けるような一流たちからのコメントが熱い。
~~~
村上春樹は、自分が書いている小説が「どんな物語になるかは僕自身にもわかりません」と断言し、次のように語る。
主人公が体験する冒険は、同時に、作家としての僕自身が体験する冒険でもあります。書いているときには、主要な人物が感じていることを僕自身も感じますし、同じ試練をくぐりぬけるんです。言い換えるなら、本を書き終えたあとの僕は、本を書きはじめたときの僕とは、別人になっているんです。
ミヒャエル・エンデもこのように言う。
わたしはよく言うのですが、わたしが書く行為は冒険のようなものだって。その冒険がわたしをどこかへ連れていき、終わりがどうなるのか、わたし自身さえ知らない冒険です。だから、どの本を書いた後も私自身がちがう人間になりました。私の人生は実際、わたしが書いた本を節として区切ることができる。本を執筆することがわたしを変えるからです。
さらに「冒険」について、エンデは語る。
本当の冒険は、そんな力が自分のなかにあるとはそれまでまるで知らなかった、そのような力を投入しなければならない状況に人を運んでゆくものです。そうして、そんなふうにして自分を知ることになる。真の冒険者は実はそれを求めているのだと思います。そして、わたしは、いわば書くことを通じてそれを行っているのです。書きながら、わたしはわたし自身について何かを体験する、そのなかには、それがわたしのなかにあることも、わたしがそれをできることも、それまでまったく知らなかったことです。考えるだけでは、それはわからないことなのです。
さらに、KJ法の川喜田二郎氏の言葉「主体」と「客体」について
創造的行為は、まずその対象となるもの、つまり「客体」を創造するが、同時に、その創造を行うことによって自らをも脱皮変容させる。つまり「主体」も創造されるのであって、一方的に対象を作り出すだけというのは、本当の創造的行為ではないのである。そして、創造的であればあるほど、その主体である人間の脱皮変容には目を瞠るものがある。
参考:最初にあるのは、「我」ではなく「混沌」である(19.12.10)
http://hero.niiblo.jp/e490086.html
これらの人たちが示していることは、小説を書くこと(つくること)は、新しい発見が生じるプロセスであり、何かを「つくる」ことはつくり始める時点ですでに自分のなかにある何かを外に出すということではなく、つくることで新たな発見が生じ、学びが深まり、成長につながるという「構造的」なものである。
「つくる」という冒険に出る。
探究的な学びとはきっと、こういうことなのだろうな、と。
この後、本書はそのかかわり方として「ジェネレーター」を提唱している。
知識を教えたりスキルを身につける機会をつくるティーチャーやインストラクターではなく話し合いの流れを促すファシリテーターでもなく、一緒につくることに参加するジェネレーターという関わりが必要になるのだと。
~~~
なるほど。「つくる」という冒険を生成するジェネレーター的なかかわりが重要なのだ、と。
さらに、もうひとつ。「自己表現」についても言及されている。
村上春樹が次のように述べる
~~~
今、世界の人がどうしてこんなに苦しむかというと、自己表現をしなくてはいけないという脅迫観念があるからですよ。だからみんな苦しむんです。・・・日本というか世界の近代文明というのは自己表現が人間存在にとって不可欠であることを押しつけているわけです。教育だってそういうものを前提条件として成り立っていますよね。まず自らを知りなさい。自分のアイデンティティーを確立しなさい。他者との差異を認識しなさい。そして自分の考えていることを少しだも正確に、体系的に、客観的に表現しなさいと。これは本当に呪いだと思う。だって自分がここにいる存在意味なんて、ほとんどどこにもないわけだから。タマネギの皮むきと同じことです。一貫した自己なんてどこにもないんです。
~~~
「創造」「つくる」とは、自分の主張や自分らしさを表現するという「自己表現」をしようと呼び掛けているのではないと井庭さんは言う。
たんに自分を表現しているのでは、そこに学びや成長は見込めない。そうではなく、自分がつくっているもの(つくられつつあるもの)が「あるべきかたち」になるようにつくることによって、自分を超えたものに出会い、気づきがあり、成長が可能となる。村上春樹はつくるものの論理に身を委ね、それについていくことで自己表現の罠から抜け出せると言う。
~~~
物語という文脈を取れば、自己表現しなくてもいいんですよ。物語がかわって表現するから。僕が小説を書く意味は、それなんです。僕も、自分を表現しようと思っていない。自分の考えていること、たとえば自我の在り方のようなものを表現しようとは思っていなくて、自分の自我がもしあれば、それを物語に沈めるんですよ。僕の自我がそこに沈んだときに物語がどういう言葉を発するかというのが大事なんです。物語というのは常に動いていくものであって、その動くという特性の中にもっとも大きな意味があるんです。だからスタティックな枠みたいなのをどんどん取り払っていくことができます。それによって僕らは「自己表現」の罠を脱することができる
~~~
これさ、「物語」とか「小説を書く」を「プロジェクト」に換えても同じだろうな。同じというか、プロジェクトという場に溶け出してこそ、いいアウトプットが出るのだと思う。そしてそれこそが「自己表現の罠」、つまりアイデンティティの呪縛を解くカギになっていくのだと。
いやあ、今日、僕確信しました。これでいいんだ、って。
プロローグは次のように締めくくられる。
このように、本格的な創造とは、つくっているものの「あるべきかたち」になるようにすることであり、その過程で、つくる対象やその世界を内側から体験することを伴う。それは自我の表出や作為というものを手放し、対象と一体になるという意味で「無我の創造」と呼びうるような創造である。そのような意味での創造の経験の機会を、教育の場では提供していくことがこれからますます重要になってくる。
~~~
・「つくる」という冒険に出る。
・その物語(プロジェクト)を走らせる。
・その物語(プロジェクト)に自我を沈める。
この繰り返しこそが「自己表現せよ」という呪いを解くカギなのだろう。
「つくりこと」から始め、発見と変容を繰り返す「場」を持つプロジェクトを設計すること。たぶん、そういうことだ。
2022年05月20日
散歩するように本を読む
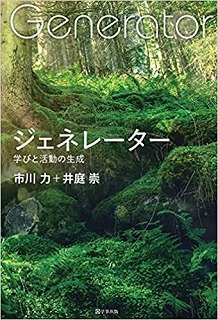
「ジェネレーター まなびと活動の生成」(市川力+井庭崇 学事出版)
もうブログを書けなくなってしまうのが残念ですが読み終わってしまいました。
最後まで揺さぶられ続けました。
今日は阿賀黎明高校でフォトスゴロクの実践をするところだったのでタイムリーでした。
エピソード8は「歩き、つくる」
ここで出てくるのは「feel度 walk」。
なんとなく気になるモノ・コト・ヒトと出「遭」いながらあてもなく歩くこと。
あてもなく歩き、発見した物事を愛でてゆくと「歩き愛でスイッチ」がONになり、5Gシステムが作動する。
★5Gシステム
1 遭遇:いつでも遭遇しているというマインドセット
2 偶然:たまたまつながる偶然な発見
3 隅:隅っこから始まるのを厭わない
4 愚:まずは愚直に続ける
5 寓:追いかけた先に物語(寓話)が生まれる
ここで出てきたキーワードは、陸奥賢さんがポリフォニックミュージアム冊子で語っていたことと同じだ。
冊子:「歩くというのは字義通り、少し止まる」ことだと考えている
本書:「歩」という漢字は、「止」と「少」という漢字を組み合わせて構成されている
!!!
きたね、これ。シンクロニシティ。
そして、こっからですよ、こっから。
面白いのは。
1 feel度 walk でMy Discovery 「アイ(I)」
写真を撮るワークをするとき、ひとりひとりが撮ってきた写真にはほぼ同じものがない。
2 My Discoveryのシェアが生み出すYour Discovery 「アイ(相)」
お互いのMy Discoveryをシェアすると他者のMy Discoveryに関心が向き始める。
3 発見がひとつに合わさるOur Discovery 「アイ(合い)」
場によってMy Discoveryを元に別の発見をする。
※発見の拡張はアイの拡張でもある。
そして、ココもよかった P224
~~~
関心の低い子は自身のない子も多く、「どうせ私の発見なんて大したことない、面白くない、誰かにバカにされたら嫌だ」と思っている。このときに普段から教師自身がfeel度walkを積み重ねていると、君も世の中のあちこちに転がっているささやかな発見を共有する仲間になったね!という思いのこもった「面白いね!」という言葉が口をついて出てしまう。この思いが相手をゆさぶり、どの発見にも「意味」を見出すことができ、優劣はないという気持ちが開く。たかが「なんとなくの発見」と侮ることができない、自己効力感を取り戻す場になる。
feel度walkは、効率性と画一化からの「逸脱」を許す。みんなが足並みをそろえて反応しなくてもよい。個々の発見するまでの時間差も個々の発見の多様さも当たり前。何かがみつかるのを待てる余白。それを受け止める寛容さ=generosityがジェネレーターの持ち味だ。励まそうとか、支援しようとかいうようなアプローチで「動機づける」のではなく、お互いのDiscoveryを素直に認め合うことで、どの瞬間でも何かしらみつけてしまうfeel度が高まり、歩き愛でスイッチがONになるのである。
~~~
いやあ、これです。僕が「場のチカラ」にフォーカスし続けた理由。「自分」ていう境目をなくすために、まずはアイデアを出すところ、そして「場」を体感するところから始めてほしいと思っていたんです。なんだかうれしいなあ。
さらに、feel度walk Focus walk Ferment walkで探索・試行・表現のサイクルを回していくことが大切だと言います。feel度walkすると気になるものが生まれそれに焦点を当てたFocus walkが始まる。すると自ずと気になった物を追いかけ続け、仮説が発酵して現れるFerment walkへと移行する。
この3つのwalkを続けていると自ずと独創的仮説が生成され、それを追究する「プロジェクト」が始まる。
なるほど。walk(観察) ⇒仮説⇒プロジェクトか。
そうだよね。
「プロモート」のために観察し、感じること(21.9.20)
http://hero.niiblo.jp/e492042.html
昨年の探究学習の勉強会で「プロモート」のための観察力っていうキーワードがあったけど。
これってそのまま探究の授業、特に地域の魅力発信のプロジェクトには使えるだろうなと。
workの時もwalkと同じように、最初はfeel度workを行う。
直観の赴くままにあちこちさまよいながら思考を進めて、発見感度を研ぎ澄ますworkがfeel度workであり、そこからFusion workへと発展する。Fusionとは2つのものが合わさること。似ている二つを比べて違いを見つけたり、全く違うものに共通点を見いだしたりすること。さらに発展して、Fantasy workへとつながる。これはFusionによって仮説が更新され続けて見えてきたことを作品化しようとする動きのことだ。
ここで読書の話も出てきます。
「私たちはFision workやFantasy workにつながる「仮説」の芽を伸ばすために読んでいる。だから自分の仮説にヒットする部分がないかどうかを探しながらパラパラと読み進める。直接仮説を後押ししている部分があればよし。仮説の反例でもよし。新たな発想を刺激してくれる部分があってもよい。流し読み、斜め読みで気になる部分を探すのは、まさに「散策して発見する」のと同じ感覚だ。
~~~
なるほどなあ。
プロジェクトとか探究のカギは、feel度walk=観察し、感じる散歩なのかもしれないなあと。
それは読書でも同じだ。
感性と好奇心を発揮しながら、町を歩き、観察し、発見する。本を読み、感じ、発見する。
その身体的な解放と、精神的なオープンマインドがカギを握るのだろう。
昨日は友人と「スターバックスエクスペリエンス」の話をしていた。「レシピはあるけどマニュアルがない」スターバックスの研修。「スターバックスはコーヒーを売っているのではなく、サードプレイスを提供している」お店という「舞台」を、つくり続けているのだろう。「舞台」をつくること、それは「舞台」を構成する要素にアプローチするということ。
その話の中で一番!!と来たのが「外へのブランディングと内なるブランディング」。
「スターバックスエクスペリエンス」を支える最大のものは、空間を共に構成するスタッフの「誇り」「誇らしさ」なのだろうと。その「誇り」が同じ空間を共にするお客様に伝わることが最大のブランディングになっているのだろう。
外に対するブランディングには、お金がかかるプロの助けが必要だ。もちろんそれも、スターバックスはやっているのだろうけど。大切なのは「内なるブランディング」でスタッフの誇りを生み出すことだ。
外なるブランディングは空間を共にしていない分、洗練された言葉やデザインが必要になる。しかし、内なるブランディングは目に見えない「誇り」そのものの勝負だから、今すぐにできるし、工夫次第でお金はかからない。そんな風に場づくり、組織づくりをしていくほうがいいんだろうな。それは1本の授業だとしても同じだなあと。
高校の探究の授業の話で言えば、地域の大人も、生徒本人たちも、先生たちも、「ジェネレーター」になっていくこと。生成の場に身を置くこと。それを繰り返した先に、お互いにいい授業だと思える「舞台」が整っていくこと。その授業に参加できることを嬉しく思うこと。
そんな「エクスペリエンス」を生んでいく授業が次々と連鎖させていきたいなと。
2022年05月18日
「自分」から「場」へ
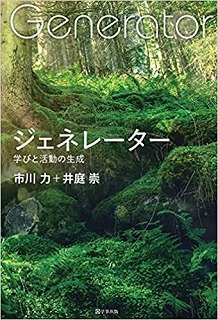
「ジェネレーター まなびと活動の生成」(市川力+井庭崇 学事出版)
僕としてのクライマックス


「場の力」「中動態」・・・
いや、ホント、ここまでやってきてよかったな、と。
僕が「場のチカラ」という言葉を初めて使ったのは、
ブログによれば2009年だったようだ。
その後、茨城の取材インターンひきだしや田舎インターンのにいがたイナカレッジによって磨かれた。
「好き」と「刺激」のあいだ(18.9.5)
http://hero.niiblo.jp/e488038.html
今も、大学生にも高校生にも「成果を生み出すのは個人の力ではなく、場のチカラなんです」って言い続けているし、それを「体感」するところから始めたいということで、偏愛マップ⇒インタビューワークをしたり、カヤック風ブレストをしたり、フォトスゴロクをつくったりしてきた。
この本にもエピソード7(P196)で「なりきる」っていうのが紹介されていて、これは「探究ネーム」の設定によって目指していたものと近いものだった。「なりきりワークショップ」もコンテンツに加えたい。
この本で紹介されているのが「電柱好き」になりきってインタビューを受けるというもの。これもひとりじゃなくて2対2くらいでワークすると面白いかもしれない。「本日のゲストは、電柱をこよなく愛する電柱ブラザーズのみなさんです~パチパチパチ」などと言いながら、テレビ番組さながらインタビューを行う。これも大人とこどもミックスでやったら楽しいだろうね。
この「なりきる」というのは「リフレーム」の練習だと市川さんは言う。
http://hero.niiblo.jp/e492190.html
目的地を決めないこと、地図とコンパスを持たないこと(21.11.25)
このときにえぽっくにとってコーディネートとは?で定義されたのが
・無理でしょ、と思えることをできるようにつなぐ
・面白がる(リフレーミング)
・リソースを拡張する
ことだと。たしかに、コーディネートの価値は、ここにある。
・不可能(だと感じること)を可能にするために「場をつくること(立ち位置を知ることとイメージの共有)」
・新しいアイデア、発想、具体先を出すために「面白がる(⇒リフレーミング)すること」
・それらの実行によって、自分の手持ちだでなく「資源(リソース)を拡張すること」
・仮説を実行した後にふりかえることによって「検証すること」
これはそのままジェネレーターシップにつながっていく。
そのリフレームの練習が市川さんの言う「なりきる」なのだと。
広島の杉本さんが「読書会で好奇心は育むことができる」と言った
http://hero.niiblo.jp/e491170.html
そのキーワードも面白がる、だった。
本書のエピソード6「場の力」から引用する
~~~
自分が属する組織や社会を変えようとすることはとても大事だが、ジェネレーターシップの本質は自分がどう変わるかというところにある。自分が率先して面白い状況をつくりだし、そこに自分がまず没入し、中動態的な生き方をしてゆく。そのために、親子、友達というような思いを共有する小さな仲間とともにジェネレーターシップを発揮する場をつくることからスタートするのがよい。
面白がる場は、決して人と何かをする場だけに限らない。植物や野菜を育てるような自然と関わる場を持つのもいい。植物を育てようというとき、僕らができるのは水と肥料をやるというぐらいで、ほとんどコントロールできない。「こんな花が咲いた」「こんなに実ができた」「今年のミニトマトは調子が悪いな」というように相手が育ってゆくのに寄り添ってゆくしかない。相手が人間だと、相手側の都合や作為が自分に絡んでくるし、相手を変えてやろう、コントロールしようという気持ちが出てきてしまう。しかし、植物相手にはそういう気持ちが働かないので、場に任せ、感じるためのよいトレーニングになる。
(中略)
野菜づくりに没入してもよし、みんなで料理をつくってみるのを楽しむ会からスタートしてもよい。そうすると、個の境目が消えてみんながつくるプロセスに没入する瞬間が訪れる。つくりながら気づいたちょっとしたことをみんなでワイワイ語りあっていくうちに、自らフタをしてきた「面白がる」感覚が目覚めるはずだ。
~~~
「個の境目が消えてみんながつくるプロセスに没入する瞬間が訪れる」
いやあ、それです。「境目をあいまいにすること」「場に溶けだすこと」
それを体感してもらいたいんです。
この部分の続きでは、
大人と子どもが一緒に企み、思いつきを解き放つ場をつくる例として、子どもたちと身のまわりを散策することを薦めている。
~~~以下メモ
子どもたちは、人ではなく人工物にも草にも虫にもフラットな関係性を気づく。子どもと一緒になって歩く「場」に参加し、子どもの感性に触れることで自ずと大人の鎧がとれてゆくだろう。
天真爛漫に見える子どもたちも実は、誰かの期待に応えようとしたり、「そんなのあるわけないよね」と言われることを恐れていたり、好奇心のフタが閉じかかっていることが多い。大人と同じくらい、場合によってはそれ以上に、ここは思いつきを披露する場だという認識を持たせることはとても重要である。
外をあてもなく歩くのがよいのは、会議室や教室のような閉じた空間を飛び出ると、頭と体と心が自ずとゆるむからである。
大人と子どもが一緒に学ぶシチュエーションをつくることはこれからの学びの場づくりにおいてとても大事になってくる。そのときに大人「が」子ども「を」教えるのではなく、大人「と」子どもが対等に同じことをしたり、つくったりすることが大きなカギを握る。
~~~
P173に、子どもが大人とタッグを組むことの効用がまとめられていて
子ども⇔大人
目:解像度⇔周辺視
耳:問いかけ⇔受けとめ
口:思いつき⇔雑談
手:描写力⇔記憶力
と表現されている。なるほど。
このほかにも「強者と弱者が生まれないフラットな関係を生み出すメタメタマップ」など、「まなぶ」から「つくる」へのシフトを言っていた僕にとってはうなずくばかり。「つくる」にフォーカスすることで人はフラットになる。
今日の最後に、「場」についての記載を引用する。
~~~
「誰が」発見したかは生成・発見の連鎖においてなんら重要ではない。明らかにジェネレーターがよいアイデアを出したら採用される。大切なのは、よいアイデアかどうか本気になって追究する場であるという共通認識が参加者全体にあることだ。
それぞれの強みを発揮し、お互いの発見を面白がり、リスペクトしあう。これがスーパーフラットな関係性でつくり続けるということだ。社会関係が優先される場からともにつくる場へとシフトすることで、こうした関係性が生まれ、ジェネレーターは、出し惜しみしないで本気で相手と関わることができる。
~~~
師匠にあこがれ、師匠のようになろうと「周辺」の軽い仕事から参加し、次第に「中心」の重要な仕事を任されるという「正統的周辺参加」な形ではなく、好奇心がだんだんと目覚め、仕事のプロセス自体を面白がるようになり、ともに表現し、作品をつくりだすためにコラボレーションする「好奇心誘発参加」という形ができる。こうして、相互の関係が対等でありながら、創造に真剣に向き合う場がジェネレートする。(P161)
~~~
「作品をつくるために」っていうのがいいですね。
そしてラスト「場の力」に関しての言及
~~~
ジェネレーターは失敗を引き受け、場を盛り上げ、明るく、面白がれる人であることは間違いない。しかし、その力は個人の属人的な能力や性格を源泉としたものではなく、創造の「場」が生み出す力=Field Forceなのだ。
心は揺らぐものと覚悟し、心に依存せず、発見と創造のプロセスに身を任せる。自分の心の強さで乗り越えるのではなく、「場」に身を委ね、「場」を感じとり、柔軟に問題を解決しようとしている。
すぐに解決されることはなく、解決したと思ったらまた新たな課題が出てくるのが何かをつくるプロセスである。まさに「終わりが始まり」としか言いようがない。このプロセスが繰り広げられる「場」はジェネレーターにとっても、参加者にとっても一世一代の「舞台」に等しい。それぐらいやりがいがあるし、そこで生まれたものを世に披露したいという思いも強くなる。
ジェネレーターは、新たな意味づけを繰り返し、発見と創造の連鎖が生成する「舞台」の上で、「自分」が考えるととらえるのではなく、逆に「自分」の心を突き放して、創造のプロセスに一体化して中動態的に動き続けるのである。
~~~
いやあ、もう、ありがとうございます。
感謝しかありません。キーワード全部入ってます。
トンネル開通です。
アイデンティティ・クライシスのトンネルとクリエイティブ・ラーニングのトンネルは実は1本のトンネルだったんだなあと。その交点に「中動態」があり「場のチカラ」があり「ジェネレーターシップ」があった。
そしてそれは「舞台」であり「委ねる場」でもあった。
成果を生む出すのは、発見・創造を生むのは個人の力でもチームのチカラでもなく「好奇心」により駆動されフラットな関係で個人が溶け出している「場」のチカラだった。
なんだかうれしい気持ちでいっぱいです。
これから実践していきます。
ステキな本をありがとうございました。
2022年05月17日
トンネル開通
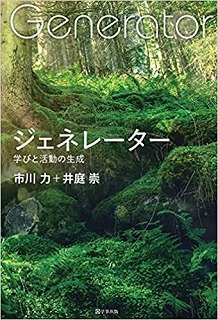
「ジェネレーター まなびと活動の生成」(市川力+井庭崇 学事出版)
P150 ジェネレーターは生成の場となる-中動態としてしか表せない出来事
ついに、きました中動態。長いこと掘ってきたトンネルがココで開通するとは。
僕が掘ってきたのはアイデンティティ、自分らしさという呪縛について、だったのだけど、
それを創造的な学び(=クリエイティブラーニング)というトンネルを掘ってきた人がいるんだって。
能動-受動ではない中動態という世界があることを知ったのは、2018年の夏
http://hero.niiblo.jp/e487965.html
「やりたいことは何か?」「何になりたいのか?」への違和感(18.8.20)
~~~上記ブログより引用
ギリシア世界には、「意志」は存在しないし、それに伴って「未来」も存在しない。過去からつづく流れの中で、状態(状況)としての今がある。能動態‐受動態という言語体系は、「この行為は誰のものか?」と問うが、その問いはそんなに大切なのか?大切だとしたら、それが大切とされるようになったのはいつからなのか?そんな問いが浮かぶ。
「やりたいことは何か?」「何になりたいのか?」この二つはまさに「意志」と「未来」を問う質問なのではないか。
あたりまえだけど、「言葉」と「世界」は相互に作用している。「言葉」が「世界」を規定し、「世界」が「言葉」を規定している。だから、「やりたいことは何か?」と問われれば、「やりたいことは何だろう?」と考え、それに答えようとしてしまう。
でもさ、そもそも、「意志」や「未来」が存在しないとしたら。能動態と受動態の対立の世界に生きていなかったとしたら。
もしかしたら、そんなところにこれらふたつの問いの違和感の正体があるような、ないような気がする本です。
~~~
大学生の「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」のつらさのの正体はどこにあるのか?
そんな問いの中で、僕は中動態に出会いました。
そしてその解決策として、「場のチカラ」にフォーカスし、「学ぶ」から「つくる」へのシフトを図り、他者や地域の大人と「ともにつくる」プロジェクトを志向してきました。
僕にとって、「つくる」=クリエイティブは「自分らしさ問題を解決する」という意味では手段だったのかもしれません。
「存在」は創造の場のエッジにある、とかつて考え、創造する共同体の中に身を置くことで、その場にたしかにいたという実感こそが「存在」を承認してくれるのだと考えていました。
今だったら「過去を継いでいく」という方向でしょうか。
P154~156に、トンネル開通部分の話が出ているので抜粋する
~~~
森田亜紀さんは「芸術の中動態」のなかで、次のように説明している
「中動態で表される事態において、主語は動詞の表す過程の中にいわば巻き込まれている。言い換えれば、中動態の動詞は、名詞の主語に従属する述語ではない。中動態によって、われわれは主語を前提としない述語、さらに言えば、主語に先立ち主語をそこから成立させる述語というものまで考えることができるように思われる。」
まさにこの意味で中動態の状態にあるのが「ジェネレート」ということの本質なのだ。生成の現場に入り込むと、自分はたしかに関わってはいたが、「自分がジェネレートした」という自覚はなく、何をしたらそうなったのかということも明確にはわからない。しかし、ジェネレートされた場にいたという実感だけは確実に残る。
ジェネレーターとして何かをしたという能動的行為の記憶ではなく、出来事の中にいて、その一翼を担っていたという体感だけが残っている。自分がその場に溶け込み、自分たちを場として生成が起き、それを自分も体験している。そのような出来事への関わりは、まさに中動態で表されるような出来事なのだ。
そうであるのに、「ジェネレート」ということを、「誰かがジェネレートする」というように能動的な行為としてとらえると、僕や市川さんは何をしているのか?という問いになってしまう。けれども、そういうものではなく、そもそもジェネレートという出来事が起きるのだ。そこに僕らは関わり、巻き込まれ、参加し、味わい、その一翼を担うということなのだ。
古代ギリシア語やサンスクリット語にあった中動態という考えが、その後なくなってしまったのは、人間中心の世界観が強固になってきたからではないだろうか。僕は古代ギリシアと東洋の考えは通じ合う部分が多いことから、人類は古くは西も東も同じような感覚を持っていたのではないかと考えている。その後、西洋のロゴス的世界観が強固となり、人間中心の近代的自我の意識が強くなり、現在のような世界観に到達したと思っている。
そういう世界観のまま、「ジェネレーター」を捉えようとすると、そこで起きていることは異なる、変形を伴った理解になってしまうだろう。なぜなら、能動態/受動態のフレームではとらえられない中動態で表されるような出来事に「参加」し、それをますます勢いづけているのが「ジェネレーター」だからだ。能動態/受動態で分けて考えてしまうから、ジェネレーターという「主体」が周りの他の人たちに何かしているという話になってしまう。しかし、そうではない。僕たちが提唱している「ジェネレーター」は、中動態で表されるような出来事の「場」に溶け込み、なりきる人なのだ。
~~~
トンネル開通。光が、見えた。にいがたイナカレッジや取材インターンや、総合的な探究の時間で目指してきたこと。
場のチカラ、場に溶ける、場を主語にする、チューニングする、魔法をかける編集、まなぶからつくるへ。これらのキーワードは、「つくる」ことにとっても大切だったのだ。
協働から共創へ
ってきっと中動態的なアプローチによって達成されていくのだろう。
そしてそれは、自分らしさ問題をも解決する方法になっていくのだと、予感できた朝です。
2022年05月14日
探究の森へようこそ
風舟の正式名称は、探究の森交流館「風舟」。
つまり、探究するための森だ。
昨日話していて出てきたキーワードは
・心身を解放し、五感を発揮すること
・境界をあいまいにすること
・出会うこと、つくること
たぶんこの順番なのかもしれない。
目的・目標に向かう小さなベクトルではなくて、大いなる流れに「委ねてみる」こと。「流れ」とは、空間的には人間社会よりずっと広い森の生態系だったり、時間的には人生よりもずっと長い何百年単位の歴史だったりするのだろう。
たぶんそこに「身を置く」ことが大切なのだと思う。「原点」とは、始まり、スタートラインであると共に、様々なリレーの中継ランナーとしてここに存在する、という物語の終着点でもある。
そこに身を置くことができる「場」を作っていきたいと思った。
そんな思いを持ちながら、タイムリーに読み進めている本。
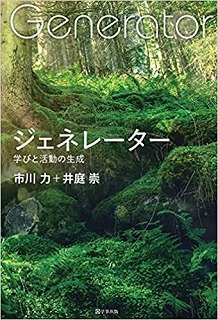
「ジェネレーター まなびと活動の生成」(市川力+井庭崇 学事出版)
読み進めていると
「俺もなかなかいいセン行ってるんじゃないか」と自己肯定感が上がります。(笑)
~~~ここから引用
一人ひとりを、分割不可能なひとつの原子のように捉えるのではなく「いくつもの創造実践を行っている複合」として捉える見方のほうが自然でよりよいと思う。
自分のなかどのような創造実践が含まれているかは、人それぞれ違う。その組み合わせこそが個性と呼び得るものだろう。
さて、そういういくつもの創造実践の複合としての人が集まると何が起こるか。1人では高度なことができないことでも、複数人が集まって、それぞれの創造実践の力と経験を持ち寄ることで、1人ではなし得なかったことを行うことができる。これがコラボレーションということである。
~~~
「アイデンティティ(自分らしさ)の危機」問題とその解決法。「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」という大学生に出会ってから研究してきたテーマ。
僕はそれを「場のチカラ」で解決しようとしてきた。実践の場は、にいがたイナカレッジ、取材型インターン「ひきだし」、そして高校の探究の授業だった。
「自分」という輪郭を溶かし、「場」の一員となること。「創造する場の一員となった」という経験を積み重ねること。その積み重ねと組み合わせがその人のアイデンティティをつくるということ。
「存在は創造のエッジにある」そんな仮説。
http://hero.niiblo.jp/e491178.html
(20.11.10)
それはまさに試行錯誤のプロセスの途中にあったわけだけど、この本を読んで、その創造には「ジェネレーター」的な関わりが必要なのだと実感した。
第2部 ジェネレーターの役割のところの5G(禺)の話が面白かったので、引用します。
1 遭遇:いつでも遭遇しているというマインドセット
2 偶然:たまたまつながる偶然な発見
3 隅:隅っこから始まるのを厭わない
4 愚:まずは愚直に続ける
5 寓:追いかけた先に物語(寓話)が生まれる
いいですね。本書にも書いてありますがクランボルツ博士の「計画された偶発性理論」にも通じる5Gの話。僕はこれを、個人の単位、チームの単位ではなくて「場」の単位でやれないだろうか、と試行錯誤しているのではないか、と。
解決したい課題は「(特に10代20代の)アイデンティティの危機」。
その原因と対策は
1 「やりたいことは何か?」という問いに代表される夢・目標至上主義
⇒学校教育の構造(システム)上の問題(評価を前提としたカリキュラム、目標管理)
⇒「総合的な探究の時間」などで「実践⇒ふりかえり⇒計画」のサイクルを実践してみる
2 共同体の解体
⇒地域、家庭、会社という共同体が解体され、社会と個人が直接向き合わなければならないこと
⇒「場のチカラ」にフォーカスし、創造する一時的な共同体を体感し、その一部であるという実感を得る
3 「自分」そのものの定義
⇒共同体や他者から切り離された存在(個)としての「自分」
⇒場を感じたり、委ねたりして、「自分」という境界をあいまいにする
最大の危機は「存在の承認」問題だと思う。
10代、20代は(いやもしかしたら僕ら世代、いや僕自身も)、「存在の承認」を求めて彷徨っている。
「自分はこの世に存在していていいのだろうか?」
「自分は無価値なのではないか?」
という不安の中にいる。
山竹伸二さんは「存在の承認」と「行為の承認」を分けて考えた方がいいと言います。
http://hero.niiblo.jp/e491900.html
「自由」を取るか「承認」を取るか(21.7.18)
「ジェネレーター」で書かれているように、世の中は、「創造社会」に向かっていくのでしょう。それを突き動かしていくジェネレーター的存在が必要とされるのでしょう。
しかし、その「創造」以前に、「存在の承認」が必要だと思うし、それこそが心理的安全性を高め、創造力の源になっていくと思ってます。
そしてその「存在の承認」においては、「物語の継承」が重要になってくるという仮説をもっています。
探究の森交流館「風舟」のある阿賀町津川は、かつて会津藩の河港として栄え、人、モノ、情報が交流する地域拠点だったという歴史があります。
その物語を継いでいく、ということ。
つくる、という現在から未来に向かってのベクトル。
継ぐ、という過去から現在に向かっているベクトル。
その交差する場所に「存在」と「アイデンティティ」と「創造」を同時に満たす何かがあるんじゃないか、っていうのが僕の仮説です。
つまり、探究するための森だ。
昨日話していて出てきたキーワードは
・心身を解放し、五感を発揮すること
・境界をあいまいにすること
・出会うこと、つくること
たぶんこの順番なのかもしれない。
目的・目標に向かう小さなベクトルではなくて、大いなる流れに「委ねてみる」こと。「流れ」とは、空間的には人間社会よりずっと広い森の生態系だったり、時間的には人生よりもずっと長い何百年単位の歴史だったりするのだろう。
たぶんそこに「身を置く」ことが大切なのだと思う。「原点」とは、始まり、スタートラインであると共に、様々なリレーの中継ランナーとしてここに存在する、という物語の終着点でもある。
そこに身を置くことができる「場」を作っていきたいと思った。
そんな思いを持ちながら、タイムリーに読み進めている本。
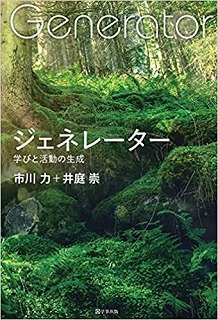
「ジェネレーター まなびと活動の生成」(市川力+井庭崇 学事出版)
読み進めていると
「俺もなかなかいいセン行ってるんじゃないか」と自己肯定感が上がります。(笑)
~~~ここから引用
一人ひとりを、分割不可能なひとつの原子のように捉えるのではなく「いくつもの創造実践を行っている複合」として捉える見方のほうが自然でよりよいと思う。
自分のなかどのような創造実践が含まれているかは、人それぞれ違う。その組み合わせこそが個性と呼び得るものだろう。
さて、そういういくつもの創造実践の複合としての人が集まると何が起こるか。1人では高度なことができないことでも、複数人が集まって、それぞれの創造実践の力と経験を持ち寄ることで、1人ではなし得なかったことを行うことができる。これがコラボレーションということである。
~~~
「アイデンティティ(自分らしさ)の危機」問題とその解決法。「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」という大学生に出会ってから研究してきたテーマ。
僕はそれを「場のチカラ」で解決しようとしてきた。実践の場は、にいがたイナカレッジ、取材型インターン「ひきだし」、そして高校の探究の授業だった。
「自分」という輪郭を溶かし、「場」の一員となること。「創造する場の一員となった」という経験を積み重ねること。その積み重ねと組み合わせがその人のアイデンティティをつくるということ。
「存在は創造のエッジにある」そんな仮説。
http://hero.niiblo.jp/e491178.html
(20.11.10)
それはまさに試行錯誤のプロセスの途中にあったわけだけど、この本を読んで、その創造には「ジェネレーター」的な関わりが必要なのだと実感した。
第2部 ジェネレーターの役割のところの5G(禺)の話が面白かったので、引用します。
1 遭遇:いつでも遭遇しているというマインドセット
2 偶然:たまたまつながる偶然な発見
3 隅:隅っこから始まるのを厭わない
4 愚:まずは愚直に続ける
5 寓:追いかけた先に物語(寓話)が生まれる
いいですね。本書にも書いてありますがクランボルツ博士の「計画された偶発性理論」にも通じる5Gの話。僕はこれを、個人の単位、チームの単位ではなくて「場」の単位でやれないだろうか、と試行錯誤しているのではないか、と。
解決したい課題は「(特に10代20代の)アイデンティティの危機」。
その原因と対策は
1 「やりたいことは何か?」という問いに代表される夢・目標至上主義
⇒学校教育の構造(システム)上の問題(評価を前提としたカリキュラム、目標管理)
⇒「総合的な探究の時間」などで「実践⇒ふりかえり⇒計画」のサイクルを実践してみる
2 共同体の解体
⇒地域、家庭、会社という共同体が解体され、社会と個人が直接向き合わなければならないこと
⇒「場のチカラ」にフォーカスし、創造する一時的な共同体を体感し、その一部であるという実感を得る
3 「自分」そのものの定義
⇒共同体や他者から切り離された存在(個)としての「自分」
⇒場を感じたり、委ねたりして、「自分」という境界をあいまいにする
最大の危機は「存在の承認」問題だと思う。
10代、20代は(いやもしかしたら僕ら世代、いや僕自身も)、「存在の承認」を求めて彷徨っている。
「自分はこの世に存在していていいのだろうか?」
「自分は無価値なのではないか?」
という不安の中にいる。
山竹伸二さんは「存在の承認」と「行為の承認」を分けて考えた方がいいと言います。
http://hero.niiblo.jp/e491900.html
「自由」を取るか「承認」を取るか(21.7.18)
「ジェネレーター」で書かれているように、世の中は、「創造社会」に向かっていくのでしょう。それを突き動かしていくジェネレーター的存在が必要とされるのでしょう。
しかし、その「創造」以前に、「存在の承認」が必要だと思うし、それこそが心理的安全性を高め、創造力の源になっていくと思ってます。
そしてその「存在の承認」においては、「物語の継承」が重要になってくるという仮説をもっています。
探究の森交流館「風舟」のある阿賀町津川は、かつて会津藩の河港として栄え、人、モノ、情報が交流する地域拠点だったという歴史があります。
その物語を継いでいく、ということ。
つくる、という現在から未来に向かってのベクトル。
継ぐ、という過去から現在に向かっているベクトル。
その交差する場所に「存在」と「アイデンティティ」と「創造」を同時に満たす何かがあるんじゃないか、っていうのが僕の仮説です。
2022年05月11日
つくることによる学びの時代
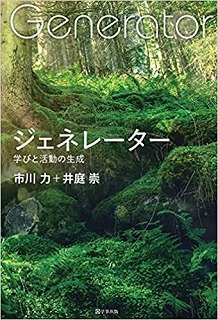
「ジェネレーター まなびと活動の生成」(市川力+井庭崇 学事出版)
読書の醍醐味は、これまでのキーワードがつながってくる感じだと思うし、自分が失敗した理由が分かる、とかそういうことなのだろう。
「つながった!」みたいな感覚になれる本に出合った。
ジェネレーター。
日本語訳すると「生成する人」となる。
いきなり冒頭から熱い。
これからの時代は、どんな人も創造的に暮らす時代だと言えるでしょう。「創造的な暮らし」というと、これまでとは異なる新しいことのように聴こえるかもしれませんが、工業化・産業化が進む前はごく当たり前のことでした。なぜなら、私たちは日常で必要なものを自分たちでつくって生活していたからです。ものだけではなく、生活の知恵・仕組みもこうして日々の暮らしの中で、仲間とともに自分なりに工夫して生み出していました。むしろ、人間が創造的に暮らすというのは、自然なことだったのです。
そうだよ、そうだよ!って。これだけで熱くなっちゃいますね。これまで「場のチカラ」とか「発見と変容」とか「伴奏者」とかって言ってたのは、整理すると、ジェネレートするってことなんだなあと。
~~~
ジェネレーターは気になった「雑」をひとまず集め、集まったカオスで混沌と見えるものから面白いアイデア、意外な発想、これまでにない工夫が「生成」することを体感していて、無関係なことを重ね合わせる流れに身を任せ、「雑」から「生成」が起こる醍醐味を知っている人のこと。
何かを自分なりにつくりだして生きる創造的な暮らしでは、素人であり、初めて何かに挑戦する人たちどうしが小さな仲間となってプロジェクトに取り組んでいかなければなりません。この点においては大人も子どもも同じ立場。教師と生徒という固定的関係性もありません。
~~~
そうそう、そうなのよ!みたいな共感だらけ。
僕の文脈で言えば、それこそがアイデンティティ問題に対抗する切り札だと思っている。
第1章からはP34以降の井庭さんと市川さんの出会いによる「ジェネレーター概念の誕生」からメモを取ります。
パターン・ランゲージの国際学術会議で発表した「ペタゴジカル・パターン・フォー・クリエイティブ・ラーニング」(創造的な学びのための教授法パターン)より3つのエッセンス
1 ディスカバリー・ドリブン・エクスパンディング(発見の広がり)
どうしたら一人ひとりの子どもたちがコラボレーションに本当に参加できるようになるかの工夫
マイ・ディスカバリー(自分の発見)を味わう⇒
ユア・ディスカバリー(相手の発見)を認め合う⇒
アワー・ディスカバリー(私たちの発見)へと向かう
いろいろ話していくなかで、みんなで気づくことが出てくる。これはもはや誰かの1人の発見ではなく、自分たちで発見したものになる。こういう段階を経ずにいきないコラボレーションをやろうとするとうまくいかないのだ。
~~~
わー。いきなりね。これ、僕がやっているところで言えばミーティング前の「チューニング」とか、フォトスゴロクのような自己開示ツール(ワークショップ)を使いながら、やっていることなのかもしれません。
2 チャレンジング・ミッション(挑戦的なミッション)
みんなで取り組むのは、魅力的だけれども、一見どうやってよいのかわからないくらいチャレンジングなものを設定するというものだ。一般的に探究プロジェクトは、一人ひとりの内発的なものでなければ意味がないと思われやすいが、自分で思いつけることのちょっと先のチャレンジングなレベルのほうがいいのだ。魅力的で、ちょっと冒険的なミッションになるように設定するのだ。
~~~
これも!!ですね。内発的動機づけを重要視するあまりに課題やミッションが凡庸になってしまっていること。
3 ジェネレイティブ・パーティシパント(生成的な参加者)
ティーチャーでもファシリテーターでもなく、「ジェネレ―ティブ・パーティシパント」(生成的参加者)として、学び手の活動に一緒に参加する存在なのだ。市川さんの取り組みは心から子どもたちの発見を面白がり、一緒にチャレンジングなミッションに取り組む、そんな姿を目の当たりにした。
~~~
これが「発見と変容」をともに楽しむ「伴奏者」っていうことなのだろうな、と。
そして、そのあと、P41から始まっている「ティーチャー、ファシリテーター、そしてジェネレーターへ」で興奮は最高潮に。
ここ100年とこれからの社会の変化と豊かさ指標
1 Consumption(コンサンプション:消費)を中心とした消費社会⇒どれだけ商品やサービスを享受しているか
2 Communication(コミュニケーション:)を中心とした情報社会⇒どれだけよい関係やコミュニケーションをしているか
3 Creation(クリエイション:創造)を中心とした創造社会⇒どれだけ生み出しているか、どれだけ創造的でいるか
まなび方の変化
ラーニング1.0:Individual(thinking)⇒Subject study⇒teacher
ラーニング2.0:Social(communication)⇒Workshop⇒Faclitator
ラーニング3.0:Creative(discovery)⇒Creative project⇒Generative Paticipant
これもすごいよね。
ひれ伏すしかない。
ワークショップ3.0を思い出した
http://hero.niiblo.jp/e477213.html
我々は宇宙飛行士ではないし、ここは宇宙ではない(16.2.22)
消費社会⇒情報社会⇒創造社会と移り変わる中で、
ティーチャーからファシリテーターへ、そしてジェネレーターへと
必要がかわっていく。
ここでの最大のポイントだと思うのが
つくることによる学びの時代においては、学びの支援者は、ともにつくることに取り組む。もはや他人事ではなく自分事として、本気で参加する。その参加の中に、つくることへの貢献があり、交流があり、学び合いが生じるのだ。
ジェネレーターは、コミュニケーションをつなぐだけでなく、そこに新たな意味を付加して場に返す。そうすると、もとの発言の意図からはズレてしまう。ズレてしまうというとネガティブに聞こえるが、そのズレこそが創造的であるということだ。
~~~
こんな感じで、話は続いていくのだけど、今日はこのへんで。
2022年05月08日
「みんな」と「他者」と「自分」のあいだを行き来し、手づくりする

「手づくりのアジール-土着の知が生まれるところ」(青木真兵 晶文社)
前回書いたのが4月8日なので、ちょうど1か月が過ぎてしまいました。
ラストはシビれながらも読み終わりました。
前回は労働的価値と存在の承認というタイトルで書きました。
http://hero.niiblo.jp/e492378.html
今回はその続き。
~~~P159「手づくりのアジール」より一部引用
商品は「みんなのため」のものです。「みんなのため」とは、お金を払えば誰もが公平に購入可能ということです。そして現代社会はその原理によって成り立っています。
お金は殿様だろうが、一般庶民だろうが、誰でも同じように使えます。ここにお金の平等性があります。しかしお金自体は平等でも、持っている量が平等でなければ、もしくは稼げる機会が平等でなければ、お金によって平等な社会は実現しません。逆に、お金が限られた人たちのところに偏り、格差社会が発生しているのが現代の問題です。
ということで、これからは「みんなのため」ではなく、「自分のため」に生きていくべきだと思います。それは自分たちや身の回りのものを「商品として見ない」ということです。より速く、より安い。一分一秒無駄にしないのは、商品的な価値観です。そして世の中で評価されることの多くは、商品的な価値観で成り立っています。
ぼくたちは「自分」を確固たるものにするために、どうしても「他者との違い」を求めてしまいます。世間ではどんな人が求められているか、自分はどのような人になるべきなのか。ここで一番重視されているのはニーズです。ニーズに応えるためには、常に「他者」からの視点を意識し続けていかなくてはなりません。
真っ先に「他者」の視線を意識するということは、まず市場のニーズを考えねばならない商品と同じです。こうした商品のような人の問題点は、「人が集まっていない」場所と「たくさんの人が求めていない」ものに価値を見いだせなくなってしまうことです。
何かを成し遂げようとすることは、商品的人間として「みんなのため」に生きていくということです。一方手づくり人間は、「自分のために」生きていきます。「自分らしく」とか「自分らしくない」とか、そういうことは気にしません。「自分らしく」生きていくとは、実は商品的人間として生きていくことを意味します。商品的人間の特徴は、他者の眼差しが内面化されている、ということです。社会的評価を気にしてしまうとも言い換えられます。
手づくりとは、誰もが対価を払えば手に入れられる商品とは異なり、自身の個別性、身体性を手がかりに行う行為です。そして個別性や身体性に触れるためには、コントロールできない、社会の外部が自分の中にもあることを認める必要があります。
手づくりの原理とは、「お金がなくても生きていける力」であり、社会的評価を気にしなくても生きていける力です。
~~~ここまで一部引用
なるほど~。
アイデンティティ問題の根源がここにあるような気がしますね。
「自分らしく」あろうとして、他者との差別化を図る。
しかもそれが「測定可能な(数値化できる)」差別化を目指していること。
ここに最大の矛盾があるように思います。
この本にはお金の例が示されていますが、測定可能な指標で自分らしさを表現することは、原理的に不可能ではないかと僕は思うのです。だって、上には上がいますから。
先日、陸奥さん本人に阿賀町でやってもらったフォトスゴロクの解説本、福島県立博物館「ポリフォニックミュージアム」冊子を改めて読んでいたら、陸奥さんの言葉に!!!としました。
~~~一部引用
僕は普段は「観光家」を名乗って活動している。僕なりの定義では、観光とは「その人の世界観に光を当てて揺さぶること」だと考えている。
「観」というのは、その人の思考や認識、指針、態度、行動を意味する。その人がどのように人生を考えているか?恋愛を捉えているか?仕事をしようとしているか?といったことを表現する時に「観」が使われる。
対象の新しい側面、新しい一面を発見し、その人の思考や認識、指針、態度、行動を変容させる。よりニュートラルになり、よりフラットになり、より自由になっていく。世界観が広がったり、深まったりする。
こうした「観光」を発生させるのに、必要不可欠なものが「他者」だ。「他者」こそは、自分と全く違う世界観を持つ存在であり、想定外のものであるから。
僕は常に、自分にないもの、想定だにしないものとの出会いを求めているし、「他者」と出会う機会、「他者」と共にいる時間、「他者」について考える空間を作りたいと考えている。白河でも僕は「他者」との出会いを求めて逍遥した。
~~~
カッコええなあ、陸奥さん。ステキすぎます。師匠と呼ばせてください。
「手づくりのアジール」の青木さんは、もうひとつの原理を持つ場所として「彼岸の図書館」を奈良県の山奥でやっている。
「フォトスゴロク」の陸奥さんは、全国各地に、自分とは違う世界観に出会う機会と時間、空間を生み出している。
僕も方向性としては、それに近いように思う。
「他者」に触れ合う機会、時間、空間をつくること。
社会(仕事)の原理と生活(暮らし)の原理のあいだに、
リアルな場(メディア)をつくっていくこと。
「みんな」と「他者」と「自分」のあいだを行き来し、また異質な他者と協働しながら、手づくりの原理を大切にしてつくっていく今を重ねていきたい。
この高台に、中途半端であいまいな「アジールのようなもの」をつくっていきたい。




