2022年05月14日
探究の森へようこそ
風舟の正式名称は、探究の森交流館「風舟」。
つまり、探究するための森だ。
昨日話していて出てきたキーワードは
・心身を解放し、五感を発揮すること
・境界をあいまいにすること
・出会うこと、つくること
たぶんこの順番なのかもしれない。
目的・目標に向かう小さなベクトルではなくて、大いなる流れに「委ねてみる」こと。「流れ」とは、空間的には人間社会よりずっと広い森の生態系だったり、時間的には人生よりもずっと長い何百年単位の歴史だったりするのだろう。
たぶんそこに「身を置く」ことが大切なのだと思う。「原点」とは、始まり、スタートラインであると共に、様々なリレーの中継ランナーとしてここに存在する、という物語の終着点でもある。
そこに身を置くことができる「場」を作っていきたいと思った。
そんな思いを持ちながら、タイムリーに読み進めている本。
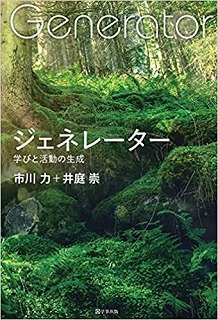
「ジェネレーター まなびと活動の生成」(市川力+井庭崇 学事出版)
読み進めていると
「俺もなかなかいいセン行ってるんじゃないか」と自己肯定感が上がります。(笑)
~~~ここから引用
一人ひとりを、分割不可能なひとつの原子のように捉えるのではなく「いくつもの創造実践を行っている複合」として捉える見方のほうが自然でよりよいと思う。
自分のなかどのような創造実践が含まれているかは、人それぞれ違う。その組み合わせこそが個性と呼び得るものだろう。
さて、そういういくつもの創造実践の複合としての人が集まると何が起こるか。1人では高度なことができないことでも、複数人が集まって、それぞれの創造実践の力と経験を持ち寄ることで、1人ではなし得なかったことを行うことができる。これがコラボレーションということである。
~~~
「アイデンティティ(自分らしさ)の危機」問題とその解決法。「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」という大学生に出会ってから研究してきたテーマ。
僕はそれを「場のチカラ」で解決しようとしてきた。実践の場は、にいがたイナカレッジ、取材型インターン「ひきだし」、そして高校の探究の授業だった。
「自分」という輪郭を溶かし、「場」の一員となること。「創造する場の一員となった」という経験を積み重ねること。その積み重ねと組み合わせがその人のアイデンティティをつくるということ。
「存在は創造のエッジにある」そんな仮説。
http://hero.niiblo.jp/e491178.html
(20.11.10)
それはまさに試行錯誤のプロセスの途中にあったわけだけど、この本を読んで、その創造には「ジェネレーター」的な関わりが必要なのだと実感した。
第2部 ジェネレーターの役割のところの5G(禺)の話が面白かったので、引用します。
1 遭遇:いつでも遭遇しているというマインドセット
2 偶然:たまたまつながる偶然な発見
3 隅:隅っこから始まるのを厭わない
4 愚:まずは愚直に続ける
5 寓:追いかけた先に物語(寓話)が生まれる
いいですね。本書にも書いてありますがクランボルツ博士の「計画された偶発性理論」にも通じる5Gの話。僕はこれを、個人の単位、チームの単位ではなくて「場」の単位でやれないだろうか、と試行錯誤しているのではないか、と。
解決したい課題は「(特に10代20代の)アイデンティティの危機」。
その原因と対策は
1 「やりたいことは何か?」という問いに代表される夢・目標至上主義
⇒学校教育の構造(システム)上の問題(評価を前提としたカリキュラム、目標管理)
⇒「総合的な探究の時間」などで「実践⇒ふりかえり⇒計画」のサイクルを実践してみる
2 共同体の解体
⇒地域、家庭、会社という共同体が解体され、社会と個人が直接向き合わなければならないこと
⇒「場のチカラ」にフォーカスし、創造する一時的な共同体を体感し、その一部であるという実感を得る
3 「自分」そのものの定義
⇒共同体や他者から切り離された存在(個)としての「自分」
⇒場を感じたり、委ねたりして、「自分」という境界をあいまいにする
最大の危機は「存在の承認」問題だと思う。
10代、20代は(いやもしかしたら僕ら世代、いや僕自身も)、「存在の承認」を求めて彷徨っている。
「自分はこの世に存在していていいのだろうか?」
「自分は無価値なのではないか?」
という不安の中にいる。
山竹伸二さんは「存在の承認」と「行為の承認」を分けて考えた方がいいと言います。
http://hero.niiblo.jp/e491900.html
「自由」を取るか「承認」を取るか(21.7.18)
「ジェネレーター」で書かれているように、世の中は、「創造社会」に向かっていくのでしょう。それを突き動かしていくジェネレーター的存在が必要とされるのでしょう。
しかし、その「創造」以前に、「存在の承認」が必要だと思うし、それこそが心理的安全性を高め、創造力の源になっていくと思ってます。
そしてその「存在の承認」においては、「物語の継承」が重要になってくるという仮説をもっています。
探究の森交流館「風舟」のある阿賀町津川は、かつて会津藩の河港として栄え、人、モノ、情報が交流する地域拠点だったという歴史があります。
その物語を継いでいく、ということ。
つくる、という現在から未来に向かってのベクトル。
継ぐ、という過去から現在に向かっているベクトル。
その交差する場所に「存在」と「アイデンティティ」と「創造」を同時に満たす何かがあるんじゃないか、っていうのが僕の仮説です。
つまり、探究するための森だ。
昨日話していて出てきたキーワードは
・心身を解放し、五感を発揮すること
・境界をあいまいにすること
・出会うこと、つくること
たぶんこの順番なのかもしれない。
目的・目標に向かう小さなベクトルではなくて、大いなる流れに「委ねてみる」こと。「流れ」とは、空間的には人間社会よりずっと広い森の生態系だったり、時間的には人生よりもずっと長い何百年単位の歴史だったりするのだろう。
たぶんそこに「身を置く」ことが大切なのだと思う。「原点」とは、始まり、スタートラインであると共に、様々なリレーの中継ランナーとしてここに存在する、という物語の終着点でもある。
そこに身を置くことができる「場」を作っていきたいと思った。
そんな思いを持ちながら、タイムリーに読み進めている本。
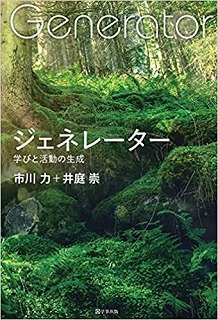
「ジェネレーター まなびと活動の生成」(市川力+井庭崇 学事出版)
読み進めていると
「俺もなかなかいいセン行ってるんじゃないか」と自己肯定感が上がります。(笑)
~~~ここから引用
一人ひとりを、分割不可能なひとつの原子のように捉えるのではなく「いくつもの創造実践を行っている複合」として捉える見方のほうが自然でよりよいと思う。
自分のなかどのような創造実践が含まれているかは、人それぞれ違う。その組み合わせこそが個性と呼び得るものだろう。
さて、そういういくつもの創造実践の複合としての人が集まると何が起こるか。1人では高度なことができないことでも、複数人が集まって、それぞれの創造実践の力と経験を持ち寄ることで、1人ではなし得なかったことを行うことができる。これがコラボレーションということである。
~~~
「アイデンティティ(自分らしさ)の危機」問題とその解決法。「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」という大学生に出会ってから研究してきたテーマ。
僕はそれを「場のチカラ」で解決しようとしてきた。実践の場は、にいがたイナカレッジ、取材型インターン「ひきだし」、そして高校の探究の授業だった。
「自分」という輪郭を溶かし、「場」の一員となること。「創造する場の一員となった」という経験を積み重ねること。その積み重ねと組み合わせがその人のアイデンティティをつくるということ。
「存在は創造のエッジにある」そんな仮説。
http://hero.niiblo.jp/e491178.html
(20.11.10)
それはまさに試行錯誤のプロセスの途中にあったわけだけど、この本を読んで、その創造には「ジェネレーター」的な関わりが必要なのだと実感した。
第2部 ジェネレーターの役割のところの5G(禺)の話が面白かったので、引用します。
1 遭遇:いつでも遭遇しているというマインドセット
2 偶然:たまたまつながる偶然な発見
3 隅:隅っこから始まるのを厭わない
4 愚:まずは愚直に続ける
5 寓:追いかけた先に物語(寓話)が生まれる
いいですね。本書にも書いてありますがクランボルツ博士の「計画された偶発性理論」にも通じる5Gの話。僕はこれを、個人の単位、チームの単位ではなくて「場」の単位でやれないだろうか、と試行錯誤しているのではないか、と。
解決したい課題は「(特に10代20代の)アイデンティティの危機」。
その原因と対策は
1 「やりたいことは何か?」という問いに代表される夢・目標至上主義
⇒学校教育の構造(システム)上の問題(評価を前提としたカリキュラム、目標管理)
⇒「総合的な探究の時間」などで「実践⇒ふりかえり⇒計画」のサイクルを実践してみる
2 共同体の解体
⇒地域、家庭、会社という共同体が解体され、社会と個人が直接向き合わなければならないこと
⇒「場のチカラ」にフォーカスし、創造する一時的な共同体を体感し、その一部であるという実感を得る
3 「自分」そのものの定義
⇒共同体や他者から切り離された存在(個)としての「自分」
⇒場を感じたり、委ねたりして、「自分」という境界をあいまいにする
最大の危機は「存在の承認」問題だと思う。
10代、20代は(いやもしかしたら僕ら世代、いや僕自身も)、「存在の承認」を求めて彷徨っている。
「自分はこの世に存在していていいのだろうか?」
「自分は無価値なのではないか?」
という不安の中にいる。
山竹伸二さんは「存在の承認」と「行為の承認」を分けて考えた方がいいと言います。
http://hero.niiblo.jp/e491900.html
「自由」を取るか「承認」を取るか(21.7.18)
「ジェネレーター」で書かれているように、世の中は、「創造社会」に向かっていくのでしょう。それを突き動かしていくジェネレーター的存在が必要とされるのでしょう。
しかし、その「創造」以前に、「存在の承認」が必要だと思うし、それこそが心理的安全性を高め、創造力の源になっていくと思ってます。
そしてその「存在の承認」においては、「物語の継承」が重要になってくるという仮説をもっています。
探究の森交流館「風舟」のある阿賀町津川は、かつて会津藩の河港として栄え、人、モノ、情報が交流する地域拠点だったという歴史があります。
その物語を継いでいく、ということ。
つくる、という現在から未来に向かってのベクトル。
継ぐ、という過去から現在に向かっているベクトル。
その交差する場所に「存在」と「アイデンティティ」と「創造」を同時に満たす何かがあるんじゃないか、っていうのが僕の仮説です。




