2021年07月18日
「自由」を取るか「承認」を取るか
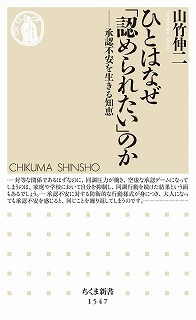
「ひとはなぜ認められたいのか」(山竹伸二 ちくま新書)
本屋「ツルハシブックス」時代(2013年ごろ)近くにあった新潟大学の学生の話を聞いていて、猛烈に印象に残った言葉。
「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」
本人たちにとっては、生きるか死ぬかに値するような大きな問い。
そして、その解決策を
「(自己を分析して)やりたいことが見つかること」「(小さな挑戦と成功により)自分に自信をつけること」
だと思っていること。
本当か?
って思った。
そもそも「やりたいことがわからない」ことが課題なのか?
「やりたいことがわからなくて苦しい」ことが本当の課題なのではないか?
サンクチュアリ出版を立ち上げた高橋歩は著書「LOVE&FREE」の中で言う。
「夢があろうとなかろうと楽しく生きてる奴が最強」だと。
ではなぜ、「やりたいことがわからない」はこんなにも苦しいのか?
その原因について知りたいと思った。(探究の入り口)
ひとつは、いわゆる「キャリア教育」の目標設定・達成型の仕組みが時代・社会に合っていないこと。
(これについては、他の記事でたくさん書いているので今回は触れない)
参考:http://hero.niiblo.jp/e273966.html (夢リテラシー 13.7.18)⇐8年前の今日ですね
もうひとつが、「承認(欲求)」だった。
参考:http://hero.niiblo.jp/e291471.html (承認欲求と他者評価 13.10.24)
この承認には3種類あるっていうのがヒントになって、たくさんの大学生にこの本を薦めた。
1 親和的承認
家族、恋人、親しい友人など、愛情と信頼の関係にある他者によって、「ありのままの自分」を無条件に受け入れてもらっていると感じられるような承認である。
2 集団的承認
集団が共有する価値観・ルールに基づいて行動することで集団にとって必要な存在となり、承認を得ることができる。
3 一般的承認
不特定多数の他者一般から認められること。例えば、災害ボランティアで現地に赴くというのは、なかなかできることではないから、一般的に、素晴らしいことだと思われる。そのような承認。
この本を読んでいて思い出したことがある。2004年の中越地震ボランティアだ。震度7の川口町で長期的に活動していたボランティアのひとりに聞いた。「こんなに仕事休んで大丈夫なんですか?」大丈夫だった。なぜなら仕事をしていなかった、いわゆる「ニート」状態だったからだ。そんな彼を駆動させていたのが被災者からもらう「ありがとう」だったのではないか。そこに「承認」があったのではないか、と改めて思った。
そして、2021年、待望の続編がこの本。
「ひとはなぜ認められたいのか?」
今回もより分かりやすく、時代・社会に合わせる形で(コロナ過の同調圧力とかも書いてあります)「承認」という課題について書いてあります。
まず最初に考えないといけないのは、「存在の承認」と「行為の承認」です。
上でいうところの1親和的承認:ありのままの自分を受け入れてくれることがまさに「存在の承認」です。役に立っているかどうかに関わらず、そこに存在しているだけで価値があるのです。
2集団的承認については、その集団にとって価値のある行為が承認の条件ですから、基本的には「行為の承認」です。学校の部活で、先に出て仲間のために練習の準備をしていたら、仲間から評価され承認されるでしょう。3一般的承認も「行為の承認」要素が多くなります。
ここでもう一つ、本書では「自己承認」というキーワードが出てきます。つまり「自分で自分を承認する」ということです。たとえばSNSでいいね!が付くなど、自己承認を助けてくれるツールもあります。自分が属する集団において承認の不安があっても、社会の中で共有されている価値観を理解していれば自己承認によって乗り越えられる可能性があります。
次に紹介したいのが「自由」と「承認」の葛藤です。
自由への欲望(~したい)と承認への欲望(~すべき)はしばしば葛藤します。自由になりたいと思いながらも、親や先生の言うことを守ることでしか承認が得られないとしたら、それは葛藤することになります。
「承認不安」にどのように対処するのか?について、本文には以下のように書かれています。
~~~
承認への欲望を優先する対処法でよくあるのは、「コミュニケーション・スキルを磨く」というものです。コミュニケーションの上手い人は、周囲の人々の受けもよく、好印象をもたれやすいため、「受け入れられている」「認められている」と感じる機会が多いはずです。
そもそも現代社会は第3次産業が中心で、コミュニケーション能力が仕事の評価に直結しやすい面がありますので、この力があれば承認を得る可能性が非常に高くなります。
周囲に同調し、過剰に場の空気を読み、自分の本音を抑えることでしかコミュニケーションを乗り切れない人は、自由を失い、自己不全感を抱くようになるでしょう。
一方、自由を優先する場合には、「承認を求めずに自分のやりたいことをやる」という態度に徹するやり方があります。
しかし、他人の承認を気にしないですませるためには、自分なりの信念、価値観を信じ、自己承認できなければ難しいと思います。それが独善的自己承認によるものならば、周囲の承認は得られないため、やがて耐えきれなくなり、承認不安が再び募る可能性が高いです。
そもそも承認不安の強い人は、周囲の目など気にするな、自分のしたいこと、すべきことをすればよい、と助言したところで、「それができるなら苦労はしない」と思うはずです。
また、幼い頃から承認不安を抱えてきた人は自分のしたいことを思う存分にした経験が乏しいため、自分がなにをしたいのか、なにをすべきなのか、よくわからないかもしれません。
~~~
これなんじゃないか?
「受験勉強して国立大学に合格する」っていうのは、「承認」を優先したってことなのではないか、って。
だからこそ大学に進学してしまったが最後、評価者(評価してくれる他者)を失い、不安になり、どうすればいいかわからないのではないか?
ここで、承認不安を解決するための自己分析の方法が紹介されています。
1 自分の心の動き(本心)を見つめる
2 したい(欲望)とこわい(不安)が浮かび上がる:自己了解
3 したいのにできない、こわいのはなぜか考える
4 自己ルールを自覚(したいけど、〇〇しなければ、嫌われる)
5 自己ルールの分析(過去の人間関係、出来事を振り返る)
6 自己ルールが歪んでいれば修正する。
これを支援できるとしたら、大切なのは最初の信頼関係づくり、つまり親和的承認です。
これをどうつくっていくか?しかもそれを個人対個人ではなくて、「場」としてつくっていけるか?その「場」の構成要素としては人だけではなく、本とか本棚とかも有効なのではないか。(本棚から人も世界も多様であり、多様であっていいというメッセージを発することができる)
「誰と」「いつ」「どこで」というような瞬間的な「場」と「営み」と呼ばれるような人生を超えた時間軸を合わせもつような空間をつくっていくことなのではないか。
それによって、高校生だけではなく、関わるスタッフも、地域の大人も、「自由」と「承認」を同時に満たしていけるような、そんな場をつくれないだろうか?
これが僕のいまの探究テーマ(問い)です。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |










