2013年09月30日
商店街インターンシップの意義
「インターンシップ」とは
何のためにやるのだろうか?
「成長」とは
いったいなんだろうか?
3年生で始めるインターンシップは
「就職」に向けての準備期間
としての意味合いが濃くなってしまう。
すると、
どうしても「スキルアップ」に
方向が向いてしまう。
だから、
1、2年生で始めるべきだと思う。
その場合、「成長」とは何か?
もっとも大切なのは、
「試作マインド」を身に付けることだと僕は思う。
やってみた。
うまくいった。うまくいかなかった。
ふりかえる。
またやってみる。
就職試験というのは、
ある意味、失敗が許されない(と思い込んでいるだけだが)。
人生は失敗だらけだ。
そして、敗者復活戦だ。
それを体感することこそ、
1、2年次でやるべきことだと思う。
そうだとすると、
商店街インターンシップは非常に魅力的だ。
試しにやってみる。
失敗する。
リカバリーする。
そんな繰り返しができる。
そこにさらに
「共感」、特に「課題共感」を生んでいけるかが
ポイントになってくるのだろう。
マクロ視点とミクロ視点を組み合わせて
プログラムを作っていく必要がある。
フレッシュ本町商店街で一番感じたのは、
ひとつは、「若いというだけで価値がある」という
圧倒的な自己承認と
たくさんの差し入れをもらって、
商店街の人に喜んでもらいたいと行動した。
「行動する」「はたらく」の原動力は
恩返しであると体感できたことだろう。
その先に、
長期的視点や経済的視点を
入れていくこと。
この経験が、人生を創っていく。
これが5年後に確信に変わっていくことを信じて、
今は僕が試作をしていくときだ。
何のためにやるのだろうか?
「成長」とは
いったいなんだろうか?
3年生で始めるインターンシップは
「就職」に向けての準備期間
としての意味合いが濃くなってしまう。
すると、
どうしても「スキルアップ」に
方向が向いてしまう。
だから、
1、2年生で始めるべきだと思う。
その場合、「成長」とは何か?
もっとも大切なのは、
「試作マインド」を身に付けることだと僕は思う。
やってみた。
うまくいった。うまくいかなかった。
ふりかえる。
またやってみる。
就職試験というのは、
ある意味、失敗が許されない(と思い込んでいるだけだが)。
人生は失敗だらけだ。
そして、敗者復活戦だ。
それを体感することこそ、
1、2年次でやるべきことだと思う。
そうだとすると、
商店街インターンシップは非常に魅力的だ。
試しにやってみる。
失敗する。
リカバリーする。
そんな繰り返しができる。
そこにさらに
「共感」、特に「課題共感」を生んでいけるかが
ポイントになってくるのだろう。
マクロ視点とミクロ視点を組み合わせて
プログラムを作っていく必要がある。
フレッシュ本町商店街で一番感じたのは、
ひとつは、「若いというだけで価値がある」という
圧倒的な自己承認と
たくさんの差し入れをもらって、
商店街の人に喜んでもらいたいと行動した。
「行動する」「はたらく」の原動力は
恩返しであると体感できたことだろう。
その先に、
長期的視点や経済的視点を
入れていくこと。
この経験が、人生を創っていく。
これが5年後に確信に変わっていくことを信じて、
今は僕が試作をしていくときだ。
2013年09月29日
ツルハシ一箱古本市~出店者募集
昨年も開催しました、
ツルハシ一箱古本市
今年はなんと、2日連続開催します。

注:斎藤優介さんが参加決定しているわけではございません。出演感謝!!
いつもお世話になっている
ツルハシブックスユーザーの
皆様の交流の場でもあります。
10月5日(土)10:00~15:00
Whats niigata オープニングイベント
@万代橋ちかくのやすらぎ堤(ホテルオークラ側)
http://nvision-pjt.jp/event/20130918_298.html
10月6日(日)11:00~15:00
@西区役所出張所(内野駅前)
うちのDEアートの
アートマルシェ内でこじんまりとやっています。
http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~bijyutsuka/uchino/top.html
参加費500円です。(1日でも2日でも同じです!)
先着5名まで、受付しています。
申し込みは西田まで。
直前の告知で申し訳ありませんが、
お待ちしています。
ツルハシ一箱古本市
今年はなんと、2日連続開催します。

注:斎藤優介さんが参加決定しているわけではございません。出演感謝!!
いつもお世話になっている
ツルハシブックスユーザーの
皆様の交流の場でもあります。
10月5日(土)10:00~15:00
Whats niigata オープニングイベント
@万代橋ちかくのやすらぎ堤(ホテルオークラ側)
http://nvision-pjt.jp/event/20130918_298.html
10月6日(日)11:00~15:00
@西区役所出張所(内野駅前)
うちのDEアートの
アートマルシェ内でこじんまりとやっています。
http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~bijyutsuka/uchino/top.html
参加費500円です。(1日でも2日でも同じです!)
先着5名まで、受付しています。
申し込みは西田まで。
直前の告知で申し訳ありませんが、
お待ちしています。
2013年09月28日
「colorful」発売されました~祝!うちのDEアート開幕
うちのDEアート、本日開幕します。
(9月28日~10月13日)
ツルハシブックスでは映像作品の放映をやっています。

そして、間に合いました。
yuuki nakazawaの
新アルバム「colorful」
が発売されました。
待望の。
本当に待望の1枚です。
この中の6曲目「十人十色」。
僕の中でいちばん大好きな一曲です。
聞いているだけで、
ああ、俺は俺でいいんだ。
今日から一歩、また踏み出していこう。
そんな気持ちにさせてくれる1曲です。
去年のクリスマスライブで、
アンコールしてしまいました。
これを書いている今もリピートでかかっています。
胸がキュンとなります。
中澤友希、プロデビューアルバム
「colorful」は1800円。
ツルハシブックスに80枚、取り扱い中です。
BGMにもかかっていますので聞いてみてください。
新潟が生んだピアニスト、
中澤友希をどうか応援よろしくお願いします!
オフィシャルサイトはコチラ。
http://yuukinakazawa.com/
(9月28日~10月13日)
ツルハシブックスでは映像作品の放映をやっています。

そして、間に合いました。
yuuki nakazawaの
新アルバム「colorful」
が発売されました。
待望の。
本当に待望の1枚です。
この中の6曲目「十人十色」。
僕の中でいちばん大好きな一曲です。
聞いているだけで、
ああ、俺は俺でいいんだ。
今日から一歩、また踏み出していこう。
そんな気持ちにさせてくれる1曲です。
去年のクリスマスライブで、
アンコールしてしまいました。
これを書いている今もリピートでかかっています。
胸がキュンとなります。
中澤友希、プロデビューアルバム
「colorful」は1800円。
ツルハシブックスに80枚、取り扱い中です。
BGMにもかかっていますので聞いてみてください。
新潟が生んだピアニスト、
中澤友希をどうか応援よろしくお願いします!
オフィシャルサイトはコチラ。
http://yuukinakazawa.com/
2013年09月27日
物を書いたり、編集したりする仕事は、生き方の集積なのだ
「物を書いたり、編集したりする仕事は、生き方の集積なのだ」(見城徹)
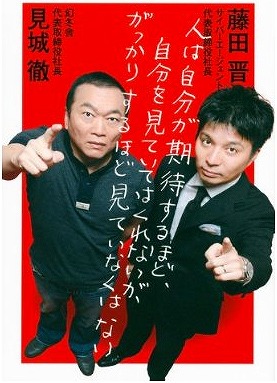
人は自分が期待するほど、自分を見ていてはくれないが、がっかりするほど見ていなくはない(講談社)
現在は文庫化されてます。

絶望しきって死ぬために、今を熱狂して生きろ (講談社プラスアルファ文庫)
すごいよ。
さすが幻冬舎、伝説の社長。
この中で強烈なのが、
「講演会、養成講座、人材交流会は人をダメにする三悪である。」
と言い切る見城さん。
~~~ここから引用
講演会や養成講座、人材交流会は、
そこで何かを得られた、出席して良かったという、
誤解や自己満足で成り立っているのだから
世の中にこれほど罪深いものはない。
僕の人生は僕だけのものだ。
僕の話を聞いたからといって、
同じように生きられるわけがない。
講演を聞いて、自分の人生を変えようと思うなど
他力本願もはなはだしい。
人生とは、打ちのめされたり、圧倒的努力をして戦ったりして、
障壁を乗り越えてゆくものだ。
人の話から何かを得たり、
ビジネスに役立てようという考え自体が安易なのである。
~~~ここまで引用
とバッサリ。
僕自身はそんなに好んではいかないけど、
好きな著者だったら、実際にお会いして空気感を感じたいと思う。
で、シビれたのは冒頭の一言。
「物を書いたり、編集したりする仕事は、生き方の集積なのだ。
養成講座に通うより、自分の人生に真摯に向き合った方が、
よほど優れたライターや編集者になれる。小手先のテクニックなど意味がない。
これは程度の差こそあれ、すべての仕事に言えることだ。」
いいですね。
たしかにそうだな。
全ての仕事は生き方の集積なのですね。
熱いぜ、見城さん。
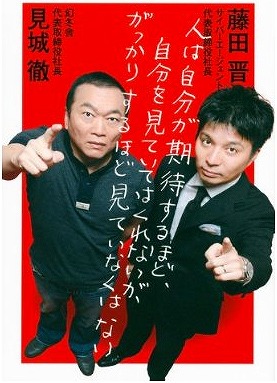
人は自分が期待するほど、自分を見ていてはくれないが、がっかりするほど見ていなくはない(講談社)
現在は文庫化されてます。

絶望しきって死ぬために、今を熱狂して生きろ (講談社プラスアルファ文庫)
すごいよ。
さすが幻冬舎、伝説の社長。
この中で強烈なのが、
「講演会、養成講座、人材交流会は人をダメにする三悪である。」
と言い切る見城さん。
~~~ここから引用
講演会や養成講座、人材交流会は、
そこで何かを得られた、出席して良かったという、
誤解や自己満足で成り立っているのだから
世の中にこれほど罪深いものはない。
僕の人生は僕だけのものだ。
僕の話を聞いたからといって、
同じように生きられるわけがない。
講演を聞いて、自分の人生を変えようと思うなど
他力本願もはなはだしい。
人生とは、打ちのめされたり、圧倒的努力をして戦ったりして、
障壁を乗り越えてゆくものだ。
人の話から何かを得たり、
ビジネスに役立てようという考え自体が安易なのである。
~~~ここまで引用
とバッサリ。
僕自身はそんなに好んではいかないけど、
好きな著者だったら、実際にお会いして空気感を感じたいと思う。
で、シビれたのは冒頭の一言。
「物を書いたり、編集したりする仕事は、生き方の集積なのだ。
養成講座に通うより、自分の人生に真摯に向き合った方が、
よほど優れたライターや編集者になれる。小手先のテクニックなど意味がない。
これは程度の差こそあれ、すべての仕事に言えることだ。」
いいですね。
たしかにそうだな。
全ての仕事は生き方の集積なのですね。
熱いぜ、見城さん。
2013年09月26日
振り返りの重要性
3週間のインターンシップ期間中
「振り返り」をこれでもか、というくらいやる。
プロジェクトの振り返り
個人振り返り
そして、振り返りの振り返り
これらを徹底してやることが必要だ。
ただ、振り返りを書いて、
シェアするのではなく、
学びを深めるための質問をする。
森田英一さんの言う「貢献する質問」。
「貢献する質問」を意識することで、
学生同士が相互コーチングができるようになる。
個人目標の設定。
これもインターン中に書いてもらうのではなく、
自分のペースで、過去を振り返り、
事前、中間、事後で見直してみること。
やはり個人面談が必要で、
丁寧に目的・目標を確認していくこと。
どうしても、プロジェクトの進捗に
アタマが引っ張られてしまうから、
それを切り替えていく必要がある。
今回の活動を踏まえて、
次回への改善策は
1 事前・中間・事後の個人面談を行い、インターンの意味づけ、目的・目標を確認する。
2 メンバー同士のバックボーン共有をもっと早い段階で行う。ex「人生モチベーショングラフ」など
3 会議ファシリテーション技術を4日目5日目にレクチャーする。(会議ルール、司会の役割、メモ手法など)
ex「AかBか選ぶ会議ではなく、いいアイデア(解決策)を出す会議の重要性
4 案件ごとの振り返りシートを作成する。(A3用紙に全員メモ形式で振り返り、まとめる)
5 プロジェクト振り返りと個人振り返りを明確に分ける。(シートを分ける、時間を分ける)
6 5に応じて、翌日の目標設定を行い、それを記入するシートをつくる。
7 目的と手段が逆転しやすいので、「成果とは何か」という問いをベースに目的と手段を確認する問いかけを継続する。
キーワード
・コミュニケーション力は0が1になるのではなく、0と1の間に無限に広がっている。⇒慣れの問題
・「あなたのことを知りたい」がヒアリングの基本
・恩返しが行動の源泉
・深い話ができるために、慣れてきたら1人ずつヒアリングに行くのもあり。
・目的⇒課題⇒方法という思考の確認
オペレーション
・15:30~16:00 プロジェクト振り返り
・16:00~16:30 個人振り返り
・16:30~17:00 相互コーチング・翌日の目標設定
・プレゼン前日はプレゼン作成に集中させる。(15日間+2日が必要)
・プレゼン当日は午前はリハーサルをする。(合宿もあり)
以上、私の3週間振り返りでした。
「振り返り」をこれでもか、というくらいやる。
プロジェクトの振り返り
個人振り返り
そして、振り返りの振り返り
これらを徹底してやることが必要だ。
ただ、振り返りを書いて、
シェアするのではなく、
学びを深めるための質問をする。
森田英一さんの言う「貢献する質問」。
「貢献する質問」を意識することで、
学生同士が相互コーチングができるようになる。
個人目標の設定。
これもインターン中に書いてもらうのではなく、
自分のペースで、過去を振り返り、
事前、中間、事後で見直してみること。
やはり個人面談が必要で、
丁寧に目的・目標を確認していくこと。
どうしても、プロジェクトの進捗に
アタマが引っ張られてしまうから、
それを切り替えていく必要がある。
今回の活動を踏まえて、
次回への改善策は
1 事前・中間・事後の個人面談を行い、インターンの意味づけ、目的・目標を確認する。
2 メンバー同士のバックボーン共有をもっと早い段階で行う。ex「人生モチベーショングラフ」など
3 会議ファシリテーション技術を4日目5日目にレクチャーする。(会議ルール、司会の役割、メモ手法など)
ex「AかBか選ぶ会議ではなく、いいアイデア(解決策)を出す会議の重要性
4 案件ごとの振り返りシートを作成する。(A3用紙に全員メモ形式で振り返り、まとめる)
5 プロジェクト振り返りと個人振り返りを明確に分ける。(シートを分ける、時間を分ける)
6 5に応じて、翌日の目標設定を行い、それを記入するシートをつくる。
7 目的と手段が逆転しやすいので、「成果とは何か」という問いをベースに目的と手段を確認する問いかけを継続する。
キーワード
・コミュニケーション力は0が1になるのではなく、0と1の間に無限に広がっている。⇒慣れの問題
・「あなたのことを知りたい」がヒアリングの基本
・恩返しが行動の源泉
・深い話ができるために、慣れてきたら1人ずつヒアリングに行くのもあり。
・目的⇒課題⇒方法という思考の確認
オペレーション
・15:30~16:00 プロジェクト振り返り
・16:00~16:30 個人振り返り
・16:30~17:00 相互コーチング・翌日の目標設定
・プレゼン前日はプレゼン作成に集中させる。(15日間+2日が必要)
・プレゼン当日は午前はリハーサルをする。(合宿もあり)
以上、私の3週間振り返りでした。
2013年09月25日
答えより問い
大学時代に学ばなければならないことは
たくさんあるだろうけど、
もっとも大切だと思うのは、
「問い」の重要性ではないだろうか。
先日。
インターンの振り返りをしていたとき。
「今回の活動を振り返り、どのように改善したらよいか?」
というようなお題に対して、たくさんの案が出てきたの。
「その中でベスト5を決めてください」
と言ったら、即座に多数決を取ろうとした学生たち。
「多数決ではなくて、話し合いで決めてください。」
と言うと、少し戸惑いながら、
ひとりひとりがコメントをして、なんとかベスト5が決まった。
高校生までは、
何か正解があって、しかもそれはだいたいが
先生というか大人が握っていて、
それに正答することに価値があると思ってきた。
あるいは、会議とは
AかBかCのどれが正解かを決めることであって、
AでもBでもCでもないZを生み出す会議なんて聞いたことがなかった。
そうか。
そこに藤原さんたちがやっていた
よのなか科の実践がチャレンジしていたのだなあと思った。
「正解」から「納得解」へ。いま、その意味が実感できる。
世の中にも、人生にも正解なんてないのだから、
答えを求める自分と決別しなければならない。
そのための有効な手法が
商店街インターンシップなのだと思う。
企業インターンシップと違い、
「売り上げが上がる」ことや
「効率的にやること」だけに価値があるのではない。
そもそも「価値とはなんだろうか?」
という問いを持たなければいけない。
そこで立てた仮説に対して、
アクションを起こして、検証していく。
それがうまくいく場合もあるし、
うまくいかない時の方が多いだろう。
そのときに、どのくらい振り返りができるか?
そこがポイントになってくる。
うまくいったとき、いかなかったとき。
どうしてそうなったのか?
と問い、それを次のアクションにつなげていくこと。
「試作力」
これがこれからの時代に必要となってくるだろう。
答えより問い。
それをいかに言葉でなく伝えるか。
これがコーディネーターの腕の見せ所である。
たくさんあるだろうけど、
もっとも大切だと思うのは、
「問い」の重要性ではないだろうか。
先日。
インターンの振り返りをしていたとき。
「今回の活動を振り返り、どのように改善したらよいか?」
というようなお題に対して、たくさんの案が出てきたの。
「その中でベスト5を決めてください」
と言ったら、即座に多数決を取ろうとした学生たち。
「多数決ではなくて、話し合いで決めてください。」
と言うと、少し戸惑いながら、
ひとりひとりがコメントをして、なんとかベスト5が決まった。
高校生までは、
何か正解があって、しかもそれはだいたいが
先生というか大人が握っていて、
それに正答することに価値があると思ってきた。
あるいは、会議とは
AかBかCのどれが正解かを決めることであって、
AでもBでもCでもないZを生み出す会議なんて聞いたことがなかった。
そうか。
そこに藤原さんたちがやっていた
よのなか科の実践がチャレンジしていたのだなあと思った。
「正解」から「納得解」へ。いま、その意味が実感できる。
世の中にも、人生にも正解なんてないのだから、
答えを求める自分と決別しなければならない。
そのための有効な手法が
商店街インターンシップなのだと思う。
企業インターンシップと違い、
「売り上げが上がる」ことや
「効率的にやること」だけに価値があるのではない。
そもそも「価値とはなんだろうか?」
という問いを持たなければいけない。
そこで立てた仮説に対して、
アクションを起こして、検証していく。
それがうまくいく場合もあるし、
うまくいかない時の方が多いだろう。
そのときに、どのくらい振り返りができるか?
そこがポイントになってくる。
うまくいったとき、いかなかったとき。
どうしてそうなったのか?
と問い、それを次のアクションにつなげていくこと。
「試作力」
これがこれからの時代に必要となってくるだろう。
答えより問い。
それをいかに言葉でなく伝えるか。
これがコーディネーターの腕の見せ所である。
2013年09月24日
自分を経営する
green drinks 新潟内野 第2回のゲスト
やっぱり人前で話すのは難しくて、
特にパワポなしのフリートークだと
どこにクライマックスがきているのか、分からないので
ちょっと不完全燃焼でした。
僕は話題提供者だから
もっと話は短くてよかったのかも。
いろんな質問をもらいました。
・働くとは?
・3年勤める必要はあるのか?
・モチベーションをどうキープするのか?
・仕事をどう選択したらいいのか?
・ブラック企業の見分け方
全てに答えていったわけではないので、
ちょっと考えを整理する。
昨日のポイントは、
もっとも大切なのは、「感性」を大切にする。
それって、
会社で言えば、「コンセプト」のことだと思う。
一方、人には「芯のある人」というのがある。
これはきっと会社で言えば、「ビジョン」ということになる。
ナリワイ時代を迎えつつある今。
「自分を経営する」ということが
とても必要なのだろうなあと改めて思った。
メインの仕事(=本業)があって、
その休みの時にいろいろ活動し、
本業へのエネルギーを蓄えたり、
人脈を広げたりする、
いわば「メイン商品経営」型作戦
ナリワイ的仕事を多数組み合わせて
自分の人生をカタチ作っていく、
「多角化経営」型作戦
大好きな趣味があって、
それを中心に仕事をつないで生きていく
「遊びメイン型」作戦
大切なのは、自分を経営するということ
なのかもしれない。
「人のつながり」
これは経営の何よりの財産になる。
green drinksもそのための1歩になればいい。
やっぱり人前で話すのは難しくて、
特にパワポなしのフリートークだと
どこにクライマックスがきているのか、分からないので
ちょっと不完全燃焼でした。
僕は話題提供者だから
もっと話は短くてよかったのかも。
いろんな質問をもらいました。
・働くとは?
・3年勤める必要はあるのか?
・モチベーションをどうキープするのか?
・仕事をどう選択したらいいのか?
・ブラック企業の見分け方
全てに答えていったわけではないので、
ちょっと考えを整理する。
昨日のポイントは、
もっとも大切なのは、「感性」を大切にする。
それって、
会社で言えば、「コンセプト」のことだと思う。
一方、人には「芯のある人」というのがある。
これはきっと会社で言えば、「ビジョン」ということになる。
ナリワイ時代を迎えつつある今。
「自分を経営する」ということが
とても必要なのだろうなあと改めて思った。
メインの仕事(=本業)があって、
その休みの時にいろいろ活動し、
本業へのエネルギーを蓄えたり、
人脈を広げたりする、
いわば「メイン商品経営」型作戦
ナリワイ的仕事を多数組み合わせて
自分の人生をカタチ作っていく、
「多角化経営」型作戦
大好きな趣味があって、
それを中心に仕事をつないで生きていく
「遊びメイン型」作戦
大切なのは、自分を経営するということ
なのかもしれない。
「人のつながり」
これは経営の何よりの財産になる。
green drinksもそのための1歩になればいい。
2013年09月23日
「自由」による不幸

「そろそろ会社辞めようかな」と思っている人に一人でも食べていける知識をシェアしようじゃないか。
(山口揚平 アスキーメディアワークス)
本日のgreen drinksのために、
もういちど読み直す。
いきなり冒頭からガツンと来ます。
~~~ここから引用(一部省略)
「三丁目の夕日」の時代が幸福だったのは、
日本が高度経済成長期にあったからではなくて、
生き方の選択肢が少なかったからではないでしょうか。
希望をもって生きることができたのは、
日本人の人生パターンが今よりも単純な時代だったからとも思えます。
現在の若者の不幸は経済的貧困によるのではなく、
本当は主体的に人生を選択する勇気と知識の欠如によるものなのです」
自由であるというのは辛いことです。
選択を自らしなければならないという点において、
僕たちは不幸なのです。
それでも、好むと好まざるとにかかわらず、
僕たちは現在の日本に生まれ、
これからの自分の人生を選択していかなければいけません。
~~~ここまで引用
なるほど。
自ら選択しなければいけないというのは
たしかに辛いことなのかもしれない。
いま。
時代が転換期に来ていると言われる。
山口さんが言うように、
こういう激変期に、働こうとしても
搾取される場合が多い、というのは本当だろう。
ニートや引きこもりを
戦略的にやっているとしたら、
それはそれで賢い選択なのだろうと思う。
僕は大学生の地域でのインターンシップなどを7年くらいやりながら、
若者の苦しさ、生きづらさの正体をキャリア的視点から知りたいと思っていた。
その原因は、3つ。
1
工業社会、成長社会が終わり、
「専業」という思想が成り立つ前提が崩れてきた。
2
にも関わらず、日本社会からの
「同調圧力」がものすごい。
3
「同調圧力」にも関わらず、
世の中は、「自分らしく生きよう」と
ひとりで自立して生きていくことを推奨している。
1
「専業」というのは効率化のための手法であって、正解ではない。
工業社会のときに、1つでも多くの、1円でも安いテレビや自動車を
作るための社会システムのことである。
ひとりの人が
材料を集めて、切って貼ってつくるよりも、
分業したほうが速い、つまり効率がいいというだけだ。
しかしながら、
すでに工業製品が大量に売れる時代は終わり、
企業は「多角化」が至上(市場)命題なのに、
そこで働く人たちはなぜか副業が禁止され、
リストラにあったとき、放り出されてしまう。
だから、週末起業ではないけれど、
個人が様々な仕事を持っていることはかなり重要だし、
必ずしも正社員で働くことにはメリットはあまりない。
2
それにも関わらず、
太古の昔、農業が始まったときから、
日本社会の同調圧力はものすごく、
(そうしないと米が獲れないからね)
それが多様な生き方にブレーキをかけているし、
世間的には圧倒的少数派であるということで、
ニートや引きこもりを精神的に苦しめている。
3
「同調圧力」にも関わらず、
「自分らしく生きろ」というメッセージを
受け続けているので、
どうしたらいいか分からないダブルバインド状態に置かれている。
この3つの課題をクリアしていくために、
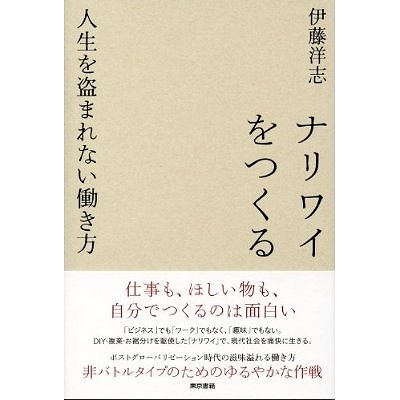
「ナリワイをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)
がもっとも熱く、無理なく、楽しく
やれることなのかなあと今は思っています。
なんだか、
TMネットワークの「Seven days war」が
流れてきますね。
Seven days war 戦うよ
僕たちの場所 この手で守るため
Seven days war Get place to live
ただ素直に生きるために
2013年09月22日
空間デザインと対話デザイン
「場」づくりというのは、
「空間デザイン」と「対話(コミュニケーション)デザイン」
から構成される。
「空間デザイン」
たとえば、イベントなどで、イスの配置を変える。
「対話デザイン」
たとえば、偏愛マップのようなツールを使って自己紹介する。
ツルハシブックスでは、
今井さんが「空間デザイン」をプロデュースし、
僕は「対話デザイン」を考えている。
昨日から粟島にアンケート調査で来ている。
初対面でも
「アンケート調査」だと言われると、
距離が縮まる気がする。
そして、
アンケート項目の序盤に
「人には教えたくない粟島のステキな場所」
という質問があるので、これを対話によって引き出すことで
2人の距離は縮まっていく。
コミュニケーションの鉄則はただひとつ。
「あなたのことをもっと知りたい」という姿勢だ。
それをアンケートやインタビューといった方法、
あるいはその中にある小さな質問で表現していくこと。
こういうのを考えるのが好きなのだなあと
ひとり実感していました。
昨日は釣りもしてましたので、
初対面でも仲良くなれる協働作業、
とてもいいですね。

人生最高のアサヒスーパードライが飲める粟島で、
みなさんの会社も研修してみませんか?
チームワークを高める、
コミュニケーション・デザイン、承ります。
「空間デザイン」と「対話(コミュニケーション)デザイン」
から構成される。
「空間デザイン」
たとえば、イベントなどで、イスの配置を変える。
「対話デザイン」
たとえば、偏愛マップのようなツールを使って自己紹介する。
ツルハシブックスでは、
今井さんが「空間デザイン」をプロデュースし、
僕は「対話デザイン」を考えている。
昨日から粟島にアンケート調査で来ている。
初対面でも
「アンケート調査」だと言われると、
距離が縮まる気がする。
そして、
アンケート項目の序盤に
「人には教えたくない粟島のステキな場所」
という質問があるので、これを対話によって引き出すことで
2人の距離は縮まっていく。
コミュニケーションの鉄則はただひとつ。
「あなたのことをもっと知りたい」という姿勢だ。
それをアンケートやインタビューといった方法、
あるいはその中にある小さな質問で表現していくこと。
こういうのを考えるのが好きなのだなあと
ひとり実感していました。
昨日は釣りもしてましたので、
初対面でも仲良くなれる協働作業、
とてもいいですね。

人生最高のアサヒスーパードライが飲める粟島で、
みなさんの会社も研修してみませんか?
チームワークを高める、
コミュニケーション・デザイン、承ります。
2013年09月21日
「わかりやすく」ある必要はない
世の中はグラデーションだ。
白か黒かではなくて、
「白と黒のその間に無限の色が広がって」(by Mr.children 「gift」)
いるのだろうと思う。
人は自分に理解できないのは気持ち悪いから、
「白」か「黒」かどちらかでないと困る。
「コミュニケーション力」も「リーダーシップ」も
0が1になるなんてことは決してない。
「0」と「1」の間に
無限の段階があって、
しかもそれは徐々に上がっていくわけではなくて
気がついたら、ついているのだ。
それを教育システムの中で評価をするのは
非常に難しいのだけど。
「ナリワイをつくる」に出ている専業思想もそうだ。
本業はなんですか?
僕もここ13年くらい、ずっと言われ続けたけど、
そもそもその質問ってなんのためにするのか?
自分が簡単に理解するためではないのか。
とりあえず本屋さんって言えるようになって
ホッとしている僕もいるのだけど。
「わかりやすく」ある必要は本当はないのかもしれない。
「わからない」ときに、どれくらい、対話ができるか。
それのほうが大切だと思う。
反対に、この人は公務員だから、銀行員だから、
きっとしっかり者でカタいんだろうとか、
決めてしまうことの方が人生の幅を狭める。
わかりやすくするのではなく、
対話を通して、少しずつ理解しようとすること。
そこからなのではないか。
世の中には無限の色が広がっているのです。
白か黒かではなくて、
「白と黒のその間に無限の色が広がって」(by Mr.children 「gift」)
いるのだろうと思う。
人は自分に理解できないのは気持ち悪いから、
「白」か「黒」かどちらかでないと困る。
「コミュニケーション力」も「リーダーシップ」も
0が1になるなんてことは決してない。
「0」と「1」の間に
無限の段階があって、
しかもそれは徐々に上がっていくわけではなくて
気がついたら、ついているのだ。
それを教育システムの中で評価をするのは
非常に難しいのだけど。
「ナリワイをつくる」に出ている専業思想もそうだ。
本業はなんですか?
僕もここ13年くらい、ずっと言われ続けたけど、
そもそもその質問ってなんのためにするのか?
自分が簡単に理解するためではないのか。
とりあえず本屋さんって言えるようになって
ホッとしている僕もいるのだけど。
「わかりやすく」ある必要は本当はないのかもしれない。
「わからない」ときに、どれくらい、対話ができるか。
それのほうが大切だと思う。
反対に、この人は公務員だから、銀行員だから、
きっとしっかり者でカタいんだろうとか、
決めてしまうことの方が人生の幅を狭める。
わかりやすくするのではなく、
対話を通して、少しずつ理解しようとすること。
そこからなのではないか。
世の中には無限の色が広がっているのです。
2013年09月20日
遠回りした学びこそ価値
15日間のインターンシッププログラムが終了。
今回のお題は、商店街の人たちとコミュニケーションを取りながら、
一緒に何ができるか、考え、実行するというプラン。
1週目。
うまくヒアリングができない。
だから、何も頼まれない。
マップ作りと料理イベントの開催を思いつく。
そのプロセスで
マップ作りが目的化してしまい、
そもそも、なぜマップなのか?
なぜ料理イベントなのか?
という思考が浅いことに気づき、
2週目で再びヒアリングを開始。
20件の案件をこなしながら、徐々にヒアリングができていく。
やっとエンジンがかかってきたところで終わり。
お茶屋さんに飾ったマップは、
なかなかいいものができたと思う。

振り返りの時間。
いつも、この瞬間、僕は天職だと思うのです。
いい空気感。
個人とグループの振り返りのやりとり。
学生のひとりが言いました。
「今までは効率よくやることに価値があると思ってきたけど、
遠回りしたことで見えてきたものがあるし、このメンバーでよかったと思えた。」
そうそう。
それです。
みなさんが生きていく世の中は、
答えのない世の中です。
目の前の人と対話し、一緒に考え、実行していくこと。
そして失敗し、振り返り、またチャレンジしていくこと。
その繰り返し以外の方法はないのです。
「なんのためにやっているのか?」
「何が価値なのか?」
そんなことを考えながら、対話を、アクションを続けていくこと。
それを体感することが大学時代に必要な経験なのだと思います。
そして下本町商店街のみなさんには
多大なご協力と大量の差し入れを頂きました。
ちょうどタイミングよく
「評価と贈与の経済学」(内田樹 岡田斗司夫 徳間ポケット)
を読んでいて、このインターンシップの価値が
おぼろげながら見えてきました。
~~~ここから引用
仕事をもらいに行くのではなく、
「何かやることありますか?」というお手伝いをしに行く。
無理やり仕事を作る。
そういったことも大切ですよね。
(中略)
親切って使ったら目減りするものじゃないから。
親切にすればするほど、親切の総量は増えていく。
親切にされた人は他の人にも親切にするから。
(中略)
自分が他人から何をしてもらえるかよりも先に、
自分が他人に何をしてあげられるかを考える人間だけが
贈与のサイクルに入ることができる。
~~~ここまで引用
こういう理論の実践の場、体感の場
が今回のインターンシップだったのかもしれません。
人のモチベーションは
贈り物をもらったときに、そのお返しをしたいということで高まる。
「贈与と反対給付」
これが経済の原点でもあり、行動の原点でもある。
やる前から、「これをやったらどんなメリットや意味があるんだ?」
と問いを立てているようでは、なにも始まりません。
やる前の意味づけが非常に難しい
インターンシップですが、やる意義はすごくある取り組みです。
下本町商店街の皆様、
貴重な機会をありがとうございました。
また一緒に素敵な瞬間つくっていきましょう。
今回のお題は、商店街の人たちとコミュニケーションを取りながら、
一緒に何ができるか、考え、実行するというプラン。
1週目。
うまくヒアリングができない。
だから、何も頼まれない。
マップ作りと料理イベントの開催を思いつく。
そのプロセスで
マップ作りが目的化してしまい、
そもそも、なぜマップなのか?
なぜ料理イベントなのか?
という思考が浅いことに気づき、
2週目で再びヒアリングを開始。
20件の案件をこなしながら、徐々にヒアリングができていく。
やっとエンジンがかかってきたところで終わり。
お茶屋さんに飾ったマップは、
なかなかいいものができたと思う。

振り返りの時間。
いつも、この瞬間、僕は天職だと思うのです。
いい空気感。
個人とグループの振り返りのやりとり。
学生のひとりが言いました。
「今までは効率よくやることに価値があると思ってきたけど、
遠回りしたことで見えてきたものがあるし、このメンバーでよかったと思えた。」
そうそう。
それです。
みなさんが生きていく世の中は、
答えのない世の中です。
目の前の人と対話し、一緒に考え、実行していくこと。
そして失敗し、振り返り、またチャレンジしていくこと。
その繰り返し以外の方法はないのです。
「なんのためにやっているのか?」
「何が価値なのか?」
そんなことを考えながら、対話を、アクションを続けていくこと。
それを体感することが大学時代に必要な経験なのだと思います。
そして下本町商店街のみなさんには
多大なご協力と大量の差し入れを頂きました。
ちょうどタイミングよく
「評価と贈与の経済学」(内田樹 岡田斗司夫 徳間ポケット)
を読んでいて、このインターンシップの価値が
おぼろげながら見えてきました。
~~~ここから引用
仕事をもらいに行くのではなく、
「何かやることありますか?」というお手伝いをしに行く。
無理やり仕事を作る。
そういったことも大切ですよね。
(中略)
親切って使ったら目減りするものじゃないから。
親切にすればするほど、親切の総量は増えていく。
親切にされた人は他の人にも親切にするから。
(中略)
自分が他人から何をしてもらえるかよりも先に、
自分が他人に何をしてあげられるかを考える人間だけが
贈与のサイクルに入ることができる。
~~~ここまで引用
こういう理論の実践の場、体感の場
が今回のインターンシップだったのかもしれません。
人のモチベーションは
贈り物をもらったときに、そのお返しをしたいということで高まる。
「贈与と反対給付」
これが経済の原点でもあり、行動の原点でもある。
やる前から、「これをやったらどんなメリットや意味があるんだ?」
と問いを立てているようでは、なにも始まりません。
やる前の意味づけが非常に難しい
インターンシップですが、やる意義はすごくある取り組みです。
下本町商店街の皆様、
貴重な機会をありがとうございました。
また一緒に素敵な瞬間つくっていきましょう。
2013年09月19日
その常識は人を幸せにするのか?
「常識だから」という理由で、不幸になっていないか。
「常識だから」と言われて、窮屈な思いをしていないか。
「常識だから」と思って、あきらめていないだろうか。
「若者は自立して働かなければならない。」
という常識が、どれほどの若者を苦しめているだろう。
「定職について、安定した暮らしを送るのが幸せ」
という常識が、どれほどのフリーターを苦しめているだろう。
「常識」は本来集団に生きる人を幸せにするためにあるはずだから、
もし、その常識が多くの人を苦しめているとしたら
常識そのものを変えなくてはいけないだろう。
「1度会社に入ったからには3年は勤めるべし」
という常識は、誰を幸せにしているのだろう?
かつて、それが人を幸せにした時代があった、
それは認めよう。
3年くらい勤めないと
責任のある仕事を任せてはもらえないから、
「経験」とは呼べない。
しかしながら、
社員の育成システムが機能する余裕がなくなっている今、
「3年」という期間の重みはどこにあるのだろうか?
そこでついた「スキル」は、どこの会社でも通用するのか?
残念ながらそんなことはない。
ネットワーク(人脈)は?
これはある程度は通用するだろう。
もう一度、
「一度就職したら、3年は勤めるべきだ。」
という常識を、検証することが必要なのではないか。
9月23日(月祝)
19:00~21:00 ツルハシブックス2Fイロハニ堂で
green drinks 新潟内野第2回ゲストとしてお話します。
題して
「石の上にも3年は本当か?」
参加費
社会人1500円 学生500円(軽食付)です。
お問い合わせはツルハシブックスまで。
「常識だから」と言われて、窮屈な思いをしていないか。
「常識だから」と思って、あきらめていないだろうか。
「若者は自立して働かなければならない。」
という常識が、どれほどの若者を苦しめているだろう。
「定職について、安定した暮らしを送るのが幸せ」
という常識が、どれほどのフリーターを苦しめているだろう。
「常識」は本来集団に生きる人を幸せにするためにあるはずだから、
もし、その常識が多くの人を苦しめているとしたら
常識そのものを変えなくてはいけないだろう。
「1度会社に入ったからには3年は勤めるべし」
という常識は、誰を幸せにしているのだろう?
かつて、それが人を幸せにした時代があった、
それは認めよう。
3年くらい勤めないと
責任のある仕事を任せてはもらえないから、
「経験」とは呼べない。
しかしながら、
社員の育成システムが機能する余裕がなくなっている今、
「3年」という期間の重みはどこにあるのだろうか?
そこでついた「スキル」は、どこの会社でも通用するのか?
残念ながらそんなことはない。
ネットワーク(人脈)は?
これはある程度は通用するだろう。
もう一度、
「一度就職したら、3年は勤めるべきだ。」
という常識を、検証することが必要なのではないか。
9月23日(月祝)
19:00~21:00 ツルハシブックス2Fイロハニ堂で
green drinks 新潟内野第2回ゲストとしてお話します。
題して
「石の上にも3年は本当か?」
参加費
社会人1500円 学生500円(軽食付)です。
お問い合わせはツルハシブックスまで。
2013年09月18日
会議の価値
メールのやりとりと
スカイプ会議と
顔を合わせた会議
何が違うのだろうか?
昨日はインターンシップの学生の会議で
重要な案件を話し合っていた。
会議というのは、なかなか難しい。
もちろん会議のゴールは合意形成であるのだから
ひとりひとりが納得した結果が出るのが望ましい。
ひとりの意見が強い人が
引っ張っていって合意するのではなく、
みんなが自分のアイデアを出し合って、
話し合っていくことが大切だ。
そこで考えてもらう。
みんながアイデアを出すには、どうするか。
・挙手をしてから発言する
・考える時間をとってみる。
・ホワイトボードに書き出し、整理しながら話す
などなど。
いろんな話が出てきたのだが。
ここでもまた「目的と手段の逆転」が起こる危険がある。
つまり、「みんなが均等に話す」ことが目的になってしまうことだ。
もしこれが、A案とB案があって、
どちらかに決定するための会議であるならば、
全員の意見を均等に聞くことが大切だろう。
しかし、現在取り組んでいる課題は非常に創造性の高い、
答えのない課題だ。
その場合に、必要なことはなんだろうか?
やはり、一言で言えば、雰囲気づくり。
話しやすい「場」をつくる。
だから、
司会の役割が重要。
始まる前の会議ルールの共有も大切。
いい会議とは?
というお題に対して、もう少し議論を深めてもよかった。
・否定しない
・コメントしない
・代替案を出す
会議の全体の流れも確認しておくことも大切。
・目的と前提の確認
・議題の確認
・終了予定時刻の確認
こういうのは実践で
慣れていくしかないから、
随所にこういう講座をやってもいいかなと思いました。
なかなかこちらが学ぶことが多い
インターンシップになっています。
スカイプ会議と
顔を合わせた会議
何が違うのだろうか?
昨日はインターンシップの学生の会議で
重要な案件を話し合っていた。
会議というのは、なかなか難しい。
もちろん会議のゴールは合意形成であるのだから
ひとりひとりが納得した結果が出るのが望ましい。
ひとりの意見が強い人が
引っ張っていって合意するのではなく、
みんなが自分のアイデアを出し合って、
話し合っていくことが大切だ。
そこで考えてもらう。
みんながアイデアを出すには、どうするか。
・挙手をしてから発言する
・考える時間をとってみる。
・ホワイトボードに書き出し、整理しながら話す
などなど。
いろんな話が出てきたのだが。
ここでもまた「目的と手段の逆転」が起こる危険がある。
つまり、「みんなが均等に話す」ことが目的になってしまうことだ。
もしこれが、A案とB案があって、
どちらかに決定するための会議であるならば、
全員の意見を均等に聞くことが大切だろう。
しかし、現在取り組んでいる課題は非常に創造性の高い、
答えのない課題だ。
その場合に、必要なことはなんだろうか?
やはり、一言で言えば、雰囲気づくり。
話しやすい「場」をつくる。
だから、
司会の役割が重要。
始まる前の会議ルールの共有も大切。
いい会議とは?
というお題に対して、もう少し議論を深めてもよかった。
・否定しない
・コメントしない
・代替案を出す
会議の全体の流れも確認しておくことも大切。
・目的と前提の確認
・議題の確認
・終了予定時刻の確認
こういうのは実践で
慣れていくしかないから、
随所にこういう講座をやってもいいかなと思いました。
なかなかこちらが学ぶことが多い
インターンシップになっています。
2013年09月17日
「人に惚れる」から始まる縁~ニイダヤ水産に集まる人たち
いわき・ニイダヤ水産に行ってきました。
ニイダヤ水産復活から1年。
15日16日と1周年記念イベント、の予定、でしたが、
台風直撃のため、16日のイベントは中止。
15日には、新潟大学4年の阿部桃子さんも
バスを乗り継いでいわきに駆けつけました。
彼女は2年次にニイダヤ水産復活プロジェクトに関わり、
半年の間、新潟市内の飲食店につぶ貝を売り込んだり、頑張っていた。
つぶ貝を売り込め(12.1)
http://www.youtube.com/watch?v=9xQixtXAkFs
粟島×ニイダヤ水産(12.2)
http://www.youtube.com/watch?v=aPWuCv8Ex8k
チャリティー鍋(12.3)
http://www.youtube.com/watch?v=fxKAIyEXQRs
ニイダヤ復活(12.8)
http://www.youtube.com/watch?v=dOQuLfWbHD8
復活から1年。

賀沢さん、お元気そうで。
サンマとつみれ汁(新潟県産イワシ使用)

そして、粟島からも神丸さん、高木さんが登場。

台風の中、みんな駆け付けました。
結局、みんな、
賀沢さんが好きなんだよね。
ただ、それだけ。
「人に惚れる」ということで縁が生まれ、
その「縁」が人をつなげ、そして人を動かすのだろうと思う。
震災の1週間前、横田さんに再会。
新大の菊地さんから何かしたいと言われて、
横田さんに相談。
「いわきのニイダヤ水産、残したいんだ」
と言われた。
そのときは、僕は賀沢さんに面識がなかったのだけど、
横田さんがそう言うのなら、僕もそうしようと思った。
ツルハシブックスのオープンもあり、
当時、東日本大震災への支援は、何もしていなかった。
「いわき・ニイダヤ水産だけ、何かやろう。」
そう決めて取り組んできた2年半。
原発事故の収束も見えず、
厳しい状況に置かれているニイダヤ水産ですが、
新潟・北海道などから、魚を仕入れ、
屋内で干物を作っています。
横田さんを始め、
数々の旅館の料理長が
「ニイダヤ水産はつぶしてはならない」
と強く語ったほどの技術。
完全無添加の干物は
ツルハシブックスで取扱いしています。
アジ開き・イワシ味醂は新潟県産の魚を使用しています。
ぜひ一度、ご賞味ください。
賀沢さんに会いに、
いわきに行きたくなりますよ。
ニイダヤ水産復活から1年。
15日16日と1周年記念イベント、の予定、でしたが、
台風直撃のため、16日のイベントは中止。
15日には、新潟大学4年の阿部桃子さんも
バスを乗り継いでいわきに駆けつけました。
彼女は2年次にニイダヤ水産復活プロジェクトに関わり、
半年の間、新潟市内の飲食店につぶ貝を売り込んだり、頑張っていた。
つぶ貝を売り込め(12.1)
http://www.youtube.com/watch?v=9xQixtXAkFs
粟島×ニイダヤ水産(12.2)
http://www.youtube.com/watch?v=aPWuCv8Ex8k
チャリティー鍋(12.3)
http://www.youtube.com/watch?v=fxKAIyEXQRs
ニイダヤ復活(12.8)
http://www.youtube.com/watch?v=dOQuLfWbHD8
復活から1年。

賀沢さん、お元気そうで。
サンマとつみれ汁(新潟県産イワシ使用)

そして、粟島からも神丸さん、高木さんが登場。

台風の中、みんな駆け付けました。
結局、みんな、
賀沢さんが好きなんだよね。
ただ、それだけ。
「人に惚れる」ということで縁が生まれ、
その「縁」が人をつなげ、そして人を動かすのだろうと思う。
震災の1週間前、横田さんに再会。
新大の菊地さんから何かしたいと言われて、
横田さんに相談。
「いわきのニイダヤ水産、残したいんだ」
と言われた。
そのときは、僕は賀沢さんに面識がなかったのだけど、
横田さんがそう言うのなら、僕もそうしようと思った。
ツルハシブックスのオープンもあり、
当時、東日本大震災への支援は、何もしていなかった。
「いわき・ニイダヤ水産だけ、何かやろう。」
そう決めて取り組んできた2年半。
原発事故の収束も見えず、
厳しい状況に置かれているニイダヤ水産ですが、
新潟・北海道などから、魚を仕入れ、
屋内で干物を作っています。
横田さんを始め、
数々の旅館の料理長が
「ニイダヤ水産はつぶしてはならない」
と強く語ったほどの技術。
完全無添加の干物は
ツルハシブックスで取扱いしています。
アジ開き・イワシ味醂は新潟県産の魚を使用しています。
ぜひ一度、ご賞味ください。
賀沢さんに会いに、
いわきに行きたくなりますよ。
2013年09月16日
ひとりでも生きていける時代は終わった

「評価と贈与の経済学」
(内田樹 岡田斗司夫 徳間ポケット)
内田樹さんは言います。
~~~ここから引用
1980年代以降のイデオロギーは、
他人がおなじ家のなかにいるせいで、
可動域が制約される、自由なふるまいが許されない、
自己実現が妨げられている、
だから「家族は解体すべきだ」
という考え方を流布しましたよね。
自分の欲望を実現すること、
好きな生き方をすることが人間の最優先の
目標だと言われてきた。
でも、そんなイデオロギーが大声で言われるようになったのって
ほんとうにごくごく最近の話ですよ。
そんな話、江戸時代でも明治時代でも、戦後すぐでも、ありえなかった。
「自己実現があらゆることに優先する」
なんて言ったら、気が狂っていると思われましたよ。
あらゆることに優先するのは「集団が生き延びること」ですから。
単独で「誰にも迷惑かけない、かけられない」生き方を貫くより、
集団的に生きて「迷惑をかけたり、かけられたり」するほうが
生き延びる確率が圧倒的に高いんですから。
~~~ここまで引用
なるほど。
「自己実現があらゆることに優先する」
というのは、
経済の養成だったように思います。
「第四の消費」で三浦展さんも同じようなことを書いていたけど、
経済成長というか、
工業、とくにテレビなど家電の製造業が
メインだったときに、
すでに「一家に一台」
あったものを
「自己実現のために」「ひとり一台」
買った方がいい。
テレビは一部屋に一台あったほうが
チャンネル争いをしなくてもいいとか、
そもそも同居をやめて、一人暮らしを始めれば、
冷蔵庫も洗濯機ももう一台ずつ必要になるのだから。
こうして、ポスト団塊世代の消費の減少
(詳しくは「デフレの正体」(藻谷浩介)へ)
による日本経済の落ち込みを抑えて
きたのだろうと思います。
「自己実現」というイデオロギーの裏には、
そういう事情もあったと。
結果。
必要以上に「自立」(特に経済的自立)
がひとりひとりに求められるようになり、
結果、苦しくなった若者が弾きだされ、
現代社会での働けない若者や精神的に苦しい若者を
生み出しているのではないかと思います。
ひとりでも生きていける時代は終わったとこの本ではいい。
岡田さんは「拡張型家族」を作っていくことを提唱しています。
「お金をいっぱい持っているのに、奢る相手というか、
誰かを養うあてが全然ない人たちと、
なんかいろんなことやりたいんだけどもとりあえず働くところがないとか、
住むところがないといった人たちがうまく組み合わされば拡張型家族は作れますよね」
(本文より引用)
なるほどな。
拡張型家族。
一家を構える、というと
あっち系の人たちになってしまうけど、
そういう感じ。
これからの時代を占うステキな1冊。
追加注文しておきます。
2013年09月15日
努力と報酬は一致しない

「評価と贈与の経済学」
(内田樹 岡田斗司夫 徳間ポケット)
読み始めました。
いいですね、このコンビ。
~~~いきなり引用
岡田さん談:
いましている努力に対して未来の報酬が約束されないと
働く気がしないという人が増えてきたけどさ、
いましている努力に対して未来の報酬が約束された
時代なんて、これまでだってなかったんだよ。
だって、明治維新からあと、20年おきに戦争してたんだぜ。
「約束された未来」なんてあるはずないじゃない。
報酬の約束なんかなくても、とりあえず生き延びないといけないからって
みんな必死で生きてたんだ。
努力と報酬が相関するというのは、理想なの。
はっきり言えば、嘘なの。
努力と報酬は原理的に相関しないの、全然。
するときもあるかもしれないけど、それは例外。
~~~ここまで引用
報酬は運である。
なるほど。
これに対して内田先生
~~~ここから引用
「努力したら、最終的には報酬がある」
ということは言ってもいいと思う。
でも、どんな報酬がいつもらえるのかは
事前には予測できない。
ある種の努力をしているうちに、
思いもかけないところから、
思いもかけないかたちで「ごほうび」がくる。
それはまさに「思いもかけないもの」であって
努力の量に相関するわけじゃない。
~~~ここまで引用
なるほどね。
だから
「努力した分について、すぐに報酬よこせ」
っていうのは、原理的に成り立たないのね。
これはなんとなく分かるなあ。
これを若い人にどう伝えようか、っていうデザインが問われてますね。
2013年09月14日
即日満席のワークショップで新たな価値は生まれるか?
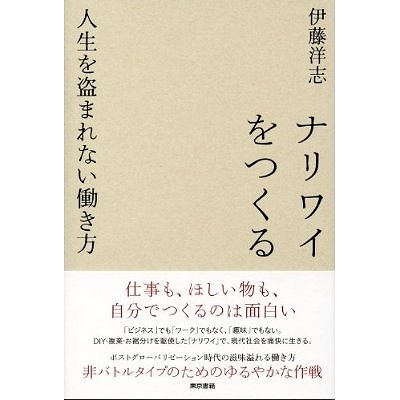
眼からウロコ落ちまくる本、
「ナリワイをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)
これは、ヤバいっす。
熱いっす。
イベントを立てて、定員がなかなか埋まらずに、
赤字の恐怖と戦いながら、
ラスト1週間、知り合いを誘いまくる、
という経験がある人は多いだろう。
では、
「即日満席」というのがいいのだろうか?
そりゃ、ビジネス的にはいいのだろうけど、
果たして、そのイベントで「新たな価値」が生まれるだろうか?
「場のチカラ」は多様性や偶然性が創ると僕は思う。
もし、即日満席のワークショップがあったとしたら、
それは、講師がとても有名な人だったりだとか、
楽しすぎてリピーターが何度も来ているイベントだったりする。
そこに「多様性」や「偶然性」の要素は少ない。
~~~ここから引用
募集開始してすぐに満席ということは、
「たまたま知って受講しました」ということが
少ないことを意味する。
異なる世界からの新しい出会いが生まれにくくなっている
可能性が高いのである。
(中略)
教育に関わるビジネスについては
やっている人が儲かるのはいいけど、
学びが実になるなるのかどうか、
本来はそっちのほうが重要である。
もちろん、自己啓発的セミナーの多くが教育ではなく
もはやエンターテイメント化しているので、
芸人のライブを見に行くと考えればまあ理解はできる。
~~~ここまで
いやあ。
切れ味スルドいなあ、伊藤さん。
ワークショップでは「新たな価値」を生み出すことが重要で、
それには「多様性」や「偶然性」が必要であるから、
即日満席よりはぼちぼち満席のほうがいい。
なるほどね~。
もう、「独立国家のつくり方」(坂口恭平 講談社新書)
のように、世界が複層に見えてきます。
現代社会の矛盾に苦しむすべての若者に届けたい本。
ナリワイをつくる。
これは3ケタ、売りましょう。
そして伊藤洋志さんを新潟に呼ぶのです!
2013年09月13日
ナリワイ時代

「ナリワイをつくる」の伊藤さんにお会いしてきました。
サインももらいました!

とにかくこの本、キーワードに
あふれていて、付箋が足りません。
一例を~~~ここから引用
なんでもこれ一本で飯が食えて一人前、
という現代社会の常識に捉われると、
この面白さは消えてしまう
そもそも起業の起源を考えてみれば、
皆がやるのが面倒なことを誰かがやってくれたら
ありがたいなあということを
やる気のある人が担当してきた、ということだ。
そもそも現代社会にはナリワイのネタは無限にある。
なぜなら、世の中が矛盾だらけだからだ。
~~~ここまで。
いやあ、いいでしょう。
世の中が生きづらい根本原因は
「専業社会」にかなりのウエイトがある。
しかもその専業社会のメリットは、
作業効率性、生産性だけだとしたら、
もはや、そのメリットが生きる会社は少ない。
高度に分業化された
東京という街では、
スキマやニッチな専業で生きていく
というところまで行った。
しかもそれは、
生活コストが高いから、という理由から
専業(たくさん稼ぐ)になっているともいえる。
それは豊かなのか?
という根本的な問いかけを
「ナリワイをつくる」が問いかける。
専業からナリワイへ。
間違いなく、時代はそちらに流れている。
ワークライフバランスではなく
ワークワークバランス。
ワクワクできる、仕事バランス、始めませんか?
2013年09月12日
「場」を売るということ
マイクロライブラリーサミット
つながりで、東京近郊の3ライブラリー
に行ってきました。
下北沢 オープンソースカフェ

リブライズの仕組み、
HAKKUTSUに応用できないか
相談しました。
渋谷 co-ba

ステキなコワーキングスペースのライブラリーがありました。
ここで出会って、ビジネス始めました、という2人がいました。
船橋 情報ステーション

聞けば聞くほど熱い、船橋の市民運営の図書館。
「図書館をまるごと売っているんです」
カッコよかったなあ。
「場」を売るということ。
10年前には説明できなかった世界が
だんだんと広がりつつあるのを感じました。
ワクワクしました。
ありがとう。
つながりで、東京近郊の3ライブラリー
に行ってきました。
下北沢 オープンソースカフェ

リブライズの仕組み、
HAKKUTSUに応用できないか
相談しました。
渋谷 co-ba

ステキなコワーキングスペースのライブラリーがありました。
ここで出会って、ビジネス始めました、という2人がいました。
船橋 情報ステーション

聞けば聞くほど熱い、船橋の市民運営の図書館。
「図書館をまるごと売っているんです」
カッコよかったなあ。
「場」を売るということ。
10年前には説明できなかった世界が
だんだんと広がりつつあるのを感じました。
ワクワクしました。
ありがとう。
2013年09月11日
ハーバードもオックスフォードも教育事業で儲けてはいない

「そろそろ会社辞めようかな」と思っている人に一人でも食べていける知識をシェアしようじゃないか。
(山口揚平 アスキーメディアワークス)
3日目です。
ハーバードビジネススクール。
言わずと知れた名門中の名門。
建物のほとんどは、
卒業生たちの寄付によって
建てられている。
そして、ビジネススクールらしく、
資金運用でもかなりの額を稼いでいて、
過去20年間の年平均リターンは11.9%と
素晴らしい成績を収めている。
イギリスの名門、オックスフォード大学も
収益の土台は、不動産収益となっている。
大学が都市一帯の不動産を所有しているので
街の価値があがると収益が上がるシステムになっている。
そして、
山口さんは言う。
~~~ここから引用
実を言うと、教育事業そのもの(授業料など)で利益を上げている組織は
世の中にはきわめて少ないのです。
なぜなら教育とは、それが本質的に役に立つものであるほど
成果が上がるまでに時間がかかるので、
教育を提供した時点で価値が感じられるものではないからです。
したがって、教育を提供する機関にはお金が落ちにくくなります。
よい教育機関(長く続く知識を提供する機関)ほど、
儲けることが難しいのが実際なのです。
~~~ここまで引用
うお~。
そうだったのか!
なんとも衝撃。
だから日本には受験対策の塾しか
民間教育機関としては難しいのか。
こりゃ、面白い。
本質的に役に立つ教育機関をするには、
本業ではないところで稼ぐことが必要なのですね。
がんばろうぜ、ツルハシブックス。





