2014年03月31日
そう思える一瞬のために
ツルハシブックスの日曜日。
雨が降っていた昨日は、とても静かだった。
静かな日曜日の午後。
日曜日の夕方、必ず寄ってくれる風間さんの姿が見えた。
昨日はちょっと遅めの17時半くらい。
鞄の奥から取り出された本は、
ツルハシブックスの3周年のプレゼントだった。
先週は賑やかすぎて渡しそびれたのだという。

「点滴ポール 生き抜くという旗印」(岩崎航 ナナロク社)
心に突き刺さる歌の数々。
その中のひとつ
本に向かって
鶴嘴(つるはし)を
炭鉱夫のように
ふるい続ける
読書もある
ツルハシ、出てきてる!
思えば、22歳~24歳のころの読書は、
そんなふうだったのかもしれないと思い出した。
何が見つかるかわからないけど、
何かを見つけたかった。
だから、本を読んだ。
「生きてるぜ」
と思えるような生き方をするには、
どうしたらいいのだろう?
そんな問いかけにヒントをくれるのは、
本と人だった。
全国を旅し、農家に出会った。
僕にとってこだわり農家の人たちは、
アーティストそのものだった。
自分の農法に誇りを持ち、
作られた野菜に自信を持って出荷する。
「その草を残すべきか、刈るべきか、
畑に立つと自然とわかるようになる」
その瞬間。
自らの生を燃焼させて、草を刈るかどうか決める。
もちろん、草には草の生命があり、
草を刈るというのは、その生命を奪うことに他ならない。
だからその瞬間、全力を尽くす。
そんな農のカタチを見て、
僕はそんな風に生きたいと思った。
僕は生まれてきた。
今、ここにいるために。
あなたに出会うために。
そして、いま、生きている。
そう思える一瞬のために。
1998年11月23日。
軌保博光さんに出会った。
対談で、
なんのための映画を撮るのか?
という質問に対して、
「映画を撮っているとき、いま俺めっちゃ輝いてる、
とか俺めっちゃカッコイイとか思える瞬間があるんです。
だから僕は映画を撮りたい。」
人生はそんな一瞬のためにあるのかもしれないと思った。
3周年に素敵なメッセージをいただきました。
風間さん、ありがとう。
抜粋した3つを最後に。
本当に
心の底から
願っていることに
向き合えば
いのち 輝く
本当に
そう思わなければ
祈りでは
なく
呟きなんだ
たしかにその形は
違う、けれども
気づいた
いつの間にか
届いた 祈り
雨が降っていた昨日は、とても静かだった。
静かな日曜日の午後。
日曜日の夕方、必ず寄ってくれる風間さんの姿が見えた。
昨日はちょっと遅めの17時半くらい。
鞄の奥から取り出された本は、
ツルハシブックスの3周年のプレゼントだった。
先週は賑やかすぎて渡しそびれたのだという。

「点滴ポール 生き抜くという旗印」(岩崎航 ナナロク社)
心に突き刺さる歌の数々。
その中のひとつ
本に向かって
鶴嘴(つるはし)を
炭鉱夫のように
ふるい続ける
読書もある
ツルハシ、出てきてる!
思えば、22歳~24歳のころの読書は、
そんなふうだったのかもしれないと思い出した。
何が見つかるかわからないけど、
何かを見つけたかった。
だから、本を読んだ。
「生きてるぜ」
と思えるような生き方をするには、
どうしたらいいのだろう?
そんな問いかけにヒントをくれるのは、
本と人だった。
全国を旅し、農家に出会った。
僕にとってこだわり農家の人たちは、
アーティストそのものだった。
自分の農法に誇りを持ち、
作られた野菜に自信を持って出荷する。
「その草を残すべきか、刈るべきか、
畑に立つと自然とわかるようになる」
その瞬間。
自らの生を燃焼させて、草を刈るかどうか決める。
もちろん、草には草の生命があり、
草を刈るというのは、その生命を奪うことに他ならない。
だからその瞬間、全力を尽くす。
そんな農のカタチを見て、
僕はそんな風に生きたいと思った。
僕は生まれてきた。
今、ここにいるために。
あなたに出会うために。
そして、いま、生きている。
そう思える一瞬のために。
1998年11月23日。
軌保博光さんに出会った。
対談で、
なんのための映画を撮るのか?
という質問に対して、
「映画を撮っているとき、いま俺めっちゃ輝いてる、
とか俺めっちゃカッコイイとか思える瞬間があるんです。
だから僕は映画を撮りたい。」
人生はそんな一瞬のためにあるのかもしれないと思った。
3周年に素敵なメッセージをいただきました。
風間さん、ありがとう。
抜粋した3つを最後に。
本当に
心の底から
願っていることに
向き合えば
いのち 輝く
本当に
そう思わなければ
祈りでは
なく
呟きなんだ
たしかにその形は
違う、けれども
気づいた
いつの間にか
届いた 祈り
2014年03月30日
モノを介して、「何か」を売る
モノを介して、「何か」を売る時代に突入した。

「ミッション」(岩田松雄 アスコム)
を読んでからというもの、
出張先ではほぼ
スターバックス朝活をしているのは、
朝早く空いているからだし、
7時~9時まで2時間過ごしても、大丈夫な安心感がある。
そして何より、スターバックスクオリティな
店員さんの印象がいい。
わずか300円でそんな時間を買えるというのは
本当に素晴らしいと思う。
スターバックスのコーヒーを
持ち帰りで買う人はどういうことなんだろう?
スターバックスを選んでいる自分が好きなのか。
モノはすでにいっぱいある。
何も要らない。
だから、
これからは
モノを介して何かを売ることが必要となってくる。
小阪裕司さんは15年以上前に
「ワクワクするビジネスに不況はない」
のなかで、
ヴィレッジヴァンガードなどの例をだし、
「ワクワク」の重要性を説いた。
その「ワクワク」を言語化したいとずっと思っていた。
昨年11月に佐賀県武雄市図書館に行き、
空間の持つパワーに圧倒された。
その月末に
内沼晋太郎さん×佐藤雄一さんのトークイベントで
なんとなくそれが言語化された。
1月の青森行の帰りに、
目指すべき空間の形が見えた。
「多様性」と「偶然性」が「可能性」を生んでいく。
だからこそ、本屋が必要だし、
そこにこそ存在意義がある。
本屋が劇場(theater)になったら、
きっともっとワクワクする空間だろう。
これこそがネット書店にはできない、
本屋だけの道。
そしてそこにモノを介した「何か」が発生し、
人々はそれを求めてやってくる。
そんなことを改めて考えて、
日本最高峰の書店員さんとの会話でした。
いい時間をありがとうございました。

「ミッション」(岩田松雄 アスコム)
を読んでからというもの、
出張先ではほぼ
スターバックス朝活をしているのは、
朝早く空いているからだし、
7時~9時まで2時間過ごしても、大丈夫な安心感がある。
そして何より、スターバックスクオリティな
店員さんの印象がいい。
わずか300円でそんな時間を買えるというのは
本当に素晴らしいと思う。
スターバックスのコーヒーを
持ち帰りで買う人はどういうことなんだろう?
スターバックスを選んでいる自分が好きなのか。
モノはすでにいっぱいある。
何も要らない。
だから、
これからは
モノを介して何かを売ることが必要となってくる。
小阪裕司さんは15年以上前に
「ワクワクするビジネスに不況はない」
のなかで、
ヴィレッジヴァンガードなどの例をだし、
「ワクワク」の重要性を説いた。
その「ワクワク」を言語化したいとずっと思っていた。
昨年11月に佐賀県武雄市図書館に行き、
空間の持つパワーに圧倒された。
その月末に
内沼晋太郎さん×佐藤雄一さんのトークイベントで
なんとなくそれが言語化された。
1月の青森行の帰りに、
目指すべき空間の形が見えた。
「多様性」と「偶然性」が「可能性」を生んでいく。
だからこそ、本屋が必要だし、
そこにこそ存在意義がある。
本屋が劇場(theater)になったら、
きっともっとワクワクする空間だろう。
これこそがネット書店にはできない、
本屋だけの道。
そしてそこにモノを介した「何か」が発生し、
人々はそれを求めてやってくる。
そんなことを改めて考えて、
日本最高峰の書店員さんとの会話でした。
いい時間をありがとうございました。
2014年03月29日
メディアに期待するものは情報ではなくコミュニティとコミュニケーション

3月29日(土)付朝日新聞新潟版に
唐澤さんのにいがたレポと一緒に
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」が
掲載されています。
(僕ものぞいているところ、映ってる。笑)

「メディア化する企業はなぜ強いのか」(小林弘人 技術評論社)
久しぶりに2年ほど前の本を引っ張り出して読んでみると、
いま、まさに起こっていることが書いてある。
かつて、「雑誌」とは、情報を得るために存在した。
いや、いまもそうなのかもしれない。
しかし。
誰もが実感しているように、
インターネット常時接続(死語)時代を迎え、
個人が手にする情報は飛躍的に伸びた。
いや、もはや管理できないレベルに溢れた。
雑誌に限らず、
あらゆるメディアは、
もはや、「情報を届ける」だけでは、
十分ではない。

図は、上記の本に出てくる、
メディア空間の拡張と期待役割の変化である。
~~~ここから引用
図1-5を見てください。
図の中の左側は、ちょっと昔の話です。
情報を届けることが換金化手段であり、
情報を届けてから、メディアの外部にコミュニティが誕生しました。
しかしメディア空間が拡張されたおかげで、ユーザーは情報を手にするだけでは
飽き足らなくなりました。欲求が拡張したのです。
図1-5の右側は、メディア内にコミュニティが組成された場合を指します。
たとえば、そこでユーザーはメディアが届けた情報以外に、
自分たちも情報を発信でき、さらに共有します。
そこで何を求めるのかというと、もはや、メディア側が
発信した情報だけではありません。
むしろ、ここでの情報は、
コミュニティを接合するためのネタにしか過ぎないと言っても過言ではありません。
(中略)
このコミュニティの参加者たちは何を欲して、ここに集うのでしょうか?
彼ら/彼女らはいったいメディアに何を期待しているのでしょうか?
あるいは何を期待していないのでしょうか?
~~~ここまで引用
この後、本の中では
バイクの愛好者たちのコミュニティを例に、
イギリスのメーカーと交渉して、
部品などを販売仲介することが換金化の方法だと説く。
これは面白い。
換金ポイントの変化。
変化というか拡張。
これがこれからもメディアの難しさと面白さなのだと思った。
そして何より、
おそらくはユーザーがメディアに求める最大のものは、
コミュニティとコミュニケーションなのではないかと僕は思う。
「情報を届ける」ことだけが使命であるメディアは
徐々に終焉していく。
これからはコミュニティとコミュニケーションを伴った、
換金ポイントの多様なメディアだけが支持されていく。
そしてそれを自前で持つことが
企業が伸びていく条件だ。
ツルハシブックスのメディア化というお題、
唐澤さんと一緒に考えてみたいです。
2014年03月28日
「目的は何か」を考え抜くこと

世界一シンプルな戦略の本(長沢朋哉 PHP)
を読み直す。
戦略とは何か?
そんな問いにシンプルに答える傑作。
大学生にもよく分かる。
著者は
「戦略」=「目的」+「手段」
だと言います。たしかにシンプル。
そして
「戦略」を立てる出発点は「目的は何か」を考え抜くこと
さらに
「目的」が具体的かつ明快に設定できれば「戦略作り」の道程は半分終了
そしてポイントは
「戦略の階層性」を理解し、
「どの階層の戦略が適切なのかを考えること」が重要だと言います。
そのうえで重要なのが「捨てる」ということ。
選ばなかったものを捨てる、それが集中するということです。
著者はまとめて言います。
「よい戦略」とは
「目的と手段」が現状分析に基づいて
それぞれ適切に「選択」され「集中」されているもの
そこでこれを、キャリア設計に当てはめてみる。
神戸大学の金井壽宏先生によると、
先の見えない社会における個人のキャリア形成は
普段は「キャリア・ドリフト」(一期一会型キャリア形成)をして、
節目では「キャリア・デザイン」(目標設定型キャリア形成)をすることが重要だと言う。
その節目におけるキャリアデザインを考えるときに、
この戦略の考え方が重要になってくる。
「目的は何か」を考え抜くこと。
僕自身もそれは同じだ。
「目的は何か」を問うこと。
そういう意味で考えると、
「目的」は
中学高校大学の時のキャリア思考に「キャリア・ドリフト」型を入れ、
小さなチャレンジを繰り返すことで、「成長思考(成長的知能観)」のスイッチを入れること。
になるのかもしれない。
「夢・目標を持て」一辺倒だったキャリア形成支援を
「とりあえず何かやってみる」というような自発的モチベーションに替え、
やってみたら意外にやれる、とか
知らなかった自分に気づく、とか
チームならできるかもしれない、とか
そういう感覚を得ていくことで、
「才能思考(固定的知能観)」を脱していくことが
大切なのだと思う。
そのための手段が
大学とコラボで行う商店街や中山間地、離島でのプログラムづくりであり、
ツルハシブックスで行う屋台での商売体験だ。
これらの活動を階層化して、
不要なところを捨てていくこと。
これを「キャリアデザイン」というのかもしれない。
目的は何かを考え抜き、戦略を階層化し、選択と集中を行う。
先の見えない時代。
企業も、個人も、「自分を経営する」ことが求められる。
あなたの目的は、なんですか?
2014年03月27日
「本のある空間」と「コミュニケーションのある空間」
名作マンガ「スラムダンク」の1シーン。
「お前はまだその可能性を活かしきれてねえ」
と仙道が流川に言う。
1対1はオフェンスの1つの選択肢にすぎない。
そして、ルカワは、1対1に固執せずに、パスを出す。
そこから活路を見出していく。
そう。
それそれ。
パスを出すということ。
「本を読む」
あるいは
「本を買う」「本を借りる」
というのは、
「本」の可能性のひとつに過ぎない。
そんな思いが体現されている本
「HAB(Human and Bookstore)」
の第1弾、新潟編の最初の10冊が売り切れました。
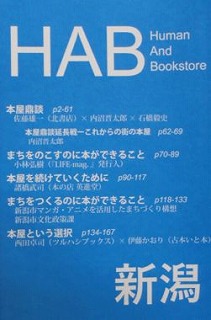
本日27日の午後、編集長の松井さんがツルハシブックスに
追加の10冊を自ら届けて下さいます!
ありがたい!
編集長のサインがほしい方は本日午後を目指して来てください。
ツルハシブックスのニシダタクジ×古本いと本伊藤かおり
の対談が収録。
仕事を辞めようか悩んでいる人に
向けての熱いメッセージが収録されている。
僕の中での対談中の名言は
「感性は自覚なく死んでいく」かなあ。
自分の感性にウソをついて生きていくと、
感性が死んでいくっていう話。
あそこでいと本と共感できたのがよかった。

「本の逆襲」(内沼晋太郎 朝日出版社)
にも、
「本」や「本屋」のこれからがたくさん詰まっています。
ひとつ。
「本のある空間」で語られている
「本を介したコミュニケーション」
「本」が目的ではなく手段として使われるということ。
ここがすごく大切だと思う。
人は、本を読みたいのではなく、コミュニケーションがしたい。
わかりあえないのだとしても、なんとか少しでも相手を理解したい。
そういう思いを持つ人にとって、
本というのは極めて有効なツールとなり得るし、
本のある空間はそういう場になる。
「ビブリオバトル」(本のプレゼン大会)や
「ブクブク交換」(名刺交換のように本を交換する)など
本を介したコミュニケーションの場をたくさんつくっていくことが
求められていると思う。
一箱古本市は、
まちを舞台にしたコミュニケーション空間の提供だもの。
そうやって「本のある空間」をたくさんつくっていくことで、
冒頭の仙道のセリフのように
本の可能性が拓き、それと同時に人がアクションするきっかけが生まれ、
本を通して、人の可能性が開花していくのではないかと思うのだ。
「本のある空間」は「コミュニケーションのある空間」になり得る。
しかし、そこは、
「効率化」という波の中で、どんどん失われていったもの。
大型書店や図書館には、検索機が設置され、
シャイな僕なんかは店員さんよりに聞くよりも検索機で検索してしまう。
そこに、コミュニケーションは存在しない。
それは、ネット書店のほうがいいでしょう。
検索して、自宅へ配送。
超便利だ。
昨日、日経MJ(3月26日号)に載っていた
コスモスベリーズという成長企業の話。

ヤマダ電機の流通網を使って、
おもに高齢者向けに、電化製品を販売する。
ヤマダの流通網を使っているので、在庫を持つ必要はない。
ヤマダ電機の価格より5%~8%ほど高く設定しているのだが、
アフターサービスが必要な高齢者から支持されているのだという。
この店内写真がすごい。

これ、電器屋さんか?
なんかよくある、商店街活性化対策で
作られた居場所みたいな感じ。
ここではパソコン教室などが行われ、
高齢者とのコミュニケーション機会を増やしている。
こうして、インターネットの設定やトイレのリフォーム
換気扇の掃除や草刈りなどの有料サービスも行う。
今後は
料理教室を行ったり、食料品を取り扱うことも検討中だという。
「業種から業態へ」とコスモスベリーズの三浦会長は言うが、
それは、まさに高齢者とのコミュニケーションの場づくりから始まるのだ。
もしかしたら、その入り口に、「本」がなれるのかもしれない。
「本」「食」「農」というコミュニケーションツールを
地域に落とし込んでいくデザインが
いまこそ求められている。
「お前はまだその可能性を活かしきれてねえ」
と仙道が流川に言う。
1対1はオフェンスの1つの選択肢にすぎない。
そして、ルカワは、1対1に固執せずに、パスを出す。
そこから活路を見出していく。
そう。
それそれ。
パスを出すということ。
「本を読む」
あるいは
「本を買う」「本を借りる」
というのは、
「本」の可能性のひとつに過ぎない。
そんな思いが体現されている本
「HAB(Human and Bookstore)」
の第1弾、新潟編の最初の10冊が売り切れました。
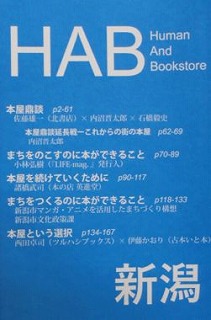
本日27日の午後、編集長の松井さんがツルハシブックスに
追加の10冊を自ら届けて下さいます!
ありがたい!
編集長のサインがほしい方は本日午後を目指して来てください。
ツルハシブックスのニシダタクジ×古本いと本伊藤かおり
の対談が収録。
仕事を辞めようか悩んでいる人に
向けての熱いメッセージが収録されている。
僕の中での対談中の名言は
「感性は自覚なく死んでいく」かなあ。
自分の感性にウソをついて生きていくと、
感性が死んでいくっていう話。
あそこでいと本と共感できたのがよかった。

「本の逆襲」(内沼晋太郎 朝日出版社)
にも、
「本」や「本屋」のこれからがたくさん詰まっています。
ひとつ。
「本のある空間」で語られている
「本を介したコミュニケーション」
「本」が目的ではなく手段として使われるということ。
ここがすごく大切だと思う。
人は、本を読みたいのではなく、コミュニケーションがしたい。
わかりあえないのだとしても、なんとか少しでも相手を理解したい。
そういう思いを持つ人にとって、
本というのは極めて有効なツールとなり得るし、
本のある空間はそういう場になる。
「ビブリオバトル」(本のプレゼン大会)や
「ブクブク交換」(名刺交換のように本を交換する)など
本を介したコミュニケーションの場をたくさんつくっていくことが
求められていると思う。
一箱古本市は、
まちを舞台にしたコミュニケーション空間の提供だもの。
そうやって「本のある空間」をたくさんつくっていくことで、
冒頭の仙道のセリフのように
本の可能性が拓き、それと同時に人がアクションするきっかけが生まれ、
本を通して、人の可能性が開花していくのではないかと思うのだ。
「本のある空間」は「コミュニケーションのある空間」になり得る。
しかし、そこは、
「効率化」という波の中で、どんどん失われていったもの。
大型書店や図書館には、検索機が設置され、
シャイな僕なんかは店員さんよりに聞くよりも検索機で検索してしまう。
そこに、コミュニケーションは存在しない。
それは、ネット書店のほうがいいでしょう。
検索して、自宅へ配送。
超便利だ。
昨日、日経MJ(3月26日号)に載っていた
コスモスベリーズという成長企業の話。

ヤマダ電機の流通網を使って、
おもに高齢者向けに、電化製品を販売する。
ヤマダの流通網を使っているので、在庫を持つ必要はない。
ヤマダ電機の価格より5%~8%ほど高く設定しているのだが、
アフターサービスが必要な高齢者から支持されているのだという。
この店内写真がすごい。

これ、電器屋さんか?
なんかよくある、商店街活性化対策で
作られた居場所みたいな感じ。
ここではパソコン教室などが行われ、
高齢者とのコミュニケーション機会を増やしている。
こうして、インターネットの設定やトイレのリフォーム
換気扇の掃除や草刈りなどの有料サービスも行う。
今後は
料理教室を行ったり、食料品を取り扱うことも検討中だという。
「業種から業態へ」とコスモスベリーズの三浦会長は言うが、
それは、まさに高齢者とのコミュニケーションの場づくりから始まるのだ。
もしかしたら、その入り口に、「本」がなれるのかもしれない。
「本」「食」「農」というコミュニケーションツールを
地域に落とし込んでいくデザインが
いまこそ求められている。
2014年03月26日
ライブラリーとミュージアムのあいだ
ライブラリー(図書館)とは、
なんのために存在するのだろう?
と問いかけたのは、
礒井さんたちの「まちライブラリー」
に出会ったときからだった。
「本こそが人をつなぐ」と
いうコンセプトでたくさんの人が持ち寄った本を
展示し、イベントを行っている。

http://opu.is-library.jp/
「まちライブラリー@大阪府立大学」
これから目指していくのは、
「ライブラリーとミュージアムのあいだ」
なのかもしれないとふと思った。
あるいは、ライブラリー×ミュージアムなのかもしれないと思った。
そしてそこにコミュニケーション機会がプラスされたコミュニティを
人は欲しているのではないか。
本こそが
人と人をつなぐ最強のツールだと、街で暮らす人たちは実感している。
だから、コワーキングスペースには、
自分たちの価値観を表現するための
ライブラリーが設置されている。
それは、既存のライブラリーでは、もはやない。
ライブラリーよりもより、「ライブな」空間。
生きてるぜ!
っていうのを表現している40㎝四方の空間。
それは、その人のミュージアムだと言ってもいいかもしれない。
マイ坂本龍馬記念館、みたいなものだ。
坂本龍馬記念館には、
坂本龍馬を知るための、服や刀、手紙などが編集されて置かれている。
生誕から最期の時まで、
人生の転機や苦悩、活躍がわかるように配置されている。
こういうのが
小さなライブラリーでできるのではないか。
ライブラリー×ミュージアム。
ひとりの作家だったり、
自分が好きな作家グループだったりを
その他のグッズと並べて、伝えるために編集する。
きっとそこには新しいコミュニケーションが誕生していく。
そして、本への扉が開かれる瞬間がある。
そんな小さなライブラリーに
武雄市図書館のようなフロンティアを感じるのは
僕だけだろうか。
なんのために存在するのだろう?
と問いかけたのは、
礒井さんたちの「まちライブラリー」
に出会ったときからだった。
「本こそが人をつなぐ」と
いうコンセプトでたくさんの人が持ち寄った本を
展示し、イベントを行っている。

http://opu.is-library.jp/
「まちライブラリー@大阪府立大学」
これから目指していくのは、
「ライブラリーとミュージアムのあいだ」
なのかもしれないとふと思った。
あるいは、ライブラリー×ミュージアムなのかもしれないと思った。
そしてそこにコミュニケーション機会がプラスされたコミュニティを
人は欲しているのではないか。
本こそが
人と人をつなぐ最強のツールだと、街で暮らす人たちは実感している。
だから、コワーキングスペースには、
自分たちの価値観を表現するための
ライブラリーが設置されている。
それは、既存のライブラリーでは、もはやない。
ライブラリーよりもより、「ライブな」空間。
生きてるぜ!
っていうのを表現している40㎝四方の空間。
それは、その人のミュージアムだと言ってもいいかもしれない。
マイ坂本龍馬記念館、みたいなものだ。
坂本龍馬記念館には、
坂本龍馬を知るための、服や刀、手紙などが編集されて置かれている。
生誕から最期の時まで、
人生の転機や苦悩、活躍がわかるように配置されている。
こういうのが
小さなライブラリーでできるのではないか。
ライブラリー×ミュージアム。
ひとりの作家だったり、
自分が好きな作家グループだったりを
その他のグッズと並べて、伝えるために編集する。
きっとそこには新しいコミュニケーションが誕生していく。
そして、本への扉が開かれる瞬間がある。
そんな小さなライブラリーに
武雄市図書館のようなフロンティアを感じるのは
僕だけだろうか。
2014年03月25日
これからの〇〇の話をしよう

「ソーシャルデザイン」

「日本をソーシャルデザインする」
「グリーンズ~ほしい未来はつくろう」
http://greenz.jp/
がプロデュースした2冊の書籍。
大学生がデザイン思考を身に付けるには
入門編の2冊。
久しぶりに読み直してみる。
「これからの〇〇」というマジックワード。
これ。
ワクワクの会議のネタになるなあと思って。
かつて
「これからの正義の話をしよう」
って本が売れたけど。
あれってネーミングの勝利なのかもしれないと思った。
「これからの」
って言われただけで
ちょっとワクワクするもんね。
そう言えば、卒業生の松尾くんたちがやった
「これからの新潟の話をしよう」
ってのも、かなりの人を集めたなあと思い出した。
すべての会議を
そうやってタイトルつけただけで少し面白くなるんじゃないかと思った。
そう言えば、
ブックディレクター内沼晋太郎の本屋さん下北沢B&Bは
「これからの街の本屋」
と言っている。
「これからの」
と付けただけで、
それはポジティブなQを伴って聞こえてくる。
「商店街活性化会議」
ではなくて、
「これからの商店街の話をしよう」
というと、
なんかポジティブな感じしませんか?
これ、いいかもしれないな。
しかも、こういうのが
「カタルタ」と一緒に語られると
楽しい気がします。
これからの〇〇の話をしよう
始めてみませんか?
2014年03月24日
8つのインテリジェンス
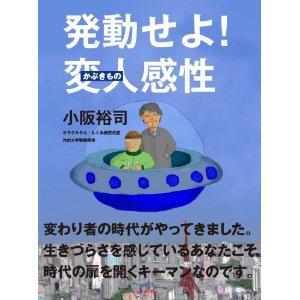
「発動せよ、変人感性」(小阪裕司 ぼくら社)
小阪先生の最新作。
絵本です。
大人向け?
高校生大学生くらいから読める本。
これからは変わり者の時代がやってくる。
いや、やってこなければならないということです。
終盤の一節
~~~ここから引用
「指標はひとつじゃありません。」
この社会には、人の優劣をはかろうとする風潮があります。
学校教育も、しかりです。
しかし、そもそも人間の知能、インテリジェンスを
はかる指標が複数あることを知っている先生は多くありません。
ハワードガードナーというハーバード大学の教授によれば、
最低でも8つのインテリジェンスが認められています。
(中略)
しかし、いま教育現場で行われている測定方法では、
限られたインテリジェンスしかはかることはできません。
それなのに、できる人、できない人のレッテルを貼り、
それを生徒たちに信じこませてしまう。
非常に恐ろしい行為だと思うんです。
対抗手段はひとつ。
自分を信じることです。
~~~ここまで引用
と。
熱いメッセージが続く1冊。
価値観が揺らいでいる時代にガツンと一撃を食らわせる1冊です。
中学生高校生の不登校の子にオススメ。
あ、保健室なんかにいかがですかね?
いいかもしれません。
「学校におけるインテリジェンスの価値観は多くある中のひとつに過ぎない。」
そこから出発する必要があると思います。
しかも、学校で価値があるとされる「学力」は
「暗記力」と「情報処理力」あるいは「忍耐力」
だけなのですから、
これらはすべて、コンピューターとロボットで置き換え可能です。
「効率化」
が新しい価値を生まなくなった今、
求められる力は、それ以外のインテリジェンスなのではないでしょうか。
自分自身のインテリジェンスは
たくさん行動する中で見出していくことしかできません。
そして小阪先生言います。
「そして覚えておいてほしい。その、君の持つインテリジェンスは、
他の誰かを幸せにするためにあるのです。」
熱い。
ステキです。
さあ、あなたのまだ見ぬインテリジェンスは誰を幸せにするのでしょう?
そんな風に子どもたちと接する教育者が増えてほしいなあと思います。
2014年03月23日
200年隠れていた「贈与と交換」の経済

「心の時代にモノを売る方法」(小坂裕司 角川ONEテーマ21)
あらためて読み直す。
自分たちは少数派なのか、
それともアーリーアダプター(市場全体の13.5%を占めるという、アンテナの高い人たち)なのか。
そんな問い。
科学と宗教の境目がなくなっていくように、
ビジネスと芸術の境もなくなりつつあるに思う。
「心の時代にモノを売る方法」は、
世の中で起こっている非合理的な「不思議なこと」
が決して、不思議なことではないと示してくれる。
著者は、すでに「新しい消費は始まっている」という。
全国各地で「生活必需品」ではなく、「心を豊かにする商品」を
主体としたビジネスが伸びている。
それは地元スーパーのような場所でも同じだ。
まさに「スペンド・シフト(消費活動の転換)」が起こっている。
この本の中で引用されている
山崎正和「社交する人間」(中公文庫)に書かれていることは、
世界の見え方が変わる一節だ。
産業革命以降、
(1760年代にイギリスで始まったとされる)
250年間続いた工業社会における経済の軸は
「生産」と「分配」だった。
そして山崎氏はそれを
「経済の第一の系統」と呼ぶ。
そして
「生産と分配を行う集団は一つの同質の欲望の体系によって、
言い換えれば共通の需要、必需品の観念を絆として結ばれてきた。」
簡単に言えば、
みんながマイホームや自動車やテレビや家電をほしがっていた。
「カローラからコロナ、クラウン」「14インチから20インチ、37インチ」
とみんなが思っていたということ。
なるほど。
もしかしたら、ここに、
日本の急速な経済成長の源があるような気がする。
つまり。
農村社会のモデルをそのまま工業社会に当てはめたのだ。
共通の需要、それはかつては「米」だった。
それを最大限確保するため、地域社会は団結していった。
こうしてムラ社会が形成された。
それがそのまま、
工業社会全体にスケールアップしたのが、
日本の経済成長ではなかったか。
みんなが、所得が増えれば、いいものをどんどん買えれば幸せになれると信じ、
そこに向かってきた社会。
もちろん。
それによって税収が増加し、社会福祉も充実したということが十分にあるだろう。
生産と分配の経済によって自分たちの生活が支えられているのは明白で
これからも続いていくのは間違いない。
しかし、それが最も重視される社会は終わりを告げつつある、と小阪さんは言う。
ではどのような社会が来ているのか。
山崎氏によれば、
これまで一括りに「経済活動」と呼ばれてきた営みは、
起源の異なる二種類の活動の複合からなっているとする。
~~~ここから引用1
「経済の第一の系統は生産と分配の経済であって、
これは同質的で均一的な集団を形成しながら、
それによって生産物の効率的な増産を目標としてきた。
これに対して第二の系統をつくるのが贈与と交換の経済であって、
言葉を換えれば社交と商業の経済だといえる。
(社交する人間より)
生産と分配の経済がよりどころにした
「共通の需要、必需品の観念」という絆は崩れた。
今の消費者にとって、必需品の観念は共通ではない。
誰もが自家用車を欲しがり、マイホームを欲しがった時代は終わったからだ。
(中略)
新しい消費社会に「待ってました」とばかり受け入れられるビジネスのありようは、
まさに氏が言うように、同じく「ビジネス」を呼ばれながら、工業社会のそれとは
まったく頃なる別種のもののようだと。
そう、それは起源すら異なる別種のものなのだ。
ビジネスには、まったく異なる二種類の系統が存在するのである。
そして、「心の豊かさと毎日の精神的充足感」への希求が主流をなしてくると共に、
長らく―おそらく産業革命以来200年以上も―「生産と分配の経済」の陰に隠れていたもうひとつの系統、
「贈与と交換」そして「社交と商業」の経済が、再び表舞台に出てきたのである。
~~~ここまで引用1
うわあ。
って感じだ。
以前に読んでいたのだけど、あらためて読むと衝撃。
そしてさらに衝撃は続く。
~~~ここから引用2
ここでの決定的な原則は、
行動に当たって目的が固定化されておらず、
一回ごとの試みによってそれが模索されるということである。
交換はその起源である無償の互酬の名残をとどめ、
常に需要のないところに新しく需要を作り出さねばならない。
けだしキリギリスの歌にはあらかじめ予想できる需要はなく、
一回ずつそれが歌われ、人に喜ばれて初めて商品となるはずである。
(社交する人間より)
もうひとつの経済(贈与と交換の経済)の決定的な原則は
1 1回ごとの試みによって(お客さんに喜ばれるかどうか)が模索される
2 常に需要のないところに新しく需要を作り出す
3 あらかじめ需要は予測され得ない
~~~ここまで引用2
うお~。みたいな。
「試作品」の時代は、決定的な原則なのですね。
双方向コミュニケーションも時代の必然なんだ!って。
さらに、山崎氏の本からの引用はつづく
~~~ここから引用3
じっさい、伝統的な商人はつねに遠く旅をする人間であり、
異文化の世界から珍しい宝を運ぶ人間であった。
彼は旅先でそれが必要とされるかどうかを予期することはできず、
かりに必要とされてもどんな対価を求められるかを予測することはできなかった。
商人はめぐりあった消費者に商品の物語を説き、
その心を魅惑する会話の成功とともに需要を創造したのであった。
この交易が反復されて市場が形成され、
次第に需要の大半が予測可能となっても、
一回ごとの個別の商品の取引においては、
同じ冒険が繰り返されたはずである。
(社交する人間より)
~~~ここまで引用3
これ、面白いでしょう。
モノを売るっていうのは、
かつて、冒険だったんですね。
「商人はめぐりあった消費者に商品の物語を説き、
その心を魅惑する会話の成功とともに需要を創造したのであった。」
素敵じゃないですか。
モノを売るというのはそういう冒険に出るということ。
一期一会の出会いを大切に物語を語るということ。
この200年間、生産と分配の経済の陰に隠れていた
贈与と交換の経済が歴史の表舞台に出始めている。
そんなことを実感させてくれる
ツルハシブックスの毎日です。
本日が3周年記念イベント最終日です。
みなさまのご来店をお待ちしています。
昨日の屋台はゴーさんとやっぴさんでした。

2014年03月22日
学びあいの場づくりで希望を生む

山口県の小学生はみんな読んでいる、
「松陰読本」(山口県教育会)
ツルハシブックスで500円(税込)で販売しています。
昨日は、
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」
飯塚商店でした。

今回は米の味比べ!
1 飯塚商店の特選コシヒカリ「収穫物語」
2 地元産特別栽培コシヒカリ
3 佐渡産送風乾燥コシヒカリ
4 魚沼六日町産特別栽培コシヒカリ
5 スーパー原信のコシヒカリ
選んで、精米します。
そのあいだ「米は生きている」の講座。
米は生きているんです。
呼吸しているんです。
だから、おいしいコメに必要なのは、
最適な水分量。
冬を越えて、夏を迎えると、
だんだんコメの水分含量が減ってきます。
そうするとどうしてもパサパサした米になります。
それを解消するには
密閉容器(タッパー)にいれて、
その中に杯1杯の水を入れて、
米に水分を吸わせます。
そうすると、味が復活するというお話を聞きました。
飯塚商店でも
米の保管庫には、除湿器と加湿器が
完備されていて、最適な温度と湿度(企業秘密です)に
保たれているそうです。
そして、なんといっても飯塚さんの味覚のするどさ。
同じ人が作っても、
最初に刈った稲からとれたものと
最後に刈ったものでは味が違う。
同じ人がつくっても、田んぼの水の関係で、
味が変わってくる。
もちろん作る年によって、
同じ人でも味は変わる。
言われてみれば、たしかにそうなんだけど。
なんというか、
それくらい「米は生きている」ってこと。
そして、いよいよ。
待ちに待った食味テイスティング。
目隠しされた5種類の米で一番おいしい米を
指さします。
8人がいっせいに「これだ!」
と指差し、8人中4人に支持されたのは、なんと。
飯塚商店の特選コシヒカリ「収穫物語」でした。
これが甘くて超おいしいの。
ピカピカ光っているのは、飯塚さんのこだわりで、
少し多く削っているから。
これで、
10㎏4,500円って安いです。
スーパーよりは1割~2割高いのだけど、
魚沼コシヒカリよりも人気な飯塚商店の「収穫物語」
ツルハシブックスでもPRしていこうと思います。
ご用命は、元農学部植物栽培学講座、稲作専攻、
論文テーマは「コシヒカリの不耕起栽培に関する研究」の
店主がいるツルハシブックスへ。
それにしても、飯塚さん、楽しそうだったなあと。
吉田松陰先生のエピソードを思い出しちゃいました。
海外渡航の罪で投獄された松陰先生
隣の人が俳句を詠んでいたら、
「その俳句、みんなに教えてくれませんか?」と
向かいの人が書を書いていたら、
「その書で書道教室やりましょう。」と
ひとりひとりの特技をミニ講座にしていったのです。
すると、今まで暗く沈んでいた人たち
(一生、獄から出られないので)
がみるみる明るくなっていったのです。
たとえ獄中であっても、
学びあいの環境をつくれば、希望が生まれる。
僕はこのエピソードに衝撃を受け、
吉田松陰先生に会いに、
そして、希望が生まれた「野山獄」のあとに行きたくて、
一路、山口県萩を目指しました。
いまから10年前の2004年でした。
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」で生まれる希望。
それは、
「コストパフォーマンス」という獄の中で
生きている私たちへの小さな希望なのかもしれません。
終了まであと3日。
次回が確実にありそうな予感です。
飯塚さん、ありがとうございました。

2014年03月21日
効率化のデザインから対話のデザインへ

2014年3月21日付新潟日報地域版に
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」
が掲載されました。
今回の企画、
何がスゴいかというと、
みんなのモチベーションが高い、ということ。
実行委員会のみんなの
集客へのモチベーションがすごく高い。
だからほとんどの講座は定員いっぱい。
そして店主の講座への意欲が高い。
これも伝えたい、あれも伝えたい、
そんな思いがたくさんあって、時間が足りないくらい。
昨日の大口屋さんでの講座も、
これでもか!というくらい、
お店の商品を開けて、試食させてくれるという
事態になって、すごく楽しかったです。
コミュニケーションデザインの力を
あらためて感じます。
どうやったら、やる気を引き出せるのか。
それ以前に、好きなお店の店主と
どうやって仲良くなるのか?
「効率化」から「対話」へ。
世の中はそんな時代を迎えていると思います。
もっとひとりひとりが自分の感性を大切にする時代。
求められるのは
「効率化のデザイン」ではなく、
「対話のデザイン」、コミュニケーションデザイン
そういえば。
広告もそういうふうになっていっている。
生産者目線ではなく、生活者目線。
一方向ではなく、双方向。
そんなコミュニケーションデザインが学べる場としても、
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」
はとても魅力的だなあと思いました。
まだ終わっていないけど、次回が楽しみになってきました。
2014年03月20日
ツルハシブックスは本日で3年となりました
2011年3月20日。
ツルハシブックスはスタートしました。
まだまだ日本中が
大きな震災の中、何ができるのか、と
模索している中、
「持ち場を守る」という思いの中で、スタートしました。
周りの方々に支えられて、
なんとか3年を迎えることになりました。
本当にありがとうございます。
昨年3月20日には
2Fに「うちのカフェ イロハニ堂」がオープンして、
地元の方もたくさん足を運んでくれるようになり、
店頭にない本の注文も増えてきました。
今年の初めからスタートした
中学生・高校生に本屋を届ける移動ブックカフェ「ツルハシ号」プロジェクトには、
3月19日時点で、店頭で98名の寄付侍が誕生(総額 166,000円)
クラウドファウンディングFAAVO新潟で52名(総額 318,000円)、
計150名の寄付侍が誕生しています。

コミュニティデザイナー、山崎亮さん、なっぱさんにも77人目78人目の寄付侍になっていただきました。
ありがとうございます。
4月上旬には、ツルハシ号を購入し、
移動ブックカフェがお披露目したいと思っております。
金額的にはあと7万円ほどの資金が必要です。
引き続き、寄付侍のご協力をお待ちしています。
4年目を迎えるにあたって、
・ツルハシブックスの場としての魅力向上
・若者向けの企画の継続する体制づくり
の2つを行っていきたいと考えています。
「ツルハシブックスの場としての魅力向上」は
まずは、原点に回帰し、魅せる本屋へ。
若者限定の地下の古本発掘や、
若者が集まるイベントなどを行って、コミュニティに支えられた
ツルハシブックスですが、
「1冊の本で人生は変わる。本屋には新しい人生が転がっている。」
という初志に戻り、本の魅力を伝えていくことをさらに考えていきたいと考えています。
今年1月~3月の模様替えによって、メインとなるのは入って左側の壁一面。
そして奥のテーブル台、さらには独立した4つの本棚のシマ。
これらを活用して、本を読んでみたくなるプレゼンテーションを考えたいと思います。
そして、もうひとつは場として使ってもらうということ。
奥のテーブルから本を移動することによって、
8人~10名ほどは座れるミーティングスペースが誕生します。
ここを活用したトークイベントや、
あるいは明日からの3日間で試験的に行う屋台を使ったイベント
なども考えていきたいと思います。
また、3Fで行っている中学生高校生のための自習型学習塾「野山塾」
の子どもたちが何かを販売する「自営業体験」としての場としても
活用したいと考えています。
次に「若者向けの企画を継続する体制づくり」に関しては
1 中学生・高校生のための移動ブックカフェ「ツルハシ号」
2 高校生・大学生がプロデュースする商店街ミニ講座「うちのまち なじみのお店 ものがたり」
3 大学生・社会人がチャレンジする「食」と「農」を活用したビジネスを試験的に行うパラレル・キャリア・プラットフォームづくり
という3つのプロジェクトが動いていくかと思います。
これらのプロジェクトに対して、地域の人たちや、若者自身の関心領域へ
資金的にも、人材的にもアプローチできるような仕組みをつくりたいと思っています。
石の上にも3年と言いますが、
運営的にはまだまだかなり厳しい状況が続いています。
思いのある方々の力を借りながら、越えていきたいと思っています。
3年間でもっとも印象に残っているのは、昨年4月28日のこと。
2002年1月、僕の活動の原点となった家庭教師の経験。
受験勉強合宿の時に人生最高のすき焼きを食べて、
「中学生・高校生と一緒に将来を見つめる仕事がしたい」
「地域の人が中学生高校生と出会える仕組みをつくりたい」
と思わせてくれた、
当時不登校の中学校3年生だった平井くんがツルハシブックスに来店。
11年ぶりの再会。26歳になっていた彼が
「寄付侍になりたいんですけど」と言ってくれたこと。
お店をやるってことは、そんなドラマが生まれる場を創るってことなのかもしれません。
お客さんひとりひとりを共演者として、
新しい物語が生まれていく小さな本屋、
ツルハシブックスをこれからも一緒につくっていきましょう。
☆寄附侍を募集しています☆
1,000円の寄附で寄附侍認定バッチを差し上げます。※学生は500円で認定します!
3,000円の寄附で寄附侍名刺を100枚、作成します。
5,000円の寄附でバッチ+名刺+本の妖精が選ぶあなたにぴったりな1冊がプレゼントされます。
寄附侍になる方法は以下の2つです。
1 店頭寄附
ツルハシブックス店頭で受け付け用紙がありますので、
そちがにご記入の上、お申し出ください。
2 直接振込で寄附
事前にメール等で、氏名、住所、連絡先電話、メールを記入の上、
郵便振替口座 00580-2-92404 加入者名 NPO法人ヒーローズファーム
または
第四(ダイシ)銀行内野(ウチノ)支店(普)1858245
口座名義 NPO法人ヒーローズファーム 代表理事 西田卓司
へお振込みください。
ツルハシブックスはスタートしました。
まだまだ日本中が
大きな震災の中、何ができるのか、と
模索している中、
「持ち場を守る」という思いの中で、スタートしました。
周りの方々に支えられて、
なんとか3年を迎えることになりました。
本当にありがとうございます。
昨年3月20日には
2Fに「うちのカフェ イロハニ堂」がオープンして、
地元の方もたくさん足を運んでくれるようになり、
店頭にない本の注文も増えてきました。
今年の初めからスタートした
中学生・高校生に本屋を届ける移動ブックカフェ「ツルハシ号」プロジェクトには、
3月19日時点で、店頭で98名の寄付侍が誕生(総額 166,000円)
クラウドファウンディングFAAVO新潟で52名(総額 318,000円)、
計150名の寄付侍が誕生しています。

コミュニティデザイナー、山崎亮さん、なっぱさんにも77人目78人目の寄付侍になっていただきました。
ありがとうございます。
4月上旬には、ツルハシ号を購入し、
移動ブックカフェがお披露目したいと思っております。
金額的にはあと7万円ほどの資金が必要です。
引き続き、寄付侍のご協力をお待ちしています。
4年目を迎えるにあたって、
・ツルハシブックスの場としての魅力向上
・若者向けの企画の継続する体制づくり
の2つを行っていきたいと考えています。
「ツルハシブックスの場としての魅力向上」は
まずは、原点に回帰し、魅せる本屋へ。
若者限定の地下の古本発掘や、
若者が集まるイベントなどを行って、コミュニティに支えられた
ツルハシブックスですが、
「1冊の本で人生は変わる。本屋には新しい人生が転がっている。」
という初志に戻り、本の魅力を伝えていくことをさらに考えていきたいと考えています。
今年1月~3月の模様替えによって、メインとなるのは入って左側の壁一面。
そして奥のテーブル台、さらには独立した4つの本棚のシマ。
これらを活用して、本を読んでみたくなるプレゼンテーションを考えたいと思います。
そして、もうひとつは場として使ってもらうということ。
奥のテーブルから本を移動することによって、
8人~10名ほどは座れるミーティングスペースが誕生します。
ここを活用したトークイベントや、
あるいは明日からの3日間で試験的に行う屋台を使ったイベント
なども考えていきたいと思います。
また、3Fで行っている中学生高校生のための自習型学習塾「野山塾」
の子どもたちが何かを販売する「自営業体験」としての場としても
活用したいと考えています。
次に「若者向けの企画を継続する体制づくり」に関しては
1 中学生・高校生のための移動ブックカフェ「ツルハシ号」
2 高校生・大学生がプロデュースする商店街ミニ講座「うちのまち なじみのお店 ものがたり」
3 大学生・社会人がチャレンジする「食」と「農」を活用したビジネスを試験的に行うパラレル・キャリア・プラットフォームづくり
という3つのプロジェクトが動いていくかと思います。
これらのプロジェクトに対して、地域の人たちや、若者自身の関心領域へ
資金的にも、人材的にもアプローチできるような仕組みをつくりたいと思っています。
石の上にも3年と言いますが、
運営的にはまだまだかなり厳しい状況が続いています。
思いのある方々の力を借りながら、越えていきたいと思っています。
3年間でもっとも印象に残っているのは、昨年4月28日のこと。
2002年1月、僕の活動の原点となった家庭教師の経験。
受験勉強合宿の時に人生最高のすき焼きを食べて、
「中学生・高校生と一緒に将来を見つめる仕事がしたい」
「地域の人が中学生高校生と出会える仕組みをつくりたい」
と思わせてくれた、
当時不登校の中学校3年生だった平井くんがツルハシブックスに来店。
11年ぶりの再会。26歳になっていた彼が
「寄付侍になりたいんですけど」と言ってくれたこと。
お店をやるってことは、そんなドラマが生まれる場を創るってことなのかもしれません。
お客さんひとりひとりを共演者として、
新しい物語が生まれていく小さな本屋、
ツルハシブックスをこれからも一緒につくっていきましょう。
☆寄附侍を募集しています☆
1,000円の寄附で寄附侍認定バッチを差し上げます。※学生は500円で認定します!
3,000円の寄附で寄附侍名刺を100枚、作成します。
5,000円の寄附でバッチ+名刺+本の妖精が選ぶあなたにぴったりな1冊がプレゼントされます。
寄附侍になる方法は以下の2つです。
1 店頭寄附
ツルハシブックス店頭で受け付け用紙がありますので、
そちがにご記入の上、お申し出ください。
2 直接振込で寄附
事前にメール等で、氏名、住所、連絡先電話、メールを記入の上、
郵便振替口座 00580-2-92404 加入者名 NPO法人ヒーローズファーム
または
第四(ダイシ)銀行内野(ウチノ)支店(普)1858245
口座名義 NPO法人ヒーローズファーム 代表理事 西田卓司
へお振込みください。
2014年03月19日
世界と対話する方法
世界と対話するには、どうしたらいいのか?
書道科の卒業生と話をしていて、
そんなことをふと思った。
書を通して、世界と対話する。
もしかしたらみんな
世界と対話する方法を知りたいのではないか。
自己を表現し、
そのリアクションを見て、また表現する。
そんなことをしたいのではないか。
思えば僕も
そういう強い衝動を持っていた。
「何かで自分を、自分の思いを表現したい」
それはきっと、
まきどき村という畑での活動として、カタチになった。
そして今。
たぶん本屋さんという表現をしているのかもしれない。
ひとりひとりはいま、表現の場を必要としている気がする。
「世界と対話する。」
そんな空間がたくさんできたらいいなあと思う。
書道科の卒業生と話をしていて、
そんなことをふと思った。
書を通して、世界と対話する。
もしかしたらみんな
世界と対話する方法を知りたいのではないか。
自己を表現し、
そのリアクションを見て、また表現する。
そんなことをしたいのではないか。
思えば僕も
そういう強い衝動を持っていた。
「何かで自分を、自分の思いを表現したい」
それはきっと、
まきどき村という畑での活動として、カタチになった。
そして今。
たぶん本屋さんという表現をしているのかもしれない。
ひとりひとりはいま、表現の場を必要としている気がする。
「世界と対話する。」
そんな空間がたくさんできたらいいなあと思う。
2014年03月18日
「リスペクト」のある社会
「失われた10年」とは、
その国の経済が長く低迷した時代のことを呼ぶ。
日本ではバブル経済崩壊後の
1990年代~2000年代初頭にかけての期間。
だとすると
「失われた60年」という言葉があるとすると、
1954年から始まった経済成長・工業化路線は、
もちろん、得たものはたくさんあったかもしれないが、
その代償もたくさん払っているような気がする。
「商店街」や「地域コミュニティ」はその代表格だろうと思う。
「効率化」「コストパフォーマンス」に価値を置く社会では、
「商店街」と「地域コミュニティ」は衰退せざるを得ない。
しかし。
「効率化」と「コストパフォーマンス」という価値観によって、
もっとも失われたものは、
「リスペクト」のある社会ではないだろうか。
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」は
商店街の店主が、日々をていねいに生きているか、
を心から実感させられる。
それを感じると、
「この店で買いたい」と思う。
そこに
「好き」と「リスペクト」が起こるからだ。
2009年から「農家ファンクラブ」というのをつくり、
農家を勝手に応援していたが、
そのときのキーワードは「尊敬と感謝」だった。
それに近いものが商店街でも起こる。
「営み」の中で生きているということ。
そこに「好き」や「リスペクト」を感じられる
生活がしたい、と心から思う。
「コストパフォーマンス」だけが価値観だなんて、
つまらない人生というか、
それこそロボットやコンピューターで置き換え可能な人生だろう。
社会全体を覆うその価値観によって、
「働けない、働かない若者」は「価値がない」と断じられてしまう。
そのひとりひとりに対してのリスペクトはほとんどない。
就職活動はお見合いに例えられるが、
「お見合い」を本当にしているのは、一部優秀な学生に限られる。
そうではない学生は、
なんとかしてギリギリ引っかかろうと、
SPI対策をし、面接の練習をして、
大学受験のように、就職活動に臨む。
そこに「リスペクト」は存在しない。
きっと、取り戻すべきは、
「リスペクト」のある社会なのではないかな。
もしかすると、
商店街と農家から、その変革は始まるのかもしれない。

うちのまち なじみのお店 ものがたり@児玉輪店
そんなことを思うと、
ここ、新潟市西区西蒲区に大きなフロンティアを感じる。
その国の経済が長く低迷した時代のことを呼ぶ。
日本ではバブル経済崩壊後の
1990年代~2000年代初頭にかけての期間。
だとすると
「失われた60年」という言葉があるとすると、
1954年から始まった経済成長・工業化路線は、
もちろん、得たものはたくさんあったかもしれないが、
その代償もたくさん払っているような気がする。
「商店街」や「地域コミュニティ」はその代表格だろうと思う。
「効率化」「コストパフォーマンス」に価値を置く社会では、
「商店街」と「地域コミュニティ」は衰退せざるを得ない。
しかし。
「効率化」と「コストパフォーマンス」という価値観によって、
もっとも失われたものは、
「リスペクト」のある社会ではないだろうか。
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」は
商店街の店主が、日々をていねいに生きているか、
を心から実感させられる。
それを感じると、
「この店で買いたい」と思う。
そこに
「好き」と「リスペクト」が起こるからだ。
2009年から「農家ファンクラブ」というのをつくり、
農家を勝手に応援していたが、
そのときのキーワードは「尊敬と感謝」だった。
それに近いものが商店街でも起こる。
「営み」の中で生きているということ。
そこに「好き」や「リスペクト」を感じられる
生活がしたい、と心から思う。
「コストパフォーマンス」だけが価値観だなんて、
つまらない人生というか、
それこそロボットやコンピューターで置き換え可能な人生だろう。
社会全体を覆うその価値観によって、
「働けない、働かない若者」は「価値がない」と断じられてしまう。
そのひとりひとりに対してのリスペクトはほとんどない。
就職活動はお見合いに例えられるが、
「お見合い」を本当にしているのは、一部優秀な学生に限られる。
そうではない学生は、
なんとかしてギリギリ引っかかろうと、
SPI対策をし、面接の練習をして、
大学受験のように、就職活動に臨む。
そこに「リスペクト」は存在しない。
きっと、取り戻すべきは、
「リスペクト」のある社会なのではないかな。
もしかすると、
商店街と農家から、その変革は始まるのかもしれない。

うちのまち なじみのお店 ものがたり@児玉輪店
そんなことを思うと、
ここ、新潟市西区西蒲区に大きなフロンティアを感じる。
2014年03月17日
「ものがたり」のものがたり
うちのまち なじみのお店 ものがたり
2日目は「匠 for Hair」。
美容室で髪のお悩み解決じゅく。

まずは頭皮にやさしいシャンプー講座。
「リンスとトリートメントの違いがわかりますか?」
「えっ。なんですかそれ?」
「トリートメントは髪だけにつけてください」
そこで、
「ドルチェとデザートってどう違うんですか?」と
新潟レポの唐澤さんの取材(+ボケ+ツッコミ)もあって、
素敵な時間となりました。

こんな感じの風景。
参加者9名が思い思いの髪の悩みを相談していました。
本日は児玉輪店、自転車屋さんです。
30年乗れる整備の秘訣、教えてもらいましょう。
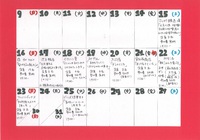
唐澤さんに取材を受けて、あらためて。
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」は
東京都渋谷区の「シブヤ大学」を発祥とする
20代社会人向けの「学びあいコミュニティづくり」と
愛知県岡崎市の「まちゼミ」を発祥とする
商店主が自分のお店で小さな講座を行う企画を
組み合わせたものです。
シブヤ大学のつくり方学科
というのをモグリで受講していた2009年度。
ファンドレイジング教会の鵜尾さんの講座など、
シビれる講座がたくさんでした。
固く言えば、「都市型の20代社会人向けの社会教育プラットフォーム」としてのシブヤ大学。
授業コーディネーターが講師の人と打ち合わせをして、講座内容を決定し、集客もし、授業を作り上げていくモデル。
これをやるには、新潟は若者の母数と、都市の集積している感じが足りないなあと。
また僕が万代や古町でやるイメージがなかったので、
シブヤ大学モデルは断念。
その次に飛び込んできたのが2012年度の「まちゼミ」の松井さんとの出会い。
商店主が主体となって講座を実施して、
商店街がコミュニケーションを取り戻し、お客さんが戻ってくるモデル。
こういうのがいいと思ったのだけど。
「まちゼミ」をやるには、主体的に動いてくれる商店主の数が
そんなに多くはないだろうということで、思い切って実施に踏み切れず。
また、もともと、
ツルハシブックスを商店街に出した経緯の初心は、
商店街を舞台にした大学生の学びのプログラムを作りたかったので、
そういう路線にもしたくって。
そうしたら、2013年度は
熊本の「マチナカレッジ」モデルに出会いました。
大学生と20代社会人が主体的に行動し、楽しい講座を作り上げているモデル。
ここは運営システムが非常に素晴らしいなあと思いました。
ということで、
シブヤ大学の授業コーディネーターを大学生がやり、
舞台を商店街の各お店でやるような
「まちゼミ+授業コーディネーター」なプログラムにしたいということで、
今回は実験的にやっています。
運営の仕組みは、「マチナカレッジ」さんの半年スパンの
実行委員会費制で行ければと思っています。
「シブヤ大学」+「まちゼミ」+「マチナカレッジ」
を組み合わせた企画。
(そう言うと、なんだかすごそうだ)
それが
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」です。
昨日の美容室はすごくシブヤ大学っぽいオシャレ感じだったし、
おとといの味噌屋さんは、まちゼミっぽいシブい感じでしたね。
今回のテスト版を経て、
2014年度からの定期開催を目指していきます。
次回はおそらく「和食」をテーマにした連続講座が
開催されると思いますので、お楽しみに。
2日目は「匠 for Hair」。
美容室で髪のお悩み解決じゅく。

まずは頭皮にやさしいシャンプー講座。
「リンスとトリートメントの違いがわかりますか?」
「えっ。なんですかそれ?」
「トリートメントは髪だけにつけてください」
そこで、
「ドルチェとデザートってどう違うんですか?」と
新潟レポの唐澤さんの取材(+ボケ+ツッコミ)もあって、
素敵な時間となりました。

こんな感じの風景。
参加者9名が思い思いの髪の悩みを相談していました。
本日は児玉輪店、自転車屋さんです。
30年乗れる整備の秘訣、教えてもらいましょう。
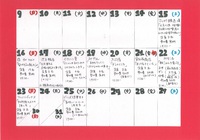
唐澤さんに取材を受けて、あらためて。
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」は
東京都渋谷区の「シブヤ大学」を発祥とする
20代社会人向けの「学びあいコミュニティづくり」と
愛知県岡崎市の「まちゼミ」を発祥とする
商店主が自分のお店で小さな講座を行う企画を
組み合わせたものです。
シブヤ大学のつくり方学科
というのをモグリで受講していた2009年度。
ファンドレイジング教会の鵜尾さんの講座など、
シビれる講座がたくさんでした。
固く言えば、「都市型の20代社会人向けの社会教育プラットフォーム」としてのシブヤ大学。
授業コーディネーターが講師の人と打ち合わせをして、講座内容を決定し、集客もし、授業を作り上げていくモデル。
これをやるには、新潟は若者の母数と、都市の集積している感じが足りないなあと。
また僕が万代や古町でやるイメージがなかったので、
シブヤ大学モデルは断念。
その次に飛び込んできたのが2012年度の「まちゼミ」の松井さんとの出会い。
商店主が主体となって講座を実施して、
商店街がコミュニケーションを取り戻し、お客さんが戻ってくるモデル。
こういうのがいいと思ったのだけど。
「まちゼミ」をやるには、主体的に動いてくれる商店主の数が
そんなに多くはないだろうということで、思い切って実施に踏み切れず。
また、もともと、
ツルハシブックスを商店街に出した経緯の初心は、
商店街を舞台にした大学生の学びのプログラムを作りたかったので、
そういう路線にもしたくって。
そうしたら、2013年度は
熊本の「マチナカレッジ」モデルに出会いました。
大学生と20代社会人が主体的に行動し、楽しい講座を作り上げているモデル。
ここは運営システムが非常に素晴らしいなあと思いました。
ということで、
シブヤ大学の授業コーディネーターを大学生がやり、
舞台を商店街の各お店でやるような
「まちゼミ+授業コーディネーター」なプログラムにしたいということで、
今回は実験的にやっています。
運営の仕組みは、「マチナカレッジ」さんの半年スパンの
実行委員会費制で行ければと思っています。
「シブヤ大学」+「まちゼミ」+「マチナカレッジ」
を組み合わせた企画。
(そう言うと、なんだかすごそうだ)
それが
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」です。
昨日の美容室はすごくシブヤ大学っぽいオシャレ感じだったし、
おとといの味噌屋さんは、まちゼミっぽいシブい感じでしたね。
今回のテスト版を経て、
2014年度からの定期開催を目指していきます。
次回はおそらく「和食」をテーマにした連続講座が
開催されると思いますので、お楽しみに。
2014年03月16日
味噌を買いに商店へ
スーパーに持っていけば、安く買い叩かれる。
それでは、小さな店はやってけない。
マルカク醸造場
味噌・醤油の製造販売。

お父さんの熱弁が続く。
味噌がいかに体にいいのか?
「減塩」運動のやり玉に味噌汁が
挙がったことの不思議さ。
新聞に味噌の健康効果についての記事が
載るたびに大量にコピーして配る。
ここに、
「誇り」あふれるひとりの店主がいた。
「あなたは誰が作った味噌を食べたいですか?」
そんなキャッチが浮かぶ。
味噌を買いに商店へ。
また味噌を買いに行きたいから、
毎日、お父さんの顔を浮かべて味噌汁を作る。
そんなライフスタイルもステキだなあって思う。

みんな、いい顔しています。
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」
始まりました。

3月15日(土)14:00 マルカク醸造場「元気の源、味噌の効用と味噌屋のカンタン味噌料理のミソ」 定員8名 参加費無料
3月16日(日)19:30 匠for Hair「髪のお悩み解決じゅく」 定員 15名 参加費無料
3月17日(月)14:00 児玉輪店「30年乗れる点検の秘訣と乗り方」定員8名 参加費無料 ※自転車持ち込み歓迎
3月18日(火)14:00 イロハニ堂「おしゃれ女子のためのひとりカフェ入門」定員4名 参加費 500円
3月19日(水)14:00 みやん「まゆをキレイに~ステキな女性への第一歩」定員4名 参加費無料
3月20日(木)10:00 大口屋「ダシのとり方」 定員8名 参加費 500円(昼食付)
3月21日(金)11:00 飯塚商店「米は生きている」定員8名 参加費 300円(おにぎり付)
3月23日(日)10:00 ツルハシブックス「初対面の人との接し方」定員8名 参加費無料
3月25日(火)17:00 ビーンズ倶楽部「美味しいコーヒーの淹れ方」定員8名 参加費500円(コーヒー飲み比べ付)
会場はそれぞれのお店となります。
参加問い合わせはツルハシブックスまで。
それでは、小さな店はやってけない。
マルカク醸造場
味噌・醤油の製造販売。

お父さんの熱弁が続く。
味噌がいかに体にいいのか?
「減塩」運動のやり玉に味噌汁が
挙がったことの不思議さ。
新聞に味噌の健康効果についての記事が
載るたびに大量にコピーして配る。
ここに、
「誇り」あふれるひとりの店主がいた。
「あなたは誰が作った味噌を食べたいですか?」
そんなキャッチが浮かぶ。
味噌を買いに商店へ。
また味噌を買いに行きたいから、
毎日、お父さんの顔を浮かべて味噌汁を作る。
そんなライフスタイルもステキだなあって思う。

みんな、いい顔しています。
「うちのまち なじみのお店 ものがたり」
始まりました。

3月15日(土)14:00 マルカク醸造場「元気の源、味噌の効用と味噌屋のカンタン味噌料理のミソ」 定員8名 参加費無料
3月16日(日)19:30 匠for Hair「髪のお悩み解決じゅく」 定員 15名 参加費無料
3月17日(月)14:00 児玉輪店「30年乗れる点検の秘訣と乗り方」定員8名 参加費無料 ※自転車持ち込み歓迎
3月18日(火)14:00 イロハニ堂「おしゃれ女子のためのひとりカフェ入門」定員4名 参加費 500円
3月19日(水)14:00 みやん「まゆをキレイに~ステキな女性への第一歩」定員4名 参加費無料
3月20日(木)10:00 大口屋「ダシのとり方」 定員8名 参加費 500円(昼食付)
3月21日(金)11:00 飯塚商店「米は生きている」定員8名 参加費 300円(おにぎり付)
3月23日(日)10:00 ツルハシブックス「初対面の人との接し方」定員8名 参加費無料
3月25日(火)17:00 ビーンズ倶楽部「美味しいコーヒーの淹れ方」定員8名 参加費500円(コーヒー飲み比べ付)
会場はそれぞれのお店となります。
参加問い合わせはツルハシブックスまで。
2014年03月15日
その店を選ぶ自分が好き
なぜ、あの人は同じ会社のものばかり、買い続けるのか?
ロングエンゲージメント。
そんなことを考えさせられる1日でした。
究極。
人が買い続けるのは、
「その店を選ぶ自分が好き」
「その店で買い続ける自分が好き」
なんだなあと。
それってなんだろう?
「コストパフォーマンス」ではない価値観を
表現しているお店。
そういうことなんですよね。
たとえば。
コメダ珈琲。
11時までに行くと、
トーストとゆでたまごがサービスされます。
10時過ぎから11時。
コメダ珈琲は来店客の1度目のピークを迎えます。
ひと仕事終えた、家庭の主婦の方が
その時間を目指してくるからです。
コーヒー自体は、400円~と決して安くはないのですが、
その名古屋風の「トーストとゆでたまごサービス」というお得感が
人を惹きつけるのでしょう。
あとは、何時間でもそこに居座ってもいい安心感もあります。
400円~500円という出費で
朝食と数時間の居場所を提供している、
そんな「コストパフォーマンス」の高さがあります。
また、ドトールやスタバのようなセルフ式ではないので、
「注文の仕方がよく分からない」という
年配の方の不安を解消していると思います。
あるいは、
かつての古き良き喫茶店に回帰しているのかもしれません。
喫茶店で待ち合わせ、友達と談笑したあの頃を思い出させるのかもしれません。
しかし。
そこには、話を聞いてくれたマスターは不在です。
だから、
その店である必然性はありません。
たとえば、コメダ珈琲の新潟新和店に行こうと思っていたけど、
ちょっと予定が変わったので、青山のイオンの中のコメダでいいかな、ということが起こります。
もちろん、席配置などで、圧倒的に僕は新和店のほうがくつろぐのだけど、
それだけでは、新和店でなければダメだ、という理由にはなりません。
その店でなければ。
それは、たとえば、ラーメン「いっとうや」
かつて、僕がmixi上でファンクラブをつくっていた
ラーメン店です。
最初はもちろん、味が好きなんですけど、
ラーメンに込められた心意気がとても素敵なんです。
ビックリしたのは、
生ビールの泡のクリーミーさが
そのへんの居酒屋レベルを遥かに凌ぐことです。
そして、
メニューの下の方に書いてある
「お子様が近くにいらっしゃるときは、禁煙にご協力お願いします」
そんなこと書いてあるラーメン屋さん、ありますか?
ほかにもいろいろあって、
「僕がいっとうやを選ぶ理由」
っていう小冊子がかけそうなくらいなんですが。(笑)
好きっていうのはいいなあと思います。
大好きなお店で食事をするっていう喜び。
きっとツルハシブックス2Fのイロハニ堂もそういうお客さんがたくさんいるんだろうなって。
そして。
新潟大学前の居酒屋「よし半」
昔ながらの大衆居酒屋です。
僕が大学の頃から残っている居酒屋は
おそらく4,5件くらいしかないのではないかな。
チェーン店や激安店は、飲み放題もついて、2000円とか
いう破格の価格でやっています。
ただ、酔って盛り上がればいい、という人は、
そちらを選択するでしょう。
そこで、このメニューの言葉

熱い。
素晴らしい。
なぜ、私たちは飲み放題をやらないのか?
私たちにとって「価値」とはなにか?
これを表現しています。
そして、学生のゼミの飲み会などでは、
気の利かない学生に対して、
「ほら、先生のコップ、空になってるよ」
というおせっかいぶりを発揮。
そんなエピソードに詰まったお店、よし半。
もちろん料理のクオリティも素晴らしく、
特に、定番のもつ煮と牛すじ煮は、毎日売り切れになるほどの人気。
ただ、立地的に駅からは15分~20分くらい歩くことになるので、
その点だけ、冬や悪天候のときはつらいかなと。
遠方の方、ツルハシブックスにご来店の際は、
ぜひ行ってみて欲しいお店です。
選ばれる店、
いや、選ばれ続ける店は、
「その店を選ぶ自分が好き」なお客さんに支えられたお店です。
あなたのお店は、
「最高のコストパフォーマンス」で勝負しますか?
それとも、
「その店を選ぶ自分が好き」なお客さんのリピート率で勝負しますか?
ラーメン屋や居酒屋のようにメニューでも勝負できるお店ではなくて、
どこで買っても、誰から買っても同じだという商品を扱っているお店には、
必須の問いになってくるのではないでしょうか。
ラーメン屋や居酒屋も、激しい競争の中、
そうやって伸び、そして残ってきたのに、
本屋はそれをやらずに消えていってどうするんだと強く思いました。
ロングエンゲージメント。
そんなことを考えさせられる1日でした。
究極。
人が買い続けるのは、
「その店を選ぶ自分が好き」
「その店で買い続ける自分が好き」
なんだなあと。
それってなんだろう?
「コストパフォーマンス」ではない価値観を
表現しているお店。
そういうことなんですよね。
たとえば。
コメダ珈琲。
11時までに行くと、
トーストとゆでたまごがサービスされます。
10時過ぎから11時。
コメダ珈琲は来店客の1度目のピークを迎えます。
ひと仕事終えた、家庭の主婦の方が
その時間を目指してくるからです。
コーヒー自体は、400円~と決して安くはないのですが、
その名古屋風の「トーストとゆでたまごサービス」というお得感が
人を惹きつけるのでしょう。
あとは、何時間でもそこに居座ってもいい安心感もあります。
400円~500円という出費で
朝食と数時間の居場所を提供している、
そんな「コストパフォーマンス」の高さがあります。
また、ドトールやスタバのようなセルフ式ではないので、
「注文の仕方がよく分からない」という
年配の方の不安を解消していると思います。
あるいは、
かつての古き良き喫茶店に回帰しているのかもしれません。
喫茶店で待ち合わせ、友達と談笑したあの頃を思い出させるのかもしれません。
しかし。
そこには、話を聞いてくれたマスターは不在です。
だから、
その店である必然性はありません。
たとえば、コメダ珈琲の新潟新和店に行こうと思っていたけど、
ちょっと予定が変わったので、青山のイオンの中のコメダでいいかな、ということが起こります。
もちろん、席配置などで、圧倒的に僕は新和店のほうがくつろぐのだけど、
それだけでは、新和店でなければダメだ、という理由にはなりません。
その店でなければ。
それは、たとえば、ラーメン「いっとうや」
かつて、僕がmixi上でファンクラブをつくっていた
ラーメン店です。
最初はもちろん、味が好きなんですけど、
ラーメンに込められた心意気がとても素敵なんです。
ビックリしたのは、
生ビールの泡のクリーミーさが
そのへんの居酒屋レベルを遥かに凌ぐことです。
そして、
メニューの下の方に書いてある
「お子様が近くにいらっしゃるときは、禁煙にご協力お願いします」
そんなこと書いてあるラーメン屋さん、ありますか?
ほかにもいろいろあって、
「僕がいっとうやを選ぶ理由」
っていう小冊子がかけそうなくらいなんですが。(笑)
好きっていうのはいいなあと思います。
大好きなお店で食事をするっていう喜び。
きっとツルハシブックス2Fのイロハニ堂もそういうお客さんがたくさんいるんだろうなって。
そして。
新潟大学前の居酒屋「よし半」
昔ながらの大衆居酒屋です。
僕が大学の頃から残っている居酒屋は
おそらく4,5件くらいしかないのではないかな。
チェーン店や激安店は、飲み放題もついて、2000円とか
いう破格の価格でやっています。
ただ、酔って盛り上がればいい、という人は、
そちらを選択するでしょう。
そこで、このメニューの言葉

熱い。
素晴らしい。
なぜ、私たちは飲み放題をやらないのか?
私たちにとって「価値」とはなにか?
これを表現しています。
そして、学生のゼミの飲み会などでは、
気の利かない学生に対して、
「ほら、先生のコップ、空になってるよ」
というおせっかいぶりを発揮。
そんなエピソードに詰まったお店、よし半。
もちろん料理のクオリティも素晴らしく、
特に、定番のもつ煮と牛すじ煮は、毎日売り切れになるほどの人気。
ただ、立地的に駅からは15分~20分くらい歩くことになるので、
その点だけ、冬や悪天候のときはつらいかなと。
遠方の方、ツルハシブックスにご来店の際は、
ぜひ行ってみて欲しいお店です。
選ばれる店、
いや、選ばれ続ける店は、
「その店を選ぶ自分が好き」なお客さんに支えられたお店です。
あなたのお店は、
「最高のコストパフォーマンス」で勝負しますか?
それとも、
「その店を選ぶ自分が好き」なお客さんのリピート率で勝負しますか?
ラーメン屋や居酒屋のようにメニューでも勝負できるお店ではなくて、
どこで買っても、誰から買っても同じだという商品を扱っているお店には、
必須の問いになってくるのではないでしょうか。
ラーメン屋や居酒屋も、激しい競争の中、
そうやって伸び、そして残ってきたのに、
本屋はそれをやらずに消えていってどうするんだと強く思いました。
2014年03月14日
対話からスモールビジネスを生む
昨日は、プレゼンでした。
ぜんぜん伝える力がないなあって思いました。
言語が違う人たちをどのようにつないでいくか
それが僕ら世代の役割であるのに、
僕自身がそれを放棄してはいけないなあと思いました。
ツルハシブックスは、ニュービジネスなのか?
という問い。
これに答えられなかった自分の未熟さを感じました。
ツルハシブックスをビジネス社会から見ると、どうなるのか?
という問いにもっと答えていかないといけないと思いました。
反省会を含めて、
帰りの電車でひとり振り返り。
ツルハシブックスを地域経済視点から見ると、
「パラレル・キャリア・プラットフォーム」
なのだと思います。
「成長産業は雇用を生まない」ということは、
これからますます雇用、特に正規雇用の機会は減っていきます。
これは社会の変化の必然であり、
言い方を替えれば、
この60年が特殊な「正規雇用の時代」
だったと言えるでしょう。
それを可能にしたのは、
人口増を背景とした工業社会の発展です。
日本経済が飛躍的に経済成長を遂げたのは
1954年からだと言われています。
工業に設備を投資し、大量生産・大量消費が可能になったのです。
2014年現在60歳の人までは、
この高度経済成長期突入以降の日本しか知りません。
このときから始まった価値観は「効率化」です。
「効率化」思想は、60年の時をかけて、
日本の隅々にまで行き渡りました。
「効率化」思想は工場では、
「分業」の考えを発展させました。
テレビをひとりでつくるよりも、
あなたは部品を組み立て、あなたはテレビ枠をつける
こうしたほうが何十倍、何百倍も多く生産できるからです。
「分業」の発展は「専業」の思想、
仕事VS余暇(プライベート)の思想を生みました。
こうして、
地域コミュニティから祭りなどの行事が消えていきます。
地域の行事に参加することは、
自分の人生にとって、効率的ではないからです。
地域から農業が消えていきます。
工業のほうが効率的だからです。
都会に若者は出ていきます。
都会のほうが効率的に稼げるからです。
こうして、地域商店街や農業を中心とした地域産業は疲弊し、
厳しい経済状況におかれる中で、原発の立地が進みました。
しかし。
あれから60年が過ぎ、社会は大きく変わりました。
ビジネスの領域も変わりました。
もはや、「効率化」では価値は生めません。
そもそも前提となっていた人口増が崩れ、
人口減少社会に突入しているので、
「効率化」が価値を生めないのは仕方ありません。
「ナリワイをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)
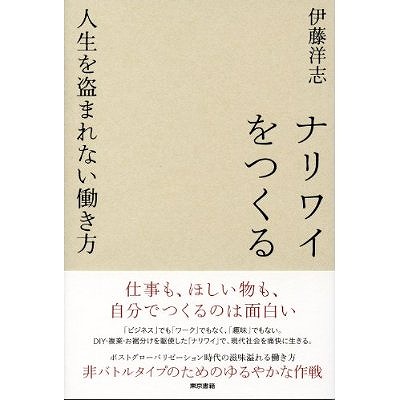
で伊藤さんが言っているように、
この60年だけが、特殊な専業の時代だったと
言えるのではないでしょうか。
これからの時代、
ひとつの仕事だけで十分な収入を得ていくのは難しいことだと思います。
だからこそ、
地域の資源を生かした、スモールビジネスを
自ら創っていくことが求められます。
それには、東京よりも、新潟のほうが、
新潟市中心部よりも、西区内野のような、
田園地帯と住宅地帯が混在する場所のほうが
スモールビジネスを生んでいく可能性が高いと考えられます。
ツルハシブックスは、
「農」「食」をテーマにした
「パラレル・キャリア・プラットフォーム」
になり得ると僕は思います。
そして、それこそが地域再生の具体的方法
になっていくのではないかと思うのです。
「本業で食えない。」
それは、地域にとっては、嘆くことばかりではなく、
ふたたび地域に若者が入ってきて、
小さなビジネスを起こしていくチャンスの時代の
到来を予感させます。
「農」と「食」、あるいは「本」をキーワードに、
地域と対話し、上の世代と対話し、自分を活かせる
スモールビジネスを生んでいく。
あるいは、ひとりではなくチームで取り組んでみる。
そうして、スモールビジネスが数多く生まれていく。
そんなプラットフォームが地域には必要なのではないでしょうか。
「対話によるスモールビジネスづくり」
そんな文化を創っていくこと、
そこにツルハシブックスの使命のひとつがあるのでは、
と思いを新たにしたプレゼンテーションでした。
なんだか楽しくなってきました。
それにしても、まだまだ経済社会言語での対話がうまくできないのは、
まだまだ努力が必要です。
ぜんぜん伝える力がないなあって思いました。
言語が違う人たちをどのようにつないでいくか
それが僕ら世代の役割であるのに、
僕自身がそれを放棄してはいけないなあと思いました。
ツルハシブックスは、ニュービジネスなのか?
という問い。
これに答えられなかった自分の未熟さを感じました。
ツルハシブックスをビジネス社会から見ると、どうなるのか?
という問いにもっと答えていかないといけないと思いました。
反省会を含めて、
帰りの電車でひとり振り返り。
ツルハシブックスを地域経済視点から見ると、
「パラレル・キャリア・プラットフォーム」
なのだと思います。
「成長産業は雇用を生まない」ということは、
これからますます雇用、特に正規雇用の機会は減っていきます。
これは社会の変化の必然であり、
言い方を替えれば、
この60年が特殊な「正規雇用の時代」
だったと言えるでしょう。
それを可能にしたのは、
人口増を背景とした工業社会の発展です。
日本経済が飛躍的に経済成長を遂げたのは
1954年からだと言われています。
工業に設備を投資し、大量生産・大量消費が可能になったのです。
2014年現在60歳の人までは、
この高度経済成長期突入以降の日本しか知りません。
このときから始まった価値観は「効率化」です。
「効率化」思想は、60年の時をかけて、
日本の隅々にまで行き渡りました。
「効率化」思想は工場では、
「分業」の考えを発展させました。
テレビをひとりでつくるよりも、
あなたは部品を組み立て、あなたはテレビ枠をつける
こうしたほうが何十倍、何百倍も多く生産できるからです。
「分業」の発展は「専業」の思想、
仕事VS余暇(プライベート)の思想を生みました。
こうして、
地域コミュニティから祭りなどの行事が消えていきます。
地域の行事に参加することは、
自分の人生にとって、効率的ではないからです。
地域から農業が消えていきます。
工業のほうが効率的だからです。
都会に若者は出ていきます。
都会のほうが効率的に稼げるからです。
こうして、地域商店街や農業を中心とした地域産業は疲弊し、
厳しい経済状況におかれる中で、原発の立地が進みました。
しかし。
あれから60年が過ぎ、社会は大きく変わりました。
ビジネスの領域も変わりました。
もはや、「効率化」では価値は生めません。
そもそも前提となっていた人口増が崩れ、
人口減少社会に突入しているので、
「効率化」が価値を生めないのは仕方ありません。
「ナリワイをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)
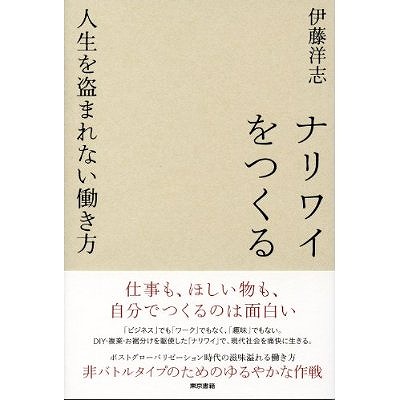
で伊藤さんが言っているように、
この60年だけが、特殊な専業の時代だったと
言えるのではないでしょうか。
これからの時代、
ひとつの仕事だけで十分な収入を得ていくのは難しいことだと思います。
だからこそ、
地域の資源を生かした、スモールビジネスを
自ら創っていくことが求められます。
それには、東京よりも、新潟のほうが、
新潟市中心部よりも、西区内野のような、
田園地帯と住宅地帯が混在する場所のほうが
スモールビジネスを生んでいく可能性が高いと考えられます。
ツルハシブックスは、
「農」「食」をテーマにした
「パラレル・キャリア・プラットフォーム」
になり得ると僕は思います。
そして、それこそが地域再生の具体的方法
になっていくのではないかと思うのです。
「本業で食えない。」
それは、地域にとっては、嘆くことばかりではなく、
ふたたび地域に若者が入ってきて、
小さなビジネスを起こしていくチャンスの時代の
到来を予感させます。
「農」と「食」、あるいは「本」をキーワードに、
地域と対話し、上の世代と対話し、自分を活かせる
スモールビジネスを生んでいく。
あるいは、ひとりではなくチームで取り組んでみる。
そうして、スモールビジネスが数多く生まれていく。
そんなプラットフォームが地域には必要なのではないでしょうか。
「対話によるスモールビジネスづくり」
そんな文化を創っていくこと、
そこにツルハシブックスの使命のひとつがあるのでは、
と思いを新たにしたプレゼンテーションでした。
なんだか楽しくなってきました。
それにしても、まだまだ経済社会言語での対話がうまくできないのは、
まだまだ努力が必要です。
2014年03月13日
数値化領域と非数値化領域
「ジェネリック・スキル」
社会で活躍するために必要なスキル。
現在社会で活躍している
社会人の人たちの思考行動特性を
指標化し、それを測るテストも出始めた。
これによって、
いわゆる「キャリア教育」の数値化を目指す。
指標となるのは
「リテラシー」と「コンピテンシー」
「リテラシー」は、
情報収集力、情報分析力、課題発見力、
構想力、表現力からの実行力育成を目指す。
「コンピテンシー」は、
「対人基礎力」:親和力、協働力、統率力
「対自己基礎力」:感情制御力、自己創出力、行動持続力
「対課題基礎力」:課題発見力、計画立案力、実践力
これらが数値的に向上すれば、
社会で活躍できる人材が育っている、という理論。
なるほどなあ、と思った。
たしかにそれを数値化できれば、
目標数値のあるキャリア教育が可能になる。
しかし。
それが全てではないとも思う。
言語化できない、数値化できない
領域の何かも必要だと思う。
それを言語化できないけど。
九州国際大学の山本先生が
面白いスライドを提示してくれた。
「ガクチカ」から見るコンピテンシー
「ガクチカ」とは、
就職の面接でよく問われる、
「あなたは学生時代に何に力を入れましたか?」という質問のこと。
その答えは、
部活、ボランティア、アルバイトでもなんでもいいのだけど、
その追加の質問でコンピテンシーが測れるという。
追加の質問で
「対人基礎力」を測るには、
・団体・組織の雰囲気づくりのために何をしましたか?
・団体・組織で働くためにどんなことをしましたか?
・後輩をどのように指導しましたか?
・対立が起きた時、どのように対処しましたか?
という質問。
「対自己基礎力」は
・団体・組織の中であなたはどのような役割を果たす人間だと思いますか?
・困ったとき、落ち込んだとき、どのように対処しますか?
・成功体験、失敗体験から何を学びましたか?
・あなたが目標とする人はいますか?
「対課題基礎力」は
・自分なりにどのような目標をたてたのですか?
・どんな計画を立てて目標にのぞみましたか?
・その後、どんな改善をしたのですか?
とまあ、こんな感じ。
これは面白いなあと。
就活する前というか、
1年次から2年次に上がるときに、
こういう質問をしたほうがいいのではないかな、と思った。
すべての活動をしていく上で、
これらの質問に答えられないということは、
その組織の活動が弱いか、あるいは自分のコミット度が足りないということに
なるのではないか。
面白いなあと思ったのは、
とある大学の数値で、
一般入試と推薦・AO入試の子の
リテラシーとコンピテンシーの差が見られたという報告。
一般入試の学生はリテラシーが相対的に高く、
推薦・AO入試の学生はコンピテンシーが相対的に高い。
リテラシーの方は、受験をくぐり抜けたほうが数値が高くなるのはなんとなくわかるのだけど、
リテラシーが向上することとコンピテンシーの向上が連動していないというのは、
少し面白いなあと思った。
受験によって、あるいは受験成功によって、失われる何かがあるのかもしれない、ということ。
こういうのってどうしてなのか、すごく知りたいなあと思う。
こういう数値化領域の話は、
そんなに考えたことがなかったので、面白いなあと感じた。
数値化領域と非数値化領域が
バランスを取りながら向上していくような機会の提供。
これが必要なのだろうと思う。
大学としては、数値化領域を
本屋としては、非数値化領域を
担当していくことなのかもしれない。
今日もワクワクした1日を。
社会で活躍するために必要なスキル。
現在社会で活躍している
社会人の人たちの思考行動特性を
指標化し、それを測るテストも出始めた。
これによって、
いわゆる「キャリア教育」の数値化を目指す。
指標となるのは
「リテラシー」と「コンピテンシー」
「リテラシー」は、
情報収集力、情報分析力、課題発見力、
構想力、表現力からの実行力育成を目指す。
「コンピテンシー」は、
「対人基礎力」:親和力、協働力、統率力
「対自己基礎力」:感情制御力、自己創出力、行動持続力
「対課題基礎力」:課題発見力、計画立案力、実践力
これらが数値的に向上すれば、
社会で活躍できる人材が育っている、という理論。
なるほどなあ、と思った。
たしかにそれを数値化できれば、
目標数値のあるキャリア教育が可能になる。
しかし。
それが全てではないとも思う。
言語化できない、数値化できない
領域の何かも必要だと思う。
それを言語化できないけど。
九州国際大学の山本先生が
面白いスライドを提示してくれた。
「ガクチカ」から見るコンピテンシー
「ガクチカ」とは、
就職の面接でよく問われる、
「あなたは学生時代に何に力を入れましたか?」という質問のこと。
その答えは、
部活、ボランティア、アルバイトでもなんでもいいのだけど、
その追加の質問でコンピテンシーが測れるという。
追加の質問で
「対人基礎力」を測るには、
・団体・組織の雰囲気づくりのために何をしましたか?
・団体・組織で働くためにどんなことをしましたか?
・後輩をどのように指導しましたか?
・対立が起きた時、どのように対処しましたか?
という質問。
「対自己基礎力」は
・団体・組織の中であなたはどのような役割を果たす人間だと思いますか?
・困ったとき、落ち込んだとき、どのように対処しますか?
・成功体験、失敗体験から何を学びましたか?
・あなたが目標とする人はいますか?
「対課題基礎力」は
・自分なりにどのような目標をたてたのですか?
・どんな計画を立てて目標にのぞみましたか?
・その後、どんな改善をしたのですか?
とまあ、こんな感じ。
これは面白いなあと。
就活する前というか、
1年次から2年次に上がるときに、
こういう質問をしたほうがいいのではないかな、と思った。
すべての活動をしていく上で、
これらの質問に答えられないということは、
その組織の活動が弱いか、あるいは自分のコミット度が足りないということに
なるのではないか。
面白いなあと思ったのは、
とある大学の数値で、
一般入試と推薦・AO入試の子の
リテラシーとコンピテンシーの差が見られたという報告。
一般入試の学生はリテラシーが相対的に高く、
推薦・AO入試の学生はコンピテンシーが相対的に高い。
リテラシーの方は、受験をくぐり抜けたほうが数値が高くなるのはなんとなくわかるのだけど、
リテラシーが向上することとコンピテンシーの向上が連動していないというのは、
少し面白いなあと思った。
受験によって、あるいは受験成功によって、失われる何かがあるのかもしれない、ということ。
こういうのってどうしてなのか、すごく知りたいなあと思う。
こういう数値化領域の話は、
そんなに考えたことがなかったので、面白いなあと感じた。
数値化領域と非数値化領域が
バランスを取りながら向上していくような機会の提供。
これが必要なのだろうと思う。
大学としては、数値化領域を
本屋としては、非数値化領域を
担当していくことなのかもしれない。
今日もワクワクした1日を。
2014年03月12日
これからのビジネスの価値はどう変わるのか?
「価値がある」とは、いったいなんだろうか?
東日本大震災から3年。
価値観が大きく揺らいでいる、と言われる。
では、これから来る時代に向けて、
ビジネスは何ができるだろうか?
ビジネスとして「新しい」とは何か?
「価値がある」とはなんだろうか?
3年前。
震災真っ只中に、
小さな本屋「ツルハシブックス」はスタートした。
本屋という業界は非常に厳しいと言われる。
利益率の低さ、
雑誌、書籍の販売数の低下、などなど。
本屋を取り巻く状況は厳しい。
では一方、
伸びている本屋とはどんな本屋か?
TSUTAYA、あるいは、ヴィレッジヴァンガード。

「ロングエンゲージメント~なぜあの人は同じ会社のものばかり買い続けるのか?」(京井良彦 あさ出版)
によると、
「共感」の時代に必要なのは、
「コンセプト(全体像)」
「ストーリー(物語)」
「デザイン」
だという。
おじさんたちは、
TSUTAYAはDVDレンタルで、
ヴィレッジヴァンガードは雑貨で利益を出しているんでしょう?
と言って、何かわかったような気になってしまう。
TSUTAYAは、社長の言葉を借りれば、
「ライフスタイルを売っている」というコンセプトがあり、
ヴィレッジヴァンガードに来るお客さんが求めているのは、
商品そのものではなく、偶然の出会いやワクワクといった
感性的な価値ではないか。
そして、最近出てきたのは
個人経営の複合書店。
下北沢B&Bは毎日著者などのトークイベントを開催している。
本屋というのは、
プラットフォームとして非常に魅力的だと
始めてみてからわかった。
そこには、本と人の多様性と偶然性があふれているので、
人々が無意識のうちに可能性を感じてしまう空間が出来上がる。
そして、「ワークデザイン」のあの一節
「成長産業はもはや雇用を生まない」
接客しながらお客さんの顔を覚えて次に買う商品を提案した時代は、
「ポテトもいかがですか?」とマニュアル化された後に、
「この本を買った人はこちらの本も買っています」、とコンピューターが
データから自動的に提案する時代になった。
この変化に真剣に向き合うとしたら、
いま、日本海側の小さな地方都市・新潟では、
どんなことを目指すべきなのか?
ビジネスにおける価値とはなんだろうか?
どんな文化を創っていきたいのか?
その大きな絵に向けて、
小さな本屋はどんな役割を果たしていくのか?
「ワークデザイン」によると、
世の中は「消費社会」から「生産社会」へのシフト中
なのだという。
「生理的・尊厳欲求」から「自己実現・貢献欲求」へ。
「消費・勝ち負け」から「生産・共生」の価値観へ。
主役は「大企業」から「個人・チーム」に替わり、
職業数は増え、「大量生産・消費」から「多品種適量生産」へシフトする。
そうなると、
新しいビジネスのスタートは、
「お金」ではなく「コミュニティ(ソーシャルキャピタル)」になっていく。
そんなプラットフォームが必要だとすると、
多機能型の小さな本屋さんというのは、
そのプラットフォームになりうるのではないかと思う。
ツルハシブックスであれば、
その立地条件を生かして、
「農業生産」と「大学生」、「商店街」や「都市型生活者」
などを組み合わせた小さなビジネスを起こしていく場。
それを「本屋」がつないでいく。
そういうのは、想像できるのではないか。
これからのビジネスにおける価値とは何か?
という問いからすれば、
そういうプラットフォームが地域にあるというのは、
大きな価値があると僕は思う。
東日本大震災から3年。
価値観が大きく揺らいでいる、と言われる。
では、これから来る時代に向けて、
ビジネスは何ができるだろうか?
ビジネスとして「新しい」とは何か?
「価値がある」とはなんだろうか?
3年前。
震災真っ只中に、
小さな本屋「ツルハシブックス」はスタートした。
本屋という業界は非常に厳しいと言われる。
利益率の低さ、
雑誌、書籍の販売数の低下、などなど。
本屋を取り巻く状況は厳しい。
では一方、
伸びている本屋とはどんな本屋か?
TSUTAYA、あるいは、ヴィレッジヴァンガード。

「ロングエンゲージメント~なぜあの人は同じ会社のものばかり買い続けるのか?」(京井良彦 あさ出版)
によると、
「共感」の時代に必要なのは、
「コンセプト(全体像)」
「ストーリー(物語)」
「デザイン」
だという。
おじさんたちは、
TSUTAYAはDVDレンタルで、
ヴィレッジヴァンガードは雑貨で利益を出しているんでしょう?
と言って、何かわかったような気になってしまう。
TSUTAYAは、社長の言葉を借りれば、
「ライフスタイルを売っている」というコンセプトがあり、
ヴィレッジヴァンガードに来るお客さんが求めているのは、
商品そのものではなく、偶然の出会いやワクワクといった
感性的な価値ではないか。
そして、最近出てきたのは
個人経営の複合書店。
下北沢B&Bは毎日著者などのトークイベントを開催している。
本屋というのは、
プラットフォームとして非常に魅力的だと
始めてみてからわかった。
そこには、本と人の多様性と偶然性があふれているので、
人々が無意識のうちに可能性を感じてしまう空間が出来上がる。
そして、「ワークデザイン」のあの一節
「成長産業はもはや雇用を生まない」
接客しながらお客さんの顔を覚えて次に買う商品を提案した時代は、
「ポテトもいかがですか?」とマニュアル化された後に、
「この本を買った人はこちらの本も買っています」、とコンピューターが
データから自動的に提案する時代になった。
この変化に真剣に向き合うとしたら、
いま、日本海側の小さな地方都市・新潟では、
どんなことを目指すべきなのか?
ビジネスにおける価値とはなんだろうか?
どんな文化を創っていきたいのか?
その大きな絵に向けて、
小さな本屋はどんな役割を果たしていくのか?
「ワークデザイン」によると、
世の中は「消費社会」から「生産社会」へのシフト中
なのだという。
「生理的・尊厳欲求」から「自己実現・貢献欲求」へ。
「消費・勝ち負け」から「生産・共生」の価値観へ。
主役は「大企業」から「個人・チーム」に替わり、
職業数は増え、「大量生産・消費」から「多品種適量生産」へシフトする。
そうなると、
新しいビジネスのスタートは、
「お金」ではなく「コミュニティ(ソーシャルキャピタル)」になっていく。
そんなプラットフォームが必要だとすると、
多機能型の小さな本屋さんというのは、
そのプラットフォームになりうるのではないかと思う。
ツルハシブックスであれば、
その立地条件を生かして、
「農業生産」と「大学生」、「商店街」や「都市型生活者」
などを組み合わせた小さなビジネスを起こしていく場。
それを「本屋」がつないでいく。
そういうのは、想像できるのではないか。
これからのビジネスにおける価値とは何か?
という問いからすれば、
そういうプラットフォームが地域にあるというのは、
大きな価値があると僕は思う。





