2021年05月25日
プレイスでもコミュニティでもなく

「イドコロをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)
オンライン劇場ツルハシブックス1周年記念のゲストにも来ていただいた
伊藤さんの新刊。
いまこそ、読む本。
って感じです。
サブタイトルが「乱世で正気を失わないための暮らし方」なのですが、これ、まさに。
「思考の免疫系」という切り口で、現代社会の様々な罠・誘惑に対処していく必要性を語ります。
まずは「イドコロ」の定義から。
イドコロはコミュニティでもなく、あくまで人がいる「淀み」であることも重要な認識である。たまたま居合わせた人が適当な範囲で交流することが正気を保ち、元気でいることにつながる。そういう人が居合わせる淀みが、アクセスしやすいところに複数あるのが暮らしやすい世の中であると思う。
小さな広場たる「イドコロ」をつくること。自分の意識だけに頼らず正気を失いにくい環境について考え、それぞれを身の回りに整備することで全体として心の健康を保ちやすい条件を整えていく作戦だ。
井戸端会議は井戸という共有している家事インフラを起点にしたイドコロである。
ハードと、アプリと、研修。3つがそろって初めてイドコロになる。
正気を失わないために、必要なのは1つの「コミュニティ」ではなく複数の「イドコロ」。そしてそれはひとりでも創ることができる。
正気を失わせる精神的な病原菌が世の中に溢れていて、それに対処するには身体的な免疫と同じ構造が必要。それは複雑系であり意図して設計する必要がある。
自分が元気になる「場」を複数個持つこと。それは必ずしも他者とのコミュニケーションを必要としない。
~~~ここまで。
そうそう。
「イドコロ」は「コミュニティ」ではないのです。
コミュニティはひとりでは作れず、外部があり、メンバーシップがあり、もしかしたら目的・目標があり、その場合は役割と責任が発生する。「イドコロ」はひとりでも成立し、境界があいまいである。
オンラインツルハシで一番印象に残った一言は、「イドコロ」を通して思考の余白をつくる、でした。
あー、なるほど。
正気を失わないってそういうことかと。
生活の余白だけじゃなく、思考の余白が無くなっていくと、人は正気を失ってしまうんだ。
イドコロを意識して持って(作って)いくことがとても大切になっていくんだなと。
オンラインツルハシの第3部は新潟市の畑サークル「まきどき村」のトークだったのだけど。
※現在屋根葺き替えのクラウドファンディング中です。
https://camp-fire.jp/projects/view/410826
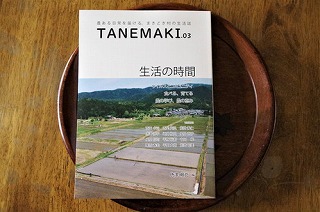
https://karasawa.thebase.in/
こちらの冊子TANEMAKI3にも紹介されているけど、
まきどき村ってみんなにとっての「イドコロ」なんだなあと。
この冊子の終わりに紹介されている「システム」と「生活世界」っていう対比も、まさにそれで。
いつのまにか「システム」が肥大化して、生活世界がそれに取り込まれて、僕たちは「イドコロ」を失った。
「社会人になる」とは、「システムに適応する」とほぼ同義語となっている。
しかし。多くの人たちが実感しているように、「システムに適応する」だけでは「生きられない」のだ。(「社会人」にはなれるけど)
「イドコロをつくる」には、「自然系イドコロ」(仕事や生活に関わる、継続性が高いもの)と「獲得系イドコロ」(強い趣味の集まりや、お店や公園など
の場を活用した比較的インスタントなもの)という分類というように表現されているけど、「まきどき村」という活動は、「獲得系イドコロ」でありながらも、その背景に農や地域といった時間的な長さ(まきどき村的に言えば「営み」)があるので、「イドコロ」として魅力的なのではないか、と思った。
また、まきどき村を取材した大学生に衝撃を与えた、「目的がない」ということも、イドコロにとってとても重要なのだと、伊藤さんも言っている。
~~~
何か明確な目的がある集団は、プレッシャーがある。目的がなければそもそも利害関係も生じない。そういう集まりは、生産性がないと無駄扱いされるが、正気を保つには欠かせないものだと思う。
会話と共同作業によって友情は維持される。
人と人が直接会話・対話するのではなくて、何かを介してコミュニケーションするということ。
~~~
僕たちは「イドコロ」を必要としている。そしてそれは、「システム」(仕事場、経済社会)にも、「生活世界」(暮らし、地域社会)にも複数個あることが必要である。
そんな意識を持つこと。
働く暮らす場所として魅力ある地域とは、そんな「イドコロ」をつくる場(可能性)がたくさんある地域のことなのだろうなと思った。
単なる場(プレイス)でも、役割を果たさなければならないコミュニティでもなく、無数の「イドコロ」をつくっていくこと。そしてそれを意識していくこと。
「イドコロ」というコンセプトは、この町をさらに魅力的にすると感じている。
2021年02月09日
「過程」としての学びと「手段」としての学び
なぜ人は本を読むのだろうか。
なぜ人は本を読まなくなったのだろうか。
なぜ人は本屋に行くのだろうか。
なぜ人は本屋に行かなくなったのだろうか。
そんな問い。
マイプロ関東summitで知り合った高校生のからの一言で、何か見えた
「確かに、本は学びの目的ではなく、過程という感じがしますね。本を開くまで何が書いてあるかは分からないですし、読むこと以上に、本からその人が何を考えて、得るのかが大切な気がします。」
それか!!
「過程」なんだなあ。
本屋に行くことも、本棚を眺めることも、本を読んでいる行為も。
目的ではなくて過程だ。
「〇〇のために」する読書は楽しくない。
「過程」であるからこそ、いま、ここ、この瞬間を楽しめるのかもしれない。
って思っていたところに
「結局「学び」の定義ってどこまで入るのでしょうか?私は、人生の経験そのものが学びのような気がします。辛くてもそこから得たものは学びなのかなと。そうすると瞬間だけを切り取れば必ずしも楽しいだけではないかもしれません。」
そうか!!
「一生学び続けるには?」と問うのではなくて、
「人生の経験=学びの舞台」にするためには?
と問わないといけないのか。
って。
そんな対話。
「過程」というキーワード。
それは、「営み」にも通じる。
そして、「機会として学ぶ」にも。
いわゆる「勉強」のつまらなさは端的に言うと、
(自ら設定したわけではない)目標に向かっての手段として勉強している(させられている)からであると言える。
マイプロジェクトをやっている高校生のプロジェクトという「まなび」の楽しさは、
自己の在り方生き方と一体的で不可分のテーマで(自ら設定した)目標(しかもその目標には到達点がない)に向かい、瞬間的には「機会」として、長期的には「過程」としてプロジェクトに取り組んでいる「まなび」にあるのではないか。
それは、その人の人生そのものであると言えるだろう。
だって、「過程」なのだから。
人生も学びも「営み」であり、「プロジェクト」はその過程の小さな点に過ぎない。
(「プロジェクト」:独自の価値を生むための期限のある業務)
目標のある「プロジェクト」として見れば、いまやっていることは、「手段」に過ぎない。
しかし、人生という「営み」からすれば、全てのやっていることは「過程」となる。
そして「過程」という感覚は、
「いま、ここ、この瞬間」というマインドフルネスと矛盾しない。
「過程」である今を生きる。
そしていまという「場」を動的に捉える。
いま、ここ、この瞬間をチューニングする。
「いつ、どこで、誰と」を確認しながら合わせていく。
そんな「過程」としての学び。
そんな学びを実現できる地域協働を創っていけないだろうか。
なぜ人は本を読まなくなったのだろうか。
なぜ人は本屋に行くのだろうか。
なぜ人は本屋に行かなくなったのだろうか。
そんな問い。
マイプロ関東summitで知り合った高校生のからの一言で、何か見えた
「確かに、本は学びの目的ではなく、過程という感じがしますね。本を開くまで何が書いてあるかは分からないですし、読むこと以上に、本からその人が何を考えて、得るのかが大切な気がします。」
それか!!
「過程」なんだなあ。
本屋に行くことも、本棚を眺めることも、本を読んでいる行為も。
目的ではなくて過程だ。
「〇〇のために」する読書は楽しくない。
「過程」であるからこそ、いま、ここ、この瞬間を楽しめるのかもしれない。
って思っていたところに
「結局「学び」の定義ってどこまで入るのでしょうか?私は、人生の経験そのものが学びのような気がします。辛くてもそこから得たものは学びなのかなと。そうすると瞬間だけを切り取れば必ずしも楽しいだけではないかもしれません。」
そうか!!
「一生学び続けるには?」と問うのではなくて、
「人生の経験=学びの舞台」にするためには?
と問わないといけないのか。
って。
そんな対話。
「過程」というキーワード。
それは、「営み」にも通じる。
そして、「機会として学ぶ」にも。
いわゆる「勉強」のつまらなさは端的に言うと、
(自ら設定したわけではない)目標に向かっての手段として勉強している(させられている)からであると言える。
マイプロジェクトをやっている高校生のプロジェクトという「まなび」の楽しさは、
自己の在り方生き方と一体的で不可分のテーマで(自ら設定した)目標(しかもその目標には到達点がない)に向かい、瞬間的には「機会」として、長期的には「過程」としてプロジェクトに取り組んでいる「まなび」にあるのではないか。
それは、その人の人生そのものであると言えるだろう。
だって、「過程」なのだから。
人生も学びも「営み」であり、「プロジェクト」はその過程の小さな点に過ぎない。
(「プロジェクト」:独自の価値を生むための期限のある業務)
目標のある「プロジェクト」として見れば、いまやっていることは、「手段」に過ぎない。
しかし、人生という「営み」からすれば、全てのやっていることは「過程」となる。
そして「過程」という感覚は、
「いま、ここ、この瞬間」というマインドフルネスと矛盾しない。
「過程」である今を生きる。
そしていまという「場」を動的に捉える。
いま、ここ、この瞬間をチューニングする。
「いつ、どこで、誰と」を確認しながら合わせていく。
そんな「過程」としての学び。
そんな学びを実現できる地域協働を創っていけないだろうか。
2019年11月08日
「ギャップ萌え人材」の育成
11月4-5日
「黎明学舎」&阿賀町の面白い人に会うツアーでした。
スケジュールはこんな感じ。
4日
9:00~10:30 くるみ洗い


10:30~13:00 フリートーク&きのこ園ランチ

14:00~15:00 ぎんなん拾い

15:00~17:30 「黎明学舎」公開ミーティング

17:30~19:30 買い出し、津川温泉
20:00~22:00 交流会
5日
9:00~10:00 昨日の振り返り
10:00~12:00 目黒農園見学

参加いただいたみなさん、たいへんありがとうございました。
公開ミーティングでは、たくさんの気づきがありました。
11月3日に長岡の正徳館高校フェスティバルにお邪魔して、
杉崎さんプロデュースのかき氷をいただいて、



ふたば未来学園高校のコーディネーター長谷川さんの講演
これもタイミングがよかった。小林先生ありがとうございます。
~~~以下講演メモ
なぜ高校と地域は協働しないといけないのか?
「地域」:担い手をつくるため
「教育」:子どもの自立のため
子どもが未来(自分と地域)のつくり手となるために必要な資質・能力という目標を共有する。
「ヒューマンライブラリー」という対話の場。
「背負う」ことが原動力になっているとは思うけど、そこまで背負わなくてもいいのではないか、ってちょっと思った。「地域のためにあるあなた」というアイデンティティ構築はだんだんつらくなる。「役に立たないといけない」みたいになるから。
かかわり過ぎず、放置しすぎない。
1 机上に留まらない生徒の資質・能力の向上
2 地域に愛着を持ち、社会への参画意識が高まる。
総合的探究の時間。
「高等学校では、生徒自身が自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題を自ら発見し、解決していくことが期待されている。」(文部科学省)
自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題を自ら発見する。
これ、すごい言葉だなと。地域課題じゃなくて、生徒が中心なんだよね。
管理栄養士になりたい
→スーパーでおばあちゃんが惣菜をたくさん買ってた
→高齢者向け料理教室をやったらどうか
→もっと言えば野菜作りを一緒にやるのはどうか
→畑をつくってそこに人を呼んだらどうか
→チラシをつくって告知
→参加者ゼロだった
うまくいかない!!
みたいな出発点。
机上では想像できない提案と実践の壁。
プロジェクト学習にとって最も必要なのは真正性、つまりリアル。
「地域」はまさに「リアル」そのもの。
生徒の学びを中心に探究を設計する。
地域課題解決、地域活性化は目的ではなく結果。
「コンソーシアムをつくる」っていうのが目的になるのではなくて、機能を限定して、「価値」を共有していくことを重ねていくことが大切だと思う。
まずは「探究」サポーター的な横断的集まりから始めていったらいいと思う。
「探究」:深く考えて物事の真相・在り方などを明らかにすること
まわりの大人こそがやらないといけない。
生徒が変わる体験をつくり、それを見せる。
地域の人の「出番」をつくること。
ここで力を借りたいと設定すること。
徹底して生徒にフォーカスすることで、結果地域のためになると思う。
~~~ここまで講演メモ
そして、11月5日の公開ミーティング。
10月25日の「学校3.0」でもらったカタリバの説明資料が
非常にわかりやすかったので、それを参考に
黎明学舎のミッションについて考えるワークをした。
自己紹介→それぞれ「背景」について話す→キーワード出し
→ミッションについて話す。
みたいな感じだったかな。
アドリブだったけどうまく流れた。
~~~ここからミーティングメモ
小田切先生の言う「誇りの空洞化」と同時に、アイデンティティの空洞化が起こっていたのかもしれない。
アイデンティティを「仕事」というか職業に求めなければいけないつらさ。
それをキャリア教育は助長していないか?
「キャリアを自分で切り拓く」とは、価値の決定権を自らが持つこと、なのではないか。
「よいチーム」とは、価値をその都度みんなで設定・設計しているチームなのではないか?
石川くんの「充実感がある。くるみは嘘つかない」っていう発言もよかった。
くるみという圧倒的なリアル。
自ら価値を設定し、それを実感できる機会をつくり出すこと。
一言で言えば「この町で遊べること」
「ふるさと創りびと」とは、そういう人。
「高校生を応援するプロジェクト」と「まちの当事者(プレイヤー)を増やすプロジェクト」は同時に起こる。
同時に起こるというか、高校生という題材を追いかけることで、まちの当事者が増えていく。
「かかわりしろ」を増やす、とか、地域内でも、関係人口的なアプローチが有効なのかもしれない。
・労力を出す
・道具を出す
・お金を出す
・情報を出す(アイデア、人を紹介)
みたいなメニューの設定。
「手伝いたいのだけど?」
「はい、こんなメニューがあります」
みたいな。
気がついたら、当事者(まちのプレイヤー)になっている。
そんなデザインをつくろうよ。
まちづくり会議の目的は何か?って言われたら、まちの当事者(プレイヤー)を増やすこと、なのだけど、
まちの当事者を増やすのが目的だとしたら、まちづくり会議よりも、高校生の探究のサポートをしてもらったほうがいいのかもしれない。
アイデンティティ(自分らしさ)の危機と、ふるさとの危機(誇りの空洞化)は、同時に起こっていたんだ。
「まちを何とかしよう。」と並行して、ひとを育てること。
いや、ひとを育てることを繰り返して、結果、「まち」がつくられる。
高校生の生きづらさは、「部活」と「勉強」の価値軸しか与えられていないこと。
しかもそれは他者からの評価という量的な指標によって決まる。
価値軸の選択肢を増やし、そういう大人に出会い、リアルを体験・体感すること。
「ふるさと創りびと」の結果、自分の価値軸を自分で掴み取っていけること。
無数の「放課後社会」をつくるんだ。ね、坂口恭平さん。
どうワクワクをつくるのか?
田舎こそ、価値軸、つまり「放課後社会」がたくさんある。しかもそれが「リアル」なものとしてあるから体感できる。
「部活」と「勉強」という価値が一元化された「学校社会」の息苦しさを開放していくフィールドをまちにつくっていく。
変動する「価値」をその都度とらえながら歩いていく。
~~~ここまでミーティングメモ
「ふるさと創りびと」というコンセプトは8月に決まったものだけど、
そこに至る背景とその先にあるビジョンを考える時間。
「勉強」と「部活」という価値観。
数値化され、序列化される価値。
そこにはやはり、「効率化」という工業社会の要請があった。
そもそも学校は
「最小の労力で、(工場労働者として)一人前の人材を育てる」
という「効率化」というコンセプトで始まった。
おそらくは社会全体が「効率化」という価値観を信じた。
http://hero.niiblo.jp/e489486.html
なぜ、「教養」は死んだのか?(19.6.26)
このブログに引用した本に書いてあるように、
「効率化」の名のもとに「教養」は死んだ。
しかし。工業社会はもう終わってしまったのだ。
いや、終わってはいないのだけど、少なくとも国民のほとんどが製造業に就職して、マイホームを買えて、老後も安泰っていう時代は終わった。
僕たちは生まれた時から、そういう時代を生きてきたから、
信じられないかもしれないけども・・・
「効率化」とは、「価値の一元化」そしてそれによる「序列化」のこと。
数値化し、量的に見るということ。その前提が崩れ去っている。
価値は常に流動し、しかもそれは同じモノサシでは測れない。
そのほうがよっぽどリアルで、量的な指標しかない社会のほうがパロディに思えてくる。
誰かが設定した価値に対して、量的に反応して一喜一憂するのではなく、
自らが価値を設定し、それを分かち合える仲間とチームを組み、
その価値に共感してくれる人に商品やサービスを届ける。
それを作っていかなくてはいけない。
そこで「ふるさと創りびと」なのだけど、
自ら価値を生んでいくためにまちの資源を題材にして創造的行為に没頭すると、
そこがふるさとになっていくこと。
そんな学びができる学校を、地域をつくっていきたいと思った。
それは高校生だけじゃなく、そこに住んでいる人たちも同じく必要なことなのだ。
「誇りの空洞化」は「自分らしさの空洞化」でもあった。
そんな話を振り返っていて、
高知大学2年の檜山さんを送りながら
車の中で思いついたキーワード。
「ギャップ萌え人材」
ああ、ありかもと思った。
いま、テレビに出てる人たち。
〇〇芸人。
それって、〇〇を探究した「探究芸人」なのではないか。
それを「芸人」と掛け合わせることによって、「個性」を生んでいるのではないか。
そして芸人イメージとのギャップがあればあるほど人はそれを面白いと思う。
エンターテイメントの本質は予測不可能性だから。
少女漫画の定番みたいな、
普段は不良なのに、捨て犬に給食の残りをあげたりしていると、
そういう人を人は面白いと思うし、恋に落ちてしまう。
ギャップ萌え人材。
これ、高校生向けには使っていけそうです。
探究する人はギャップ萌えを手に入れやすい。
それって人生戦略的にはアリだよな、と。
「黎明学舎」&阿賀町の面白い人に会うツアーでした。
スケジュールはこんな感じ。
4日
9:00~10:30 くるみ洗い


10:30~13:00 フリートーク&きのこ園ランチ

14:00~15:00 ぎんなん拾い

15:00~17:30 「黎明学舎」公開ミーティング

17:30~19:30 買い出し、津川温泉
20:00~22:00 交流会
5日
9:00~10:00 昨日の振り返り
10:00~12:00 目黒農園見学

参加いただいたみなさん、たいへんありがとうございました。
公開ミーティングでは、たくさんの気づきがありました。
11月3日に長岡の正徳館高校フェスティバルにお邪魔して、
杉崎さんプロデュースのかき氷をいただいて、



ふたば未来学園高校のコーディネーター長谷川さんの講演
これもタイミングがよかった。小林先生ありがとうございます。
~~~以下講演メモ
なぜ高校と地域は協働しないといけないのか?
「地域」:担い手をつくるため
「教育」:子どもの自立のため
子どもが未来(自分と地域)のつくり手となるために必要な資質・能力という目標を共有する。
「ヒューマンライブラリー」という対話の場。
「背負う」ことが原動力になっているとは思うけど、そこまで背負わなくてもいいのではないか、ってちょっと思った。「地域のためにあるあなた」というアイデンティティ構築はだんだんつらくなる。「役に立たないといけない」みたいになるから。
かかわり過ぎず、放置しすぎない。
1 机上に留まらない生徒の資質・能力の向上
2 地域に愛着を持ち、社会への参画意識が高まる。
総合的探究の時間。
「高等学校では、生徒自身が自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題を自ら発見し、解決していくことが期待されている。」(文部科学省)
自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題を自ら発見する。
これ、すごい言葉だなと。地域課題じゃなくて、生徒が中心なんだよね。
管理栄養士になりたい
→スーパーでおばあちゃんが惣菜をたくさん買ってた
→高齢者向け料理教室をやったらどうか
→もっと言えば野菜作りを一緒にやるのはどうか
→畑をつくってそこに人を呼んだらどうか
→チラシをつくって告知
→参加者ゼロだった
うまくいかない!!
みたいな出発点。
机上では想像できない提案と実践の壁。
プロジェクト学習にとって最も必要なのは真正性、つまりリアル。
「地域」はまさに「リアル」そのもの。
生徒の学びを中心に探究を設計する。
地域課題解決、地域活性化は目的ではなく結果。
「コンソーシアムをつくる」っていうのが目的になるのではなくて、機能を限定して、「価値」を共有していくことを重ねていくことが大切だと思う。
まずは「探究」サポーター的な横断的集まりから始めていったらいいと思う。
「探究」:深く考えて物事の真相・在り方などを明らかにすること
まわりの大人こそがやらないといけない。
生徒が変わる体験をつくり、それを見せる。
地域の人の「出番」をつくること。
ここで力を借りたいと設定すること。
徹底して生徒にフォーカスすることで、結果地域のためになると思う。
~~~ここまで講演メモ
そして、11月5日の公開ミーティング。
10月25日の「学校3.0」でもらったカタリバの説明資料が
非常にわかりやすかったので、それを参考に
黎明学舎のミッションについて考えるワークをした。
自己紹介→それぞれ「背景」について話す→キーワード出し
→ミッションについて話す。
みたいな感じだったかな。
アドリブだったけどうまく流れた。
~~~ここからミーティングメモ
小田切先生の言う「誇りの空洞化」と同時に、アイデンティティの空洞化が起こっていたのかもしれない。
アイデンティティを「仕事」というか職業に求めなければいけないつらさ。
それをキャリア教育は助長していないか?
「キャリアを自分で切り拓く」とは、価値の決定権を自らが持つこと、なのではないか。
「よいチーム」とは、価値をその都度みんなで設定・設計しているチームなのではないか?
石川くんの「充実感がある。くるみは嘘つかない」っていう発言もよかった。
くるみという圧倒的なリアル。
自ら価値を設定し、それを実感できる機会をつくり出すこと。
一言で言えば「この町で遊べること」
「ふるさと創りびと」とは、そういう人。
「高校生を応援するプロジェクト」と「まちの当事者(プレイヤー)を増やすプロジェクト」は同時に起こる。
同時に起こるというか、高校生という題材を追いかけることで、まちの当事者が増えていく。
「かかわりしろ」を増やす、とか、地域内でも、関係人口的なアプローチが有効なのかもしれない。
・労力を出す
・道具を出す
・お金を出す
・情報を出す(アイデア、人を紹介)
みたいなメニューの設定。
「手伝いたいのだけど?」
「はい、こんなメニューがあります」
みたいな。
気がついたら、当事者(まちのプレイヤー)になっている。
そんなデザインをつくろうよ。
まちづくり会議の目的は何か?って言われたら、まちの当事者(プレイヤー)を増やすこと、なのだけど、
まちの当事者を増やすのが目的だとしたら、まちづくり会議よりも、高校生の探究のサポートをしてもらったほうがいいのかもしれない。
アイデンティティ(自分らしさ)の危機と、ふるさとの危機(誇りの空洞化)は、同時に起こっていたんだ。
「まちを何とかしよう。」と並行して、ひとを育てること。
いや、ひとを育てることを繰り返して、結果、「まち」がつくられる。
高校生の生きづらさは、「部活」と「勉強」の価値軸しか与えられていないこと。
しかもそれは他者からの評価という量的な指標によって決まる。
価値軸の選択肢を増やし、そういう大人に出会い、リアルを体験・体感すること。
「ふるさと創りびと」の結果、自分の価値軸を自分で掴み取っていけること。
無数の「放課後社会」をつくるんだ。ね、坂口恭平さん。
どうワクワクをつくるのか?
田舎こそ、価値軸、つまり「放課後社会」がたくさんある。しかもそれが「リアル」なものとしてあるから体感できる。
「部活」と「勉強」という価値が一元化された「学校社会」の息苦しさを開放していくフィールドをまちにつくっていく。
変動する「価値」をその都度とらえながら歩いていく。
~~~ここまでミーティングメモ
「ふるさと創りびと」というコンセプトは8月に決まったものだけど、
そこに至る背景とその先にあるビジョンを考える時間。
「勉強」と「部活」という価値観。
数値化され、序列化される価値。
そこにはやはり、「効率化」という工業社会の要請があった。
そもそも学校は
「最小の労力で、(工場労働者として)一人前の人材を育てる」
という「効率化」というコンセプトで始まった。
おそらくは社会全体が「効率化」という価値観を信じた。
http://hero.niiblo.jp/e489486.html
なぜ、「教養」は死んだのか?(19.6.26)
このブログに引用した本に書いてあるように、
「効率化」の名のもとに「教養」は死んだ。
しかし。工業社会はもう終わってしまったのだ。
いや、終わってはいないのだけど、少なくとも国民のほとんどが製造業に就職して、マイホームを買えて、老後も安泰っていう時代は終わった。
僕たちは生まれた時から、そういう時代を生きてきたから、
信じられないかもしれないけども・・・
「効率化」とは、「価値の一元化」そしてそれによる「序列化」のこと。
数値化し、量的に見るということ。その前提が崩れ去っている。
価値は常に流動し、しかもそれは同じモノサシでは測れない。
そのほうがよっぽどリアルで、量的な指標しかない社会のほうがパロディに思えてくる。
誰かが設定した価値に対して、量的に反応して一喜一憂するのではなく、
自らが価値を設定し、それを分かち合える仲間とチームを組み、
その価値に共感してくれる人に商品やサービスを届ける。
それを作っていかなくてはいけない。
そこで「ふるさと創りびと」なのだけど、
自ら価値を生んでいくためにまちの資源を題材にして創造的行為に没頭すると、
そこがふるさとになっていくこと。
そんな学びができる学校を、地域をつくっていきたいと思った。
それは高校生だけじゃなく、そこに住んでいる人たちも同じく必要なことなのだ。
「誇りの空洞化」は「自分らしさの空洞化」でもあった。
そんな話を振り返っていて、
高知大学2年の檜山さんを送りながら
車の中で思いついたキーワード。
「ギャップ萌え人材」
ああ、ありかもと思った。
いま、テレビに出てる人たち。
〇〇芸人。
それって、〇〇を探究した「探究芸人」なのではないか。
それを「芸人」と掛け合わせることによって、「個性」を生んでいるのではないか。
そして芸人イメージとのギャップがあればあるほど人はそれを面白いと思う。
エンターテイメントの本質は予測不可能性だから。
少女漫画の定番みたいな、
普段は不良なのに、捨て犬に給食の残りをあげたりしていると、
そういう人を人は面白いと思うし、恋に落ちてしまう。
ギャップ萌え人材。
これ、高校生向けには使っていけそうです。
探究する人はギャップ萌えを手に入れやすい。
それって人生戦略的にはアリだよな、と。
2019年07月25日
「百姓」をアップデートする
「百姓」をアップデートする。
「田舎には仕事がない」のではなく、
「田舎にはサラリーマン仕事が少ない」というのが真実だ。
「地方に人を呼ぶには雇用の拡大を」
というのは、ある意味、真実だろう。
「サラリーマン」という働き方は
直近わずか50年の特殊な働き方だったと、
伊藤洋志さんは「ナリワイをつくる」で言っている。

http://hero.niiblo.jp/e441317.html
「50年間だけの成功モデル」
http://hero.niiblo.jp/e279962.html
「専業思想がコミュニティを崩壊させた」
http://hero.niiblo.jp/e477992.html
「本業じゃないほうが本質的なことができる」
昨日、阿賀町で自然薯を栽培している
目黒さんの話が僕の中で熱かった。
小中学生のエゴマの植え付け体験を受け入れたら
時期がちょっと遅くなっちゃって、今年は収穫量が減るかも。
でも、学びのためには毎年受け入れるよ、みたいな。
この前、お義父さんの小屋づくりの
玄関にセメントを流しこむ作業をしたとき、金属のコテじゃなくて、
木をコテの形に切って取っ手(それも木)をつけただけの
お手製のコテで上手に塗っていて、感動した。
ああ。
ブリコラージュっていうのはそういうことか、と。
百姓っていうのは、「自分でつくる」っていうことなんだ。
「仕事」っていう概念が変わりつつある時代に生きていると思う。
だとしたら、
人は自ら、自らの「仕事」を定義しなければならない。
目黒さんの話は、まさにそれだった。
「価値」は何か?
エゴマをたくさん取ることか。
それともエゴマの植え付け体験を子どもたちにしてもらうことか。
それを自ら定義して、実践すること。
それが百姓なのではないか、と思った。
子どもたちに伝えていかないといけないのは、
そういう百姓スピリットなのではないか。
いい大学いい会社に入ったから幸せになれるわけではない。
いい師匠いい仲間にめぐり合えたから幸せになれるわけでもない。
唯一幸せになれるのは、幸せを自ら定義した者である。
と2か月ほど前につぶやいたのだけど、
「幸せ」だけじゃなく、「仕事」も自ら定義すること。
そしてそれを自らつくってみること。
百姓とは、
仕事をたくさん持つ人のことであり、
仕事を自らつくる人のことであり、
仕事を自ら定義し、自らの価値観に従って実行する人のことである
それが百姓2.0なのかもしれない。
「田舎には仕事がない」のではなく、
「田舎にはサラリーマン仕事が少ない」というのが真実だ。
「地方に人を呼ぶには雇用の拡大を」
というのは、ある意味、真実だろう。
「サラリーマン」という働き方は
直近わずか50年の特殊な働き方だったと、
伊藤洋志さんは「ナリワイをつくる」で言っている。

http://hero.niiblo.jp/e441317.html
「50年間だけの成功モデル」
http://hero.niiblo.jp/e279962.html
「専業思想がコミュニティを崩壊させた」
http://hero.niiblo.jp/e477992.html
「本業じゃないほうが本質的なことができる」
昨日、阿賀町で自然薯を栽培している
目黒さんの話が僕の中で熱かった。
小中学生のエゴマの植え付け体験を受け入れたら
時期がちょっと遅くなっちゃって、今年は収穫量が減るかも。
でも、学びのためには毎年受け入れるよ、みたいな。
この前、お義父さんの小屋づくりの
玄関にセメントを流しこむ作業をしたとき、金属のコテじゃなくて、
木をコテの形に切って取っ手(それも木)をつけただけの
お手製のコテで上手に塗っていて、感動した。
ああ。
ブリコラージュっていうのはそういうことか、と。
百姓っていうのは、「自分でつくる」っていうことなんだ。
「仕事」っていう概念が変わりつつある時代に生きていると思う。
だとしたら、
人は自ら、自らの「仕事」を定義しなければならない。
目黒さんの話は、まさにそれだった。
「価値」は何か?
エゴマをたくさん取ることか。
それともエゴマの植え付け体験を子どもたちにしてもらうことか。
それを自ら定義して、実践すること。
それが百姓なのではないか、と思った。
子どもたちに伝えていかないといけないのは、
そういう百姓スピリットなのではないか。
いい大学いい会社に入ったから幸せになれるわけではない。
いい師匠いい仲間にめぐり合えたから幸せになれるわけでもない。
唯一幸せになれるのは、幸せを自ら定義した者である。
と2か月ほど前につぶやいたのだけど、
「幸せ」だけじゃなく、「仕事」も自ら定義すること。
そしてそれを自らつくってみること。
百姓とは、
仕事をたくさん持つ人のことであり、
仕事を自らつくる人のことであり、
仕事を自ら定義し、自らの価値観に従って実行する人のことである
それが百姓2.0なのかもしれない。
2018年11月07日
「挑戦」するな、「実験」せよ

「情報生産者になる」(上野千鶴子 ちくま新書)
鳥取・定有堂書店で購入。
まだまだ冒頭なのだけど、いい言葉入ってます。
わかりやすい。
「情報はノイズから生まれます。
ノイズとは違和感、こだわり、疑問、ひっかかり・・・のことです。」
「情報とは、システムとシステムの境界に生まれます。
複数のシステムの境界に立つ者が、いずれをもよりよく洞察することができるからです。」
なるほど。
たしかにそうかもしれないですね。
「違和感」をキャッチできるか、
キャッチした違和感を情報に変換できるか、
これがカギを握っていると思います。
僕が違和感を感じてきた言葉。
「挑戦」とか「目標」とか。
大学生の言葉でいえば、
「やりたいことがわからない」
「自分に自信がない」
かもしれない。
「自信」とは「やったことがあること」だと
たしか堀江さんが言っていたのだけど、
その理屈でいけば、
「やってみる」ことがとても大切なんだと思う。
「自分に自信がない」と言っている若者に対して、
いわゆる「スモールステップ理論」がある。
つまり、小さなチャレンジを繰り返して、
だんだんと大きなチャレンジをしていく、というもの。
しかし、この理論には重大な見落としがある。
本当に自信がない人は最初の小さなチャレンジのドミノが倒れないのだ。
だから、その人はいつまで立っても自信がつくことはない。
「やってみる」人を増やす。
これはたしか、2014年に「にいがた未来考房」の立ち上げの
時に使ったように思うが、
昨日、大学生からのツッコミを受けて見えてきたもの。
「チャレンジできない」ことを気にして、
「チャレンジしなきゃ」と思っている人は多いが、
実際にその人たちは何もはじめていない。
チャレンジする前に「トライ」があることを忘れてしまっている。
そうか。
実験か、と思った。
挑戦ではなく、実験をすること。
「挑戦」には「目的」「目標」があり、成功と失敗があるが、
「実験」には「目的」「目標」がなく、結果があるだけだ。
「挑戦」ではなく、「実験」
そしてその結果を出すのは、個人でもチームではなく、「場のチカラ」
であること。
だから、ふりかえりをするとき、
「予想しなかったよかったこと」も
「予想しなかった悪かったこと」も
結果にすぎない。
次からどうしようか。
そのための材料に過ぎない。
たぶんそういう思考でプロジェクトに参加していくこと。
予想できなかった「結果」を楽しむこと。
その先を、見てみたい。
やったことがないからやってみた。
やってみるの理由はそれだけでいい。
人は「やってみる」を繰り返すことで
生きていくのだ。
2018年10月29日
「余白」とは、境界をあいまいにして「委ねる」こと
余白おじさん。
昨年「新城劇場」(現在はリニューアルオープンしてブックカフェになってます)
のオープンの時に
webマガジン「温度」の碇さんにつけられたニックネーム。
http://ondo-books.com/bookstore-report/188
当時はおじさんを認めたくなくて(笑)、
「余白デザイナー」と名乗っていたりするのだけど。
あらためて
「余白」について考えてみる。
場にも、仕事にも、組織にも、人生にも、「余白」が必要だと思う。
世の中が閉鎖系から開放系へと進んでいる。
閉鎖系で機能したフレームワークが
どんどん通用しなくなっていく。
「余白」をデザインするとは、
「境界」をあいまいにすること、だと思う。
それが「心地よさ」や「ワクワク」を生むのではないかという仮説。
気がついたら私も本屋という舞台の共演者になっていました。
これがツルハシブックスのキャッチコピーだったのだけど。
それは、店員とお客の境界を溶かしていくことだと思った。
そこに立っている人が店員なのか、お客なのか、
あいまいな状態にすることで
自分自身もあいまいな状態になる。
そこで共演者になれるのだと思う。
それが場の余白ではないか。
仕事の余白は、目標以外の成果を意識すること。
インターンシップの余白は、目標を設定しすぎないこと。
にいがたイナカレッジのプログラムのように、
参加者が地域の人と触れあう中で、
ゴールを再設計、設定すること。
それは、言葉にすれば「委ねる」ということ。
未知なるものに委ねる。
そして、ふりかえること。
きっとそういうこと。
僕自身は現代美術家として、
「リレーショナルアート」領域を創造していくのだけど、
それって、余白をつくること。
つまり、
境界をあいまいにして、委ねること、なのかもしれない。
場にも、仕事にも、組織にも、人生にも、
ワークショップにも、「余白」が必要だって
そういうことなのではないかな。

写真は南魚沼・ヤミーのかぐらなんばんジェラート
めちゃめちゃ辛いです。
アイスの余白に作っちゃってますね。(笑)
昨年「新城劇場」(現在はリニューアルオープンしてブックカフェになってます)
のオープンの時に
webマガジン「温度」の碇さんにつけられたニックネーム。
http://ondo-books.com/bookstore-report/188
当時はおじさんを認めたくなくて(笑)、
「余白デザイナー」と名乗っていたりするのだけど。
あらためて
「余白」について考えてみる。
場にも、仕事にも、組織にも、人生にも、「余白」が必要だと思う。
世の中が閉鎖系から開放系へと進んでいる。
閉鎖系で機能したフレームワークが
どんどん通用しなくなっていく。
「余白」をデザインするとは、
「境界」をあいまいにすること、だと思う。
それが「心地よさ」や「ワクワク」を生むのではないかという仮説。
気がついたら私も本屋という舞台の共演者になっていました。
これがツルハシブックスのキャッチコピーだったのだけど。
それは、店員とお客の境界を溶かしていくことだと思った。
そこに立っている人が店員なのか、お客なのか、
あいまいな状態にすることで
自分自身もあいまいな状態になる。
そこで共演者になれるのだと思う。
それが場の余白ではないか。
仕事の余白は、目標以外の成果を意識すること。
インターンシップの余白は、目標を設定しすぎないこと。
にいがたイナカレッジのプログラムのように、
参加者が地域の人と触れあう中で、
ゴールを再設計、設定すること。
それは、言葉にすれば「委ねる」ということ。
未知なるものに委ねる。
そして、ふりかえること。
きっとそういうこと。
僕自身は現代美術家として、
「リレーショナルアート」領域を創造していくのだけど、
それって、余白をつくること。
つまり、
境界をあいまいにして、委ねること、なのかもしれない。
場にも、仕事にも、組織にも、人生にも、
ワークショップにも、「余白」が必要だって
そういうことなのではないかな。

写真は南魚沼・ヤミーのかぐらなんばんジェラート
めちゃめちゃ辛いです。
アイスの余白に作っちゃってますね。(笑)
2018年08月31日
「自分に自信がない」の「自分」って何だ?
明日は茨城県日立市で「若松ミライ会議」の拡大版。
復習しようと。
「顧客」と「価値」の視点から過去を見つめなおす(18.7.12)
http://hero.niiblo.jp/e487733.html
「私」を外す、という美学(17.3.28)
http://hero.niiblo.jp/e484378.html
あらためて。
「日本人は何を考えて生きてきたのか(斎藤孝 洋伝社)より
西田幾多郎の言葉。
「主客があるかのように思うのは、私たちの思い込みにすぎない。実は主客未分のほうが本来の姿であり、純粋な経験である。経験の大もとを純粋な経験だとすると、純粋経験は主客未分でおこっているはずだ。本質を捉えようとするならば、私というものを前提として考えるのではなく、むしろ主客を分けることができない純粋経験こそを追求するべきだと考えたのです。」
そして、鈴木大拙もつづく。
「禅は科学、または科学の名によって行われる一切の事物とは反対である。禅は体験的であり、科学は非体験的である。非体験的なるものは抽象的であり、個人的経験に対してはあまり関心を持たぬ。体験的なるものはまったく個人に属し、その体験を背景としなくては意義を持たぬ。科学は系統化(システマゼーション)を意味し、禅はまさにその反対である。言葉は科学と哲学には要るが、禅の場合には妨げとなる。なぜであるか。言葉は代表するものであって、実体そのものではない。実体こそ、禅においてもっとも高く評価されるものなのである。」
これ、中動態を学んだ今、めっちゃよくわかるね。
自分の過去に、「顧客」と「価値」があって、
それはすごく体験的で、個人的なもので、
そもそも「自分に自信がない」というときの
「自分」ってなんだろう?
と、「やりたいことがわからない」
ことが苦しいから、「やりたいこと」を探してしまうけど、
「自分に自信がない」
ことが苦しいから、自分に自信をつけようとしてしまうけど。
そもそも、やりたいことって何か?
とか
自分に自信がない場合の「自分」って何か?
みたいなことって問わないもんね。
僕はかつて、
「自分に自信がない」と言ってきた若者に対して、
「自信がなくても始められたらいい」
と思っていた。
だから、上田信行先生に出会って、
キャロル・ドゥエック先生の本を読み、
固定的知能観と成長的知能観について学んだ。
「自信がない」は後天的に獲得した資質である(14.12.29)
http://hero.niiblo.jp/e459844.html
やればできる(かもしれない)、
つまり自信がある状態が通常で、
自信がない(からやれない)
というのは後から獲得している。
だから、始めたらいい。
と言っていたけど。
自信がどうの、っていうよりはまず「自分」というか
アイデンティティについて取り組んでいく必要がある。
そのためには、自分の過去を知ること。
過去の結果としての自分を受け入れること。
状況に身を委ねること。
「自分」を知ること
「社会」を知ること
そこから「自分」を見つめなおすこと。
明日の「ミライ会議」がそんな場になったらいい。
これから明日の予習をこの本で。

「We are lonely,but not alone」(佐渡島庸平 幻冬舎)
復習しようと。
「顧客」と「価値」の視点から過去を見つめなおす(18.7.12)
http://hero.niiblo.jp/e487733.html
「私」を外す、という美学(17.3.28)
http://hero.niiblo.jp/e484378.html
あらためて。
「日本人は何を考えて生きてきたのか(斎藤孝 洋伝社)より
西田幾多郎の言葉。
「主客があるかのように思うのは、私たちの思い込みにすぎない。実は主客未分のほうが本来の姿であり、純粋な経験である。経験の大もとを純粋な経験だとすると、純粋経験は主客未分でおこっているはずだ。本質を捉えようとするならば、私というものを前提として考えるのではなく、むしろ主客を分けることができない純粋経験こそを追求するべきだと考えたのです。」
そして、鈴木大拙もつづく。
「禅は科学、または科学の名によって行われる一切の事物とは反対である。禅は体験的であり、科学は非体験的である。非体験的なるものは抽象的であり、個人的経験に対してはあまり関心を持たぬ。体験的なるものはまったく個人に属し、その体験を背景としなくては意義を持たぬ。科学は系統化(システマゼーション)を意味し、禅はまさにその反対である。言葉は科学と哲学には要るが、禅の場合には妨げとなる。なぜであるか。言葉は代表するものであって、実体そのものではない。実体こそ、禅においてもっとも高く評価されるものなのである。」
これ、中動態を学んだ今、めっちゃよくわかるね。
自分の過去に、「顧客」と「価値」があって、
それはすごく体験的で、個人的なもので、
そもそも「自分に自信がない」というときの
「自分」ってなんだろう?
と、「やりたいことがわからない」
ことが苦しいから、「やりたいこと」を探してしまうけど、
「自分に自信がない」
ことが苦しいから、自分に自信をつけようとしてしまうけど。
そもそも、やりたいことって何か?
とか
自分に自信がない場合の「自分」って何か?
みたいなことって問わないもんね。
僕はかつて、
「自分に自信がない」と言ってきた若者に対して、
「自信がなくても始められたらいい」
と思っていた。
だから、上田信行先生に出会って、
キャロル・ドゥエック先生の本を読み、
固定的知能観と成長的知能観について学んだ。
「自信がない」は後天的に獲得した資質である(14.12.29)
http://hero.niiblo.jp/e459844.html
やればできる(かもしれない)、
つまり自信がある状態が通常で、
自信がない(からやれない)
というのは後から獲得している。
だから、始めたらいい。
と言っていたけど。
自信がどうの、っていうよりはまず「自分」というか
アイデンティティについて取り組んでいく必要がある。
そのためには、自分の過去を知ること。
過去の結果としての自分を受け入れること。
状況に身を委ねること。
「自分」を知ること
「社会」を知ること
そこから「自分」を見つめなおすこと。
明日の「ミライ会議」がそんな場になったらいい。
これから明日の予習をこの本で。

「We are lonely,but not alone」(佐渡島庸平 幻冬舎)
2018年05月23日
「予測不可能」という価値
僕が「予測不可能性」というキーワードを
意識し始めたのは、昨年5月の
法政大学長岡ゼミの「カフェゼミ」だった。
「つながるカレー」の会@日本橋。
加藤さんの、
あまったカレーの話に、シビれた。
エンターテイメントとは、予測不可能性であると思った。
http://hero.niiblo.jp/e484808.html
「予測できない」というモチベーション・デザイン
(17.5.19)
そして、7月の「アルプスブックキャンプ」で
藤本さんに出会う。
http://hero.niiblo.jp/e485488.html
「出会うたんです」(17.8.1)
彼は、予測不可能なことに出会った自分自身という
現象を記事にしていくことで、魅力的なものになると言った。
それが「魔法をかける」ということなのだと。
そして、それはコミュニケーションデザインとしても
使えるな、と思っている。
エンターテイメントの本質が
「予測不可能性」であると仮定する。
すると、
工業社会における「仕事」には、「予測不可能性」はほとんどない。
それが、「疎外」のひとつの要因だったのではないか。
人は、やっていることを楽しむために、
「予測不可能性」を必要としている。
クラフト(手作り)の楽しさは、
ていねいさ、クオリティの高さだけではなく、
「何ができるか分からない」という予測不可能性にもあるのではないか。
大量生産の工業製品(100円ショップに並んでいるようなもの)や
チェーン店の均質化された料理にワクワクしないのは、
(別にワクワクを求めているわけじゃないのかもしれないけど)
そこに予測不可能性が存在しないからではないのか。
「注文をまちがえる料理店」や
何が出てくるか分からないサービスエリアの定食は、
それを見事にエンターテイメントビジネスへと変更したのではないか。
工業社会にとって、
「予測可能」であることは絶対の価値があった。
そしてそれを可能にしたのは、「増え続ける人口」だった。
多くの人々は、
「生き延びる」という価値のために、
「予測可能」な生き方を選択した。
会社員となり、厚生年金に入り、
30年以上のローンを組み、マイホームを建て、
老後は悠々自適に過ごす。
そんなストーリーを「生き延びる」ために選択した。
(させられた、のかもしれない)
「目標を達成する。」こと。
それは予測の実現と同義である。
学校はそこにこそ「価値」があるんだと教え続けた。
その仮説は、おそらく正しかった。
そうやって我が国は世界に類を見ない
経済成長を遂げることができた。
ところが。
もう、その前提が変わってしまった。
人口は減り続け、
工業社会から作り出されるモノを
それ相応の対価を払って手に入れようと思う人は、
世界中にほとんど残っていない。
そもそも。
「予測可能」というもの自体が、
エンターテイメントと逆の感情、つまり、つまらないという感情を生むのだ。
もちろんこれは、僕の場合、なのかもしれない。
「達成動機」という話を聞いたことがある。
世の中には「達成動機」が強い、
つまり目標を達成することに対して、
特に喜びを感じる種類の人たちがいるのだという。
その人は、ビジネスで成功する確率が非常に高いのだと。
「夢に日付を」と言って、達成できる人のことだ。
しかし、自己啓発書を読む多くの人は
「自分に甘いから目標を達成できない」
と思っている。
しかし、本当はそうじゃなくて、
「達成動機が強いから達成できる」、そういう人がいるのだ。
ということなのかもしれない。
(僕が自分に甘いからこういうことを言っているのかもしれない。)
僕がツルハシブックスをやっているとき。
特に地下古本コーナーHAKKUTSUの取材を受けて、
もっとも困った質問が、
「本を発掘した若者に、どうなってほしいですか?」
だった。
つまり、このプロジェクトの目的・目標は何か?
と聞かれたのだ。
その時の僕の気持ちは、
エリカ様バリの「べつに・・・」だった。
別にどうもなってほしくない。
僕はただ、本を届けたかった。それだけだ。
僕にとってその「機会提供」が価値だ。
今なら、その先を説明できる。
僕がなぜ、それをやっていたのか?
暗闇で懐中電灯を片手に、
本の表紙に貼ってあるメッセージを頼りに、
直感を働かせて本を手に取る。
それを買う。
それの行為は、発掘した本人だけではなく、
特に「僕にとって」予測不可能性の高い行為だ。
だから僕はそれをエンターテイメントだと思ったのだ。
だからこそ、そんな活動をやっているのだ。
そして、大学の中に身を置いてみて、
その他でもいろいろ非営利活動に取り組んでみて、
僕が分かったこと。
ミーティングと振り返りを楽しむこと。
場のチカラで何かを創造すること。
そのために個人として、
「評価」ではなく「承認」が重要なのだ知ること。
「承認」が得られる「場」「チーム」を手に入れること。
たぶんそれ。
そこにも、「予測不可能性」というキーワードが入ってくる。
「最近会ったよかったこと」という「チューニング」から始まるミーティング。
「今日のミーティングの感想は」という「チューニング」で終わるミーティング。
「予測できなかった悪かったこと」(反省点)だけでなく「予測できなかったよかったこと」
という予測不可能性を楽しむための振り返りの手法。
メンバーそれぞれの過去を掘り下げるという、
「顧客」を探すビジョンセッション的ワークショップ。
そんなのを積み重ねて、
「承認」が得られる場をつくる。
そして、「学び」のある場をつくる。
「学び」という予測不可能性を感じられる場をつくる。
それが活動のモチベーションのドライブにとって、最も大切なことだと思う。
たぶんこれが、これから僕がやっていくこと。
ともに学ぼう。
その先にある、予測不可能な何かを見てみたいから。
意識し始めたのは、昨年5月の
法政大学長岡ゼミの「カフェゼミ」だった。
「つながるカレー」の会@日本橋。
加藤さんの、
あまったカレーの話に、シビれた。
エンターテイメントとは、予測不可能性であると思った。
http://hero.niiblo.jp/e484808.html
「予測できない」というモチベーション・デザイン
(17.5.19)
そして、7月の「アルプスブックキャンプ」で
藤本さんに出会う。
http://hero.niiblo.jp/e485488.html
「出会うたんです」(17.8.1)
彼は、予測不可能なことに出会った自分自身という
現象を記事にしていくことで、魅力的なものになると言った。
それが「魔法をかける」ということなのだと。
そして、それはコミュニケーションデザインとしても
使えるな、と思っている。
エンターテイメントの本質が
「予測不可能性」であると仮定する。
すると、
工業社会における「仕事」には、「予測不可能性」はほとんどない。
それが、「疎外」のひとつの要因だったのではないか。
人は、やっていることを楽しむために、
「予測不可能性」を必要としている。
クラフト(手作り)の楽しさは、
ていねいさ、クオリティの高さだけではなく、
「何ができるか分からない」という予測不可能性にもあるのではないか。
大量生産の工業製品(100円ショップに並んでいるようなもの)や
チェーン店の均質化された料理にワクワクしないのは、
(別にワクワクを求めているわけじゃないのかもしれないけど)
そこに予測不可能性が存在しないからではないのか。
「注文をまちがえる料理店」や
何が出てくるか分からないサービスエリアの定食は、
それを見事にエンターテイメントビジネスへと変更したのではないか。
工業社会にとって、
「予測可能」であることは絶対の価値があった。
そしてそれを可能にしたのは、「増え続ける人口」だった。
多くの人々は、
「生き延びる」という価値のために、
「予測可能」な生き方を選択した。
会社員となり、厚生年金に入り、
30年以上のローンを組み、マイホームを建て、
老後は悠々自適に過ごす。
そんなストーリーを「生き延びる」ために選択した。
(させられた、のかもしれない)
「目標を達成する。」こと。
それは予測の実現と同義である。
学校はそこにこそ「価値」があるんだと教え続けた。
その仮説は、おそらく正しかった。
そうやって我が国は世界に類を見ない
経済成長を遂げることができた。
ところが。
もう、その前提が変わってしまった。
人口は減り続け、
工業社会から作り出されるモノを
それ相応の対価を払って手に入れようと思う人は、
世界中にほとんど残っていない。
そもそも。
「予測可能」というもの自体が、
エンターテイメントと逆の感情、つまり、つまらないという感情を生むのだ。
もちろんこれは、僕の場合、なのかもしれない。
「達成動機」という話を聞いたことがある。
世の中には「達成動機」が強い、
つまり目標を達成することに対して、
特に喜びを感じる種類の人たちがいるのだという。
その人は、ビジネスで成功する確率が非常に高いのだと。
「夢に日付を」と言って、達成できる人のことだ。
しかし、自己啓発書を読む多くの人は
「自分に甘いから目標を達成できない」
と思っている。
しかし、本当はそうじゃなくて、
「達成動機が強いから達成できる」、そういう人がいるのだ。
ということなのかもしれない。
(僕が自分に甘いからこういうことを言っているのかもしれない。)
僕がツルハシブックスをやっているとき。
特に地下古本コーナーHAKKUTSUの取材を受けて、
もっとも困った質問が、
「本を発掘した若者に、どうなってほしいですか?」
だった。
つまり、このプロジェクトの目的・目標は何か?
と聞かれたのだ。
その時の僕の気持ちは、
エリカ様バリの「べつに・・・」だった。
別にどうもなってほしくない。
僕はただ、本を届けたかった。それだけだ。
僕にとってその「機会提供」が価値だ。
今なら、その先を説明できる。
僕がなぜ、それをやっていたのか?
暗闇で懐中電灯を片手に、
本の表紙に貼ってあるメッセージを頼りに、
直感を働かせて本を手に取る。
それを買う。
それの行為は、発掘した本人だけではなく、
特に「僕にとって」予測不可能性の高い行為だ。
だから僕はそれをエンターテイメントだと思ったのだ。
だからこそ、そんな活動をやっているのだ。
そして、大学の中に身を置いてみて、
その他でもいろいろ非営利活動に取り組んでみて、
僕が分かったこと。
ミーティングと振り返りを楽しむこと。
場のチカラで何かを創造すること。
そのために個人として、
「評価」ではなく「承認」が重要なのだ知ること。
「承認」が得られる「場」「チーム」を手に入れること。
たぶんそれ。
そこにも、「予測不可能性」というキーワードが入ってくる。
「最近会ったよかったこと」という「チューニング」から始まるミーティング。
「今日のミーティングの感想は」という「チューニング」で終わるミーティング。
「予測できなかった悪かったこと」(反省点)だけでなく「予測できなかったよかったこと」
という予測不可能性を楽しむための振り返りの手法。
メンバーそれぞれの過去を掘り下げるという、
「顧客」を探すビジョンセッション的ワークショップ。
そんなのを積み重ねて、
「承認」が得られる場をつくる。
そして、「学び」のある場をつくる。
「学び」という予測不可能性を感じられる場をつくる。
それが活動のモチベーションのドライブにとって、最も大切なことだと思う。
たぶんこれが、これから僕がやっていくこと。
ともに学ぼう。
その先にある、予測不可能な何かを見てみたいから。
2018年02月28日
「サードプレイス」から「アナザー・バリュー・スペース」へ
「サードプレイス」とは、本当は何なのか?
「サードプレイス」は、本当に必要なのか?
昨日の「有縁」「無縁」の話を受けて、
考えたこと。
「無縁」社会とは、「有縁」社会のように、
一人ひとりが縁を結ばず、金だけが支配している社会で、
だからこそ、そこには中央権力が定める法律も及ばないし、
世俗のしきたりも希薄である。
しかし、それが
「有縁」社会のセーフティネットになっている。
つまり、有縁社会からはじき出されても、
行く場所があるということ。死ななくてもよいということ。
有縁社会は無縁社会を必要とし、
無縁社会はまた有縁社会を必要としている。
これを、現代に当てはめるとなんだろうか。
「非日常空間」が必要だと言われる。
あるいは、「非日常体験」が観光にとって重要だと言われる。
たとえば、家族と温泉に行く。
たとえば、デートでテーマパークに行く。
あれは「非日常空間」だろうか。
たとえば、ひとりでカフェに行く。
たとえば、仲間と行きつけの居酒屋に行く。
それは、近すぎて「日常空間」だろうか。
川崎・新城劇場のミーティングで、
「居心地のいい場所」というテーマで話した時、
「カフェにいる時間」だと答えたメンバーに、
どうして?と聞いたら、
カフェに入って、飲み物を目の前にしたとき、
その瞬間、「目的・目標」から解放された、と
感じるからだという。
メモをとったり、手紙を書いたりするらしいのだけど。
あの話を思い出した。
非日常空間、あるいは、サードプレイスとは、
日常とは異なる価値観が支配する空間であり、
その場に身をおくことは、根源的に大切なことなのではないか。
上記の彼女がカフェに行くのは、
「目的・目標から解放された空間」に身を置きたいからではないか。
そういう意味では、ストレス解消のため1泊2日で温泉に行く、とか
乗り物による刺激やスリル、大量の消費をするために行くテーマパークは、
「日常の価値観(効率化や消費第一主義)」のまま、
時間を過ごしていることにならないだろうか。
もちろん、コンセプトのあるホテルや、歴史ある温泉旅館、
思いや祈りのこもったテーマパークでは、ある程度の非日常を味わえるだろう。
そうか。
「日常」と「非日常」を決めるのは、
場所そのものではなくて、
場所に込められた思いや歴史などの
「価値観」なのではないかと。
休みの日に、
団体スポーツを楽しんだり、
ひとりで山に登ったり、
酒を飲みに行ったり、
もしくはギャンブルをしたりするのは、
そこが、違う価値観が支配する空間だからじゃないのか。
本当に必要なのは、
「サードプレイス」という場所ではなく、
「アナザー・バリュー・スペース(タイム)」
とでもいうのか、
日常とは異なる価値観に
支配される場や空間、時間ではないか。
そして、その価値観は、必ずしも
明確に言語化される必要はなくて、
それをなんとなく感じられればいいのだと思う。
福島県白河市のカフェ・エマノンには、
言語化されない「ベクトル感」があり、
それを感じたくて高校生は集うのだろうと思う。
次は「ベクトル感」について書こうかな。
「サードプレイス」は、本当に必要なのか?
昨日の「有縁」「無縁」の話を受けて、
考えたこと。
「無縁」社会とは、「有縁」社会のように、
一人ひとりが縁を結ばず、金だけが支配している社会で、
だからこそ、そこには中央権力が定める法律も及ばないし、
世俗のしきたりも希薄である。
しかし、それが
「有縁」社会のセーフティネットになっている。
つまり、有縁社会からはじき出されても、
行く場所があるということ。死ななくてもよいということ。
有縁社会は無縁社会を必要とし、
無縁社会はまた有縁社会を必要としている。
これを、現代に当てはめるとなんだろうか。
「非日常空間」が必要だと言われる。
あるいは、「非日常体験」が観光にとって重要だと言われる。
たとえば、家族と温泉に行く。
たとえば、デートでテーマパークに行く。
あれは「非日常空間」だろうか。
たとえば、ひとりでカフェに行く。
たとえば、仲間と行きつけの居酒屋に行く。
それは、近すぎて「日常空間」だろうか。
川崎・新城劇場のミーティングで、
「居心地のいい場所」というテーマで話した時、
「カフェにいる時間」だと答えたメンバーに、
どうして?と聞いたら、
カフェに入って、飲み物を目の前にしたとき、
その瞬間、「目的・目標」から解放された、と
感じるからだという。
メモをとったり、手紙を書いたりするらしいのだけど。
あの話を思い出した。
非日常空間、あるいは、サードプレイスとは、
日常とは異なる価値観が支配する空間であり、
その場に身をおくことは、根源的に大切なことなのではないか。
上記の彼女がカフェに行くのは、
「目的・目標から解放された空間」に身を置きたいからではないか。
そういう意味では、ストレス解消のため1泊2日で温泉に行く、とか
乗り物による刺激やスリル、大量の消費をするために行くテーマパークは、
「日常の価値観(効率化や消費第一主義)」のまま、
時間を過ごしていることにならないだろうか。
もちろん、コンセプトのあるホテルや、歴史ある温泉旅館、
思いや祈りのこもったテーマパークでは、ある程度の非日常を味わえるだろう。
そうか。
「日常」と「非日常」を決めるのは、
場所そのものではなくて、
場所に込められた思いや歴史などの
「価値観」なのではないかと。
休みの日に、
団体スポーツを楽しんだり、
ひとりで山に登ったり、
酒を飲みに行ったり、
もしくはギャンブルをしたりするのは、
そこが、違う価値観が支配する空間だからじゃないのか。
本当に必要なのは、
「サードプレイス」という場所ではなく、
「アナザー・バリュー・スペース(タイム)」
とでもいうのか、
日常とは異なる価値観に
支配される場や空間、時間ではないか。
そして、その価値観は、必ずしも
明確に言語化される必要はなくて、
それをなんとなく感じられればいいのだと思う。
福島県白河市のカフェ・エマノンには、
言語化されない「ベクトル感」があり、
それを感じたくて高校生は集うのだろうと思う。
次は「ベクトル感」について書こうかな。
2018年02月18日
ソフトとしての本屋
「ツルハシブックスは、ハードとしての本屋ではなく、
ソフトとしての本屋になっていくんじゃないか?」
たしか、ツルハシブックスの閉店が決まった会議の時に
山田さんが言っていた言葉だったような。
そんな山田さんは、
「古本詩人ゆよん堂」をつくった。
ツルハシブックスとはなんだったのか。
そして、ツルハシブックスを立ち上げた自分はなんだったのか。
そもそも、偶然に導かれたことから始まった。
・インターン事業が軌道に乗りつつあり、
・学生を集めるのがたいへんになって、
・事務所を構えたいと思って、内野に来たら、
・その事務所が激しく欠陥物件で、半年で移動せざるを得ず、
・駅前で物件を探していたら、駅前一等地に「貸」が出ていて、
・新潟市の中心市街地活性化の施策もあったり、
・カフェをやりたいという宮澤くんの存在もあり、
・1階どうしよう?って話で人を集める場をつくらなきゃって思って
・人が集まると言えば駄菓子屋、で、そうなりかけたんだけど、
・そういえば、俺、ヴィレッジヴァンガード郡山アティ店で
・まちを創れる本屋に憧れていて
・本屋で人が集まる場を作れたら面白いな
って思って、
ツルハシブックスになったんだな。
すごい偶然。
あそこの正式名所は、
「ウチノ・コラボレーション・ラボラトリー」
内野地域で、協働を生む、実験場。
これがコンセプトだった。
地下古本コーナー「HAKKUTSU」が話題になって、
全国から人が集まってきていたけど、
本来の価値は、本を売ることではなく、
コラボレーションの実験が起こること、としていた。
実際にツルハシブックスから始まったものは、
・野菜ソムリエランチ
・にしかん・農家マップ制作
・フリーペーパー「内野日和」の作成
・うちのまち なじみのおみせ ものがたり(商店街でのミニゼミ)
・社長10人×新潟の学生50人「夜景企画会議」
などなど。
もっとあると思うのだけど、
そう考えるといろんなことが起こっているよな。
実際に、それは本屋じゃないくてもできるんじゃないか?
って言われたし、
ツルハシブックスに来て、本を買わないお客さんは
多かったし、本の売り上げは上がらなかったし。
なんで本屋なんですか?
本屋である必要があったのか?
って聞かれたけど。
僕は本屋だから、しかもそれが新刊書店だから
できたようなところはあると思っている。
本のある空間のチカラがあるのだ。
人と人のコミュニケーションのツール。
そして、多様性の許容。
さらに、空気感の入れ替え。
たぶんこの3つが
「場」にとってプラスの影響をもたらす本の効能だと思う。
ツルハシブックスがハードからソフトになる。
それはつまり、ツルハシブックスの実態から出てきた学びを
ほかの場に応用していくことだろう。
そういう意味では、
以上3つのポイントをどう具体的につくっていくか。
それがポイントなのだろうと思う。
本屋の先に、何を見るか。
それを語りながらつくっていきたい。
今日は多治見で本屋づくりプロジェクトのキックオフです。

ソフトとしての本屋になっていくんじゃないか?」
たしか、ツルハシブックスの閉店が決まった会議の時に
山田さんが言っていた言葉だったような。
そんな山田さんは、
「古本詩人ゆよん堂」をつくった。
ツルハシブックスとはなんだったのか。
そして、ツルハシブックスを立ち上げた自分はなんだったのか。
そもそも、偶然に導かれたことから始まった。
・インターン事業が軌道に乗りつつあり、
・学生を集めるのがたいへんになって、
・事務所を構えたいと思って、内野に来たら、
・その事務所が激しく欠陥物件で、半年で移動せざるを得ず、
・駅前で物件を探していたら、駅前一等地に「貸」が出ていて、
・新潟市の中心市街地活性化の施策もあったり、
・カフェをやりたいという宮澤くんの存在もあり、
・1階どうしよう?って話で人を集める場をつくらなきゃって思って
・人が集まると言えば駄菓子屋、で、そうなりかけたんだけど、
・そういえば、俺、ヴィレッジヴァンガード郡山アティ店で
・まちを創れる本屋に憧れていて
・本屋で人が集まる場を作れたら面白いな
って思って、
ツルハシブックスになったんだな。
すごい偶然。
あそこの正式名所は、
「ウチノ・コラボレーション・ラボラトリー」
内野地域で、協働を生む、実験場。
これがコンセプトだった。
地下古本コーナー「HAKKUTSU」が話題になって、
全国から人が集まってきていたけど、
本来の価値は、本を売ることではなく、
コラボレーションの実験が起こること、としていた。
実際にツルハシブックスから始まったものは、
・野菜ソムリエランチ
・にしかん・農家マップ制作
・フリーペーパー「内野日和」の作成
・うちのまち なじみのおみせ ものがたり(商店街でのミニゼミ)
・社長10人×新潟の学生50人「夜景企画会議」
などなど。
もっとあると思うのだけど、
そう考えるといろんなことが起こっているよな。
実際に、それは本屋じゃないくてもできるんじゃないか?
って言われたし、
ツルハシブックスに来て、本を買わないお客さんは
多かったし、本の売り上げは上がらなかったし。
なんで本屋なんですか?
本屋である必要があったのか?
って聞かれたけど。
僕は本屋だから、しかもそれが新刊書店だから
できたようなところはあると思っている。
本のある空間のチカラがあるのだ。
人と人のコミュニケーションのツール。
そして、多様性の許容。
さらに、空気感の入れ替え。
たぶんこの3つが
「場」にとってプラスの影響をもたらす本の効能だと思う。
ツルハシブックスがハードからソフトになる。
それはつまり、ツルハシブックスの実態から出てきた学びを
ほかの場に応用していくことだろう。
そういう意味では、
以上3つのポイントをどう具体的につくっていくか。
それがポイントなのだろうと思う。
本屋の先に、何を見るか。
それを語りながらつくっていきたい。
今日は多治見で本屋づくりプロジェクトのキックオフです。

2018年01月03日
「どうぐや」になる
「夢はのりもの」
2016年、
「ゆめのはいたつにん」(教来石小織 センジュ出版)
を読んで思ったこと。
2017年末、
PCシステム屋さん、
料理道具屋さん、
そして出版社(これはセンジュ出版さんですが)
に話を聞いて、
キーワードは「どうぐ」かもしれないと思った。
そんなとき、
1月1日朝、毎日新聞のAI特集で
yoshikiがAIと音楽について語っていた。
~~~以下、一部引用
AIでヒット曲は作ることができる。
ただ同時に「曲が売れる(ヒットする)」ということに、
そんなに意味があるのかな、と僕は思ってしまうんですね。
「売れたい」つまり「お金を稼ぎたい」ということであれば、
もっといい職業ってありますよね。
わざわざ芸術家である必要はないわけです。
メロディーってなんか突然降ってくるというか、説明不可能なもの。
どうしようもない悲しみや怒りを音楽を通して表現した。
そこに没頭するだけでも自分は救われていたと思います。
音楽という芸術表現があったからこそ、
僕は今まで生きてこられたと思うんですね。
作曲は、目の前に広がる芸術という海に飛び込んでいくイメージ。
理論じゃ語れない「何か」が芸術の中にあると、そう思いたいですよね。
すべてAIにできてしまったら、自分たちの存在価値がなくなってしまうので。
AIはライバルではなくて、友。
「何のために音楽をやるか」ということに尽きると思うんです。
「音楽で売れたい」って思ったらAIが脅威になる可能性があります。
でも見方を変えれば、そういう風には思えないんじゃないかな。
これまでもデジタル技術の発達によって、
作曲の選択肢はどんどん広がっています。
デジタル化のいいところはいっぱいあって、使わない手はない。
同じようにAIも、「心の友」だと思って、共存していけばいいと思います。
~~~以上、一部引用
そうそう。
AIって道具なんですよね。
ただ、それだけ。
本と同じ。
どの乗り物に乗るのか?っていう話。
そのくらい自分を相対化というか、俯瞰化して
見れたらいいなと思う。
本も、PCも、AIも、職業も、夢も、
ぜんぶ乗り物にすぎない。
目的地ではないんだ。
夢や目標に乗って、
その先の地平を見に行くんだ。
yoshikiも言ってる。
「何のために音楽をやるか」ということに尽きると思うんです。
それだ。
WHY?
なぜ、その乗り物に乗るんだ?
っていう問い。
そんな問いから2018年を始めてみようと思う。
そして、僕の今年のテーマは
「どうぐや」なのかもしれません。
武器も、防具も、薬草も、乗り物も
売っているような、そんな「どうぐや」
になりたいなと思います。
誰かもそんなこと言っていたような気がする。
2016年、
「ゆめのはいたつにん」(教来石小織 センジュ出版)
を読んで思ったこと。
2017年末、
PCシステム屋さん、
料理道具屋さん、
そして出版社(これはセンジュ出版さんですが)
に話を聞いて、
キーワードは「どうぐ」かもしれないと思った。
そんなとき、
1月1日朝、毎日新聞のAI特集で
yoshikiがAIと音楽について語っていた。
~~~以下、一部引用
AIでヒット曲は作ることができる。
ただ同時に「曲が売れる(ヒットする)」ということに、
そんなに意味があるのかな、と僕は思ってしまうんですね。
「売れたい」つまり「お金を稼ぎたい」ということであれば、
もっといい職業ってありますよね。
わざわざ芸術家である必要はないわけです。
メロディーってなんか突然降ってくるというか、説明不可能なもの。
どうしようもない悲しみや怒りを音楽を通して表現した。
そこに没頭するだけでも自分は救われていたと思います。
音楽という芸術表現があったからこそ、
僕は今まで生きてこられたと思うんですね。
作曲は、目の前に広がる芸術という海に飛び込んでいくイメージ。
理論じゃ語れない「何か」が芸術の中にあると、そう思いたいですよね。
すべてAIにできてしまったら、自分たちの存在価値がなくなってしまうので。
AIはライバルではなくて、友。
「何のために音楽をやるか」ということに尽きると思うんです。
「音楽で売れたい」って思ったらAIが脅威になる可能性があります。
でも見方を変えれば、そういう風には思えないんじゃないかな。
これまでもデジタル技術の発達によって、
作曲の選択肢はどんどん広がっています。
デジタル化のいいところはいっぱいあって、使わない手はない。
同じようにAIも、「心の友」だと思って、共存していけばいいと思います。
~~~以上、一部引用
そうそう。
AIって道具なんですよね。
ただ、それだけ。
本と同じ。
どの乗り物に乗るのか?っていう話。
そのくらい自分を相対化というか、俯瞰化して
見れたらいいなと思う。
本も、PCも、AIも、職業も、夢も、
ぜんぶ乗り物にすぎない。
目的地ではないんだ。
夢や目標に乗って、
その先の地平を見に行くんだ。
yoshikiも言ってる。
「何のために音楽をやるか」ということに尽きると思うんです。
それだ。
WHY?
なぜ、その乗り物に乗るんだ?
っていう問い。
そんな問いから2018年を始めてみようと思う。
そして、僕の今年のテーマは
「どうぐや」なのかもしれません。
武器も、防具も、薬草も、乗り物も
売っているような、そんな「どうぐや」
になりたいなと思います。
誰かもそんなこと言っていたような気がする。
2017年07月19日
小さなゆうびんせん
小さなゆうびんせん
人はみな、ひとり乗りの小さなゆうびんせんとして、生まれてくる。
少しの手紙を携えて。
でもその手紙には、あて名が無い。
差出人の名前もこすれて消えかかっている。
学校や会社という大きな船。
たくさんの手紙を預かって、どこかに届ける。
大きな船に、小さな舟ごと、乗り込むこともできる。
そこでは、目的地に早く着くために、
船長の指示に従い、効率が求められる。
大きな船は安定していて、揺れることがあまりない。
いつのまにか、船に乗っていることも忘れてしまいそうになる。
効率を求めすぎて、目の前のことをやるのに精いっぱいになる。
その船を途中で降りることもできる。
またひとり乗りの小さな舟でこぎ出したり、
20人乗りの船に乗り換えたり、
仲間と一緒に3人乗りの船をつくってもいい。
小さい舟は不安定だ。よく揺れる。
ひとりひとりが考え、判断しなきゃいけない。
大切なのは、
このふねは、どこに向かっているのか?
誰に手紙を届けるのか?
この船旅を誰と一緒にしたいのか?
のんびり行きたいのか、はやく行きたいのか?
そんな話し合いをすることだ。
時には、港町に立ち寄り、酒を酌み交わし、
次の行先を決めるんだ。
ひとりひとりが預かっている手紙。
その手紙を待っている人がどこかにいるはずだから、
今日も、その船を漕ぎ出していこう。
人はみな、ひとり乗りの小さなゆうびんせんとして、生まれてくる。
少しの手紙を携えて。
でもその手紙には、あて名が無い。
差出人の名前もこすれて消えかかっている。
学校や会社という大きな船。
たくさんの手紙を預かって、どこかに届ける。
大きな船に、小さな舟ごと、乗り込むこともできる。
そこでは、目的地に早く着くために、
船長の指示に従い、効率が求められる。
大きな船は安定していて、揺れることがあまりない。
いつのまにか、船に乗っていることも忘れてしまいそうになる。
効率を求めすぎて、目の前のことをやるのに精いっぱいになる。
その船を途中で降りることもできる。
またひとり乗りの小さな舟でこぎ出したり、
20人乗りの船に乗り換えたり、
仲間と一緒に3人乗りの船をつくってもいい。
小さい舟は不安定だ。よく揺れる。
ひとりひとりが考え、判断しなきゃいけない。
大切なのは、
このふねは、どこに向かっているのか?
誰に手紙を届けるのか?
この船旅を誰と一緒にしたいのか?
のんびり行きたいのか、はやく行きたいのか?
そんな話し合いをすることだ。
時には、港町に立ち寄り、酒を酌み交わし、
次の行先を決めるんだ。
ひとりひとりが預かっている手紙。
その手紙を待っている人がどこかにいるはずだから、
今日も、その船を漕ぎ出していこう。
2017年06月17日
「共鳴」から始まるプロジェクト
「チューニング」っていうマイブーム。
先週金沢文庫「キッチンのある本屋」プロジェクト
のミーティング前の平野さんとのメッセージのやりとりでも
自然と出てきた言葉。
初めての人もいるから、
いきなりミーティングしないで、
8時に集合して、称名寺散歩して、
ちょっとチューニングしてから行く。
って。

「チューニング」。
それはもちろんコミュニケーションだ。
1つは感情のコミュニケーション。
「最近あったよかったこと」
「今日のミーティングをやってみてどうだったか?」
そうやって、感情を言葉にする「チューニング」。
もうひとつは、非言語のコミュニケーション。
一緒にご飯を食べる。
ご飯をつくる。
散歩をする。
農作業をする。
そうやって相手を
「感覚的に」「なんとなく」
知っていくこと。
音楽で言えば「音合わせ」をしている状態。
そこには、
「共感」というよりは、「共鳴」が起こる。
「共感」っていうのは、言葉だけでもできる。
でも「共鳴」っていうのはもっと肌感覚で、
感じないとできない。
プロジェクトってそういうものなのかもしれないなと。
ハックツの宮本もコメタクの吉野も
「なんか一緒にやってみたいな」
というのから始まっている。
それは本当に「なにか」だったんだと
今は思う。
感覚的な何か。
一緒に踊りたかったのか、歌いたかったのか、
奏でたかったのか。
そういう感じ。
楽器としての自分を、引き出してくれるような、
そんな出会い。
共鳴から始まるプロジェクト。
そしてそれはチューニングを繰り返しながら進んでいく。
いま、この瞬間が、ひとつの音楽なのだ。
そんなプロジェクトの進め方。
ひとつひとつのミーティングが
楽曲であるような、そんな時間。
今日はいい音出せたかな、
とふりかえるようなミーティングをしたい。
「目的から考える。」
と口癖のようにいつも言われてきた。
それはもちろんそうなのだけど。
ひとりひとり、いやひとつひとつの楽器が
いい音出してこそ、いい音楽、いい仕事だったと
言えるのではないかな。
そのためには、目的から考える、その前に、
チューニングから、共鳴から始めたほうがよいのではないか。
僕はそんな「チューニング」をする人に
なりたいかもしれない。
チューニング・デザイナー
ってどうですか?(笑)
先週金沢文庫「キッチンのある本屋」プロジェクト
のミーティング前の平野さんとのメッセージのやりとりでも
自然と出てきた言葉。
初めての人もいるから、
いきなりミーティングしないで、
8時に集合して、称名寺散歩して、
ちょっとチューニングしてから行く。
って。

「チューニング」。
それはもちろんコミュニケーションだ。
1つは感情のコミュニケーション。
「最近あったよかったこと」
「今日のミーティングをやってみてどうだったか?」
そうやって、感情を言葉にする「チューニング」。
もうひとつは、非言語のコミュニケーション。
一緒にご飯を食べる。
ご飯をつくる。
散歩をする。
農作業をする。
そうやって相手を
「感覚的に」「なんとなく」
知っていくこと。
音楽で言えば「音合わせ」をしている状態。
そこには、
「共感」というよりは、「共鳴」が起こる。
「共感」っていうのは、言葉だけでもできる。
でも「共鳴」っていうのはもっと肌感覚で、
感じないとできない。
プロジェクトってそういうものなのかもしれないなと。
ハックツの宮本もコメタクの吉野も
「なんか一緒にやってみたいな」
というのから始まっている。
それは本当に「なにか」だったんだと
今は思う。
感覚的な何か。
一緒に踊りたかったのか、歌いたかったのか、
奏でたかったのか。
そういう感じ。
楽器としての自分を、引き出してくれるような、
そんな出会い。
共鳴から始まるプロジェクト。
そしてそれはチューニングを繰り返しながら進んでいく。
いま、この瞬間が、ひとつの音楽なのだ。
そんなプロジェクトの進め方。
ひとつひとつのミーティングが
楽曲であるような、そんな時間。
今日はいい音出せたかな、
とふりかえるようなミーティングをしたい。
「目的から考える。」
と口癖のようにいつも言われてきた。
それはもちろんそうなのだけど。
ひとりひとり、いやひとつひとつの楽器が
いい音出してこそ、いい音楽、いい仕事だったと
言えるのではないかな。
そのためには、目的から考える、その前に、
チューニングから、共鳴から始めたほうがよいのではないか。
僕はそんな「チューニング」をする人に
なりたいかもしれない。
チューニング・デザイナー
ってどうですか?(笑)
2017年06月13日
「チューニング」から始まる。
チューニング【tuning】
( 名 ) スル
①
受信機や受像機のダイヤルを回して周波数を同調させ、特定の放送局を選択すること。
②
楽器の音程を正確に合わせること。音合わせをすること。
(コトバンク 大辞林第三版より)
ジャズセッションのような
「場」をつくりたいと思う。
そこに居合わせた人が
歌いだしたり、踊りだしたり、
新たに楽器を持って来て、演奏を始めたり、するような場を。
それを見ているだけでも
楽しくなってしまうような場をつくりたい。
「多様性」と「偶然性」が「可能性」を生む。
とソトコトの取材の時に答えたけれど。
その「場」には
ジャズセッションのような、
五感に響く何か、が必要なのかもしれない。
6月11日(日)朝8時。
金沢文庫駅集合。
称名寺まで歩く。
素敵な風景が広がっている。

いったん駅に戻って、
パンを買って、10時過ぎにミーティング開始。
2時間。それは「チューニング」の時間。
いや、ミーティングの場も、
最初はそれぞれの思いを語ってた。
次の日程、内容などは
最後の30分だけだった気がする。
初参加の人がいるとき、
そこには「チューニング」の時間が必要になるのかもしれない。
音合わせの時間。
それぞれの楽器の音を出してみて、
音を合わせていく。
今回は高音の人が多いから
自分は低音でいこう、とか?
(音楽やったことがないのでよく分からない。笑)
プロジェクトが始まるとき。
そこにはチューニングの時間が必要だ。
一緒にご飯を食べたり、飲み会したり、
一緒にご飯を作ったり、キャンプをしたり。
「ミーティングとは感性をチューニングすること」
http://hero.niiblo.jp/e484576.html
(17.4.23)
のように、
チューニングっていうのはすごく大切なのだと思う。
自分の音、ちゃんと出せてるか、って。
そう。
もしかしたら、「場」に必要なものって
チューニングなのかもしれない。
もし、ジャズセッションのようなまちを
作りたいのだとしたら、
今回の金沢文庫でやる
シェアキッチンのある本屋プロジェクト(仮)で
つくる「場」は、キッチンは、本屋は、
ひとつの楽器になるのかもしれないなと。
そこに集まってくる人たちと、
「こいつ、どんな音を出すんだろう」って、
「こいつ、なかなかいい音出しそうだな」って、
チューニングして、音楽を生み出していく。
そんな場になるのではないか。
ジャズセッションのようなまち。
シェアキッチンのある本屋(仮)は、
その最初の音になりたい。
( 名 ) スル
①
受信機や受像機のダイヤルを回して周波数を同調させ、特定の放送局を選択すること。
②
楽器の音程を正確に合わせること。音合わせをすること。
(コトバンク 大辞林第三版より)
ジャズセッションのような
「場」をつくりたいと思う。
そこに居合わせた人が
歌いだしたり、踊りだしたり、
新たに楽器を持って来て、演奏を始めたり、するような場を。
それを見ているだけでも
楽しくなってしまうような場をつくりたい。
「多様性」と「偶然性」が「可能性」を生む。
とソトコトの取材の時に答えたけれど。
その「場」には
ジャズセッションのような、
五感に響く何か、が必要なのかもしれない。
6月11日(日)朝8時。
金沢文庫駅集合。
称名寺まで歩く。
素敵な風景が広がっている。

いったん駅に戻って、
パンを買って、10時過ぎにミーティング開始。
2時間。それは「チューニング」の時間。
いや、ミーティングの場も、
最初はそれぞれの思いを語ってた。
次の日程、内容などは
最後の30分だけだった気がする。
初参加の人がいるとき、
そこには「チューニング」の時間が必要になるのかもしれない。
音合わせの時間。
それぞれの楽器の音を出してみて、
音を合わせていく。
今回は高音の人が多いから
自分は低音でいこう、とか?
(音楽やったことがないのでよく分からない。笑)
プロジェクトが始まるとき。
そこにはチューニングの時間が必要だ。
一緒にご飯を食べたり、飲み会したり、
一緒にご飯を作ったり、キャンプをしたり。
「ミーティングとは感性をチューニングすること」
http://hero.niiblo.jp/e484576.html
(17.4.23)
のように、
チューニングっていうのはすごく大切なのだと思う。
自分の音、ちゃんと出せてるか、って。
そう。
もしかしたら、「場」に必要なものって
チューニングなのかもしれない。
もし、ジャズセッションのようなまちを
作りたいのだとしたら、
今回の金沢文庫でやる
シェアキッチンのある本屋プロジェクト(仮)で
つくる「場」は、キッチンは、本屋は、
ひとつの楽器になるのかもしれないなと。
そこに集まってくる人たちと、
「こいつ、どんな音を出すんだろう」って、
「こいつ、なかなかいい音出しそうだな」って、
チューニングして、音楽を生み出していく。
そんな場になるのではないか。
ジャズセッションのようなまち。
シェアキッチンのある本屋(仮)は、
その最初の音になりたい。
2017年02月28日
その点は、角か桂馬か
菊地くんと朝活。
過去の出来事を振り返って、
意味づけをして、
それが今につながっている、
って思うことがある。
たとえば、ぼくの場合は、
不登校の中学校3年生の家庭教師をしたとき。
「ああ、ぼくはこれを仕事にしたい」
と心の底から思ったのだけど、
「これ」がどれなのか?何なのか?
っていうのは今も問いかける。
その当時は、
「中学生にとっては、無職の若者(当時の僕)のような
地域の多様な大人に出会うことが必要ではないか。
とNPO法人を設立したけど。
そして、それは、10年の時を超えて、
地下古本コーナー「HAKKUTSU」として結実する。

しかし。
その後、僕は「本の処方箋」というコンテンツを手に入れる。
人の悩みを聞き、本を処方する、というもの。
これはどちらかというと、
本を処方するよりも、人の悩みを聞くほうに
重きが置かれる。
そのことを友人に話したら、
「人と向き合いたいんですね」って言われ、
いや、そうじゃないなと思った。
向き合いたくない。
人の話を聞くのも実はそんなに得意ではなかった。
でも、本のほうを向いて、なら
話を聞くことができる、ってことがわかった。
そのとき。
あのときの中学生とのエピソードが少し違って見えた。
これを仕事にしたい。
の「これ」は、中高生と地域の大人が出会う場所、ではなくて、
ともに悩みたかった
のかもしれないと思った。
未来は見えないけど、
そこに向かって、ともに悩む。
「本の処方箋」っていうのは、そういうコンテンツだ。
そうやって、過去の点の見え方が変わってくる。
「コネクティング・ドット」は、
スティーブ・ジョブズの有名なスピーチの一節だけど、
菊地くんに言わせると、
「あの時打った将棋の駒が、ここに効いてきたのか」
っていう感覚。
それ、いいね。
ジョブズより日本的だね。
人生が巨大な将棋盤だとしたら、
あの時、打った角が、いま、ここに効いてくる。
「そんなにナナメに行けるんだ!」みたいな。
予想だにしない巨大な桂馬が、
時空を飛び越えて、目の前に現れる。
あなたが今、打った点。
それがもし将棋盤の上だとしたら、
その点は、角か桂馬か。
過去の出来事を振り返って、
意味づけをして、
それが今につながっている、
って思うことがある。
たとえば、ぼくの場合は、
不登校の中学校3年生の家庭教師をしたとき。
「ああ、ぼくはこれを仕事にしたい」
と心の底から思ったのだけど、
「これ」がどれなのか?何なのか?
っていうのは今も問いかける。
その当時は、
「中学生にとっては、無職の若者(当時の僕)のような
地域の多様な大人に出会うことが必要ではないか。
とNPO法人を設立したけど。
そして、それは、10年の時を超えて、
地下古本コーナー「HAKKUTSU」として結実する。

しかし。
その後、僕は「本の処方箋」というコンテンツを手に入れる。
人の悩みを聞き、本を処方する、というもの。
これはどちらかというと、
本を処方するよりも、人の悩みを聞くほうに
重きが置かれる。
そのことを友人に話したら、
「人と向き合いたいんですね」って言われ、
いや、そうじゃないなと思った。
向き合いたくない。
人の話を聞くのも実はそんなに得意ではなかった。
でも、本のほうを向いて、なら
話を聞くことができる、ってことがわかった。
そのとき。
あのときの中学生とのエピソードが少し違って見えた。
これを仕事にしたい。
の「これ」は、中高生と地域の大人が出会う場所、ではなくて、
ともに悩みたかった
のかもしれないと思った。
未来は見えないけど、
そこに向かって、ともに悩む。
「本の処方箋」っていうのは、そういうコンテンツだ。
そうやって、過去の点の見え方が変わってくる。
「コネクティング・ドット」は、
スティーブ・ジョブズの有名なスピーチの一節だけど、
菊地くんに言わせると、
「あの時打った将棋の駒が、ここに効いてきたのか」
っていう感覚。
それ、いいね。
ジョブズより日本的だね。
人生が巨大な将棋盤だとしたら、
あの時、打った角が、いま、ここに効いてくる。
「そんなにナナメに行けるんだ!」みたいな。
予想だにしない巨大な桂馬が、
時空を飛び越えて、目の前に現れる。
あなたが今、打った点。
それがもし将棋盤の上だとしたら、
その点は、角か桂馬か。
2017年02月24日
すべては機会でしかない
大学時代に、
環境問題啓蒙系のNPOを少しかじっていた。
新潟で活動していた人たちは
歯医者さんとか大学の先生とか、
いわゆるハイソな人たちが多かった。
彼らの探究心は
環境だけにとどまらずに、
「豊かさとは何か」という根源的なところに
迫っていっていた。
「西田くんも来ない?学割でタダでいいよ」
って、講演5000円懇親会5000円(たしか)
のところに呼ばれていった。
出会ったのは、
小林正観先生でした。
ブレイクしたのはその当時から
10年くらい経ってからだと思うので、
本当にマニアックな頃。
そのときに「正しく観る」ということを、
教えてもらった。
今でも印象に残っているのは、
出来事によいことも悪いことも、
幸せも不幸せもない。
そう思う自分の心があるだけだ。
出来事はすべてニュートラルだ。
般若心経の
「色即是空 空即是色」
の話とか聞いていた。
「空」というのは
「無」ではなく、「空」なんだ。
そこに色はついていない。
それに色をつけるのは人の心だ。
出来事にプラスもマイナスもない。
そこに出来事があるだけだ。
それ以来。
何かが起こるたびに、
「これは何の機会なのだろう?」
と問いかけるようにしてきたし、
実際そうなってきたと思う。
ツルハシブックスは経営難のおかげで、
劇団員というコンセプトに出会い、
山田正史と井上有紀というスターを生んだ。
家賃フェスや灯油フェスという伝説を生んだ。
機会でしかない。
だとしたら、目の前にあるものは
どんなきっかけなんだろう。
環境問題啓蒙系のNPOを少しかじっていた。
新潟で活動していた人たちは
歯医者さんとか大学の先生とか、
いわゆるハイソな人たちが多かった。
彼らの探究心は
環境だけにとどまらずに、
「豊かさとは何か」という根源的なところに
迫っていっていた。
「西田くんも来ない?学割でタダでいいよ」
って、講演5000円懇親会5000円(たしか)
のところに呼ばれていった。
出会ったのは、
小林正観先生でした。
ブレイクしたのはその当時から
10年くらい経ってからだと思うので、
本当にマニアックな頃。
そのときに「正しく観る」ということを、
教えてもらった。
今でも印象に残っているのは、
出来事によいことも悪いことも、
幸せも不幸せもない。
そう思う自分の心があるだけだ。
出来事はすべてニュートラルだ。
般若心経の
「色即是空 空即是色」
の話とか聞いていた。
「空」というのは
「無」ではなく、「空」なんだ。
そこに色はついていない。
それに色をつけるのは人の心だ。
出来事にプラスもマイナスもない。
そこに出来事があるだけだ。
それ以来。
何かが起こるたびに、
「これは何の機会なのだろう?」
と問いかけるようにしてきたし、
実際そうなってきたと思う。
ツルハシブックスは経営難のおかげで、
劇団員というコンセプトに出会い、
山田正史と井上有紀というスターを生んだ。
家賃フェスや灯油フェスという伝説を生んだ。
機会でしかない。
だとしたら、目の前にあるものは
どんなきっかけなんだろう。
2017年01月22日
「営み」に会いたくなる旅
旅先でも、
地元の人が行く店が好きだ。
まちの定食屋さんとか、
中華料理屋さんとか。
九州だったら、酒屋で立ち飲みする角打ちが好きだ。




北九州・小倉の平尾酒店。
北九州出身のかなさんとメッセージやりとりをしていて、
「観光の原点も営みだと思います。
その場所の営みに魅力を感じた時に
本当にまた行きたい場所になるなあ!、と
いろんな場所に行ってみて感じました。」
!!!
って。
それだ!!
って。
人に会いたくなるっていうのもあるけど、
最初に行く場所は、知っている人がいない。
だから、
「営み」のあるところに行きたくなる。
「営み」
っていい言葉だなって。
大きく言えば「暮らし」なのだけど。
なんというか、
完結していない、つながっている、
そんな感じ。
こうやって生きてきた。
っていう生を感じる。
だから、旦過市場のような場所に
人は惹かれるのだろうなと。
きっと、これからの旅は、そのようになっていく。
「営み」に出会う旅。
農業だったり、
お店だったり、
それはいろいろあるのだろうけど、
「営み」に惹かれる人はたくさんいるのだろう。
そしてその営みの中に「人」がいて、
人の「暮らし」があって、
そこに来訪者としての旅人がいる。
そしてまた、その「営み」に会いたくなるのだ。
これからの観光はそう変わっていく。
そんな予感がした1通のメッセージでした。
かなさん、ありがとう。
地元の人が行く店が好きだ。
まちの定食屋さんとか、
中華料理屋さんとか。
九州だったら、酒屋で立ち飲みする角打ちが好きだ。




北九州・小倉の平尾酒店。
北九州出身のかなさんとメッセージやりとりをしていて、
「観光の原点も営みだと思います。
その場所の営みに魅力を感じた時に
本当にまた行きたい場所になるなあ!、と
いろんな場所に行ってみて感じました。」
!!!
って。
それだ!!
って。
人に会いたくなるっていうのもあるけど、
最初に行く場所は、知っている人がいない。
だから、
「営み」のあるところに行きたくなる。
「営み」
っていい言葉だなって。
大きく言えば「暮らし」なのだけど。
なんというか、
完結していない、つながっている、
そんな感じ。
こうやって生きてきた。
っていう生を感じる。
だから、旦過市場のような場所に
人は惹かれるのだろうなと。
きっと、これからの旅は、そのようになっていく。
「営み」に出会う旅。
農業だったり、
お店だったり、
それはいろいろあるのだろうけど、
「営み」に惹かれる人はたくさんいるのだろう。
そしてその営みの中に「人」がいて、
人の「暮らし」があって、
そこに来訪者としての旅人がいる。
そしてまた、その「営み」に会いたくなるのだ。
これからの観光はそう変わっていく。
そんな予感がした1通のメッセージでした。
かなさん、ありがとう。
2016年12月31日
「学校」から「市場」へ
「学校」という仕組みは、
近代社会の成立とともに成立した。
一斉授業
集団行動
上意下達
それは、おそらく、
工場や軍隊で機能する人々を養成するためであった。
富国強兵。
それがないと、諸外国に侵略されてしまう。
そんな危機感の中、
明治維新後、我が国は急速に近代化した。
そしてそれは、一時期成功し、また失敗したかに見えた。
しかし、第二次世界大戦後。
第二次産業革命の中でふたたび花を開く。
工業社会。
人口が増え続け(人口ボーナス)
それに伴った家電製品が売れ続け、
かつ、安価な労働力が提供され続ける。
それがかみ合った結果、
空前の経済成長が起こった。
そこに「学校」あるいは「教育」は大きく機能した。
2016年11月21日 20代の宿題
http://hero.niiblo.jp/e482895.html
ところが。
時代のほうが変わってしまった。
もう、家電は売れない。
全世帯に行き渡ってしまったから。
人口は増え続けてはいないから。
日本の人件費は上昇し、
海外との価格競争に勝てない企業は、
工場を海外に移転して生き残りを図る。
売るのも当然海外の市場だ。
もう、前提が変わってしまっているのだ。
それなのに、「学校」「教育」は
構造的にはあまり変わっていない。
多くの場合、高校まで、
一斉授業、集団行動、上意下達
を叩き込まれる。
そこで、「人と違っていること」を
悪いことだと思い、個性を抑え込むことも多い。
不登校であること、マイノリティであることで、
「世間」に対して負い目を感じてしまう。
ところが大学に入った瞬間に
個性は武器となり、就職活動ではそれが問われる。
もう、「学校」ではないのかもしれない。
いや、今でも、
大きな組織に入って、働こうと思うのならば、
集団行動、上意下達は必須の条件だろう。
しかし、もし、
自分の個性を生かした
スモールビジネスを興していくことを
将来としてイメージするならば、
そのチカラは「学校」だけでは、
磨かれないのかもしれない。
いや、「学校」ではむしろ、
そのチカラが削がれていくかもしれない。
そのチカラとは、
「感性」であり、「想像力」であり、「創造力」だ。
だから、
「学校」ではなく、「市場」なのかもしれないと思った。
「店」の語源は「見世」、つまり、
誰かに見せるためのものだった。
現金をやりとりするかしないかにかかわらず、
何かを「見世」る、
そんな場をつくることが、
これからの「学び」の場になっていくのではないか、
かつてはそれを学びの場として、
人は考え、試行錯誤し、自分なりの生き方を
探していったのではないか。
「学校」から「市場」へ。
未来がそこにあるような気がした、12月29日のミーティングだった。
近代社会の成立とともに成立した。
一斉授業
集団行動
上意下達
それは、おそらく、
工場や軍隊で機能する人々を養成するためであった。
富国強兵。
それがないと、諸外国に侵略されてしまう。
そんな危機感の中、
明治維新後、我が国は急速に近代化した。
そしてそれは、一時期成功し、また失敗したかに見えた。
しかし、第二次世界大戦後。
第二次産業革命の中でふたたび花を開く。
工業社会。
人口が増え続け(人口ボーナス)
それに伴った家電製品が売れ続け、
かつ、安価な労働力が提供され続ける。
それがかみ合った結果、
空前の経済成長が起こった。
そこに「学校」あるいは「教育」は大きく機能した。
2016年11月21日 20代の宿題
http://hero.niiblo.jp/e482895.html
ところが。
時代のほうが変わってしまった。
もう、家電は売れない。
全世帯に行き渡ってしまったから。
人口は増え続けてはいないから。
日本の人件費は上昇し、
海外との価格競争に勝てない企業は、
工場を海外に移転して生き残りを図る。
売るのも当然海外の市場だ。
もう、前提が変わってしまっているのだ。
それなのに、「学校」「教育」は
構造的にはあまり変わっていない。
多くの場合、高校まで、
一斉授業、集団行動、上意下達
を叩き込まれる。
そこで、「人と違っていること」を
悪いことだと思い、個性を抑え込むことも多い。
不登校であること、マイノリティであることで、
「世間」に対して負い目を感じてしまう。
ところが大学に入った瞬間に
個性は武器となり、就職活動ではそれが問われる。
もう、「学校」ではないのかもしれない。
いや、今でも、
大きな組織に入って、働こうと思うのならば、
集団行動、上意下達は必須の条件だろう。
しかし、もし、
自分の個性を生かした
スモールビジネスを興していくことを
将来としてイメージするならば、
そのチカラは「学校」だけでは、
磨かれないのかもしれない。
いや、「学校」ではむしろ、
そのチカラが削がれていくかもしれない。
そのチカラとは、
「感性」であり、「想像力」であり、「創造力」だ。
だから、
「学校」ではなく、「市場」なのかもしれないと思った。
「店」の語源は「見世」、つまり、
誰かに見せるためのものだった。
現金をやりとりするかしないかにかかわらず、
何かを「見世」る、
そんな場をつくることが、
これからの「学び」の場になっていくのではないか、
かつてはそれを学びの場として、
人は考え、試行錯誤し、自分なりの生き方を
探していったのではないか。
「学校」から「市場」へ。
未来がそこにあるような気がした、12月29日のミーティングだった。
2016年12月04日
逢着(ほうちゃく)
ツルハシブックスは、
「偶然」という名のアートプロジェクトだった。
そしてそれは、
「居場所」になることによって、
急速に「偶然」機能を失っていく。
「居場所」は日常であるからだ。
そして「常連」は、コミュニティであるからだ。
昨日は千林商店街を
陸奥賢さんと一緒に歩いた。




寄贈本読書会の中で、
陸奥さんが放つ一言一言にちょっとドキドキした。
かつて、わが国には「歌垣」というものがあり、
そこで、男女が歌を歌いあって、求愛したという。
歌垣は、世間から離れた場であり、
そこでは、人は、この世のものではなくなった。
匿名性のある人になり、
歌を歌いあい、愛を求めた。
そんな歌垣を現代に復活させる
「歌垣風呂」という活動を陸奥さんは行っている。
銭湯で男女が
男湯女湯に分かれて歌を歌いあう。
そのフィーリングで、カップルが成立するという
「感性合コン」だ。
顔が見えない相手を、
声と雰囲気で判断し、この人よさそうだな、と決める。
そんな企画。
ああ。
もう一度、「考える」から「感じる」への
シフトが始まっているんだなと。
いや、そもそも、現在のお見合いのシステムのように、
年収いくらとか職業はなにか、とか年齢条件とか、
そんな言語化できる情報で、結婚相手を決めるなんて、
そんな「効率的」な方法で本当にいいのだろうか?
それって、この150年の「近代国民国家」、
つまり、「富国強兵」的な、効率を重視した
システムの中だけの常識なんじゃないか。
もっと人は、感性を発動させていいと思う。
いや、そのほうが圧倒的に自然というか、普通だろうと思う。
陸奥さんのやっている活動は、
「歌垣風呂」だけでなく、
「まわしよみ新聞」にしても、
「直観読みブックマーカー」にしても、
「偶然」と「必然」のあいだ
を行き来しているように思う。
そして人間の持つ「感性」をより研ぎ澄ます
ような活動であるように思う。
時代の最先端。
これからは「感じる」時代なのだ、きっと。
もしかしたら、暗やみ本屋ハックツも、
そんな場所なのかもしれない。
そんな陸奥さんに、
偶然と必然のあいだってなんていうんですか?
って聞いてみたら、
逢着(ほうちゃく)っていう言葉が返ってきた。
逢着(ほうちゃく)
[名](スル)出あうこと。出くわすこと。行きあたること。「難問に―する」
(コトバンクより)
なるほど。
意図しているのか意図していないのか、
のぎりぎりのところで出会うこと。
アクシデントではなく、
予定通りでもなく、逢着する。
同じ出来事が人によって、
偶然とも必然ともとれるのだけど、
そうそう。
それって逢着なんだね。
そういうのに出会える場所のことを
第3の場所と呼ぶのかもしれないなと思った。
僕がツルハシブックスを
「偶然」が起こる「本屋のような劇場」と名乗っていたのは、
おそらくは、その「逢着」を生みたかったのだ。
少しだけ意図しているけど、
たまたま出会う何か。
それを感じ取る感性。
それが本屋さんであるということなのかもしれない。
本屋さんが第3の場所であることなのかもしれない。
場としての緊張感、一期一会が
必要なのかもしれない。
偶然と必然のあいだ。
そこに、ひとりひとりの感性を発動させ、
つかみとり、そこから未来が始まっていくのだ、きっと。
「偶然」という名のアートプロジェクトだった。
そしてそれは、
「居場所」になることによって、
急速に「偶然」機能を失っていく。
「居場所」は日常であるからだ。
そして「常連」は、コミュニティであるからだ。
昨日は千林商店街を
陸奥賢さんと一緒に歩いた。




寄贈本読書会の中で、
陸奥さんが放つ一言一言にちょっとドキドキした。
かつて、わが国には「歌垣」というものがあり、
そこで、男女が歌を歌いあって、求愛したという。
歌垣は、世間から離れた場であり、
そこでは、人は、この世のものではなくなった。
匿名性のある人になり、
歌を歌いあい、愛を求めた。
そんな歌垣を現代に復活させる
「歌垣風呂」という活動を陸奥さんは行っている。
銭湯で男女が
男湯女湯に分かれて歌を歌いあう。
そのフィーリングで、カップルが成立するという
「感性合コン」だ。
顔が見えない相手を、
声と雰囲気で判断し、この人よさそうだな、と決める。
そんな企画。
ああ。
もう一度、「考える」から「感じる」への
シフトが始まっているんだなと。
いや、そもそも、現在のお見合いのシステムのように、
年収いくらとか職業はなにか、とか年齢条件とか、
そんな言語化できる情報で、結婚相手を決めるなんて、
そんな「効率的」な方法で本当にいいのだろうか?
それって、この150年の「近代国民国家」、
つまり、「富国強兵」的な、効率を重視した
システムの中だけの常識なんじゃないか。
もっと人は、感性を発動させていいと思う。
いや、そのほうが圧倒的に自然というか、普通だろうと思う。
陸奥さんのやっている活動は、
「歌垣風呂」だけでなく、
「まわしよみ新聞」にしても、
「直観読みブックマーカー」にしても、
「偶然」と「必然」のあいだ
を行き来しているように思う。
そして人間の持つ「感性」をより研ぎ澄ます
ような活動であるように思う。
時代の最先端。
これからは「感じる」時代なのだ、きっと。
もしかしたら、暗やみ本屋ハックツも、
そんな場所なのかもしれない。
そんな陸奥さんに、
偶然と必然のあいだってなんていうんですか?
って聞いてみたら、
逢着(ほうちゃく)っていう言葉が返ってきた。
逢着(ほうちゃく)
[名](スル)出あうこと。出くわすこと。行きあたること。「難問に―する」
(コトバンクより)
なるほど。
意図しているのか意図していないのか、
のぎりぎりのところで出会うこと。
アクシデントではなく、
予定通りでもなく、逢着する。
同じ出来事が人によって、
偶然とも必然ともとれるのだけど、
そうそう。
それって逢着なんだね。
そういうのに出会える場所のことを
第3の場所と呼ぶのかもしれないなと思った。
僕がツルハシブックスを
「偶然」が起こる「本屋のような劇場」と名乗っていたのは、
おそらくは、その「逢着」を生みたかったのだ。
少しだけ意図しているけど、
たまたま出会う何か。
それを感じ取る感性。
それが本屋さんであるということなのかもしれない。
本屋さんが第3の場所であることなのかもしれない。
場としての緊張感、一期一会が
必要なのかもしれない。
偶然と必然のあいだ。
そこに、ひとりひとりの感性を発動させ、
つかみとり、そこから未来が始まっていくのだ、きっと。
2016年11月08日
「やりたいことは何か?」ではなく「顧客は誰か?」
問いって大事だ。
どんな問いを立てるかで人生は決まる。
その最初の問いが、
あまりにも一元化しているのではないか。
「やりたいことは何か?」
多くの人が人生をここから入ってしまう。
それは、学校教育や家庭での、
「将来、何になりたいんだ?」という問いかけと
「13歳のハローワーク」や、
マスコミによる「ひとつのことをやり続けることがカッコイイ」
的な価値観によって、半ば脅迫のように機能している。
中学生のときにぼんやりと「おれ、なにやりたいんだろ?」と問いが始まり、
ひとまず先延ばしにして受験勉強頑張って、
大学生になって、もやもやしながら3年間をすごし、
いざ、就職活動になって、たまたまツルハシブックスに来て、
「やりたいことがわからないんです」
と悩みを打ち明ける。
それ、たぶん、問いが違うんです。
出発点が違うんです。
「13歳のハローワークの呪い」
http://hero.niiblo.jp/e482630.html
(2016.11.1 20代の宿題)
に紹介したように、
職業は、ごくシンプルに、人間社会の役割分担の結果として、
社会の必要を満たすためにそこにあるものだ。
ゴミを拾うのが大好きな人間がいるからゴミが生まれているのではない。
ゴミ愛好家のために廃品回収業という職業が考案されたわけでもない。
それなんだよね。
そんなことをぼんやりと考えながら昨夜、本屋さんで見つけた本。
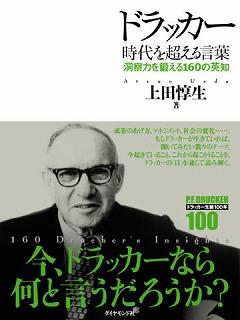
「ドラッカー 時代を超える言葉ー洞察力を鍛える160の英知」(上田惇夫 ダイヤモンド社)
53番目。
いつも引用しているドラッカーの5つの質問。
1 われわれのミッションは何か
2 われわれの顧客は誰か
3 顧客にとっての価値は何か
4 われわれにとって成果は何か
5 われわれの計画は何か
ツルハシブックスサムライ合宿で確認している
5つの質問。
そして54番目
「事業を決めるのはあなたではない」
事業が何かを決めるのは顧客である。
社名や定款ではない。
顧客が満足する欲求が事業を決める。
事業の目的は顧客の創造である。
さらに57番目
「事業が何かを知る第一歩が、顧客は誰かを考えることである。
次に、顧客はどこにいるか、顧客はいかに買うか、
顧客はいかに到達するかを考えることである。」
ドラッカーは「経営の神様」と呼ばれたが、
先行きの不透明なこの時代においては、
誰もが「自らの人生を経営する」という気持ちを
持つ必要がある。
つまり、キャリア=仕事を考える上で、
ドラッカーの経営の視点というのは、
非常に有意義であると言えるだろう。
ここで冒頭の問いに戻る。
「やりたいことは何か?」
という問いは、事業を立案するうえで、
重要な問いではない。
事業を決定するのは顧客であるからだ。
ツルハシブックスにとって、顧客とは、
人生に悩む中学生高校生大学生だった。
それを「本屋のような劇場」を通して、
「きっかけ」を提供していくこと。
そんなことを目指していた。
2002年、27歳の時に、
不登校の中学3年生の家庭教師をして、
僕は「顧客」に出会った。
まったく話をしてくれなかった彼が、
だんだんと笑顔になり、話をするようになった。
中学生には、「地域の多様な大人」が
必要なのだと思った。
10年の時が過ぎ、
2011年にツルハシブックスが開業。
7月には地下古本コーナー「HAKKUTSU」が誕生。
地域の大人と中高生をつなぐ方法を手に入れた。
そして実際に中高生や悩める大学生・20代の若者が
集まってきた。
そして、その次の問いに進む。
「顧客にとっての価値は何か?」
そうして、気がついたことがある。
ツルハシブックスというか、僕自身の提供価値は、
「共に悩む」なのではないかと。
「共に悩む」という提供価値
http://hero.niiblo.jp/e475287.html
(2015.12.13 20代の宿題)
その場を提供するのに、
「本屋」という空間が最適なのではないかと感じた。
もちろん、結果論なのだけれども。
そして、偶然にも、「本の処方箋」というツールを手に入れた。
それによって、お客さんの心が開き、
悩みを話してくれることを知った。
そして、その「空間」が保てなくなったからこそ、
ツルハシブックスは閉店したのではないだろうか。
大学時代、誰もが
「自分の仕事探しの旅」に出る。
その出発点で問うべきは、
「やりたいことは何か?」ではなくて、
「顧客は誰か?」だ。
そして、その仮説としての顧客に対して、
サービス提供を行い、
「顧客にとっての価値」を考え続ける。
そうやって、自らの人生を経営し始めるのではないか。
僕が伝えたいのは、きっとそういうこと。
どんな問いを立てるかで人生は決まる。
その最初の問いが、
あまりにも一元化しているのではないか。
「やりたいことは何か?」
多くの人が人生をここから入ってしまう。
それは、学校教育や家庭での、
「将来、何になりたいんだ?」という問いかけと
「13歳のハローワーク」や、
マスコミによる「ひとつのことをやり続けることがカッコイイ」
的な価値観によって、半ば脅迫のように機能している。
中学生のときにぼんやりと「おれ、なにやりたいんだろ?」と問いが始まり、
ひとまず先延ばしにして受験勉強頑張って、
大学生になって、もやもやしながら3年間をすごし、
いざ、就職活動になって、たまたまツルハシブックスに来て、
「やりたいことがわからないんです」
と悩みを打ち明ける。
それ、たぶん、問いが違うんです。
出発点が違うんです。
「13歳のハローワークの呪い」
http://hero.niiblo.jp/e482630.html
(2016.11.1 20代の宿題)
に紹介したように、
職業は、ごくシンプルに、人間社会の役割分担の結果として、
社会の必要を満たすためにそこにあるものだ。
ゴミを拾うのが大好きな人間がいるからゴミが生まれているのではない。
ゴミ愛好家のために廃品回収業という職業が考案されたわけでもない。
それなんだよね。
そんなことをぼんやりと考えながら昨夜、本屋さんで見つけた本。
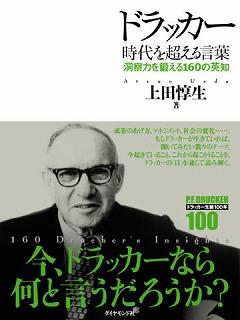
「ドラッカー 時代を超える言葉ー洞察力を鍛える160の英知」(上田惇夫 ダイヤモンド社)
53番目。
いつも引用しているドラッカーの5つの質問。
1 われわれのミッションは何か
2 われわれの顧客は誰か
3 顧客にとっての価値は何か
4 われわれにとって成果は何か
5 われわれの計画は何か
ツルハシブックスサムライ合宿で確認している
5つの質問。
そして54番目
「事業を決めるのはあなたではない」
事業が何かを決めるのは顧客である。
社名や定款ではない。
顧客が満足する欲求が事業を決める。
事業の目的は顧客の創造である。
さらに57番目
「事業が何かを知る第一歩が、顧客は誰かを考えることである。
次に、顧客はどこにいるか、顧客はいかに買うか、
顧客はいかに到達するかを考えることである。」
ドラッカーは「経営の神様」と呼ばれたが、
先行きの不透明なこの時代においては、
誰もが「自らの人生を経営する」という気持ちを
持つ必要がある。
つまり、キャリア=仕事を考える上で、
ドラッカーの経営の視点というのは、
非常に有意義であると言えるだろう。
ここで冒頭の問いに戻る。
「やりたいことは何か?」
という問いは、事業を立案するうえで、
重要な問いではない。
事業を決定するのは顧客であるからだ。
ツルハシブックスにとって、顧客とは、
人生に悩む中学生高校生大学生だった。
それを「本屋のような劇場」を通して、
「きっかけ」を提供していくこと。
そんなことを目指していた。
2002年、27歳の時に、
不登校の中学3年生の家庭教師をして、
僕は「顧客」に出会った。
まったく話をしてくれなかった彼が、
だんだんと笑顔になり、話をするようになった。
中学生には、「地域の多様な大人」が
必要なのだと思った。
10年の時が過ぎ、
2011年にツルハシブックスが開業。
7月には地下古本コーナー「HAKKUTSU」が誕生。
地域の大人と中高生をつなぐ方法を手に入れた。
そして実際に中高生や悩める大学生・20代の若者が
集まってきた。
そして、その次の問いに進む。
「顧客にとっての価値は何か?」
そうして、気がついたことがある。
ツルハシブックスというか、僕自身の提供価値は、
「共に悩む」なのではないかと。
「共に悩む」という提供価値
http://hero.niiblo.jp/e475287.html
(2015.12.13 20代の宿題)
その場を提供するのに、
「本屋」という空間が最適なのではないかと感じた。
もちろん、結果論なのだけれども。
そして、偶然にも、「本の処方箋」というツールを手に入れた。
それによって、お客さんの心が開き、
悩みを話してくれることを知った。
そして、その「空間」が保てなくなったからこそ、
ツルハシブックスは閉店したのではないだろうか。
大学時代、誰もが
「自分の仕事探しの旅」に出る。
その出発点で問うべきは、
「やりたいことは何か?」ではなくて、
「顧客は誰か?」だ。
そして、その仮説としての顧客に対して、
サービス提供を行い、
「顧客にとっての価値」を考え続ける。
そうやって、自らの人生を経営し始めるのではないか。
僕が伝えたいのは、きっとそういうこと。





