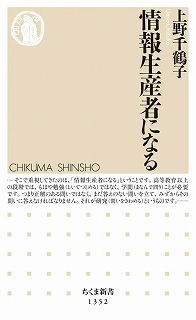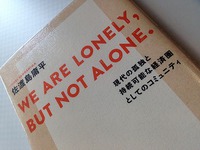2018年10月29日
「余白」とは、境界をあいまいにして「委ねる」こと
余白おじさん。
昨年「新城劇場」(現在はリニューアルオープンしてブックカフェになってます)
のオープンの時に
webマガジン「温度」の碇さんにつけられたニックネーム。
http://ondo-books.com/bookstore-report/188
当時はおじさんを認めたくなくて(笑)、
「余白デザイナー」と名乗っていたりするのだけど。
あらためて
「余白」について考えてみる。
場にも、仕事にも、組織にも、人生にも、「余白」が必要だと思う。
世の中が閉鎖系から開放系へと進んでいる。
閉鎖系で機能したフレームワークが
どんどん通用しなくなっていく。
「余白」をデザインするとは、
「境界」をあいまいにすること、だと思う。
それが「心地よさ」や「ワクワク」を生むのではないかという仮説。
気がついたら私も本屋という舞台の共演者になっていました。
これがツルハシブックスのキャッチコピーだったのだけど。
それは、店員とお客の境界を溶かしていくことだと思った。
そこに立っている人が店員なのか、お客なのか、
あいまいな状態にすることで
自分自身もあいまいな状態になる。
そこで共演者になれるのだと思う。
それが場の余白ではないか。
仕事の余白は、目標以外の成果を意識すること。
インターンシップの余白は、目標を設定しすぎないこと。
にいがたイナカレッジのプログラムのように、
参加者が地域の人と触れあう中で、
ゴールを再設計、設定すること。
それは、言葉にすれば「委ねる」ということ。
未知なるものに委ねる。
そして、ふりかえること。
きっとそういうこと。
僕自身は現代美術家として、
「リレーショナルアート」領域を創造していくのだけど、
それって、余白をつくること。
つまり、
境界をあいまいにして、委ねること、なのかもしれない。
場にも、仕事にも、組織にも、人生にも、
ワークショップにも、「余白」が必要だって
そういうことなのではないかな。

写真は南魚沼・ヤミーのかぐらなんばんジェラート
めちゃめちゃ辛いです。
アイスの余白に作っちゃってますね。(笑)
昨年「新城劇場」(現在はリニューアルオープンしてブックカフェになってます)
のオープンの時に
webマガジン「温度」の碇さんにつけられたニックネーム。
http://ondo-books.com/bookstore-report/188
当時はおじさんを認めたくなくて(笑)、
「余白デザイナー」と名乗っていたりするのだけど。
あらためて
「余白」について考えてみる。
場にも、仕事にも、組織にも、人生にも、「余白」が必要だと思う。
世の中が閉鎖系から開放系へと進んでいる。
閉鎖系で機能したフレームワークが
どんどん通用しなくなっていく。
「余白」をデザインするとは、
「境界」をあいまいにすること、だと思う。
それが「心地よさ」や「ワクワク」を生むのではないかという仮説。
気がついたら私も本屋という舞台の共演者になっていました。
これがツルハシブックスのキャッチコピーだったのだけど。
それは、店員とお客の境界を溶かしていくことだと思った。
そこに立っている人が店員なのか、お客なのか、
あいまいな状態にすることで
自分自身もあいまいな状態になる。
そこで共演者になれるのだと思う。
それが場の余白ではないか。
仕事の余白は、目標以外の成果を意識すること。
インターンシップの余白は、目標を設定しすぎないこと。
にいがたイナカレッジのプログラムのように、
参加者が地域の人と触れあう中で、
ゴールを再設計、設定すること。
それは、言葉にすれば「委ねる」ということ。
未知なるものに委ねる。
そして、ふりかえること。
きっとそういうこと。
僕自身は現代美術家として、
「リレーショナルアート」領域を創造していくのだけど、
それって、余白をつくること。
つまり、
境界をあいまいにして、委ねること、なのかもしれない。
場にも、仕事にも、組織にも、人生にも、
ワークショップにも、「余白」が必要だって
そういうことなのではないかな。

写真は南魚沼・ヤミーのかぐらなんばんジェラート
めちゃめちゃ辛いです。
アイスの余白に作っちゃってますね。(笑)
Posted by ニシダタクジ at 06:52│Comments(0)
│言葉
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。