2021年07月30日
「できるかも」「やってみようか」のつくり方

昨日は阿賀黎明探究パートナーズの「地域学」中間振り返りでした。
リアルな現場があることの良さは、「実現可能性」をリアルに感じられること、かなと思った。机上で「できる、できない」をやると、自信のない生徒、成功体験のない生徒は、どうしても「できない」という結論になってしまうけど、
昨日のまちづくりチームや、観光チームの話を聞いていると「いろんな方法がある」ということをリアルに体感したり、それをやってきた大人に接することで、「それくらいだったら、できるかも」が生まれていく。それって、最初の1歩なのかもしれないなと。
まず、「やりたい」という意志があるのではなく、「できるかも」「やってみようか」という感覚があるのかもしれない。
そもそも僕は、意志という神話を信じてはいないのだけども・・・
参考:「手段」としての学びから「機会」としての学びへ(19.7.6)
http://hero.niiblo.jp/e489527.html
地域学というほぼ必修の授業で(半ば強制的に)、地域のおもしろい(わけのわからない)オッサンに出会い。リアルな現場を目の前にして、「いやいや無理でしょ」が「できるかも」「やってみようか」に変わっていくこと。そこから始まっていくものがあるのではないか、って思う。
「マイプロ以前」みたいなやつ。
そこが大切なのかもしれないなと。
今日から読み始めた本
「本物をまなぶ学校」(自由学園 婦人之友社)

「自由学園」って聞いてはいたけど、実態を知らず。
いきなり冒頭からシビれております。
~~~
自由学園の「自由」とは、自然界の制約からの「自由」でも、家族やコミュニティからの「自由」でもない。過去からの「自由」でも、社会からの「自由」でもない。そして、生活と教育を切断し、頭と体と魂を切り離し、過去を切り捨てる、いわゆる自由主義者の「自由」でもない。逆にそれは、教育と生活との、頭と体と魂との、過去と未来との、個人と社会との調和を志し、それを実際に学校という場で、試し、つくりだす自由だ。
この学校の創立者たちはこう考えていたという。学校は今ある社会の模倣ではない。そこに人材を送り込むためのものでもない。学校は今ない社会をつくる人たちを育てるのだ、と。
~~~
いいですね。
「自由」ってなんだっけ?
という問いがまず投げ込まれます。
そして第2章「自分で考える、生活に学ぶ」に続いていきます。
~~~
学校は、置き換え可能な人材をつくり出す場ではなく、一人ひとりを大切にし、新しい社会へのビジョンを持った人が育つ場でありたいという信念です。ですから学校は、今の社会を模倣していてはダメなんです。今は教育現場にグローバルな競争に打ち勝つ人材育成が求められていますが、この学校は人材育成ではなく、どんな時代どんな社会にあっても、自分の人生を自分らしく歩み、そしてよい社会とは何かと自分の頭で考え、それをつくっていく人が育つことを願っています。
~~~
これですね。そうそう。
学校が「人材」を育成しているから、ますます生徒は「自信」と「存在」を失っていくのだろうと。
承認を求め、勉強を頑張り、資格を取り、技術を磨いた結果、「交換可能な人材(グローバル人材とはそういうことだ)」になってしまい、ますます承認不安(特に存在承認不安)に陥るというジレンマ。
生活の中にある、小さな「場」。
そこには、何百年と続いてきた「営み」がある。リアルな「暮らし」がある。
「いやいや無理でしょ」から大人を含めた周りの環境によって「できるかも」「やってみようか」が生まれる。
そこから始まるのではないか、と思う。
昨日の中間振り返りで福祉チームが話していた。「若い人が来ることでお年寄りたちは孫ができたみたいですごく喜んでいる。料理の話とかをしていた。今後生徒たちをどうやって活かしていくか?が私たちの課題」
そうなんですよね。チームとして、場として、どうしていくか。だからこそ、昨日の振り返りでも
「15分前に帰ってきて、全体で振り返りを行い、大人達も振り返りに(プレイヤーとして)参加する」
「その際に、自分たちの授業目標である問いを発して、生徒のリアクションを見る」
という2つが改善策として出てきました。
活動が学びにつながるように、振り返りをすること。それは高校生だけではなく、大人も一緒だということ。共に見つけ合うこと。たぶんそうやって場をつくっていくことなのだろうなと思った。
ということで、
そんな地域の大人たちがともに学ぶ授業がある阿賀黎明高校の現地説明会は8月21日(土)22日(日)です。
21日(土)は新潟駅MOYORe:で、参加型のワークショップで新しいまなびの場を構想します。
https://www.agareimei.com/posts/19611879?categoryIds=477469


22日(日)は現地見学会です。
申し込み・問い合わせはこちらから。
https://www.agareimei.com/posts/19710284?categoryIds=477469
明日7月31日8月1日は「地域みらい留学」合同オンライン説明会です。
https://c-mirai.jp/
こちらでもお待ちしています。
2021年07月28日
「オレンジ星人」を作ってはいないか?
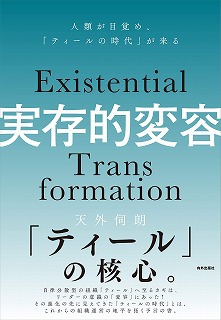
「実存的変容」(天外伺朗 内外出版社)
キーワードに惹かれて購入しました。
ティール組織(フレデリック・ラルー 英知出版)
の組織の変遷(進化)に合わせて、人はどのように変容していくか、
というのが書いてあります。
ちなみにティールに至る道は
1 レッド(衝動型)
2 アンバー(順応型)
3 オレンジ(達成型)
4 グリーン(多元型)
5 ティール(進化型)
ということでティールは青緑色なんです。
「実存的変容」を読んでいて一番ヒットしたのは「オレンジ星人」でした。(P132)
1 善良で立派な社会人、親切な隣人、良き家庭人を装うことができる
2 責任感があり、勤勉でよく働く
3 人間集団の中で、適切な立ち位置を見出し、チームワークよく仕事を遂行できる
・・・とまあ25項目あるんですけど。(長い)
つまり、オレンジな組織に適応するために
ひとりひとりが「オレンジ星人」として養成されているということです。
本書では、意識レベルの上に上がってくる下のレベルにはモンスターが住んでいて、それを抑圧して、ペルソナ(仮の自分)を作り上げていると説明されています。
~「実存的変容」というのは、モンスターの支配から逃れて自分の人生を取り戻すことです。~
と本書にはあるのですが、「変容」という言葉にビビっときます。
いちばん面白かったのは、ココ。
成長のための方法論である「目標をしっかり持ち、それに向かって努力する」は「意識の変容」にはまったく役に立たない。
まさに学校は、オレンジ星人をつくっているんじゃないか?
それは適応であって、価値ではないのではないか。
そんな風に感じています。
2021年07月23日
「存在」と「創造」
来週31日のオンラインツルハシ打ち合わせ。
デンマークのフォルケホイスコーレに留学中のミクさんと話をしていた。
問い(ベクトル)が近い人と話をするのは楽しい。
タイトルは、
その人自身に出会える仕組みとしての「福祉」
~海を見せる学び舎フォルケホイスコーレより
かな。
僕としては高校や寮運営にも通じるなと思って聞いてました。
・「先生」と「生徒」のようなロール(役割)がない。
・対話することで決めていく。
・プレゼンス(存在)とトゥギャザネス(一緒にいること)
・人間中心主義としての福祉:その人自身に出会える仕組みづくり
・ルールはなくて哲学がある
・海を見せる。船は自分で作ってね。
みたいなメモ。
来週31日をお楽しみに。
そうそう。
ロール(役割)ね。
生徒と先生。
高校生とサポーター。
そのロールとして人は人に接してしまう。
ロールは人を数字、統計データにしてしまう。
昨日、違和感があったのは「成長」という言葉だ。
VUCAの時代に「成長」なんてあり得るのだろうか?なんてことを考えてしまう。
高校生に対して、「成長した」という評価をすることは、世の中が(または共同体が)確実にそちらのほうに向かっていて、そこに役に立つ人材になった。という意味になると思う。
できないことができるようになる。
それは「成長」ではなくて「変化」にすぎない。
昨日の夜は「進化思考」の読書会的集まりだったのだけど。

その前に本を読み直していて、思ったこと。
~~~
自分は生きていてもいいんだという「存在の承認」を家族ではなくて「場」が代替できないか?という問いに挑んできたのかも。その「場」は「進化思考」的に言えば創造の場で、変異(多様性、一回性)と適応(営み、長期的)の真ん中にあるもの、なのかもしれない。「創造」と「営み」の交点に存在が生まれる。
わたしたちは進化し続けている。環境が変わり続けているとしたら「成長」などあり得ない。そこには「変化」があり、それが「進化」であったことを事後的に知るのだ。その過程に立っているとしたら、僕たちはみな1年生であり、今日が残りの人生の最初の日であり、これまでの人生の最後の日なのだ。
~~~
「成長」(進化)とは、事後的にわかるものであり、現時点では「変化」にすぎない。
簡単に「成長した」という評価をすることで、高校生は「行為の承認」を得てしまうのではないか。
その前に「存在の承認」が必要なのではないか。
「福祉」とは、その人自身に出会える仕組みづくりだとミクさんは言った。
まずはどこまでもその人を知ること。過去だけではなく、今どう感じているか?を知ること。知りたいと思うこと。
「存在の承認」が得られる「場」をつくること。それはロール(役割)から解放され、その人自身を見ることであり、弱さも貴重なひとつの変異として、創造する場の一員としてそこにあること、なのかもしれない。
「存在」と「創造」。そんな場をつくりたい。
デンマークのフォルケホイスコーレに留学中のミクさんと話をしていた。
問い(ベクトル)が近い人と話をするのは楽しい。
タイトルは、
その人自身に出会える仕組みとしての「福祉」
~海を見せる学び舎フォルケホイスコーレより
かな。
僕としては高校や寮運営にも通じるなと思って聞いてました。
・「先生」と「生徒」のようなロール(役割)がない。
・対話することで決めていく。
・プレゼンス(存在)とトゥギャザネス(一緒にいること)
・人間中心主義としての福祉:その人自身に出会える仕組みづくり
・ルールはなくて哲学がある
・海を見せる。船は自分で作ってね。
みたいなメモ。
来週31日をお楽しみに。
そうそう。
ロール(役割)ね。
生徒と先生。
高校生とサポーター。
そのロールとして人は人に接してしまう。
ロールは人を数字、統計データにしてしまう。
昨日、違和感があったのは「成長」という言葉だ。
VUCAの時代に「成長」なんてあり得るのだろうか?なんてことを考えてしまう。
高校生に対して、「成長した」という評価をすることは、世の中が(または共同体が)確実にそちらのほうに向かっていて、そこに役に立つ人材になった。という意味になると思う。
できないことができるようになる。
それは「成長」ではなくて「変化」にすぎない。
昨日の夜は「進化思考」の読書会的集まりだったのだけど。

その前に本を読み直していて、思ったこと。
~~~
自分は生きていてもいいんだという「存在の承認」を家族ではなくて「場」が代替できないか?という問いに挑んできたのかも。その「場」は「進化思考」的に言えば創造の場で、変異(多様性、一回性)と適応(営み、長期的)の真ん中にあるもの、なのかもしれない。「創造」と「営み」の交点に存在が生まれる。
わたしたちは進化し続けている。環境が変わり続けているとしたら「成長」などあり得ない。そこには「変化」があり、それが「進化」であったことを事後的に知るのだ。その過程に立っているとしたら、僕たちはみな1年生であり、今日が残りの人生の最初の日であり、これまでの人生の最後の日なのだ。
~~~
「成長」(進化)とは、事後的にわかるものであり、現時点では「変化」にすぎない。
簡単に「成長した」という評価をすることで、高校生は「行為の承認」を得てしまうのではないか。
その前に「存在の承認」が必要なのではないか。
「福祉」とは、その人自身に出会える仕組みづくりだとミクさんは言った。
まずはどこまでもその人を知ること。過去だけではなく、今どう感じているか?を知ること。知りたいと思うこと。
「存在の承認」が得られる「場」をつくること。それはロール(役割)から解放され、その人自身を見ることであり、弱さも貴重なひとつの変異として、創造する場の一員としてそこにあること、なのかもしれない。
「存在」と「創造」。そんな場をつくりたい。
2021年07月22日
LOVE&FREE
2001年。
サンクチュアリ出版の営業デビューしたときに
最初に営業した本。
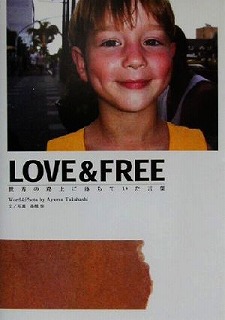
「LOVE&FREE」(高橋歩 サンクチュアリ出版)
新潟市内の本屋をくまなく回って、
「はじめまして、サンクチュアリ出版です。新刊のご案内に・・・」みたいな。
「え?紀行文?旅エッセイ?ウチそういうの弱いんだよね~。じゃあ棚イチで。新刊なら3冊で平台おいてもいいけど。」みたいな。
「平台お願いしまーす」みたいな。
結果、この本が順調に版を重ねることで、僕は出版社の営業として本屋さんに話を聞いてもらえるようになった。
ちなみにこの本は名言が詰まっていて、ラストはドキドキしてページをめくる手が止まらなくなります。
先日紹介した「夢があろうとなかろうと楽しく生きてる奴が最強」も、祭りの写真とともに納められています。今でも震えるなあ。
という前振りで。
本日は、NHK100分で名著「善の研究 西田幾多郎」(解説 若松英輔)

「善の研究」は難解であると言われていて、まだ読めてないのですが、
こういう入門編があるといいですよね。
なんとびっくり若松さんは最終章である「知と愛」から読んでいけ、と言います。
~~~
知と愛とは普通には全然相異なった精神作用であると考えられて居る。しかし余はこの二つの精神作用は決して別種の者ではなく、本来同一の精神作用であると考える。しからば如何なる精神作用であるか、一言にて言えば主客合一の作用である。我が物に一致する作用である。(第四編 宗教 第五章 知と愛)
「知る」と「愛する」という営みは一見すると二つの異なる認識の方法のように映る。しかし、そうではない、と西田はいいます。それらは「主客合一の作用」、すなわち自分と対象が一つになろうとするとき、共に動き始めるものだと考えています。
普通の知とは非人格的対象の知識である。たとい対象が人格的であっても、これを非人格的として見た時の知識である。これに反し、愛とは人格的対象の知識である、たとい対象が非人格的であってもこれを人格的として見た時の知識である。(同前)
ここでの「人格的対象」は、「生けるもの」と置き換えることができます。「非人格的対象」は「止まっているもの」ということになります。私たちは「生けるもの」を生きた存在として感じるとき、内なる愛をもってそれに接する。だが、愛が失われた目で世界を見るとき、「生けるもの」は生命なきもの、すなわち「止まっているもの」であるかのように映る、というのです。
また我々が他人の杞憂に対して、全く自他の区別がなく、他人の感ずる所を直に自己に感じ、共に笑い共に泣く、この時我は他人を愛しまたこれを知りつつあるのである。(同前)
「知と愛」は西田にとって同じもので、二つは別な側面を持っているだけなのです。それを近代人は分けて考えてしまっていた。私たちは「知と愛」をもう一度、一緒にしなければならない。さらに、それを一つにすることによって見えてくるものを世に告げることが哲学の役割だというのです。
西田にとって「愛」とは生けるものの本質を掴むちからです。花の中には生けるもの、いのちがある。それを感じたときに私たちは花を愛し、そして花に愛されていると感じる。花に愛されるというのは、花との交わりが生まれるということです。
~~~
なるほど。「知」と「愛」ですね。
「主客合一」とか「主客未分」は僕も好きな概念です。
「私」を外すという美学(17.3.28)
http://hero.niiblo.jp/e484378.html
ここに書いた西田の言葉。
「主客があるかのように思うのは、私たちの思い込みにすぎない。実は主客未分のほうが本来の姿であり、純粋な経験である。経験の大もとを純粋な経験だとすると、純粋経験は主客未分でおこっているはずだ。本質を捉えようとするならば、私というものを前提として考えるのではなく、むしろ主客を分けることができない純粋経験こそを追求するべきだと考えたのです。」
これ「中動態の世界」にも通じていくなあと思ってます。
愛とは、分けないこと、そして感じること、なのかもしれません。
そして「個」と「善」についての記述に移ります。
~~~
近代では、「個」が尊重され、「私」が「私」の人生を「私流」に生きることがよしとされました。それ以前はさまざまなところで「個」が束縛され、大きな不自由を強制されていたのです。国、宗教、共同体などが「個」であろうとすることを阻害していました。
「個」の自由、これは社会的な出来事としては、大変重要な、文字通り革命的な出来事でした。しかし、「個」で生きることに慣れた私たちは、他者とのつながりを忘れがちになっていることも否めません。
社会生活における「個」と、他者と共にある「個」は両立し得ます。この二つの「個」がともに開花することが、西田のいう「善」なのです。
~~~
これ、「LOVE&FREE」に書いてあることじゃないかって。
高橋歩さんは、「LOVE OR FREEじゃない。LOVE&FREEなんだ」と言った。
社会生活における「個」と他者と共にある「個」は両立できる。
まさに「愛」と「自由」は両立できるのだと西田幾多郎は言うのです。
たぶんこういう感覚が高校生たちにとって必要なのだろうと思う。
サンクチュアリ出版の営業デビューしたときに
最初に営業した本。
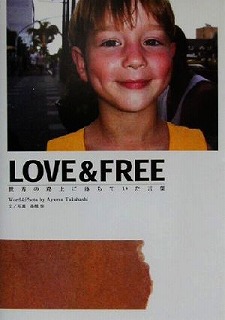
「LOVE&FREE」(高橋歩 サンクチュアリ出版)
新潟市内の本屋をくまなく回って、
「はじめまして、サンクチュアリ出版です。新刊のご案内に・・・」みたいな。
「え?紀行文?旅エッセイ?ウチそういうの弱いんだよね~。じゃあ棚イチで。新刊なら3冊で平台おいてもいいけど。」みたいな。
「平台お願いしまーす」みたいな。
結果、この本が順調に版を重ねることで、僕は出版社の営業として本屋さんに話を聞いてもらえるようになった。
ちなみにこの本は名言が詰まっていて、ラストはドキドキしてページをめくる手が止まらなくなります。
先日紹介した「夢があろうとなかろうと楽しく生きてる奴が最強」も、祭りの写真とともに納められています。今でも震えるなあ。
という前振りで。
本日は、NHK100分で名著「善の研究 西田幾多郎」(解説 若松英輔)

「善の研究」は難解であると言われていて、まだ読めてないのですが、
こういう入門編があるといいですよね。
なんとびっくり若松さんは最終章である「知と愛」から読んでいけ、と言います。
~~~
知と愛とは普通には全然相異なった精神作用であると考えられて居る。しかし余はこの二つの精神作用は決して別種の者ではなく、本来同一の精神作用であると考える。しからば如何なる精神作用であるか、一言にて言えば主客合一の作用である。我が物に一致する作用である。(第四編 宗教 第五章 知と愛)
「知る」と「愛する」という営みは一見すると二つの異なる認識の方法のように映る。しかし、そうではない、と西田はいいます。それらは「主客合一の作用」、すなわち自分と対象が一つになろうとするとき、共に動き始めるものだと考えています。
普通の知とは非人格的対象の知識である。たとい対象が人格的であっても、これを非人格的として見た時の知識である。これに反し、愛とは人格的対象の知識である、たとい対象が非人格的であってもこれを人格的として見た時の知識である。(同前)
ここでの「人格的対象」は、「生けるもの」と置き換えることができます。「非人格的対象」は「止まっているもの」ということになります。私たちは「生けるもの」を生きた存在として感じるとき、内なる愛をもってそれに接する。だが、愛が失われた目で世界を見るとき、「生けるもの」は生命なきもの、すなわち「止まっているもの」であるかのように映る、というのです。
また我々が他人の杞憂に対して、全く自他の区別がなく、他人の感ずる所を直に自己に感じ、共に笑い共に泣く、この時我は他人を愛しまたこれを知りつつあるのである。(同前)
「知と愛」は西田にとって同じもので、二つは別な側面を持っているだけなのです。それを近代人は分けて考えてしまっていた。私たちは「知と愛」をもう一度、一緒にしなければならない。さらに、それを一つにすることによって見えてくるものを世に告げることが哲学の役割だというのです。
西田にとって「愛」とは生けるものの本質を掴むちからです。花の中には生けるもの、いのちがある。それを感じたときに私たちは花を愛し、そして花に愛されていると感じる。花に愛されるというのは、花との交わりが生まれるということです。
~~~
なるほど。「知」と「愛」ですね。
「主客合一」とか「主客未分」は僕も好きな概念です。
「私」を外すという美学(17.3.28)
http://hero.niiblo.jp/e484378.html
ここに書いた西田の言葉。
「主客があるかのように思うのは、私たちの思い込みにすぎない。実は主客未分のほうが本来の姿であり、純粋な経験である。経験の大もとを純粋な経験だとすると、純粋経験は主客未分でおこっているはずだ。本質を捉えようとするならば、私というものを前提として考えるのではなく、むしろ主客を分けることができない純粋経験こそを追求するべきだと考えたのです。」
これ「中動態の世界」にも通じていくなあと思ってます。
愛とは、分けないこと、そして感じること、なのかもしれません。
そして「個」と「善」についての記述に移ります。
~~~
近代では、「個」が尊重され、「私」が「私」の人生を「私流」に生きることがよしとされました。それ以前はさまざまなところで「個」が束縛され、大きな不自由を強制されていたのです。国、宗教、共同体などが「個」であろうとすることを阻害していました。
「個」の自由、これは社会的な出来事としては、大変重要な、文字通り革命的な出来事でした。しかし、「個」で生きることに慣れた私たちは、他者とのつながりを忘れがちになっていることも否めません。
社会生活における「個」と、他者と共にある「個」は両立し得ます。この二つの「個」がともに開花することが、西田のいう「善」なのです。
~~~
これ、「LOVE&FREE」に書いてあることじゃないかって。
高橋歩さんは、「LOVE OR FREEじゃない。LOVE&FREEなんだ」と言った。
社会生活における「個」と他者と共にある「個」は両立できる。
まさに「愛」と「自由」は両立できるのだと西田幾多郎は言うのです。
たぶんこういう感覚が高校生たちにとって必要なのだろうと思う。
2021年07月19日
必要なのはゴールではなく、ベクトルそのもの
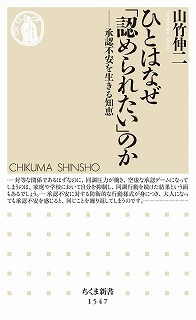
「ひとはなぜ認められたいのか」(山竹伸二 ちくま新書)
読みました。
「自由」と「承認」そして「アイデンティティ」。
そんなキーワードの人にオススメです。
特に「やりたいことがわからない」と深刻に悩んでいる人。
まずはその原因、
「やりたいことがわからない」はなぜこんなにも苦しいのか?
を探ってみませんか?
3年前に書いたのはこれ
「夢」や「目標」にアイデンティティを依存しないこと(18.9.25)
http://hero.niiblo.jp/e488165.html
若者のアイデンティティ不安は、「役割」の喪失から来るのではないか?という仮説。
「役割の喪失」は「承認の喪失」という見方もできる。
「ひとはなぜ認められたいか」には、歴史を振り返って、以下のような記述がある。
~~~
近代以前の価値観が一元化された世界では、その価値基準に沿った行動しか許されなかったため、自由に行動することはできませんでした。しかし、その価値観に合わせて行動していれば、周囲から認められ、自分の価値を見出すことができます。特に宗教的価値観の影響は大きく、ヨーロッパにおけるキリスト教、中東地域のイスラム教、インドのヒンズー教など、宗教は古代からその社会の行動の価値をはかる重要な基準だったのです。
しかし科学の発達とともに、こうした宗教的な価値観の絶対性はゆらぎ、それと同時に、人間は自由に生きる権利がある、という考え方が生まれました。啓蒙思想の広がりとともに、自由に生きられる権利が構想され、世界は徐々に「自由な社会」を理想とするようになったのです。
とはいえ、近代になっても最初は伝統的価値観が根強く残っていましたからその価値観に反する考え方、新しい生き方を示せば、社会から批判され、自分勝手な利己主義と見なされました。
「個人の自由」と「社会の承認」が対立し、自由と承認の葛藤に悩まされる人が増えていったのです。
やがて20世紀になると、科学技術の進歩、資本主義社会の発展、二度の世界大戦を経て、伝統的価値観は徐々に解体されていきます。
社会は個人の自由を大幅に認めはじめ、社会に対する抑圧感、社会との葛藤も薄れましたし、多くの場面で自由に行動できるようになったのも事実ですが、今度は承認の基準である社会の価値観が不透明になったので、どうすれば周囲に自分の価値を認めてもらえるか、それがわからなくなってしまったのです。
承認不安はアイデンティティの不安と密接に関係しています。
近代以前なら共通の社会規範・価値観によってアイデンティティも明確でしたが、そうした大きな価値観がなくなると、私たちは根無し草のようになり、自分が何者なのかを自分で探し求めなければなりません。しかも、自由な社会であるはずなのに、「自分らしく生きろ」とか「個性が大事だ」などと言われながら、独自のアイデンティティを見出す必要性に迫られています。
認められるための価値基準を失った人々は、強い承認不安に煽られ、身近な人々の言動に左右され、同調行動に駆られやすくなりました。しかしそのような行為は、とりあえず批判を免れ、かりそめの承認を維持することはできても、自分の存在価値に自信を持つことができません。
~~~
まさにこれ。私たちは、自由になったからこそ、承認される基準を失ったのです。
そしてこの傾向が強まるのが小学校高学年から中学生くらいの思春期であると言います。
そしてまさにこの時期に、学校(的)社会においては、いわゆるキャリア教育という名の何かが始まるのです。
プロフェッショナル的なビデオを見せられたりロールモデル的な大人の講演を聞いたりして、「やりたいことは何か?」「将来の夢(なりたい職業)は何か?」という問いを受けることで、「やりたいことがわからない」という苦しみを抱え、アイデンティティの不安に苛まれることになるのではないか、というのが僕の仮説です。
本書にも書かれているように、まず取り戻されなければいけないのは「存在の承認」(ありのままの自分を認めること、認められること)です。
~~~
「存在の承認」が保証されれば、私たちは自由に生きることができます。あるがままの自分が否定されないのですから、それも当然でしょう。だから、「存在の承認」は自由の承認でもあるのです。そこに自由と承認の葛藤はありません。自由と承認の葛藤は、自由と「行為の承認」との葛藤であり、自由な行為に対する価値評価が問題になるときにのみ顕在化するのです。
承認不安の増大は自由に行動することを不可能にします。理由は二つあって、ひとつは不安を避けることで心身ともに疲れはて、やりたいことができなくなるから。もうひとつは、承認不安は「自由に行動すれば人から認められないかもしれない」という不安でもあるからです。
自由に生きるためには、自分の「したい」ことを自覚し、それを遂行する力が必要なのですが、それは「自己了解ができる」ということでもあります。自己了解の力が形成されるには感情が受け入れられ、共感を得ることが必要です。
ロジャースは共感や自己一致をセラピーの中心に置き、カウンセラーやセラピストに必要な条件は、相談者を無条件に価値ある存在として配慮すること、相談者の感情に共感し、理解しようとすること、そして自分の感情を自覚し、言動が一致していることという三つの条件を示したのです。
~~~
「存在の承認」をどのようにつくっていくか。
これはすごく大きな課題なのだろうなあと。
あと、前半部分ですごく思ったのは、「やりたいことは何か?」という問いに対しての向き合い方が違うのではないかと。
「探究」とスピノザ哲学(20.12.2)にあるように
http://hero.niiblo.jp/e491214.html
人間の本質はカタチではなくコナトゥス(こうあろうとする力)であるとすれば。
本当に必要なのは、やりたいことやなりたい職業っていうゴールではなくて、
ベクトルそのものなのではないか、っていうこと。
ベクトルがあれば、人は生きられる。
そのベクトルをつくる方法論のひとつがゴール(目標)を持つことだとは思うけど、それは唯一の方法ではないのではないか、ということ。
言語化されない、心動かされる何かによって、生まれてくるベクトルもあるのではないか、って。
そのベクトルこそを必要としているのではないか。
そのためには、感性を発動させる環境に身を置くことだし、「存在の承認」を与えてくれる場、あるいは他者に囲まれていること、なのだろうね。
そんな「場」をつくりたいのですよ。
2021年07月18日
「自由」を取るか「承認」を取るか
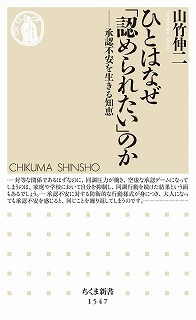
「ひとはなぜ認められたいのか」(山竹伸二 ちくま新書)
本屋「ツルハシブックス」時代(2013年ごろ)近くにあった新潟大学の学生の話を聞いていて、猛烈に印象に残った言葉。
「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」
本人たちにとっては、生きるか死ぬかに値するような大きな問い。
そして、その解決策を
「(自己を分析して)やりたいことが見つかること」「(小さな挑戦と成功により)自分に自信をつけること」
だと思っていること。
本当か?
って思った。
そもそも「やりたいことがわからない」ことが課題なのか?
「やりたいことがわからなくて苦しい」ことが本当の課題なのではないか?
サンクチュアリ出版を立ち上げた高橋歩は著書「LOVE&FREE」の中で言う。
「夢があろうとなかろうと楽しく生きてる奴が最強」だと。
ではなぜ、「やりたいことがわからない」はこんなにも苦しいのか?
その原因について知りたいと思った。(探究の入り口)
ひとつは、いわゆる「キャリア教育」の目標設定・達成型の仕組みが時代・社会に合っていないこと。
(これについては、他の記事でたくさん書いているので今回は触れない)
参考:http://hero.niiblo.jp/e273966.html (夢リテラシー 13.7.18)⇐8年前の今日ですね
もうひとつが、「承認(欲求)」だった。
参考:http://hero.niiblo.jp/e291471.html (承認欲求と他者評価 13.10.24)
この承認には3種類あるっていうのがヒントになって、たくさんの大学生にこの本を薦めた。
1 親和的承認
家族、恋人、親しい友人など、愛情と信頼の関係にある他者によって、「ありのままの自分」を無条件に受け入れてもらっていると感じられるような承認である。
2 集団的承認
集団が共有する価値観・ルールに基づいて行動することで集団にとって必要な存在となり、承認を得ることができる。
3 一般的承認
不特定多数の他者一般から認められること。例えば、災害ボランティアで現地に赴くというのは、なかなかできることではないから、一般的に、素晴らしいことだと思われる。そのような承認。
この本を読んでいて思い出したことがある。2004年の中越地震ボランティアだ。震度7の川口町で長期的に活動していたボランティアのひとりに聞いた。「こんなに仕事休んで大丈夫なんですか?」大丈夫だった。なぜなら仕事をしていなかった、いわゆる「ニート」状態だったからだ。そんな彼を駆動させていたのが被災者からもらう「ありがとう」だったのではないか。そこに「承認」があったのではないか、と改めて思った。
そして、2021年、待望の続編がこの本。
「ひとはなぜ認められたいのか?」
今回もより分かりやすく、時代・社会に合わせる形で(コロナ過の同調圧力とかも書いてあります)「承認」という課題について書いてあります。
まず最初に考えないといけないのは、「存在の承認」と「行為の承認」です。
上でいうところの1親和的承認:ありのままの自分を受け入れてくれることがまさに「存在の承認」です。役に立っているかどうかに関わらず、そこに存在しているだけで価値があるのです。
2集団的承認については、その集団にとって価値のある行為が承認の条件ですから、基本的には「行為の承認」です。学校の部活で、先に出て仲間のために練習の準備をしていたら、仲間から評価され承認されるでしょう。3一般的承認も「行為の承認」要素が多くなります。
ここでもう一つ、本書では「自己承認」というキーワードが出てきます。つまり「自分で自分を承認する」ということです。たとえばSNSでいいね!が付くなど、自己承認を助けてくれるツールもあります。自分が属する集団において承認の不安があっても、社会の中で共有されている価値観を理解していれば自己承認によって乗り越えられる可能性があります。
次に紹介したいのが「自由」と「承認」の葛藤です。
自由への欲望(~したい)と承認への欲望(~すべき)はしばしば葛藤します。自由になりたいと思いながらも、親や先生の言うことを守ることでしか承認が得られないとしたら、それは葛藤することになります。
「承認不安」にどのように対処するのか?について、本文には以下のように書かれています。
~~~
承認への欲望を優先する対処法でよくあるのは、「コミュニケーション・スキルを磨く」というものです。コミュニケーションの上手い人は、周囲の人々の受けもよく、好印象をもたれやすいため、「受け入れられている」「認められている」と感じる機会が多いはずです。
そもそも現代社会は第3次産業が中心で、コミュニケーション能力が仕事の評価に直結しやすい面がありますので、この力があれば承認を得る可能性が非常に高くなります。
周囲に同調し、過剰に場の空気を読み、自分の本音を抑えることでしかコミュニケーションを乗り切れない人は、自由を失い、自己不全感を抱くようになるでしょう。
一方、自由を優先する場合には、「承認を求めずに自分のやりたいことをやる」という態度に徹するやり方があります。
しかし、他人の承認を気にしないですませるためには、自分なりの信念、価値観を信じ、自己承認できなければ難しいと思います。それが独善的自己承認によるものならば、周囲の承認は得られないため、やがて耐えきれなくなり、承認不安が再び募る可能性が高いです。
そもそも承認不安の強い人は、周囲の目など気にするな、自分のしたいこと、すべきことをすればよい、と助言したところで、「それができるなら苦労はしない」と思うはずです。
また、幼い頃から承認不安を抱えてきた人は自分のしたいことを思う存分にした経験が乏しいため、自分がなにをしたいのか、なにをすべきなのか、よくわからないかもしれません。
~~~
これなんじゃないか?
「受験勉強して国立大学に合格する」っていうのは、「承認」を優先したってことなのではないか、って。
だからこそ大学に進学してしまったが最後、評価者(評価してくれる他者)を失い、不安になり、どうすればいいかわからないのではないか?
ここで、承認不安を解決するための自己分析の方法が紹介されています。
1 自分の心の動き(本心)を見つめる
2 したい(欲望)とこわい(不安)が浮かび上がる:自己了解
3 したいのにできない、こわいのはなぜか考える
4 自己ルールを自覚(したいけど、〇〇しなければ、嫌われる)
5 自己ルールの分析(過去の人間関係、出来事を振り返る)
6 自己ルールが歪んでいれば修正する。
これを支援できるとしたら、大切なのは最初の信頼関係づくり、つまり親和的承認です。
これをどうつくっていくか?しかもそれを個人対個人ではなくて、「場」としてつくっていけるか?その「場」の構成要素としては人だけではなく、本とか本棚とかも有効なのではないか。(本棚から人も世界も多様であり、多様であっていいというメッセージを発することができる)
「誰と」「いつ」「どこで」というような瞬間的な「場」と「営み」と呼ばれるような人生を超えた時間軸を合わせもつような空間をつくっていくことなのではないか。
それによって、高校生だけではなく、関わるスタッフも、地域の大人も、「自由」と「承認」を同時に満たしていけるような、そんな場をつくれないだろうか?
これが僕のいまの探究テーマ(問い)です。
2021年07月17日
一生残る問いを投げかけることができるか?

「探求のススメ」(宮地勘司 教育開発研究所)
15年以上にわたり、「クエスト」という教育プログラムを
学校現場に提供してきた「教育と探求社」代表の宮地さんの渾身の1冊。
「総合的な探究の時間」の設計している人にはおすすめの1冊。
タイムリーすぎて泣けてきました。本屋の神様、ありがとう。(新潟紀伊国屋書店で購入)
実践者の言葉はホントすごいなと。かっこいい。
まず紹介したいのは
「ファシリテーター」としての教師のあり方。
「教育と探求社」の「クエスト」プログラムでは、ファシリテーターのあり方として以下の4つを先生方に伝えている。
~~~以下P39~引用
1 信じること
どんな生徒のなかにもある、成長の可能性を信じることです。生徒が自分の思いを発露すること、仲間とのやり取りのなかから新たに何かをつくり出すこと、そこから新たな学びを得ること、そのことが生徒にとっては歓びとなり、成長となること。たったひとつの正解も、勝ち負けもない世界では、誰もがオンリーワンの輝きを放つことができます。そのことを教師が深く理解していることが大切です。
2 感じること
生徒の微妙な変化、柔らかな変化を常に繊細に感じ取ることです。表には出せなくとも、生徒の心のなかにはさまざまな揺らぎや複雑な変化が瞬間ごとに起こっています。先生はそこに意識を向けてください。わだかまりや違和感がありそうな顔、なにか言いたそうな気配に敏感になり、必要に応じてタイムリーに声かけをします。生徒の最終アウトプットの出来不出来で判断するのではなく、それ以前にある柔らかな心の動きと対話するようにしましょう。
3 待つこと
生徒の成長は、計画的、合理的には起こりません。それは生徒の内側から潮が満ちるように自然に起こります。赤ん坊が言葉を発するとき、自分の足で立ち上がるタイミングを計測することはできません。
知識の詰め込みやスキルのトレーニングであれば、どれくらい時間をかければどれくらいの成果が出るのか、ある程度予測できます。しかし、人の本質的な成長は、時間で計測したり、予測したりすることはむずかしいものです。教師は全力で応援し、信じて待つことしかできません。そしてそのような教師の意識やあり方こそが、生徒を安心させ、信頼を醸成し、成長を促すことになるのです。
4 一緒にいること
これまでの学びにおいては、先生は知識の番人として生徒の向かい側に対峙していたかもしれません。膨大で、複雑で、堅牢な知の体系を教師は自らの後ろに背負い、それを分解し、少しずつ、わかりやすく、秩序立てて、ときに事例をまじえながら生徒に届ける役割を担っていました。
しかし、クエストの学びにおいては、生徒は知の探求者です。自らの興味・関心に沿いながら、まるでRPG(ロールプレイングゲーム)のように、積極的に学んでいきます。先生はそんな生徒の伴走者として常に生徒の傍らにいて、同じ方向を向き、生徒を応援しながらともに歩んでいきます。教師は、管理者、裁定者の地位を自ら進んで降りることが必要です。
~~~ここまで引用
あまりにも大切にしたいので、写経してしまいました。
すごい。
信じること、感じること、待つこと、一緒にいること、ですね。
スクールウォーズの「愛とは、相手を信じ、待ち、許してやること」を思い出しました。
あとは大事マンブラザーズバンドの「負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと」と。
(いまユーチューブで検索しました。笑)
特に大人に必要なのは、「感じること」なんだろうと思います。
生徒のちょっとした変化を感じ、タイムリーに声掛けをする。
それが大人にとっても大きな学びにつながるのだろうと思います。
あとまた少しメモを。
~~~
子どもが自ら学びを取り戻すための工夫
1 自分が学びの起点となる。
野性的な学びの力を賦活するためには、自分という存在が欠かせません。社会構成主義で言うところの唯一無二の客観的真実があるのではなく、意味が関係性の中に立ち現れるという学習観においては、自分の存在自体が学びのプロセスに含まれている必要があります。
水槽を客観的に外から観察するのではなく、自らもその水槽の中で魚たちとともに泳ぐのです。客観的な個体のような知識の塊を自分という袋の中に順番に入れていくような学びではなく、世界と自分との対話を通じて、その関係性の中に意味が立ち現れるわけですから、自分という存在なしには学びは起動しないのです。
(中略)
何気ない日常の気づきからイノベーションを起こしてみるという原初的な体験をすることが、子どもたちの野生の探求心に火をつけるのです。自分と切り離されて世界のどこかに格納された立派な知識ではなくて、自分との関係性のなかから紡ぎ出された「意味や想いを内包した知」を扱うことをとてもとても大切にしています。
(中略)
2 生きた素材で学ぶ
生きた素材は、こちらが働きかけることでほんの少しかもしれませんが変化する可能性があります。たとえほんの少しでも何かが変えられるとしたら、自分がこの世に生きている意味を実感することができます。自分にも居場所があるのだと思えるようになるかもしれません。
3 一貫したストーリーで学ぶ
物語の世界観があり、コンセプトに沿った初期の状況設定があり、自分たちの役割が決まれば物語は自動的に展開し始め、生徒たちは主体的に動き出します。
4 心理的安全性を確保する
そして、クエストの3つの目的
1 生徒が自ら学び、成長する
2 学校が学び合いの場となる
3 社会とつながり、社会を変える
~~~
第3章クエストエデュケーションとは何か?で紹介されている
企業探究コースの内容も参考になるなあと。
1 フィールドワーク・・・職場体験(現場を知る)
2 アンケート・・・初仕事(顧客を知る)
3 ミッション提示・・・プロジェクトのスタート
このミッション提示の時に、哲学的な問いを投げかける、という方法。
「人が生きる原点を支える大和ハウスの世界に広がる新商品を開発せよ」とか。
生徒たちは「生きる原点」という問いに対してブレストを重ね、提案を考えます。
「思い出」「利便性を求める進化の力」「温かい食事」という原点に対して
このようなサービスができるのではないか、と語ります。
~~~
「人が生きる原点」という普遍的かつ本質的価値をとことん探求し、そこから出される企画に関しては正解はなく自由であるという構造が子どもたちの創造力を発露させるのです。
いやあ、すごい。すごいわ。
この実践を通して、生徒だけではなく教師も企業人も変化が起こると宮地さんは言います。
先生は対話型の授業スタイルへとシフトし、企業人のリーダーシップも対話型になります。
今回、いちばん心震えたのは、企業人のエピソードでした。
~~~
若手の女性技術者が学校訪問をし、生徒から「〇〇さんが、仕事をしてきたなかで、もっとも企業理念を実現できたと思う仕事について教えてください」と問われたことがあります。彼女は想定外の質問にドギマギしながら、なんとか経験を高速で振り返り、内なる思いを探索し、答えを絞り出します。終了後「これまで受けたどの研修よりも厳しかった」と私にフィードバックをくれました。生徒たちの純粋な瞳の前にうそやいい加減なことは言えません。瞬間的な振り返りではありますが、「私は企業理念というものにどのように向き合い実践しているのか」、本気の内省から得られた気づきが大きかったと思います。
またある企業の現場の担当者はこんなことを言っていました。
「学校を訪問すると多くの生徒に出会います。しかし、一人の生徒とコミュニケーションできるのはほんの5分もない。ですから、ただ漫然とやりとりするのではなくて、彼らの心に一生残る問いをこちらが投げかけることができるかということを大切にしています。決して簡単なことではありませんんが、それが企業が教育にかかわらせていただく責任だと思うのです。
~~~
すごいな、この真剣勝負。
涙でる。
第3章はこのように締めくくられます。
「世の中にはほんとうに正解はなく、多くのまだ見ぬ可能性に満ちている。自分は自由で創造性に満ちている。社会は少しずつでも変えることができる。それゆえに人生は生きるに値する」生徒が心の底からそう思えたら、それで教育は成功ではないでしょうか?
アツいなあ。ホント、それです。
そんな実感が持てる授業や課外活動、マイプロをつくっていきたいなと思います。
学びは「大いなるものへの過程である今を瞬間的に切り取ったもの」だと思う。それは、大学合格や就職内定と言った短いスパンのものではなく、自分の人生の長さや、自分ひとりの人生というスケールを超えた「大いなるもの」に向けた「過程」であると思う。
その「過程」において、「先に生まれた」ことは、なんのアドバンテージでもない。
いま、この瞬間、この空間で、自分の心がどうしようもなく動く何かを発見し、それがもし課題があるとすればその課題を解決したいと思い、行動すること。
そこに伴走する大人たちもまた、問いを持ち、活動し、問いに答えていくこと。
「一生残る問いを投げかけることができるか?」という観点はすごい。
15歳から18歳に出会った問いで、人生は動くのだから。
問いというベクトルを得ること、そしてプロジェクトで小さな変化を起こすこと。
そこに「存在」もあると思う。
大学生の「存在」に対する不安は、「知りたい、わかりたい」という本来の「野性的欲求」を受験というシステムに適応するために制御ししてきたことに大きな原因があるのかもしれない。勉強するといいことがあるという「利得欲求」を学習のモチベーションとしてきたとしたら、努力して大学に入った人ほど入学前に知的好奇心を発動しないようになっているのではないか。
「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」という存在に対する不安は、「未来をこの手でつくっている」という実感の少なさからも来るのではないか。そうだとすると、高校生のときに何を学ぶか、大学生の夏休みをどうすごすか?という問いに対して、「小さな共同体で、リアルな実感のある実践的な学びをすることで、未来は自分の手の内にあると実感する」ことから始まるのではないか。
今月にはまた地域みらい留学説明会がある。
これをどのように表現していけばいいのかな。
2021年07月15日
「本当のわたし」という幻想
就職活動。
「自分とは何か?」という問いに、多くの高校生大学生が苦しんでいる。
それは、現象としては「やりたいことがわからない」や「自分に自信がない」ということなのだろう。
あとは、よく就職意識調査などで問われる、「人のためになる仕事がしたい」とか「人の役に立つ仕事がしたい」とか。
その根本にある、「本当のわたしって何?」とか「わたしは何がしたいの?」っていう問いがグルグルする。
今日はそんなあなたに贈る1冊。

「利他」とは何か?(伊藤亜紗編 集英社新書)
第2章「利他はどこからやってくるのか?」(中島岳志)より
「わらしべ長者」の話から。
観音様にお告げを聞きに来た若者に、夢に出てきたお坊さんが言った
「最初に手に触れたものが観音様からの贈り物だから大切にしなさい」
を実践しようとしたらいきなりコケてしまって、手元には1本のワラが。
ワラか・・・(笑)
大切に持って歩いているとアブが飛び回ってうるさいので捕まえてワラに括りつけて
振り回して遊びながら言った、すると子どもを連れた女性がやってきて、
その子どもがワラがほしいとねだる。
そうすると若者はあっさりとワラをあげてしまうのです。
これが出発点になっているところが「わらしべ長者」のポイントだと説きます。
つまり、結果としての間接互恵のシステムであり、行為を行った時点では間接互恵が前提とされていない、ということです。
自分が行ったら何かがかえってくるという前提で行った行為ではなく、結果として何かがかえってくるというのが非常に重要な問題ではないのか。それは衝動的なもの、思わずやってしまうこと、理由がつかない因果の外部の行為として行われいるものです。
~~~
このあと、仏教の話に続きます。
~~~
仏教の根本は「アートマン」の否定です。アートマンとは絶対的な我を指すヒンドゥー教の概念です。
コータマ・シッダールタは、アートマン、すなわち絶対的な我は存在しないことを解きました。本当の「我」はどこまで追求しても存在しないことが仏教にとっては非常に大切なのです。むしろ、存在するのは、縁起的現象としての「私」というものだけであるということです。
五蘊(ごうん)=色(=肉体)、受(=感覚)、想(=想像)、行(=心の作用)、識(=意識)
この五つの要素がたまたま結合した結果として「私」というものが存在していると仏教では考えます。
そして、五蘊の複合体である私は、いろいろな縁によって無数に変容していきます。たとえば、誰かと話をすることによって影響を受けると、私の五蘊の結合体は変容する。つまり、昨日の私と今日の私というのは変化している。本質的なアートマンなどというものに支配されず、我に対する執着を超え、無数の出会いによって変容していく「私」という現象こそが本当の「私」である。
~~~
なるほど。
「自分」っていうのがそもそもキリスト教の「神」に対する概念ですもんね。
仏教の「私」感のほうがしっくりと来ます。
もうひとつ仏教の話を。
第3章 美と奉仕と利他(若松英輔)より
柳宗悦「民藝」の思想から
ここでは「不二」の哲学が説明されています。
~~~
それは凡て現世での避け難い出来事なのである。仏の国のことではないからである。ここは二元の国である。二つの間の矛盾の中に彷徨うのがこの世の有様である(中略)。人間のこの世における一生は苦しみであり悲しみである。生死の二と自他の別はその悲痛の最たるものである。だがこのままでよいのであろうか。それを超えることはできないものであろうか。二に在って一に達する道はないであろうか?(『新編 美の法門』柳宗悦)
「二に在って一に達する道」、これが「不二」の世界である。生と死、自と他の存在はそのままでありながら、「二」の壁をこえることはできないか、と柳は訴える。「二」の壁を超える「不二」、それが仏教の説く「利他」と響き合うことはいうまでもありません。
(中略)
柳はそれを民藝という「美」によって表現しようとします。
利他は「他」と「自」がおのずと一つになっていなければ起こり得ない、という基本的かつ肉感的な認識が柳にはありました。そしてまた利他の本質は、人間の主体性の産物ではなく、非・人間的実在との呼応において現象するとも考えていました。
利他とは個人が主体的に起こそうとして生起するものではない。それが他者によって用いられたときに現出する。利他とは、自他のあわいに起こる「出来事」だといも言えます。
~~~
いいですね。
歴史や仏教、学びたくなってきますね。
「自分とは何か?」という終わりのない問いは、そこまでさかのぼらないと解けないのかもしれません。
「私」というものがあるのではなく、私というのは「現象」に過ぎない。
僕はそれを「場」という考え方でとらえようとしているし、身体性を大切にしたいなあと思っている。
いったん「私」を「場」に溶かして、「場」を主語に活動してみる。
「場」が発見し、「場」が創造する。
そこに現象としての「私」が現れる。
そのすべてが「本当のわたし」であり、常に変化(変容)し続ける。
そんな体感が無ければ、(本人たちにとって)深刻な「自分とは何か?」問題は解決しないのではないかというのが私の仮説です。
そんな機会をつくっていきたいと思ってます。
「自分とは何か?」という問いに、多くの高校生大学生が苦しんでいる。
それは、現象としては「やりたいことがわからない」や「自分に自信がない」ということなのだろう。
あとは、よく就職意識調査などで問われる、「人のためになる仕事がしたい」とか「人の役に立つ仕事がしたい」とか。
その根本にある、「本当のわたしって何?」とか「わたしは何がしたいの?」っていう問いがグルグルする。
今日はそんなあなたに贈る1冊。

「利他」とは何か?(伊藤亜紗編 集英社新書)
第2章「利他はどこからやってくるのか?」(中島岳志)より
「わらしべ長者」の話から。
観音様にお告げを聞きに来た若者に、夢に出てきたお坊さんが言った
「最初に手に触れたものが観音様からの贈り物だから大切にしなさい」
を実践しようとしたらいきなりコケてしまって、手元には1本のワラが。
ワラか・・・(笑)
大切に持って歩いているとアブが飛び回ってうるさいので捕まえてワラに括りつけて
振り回して遊びながら言った、すると子どもを連れた女性がやってきて、
その子どもがワラがほしいとねだる。
そうすると若者はあっさりとワラをあげてしまうのです。
これが出発点になっているところが「わらしべ長者」のポイントだと説きます。
つまり、結果としての間接互恵のシステムであり、行為を行った時点では間接互恵が前提とされていない、ということです。
自分が行ったら何かがかえってくるという前提で行った行為ではなく、結果として何かがかえってくるというのが非常に重要な問題ではないのか。それは衝動的なもの、思わずやってしまうこと、理由がつかない因果の外部の行為として行われいるものです。
~~~
このあと、仏教の話に続きます。
~~~
仏教の根本は「アートマン」の否定です。アートマンとは絶対的な我を指すヒンドゥー教の概念です。
コータマ・シッダールタは、アートマン、すなわち絶対的な我は存在しないことを解きました。本当の「我」はどこまで追求しても存在しないことが仏教にとっては非常に大切なのです。むしろ、存在するのは、縁起的現象としての「私」というものだけであるということです。
五蘊(ごうん)=色(=肉体)、受(=感覚)、想(=想像)、行(=心の作用)、識(=意識)
この五つの要素がたまたま結合した結果として「私」というものが存在していると仏教では考えます。
そして、五蘊の複合体である私は、いろいろな縁によって無数に変容していきます。たとえば、誰かと話をすることによって影響を受けると、私の五蘊の結合体は変容する。つまり、昨日の私と今日の私というのは変化している。本質的なアートマンなどというものに支配されず、我に対する執着を超え、無数の出会いによって変容していく「私」という現象こそが本当の「私」である。
~~~
なるほど。
「自分」っていうのがそもそもキリスト教の「神」に対する概念ですもんね。
仏教の「私」感のほうがしっくりと来ます。
もうひとつ仏教の話を。
第3章 美と奉仕と利他(若松英輔)より
柳宗悦「民藝」の思想から
ここでは「不二」の哲学が説明されています。
~~~
それは凡て現世での避け難い出来事なのである。仏の国のことではないからである。ここは二元の国である。二つの間の矛盾の中に彷徨うのがこの世の有様である(中略)。人間のこの世における一生は苦しみであり悲しみである。生死の二と自他の別はその悲痛の最たるものである。だがこのままでよいのであろうか。それを超えることはできないものであろうか。二に在って一に達する道はないであろうか?(『新編 美の法門』柳宗悦)
「二に在って一に達する道」、これが「不二」の世界である。生と死、自と他の存在はそのままでありながら、「二」の壁をこえることはできないか、と柳は訴える。「二」の壁を超える「不二」、それが仏教の説く「利他」と響き合うことはいうまでもありません。
(中略)
柳はそれを民藝という「美」によって表現しようとします。
利他は「他」と「自」がおのずと一つになっていなければ起こり得ない、という基本的かつ肉感的な認識が柳にはありました。そしてまた利他の本質は、人間の主体性の産物ではなく、非・人間的実在との呼応において現象するとも考えていました。
利他とは個人が主体的に起こそうとして生起するものではない。それが他者によって用いられたときに現出する。利他とは、自他のあわいに起こる「出来事」だといも言えます。
~~~
いいですね。
歴史や仏教、学びたくなってきますね。
「自分とは何か?」という終わりのない問いは、そこまでさかのぼらないと解けないのかもしれません。
「私」というものがあるのではなく、私というのは「現象」に過ぎない。
僕はそれを「場」という考え方でとらえようとしているし、身体性を大切にしたいなあと思っている。
いったん「私」を「場」に溶かして、「場」を主語に活動してみる。
「場」が発見し、「場」が創造する。
そこに現象としての「私」が現れる。
そのすべてが「本当のわたし」であり、常に変化(変容)し続ける。
そんな体感が無ければ、(本人たちにとって)深刻な「自分とは何か?」問題は解決しないのではないかというのが私の仮説です。
そんな機会をつくっていきたいと思ってます。
2021年07月10日
「自分軸」の見つけ方

「生命科学的思考」 (高橋祥子 ニューズピックス)
読み終わりました。今日は、
第3章 一度きりの人生をどう生きるか~個人への応用
から。
この前のオンラインツルハシブックスのテーマは「自分軸」
だったのですけど、それに対してのひとつのメッセージを。
以下メモ
~~~
覚悟はまるでブロックチェーンのように、後からは改竄できない小さな約束を一つずつ刻んで未来へと繋がっていきます。それは誰にも改竄されないし奪うことのできないもの。覚悟とは、いつだって自由なものなのです。
もし「主観的な意志を持ちたいけどどうすればいいのかわからない」という人に向けて私がアドバイスするとしたら、「カオスな環境に身を置くべきだ」と伝えます。カオスは混沌という意味で、「秩序がなく、予測が不可能な環境」と表現できます。
カオスで予測不可能な環境に置かれると、「なぜ予測できない方向に向かってしまうのか」「なぜこんな理不尽な目にあわないといけないのか」「なぜ世の中はこうなっているのか」など疑問が生まれるようになります。
カオスであればあるほど疑問は生まれやすくなり、ひいては主観につながります。
「なぜ」という言葉から始まる疑問はとても重要だと私は考えています。5W1Hのうち、WHY以外の5つは客観的な視点から疑問が生じえます。一方「なぜ」から始まる疑問は、社会だけではなく自分の主観に紐づいています。
「なぜ」が発生した瞬間、その問いに対する思考に主観が生まれます。「なぜ」という疑問を設定することで、主観的な命題に気づくことができ、何を目指したいのか、そのために自分はどう行動すべきかという「自分軸」が発生します。
~~~
「やりたいことがわからない」とか「自分の軸が見つからない」とかいう人たちへのメッセージとして、かなり実践的ですね。
そもそも「やりたいこと」を職業名で答えることはまったくのナンセンスなので外しますが、
「やりたいこと=主観的な意志」だとして、それを見つけるためにはカオスに身を置くこと。
つまり、学校的空間のような「秩序だった」ところからでは生まれないということです。
なぜ生まれないか?というと、
予測不可能な、理不尽な状況、つまり「違和感」が生じる状況に置かれることで、
ひとは「なぜ?」と考えるからです。
その「なぜ?」という問いこそが、主観的な意志につながる糸口になるからです。
「なぜ?」という問いはもちろんテレビやネット、本からでも得ることができるでしょう。
僕の仮説としては、おそらくはそこに身体性が必要なのかなと考えます。
頭だけでなく体と心が動かされること。
そこから「なぜ?」が生まれる必要があるのかなと思います。
このあと、この章にはニーチェの言葉
「過去が現在に影響を与えるように、未来も現在に影響を与える」(フリードリヒ・ニーチェ)
から、「情熱」についての解釈があります。
~~~
未来差分の大きさと良い未来に向かって動き出す初速の掛け算、いわば積分量が情熱の源泉であると私は考えています。
意識高い系=未来差分の大きさは認識できているものの、動きださないため初速がゼロ
初速が出ていても、未来差分が認識できていない人は情熱が失われてルーティンになる
~~~
さらに、「エントロピー増大則」の説明から、ほっておくと乱雑になってしまう宇宙の法則から生命である人間は逃れられないと説き、「人間は生きて身体を維持している間、生物はまったく変化せずに身体を維持しているわけではなく、常にエネルギーを摂取し細胞を入れ替えて、常に変化しながら結果として「変わっていないように見える」ようにしているのです。」と動的平衡を説明します。
「エントロピーは無限に増大しますが、その状態に秩序を与えるために要するエネルギーは人でも企業でも国でも有限であるため、そのエネルギーをどこに投入するかを意志を持って決めることが重要となります。」
これ、人も、組織も、まちも、全部そうなんだよね。
エントロピー増大の法則に抗うためのエネルギーをどこに使うか?っていう話。
「主観的な意志」、僕的に言えばベクトルをどこに持ってくるのか?
それこそが昨日の話である「自分を知る」ということで、
「自分軸」っていうのは、「なぜ?」という疑問詞から始まっていくし、
それを得るためには予測不可能な場(カオス)に身を置くことが必要なのだと。
「やりたいこと」とか「自分軸」とかってそうやって始まっていくよなあ、っていう話に納得。
2021年07月09日
「課題」と「意志」

「生命科学的思考」 (高橋祥子 ニューズピックス)
読書日記つづき。
今日は第2章「生命原則に抗い、自由に生きる」より。
ここで言う「生命原則」とは、
すべての生命活動には「個体として生き残り、種が反映するために行動する」という共通の原則が関係しています。のことです。(本書より)
今日は「課題」について考えます。
探究学習、プロジェクト学習において、もっとも難しいのが「課題設定」だと言われていますし、その実感があります。
今日はそもそも「課題」ってなんだっけ?みたいなところから。
~~~以下本書より引用
前述した課題のほとんどは、客観的に設定された課題ではなく、それが解決された状態を私たちが主観的に望むことで初めて課題となるものです。つまり、自ら選んで「課題」を設定できるということ自体が極めて自由かつ主体的な性質を持つものです。
課題が存在するということは、現状よりもいい状態がすでに頭の中にある、ということです。
世界の現状に満足しておらず、もし今のままでは未来も同じ状況になってしまう、それではいけない、未来を理想の姿とすべく今から行動を起こさなければならない、と考える個人の「行動を起こすべき理由」こそが「課題」です。
課題を認識した時点で、自分が主観的に目指したい未来像はすでにその人の手中にあります。
未来の思い描く状況と現在の状況に差分があり、さらに現状維持のままでは思い描く未来に到達できないことがわかったとき、その未来差分を解消しようと行動が生まれます。そして、行動の初速が伴うことで情熱が生まれます。
課題というと、「解決しなければならないもの」とネガティブに捉えられがちですが、本質は「解決することでより良い未来に到達できるものであり、それを意識づけてくれるもの」です。
課題を見つめることで自身の主観的な意志をしっかり認識して行動に移していくからこそ、より良い未来に行くための原動力が得られます。
~~~
「課題」=「行動を起こすべき理由」であり、それは主観的な未来像に基づいている。
それなんですよね。
SDGsを出発点にしてもいいとは思うんですけど、それが「主観的な未来像」になっているかどうか、っていう。
国連が言っているから、ニュースで言っていたから、ということではなく。
理想の未来像と成り行きの未来像のギャップが課題であり、現状から理想の未来へ向かうベクトルが「自分」なのかなと思います。
もうひとつこの章で挙げておきたいのが「利他主義」と「生物的人間と科学的人間」について
~~~
利他主義はしばしば自己犠牲と同一視されがちですが、利他主義においては、自分と他者を対立関係として捉える意味合いは弱く、ほとんどのケースでは「自分を含めた集団が良くなること」を意味します。
利己主義の延長上にある利他主義として、他者のことも考えて行動することで集団としての生存につながり、結果として自分も生き延びることになります。
情報という客観的なものを理解した上で、感情という主観的なものをベースに行動を起こすことが大切です。
「人間は生物的人間と科学的人間の二つの側面を持っている」(「化学と私」福井謙一)
生物的人間:人間の持つ感覚や感情によって自分の認識で世界を捉えていく側面
科学的人間:自分の持つ科学リテラシーによって世界を捉えていく側面
~~~
「利他主義」は「利己主義」と対立するのではなく、空間的・時間的に広く見た時に利己主義の延長上にある、ということです。いや、そうなんだよね。
感情と情報、主観と客観。
そのどちらもが必要なのだけど。
この本にも書いてあるように、「科学」に偏重してきたこの世の中では、「自分(自分の感情・主観)を知る」ということがあまり大切にされてこなかったように思います。
~~~
情報をつかむことも大事ですが、より大事なのは変わりゆく世界の中でも自分にとって変わらない主観的な軸は何かを発見することです。軸を発見できれば、また別の予測不可能な変化が起こっても、それでも生きていくことができます。主観は、人によって大きく異なります。情報はその気になれば誰でも集めることができますが、そういった代替性の高いものを全部そぎ落としたとき、最後に残るものが主観です。この主観こそがAIに代替できないものです。AIは入力された情報のみをもとに判断を行うため、人が持つような主観はなく、だからこそ思い込みや勘違いなどを排除できる利点があります。一方の人間の本質は何かといえば、思い込みを含めた主観にこそあるのではないでしょうか。
~~~
思い込み、勘違い。
これがいろんな人の「原動力」となっているのは間違いないと思う。
そう人を駆動するのは情報や科学ではなくて「主観」なんだと。
その「主観」にフォーカスすることが大切なのではないか。
印象に残ったことは何か?
やってみて、どう感じたか?
そんな振り返りをしていくの中で、心が動き(あるいは心の動きを振り返り)課題が言語化されていく。
取り組みたい課題を知るということは、自分を知るということだ。
自分の心が動く「課題」を知ることで自らの「意志」を知る。行動し、それを確かめる。
きっとその繰り返しなのだろうなあ。
2021年07月08日
「多様性」という生存戦略

「生命科学的思考」 高橋祥子 ニューズピックス
前回はパラパラと読んでいたのですが、今回は仙台の山崎さんが読んでいたのでタイミングよく再読中です。
「マルチ・ポテンシャライト」の次っていうのがまた良くて。
ひとまず第1章だけ紹介します。
~~~
基本的にすべての生命活動には「個体として生き残り、種が反映するために行動する」という共通の原則が関係しています。
新しい「生」だけでなく「死」という仕組みもセットで持つことは、生命の非連続性を強制的に創出する手段として機能します。環境の変化のスピードは大きく、一つひとつの個体が連続性を持ったまま適応するには限界があります。そこで、新しい生命を常に作り続け、来たるべき環境の変化に備えようとするのです。
孤独感は人と集団で生活することで生き延びてきた人類が、一人で生きることを避けるための機能です。
「個体が生き残る」ことと「種が繁栄する」ことは並列ではなく、優先順位があります。まず個体として生き残ることが先で、個体としての生存の可能性が担保されてくると、次に種が繁栄するために行動するようになります。
時間的視野を自由に選択できるとは、過去と未来を1日、1週間のような短期だけでなく、1年、10年から1万年、100万年などの長期でも自由に捉えられる状態です。
一人の個体の中でDNAの配列が一生変わらないとなると、刻々と変化する外界の環境や体内の状況に変化するのが難しいように思えます。しかし、実際には変化する体内外の環境に対応するため遺伝子の「発現量」は日々変化しています。
DNAは長期間にわたって変わらず、RNAまたはタンパク質などの分子は環境に応じて量が変化する。同じ生命の中に複数の時間軸の仕組みを持つことで長期的な変化にも短期的な変化にも対応することができます。生命はまだ見ぬ未来への進化のためのセレンディピティ(想定外の発見)を求めて、DNAのコピーミスという不安定性を、個体が死ぬかもしれないリスクを取りながらも、種の存続のため命をかけ担保しているのです。
多様性は、進化のために必要不可欠な要素です。進化は「進」という文字が入っているために、ある目的に向かって一直線に進む合目的なものと捉えられがちです。しかし実際はそうではなく、環境が変化したときにたまたま生存に有利だったものだけが生き残ることで事後的に合目的かのようにみなされうる現象です。
~~~
僕のメモ
・生命は非連続性を意図的に創出している⇒生き延びるため
・「個体が生き残る⇒種が繁栄する」という順番
・視野を自由に選択するために歴史や哲学を学ぶ必要があるよね。
・DNAの配列は変わらないけど発現量は日々変化している。
⇒これ、「マルチ・ポテンシャライト」の話じゃないか
・DNAのコピーミスは一定の割合で起こるようにプログラムされている⇒進化(生き延びるための変化)のため
・「進化」は多数の変異の中で変化する環境下でたまたま生存に有利だったものが事後的に分かる現象であり、「多様性」はそのためにある。
って感じですかね。
「多様性」が大切だと言われる。それは決して道徳などではなく、生存戦略なのだと。
たとえば、毎日外食で同じチェーンストアで食事をするより、その町にしかない食堂の空間で食べる町中華が美味しい。
(写真は会津宮下駅前の双葉食堂の焼きそばラーメン)



まあ、それは置いといて。(笑)
昨日も只見高校の総合的な探究の時間でも説明した
「越境・遭遇」⇒「対話・協働」⇒「試行・省察」
「越えて、ともに、やってみる」のサイクルの中で、
自分自身のDNAの発現量をいろいろ試してみることであり、様々な役を演じてみることであり、環境の変化に適応するチームをつくるために、多様な人と対話・協働することなのだなあと。
2021年07月07日
あなたの人生にどの程度の「多様性」が必要か?

「マルチ・ポテンシャライト」(エミリー・ワプニック PHP研究所)
読み進めています。面白い本です。
起業家の書くビジネス書は、これのどれかに当てはまっている気がします。
何よりも、昨日も書きましたが、1つの仕事に絞ってそれを目指し、就き、磨き、プロフェッショナルになる、みたいな思想は、誰のためにあるんだろうか?って思います。そもそも時代の早い流れに合っていないし。
この本には、人生において必要なものを3つの視点から説明します。
1 「お金」
2 「意義」
3 「多様性」
よくありがちなのは、「お金」なのか「やりがい」なのか?みたいな二択。
これを真剣に考えてしまうなんて、完全に問いのマジックにかかっていると思う。
この3つすべてが必要だし、その必要度は人によって違う。
なによりもこの3つを実現するのが「1つの仕事」であるとは限らない。
「仕事」なのか「趣味」(もしくは「家庭」)なのか?
みたいな問いと同じくらい意味がないと思う。
今日は特に
3 「多様性」について取り上げたいと思う。
以下、一部引用する(P80幸せに生きる秘訣その3:多様性)
~~~
「好きなことを仕事にすれば、一生働かなくてすむ」
このアドバイスは、マルチ・ポテンシャライトにはあまり役に立たない。なぜなら、幸せになるために「多様性」を求めるよう生まれついているからだ。
進路ガイダンスのたぐいは、世の中には多様性が欠かせない人間がいることを、ほとんど理解していない。同時に複数の分野で仕事を始めるのを支援してくれるキャリア・カウンセラーはまずいないし、キャリアにまつわる本も、選択肢を一つに絞って「ぴったりな」職業へと導こうとする。いくつもの興味を組み合わせ、いくつもの役割を演じられる多面的な仕事を考え出すのを手伝ってはくれない。
どの程度の多様性が必要かは人によって違うだけでなく、ある人の人生の中でも変化する。(中略)私たちはさまざまな季節を経験する。一つの分野にどっぷり浸るのが心地よい時期もあれば、多様性から元気をもらい、わくわくする時期もある。
~~~
このあと、「あなたは多様性をどれくらい求めているか?」というセルフチェックがある。
自分がプロジェクトをいくつくらい抱えるのが最適なのか理解するためのワークだ。
これ、いい視点だなあと。
「興味関心は多いのだけど、何をやってもすぐ飽きるし、続かない」という相談をたまに受けることがあるけど、それって、あなたの人生にとって「多様性」が重要であるということではないのか?
「1つのことを究めてプロフェッショナルになる」というモデルは、実は一部のエンターテイメントビジネスなどの「無くならない(続いていく)仕事」に限られるのではないか。
次の章ではマルチ・ポテンシャライトの4つの働き方(ワークモデル)が紹介されている。これがなかなか興味深い。
1 グループハグ・アプローチ:1つの多面的な仕事やビジネスに関わることで職場で多くの役割を担い、いくつもの分野を行き来できること⇒いわゆる「総合職」「クリエイティブクラス」的なアプローチ
2 スラッシュ・アプローチ:パートタイムの仕事やビジネスをいくつか掛け持ちし、その間を日常的に飛び回っていること⇒いわゆる「劇団員」的あるいは「ナリワイをつくる」的なアプローチ
3 アインシュタイン・アプローチ:生活を支えるのに十分な収入を生み出し、ほかの情熱を追求する時間とエネルギーを残してくれる、フルタイムの仕事に携わること:公務員をやりながら研究をする的なアプローチ。
4 フェニックス・アプローチ:ある業界で数カ月、もしくは数年働いたあと、方向転換して、新たな業界で新たなキャリアをスタートさせること:いままでと全然違う業界に突然転職をする、みたいなアプローチ。
~~~
重要なのは、このどれかが「答え」ではないということ。4つのアプローチを組み合わせてもいいし、数年ごとにモデルを変えても、混ぜてハイブリッドにしても、何の問題もない、ということ。
読んでいて思ったのは、これは人生の経営戦略そのものだなと。僕も意識せずに、40歳でサラリーマン初体験っていうのは、「フェニックス・アプローチ」をしていたのだなあと。
重要な問いは、あなたの人生にどの程度の「多様性」が必要なのか?だと思う。
そしてそれを知るには、「プロジェクト」をやってみること、なのかもしれない。仕事とは、人生とは、プロジェクト(の組み合わせ)であるから。
2021年07月06日
越えて、ともに、やってみる
地元中学3年生に対しての高校説明会でした。
他の高校のプレゼンを見ていたら、
「これだけの進学実績があるし、先輩もいるから、大学に進学したい人は来てね」
「勉強して進学したい子も、部活を頑張りたい子も、地域で活動したい子も、うちの高校に来たら何でもできるから、みんな来てね。」
みたいな感じ。プレゼンも上手だし。
いや、スペックでは全然勝てないな、と。
だから、昨日の寮の話じゃないけど、前提を疑うこと。
高校って、どんな場所だっけ?
・やりたいことを見つけて、進路選択をし、力をつけて、将来につなげる場。
本当ですか?と。
そこで、今朝読んでいたこの本。

「マルチ・ポテンシャライト」(エミリー・ワプニック PHP研究所)
副題は「好きなことを次々と仕事にして、一生食っていく方法」です。(及川さんが好きそうなタイトルです・・・)
TEDトークの書籍化ですが、やっぱりわかりやすいですよね、主張の順序がいい。
今回は最初の方しか読んでいないのですが、昨日の話と少しつながってくるので少しアプトプットしてみます。
まずはここから。
~~~
大人になったら何になりたいの?」という質問が、夢を膨らませる楽しいゲームから、何やら深刻で、不安な気持ちをあおるような問いに変わってしまう。「現実的な答えを出さなくちゃ」というプレッシャーが生まれる。
はっきり「一つ」とは言っていないが、「大人になったら何になりたいの?」は、「この人生で許されるアイデンティティは一つだけ。だから、どれにするの?」という意味だ。
~~~
ツルハシブックス時代に、主に新潟大学の大学生が悩んでいたことは、「やりたいことが分からない」と「自分に自信がない」だった。
キャリア(仕事選び、就職活動)の問題が深刻なのは、それがアイデンティティの問題に直結しているからである。
「やりたいことがわからない」と「自分に自信がない」は違うことを言っているようで、その根にはアイデンティティの危機がある。それを言えてはじめて自分は個人(大学生)として承認されるからだ。
そしてその根には学校(化)社会しか目の前に存在しないことが挙げられる。学校(化)社会は、目標を設定しそれに向かって歩みを進めることを前提としている。PDCAを回すために、計測可能であることが重要になる。
なりたいものが具体的職業の場合(しかもそこそこ生活していける専業の)は歓迎されるが、いわゆる在り方や抽象的なコンセプトの場合は、ほとんど認められないし、本人も納得できていないだろう。
昨日のプレゼンは、この話から入ったほうがよかったか。(時間ないけど)
「やりたいことは何か?」という問いと、問いの前提である、目標達成型でスペシャリストとして専業で仕事をするスタイルは、現在のような予測不可能な時代には、リスクが高いのだと。
だから、昨日も少し話したけど、
「越境・遭遇」⇒「対話・協働」⇒「試行・省察」のサイクルを回していくことが大切で。
しかもその主語は、個人単位ではなく、「個人」と「場」の動的平衡的な主体であると。
個人では「問い⇒機会⇒振り返り」が起こり、「場」では、機会⇒対話・協働⇒試行が起こる。
それを具体的にやっていくのがプロジェクト型学習であり、プロジェクト学習の前提として越境による他者(または環境)との遭遇と、他者理解のための対話がある。だから、地域の多様な人たちが関わる必要があり、学校を飛び出して地域を舞台に試行してみる必要があるし、それをコーディネートする人たちも必要になる。
キャリア的な視点でいけば、高校生がなりたいものやロールモデルを見つけるために地域(の人や環境)があるのではなく、プロジェクトのメンバーとしての多様性や越境・遭遇・対話のために、協働・試行・省察のパートナーとしてそこにあるのだと思う。
そういう意味では、一般的な高校説明の文脈で語られるような
・やりたいことを見つけて、進路選択をし、力をつけて、将来につなげる
場としてあるよりも、
「越境・遭遇」の機会をつくり、「対話・協働」する多様な人たちがいて、「試行・省察」する、というプロジェクト型の学習は、予測不可能な、答えのない時代において、一生使えるマインドやスキルを磨くのではないか、ということ。
さらに言えば、「マルチ・ポテンシャライト」に書いてあるような
~~~
マルチ・ポテンシャライトのスーパーパワー
1 アイデアを統合できる
2 学習速度が速い
3 適応能力が高い
4 大局的な視点を持っている
5 さまざまな分野をつなぐ「通訳」になれる
~~~
を、「場」として発揮できないか?という感覚を、プロジェクトを通じて得ていくことは、一生使えるスキルというかマインドになるのではないか、と考えられる。
マルチ・ポテンシャライトの64ページはこんな見出しで始まる。
「これは単なるキャリア論ではない―人生設計そのものだ」
もはや「やりたいことは何か?」と問いかけている時代や社会ではないのだ。
予測不可能な社会を、未来を、何とか生きていくために、
「越境・遭遇」し、「対話・協働」し、「試行・省察」する。
「越えて、ともに、やってみる」
そんなまなびを創造していく必要があるし、それは楽しいことだと僕は思っています。
他の高校のプレゼンを見ていたら、
「これだけの進学実績があるし、先輩もいるから、大学に進学したい人は来てね」
「勉強して進学したい子も、部活を頑張りたい子も、地域で活動したい子も、うちの高校に来たら何でもできるから、みんな来てね。」
みたいな感じ。プレゼンも上手だし。
いや、スペックでは全然勝てないな、と。
だから、昨日の寮の話じゃないけど、前提を疑うこと。
高校って、どんな場所だっけ?
・やりたいことを見つけて、進路選択をし、力をつけて、将来につなげる場。
本当ですか?と。
そこで、今朝読んでいたこの本。

「マルチ・ポテンシャライト」(エミリー・ワプニック PHP研究所)
副題は「好きなことを次々と仕事にして、一生食っていく方法」です。(及川さんが好きそうなタイトルです・・・)
TEDトークの書籍化ですが、やっぱりわかりやすいですよね、主張の順序がいい。
今回は最初の方しか読んでいないのですが、昨日の話と少しつながってくるので少しアプトプットしてみます。
まずはここから。
~~~
大人になったら何になりたいの?」という質問が、夢を膨らませる楽しいゲームから、何やら深刻で、不安な気持ちをあおるような問いに変わってしまう。「現実的な答えを出さなくちゃ」というプレッシャーが生まれる。
はっきり「一つ」とは言っていないが、「大人になったら何になりたいの?」は、「この人生で許されるアイデンティティは一つだけ。だから、どれにするの?」という意味だ。
~~~
ツルハシブックス時代に、主に新潟大学の大学生が悩んでいたことは、「やりたいことが分からない」と「自分に自信がない」だった。
キャリア(仕事選び、就職活動)の問題が深刻なのは、それがアイデンティティの問題に直結しているからである。
「やりたいことがわからない」と「自分に自信がない」は違うことを言っているようで、その根にはアイデンティティの危機がある。それを言えてはじめて自分は個人(大学生)として承認されるからだ。
そしてその根には学校(化)社会しか目の前に存在しないことが挙げられる。学校(化)社会は、目標を設定しそれに向かって歩みを進めることを前提としている。PDCAを回すために、計測可能であることが重要になる。
なりたいものが具体的職業の場合(しかもそこそこ生活していける専業の)は歓迎されるが、いわゆる在り方や抽象的なコンセプトの場合は、ほとんど認められないし、本人も納得できていないだろう。
昨日のプレゼンは、この話から入ったほうがよかったか。(時間ないけど)
「やりたいことは何か?」という問いと、問いの前提である、目標達成型でスペシャリストとして専業で仕事をするスタイルは、現在のような予測不可能な時代には、リスクが高いのだと。
だから、昨日も少し話したけど、
「越境・遭遇」⇒「対話・協働」⇒「試行・省察」のサイクルを回していくことが大切で。
しかもその主語は、個人単位ではなく、「個人」と「場」の動的平衡的な主体であると。
個人では「問い⇒機会⇒振り返り」が起こり、「場」では、機会⇒対話・協働⇒試行が起こる。
それを具体的にやっていくのがプロジェクト型学習であり、プロジェクト学習の前提として越境による他者(または環境)との遭遇と、他者理解のための対話がある。だから、地域の多様な人たちが関わる必要があり、学校を飛び出して地域を舞台に試行してみる必要があるし、それをコーディネートする人たちも必要になる。
キャリア的な視点でいけば、高校生がなりたいものやロールモデルを見つけるために地域(の人や環境)があるのではなく、プロジェクトのメンバーとしての多様性や越境・遭遇・対話のために、協働・試行・省察のパートナーとしてそこにあるのだと思う。
そういう意味では、一般的な高校説明の文脈で語られるような
・やりたいことを見つけて、進路選択をし、力をつけて、将来につなげる
場としてあるよりも、
「越境・遭遇」の機会をつくり、「対話・協働」する多様な人たちがいて、「試行・省察」する、というプロジェクト型の学習は、予測不可能な、答えのない時代において、一生使えるマインドやスキルを磨くのではないか、ということ。
さらに言えば、「マルチ・ポテンシャライト」に書いてあるような
~~~
マルチ・ポテンシャライトのスーパーパワー
1 アイデアを統合できる
2 学習速度が速い
3 適応能力が高い
4 大局的な視点を持っている
5 さまざまな分野をつなぐ「通訳」になれる
~~~
を、「場」として発揮できないか?という感覚を、プロジェクトを通じて得ていくことは、一生使えるスキルというかマインドになるのではないか、と考えられる。
マルチ・ポテンシャライトの64ページはこんな見出しで始まる。
「これは単なるキャリア論ではない―人生設計そのものだ」
もはや「やりたいことは何か?」と問いかけている時代や社会ではないのだ。
予測不可能な社会を、未来を、何とか生きていくために、
「越境・遭遇」し、「対話・協働」し、「試行・省察」する。
「越えて、ともに、やってみる」
そんなまなびを創造していく必要があるし、それは楽しいことだと僕は思っています。
2021年07月05日
阿賀黎明高校「緑泉寮」の特徴
地域みらい留学の「寮での暮らし」のプレゼンを聞いていて思ったこと。
新築、個室、WiFi完備、買い物至便、学校まで徒歩数分・・・
とベネフィット合戦に戦いを挑んでも仕方ないし、
むしろそれが(誰にとって、何にとって、学びにとって)価値なのか?問いかけたい。
むしろ「緑泉寮」の
1 リノベ:地域資源を再活用している:地域課題どころか日本建築界の課題
2 学校から4㎞離れている:学校とは違う空間、場として機能。通学時間の発見があるかも
:狭いコミュニティからの脱出、学校生活を俯瞰して見ることができる。
3 2人部屋:対話を必要とする、安全面、健康面の問題。同室の生徒が不調に気づく。
4 高台に位置し、買い物が不便:余計なものを買う必要がない。
:高校の近くには買い物する場所はたくさんある。
まあ、魅力は、やっぱり日帰り温泉併設して、
・ゆっくりお風呂に入れるのと、
・地域の人と話せることと、
・飲食物や雑貨の販売ができたりすること
でしょうね。
やっぱ弱者としては逆張りで行きたいのと、
そもそも、どうぞ来てください、っていうスタンスではなくて、
一緒につくる仲間を募集しているんだっていう基本線は大切にしたい。
新築、個室、WiFi完備、買い物至便、学校まで徒歩数分・・・
とベネフィット合戦に戦いを挑んでも仕方ないし、
むしろそれが(誰にとって、何にとって、学びにとって)価値なのか?問いかけたい。
むしろ「緑泉寮」の
1 リノベ:地域資源を再活用している:地域課題どころか日本建築界の課題
2 学校から4㎞離れている:学校とは違う空間、場として機能。通学時間の発見があるかも
:狭いコミュニティからの脱出、学校生活を俯瞰して見ることができる。
3 2人部屋:対話を必要とする、安全面、健康面の問題。同室の生徒が不調に気づく。
4 高台に位置し、買い物が不便:余計なものを買う必要がない。
:高校の近くには買い物する場所はたくさんある。
まあ、魅力は、やっぱり日帰り温泉併設して、
・ゆっくりお風呂に入れるのと、
・地域の人と話せることと、
・飲食物や雑貨の販売ができたりすること
でしょうね。
やっぱ弱者としては逆張りで行きたいのと、
そもそも、どうぞ来てください、っていうスタンスではなくて、
一緒につくる仲間を募集しているんだっていう基本線は大切にしたい。
2021年07月02日
ドアに出会うこと、ドアを開けること、ドアの向こうに行ってみること
7月2日付読売新聞新潟版に「阿賀黎明高校魅力化プロジェクト」が掲載されています。
https://www.yomiuri.co.jp/local/niigata/news/20210701-OYTNT50053/
7月3日4日は「地域みらい留学」合同説明会があります。
https://c-mirai.jp/
https://c-mirai.jp/schools/18
週明けには地元の中学で説明があります。
昨日は、地元の中学で、「トークフォークダンス」に出演してきました。
「なぜ、赤い服なんですか?」って聞かれました。
自己紹介からの夢人生グラフを書いて、説明しました。
「伝えたいメッセージ」というのをあまり気にせずに、ここ10年のストーリーを話しました。
「対話」のデザイン的に言えば、ヒットするキーワードに、疑問詞表をくっつけて話せば、対話の助けになるなあ、と思いました。
越えて「機会」「越境」
ともに「対話」「協働」
やってみる「実験」「試行」
なのかなと思いました。
今回のトークフォークダンスのような「機会」というドアを開けて、まずは心を「越境」させ、「対話」を重ねることで場に溶けていって「協働」が可能になり、「実験」的に「試行」してみる。その「実験」「試行」が「機会」となって、次のドアを開ける。個人ベースで言えば、「問い」⇔「機会(実践)」⇔「ふりかえり」のサイクルを同時に回しながら。
特に大切なのは、やはり最初の「ドアに出会うこと」「ドアを開けること」「ドアの向こうにいってみること」これをいかに意識せずにやれるか?ということを大切にしてきた、と思います。
ツルハシブックスという本屋のような「場」は、ドアを前にして、対話している中で、気がついたらドアの向こう側にいる、そんなデザインに結果的になっていました。そのドアを開けさせたのは「偶然」というカギでした。
ツルハシブックスに行く理由を、「誰かに会えるから」だと表現した大学生がいました。あの空間の価値、中心的なお客像である大学生・中高生にとっての価値は「偶然」でした。
いま、中学や高校の授業や課外活動の現場で、
「ドアと出会い、ドアを開け、ドアの向こうに行く」
を実践するとしたら、どうなるのでしょうか。
そのカギはなんでしょうか。
「対話性」と「身体性」なのかもしれません。
ともに感じること。
感情と感覚とを「場」に差し出すこと。
「対話」と「体感」
この町には美しい風景があります。たくさんのドアがあります。
対話と実験と発見のプロセスをともにする大人がいます。
阿賀町で、あなたを待ってます。

https://www.yomiuri.co.jp/local/niigata/news/20210701-OYTNT50053/
7月3日4日は「地域みらい留学」合同説明会があります。
https://c-mirai.jp/
https://c-mirai.jp/schools/18
週明けには地元の中学で説明があります。
昨日は、地元の中学で、「トークフォークダンス」に出演してきました。
「なぜ、赤い服なんですか?」って聞かれました。
自己紹介からの夢人生グラフを書いて、説明しました。
「伝えたいメッセージ」というのをあまり気にせずに、ここ10年のストーリーを話しました。
「対話」のデザイン的に言えば、ヒットするキーワードに、疑問詞表をくっつけて話せば、対話の助けになるなあ、と思いました。
越えて「機会」「越境」
ともに「対話」「協働」
やってみる「実験」「試行」
なのかなと思いました。
今回のトークフォークダンスのような「機会」というドアを開けて、まずは心を「越境」させ、「対話」を重ねることで場に溶けていって「協働」が可能になり、「実験」的に「試行」してみる。その「実験」「試行」が「機会」となって、次のドアを開ける。個人ベースで言えば、「問い」⇔「機会(実践)」⇔「ふりかえり」のサイクルを同時に回しながら。
特に大切なのは、やはり最初の「ドアに出会うこと」「ドアを開けること」「ドアの向こうにいってみること」これをいかに意識せずにやれるか?ということを大切にしてきた、と思います。
ツルハシブックスという本屋のような「場」は、ドアを前にして、対話している中で、気がついたらドアの向こう側にいる、そんなデザインに結果的になっていました。そのドアを開けさせたのは「偶然」というカギでした。
ツルハシブックスに行く理由を、「誰かに会えるから」だと表現した大学生がいました。あの空間の価値、中心的なお客像である大学生・中高生にとっての価値は「偶然」でした。
いま、中学や高校の授業や課外活動の現場で、
「ドアと出会い、ドアを開け、ドアの向こうに行く」
を実践するとしたら、どうなるのでしょうか。
そのカギはなんでしょうか。
「対話性」と「身体性」なのかもしれません。
ともに感じること。
感情と感覚とを「場」に差し出すこと。
「対話」と「体感」
この町には美しい風景があります。たくさんのドアがあります。
対話と実験と発見のプロセスをともにする大人がいます。
阿賀町で、あなたを待ってます。

2021年07月01日
「手応え」のある暮らし
20代前半、畑をやらなければ「生きられない」と思っていた。
就職するより定期収入を得るよりも、畑をやることほうがはるかに重要度が高いと思った。
その理由が、ようやく言語化された。

「人類堆肥化計画」(東千茅 創元社)
いまこそ、読んでおいてよかったなあと思った1冊。
現在、魅力化プロジェクトの新しいパンフレットを作成中で。
https://www.agareimei.com/
あらためて令和3年度生徒募集の冊子を読み直して
「暮らし」をシェアして「まなび」をつくる、とか
「阿賀町まなびサイクル」とか。
そういうの、まだまだできていないな、と。
昨日の続きですけど、
クライマックスにはやはり、「自我」の話につながってきました。
~~~ここから引用(つち式二〇一七より)
最初わたしは、個体として十全に生きようとして、米、大豆、鶏卵を自給し始めたのだった。そうして彼らとの緊密な関係を築いたことで、かえって個我というそれまでにこだわってきた枠が侵犯される結果となり、あまつさえその侵犯されてあることにこの上ない悦びを感じている。個体としての十全さの最果ては、個体としてだけではいられなくなることであったのだ。
食糧の自給自足などという事態は実際にはありえず、農耕はいつも食糧となる生物との協働である。そうして生きよう生きようとすればするほど、作物/家畜とのずぶずぶの関係は深度を増して、元には戻れない。
なぜ杉林を雑木林にしたいのかといえば、単純に生き物の種類と数を増やしたいからだ。それだけだが、それ以上のことがあるだろうか。
人-間を変わらずに補強するのではなく、逆に人-間を超えて言葉や物語を拡張していこうではないか。異種たちに接触して自己が変容してしまうことは恐るべき事態ではあっても、自粛すべき事柄ではない。恐れは悦楽の予告に他ならない。
~~~
すごいですね。
カッコイイです。
言葉がいちいちシビれます。
「自我」という感覚からどのように解放されたのか、リアリティがあります。
じゃあ、どうすればいいのか?に対して、
筆者は「扉を開く」「寝転ぶ」「甘やかす」ことだと言う。
詳しくは本書を読んでいただくとして、今日は「甘やかす」を。
~~~
甘やかし甘やかされる関係を持つことは、〈わたし〉と〈あなた〉という個別具体的な間柄になるということである。それらは、この茫々たる生物界、ひいては宇宙において、ある固有の煌めきとして現出する。わたしとあなたとの接触によって生じるその光は、互いにかけがえのない存在として二者を照らす。無論それらはどれも、多くの人々が歯牙にも掛けないごく小さな物語だ。ただ、この広大な世界に二つとない物語である。
結局のところ、わたしたちはほんの小さな存在なのであって、大きな物語が取りこぼす「大事でない」身の回りの小さな物語だけが、わたしたちの生活に手応えを与えてくれる。私たちが実質的に関われるのは、宇宙の中のほんの小さな一点一点である。けれども、その一点に徹することで世界は発光する。
~~~
生活に手応えを与えてくれる、か。「手応え」。
大切なのは、夢とか目的とか目標とか意味とか、そういうやつの前に「手応え」なんじゃないのか、って思う。そしてその手応えを与えてくれるのは「目標達成」の瞬間などではなくて、「大事でない」身の回りの小さな物語なんだと。
「その一点に徹することで世界は発光する。」
僕にはこの「発光」体験がある。1999年8月1日。竹炭を焼くために、竹を切っていた。
予想最高気温は35度超。早朝から作業していたが、素人だった5名は、午前8時の段階ですでに疲労の色が濃かった。すると、地元のおばあちゃんがやってきて、「何してるんだね~?」と声をかけてきた。(知らない人が竹を切っていたので不信に思ったかもしれない。)
「竹炭を焼くために竹を切っているんです。」
「そうか、暑いのに大変だね~」
と言い残し、おばあちゃんは去っていった。
10分後。
おばあちゃんは戻ってきた。手にトマトの入った袋を下げて。
このタイミングで休憩することした。
トマトをかじった。顔を見合わせた。
世界が輝いて見えた。
このために畑始めたんだ、って思った。
日々の暮らしの中には、世界が「発光」する瞬間がある。それは本当に取るに足らないささいなことなのだろう。
そんな「発光」の瞬間を、この町の中学生高校生たちと、紡いでいきたいとあらためて思った。
この本を紹介してくれた「ウチノ食堂」さんありがとうございました。
ようやく読めました。
就職するより定期収入を得るよりも、畑をやることほうがはるかに重要度が高いと思った。
その理由が、ようやく言語化された。

「人類堆肥化計画」(東千茅 創元社)
いまこそ、読んでおいてよかったなあと思った1冊。
現在、魅力化プロジェクトの新しいパンフレットを作成中で。
https://www.agareimei.com/
あらためて令和3年度生徒募集の冊子を読み直して
「暮らし」をシェアして「まなび」をつくる、とか
「阿賀町まなびサイクル」とか。
そういうの、まだまだできていないな、と。
昨日の続きですけど、
クライマックスにはやはり、「自我」の話につながってきました。
~~~ここから引用(つち式二〇一七より)
最初わたしは、個体として十全に生きようとして、米、大豆、鶏卵を自給し始めたのだった。そうして彼らとの緊密な関係を築いたことで、かえって個我というそれまでにこだわってきた枠が侵犯される結果となり、あまつさえその侵犯されてあることにこの上ない悦びを感じている。個体としての十全さの最果ては、個体としてだけではいられなくなることであったのだ。
食糧の自給自足などという事態は実際にはありえず、農耕はいつも食糧となる生物との協働である。そうして生きよう生きようとすればするほど、作物/家畜とのずぶずぶの関係は深度を増して、元には戻れない。
なぜ杉林を雑木林にしたいのかといえば、単純に生き物の種類と数を増やしたいからだ。それだけだが、それ以上のことがあるだろうか。
人-間を変わらずに補強するのではなく、逆に人-間を超えて言葉や物語を拡張していこうではないか。異種たちに接触して自己が変容してしまうことは恐るべき事態ではあっても、自粛すべき事柄ではない。恐れは悦楽の予告に他ならない。
~~~
すごいですね。
カッコイイです。
言葉がいちいちシビれます。
「自我」という感覚からどのように解放されたのか、リアリティがあります。
じゃあ、どうすればいいのか?に対して、
筆者は「扉を開く」「寝転ぶ」「甘やかす」ことだと言う。
詳しくは本書を読んでいただくとして、今日は「甘やかす」を。
~~~
甘やかし甘やかされる関係を持つことは、〈わたし〉と〈あなた〉という個別具体的な間柄になるということである。それらは、この茫々たる生物界、ひいては宇宙において、ある固有の煌めきとして現出する。わたしとあなたとの接触によって生じるその光は、互いにかけがえのない存在として二者を照らす。無論それらはどれも、多くの人々が歯牙にも掛けないごく小さな物語だ。ただ、この広大な世界に二つとない物語である。
結局のところ、わたしたちはほんの小さな存在なのであって、大きな物語が取りこぼす「大事でない」身の回りの小さな物語だけが、わたしたちの生活に手応えを与えてくれる。私たちが実質的に関われるのは、宇宙の中のほんの小さな一点一点である。けれども、その一点に徹することで世界は発光する。
~~~
生活に手応えを与えてくれる、か。「手応え」。
大切なのは、夢とか目的とか目標とか意味とか、そういうやつの前に「手応え」なんじゃないのか、って思う。そしてその手応えを与えてくれるのは「目標達成」の瞬間などではなくて、「大事でない」身の回りの小さな物語なんだと。
「その一点に徹することで世界は発光する。」
僕にはこの「発光」体験がある。1999年8月1日。竹炭を焼くために、竹を切っていた。
予想最高気温は35度超。早朝から作業していたが、素人だった5名は、午前8時の段階ですでに疲労の色が濃かった。すると、地元のおばあちゃんがやってきて、「何してるんだね~?」と声をかけてきた。(知らない人が竹を切っていたので不信に思ったかもしれない。)
「竹炭を焼くために竹を切っているんです。」
「そうか、暑いのに大変だね~」
と言い残し、おばあちゃんは去っていった。
10分後。
おばあちゃんは戻ってきた。手にトマトの入った袋を下げて。
このタイミングで休憩することした。
トマトをかじった。顔を見合わせた。
世界が輝いて見えた。
このために畑始めたんだ、って思った。
日々の暮らしの中には、世界が「発光」する瞬間がある。それは本当に取るに足らないささいなことなのだろう。
そんな「発光」の瞬間を、この町の中学生高校生たちと、紡いでいきたいとあらためて思った。
この本を紹介してくれた「ウチノ食堂」さんありがとうございました。
ようやく読めました。




