2019年02月27日
「委ねる」という「創造的脱力」
本屋であることの意味は「委ねられる」ことだと思った。
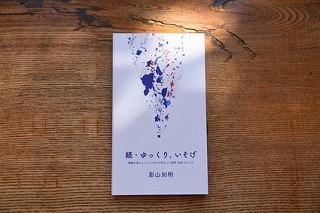
「続・ゆっくり、いそげ」に出てくるおでんの話が好きだ。
ダイコンも、昆布も、厚揚げも、
場(つゆ)に溶けているというか、
一部は活かされ、一部は貢献している。
その度合いは、場に委ねられている。
目的をもって始めないこと
課題を解決しないこと
は、若者と活動するときの重要なことだと
10月に気付いた。
「いま」を大切にすること。
「いま」を未来のための手段にしないこと。
「就活の違和感」の多くも、
そういうところに起因しているのではないか。
自らを「商品化」して売り込むこと。
そしてそれは「交換可能」であること。
常に「就職」というゴールに向かっていること。
そして何より、
「就活」のコミュニケーションがフラットではないこと。
フラットじゃないコミュニケーションからは
「創造」「学び」は生まれにくいこと。
だから、そのプロセスが楽しくないこと。
本屋は委ねる。
立ち飲み屋も委ねる。
ワークショップも委ねる。
僕はそういうのが好きなのだろうなと思った。
「委ねる」ことで、そこに「予測不可能性」が生まれて、
その「予測不可能性」の前で、人はフラットになる。
目標を持って、その達成に向けて進んでいる場合、
「予測不可能性」は排除すべき「ノイズ」でしかない。
タイトなスケジュールの中で、
そのゴールを達成しようとしている中で
失われていく「ノイズ」
http://hero.niiblo.jp/e488367.html
(18.11.7 挑戦するな、実験せよ)
に取り上げた本「情報生産者になる」で
上野千鶴子さんは、
「情報はノイズから生まれます。ノイズとは違和感、こだわり、疑問、ひっかかり・・・のことです。」
「情報とは、システムとシステムの境界に生まれます。複数のシステムの境界に立つ者が、いずれをもよりよく洞察することができるからです。」
と言う。
そうそう。
そこから「情報」が生まれ、「情報」から「創造」が生まれる。
そしてそれこそが「学ぶ楽しさ」
そのものなのではないかと思う。
だから、「委ねる」ことだと思う。
自分が目標を決めて進む「キャリアデザイン」ではなく、
流れに身を委ねてみる「キャリアドリフト」。
そこから感じた「ノイズ」をキャッチして、
次のステージへ進む。
たぶんそういうこと。
僕がつくりたいのは、
「委ねる」という「創造的脱力」
だから、アウトプットの形は、
本屋と立ち飲みとワークショップ含めた場のデザインになるのかもしれません。
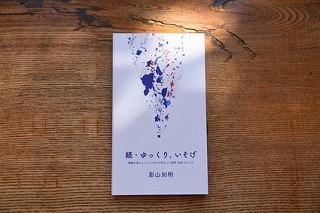
「続・ゆっくり、いそげ」に出てくるおでんの話が好きだ。
ダイコンも、昆布も、厚揚げも、
場(つゆ)に溶けているというか、
一部は活かされ、一部は貢献している。
その度合いは、場に委ねられている。
目的をもって始めないこと
課題を解決しないこと
は、若者と活動するときの重要なことだと
10月に気付いた。
「いま」を大切にすること。
「いま」を未来のための手段にしないこと。
「就活の違和感」の多くも、
そういうところに起因しているのではないか。
自らを「商品化」して売り込むこと。
そしてそれは「交換可能」であること。
常に「就職」というゴールに向かっていること。
そして何より、
「就活」のコミュニケーションがフラットではないこと。
フラットじゃないコミュニケーションからは
「創造」「学び」は生まれにくいこと。
だから、そのプロセスが楽しくないこと。
本屋は委ねる。
立ち飲み屋も委ねる。
ワークショップも委ねる。
僕はそういうのが好きなのだろうなと思った。
「委ねる」ことで、そこに「予測不可能性」が生まれて、
その「予測不可能性」の前で、人はフラットになる。
目標を持って、その達成に向けて進んでいる場合、
「予測不可能性」は排除すべき「ノイズ」でしかない。
タイトなスケジュールの中で、
そのゴールを達成しようとしている中で
失われていく「ノイズ」
http://hero.niiblo.jp/e488367.html
(18.11.7 挑戦するな、実験せよ)
に取り上げた本「情報生産者になる」で
上野千鶴子さんは、
「情報はノイズから生まれます。ノイズとは違和感、こだわり、疑問、ひっかかり・・・のことです。」
「情報とは、システムとシステムの境界に生まれます。複数のシステムの境界に立つ者が、いずれをもよりよく洞察することができるからです。」
と言う。
そうそう。
そこから「情報」が生まれ、「情報」から「創造」が生まれる。
そしてそれこそが「学ぶ楽しさ」
そのものなのではないかと思う。
だから、「委ねる」ことだと思う。
自分が目標を決めて進む「キャリアデザイン」ではなく、
流れに身を委ねてみる「キャリアドリフト」。
そこから感じた「ノイズ」をキャッチして、
次のステージへ進む。
たぶんそういうこと。
僕がつくりたいのは、
「委ねる」という「創造的脱力」
だから、アウトプットの形は、
本屋と立ち飲みとワークショップ含めた場のデザインになるのかもしれません。
2019年02月22日
「ただいま」って言える場所
茨城大学iopラボ「場づくりラボ」スピンオフ
場づくり公務員と行くWagtail見学ツアーでした。



水戸市南町にあるコワーキングスペースWagtail。
ビジター500円で4時間というコワーキングスペース
http://www.wagtailmito.jp/
会員になると、イベントスペースも無料で使えるという
これ、近くにあったらいいなあと思える。
いちばんよかったのはハードが立体的だったこと。
もともと洋服屋さんだったところなので
フロアの仕切りがオープンになっていて、アイデアが浮かびそう。
そんな見学ツアーのあとで小泉さんのお話。
~~~以下メモ
創業・副業支援:社会保険料を1.5倍払ってね。
ワグテイル:公設(水戸市)民営(公社)
場にいない「場づくり」の難しさ
企業創業支援っていうマジの人だけに特化しない
やりたいけど、どうしようかなあという人に使ってもらう
畑をやる部活:ローカルならでは。
飲み会以外のコミュニケーションのデザイン。
「地域」と「行政」を結ぶ価値
場づくりは、結ぶこと
公務員=ジェネラリストが求められる。
最近は中途採用が増えている。
中途専門職員:公募しなくていい。
唯一の価値:なくなった。
「価値はなんだっけ?」と考え始めている。
水戸だけではおさまりきれない。
価値の考え方を再構築する。
働くと住むをもっと自由に。
好きなまちで仕事をしたい。
拠点=ただいまって言える場所。
~~~ここまでメモ
小泉さんのお話、おもしろかったなあ。
公務員っていう立場とか、自分のおかれている環境とかを
デザインしているなあと思った。
ワグテイルの仕組みも
公設民営っていうことでのイベントの自由度が
上がったりして、仕組みとして面白いなあと思った。
僕も「本屋のつくり方講座」をやろうと思います。
ありがとうございました。
場づくり公務員と行くWagtail見学ツアーでした。



水戸市南町にあるコワーキングスペースWagtail。
ビジター500円で4時間というコワーキングスペース
http://www.wagtailmito.jp/
会員になると、イベントスペースも無料で使えるという
これ、近くにあったらいいなあと思える。
いちばんよかったのはハードが立体的だったこと。
もともと洋服屋さんだったところなので
フロアの仕切りがオープンになっていて、アイデアが浮かびそう。
そんな見学ツアーのあとで小泉さんのお話。
~~~以下メモ
創業・副業支援:社会保険料を1.5倍払ってね。
ワグテイル:公設(水戸市)民営(公社)
場にいない「場づくり」の難しさ
企業創業支援っていうマジの人だけに特化しない
やりたいけど、どうしようかなあという人に使ってもらう
畑をやる部活:ローカルならでは。
飲み会以外のコミュニケーションのデザイン。
「地域」と「行政」を結ぶ価値
場づくりは、結ぶこと
公務員=ジェネラリストが求められる。
最近は中途採用が増えている。
中途専門職員:公募しなくていい。
唯一の価値:なくなった。
「価値はなんだっけ?」と考え始めている。
水戸だけではおさまりきれない。
価値の考え方を再構築する。
働くと住むをもっと自由に。
好きなまちで仕事をしたい。
拠点=ただいまって言える場所。
~~~ここまでメモ
小泉さんのお話、おもしろかったなあ。
公務員っていう立場とか、自分のおかれている環境とかを
デザインしているなあと思った。
ワグテイルの仕組みも
公設民営っていうことでのイベントの自由度が
上がったりして、仕組みとして面白いなあと思った。
僕も「本屋のつくり方講座」をやろうと思います。
ありがとうございました。
2019年02月21日
「活性化」ってなに?

「インターンシップ・地域活動フォーラム」ににいがたイナカレッジチームと行ってきました。
~~~ひとまずメモ
「活性化ってなに?」っていう問いをまず考えないといけない。
イナカレッジ:地域と自分の価値探究コミュニティ
「価値は何か?」っていう問いを企業も地域も学生も自らに問いかけること
⇒自信ないけど表現する⇒価値を再発見する
自分×地域で価値観・暮らし方・仕事を学びあい、価値を探求する。
イナカレッジOB工藤くん
就職の非現実感と就活の拒絶感。
自分は何がしたいんだろう?
感情が揺れ動いていた。感情のプール。
地域の人とのかかわり→僕のことを認めてくれた。
自分が人生楽しく生きるためには何が必要なんだろう?
⇒関係性。認めてもらう、こと。
それだけでは生きられないけど、それがあれば生きられるもの。
米を売る:難しい⇒何もできねえよ。
米、水、土がどう違うのか?を説明した。
「学びのスタンス」の学びになった。
興味なかったものに対して、どう学んでいくか?
⇒だんだん面白くなっていった
イナカレッジの効果
・集落の人たちの会話ができた。
・お母さんや若い人の出番ができた。
・役場との距離が縮まった。
・こんなに大学生と仲良くなると思わなかった。
くろださんの感想
・生きてるっていいなって思えた。心の余裕ができた。
集落のおばあちゃんが「地域のためにできることはないか?」って聞いてきたのは、
「地域に来る大学生のために何かできることはないか?」っていう問いから始まっているのではないか。
イナカレッジ受け入れ地域の人の言葉。
「地域活性化」は、「起業」とか「商品開発」ではなく、世代をこえて笑いながら話ができること。
そうそう。「活性化」って結果じゃない。
・課題を解決しないこと
・目的をもってはじめないこと
価値は、地域と、その活動そのものの中にある。
地域の場づくりにとって必要な大学生による「前向きな空気ができる」
っていうのは福島白河・コミュニティカフェエマノンのときに思った「ベクトル感」のことじゃないかな。
~~~ここまでメモ。
あとはイナカレッジ金子さんが書いてきたペーパーがすごいので、
それはのちほど共有します。
イナカレッジってなんだろう?って。
地域の当事者を増やす。
それは中越地震の復興というフィールドからやってきた
イナカレッジの原点なのだと思う。
それは「地域づくり」(あえて使う)
にとっても同じことで、
そこに対して「大学生」というコミュニケーションツールを
投入することで、地域の当事者が増えていくということが
起こっているのだろうと思う。
「活性化」は
起業や商品開発のことではなくて笑いながら話ができること。
だと。
そうそう。
ひとりひとりがつくるひとりになること。
それを繰り返していくこと、なのかもしれません。
2019年02月18日
劇場とサーカス
山田正史さん。
元ツルハシブックス「山田店長」。
現在は
「古本詩人ゆよん堂」店主。
ゆよん堂の由来は
中原中也の詩「サーカス」。
「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」
からだ。
詩をメインに取り扱う古本屋さん。
「生きるって何か?」
と問いかけてくる。
テーマは「サーカス」。
そして、「サーカス」と言えば、
道化師=クラウンの存在は欠かせない。
そういえば、僕の本屋としての出発点は
「ホスピタルクラウン」(大棟耕介 サンクチュアリ出版)
だったのだけど。

本屋は、サーカス小屋なのかもしれない。
そう思った。
僕はずっと劇場だと思っていたのだけど。
それはすごく瞬間的な切り取りなのかもしれない。
もう少し長いスパンというか、
そこで過ごす時間という切り口で切ってみると、
「サーカス」のようになるのではないか、と。
そしてそこに必要なのは道化師=クラウンの存在。
いかに相手を笑わせるか、
つまり、心を開かせるか、ということ。
そうやって、サーカスの会場の人たちが
観客から共演者に変わっていく。
いや、本屋というより、
世の中は巨大なサーカス小屋なのかもな。
サーカスを見に来ただけのお客と
いかに共演者になるのか。
「本屋」そのものがクラウンになるんじゃないか。
そうやって社会と、世の中と対話しようとしているのかもしれない。
元ツルハシブックス「山田店長」。
現在は
「古本詩人ゆよん堂」店主。
ゆよん堂の由来は
中原中也の詩「サーカス」。
「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」
からだ。
詩をメインに取り扱う古本屋さん。
「生きるって何か?」
と問いかけてくる。
テーマは「サーカス」。
そして、「サーカス」と言えば、
道化師=クラウンの存在は欠かせない。
そういえば、僕の本屋としての出発点は
「ホスピタルクラウン」(大棟耕介 サンクチュアリ出版)
だったのだけど。

本屋は、サーカス小屋なのかもしれない。
そう思った。
僕はずっと劇場だと思っていたのだけど。
それはすごく瞬間的な切り取りなのかもしれない。
もう少し長いスパンというか、
そこで過ごす時間という切り口で切ってみると、
「サーカス」のようになるのではないか、と。
そしてそこに必要なのは道化師=クラウンの存在。
いかに相手を笑わせるか、
つまり、心を開かせるか、ということ。
そうやって、サーカスの会場の人たちが
観客から共演者に変わっていく。
いや、本屋というより、
世の中は巨大なサーカス小屋なのかもな。
サーカスを見に来ただけのお客と
いかに共演者になるのか。
「本屋」そのものがクラウンになるんじゃないか。
そうやって社会と、世の中と対話しようとしているのかもしれない。
2019年02月14日
プロジェクトと自分の関係
2月10日の「OMO Niigata」のプレゼン。
いかに自分を掘っていけるか、
そしてそれを面白がれるか、
でプレゼンの共感度が変わるんだと実感した。
昨日は、電車の中で

「beの肩書き」(兼松佳宏 グリーンズ)
を読みつつ、
午後は、「マイプロ」
https://my-pro.me/
の話を聞いた。
そのプロジェクトは、
自らの中にあるどんな経験から始まっているのか?
なぜ、そう思うのか?
を受講生と一緒に考えていくというスタイル。
「自己開示」を促す
場の力の高め方がすごいなと思った。
(しかも東京のオフィスで)
そして今日はふたたび
「beの肩書き」を読み直す。
僕も2018年頭にやってみたのだけど。
その際のワークレシピはこちら
https://medium.com/be%E3%81%AE%E8%82%A9%E6%9B%B8%E3%81%8D-%E6%8E%A2%E7%A9%B6%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89/be-for-new-year-7c1122061824
これ、問いが素敵だなあと。
よく生きるってなんだろう?
って考えさせられる。
「beの肩書きインタビュー」
5つの質問
1 自分では当たり前でも、2人以上の人から「すごいね」と言われたことは?
旅行プランを立てることかなあ。
食べログで素敵な店を探す方法とか。
アイデアだしたりとか。
2 こういう瞬間こそが幸せだなあと思うことは?
これは「場」を作りながら外から見ているとき。
(ワークショップの振り返りしているとき、とか)
あとは歴史ある食堂で常連の人たちと一緒にご飯食べているとき、とか。
3 時間が経つのも忘れるくらい、情熱を持って取り組んでいることは?
「違和感を解き明かす」っていうこと?
自分で問いを立てて、それに仮説を立てていく、みたいな。
4 何かに感動したときに、思わずやってしまいそうなことは?
ツイッターにつぶやく。
翌日ブログにする。
5 この人生でやっておきたいなあと思うことは?
本を残す。
素人でもやれる本屋の仕組みを残す。
ってまあ、こんな感じ。
兼松さんは大切なのは
「リフレーミング」だという。
これは心理学用語で
「無意識下の解釈の枠組み(フレーム)に気づき、
異なるとらえ方を通じて、新たな意味を構築すること」
のこと。
たしかに、
インタビューでの問いとか、他者との対話によって、
見方が変わることってある。
僕も、12月にとある募集の要項を記入していて、
「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン」が得意だと認識したのだけど、
「続・ゆっくり、いそげ」によって、
それは、コミュニケーションデザインが得意なのではなくて、
「フラットじゃないコミュニケーション」の現場にいることが
何より耐えられなかったからだと気づいた。
それくらい、プロジェクトと自分っていうのは
非常に近いところにあるのだと。
それをどのように掘り下げていくか。
そしてそこに「場のチカラ」の力を借りるか。
そうやって、共感されるプロジェクトが
生まれていくのだろうなと思った。
プロジェクトメンバーのひとりとして、そこにいること。
場のチカラに貢献すること。
プロジェクトリーダーだけじゃなくて、
メンバーも自らのバックボーンに気づくこと。
そうやって生まれていくプロジェクト。
みんなのbeが合わさって、
ひとつのプロジェクトになっていくような、
そんな「場」を作りたいなあと思うのです。
いかに自分を掘っていけるか、
そしてそれを面白がれるか、
でプレゼンの共感度が変わるんだと実感した。
昨日は、電車の中で

「beの肩書き」(兼松佳宏 グリーンズ)
を読みつつ、
午後は、「マイプロ」
https://my-pro.me/
の話を聞いた。
そのプロジェクトは、
自らの中にあるどんな経験から始まっているのか?
なぜ、そう思うのか?
を受講生と一緒に考えていくというスタイル。
「自己開示」を促す
場の力の高め方がすごいなと思った。
(しかも東京のオフィスで)
そして今日はふたたび
「beの肩書き」を読み直す。
僕も2018年頭にやってみたのだけど。
その際のワークレシピはこちら
https://medium.com/be%E3%81%AE%E8%82%A9%E6%9B%B8%E3%81%8D-%E6%8E%A2%E7%A9%B6%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89/be-for-new-year-7c1122061824
これ、問いが素敵だなあと。
よく生きるってなんだろう?
って考えさせられる。
「beの肩書きインタビュー」
5つの質問
1 自分では当たり前でも、2人以上の人から「すごいね」と言われたことは?
旅行プランを立てることかなあ。
食べログで素敵な店を探す方法とか。
アイデアだしたりとか。
2 こういう瞬間こそが幸せだなあと思うことは?
これは「場」を作りながら外から見ているとき。
(ワークショップの振り返りしているとき、とか)
あとは歴史ある食堂で常連の人たちと一緒にご飯食べているとき、とか。
3 時間が経つのも忘れるくらい、情熱を持って取り組んでいることは?
「違和感を解き明かす」っていうこと?
自分で問いを立てて、それに仮説を立てていく、みたいな。
4 何かに感動したときに、思わずやってしまいそうなことは?
ツイッターにつぶやく。
翌日ブログにする。
5 この人生でやっておきたいなあと思うことは?
本を残す。
素人でもやれる本屋の仕組みを残す。
ってまあ、こんな感じ。
兼松さんは大切なのは
「リフレーミング」だという。
これは心理学用語で
「無意識下の解釈の枠組み(フレーム)に気づき、
異なるとらえ方を通じて、新たな意味を構築すること」
のこと。
たしかに、
インタビューでの問いとか、他者との対話によって、
見方が変わることってある。
僕も、12月にとある募集の要項を記入していて、
「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン」が得意だと認識したのだけど、
「続・ゆっくり、いそげ」によって、
それは、コミュニケーションデザインが得意なのではなくて、
「フラットじゃないコミュニケーション」の現場にいることが
何より耐えられなかったからだと気づいた。
それくらい、プロジェクトと自分っていうのは
非常に近いところにあるのだと。
それをどのように掘り下げていくか。
そしてそこに「場のチカラ」の力を借りるか。
そうやって、共感されるプロジェクトが
生まれていくのだろうなと思った。
プロジェクトメンバーのひとりとして、そこにいること。
場のチカラに貢献すること。
プロジェクトリーダーだけじゃなくて、
メンバーも自らのバックボーンに気づくこと。
そうやって生まれていくプロジェクト。
みんなのbeが合わさって、
ひとつのプロジェクトになっていくような、
そんな「場」を作りたいなあと思うのです。
2019年02月13日
「そもそも自分とは何か?」という問い自体が無効化されていく

「beの肩書き」(兼松佳宏 グリーンズ)
https://greenz.jp/benokatagaki/
大阪・スタンダードブックストア心斎橋で購入。
いっつも、いい本あるなあと。
すごいなあと。
僕にいちばん合っている本屋さんかもなあ。
ということで、いつもの読書メモ
~~~ここからメモ
そもそも肩書きの役割とは、自分と他者とのコミュニケーションをより円滑にするために、自分のことについて端的に知ってもらうための糸口を提供することです。
セラピストとしての運転手さん。
職人としての運転手さん。
doは同じだったとしても、ひとりひとりのbeは違うのです。
肩書きを与えるのは誰か?
「夢を叶える」とはどういうことか?
かつて「小説家になりたい」という夢を持っていたけれど、いまは別の仕事をしている、という方であっても、「商品開発担当」として商品のストーリーを組み立てたり、「保育士」としてオリジナルな絵本をつくったりしているとしたら、その夢は叶っていると言えるかもしれません。
doの肩書き×beの肩書きの意外な組み合わせこそ、ひとりひとりの個性そのものなのです。
デザイナーである限り、変わり続けなきゃならない宿命がある。
「一生続けたい」と思えるくらい好きな分野で、具体的ニーズがあって、勝手に解釈される可能性がある肩書き。それが発酵デザイナー。
僕自身が発酵デザイナーとは何なのかよくわかっていなくて。年に一度くらいアップデートしている。
「そもそも自分とは何か」という問い自体が無効化されていく。
~~~ここまでメモ
うわー!って(笑)
言語化できない(笑)
問いに詰まっているなあと。
「肩書き」とか「夢を叶える」っていう意味が変わってきているのだと。
小倉ヒラクさんの
「発酵デザイナー」っていう肩書自体が問いになっているし、
その問いの答え方によって、
いろんな仕事が生まれていくんだなと。
「仕事をつくる」ってそういうことなのか、と。
面白かった。
昔の「肩書き」って(今もそうかもしれないけど)、
そんなに変わらないことを前提につけている。
それが「doの肩書き」なんだろうな。
いま、doは変わりゆく。
同じことをずっとやっているっていうのは、なかなかない。
それを「13歳のハローワーク」は
プロフェッショナルと呼んだのだろうけど。
だからこそ、人はbeの肩書きを必要としている。
夢の叶え方、としても、
その仕事っていうことじゃなくて、
上に書いてあるような「小説家」とか。
そういえば、僕も小学生のときに、「つくば科学万博」に
何度か行って、化学者になりたかった。
実験室で白衣来て、試薬を混ぜ合わせるやつ。
で、爆発してドリフみたいな頭になるの。(笑)
それって今でいうところの本屋かもしれないですよね。
人と本や人と人を本屋の中で混ぜ合わせたいのですよ。
大学生と田舎とか。
意外に、beの肩書きへと落とし込んでいけば、
人は一貫している、というより、一貫せざるを得ないんじゃないですかね。
そうすると、僕自身のbeの肩書きはなんだろう?っていうね。
まだ、この本は読み始めたばかりなのだけど、
小倉ヒラクさんのところはめちゃめちゃよかったなあ。
★「そもそも自分とは何か?」という問い自体が無効化されていく★
そういう状態にあることを、
人は天職というか、「天職にある」と感じるのかもしれない。
2019年02月12日
なんのために、この船に乗ったんだっけ?

「常識的で何か問題でも?」(内田樹 朝日新書)
これは、だいぶ、きますね。
きてますね。
AERAの連載の再編集。
いちばん印象に残ったのは、
戦時中の太宰治の話。
P85「戦時下、太宰の文学的抵抗が見せたもの」
~~~以下引用
でも、私がもっとも興味を引かれたのは、多くの作家が書くことをやめてしまった戦時下に太宰が「駈込み訴へ」「津軽」「新釈諸国噺」「お伽草紙」など代表作のほとんどを書いていたという歴史的事実のほうである。
高橋によれば、それは作家がいったい何を言いたくてそんなことを書いたのか、韜晦なのか、迂回的な戦意高揚なのか、さっぱり底の読めないこれらの作品群こそが文学の独壇場だったからだ。
戦争とは、すべてのものを敵か味方かに切り分け、その上で「敵を殺す」という恐ろしいほど単純な枠組みの中に世界を縮減する企てだ。
戦争に真に反対できるのは「個別性」と「複雑性」の原理だけだと私も思う。それは「私が何ものであり、私が何を言いたいのか」を誰にも決定させないという太宰の文学的抵抗のうちにひとつの理想を見出すことである。文学に一票。
~~~以上引用
太宰の文章は、「よくわからなかった」。
戦争に反対なのか、戦意高揚なのか、
まったくわからなかった。
そこが文学の奥深さだった。
戦争とは究極の二元論、単純化である。
その反対を行こうとすれば、
多元で、複雑系の中に身を置くことだと。
なるほど。
まさにこれは現代とは逆だなあと思った。
そして、この本のラストのあとがきに、内田さんは書いている。
~~~ここからさらに引用
官邸が熟知しており、僕が過小評価していたのは、現代日本人が厳密で客観的な格付けシステムに嗜癖しているということでした。
入力と出力の間にシンプルな相関関係がある仕組みは、「ペニー・ガム・システム」とも呼ばれます。ペニー硬貨を投じると必ずガムが出て来る自動販売機の仕組みです。このシステムを現代人は偏愛しております。特に若い人たちにこの傾向が顕著である。
若い世代に「格付けシステム」への偏愛があることをはじめて僕が感じたのは、20年ほど前のフランス文学会のことでした。
フランス文学会では、その頃から研究発表が「19世紀文学」の分科会に異常に集中するようになりました。
この3分野には世界的なレベルの日本人の「大家」がそろっていたということです。ですから、その分野での研究発表に対する客観的評価はたいへん信頼性が高かった。
そして若手の研究者にとっては、これらの分野の世界的権威の諸先生に高く評価されたら、大学のテニュアのポストに指先がかかったということを意味します。
査定の厳正さを優先的に配慮すると、若手の研究者は「できるだけみんながよく知っている分野」を選択することになります。でも、学問研究においてそれをやってしまうと、研究領域の多様性・豊饒性を考えるとよいことではありません。
でも、研究についての精度の高い格付けを優先させると、そうせざるを得ない。その結果、「みんなができることを、みんなよりうまくできるようになること」を若手の研究者たちが競うようになった。
そうして、仏文学は素人から見ると、面白くもおかしくもない「内輪のパーティ」になってしまった。気が付いたら、大学の仏文科に進学してくる学生がいなくなってしまった。
研究者たちが精度の高い格付けシステムを要請したのは、フェアなポスト配分という点では合理的な解でした。でも、格付けの安定性だけを配慮しているうちに、按分されるもともとの原資は、誰がどうやって創り出すかについては考えるのをやめてしまった。
フランス文学研究の原資とは何でしょうか。
それは、「フランス文学って面白い。もっと知りたい。専門家の話を聴きたい」という大量の「非専門家」たちです。それ以外にありません。
そのような素朴な心情を軽んじて、専門家同士の競争に熱中していたら、ある時点で奪い合うリソースそのものがなくなってしまった。「誰かがみんなのためにそのような特異な専門分野を担当する必要がある。」という集団的合意の大切さを忘れてしまっていたからです。
精度の高い格付けを求める心性が過度になると、専門家たちが「誰のために・誰に代わって」この仕事をしているのかという問いを自分に向けることができなくなってしまうという痛ましい事実を教えられました。
人間はひとりひとり特異な個性と才能に恵まれている。それを生かして「余人をもって代え難い」タスクを引き受けることが人としての生き甲斐じゃないかということです。
全員が「他の人ができないことができる」ようにばらけている集団では、たしかにメンバーの格付けはむずかしい(というか不可能)でしょう。でも、そういう集団はさまざまなタイプの危機に対応できます。危機耐性ではすぐれています。
その逆に、メンバーの全員が同じ種類の知識や技能しか持たず、量的な差があるだけの集団を考えてみてください。たしかに全員が規格化されていれば、集団内部での格付けは簡単です。
でも、集団として生き延びる力は弱くなる。「みんなができること」以外の知識や技能を要求する問題には誰も対応できないからです。
僕は集団として生き延びるためにさまざまな社会的能力は開発されるべきであると信じています。ですから、集団内部的な格付けを容易にするために成員を規格化することにはつよく反対します。集団が弱くなるからです。
でも、僕のように考える人は今の日本では圧倒的な少数意見です。ほとんどの人は「誰でもできることを他の人よりうまくできる」という相対的な優劣の競争で上位にランクされることに熱中している。
~~~ここまでさらに引用
いやあ、抜粋できなくて、
またしても全文書いてしまった。
これはリアルだなあと。
そしてわかりやすい他者評価を過度に求めてしまう
大学生の不安にも当てはまるなあと。
アイデンティティの不安と、他者評価への依存。
これには相関関係があると思う。
自らのアイデンティティを
他者からの、それも権威ある何者かからの評価に
頼ってしまうこと。
そのスパイラルこそが、
大学生を生きづらくしているのだと僕は思う。
上記のフランス文学会で起こっていること。
「評価しないと出世できない」
これはある意味事実なのだろう。
そしてその環境に適応する人々は、
「お客はだれか?」という問いをだんだんと失わせていった。
いつのまにか、お客(幸せにする対象)がいなくなっていた。
「課題解決」や「目標達成」は予測可能な未来である。
僕はエンターテイメントの本質は「予測不可能性」にあると思っていて、
だからこそ「課題解決」や「目標達成」そのものは
つまらないのだと思う。
達成した先にある未来が、
せいぜい「予想以上にほめられる」ことくらいだからだ。
日曜日のOMOのプレゼンテーションでも、
その先にある未来に予測不可能なワクワクがあった
新潟の水の上を生かすプランがグランプリをとった。
なんのために、この船に乗ったんだっけ?という問いと、
その先にある予測不可能な何かに対して、人はワクワクするのだろうと思った。
僕たちは生き延びるために、何をするのか?
そんな問いをあらためて考えた1冊となった。
2019年02月11日
「明日から何やりますか?」



OMO Niigata vol2のプレゼンを見に行ってきました。
Q:OMOとは...?
A:”ジブンゴト”の問題意識を持ち、行政の縦割組織や民間との壁を越え、”本気で”課題解決に取り組むマインドを持った自治体職員のための官民協働プロジェクトです。「One for a Million. a Million for One」の頭文字を取って名付けられました。
だそうです。
2泊3日(合宿じゃないですけど)
で出てきたNPO立ち上げプランを聞くという場所でした。
印象に残ったプレゼンは
「救急救命士」を地域にひらくっていうプラン。
佐渡こそルイーダの酒場的に
技能をもった人たちとの出会いの場が必要だっていうプラン
「疎開」「防災」「地域間連携」というキーワードで
新潟のフィールドを使って関係人口を育むっていうプラン
「水の上貸します」ということで
新潟湊の水上で泊まったり、演劇やったり、お店やったり、っていうプラン
などなど。
審査員からの質疑応答も面白かった。
一番印象に残った質問が
「明日から何やりますか?」だった。
そっか。
それに答えられない事業は始まらないんだ、と。
これ、2月7日の支援者サミットの話に似てるなと。
http://hero.niiblo.jp/e488865.html
「伴奏型支援」(19.2.9)
出てきたアイデアに対して、
「明日から何やりますか?」
と問うことで、アクションにつながるのでは、と思った。
そしてもうひとつ、印象的だったこと。
「課題解決にフォーカスしすぎて、面白がることを忘れている」
という発言。
面白がれないと、仲間がやってこない。
それもやっぱり事業が始まらない。
たぶん、この2つなのだろうと思った。
課題に対して、どのように面白がれるか?
あるいは面白がることで、結果的に課題を解決できるか?
これって、とても大切なことなのだろうと思った。
クラウドファンディングの支援が集まる方法でもあるなと。
・面白がれるということ
・明日からやることが思い浮かぶということ
この2つはリンクしていると思うけどね。
あと、「疎開ツアーズ」チームの
プレゼンを聞いていて思ったこと。
「価値」をズラすっていうこと。
「関係人口」をどのように増やすか、ってずっとプランを考えていて、
疎開はコンテンツの1つに過ぎなかったのだけど、
発表当日の朝にそれを逆にして、疎開ツアーメインのプランになった。
キャッシュポイントをズラすっていうのはよく聞くのだけど、
「価値をズラす」っていうことも面白いなと。
事業価値をたくさんの人に知ってもらい、
結果、課題が解決するということになるのだろうなと思った。
関係人口を目的にしないで、
いざというときに備えるためのプラン。
特に自治体職員は、非常時には不眠不休の働きを
することになる可能性が高いので、このようなプランが有効なのだろうと思った。
結果、「関係人口」は増えるし、
子どもの教育上にとっても大きな学びがあるように思うし、
「第3の大人」にも出会えるなと。
そうやって価値をズラしていくこと。
そして、今回もあらためて思ったのは
たった1人の思いから始まる、
たった1人の問いから始まる、
ということ。
7日に水戸部さんがプレゼンしていたように、
個人のパーソナルな出来事、原体験にもっと迫ってもいいのではと思った。
・救急救命士の思い
・佐渡には魅力的な人がたくさんいるのだという思い
・新潟の海の魅力を引き出したいという思い
・東日本大震災の被災自治体の職員の声
そんなリアルから始まった事業・プレゼンには力があった。
そして。
もうひとつ考えたこと。
事業の始まりには、
「顧客」アプローチと「価値」アプローチ
があるのだと。
よくやられている「課題解決」っていうのは、
「価値アプローチ」であり、
その中でも、マイナスを0またはプラスにするので、
ワクワクが少ないのかもしれないなと。
そこで「面白がれるかどうか。」が重要になる。
「顧客」アプローチの中に、自らの過去を掘り、源泉を探す、みたいなのがあるのだろうと。
最初のお客が自分(過去の自分)であるっていうアプローチ、
もしくはリアルに出会った人がお客である、っていう2つのアプローチがある。
グランプリの「SEA JOINT」のプランは、個人のワクワクから始まっているし、
そんなことできたら楽しいだろうな~っていう面白がれる要素がたくさんあった。
新潟っぽかったし。港湾事務所とか役所の人のほうがつながりやすいだろうし。
たぶん、「顧客」アプローチ
の中でも自らを掘っていく、というのがあって、
それを事業化によって「価値」に変えていく。
(そのプロセスで「課題解決」も起こるかもしれない)
そしてその「価値」をみんなで面白がりながら
事業への参加・参画者が増えていく、という構図なのかなと思った。
順番としては、「顧客」アプローチ(過去・原体験を振り返る)があって、
そこに共感者が増えることで「価値」に変わっていき、
それを面白がれる編集を行って、
事業を行いながら、もういちど「顧客」に届いているか?を
検証していくというサイクルなのではないかなと思った。
「課題解決」から出発しないこと
おもしろがれる要素を作ること。
そして、審査員のこの質問に答えられること。
「明日から何やりますか?」
2019年02月10日
「営み」の中にある「畑」と「本屋」
2018年9月。
大正大学「地域実習」でお邪魔した
柏崎・荻ノ島集落。


そのときのレポート
「地域の個性の構成員になる」(18.9.20)
http://hero.niiblo.jp/e488131.html
7日のフォーラムでもお隣だった
春日さんと共に登壇した橋本さんの話を
思い出していた。
橋本さんは京都府立大公共政策からイナカレッジ長期インターンに参加し、
荻ノ島へ移住、1年目。
「会社ではたらく」よりも「米、野菜を自分でつくって百姓的に生きる」ほうが安定しているのではないか?
いまは5つ以上の仕事をしていると言っていた。
そんな橋本さんのコメントを思い出させるような本にあった。

「常識的で何か問題でも?」(内田樹 朝日新書)
AERAの連載の再編集なのだけど。
内田さんの農業へのまなざし、というか表現力に
うなったのは、この本からだった。
営みと「天の恵み」という贈与と返礼(18.12.14)
http://hero.niiblo.jp/e488552.html
今回も素敵なフレーズがあったので、こちらに引用する。
~~~ここからメモ
文明と自然のインターフェースに立ち、自然からの贈与を人間社会に有用なものに変換する仕事には、人間性の根源に触れる何かがある。
うまく説明できないけれど、そのような場では、たぶん都市とは違う時間が流れているのだと思う。人工的な環境にいる限り決して発動しない脳内部位が活性化し、それまで使うことのなかった知覚が動き出すのではないかと思う。自分の身体が豊かな、手つかずの埋蔵資源で満たされていることに気づく。
自分自身の豊かさに気づくことのほうが、現金収入の多寡よりも大切だと彼らは直感したのだと思う。
~~~ここまでメモ
橋本くんが移住した理由って、
これなんじゃないか。
って思った。
農業(畑をやる)っていうのは、まさにそのような
贈与と返礼のまっただ中で、
自分の身体を使いながら、
自らの埋蔵資源に気づく、という営みなのではないか。
それを都市部で、バーチャルかもしれないけど、
ぎりぎり再現しようと思ったら、
「本屋」になるのではないか、とも思った。
もしかしたら「クルミドコーヒー」もそうなのかもしれない。
カフェのほうが「食べる」という身体性を伴っているし。
「本屋」を再定義すると、
本という先人からの贈与の真っただ中にあり、
その営みに組み込まれるように、
本屋に行き、本を買い、本を読む。
その繰り返しの中で、自分の中の埋蔵資源に気づいていくこと。
そして何かお返しをしなくては、と思うこと。
ああ、その通りだと思った。
「畑」と「本屋」はそういう意味で似ているのだ。
あ、僕が畑をやってから本屋になった理由がもうひとつ
見つかりました。
「営み」の中にある、という身体性を伴う経験が
自分自身やもっと大いなるものとの
コミュニケーションデザインが可能になるからです。
さて。
次は飲食店なのかもしれないな、と予感しました。
大正大学「地域実習」でお邪魔した
柏崎・荻ノ島集落。


そのときのレポート
「地域の個性の構成員になる」(18.9.20)
http://hero.niiblo.jp/e488131.html
7日のフォーラムでもお隣だった
春日さんと共に登壇した橋本さんの話を
思い出していた。
橋本さんは京都府立大公共政策からイナカレッジ長期インターンに参加し、
荻ノ島へ移住、1年目。
「会社ではたらく」よりも「米、野菜を自分でつくって百姓的に生きる」ほうが安定しているのではないか?
いまは5つ以上の仕事をしていると言っていた。
そんな橋本さんのコメントを思い出させるような本にあった。

「常識的で何か問題でも?」(内田樹 朝日新書)
AERAの連載の再編集なのだけど。
内田さんの農業へのまなざし、というか表現力に
うなったのは、この本からだった。
営みと「天の恵み」という贈与と返礼(18.12.14)
http://hero.niiblo.jp/e488552.html
今回も素敵なフレーズがあったので、こちらに引用する。
~~~ここからメモ
文明と自然のインターフェースに立ち、自然からの贈与を人間社会に有用なものに変換する仕事には、人間性の根源に触れる何かがある。
うまく説明できないけれど、そのような場では、たぶん都市とは違う時間が流れているのだと思う。人工的な環境にいる限り決して発動しない脳内部位が活性化し、それまで使うことのなかった知覚が動き出すのではないかと思う。自分の身体が豊かな、手つかずの埋蔵資源で満たされていることに気づく。
自分自身の豊かさに気づくことのほうが、現金収入の多寡よりも大切だと彼らは直感したのだと思う。
~~~ここまでメモ
橋本くんが移住した理由って、
これなんじゃないか。
って思った。
農業(畑をやる)っていうのは、まさにそのような
贈与と返礼のまっただ中で、
自分の身体を使いながら、
自らの埋蔵資源に気づく、という営みなのではないか。
それを都市部で、バーチャルかもしれないけど、
ぎりぎり再現しようと思ったら、
「本屋」になるのではないか、とも思った。
もしかしたら「クルミドコーヒー」もそうなのかもしれない。
カフェのほうが「食べる」という身体性を伴っているし。
「本屋」を再定義すると、
本という先人からの贈与の真っただ中にあり、
その営みに組み込まれるように、
本屋に行き、本を買い、本を読む。
その繰り返しの中で、自分の中の埋蔵資源に気づいていくこと。
そして何かお返しをしなくては、と思うこと。
ああ、その通りだと思った。
「畑」と「本屋」はそういう意味で似ているのだ。
あ、僕が畑をやってから本屋になった理由がもうひとつ
見つかりました。
「営み」の中にある、という身体性を伴う経験が
自分自身やもっと大いなるものとの
コミュニケーションデザインが可能になるからです。
さて。
次は飲食店なのかもしれないな、と予感しました。
2019年02月09日
「伴奏型支援」
2月7日(木)@新潟県庁
「地域づくり支援者サミット」に出席してきました。
大正大学「地域実習」でご一緒した
柏崎まちづくりネットあいさの水戸部さんに注目していて、
そのプレゼンが聞きたかったので。
1 新潟空港でバス停までダッシュ 12:50
2 新潟駅で南口から万代口へダッシュ 13:25
3 新潟県庁で西回廊講堂へダッシュ13:45
で、なんとか水戸部さんのプレゼン2分前に会場入り。
受付してなくてすみません。


すごい人数でした。
まあ、3分の2は自治体の人でしたけど。
登壇者はフレッシュな人たちだったなあと。
柏崎の水戸部さん
糸魚川の屋村さん
川口の砂川さん
新鮮だったなあと。
たぶん、こっち系のイベントには
ヒーローズファーム始めてから行っていないから
10年以上ぶりになるのではないかな。
しばらく行かないうちに、自分が若手じゃなくなってた。(笑)
一番の感想は、特に上の3人みたいに
現場で体当たりでやってきた人たちの生の声って
めちゃめちゃ響くなあと。
実践者の声はリアリティが違うなと。
3人のお話を中心にメモ。
~~~ここからメモ
まちのプレイヤーを増やす。
キーワードは「欠落」と「有意味性」。
「欠落を抱えている人」を探す。
それをどう「欠落を補う人」に変えるか?
欠落を補う「有意味性」
「あなたはなぜそれをやらなければならないのか?」に対する答え。
有意味性とはなにか?
・過去に欠落や喜怒哀楽、得意不得意を見つけ、自己開示する
・なぜか?には理由があり、理由である原体験は模倣できない
そこから導かれる答えはあなたにしかないストーリーになる。
そこに有意味性を見つけること。
まちにプレイヤーが少ないこと
↑
まち・社会とふれる機会が少ないこと
↑
まちでの生き方の選択肢が少ないこと
⇒まちにふれて自分の生き方をふれる機会が必要
学校教育のインプットと社会で求められるアウトプットのギャップ
「協調性」「空気を読む力」⇒「独自性」「当たり前を疑う力」
「まんべんなく能力を伸ばすバランス型人材」⇒「特徴や個性のある特化型人材」
大きなギャップがある。
「チェンジメーカー」柏崎の中学生から大学生までの次代の担い手にソーシャルアントレプレナーシップを持ってもらうための教育プログラムを提供することで、柏崎の未来を担う起業家の発掘を目指すローカルプロジェクト。
「民間メンター」:地域の起業家の伴走型支援、
「社会とお金」:地域課題解決を事業化する方法、
「起業家精神」:感じたこと、考えたことから自主的・主体的に行動すること
↑ここまで柏崎まちづくりネットあいさの水戸部さんのプレゼンメモ。
めちゃめちゃ共感しました。
そういう「場」を地域でいかに作れるか、っていうこと。
そして、なんといっても、昨日の地域づくり支援者サミットの主演は、屋村さんでした。
面白かったし、プレゼンかっこよかった。
旦那さんの「スライド10枚以上残して終わる人なかなかいませんよ」
っていうコメントもさらによかった。笑
ということで、屋村さんプレゼンメモ
「波と母船」(糸魚川市木浦地域)
2018年春、長者温泉ゆとり館を引き継ぐ。
致しません。
地域起こし
地域活性化
そこに地域住民への思いやりはある?
若者に「あなたたちの地域は何もない」と言われたら悲しい。
「そのままの知恵、暮らし」を宝ものにするだけ。
地域・残し
「変えたほうがいい」と思っているものはありません。
「見方、見る方向が変わっているだけ」です。
今あるその暮らしを学んで、磨いて輝かせて
私たち世代から次世代に残してつないでいくだけ。
それがこの地域を「のこす」ことにつながると考えています。
★ここ、ホントそれ、って。
「地域」ってなに?
いままでの「地域づくり」は、
実体のない「地域」を支援してきたのではないか。
地域って、ひとりうひとりの暮らしの集合体だろうと。
ひとりひとりをリスペクトしているのかっていう問いに詰まってた。
「地域を置いてきぼりにしない」を学ぶ。
地域への説明の大切さ。
あとは、相談→解決の流れを繰り返す、という。
ブリコラージュの精神にあふれた、地域づくりのお手本のような事例だったなと。
相談して、地域の誰かが、いっちょやってやるか、
って立ち上がって、解決していった。すげーな。
プロセス(経過、順番)デザイン
進め方は慎重に。
誰の為に?何の為に?どうしてやるの?そこに愛はあるか?
・地域への思いやりがあって私たちの活動がある
・地域の思いを丁寧にくみ取ることをおろそかにしない
・進める順番、配慮、気付きを10個くらい考える
・地域でコトを動かすには「良いこと」「悪いこと」の判断ではなく筋の通し方で始まるか始まらないかが決まっていく。
★これ、リアル。実践から出てくる言葉で重い。
プレイヤーやったことないのに、中間支援ができるのか?っていう問いになってる。
「ぼちぼちたけだ」砂川さんのデザインも素敵だった。
・紙ベースで手書き。難しい漢字は使わない。
・コンビニでコピーできる「白黒A3サイズ」
・発行日を決めない。ネタが集まり次第発行
・なるべく手渡し
・ニヤリと笑えるネタや書き方を工夫。
・捨てられないように裏側はイラストマップ
・批判しない 傷つけない マイナスオーラ出さない
・集落情報だけでなく、地域や代表の関係性の情報も載せる。
7世帯の竹田集落に配る新聞「ぼちぼちたけだ」
7部だけすればいいという。
(増刷はコンビニですぐにできる)
いいなあ、この力の抜け具合。
~~~
現場のリアル。
それが詰まった、すてきな報告会だった。
それを踏まえて役所はどうするのか?
中間支援団体どうするのか?
みたいな会議だったのだけど。
メモにも書いたけど、屋村さんの言っていたことって
実際の現場飛び込んで、右往左往したからこそ
リアリティがあって、そうそう、そうそうって思えるのであって、
大学の先生や、コーディネーターや地域づくりの重鎮が
「筋を通すことが大事です」とか言われても、
そんなに響かないんだろうな。
「ひとり」や「ひとりひとり」にフォーカスしている重みがあるなあと感じた。
しばらく行かないうちに時代は変わったんだ。
地域づくりしたい。
⇒
コーディネーター養成講座に出て、
⇒
地域づくりワークショップを開催して、
⇒
付箋にアイデアだして、
⇒
「それいいね」と思うけど誰もやらない。
そんな時代の終わりを感じた。
(僕がそっちの業界に行かなかった理由です)
プレイヤーが飛び込んで、
地域とコミュニケーションしながら、
一緒に作っていくこと。
その「一緒につくる」の部分に、
「自分は支援者だ」と思っている人は入っていけない。
「支援・被支援の時代」の終わりを感じた。
誰が「つくる」のか?
支援者か、被支援者か?
その問いが存在している地域では
「つくる」ことは起こらないと思った。
もっと、今を、ライブに生きること。
ひとりひとりの人生に、暮らしに、フォーカスすること。
そしてやってみること。
相談すること。
発信すること。
そうやって、結果、つくられていく地域。
地域づくりは目的ではなく、結果なんだなと。
そんな方法論を、
「伴奏型支援」と名付けられないだろうか。
こういうレポートタイプのブログは、
ツイッターでメモを起こして、
そのあとからそれを眺めながら記事を書いていくのだけど、
パソコンやスマホでメモを打っていると
「誤変換」されることがたまにある。
水戸部さんのプレゼンに出てくる、
「伴走型支援」と打とうとして、
「伴奏型支援」に変換された。
えっ。
いいじゃん。伴奏型支援。
ジャズのような、即興音楽のような、
そういう「場」を地域に作っていく人。
もちろん自分自身もひとつの楽器になり、
そこに加わっているという。
それって、
どっちが支援されているんですか?みたいな。
そういう「場」をつくっていくような
地域づくりが始まっていく、
そんな予感のしたフォーラムでした。
楽しかった。
「地域づくり支援者サミット」に出席してきました。
大正大学「地域実習」でご一緒した
柏崎まちづくりネットあいさの水戸部さんに注目していて、
そのプレゼンが聞きたかったので。
1 新潟空港でバス停までダッシュ 12:50
2 新潟駅で南口から万代口へダッシュ 13:25
3 新潟県庁で西回廊講堂へダッシュ13:45
で、なんとか水戸部さんのプレゼン2分前に会場入り。
受付してなくてすみません。


すごい人数でした。
まあ、3分の2は自治体の人でしたけど。
登壇者はフレッシュな人たちだったなあと。
柏崎の水戸部さん
糸魚川の屋村さん
川口の砂川さん
新鮮だったなあと。
たぶん、こっち系のイベントには
ヒーローズファーム始めてから行っていないから
10年以上ぶりになるのではないかな。
しばらく行かないうちに、自分が若手じゃなくなってた。(笑)
一番の感想は、特に上の3人みたいに
現場で体当たりでやってきた人たちの生の声って
めちゃめちゃ響くなあと。
実践者の声はリアリティが違うなと。
3人のお話を中心にメモ。
~~~ここからメモ
まちのプレイヤーを増やす。
キーワードは「欠落」と「有意味性」。
「欠落を抱えている人」を探す。
それをどう「欠落を補う人」に変えるか?
欠落を補う「有意味性」
「あなたはなぜそれをやらなければならないのか?」に対する答え。
有意味性とはなにか?
・過去に欠落や喜怒哀楽、得意不得意を見つけ、自己開示する
・なぜか?には理由があり、理由である原体験は模倣できない
そこから導かれる答えはあなたにしかないストーリーになる。
そこに有意味性を見つけること。
まちにプレイヤーが少ないこと
↑
まち・社会とふれる機会が少ないこと
↑
まちでの生き方の選択肢が少ないこと
⇒まちにふれて自分の生き方をふれる機会が必要
学校教育のインプットと社会で求められるアウトプットのギャップ
「協調性」「空気を読む力」⇒「独自性」「当たり前を疑う力」
「まんべんなく能力を伸ばすバランス型人材」⇒「特徴や個性のある特化型人材」
大きなギャップがある。
「チェンジメーカー」柏崎の中学生から大学生までの次代の担い手にソーシャルアントレプレナーシップを持ってもらうための教育プログラムを提供することで、柏崎の未来を担う起業家の発掘を目指すローカルプロジェクト。
「民間メンター」:地域の起業家の伴走型支援、
「社会とお金」:地域課題解決を事業化する方法、
「起業家精神」:感じたこと、考えたことから自主的・主体的に行動すること
↑ここまで柏崎まちづくりネットあいさの水戸部さんのプレゼンメモ。
めちゃめちゃ共感しました。
そういう「場」を地域でいかに作れるか、っていうこと。
そして、なんといっても、昨日の地域づくり支援者サミットの主演は、屋村さんでした。
面白かったし、プレゼンかっこよかった。
旦那さんの「スライド10枚以上残して終わる人なかなかいませんよ」
っていうコメントもさらによかった。笑
ということで、屋村さんプレゼンメモ
「波と母船」(糸魚川市木浦地域)
2018年春、長者温泉ゆとり館を引き継ぐ。
致しません。
地域起こし
地域活性化
そこに地域住民への思いやりはある?
若者に「あなたたちの地域は何もない」と言われたら悲しい。
「そのままの知恵、暮らし」を宝ものにするだけ。
地域・残し
「変えたほうがいい」と思っているものはありません。
「見方、見る方向が変わっているだけ」です。
今あるその暮らしを学んで、磨いて輝かせて
私たち世代から次世代に残してつないでいくだけ。
それがこの地域を「のこす」ことにつながると考えています。
★ここ、ホントそれ、って。
「地域」ってなに?
いままでの「地域づくり」は、
実体のない「地域」を支援してきたのではないか。
地域って、ひとりうひとりの暮らしの集合体だろうと。
ひとりひとりをリスペクトしているのかっていう問いに詰まってた。
「地域を置いてきぼりにしない」を学ぶ。
地域への説明の大切さ。
あとは、相談→解決の流れを繰り返す、という。
ブリコラージュの精神にあふれた、地域づくりのお手本のような事例だったなと。
相談して、地域の誰かが、いっちょやってやるか、
って立ち上がって、解決していった。すげーな。
プロセス(経過、順番)デザイン
進め方は慎重に。
誰の為に?何の為に?どうしてやるの?そこに愛はあるか?
・地域への思いやりがあって私たちの活動がある
・地域の思いを丁寧にくみ取ることをおろそかにしない
・進める順番、配慮、気付きを10個くらい考える
・地域でコトを動かすには「良いこと」「悪いこと」の判断ではなく筋の通し方で始まるか始まらないかが決まっていく。
★これ、リアル。実践から出てくる言葉で重い。
プレイヤーやったことないのに、中間支援ができるのか?っていう問いになってる。
「ぼちぼちたけだ」砂川さんのデザインも素敵だった。
・紙ベースで手書き。難しい漢字は使わない。
・コンビニでコピーできる「白黒A3サイズ」
・発行日を決めない。ネタが集まり次第発行
・なるべく手渡し
・ニヤリと笑えるネタや書き方を工夫。
・捨てられないように裏側はイラストマップ
・批判しない 傷つけない マイナスオーラ出さない
・集落情報だけでなく、地域や代表の関係性の情報も載せる。
7世帯の竹田集落に配る新聞「ぼちぼちたけだ」
7部だけすればいいという。
(増刷はコンビニですぐにできる)
いいなあ、この力の抜け具合。
~~~
現場のリアル。
それが詰まった、すてきな報告会だった。
それを踏まえて役所はどうするのか?
中間支援団体どうするのか?
みたいな会議だったのだけど。
メモにも書いたけど、屋村さんの言っていたことって
実際の現場飛び込んで、右往左往したからこそ
リアリティがあって、そうそう、そうそうって思えるのであって、
大学の先生や、コーディネーターや地域づくりの重鎮が
「筋を通すことが大事です」とか言われても、
そんなに響かないんだろうな。
「ひとり」や「ひとりひとり」にフォーカスしている重みがあるなあと感じた。
しばらく行かないうちに時代は変わったんだ。
地域づくりしたい。
⇒
コーディネーター養成講座に出て、
⇒
地域づくりワークショップを開催して、
⇒
付箋にアイデアだして、
⇒
「それいいね」と思うけど誰もやらない。
そんな時代の終わりを感じた。
(僕がそっちの業界に行かなかった理由です)
プレイヤーが飛び込んで、
地域とコミュニケーションしながら、
一緒に作っていくこと。
その「一緒につくる」の部分に、
「自分は支援者だ」と思っている人は入っていけない。
「支援・被支援の時代」の終わりを感じた。
誰が「つくる」のか?
支援者か、被支援者か?
その問いが存在している地域では
「つくる」ことは起こらないと思った。
もっと、今を、ライブに生きること。
ひとりひとりの人生に、暮らしに、フォーカスすること。
そしてやってみること。
相談すること。
発信すること。
そうやって、結果、つくられていく地域。
地域づくりは目的ではなく、結果なんだなと。
そんな方法論を、
「伴奏型支援」と名付けられないだろうか。
こういうレポートタイプのブログは、
ツイッターでメモを起こして、
そのあとからそれを眺めながら記事を書いていくのだけど、
パソコンやスマホでメモを打っていると
「誤変換」されることがたまにある。
水戸部さんのプレゼンに出てくる、
「伴走型支援」と打とうとして、
「伴奏型支援」に変換された。
えっ。
いいじゃん。伴奏型支援。
ジャズのような、即興音楽のような、
そういう「場」を地域に作っていく人。
もちろん自分自身もひとつの楽器になり、
そこに加わっているという。
それって、
どっちが支援されているんですか?みたいな。
そういう「場」をつくっていくような
地域づくりが始まっていく、
そんな予感のしたフォーラムでした。
楽しかった。
2019年02月07日
予測不可能な未来に対してフラットであること
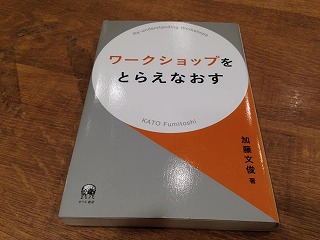
「ワークショップをとらえなおす」(加藤文俊 ひつじ書房)
あ、あの「つながるカレー」の加藤先生、こんな本を!
と思って購入。
まだ読み途中なのだけど、
ビビビって来るキーワードと記述が多い。
P29の
フィールド(フィールドワーク)とコンセプト(コンセプトワーク)のあいだにある
メディア、ラボラトリーワークとしてのワークショップ
という表現にはめちゃめちゃしっくりくるし、
現代の安易なワークショップ型イベントに対して、
警鐘を鳴らしているというか、問いを投げかけている。
たとえば、
「こなすだけ」のワークショップ
「アリバイ」としてのワークショップ
この2つのワードだけとっても、
僕が大学生の終わりごろに2年連続で参加した
ワークショップの違和感をめちゃめちゃ表現している。
あれ、このワークショップ、
去年と同じことを、同じ人が、同じ手法でやっている、
と、強烈な違和感を感じて、
僕はその業界から距離を置くようになった。
というわけで、
本文を読みながらメモの途中経過
~~~ここから
ひとりひとりを「個人」として大事にするんじゃなくて、「存在」として大事にする。
場を主、人を従としてみる。
でも、場を構成するもっとも大きな要素は人なのだ。
そうすると、何が起こるか。
フラットっていうのは、上下関係だけのことじゃないのかもな。
時間軸とかもめっちゃ重要。
僕は答えを知ってて、君は知らないみたいなのってフラットじゃないよね。
映画の結末を知ってる人と知らない人、みたいな関係性とか。
ワークショップでさえ、企画者、設計者と参加者は時間軸においては、フラットではないよね。
「させられる」ことによって、予測不可能性が生まれ、そこに創造の種が蒔かれる、ようなことは起こらないのか?
ほめるという行為は人を評価者と被評価者に分ける。
~~~ここまでメモ
この本を読みながら、
「フラットな関係性」についてあらためて考えていたようだ。(笑)
フラットな関係性というのを
時間軸でとらえる、っていうのが最近気になることで、
予測不可能な未来に対して、人はフラットになるし、
いま終わったばかりのイベントに対しても、人はフラットになる。
だから、企画会議(キカクカイギ)とか、
ふりかえりとかっていうコンテンツを充実させようとしているのかも。
うんうん。
もしかしたら、そういうところが「フラット」の入り口なのかもしれません。
読み進めます。
2019年02月06日
大学‐地域連携のホンモノ化
タイミングよく、まちとしごと総合研究所@京都のスタッフ募集の説明会に。


始まりましたっ
えっ
カレー?


はい。
最初のプログラムはカレーを食べるところから。
参加費1000円の中に含まれています。笑

そして東さんと三木さんのトーク。
面白かったなあ。
~~~以下メモ
大学、行政、企業、地域のあいだ。
ひとりじゃできないことをみんなでやろう。
多くの人がまちに関わる起点をつくる。
対話・着想→実験・研究→事業化
福岡カレー部。
カフェめぐり。
好きなことを追求していくと仲間が増えていく。
ファシリテーションは後継ぎ、フードロス、学校教育をテーマに、
講座は、local to local、クリエイティブ、創業みたいなテーマで。
やりたいことある人とプロジェクトやりたい。
三木俊和さんの原点。
先生って何だよ??
っていう問い。
違和感から出発してる。
叩かれて、反発する。
当たり前だったことが当たり前じゃなくなっていく。
その変人は大事なことを言ってる人かもしれない。
その人を最初に応援する人になる。
市民活動センターが事務所貸し、会議室貸しになっていないか。
そうであるなら、ビル管理会社に委託したほうがいいよね。
でもそれって地域の人のためになるの?
まちの公共空間をアイデアとコンセプトで次へ。
市民活動センターをリデザインして、コミュニティ・ラーニング・センターにする。
変わり続ける人のためのインフラになる。
インフラっていう言葉も、ハードだけの意味合いじゃなくて、ソフトが起こる、とか、ソフトが循環する仕組み、みたいな意味合いで使われてくるのかもしれない。
コミュニティ・ラーニング・センター
新しいことを知る、出会いがある。「循環」こそがインフラ
高齢者ふれあいサロン
ゆっくり過ごそう→イキイキ過ごそう
なんでも与えるのではなくて、作ってもらう。
「まごころおにぎりプロジェクト」
まちの担い手づくりを次へ。
窓口に来てくれてから始まる。→人こない。
まちうけるセンターから出向くセンターへ。
そのために大学連携。学生と一緒に地域に入っていく。
大学がやる地域連携より、地域がやる大学連携の方が学生にとって学びがあるのではないか。
地域のほうが主導したほうがいい。
大学のプログラムは学生の失敗(の機会)奪っているのではないか。
「うまくいかないことがあるんだ!」っていう気づき。
若者に挑戦し、失敗する権利を返してあげる。
・大学ー地域連携のホンモノ化。
・SDGsが上辺になっていないか。
・大学は本当に行ったほうがいいのか?
・専門系高校の復権
・ビジコンとか、大人用のインフラを厳しくしたのを若者に出してないか?
・私たちは育むことを委ねすぎた。
ハコ×デザイン×コーディネーター×地域
コーディネーター=人って大事だな、と改めて。
昨日だって、崇仁の藤尾さん、人を見に来てたというか、感じに来ていたんだもんなあ。
そうやって、「だれとやるか?」を大切にすることからひとりひとりを大切にするまちづくりが始まるのではないかな、と。
ダイバーシティ×シチズンシップ「ダイバーシチズンセンター」
広い意味でのダイバーシティが試されている。
大学×地域のホンモノ化
体験型プログラムを超えていく。
教育機関が主体となったプログラムでできるのか?
地域側の覚悟が必要なんじゃないか?
単位なしの課外活動であること。
「群れるな散れ」
→得意なことが違うから会った時のネタが新鮮。
接触頻度が多いことそのものに価値があるわけじゃない。
「まちづくり」キーワードなさまざまなことがジャンルが違うことで、受けられるかもしれない。
まちごと総研の東&三木、すてきなチームだなと。
やりたい!っていうポジティブな人→東さん
困っている!なんとかしたいっていう人→三木さん
っていう両方からできる。
大学生が地域にかかわることのメリット。
→「瞬間的な熱量」がすごい。
~~~ここまでメモ。
キーワード的にヒットしたのは、
・コーディネーターの人としての魅力
・人の「多様性」
・インフラ=循環
あたりでしょうか。
そして何よりも、三木さんのラストにお話されていた
「大学‐地域連携のホンモノ化」というメッセージ。
ホンモノ化ってことは、
ホンモノじゃないプログラムがめちゃめちゃあるってことですよね。
三木さんが言っていた
「大学側が主導権とるのではなくて、地域側が主導権とる」
っていう。
大学がやる地域連携と
地域がやる大学連携と
全然違うなと。
やってることは学生が地域に出て何かやっているのだけど。
本当は、そのど真ん中に「協働」プロジェクトをつくっていく、
っていうことなのだろうなと。
そしてここにも、
クルミドコーヒー影山さんのいう、
「リザルトパラダイム」の影響がめちゃめちゃあるなあと。
大学のプログラム(単位あり)の場合、アウトプット(目的)を定め、
そこに向かって(最短距離で)いくようにプログラムが設計される。
そこで、落とされていくもの。
目的と違う地域で感じたもの。
学生、地域の人ひとりひとりの「存在」。
それが、
大学の地域連携を「ニセモノ」にしているんじゃないのか。
「課題解決策を考え、提案すること、プラン作り」
が目的になるあまり、
地域の人も、自分たちも置き去りになっていないか。
そのプロセスが軽視されていないか。
そんな問いがあった。
三木さんが学生の価値は、
「瞬間的な熱量」ですって言っていたけど、
それ、それ、って。
それを引き出すには、
大学が差し出すカリキュラムではなかなか難しいのかもなあと。
僕はインターン事業やっていたとき、
学生の価値は、
「イノセンス(いい意味の無知)」と「行動力」だと思っていたけど、
「瞬間的な熱量」っていうのもまさにそれだなあと。
冷え切った鉄に熱をかけて、
変形していくような瞬間的な熱量が発生する時がある。
それを発生させるのが場のチカラであると思っていて、
その場のチカラを高めるのは、本のある空間だと思っている。
だから今、僕は本屋という手法をとっているのではないかなあと。
あらためて自分を確認した説明会となりました。
東さん、三木さん、ありがとうございました。
次回は現場にお邪魔しますっ。


始まりましたっ
えっ
カレー?


はい。
最初のプログラムはカレーを食べるところから。
参加費1000円の中に含まれています。笑

そして東さんと三木さんのトーク。
面白かったなあ。
~~~以下メモ
大学、行政、企業、地域のあいだ。
ひとりじゃできないことをみんなでやろう。
多くの人がまちに関わる起点をつくる。
対話・着想→実験・研究→事業化
福岡カレー部。
カフェめぐり。
好きなことを追求していくと仲間が増えていく。
ファシリテーションは後継ぎ、フードロス、学校教育をテーマに、
講座は、local to local、クリエイティブ、創業みたいなテーマで。
やりたいことある人とプロジェクトやりたい。
三木俊和さんの原点。
先生って何だよ??
っていう問い。
違和感から出発してる。
叩かれて、反発する。
当たり前だったことが当たり前じゃなくなっていく。
その変人は大事なことを言ってる人かもしれない。
その人を最初に応援する人になる。
市民活動センターが事務所貸し、会議室貸しになっていないか。
そうであるなら、ビル管理会社に委託したほうがいいよね。
でもそれって地域の人のためになるの?
まちの公共空間をアイデアとコンセプトで次へ。
市民活動センターをリデザインして、コミュニティ・ラーニング・センターにする。
変わり続ける人のためのインフラになる。
インフラっていう言葉も、ハードだけの意味合いじゃなくて、ソフトが起こる、とか、ソフトが循環する仕組み、みたいな意味合いで使われてくるのかもしれない。
コミュニティ・ラーニング・センター
新しいことを知る、出会いがある。「循環」こそがインフラ
高齢者ふれあいサロン
ゆっくり過ごそう→イキイキ過ごそう
なんでも与えるのではなくて、作ってもらう。
「まごころおにぎりプロジェクト」
まちの担い手づくりを次へ。
窓口に来てくれてから始まる。→人こない。
まちうけるセンターから出向くセンターへ。
そのために大学連携。学生と一緒に地域に入っていく。
大学がやる地域連携より、地域がやる大学連携の方が学生にとって学びがあるのではないか。
地域のほうが主導したほうがいい。
大学のプログラムは学生の失敗(の機会)奪っているのではないか。
「うまくいかないことがあるんだ!」っていう気づき。
若者に挑戦し、失敗する権利を返してあげる。
・大学ー地域連携のホンモノ化。
・SDGsが上辺になっていないか。
・大学は本当に行ったほうがいいのか?
・専門系高校の復権
・ビジコンとか、大人用のインフラを厳しくしたのを若者に出してないか?
・私たちは育むことを委ねすぎた。
ハコ×デザイン×コーディネーター×地域
コーディネーター=人って大事だな、と改めて。
昨日だって、崇仁の藤尾さん、人を見に来てたというか、感じに来ていたんだもんなあ。
そうやって、「だれとやるか?」を大切にすることからひとりひとりを大切にするまちづくりが始まるのではないかな、と。
ダイバーシティ×シチズンシップ「ダイバーシチズンセンター」
広い意味でのダイバーシティが試されている。
大学×地域のホンモノ化
体験型プログラムを超えていく。
教育機関が主体となったプログラムでできるのか?
地域側の覚悟が必要なんじゃないか?
単位なしの課外活動であること。
「群れるな散れ」
→得意なことが違うから会った時のネタが新鮮。
接触頻度が多いことそのものに価値があるわけじゃない。
「まちづくり」キーワードなさまざまなことがジャンルが違うことで、受けられるかもしれない。
まちごと総研の東&三木、すてきなチームだなと。
やりたい!っていうポジティブな人→東さん
困っている!なんとかしたいっていう人→三木さん
っていう両方からできる。
大学生が地域にかかわることのメリット。
→「瞬間的な熱量」がすごい。
~~~ここまでメモ。
キーワード的にヒットしたのは、
・コーディネーターの人としての魅力
・人の「多様性」
・インフラ=循環
あたりでしょうか。
そして何よりも、三木さんのラストにお話されていた
「大学‐地域連携のホンモノ化」というメッセージ。
ホンモノ化ってことは、
ホンモノじゃないプログラムがめちゃめちゃあるってことですよね。
三木さんが言っていた
「大学側が主導権とるのではなくて、地域側が主導権とる」
っていう。
大学がやる地域連携と
地域がやる大学連携と
全然違うなと。
やってることは学生が地域に出て何かやっているのだけど。
本当は、そのど真ん中に「協働」プロジェクトをつくっていく、
っていうことなのだろうなと。
そしてここにも、
クルミドコーヒー影山さんのいう、
「リザルトパラダイム」の影響がめちゃめちゃあるなあと。
大学のプログラム(単位あり)の場合、アウトプット(目的)を定め、
そこに向かって(最短距離で)いくようにプログラムが設計される。
そこで、落とされていくもの。
目的と違う地域で感じたもの。
学生、地域の人ひとりひとりの「存在」。
それが、
大学の地域連携を「ニセモノ」にしているんじゃないのか。
「課題解決策を考え、提案すること、プラン作り」
が目的になるあまり、
地域の人も、自分たちも置き去りになっていないか。
そのプロセスが軽視されていないか。
そんな問いがあった。
三木さんが学生の価値は、
「瞬間的な熱量」ですって言っていたけど、
それ、それ、って。
それを引き出すには、
大学が差し出すカリキュラムではなかなか難しいのかもなあと。
僕はインターン事業やっていたとき、
学生の価値は、
「イノセンス(いい意味の無知)」と「行動力」だと思っていたけど、
「瞬間的な熱量」っていうのもまさにそれだなあと。
冷え切った鉄に熱をかけて、
変形していくような瞬間的な熱量が発生する時がある。
それを発生させるのが場のチカラであると思っていて、
その場のチカラを高めるのは、本のある空間だと思っている。
だから今、僕は本屋という手法をとっているのではないかなあと。
あらためて自分を確認した説明会となりました。
東さん、三木さん、ありがとうございました。
次回は現場にお邪魔しますっ。
2019年02月05日
「問い」の種を蒔く
「続・ゆっくり、いそげの朝」のために
土曜日の移動中にもう一度読み直してのメモ。
(対談のネタ帳です)
話せたことも、
話せなかったこともあったけど、ひとまず次回に向けて。

~~~ここからメモ
「リザルトパラダイム」
教育・NPO・ボランティアの世界こそ、そこに染まっている。
理念・目的のために人が手段化されてしまう。
ひとりひとりが大切にされない。
エンジニアリング⇔ブリコラージュ
「自らに利用価値がある」と言わないといけない
⇒就活の違和感
植物の創発特性。
事業体や組織の成長であり秘めた力は、
測ろうとするのではなく、感じること。(P50)
haveの目標:もっともっとほしくなる
doの目標:すぐに実現しない。人生を不足と未達成で埋め尽くす。
beの目標:「今、ここで」達成することができる。
beをベースにしたdoを考える。
どうありたいか、どうしたいかではなく、
「どうありたくないか」「どうしたくないか」を見つける。
「不快感」や「違和感」から気づく。(P71)
「フラットじゃないコミュニケーション」
⇒何も生まない。足し算でしかない。
・目的地がわからない。
・自分のあり方が美しくない。
Noの経験が次なるYesを生む。(P72)
コンサルに入った動機は、5日間10万円。(P84)
いのちのつながりが縁となって居場所に残っていく。
場の力=空間×関係性×記憶
境界線が伸び縮みする
「自己決定に基づいた参加者だけで始められる」
「参加と退出に対して開かれている」
▽の組織
・いいアイデアに到達できる
・当事者性が増す
・成長点が増える
「参加」と「ケア」
予測不可能な未来に対してフラット
アイデア、価値観、美意識を持ち寄り、
合わせ、形成されるチームの価値観。
共通言語、価値観だって絶対的ではなく、
つねにダイナミックに動き続けている。
「一人一人の自由と自己決定」と
「組織としての意思決定」が矛盾しない。
他動詞と自動詞(P189)
「人を集めるには?」
→「人が自然と集まるようなお店をつくるには?」
「かえるライブラリーは変えない」
人は育つ、学ぶ、変わる。
Dメンバーが居場所のジレンマを生み出す。(P194)
一人一人のいのちが最大化するという戦略。
「目的地に向け、できるだけ時間やコストをかけることなく、いかに最短距離でたどり着くか」
企業経営においても、まちづくりにおいても、政治においても、教育においても
医療においても、メディアにおいても、スポーツにおいても、NPO活動においても、
当然となっている。
「生産性」が問われるようになると人間は手段化する(P201)
我々の一人一人には、手に取ることのできる、生きた魂があります。システムにはそれがありません。
システムを独り立ちさせてはなりません。システムが我々をつくったのではありません。
我々がシステムを作ったのです。(村上春樹『雑文集ー壁と卵』(P210)
システムをつくるためには原初的な「問い」がいる
現代はそれが「生産性の高い社会をつくるには」なのであり、
その問いに答えようとしている。(P228)
~~~ここまでメモ
影山さんのいうように、場って「土」のようなものなのかもしれないなと思ったし、
土でありたいと僕も思う。
土としての本屋が育むのは、人じゃなくて、
「問い」の種なのかもしれない、って思った。
もちろん問いを生むのは人なのだけど。
「違和感」や「ワクワク」を文字から、本から、人から、空間から
キャッチして、問いが生まれること。
それをやって行きたいのかもしれない。
「ブランド」ってなんだろう?って考えた。
多くの人が価値だと認識しているから、
その商品・サービスはブランド化する。
高い金銭的な価値やリピート客、ファンをつくる。
じゃあ、「問い」はどうだろうか?
接する人の心と頭の中に、
なぜ?という疑問符やなんだろう?という違和感を起こす。
人はそれをわかりたくて、
もう一度その場所に行きたくなる、もう一度その人に会いたくなる。
参考:何を考えているか分からないと、もう一度会いたくなる(17.1.24)
http://hero.niiblo.jp/e483798.html
「ユニクロがフリースを二千万着売ったのは、割安感ではなく、
どうしてこんなに安いのか、その合理的理由がわからないという、
考量不可能性がもう一度ユニクロに行かねば、
という消費者サイドの焦燥感に点火したのではなかったか。」
そんな「わからなさ」や「問い」そのものがその場所に再び人を運んでくる。
(あるいは日曜日のように、イベント後にそこにずっといたいような気持ちになる)
そんな「問い」の種が蒔かれるような、場を、本屋を
作っていくのが、僕の勘違いミッションなのだろうなあと思いました。
影山さんのコール、めちゃめちゃ響きました。
まだまだレスポンスしたいと思います。
いい機会をありがとうございました。
※「続・ゆっくり、いそげ」はウチノ食堂・藤蔵内のかえるライブラリーで買うことができます。(残り1冊ですが)
また入荷します~
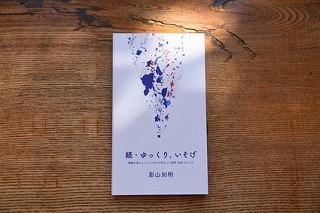
土曜日の移動中にもう一度読み直してのメモ。
(対談のネタ帳です)
話せたことも、
話せなかったこともあったけど、ひとまず次回に向けて。

~~~ここからメモ
「リザルトパラダイム」
教育・NPO・ボランティアの世界こそ、そこに染まっている。
理念・目的のために人が手段化されてしまう。
ひとりひとりが大切にされない。
エンジニアリング⇔ブリコラージュ
「自らに利用価値がある」と言わないといけない
⇒就活の違和感
植物の創発特性。
事業体や組織の成長であり秘めた力は、
測ろうとするのではなく、感じること。(P50)
haveの目標:もっともっとほしくなる
doの目標:すぐに実現しない。人生を不足と未達成で埋め尽くす。
beの目標:「今、ここで」達成することができる。
beをベースにしたdoを考える。
どうありたいか、どうしたいかではなく、
「どうありたくないか」「どうしたくないか」を見つける。
「不快感」や「違和感」から気づく。(P71)
「フラットじゃないコミュニケーション」
⇒何も生まない。足し算でしかない。
・目的地がわからない。
・自分のあり方が美しくない。
Noの経験が次なるYesを生む。(P72)
コンサルに入った動機は、5日間10万円。(P84)
いのちのつながりが縁となって居場所に残っていく。
場の力=空間×関係性×記憶
境界線が伸び縮みする
「自己決定に基づいた参加者だけで始められる」
「参加と退出に対して開かれている」
▽の組織
・いいアイデアに到達できる
・当事者性が増す
・成長点が増える
「参加」と「ケア」
予測不可能な未来に対してフラット
アイデア、価値観、美意識を持ち寄り、
合わせ、形成されるチームの価値観。
共通言語、価値観だって絶対的ではなく、
つねにダイナミックに動き続けている。
「一人一人の自由と自己決定」と
「組織としての意思決定」が矛盾しない。
他動詞と自動詞(P189)
「人を集めるには?」
→「人が自然と集まるようなお店をつくるには?」
「かえるライブラリーは変えない」
人は育つ、学ぶ、変わる。
Dメンバーが居場所のジレンマを生み出す。(P194)
一人一人のいのちが最大化するという戦略。
「目的地に向け、できるだけ時間やコストをかけることなく、いかに最短距離でたどり着くか」
企業経営においても、まちづくりにおいても、政治においても、教育においても
医療においても、メディアにおいても、スポーツにおいても、NPO活動においても、
当然となっている。
「生産性」が問われるようになると人間は手段化する(P201)
我々の一人一人には、手に取ることのできる、生きた魂があります。システムにはそれがありません。
システムを独り立ちさせてはなりません。システムが我々をつくったのではありません。
我々がシステムを作ったのです。(村上春樹『雑文集ー壁と卵』(P210)
システムをつくるためには原初的な「問い」がいる
現代はそれが「生産性の高い社会をつくるには」なのであり、
その問いに答えようとしている。(P228)
~~~ここまでメモ
影山さんのいうように、場って「土」のようなものなのかもしれないなと思ったし、
土でありたいと僕も思う。
土としての本屋が育むのは、人じゃなくて、
「問い」の種なのかもしれない、って思った。
もちろん問いを生むのは人なのだけど。
「違和感」や「ワクワク」を文字から、本から、人から、空間から
キャッチして、問いが生まれること。
それをやって行きたいのかもしれない。
「ブランド」ってなんだろう?って考えた。
多くの人が価値だと認識しているから、
その商品・サービスはブランド化する。
高い金銭的な価値やリピート客、ファンをつくる。
じゃあ、「問い」はどうだろうか?
接する人の心と頭の中に、
なぜ?という疑問符やなんだろう?という違和感を起こす。
人はそれをわかりたくて、
もう一度その場所に行きたくなる、もう一度その人に会いたくなる。
参考:何を考えているか分からないと、もう一度会いたくなる(17.1.24)
http://hero.niiblo.jp/e483798.html
「ユニクロがフリースを二千万着売ったのは、割安感ではなく、
どうしてこんなに安いのか、その合理的理由がわからないという、
考量不可能性がもう一度ユニクロに行かねば、
という消費者サイドの焦燥感に点火したのではなかったか。」
そんな「わからなさ」や「問い」そのものがその場所に再び人を運んでくる。
(あるいは日曜日のように、イベント後にそこにずっといたいような気持ちになる)
そんな「問い」の種が蒔かれるような、場を、本屋を
作っていくのが、僕の勘違いミッションなのだろうなあと思いました。
影山さんのコール、めちゃめちゃ響きました。
まだまだレスポンスしたいと思います。
いい機会をありがとうございました。
※「続・ゆっくり、いそげ」はウチノ食堂・藤蔵内のかえるライブラリーで買うことができます。(残り1冊ですが)
また入荷します~
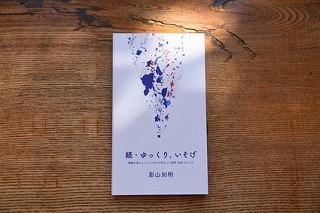
2019年02月04日
「自己開示する」と「自己開示させられる」のあいだ
「続・ゆっくり、いそげの朝」@胡桃堂喫茶店(2019.2.3)

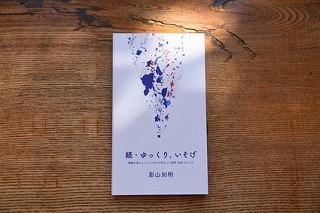
※新潟内野・「ウチノ食堂藤蔵」内の「APARTMENT BOOKS」でも販売しています。
新年に「続・ゆっくり、いそげ」を読んでから
心地よい敗北感(この場合の敗北ってなんでしょうね。言語化やコンセプト化への敗北感なのか)
に浸っている中でも何かムズムズとしていたところ、
影山知明さんにお誘いいただき、国分寺・胡桃堂喫茶店での
「続・ゆっくり、いそげの朝」で対談してきました。
テーマは「場」ということだったのですが。
面白かったのは、
影山さんがいう場の力(影山さんは漢字表記)は、
「空間」×「関係性」×「記憶」
っていうことで、
だんだんと積み重なっていくものという感覚だったのに対して
僕が昨年考えたのは。
1 誰とやるか
2 いつやるか
3 どこでやるか
っていう比較的インスタントというか、
その瞬間の場のチカラ(カタカナ表記)について
考えているのだなあと。
影山さんの言葉を借りれば、
僕は「場」へのインプットに力点を置いていて
影山さんは「場」からのアウトプットを大事にしている。
それは、
「土になりたい」「土でありたい」
という言葉にも表されているけど、
植物を育てるように、
種を蒔き、水をあげ、コンディションを整えて、
目を出してくれるのを待つ、というもの。
それが「続・ゆっくり、いそげ」のテーマである
△を▽に。だ。
文字にすればリザルト・パラダイムからプロセス・パラダイムへ
人を手段化するのではなく、ひとりひとりの人から始まる経済、世の中。
僕のワークショップの時の肩書は、チューニング・ファシリテーター。
影山さんは、そのようなファシリテーションがあまりしっくりこない、という。
無理やり「自己開示させられている」のはないか、と思うからだという。
なるほど!
と思った。
たしかに、「自己開示させられている」と不快(大げさに言えば)
に思った人が何人かいた場合、
その場の雰囲気は、なんかおかしなものになるのではないか。
その通りだなあと思った。
そして、
「自己開示する」と「自己開示させられる」のあいだ
そこには無数のグラデーションがあるのではないかと思った。
ある1冊の本を思い出した。
「中動態の世界」(國分功一郎 医学書院)。

http://hero.niiblo.jp/e487965.html
(「やりたいことは何か?」「何になりたいのか?」への違和感 18.8.20)
一部だけ抜粋すると
~~~
能動と受動を対立させる言語は、行為にかかわる複数の要素にとっての共有財産とでも言うべきこの過程を、もっぱら私の行為として、すなわち、私に帰属させるものとして記述する。出来事を私有化すると言ってもよい。
「する」か「される」かで考える言語、能動態と受動態を対立させる言語は、ただ、「この行為は誰のものか」と問う。
出来事を描写する言語から、行為を行為者へと帰属させる言語への移行。
意志とは行動や技術をある主体に所属させるのを可能にしている装置。
私は姿を現す。つまり、私は現れ、私の姿が現される。そのことについて現在の言語は、「お前の意志は?」と尋問してくるのだ。それは言わば、尋問する言語である。
~~~
「自己開示する」と「自己開示される」
の差は、実はあいまいなものだと思った。
影山さんが「続・ゆっくり、いそげ」の中で一貫して言っている
「リザルト・パラダイム」に組み込まれ、人が手段化されることへの違和感。
それは、「させられる」ことへの違和感、なのかもしれない。
~~~
P197
サポートする側としても、支援「させられる」のではなく、
自己決定に基づいて支援「する」のであれば、
それはギブし合う(支援し合う)関係となる。
~~~
それにはめちゃめちゃ同意できるし、その通りだと思うのだけど、
「させられる」と「する」の差は、紙一重なのではないか、と思うのだ。
同じ行為であっても、「セクハラ・パワハラ」に該当するかどうかは、
当人たちがそれをどのように捉えるか、にかかっているように、
発言や行動などの事実のみで、それを判断することはできない。
「支援させられる」のか、「支援する」のか、
「自己開示させられる」のか、「自己開示する」のか、
っていうのも、非常に線引きが難しいところだと思う。
たとえば、
「自己開示させられている」と認識した上で、
あえて、ここはそういう場だから、そういう場づくりに向けて、
「自己開示する自分を演じよう」と思ったとき、
それは「自己開示している」のか、「自己開示させられている」のか。
おそらくは、本屋である、ということは、
そのあいだをつくろうとしているのではないかと思っている。
たとえば、「本の処方箋」。
あなたの悩みを聞いて、本を3冊、処方します。
問診票を書いてもらい、話を聞く。
聞いている僕がびっくりするようなリアルな悩みを話してくれる。
それはマクロでみれば、「自己開示させられている」
自己開示をさせる手法として、見ることもできる。
しかし、ミクロで見れば、
その「場」には、自ら「自己開示する」あるいは「自己開示してしまう」
ような何かが存在している。
ひとつめに、僕が初対面の本屋のおじさんであること。
ふたつめに、本を処方したくらいでは、その悩みは到底解決しないということ。
この2つが、自己開示を促すことになる。
もしくは、
本屋さんの店内で、飲み会をしている。(営業時間中)
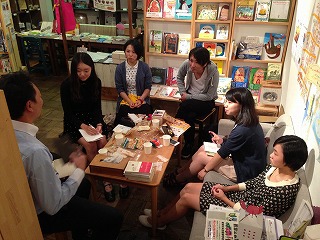
とある中学2年生女子がお姉ちゃんの塾の送り迎えの合間に、
お父さんと一緒に立ち寄ったら、なんか、飲み会してる。
「部活なにやってるの?」と聞かれる。
「実は、部活やめてやることがないんです。」と答える。
「屋台をやってみたら?」と言われて、友達をお菓子の屋台をやってみる。
(ツルハシブックスで実際に起こった話)

つまり、「する」と「される」のあいだは非常にあいまいなんだということ。
僕はそれが「場」なのだろうと思う。
「続・ゆっくり、いそげ」の中で影山さんは場が力を持つときの
5つの条件を紹介していて、
4つ目に「主客同一の要素があること」
が出てくるのだけど、
僕としては、
「主客同一」というより、西田幾多郎風に
「主客未分」な状態なのだと思う。
そして、「主客未分」とは、
「する」と「される」の境目があいまいな状態なのではないかと思う。
「支援する」と「支援される」があいまいな状態。
そういう場こそが場のチカラを発揮するのではないかと思う。
昨日の話で言えば、「参加」と「ケア」が同時に起こるということ。
本屋さんっていう空間は、それが作りやすいのではないかと思った。
今回のトークでの一番の問いはここでした。
「問いを得られる場」「問いをつかめる場」って大切だなあとあらためて。
「続・ゆっくり、いそげ」のラストに、こう書いてある。
~~~
システムをつくるには、それをつくるための原初的な問いがいる。
現代はそれが「生産性の高い社会をつくるには」なのであり、
その問いに答えようとしていると考えれば、
今の経済も政治も教育も、ある意味よくできていると言える。
~~~
新しいシステムをつくるには、「問い」がいる。
1999年、24歳の時に始めた「まきどき村」は、
僕の中の「豊かさってなんだ?」っていう問いへのアウトプットだし。
ツルハシブックスの地下古本コーナーHAKKUTSUだって、
「15歳と地域の多様な大人に出会わせるには?」という問いから始まっている。
昨日もトーク終了後に、たくさんの人が
会場にそのまま残ってランチやお茶を楽しみながら、
延長戦として話していた。
投げ込まれた問い、あるいは自分の中で生まれた問いを
そのまま自分の中だけで消化できず、みんなでシェアしていたのかもしれない。
そういう問いから、システムは生まれていくし
「システム」っていう言い方が大袈裟ならば、
仕組みやプロジェクトが生まれていく。
そういう「場」を僕はつくりたいし、
それが「本屋」だったら素敵だなあと思う。
そうやって生まれてくる「問い」に対して、
人はフラットになれると思う。
今回影山さんと話して僕が確認したのは、
・僕が「いま」にフォーカスしているということ。
・僕が主客未分、あるいは「する」「される」という概念があいまいであることを望んでいること。
「本屋のような劇場」
を目指していたのは、おそらくはそういうことなのだろうと思った。
影山さん、今田さん、参加されたみなさん、
素敵な「場」をありがとうございました。

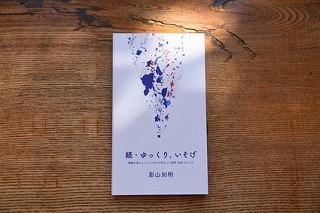
※新潟内野・「ウチノ食堂藤蔵」内の「APARTMENT BOOKS」でも販売しています。
新年に「続・ゆっくり、いそげ」を読んでから
心地よい敗北感(この場合の敗北ってなんでしょうね。言語化やコンセプト化への敗北感なのか)
に浸っている中でも何かムズムズとしていたところ、
影山知明さんにお誘いいただき、国分寺・胡桃堂喫茶店での
「続・ゆっくり、いそげの朝」で対談してきました。
テーマは「場」ということだったのですが。
面白かったのは、
影山さんがいう場の力(影山さんは漢字表記)は、
「空間」×「関係性」×「記憶」
っていうことで、
だんだんと積み重なっていくものという感覚だったのに対して
僕が昨年考えたのは。
1 誰とやるか
2 いつやるか
3 どこでやるか
っていう比較的インスタントというか、
その瞬間の場のチカラ(カタカナ表記)について
考えているのだなあと。
影山さんの言葉を借りれば、
僕は「場」へのインプットに力点を置いていて
影山さんは「場」からのアウトプットを大事にしている。
それは、
「土になりたい」「土でありたい」
という言葉にも表されているけど、
植物を育てるように、
種を蒔き、水をあげ、コンディションを整えて、
目を出してくれるのを待つ、というもの。
それが「続・ゆっくり、いそげ」のテーマである
△を▽に。だ。
文字にすればリザルト・パラダイムからプロセス・パラダイムへ
人を手段化するのではなく、ひとりひとりの人から始まる経済、世の中。
僕のワークショップの時の肩書は、チューニング・ファシリテーター。
影山さんは、そのようなファシリテーションがあまりしっくりこない、という。
無理やり「自己開示させられている」のはないか、と思うからだという。
なるほど!
と思った。
たしかに、「自己開示させられている」と不快(大げさに言えば)
に思った人が何人かいた場合、
その場の雰囲気は、なんかおかしなものになるのではないか。
その通りだなあと思った。
そして、
「自己開示する」と「自己開示させられる」のあいだ
そこには無数のグラデーションがあるのではないかと思った。
ある1冊の本を思い出した。
「中動態の世界」(國分功一郎 医学書院)。

http://hero.niiblo.jp/e487965.html
(「やりたいことは何か?」「何になりたいのか?」への違和感 18.8.20)
一部だけ抜粋すると
~~~
能動と受動を対立させる言語は、行為にかかわる複数の要素にとっての共有財産とでも言うべきこの過程を、もっぱら私の行為として、すなわち、私に帰属させるものとして記述する。出来事を私有化すると言ってもよい。
「する」か「される」かで考える言語、能動態と受動態を対立させる言語は、ただ、「この行為は誰のものか」と問う。
出来事を描写する言語から、行為を行為者へと帰属させる言語への移行。
意志とは行動や技術をある主体に所属させるのを可能にしている装置。
私は姿を現す。つまり、私は現れ、私の姿が現される。そのことについて現在の言語は、「お前の意志は?」と尋問してくるのだ。それは言わば、尋問する言語である。
~~~
「自己開示する」と「自己開示される」
の差は、実はあいまいなものだと思った。
影山さんが「続・ゆっくり、いそげ」の中で一貫して言っている
「リザルト・パラダイム」に組み込まれ、人が手段化されることへの違和感。
それは、「させられる」ことへの違和感、なのかもしれない。
~~~
P197
サポートする側としても、支援「させられる」のではなく、
自己決定に基づいて支援「する」のであれば、
それはギブし合う(支援し合う)関係となる。
~~~
それにはめちゃめちゃ同意できるし、その通りだと思うのだけど、
「させられる」と「する」の差は、紙一重なのではないか、と思うのだ。
同じ行為であっても、「セクハラ・パワハラ」に該当するかどうかは、
当人たちがそれをどのように捉えるか、にかかっているように、
発言や行動などの事実のみで、それを判断することはできない。
「支援させられる」のか、「支援する」のか、
「自己開示させられる」のか、「自己開示する」のか、
っていうのも、非常に線引きが難しいところだと思う。
たとえば、
「自己開示させられている」と認識した上で、
あえて、ここはそういう場だから、そういう場づくりに向けて、
「自己開示する自分を演じよう」と思ったとき、
それは「自己開示している」のか、「自己開示させられている」のか。
おそらくは、本屋である、ということは、
そのあいだをつくろうとしているのではないかと思っている。
たとえば、「本の処方箋」。
あなたの悩みを聞いて、本を3冊、処方します。
問診票を書いてもらい、話を聞く。
聞いている僕がびっくりするようなリアルな悩みを話してくれる。
それはマクロでみれば、「自己開示させられている」
自己開示をさせる手法として、見ることもできる。
しかし、ミクロで見れば、
その「場」には、自ら「自己開示する」あるいは「自己開示してしまう」
ような何かが存在している。
ひとつめに、僕が初対面の本屋のおじさんであること。
ふたつめに、本を処方したくらいでは、その悩みは到底解決しないということ。
この2つが、自己開示を促すことになる。
もしくは、
本屋さんの店内で、飲み会をしている。(営業時間中)
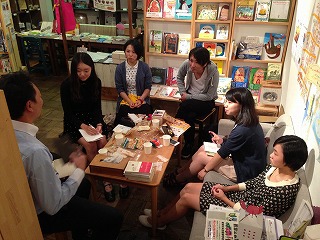
とある中学2年生女子がお姉ちゃんの塾の送り迎えの合間に、
お父さんと一緒に立ち寄ったら、なんか、飲み会してる。
「部活なにやってるの?」と聞かれる。
「実は、部活やめてやることがないんです。」と答える。
「屋台をやってみたら?」と言われて、友達をお菓子の屋台をやってみる。
(ツルハシブックスで実際に起こった話)

つまり、「する」と「される」のあいだは非常にあいまいなんだということ。
僕はそれが「場」なのだろうと思う。
「続・ゆっくり、いそげ」の中で影山さんは場が力を持つときの
5つの条件を紹介していて、
4つ目に「主客同一の要素があること」
が出てくるのだけど、
僕としては、
「主客同一」というより、西田幾多郎風に
「主客未分」な状態なのだと思う。
そして、「主客未分」とは、
「する」と「される」の境目があいまいな状態なのではないかと思う。
「支援する」と「支援される」があいまいな状態。
そういう場こそが場のチカラを発揮するのではないかと思う。
昨日の話で言えば、「参加」と「ケア」が同時に起こるということ。
本屋さんっていう空間は、それが作りやすいのではないかと思った。
今回のトークでの一番の問いはここでした。
「問いを得られる場」「問いをつかめる場」って大切だなあとあらためて。
「続・ゆっくり、いそげ」のラストに、こう書いてある。
~~~
システムをつくるには、それをつくるための原初的な問いがいる。
現代はそれが「生産性の高い社会をつくるには」なのであり、
その問いに答えようとしていると考えれば、
今の経済も政治も教育も、ある意味よくできていると言える。
~~~
新しいシステムをつくるには、「問い」がいる。
1999年、24歳の時に始めた「まきどき村」は、
僕の中の「豊かさってなんだ?」っていう問いへのアウトプットだし。
ツルハシブックスの地下古本コーナーHAKKUTSUだって、
「15歳と地域の多様な大人に出会わせるには?」という問いから始まっている。
昨日もトーク終了後に、たくさんの人が
会場にそのまま残ってランチやお茶を楽しみながら、
延長戦として話していた。
投げ込まれた問い、あるいは自分の中で生まれた問いを
そのまま自分の中だけで消化できず、みんなでシェアしていたのかもしれない。
そういう問いから、システムは生まれていくし
「システム」っていう言い方が大袈裟ならば、
仕組みやプロジェクトが生まれていく。
そういう「場」を僕はつくりたいし、
それが「本屋」だったら素敵だなあと思う。
そうやって生まれてくる「問い」に対して、
人はフラットになれると思う。
今回影山さんと話して僕が確認したのは、
・僕が「いま」にフォーカスしているということ。
・僕が主客未分、あるいは「する」「される」という概念があいまいであることを望んでいること。
「本屋のような劇場」
を目指していたのは、おそらくはそういうことなのだろうと思った。
影山さん、今田さん、参加されたみなさん、
素敵な「場」をありがとうございました。
2019年02月01日
「人を手段化しない」場のチカラ
2月3日の日曜日の胡桃堂喫茶店でのトークに向けて、
本の読みなおしと、過去ブログの整理。
健全な負債感を持つという豊かさ
http://hero.niiblo.jp/e472045.html
(15.8.24)
2700円のシュトーレンを買うということ
http://hero.niiblo.jp/e474894.html
(15.12.1)
第四次元の芸術
http://hero.niiblo.jp/e488654.html
(19.1.2)
「顧客」から入るか、「価値」から入るか
http://hero.niiblo.jp/e488667.html
(19.1.4)
「構想力」と「場のチカラ」
http://hero.niiblo.jp/e488729.html
(19.1.15)
このあたり。
もう一度読みつつ、本も読み返して行きます。
一番話したいのは
「支援の話法」だったり「場のチカラ」だったり、
「人を手段化しない」だったり、
「顧客」から入るか、「価値」から入るか、とかかなあ。
1人の「顧客」から入って、
それが多くの人にとっての価値になっていく
っていうのがビジネスの重要なことなのだろうけど。
まさに手紙を届けるっていうことなのだろうけど。
そこの継続とモチベーションとひとりひとりを大切にする、
と場のチカラみたいなやつがリンクしているように僕は思うのです。
そんな話をもやもやしたいなあ。
本の読みなおしと、過去ブログの整理。
健全な負債感を持つという豊かさ
http://hero.niiblo.jp/e472045.html
(15.8.24)
2700円のシュトーレンを買うということ
http://hero.niiblo.jp/e474894.html
(15.12.1)
第四次元の芸術
http://hero.niiblo.jp/e488654.html
(19.1.2)
「顧客」から入るか、「価値」から入るか
http://hero.niiblo.jp/e488667.html
(19.1.4)
「構想力」と「場のチカラ」
http://hero.niiblo.jp/e488729.html
(19.1.15)
このあたり。
もう一度読みつつ、本も読み返して行きます。
一番話したいのは
「支援の話法」だったり「場のチカラ」だったり、
「人を手段化しない」だったり、
「顧客」から入るか、「価値」から入るか、とかかなあ。
1人の「顧客」から入って、
それが多くの人にとっての価値になっていく
っていうのがビジネスの重要なことなのだろうけど。
まさに手紙を届けるっていうことなのだろうけど。
そこの継続とモチベーションとひとりひとりを大切にする、
と場のチカラみたいなやつがリンクしているように僕は思うのです。
そんな話をもやもやしたいなあ。




