2022年10月28日
「きっかけ・行動・学び」のスパイラルの中に自分の「軸」がある
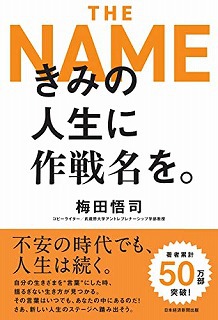
「きみの人生に作戦名を。」(梅田悟司 日本経済新聞出版)
取材型インターン「ひきだし」の事後研修でも
引用させてもらっている「言葉にできるは武器になる」の梅田さんの新刊。
これ、高校でも非常に有用だなあと。
~~~
小説の書き方には2種類があり
・理想から逆算して一歩を踏み出す「バック・キャスティング型」
「プロット」と呼ばれる設計図をもとに骨組みを完成させ肉付けを行う方法
・現在から過去との関係性を見出す「コネクティング・ザ・ドット型」
登場人物をとにかく解像度高く設定し、主人公が動き出すように書いていく方法
村上春樹とかは後者なわけですけど、
http://hero.niiblo.jp/e492460.html
(「つくる」こと、発見と変容 22.5.24)
梅田さんの場合は
「過去と現在を振り返り、近未来を展望しながら、コネクティング・ザ・ドットを行う。そこで得られた大きな物語性を意識しながら、自分軸を見つける。その先にある可能性を意識しながらバック・キャスティングによって超長期を見据えながら超短期を淡々とこなしていく。両者の繰り返しの中で、自分だけの道を見出すべく、言語化と行動を行っている。」のだという。
目に見える「行動」ばかりに気を取られてしまうのではなく、その前後に存在する「きっかけ」と「学び」をセットにする。
「経験」とは「行動」そのものだけでなく、「きっかけ・行動・学び」がセットになったものである。
そこで注目したいのが経験によって生まれた学びが、新たなきっかけとなって、新たな行動を生み出す有機的なつながりである。外から見るとやっていることはバラバラに見えるかもしれないが、自分の中では無意識のうちに学びときっかけがらせん状につながり、歩みを進めているのだ。
きっかけ⇒行動⇒学びと過去⇒現在⇒未来をクロスさせた9マスによって、「行動」の見える一貫性と、らせん状につながる見えない一貫性が見えてくる。
1つひとつの行動に着目しながらも、その行動だけで自分を判断しないこと。そして、様々な行動や出来事の根底に流れている価値観に光を当てることによって見えない一貫性を見ようとすること。
行動単位で考えるのではなく、地続きの人生に意識を向けること。
人生を器として考え、その中に蓄積されているものに光を当てることである。
価値の3階層
1 物性:スペック⇒機能的ベネフィット
2 利便性:メリット⇒情緒的ベネフィット
3 役割:存在意義⇒社会的ベネフィット
~~~
取材型インターンなどをやっていて、一番多く聞かれるキーワードが「軸」だ。
自分の軸を見つけたい。軸になるものが見つからない。軸を見つけるにはどうしたらいいのか。
研修などのアイスブレイクで使われるライフチャート(モチベーショングラフ)は、「出来事」と「感情」をグラフで表したものだ。
http://hero.niiblo.jp/e491346.html
(「場」とともにある「わたしたち」 22.1.12)
自分の「軸」を見つけようとするときに書くべきは、ライフチャートではなくて、「きっかけ・行動・学び」のストーリーだ。
人生において重要なすべての「行動」に、きっかけがあり、学びがある、という前提で、人生を振り返ること。
そこで見えてくるのは、スピノザ的に言うと「コナトゥス」つまりベクトル(方向感)だ。「問い⇒行動⇒ふりかえり」という探究的学びのスパイラルも同じく、行動だけでなく、きっかけと学びを行動と一緒に考えることで、やっと自分自身の軸(≒価値観)が見えてくるのだろう。
探究学習においても、きっかけ(問い)⇒行動⇒学び(ふりかえり)のスパイラルと、振り返りの際の「感情」ふりかえりと「思考スキル」「社会情動スキル」を道具として使えたか?という達成度を測るような振り返りシートをつくっていくことが、将来のキャリア形成における「自分の軸」を自覚することに有効なのではないか、と考えた。
2022年10月24日
学びの舟に乗るための「評価」
東北芸術工科大学での「探究型学習研究大会」に行ってきました。
2020年SCHシンポジウム以来の芸工大でした。


大槌のカンノさんも久しぶりにお会いできました。
現場行ってみたくなりました。
全体的なまとめは報告書に書くとして。
このブログでは田村学先生の演題の3つのテーマのうちのひとつである「評価基準の設定方法」について。今まで僕が思っていた違和感そのものがクリアになったのでここにメモしておきます。
評価基準の基本フォーマット
「~について・~を(学習対象・学習活動)、~しながら・~して、~している(行為)」
~しながら、~してには
思考スキル(比較・分類・関連付け・多面):頭の中で作用するスキルと
社会情動スキル(誠実・外向・協調・開放・安定):行動・態度に現れる非認知能力(テストで測りにくい)
が入る。(評価基準の言語要素)
誠実:最後まで
外向:自分から
協調:力を合わせて
開放:オープンマインドで
安定:状況に左右されない
評価基準の機能・役割
教師:子どもの見取り、授業のデザイン
子ども:言葉による自覚、手ごたえの実感
好奇心・自立的欲求・向社会的欲求⇒学習活動⇒充実感・達成感・自己有能感・一体感⇒次なる好奇心・・・
資質・能力の育成⇒姿の積み重ね・繰り返し このための「評価」
~~~
「授業」があって「評価」があるのではなく、評価基準を定めることで授業を作り上げていく。育てたい資質・能力があり、それをどのように測るかの評価基準があって、そのために授業を設計する。もし、育てたい資質・能力が非認知スキル(態度)である場合は、いわゆるペーパーテストでは測りにくい。そして非認知スキル(態度)を評価する場合は、生徒自身がそれを自覚し、手応えを実感できる必要がある。目指す態度が言語化できているからこそ、生徒は自覚・実感し、それが態度化(変容)につながっていく。
~~~
質疑応答で自己評価とルーブリックについて聞いたのだけど、まさに僕が抱えていた違和感だった数値化に対して、「なんとなく評価できている」という勘違いを生むのでは?と回答いただいた。いやあ、なんかクリアになりました。
「評価」に対する僕自身の認識が一変した。
「評価」って、近代の目標主義の呪縛だと思っていた。
成績をつけるための方法だと思っていた。
でも、そうじゃないよね。
新しい学力観に基づく新カリキュラムになってこれからの学びをともに創っていく、としたら。
教師と生徒は、教える‐教わるの関係ではなくて、資質・能力を育む「学び」という目的地(いや、それはプロセスなのだけど)に向かうための指針(コンパス)を必要としている。
そのコンパスこそが「評価基準」なのかもしれない。「評価基準」は、この舟がどこに向かっているのかを示してくれる。乗組員が力を合わせて、天候不順や外敵と戦い、あるいは外部の協力者とも力を合わせながら、その方向に向かって進んでいく。
学びの舟に乗る。そこには、コンパスが必要だ。
それが「評価」の役割なのではないかと強く感じた1日だった。
夜、金曜日に「焚き火」主催者の山崎さんのホーム・秋保にいってきた。

「焚き火」というコミュニケーションがあるのだと。
「場」の体感という意味でも、非常に楽しい時間となった。
焚き火とは、火であり、音であり、熱であり、匂いであり、空気感なんだよね。
心身の解放とはつまり、五感を解放すること。
その方法、場としての「焚き火」。
焚き火という舟に乗るっていう感じ。
そんな旅が焚き火ではできるのだろう。
舟っていうメタファー、なんだか使えそうですね。
2020年SCHシンポジウム以来の芸工大でした。


大槌のカンノさんも久しぶりにお会いできました。
現場行ってみたくなりました。
全体的なまとめは報告書に書くとして。
このブログでは田村学先生の演題の3つのテーマのうちのひとつである「評価基準の設定方法」について。今まで僕が思っていた違和感そのものがクリアになったのでここにメモしておきます。
評価基準の基本フォーマット
「~について・~を(学習対象・学習活動)、~しながら・~して、~している(行為)」
~しながら、~してには
思考スキル(比較・分類・関連付け・多面):頭の中で作用するスキルと
社会情動スキル(誠実・外向・協調・開放・安定):行動・態度に現れる非認知能力(テストで測りにくい)
が入る。(評価基準の言語要素)
誠実:最後まで
外向:自分から
協調:力を合わせて
開放:オープンマインドで
安定:状況に左右されない
評価基準の機能・役割
教師:子どもの見取り、授業のデザイン
子ども:言葉による自覚、手ごたえの実感
好奇心・自立的欲求・向社会的欲求⇒学習活動⇒充実感・達成感・自己有能感・一体感⇒次なる好奇心・・・
資質・能力の育成⇒姿の積み重ね・繰り返し このための「評価」
~~~
「授業」があって「評価」があるのではなく、評価基準を定めることで授業を作り上げていく。育てたい資質・能力があり、それをどのように測るかの評価基準があって、そのために授業を設計する。もし、育てたい資質・能力が非認知スキル(態度)である場合は、いわゆるペーパーテストでは測りにくい。そして非認知スキル(態度)を評価する場合は、生徒自身がそれを自覚し、手応えを実感できる必要がある。目指す態度が言語化できているからこそ、生徒は自覚・実感し、それが態度化(変容)につながっていく。
~~~
質疑応答で自己評価とルーブリックについて聞いたのだけど、まさに僕が抱えていた違和感だった数値化に対して、「なんとなく評価できている」という勘違いを生むのでは?と回答いただいた。いやあ、なんかクリアになりました。
「評価」に対する僕自身の認識が一変した。
「評価」って、近代の目標主義の呪縛だと思っていた。
成績をつけるための方法だと思っていた。
でも、そうじゃないよね。
新しい学力観に基づく新カリキュラムになってこれからの学びをともに創っていく、としたら。
教師と生徒は、教える‐教わるの関係ではなくて、資質・能力を育む「学び」という目的地(いや、それはプロセスなのだけど)に向かうための指針(コンパス)を必要としている。
そのコンパスこそが「評価基準」なのかもしれない。「評価基準」は、この舟がどこに向かっているのかを示してくれる。乗組員が力を合わせて、天候不順や外敵と戦い、あるいは外部の協力者とも力を合わせながら、その方向に向かって進んでいく。
学びの舟に乗る。そこには、コンパスが必要だ。
それが「評価」の役割なのではないかと強く感じた1日だった。
夜、金曜日に「焚き火」主催者の山崎さんのホーム・秋保にいってきた。

「焚き火」というコミュニケーションがあるのだと。
「場」の体感という意味でも、非常に楽しい時間となった。
焚き火とは、火であり、音であり、熱であり、匂いであり、空気感なんだよね。
心身の解放とはつまり、五感を解放すること。
その方法、場としての「焚き火」。
焚き火という舟に乗るっていう感じ。
そんな旅が焚き火ではできるのだろう。
舟っていうメタファー、なんだか使えそうですね。
2022年10月14日
「推し」と「表現欲求」
自己表現したい。いわゆる表現欲求。
その前には承認の欲求がある。
http://hero.niiblo.jp/e487501.html
参考:「やりたいことがわからない」と「自分に自信がない」(18.5.31)
山竹伸二さんは「認められたいの正体」(講談社現代新書 2011)
の中で、承認の3ステップとして、
「親和的承認」(ありのままの自分を承認される。存在承認)
「集団的承認」(集団の中で役割を果たすことで承認される。役割承認)
「一般的承認」(一般的によいとされていることで承認される。一般承認)
の3つを提示した。
この中でも特に重要だと思ったのが、「親和的承認」、つまり存在の承認である。
工業化や核家族化、脱コミュニティ化が進み、地域行事や祭りがなくなり、家族も離れ離れになり、ついにはウイルスの影響もあり、会社という共同体もその意味では解体されつつある。
失われた機会は、存在承認の場であり、声掛けであり、体感である。
「自分がここに存在していいのか?」
中高生に限らず、自分を含め多くの大人たちもそんな問いを抱えながら生きている。
そこで出てくるのが「推し」である。
昔で言えば「ファン」であろうか。
心理学者アルバート・バンデューラは、自己効力感を高める要因として以下の4つを挙げた
参考:https://studyhacker.net/albert-bandura
1 直接的達成経験
2 代理体験
3 言語的説得
4 生理的・情動的喚起
この 2 代理体験
と、表現欲求とが組み合わさったのが「推し」であると言えるのではないか。自己効力感というほどではないけども「推し」の活躍によって自分自身のテンションが上がるという代理体験がある。
そしてもうひとつは表現欲求。
これは「推し」を通して自分を表現する、というか、そういう感じだ。
人は誰もが承認欲求を前提とした「表現欲求」を持っている、と仮定する。しかし、誰しもがSNSを通じて容易に発信できるようになった現在においても、アーティストや「セルフブランディング」みたいに、自己そのものを表現の対象であり方法にしていくという人は、そんなに多くはないだろう。
だから人は「代理者」つまり「推し」を通じて自己表現をし、「推し」が認められていく(人気が出る)のに伴っていい気分になっていくのだと思う。
それは元を探れば、承認欲求に行き着くのかもしれない。
認められたい。
自分がいまここに存在していていいのか、確かめたい。
http://hero.niiblo.jp/e491214.html
参考:「探究」とスピノザ哲学(20.12.2)
スピノザは人間の本質は形ではなくベクトル(スピノザの言葉で言えばコナトゥス)だと言った。「推し」とはまさに「ベクトル」そのものだ。
たぶん高校生の「マイプロジェクト」も、根源的には表現欲求が、その前には承認の欲求があるのだろうと思う。
存在の承認。まずはそこから構築していく必要がある。
それは表現の欲求の発露の仕方にヒントがあるのかもしれない。
テレビやネット、スポーツの中の「推し」もいいのだけど、リアルな、対話できる、相互フィードバックできる「推し」や「仲間」や「プロジェクト」を実施し、コミュニケーションを来る返しながら何かをつくっていくこと、一緒に表現していくこと。
それを地域がサポートできるといいのかなと思いました。
「推し」の提供も含めて、ね。
その前には承認の欲求がある。
http://hero.niiblo.jp/e487501.html
参考:「やりたいことがわからない」と「自分に自信がない」(18.5.31)
山竹伸二さんは「認められたいの正体」(講談社現代新書 2011)
の中で、承認の3ステップとして、
「親和的承認」(ありのままの自分を承認される。存在承認)
「集団的承認」(集団の中で役割を果たすことで承認される。役割承認)
「一般的承認」(一般的によいとされていることで承認される。一般承認)
の3つを提示した。
この中でも特に重要だと思ったのが、「親和的承認」、つまり存在の承認である。
工業化や核家族化、脱コミュニティ化が進み、地域行事や祭りがなくなり、家族も離れ離れになり、ついにはウイルスの影響もあり、会社という共同体もその意味では解体されつつある。
失われた機会は、存在承認の場であり、声掛けであり、体感である。
「自分がここに存在していいのか?」
中高生に限らず、自分を含め多くの大人たちもそんな問いを抱えながら生きている。
そこで出てくるのが「推し」である。
昔で言えば「ファン」であろうか。
心理学者アルバート・バンデューラは、自己効力感を高める要因として以下の4つを挙げた
参考:https://studyhacker.net/albert-bandura
1 直接的達成経験
2 代理体験
3 言語的説得
4 生理的・情動的喚起
この 2 代理体験
と、表現欲求とが組み合わさったのが「推し」であると言えるのではないか。自己効力感というほどではないけども「推し」の活躍によって自分自身のテンションが上がるという代理体験がある。
そしてもうひとつは表現欲求。
これは「推し」を通して自分を表現する、というか、そういう感じだ。
人は誰もが承認欲求を前提とした「表現欲求」を持っている、と仮定する。しかし、誰しもがSNSを通じて容易に発信できるようになった現在においても、アーティストや「セルフブランディング」みたいに、自己そのものを表現の対象であり方法にしていくという人は、そんなに多くはないだろう。
だから人は「代理者」つまり「推し」を通じて自己表現をし、「推し」が認められていく(人気が出る)のに伴っていい気分になっていくのだと思う。
それは元を探れば、承認欲求に行き着くのかもしれない。
認められたい。
自分がいまここに存在していていいのか、確かめたい。
http://hero.niiblo.jp/e491214.html
参考:「探究」とスピノザ哲学(20.12.2)
スピノザは人間の本質は形ではなくベクトル(スピノザの言葉で言えばコナトゥス)だと言った。「推し」とはまさに「ベクトル」そのものだ。
たぶん高校生の「マイプロジェクト」も、根源的には表現欲求が、その前には承認の欲求があるのだろうと思う。
存在の承認。まずはそこから構築していく必要がある。
それは表現の欲求の発露の仕方にヒントがあるのかもしれない。
テレビやネット、スポーツの中の「推し」もいいのだけど、リアルな、対話できる、相互フィードバックできる「推し」や「仲間」や「プロジェクト」を実施し、コミュニケーションを来る返しながら何かをつくっていくこと、一緒に表現していくこと。
それを地域がサポートできるといいのかなと思いました。
「推し」の提供も含めて、ね。




