2021年09月27日
「つくる」ために一緒に「見て」「感じる」
昨日はオンライン劇場ツルハシブックスvol.17
ゲストはウチノ食堂 藤蔵の野呂巧さん。
いやあ、なかなかのもやもやした時間でしたね。
~~~ここからメモ
その店に行く目的(理由)が1つではないようなお店。
「飲食店」「雑貨屋」とかでくくられないようなお店。
「あいまいさ」「偶然性」をもって人に出会う空間。
「性に合う」っていわゆる「生きるように働く」ってやつか。身体的にも、精神的にも。
フランスのカフェも、イギリスのパブも、スペインのバルも。いろんな人がいろんな使い方をしている場所。日本でいえば、酒も飲める大衆食堂、か。または本屋。
TSUTAYAの最大の魅力は、目的なく行ける場所だったことなのかもな。目的がないから落ちている「偶然」にレスポンス(反応)できる。
「日常」が「目的」によって余白部分を失いつつある。「余白」とは境界のあいまいな部分にある何か。多様性を受け入れ可能にするのは「余白」であると思うのだけど、「多様性が大事だ」と言葉にしてしまうとそこが「余白」ではなくなる気がする。
「日常」が「目的」によって余白部分を失いつつある。「余白」とは境界のあいまいな部分にある何か。
多様性を受け入れ可能にするのは「余白」であると思うのだけど、「多様性が大事だ」と言葉にしてしまうとそこが「余白」ではなくなる気がする。
~~~
とここまでは前座。
ここからが「食堂から見える人類学」の話です。
~~~
「お店という装置を通してどうまちを観察するか?」という問い。
「定食」がこの町にない。米屋も味噌屋もある町で、定食が出せるのではないか。
そこに来る人と何ができるか、考えたいし、一緒につくりたい。
自分もこの町に入り込んだ。取材を受けた時、それが自分に来ているのか、お店に来ているのか、戸惑った。「自分ーお店」は同時に変わっている。変化し合う関係。
学問とは自分と「(研究)対象」を分けて考える。自分と対象あいだに境界線を引く。そんな線を引いている時代じゃない。
「はみだしの人類学」思い出しました。
http://hero.niiblo.jp/e491269.html
他者との「つながり」によって「わたし」の輪郭がつくり出され、同時にその輪郭からはみ出す動きが変化へと導いていく。だとしたら、どんな他者と出会うかが重要な鍵になる。
その「はみだし方」が「一回性」(一期一会)をつくるのかもしれません。その瞬間の感じ合い、はみだし合う関係性が。
「つくる」前に「感じる」ことがあり、「感じる」前に「見る(観る、視る)」ことがある。お店づくり、場づくりをするには、まずは「店」や「場」を一緒に見つめて、感じて、そして創っていくんだ。
向き合わずに、同じ方向を見つめること。これが「つくる」コミュニケーションの基本なのではないか。1対1で向き合う関係ではなく、そこに見つめる対象をつくること。余白(隙)があったら自分も創造性を発揮できるような「場」。そういうもの。
「コワーキングスペース」と「商店街」の違い。
コワーキング:「コラボレーション」のためにあなたの「スキル」を提示してください、っていう。
商店街:暮らしを前提として、そこにいるメンバーでブリコラージュしてつくっていきましょう、っていう。
~~~
「愛するということはお互いに見つめ合うことではなく、一緒に同じ方向を見ること」(サンテクジュペリ)を思い出した。
そしてやはり、観察すること。
「つくる」ためのプロセスについて、考えさせられた。
お店のような「リアルメディア」において、
一回性の高い(一期一会の)場をつくるには、
そういうプロセスが必要なんだと。
一緒に
場を見つめること。
場を感じること。
そして、場に溶けていくこと。
野呂さんが言っていた
「そこに来る人と何ができるか、考えたいし、一緒につくりたい。」
っていうの。
そこに戻っていきたいな、って思った。
境界をあいまいにし、余白をつくり、場に溶けていく。
そんな空間を、場をつくっていくこと。
一緒に観て、感じること。
そこからしか「つくる」は始まらない。
ゲストはウチノ食堂 藤蔵の野呂巧さん。
いやあ、なかなかのもやもやした時間でしたね。
~~~ここからメモ
その店に行く目的(理由)が1つではないようなお店。
「飲食店」「雑貨屋」とかでくくられないようなお店。
「あいまいさ」「偶然性」をもって人に出会う空間。
「性に合う」っていわゆる「生きるように働く」ってやつか。身体的にも、精神的にも。
フランスのカフェも、イギリスのパブも、スペインのバルも。いろんな人がいろんな使い方をしている場所。日本でいえば、酒も飲める大衆食堂、か。または本屋。
TSUTAYAの最大の魅力は、目的なく行ける場所だったことなのかもな。目的がないから落ちている「偶然」にレスポンス(反応)できる。
「日常」が「目的」によって余白部分を失いつつある。「余白」とは境界のあいまいな部分にある何か。多様性を受け入れ可能にするのは「余白」であると思うのだけど、「多様性が大事だ」と言葉にしてしまうとそこが「余白」ではなくなる気がする。
「日常」が「目的」によって余白部分を失いつつある。「余白」とは境界のあいまいな部分にある何か。
多様性を受け入れ可能にするのは「余白」であると思うのだけど、「多様性が大事だ」と言葉にしてしまうとそこが「余白」ではなくなる気がする。
~~~
とここまでは前座。
ここからが「食堂から見える人類学」の話です。
~~~
「お店という装置を通してどうまちを観察するか?」という問い。
「定食」がこの町にない。米屋も味噌屋もある町で、定食が出せるのではないか。
そこに来る人と何ができるか、考えたいし、一緒につくりたい。
自分もこの町に入り込んだ。取材を受けた時、それが自分に来ているのか、お店に来ているのか、戸惑った。「自分ーお店」は同時に変わっている。変化し合う関係。
学問とは自分と「(研究)対象」を分けて考える。自分と対象あいだに境界線を引く。そんな線を引いている時代じゃない。
「はみだしの人類学」思い出しました。
http://hero.niiblo.jp/e491269.html
他者との「つながり」によって「わたし」の輪郭がつくり出され、同時にその輪郭からはみ出す動きが変化へと導いていく。だとしたら、どんな他者と出会うかが重要な鍵になる。
その「はみだし方」が「一回性」(一期一会)をつくるのかもしれません。その瞬間の感じ合い、はみだし合う関係性が。
「つくる」前に「感じる」ことがあり、「感じる」前に「見る(観る、視る)」ことがある。お店づくり、場づくりをするには、まずは「店」や「場」を一緒に見つめて、感じて、そして創っていくんだ。
向き合わずに、同じ方向を見つめること。これが「つくる」コミュニケーションの基本なのではないか。1対1で向き合う関係ではなく、そこに見つめる対象をつくること。余白(隙)があったら自分も創造性を発揮できるような「場」。そういうもの。
「コワーキングスペース」と「商店街」の違い。
コワーキング:「コラボレーション」のためにあなたの「スキル」を提示してください、っていう。
商店街:暮らしを前提として、そこにいるメンバーでブリコラージュしてつくっていきましょう、っていう。
~~~
「愛するということはお互いに見つめ合うことではなく、一緒に同じ方向を見ること」(サンテクジュペリ)を思い出した。
そしてやはり、観察すること。
「つくる」ためのプロセスについて、考えさせられた。
お店のような「リアルメディア」において、
一回性の高い(一期一会の)場をつくるには、
そういうプロセスが必要なんだと。
一緒に
場を見つめること。
場を感じること。
そして、場に溶けていくこと。
野呂さんが言っていた
「そこに来る人と何ができるか、考えたいし、一緒につくりたい。」
っていうの。
そこに戻っていきたいな、って思った。
境界をあいまいにし、余白をつくり、場に溶けていく。
そんな空間を、場をつくっていくこと。
一緒に観て、感じること。
そこからしか「つくる」は始まらない。
2021年09月26日
「プロモート」のために観察し、感じること
探究学習コミュニティ2回目。
ゲストは後藤寛勝さんと水戸部智さん。
新潟で活躍する2名から学ぶ「探究的」な姿勢。
シビれる名言だらけでしたのでメモに残します。
~~~
「未来の自分に期待しない」「自分の世界を広げられるのは自分だけ」
このまま受験勉強に取り組む、というのは「思考停止への恐怖感」があった。
違和感のキャッチと言語化。思考停止しないために、その機会と時間を持つこと。
「国公立大学に入学する」という理想的生徒像をプロデュースする先生という構図から、「何がやりたいがわからない」から、たくさん拾い上げて助長するというプロモートする地域の大人と先生という構図へ。
「プロデュース」と「プロモート」。
「プロモート」とは、予測不可能な未来に対しての謙虚な姿勢のような気がした。
「プロデュース」するほど、未来に確信ありますか?っていう。
「ファシリテーター」は「プロデューサー」ではなく「プロモーター」なのか。
プロデュースの主体は自分(プロデューサー)で、プロモートの主体は商品。
「プロモーション」とは、商品の特長を引き出して、アピールすること。
以上後藤さん
人から求められること⇒最後のバッターボックスだな、って。最後のバッターボックス。っていいな。機会を大切にしようと。バット振っていこうと。
地域に「ふれる」⇒やりたいことを「さがす」⇒自分らしい生き方に「きづく」⇒目標に向かって「うごく」
すこしずつ、すこしずつ。
「調べる」⇒「考える」⇒「やってみる」を繰り返す。
繰り返しの中で自分のモノサシが見つかる。⇒周りの評価基準に左右されなくなる。
挫折=モノサシの精度が上がる
パッションを維持できるか⇔金を回せるか
という事業の両輪。
WHYとHOWの両輪、か。
なぜ今、自分がそれをやらないといけないのか?に答え続けること。
以上水戸部さん
~~~
「やりたいことがわからない」というときのやりたいことって、whatじゃなくてwhyなのでは、と思った。
なぜ?を教えてほしいんだ。でも、なぜ?は、主観であり、その源泉は自分の中にしかない。「経験」から「違和感」をキャッチし「なぜ?」を磨こう、と。
昨日の最大の学びは「自分を信じすぎないこと」でした。
「信じること」より「感じること」
「プロデュース」から「プロモート」へのシフト。
予測不可能な「未来」に対するリスペクトを。
「挑戦」よりも「実験」のほうが、観察したり、感じたりすることに重点が置かれそう。成果を示すよりも、結果を観察しよう、と。
そんな基本姿勢が大切なのでは、と思っていたら、タイミングよく1冊の本が。

「観察力の鍛え方」(佐渡島庸平 SB新書)
いやあ、タイミングがいいなあと。
「探究学習に必要な姿勢」ってこういうことなのではないかと。
一方で、現在行われているいわゆる「キャリア教育」っていうのが大丈夫かなと。
少し抜粋メモ
~~~
いい観察は、ある主体が、物事に対して仮説を持ちながら、客観的に物事を観て、仮説とその物事の状態のズレに気づき、仮説の更新を促す。
計画→実行→振り返り→計画というサイクルにおいて、起点にすべきは計画ではなくて、振り返り。
オリジナリティとは、型がないのではない。型と型を組み合わせるときに生まれる。いかに遠い型と組み合わせるかが革新を生み出す。
自問自答を繰り返すことで、価値観をモノサシへの進化させる、か。
~~~
読んでいて、「自信がない」っていうのは観察力を鍛える、という意味ではいいことなのではないか、って思えてきた。
自信がない、というのは、観察することが得意になる可能性があるということ。「自信がない」という相談を受けたら「観察力を磨け」とアドバイスするのがいいのかも、と。
今朝は第3章「観察は、いかに歪むか 認知バイアス」を読んでいたのだけど、これはホント、その通りすぎてすごいな、と。
以下に一覧で挙げておく。
・確証バイアス:仮説を強化する情報ばかりが見えるようになる
・ネガティビティバイアス:ポジティブな未来は漠然としか描けないがネガティブなことは仔細に思い浮かぶ
・同調バイアス:みんながそう言っているから、と多数派の意見を支持すること
・ハロー効果:顕著に目立つある特徴に引きずられて、他の特徴がゆがめられる
・生存者バイアス:成功した人の意見には特別な何かがあると思ってしまう
・根本的な帰属の誤り:問題の原因を個人の資質や能力に求めてしまう
・後知恵バイアス:物事が起きてから、それが予測可能だったと考える傾向
・正常性バイアス:異常事態になった時に、パニックになるのを防ぐために、予期せぬ出来事には鈍感に反応するバイアス
~~~
各バイアスにどのように対処し、あるいはむしろそのバイアスを推進力に変えていくか?については、本書を読んで頂きたい。
今日は2つ紹介します。
1つ目はネガティビティバイアスについて
自然の中に暮らしていてどこに危険が潜んでいるかわからない時代は、悲観的であることが、人の生存を助けたのだろう。
そうか。「自信がない」とか「悲観的に考える」っていうのは動物である人にとってはデフォルト(初期設定)なんだな、と。
2つ目は「炎上」について。「炎上」とは現代の魔女狩りで、後知恵バイアスと根本的な帰属の誤りによって起こる。
昔の魔女狩りと同じことが形を変えて、現代でも再現されている。昔は火炙りになり殺されたが、今はマスコミ、SNSで集中砲火にあい、社会的地位から引きずりおろされる。本人の意思や能力が本当に問題であれば、魔女がいなくなれば状態は改善されるはずだが、環境、仕組みが要因だから何も変わらない。そして、また次の魔女を探しにかかる。リーダーを担える能力と気概のある人が、社会から排除されていき、緩やかに社会は弱体化していく。
昔の人たちは、この2つのバイアスで間違った判断をしすぎるのを防ぐために、「妖精」を考え出したのかなと僕は思う。
もしも、起きている問題が、妖精のせいであれば、個人を責める必要がなくなる。集団全体の気持ちが、個人の人格へと執着するのを防ぐ。代わりに、妖精の気持ちを鎮めるための儀式が必要になるのだ。
妖精は、昔の人たちが、無知だから信じてしまった迷信ではない。対立を生み出すことなく、バイアスから自分たちを守る、人間ならではの知恵なのではないか。その知恵を僕たちは、科学的であることが正義であるという考えの下に捨ててしまった。
~~~
うーん、なるほど、と。
「科学的であること」の迷走が起こっているのだなあと。
バイアスの話を読んでいて思ったのだけど、世の自己啓発本と呼ばれている本の多くは、バイアスの強化もしくはバイアスの否定なんだな。成功者の○○とか、不安の何%は幻想、だとか。「バイアス」とは何かを認識することって大事だ。そのメガネで見えてます?みたいな。そう考えると、いわゆる「キャリア教育」で行われていることっていうのはバイアスだらけでまったく科学的じゃないな、と。
探究学習の起点も、科学の原点に返り
「観察」と「振り返り(そして発見)」に置いた方がいいのだなと。
僕たちはバイアスという色眼鏡を通して世の中を見ている、いや自分自身に対してもそうなのかもしれない。自分はこういう性格だから、とか。ジョハリの窓とかそういうのを外して見てみる効果があるのかも。
探究学習コミュニティでも言っていた、「プロデュース」と「プロモート」の違い。
「自分が信じる未来」がいかに危ういか。
そんな前提に立たなければいけないのではないか。
生徒の特徴を生かし、伸ばしていく「プロモート」のために、「観察」し、「感じる」ことを強化しないといけない。
そして、この本の中に何度も出てくるコルクのミッション「物語の力で一人一人の世界を変える」に影響を受けて、僕もミッションを暫定で書いてみようと思った。
フラットな関係性をつくるコミュニケーションのデザインによって「場」をつくり、自分と地域とまなびの未来を、いま、ここから創造する。
ちょっとまだ長いので、シンプルにまとめようと思う。
ゲストは後藤寛勝さんと水戸部智さん。
新潟で活躍する2名から学ぶ「探究的」な姿勢。
シビれる名言だらけでしたのでメモに残します。
~~~
「未来の自分に期待しない」「自分の世界を広げられるのは自分だけ」
このまま受験勉強に取り組む、というのは「思考停止への恐怖感」があった。
違和感のキャッチと言語化。思考停止しないために、その機会と時間を持つこと。
「国公立大学に入学する」という理想的生徒像をプロデュースする先生という構図から、「何がやりたいがわからない」から、たくさん拾い上げて助長するというプロモートする地域の大人と先生という構図へ。
「プロデュース」と「プロモート」。
「プロモート」とは、予測不可能な未来に対しての謙虚な姿勢のような気がした。
「プロデュース」するほど、未来に確信ありますか?っていう。
「ファシリテーター」は「プロデューサー」ではなく「プロモーター」なのか。
プロデュースの主体は自分(プロデューサー)で、プロモートの主体は商品。
「プロモーション」とは、商品の特長を引き出して、アピールすること。
以上後藤さん
人から求められること⇒最後のバッターボックスだな、って。最後のバッターボックス。っていいな。機会を大切にしようと。バット振っていこうと。
地域に「ふれる」⇒やりたいことを「さがす」⇒自分らしい生き方に「きづく」⇒目標に向かって「うごく」
すこしずつ、すこしずつ。
「調べる」⇒「考える」⇒「やってみる」を繰り返す。
繰り返しの中で自分のモノサシが見つかる。⇒周りの評価基準に左右されなくなる。
挫折=モノサシの精度が上がる
パッションを維持できるか⇔金を回せるか
という事業の両輪。
WHYとHOWの両輪、か。
なぜ今、自分がそれをやらないといけないのか?に答え続けること。
以上水戸部さん
~~~
「やりたいことがわからない」というときのやりたいことって、whatじゃなくてwhyなのでは、と思った。
なぜ?を教えてほしいんだ。でも、なぜ?は、主観であり、その源泉は自分の中にしかない。「経験」から「違和感」をキャッチし「なぜ?」を磨こう、と。
昨日の最大の学びは「自分を信じすぎないこと」でした。
「信じること」より「感じること」
「プロデュース」から「プロモート」へのシフト。
予測不可能な「未来」に対するリスペクトを。
「挑戦」よりも「実験」のほうが、観察したり、感じたりすることに重点が置かれそう。成果を示すよりも、結果を観察しよう、と。
そんな基本姿勢が大切なのでは、と思っていたら、タイミングよく1冊の本が。

「観察力の鍛え方」(佐渡島庸平 SB新書)
いやあ、タイミングがいいなあと。
「探究学習に必要な姿勢」ってこういうことなのではないかと。
一方で、現在行われているいわゆる「キャリア教育」っていうのが大丈夫かなと。
少し抜粋メモ
~~~
いい観察は、ある主体が、物事に対して仮説を持ちながら、客観的に物事を観て、仮説とその物事の状態のズレに気づき、仮説の更新を促す。
計画→実行→振り返り→計画というサイクルにおいて、起点にすべきは計画ではなくて、振り返り。
オリジナリティとは、型がないのではない。型と型を組み合わせるときに生まれる。いかに遠い型と組み合わせるかが革新を生み出す。
自問自答を繰り返すことで、価値観をモノサシへの進化させる、か。
~~~
読んでいて、「自信がない」っていうのは観察力を鍛える、という意味ではいいことなのではないか、って思えてきた。
自信がない、というのは、観察することが得意になる可能性があるということ。「自信がない」という相談を受けたら「観察力を磨け」とアドバイスするのがいいのかも、と。
今朝は第3章「観察は、いかに歪むか 認知バイアス」を読んでいたのだけど、これはホント、その通りすぎてすごいな、と。
以下に一覧で挙げておく。
・確証バイアス:仮説を強化する情報ばかりが見えるようになる
・ネガティビティバイアス:ポジティブな未来は漠然としか描けないがネガティブなことは仔細に思い浮かぶ
・同調バイアス:みんながそう言っているから、と多数派の意見を支持すること
・ハロー効果:顕著に目立つある特徴に引きずられて、他の特徴がゆがめられる
・生存者バイアス:成功した人の意見には特別な何かがあると思ってしまう
・根本的な帰属の誤り:問題の原因を個人の資質や能力に求めてしまう
・後知恵バイアス:物事が起きてから、それが予測可能だったと考える傾向
・正常性バイアス:異常事態になった時に、パニックになるのを防ぐために、予期せぬ出来事には鈍感に反応するバイアス
~~~
各バイアスにどのように対処し、あるいはむしろそのバイアスを推進力に変えていくか?については、本書を読んで頂きたい。
今日は2つ紹介します。
1つ目はネガティビティバイアスについて
自然の中に暮らしていてどこに危険が潜んでいるかわからない時代は、悲観的であることが、人の生存を助けたのだろう。
そうか。「自信がない」とか「悲観的に考える」っていうのは動物である人にとってはデフォルト(初期設定)なんだな、と。
2つ目は「炎上」について。「炎上」とは現代の魔女狩りで、後知恵バイアスと根本的な帰属の誤りによって起こる。
昔の魔女狩りと同じことが形を変えて、現代でも再現されている。昔は火炙りになり殺されたが、今はマスコミ、SNSで集中砲火にあい、社会的地位から引きずりおろされる。本人の意思や能力が本当に問題であれば、魔女がいなくなれば状態は改善されるはずだが、環境、仕組みが要因だから何も変わらない。そして、また次の魔女を探しにかかる。リーダーを担える能力と気概のある人が、社会から排除されていき、緩やかに社会は弱体化していく。
昔の人たちは、この2つのバイアスで間違った判断をしすぎるのを防ぐために、「妖精」を考え出したのかなと僕は思う。
もしも、起きている問題が、妖精のせいであれば、個人を責める必要がなくなる。集団全体の気持ちが、個人の人格へと執着するのを防ぐ。代わりに、妖精の気持ちを鎮めるための儀式が必要になるのだ。
妖精は、昔の人たちが、無知だから信じてしまった迷信ではない。対立を生み出すことなく、バイアスから自分たちを守る、人間ならではの知恵なのではないか。その知恵を僕たちは、科学的であることが正義であるという考えの下に捨ててしまった。
~~~
うーん、なるほど、と。
「科学的であること」の迷走が起こっているのだなあと。
バイアスの話を読んでいて思ったのだけど、世の自己啓発本と呼ばれている本の多くは、バイアスの強化もしくはバイアスの否定なんだな。成功者の○○とか、不安の何%は幻想、だとか。「バイアス」とは何かを認識することって大事だ。そのメガネで見えてます?みたいな。そう考えると、いわゆる「キャリア教育」で行われていることっていうのはバイアスだらけでまったく科学的じゃないな、と。
探究学習の起点も、科学の原点に返り
「観察」と「振り返り(そして発見)」に置いた方がいいのだなと。
僕たちはバイアスという色眼鏡を通して世の中を見ている、いや自分自身に対してもそうなのかもしれない。自分はこういう性格だから、とか。ジョハリの窓とかそういうのを外して見てみる効果があるのかも。
探究学習コミュニティでも言っていた、「プロデュース」と「プロモート」の違い。
「自分が信じる未来」がいかに危ういか。
そんな前提に立たなければいけないのではないか。
生徒の特徴を生かし、伸ばしていく「プロモート」のために、「観察」し、「感じる」ことを強化しないといけない。
そして、この本の中に何度も出てくるコルクのミッション「物語の力で一人一人の世界を変える」に影響を受けて、僕もミッションを暫定で書いてみようと思った。
フラットな関係性をつくるコミュニケーションのデザインによって「場」をつくり、自分と地域とまなびの未来を、いま、ここから創造する。
ちょっとまだ長いので、シンプルにまとめようと思う。
2021年09月20日
「自分に自信がない」の社会学
本日の黎明ラヂオに向けてまとめておこう思います。
「やりたいことがわからない」はなぜ苦しいのか?
プレ企画第2弾「自分に自信がない」の社会学です。
1 天職などない
2 自信は要らない
3 試作の時代へ
です。
2013年当初に、金沢大学などでお話しさせてもらってものを書き直しました。
まずは
1天職などない
「13歳のハローワーク」と「世界にひとつだけの花」の2003年問題によってかけられた呪いについて。
デューク大学のデビッドソン博士の話。⇒これ、もう古いのかな。
を題材に。
そして本題
2 自信は要らない へ。
・固定的知能観と成長的知能観
・「自信がない」後天的に獲得した資質である。
・スラムダンク理論でやってみる「みんなでやればできる、かもしれない。」
3 試作の時代 へ
・答えがわからない時代」っていうのは「答えが存在しない時代」ではなくて「ひとりひとりに違う答えがある時代」という意味であり、しかもそれがいま共にしている「場」(誰といつどこで)によって変わり続けるから、暫定の答えでしかない、ということ。
予測不可能な時代
・「挑戦」という言葉への違和感。
・「挑戦」⇒「実験」:挑戦には成功or失敗があるが、実験には結果and発見がある。
・エジソン「私は失敗したことがない。ただ、1万通りの、うまく行かない方法を見つけただけだ。」
「未来」「自分」「意志」「挑戦」⇒明治時代以降に発明されたのでは?
※工業社会における価値
1 計画通りにできる
2 均一につくる
3 効率化する
学校でいうところの
⇒「目標」「計画」「努力」「反省」
⇒自信を失っていく仕組み
何のために学ぶのか?
私たちが学ぶのは、万人向けの有用な知識や技術を習得するためではありません。自分がこの世界でただひとりのかけがえのない存在であるという事実を確認するために私たちは学ぶのです。
先生は「私がこの世に生まれたのは、私にしかできない仕事、私以外の誰によっても代替できないような責務を果たすためではないか・・・」と思った人の前だけに姿を現します。
(「先生はえらい」内田樹 ちくまプリマー新書)
何のための教育なのか?
われわれは子どもたちを格付けして資源分配するために教育をしているのか、それとも子どもたち一人一人のうちの生きる知恵と力を育てるために教育しているのか、そんなことは考えるまでもないことです。そして、一人一人の生きる知恵と力を高めるためには他人と比べて優劣を論じることには何の意味もありません。まったく、何の意味もないのです。
集団を存続させるためには、子どもたちに、ある年齢に達したら「生き延びるための知識と技術」を教え込む。それが教育です。教育する主体は集団なのです。そして、教育の受益者も集団なのです。集団が存続していくというしかたで集団が受益する。
教育の受益者は子どもたち個人ではなく、共同体そのものです。共同体がこれからも継続して、人々が健康で文化的な生活ができるように、われわれは子どもを教育する。
(「サル化する世界」(内田樹 文藝春秋)
「やりたいことがわからない」はなぜ苦しいのか?
プレ企画第2弾「自分に自信がない」の社会学です。
1 天職などない
2 自信は要らない
3 試作の時代へ
です。
2013年当初に、金沢大学などでお話しさせてもらってものを書き直しました。
まずは
1天職などない
「13歳のハローワーク」と「世界にひとつだけの花」の2003年問題によってかけられた呪いについて。
デューク大学のデビッドソン博士の話。⇒これ、もう古いのかな。
を題材に。
そして本題
2 自信は要らない へ。
・固定的知能観と成長的知能観
・「自信がない」後天的に獲得した資質である。
・スラムダンク理論でやってみる「みんなでやればできる、かもしれない。」
3 試作の時代 へ
・答えがわからない時代」っていうのは「答えが存在しない時代」ではなくて「ひとりひとりに違う答えがある時代」という意味であり、しかもそれがいま共にしている「場」(誰といつどこで)によって変わり続けるから、暫定の答えでしかない、ということ。
予測不可能な時代
・「挑戦」という言葉への違和感。
・「挑戦」⇒「実験」:挑戦には成功or失敗があるが、実験には結果and発見がある。
・エジソン「私は失敗したことがない。ただ、1万通りの、うまく行かない方法を見つけただけだ。」
「未来」「自分」「意志」「挑戦」⇒明治時代以降に発明されたのでは?
※工業社会における価値
1 計画通りにできる
2 均一につくる
3 効率化する
学校でいうところの
⇒「目標」「計画」「努力」「反省」
⇒自信を失っていく仕組み
何のために学ぶのか?
私たちが学ぶのは、万人向けの有用な知識や技術を習得するためではありません。自分がこの世界でただひとりのかけがえのない存在であるという事実を確認するために私たちは学ぶのです。
先生は「私がこの世に生まれたのは、私にしかできない仕事、私以外の誰によっても代替できないような責務を果たすためではないか・・・」と思った人の前だけに姿を現します。
(「先生はえらい」内田樹 ちくまプリマー新書)
何のための教育なのか?
われわれは子どもたちを格付けして資源分配するために教育をしているのか、それとも子どもたち一人一人のうちの生きる知恵と力を育てるために教育しているのか、そんなことは考えるまでもないことです。そして、一人一人の生きる知恵と力を高めるためには他人と比べて優劣を論じることには何の意味もありません。まったく、何の意味もないのです。
集団を存続させるためには、子どもたちに、ある年齢に達したら「生き延びるための知識と技術」を教え込む。それが教育です。教育する主体は集団なのです。そして、教育の受益者も集団なのです。集団が存続していくというしかたで集団が受益する。
教育の受益者は子どもたち個人ではなく、共同体そのものです。共同体がこれからも継続して、人々が健康で文化的な生活ができるように、われわれは子どもを教育する。
(「サル化する世界」(内田樹 文藝春秋)
2021年09月19日
コミュニケーション・ツール
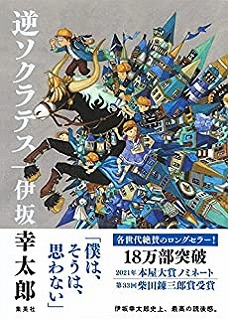
「逆ソクラテス」(伊坂幸太郎 集英社)
陽気なギャングが地球を回す、チルドレン以来の伊坂幸太郎3作目。
いやあ、すごいなあって。
小説家ってすごいな。
文章を通して「何か」を伝えてくるんだ、「何か」を。
まだ3つ目までしか読んでないのだけど、
心が持っていかれる感じがすごい。
コミュニケーション・ツール。
言葉は言葉でも、
文章は文章でも、
プレゼンとして伝えるのか、論文として伝えるのか、小説として伝えるのか。
そういうところに美学があるのだろうな、と。
「リアルメディア」
これは本屋を終えてみてから気がついたテーマでした。
「里山十帖」に見学に行った2018年10月
http://hero.niiblo.jp/e488269.html
11月には「流しのこたつ」デビューをして
http://hero.niiblo.jp/e488340.html
19年5月には桜新町の「屋台」へ
http://hero.niiblo.jp/e489321.html
僕は「本のある場」を通じて伝えようとしている。
それは、スピノザ哲学的な世界なのかもしれない。
ありえたかもしれない、もうひとつの近代(19.4.18)
http://hero.niiblo.jp/e489179.html
~~~
フーコーの「主体の解釈学」。かつて真理は体験の対象であり、それにアクセスするためには主体の変容が必要とされていた。ある真理に到達するためには、主体が変容を遂げ、いわばレベルアップしなければならない。そのレベルアップを経てはじめてその真理に到達できる。
この考え方が変わったのは17世紀であり、フーコーはその転換点を「デカルト的契機」と呼んでいます。デカルト以降、真理は主体の変容を必要としない、単なる認識の対象になってしまったというのです。
フーコーはしかし、17世紀には一人例外がいて、それがスピノザだと言っています。スピノザには、真理の獲得のためには主体の変容が必要だという考え方が残っているというわけです。これは実に鋭い指摘です。
~~~
僕が「場のチカラ」「チューニング」「発見と変容」「見つけ合い」と言っているのは、このことなんじゃないか、と。
「場」に溶けて、「場」を主体に創造することによって、アイデンティティが構築される。
その「アイデンティティ」は固定的なものではなく、常に流動しているアイデンティティだ。
万人にとっての真理があるとするデカルト的哲学と、真理はそれぞれにあり、しかもそこには変容が前提となっているスピノザ的哲学
近代が終わりを告げようとしている今、どちらが時代にあっているんだろうか。
っていうのを、問いかけたいのだよね。たぶん。
そういう「対話の場」をつくってみるのです。
ということで、「やりたいことがわからない」はなぜ苦しいのか?
明日もプレをやりますが、来月あたりから始動します。
対象は15歳~25歳です。
企画経緯
https://note.com/tsuruhashi/n/n1d9934a7ba5c
企画概要
https://note.com/tsuruhashi/n/n18ac03fcf903
2021年09月04日
「場」という舟とともに流れる自分を感じること
昨日は、探究学習コミュニティの1回目でした。
テーマはメンタルモデルを知ること。
メンタルモデルについてはこちらから。
https://sevendex.com/post/322/
こんな学びをつくりたい⇒壁になっていることは?⇒そこにあるメンタルモデルは?
というワークをグループで行いました。
僕は、キーワード的には、
発見と変容とか、伴奏者によるジャズセッションのような学びとか、書いたのですが、
一番はやはり学びの主体を「個人」から「場」へとシフトさせたい、ということでした。
そのための壁はやはり「定期テスト」かなあと。
そこにあるメンタルモデルは、評価軸がひとつで先生方がなにをもって自分たちの成果を含めて評価するのか?という問いに対して、探究学習が答えられにくい、というのがあるなあと思いました。
「評価」の呪縛だし、評価の前には「計測可能」「再現可能」であるという教育を含めた「科学」の前提も影響しているなあと。
それ以前には昨日のメモマップにも書いたけど、工業社会という前提があるのではないかなあと。
もうひとつの見つかった課題は僕自身が、「個」から「場」へと、言ってはいるけど、それがわかりやすい言葉や感覚では伝えきれていないので、そこは試行錯誤する必要があるなと。一方で言葉にすると失われるものがあるから、そこにも注意して言語と非言語(感覚)の双方からアプローチが必要だなあと。
そんな振り返りをしていたら、朝読書はタイムリーにこの本が。
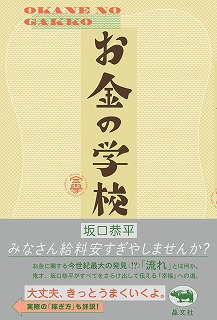
「お金の学校」(坂口恭平 晶文社)
第7章 頭の中(お花)畑だよねあんた
から。
~~~
詩はお金になりません。しかしだからといって経済ではないとは断定できないんです。(中略)お金とは経済です。でも数多ある経済のうちの一つなんです。
コツは、楽しくない時間を経済にしないことです。やりたくないことはしない。(中略)理由はそれではお金を稼げないだけでなく、他の経済の流れも堰き止めてしまうからです。
畑の中では経済がぐるぐると回り回っています。流れてます。いい感じです。心地いいです。何よりも楽しいです。
なぜなら植物は自分自身が経済であることに気付いているからです。
植物は自分が経済であることを知っている。一方、人間は自分が経済であることを知らないんです。もう困ったものです。その挙句「私はなんのために生きているのかわからない」なんてことをぬかす、いや、失礼、嘆いてしまうんです。いやはや!
植物はなんで自分が経済であることを知っているんでしょうか。簡単なことです、一人じゃないからです。植物がどこかに生えると、というか生える前から植物はすでに土の中にいまして、その時点で一人じゃありません。土がベッドです。
作品を外に発表すると、流れが発生します。経済が生まれてます。経済は素直であればあるほど、生であればあるほど、その人の一番自然な部分であればあるほど、すくすくと、植物なんですから、どんどん伸びていきます。どこまでも届いていきます。
僕の経済は常にみんなの経済なのです。僕は経済です。みんなは経済です。僕と経済とみんなは、一つの大きな流れなのです。海みたいなものです。どこまでも流れていきましょう。
~~~
きましたね。タイミングよく。「個人」じゃなくて「場」を主体にする、ということに大きなヒントがあります。
その「場」とは「流れ」の中にある「場」であり、「場」に溶けだしている自分も「流れ」を感じているはずです。
植物は自分が「経済」であることを知っている。
この本でいうところの「経済」である、とは、「流れ」があるということ。
いや、そもそも自分自身が「経済」、つまり「流れ」である、ということ。
そういう意味では、「場」とは、「流れ」のある川の中に浮かぶ小さな船のようです。
ひとりひとりも「経済」つまり「流れ」であり、また「船」でもあるのでしょう。
そのことを実感・体感したとき、「自分」とか「意志」とか、そのような問いが無効化されていくのかもしれません。
僕が探究学習でつくりたいのは、そんな「場」であり、「舟」であり、「瞬間」なのだと思いました。
体験と、言語と感覚(非言語)で、そこにアプローチしていきたいなと思います。
コミュニティの皆様、3月までよろしくお願いいたします。
テーマはメンタルモデルを知ること。
メンタルモデルについてはこちらから。
https://sevendex.com/post/322/
こんな学びをつくりたい⇒壁になっていることは?⇒そこにあるメンタルモデルは?
というワークをグループで行いました。
僕は、キーワード的には、
発見と変容とか、伴奏者によるジャズセッションのような学びとか、書いたのですが、
一番はやはり学びの主体を「個人」から「場」へとシフトさせたい、ということでした。
そのための壁はやはり「定期テスト」かなあと。
そこにあるメンタルモデルは、評価軸がひとつで先生方がなにをもって自分たちの成果を含めて評価するのか?という問いに対して、探究学習が答えられにくい、というのがあるなあと思いました。
「評価」の呪縛だし、評価の前には「計測可能」「再現可能」であるという教育を含めた「科学」の前提も影響しているなあと。
それ以前には昨日のメモマップにも書いたけど、工業社会という前提があるのではないかなあと。
もうひとつの見つかった課題は僕自身が、「個」から「場」へと、言ってはいるけど、それがわかりやすい言葉や感覚では伝えきれていないので、そこは試行錯誤する必要があるなと。一方で言葉にすると失われるものがあるから、そこにも注意して言語と非言語(感覚)の双方からアプローチが必要だなあと。
そんな振り返りをしていたら、朝読書はタイムリーにこの本が。
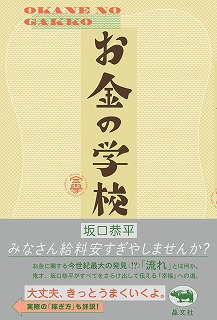
「お金の学校」(坂口恭平 晶文社)
第7章 頭の中(お花)畑だよねあんた
から。
~~~
詩はお金になりません。しかしだからといって経済ではないとは断定できないんです。(中略)お金とは経済です。でも数多ある経済のうちの一つなんです。
コツは、楽しくない時間を経済にしないことです。やりたくないことはしない。(中略)理由はそれではお金を稼げないだけでなく、他の経済の流れも堰き止めてしまうからです。
畑の中では経済がぐるぐると回り回っています。流れてます。いい感じです。心地いいです。何よりも楽しいです。
なぜなら植物は自分自身が経済であることに気付いているからです。
植物は自分が経済であることを知っている。一方、人間は自分が経済であることを知らないんです。もう困ったものです。その挙句「私はなんのために生きているのかわからない」なんてことをぬかす、いや、失礼、嘆いてしまうんです。いやはや!
植物はなんで自分が経済であることを知っているんでしょうか。簡単なことです、一人じゃないからです。植物がどこかに生えると、というか生える前から植物はすでに土の中にいまして、その時点で一人じゃありません。土がベッドです。
作品を外に発表すると、流れが発生します。経済が生まれてます。経済は素直であればあるほど、生であればあるほど、その人の一番自然な部分であればあるほど、すくすくと、植物なんですから、どんどん伸びていきます。どこまでも届いていきます。
僕の経済は常にみんなの経済なのです。僕は経済です。みんなは経済です。僕と経済とみんなは、一つの大きな流れなのです。海みたいなものです。どこまでも流れていきましょう。
~~~
きましたね。タイミングよく。「個人」じゃなくて「場」を主体にする、ということに大きなヒントがあります。
その「場」とは「流れ」の中にある「場」であり、「場」に溶けだしている自分も「流れ」を感じているはずです。
植物は自分が「経済」であることを知っている。
この本でいうところの「経済」である、とは、「流れ」があるということ。
いや、そもそも自分自身が「経済」、つまり「流れ」である、ということ。
そういう意味では、「場」とは、「流れ」のある川の中に浮かぶ小さな船のようです。
ひとりひとりも「経済」つまり「流れ」であり、また「船」でもあるのでしょう。
そのことを実感・体感したとき、「自分」とか「意志」とか、そのような問いが無効化されていくのかもしれません。
僕が探究学習でつくりたいのは、そんな「場」であり、「舟」であり、「瞬間」なのだと思いました。
体験と、言語と感覚(非言語)で、そこにアプローチしていきたいなと思います。
コミュニティの皆様、3月までよろしくお願いいたします。
2021年09月03日
「やりたいことがわからない」問いマップ
8月21日(土)の新潟駅MOYORe:のイベントに合わせて、
僕もバックキャスティングのワークシートをやりました。
10年後は図書館をつくって初代館長にしたのだけど、
5年後のところには、「大学で15コマ授業をやる」って書きました。

で、そんなタイミングでこの本を読んでいたことを思い出しまして。
杣ブックスの細井さんにも、「大切なのは真に受けて行動することだ」と言われたので。
ひとまずオンラインで15コマ(までいくかわかりませんけど)やってみようかなと思ってます。
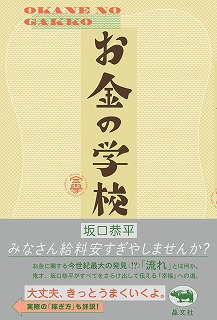
坂口恭平さんには、とりあえず「流れ」をつくれ、それが「経済」の始まりだ。
という教えを頂きましたので、そちらも真に受けて。
9月15日(水)~中学生・高校生・大学生向けのラジオ
「やりたいことがわからない」はなぜ苦しいのか(仮)をオンライン上でシリーズ化しようと思って。
※一緒にラジオつくってくれる悩める大学生を募集しています。
そんなタイミングで問いフレンドのAさんからナイスな問いをもらいまして。
「西田さんの問いはどのように変わってきたのか?」と。
なので、簡単にではありますが、書いてみました。

という感じでしょうか。
2011年のジブン発掘本屋「ツルハシブックス」の開店からずっとあった違和感が「やりたいことがわからない」はなぜこんなにも苦しいのか?でした。
そしてその解決策が「やりたいことが見つかる」ことではない、ということも何となくわかっていました。なぜなら自分自身が20代の頃、その無限ループにハマっていたからです。
僕にはやりたいことがありました。
中学生の時は、高校に入ってバスケ部に入るんだ、ということ。(実際はレギュラーになれず補欠)
高校生の時は、大学に入って沙漠緑化で地図に残る仕事を、と。
そして、大学生の時は、「種をまく人」に影響されて、畑サークル「まきどき村」を発足、就職しないでそんなことをやってました。
あきらかに「やりたいことをやる」人生を歩んできました。
ところが、不安が消えないのです。畑を始めて、人が集まってきて、それが新聞やテレビに取り上げられても、ずっと不安なのです。
胸の中には「本当にこれが自分のやりたいことなのか?」という問いがありました。
つまり。
「自分のやりたいことは何か?」という問いには終わり(答え)がない、ということです。
すべては「試作」に過ぎない、ということです。
さらに言えば、社会がこれだけ変化し続けているし、予測不可能性が高まっている中で、「やりたいこと=目標」を決めることに、どれほどの意味と価値があるのでしょうか?
細井さんのように、目の前に来たものをカラダの中に入れて、排出(放出)する。
それが「ジネン」で、楽な生き方なのではないでしょうか?
僕が文部科学大臣だったら「やりたいことは何か?」という問いを廃止したい。
その苦しさがどこから来るのか?
それは、アイデンティティ(自分らしさ)問題から来るのではないか、と思っています。
大人も子どもも、アイデンティティの不安にさらされている。その大きな原因が「所属」を失ったからだと思います。
「地域」や「会社」といったコミュニティから自由になった代わりに「所属」というアイデンティティ構築の手段を失ったのです。
今はひとりひとりの「個」が「社会」や「学校」というシステムに単独で対峙しなければなりません。
能力のある人は問題ないでしょう。世の中の変化やニーズを巧みに読み取り、新商品や新サービスを生み出したり、動画を配信したりして、うまく立ち回ることができるでしょう。
それ、全部のうち、何%の人ができるんですか?
って。
自分のやりたいことやできることを社会のニーズや未来の変化に合わせて、うまく市場にアピールし、売っていく。
本当にそれをしなければ生き残れないんでしょうか?
そもそも「個」が生き残る、生き延びることは生物的にはどれほどの価値があるのでしょうか?
2008年NHK全国学校音楽コンクールの課題曲だったアンジェラ・アキ「手紙」
僕は、この曲を聞いて、ただただ悲しくなった。
http://hero.niiblo.jp/e73613.html
(参考「手紙」10.6.16)
悩み、苦しんでいる15歳に対して、テレビの中から「今は苦しいけど、がんばればそのうちなんとかなる」としか言えない世の中が、社会が、ただただ悲しかったし、悔しかった。
そうじゃない。
人生は個人戦なんかじゃない。
「場」をつくるんだ。
「余白」のある、場を。
「営み」と他者との関係性の交点に場をつくるんだ。
そこにアイデンティティを「創造」するんだ。
「自分」も「意志」も西洋の神話なんだ。
田舎や自然の中では要らないんだ。
感覚と身体性を開放して、非言語コミュニケーションも含めてたくさんしていこう。
システムはそんなにすぐには変わらないから、
うまく折り合って、システムに適応する役を演じていこう。
創造する「場」をつくろう。
場を構成する一員になろう。
そんな場をいくつも持つことだ。
気がついたら、「やりたいことは何か?」という問い自体が無効化されている。
っていう仮説。
僕もバックキャスティングのワークシートをやりました。
10年後は図書館をつくって初代館長にしたのだけど、
5年後のところには、「大学で15コマ授業をやる」って書きました。

で、そんなタイミングでこの本を読んでいたことを思い出しまして。
杣ブックスの細井さんにも、「大切なのは真に受けて行動することだ」と言われたので。
ひとまずオンラインで15コマ(までいくかわかりませんけど)やってみようかなと思ってます。
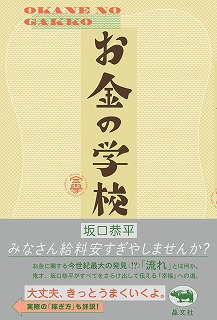
坂口恭平さんには、とりあえず「流れ」をつくれ、それが「経済」の始まりだ。
という教えを頂きましたので、そちらも真に受けて。
9月15日(水)~中学生・高校生・大学生向けのラジオ
「やりたいことがわからない」はなぜ苦しいのか(仮)をオンライン上でシリーズ化しようと思って。
※一緒にラジオつくってくれる悩める大学生を募集しています。
そんなタイミングで問いフレンドのAさんからナイスな問いをもらいまして。
「西田さんの問いはどのように変わってきたのか?」と。
なので、簡単にではありますが、書いてみました。

という感じでしょうか。
2011年のジブン発掘本屋「ツルハシブックス」の開店からずっとあった違和感が「やりたいことがわからない」はなぜこんなにも苦しいのか?でした。
そしてその解決策が「やりたいことが見つかる」ことではない、ということも何となくわかっていました。なぜなら自分自身が20代の頃、その無限ループにハマっていたからです。
僕にはやりたいことがありました。
中学生の時は、高校に入ってバスケ部に入るんだ、ということ。(実際はレギュラーになれず補欠)
高校生の時は、大学に入って沙漠緑化で地図に残る仕事を、と。
そして、大学生の時は、「種をまく人」に影響されて、畑サークル「まきどき村」を発足、就職しないでそんなことをやってました。
あきらかに「やりたいことをやる」人生を歩んできました。
ところが、不安が消えないのです。畑を始めて、人が集まってきて、それが新聞やテレビに取り上げられても、ずっと不安なのです。
胸の中には「本当にこれが自分のやりたいことなのか?」という問いがありました。
つまり。
「自分のやりたいことは何か?」という問いには終わり(答え)がない、ということです。
すべては「試作」に過ぎない、ということです。
さらに言えば、社会がこれだけ変化し続けているし、予測不可能性が高まっている中で、「やりたいこと=目標」を決めることに、どれほどの意味と価値があるのでしょうか?
細井さんのように、目の前に来たものをカラダの中に入れて、排出(放出)する。
それが「ジネン」で、楽な生き方なのではないでしょうか?
僕が文部科学大臣だったら「やりたいことは何か?」という問いを廃止したい。
その苦しさがどこから来るのか?
それは、アイデンティティ(自分らしさ)問題から来るのではないか、と思っています。
大人も子どもも、アイデンティティの不安にさらされている。その大きな原因が「所属」を失ったからだと思います。
「地域」や「会社」といったコミュニティから自由になった代わりに「所属」というアイデンティティ構築の手段を失ったのです。
今はひとりひとりの「個」が「社会」や「学校」というシステムに単独で対峙しなければなりません。
能力のある人は問題ないでしょう。世の中の変化やニーズを巧みに読み取り、新商品や新サービスを生み出したり、動画を配信したりして、うまく立ち回ることができるでしょう。
それ、全部のうち、何%の人ができるんですか?
って。
自分のやりたいことやできることを社会のニーズや未来の変化に合わせて、うまく市場にアピールし、売っていく。
本当にそれをしなければ生き残れないんでしょうか?
そもそも「個」が生き残る、生き延びることは生物的にはどれほどの価値があるのでしょうか?
2008年NHK全国学校音楽コンクールの課題曲だったアンジェラ・アキ「手紙」
僕は、この曲を聞いて、ただただ悲しくなった。
http://hero.niiblo.jp/e73613.html
(参考「手紙」10.6.16)
悩み、苦しんでいる15歳に対して、テレビの中から「今は苦しいけど、がんばればそのうちなんとかなる」としか言えない世の中が、社会が、ただただ悲しかったし、悔しかった。
そうじゃない。
人生は個人戦なんかじゃない。
「場」をつくるんだ。
「余白」のある、場を。
「営み」と他者との関係性の交点に場をつくるんだ。
そこにアイデンティティを「創造」するんだ。
「自分」も「意志」も西洋の神話なんだ。
田舎や自然の中では要らないんだ。
感覚と身体性を開放して、非言語コミュニケーションも含めてたくさんしていこう。
システムはそんなにすぐには変わらないから、
うまく折り合って、システムに適応する役を演じていこう。
創造する「場」をつくろう。
場を構成する一員になろう。
そんな場をいくつも持つことだ。
気がついたら、「やりたいことは何か?」という問い自体が無効化されている。
っていう仮説。




