2014年02月28日
コミュニティと「ナリワイ」
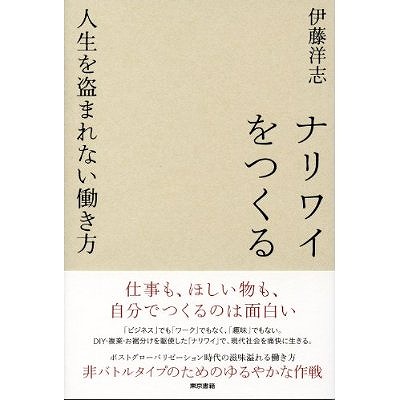
「ナリワイをつくる」(伊藤洋志)
読んで、一番感じたのは、
「専業の文化」が
地域コミュニティを崩壊させたということ。
いまの自分の
お金を稼ぐ仕事が「本業」で
それ以外をすべて「プライベート」とする考え方だ。
地域のお祭り
地域の集まり
それらがすべて「プライベート」となり、
「本業」よりも低い位置づけとなった。
「お祭りだ」と言っても、
「その日、仕事あるんで」と言えば、許されてしまう世の中を形成してきた。
結果、地域コミュニティは崩壊した。
そしていま。
高齢化に伴い、
地域を支えているリーダーがリタイアし始めた。
地域農業も風前の灯だ。
それを誰が支えるのか?
を議論していたも仕方ないので、
「専業の文化」を変えていこう。
趣味の時間に、
田舎に行き、おじいちゃんおばあちゃんと
対話をしよう。
そして、自分ができることを始めよう。
いいんだ、お金は少ししか稼げなかったとしても。
移住か、東京にとどまるか、
を悩むのではなく、
まずは田舎と一緒に何か始めてみよう。
そんな文化を創ることが
コミュニティ再生の道、なのではないか。
2014年02月27日
20年
あの日から、20年が過ぎた。
「志」を初めて友人と語った日。
それは、
大学受験のあとに乗った新幹線の車内だった。
同じ高校だったが、
ほとんど話したことがない吉川と
2時間半、話し続けた。
あっという間に東京についた。
そして、その時に
「20年後にまたここで会おう。」
とドラマみたいな約束をして、別れた。
僕たちは2人とも受験に敗れた。
それぞれ別の道に進むことになった。
僕は新潟へ。
彼は東京に。
あの日から20年が過ぎた2月26日。
僕はふたたび東京駅の京葉線ホームの上の階
(修学旅行生が集合するところ)に立った。
あっという間の20年だった。
そして、志は、まだ、何も実現できてない。
「志半ばすぎるよ」、って思った。
こんなんじゃ、終われないって。
19歳の自分に、胸を張れないって。
志 語った19の 東京駅
あの日の自分に 胸を張れるか?
そんな気持ちを詠んだ。
そして、再会。
会うたびにいつも、志を再確認させてもらう。
これからの高齢化社会に対応した都市開発の
スケールのデカい話を聞いた。
一流企業はやはり、最先端を走っているって思った。
そこに投資する余裕があるって思った。
いっぽうで僕たちのような弱小NPOもまた、
試せる立場にいるって思った。
そう言えば、
大学時代とか、まきどき村を始めたころとかに
よく言っていたっけ。
「お前は上から、俺は下から、世の中を変えていく」って。
いつか、真ん中で会おうって。
20年経っても、
なにも変わっていなかった。
俺は俺で、新しい何かを創っていくよ。
ありがとう。
ビール、ごちそうさま。
「志」を初めて友人と語った日。
それは、
大学受験のあとに乗った新幹線の車内だった。
同じ高校だったが、
ほとんど話したことがない吉川と
2時間半、話し続けた。
あっという間に東京についた。
そして、その時に
「20年後にまたここで会おう。」
とドラマみたいな約束をして、別れた。
僕たちは2人とも受験に敗れた。
それぞれ別の道に進むことになった。
僕は新潟へ。
彼は東京に。
あの日から20年が過ぎた2月26日。
僕はふたたび東京駅の京葉線ホームの上の階
(修学旅行生が集合するところ)に立った。
あっという間の20年だった。
そして、志は、まだ、何も実現できてない。
「志半ばすぎるよ」、って思った。
こんなんじゃ、終われないって。
19歳の自分に、胸を張れないって。
志 語った19の 東京駅
あの日の自分に 胸を張れるか?
そんな気持ちを詠んだ。
そして、再会。
会うたびにいつも、志を再確認させてもらう。
これからの高齢化社会に対応した都市開発の
スケールのデカい話を聞いた。
一流企業はやはり、最先端を走っているって思った。
そこに投資する余裕があるって思った。
いっぽうで僕たちのような弱小NPOもまた、
試せる立場にいるって思った。
そう言えば、
大学時代とか、まきどき村を始めたころとかに
よく言っていたっけ。
「お前は上から、俺は下から、世の中を変えていく」って。
いつか、真ん中で会おうって。
20年経っても、
なにも変わっていなかった。
俺は俺で、新しい何かを創っていくよ。
ありがとう。
ビール、ごちそうさま。
2014年02月26日
当事者と行動者のグラデーション
社会はコミュニティの集合体であり、
ひとりひとりはコミュニティの構成員である。
コミュニティを元気にしたいと思うとき。
そこには、
思いを持った「当事者」と
実際に行動できる「行動者」が必要だろうと思う。
もちろん、
「当事者」が「行動者」を兼ねるのが
いちばんいいのだが、
それをコミュニティの中だけで考えていくと、
高齢化が急速に進んでいる現在社会においては、
コミュニティの衰退が進んでいかざるを得ない。
「まちづくり当事者の減少」
この課題に突き当たる。
昨日も老舗純喫茶にお邪魔して
お昼を食べていたのだけど、
店主が言うには、
若い人がさっぱり来なくなって、
30年前のお客さんだけが来ている、と言っていた。
先日、シブヤ大学での野村先生のフューチャーセッション
でも「未公認のまちづくり当事者になる。」
という話があったけど、
まちづくり当事者をどのように増やしていくか?
というのがコミュニティの課題となる。
そして、ここで大学生の出番だ。
大学生の武器は、行動力。
特に女子の場合は、感性で行動することができるから、
「おもしろそうだ」と思えば、動ける。
それを地域の大人たちと一緒にやるような
デザインにすると、どうなるか。
金沢の東原の事例を聞くと、
まさにそういうことが起こっているのだけど、
最初は2週間の民泊だったのが、
徐々に東原に通うようになり、
最終的には移住したい!という子まで現れるのだ。
そう。
大学生がだんだんと「当事者」になっていくのだ。
そしてもうひとつ。
地域の人たちが朝市などで大学生と交流することで
「行動者」になっていくのだ。
これは、1年、2年と長い期間をかけて、形成されていく。
そもそも
「当事者性」や「行動力」は、
0が100になるものではない。
0が10になり、20が30になり、やっと50を超えたかな、
と思ったときに人生が楽しくなっていく。
「当事者」(地域の人)と「行動者」(大学生)
をうまくデザインすることで、
当事者意識と行動力の向上が相互に起こっていく。
これが、大学生を活用した
コミュニティ再構築モデルなのではないか。
当事者になったほうが、世の中は圧倒的に楽しい。
「それ、学校で習ってません。」
という発言に代表される人生の当事者意識の低さを
早い段階で修正していくこと。
そのためには、
地域コミュニティのような、ナチュナルな当事者意識
を持つ人たちと共に行動することが出発点になり得るのではないかと思う。
そしてそれは同時に、
地域コミュニティの行動力を引き出していく。
そんなまちに、僕も住みたい。
ひとりひとりはコミュニティの構成員である。
コミュニティを元気にしたいと思うとき。
そこには、
思いを持った「当事者」と
実際に行動できる「行動者」が必要だろうと思う。
もちろん、
「当事者」が「行動者」を兼ねるのが
いちばんいいのだが、
それをコミュニティの中だけで考えていくと、
高齢化が急速に進んでいる現在社会においては、
コミュニティの衰退が進んでいかざるを得ない。
「まちづくり当事者の減少」
この課題に突き当たる。
昨日も老舗純喫茶にお邪魔して
お昼を食べていたのだけど、
店主が言うには、
若い人がさっぱり来なくなって、
30年前のお客さんだけが来ている、と言っていた。
先日、シブヤ大学での野村先生のフューチャーセッション
でも「未公認のまちづくり当事者になる。」
という話があったけど、
まちづくり当事者をどのように増やしていくか?
というのがコミュニティの課題となる。
そして、ここで大学生の出番だ。
大学生の武器は、行動力。
特に女子の場合は、感性で行動することができるから、
「おもしろそうだ」と思えば、動ける。
それを地域の大人たちと一緒にやるような
デザインにすると、どうなるか。
金沢の東原の事例を聞くと、
まさにそういうことが起こっているのだけど、
最初は2週間の民泊だったのが、
徐々に東原に通うようになり、
最終的には移住したい!という子まで現れるのだ。
そう。
大学生がだんだんと「当事者」になっていくのだ。
そしてもうひとつ。
地域の人たちが朝市などで大学生と交流することで
「行動者」になっていくのだ。
これは、1年、2年と長い期間をかけて、形成されていく。
そもそも
「当事者性」や「行動力」は、
0が100になるものではない。
0が10になり、20が30になり、やっと50を超えたかな、
と思ったときに人生が楽しくなっていく。
「当事者」(地域の人)と「行動者」(大学生)
をうまくデザインすることで、
当事者意識と行動力の向上が相互に起こっていく。
これが、大学生を活用した
コミュニティ再構築モデルなのではないか。
当事者になったほうが、世の中は圧倒的に楽しい。
「それ、学校で習ってません。」
という発言に代表される人生の当事者意識の低さを
早い段階で修正していくこと。
そのためには、
地域コミュニティのような、ナチュナルな当事者意識
を持つ人たちと共に行動することが出発点になり得るのではないかと思う。
そしてそれは同時に、
地域コミュニティの行動力を引き出していく。
そんなまちに、僕も住みたい。
2014年02月25日
一流の条件
大瀧剛さんの
green drinks
熱かった。
僕が一番印象に残ったのは、
「オーラを放つ人」の話。
福島県のキャンプでの話。
超一流の人は、誰からも学ぼうとする。
子どもからも周りの人からも、
常に学ぼうとしている。
一流の条件。
「誰からも学ぼうとする」
「学び続ける」
この2つが
必須項目だなあと思いました。
ゴーさん、
シビれる時間をありがとう。
green drinks
熱かった。
僕が一番印象に残ったのは、
「オーラを放つ人」の話。
福島県のキャンプでの話。
超一流の人は、誰からも学ぼうとする。
子どもからも周りの人からも、
常に学ぼうとしている。
一流の条件。
「誰からも学ぼうとする」
「学び続ける」
この2つが
必須項目だなあと思いました。
ゴーさん、
シビれる時間をありがとう。
2014年02月24日
「商店街活性化」ではなくどんな文化を創りたいのか?
昨日の閉店後、
飯塚商店の飯塚さんがフラッと登場。
夕飯を食べながら、
アツい米談議。
僕は、大学農学部時代の6年間、
自然農法や米作り、日本型食生活の大切さ
を学んできたので、そういう話はワクワクする。
昔の家庭用精米機では熱くなってしまい
タンパク質が変性するので、米が美味しくなくなる。
とか。
その年によって同じ土地でも米の味は変化する、とか。
これは面白いなあ、
「うちのまち なじみのおみせ ものがたり」
で講座できそうだなあ。
飯塚商店のコーナーを
ツルハシブックス内「カラバコ」に設置しようと思っています。
ご飯とお味噌汁とお漬物と。
そんな日本型食生活が発信できればと思います。
まずは、
玄米、1分、3分、5分、7分、9分、上白
と7段階の精米の違いを見てもらいます。
そうやってお米に興味を持ってもらおうと思います。
コンセプトは
主に「19歳」に向けて、
ご飯の美味しさを伝えたい。
自炊をするきっかけをつくりたい。
身体の内側と外側と脳からもキレイになってもらいたい。
そんな「文化」を発信できないか、と思いました。
内野商店街には、
米屋があり、魚屋があり、魚加工品があり、
蔵元が2つもあり、酒屋があり、味噌屋があり、豆腐屋があります。
この商店街から
ご飯とお味噌汁、お漬物の「日本型食生活」を19歳に向けて発信する。
それは大きな意味があるのではないでしょうか。
いや。
そういう旗があるからこそ、人は商店街に足を運んでくれるのではないかと思います。
「商店街活性化」はゴールにはなりません。
そこに共感が生まれないからです。
「商店街活性化」は経済の問題です。
だから、ワクワクしません。
「商店街活性化」ではない、「文化の創造」に
関わることを人は求めているのではないでしょうか。
先月。
青森からの帰りに、ふと降りてきたひとつの問い。
「もし、僕たちが文化を創っているとしたら?」
この問いにひたすら答えていく半年にしようと思います。
もし僕たちが文化を創っているとしたら、
それはどんな文化だろう?
いま、何をすべきなんだろう?
中学生は高校生は大学生は、
まちの大人たちは、何を求めているのだろう?
その問いこそが、
僕はメディアの責任だと思います。
テレビも新聞もラジオも、フリーペーパーも
この問いに答えていかなければなりません。
私たちも、
本屋というメディアを持つ者として、
この問いに向き合い、試作し、修正し、
生まれてくる文化を待ちたいと思います。
「旗」を掲げて走ってきた。
気がついたら、街がにぎわっていた。
そんな「旗」を商店街は必要としています。
このまちで一緒に文化をつくりませんか?
飯塚商店の飯塚さんがフラッと登場。
夕飯を食べながら、
アツい米談議。
僕は、大学農学部時代の6年間、
自然農法や米作り、日本型食生活の大切さ
を学んできたので、そういう話はワクワクする。
昔の家庭用精米機では熱くなってしまい
タンパク質が変性するので、米が美味しくなくなる。
とか。
その年によって同じ土地でも米の味は変化する、とか。
これは面白いなあ、
「うちのまち なじみのおみせ ものがたり」
で講座できそうだなあ。
飯塚商店のコーナーを
ツルハシブックス内「カラバコ」に設置しようと思っています。
ご飯とお味噌汁とお漬物と。
そんな日本型食生活が発信できればと思います。
まずは、
玄米、1分、3分、5分、7分、9分、上白
と7段階の精米の違いを見てもらいます。
そうやってお米に興味を持ってもらおうと思います。
コンセプトは
主に「19歳」に向けて、
ご飯の美味しさを伝えたい。
自炊をするきっかけをつくりたい。
身体の内側と外側と脳からもキレイになってもらいたい。
そんな「文化」を発信できないか、と思いました。
内野商店街には、
米屋があり、魚屋があり、魚加工品があり、
蔵元が2つもあり、酒屋があり、味噌屋があり、豆腐屋があります。
この商店街から
ご飯とお味噌汁、お漬物の「日本型食生活」を19歳に向けて発信する。
それは大きな意味があるのではないでしょうか。
いや。
そういう旗があるからこそ、人は商店街に足を運んでくれるのではないかと思います。
「商店街活性化」はゴールにはなりません。
そこに共感が生まれないからです。
「商店街活性化」は経済の問題です。
だから、ワクワクしません。
「商店街活性化」ではない、「文化の創造」に
関わることを人は求めているのではないでしょうか。
先月。
青森からの帰りに、ふと降りてきたひとつの問い。
「もし、僕たちが文化を創っているとしたら?」
この問いにひたすら答えていく半年にしようと思います。
もし僕たちが文化を創っているとしたら、
それはどんな文化だろう?
いま、何をすべきなんだろう?
中学生は高校生は大学生は、
まちの大人たちは、何を求めているのだろう?
その問いこそが、
僕はメディアの責任だと思います。
テレビも新聞もラジオも、フリーペーパーも
この問いに答えていかなければなりません。
私たちも、
本屋というメディアを持つ者として、
この問いに向き合い、試作し、修正し、
生まれてくる文化を待ちたいと思います。
「旗」を掲げて走ってきた。
気がついたら、街がにぎわっていた。
そんな「旗」を商店街は必要としています。
このまちで一緒に文化をつくりませんか?
2014年02月23日
合意形成より創意形成
18日のシブヤ大学フューチャーセッションでのたくさんのキーワード。
その中でも「合意形成より創意形成」
それが、いま、
「場」がある意味であり、意義であると思う。
金曜日。
突然、ツルハシブックスに斎藤正行さんが登場。

市民映画館「シネウインド」創設者。
NPOなんて言葉がない時代に
もっともNPOらしく、
仲間を集め、ファンドレイジングをして、
映画館をつくった男。
その様子がライフマグ「シネウインド」特集号に出ています。
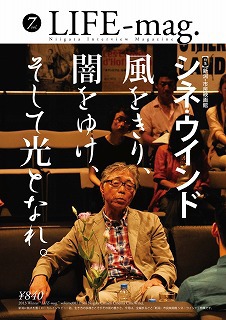
(ツルハシブックスで販売中 税込840円)
ここでの斎藤さんの
「場」のつくり方に学ぶことは多い。
~~~ここから引用
数の原理ということも考えてて、
多数が賛成したから正しいってことにはしなかった。
集ったやつらがつながって、
お互いを理解し合って、時間軸と共にみながどういう結論を出すか、
その過程を大事にした。
そこには、もちろん代表の俺の判断もある。
その判断がすべてをダメにする場合もある、
恐怖はあるよ。
(中略)
古くから知っている人ほど理解しているとは限らない。
今日、俺と出会う人が一番偉い。
今日初めて、ここに来る子は、うちらの二十八年を
評価・批評してここに来るわけだ。
だから、その子の認識が現在のウインドなんさ。
(中略)
いま俺と会ったやつが未来永劫一緒にいてほしいとは思わない。
ここを離れどこか他所へ行ったとき、
シネウインドのことを語って欲しいし、その時にはじめて見えてくることも
多いんじゃないかな。
~~~ここまで引用
いいなあと。
そういうのっていいなあって。
場とか会議ってそういうふうに
なっていくのではないかな。
このメンバー、
この議題、
この空間で話すのは二度と来ない。
だから、ひとりひとりの出演者が
最大のパフォーマンスを出すように、
会議を設計する。
結論が最初からあるわけではなくて、
その場のチカラを信じて、
みんなで生み出した何かを大切に、
次の活動につなげていくこと。
その積み重ねが
いい場といい会議をつくっていくのだろうと思った。
そしてその場や会議に立ち合った人たちが、
シネウインドだったりツルハシブックスだったりを
語り継ぐのだろうと思った。
大先輩、齋藤正行さん。
カッコイイおやじでした。
ありがとうございます。
その中でも「合意形成より創意形成」
それが、いま、
「場」がある意味であり、意義であると思う。
金曜日。
突然、ツルハシブックスに斎藤正行さんが登場。

市民映画館「シネウインド」創設者。
NPOなんて言葉がない時代に
もっともNPOらしく、
仲間を集め、ファンドレイジングをして、
映画館をつくった男。
その様子がライフマグ「シネウインド」特集号に出ています。
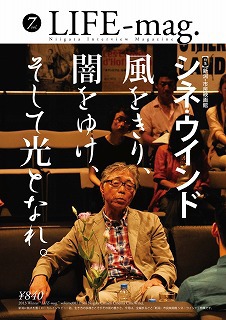
(ツルハシブックスで販売中 税込840円)
ここでの斎藤さんの
「場」のつくり方に学ぶことは多い。
~~~ここから引用
数の原理ということも考えてて、
多数が賛成したから正しいってことにはしなかった。
集ったやつらがつながって、
お互いを理解し合って、時間軸と共にみながどういう結論を出すか、
その過程を大事にした。
そこには、もちろん代表の俺の判断もある。
その判断がすべてをダメにする場合もある、
恐怖はあるよ。
(中略)
古くから知っている人ほど理解しているとは限らない。
今日、俺と出会う人が一番偉い。
今日初めて、ここに来る子は、うちらの二十八年を
評価・批評してここに来るわけだ。
だから、その子の認識が現在のウインドなんさ。
(中略)
いま俺と会ったやつが未来永劫一緒にいてほしいとは思わない。
ここを離れどこか他所へ行ったとき、
シネウインドのことを語って欲しいし、その時にはじめて見えてくることも
多いんじゃないかな。
~~~ここまで引用
いいなあと。
そういうのっていいなあって。
場とか会議ってそういうふうに
なっていくのではないかな。
このメンバー、
この議題、
この空間で話すのは二度と来ない。
だから、ひとりひとりの出演者が
最大のパフォーマンスを出すように、
会議を設計する。
結論が最初からあるわけではなくて、
その場のチカラを信じて、
みんなで生み出した何かを大切に、
次の活動につなげていくこと。
その積み重ねが
いい場といい会議をつくっていくのだろうと思った。
そしてその場や会議に立ち合った人たちが、
シネウインドだったりツルハシブックスだったりを
語り継ぐのだろうと思った。
大先輩、齋藤正行さん。
カッコイイおやじでした。
ありがとうございます。
2014年02月22日
「季節限定」こそが当たり前だ
「うちのまち なじみのおみせ ものがたり」
(3月15日~30日開催予定)
の取材で、大口屋さんに行ってきました。
大口屋さん。
ツルハシブックスのすぐ近所に
ある魚の加工品を製造・販売するお店。
化学調味料
保存料
着色料は使わない。
だから、漬物などは、発酵が進み、味が変わる。
「当たり前のことだ」
と大口さんが言う。
夏になれば、汗をかくから、しょっぱいのが欲しくなる。
冬になれば、身体を動かさないから、甘めの塩が美味しく感じる。
同じ味付けでも、
夏と冬では、感じ方が違う、と言っていた。
日本の豊かさとは、
新潟県の豊かさとはなんだろうか?
春夏秋冬がある。
季節の移り変わりがあること。
雪が降って、春が来る。
そんな中で、たくさんの食文化が花開く。
そして「郷土料理」が生まれる。
「郷土料理」とはいったいなんだろうか?
「その季節にしか獲れない野菜・魚で」
「長年の積み重ねで工夫して」
「食材の美味しさを引き出した料理」
だと言えるだろう。
だとすれば、
雪国の郷土料理のほとんどは、
「季節限定」とならざるを得ない。
1年中獲れる野菜や魚は存在しないからだ。
いや、もしかしたら干したり浸けたりして、
1年中使えるようにしているのもあるかもしれないが。
いま。
日本各地を旅行すると、
各地の「名物」と呼ばれるものを食べたくなる。
そして、各地のターミナル駅の近くには
その名物料理の看板を掲げた店がある。
しかし、そこに季節感はない。
たとえば新潟の「のっぺい」は、
里芋が獲れ始める時期に作りはじめるのが通常だろう。
1年中、同じものが食べられる。
というのは、日本の気候を考えると「異常」である。
「季節限定」こそが当たり前だ。
冬の新潟や富山に来たら、
「寒ブリ」を食べたいと思うように、
地域の旬の料理を食べることこそ、本当の旅の醍醐味なのだろう。
冬の名物料理を真夏に汗をかきながら食べる。
そんな不思議な光景はない。
そして、郷土料理には、意味がある。
たとえば、
同じ「煮菜」という料理でも、
新潟平野の方は酒粕で煮たものとなるが、
中越地方は豪雪地帯だから、
野沢菜を油でいためてから煮るようなカタチをとる。
それは、脂分をエネルギーとしてとるためだという。
そうやって考えると、
その土地、その土地の気候に合わせて、
郷土料理は作られてきた。
にもかかわらず、
まさに専業の思想なのかもしれないけど、
外からやってくる観光客のために、
郷土料理を1年中出し続けるビジネスが成立し、
そのために、
保存料、着色料を投入した結果。
その土地でなくても食べられるようになり、
物流が発達した現在においては、
もはや東京にいれば全国どこの郷土料理も食べられるようになっている。
いま。
現地で、その季節にしか食べられない料理は、
付加価値が低い料理か、日持ちが悪い商品だけになっている。
大口さんの話を聴いて、
大学生に聞いてもらいたいと思った。
「季節限定」こそが当たり前の食文化を、
大口屋さんから発信したい。
(3月15日~30日開催予定)
の取材で、大口屋さんに行ってきました。
大口屋さん。
ツルハシブックスのすぐ近所に
ある魚の加工品を製造・販売するお店。
化学調味料
保存料
着色料は使わない。
だから、漬物などは、発酵が進み、味が変わる。
「当たり前のことだ」
と大口さんが言う。
夏になれば、汗をかくから、しょっぱいのが欲しくなる。
冬になれば、身体を動かさないから、甘めの塩が美味しく感じる。
同じ味付けでも、
夏と冬では、感じ方が違う、と言っていた。
日本の豊かさとは、
新潟県の豊かさとはなんだろうか?
春夏秋冬がある。
季節の移り変わりがあること。
雪が降って、春が来る。
そんな中で、たくさんの食文化が花開く。
そして「郷土料理」が生まれる。
「郷土料理」とはいったいなんだろうか?
「その季節にしか獲れない野菜・魚で」
「長年の積み重ねで工夫して」
「食材の美味しさを引き出した料理」
だと言えるだろう。
だとすれば、
雪国の郷土料理のほとんどは、
「季節限定」とならざるを得ない。
1年中獲れる野菜や魚は存在しないからだ。
いや、もしかしたら干したり浸けたりして、
1年中使えるようにしているのもあるかもしれないが。
いま。
日本各地を旅行すると、
各地の「名物」と呼ばれるものを食べたくなる。
そして、各地のターミナル駅の近くには
その名物料理の看板を掲げた店がある。
しかし、そこに季節感はない。
たとえば新潟の「のっぺい」は、
里芋が獲れ始める時期に作りはじめるのが通常だろう。
1年中、同じものが食べられる。
というのは、日本の気候を考えると「異常」である。
「季節限定」こそが当たり前だ。
冬の新潟や富山に来たら、
「寒ブリ」を食べたいと思うように、
地域の旬の料理を食べることこそ、本当の旅の醍醐味なのだろう。
冬の名物料理を真夏に汗をかきながら食べる。
そんな不思議な光景はない。
そして、郷土料理には、意味がある。
たとえば、
同じ「煮菜」という料理でも、
新潟平野の方は酒粕で煮たものとなるが、
中越地方は豪雪地帯だから、
野沢菜を油でいためてから煮るようなカタチをとる。
それは、脂分をエネルギーとしてとるためだという。
そうやって考えると、
その土地、その土地の気候に合わせて、
郷土料理は作られてきた。
にもかかわらず、
まさに専業の思想なのかもしれないけど、
外からやってくる観光客のために、
郷土料理を1年中出し続けるビジネスが成立し、
そのために、
保存料、着色料を投入した結果。
その土地でなくても食べられるようになり、
物流が発達した現在においては、
もはや東京にいれば全国どこの郷土料理も食べられるようになっている。
いま。
現地で、その季節にしか食べられない料理は、
付加価値が低い料理か、日持ちが悪い商品だけになっている。
大口さんの話を聴いて、
大学生に聞いてもらいたいと思った。
「季節限定」こそが当たり前の食文化を、
大口屋さんから発信したい。
2014年02月21日
コスタリカ戦略

「地域の力を引き出す学びの方程式」(山下洋輔 水曜社)
池袋の東京天狼院書店にありました。
ステキな出会いをありがとうございました。

柏で行われている
柏まちなかカレッジが
成り立っていく様子が描かれていて、
とてもワクワクする1冊です。
「まち全体が教室、まちの人が先生」
をモットーに様々な講座を柏市で展開しています。
吉田松陰先生の
「野山獄」エピソードに通じるものがあり、
勝手に同志だと思いました。
たくさんの仲間を集め、
盛り上がっているまちなかカレッジの秘密は、
「コスタリカ戦略」です。
「ない」ことを売りにする方法。
場所がない、有名人を呼ぶのが難しい、専属の職員を雇えない
これは、運営費をかけず、地域の人の力を活用して、
たくさんの人が主体的に関わることができるという方法である。
~~~ここから引用
コスタリカでは、「何もない森」に多くのカナダ人が訪れているという。
なぜカナダ人が訪れるのか、コスタリカの人が不思議に思い調べたところ、
豊かな自然を求めていたと知る。
そこでコスタリカではエコツアーを整備し、
結果その自然は世界遺産に登録されたのだった。
観光収入が増加し、住民は潤った、
住宅にも工業にも、商業にも適さない「なにもない」土地が
観光資源に変わったのだった。
もう一つ、1949年からコスタリカは常設の軍隊を待っていない。
「兵士の数だけ教師を」を合言葉に、軍事予算を教育予算に回し
教育国家に転換したためだ。
このおかげで軍事クーデターは無くなった。
中米紛争の部分的解決にも功績を残したと言えるだろう。
パナマ、ハイチ、ドミニカなども常設軍を持たないのだが、
コスタリカを模範にした部分もあるそうだ。
私は、自然や平和といった
理念を強く打ち出すからこそ、
持たないことを強さに変えられるのだと学んだ。
ここから、この逆転の発想をコスタリカ戦略と命名したのであった。
~~~ここまで引用
なるほど。
そして、柏まちなかカレッジの運営方針次の5つ。
1 個人からの寄付は受けるが、企業などの大口寄付は断る
2 固定費はかけない
3 助成事業は受けない
4 法人格はとらない
5 まちづくりや交流の場であるが、「教育」を活動の柱にすえる
ということで、主体的に人が参加する仕組みを
つくっているのだ。
これはこれからの内野町のまちづくりに非常に参考になる本です。
ワクワクしました。
2014年02月20日
人生のスタートラインに立つ19歳の君へ

じゃらんの雪マジ!19~SNOW MAGICキャンペーン
http://www.jalan.net/theme/yukimaji19/
登録すると、
全国170以上のスキー場の無料リフト券が
もらえるというもの。
応募できるのは、
昨年春に高校を卒業した今年度19歳になる人たちだけ。
これは、スキー人口の動向を調べた結果、
現在スキーを楽しんでいる若者たちのほとんどが
高校を卒業してから社会人になるまで。
つまり、大学、短大、専門学校時代にスキーを始めていたのだという。
現在2シーズン目に入るこのプロジェクトは
どんどん参加ゲレンデを増やしている。
「リクルートライフスタイル」のページ
http://www.shinsotsu.recruit-lifestyle.co.jp/project/yukimaji/
これって。
結構どんなことにでも当てはまるんじゃないか。
19歳。
ひとり暮らし。
自由。
そして責任。
そこから始まった習慣は、一生モノになる可能性が高い。
だから、大学生なら1年次に、何か始めることが必要だ。
僕がアプローチしたいのは2つ。
1つは食生活。
現在、低体温の子どもが増えていて、
その原因の多くは食生活にあると言われている。
低体温だと何がいけないか、というと、
風邪などのウイルスが入ってきたときに、
それに対抗できる酵素を体内でつくり、機能させるためには、
酵素がもっとも働きやすい36度前後必要だ。
しかしながら低体温で35度前後をうろうろしていると、
酵素が働かないので、結果、風邪をひきやすくなる。
なので、体温を上げていくことは
非常に重要なことだ。
その為にはご飯を中心とした日本型食生活が
非常に重要なのだと言う。
もし、自分の育った家庭環境が
しっかりとご飯を食べない家だったとしたら、
食生活を改善するチャンスが、3回ある。
ひとり暮らしを始めたとき。
結婚したとき。
子どもを授かったとき。
このうち、タイミングが同じなのは、
19歳のときである。
19歳のときにいかにアプローチできるか、
そこに、大げさな言い方をすれば、
日本の子どもの健康がかかっている。
もうひとつ。
キャリアにかかわってくるのが思考行動特性だ。
ある出来事に対して、
どのように、考え、そして行動するか、は
20代~30代と、人生の早い段階で決まり、
その後はあまり変化しないという。
これもやはり。
目の前に来た出来事を
ピンチだと思うか、チャンスだと思うか、
行動できるか、逃げるか。
というのが20代のうちに決まってくるのだと言う。
大切なのは19歳だ。
いままで、教えられたことを
忠実に暗記、処理する学習から、
自分で考え、行動し、問いを起こし、答えていく。
そんなふうに変えていくことで
人生は大きく開けてくる。
START 19
19歳から始める、ジブン創り。
2014年02月19日
不満・不安をポジティブになれる問いに変換する

初の東京・シブヤ大学で
フューチャーセンターの講座を受けてきました。
野村恭彦さんのトークはホントにシビれます。
・企業の問いより社会起業家の問いの方が誰かの笑顔が見えてワクワクした。
・巻き込む前に巻き込まれることが必要。社会起業家のために企業は何ができるか?
・企業はお金のために存在しているわけではないので、善意のステークホルダーとして仲間にする。
・一緒に動いていくためには「一緒に動いていこうと思える共感」が必要
・フューチャーセンターという建物を先につくってはいけない。セッションができる人が先。
・フォアキャスト(現状の延長上の未来)だけでは面白くないし、想定外に対応できない。
・夢を叶える人はバックキャスティング(想像上の未来から逆算)している。
・大人になるとバックキャスティングしなくなる。(バカって言われる)
・未来がワクワクするのは、「不確実性」があるから。「確率が高い」は面白くない。
・行動する人と行動しない人の意見を平等に扱ってはいけない。
・行動する人の意見をくみとり、試作して、改善し、次につなげる。
・まちづくりの「参加者」ではなく「当事者」になることが必要
・未公認のまちづくり当事者を増やすにはどうしたらよいか?
・地域の未来ビジョンは行政が関わらなくてもできる状態が理想
・もし自分がまちづくり当事者だったら⇒クイックプロトタイピングしてみる。
などなど。
メモでいっぱいでした。
ファシリテーターにとって大切なのは、
まちに対する不満や不安を
「ポジティブな問い」「フレッシュな問い」に変換する、ということ。
たとえば、
「うちの団地も高齢化が進んで年寄ばっかで元気がないんだ」
とか
「駅前の商店街も寂れてしまって、若者が歩いてないんだ」
とかいう声を、
「高齢者が中学生のために活躍できる集会所とは?」とか
「子育てしたくなるまちになるための商店街の役割とは?」
というような、ポジティブな問いに変換すること。
それによって、
問いに共感・ワクワクするステークホルダーが
集まり、その議論の場がいい場になって、いいアイデアが生まれる。
ここで大切なのは、問いを立てる力だ。
みんなが考えたくなる、未来志向になるワクワクする問いを
生み出せる力だ。
これがファシリテーターにもっとも大切な力なのだとあらためて実感。
1 みんなが考えたくなる面白い問いを立て
2 問いにワクワクした多様な参加者が集い
3 対話の場の設計をして
4 気づきの対話で主体性を引き出し
5 仲間と一緒に協調チャレンジを起こす
こうやって未来は創られていくのだ。
「合意形成」ではなく「創意形成」だと
野村さんは言う。
そのために問いを開き続ける、
というか開かれた問いを投げかけつづける。
まずは、
おもしろい問いを生み出せる力を
つけていくこと、これがファシリテーターへの第1歩だ。
2014年02月18日
学習環境よりも学習機会、学習動機を提供する場のチカラ
放浪書房さん。

旅をしながら、
本を売り歩くという素敵なことをしています。
7月1日。
ツルハシブックスに来てもらいました。
放浪書房さんが売っているのは、
本ではなく、「一期一会」という機会だったのです。
瞬間のワクワクだったのです。
あれを思い出してみる。
放浪書房とはなんだったのか?
あれは、カッコよく言えば、
「究極の学習機会の提供」ではないか、と思う。
そして、何よりも
「偶然」があふれているというのがいいよね。
~~~ここから小説風
日常のなにげない通勤の帰り道の路上。
見慣れない屋台がそこにある。
思わず手に取った本を買ってしまう。
帰りの電車の中で読むと、
面白くてたまらなくなる。
もっと知りたい、
あるいは、旅に出たい、と思う。
しかし。
次の日、放浪書房はそこにはいない。
物語は終わり、
そして新たな物語が始まっていく。
~~~ここまで小説風
というような物語が生まれるのだ。
いま、子どもたちが一番必要としているのは、
学習環境、そして何よりも
学習機会、学習動機を提供することではないかと思う。
屋台を自分でやってみる、という学習機会。
そこから学びたいという欲求が生まれてくる。
そんなのを生んでいく場のチカラ。
放浪書房を科学する
ってなかなか面白いなあと思いました。

旅をしながら、
本を売り歩くという素敵なことをしています。
7月1日。
ツルハシブックスに来てもらいました。
放浪書房さんが売っているのは、
本ではなく、「一期一会」という機会だったのです。
瞬間のワクワクだったのです。
あれを思い出してみる。
放浪書房とはなんだったのか?
あれは、カッコよく言えば、
「究極の学習機会の提供」ではないか、と思う。
そして、何よりも
「偶然」があふれているというのがいいよね。
~~~ここから小説風
日常のなにげない通勤の帰り道の路上。
見慣れない屋台がそこにある。
思わず手に取った本を買ってしまう。
帰りの電車の中で読むと、
面白くてたまらなくなる。
もっと知りたい、
あるいは、旅に出たい、と思う。
しかし。
次の日、放浪書房はそこにはいない。
物語は終わり、
そして新たな物語が始まっていく。
~~~ここまで小説風
というような物語が生まれるのだ。
いま、子どもたちが一番必要としているのは、
学習環境、そして何よりも
学習機会、学習動機を提供することではないかと思う。
屋台を自分でやってみる、という学習機会。
そこから学びたいという欲求が生まれてくる。
そんなのを生んでいく場のチカラ。
放浪書房を科学する
ってなかなか面白いなあと思いました。
2014年02月17日
才能思考を成長思考へ
上田信行先生の
「プレイフルラーニング」の考え方が
僕の行きたい方向性にもっともマッチしている、
と実感した奈良・吉野ツアーでした。
僕がもっとも解決した課題は、
中学生高校生大学生の持つ
「才能思考」(=固定的知能観):自分の才能は生まれつき決まっている
を打破して
「成長思考」(=成長的知能観):学べば学ぶほど自分の能力は開花し続ける
を取り戻すこと
そのために、
「地域」の人や資源を活用した様々な機会やプログラムを
ツルハシブックスのような「場」を通じて、敷居を下げた形で提供していくこと。
小さなチャレンジを個人ではなくて、チームで
何かを成し遂げ、そこに役割を果たしたいと思う動機づけをして、
チャレンジの入り口をつくる。
そして、地域の人の世話になりながら、
「はたらく」ことの原点である
「恩返し」の動機づけを創っていく。
もうひとつは
「才能思考」に陥らないための
中学生高校生へのアプローチだ。
これに最も必要なのは
「視野を広げる」ということ。
学校社会では
勉強とスポーツ、芸術などが評価の対象となるが、
大人になったら、
「企画・立案する力」や
「コミュニティを形成する力」や
「さりげなくフォローする力」などが求められてくる。
そんな大人を見せることはとても大切だと思う。
「才能思考」の始まりは、中学校1年生。
同じように学んでいるのに、
隣のアイツはいい点数を取るのに、
自分は成績がよくない。
「もしかしてオレは、あたま悪いんじゃないか?」
という気持ちが芽生える。
しかし、それは本当は、
「あたま悪い」んじゃなくて、
「暗記力」と「情報処理能力」
が隣のアイツよりも少し劣っているに過ぎない。
しかもそれが求められるのは、
日本の教育システムだけなのだ。
社会に出たら、パソコンがあり、仲間がいるので、
暗記力も情報処理能力が仮に低かったとしても、
なんとかなる。
というよりも
社会に出て必要なのは、
「暗記力」と「情報処理能力」に頼らない
「思考力」や「コミュニケーション力」だろう。
そして、逆説的だが、
「思考力」や「コミュニケーション力」の重要性を知ることによって、
人は「学びたい」という思いが芽生え、
「暗記力」と「情報力能力」が向上していくのではないか。
才能思考に陥らないように、
学校以外の現場で
そのほかの能力、つまり企画立案力や人間関係形成能力を伸ばしていくこと。
失敗を重ね、失敗から学び、
さらなるチャレンジをしていくこと。
その繰り返しが人を
「成長思考」にとどまらせる。
誰もが子どもの頃は成長思考だった。
学べば学ぶほど、失敗すればするほど自分は成長できる、
と思っていた。
それを才能思考で上書きされないように、
あるいは、上書きされてしまった才能思考を解除し、
成長思考を取り戻すために、
「プレイフル」(遊びに溢れた)な学びの場をつくること。
それは、もしかしたら、日々、本屋さんで起こる出来事なのかもしれません。
扉の向こうで待っている、
悩める中学生高校生大学生に、
まずは小さな機会を、物語の始まりを届けるために、
今日もお店に立っているのです。
「プレイフルラーニング」の考え方が
僕の行きたい方向性にもっともマッチしている、
と実感した奈良・吉野ツアーでした。
僕がもっとも解決した課題は、
中学生高校生大学生の持つ
「才能思考」(=固定的知能観):自分の才能は生まれつき決まっている
を打破して
「成長思考」(=成長的知能観):学べば学ぶほど自分の能力は開花し続ける
を取り戻すこと
そのために、
「地域」の人や資源を活用した様々な機会やプログラムを
ツルハシブックスのような「場」を通じて、敷居を下げた形で提供していくこと。
小さなチャレンジを個人ではなくて、チームで
何かを成し遂げ、そこに役割を果たしたいと思う動機づけをして、
チャレンジの入り口をつくる。
そして、地域の人の世話になりながら、
「はたらく」ことの原点である
「恩返し」の動機づけを創っていく。
もうひとつは
「才能思考」に陥らないための
中学生高校生へのアプローチだ。
これに最も必要なのは
「視野を広げる」ということ。
学校社会では
勉強とスポーツ、芸術などが評価の対象となるが、
大人になったら、
「企画・立案する力」や
「コミュニティを形成する力」や
「さりげなくフォローする力」などが求められてくる。
そんな大人を見せることはとても大切だと思う。
「才能思考」の始まりは、中学校1年生。
同じように学んでいるのに、
隣のアイツはいい点数を取るのに、
自分は成績がよくない。
「もしかしてオレは、あたま悪いんじゃないか?」
という気持ちが芽生える。
しかし、それは本当は、
「あたま悪い」んじゃなくて、
「暗記力」と「情報処理能力」
が隣のアイツよりも少し劣っているに過ぎない。
しかもそれが求められるのは、
日本の教育システムだけなのだ。
社会に出たら、パソコンがあり、仲間がいるので、
暗記力も情報処理能力が仮に低かったとしても、
なんとかなる。
というよりも
社会に出て必要なのは、
「暗記力」と「情報処理能力」に頼らない
「思考力」や「コミュニケーション力」だろう。
そして、逆説的だが、
「思考力」や「コミュニケーション力」の重要性を知ることによって、
人は「学びたい」という思いが芽生え、
「暗記力」と「情報力能力」が向上していくのではないか。
才能思考に陥らないように、
学校以外の現場で
そのほかの能力、つまり企画立案力や人間関係形成能力を伸ばしていくこと。
失敗を重ね、失敗から学び、
さらなるチャレンジをしていくこと。
その繰り返しが人を
「成長思考」にとどまらせる。
誰もが子どもの頃は成長思考だった。
学べば学ぶほど、失敗すればするほど自分は成長できる、
と思っていた。
それを才能思考で上書きされないように、
あるいは、上書きされてしまった才能思考を解除し、
成長思考を取り戻すために、
「プレイフル」(遊びに溢れた)な学びの場をつくること。
それは、もしかしたら、日々、本屋さんで起こる出来事なのかもしれません。
扉の向こうで待っている、
悩める中学生高校生大学生に、
まずは小さな機会を、物語の始まりを届けるために、
今日もお店に立っているのです。
2014年02月16日
「ヨガ」で自分を開放する

「プレイフルラーニング」を読み直し、
奈良の「ネオミュージアム」にお邪魔してきた。

教育はロックンロールだ。
情熱を伝えなきゃダメなんだよ。と言う上田先生、最高。
いちばんドキっしたのは
名古屋で「party to the future」をやる
中村太郎さんとの出会い。
http://philosophy3.net/2013autumn/#pagetop
※音が鳴りますので注意
誰もが参加できる学会
http://philosophy3.net/2013autumn/#id14
ひとりではできないことも
みんなでならできる。
というコンセプトも、昨日書いたブログそのままで
ちょっと衝撃。
そのプログラム内容も面白くて、
まず最初に「ヨガ」をやるんです。
そうです。
あのヨガです。
身体を開放することで、心も脳も開放する。
ああ。
本当にそうなんだなあって思った。
小学生から60歳のおじいちゃんまで
参加するこのパーティー。
すごいって。
「ヨガ」で心を開放する。
こういうのがすごくヒットしました。
ステキな気づきをありがとう。
2014年02月15日
無力感は獲得されたものだ
プレイフルラーニングの聖地、
奈良・吉野に向かう朝。

「プレイフルラーニング」(上田信行×中原淳 三省堂)
を読み直します。
コワイことがたくさん書かれていますね。
心理学者マーティン・セリグマンによると、
「人間の無力感は学習(獲得)されたものだ」
と言います。
そして同じく心理学者のキャロル・ドゥエックが言う
「認知的動機づけ理論」
「動機づけ」つまり「やる気」は
その人の性格や気分の問題ではなく、
個人の考え方、見方の問題だということです。
そこで出てくるのが
「固定的知能観」と「成長的知能観」の問題。
頭の良さというのは、個人的なもので、変わることがない。
つまり、賢さは生まれつき決まっているのだ。
これが「固定的知能観」です。
僕が言い換えると、「才能思考」です。
もうひとつが
知能というのは、勉強すればするほど伸びる、成長する。
これを「成長的知能観」と言います。
僕が言い換えるなら「成長思考」です。
100%どっちかであることはなくて、
おそらくは、割合の問題だと思うのですが。
問題は、
「固定的知能観」が多いと、
元来持っている自分の固定された才能を
「できるだけ大きく見せる」ことが重要になり、
良い成績をとり、達成することが他者評価を受ける重要な要素になるのだから勉強するが、
成績が落ち始めると、とたんにやる気を失ってしまうということが起こります。
しかし、
「成長的知能観」を持っていれば、
「自分はもっと賢くなりたい」と考え、
他人からどう見られるかに関係なく、知らないことは尋ねることができます。
大切なのは、自分がより賢くなることで、学ぶことそのものが目的になるのです。
ドゥエック教授は、
これによって、学習のパフォーマンスは大きく変わってくると言います。
人間の使用メモリの容量が同じだとすれば、
「努力しても自分は変わらない」と思っている人は
「他人からどう見られるか?」に多くのメモリを使ってしまいます。
一方、「努力すれば自分は変われる」と思っている人は、
メモリの多くを「課題」に対して使うことができるので、
より高い成果をあげるようになるのです。
つまり、
「自分の持っている自分の知能に対する自己イメージ」が
動機に大きな影響を与えるのだと言います。
そして、
上田先生の博士論文によって、
驚くべきことが分かります。
日本の小中高生600人を対象に
調査した結果。
中学1年生の時に、
子どもは「成長的知能観」から「固定的知能観」
に変わる。
つまり、「無力感を獲得する」のです。
なんということでしょう。
おそらくはこれは、
成績の序列化が起こす悲劇なのだろうと考えられます。
同じように勉強してるのに、
隣の席のアイツのほうがテストがいい点数が獲れる。
「もしかしてオレは頭悪いんじゃないか?」
と思ってしまうのです。
しかし。
それは。
あくまで「現時点における」
日本の教育システムが求める力、
つまり、「記憶力、情報処理能力」に関して、だけなのです。
それは「才能」が決めるわけではありません。
まだ、開花していないだけなのかもしれません。
にも関わらず、
中学校1年生の段階で、
「オレには勉強の才能がない」と思ってしまう。
そしてそれは高校受験で決定的になります。
そして進路指導でも。
「あなたの成績はこのくらいだからこのくらいの高校に行きなさい」
と言われます。
こうやって獲得した「無力感」が
学習を楽しめなくしているとしたら、
これは何とかしなきゃいけないのだはないか、と思うのです。
では、どうやって、
「成長的知能観」つまり、成長思考を取り戻すか?
ここで僕は「スラムダンク」理論を使います。
最後の山王戦、
日本一のセンターと言われる河田に歯が立たない
赤木は、こう言います。
「たしかに現時点で俺は河田に負ける。
でもな、湘北は負けんぞ」
これです。
ひとりでは、かなわないけど、
チームでは負けない。
チームならできる。
この感覚から出発するしかないのだと思います。
僕は残念ながら
中学生高校生のアプローチが野山塾でしかできないので、
大学生になってから、
固定的知能観を成長的知能観に
シフトしていくことをしていくというプログラムをつくることしかできません。
誰もが子どものときは
成長的知能観を持っていました。
6歳の少年が
生まれて初めて自転車に乗る。
うまく乗れない。
そのときに、「自転車に乗る才能がない。」
とあきらめる子どもは一人もいません。
乗れるまでチャレンジしたから、いま、自転車に乗れるのです。
いつの間にか、人は無力感を学習します。
それは、才能のせいではなく、
「現時点で開花していない」
ただそれだけなのかもしれません。
「やってみなければわからない」
そう思える中学生高校生大学生を生んでいく。
それこそが大人の役割なのではないでしょうか?
チームでの小さなチャレンジを繰り返し、成長的知能観を取り戻す。
「地域」を舞台に、そんな場と機会をつくることが私たちの役割です。
奈良・吉野に向かう朝。

「プレイフルラーニング」(上田信行×中原淳 三省堂)
を読み直します。
コワイことがたくさん書かれていますね。
心理学者マーティン・セリグマンによると、
「人間の無力感は学習(獲得)されたものだ」
と言います。
そして同じく心理学者のキャロル・ドゥエックが言う
「認知的動機づけ理論」
「動機づけ」つまり「やる気」は
その人の性格や気分の問題ではなく、
個人の考え方、見方の問題だということです。
そこで出てくるのが
「固定的知能観」と「成長的知能観」の問題。
頭の良さというのは、個人的なもので、変わることがない。
つまり、賢さは生まれつき決まっているのだ。
これが「固定的知能観」です。
僕が言い換えると、「才能思考」です。
もうひとつが
知能というのは、勉強すればするほど伸びる、成長する。
これを「成長的知能観」と言います。
僕が言い換えるなら「成長思考」です。
100%どっちかであることはなくて、
おそらくは、割合の問題だと思うのですが。
問題は、
「固定的知能観」が多いと、
元来持っている自分の固定された才能を
「できるだけ大きく見せる」ことが重要になり、
良い成績をとり、達成することが他者評価を受ける重要な要素になるのだから勉強するが、
成績が落ち始めると、とたんにやる気を失ってしまうということが起こります。
しかし、
「成長的知能観」を持っていれば、
「自分はもっと賢くなりたい」と考え、
他人からどう見られるかに関係なく、知らないことは尋ねることができます。
大切なのは、自分がより賢くなることで、学ぶことそのものが目的になるのです。
ドゥエック教授は、
これによって、学習のパフォーマンスは大きく変わってくると言います。
人間の使用メモリの容量が同じだとすれば、
「努力しても自分は変わらない」と思っている人は
「他人からどう見られるか?」に多くのメモリを使ってしまいます。
一方、「努力すれば自分は変われる」と思っている人は、
メモリの多くを「課題」に対して使うことができるので、
より高い成果をあげるようになるのです。
つまり、
「自分の持っている自分の知能に対する自己イメージ」が
動機に大きな影響を与えるのだと言います。
そして、
上田先生の博士論文によって、
驚くべきことが分かります。
日本の小中高生600人を対象に
調査した結果。
中学1年生の時に、
子どもは「成長的知能観」から「固定的知能観」
に変わる。
つまり、「無力感を獲得する」のです。
なんということでしょう。
おそらくはこれは、
成績の序列化が起こす悲劇なのだろうと考えられます。
同じように勉強してるのに、
隣の席のアイツのほうがテストがいい点数が獲れる。
「もしかしてオレは頭悪いんじゃないか?」
と思ってしまうのです。
しかし。
それは。
あくまで「現時点における」
日本の教育システムが求める力、
つまり、「記憶力、情報処理能力」に関して、だけなのです。
それは「才能」が決めるわけではありません。
まだ、開花していないだけなのかもしれません。
にも関わらず、
中学校1年生の段階で、
「オレには勉強の才能がない」と思ってしまう。
そしてそれは高校受験で決定的になります。
そして進路指導でも。
「あなたの成績はこのくらいだからこのくらいの高校に行きなさい」
と言われます。
こうやって獲得した「無力感」が
学習を楽しめなくしているとしたら、
これは何とかしなきゃいけないのだはないか、と思うのです。
では、どうやって、
「成長的知能観」つまり、成長思考を取り戻すか?
ここで僕は「スラムダンク」理論を使います。
最後の山王戦、
日本一のセンターと言われる河田に歯が立たない
赤木は、こう言います。
「たしかに現時点で俺は河田に負ける。
でもな、湘北は負けんぞ」
これです。
ひとりでは、かなわないけど、
チームでは負けない。
チームならできる。
この感覚から出発するしかないのだと思います。
僕は残念ながら
中学生高校生のアプローチが野山塾でしかできないので、
大学生になってから、
固定的知能観を成長的知能観に
シフトしていくことをしていくというプログラムをつくることしかできません。
誰もが子どものときは
成長的知能観を持っていました。
6歳の少年が
生まれて初めて自転車に乗る。
うまく乗れない。
そのときに、「自転車に乗る才能がない。」
とあきらめる子どもは一人もいません。
乗れるまでチャレンジしたから、いま、自転車に乗れるのです。
いつの間にか、人は無力感を学習します。
それは、才能のせいではなく、
「現時点で開花していない」
ただそれだけなのかもしれません。
「やってみなければわからない」
そう思える中学生高校生大学生を生んでいく。
それこそが大人の役割なのではないでしょうか?
チームでの小さなチャレンジを繰り返し、成長的知能観を取り戻す。
「地域」を舞台に、そんな場と機会をつくることが私たちの役割です。
2014年02月14日
劇場型本屋
Little theater with books
tsuruhashi bookstore
が英英辞典に載るとすれば、
おそらくはこのような文が書かれるだろう。
気がつくと、
巻き込まれているような空間。
昨日。
まだ「本」で人と人をつないでいない。
と思った。
もっともっと「本」との出会い、「人」との出会いを楽しむことができる。
昨日も
たくさんのアイデアをもらった。
絵を描くのが好きな人が
小説を読むと、
そのシーンを絵に描きたくなるのだという。
そんなワンフレーズと
絵を一緒にブックカバーに閉じ込めて、
それで本を選んでもらう。
その原画展とか。
あとは図書館でアルバイトをしていた人の話。
カッコイイ男子が
本を返しに来たら、その本を読んでみる。
返却本。
これも何かぬくもりが感じられるようなイメージがある。
あと思いついたのは、くじびき読書。
10人くらいがオススメの1冊を持ってきて、
交換する「ブクブク交換」を
さらにランダムにしたくじびき読書。
自分に興味のないジャンルを知るための
いろいろな取り組み。
これは本屋だけでなく、
図書館とも一緒にやっていけたらいいと思う。
あとは、
本のワンシーンを感情移入しながら朗読する
劇場型読書。
これも本への興味を喚起してくれるかもしれない。
いけば、何かをやっている本屋。
そこは劇場のような場所かもしれない。
しかし本当は、
ひとりひとりが劇場型の人生を生きているのだと思う。
今日はどんな役とシーンが待っているのだろうか?
そんなふうにワクワクしながら、
本屋に行けたら、どんなに楽しいだろうか。
tsuruhashi bookstore
が英英辞典に載るとすれば、
おそらくはこのような文が書かれるだろう。
気がつくと、
巻き込まれているような空間。
昨日。
まだ「本」で人と人をつないでいない。
と思った。
もっともっと「本」との出会い、「人」との出会いを楽しむことができる。
昨日も
たくさんのアイデアをもらった。
絵を描くのが好きな人が
小説を読むと、
そのシーンを絵に描きたくなるのだという。
そんなワンフレーズと
絵を一緒にブックカバーに閉じ込めて、
それで本を選んでもらう。
その原画展とか。
あとは図書館でアルバイトをしていた人の話。
カッコイイ男子が
本を返しに来たら、その本を読んでみる。
返却本。
これも何かぬくもりが感じられるようなイメージがある。
あと思いついたのは、くじびき読書。
10人くらいがオススメの1冊を持ってきて、
交換する「ブクブク交換」を
さらにランダムにしたくじびき読書。
自分に興味のないジャンルを知るための
いろいろな取り組み。
これは本屋だけでなく、
図書館とも一緒にやっていけたらいいと思う。
あとは、
本のワンシーンを感情移入しながら朗読する
劇場型読書。
これも本への興味を喚起してくれるかもしれない。
いけば、何かをやっている本屋。
そこは劇場のような場所かもしれない。
しかし本当は、
ひとりひとりが劇場型の人生を生きているのだと思う。
今日はどんな役とシーンが待っているのだろうか?
そんなふうにワクワクしながら、
本屋に行けたら、どんなに楽しいだろうか。
2014年02月13日
計測可能であるという罠
上田信行先生の
「プレイフルラーニング」

読み直すべき1冊。
「教育」に興味がある人は是非読んでほしい。
ツルハシブックス、注文しようっと。
2625円の本2冊分の価値はある1冊です。
この2013年度の僕にとっての大きな問いは、
「目標を立てる」ということは、どのくらい価値があるのか?
という問い。
「目標を立てることで」失われるものがあるのではないか?
という疑問。
そしてそれを実証したいという欲求。
「プレイフルラーニング」
を読み直して、
「科学」とは、「計測可能」であるということ。
という当たり前のことに気づかされた。
上田先生の言葉には、ワクワクする何かがある。
~~~ここから引用
Q:
教育を科学的にコントロールしようという発想がいきすぎると、
「予定調和の教育」が生まれ、それが学ぶことの面白さ、楽しさを
阻害し始めたということでしょうか。
A:
そうかもしれません。教育を科学的にコントロールしようとすると、
学習者が到達するゴールを明確に行動目標として記述して、
そこに至るために、どのようにして教育内容を配列するか、
という発想になります。
しかし、僕は「ゴールに書けないものが結構ある」
ということに気づき始めていました。
でも、ゴールは明確に書かなければならないことになっているから、
「ゴールとして書きやすいものを、ゴールとして設定してしまう。」
という本末転倒が起こってくる。そういうことが往々にして見られるように
なったのです。
~~~ここまで引用
これは、すごいね。
科学とは、計測可能であるということ。
科学的であるとは、再現性があるということ。
つまり。
言語化・数値化されたわかりやすいゴールに対して、
この手法を使うと、誰でも到達します。
ということが科学だ。
教育が科学であるならば、
計測可能で再現性を持たなければならない。
そこに
非確実性の高い、
「場のチカラ」や「双方向性」の入る余地はなかなかない。
そして、
もっとも問題だと感じたのは、
「ゴールとして書きやすいものを、ゴールとして設定してしまう。」
これだ。
ここでひとつのエピソードを。
店員サムライのYくんが、
中学の時に、学年全体の前で
「夢を宣言する」という謎の授業があったのだという。
どうしよう。
明確な夢なんかないよ。
と思っていたYくんは
最近見たテレビでやっていた
弁護士が活躍する話を思い出して、
とりあえず弁護士って言っとこう、と
「将来は弁護士になって人を助けたいです。」
みたいなことを宣言したという。
いま書いてみても、ビックリするような授業というか行事だ。
そんなことをすることに何の意味があるのかまったく分からない。
どんな教育効果を目指して、そんな行事があるのだろうか。
ここで、おそろしいのは、
「ゴールとして書きやすいものを、ゴールとして設定してしまう。」
この「書きやすい」は、
キャリア教育的に言えば、
「大人を納得させやすい」ということになるのだろう。
そういうことをやっていると、
何が起こるか。
おそらくは、「学びからの逃亡」が起こるだろう。
予定調和。
ゴール逆算。
目標に向かった教育内容の配列。
そのどこに「面白さ」や「ワクワク」あるのだろうか?
結末もプロセスも決まっている。
そんな「水戸黄門」的な映画やテレビを見るだろうか?
しかも毎日毎日、4時間、5時間も。
場のチカラと
双方向性を持った空間をつくり、
何が起こるかわからない。
どんな結果が出るかはやってみてのお楽しみだ。
そんな学びの空間は作れないのだろうか?
いや。
そのほうがずっと学びが深く楽しくなるのではないか。
自分の関わりによって、
結果が変えられると体感できるのではないか。
当事者はそうやって生まれていくのではないか。
だから。
会津若松商工会議所がやっているような
お店体験プログラム「ジュニエコ」のようなことは
意義があるのではないか。
1年間のテーマの正体がだんだんと見えてきた。
学びって楽しいですね、上田先生。
「プレイフルラーニング」

読み直すべき1冊。
「教育」に興味がある人は是非読んでほしい。
ツルハシブックス、注文しようっと。
2625円の本2冊分の価値はある1冊です。
この2013年度の僕にとっての大きな問いは、
「目標を立てる」ということは、どのくらい価値があるのか?
という問い。
「目標を立てることで」失われるものがあるのではないか?
という疑問。
そしてそれを実証したいという欲求。
「プレイフルラーニング」
を読み直して、
「科学」とは、「計測可能」であるということ。
という当たり前のことに気づかされた。
上田先生の言葉には、ワクワクする何かがある。
~~~ここから引用
Q:
教育を科学的にコントロールしようという発想がいきすぎると、
「予定調和の教育」が生まれ、それが学ぶことの面白さ、楽しさを
阻害し始めたということでしょうか。
A:
そうかもしれません。教育を科学的にコントロールしようとすると、
学習者が到達するゴールを明確に行動目標として記述して、
そこに至るために、どのようにして教育内容を配列するか、
という発想になります。
しかし、僕は「ゴールに書けないものが結構ある」
ということに気づき始めていました。
でも、ゴールは明確に書かなければならないことになっているから、
「ゴールとして書きやすいものを、ゴールとして設定してしまう。」
という本末転倒が起こってくる。そういうことが往々にして見られるように
なったのです。
~~~ここまで引用
これは、すごいね。
科学とは、計測可能であるということ。
科学的であるとは、再現性があるということ。
つまり。
言語化・数値化されたわかりやすいゴールに対して、
この手法を使うと、誰でも到達します。
ということが科学だ。
教育が科学であるならば、
計測可能で再現性を持たなければならない。
そこに
非確実性の高い、
「場のチカラ」や「双方向性」の入る余地はなかなかない。
そして、
もっとも問題だと感じたのは、
「ゴールとして書きやすいものを、ゴールとして設定してしまう。」
これだ。
ここでひとつのエピソードを。
店員サムライのYくんが、
中学の時に、学年全体の前で
「夢を宣言する」という謎の授業があったのだという。
どうしよう。
明確な夢なんかないよ。
と思っていたYくんは
最近見たテレビでやっていた
弁護士が活躍する話を思い出して、
とりあえず弁護士って言っとこう、と
「将来は弁護士になって人を助けたいです。」
みたいなことを宣言したという。
いま書いてみても、ビックリするような授業というか行事だ。
そんなことをすることに何の意味があるのかまったく分からない。
どんな教育効果を目指して、そんな行事があるのだろうか。
ここで、おそろしいのは、
「ゴールとして書きやすいものを、ゴールとして設定してしまう。」
この「書きやすい」は、
キャリア教育的に言えば、
「大人を納得させやすい」ということになるのだろう。
そういうことをやっていると、
何が起こるか。
おそらくは、「学びからの逃亡」が起こるだろう。
予定調和。
ゴール逆算。
目標に向かった教育内容の配列。
そのどこに「面白さ」や「ワクワク」あるのだろうか?
結末もプロセスも決まっている。
そんな「水戸黄門」的な映画やテレビを見るだろうか?
しかも毎日毎日、4時間、5時間も。
場のチカラと
双方向性を持った空間をつくり、
何が起こるかわからない。
どんな結果が出るかはやってみてのお楽しみだ。
そんな学びの空間は作れないのだろうか?
いや。
そのほうがずっと学びが深く楽しくなるのではないか。
自分の関わりによって、
結果が変えられると体感できるのではないか。
当事者はそうやって生まれていくのではないか。
だから。
会津若松商工会議所がやっているような
お店体験プログラム「ジュニエコ」のようなことは
意義があるのではないか。
1年間のテーマの正体がだんだんと見えてきた。
学びって楽しいですね、上田先生。
2014年02月12日
双方向性と空間のあいだ

プレイフルラーニング(上田信行 三省堂)
読み直してます。
冒頭の中原淳さんのまえがきから。
「学び」や「教育」の言説空間において、
ここ十数年間に起こった変化を、
3つのワードで端的に表現するとしたら、
中原先生はこのように答えると言います。
「オルタナティブ」:既存のものとは別の
「インタラクティブ」:双方向性
「アマチュア」:教育の非専門家
つまり、
教員や教授ではない「アマチュア」が
既存のものとは別の「オルタナティブ」な学びの場を生み出し、
双方向の「インタラクティブ」なコミュニケーションをとりつつ、
学ぶようになってきた、と言えるでしょう。
この中で、
僕がもっとも注目したいのは、
「インタラクティブ」(双方向性)だ。
はたして、これが、
学校空間のような、
蛍光灯で囲まれた四角い箱、四角いデスクで可能なのだろうか?
という問い。
「学ぶことが面白い」と思えるには、
双方向性が必須であると僕が思うし、
そのためには空間のチカラはすごく大切だと思う。
そもそも。
今の時代は「誰も答えを持っていない」時代
だと言って、異論を唱える人はあまりいないだろう。
にもかからわず。
「答えを教えるためにある」ような
空間で人は学びたくなるだろうか?
答えを持っていないからこそ、
空間のチカラと、そこを構成する人のチカラを
結集して、何か仮説を立て、
アクションをしてみる。
それ以外に、未来を拓いていく方法はないんじゃないか?
と僕は思うのだが。
だから。
学びの空間は「双方向性」を生み出さなければならない。
そういう意味では、
図書館も、本屋も、まだまだやれることが多い。
学びの空間を
図書館や本屋を中心にもう一度く見直すことができるのではないかと思う。
「ドキドキするような学び」
を子どもたちも、大人たちも求めている。
答えや目標は要らない。
ただ、アクションするための仮説をつくり、
アクションする。
そんな空間をつくろうじゃないか。
そこに僕も求める学びがある。
そんな本屋にしたいです。
2014年02月11日
小さなお店が「当事者」を育む
1999年のまきどき村スタートから
15周年の2014年。
今年も
「人生最高の朝ごはん」は4月から始まります。
4月6日(日)が初日予定。
2011年のツルハシブックスからも3周年。
3月の3連休にひっそりとお祝いしましょう。
土曜日。
堀部さんの講演を聞いて感じたこと。
本というのは、
「非効率」な商品であるということ。
にも関わらず、
「効率的なシステム」を追求し、現在のシステムが形成されたこと。
だからこそ。
街の本屋の経営が厳しいのだということ。
経営が厳しいのは、
ニーズに答えていないからだ。
ツタヤで本が売れるのは、
ニーズに答えているからだ。
それは、
「本が欲しい」というニーズではなく、
「ライフスタイルを提案してほしい」というニーズ。
ツタヤの書籍売り上げが
紀伊國屋を抜いてチェーン店1位になった。
この事実をどう受け止めればいいのか?
恵文社一乗寺店。
京都市左京区という立地を活かし、
お客さんに様々な本を提案するお店。
本好きの聖地とも呼ばれる
このお店に、人はなぜ吸い寄せられるように行くのだろうか?
堀部店長の話から推測すると、
「本屋が本屋である理由」
がそこにはあるからだと思った。
本というメディアはきわめて非効率的な商品である。
本屋に行くときは、
目的をもって本を探しに行くのではなく、
「偶然」を求めていくのだと堀部さんは言っていたが、
まさにその「偶然」が詰まっている本屋さんが恵文社一乗寺店なのだと思う。
そしてその
「偶然」という「非効率的」なものを求めて、
人は電車やバスを乗り継いで、あるいは寒い中自転車を飛ばして、
一乗寺まで足を運ぶのだろう。
そこに感じられる「美しさ」があるからだ。
そんな話を咀嚼していたら、
僕は、まきどき村のことを思い出していた。
あの20代の全てをつぎ込んだ畑には、
何があったのだろうか?
日曜日の朝6時に集まって、
畑をして、
朝市で漬物を買って、
みそ汁を作って
みんなで朝ごはんを食べる。
「人生最高の朝ごはん」と呼んだ活動には、
20代が人生を賭けられるほどの魅力があったのだろうか。
そう考えると、
僕はやっぱり「問い」を発信したかったのだと思う。
本当の「幸せ」や「豊かさ」とは、
いったいなんだろうか?
そんな問いが生まれた大学生の頃。
地球環境問題、農業問題、食糧問題を入り口に、
僕は、本当の豊かさについて考えるようになった。
衝撃の1冊
「どれだけ消費すれば満足なのか?~消費社会と地球の未来」
(アランダーニング ダイヤモンド社)を読んで、
「消費を増やしても、幸せだと思う割合は変化しない」というデータを知った。
衝撃のテレビ
特命リサーチ200Xでのブータン王国の特集を見て、
日本の100分の1以下の消費で人は幸せに生きていることを知った。
では。
どうしたらいいのか?
自分で表現することだった。
尾崎豊が世の中に問いかけたように、
とまではいかないけど、
僕も畑という場を通じて、
世の中に本当の幸せ、豊かさを問いかけたいと思った。
いや、問うのではなく、自分なりに表現したいと思った。
朝起きて、畑して、
みそ汁つくって、囲炉裏を囲んで食べる。
これが豊かさなんじゃないか、と表現したかった。
そんな話を思い出した。
いま。
ふたたび。
僕の前に、「本」そして「本屋」という
非効率的なメディアがある。
僕がなぜ、この業界に来たのか。
全ては、必然だったと思えるような「偶然」の結果だ。
効率性が正しいわけではない。
いや、正しいのかもしれないけど、
効率性で人が幸せになれるわけではない。
世の中の人たちが幸せに生きるために、
もっとも大切なことは、
「当事者を増やすこと」だと僕は思う。
消費を増やしても、
人が幸せになれなかったのは、
本当に消費したくて消費したのではなく、
周りの人が消費しているから、自分も消費しようかな、
と思うくらいのモチベーションだったからだ。
堀部店長が言っていた。
「消費者ではなく、お客さんを相手にすることだ」
店がお客さんをつくり、
お客さんが店をつくり、
店が街をつくる。
そのとき。
お客さんは店の、街の当事者となっている。
小さなお店をするということは、
街の当事者を生んでいく、というアート
をさりげなく創っているのかもしれない。

絵本「せかいでいちばんつよい国」のように、
気がついたら、街に当事者が増え、世界が変わっていた。
きっとそういうことをしていくために、
小さなお店である必要があるのかもしれない。
行政やまちづくりNPOが声高に
「街の当事者を増やせ」と叫ぶのではなく、
小さなお店が、
お客さんたちと一緒に、
お店をつくっていくこと。
非効率的なようで、もっとも近道がそこにあるのかもしれない。
いや。
近道を行く必要などないのだ。
非効率的な、美しい道を、進んでいこうじゃないか。
15周年の2014年。
今年も
「人生最高の朝ごはん」は4月から始まります。
4月6日(日)が初日予定。
2011年のツルハシブックスからも3周年。
3月の3連休にひっそりとお祝いしましょう。
土曜日。
堀部さんの講演を聞いて感じたこと。
本というのは、
「非効率」な商品であるということ。
にも関わらず、
「効率的なシステム」を追求し、現在のシステムが形成されたこと。
だからこそ。
街の本屋の経営が厳しいのだということ。
経営が厳しいのは、
ニーズに答えていないからだ。
ツタヤで本が売れるのは、
ニーズに答えているからだ。
それは、
「本が欲しい」というニーズではなく、
「ライフスタイルを提案してほしい」というニーズ。
ツタヤの書籍売り上げが
紀伊國屋を抜いてチェーン店1位になった。
この事実をどう受け止めればいいのか?
恵文社一乗寺店。
京都市左京区という立地を活かし、
お客さんに様々な本を提案するお店。
本好きの聖地とも呼ばれる
このお店に、人はなぜ吸い寄せられるように行くのだろうか?
堀部店長の話から推測すると、
「本屋が本屋である理由」
がそこにはあるからだと思った。
本というメディアはきわめて非効率的な商品である。
本屋に行くときは、
目的をもって本を探しに行くのではなく、
「偶然」を求めていくのだと堀部さんは言っていたが、
まさにその「偶然」が詰まっている本屋さんが恵文社一乗寺店なのだと思う。
そしてその
「偶然」という「非効率的」なものを求めて、
人は電車やバスを乗り継いで、あるいは寒い中自転車を飛ばして、
一乗寺まで足を運ぶのだろう。
そこに感じられる「美しさ」があるからだ。
そんな話を咀嚼していたら、
僕は、まきどき村のことを思い出していた。
あの20代の全てをつぎ込んだ畑には、
何があったのだろうか?
日曜日の朝6時に集まって、
畑をして、
朝市で漬物を買って、
みそ汁を作って
みんなで朝ごはんを食べる。
「人生最高の朝ごはん」と呼んだ活動には、
20代が人生を賭けられるほどの魅力があったのだろうか。
そう考えると、
僕はやっぱり「問い」を発信したかったのだと思う。
本当の「幸せ」や「豊かさ」とは、
いったいなんだろうか?
そんな問いが生まれた大学生の頃。
地球環境問題、農業問題、食糧問題を入り口に、
僕は、本当の豊かさについて考えるようになった。
衝撃の1冊
「どれだけ消費すれば満足なのか?~消費社会と地球の未来」
(アランダーニング ダイヤモンド社)を読んで、
「消費を増やしても、幸せだと思う割合は変化しない」というデータを知った。
衝撃のテレビ
特命リサーチ200Xでのブータン王国の特集を見て、
日本の100分の1以下の消費で人は幸せに生きていることを知った。
では。
どうしたらいいのか?
自分で表現することだった。
尾崎豊が世の中に問いかけたように、
とまではいかないけど、
僕も畑という場を通じて、
世の中に本当の幸せ、豊かさを問いかけたいと思った。
いや、問うのではなく、自分なりに表現したいと思った。
朝起きて、畑して、
みそ汁つくって、囲炉裏を囲んで食べる。
これが豊かさなんじゃないか、と表現したかった。
そんな話を思い出した。
いま。
ふたたび。
僕の前に、「本」そして「本屋」という
非効率的なメディアがある。
僕がなぜ、この業界に来たのか。
全ては、必然だったと思えるような「偶然」の結果だ。
効率性が正しいわけではない。
いや、正しいのかもしれないけど、
効率性で人が幸せになれるわけではない。
世の中の人たちが幸せに生きるために、
もっとも大切なことは、
「当事者を増やすこと」だと僕は思う。
消費を増やしても、
人が幸せになれなかったのは、
本当に消費したくて消費したのではなく、
周りの人が消費しているから、自分も消費しようかな、
と思うくらいのモチベーションだったからだ。
堀部店長が言っていた。
「消費者ではなく、お客さんを相手にすることだ」
店がお客さんをつくり、
お客さんが店をつくり、
店が街をつくる。
そのとき。
お客さんは店の、街の当事者となっている。
小さなお店をするということは、
街の当事者を生んでいく、というアート
をさりげなく創っているのかもしれない。

絵本「せかいでいちばんつよい国」のように、
気がついたら、街に当事者が増え、世界が変わっていた。
きっとそういうことをしていくために、
小さなお店である必要があるのかもしれない。
行政やまちづくりNPOが声高に
「街の当事者を増やせ」と叫ぶのではなく、
小さなお店が、
お客さんたちと一緒に、
お店をつくっていくこと。
非効率的なようで、もっとも近道がそこにあるのかもしれない。
いや。
近道を行く必要などないのだ。
非効率的な、美しい道を、進んでいこうじゃないか。
2014年02月10日
目標より習慣
教育的効果の高いインターンシップ普及推進シンポジウム
に参加してきました。
高知大学の池田啓実先生の
地域協働が始まった物語に、ドキドキしました。
基調講演の慶応大学の高橋俊介先生の
アツイトークに胸が高まりました。
後半のワークショップでは
地域と大学は今後どうやって協働していくか?
の方法を語りました。
「研修」でこんなにも興奮したのは、
田坂広志さんの、あのときを思い出しました。
高橋先生の基調講演は
恐怖さえ覚える、衝撃の内容でした。
もっとも、
印象に残ったのは、
日本の試験は、
学校だけではなく、ほとんどすべての資格試験が
「暗記」を問うものとなっている。
先生が例に出せれていたのは
ワインのソムリエ試験の話。
日本のソムリエの試験はすべて暗記。
知識を問うもの。
ワインぶどうが何百種類あって、
フランスの何地方で作られているのにはこういう特徴がある・・・みたいな。
それを筆記試験でひたすら覚えるというもの。
一方、
イギリスのソムリエ試験は、こんな感じ。
「あなたはレストランでソムリエをしています。
そこに、いつも●●というワインを必ず頼むお客さんが××という料理を頼み、
「今日はちょっと違うワインを飲んでみようか」と言いました。
あなたは、どんなワインを選び、どんな言葉を添えて、
どのように提供しますか?
そう。
ソムリエとして重要なのはワインの知識ではなく、
「いかにお客さんの記憶に残る接客をするか?」
ということなのです。
だから当然、こういう試験が必要になってきます。
それでは、なぜ、
日本の試験は丸暗記型なのでしょうか。
おそらくそれは、
「客観的効率的に平等に評価が可能だから。」
ということになると思います。
言い換えれば、
「誰も評価の責任をとらない」システム
だと言えるでしょう。
評価を平等に数値化できる指標で測る。
これは、客観的効率的な尺度から見れば正しいでしょう。
しかし、試験を受ける方も評価する方も「考える」という機会を奪われているのではないでしょうか。
いまでこそ。
「自分で考える」「自分で行動する」
は経済社会が求める人材像としてもっとも重要視される人物像ですが、
もしかすると、かつては、
「考えない」「言われたとおりにやる」「その範囲内でやりがいを見出す」
というような人材が求められた。
そして、そのように制度設計された。
それがいまだに制度が生きているのではないかと思いました。
高橋先生は、力を込めておっしゃっていました。
予定通りにキャリアは作れない。
キャリアプランを立てることにあまり意味はない。
変化と専門性の時代のキャリア形成で重要なのは、
1 「目標」ではなく「習慣」
2 普遍性の高い学びの能力
3 健全な仕事観
これを、小中高大と
培っていくようにしていくことが必要なのだとおっしゃってました。
大学のキャリア教育としては
「就活支援:エントリーシートなどを指導し、内定率を上げる」と
「キャリアガイダンス:自己理解や就業体験、内省などによりやりたい仕事の幅を広げる」と
(本来の意味での)「キャリア教育:社会で仕事をする上での必須の基礎的能力や姿勢を培い、やれる仕事の幅を広げる」が
3層構造になっている。
しかし現在は
「就活支援」に偏っているので、
キャリアガイダンスとキャリア教育が
バーチャル化している傾向がある。
これらを明確に分けて、3層構造として、
1年次から産学連携を通じた
社会人基礎力と規範的仕事観(そもそも仕事とは、人のために動くことだ)
を培っていく必要がある。
1年次からの
地域とコラボしたキャリア教育の重要性を
あらためて強く感じた1日でした。
ありがとうございました。
に参加してきました。
高知大学の池田啓実先生の
地域協働が始まった物語に、ドキドキしました。
基調講演の慶応大学の高橋俊介先生の
アツイトークに胸が高まりました。
後半のワークショップでは
地域と大学は今後どうやって協働していくか?
の方法を語りました。
「研修」でこんなにも興奮したのは、
田坂広志さんの、あのときを思い出しました。
高橋先生の基調講演は
恐怖さえ覚える、衝撃の内容でした。
もっとも、
印象に残ったのは、
日本の試験は、
学校だけではなく、ほとんどすべての資格試験が
「暗記」を問うものとなっている。
先生が例に出せれていたのは
ワインのソムリエ試験の話。
日本のソムリエの試験はすべて暗記。
知識を問うもの。
ワインぶどうが何百種類あって、
フランスの何地方で作られているのにはこういう特徴がある・・・みたいな。
それを筆記試験でひたすら覚えるというもの。
一方、
イギリスのソムリエ試験は、こんな感じ。
「あなたはレストランでソムリエをしています。
そこに、いつも●●というワインを必ず頼むお客さんが××という料理を頼み、
「今日はちょっと違うワインを飲んでみようか」と言いました。
あなたは、どんなワインを選び、どんな言葉を添えて、
どのように提供しますか?
そう。
ソムリエとして重要なのはワインの知識ではなく、
「いかにお客さんの記憶に残る接客をするか?」
ということなのです。
だから当然、こういう試験が必要になってきます。
それでは、なぜ、
日本の試験は丸暗記型なのでしょうか。
おそらくそれは、
「客観的効率的に平等に評価が可能だから。」
ということになると思います。
言い換えれば、
「誰も評価の責任をとらない」システム
だと言えるでしょう。
評価を平等に数値化できる指標で測る。
これは、客観的効率的な尺度から見れば正しいでしょう。
しかし、試験を受ける方も評価する方も「考える」という機会を奪われているのではないでしょうか。
いまでこそ。
「自分で考える」「自分で行動する」
は経済社会が求める人材像としてもっとも重要視される人物像ですが、
もしかすると、かつては、
「考えない」「言われたとおりにやる」「その範囲内でやりがいを見出す」
というような人材が求められた。
そして、そのように制度設計された。
それがいまだに制度が生きているのではないかと思いました。
高橋先生は、力を込めておっしゃっていました。
予定通りにキャリアは作れない。
キャリアプランを立てることにあまり意味はない。
変化と専門性の時代のキャリア形成で重要なのは、
1 「目標」ではなく「習慣」
2 普遍性の高い学びの能力
3 健全な仕事観
これを、小中高大と
培っていくようにしていくことが必要なのだとおっしゃってました。
大学のキャリア教育としては
「就活支援:エントリーシートなどを指導し、内定率を上げる」と
「キャリアガイダンス:自己理解や就業体験、内省などによりやりたい仕事の幅を広げる」と
(本来の意味での)「キャリア教育:社会で仕事をする上での必須の基礎的能力や姿勢を培い、やれる仕事の幅を広げる」が
3層構造になっている。
しかし現在は
「就活支援」に偏っているので、
キャリアガイダンスとキャリア教育が
バーチャル化している傾向がある。
これらを明確に分けて、3層構造として、
1年次から産学連携を通じた
社会人基礎力と規範的仕事観(そもそも仕事とは、人のために動くことだ)
を培っていく必要がある。
1年次からの
地域とコラボしたキャリア教育の重要性を
あらためて強く感じた1日でした。
ありがとうございました。
2014年02月09日
答えを求めるなら本である必要がない
恵文社一乗寺店。
全国的に知られたステキな本屋さん。

最近
「街を変える小さな店~京都のはしっこ、個人店に学ぶこれからの商いのかたち」を出版した
堀部店長のお話を聞いてきました。
ドキドキするお話でした。
個人店の魅力の詰まったワクワクする話でした。
一方で、「まちの本屋」が衰退していく理由が
痛いほどわかりました。
恵文社一乗寺店の名前が
有名になり始めたころ。
「本のセレクトショップ」と呼ばれることが多かったと言います。
「本のセレクトショップ」
これは、不思議な言葉です。
雑貨でも、洋服でも、飲食店でも、
普通、個人でやっているお店は、
全て「セレクトショップ」です。
店主が自分のお気に入りを選んで、
お客さんに共感してもらって、買っていただく。
あるいは、対話の中でお客さんのニーズをくみ取って、
それを仕入れ、売る。
その繰り返しでお店が成り立っています。
ところが。
本屋だけはそうではありませんでした。
取次と呼ばれる問屋さんが、
「いま、売れている作家、あるいは雑誌」という
データから、
お店の規模によって、
たとえば、あの駅前にある大きな紀伊國屋書店には100冊くらい、
あそこの街の小さな本屋でも、5冊くらいは売れそうだから8冊くらい入れておこう。
みたいな。
問屋さんが決めた本のラインナップを
並べていただけでした。
不幸なことに、
それでも本屋の経営が成り立つ時代が長く続いたのです。
もちろん、店主の人柄も重要な要因だったと思います。
しかし、お店のかなめである商品のラインナップを決めていたのは、
ほぼ、問屋さんでした。
いま、本好きだと自称する人は、言います。
「チェーン店に行っても、同じような品ぞろえで、
POSデータどおりに本が並んでいるだけでつまらない。」
しかし、その言葉は、
何十年も前から、
本屋の全てに当てはまる言葉だったのです。
いい言い方をすれば、
全国どこの本屋にも、発売日にちゃんと本が、雑誌が届く。
「効率化、均質化」の代表選手が本屋という業界だったのです。
つまり、全国の本屋がみんな、その問屋をトップとした
チェーン店だったようなものです。
恵文社一乗寺店が「本のセレクトショップ」
と呼ばれた、というのは、そんな業界の歴史を現わしています。
そしてもうひとつ。
本屋さんが衰退した理由。
堀部さんの言葉を借りれば、
「答えを求めるなら、本である必要がない。」
もうひとつ、僕が思ったのは、
「答えを求めるなら、本屋である必要がない。」
堀部さんは言います。
本屋に行くというのは、自分の関心の外、意識の外の
ものを知りに行く、ということ。
だから、現在の「消費」のメカニズムとは違うんだ、と。
「消費」とは、欲しい、と思ったものを、
いちはやく、最小の労力、金額で手に入れること。
そこに価値がある。
「賢い消費者」にとっての関心事は
「コストパフォーマンスの最大化」である。
だから、
小さなお店は「消費者」を相手にすることはできません。
消費者ではなく、「お客さん」
として付き合ってくれる人が必要です。
本屋の「お客さん」は、
欲しい本を最小の努力と金額で欲しいのではなくて、
店主との対話や、その場にいる時間。
そして、自分の関心の外、意識の外の世界を
見せてくれる空間として、本屋を見ています。
そもそも、本を読むという行為は
短期的には「コストパフォーマンス」の低い行為です。
その読んだ本が、
いつ、どのように効いて、
どのくらいの金銭的メリットがあるのか、よく分かりません。
(一部ビジネス書には、すぐに効きそうなタイトルの本もありますが)
本屋で本を選び、
店主と対話をして、
本を買う。
買った本を持って、近くのカフェに入って読む。
ステキな生活だと思いましたか?
そのコストパフォーマンスの悪い行為を
ステキだと思う「美意識」が
小さな店、小さな本屋を支えている、
と堀部さんは言います。
僕もまったく同感です。
これからの消費、
いや、これからの働き方、生き方を
決めていくのは、
ひとりひとりの美意識しかありません。
「自分は何をもって、美しいとするのか?」
という問いを常に問われていると言ってもいいでしょう。
「コストパフォーマンス」に対して、
「美意識」で対抗していく。
いや、対抗ではないな。
美意識を持って、立っていく、ということかな。
だから。
本や本屋というメディアは、
「美しさ」を問うことをしていく必要があると思います。
答えを最速で求めるなら、
本も本屋も不要です。
しかし、それは、美しくないんじゃないか?
と思える「お客さん」たちと、
「美しさ」を問うような棚、
そして美しさを感じられるような居心地の良い空間を
共に演じていきたいと僕も思います。
もし、僕たちが「文化」を創っているとしたら。
それはどんな「文化」だろう?
全国的に知られたステキな本屋さん。

最近
「街を変える小さな店~京都のはしっこ、個人店に学ぶこれからの商いのかたち」を出版した
堀部店長のお話を聞いてきました。
ドキドキするお話でした。
個人店の魅力の詰まったワクワクする話でした。
一方で、「まちの本屋」が衰退していく理由が
痛いほどわかりました。
恵文社一乗寺店の名前が
有名になり始めたころ。
「本のセレクトショップ」と呼ばれることが多かったと言います。
「本のセレクトショップ」
これは、不思議な言葉です。
雑貨でも、洋服でも、飲食店でも、
普通、個人でやっているお店は、
全て「セレクトショップ」です。
店主が自分のお気に入りを選んで、
お客さんに共感してもらって、買っていただく。
あるいは、対話の中でお客さんのニーズをくみ取って、
それを仕入れ、売る。
その繰り返しでお店が成り立っています。
ところが。
本屋だけはそうではありませんでした。
取次と呼ばれる問屋さんが、
「いま、売れている作家、あるいは雑誌」という
データから、
お店の規模によって、
たとえば、あの駅前にある大きな紀伊國屋書店には100冊くらい、
あそこの街の小さな本屋でも、5冊くらいは売れそうだから8冊くらい入れておこう。
みたいな。
問屋さんが決めた本のラインナップを
並べていただけでした。
不幸なことに、
それでも本屋の経営が成り立つ時代が長く続いたのです。
もちろん、店主の人柄も重要な要因だったと思います。
しかし、お店のかなめである商品のラインナップを決めていたのは、
ほぼ、問屋さんでした。
いま、本好きだと自称する人は、言います。
「チェーン店に行っても、同じような品ぞろえで、
POSデータどおりに本が並んでいるだけでつまらない。」
しかし、その言葉は、
何十年も前から、
本屋の全てに当てはまる言葉だったのです。
いい言い方をすれば、
全国どこの本屋にも、発売日にちゃんと本が、雑誌が届く。
「効率化、均質化」の代表選手が本屋という業界だったのです。
つまり、全国の本屋がみんな、その問屋をトップとした
チェーン店だったようなものです。
恵文社一乗寺店が「本のセレクトショップ」
と呼ばれた、というのは、そんな業界の歴史を現わしています。
そしてもうひとつ。
本屋さんが衰退した理由。
堀部さんの言葉を借りれば、
「答えを求めるなら、本である必要がない。」
もうひとつ、僕が思ったのは、
「答えを求めるなら、本屋である必要がない。」
堀部さんは言います。
本屋に行くというのは、自分の関心の外、意識の外の
ものを知りに行く、ということ。
だから、現在の「消費」のメカニズムとは違うんだ、と。
「消費」とは、欲しい、と思ったものを、
いちはやく、最小の労力、金額で手に入れること。
そこに価値がある。
「賢い消費者」にとっての関心事は
「コストパフォーマンスの最大化」である。
だから、
小さなお店は「消費者」を相手にすることはできません。
消費者ではなく、「お客さん」
として付き合ってくれる人が必要です。
本屋の「お客さん」は、
欲しい本を最小の努力と金額で欲しいのではなくて、
店主との対話や、その場にいる時間。
そして、自分の関心の外、意識の外の世界を
見せてくれる空間として、本屋を見ています。
そもそも、本を読むという行為は
短期的には「コストパフォーマンス」の低い行為です。
その読んだ本が、
いつ、どのように効いて、
どのくらいの金銭的メリットがあるのか、よく分かりません。
(一部ビジネス書には、すぐに効きそうなタイトルの本もありますが)
本屋で本を選び、
店主と対話をして、
本を買う。
買った本を持って、近くのカフェに入って読む。
ステキな生活だと思いましたか?
そのコストパフォーマンスの悪い行為を
ステキだと思う「美意識」が
小さな店、小さな本屋を支えている、
と堀部さんは言います。
僕もまったく同感です。
これからの消費、
いや、これからの働き方、生き方を
決めていくのは、
ひとりひとりの美意識しかありません。
「自分は何をもって、美しいとするのか?」
という問いを常に問われていると言ってもいいでしょう。
「コストパフォーマンス」に対して、
「美意識」で対抗していく。
いや、対抗ではないな。
美意識を持って、立っていく、ということかな。
だから。
本や本屋というメディアは、
「美しさ」を問うことをしていく必要があると思います。
答えを最速で求めるなら、
本も本屋も不要です。
しかし、それは、美しくないんじゃないか?
と思える「お客さん」たちと、
「美しさ」を問うような棚、
そして美しさを感じられるような居心地の良い空間を
共に演じていきたいと僕も思います。
もし、僕たちが「文化」を創っているとしたら。
それはどんな「文化」だろう?





