2019年07月30日
「消費者」という「自由」

「街場の平成論」(内田樹編 晶文社)
ううーん。
って唸るばかりの本。
現実を目の前に苦しくなります。
その中でも(まだ途中ですが)
平川克美さんの「消費者」「自由」に関する記述が的確だと
思ったので、ブログに残したく、転載します。
~~~以下本文よりメモ
「週休2日制」は、単に1週間に休日が1日増えたというに止まらない変化を日本にもたらした。
週5日は労働のための日だが、残りの2日は消費のための日になったのである。
多くの日本人は、豊かな余暇を過ごすために、働くようになった。
週休2日制、労働者派遣法改正による非正規雇用の増加、24時間営業のコンビニエンスストアの隆盛という3つの変化は、日本に新たな階級としての「消費者」を生み出した。
ここでいう「消費者」とは単に市場における消費行動をするものののことではない。金さえあれば、誰からも命令されることなく自由に働き、自由に生活し、自由に余暇を楽しむことができるを内面化したものの謂である。
「消費者」は、これまでの古い慣習や、しがらみから自分を解き放つことが可能な存在であった。一人の時間を大切にし、誰からもその行動を干渉されず、好きなときに好きなものを自由に所有することができる。
消費者が持った解放感は、日本の歴史上稀有のものだったように思える。金の力が、個人を解放するという幻想を多くの日本人が共有したのである。ただし、金さえあればの話である。
そのことは、お金の万能性をさらに高める結果になったとも言えるだろう。「消費者」こそが自由と平等の享受者であるならば、お金こそがそれらを手に入れる鍵だからである。
もともと、自由も平等も旧体制転覆の熾烈な市民革命を経て人々が獲得したものであり、その結果として「個人」という強固な概念が生まれてきたという歴史的事実がある。
革命を経ない日本では、長い間「イエ」が社会の最小単位であり、「イエ」を存続させるために封建的な秩序が支配的であり、女性もまた「イエ」の存続のための重要な役割を担わされることを余儀なくされてきた。
考えてみれば、「消費者」は、革命を経なかった日本人が初めて手にした「個人」であったと言えるかもしれない。ここでも、但し書きがつく。但し、金さえあれば。
昭和天皇崩御のときの、日本総右ならえと、ビデオ屋での待ち行列という二つの相矛盾する行動は、「イエ」の価値観と「消費者」の価値観が交錯した風景でもあったのだ。
個人主義は、一人一人の人間には、他の何ものにも代えがたい価値があることを謳う思想であり、個人の権利と自由は、国家や共同体から束縛されたり、毀損されたりすべきではない最優先のものであると考える。
奇矯に響くかもしれないが、日本人がが獲得した個人の概念は、金で買ったものであり、金がなければ、その個人とは社会によって淘汰され、そのフルメンバーから除外される危険性もあったのだ。
~~~ここまで本文からメモ(平川克美 「消費者」主権国家まで)
金で買った「個人」。
つまり「消費者」としてふるまうことこそが自由への唯一の道だと多くの人が信じていた時代。
「経済合理性」という一元化した価値観に、みんなが投げ込まれていった。
そこに幸せはあったのだろうか?
他者との比較しかない。
それこそが「消費者」という自由だった。
この章のラストに平川さんも書いているけど、
経済合理性という物差しとは別の物差しを手に入れる以外にはないように思える。
そうそう。
それを自らつかみとっていくこと。
あるいは、百姓のように生み出していくこと。
それが本当に「自由」になる唯一の方法であると僕も思う。
2019年07月25日
「百姓」をアップデートする
「百姓」をアップデートする。
「田舎には仕事がない」のではなく、
「田舎にはサラリーマン仕事が少ない」というのが真実だ。
「地方に人を呼ぶには雇用の拡大を」
というのは、ある意味、真実だろう。
「サラリーマン」という働き方は
直近わずか50年の特殊な働き方だったと、
伊藤洋志さんは「ナリワイをつくる」で言っている。

http://hero.niiblo.jp/e441317.html
「50年間だけの成功モデル」
http://hero.niiblo.jp/e279962.html
「専業思想がコミュニティを崩壊させた」
http://hero.niiblo.jp/e477992.html
「本業じゃないほうが本質的なことができる」
昨日、阿賀町で自然薯を栽培している
目黒さんの話が僕の中で熱かった。
小中学生のエゴマの植え付け体験を受け入れたら
時期がちょっと遅くなっちゃって、今年は収穫量が減るかも。
でも、学びのためには毎年受け入れるよ、みたいな。
この前、お義父さんの小屋づくりの
玄関にセメントを流しこむ作業をしたとき、金属のコテじゃなくて、
木をコテの形に切って取っ手(それも木)をつけただけの
お手製のコテで上手に塗っていて、感動した。
ああ。
ブリコラージュっていうのはそういうことか、と。
百姓っていうのは、「自分でつくる」っていうことなんだ。
「仕事」っていう概念が変わりつつある時代に生きていると思う。
だとしたら、
人は自ら、自らの「仕事」を定義しなければならない。
目黒さんの話は、まさにそれだった。
「価値」は何か?
エゴマをたくさん取ることか。
それともエゴマの植え付け体験を子どもたちにしてもらうことか。
それを自ら定義して、実践すること。
それが百姓なのではないか、と思った。
子どもたちに伝えていかないといけないのは、
そういう百姓スピリットなのではないか。
いい大学いい会社に入ったから幸せになれるわけではない。
いい師匠いい仲間にめぐり合えたから幸せになれるわけでもない。
唯一幸せになれるのは、幸せを自ら定義した者である。
と2か月ほど前につぶやいたのだけど、
「幸せ」だけじゃなく、「仕事」も自ら定義すること。
そしてそれを自らつくってみること。
百姓とは、
仕事をたくさん持つ人のことであり、
仕事を自らつくる人のことであり、
仕事を自ら定義し、自らの価値観に従って実行する人のことである
それが百姓2.0なのかもしれない。
「田舎には仕事がない」のではなく、
「田舎にはサラリーマン仕事が少ない」というのが真実だ。
「地方に人を呼ぶには雇用の拡大を」
というのは、ある意味、真実だろう。
「サラリーマン」という働き方は
直近わずか50年の特殊な働き方だったと、
伊藤洋志さんは「ナリワイをつくる」で言っている。

http://hero.niiblo.jp/e441317.html
「50年間だけの成功モデル」
http://hero.niiblo.jp/e279962.html
「専業思想がコミュニティを崩壊させた」
http://hero.niiblo.jp/e477992.html
「本業じゃないほうが本質的なことができる」
昨日、阿賀町で自然薯を栽培している
目黒さんの話が僕の中で熱かった。
小中学生のエゴマの植え付け体験を受け入れたら
時期がちょっと遅くなっちゃって、今年は収穫量が減るかも。
でも、学びのためには毎年受け入れるよ、みたいな。
この前、お義父さんの小屋づくりの
玄関にセメントを流しこむ作業をしたとき、金属のコテじゃなくて、
木をコテの形に切って取っ手(それも木)をつけただけの
お手製のコテで上手に塗っていて、感動した。
ああ。
ブリコラージュっていうのはそういうことか、と。
百姓っていうのは、「自分でつくる」っていうことなんだ。
「仕事」っていう概念が変わりつつある時代に生きていると思う。
だとしたら、
人は自ら、自らの「仕事」を定義しなければならない。
目黒さんの話は、まさにそれだった。
「価値」は何か?
エゴマをたくさん取ることか。
それともエゴマの植え付け体験を子どもたちにしてもらうことか。
それを自ら定義して、実践すること。
それが百姓なのではないか、と思った。
子どもたちに伝えていかないといけないのは、
そういう百姓スピリットなのではないか。
いい大学いい会社に入ったから幸せになれるわけではない。
いい師匠いい仲間にめぐり合えたから幸せになれるわけでもない。
唯一幸せになれるのは、幸せを自ら定義した者である。
と2か月ほど前につぶやいたのだけど、
「幸せ」だけじゃなく、「仕事」も自ら定義すること。
そしてそれを自らつくってみること。
百姓とは、
仕事をたくさん持つ人のことであり、
仕事を自らつくる人のことであり、
仕事を自ら定義し、自らの価値観に従って実行する人のことである
それが百姓2.0なのかもしれない。
2019年07月24日
「計画できない」という前提で、直感と好奇心で動き続ける
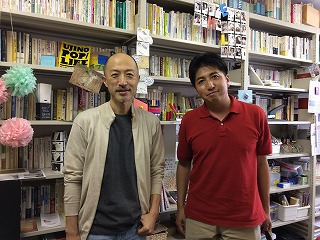
法政大学長岡研究室にお邪魔してきました。
いま参画している「阿賀黎明高校魅力化プロジェクト」
のコンセプトを考えていて、長岡先生の取り組みと
親和性が高いなあと思ったからです。
もともと、塩尻で出会ったエミリーが長岡ゼミ生で
この春卒業したのだけど、カフェゼミに誘ってもらって、
そのカフェゼミのゲストが慶応大学の「つながるカレー」の
加藤先生で、「予測不可能性」の大切さを気づかせてもらった場でした。
ということで、
長岡研究室訪問メモ。
~~~ここからメモ
長岡ゼミの基本方針:「直感」と「好奇心」で動き続ける
好奇心:興味を広げる(⇔知識を深める・技術を高める)
直感:試行錯誤で学ぶ(⇔正解を教わる/受け入れる)
漢方薬⇒長期的な変化(⇔迅速な修正)
&個別対応(⇔プログラム対応)
垂直的発達(積み上げ)⇔水平的発達
「越境」⇔「学習」(目的に向かう)
「経営学」⇔「教育工学」
「経営学」がささいな問題に厳密に回答するようになり、役に立たなくなった。
2004年パルサミーノ・レポート
https://tech.nikkeibp.co.jp/it/free/NC/TOKU2/20041228/1/
「工業的な新しいことは必ず追いつかれる」
「アメリカはイノベーションし続けないといけない」
経営学総論(2011)
プレイヤーは「企業」と「政府」と「家計」
仕組みは「交換(市場)」と「再分配(税金)」
それらを支える学問が「経営学」「経済学」「家政学」
営利性原理の脱構築:「再分配」⇔「交換」⇔「互酬」
企業とは「営利性原理」に基づく活動「利潤最大化」と「自己責任」
最小の費用(効率)で最大の成果(成長)を得ようとする合理性が求められる。
交換:等価かつ同時
互酬:仲間内だけを助ける
資本主義の基本概念モデル
(所有権の移動)
取引⇒交換:市場/企業&家計
徴収⇒再分配:国家/政府
贈与⇒互酬:共同体(コミュニティ)
「ワークシフト」(リンダ・グラットン)
精神的ゆとりの欠如
人間的つながりの欠如
経済的な格差(貧困)
協力する社会←競争する社会:「強さ」よりも「優しさ」や「思いやり」
社会の利益←個人の利益:私とみんなの幸せを考える「共」の意識
自立する個人←集団に頼る個人:所属や肩書きに頼らない幅広い「人脈」
第1のシフト:「教えられて、やらされる勉強」から
「新しいことを主体的に学び続ける」へ。
第2のシフト:「閉ざされた世界の中での孤独な競争」から
「開かれた世界の人々のネットワーク」へ
第3のシフト:「金銭欲・自己顕示欲・独占欲」から
「楽しいからやる、分かち合う歓び」へ
ワークシフト時代を生き抜くために必要な「仲間」とは、
精神的な安らぎをもたらす仲間
プロジェクトを共に進める仲間
世界を広げてくれる仲間
ソーシャルデザインの視点
「公」「共」「私」
パブリック、コモン、プライベート
未来にある世界とは?
先行きが見えない世界⇒想定外を生き抜く力
多様な価値観が交差する社会⇒葛藤と向き合い、乗り越える力
「釜石の奇跡」
・マニュアルに頼らない
・ミスを恐れず最善を尽くす
・指示を待たずに率先する
「直感」⇔「計画」
大学生の現状:
人の評価が気になる。
間違えることを恐れる。
「評価されない」前提ですすめる。
プロジェクトのゴールを作らない。
キレイな物語(目的地から再構成する)ではなく
プロセスを記述できるか?
トライ&エラーで学ぼう
(直感)⇔計画
直感で動くと間違える。
計画して動くと動けなくなる。
直感で動いたことをふりかえる「越境」学習
イノベーティブなプロジェクトほど失敗が許される。
イノベーティブじゃないプロジェクトほど計画を綿密に立てる。
プロジェクトごとの評価をしない。
3年間の自らの成長を見る。
「計画できない」という前提
~~~ここまでメモ
いちばん感じたのは、
「評価」ではなく、「ふりかえり」であるということ。
直感で動けば、間違いしかないということ。
時代がシフトするように、
考え方もそちらへシフトしないといけない。
あとは、「教育学」は「経営学」より20~30年遅れているということ。
たしかに、「人を育てる」という意味では、
経営学は絶えずトライ&エラーを繰り返してきたと言えるだろう。
その経営学が
「これからは合理性じゃないんじゃないすか?」
って15年も20年も前から言っているのに、
いまだに教育現場では目標を立てて達成するっていうのを
やっていて大丈夫なのか?と
「機会」を得て学び、それを振り返って学びに変えていく。
そんな「学び」の出発点、いや人生の出発点に立つのは、
大学生からでは遅すぎるくらいだ。早ければ早いほどいい。
Good Luck!
2019年07月13日
「機会」を「学び」にするふりかえりの重要性

昨日は茨城大学で、
授業でもサークルでも使える!楽しいミーティングの進め方2(場づくりラボ)でした。
知ってそうで知らない「ミーティング」を楽しくする方法について考えました。
ラインナップはこういう感じ。
1.自己紹介・チューニング
2.前回のおさらい(ミーティングのルール、司会のやり方、議題の3種別)
3.ドラッカーの5つの質問
4.顧客はだれか?ワークショップ
5.プロジェクトの7要素
6.ふりかえりの方法
7.感想・振り返り・次回予告
ドラッカーの5つの質問
1 ミッションは何か
2 顧客はだれか
3 顧客にとって価値は何か
4 成果は何か
5 計画は何か
からの
「顧客」アプローチと「価値」アプローチの話をしてから、
「顧客はだれか」ワークショップ。
マインドマップ式に自分の顧客を探すワーク。
そしてプロジェクト7要素の説明
7 どのように
6 何を
5 誰のために
4 なぜ
3 どこで
2 いつ
1 誰と
1~3が場のチカラ。
1~7がプロジェクト
メンバーが下のほうを決めるときに「参加」できているか?が重要。
通常の企業インターンシップは7しか裁量がないのでモチベーションが上がらない。
振り返りの重要性
「手段」としての「ミーティング」と「機会」としての「ミーティング」
イベントの目的は「目標を達成すること」なのか?
4象限ふりかえり。
よかった 悪かった
予想できた 予想できなかった
よかったことから始まり、よかったことで終わる
「反省会」で終わってはいけない。
予想しなかったよかったことは当日に振り返らないと忘れる。
これを繰り返しながら、
「予想できなかった悪かったこと」(通常の反省)をいかに楽しめるか。
予想できなかったこと=エンターテイメントの種
書くことで、自分から切り離す。場のせいにする。
~~~とまあ、こんな感じのトークでした。
以下、参加者の感想。
たのしくミーティングがしたい(切実)
→機会と手段の違いが分かった
→振り返りの方法、使いたい
→これまでの(チームでの)振り返りはあまかった(のでマイナス点が目立った)
→まずは機会をつくること
→チーム内での提案の仕方
→自分が話すボリューム
2回にわたって、楽しいミーティングの進め方を学んで自分の団体のミーティングはあまりうまくいっていないことがわかっていたけど、何がダメなのかいまいちわからずじまいだったが、何をどう改善していったらいいかわかってきたし、今まで決めることさえすればいいと思っていただけのミーティングだったが、ミーティング時代も自分も楽しめばいいし、みんなのことも楽しませればいいんだという気持ちになれた。これから自分がリーダーということで、団体をもっとよくしていくために、まずは自分のスキルアップが必要なのだと感じたし、2回にわたって得た知識を生かしていきたいと思った。前回のミーティングで1回目に教えていただいたことを少し実践してみたのですが、前にくらべて発言は多いがこそこそっと話すくらいだったため、もっと活発に発言してもらえるようにメンバー内での壁をなくしていきたいと思った。ただ本当に前にくらべたら意見も出るようになってきたため、もっとみんなが意見を出せるような場づくりを心掛けたい。
振り返りが「できなかったこと悪かったこと」を話し合っていたことがもしかして私自身が苦痛に感じていたかもしれないと思いました。自分が楽しくないことを他人に強要するのはよくないですし、楽しいミーティング作りをするためには自分から楽しまなければいけないと学べました。嫌なことから最近は逃げてはいけないと思いがちでしたが、嫌なことを楽しむという感じは思いつきませんでした。
イベントやプロジェクトを行う際に、「機会を与える」ことに注力しようとすると、「それでどうなる?」「なんのため?」など、言われて否定されることがあったが、機会を与えることに価値があることを再認識した。
「顧客はだれか?」ワークショップで過去の自分「表現や発言をすることが苦手だった自分」を考えていたが、今の自分と照らし合わせて、どう変化したのか、その変化はなぜ起こったのかを掘り下げるまで至らなかった。その部分、特に変化の起こった理由は大切だと思うので、自分なりに考えていきたいと思った。
振り返りと反省の違い。
自分のプロジェクトのミーティングでちゃんと利用する!次の年にちゃんとつなげる!自分がやり始めたことの経緯やそのことについての価値は大きいものであるということは思ったので(再認識しました)、大事にする。機会のほうが代位ということは自分も考えてます。経験が増えるので!(そこからいろいろと考えることができるので)
~~~ここまで感想
場づくりラボは、8月9月お休みです。再開は10月になる予定です!
次回もお楽しみに!
僕の感想は、
「手段」としての学びを「機会」としての学びにシフトしたい
っていうのがさらに強まったし、
「機会」を「機会」にするために、ふりかえりが必要だし。
目的・目標のための「手段」としての学びとしてとらえると、
それを達成している人は、達成していない人より優位にあるので
コミュニケーションがフラットになりにくいのではないかなと思った。
「機会」の前で人はフラットになれるのだと感じた。
今月も楽しい時間でした。
ありがとうございました。
2019年07月07日
大学生と「価値」を生むために

新潟市×にいがたイナカレッジ
「トビラ」プロジェクト第1回集合研修でした。
今回のテーマは2つで、
大学生とのプロジェクトの進め方と
プロジェクトの説明ブラッシュアップでした。
まず、プロジェクトに大学生が加わることの価値は何か?
受入れ団体の新保さんから「新たな視点」がもらえる、と話がありましたが、
まさにその通りで、一言でいえば、「イノセント」と「行動力」です。
「若者らしい斬新な発想やアイデア」ではありません。
そして、プロジェクトの定義:
「プロジェクトとは。独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施される有期性の業務である」
そして、ゴール設計の話
「行動目標」「成果目標」「意義目標」の話
★ここに入れたらよかった★
ミーティング時の安心空間の作り方
コミュニケーション力からコミュニケーション・デザインへ。
ミーティング時の議題の進め方
1 目的・前提の共有
2 報告、相談、決定の種別
3 決まったことの確認
ふりかえりの重要性
「予想できなかったよかったこと」の話
エンターテイメントとは「予測不可能性」。
~~~
とここまで前半の進め方の話。
いかに大学生と「パートナーシップ」を組んでいけるか?
そのためのミーティングと振り返りを行うことの重要性を話した。
後半は、前半のまとめとして、場のチカラ理論
場のチカラ:
7 どのように how
6 何を what
5 誰のために for whom
4 なぜ why
3 どこで where
2 いつ when
1 だれと with whom
通常の企業インターンは7にしか裁量権がないが
「トビラ」プロジェクトは1~7まで一緒に作っていける、ということ。
そして、4と5をブラッシュアップするために、
ドラッカーの5つの質問をベースにしたワークシートを作成
ドラッカーの組織経営に必要な5つの質問
1 ミッションは何か
2 顧客は誰か
3 顧客にとって価値は何か
4 成果は何か
5 計画は何か
ここの1~3を考えるワークシートを記入して
受入れ団体同士で相互インタビューを行った。
この相互インタビューが予想以上に盛り上がり、
気づきが多かったとコメントしていた。
ああ、これが場のチカラで、場によって学ぶってことだなあと。
各団体のプロジェクトはもちろん独立しているのだけど、
団体同士で、なぜ?とかその先は?とかあらためて
インタビューされることだったりすることで、
自団体にも生かせるヒントがあったりするのだなあと。
私たちの今後の課題は
・来年度プロジェクト設計(内容)の講座はやるのか、やらないのか。
⇒助成金応募のようなシートに記入してエントリーしてもらう形など
・中間研修などの位置づけ、意味づけ。
⇒コーディネーターがいるので、プロジェクトが大幅に進まない事態にはならないが、
他団体から刺激をもらう、あるいは「トビラ」プロジェクト自体を「場」としてとらえるなら
効果はあるかも。
全体の設計として
5月:プロジェクト設計講座・応募開始(受入れ団体)
6月:受入れ団体決定・学生募集開始
7月:プロジェクト説明ワーク⇒学生向けプロジェクト説明会
9月:プロジェクトの進め方講座
9月末:プロジェクト開始
11月:中間研修
12月:プロジェクト終了
1月:報告会
という感じかなあと思いました。
こういう受入れ団体向け研修はヒーローズファーム以来だったので
(しかも研修はほとんど全部中村さんがやっていた)
緊張しましたけど面白かったです。
東区プラザの屋上駐車場に出たら、いい感じの空が広がっていました。

2019年07月06日
「手段」としての学びから「機会」としての学びへ
「挑戦」という言葉に対する違和感。
それは前からあったのだけど。
かつて僕は、
「地域に挑戦の連鎖を」とかって言っていたんだけどね。
「地域」「挑戦」というキーワードに
20代がヒットしなくなっているという現実も肌で感じる。
「ありえたかもしれない、もうひとつの近代」(19.4.18)
http://hero.niiblo.jp/e489179.html

スピノザ「エチカ」の解説をする
国分功一郎さんの言葉。
「思考のOSを入れ替える。」
近代社会で培われてきた思考。
それは一言でいえば、「目的・目標は何か?」
「どうやってそれを最短距離・時間で達成するか?」
という思考だった。
それはおそらく、国民国家というシステムと工業社会の宿命だったのだろう。
それを支えたのがデカルト的哲学だったと國分先生は解説する。
だとしたら、
工業社会から次の社会へとシフトしている中で、
国民国家という仕組みそのものがグローバル企業の登場などによって
揺らいでいる中で、
「思考のOSを入れ替える」必要があるのではないか。
西洋的近代とは、
二元論であり、わかりやすさであり、目標逆算型システムであり、、、
しかし、スピノザは、
本質は自分自身がらしくあろうとする力「コナトゥス」のことであり、
「自由であるとは能動的であることであり、能動的であることはとは自らが原因であるような行為を作り出すことであり、そのような行為とは自らの力が表現されている行為を言います。ですから、どうすれば自らの力がうまく表現される行為をつくり出せるのかが、自由であるために一番大切なことになります。」(100分de名著 スピノザ「エチカ」より)
もうひとつブログ読み直し
「やりたいことは何か?」「何になりたいのか?」への違和感(18.8.20)
http://hero.niiblo.jp/e487965.html
「やりたいことは何か?」「何になりたいのか?」この二つはまさに「意志」と「未来」を問う質問なのではないか。
あたりまえだけど、「言葉」と「世界」は相互に作用している。「言葉」が「世界」を規定し、「世界」が「言葉」を規定している。
だから、「やりたいことは何か?」と問われれば、「やりたいことは何だろう?」と考え、それに答えようとしてしまう。
でもさ、そもそも、「意志」や「未来」が存在しないとしたら。能動態と受動態の対立の世界に生きていなかったとしたら。
~~~ここまでブログから引用
もし、「意志」も「未来」も存在しないとしたら。
そんな仮定。
アホらしいと思うだろうか。
僕はそこにこそ、「挑戦」という言葉への違和感の原因がある、と思っている。
(戦争に強かった)国民国家と(世界を貨幣経済という色に染めてしまった)工業社会は、「学校」という効率的な人材育成システムを生み出した。それによって、「いま」は将来という目的のための手段となった。たぶん、その思想の転換が必要だったのだろう。
そして、「意志」という概念も合わせて導入された。
目的・目標を決めて、「挑戦」する個人が素晴らしい、とされた。
いま、ぼくたちの生活は、「手段」にあふれている。
いや、「手段」にあふれてなければならない、とさえ思っているのではないか。
〇〇のために勉強する。
〇〇のために資格を取る。
インスタ映えする写真を撮るためにタピオカミルクティーを買う。(ちょっと違うか)
「学校」は、その特質上、「手段」しか提供できない。
教育目標があり、それを達成することがそもそもの設置の意義だからだ。
この前の「意味」と「意義」の話じゃないけど、
「意義」と「意味」
http://hero.niiblo.jp/e489514.html (19.7.2)
で言えば、「意義」だらけの空間だ。
僕は2005年に玉川大学の通信教育課程に編入し、中学社会の教員免許取得を目指した。
2007年に新潟県内の中学校に教育実習に2週間いった。
僕のポジションは学校ではないんじゃないか。
って思った。
2011年、僕は本屋になった。
地下に古本コーナーHAKKUTSUを作り、暗やみで本を探せるようにした。
ハックツのコンセプトは「偶然」であり、ツルハシブックスのコンセプトは「劇場」である。
一言でいえば、「機会」提供である。
ハックツは数々のメディアに掲載されたが、そのたびに答えられなかった質問がある。
「本をハックツした子どもたちに、どうなってほしいですか?」
どうなってほしくもない。
僕の役割は本を提供した時点で、すでに終わっているのだ。
ただ、機会を提供することには価値がある、と僕は思っているのだ。
いま。
2019年現在。
「手段」としての学びから「機会」としての学びへのシフトが起こっている、
と僕は思っている。
2020年の大学入試改革を含む
文部科学省「高大接続システム改革」で説明されている、学力の3要素は
①知識・技能の確実な習得(狭義の学力)
②(①を基に)思考力、判断力、表現力
③主体性を持ち、多様な人々と協働し学修する態度(主体性、多様性、協働性)
であり、それらは、「探究」学習によって可能になると言っている。
では「探究」はどのように駆動するのだろうか?
「機会」提供からこそ始まるのではないか。
人は「機会」を目前にして、心が反応する。
「共感」や「違和感」、様々な感情が起こる。
特にその「違和感」こそが、「探究」の出発点になるのではないか。
では、だれが機会を提供するのだろうか。
それは学校外の機関、多くの場合つまり地域(民間企業・NPOなどを含む)
だろうと思う。
「機会」の提供。
それによってどう心が動いたのか?動かなかったのか?
そういう意味で言えば、
「目標達成」も「機会」のひとつだ。
大切なのは、達成したかしなかったか、ではなくて、
達成しようとしているあいだに心がどのように動いたか。
どんな「違和感」を感じたのか。
その「機会」をつかみ、自分なりに仮説を立てることから
「探究」が始まっていくのだろうと思う。
ひとたび「探究」が始まってしまえば、あとは自走していく。
内発的動機付けによって駆動していく。
なんらかの成果、結果が出る。
それを外から見ている人は「挑戦」だと思う。
でも、本人は挑戦なんてしていない。
機会から得た違和感を好奇心から探究したかったのだ。
「挑戦しろ」という人は、
意志という神話を信じているかのように見える。
「意志なんて存在しない。」
僕はスピノザの考え方を支持する。
「挑戦」しなくていい。
厳しい言い方をすれば、「意志」の弱さのせいにするな。
「環境」を抜け出し、「機会」をつかみ、「違和感」をキャッチする。
そこから湧き上がる好奇心を大切に、「探究」を始めよう。
そこにこそ、本当の「遊び」が待っている。
それは前からあったのだけど。
かつて僕は、
「地域に挑戦の連鎖を」とかって言っていたんだけどね。
「地域」「挑戦」というキーワードに
20代がヒットしなくなっているという現実も肌で感じる。
「ありえたかもしれない、もうひとつの近代」(19.4.18)
http://hero.niiblo.jp/e489179.html

スピノザ「エチカ」の解説をする
国分功一郎さんの言葉。
「思考のOSを入れ替える。」
近代社会で培われてきた思考。
それは一言でいえば、「目的・目標は何か?」
「どうやってそれを最短距離・時間で達成するか?」
という思考だった。
それはおそらく、国民国家というシステムと工業社会の宿命だったのだろう。
それを支えたのがデカルト的哲学だったと國分先生は解説する。
だとしたら、
工業社会から次の社会へとシフトしている中で、
国民国家という仕組みそのものがグローバル企業の登場などによって
揺らいでいる中で、
「思考のOSを入れ替える」必要があるのではないか。
西洋的近代とは、
二元論であり、わかりやすさであり、目標逆算型システムであり、、、
しかし、スピノザは、
本質は自分自身がらしくあろうとする力「コナトゥス」のことであり、
「自由であるとは能動的であることであり、能動的であることはとは自らが原因であるような行為を作り出すことであり、そのような行為とは自らの力が表現されている行為を言います。ですから、どうすれば自らの力がうまく表現される行為をつくり出せるのかが、自由であるために一番大切なことになります。」(100分de名著 スピノザ「エチカ」より)
もうひとつブログ読み直し
「やりたいことは何か?」「何になりたいのか?」への違和感(18.8.20)
http://hero.niiblo.jp/e487965.html
「やりたいことは何か?」「何になりたいのか?」この二つはまさに「意志」と「未来」を問う質問なのではないか。
あたりまえだけど、「言葉」と「世界」は相互に作用している。「言葉」が「世界」を規定し、「世界」が「言葉」を規定している。
だから、「やりたいことは何か?」と問われれば、「やりたいことは何だろう?」と考え、それに答えようとしてしまう。
でもさ、そもそも、「意志」や「未来」が存在しないとしたら。能動態と受動態の対立の世界に生きていなかったとしたら。
~~~ここまでブログから引用
もし、「意志」も「未来」も存在しないとしたら。
そんな仮定。
アホらしいと思うだろうか。
僕はそこにこそ、「挑戦」という言葉への違和感の原因がある、と思っている。
(戦争に強かった)国民国家と(世界を貨幣経済という色に染めてしまった)工業社会は、「学校」という効率的な人材育成システムを生み出した。それによって、「いま」は将来という目的のための手段となった。たぶん、その思想の転換が必要だったのだろう。
そして、「意志」という概念も合わせて導入された。
目的・目標を決めて、「挑戦」する個人が素晴らしい、とされた。
いま、ぼくたちの生活は、「手段」にあふれている。
いや、「手段」にあふれてなければならない、とさえ思っているのではないか。
〇〇のために勉強する。
〇〇のために資格を取る。
インスタ映えする写真を撮るためにタピオカミルクティーを買う。(ちょっと違うか)
「学校」は、その特質上、「手段」しか提供できない。
教育目標があり、それを達成することがそもそもの設置の意義だからだ。
この前の「意味」と「意義」の話じゃないけど、
「意義」と「意味」
http://hero.niiblo.jp/e489514.html (19.7.2)
で言えば、「意義」だらけの空間だ。
僕は2005年に玉川大学の通信教育課程に編入し、中学社会の教員免許取得を目指した。
2007年に新潟県内の中学校に教育実習に2週間いった。
僕のポジションは学校ではないんじゃないか。
って思った。
2011年、僕は本屋になった。
地下に古本コーナーHAKKUTSUを作り、暗やみで本を探せるようにした。
ハックツのコンセプトは「偶然」であり、ツルハシブックスのコンセプトは「劇場」である。
一言でいえば、「機会」提供である。
ハックツは数々のメディアに掲載されたが、そのたびに答えられなかった質問がある。
「本をハックツした子どもたちに、どうなってほしいですか?」
どうなってほしくもない。
僕の役割は本を提供した時点で、すでに終わっているのだ。
ただ、機会を提供することには価値がある、と僕は思っているのだ。
いま。
2019年現在。
「手段」としての学びから「機会」としての学びへのシフトが起こっている、
と僕は思っている。
2020年の大学入試改革を含む
文部科学省「高大接続システム改革」で説明されている、学力の3要素は
①知識・技能の確実な習得(狭義の学力)
②(①を基に)思考力、判断力、表現力
③主体性を持ち、多様な人々と協働し学修する態度(主体性、多様性、協働性)
であり、それらは、「探究」学習によって可能になると言っている。
では「探究」はどのように駆動するのだろうか?
「機会」提供からこそ始まるのではないか。
人は「機会」を目前にして、心が反応する。
「共感」や「違和感」、様々な感情が起こる。
特にその「違和感」こそが、「探究」の出発点になるのではないか。
では、だれが機会を提供するのだろうか。
それは学校外の機関、多くの場合つまり地域(民間企業・NPOなどを含む)
だろうと思う。
「機会」の提供。
それによってどう心が動いたのか?動かなかったのか?
そういう意味で言えば、
「目標達成」も「機会」のひとつだ。
大切なのは、達成したかしなかったか、ではなくて、
達成しようとしているあいだに心がどのように動いたか。
どんな「違和感」を感じたのか。
その「機会」をつかみ、自分なりに仮説を立てることから
「探究」が始まっていくのだろうと思う。
ひとたび「探究」が始まってしまえば、あとは自走していく。
内発的動機付けによって駆動していく。
なんらかの成果、結果が出る。
それを外から見ている人は「挑戦」だと思う。
でも、本人は挑戦なんてしていない。
機会から得た違和感を好奇心から探究したかったのだ。
「挑戦しろ」という人は、
意志という神話を信じているかのように見える。
「意志なんて存在しない。」
僕はスピノザの考え方を支持する。
「挑戦」しなくていい。
厳しい言い方をすれば、「意志」の弱さのせいにするな。
「環境」を抜け出し、「機会」をつかみ、「違和感」をキャッチする。
そこから湧き上がる好奇心を大切に、「探究」を始めよう。
そこにこそ、本当の「遊び」が待っている。
2019年07月04日
貨幣経済が「質」を「量」に還元した

「仕事なんか生きがいにするな」(泉谷閑示 幻冬舎新書)
今日がラストです。
エッセンスに詰まりすぎて、ほかの本も読んでみたくなりました。
エーリッヒ・フロム「自由からの逃走」から、はじまります。
~~~ここから本文より引用
「・・・からの自由」と「・・・への自由」か。
エーリッヒ・フロム「自由からの逃走」
「自由」という名の牢獄から抜け出そうとして、ふたたび服従を求めるという構図。
個人が解放される以前にあった地縁血縁などの「第一次的絆」を断ち切っていく個性化のプロセスの中で、孤独や不安、そして自らの無力感やのしかかってくる責任の重さなど、様々な困難に直面することになります。
個別化した人間を世界に結びつけるのに、ただ一つ有効な解決方法がある。すなわちすべての人間との積極的な連帯と愛情や仕事という自発的な行為である。それらは第一次的絆とは違って、人間を自由な独立した個人として、再び世界に結びつける。
しかし、個性化の過程をおし進めていく経済的、社会的、政治的諸条件が、いま述べたような意味での個性の実現を妨げるならば、一方ではひとびとにかつて安定を与えてくれた絆はすでに失われているから、このズレは自由をたえがたい重荷に変える。
そうなると自由は疑獄そのものとなり、意味と方向とを失った生活となる。こうして、たとえ自由を失っても、このような自由から逃れ、不安から救いだしてくれる人間や外界に服従し、それらと関係を結ぼうとする、強力な傾向が生まれてくる。
ちょうど肉体的に母親の胎内に二度と帰ることができないのと同じように、子どもは精神的にも個性化の過程を逆行することはできない。もし、あえてそうしようとすれば、それはどうしても服従の性格をおびることになる。
子どもは意識的には安定と満足を感ずるかもわからないが、無意識的には、自分の払っている対価が自分自身の強さと統一性の放棄であることを知っている。
~~~ここまで引用
「たとえ自由を失っても、このような自由から逃れ、不安から救いだしてくれる人間や外界に服従し、それらと関係を結ぼうとする、強力な傾向が生まれてくる。」
フロムはまさにそれがナチスを支持する人々を生んだのだと言う。その「人間」や「外界」が、今は、新興宗教だったり、他者評価だったり、カリスマやリーダーシップだったりするのだろうな。
じゃあ、どうすればいいのか?
フロムはそれが「自発的な活動」だと言い、それは「小児」や「芸術家」のことだと著者は説明する。
~~~ここから引用
自発的な活動がなぜ自由の問題にたいする答えになるのだろうか。自発的な活動は、人間が自我の統一を犠牲にすることなしに、孤独の恐怖を克服する一つの道である。というのは、ひとは自我の自発的な実現において、かれ自身を新しく外界にー人間、自然、自分自身にー結びつけるから。
愛はこのような自発性を構成するもっとも大切なものである。しかしその愛とは、自我を相手のうちに解消するものでもなく、相手を所有してしまうことでもなく、相手を自発的に肯定し、個人的自我の確保のうえに立って、個人を他者と結びつけるような愛である。
まず第一にわれわれは、自然で自発的であったひとたちを知っている。かれらの思考、感情、行為は、かれら自身の表現であり、自動人形のそれではない。これあらのひとびとは多くは芸術家としてわれわれに知られている。事実、芸術家は自分自身を自発的に表現することができる個人と定義することができる
小さな子どもたちは自発性のもうひとつの例である。かれらは本当に自分のものを感じ、考える能力を持っている。(中略)子どもの魅力がなんであるか問うならば、私はまさにこの自発性にちがいないと思う。この自発性は、それを感知する力を失うほどには死んでいないひとびとに、深く訴えていく。じっさい、子どもにせよ芸術家にせよ、あるいはこのような年齢や職業で分類することができないひとびとにせよ、かれらの自発性ほど、魅惑的説得的なものはない。
「芸術とは、邪なるものに曇らされた世俗に向かって決然と対峙して、そこで忘れ去られてしまった自然の本性、すなわち「美」を力強く表現するものです。真の芸術家の在り方というものは、子供の持つ純粋さや創造性を保ちつつ、そこに力強く成熟したものを兼ね備えた、ただならぬ「小児」と呼ぶべきものなのです。
しかし、これは芸術家に限った話ではありません。芸術とは人間であるために「不可欠なもの」であって、決して「剰余として」身にまとうような贅沢品ではないのです。
「真の藝術家は、藝術の条件のもとで人生をわれわれを見せてくれるのではあって、人生の形式の中で藝術を見せるのではない。(オスカーワイルド)
~~~ここまで引用
かつて、宮沢賢治先生が言っていた、
誰人もみな芸術家たる感受をなせ
個性の優れる方面に於て各々止むなき表現をなせ
然もめいめいそのときどきの芸術家である
(「農民芸術概論綱要」より)
まさにこれこそが「自由」への道だと説明するのです。
ここは僕としてはとても熱くなりました。
そして、ここからが、今日の一番のポイントです。
まずは「愛」の話から。
~~~ここから引用
「愛」とは、単に他の人に向かうものだけを指すのではなく、世界の様々な物事や人生そのものに向けられるもので、対象に潜む本質を深く知ろうとしたり、深く味わおうとしたりするものです。このように好奇心に満ちた、無邪気な子供のような性質。それが「愛」というものの大切な側面なのです。
「愛」が働く時、私たちは対象を深く見つめ、耳を澄まし、そこに潜む本質を感じ取ろうとします。これによって物事に秘められた真実が、見つめる者、耳を澄ますものに、静かに開示されてきます。その時、私たちに、あたかも対象と一体になったかのような至福の経験がもたらされます。「愛」の喜びとは、そのような経験です。
われわれ人間の「頭」は、そもそもは渾然一体となっている自他を、「観察する者」と「観察される対象」とに分ける働きがあります。そうして、本来は一元的である世界を自と他に分別して、二元論的世界に変えてしまいます。もちろん、この「頭」の働きがあったおかげで、私たちは対象を認識したり、思考したりできるようになって、それを意のままに操作することさえ可能になったわけです。
しかし私たちは、これによって世界との一体感を失ってしまったのです。つまり、世界を自分から切り離したつもりで、私たちがむしろ世界から切り離されてしまったのだと言えるでしょう。「自分」という言葉の中の「分」という文字は、私たち人間が、そういう悲劇的な宿命を負っていることを静かに教えてくれているかのように思われます。
このように世界から切り離された私たちが、しかし、もう一度世界と一体であることを思い起こすことができる経験。再び一元的な世界に立ち戻ることができる経験。それを「愛」の経験と呼ぶのです。
~~~ここまで引用
なるほど。
頭と心の二元論的分割は必然だったのだなあと。
世界から自分を切り離したつもりで、むしろ世界から自分が切り離されてしまった。
これですね。
なんとなくの不安の招待。
さらに、「日常」を「遊び」に変えよ、と続きます。
~~~ここから引用
何でもないように見える「日常」こそが私たちが「生きる意味」を感じるための重要な鍵を握っているのです。
「日常」を死んだ時間として過ごしてしまうと、その退屈で苦痛な時間を耐え忍ぶために感性を硬直化させることになってしまい、ある時にたとえ素晴らしい非日常的経験を得たとしても、もはやそこに十分な喜びを感じ取ることさえできなくなってしまうでしょう。
しかしそもそも、私たちがこんな風に「日常/非日常」を区別していること自体が問題なのかもしれません。私たちは「日常」という言葉に、ついつい「ルーチンでつまらない時間」というニュアンスを込めてしまいがちなのですから。
そこでまずは、この色あせたニュアンスをまとった「日常」というものをいかに非日常化して、区別なく味わい深いものにできるか。つまり、人生の時間を丸ごと「遊ぶ」ことができるかが、問われてくるのです。
ニーチェは人間の最も成熟した在り方を「小児」という象徴で語りました。この「小児」とは「創造という遊戯」に満ちた存在です。創造こそが最高の遊戯であり、「遊ぶ」とはすなわち創造的であることです。物事を深く「味わう」ためには、その物事に向かって「小児」のように創造的に「遊ぶ」ことが大切なのです。
~~~ここまで引用
そして、このあと、この本の中で一番衝撃を受けた、ロバート・ヘンライの言葉がつづきます。
「芸術家は人生についての考え方を世界に教えている。金だけが大事だと信じている人は自分を欺いている。芸術家が教えているのは、小さな子供が無心で遊ぶように、人生も熱中して遊ぶべきだということである。ただし、それは成熟した遊びである。人の頭脳を駆使した遊びである。それが芸術であり、革新である。」(ロバート・ヘンライ「アートスピリット」)
いいですね。
熱いですね。
高校生や大学生が「地域」で「探究」をやる本当の意味はここにあるのではないでしょうか。
大学の入試改革があったから、ではなく、
それが新しい学力観だから、でもなく、
ただただ「人生を熱中して遊ぶべきだ」というメッセージを伝えるためなのではないかと。
熱くなりました。
締めは、頭と心、量と質の二元論の説明。
僕はこういうのが好きです。
~~~ここから引用
「心=身体」が感じ取った感覚を「頭」がありのままに受け取って、それをもとに様々な好奇心を発動させたり、抽象化や概念化を行って、そこから普遍的真理を抽出したりすること。これが「意味」が析出してくれるプロセスです。ともすれば「心=身体」を抑え込み支配的に振る舞いがちな「頭」なのですが、このように協働的な「頭」の用い方ができた時、そこに至福の喜びが訪れます。古代ギリシア人が「観照生活」を最も人間らしい過ごし方と考えたのは、そのためでもありました。
このように「頭」と「心」が対立せずに、互いが相乗的に喜び合っている状態。これを、私たちは「遊び」と呼ぶのです。誰しも幼い子供時代には、自然に「遊び」に夢中になっていたはずなのですが、それがどうして、こんなにも縁遠いものになってしまったのでしょう。
物事の「質」を「量」に還元してしまう貨幣経済というものが、私たちの世界を動かす支配的な価値観になってしまったことが挙げられるでしょう。お金というツールはそもそも、物々交換の不便さを解消するものとして登場し、あらゆるものを「量」に還元して交換、つまり取引を可能にしました。「質」の異なる様々なものをすべて「量」に置き換えてしまうということは、本来は暫定的・便宜的なことであって、そこに無理があるのは当然です。
しかし、いつの間にか、経済原理が世の中を動かす中心的な力を持つようになってしまい、人々は「質」の大切さを犠牲にしてまでも経済価値を追い求めるようになってしまいました。その結果、様々な物事に対しても、プロセスよりも結果のほうを重視するような考え方が、広く世の中に蔓延するようになったのです。
さらにこの「量」的に傾斜した価値観は物事に最大限の効率を求めるようになり、ロジカルな戦略を立てて物事に取り組むスタイルを生み出しました。明確な目標設定、その実現可能性やリスクはどの程度で、勝算はどの程度見込めるのか、それに投入するコストはどこまで最小限にできるのか等々、人間の「頭」の算術的なシュミレーション機能を過大に評価した考え方が、子供の勉強から大人のビジネスまで、果ては「ライフプランニング」という言葉も登場するほどに、人生のあらゆる局面までも支配するようになってしまったのです。
この一見合理的に思える方法論には、致命的な欠陥があります。「質」は「量」に還元できないという基本的な問題を抱えてるのみならず、「頭」の行うシュミレーションは単純な算術レベルに留まるものであって、人間や社会さらには人生や運命といった「複雑系」にはまったく歯が立たないものなのです。
このような効率主義を含む合目的的な思考は、ビジネスのみならず、現代人の思考全般にすっかり浸透していて、私たちはどんな小さな選択であっても「それは何の役に立つのか?」「それは損なのか得なのか?」「コストパフォーマンスはどうなのか?」「メリットやデメリットはどうなっている?」「どんなリスクがどの程度の確率で起こり得るのか?」といったことを考える癖がついてしまいました。そして、「結局」「所詮」「面倒くさい」といった言葉が乱発されるようになり、「どうせ同じ結果が得られるのなら余計なことや無駄なことはしないのが賢明だ」と考えるようになってしまった。
~~~ここまで引用
貨幣経済が「質」の異なるものを貨幣価値という一元化したものに還元してしまった。そしてそれが究極的に進んだのが現代という時代であると僕も思います。「量」や「結果」で測るなら、最小限の努力で最大の価値を生み出したほうがいい、そのように思うのは当然です。
本当にそれで幸せになれるのでしょうか?
つづけます。
~~~
ところが、そもそも「遊び」というのは「無駄」の上にこそ成り立つのであって、その「結果」はあくまで二次的に過ぎないもので、「プロセス」のところにこそ面白味があるものです。
「頭」の計画性や合理性を回避するためには、その対極にある「即興」という概念を積極的に用いてみることがとても有効な方法です。
あえて無計画、無目的に、自分の行動を即興に委ねてみることによって、私たちの決まりきった日常が、ささやかながらもエキサイティングな発見と創意工夫に満ちたものに変貌するわけです。おれを私は「偶然に身を開く」と呼んでいます。
「即興性」に加えてもうひとつ大切なこととして「面倒くさい」と感じることを、むしろ積極的に歓迎してみるという考え方があります。
~~~
「即興」。
ここで出てくるんですか。
ツルハシブックス「劇団員」のコンセプトが。
読書って楽しいなあと思います。
キーワードだらけだな、と。
「頭=脳」と「心=身体」
あまりにも頭にシフトしすぎたんだなと。
キャリア的に言えば、未来が予測不可能になって、
「目標達成」から「機会提供」へと教育がシフトしているんだなと。
「目標達成」にとって、「機会」はノイズに過ぎなく、
「即興」は説明不可能であるから、排除すべきなのだろうと。
でも、人生を遊ぶためには、創造的でなければならないのだから、
そこには「機会」を得て「即興」してみることは必須だよね。
たぶん、ぼくが伝えたいのも、そういうこと。
2019年07月03日
人生も熱中して遊ぶべきだ

「地域みらい留学」フェスタ 東京会場に行ってきました。
すごい熱気。
「地域みらい留学」とは、
都道府県の枠を越えて、地域の学校に入学し、充実した高校3年間をおくること。
公式ウェブより
https://c-mirai.jp/about.html
ということで、東京会場(渋谷)にも、
北海道から沖縄までのたくさんの高校が
カリキュラムの特徴や寮制度、公営塾の魅力などを
説明するイベントでした。
僕がいちばん印象に残っているのは、
広島県立大崎海星高校。

手作り感あふれるブースで、
高校生がたくさんいて、とにかく活気がありました。

ポストの着ぐるみ?を着ていた高校生は
「みりょくゆうびんきょく」というサークル的な活動の生徒たち。
その一環で東京にPRに来ているということでした。
楽しそうだったので、
きっと、説明をきいた中学生は「一度、見学いってみようかな」と
思った人も多かったのではないでしょうか。
大崎海星は、デザインもすごくて、
総合学習も
1年:羅針盤学=自分を知る
2年:潮目学=社会を知る
3年:航界学=マイプロジェクト
みたいな。
「時代の航界士になろう」っていいコンセプトだなあと。
ということで、イベントメモを以下に。
~~~ここからメモ
オリエンテーション
「どこで」「誰と」「何を」学ぶか?
「どこで」:地域という実社会で学ぶ。手触りのある実物未来社会の箱庭で学ぶ
「誰と」:多様な人々と学ぶ。地域の子ども、都会からきた子ども、外国から来た子ども、地域で挑戦する人、都会から来た大人と学ぶ
「何を」:社会の縮図体験としての3年間を過ごす。自ら見つけたテーマに対し、自ら動き、失敗し、支援から学ぶ
未来の社会をつくる意志ある若者を育む「地域みらい留学」
津和野高校の取り組み
新しい進路実現
・探究や実践の場が溢れている。
・問題意識の醸成や学問分野への接続が容易にできる。
・個別化したサポートができる環境である。
多様な人による多様な寄りそいのカタチがある。
「私の島は・・・」と語るばあちゃんの衝撃。
いろんな人に会えるっていうか、かかわる大人の数と種類が多いっていうか、当事者に会えるんだね、地方では。思いを持った大人、本気な大人に。もちろん、東京にもいるんだろうけど、出会えないんすよ、高校生っていう同質性集団の中では。
なりたい職業じゃなくて、どうありたいか?
→人によりそう暮らし、働き方がしたい
→鍼灸の専門学校へ。
細川さんは、ネットで「公立高校 寮」で検索して地域みらい留学にたどり着いているんだよね。
だとしたらトガッたコンセプトでウェブつくるって大事だな、と。
「どこの高校がいいのか?」
から
「どんな高校生活をしたいのか?」
っていう問いへ。
いろんな考えの人、特にタイプの違う人に話を聞けるかどうか。
⇒同質性集団から抜け出せるかどうか?
白馬高校のプレゼン。
こんな人におすすめ
・白馬でやりたいことがある
・多様な価値基準を受け入れられる
・人と協働することが好き
・新しいことにチャレンジできる
反対に、3つの誤解
1 白馬にいけば変われる⇒本人が変わらないと
2 個人の希望を優先できる⇒全日制の公立高校
3 平日でもスキーやスノボいける⇒いけない
メッセージ
1 何を学びたいのか?
2 広く学ぶ覚悟はありますか?
3 白馬で生活する覚悟はありますか?
少人数であるから多様な人に出会い、話をすることができる。地方こそ多様。
高校は生徒に正解を提示してあげることはできない。
「経験」という機会を提供することしかできない。
「職員室」は「センセイオフィス」へ。
隠岐島前高校のプレゼンもシンプルでよかった。
主体的に課題を見つけ、他者と協働して、解決まで粘りづよく取り組むこと。
それができるなら、どこの高校でも同じ。
気づく→考える→話し合う→実践する・巻き込む→ふりかえる。
「困った」って言ってくるまで助けない。
何もしゃべらないチームがあってもすぐに助けない。
困ったときに困ったと言えること。
答えのない課題は現場にあふれている。現場が近いという価値。
「正解」を探す力はネットやAIに敵わない。
「問い」を立てる力を育むこと。
どうしたら解決できるんだろう
何が本当の原因なんだろう
誰が困っているんだろう
私たちにできることは何だろう
10は1000よりはるかに小さいが、10分の1は1000分の1よりはるかに大きい。
1番の学びは寮生活の中にある。暮らしの中っていうことか。
挑戦のカタチは何通りあってもいい。
ひたすら寮で靴を揃えていくという挑戦もある。
「社会課題を解決する!」よりも、
(具体的な)誰かの課題を(当事者として)解決する!
ってことが大事だ。
ダイヤモンドはダイヤモンドでしか磨けないように人は出逢う人によって磨かれる。
高校時代に地域の高校へ進学することが新しい選択肢になる。
日本の課題に触れること。多様な人につながること。
地域がまるごと教育資源になる。
プロジェクトにとって大切なのは、真正性、つまりリアルであるということ。
地方にはリアルが詰まっている。
県外生徒がもたらしたもの。
低意欲の生徒襲来→意欲格差→挑戦格差
そこからじわじわとよくなっていく。
自地域肯定感が自己肯定感につながっていく。
誇りが必要なんだよね。生きていくには。
県外生徒募集をきっかけに教育の魅力化について大人自らが探求すること。
「高校魅力化」それこそが社会インパクトを生み出すと信じて覚悟を決めた人たちの集まりだった。
覚悟のようなものが必要。結局、誰がやるんだ?っていう。
高校存続プロジェクトから高校魅力化プロジェクトへ。
存続を目指しても存続しない。魅力がないと行かない。
高校魅力化って問いなんだと。自らが探求し続けないといけない。
キーコンセプトを決めること。
大崎海星の航界人、みたいな。
それをこういう地域の素材を使って学ぶことができます、と紹介すること。
魅力は地域の中にすでにある。
それを引き出していくプロセスにも魅力が生まれる。
キーコンセプトを人々との多様なプロセスによってつくっていく。
そして常にキーコンセプトを刷新し続けること。
課題は地域の現場にあるがソリューションは世界中にある。
都会では学べないことがウチの地域では学べます。
一緒に探求しよう、と言える人がどれだけいるか?
地域みらい留学を新しいキャリア教育の営みにしていく。
偏差値じゃない価値、自分軸で決める価値で自分の枠と地域の枠を超えていく。
地域の子どもにも外を見せることができる。
他者、つまり多様な大人と、多様なプロジェクトを行うことの意義。
プロジェクトの中で、一緒に活動した誰かが「オマエには才能がある」って言う瞬間をつくること。テクニックではなく、リアルで。
その一瞬で、生きていくモチベーションは数倍になる。そしてそれは早ければ早いほど効果が高い。
隠岐島前高校の豊田さんのプレゼン。
プロジェクトをデザインする際に重要な要素
・Authenticity(真正性、信頼性)
つまり、リアルであること。
超人口減少、超少子高齢化、財政難
日本の重要課題の最前線
しかも「人、物、金がない」
ここでの挑戦が日本の未来を切り開く。
「教育魅力化を阻む免疫のようなもの」
・学校教育を考える際の「地域文脈」へのアレルギー
→「教育文脈」と「地域文脈の2項対立構造
・新しい学びのあり方(新学力観)へのアレルギー
→「従来の教育観」から「新しい教育観」への転換
・多忙化へのアレルギー
→「業務改革・働き方改革」と「教育改革」は車の両輪
・異文化、異質なものを受け入れることへのアレルギー
→自分たちを肯定してくれない人たち、よくわからない人たち
自分たちにとっての学校や地域にとってのいい教育を
関係者の中で対話しながら探究・実践しつづけること。
・県外生徒募集に高校が関わるのは大変
※その先に何があるのかはあとの話
・教員が疲弊するのではないか
・自校は特徴がないのではないか
・外に開いたところでやる価値はあるのだろうか
〇多様性がもたらすもの
・新しい価値観との出会い
→最初は戸惑地
・自身や自地域のよさの言語化
→自己肯定感、自地域肯定感
・視点、視座が増える
自分とは違った環境で育った友人がいる
隠岐島前高校63%
島根県内 41%
島根県外 28%
~~~ここまでメモ
とまあ、こんな感じ。
結論的には「地域みらい留学」には
・特徴的なカリキュラム
・寮の支援体制
・公営塾の充実
の3つが必要なのだなと。
高知県の嶺北高校や広島県の大崎海星高校のように
初年度から生徒を集まられる高校があるということ。
キーコンセプトを明確にして
そこに向かって上記の3つを組み立てていくこと。
そういうことが必要なのだと実感した。
そしてもうひとつ、
いいタイミングで手にしていた本。

「仕事なんか生きがいにするな~生きる意味を再び考える」
(泉谷閑示 幻冬舎新書)
この本の終盤を読んだら、
なぜ、僕がここにいるのか、少しわかった気がした。
詳しくはまた別のブログに書くこととして、
今日は一番ヒットした一節を書き出す。
「芸術家は人生についての考え方を世界に教えている。金だけが大事だと信じている人は自分を欺いている。芸術家が教えているのは、小さな子供が無心で遊ぶように、人生も熱中して遊ぶべきだということである。ただし、それは成熟した遊びである。人の頭脳を駆使した遊びである。それが芸術であり、革新である。」(ロバート・ヘンライ)
たぶん。
高校魅力化とか、
地域と協働とか
マイプロジェクトとかって
結局ここに集約されていくのではないかな。
「人生も熱中して遊ぶべきだ」
伝えたいメッセージってそういうことなのだと思う。
最高の遊びとしての学びを、高校時代に経験しておくこと。
それって、めちゃめちゃ大きいと、僕は思うんですよ。
2019年07月02日
「意義」と「意味」

「仕事なんか生きがいにするな」(泉谷閑示 幻冬舎新書)
「生きづらさ」というモンスターの正体がまたひとつ、
わかりました。
それは「意義」というモンスターです。
まずは、夏目漱石先生とニーチェ先生から学ぶ、「本当の自分」探しについて。
~~~ここからメモ
「本当の自分」「自分探し」問題をどうするか。
「自分探し」への批判は
1 「労働教」による「自分探しなんて甘えだ、働け」という道徳的な説
2 そもそも「本当の自分」を知ることはできないから考えても無駄という合理的な説
両方とも、当事者本人を救うことができない。
生まれ育ってくる中で避け難く曇らされてしまい、「頭」でっかちで神経症にならざるを得ないわれわれの感覚や認識というものを、「心」を中心に回復させることができた時、人は「本当の自分」になったという内的感覚を抱きます。これは、生まれ直したかのような新鮮さと歓びに満ちたものであり、「第二の誕生」とも呼ばれます。
夏目漱石は「私の個人主義」(1914年@学習院大学の講演録)で、「ああここにおれの進むべき道があった!ようやく掘り当てた!こういう感投詞を心の底から叫び出される時、あなたがたははじめて心を安んずることができるのでしょう。」と語った。
このように「本当の自分」になる経験が起こると、必ずや一定期間の後に、「自分」への執着が消えるという新たな段階に入っていきます。
それが漱石の言う「則天去私」か。天に則り私を去る。自分という一人称への執着が消えた「超越的0人称」の境地を表している。
ニーチェはそれを、「駱駝」(未熟な0人称)→「獅子」(1人称)→「小児」(超越的0人称)という三様の変化と比喩的に述べている。
ただし、誤解してはならないのは、この駱駝として象徴されている「未熟な0人称」というものは、決して未成年のような未熟な状態を指しているわけではなく、むしろ私たちが「一人前の社会人」と呼んでいるような社会適応的な状態のことだという点です。
~~~ここまでメモ
「自分とは何か」という問いの後に、それを掘り当てると、自分への執着が消えていくという。
ニーチェの定義に従うならば、私たちはほとんどが「駱駝」(未熟な0人称)の段階にあるなと。
「何者でもない」という状態から、一瞬、何者かになって、そしてまた超越的0人称という自分への執着を超えた存在になるのだ。
そして、今日の本題、「意義」と「意味」の話に突入していきます。
~~~ここから引用とメモ
「意義」という思想が私たちを苦しめているのではないか。うつ状態に陥った人たちが、療養せざるを得なくなり、「有意義」な過ごし方ができなくなってしまうと、自らを「価値のない存在」として責めてしまう。
私たち現代人は「いつでも有意義に過ごすべきだ」と思い込んでいる、一種の「有意義病」にかかっているようなところがあります。
「意義」とは、何かの役に立つ、など、「価値」を生みことにつながるもの。
「意味」とは「意義」のような「価値」の有無を必ずしも問うものでありません。
しかも、他人にそれがどう思われるかに関係なく、本人さえそこに「意味」を感じられたのなら「意味がある」ということになる。つまり、ひたすら主観的で感覚的な満足によって決まるのが「意味」なのです。
現代では「価値」というものが「お金になる」「知識が増える」「スキルが身につく」「次の仕事への英気を養う」等々、何かの役に立つことに極端に傾斜してしまっているので、「意義」という言葉もそういう類の「価値」を生むことにつながるものを指すニュアンスになっているのです。
「意味」というものは、「意義」のような「価値」の有無を必ずしも問うものではありません。しかも、他人にそれがどう思われるかに関係なく、本人さえそこに「意味」を感じられたのなら「意味がある」ということになる。つまりひたすら主観的で感覚的な満足によって決まるのが「意味」なのです。
「意義」とは、われわれの「頭」の損得勘定に関係しているものなのですが、他方の「意味」とは、「心=身体」による感覚や感情の喜びによって捉えられるものであり、そこには「味わう」というニュアンスが込められています。
このように整理してみますと、「意義」と「意味」とは、かなり異なった概念であることがはっきりしてきます。
しかし、現代人が「生きる意味」を問う時には、ともすればつい、この「意味」と「意義」を混同してしまって、結局「生きる意義」や「価値」を問うてしまっていることが少なくないのです。そしてこれが、問題を余計難しくしてしまっているのです。
生産マシーンのごとく、常に「価値」を生むことを求められてきた私たちは、「有意義」という呪縛の中でもがき続けていて、大切な「意味」を感じるような生き方を想像する余裕すらない状態に陥ってしまっているのです。
まだ私たちが幼かった頃、一日がとても長く感じられ、未知な世界に向かって好奇心を向け、自由な空想にひたり制約のない夢を育んでいた頃、生きることは「意味」に満ち溢れていました。
当然のことながら、子供の世界から「意味」などすっかり消え去ってしまい、生きる喜びとは無関係な「意義」だけが、彼らの中に空しく積み上げられていくようになってしまったのです。
~~~ここまで引用とメモ
生きづらさの正体、見つけた。
「意義」は何か?
その行為の「目的」は?
と聞いてくる家族、学校、社会だ。
「意義」に満たされた生活は、一見充実しているように見えるが、余裕がなく、つまらない。
だからこそ、「にいがたイナカレッジ」には1か月という時間の投資が必要なのだ。
1か月の暮らしと余裕の中で「意味」を問いかける。
「価値」というものが、本来は他者評価を前提としていないことを知る。
自分たち自身(だけ)が感じられる価値。
それを追いかけていくこと。
それはまるで、子どもが自然の中で遊ぶように、夢中になること。
その前提として、自らの存在承認を得ること。
ここにいていいんだ。
若いだけで自分は価値があるんだ。
という感情から出発すること。
たぶん、そういうことのために、
1か月が必要なのだなあと改めて思いました。
まだ、夏の予定が決まっていない人は新潟という選択肢もあります。
https://inacollege.jp/




