2022年04月12日
「探究」はゲームなのだろうか

「人生はゲームなのだろうか?」(平尾昌宏 ちくまプリマー新書)
蔦屋書店新潟万代店にて購入しました。
あそこはシェアラウンジとかできていてすごいです。
ビール飲み放題1時間1320円とかしながらミーティングしたいです。
ということで。
今年のキーワードのうち熱いのは「ゲーミフィケーション」なのですけど。
http://hero.niiblo.jp/e492335.html
(ゲームにはゲームを 22.3.5)
前回のポイントは、こちら
1 アンロック(解錠)
「アンロック」はかけられた鍵を一つずつ解錠していく」という意味だ。
アンロックが用いられると、最初にプレーヤーができることはほぼ一つしかない。「スーパーマリオブラザーズ」であればジャンプしかできない。だがしばらくプレイしていると「レベルアップしました」と言われ(アイテムを取り)、たとえば火を使うことができるようになる。さらにプレイを進めると空を飛べるようになったりする。
2 レベルデザイン
「レベルデザイン」はプレイヤーの自発性を損なわずに、ゲームの難易度を高めていく。そのため、「アンロック」よりもさらに高度な手法だと位置づけることもできるだろう。
「マリオなら、ひとつのネタがあったら必ずそれを覚える場所、実際遊ぶ場所、応用する場所、極める場所がある」(任天堂・宮本茂)
この重要な2つの前に、
哲学者平尾さんが送る、「そもそもゲームとは何か?」っていう話。
まだ途中なんですけど(パートⅡまで読み終わり)
ゲームの定義は(参加者にとって共通の)
1 ゴール(目的)がある
2 ルール(制限)がある
ということです。そうしたら掃除も戦争もゲームじゃないか、みたいな話の中で出てきたのが
3 プレイヤーが自発的に参加する
そこで「ボランティア」と「仕事」の違いとか「遊び」と「仕事」の違いとか
そんな話に展開していって、
「すること自体が目的」=「遊び」=目的内在型
「することによって何か目的が達成できる」=「仕事」=目的外在型
みたいな話に展開していき、掃除や受験や戦争は個人の捉え方にもよるけど、基本はゲームじゃないよねみたいな話になっていきます。
たぶんこれ、ゲーミフィケーションの前段の部分の話ですね。
ゲーム世代(しかもソーシャル・ゲーム世代)の高校生たちと授業やプロジェクトを通じて対話していくとしたら、「ゲーム」で説明した方がよさそうです。この本だってゲームを題材にした「哲学対話」の形式となってます。
探究の授業も、授業や課外活動で高校生が取り組むプロジェクトも、「ゲーム化」していくことが必要なのではないかと。いや、それって大人たちの仕事もそうなんですけどね。
1 ゴール(目的)があって 2 ルール(制限)がある
さらに 3 自発的に参加しているプロジェクトの中で、
4 アンロック と 5 レベルデザイン をデザインしていくこと。
そんな探究の活動だったらもっと面白くなるのではないかなあと思ってます。
2022年04月09日
「越境」を繰り返し「縁」に出会う

「手づくりのアジール-土着の知が生まれるところ」(青木真兵 晶文社)
対話2 これからの「働く」を考える
まで来ました。
青木さんと百木さんの「働く」についての対談。
ハンナ・アーレントとカール・マルクスを題材にして、
資本主義のカタチについて考察をしていきます。
昨日のブログ
http://hero.niiblo.jp/e492378.html
には、就活の違和感、そのものが表現されていました。
12月には違う人の文章で、同じようなことを考えていました。
http://hero.niiblo.jp/e492232.html
(「ニーズに応える」と「人生を経営する」のあいだ 21.12.29)
今日はアーレントの「労働」と「仕事」、そして「活動」の概念から。
アーレントによると
「労働」とは自分や家族の生命・生活を維持するための私的な営みで「仕事」とは自分を超えたパブリックな「世界」と創り出す営みとされています。
働き方の点で言えば
「労働」は生命維持の必然性=必要性のために強制的に行わなくてはならないもので「仕事」は目的-手段がはっきりした合理的な生産行為であり、そこには理性や創造性を発揮する余地があるとされています。
このような意味で、アーレントは「労働」に西條の価値を置き、生産性の向上という目標に国民を統合していく「全体主義」を批判しているのです。
一方でマルクスは、「ドイツ・イデオロギー」の中で、「共産主義社会では、各人は専属の活動範囲を持たず、自分が望むどの部門でも自分を鍛えることができるし、社会が万人の生産を管理している。まさにそのおかげで、私は好きなように今日はこれを、明日はあれを行い、朝に狩りをし、午後に漁をし、夕方に家畜の世話をし、食後には批評する。しかしだからと言って、狩人、漁師、牧人、批評家になることはない。あるいはなる必要はない」と語ります。
アーレントが古代ギリシャやローマをモデルとして、西欧思想の伝統を遡ったのに対してマルクスは現在を乗り越えた未来=彼岸に向かうことによって別のシステムへ移行し、みんなが自由に生きられる社会を作ろうと考えていた。
そんな中で、ふたりは、もうひとつの道「網野善彦」について語る。
~~~
網野は、国家や社会の枠組みから溢れる、周辺に現れるもの、「無縁」を公と見ているんですね。現代で無縁というとネガティブな印象ですが、中世日本では、世間や社会のしがらみから逃れることというポジティブな意味合いがあった。
「男はつらいよ」の寅さんの実家「とらや」も、アジールに近い部分がある。まず何と言っても、葛飾・柴又は東京の端っこ、辺境の地にあるということ。そしてとらやが店を構えるのは帝釈天の参道、つまり宗教エリアであるということ。
寅さんは資本主義社会から完全にはじかれた存在でありながら、なぜか楽しそうです。いろいろ悩みはあったと思うのですが、とらやと日本各地の参道を「行ったり来たり」することで上機嫌に暮らすことができた。ああいう人物が主人公の作品が長きにわたりポピュラティを得続けているのは、日本人の中に「二つの原理を行き来するもの」への情景があるからではないかと思うんです。
網野の言う無縁の場=「公界」にはさまざまな怪しげな人びとが集います。漂泊者、商人、行者、芸能人、遊女・・・。各地域から集まった物が交換されたり、芸能が披露されたりするのですが、そこにはお寺や神社が密接に関係している。網野はこうした場が日本的な資本主義の起源としてあるのではないか、辺境的な怪しげなものから貨幣市場が広がったのではないか、というんですよね。
一か所に定住せず、移動を繰り返しながら経済活動を行い、技能(芸能)を獲得しながら多様な人びとともかかわりあっていく。宗教的な領域にも世俗的な物語にも触れるような寅さんの物語が今でも人気があるということには、どこか希望を感じます。
~~~
そっかー。
日本にはかつて、「もうひとつの資本主義」があったし、二つの原理を行き来するものへのあこがれがあったんだなあと。
これさ、いまの10代、20代にとっても重要なのではないか。
だから大学生は在学中に地方でインターンし、20代は3年限定で「地域おこし協力隊」となり、中学生は「地域みらい留学」を志向するのではないか。
それは、彼らなりの「越境」つまり「二つの原理の行き来」なのではないか。
そして、今日思ったのは、そこにこそ「縁」があるのだと。「縁:えにし、えん、ふち」は、境界に存在するのだということ。
「縁」を知るために、活かすために、「越境」が必要なんだ、と。
そういう意味でも、ここ、新潟県東蒲原郡阿賀町津川という場所。
かつて、会津藩の河港として栄えた場所。



新潟県の東の端。会津の文化と新潟の文化が混ざり合う場所。
そんな境界のまちだからこそ、できることがあるんだろうな、と。
ここにはきっと「縁」がある。
そんな体感を、みんな必要としているのではないかなあと。
2022年04月08日
「労働的価値」と「存在の承認」

「手づくりのアジール-土着の知が生まれるところ」(青木真兵 晶文社)
読み進めています。
今日は「就活の違和感」に直結する箇所があったので、
メモにいれておきます。
~~~P72より抜粋
現代社会では働く=対価としてお金をもらう労働とされ、自らを、労働力を提供する商品として売りに出すことが「働く」ことだと考えられています。そう考えると就職活動は自分を労働力へと変換していく作業に他ならず、社会に出る、社会人になるとは、労働力、商品として市場に出ていくことを指すことになる。商品は売れなければ意味がありませんから、経済とは自分が売れる商品かどうかを評価される場になります。これはやっぱりしんどいですよ。「働いていない」という状況=自分は売れ残り商品だと思うのはつらすぎます。
一方ぼくは「働く」=「労働」とか「社会」=「市場」とは考えていません。人間には労働力としての側面もありますが、商品化されない感性の部分もある。商品化の波に飲み込まれないようにどうやって自分を守っていくかが楽しく生きていくための大きなポイントだと感じます。僕にとって「働く」とは、他者や社会に働きかけることです。社会は私たちが働きかけることによって成り立っているのであり、お金を生み出す労働だけで成り立っているわけではない。
~~~
就活の違和感の正体のひとつがこれかなと。
「自らを商品化すること」
つまり、労働力としての自分を価値づけようとするあまりに、自分を失ってしまうことへの恐怖。こういうのを直感的に感じてしまっているのではないかと。
言い換えれば「商品としての価値」を「自分の存在価値」とイコールにしてしまうことで、自ら「存在の承認」を失いにいっているのではないかという不安。それが、就活に対する不安そのものなのではないかと僕は思います。
「そんな甘いことを言ってたら就職できない。」
もちろんそうでしょう。それにはそれ相応のリスクがあります。
じゃあ、どうするのか?
僕は遠回りかもしれないけど、青木さんの言う後段の「他者や社会に働きかける」という「働く」を実感することなのではないかと思っています。それも、高校生のうちに。
総合的な探究の時間やプロジェクト学習がキャリア形成に意味があるとすれば、そこだろうなと思ってます。
社会は、お金を生み出す労働だけで成り立っているのではない。
労働力としての価値=あなた個人の価値ではない。
感性を発揮して、他者や社会に働きかけ、何かを創造していくこと。そこにこそ「まなび」があると僕は思うし、最大の課題である(と僕が思う)「存在の承認」問題をクリアしていくカギがあると思っています。
阿賀黎明高校「地域学」から始まった津川商店街の空き店舗改装プロジェクト
「自分たちの居場所は自分たちで創る」は、高校生たちが巻き込まれながら作っていく創造の物語です。
https://camp-fire.jp/projects/view/552815
僕にとっては、大学生の「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」という悩みから出発した「存在の承認」問題への有効なアプローチ方法だと思っています。
あと9日、みなさまの応援よろしくお願いします。
2022年04月07日
「ともにつくる」はじまりの日
今日から新学期。そして、入学式。
首都圏や中京圏からも新入生を迎え、
14名になった寮で、新たなスタート。
僕からのメッセージはひとつだけ。
「ともに寮を創造しよう。」
「ともにつくる」
これが全体を貫くコンセプトだと僕は思っています。
寮生活も、学校の授業も、課外活動も、日々の対話も。
ハウスマスターやスタッフ、温泉や風舟のお客さんとも。
「ともにつくる」をベースに、コミュニケーションをしていきたいと思ってます。
「フラットな関係をつくるコミュニケーションのデザインが得意」
これは3年前に、とある募集要項に書かれていた
「あなたの得意なことはなんですか?」
という問いを前にしてスッと出てきた言葉です。
茨城に3年いて、岡倉天心と「現代美術家」というキーワードにたどり着きました。
デザインの目的は課題を解決することでアートの目的は問いを投げかけること
そっか。どちらかというとアートをやりたいな、と。
アートと、デザインと、ビジネスのあいだにある曖昧なものを生み出していきたいと今も思っています。
キーワードは「創造」。
創造の前で人はフラットになる。
意義軸の「役に立つ」「立たない」が無効化される。
ひとりひとりが創造のタネになる。
それはつまり創造する「場」の一員となるということ。
僕はそれが、ツルハシブックス時代から、その前のヒーローズファーム時代、もっと前の中越地震のボランティアの時からの課題である「個人のアイデンティティ」をどう捉え、どうアプローチしていくか?のひとつの方法になると思っています。
現在、阿賀黎明高校「地域学」から始まった「自分たちの居場所は自分たちでつくる」のクラウドファンディングが進行中です。
https://camp-fire.jp/projects/view/552815
高校生たちは、やればやるほどモチベーションが上がり、仲間を巻き込み、春休み中も活動していました。
残り10日、目標の半分まで来ました。
みなさまの思いのこもったご支援をいただきたく、お願いいたします。





大人も子どもも「ともにつくる」阿賀黎明高校、そして阿賀町を、応援よろしくお願いいたします。
首都圏や中京圏からも新入生を迎え、
14名になった寮で、新たなスタート。
僕からのメッセージはひとつだけ。
「ともに寮を創造しよう。」
「ともにつくる」
これが全体を貫くコンセプトだと僕は思っています。
寮生活も、学校の授業も、課外活動も、日々の対話も。
ハウスマスターやスタッフ、温泉や風舟のお客さんとも。
「ともにつくる」をベースに、コミュニケーションをしていきたいと思ってます。
「フラットな関係をつくるコミュニケーションのデザインが得意」
これは3年前に、とある募集要項に書かれていた
「あなたの得意なことはなんですか?」
という問いを前にしてスッと出てきた言葉です。
茨城に3年いて、岡倉天心と「現代美術家」というキーワードにたどり着きました。
デザインの目的は課題を解決することでアートの目的は問いを投げかけること
そっか。どちらかというとアートをやりたいな、と。
アートと、デザインと、ビジネスのあいだにある曖昧なものを生み出していきたいと今も思っています。
キーワードは「創造」。
創造の前で人はフラットになる。
意義軸の「役に立つ」「立たない」が無効化される。
ひとりひとりが創造のタネになる。
それはつまり創造する「場」の一員となるということ。
僕はそれが、ツルハシブックス時代から、その前のヒーローズファーム時代、もっと前の中越地震のボランティアの時からの課題である「個人のアイデンティティ」をどう捉え、どうアプローチしていくか?のひとつの方法になると思っています。
現在、阿賀黎明高校「地域学」から始まった「自分たちの居場所は自分たちでつくる」のクラウドファンディングが進行中です。
https://camp-fire.jp/projects/view/552815
高校生たちは、やればやるほどモチベーションが上がり、仲間を巻き込み、春休み中も活動していました。
残り10日、目標の半分まで来ました。
みなさまの思いのこもったご支援をいただきたく、お願いいたします。





大人も子どもも「ともにつくる」阿賀黎明高校、そして阿賀町を、応援よろしくお願いいたします。
2022年04月06日
2つの原理を行き来できる「自由」

「手づくりのアジール-土着の知が生まれるところ」(青木真兵 晶文社)
読み始めました。
「風舟」がどんな場所なのか?なぜ阿賀町なのか?なぜ寮なのか、温泉なのか?
みたいな問いに対してもヒントをもらえる1冊。
まずプロローグに書いてある「アジール」の説明から。
~~~プロローグより
アジールとは、古来より世界各地に存在した「時の権力が通用しない場」のことです。あらゆるものが数値化され、その序列に従って資金配分がなされる現代社会を此岸とし、「そうでない原理が働く場」として彼岸と位置づけたときに、アジールは「自宅を開いて図書館を運営する活動」それ自体がアジールを手づくりすることを意味しているのではないかと思い、本書のタイトルとしました。
~~~
そして第1章「闘う」ために逃げるのだから、考えさせられる一節を。
~~~ここから引用・まとめ
民俗学の父、柳田圀男は、「都市と農村」の中で、生産側の農村が消費側の都市に優越している点を
1 勤労を快楽にできること
2 考えて消費をすればなんとか生きていけること
3 土地からの恩恵を幸福と結びつけることができること
ここで重要なのは柳田が生きた明治から昭和前期には都市と農村という二つの原理がリアリティを持って存在したという事実です。
「二つの原理」については、イヴァン・イリイチも述べていて、もともと人類は生と死、男と女、右と左、敵と味方、都市と農村、文化と自然、秩序と混沌のように「二つの原理」のなかを聞きてきて、それらは「両義的な対照的補完性をなすもの」だったのです。つまり二つの原理は互いに補完し合っていて、どちらが欠けても世界は成り立たなくなってしまう。それが近代になり産業社会が成立する過程で、原理が一つになっていったのだと、彼は問題視しています。
~~~
そして、その世界を成立するために不可欠だったのが二つの世界をつなぐ回路としての「異人」と言いました。
本書では、これを「男はつらいよ」シリーズの寅さんを題材に説明しています。
~~~
高度経済成長期を経た一億総中流化とは、社会の原理が統一されていく過程でした。社会の総中流化、標準化は、社会の内部が「水臭い」資本主義的原理によって構築されていく過程です。そこから逃げ出し、「コスト度外視な」世界に触れることで、寅さんは生きる力を取り戻すことができた。
寅さんが「おいちゃん、それをいっちゃあおしまいだよ」と発するとき、彼は「おじさん、そんなドライなことを言ってしまうと、コモンズであるはずの家庭や故郷が社会にシステムに侵されてしまうよ」と警鐘を鳴らしているのです。
近代と前近代、文明と自然、秩序と無秩序といった二つの原理が補完性をなくし、対立的になってしまっていることが原因です。
~~~
最後に「アジール」について
~~~
網野善彦によると、前近代社会は地縁・血縁が社会の基礎にあったため、アジールは無縁の場でした。だが現代のアジールはどうでしょうか。資本主義の発展により、人々は地縁・血縁を切って個人となり、自由を得てきました。つまり「無縁」の状態を自由だと感じてきたのです。この場合の「自由」は「商品を買うこと」によって得ることができます。しかし資本主義が過度に発展した結果、経済格差が出てきました。つまり「商品を買えない」人たちが出てきたのです。
社会の外部と縁を結び直すことが必要だと思っています。それができる場を、「現代のアジール」と呼びたい。ではどうすれば、外部との回路を取り戻すことができるのでしょうか。
~~~
ヘンリー・D・ソロー「森の生活」にヒントがあると、青木さんは言います。
~~~
なぜソローが独立を果たすことができたのか。それは社会を捨て、自給自足の生活を送ったからではありません。社会の外部の原理に触れる経験をしたことで、彼が社会の内部と外部を行ったり来たりできる確信を得たからです。
相反する二つを対立させ、その対立を乗り越え、一つに統一していくことが近代的な問題解決の仕方でした。しかし社会が経済発展する段階において、都市と農村という二つの原理のうち、都市の原理だけが強くなりすぎてしまった。ソローは湖畔の森で生活することや国民の義務であった税を支払わないことによって、そもそも人間社会に存在した二つの原理を取り戻そうとしたのです。
~~~
数値化を前提として資本主義的・都市的原理に対抗できる別の原理の力を高めておかないと、なにより心が苦しくなってしまうし、自然環境も保護することができず、社会全体を存続することができません。
個人ではどうしようもできないときに必要となるのが、「場所」です。ある空間に身を置くことで、意識的に取り入れることができない情報を、身体が無意識にインストールしてくれます。そのような意味で、資本主義原理に負けない、外部と触れる経験ができる場所が必要なのです。現代社会において「異人」が生きていけるような、アジールとも呼べる、数値化不能な場所をつくりたい。
世の中に存在しないものがほしいとき。その方法は「手づくり」しかありません。むしろ「手づくり」すると、必然的にまだ形をなしていない「未分化」なものになるはずです。まず、その第一歩は逃げること。「闘う」ために逃げるのだ
~~~
いやあ、すごいキーワードだらけでしたね。シビれます。
緑泉寮に来る子たちは、もしかしたらそれを直感しているのかもしれない。
「手づくりのアジール」を必要としている。
社会も、そして自分自身も。
2つの原理があること。
今、見えている世界が唯一の世界ではないこと。
そして2つの世界は行き来できるということ。
その体感を必要としている。
だから、緑泉寮は、学校から4㎞離れている高台にあって、温泉があり、本屋があるのです。
そこは「外部」とつながる場所であり「異人」たちが集う場所。
「学校社会」や「企業社会」といった数値化される資本主義原理だけではない
数値化されない他者からの贈与や自然からの恵みがある世界が存在するのだということ。
まずはその世界を知り、場所を通じてそこにアクセスしてみること。
そして、いつのまにかそれを行き来できるようになること。
「自由」とは、そういうことなのではないかなと僕は思います。
2022年04月05日
個人と、組織と、チームと、、、
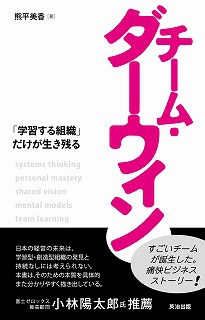
チーム・ダーウィン――「学習する組織」だけが生き残る(熊谷美香 英治出版)
2008年の本。
久しぶりに古本屋で買いまして、ビビっときて読んでみました。
「学習する組織」が小説風に書かれていて、それがまたリアルで。
ホントにこんな会社がありそうで。
石油ストーブなどを売っている老舗企業の新規プロジェクト立ち上げの話。
沖縄の離島での合宿の話がドキドキしました。
エッセンスもたくさん。
「チューニング・ファシリテーション」とか「ミライカイギ」とかの源流を見たような。
合宿のコンテンツは以下のとおり。
1 個人の未来像・・・私たちは、この会社で何をしたいのか
2 会社の未来像・・・会社は、何をしたいのか
3 チームの未来像(具体案)・・・チームは、何をしたいのか
4 今後の実行案(具体案)・・・これから何をすべきなのか?
5 プロジェクトリーダーを選ぶ、プロジェクト名を決める
なるほど。
まずはお互いがお互いを知ること:チューニングと個人と会社の未来像を描くこと。
チューニングしながら、過去を探ること。
過去を探ることで価値観を表現すること。
その先に顧客を発見すること。
これは僕風に言えばミライ会議なのだけど
http://hero.niiblo.jp/e492190.html
目的地を決めないこと、地図とコンパスを持たないこと(21.11.25)
たぶんこの繰り返しなのだろうなあと。
この本に書いてある東郷さんのようなスポンサー:「人」「モノ」「金」「情報」を集め、環境をつくる人にオッサンたちはなっていかないといけないのだろうなあと。プロジェクトの推進役ではなく、プロジェクトの進捗を管理するポジションへと徐々に移行していくことが必要なのか、と。
個人の未来のために、組織があり、
組織の未来のために、個人がある。
そしてそのあいだをつなぐのがチームだ。
様々な階層のチームがあり、そのそれぞれが機能していく。
そんな組織をつくっていくことが2022年からの宿題になっていくのだろう。
この本にあった、パーソナルマスタリーをもう一度自分に問うことにする。
「お前はどこからきて、今どこにいて、これからどこへ行くのか」
私は、なぜこの仕事に取り組むのか?
私は、この仕事で何を達成したいのか?
私は、この仕事を通じて何を得る(学ぶ)のか?
私は、次に何をしたいのか?
~~~
私の動機(モチベーション)の源泉は何か?
私は、自分らしさを活かし、世の中あるいは、周囲に対して、どのような貢献がしたいのか?
私の追い求める夢(ビジョン)は何か?
「ともにつくる」の実践。
創造に向かう瞬間に人と人はフラットになり、創造を味わったときに喜びを感じる。
地域の環境、地域の大人、高校生、スタッフの間のコミュニケーションのデザイン。
「ともにつくる」構造を多くのまなびと暮らしと仕事の場に。
~~~
新しいものを創造した瞬間
人と人をつなぐコミュニケーションデザイン
「手段として学ぶ」から機会として学ぶ」へのシフト
現時点で思いつくままに書いてみましたが、考え続けようと思います。
ひとつだけ直感しているのは、「創造」を志向する場において人はフラットになる。「強み」と「弱み」という一定基準で判断された指標が無効化し、そこにある「存在」として「創造」に貢献しようとする。
その時に、その人の「存在」は承認される。
「効率化」という思想によってコミュニティが弱体化し、コミュニティ(地域、家族、会社)からの存在承認が得られにくい社会を僕たちは生きている。
しかし「存在の承認」がベースになければ、人は生きられないのだ。じゃあどうするか?
一つの仮説は、「創造」に向かうこと。
「創造」の前で、人は場の一部になる。
そして「創造」した主体にもなる。
それがこれからの時代の「存在の承認」の手法なのではないか、と僕は直感しています。
2022年04月03日
作品名:委ねる
4月1日から本屋さんに復帰しました。
https://kazafune.fun/
阿賀町京ノ瀬、津川温泉・清川高原保養センターとなりの
ログハウスを改修し、コワーキングスペースとライブラリー+カフェの
複合施設「風舟(kazafune)」が誕生しました。
2018年から活動している「かえるライブラリー」も併設して、
みんなでつくる本屋の実験をふたたび始めようと思います。
20代は新潟市西蒲区(旧巻町)でまきどき村という畑プロジェクトを
30代は新潟市西区・内野駅前でツルハシブックスという本屋をやってきましたが。
40代は温泉+高校生の寮+本屋コワーキングをつくっていくことになります。
3年間やってきた「高校魅力化」という文脈には、引き続き側方から関わっていきたいと思っています。
3年を簡単に振り返ると
1年目は初心者として先進地(校)をひたすらめぐり、高校魅力化の「魅力」とは何か?を探究した1年でした。公営塾でかき氷を出したり、くるみやむかごを拾って、商品化したりしました。しかし、「魅力」化の本丸は、学力向上でも地域プロジェクトでもなくて「授業の魅力化」であると結論しました。大学進学希望の生徒だけではなく、すべての生徒が「まなび」を楽しめるような仕組みづくりをしたいと思いました。そして同時に、県外からの生徒募集の必要性を感じていました。
2年目のスタート直前に「コミュニティスクール」指定の話が舞い込み、「チャンス到来」と、学校運営協議会での決定を実践する地域団体設立に向けて動きました。新型コロナウイルスの直撃を受けながらも4月に団体を発足し、活動を模索してきました。「地域学」や「総合的な探究の時間」への参加・参画も少しずつ始まってきました。また、令和3年度の寮設置が決まり、「地域みらい留学」のプラットフォームで募集活動を開始しました。
3年目は寮運営の初年度であり、地域の方の授業への参画・参加が深まった1年でした。2年次のプロジェクト実践の場が設けられ、一連の流れで探究の授業が行われるようになりました。中学校へのアプローチも拡大し、総合学習の時間や職場体験などに公営塾スタッフが参画していく体制が徐々に出来上がっていった1年でした。
あらためて僕にとって高校魅力化が魅力的なプロジェクトだったのは、それが「マーケティング」であり、「組織(コミュニケーション)デザイン」であり、なおかつ「教育」だったから、なのではないかなとあらためて思います。
及川さんと取り組んだ「地域みらい留学」のオンライン化1年目の広報は、マーケティングそのものでした。他校と比較して、自分のところは何が強みなのか?誰がお客なのか?お客にとっての価値は何か?そのお客に対してどのようにメッセージを届けるか?有名校に負けないものがあるとしたらそれは何か?
そんなマーケティング的な問いの中で、
・温泉で地元の人とコミュニケーションできる
・まだ出来上がっていないからこれから一緒につくろう
というメッセージをメインに組み立てました。
高校、中学、教育委員会、地域の方、、、多くのステークホルダーをどう連携・コミュニケーションさせていくか?これも大きな問いになりました。会議の冒頭で毎回やる自己紹介で「チューニング」を図りました。「地域学」では地域の方を各プロジェクト担当に配置し、生徒とのコミュニケーションを迷いながらも試行錯誤していきました。
そして授業の魅力化。令和4年度に新課程がスタートする中で、探究的な学びとは何か?どのように地域のフィールドを活かしていくのか?授業と課外活動との接続をどうするのか?活動だけして言語化できない問題は、どのように解決するのか?どの程度フレームワークにするのか?主体性と場のチカラをどう伝えるか?
そんな問いがぐるぐるしながら先生と一緒につくっていくような時間でした。
・マーケティング
・組織(コミュニケーション)デザイン
・教育(探究的学び、プロジェクト学習)
この、僕が好きな3要素がすべて入っているのが「高校魅力化」だったのではないかと、今感じています。
そういう意味では、4月に軸足を本屋さんに移しても、同じことをやっていくように思っています。
ひとつだけ、変わるとしたら、風舟を軸足に置くことで、ふたたびリアルメディアづくりが始まる、ということです。
20代を賭けた「まきどき村」での畑を通じたコミュニケーションでの問いは「豊かさ」でした。それは大学生の時に初めて農作業をしてきた時の感動と、環境や農業のことを考える中で磨かれた「豊かさと何か?」という根源的な問いとの交差点にあったように思います。
30代を賭けた「ツルハシブックス」での本を通じたコミュニケーションでのテーマは「偶然」でした。それは目標達成型に固執している大学生のキャリア観を揺さぶったり、商店街での対話だったり、本や本屋を通じた人との出会いだったり、そんな「偶然」が生まれる場を作りたかった。
そして40代の今。風舟に軸足を置いて、つくっていきたい作品は「委ねる」なのかなあと感じています。
https://kazafune.fun/conversation/
対談ページにもありますが、豊かな自然があり、温泉があり、本があり、高校生もいる。
ここは「委ねられる」場なのかなあと。
マーケティングであり、組織デザインでもあり、教育でもある。
作品テーマは「委ねる」。
現代の美術家のリアルメディアづくりの現場に、あなたも委ねてみませんか?
https://kazafune.fun/
阿賀町京ノ瀬、津川温泉・清川高原保養センターとなりの
ログハウスを改修し、コワーキングスペースとライブラリー+カフェの
複合施設「風舟(kazafune)」が誕生しました。
2018年から活動している「かえるライブラリー」も併設して、
みんなでつくる本屋の実験をふたたび始めようと思います。
20代は新潟市西蒲区(旧巻町)でまきどき村という畑プロジェクトを
30代は新潟市西区・内野駅前でツルハシブックスという本屋をやってきましたが。
40代は温泉+高校生の寮+本屋コワーキングをつくっていくことになります。
3年間やってきた「高校魅力化」という文脈には、引き続き側方から関わっていきたいと思っています。
3年を簡単に振り返ると
1年目は初心者として先進地(校)をひたすらめぐり、高校魅力化の「魅力」とは何か?を探究した1年でした。公営塾でかき氷を出したり、くるみやむかごを拾って、商品化したりしました。しかし、「魅力」化の本丸は、学力向上でも地域プロジェクトでもなくて「授業の魅力化」であると結論しました。大学進学希望の生徒だけではなく、すべての生徒が「まなび」を楽しめるような仕組みづくりをしたいと思いました。そして同時に、県外からの生徒募集の必要性を感じていました。
2年目のスタート直前に「コミュニティスクール」指定の話が舞い込み、「チャンス到来」と、学校運営協議会での決定を実践する地域団体設立に向けて動きました。新型コロナウイルスの直撃を受けながらも4月に団体を発足し、活動を模索してきました。「地域学」や「総合的な探究の時間」への参加・参画も少しずつ始まってきました。また、令和3年度の寮設置が決まり、「地域みらい留学」のプラットフォームで募集活動を開始しました。
3年目は寮運営の初年度であり、地域の方の授業への参画・参加が深まった1年でした。2年次のプロジェクト実践の場が設けられ、一連の流れで探究の授業が行われるようになりました。中学校へのアプローチも拡大し、総合学習の時間や職場体験などに公営塾スタッフが参画していく体制が徐々に出来上がっていった1年でした。
あらためて僕にとって高校魅力化が魅力的なプロジェクトだったのは、それが「マーケティング」であり、「組織(コミュニケーション)デザイン」であり、なおかつ「教育」だったから、なのではないかなとあらためて思います。
及川さんと取り組んだ「地域みらい留学」のオンライン化1年目の広報は、マーケティングそのものでした。他校と比較して、自分のところは何が強みなのか?誰がお客なのか?お客にとっての価値は何か?そのお客に対してどのようにメッセージを届けるか?有名校に負けないものがあるとしたらそれは何か?
そんなマーケティング的な問いの中で、
・温泉で地元の人とコミュニケーションできる
・まだ出来上がっていないからこれから一緒につくろう
というメッセージをメインに組み立てました。
高校、中学、教育委員会、地域の方、、、多くのステークホルダーをどう連携・コミュニケーションさせていくか?これも大きな問いになりました。会議の冒頭で毎回やる自己紹介で「チューニング」を図りました。「地域学」では地域の方を各プロジェクト担当に配置し、生徒とのコミュニケーションを迷いながらも試行錯誤していきました。
そして授業の魅力化。令和4年度に新課程がスタートする中で、探究的な学びとは何か?どのように地域のフィールドを活かしていくのか?授業と課外活動との接続をどうするのか?活動だけして言語化できない問題は、どのように解決するのか?どの程度フレームワークにするのか?主体性と場のチカラをどう伝えるか?
そんな問いがぐるぐるしながら先生と一緒につくっていくような時間でした。
・マーケティング
・組織(コミュニケーション)デザイン
・教育(探究的学び、プロジェクト学習)
この、僕が好きな3要素がすべて入っているのが「高校魅力化」だったのではないかと、今感じています。
そういう意味では、4月に軸足を本屋さんに移しても、同じことをやっていくように思っています。
ひとつだけ、変わるとしたら、風舟を軸足に置くことで、ふたたびリアルメディアづくりが始まる、ということです。
20代を賭けた「まきどき村」での畑を通じたコミュニケーションでの問いは「豊かさ」でした。それは大学生の時に初めて農作業をしてきた時の感動と、環境や農業のことを考える中で磨かれた「豊かさと何か?」という根源的な問いとの交差点にあったように思います。
30代を賭けた「ツルハシブックス」での本を通じたコミュニケーションでのテーマは「偶然」でした。それは目標達成型に固執している大学生のキャリア観を揺さぶったり、商店街での対話だったり、本や本屋を通じた人との出会いだったり、そんな「偶然」が生まれる場を作りたかった。
そして40代の今。風舟に軸足を置いて、つくっていきたい作品は「委ねる」なのかなあと感じています。
https://kazafune.fun/conversation/
対談ページにもありますが、豊かな自然があり、温泉があり、本があり、高校生もいる。
ここは「委ねられる」場なのかなあと。
マーケティングであり、組織デザインでもあり、教育でもある。
作品テーマは「委ねる」。
現代の美術家のリアルメディアづくりの現場に、あなたも委ねてみませんか?




