2019年04月21日
「理由」はまだ、ない。
茨城県日立市・
株式会社えぽっくの「旅する冊子」プロジェクト
https://a-port.asahi.com/projects/tabisuru_sassi/
作戦会議という名の
参加学生の振り返りをやっていました。
1週間の合宿をしながら4つの企業の取材をした
取材型インターン「チームひきだし」。

写真は北茨城市・まるみつ旅館にて。
ひきだしの特徴は、
・毎日企業を取材してワークショップをしながら紹介記事を作成する。
・あらかじめ取材する企業が決まっておらず、企業を知らないまま学生はエントリーする。
学生の参加動機もさまざま。
「いろんな企業を知りたい」っていう前向きな理由(?)から
「インターンって行ったことないな、そういえば」
っていうちょっと気軽な理由。
「1週間で完結するインターン」
っていう時間ない系の理由。
「1週間実家から離れて暮らせる」
とか自由なのか不純なのかわからない理由。
うんうん。
これ、おもしろいな。
マーケティングに使える。
実家から1週間はなれて暮らす!みたいな。
1週間で完結するインターンシップ!みたいな。
逆にインターンシップを、
「ボランティア」するくらいゆるくしちゃうっていうか、
入口のハードルを下げるいう効果もありますね。
で、おもしろかったのが、やってみてどうだったか?の話。
ビフォアアフターで言えば、アフターは
・行って初めてわかることが大きかった。
・企業が直前まで知らされないのがおもしろい。
・楽しかった。自分が思っていたインターンシップと違った。
・マナー講座とかも学べてよかった。
・社長インタビューは最終面接みたいなもの。
っていうこと。
これ、いわゆる「得られる経験」みたいなところに書いてあるところ。
新たな気づきは、
・気づかないうちに、ホワイトカラー(オフィスワーク)志向になっている自分に気づいた。
・地元企業で就職先があるのか知りたかった。
・企業がわからないからこそ、「どうしてこの企業に?」と聞かれない安心感がある。
・スピード感と熱意と経験
・言葉にして伝えるのはむずかしい
僕が着目したのは、ここ。
企業がわからないからこそ、「どうしてこの企業に?」と聞かれない安心感がある。
それかも!
それ、大きいかも、って思った。
「どこの企業に行くのかわかりませんが、4社の企業の取材をします」
って言われたほうが予測不可能性が高まるし、
一番は、
どうしてこの企業に見学に来たのですか?
って聞かれない。
行動には理由があると、僕たちは教わってきた。
しかし、その理由は、
行動する前には、きちんとわからないのではないか。
「なぜ、その行動をするのか?」
っていう問いに答えられるのは、やってみた後になってから
なのではないか?
就職活動中の大学生も言っていた。
「志望動機」が明確に答えられないと。
「志望動機は?」
「それは入社した後に分かります。いまはまだ分かりません。」
そんな面接ができる会社があったらいいのに。
「理由」はまだ、ない。
でも、事後になって理由はわかるのかもしれない。
人はまだ、自分を知らない。
だから、「やってみる」んだ。
実験してみるんだ。
ひとまずは心のセンサーが
「やってみようかな」をキャッチして、
理由はわからずにやってみるんだ。
そして、後から理由がついていく。
株式会社えぽっくの提供する
「チームひきだし」プロジェクトは、
明確な目的・目標を決めずに、ひとまずはじめてみる、という、
「オルタナティブ就活」そのものな感じがしました。
2019年度も行いたいので、みなさまからの応援よろしくお願いします!
株式会社えぽっくの「旅する冊子」プロジェクト
https://a-port.asahi.com/projects/tabisuru_sassi/
作戦会議という名の
参加学生の振り返りをやっていました。
1週間の合宿をしながら4つの企業の取材をした
取材型インターン「チームひきだし」。

写真は北茨城市・まるみつ旅館にて。
ひきだしの特徴は、
・毎日企業を取材してワークショップをしながら紹介記事を作成する。
・あらかじめ取材する企業が決まっておらず、企業を知らないまま学生はエントリーする。
学生の参加動機もさまざま。
「いろんな企業を知りたい」っていう前向きな理由(?)から
「インターンって行ったことないな、そういえば」
っていうちょっと気軽な理由。
「1週間で完結するインターン」
っていう時間ない系の理由。
「1週間実家から離れて暮らせる」
とか自由なのか不純なのかわからない理由。
うんうん。
これ、おもしろいな。
マーケティングに使える。
実家から1週間はなれて暮らす!みたいな。
1週間で完結するインターンシップ!みたいな。
逆にインターンシップを、
「ボランティア」するくらいゆるくしちゃうっていうか、
入口のハードルを下げるいう効果もありますね。
で、おもしろかったのが、やってみてどうだったか?の話。
ビフォアアフターで言えば、アフターは
・行って初めてわかることが大きかった。
・企業が直前まで知らされないのがおもしろい。
・楽しかった。自分が思っていたインターンシップと違った。
・マナー講座とかも学べてよかった。
・社長インタビューは最終面接みたいなもの。
っていうこと。
これ、いわゆる「得られる経験」みたいなところに書いてあるところ。
新たな気づきは、
・気づかないうちに、ホワイトカラー(オフィスワーク)志向になっている自分に気づいた。
・地元企業で就職先があるのか知りたかった。
・企業がわからないからこそ、「どうしてこの企業に?」と聞かれない安心感がある。
・スピード感と熱意と経験
・言葉にして伝えるのはむずかしい
僕が着目したのは、ここ。
企業がわからないからこそ、「どうしてこの企業に?」と聞かれない安心感がある。
それかも!
それ、大きいかも、って思った。
「どこの企業に行くのかわかりませんが、4社の企業の取材をします」
って言われたほうが予測不可能性が高まるし、
一番は、
どうしてこの企業に見学に来たのですか?
って聞かれない。
行動には理由があると、僕たちは教わってきた。
しかし、その理由は、
行動する前には、きちんとわからないのではないか。
「なぜ、その行動をするのか?」
っていう問いに答えられるのは、やってみた後になってから
なのではないか?
就職活動中の大学生も言っていた。
「志望動機」が明確に答えられないと。
「志望動機は?」
「それは入社した後に分かります。いまはまだ分かりません。」
そんな面接ができる会社があったらいいのに。
「理由」はまだ、ない。
でも、事後になって理由はわかるのかもしれない。
人はまだ、自分を知らない。
だから、「やってみる」んだ。
実験してみるんだ。
ひとまずは心のセンサーが
「やってみようかな」をキャッチして、
理由はわからずにやってみるんだ。
そして、後から理由がついていく。
株式会社えぽっくの提供する
「チームひきだし」プロジェクトは、
明確な目的・目標を決めずに、ひとまずはじめてみる、という、
「オルタナティブ就活」そのものな感じがしました。
2019年度も行いたいので、みなさまからの応援よろしくお願いします!
2019年04月18日
ありえたかもしれない、もうひとつの近代

「NHK100分de名著 スピノザ『エチカ』」
2回目の読了。
読めば読むほどすごい。
そして、冒頭の見出し、
「ありえたかもしれない、もうひとうの近代」
というキャッチコピーが2回目にして、しっくりとくる。
西洋的近代とは、
二元論であり、わかりやすさであり、目標逆算型システムであり、、、
っていうのが
スタンダードで、それが時代にあっていないんじゃないか?
っていう話はたくさん出ているのだけど、
そもそもそのシステムっていうのはどこから始まったんだっけ?
っていうので、
当然、産業革命以来の社会システムの変化を挙げるのだけど。
そのシステムを作り上げた要因として、「デカルト的哲学」があったのだなあと。
その哲学が社会状況と見事に符合して、現在の社会の価値観、哲学、倫理ができていったのだなあと。
~~~ここから本文より引用
私たちがいま国家だと思っている、領域があって主権がある国家という形態は、17世紀半ばになって出てきたものです。
いわゆる近代科学もこの時期に出てくる。たとえばニュートンは17世紀後半に活躍した人です。その科学の支えであった近代哲学も同じ時期に現れました。17世紀は本当に現代というものを決定づけた重要な時代なのです。
私はその意味でこの世紀を、思想的なインフラを整備した時代と呼んでいます。たとえばデカルトは近代哲学の、ホッブスは近代政治思想のインフラを作った人です。そのインフラの上に、続く18世紀の思想が荘厳なアーキテクチャー、つまり建築物を築いていきます。たとえばカントの哲学やルソーの政治思想をそれにあたるものと考えることができるでしょう。
そうすると、17世紀はある意味で転換点であり、ある一つの思想的方向性が選択された時代だったと考えることができます。歴史に「もしも」はありえませんが、別の方向が選択されていた可能性もあったのではないかと考えることはできます。私の考えでは、スピノザはこの可能性を示す哲学なのです。それは「ありえたかもしれない、もうひとつの近代」に他なりません。
~~~ここまで本文より引用
このあと、「真理」についてのデカルトとスピノザの比較があります。
「デカルトの真理観の特徴は、真理を、公的に人を説得するものとして位置づけているところです。真理は公的な精査に耐えうるものでなければならないわけです。私は考えている、考えているならば、その考えている私は存在している。と言われれば反論できない。」
「スピノザの考える真理は他人を説得するようなものではありません。そこでは真理と真理に向き合う人の関係だけが問題になっています。だから、真理が真理自身の規範であると言われるのです。いわば、真理に向き合えば、真理が真理であることは分かるということです。」
これさ、哲学は何のために、誰のためにあるのか?
っていう問いになっているな、と。
デカルトは誰をも説得することができる公的な真理を重んじました。実際はそこで目指されていたのはデカルト本人を説得することであったわけですが。それに対しスピノザの場合は、自分と真理の関係だけが問題にされています。自分がどうやって真理に触れ、どうやってそれを獲得し、どうやってその真理自身から真理性を告げ知らされるか、それを問題にしているのです。だから自分が獲得した真理で人を説得するとか反論を封じるとか、そういうことは全く気にしていないわけです。
「哲学」って生きるとは何か?という究極の問いに対する仮説にすぎないだと僕は思うのだけど、デカルトは、他者を説得するとか納得させるとか、何かのための哲学になっちゃってるんじゃないかと。これこそが、まさに近代社会との分岐点でしょ。近代工業社会にはデカルトのほうがめちゃめちゃマッチするのだけどね。
そして、この後、この本は(僕の中の)クライマックスへ向かう。
~~~ここから引用
私たちの考え方は強く近代科学に規定されています。私たちの思考のOSは近代科学的です。ですから、そのOSはスピノザ哲学をうまく走らせることはできないかもしれません。
これこそが私が「はじめに」で述べた、「頭の中でスピノザ哲学を作動させるためには、思考のOS自体を入れ替えなければならない」ということの意味に他なりません。
近代科学はデカルト的な方向で発展しました。その発展は貴重です。私たちは日々、その恩恵に与って生きています。そしてまた、公的に証明したり、エヴィデンスを提示することもとても大切です。それを否定するのは馬鹿げています。しかし、そのことを踏まえた上で、同時に、スピノザ哲学が善悪、本質、自由、そして能動をあのように定義した理由を考えていただきたいのです。
近代科学はとても大切です。ただ、それが扱える範囲はとても限られています。
フーコーの「主体の解釈学」。かつて真理は体験の対象であり、それにアクセスするためには主体の変容が必要とされていた。ある真理に到達するためには、主体が変容を遂げ、いわばレベルアップしなければならない。そのレベルアップを経てはじめてその真理に到達できる。
この考え方が変わったのは17世紀であり、フーコーはその転換点を「デカルト的契機」と呼んでいます。デカルト以降、真理は主体の変容を必要としない、単なる認識の対象になってしまったというのです。
フーコーはしかし、17世紀には一人例外がいて、それがスピノザだと言っています。スピノザには、真理の獲得のためには主体の変容が必要だという考え方が残っているというわけです。これは実に鋭い指摘です。
~~~ここまで引用
スピノザ、すげーなって。
僕が大学時代からいろいろ感じて、学んだことが
ダイジェストで説明されてくる感じ。
「場のチカラ」とか「チューニング」とか「リアルメディア」とか
めちゃめちゃスピノザ的だなあと思った。
そして、火曜日に小田原で後藤タツヤと話して、
熱海でとっくんと話して、さらにそれが確信を増した。
「機会提供」そのものの価値。
それを本屋の棚を通じて表現すること。
教育の最大の矛盾は、目的・目標をもって始めなければいけないこと。
そして評価を前提をしなければいけないこと。
でも、エンターテイメントの本質は予測不可能性にある、ということ
それはまさに近代(工業)社会と僕を含めた若者が感じている違和感の
ギャップそのものであるのだけど。
でもさ。
スピノザ的に言えば、本質は自分らしくありたいとする力(コナトゥス)であって、
人によって、真理は異なるだろうし、その真理の獲得のためには自らの変容が必要なわけですよ。
ってことはさ。
「機会提供」こそが、人を育てるんじゃないの?って。
その人がその「機会」によって、どうなるかっていうのは、
あまり重要じゃないというか、
むしろ、その機会提供によって、自らがどうなるか?
っていう問いのほうが大切なんじゃないのか?
「挑戦するな、実験しよう」
にいがたイナカレッジの連載で掲げたコピーの意味が、スピノザを読んだ今ならわかる。
去年の夏にこはるんが言ってた
「イナカレッジは自分を知るプログラムです」の意味が、今ならわかる。
そして僕が本屋をたくさん作ろうとしていることの意味も。
機会を提供したい。本棚で表現したいのは、なぜなのか?
実験するために。
実験し、自分なりの「真理」にたどりつくために。
そのたどり着く過程で、自らを変容させるために。
いや、ために、じゃないんだよ。
生きることそのものが、そのプロセスの中にただ、ある。
根源的欲求として、ただ存在するのだ。
本棚に刺さっている1冊の本。
1冊の本から実験の旅が始まる。
そんな本棚をつくりたいと心から思う。
あなたもそんな本棚をつくるひとりになりませんか?
2019年04月14日
実験しないと分からない

午前の松本での本屋宇宙旅行オープン記念イベントの後、
東京・湯島のかえるライブラリー・ラボで、本の処方箋やってました。
「二拠点居住」「地方で仕事をつくる」とかのテーマで話して、
大学2年生の中野さんに処方されたのは、
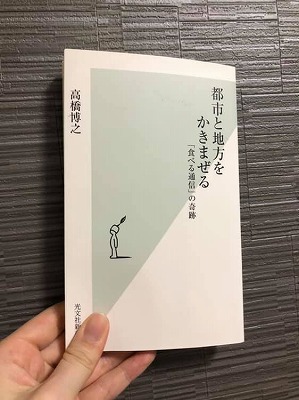
「都市と地方をかきまぜる~「食べる通信」の奇跡」(高橋博之 光文社新書)
でした。
こうやって、「本の処方箋」やって貸し出すライブラリーになったらいいのかも。
ということで、今日の1冊。

100分de名著 スピノザ「エチカ」(解説 國分功一郎)
テレビは見ていないのだけど、
古本屋で見つけてしまい、購入。
いきなり面白い。
國分さんの説明、わかりやすいなあ。
「エチカ」は考え方のOSが違う、と國分さんは説明します。
エチカの語源はギリシア語のエートスなのですが、ここまで遡るとおもしろいことが分かります。エートスは、慣れ親しんだ場所とか、動物の巣や住処を意味します。そこから転じて、人間が住む場所の習俗や習慣を表すようになり、さらには私たちがその場所に住むに当たってルールとすべき価値の基準を意味するようになりました。つまり倫理という言葉の根源には、自分がいまいる場所でどのように住み、どのように生きていくかという問いがあるわけです。
と始まります。
倫理とは、ひとりひとりの環境によって変わってくる。
「自然界に「完全/不完全」の区別が存在しないように、自然界にはそれ自体として善いものとか、それ自体として悪いものは存在しない。」とスピノザは言います。完全/不完全の考えは、我々が形成する一般的観念(偏見)との比較によってもたらせれる。善悪は、組合せによってもたらされる。「憂鬱な人」にとっての音楽はいい影響を与えるが、「悲傷の人」にとっては邪魔でしかないかもしれない。
その上で「自分にとって」善いものを判断しなければならないのだと。
~~~ここから引用
私にとって善いものとは、私とうまく組み合わさって私の「活動能力を増大」させるものです。そのことを指してスピノザは、「より小さな完全性から、より大なる完全性へ移る」とも述べます。
いわゆる道徳とスピノザ的な倫理の違い。道徳は既存の超越的な価値を個々人に強制します。そこでは個々人の差は問題になりません。
それに対してスピノザ的な倫理はあくまでも組み合わせで考えますから、個々人の差を考慮するわけです。この人にとって善いものはあの人にとっては善くないかもしれない。この人はこの勉強法でうまく知識が得られるけれども、あの人はそうでないかもしれない。そのように個別具体的に考えることをスピノザの倫理は求めます。
個別具体的に組み合わせを考えるということは、何と何がうまく組み合うかはあらかじめ分からないということでもあります。たとえばあるトレーニングの方法が自分に合っているのかどうか。それはやってみないと分かりません。その意味で、スピノザの倫理学は実験することを求めます。どれとどれがうまく組み合わされるかを試してみるということです。
もともとは道徳もそのような実験に基づいていたはずです。それが忘れられて結果だけが残っているのです。ですから、道徳だから拒否すべきということにはなりません。ただ、個々人の差異や状況を考慮に入れずに強制されることがあるならば注意が必要になるわけです。
~~~ここまで引用
これがスピノザの善悪についての考え方。
いやあ、今こそ哲学っていう感じですね。
僕たちは今、哲学なくしては生きられない時代を歩き始めているのではないかなあと。
善悪は組み合わせなのだから、実験してみるしかない。
ほかの人にとっては良くても、自分にとっては悪いことがありうると。
「考え続けること」が必須なのだなあと。
そして、この本は2日目の「本質」に移っていきます。
ここで重要なのは、「コナトゥス」という考え方です。
~~~ここから引用
「おのおのが物が自己の有(存在)に固執しようと努める努力はその物の現実的本質にほかならない。」
ここで「努力」と訳されているのがコナトゥスで、「自分の存在を維持しようとする力」のことです。
大変興味深いのは、この定理でハッキリと述べられているように、ある物が持つコナトゥスという名の力こそが、その物の「本質」であるとスピノザが考えていることです。
古代ギリシアの哲学は「本質」を基本的に「形」ととらえていました。ギリシア語で「エイドス eidos」と呼ばれるものです。これは「見る」という動詞から来ている単語で、「見かけ」や「外見」を意味します。哲学用語では「形相」と訳されます。英語では「form」です。
このエイドス的なものの見方は、道徳的判断とも結びついてきます。人間について考えてみましょう。男性と女性というのも、確かにそれぞれ一つのエイドスとしてとらえることができます。
そうすると、たとえばある人は女性を本質とする存在としてとらえられることになる。その時、その人がどんな個人史を持ち、どんな環境で誰とどんな関係を持って生きてきて、どんな性質の力を持っているのかということは無視されてしまいます。その代わりに出てくるのは、「あなたは女性であることを本質としているのだから、女性らしくありなさい」という判断です。エイドスだけから本質を考えると、男は男らしく、女は女らしく、ということになりかねないわけです。
それに対しスピノザは、各個体が持っている力に注目しました。物の形ではなく、物が持っている力を本質と考えたのです。そう考えるだけで、私たちのものの見方も、さまざまな判断の仕方も大きく変わります。「男だから」「女だから」という考え方が出てくる余地はありません。
たとえば、この人は体はあまりつよくはないけれども、繊細なものの見方はするし、人の話を聞くのが上手で、しかもそれを言葉にすることに優れている。だからこの人にはこんな仕事があっているだろう・・・。そんな風に考えられるわけです。
そして、当然ながら、このような本質のとらえ方は、活動能力の概念に結びついてきます。活動能力を高めるためには、その人の力の性質が決定的に重要です。一人一人の力のありようを具体的に見て、組み合わせを考えていく必要があるからです。
どのような性質を持った人が、どのような場所、どのような環境に生きているのか。それを具体的に考えた時にはじめて活動能力を高める組み合わせを探し当てることができる。
ですから、本質をコナトゥスとしてとらえることは、私たちの生き方そのものと関わってくる、ものの見方の転換なのです。
~~~ここまで引用
うわー。
「場のチカラ」ってこういう考え方もできるなあと。
僕の「にいがたイナカレッジ」での肩書は、
「チューニング・ファシリテーター」なのだけど、
ミーティング中にしている「チューニング」っていうのは、
スピノザ的に言えば、
「それに対しスピノザは、各個体が持っている力に注目しました。物の形ではなく、物が持っている力を本質と考えたのです。そう考えるだけで、私たちのものの見方も、さまざまな判断の仕方も大きく変わります。「男だから」「女だから」という考え方が出てくる余地はありません。たとえば、この人は体はあまりつよくはないけれども、繊細なものの見方はするし、人の話を聞くのが上手で、しかもそれを言葉にすることに優れている。だからこの人にはこんな仕事があっているだろう・・・。そんな風に考えられるわけです。そして、当然ながら、このような本質のとらえ方は、活動能力の概念に結びついてきます。活動能力を高めるためには、その人の力の性質が決定的に重要です。一人一人の力のありようを具体的に見て、組み合わせを考えていく必要があるからです。」
これのことですよね!
そして、「本の処方箋」っていうのも、まさにその人の「コナトゥス」を見つけ出す旅なのかもしれない。
その見つけ出す旅の中で、「場のチカラ」が高まって、本の妖精が本を届けてくれる。
そんな活動なのかもしれないなと。
何より、前半部分であった、善悪は実験しないとわからない。
っていうのがまさにその通りだなあと。
自分に向いている仕事とか
いろいろ自己分析したら出てくるんだろうけど、
実際はやってみなければわからないし、
その職場で誰と組み合わさるか?(いい上司、悪い上司とかではなく)
っていうのがとても大切なのだと。
「本屋宇宙旅行オープン記念イベント」で菊地さんが言っていた、
・どのまちで、店を開けたいのか?
・暮らしたいまちってどんなまち?
・暮らしたいから加わりたい
松本というまち:
個人店のマスター(店主)が他のお店を紹介してくれるまち
→「目の前のお客さんを喜ばせたい」と思っているから
昔から街道の交差点
→人とモノ、情報、文化が行き交う
そして、住みたいまちに何を加えたらいいのか?
⇒それは独立系の本屋
みたいなこと、って
「コナトゥス」を大切にしてきて、
「組み合わせ」を実験し続けた結果、
「栞日」にたどり着いて、今なお進化し続けて行っている。
だから、「栞日」に行くと、
自らの本質である「コナトゥス」が
強まっていくのかもしれない。
僕が2017年から研究してきた
「場のチカラ」とか「チューニング・ファシリテーション」
が理論的に補強されたような気がして楽しいイベント&読書でした。
自分の本質である「コナトゥス」はなんだろう?
2019年04月11日
船の行き先を知っているということ

なぜ関西のローカル大学「近大」が、志願者数日本一になったのか(山下柚実 光文社)
読んだ後にジーン熱くなるタイプの
ビジネス書が好きです。
この本。
めちゃめちゃ問いに詰まってるよ、って。
熱いっす。
って何度も思った。
「価値とは何か?」
と問いたいすべての人に贈りたい1冊です。
僕がこの本を手に取ったのは、
「近大マグロ」誕生までのプロジェクトXのVTRを見たからです。
近大の教育方針。(公式webより)
本学は、未来志向の「実学教育と人格の陶冶」を建学の精神とし、「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人の育成」を教育理念として掲げてきました。この「建学の精神」と「教育理念」は、知識基盤社会へ転換しようとする21世紀の日本において、いっそう必要とされる理念であると自負します。本学が、総合大学として各学部の特色を生かしながら、共に手を携えて目指そうとしているのは、「実学教育」と「人格の陶冶」の融合です。真の「実学」とは、必ずしも直接的な有用性を志向するだけではなく、その事柄の意味を学び取ることを含みます。現実に立脚しつつも、歴史的展望をもち、地に足をつけて、しなやかな批判精神やチャレンジ精神を発揮できる、創造性豊かな人格の陶冶を志向するものです。「自主独往の気概に満ち」、生涯にわたって自己の向上に励み、社会を支える高い志をもつことが「人に愛され、信頼され、尊敬される」ことにつながります。このような学生を社会に送り出すことが、これからの時代に、本学が目指す社会的使命であります。
「実学」ってそういうことだったんだ。
「松下村塾」で吉田松陰先生が伝えたかった
「実学」もまさにこのことだろうと思った。
その次に出てくるのは、
女子トイレの数やパウダールーム
オープンキャンパスでの在校生の対応など
「お客は誰か?」
近大らしさ、それは、受験生を「お客さま」と位置づけて、「相手の立場を優先する」こと。最高学府に「入れてあげる」という目線からではなく、「よくいらっしゃいました」と心から歓迎すること。
であると山下さんは言う。
何よりもそれを象徴するのが入学式の現場だと。
~~~ここから引用
「入学式は、新入生たちに全力で大学生活に取り組む決意をしてもらう、最大のチャンスなんです。その大切な瞬間を、私たちの思いを真心込めて伝えていく大切な時間にしたいんです。」
「不本意新入生」と大学がどう向き合うのかは、入学してくる学生に意欲や勇気を持ってもらう教育問題であると同時に、大学の経営問題でもあるのだ。
入学式という一瞬の時間によって、「不本意新入生」の意識をいかに転換し、近大に入学して良かったと思える大学生に変えていくことができるのか。
「よくぞ近大に入学してくれました」という感謝の思いを伝えることができれば、新入生は新たなるモチベーションを獲得し、大学はその結果として安定した授業料収入を確保できる。
「一人の天才より百人の中堅という分厚い中間層を育てていくことが、実学教育を掲げる私たちの重要な役割なのです。」
~~~ここまで引用
「不本意新入生」
偏差値という序列の中で、少なくない高校生が、
「不本意入学」を強いられる。
つまり、第一志望ではない大学への進学だ。
そんな新入生をどう迎えるか。
その1点から近大は入学式をド派手に行っている。
そしてラストに出てくる「三つの目標」。
これ、書いちゃうとネタバレになってしまうのだけど。
2012年12月、近大を離れることになった世耕弘成は、
全職員を一堂に集め、近大が未来に輝く近代であるための
「三つの目標」を掲げた。
1 10年以内に「関関同立」に追いつき、追い越す
2 偏差値や大学のランクで測れない、次元の違う独自性を持った大学になる
3 世の中の役に立つ大学になる
これが、職員一同に浸透しているのだという。
すごい。
とただ、思った。
みんなが乗る船の行き先を知っている、ということ。
それって、伝わってるよって思った。
6年連続志願者数日本一(併願率とかはおいといて)のヒミツ。
それを単に
「広報うまくやってるからなあ、近大は」
と思っていた自分が恥ずかしくなった。
そんなことじゃない。
18歳はそんなことに騙されない。
近大が送り出すオープンキャンパスなどのひとつひとつのコンテンツや
広報一つ一つに、お客は誰か?という問いと仮説を感じるのだろうと思う。
そして何より、
職員ひとりひとり、学生ひとりひとりが、
「近大」という船の行き先を知り、そこへ到達するために
自らはどんな貢献ができるのか?を考え、
その一手を打っているのだろうと思った。
参りました、近大。
さわやかな風をありがとう。
さて、あなたが乗っている船の行き先はどこですか?
2019年04月10日
「運命の人」という勘違い

「先生はえらい」(内田樹 ちくまプリマー新書)
内田さんの著作の中でも大好きな本のひとつ。
「学ぶ」とは何か?
そんな問いをくれる本です。
「働くこと」やそもそも「学ぶこと」
が楽しくなく、つらいことであることの理由のひとつに、
「師匠」と呼べる人(先輩)がいないことがあげられると思います。
退職した理由で
「先輩を見ていて、自分の5年後、10年後だと思って不安になった」
というのを何度か聞いたことがあります。
目指すべき「ロールモデル」が社内にいない。
それはつらいことなのだろうと思います。
しかし、本書によれば、
「師匠」とは、そのような目指すべき立派な人でなくてもよい、
ということになります。
そもそも師匠とは?
学びとは?
そんな根源的な問いをもらうのに最適な1冊です。
この本の冒頭では、「学び」と「恋愛」をうまく結び付けていて、
中学生でもわかるようになっています。
~~~以下、本書より引用
師との出会いに偶然ということはありません
先生というのは、出会う以前であれば「偶然」と思えた出会いが、出会った後になったら「運命的必然」としか思えなくなるような人のことです。これが「先生」の定義です。
あなたが「えらい」と思った人、それがあなたの先生である。
先生を求めて長く苦しい旅をした人間だけに、先生と出会うチャンスは訪れます。
「尊敬できる先生」というのは「恋人」に似ています。恋愛というのは、「はたはいろいろ言うけれど、私にはこの人が素敵に見える」という客観的判断の断固たる無視の上にしか成立しないものです。
自分の愛する人が世界最高に見えてしまうという「誤解」の自由と、審美的基準の多様性によって、わが人類はとりあえず今日まで命脈を保ってきたわけです。生物種というのは、多様性を失うと滅亡してしまうんですからね。
師弟関係というのは、基本的に美しい誤解に基づくものです。その点で、恋愛と同じなんです。
あなたが「あ、この人には、そういうところがあるんだ」と思い、「そういうところ」に気がついているのは私ひとりだという確信があるから、どきどきしちゃうわけですね。
「誰も気づいていないことに、私だけが気づいていた」という経験て、たぶん人間にとって、「私が私であること」のたしかな存在証明を獲得したような気になるからでしょうね。恋も科学の実験もそういう意味では、とても人間的な営みなんです。
先生も同じです。誰も知らないこの先生の素晴らしいところを、私だけは知っている、という「誤解」からしか師弟関係は始まりません。
プロの人なら言うことは決まっている。「技術に完成はない」と「完璧を逸する仕方において創造性はある」です。この二つが「学ぶ」ということの核心にある事実です。
ことばはむずかしいですけれど、これはじつは恋愛とまったく同じなんです。「恋愛に終わりはない」そして、「失敗する仕方において私たちは独創性を発揮する」。
私たちが学ぶのは、万人向けの有用な知識や技術を習得するためではありません。自分がこの世界でただひとりのかけがえのない存在であるという事実を確認するために、私たちは学ぶのです。
「この先生のこのすばらしさを知っているのは、あまたある弟子の中で私ひとりだ」という思い込みが弟子には絶対に必要です。
それは恋愛において、恋人たちのかけがえのなさを伝えることばが「あなたの真の価値を理解しているのは、世界で私しかいない」であるのと同じです。
「自分がいなければ、あなたの真価を理解する人はいなくなる」という前提から導かれるのは、次のことばです。だから私は生きなければならない。
~~~ここまで本書より引用
本当はもっともっとメモしたのですけど、
きりがないので今日はこの部分から。
一番強調したいのは、ラストのところです。
私たちが学ぶのは、万人向けの有用な知識や技術を習得するためではありません。自分がこの世界でただひとりのかけがえのない存在であるという事実を確認するために、私たちは学ぶのです。
「この先生のこのすばらしさを知っているのは、あまたある弟子の中で私ひとりだ」という思い込みが弟子には絶対に必要です。
それは恋愛において、恋人たちのかけがえのなさを伝えることばが「あなたの真の価値を理解しているのは、世界で私しかいない」であるのと同じです。
「自分がいなければ、あなたの真価を理解する人はいなくなる」という前提から導かれるのは、次のことばです。だから私は生きなければならない。
この4つのフレーズから、
「学ぶ」とは?から始まって、「生きる」とは?まで進んでいる。
弟子になること。
それは「生きる意味」を見つけるということ。
大げさに言えば、そういうことなのかもしれない。
しかもそれは恋愛に似ている。
つまり、思い込みなんだと。
この出発点。
これが大切なことなのかなあと思います。
僕たちが学ぶのは、有用な知識や技術を習得するためではなく、
自らがかけがえのない存在であるという事実を確認するため。
そうなんですよ。
学ぶということの目的は、「グローバル人材」になって、
「エンプロイアビリティ」(雇用され得る能力)を高め、
「コモディティ化」(交換可能になること)するためではないんですよ。
そのためには、師匠に出会うこと。
師匠の教えを誤読すること。
そして、行動すること。
その繰り返しでしかない。
僕は山口・萩で吉田松陰先生に
「学びあいの場づくりこそが希望を生む」
と学び
茨城・五浦で岡倉天心先生に、
「世界はひとつなんだ。まあお茶でも飲もうじゃないか」
と学び
岩手・花巻で宮沢賢治先生に
「永久の未完成、これ完成である」
と学んだ。
彼らを師匠だと思うのは思い込みや勘違いに過ぎない。
(だって、お前が弟子だ、って言われてないから)
それは、「運命の人」に出会って結婚するのと同じだ。
師匠の教えを誤読し、自分なりのプロジェクトを作っていくこと。
そして師匠が出す問いに仮説検証を繰り返していくこと。
それが、自分が自分であるために、行っているのだなあとあらためて思いました。
さて、あなたの師匠は誰ですか?
2019年04月09日
「問い」をもらう「場」としての「本屋」と「地域」
昨日のブログに書いた

「学校をつくり直す」(苫野一徳 河出新書)
からの

「ふるさとを元気にする仕事」(山崎亮 ちくまプリマー新書)
「探究」ってこういうことなんじゃないかとあらためて思った。
地方こそ、地域社会こそ、「探究」の宝庫だと。
僕の「探究」の入り口は、
2002年の中3不登校男子、シンタロウとの出会いだった。
そこから、
「生きる力」ってなんだろう?っていう問いが始まった。
ツルハシブックスの店に立っていたとき、
「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」
と深刻に語る大学生を前にして、
「やりたいこと」とか「自信」ってそもそもなんだ?
働くってなんだろう?っていう問いが始まった。
30歳の時、社会科の教師になろうと思って、
玉川大学通信教育学部に3年次編入。
介護等体験も、2週間の教育実習もやったけど、
「自分のフィールドは学校そのものじゃない」と思って中退。
学校そのものじゃないというより、
何かを教えるようなスタンスじゃない、と思った。
2004年に「小説吉田松陰」(童門冬二 集英社文庫)に
出会い、野山獄エピソードに「これだ!」と直感。
以降、「学びあえば希望を生むことができる」
をコンセプトにしてきた。
そして、そのための「機会提供」を行うこと。
「機会提供」というコンセプトは、目的を持って始めないということ。
そしてそれは、「予測不可能性」を大切にするということだと最近になって気がついた。
今でも「暗やみ本屋ハックツ」のイベントに引き継がれている。
今でもたぶん、それは変わらないのだろうと思う。
本屋には、宝物が眠っている。
それは「探究」を駆動する何か、だ。
そしてそれは、「地域」にも、「地域の人」にも同じく眠っている。
「地域の課題解決」が叫ばれているが、
「解決」したいと心から思うのは、一般的「課題」じゃなくて、
具体的な誰かが困っていることだ。
それを解決することで楽しい未来が待っているようなこと。
それに出会えること。
それが「本屋」と「地域」の魅力だろうと思う。
「本」や「地域の人」に出会い、心が動くこと。
「衝撃」や「共感」だったり、「何とかしたい」と思うこと。
そこから「探究」が「学び」が駆動していく。
そういう場所をつくりたいんだ。
そんな学びを駆動させる1冊に
偶然にも出会える本屋を、一緒につくらないか?
「探究」を発動するような地域を、場を
一緒につくらないか?

「学校をつくり直す」(苫野一徳 河出新書)
からの

「ふるさとを元気にする仕事」(山崎亮 ちくまプリマー新書)
「探究」ってこういうことなんじゃないかとあらためて思った。
地方こそ、地域社会こそ、「探究」の宝庫だと。
僕の「探究」の入り口は、
2002年の中3不登校男子、シンタロウとの出会いだった。
そこから、
「生きる力」ってなんだろう?っていう問いが始まった。
ツルハシブックスの店に立っていたとき、
「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」
と深刻に語る大学生を前にして、
「やりたいこと」とか「自信」ってそもそもなんだ?
働くってなんだろう?っていう問いが始まった。
30歳の時、社会科の教師になろうと思って、
玉川大学通信教育学部に3年次編入。
介護等体験も、2週間の教育実習もやったけど、
「自分のフィールドは学校そのものじゃない」と思って中退。
学校そのものじゃないというより、
何かを教えるようなスタンスじゃない、と思った。
2004年に「小説吉田松陰」(童門冬二 集英社文庫)に
出会い、野山獄エピソードに「これだ!」と直感。
以降、「学びあえば希望を生むことができる」
をコンセプトにしてきた。
そして、そのための「機会提供」を行うこと。
「機会提供」というコンセプトは、目的を持って始めないということ。
そしてそれは、「予測不可能性」を大切にするということだと最近になって気がついた。
今でも「暗やみ本屋ハックツ」のイベントに引き継がれている。
今でもたぶん、それは変わらないのだろうと思う。
本屋には、宝物が眠っている。
それは「探究」を駆動する何か、だ。
そしてそれは、「地域」にも、「地域の人」にも同じく眠っている。
「地域の課題解決」が叫ばれているが、
「解決」したいと心から思うのは、一般的「課題」じゃなくて、
具体的な誰かが困っていることだ。
それを解決することで楽しい未来が待っているようなこと。
それに出会えること。
それが「本屋」と「地域」の魅力だろうと思う。
「本」や「地域の人」に出会い、心が動くこと。
「衝撃」や「共感」だったり、「何とかしたい」と思うこと。
そこから「探究」が「学び」が駆動していく。
そういう場所をつくりたいんだ。
そんな学びを駆動させる1冊に
偶然にも出会える本屋を、一緒につくらないか?
「探究」を発動するような地域を、場を
一緒につくらないか?
2019年04月08日
「共同探究者」になるということ

「学校をつくり直す」(苫野一徳 河出新書)
読みました。
長野県伊那市で「まあるい学校」やってた濱ちゃんに
紹介されて読んだのが苫野さんの「教育の力」でした。
あれから5年。
「公教育をイチから考えよう」(リヒテルズ直子・苫野一徳 日本評論社)
にも記載がありましたが、
「教育の個別化、協同化、プロジェクト化」
に僕もめちゃめちゃ賛同しています。
特にプロジェクト化について、
大学生のインターンシッププログラムを
考えていたというのもあって、
その機会をどうやってつくるか、
っていうのを僕もひたすら考え続けています。
そしてそもそも、本屋っていうのは、
そのような「プロジェクト」への入り口、機会を提供している場
なのではないかと。
人との出会いや本との出会いによって
「知りたい」「学びたい」という「探究」の心が駆動していくのではないかと
あらためて思った1冊でした。
ということで、本文より引用
~~~ここから引用
「自由の相互承認」を原理(根本ルール)とした社会を築くこと。これ以外に、人類が「自由」に平和に生きる道はない。これが哲学者の出した答えでした。そしてわたしの考えでは、この原理こそ、一万年におよぶ戦争の歴史を経て、人類がついに到達した英知の結晶にほかならないのです。
公教育は、すべての子どもに「自由の相互承認」の感度を育むことを土台に、「自由」に生きるための力を育むことを通して、「自由の相互承認」を原理としたこの市民社会の礎を築くためにあるのです。
苫野さんからの3つの問い
1 現代において「自由」に生きるための“力”とは何か?
2 その“力”はどうすれば育めるのか?
3 「自由の相互承認」の感度はどうすれば育めるのか?
「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合」そして、カリキュラムの中核を「プロジェクト」あるいは「探究」へと転換すること。
それはつまり、出来合いの問いと答えばかり学ぶ学びではなく、「自分(たち)なりの問いを立て、自分(たち)なりの仕方で、自分(たち)なりの答えにたどり着く」、そんな「探求型の学び」です。
学校はこれまで、多くの場合、子どもたちに「問いを立てる」という経験さえ十分に保障できてきませんでした。学ぶべきことはあらかじめ決められ、そしてそれを、決められた順序に従って勉強するように強いてきたのです。
わたし自身、「探究」という言葉を、「学び」それ自体として、つまり、そもそも学びとは「探究」にほかならない、という意味を込めて使っています。「プロジェクト」という言葉は、この「探究」を駆動するための方法概念です。
要するに、子どもたちの「探究」を駆動するために学校での学びを「プロジェクト化」していく必要がある。
「プロジェクトの類型」
1 課題解決型プロジェクト
2 知的発見型プロジェクト
3 創造型プロジェクト
子どもたちが「探究」によって学ぶとき、教師は「探究」をサポート、ガイドする「共同探究者」「探究支援者」になる必要があります。「共同探究者」「探究支援者」としての教師は、どれだけAIが進化したとしても、あるいはAI時代においてはなおのこと、これからますます必要とされていくはずです。
わたしたちには、今、自分はどう生きれば幸せなのか、自由になれるのか、そしてそれはどうすれば可能なのかという、自らの人生の問いそれ自体を立て、またその答えを見つけていく力が必要なのです。
「探究」の四つのステップ
1「テーマ」:探究テーマの発見・選択、およびそのテーマに浸りきる
2「問い」:探究テーマに関する「問い」を立てる
3「方法」:「問い」を解くための方法を考え出し、実行する
4「発表」:探求の成果を持ち寄り、交換し、学び合う
子どもたちの学びをもっと「遊び」にしていこうということでもあります。より正確に言うと、「遊び」と「学び」を、もっと連続的なものにしていこう、と。
幼少期の遊び浸りがその後の学び浸りの土台になる、というのは幼児教育の基本です。子どもたちは遊びの中で、自分の関心をとことん追求すること、粘り強く探究すること、また人と協働したり折り合いをつけたりすることなどを学んでいくのです。
学びは本来、とんでもなくワクワクするものなのです。新しいことを知ること、そのことで自分が成長していくのを実感することが、ワクワクしないはずがありません。
でも、小学校に入った途端に、遊びと学びは分断されてしまいます。先生は言います「はい、遊びの時間は終わり。今は勉強する時間です!」遊びとお勉強はまったく別のものにされてしまうのです。遊びは楽しいものでお勉強は嫌なものになるのです。
「探究」とは、本来最高の「遊び」である。そう、わたしは改めて言いたいと思います。子どもたちの「遊び」を見れば、それは一目瞭然です。あの「遊び」が、高度の「探求」でなくて一体何でしょう。
~~~ここまで引用
大人の役割は、
「共同探究者」「探究支援者」となること。
いや、大人に対する子どもの役割ではなくて、
人と人との関係性は、そこから始まるのかもしれない。
かつて僕の師匠の塩見直紀さんが
「一人一研究所の時代」と言っていた。
それぞれが、
それぞれのテーマで「探究」している。
本書にあるのような、
「自分(たち)なりの問いを立て、自分(たち)なりの仕方で、自分(たち)なりの答えにたどり着く」、そんな「探求型の学び」を共に進めていく関係性があること。
それって人生において必要なのではないかなと思った。
そして、僕が茨城でやりたかったけど、まったくできなかったこと。
「地方は、過疎化や少子高齢化をはじめとする社会問題のいわば「宝庫」であるから、であり、むしろ地域の人たちと共に解決していく「探究」の学びをデザインすることができる。学校や世代を超えたプロジェクトチームを発足することもできるでしょう。」
そうそう、こういうの。
これをやっていくこと。
本屋っていうのは、本のある空間っていうのは、
本と出会い、そして人と出会うことによって、
その入り口を作っているのではないかな。
学びと遊びが連続的に起こっていくこと。
それこそが「探究」の楽しさであると思う。
「挑戦」の連鎖じゃなくて、
「学び」と「遊び」と「さらなる学び」の連鎖をつくっていきたいな、と。
2019年04月06日
「師匠」に出会い、「弟子」になること

山口・萩・吉田松陰生誕地から萩の街を望む。
僕の師匠は、29歳のときから、吉田松陰先生で、それは、

「小説・吉田松陰」(童門冬二 集英社文庫)を読んだ時の
「野山獄」エピソードの衝撃からだった。
みなを師匠とし、書道教室や俳句教室を始め、
獄中を学び舎に変えてしまった。
雰囲気は一変。希望にあふれた。
「どんな場、境遇でも、学び合うことで希望が生まれる」
これが僕の原点となった。
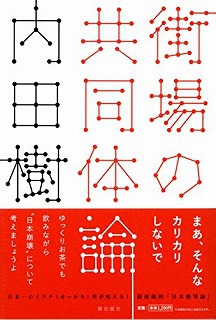
「街場の共同体論」(内田樹 潮出版社)の最終章、
「弟子という生き方」にシビれた。
現代に足りないのは、
「師匠」と「弟子」なのではないか、と思った。
会社に足りないのは、
「ロールモデル」ではなく「師匠」ではないかと。
~~~以下引用
弟子になったものは、自学自習のサイクルに入り込んでしまう。
師を持つ弟子のポジションときうのは、そうやって聞くと、無限に解釈し続けるばかりで、なんだかたいへんみたいですけれど、実は大きなメリットがあるんです。それは、自分を守る必要がない、ということです。
自分の今の手持ちのフレームワークや、今の自分が使える技などは、いつ捨てても平気なんです。先生がいるから。「お前のその知識や技術は使い物にならない」と誰かに言われても、全然気にならない。
だって、まさに自分の手持ちの知識や技術が使い物にならないからこそ、師について学んでいるわけで、「そんなこと、先刻ご承知だい」ということです。
「あんたに言われるよりはるか前から、自分がどれくらいのものを知らないか、技が使えないか、誰よりも自分が知ってますよ。だから師匠に就いて学んでいるんじゃないか」という話です。
だから、「知らない」「できない」ということによるストレスがない。自分がその道の開祖とか、学派の学祖とかであったら、「知らない」や「できない」は許されません。
でも、違う。いくらでも間違えることができる。いくらでも失敗することが許される。この広々とした「負けしろ」が、弟子というポジションの最大の贈り物です。今の自分の知見や技術に「居着かない」でいられる。この開放性が、弟子であることの最大のメリットだと思います。
孔子が治世の理想としたのは、周公の徳治です。でも、すでに孔子の時代においてさえ、魯の国において、周公の治績は忘れ去られようとしていました。孔子はその絶えかけた伝統の継承者として名乗りを上げた。
そして、自分は古い知の伝統の継承者であり、私の教えには何も新しいものはないと高らかに宣言したのです。自分は何も創造せず、ただ祖述するのみである、と。
かつて白川静先生は、ここの「無主体的な主体の自覚」のうちに、孔子の「創造の秘密」があると道破しました。自分にはオリジナリティがない、私の説はどれも先賢の不正確なコピーに過ぎない。そう自己規定することによって、孔子は思考の自由と豊かな創造性を手に入れたのです。
孔子と周公のこの関係が、師弟関係の原型だと僕は思います。周公を師に選んだのは孔子自身です。孔子が進んで弟子のポジションを選んだ。そして、その「周公に師事する構え」それ自体を、顔回や子路をはじめとする孔門のすべての弟子たちが模倣することとなった。
弟子たちに思考の自由と創造性を賦与するために、孔子は弟子のポジションを取ったのです。そういうものなんです。
~~~以上引用
「自由」ってなんだろう?
「オリジナリティー」ってなんだろう?
って思った。
「自分は伝統の継承者であって、私の教えには何も新しいものはない。」
この圧倒的な強さ。
そして自由。
そして何より、
「弟子」なんて、勘違いや思い込みに過ぎないっていうこと。
あの孔子でさえ、勝手に弟子を名乗っていただけなんだと。
「師匠」とは、「問い」そのものである。
本文にも書いてあるけど、
師匠が答えを教えなければ、
弟子は「なぜ、師匠は答えを教えないのだろう?」と問い、
師匠が答えを教えれば、
弟子は「なぜ、師匠は答えを教えたのだろう?」と問うこと。
そういうスパイラルに入っていくことが
弟子になるということ。
だから、師匠には何度も会いに行かないといけない。
そのときどきの師匠を持ってもいい。

花巻・宮沢賢治の墓所にて。
僕の師匠元祖は、宮沢賢治先生だった。
「農民芸術概論綱要」を読み、心が打ち抜かれた。
花巻に行くたびに、問いをもらう。
「永久の未完成これ完成である」
それはいったいどういう意味なのか。
どう行動すればいいのか。
そこに対する、問いをもらえる。
「師匠」に出会うこと。
「弟子」として生きること。
それは不自由ではなく、圧倒的な自由だ。
僕は継承者にすぎない。
オリジナリティーなど何もない。
そう言える強さと自由こそが
オリジナルなものを生んでいくのではないか、と思った。
「師匠」に出会うこと。
「いや、僕の周りには、そんな素敵な人はいないよ。」
と言っている場合じゃない。
師匠なんて、勘違いと思い込みなのだから。
さて。
吉田松陰と宮沢賢治と岡倉天心の継承者として、
僕はどんな次の一手を打とうかな。
2019年04月05日
「消費主体としての自分」とアイデンティティ・クライシス
昨日は、内野町で「おうちのごはん」のごはん会でした。

自己紹介で、ひとりの大学生が「シェアハウスしてます」って言ってて、
ああ、シェアハウスは住むものじゃなくて、するものなんだな、と。
(作りつつ住んでいるので「住む」と「つくる」両方やっているという意味なんだそう)
今日はそんなのにもつながる話を。
「就活の違和感」とか、「自分に自信がない」とか、「やりたいことがわからない」とかって、
結局「アイデンティティ・クライシス=(自分らしさ危機)」につながってくるなと思う。
自分とは何か?
自分らしさとは何か?
自分にはどんな価値があるのか?
その「自分」っていうのが違うんじゃないかっていうのが
ひとつのアプローチで。
もうひとつのアプローチ。
それは「アイデンティティ・クライシス」が
どのように生み出されてきたのか?ということ
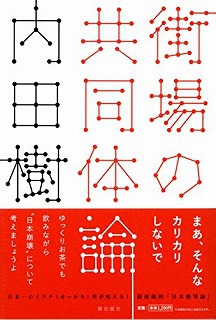
「街場の共同体論」(内田樹 潮出版社)
この本に的確に指摘されているなあと。
~~~以下メモ
経済成長のための最適解を求めた結果、最も合理的な政策は「家族解体」でした。消費活動を活性化するためには家族の絆がしっかりしていて、家族たちが連帯し、支えあっていては困る。だから、国策として家族解体が推し進められたのです。
どうして、経済成長のためには家族解体が必要だったのか。問題は消費単位です。「誰が」、あるいは「何が」消費活動を行うのか。それを考えてください。近代社会では久しく消費単位は家族でした。家族のそれぞれが労働によって、いくばくかの収入を「家計」に入れる。その使途についても家族全体の合意が必要でした。
自分の消費行動について他人から批判的なコメントをされることは、現代人にとって最も耐え難い苦痛のひとつなのです。現代人は、自分の消費行動に関するコメントを、自分の人格についてのコメントとして受け取るように教え込まれているからです。
「あなたが何ものであるかは、あなたがどのような商品を購入したかによって決せられる」そのような消費者哲学に基づいて、現代人のアイデンティティは構築されています。
どういう家に住んで、どういう服を着て、どういう車に乗って、どういう家具に囲まれて、どういうワインを飲んで、どういうレストランで食事をして、どういうリゾートでバカンスを過ごすか。そういう消費行動によって、「あなたが何ものであるか」は決定される。
だから、商品購入ができない人間は「何もの」でもありえないのだ。長い時間かけて現代人はそう教え込まれてきました。
「自分らしく」生きるためには、消費行動におけるフリーハンドを手に入れるしかない。何を買うのか自己決定できる環境で暮らすこと。その消費活動が「身の程」と引き比べて適切であるかどうかということについて、誰にも口を差し挟ませないこと。それがすべての日本人にとって喫緊の課題となりました。
バブル期以前まで、自分が「何もの」であるかは、消費行動によってではなく、労働行動によって示すものと僕たちは教えられてきました。「何を買うか」ではなく、「何を作り出すか」によって、アイデンティティは形成されていた。
自分が作り出したものの有用性や、質の高さや、オリジナリティについて他者から承認を得ることで、僕らは自らのアイデンティティを基礎づけてきた。
でも、80年代からの消費文化は、そのルールを変えてしまいました。それがこの時期の最大の社会的変化だったと思います。「労働」ではなく「消費」が、人間の第一次的な社会活動になったのです。
「何を作るか」ではなく、「何を買うか」を基準に、人間の値踏みをするようになった。その場合、消費の原資となる金をどのようにして手に入れたかは、原則的に不問に付されます。
この新しい貨幣観は、僕たちの労働観にも本質的な変化をもたらさずにはいませんでした。日本人に刷り込まれた新しい労働観というのは次のようなものでした。最も少ない努力で、最も効率よく、最も大量の貨幣を獲得できるのが、「よい労働」である。
労働の価値は、かつてはどのように有用なもの、価値あるものを作り出したかによって考量されました。バブル期以降はもうそうではありませんでした。その労働がどれほどの収入をもたらしたかによって、労働の価値は考量されることになった。そういうルールに変わったのです。
ですから、最もわずかな労働時間で巨額の収入をもたらすような労働形態が最も賢い働き方だということになる(例えば、金融商品の売買)。一方、額に汗して働き、使用価値の高い商品を生み出しても、高額の収入をもたらさない労働は社会的劣位に位置づけられました(例えば、農林水産業)。
そのようにして現代人の労働するモチベーションは、根元から傷つけられていった。
~~~以上メモ
1980年代以降の「消費文化」は、
アイデンティティをずらすことに成功した。
「生産者」としてではなく「消費者」として。
そして得たマインドが、
「最も少ない努力で、最も効率よく、最も大量の貨幣を獲得できるのが、「よい労働」である。」だった。
いや、これリアルにそうだなあと。
僕が20代のころに見た雑誌の連載で、
「わずか半年で株取引で1億円つくった」みたいな
大学生の連載があって、
えっ。
それ、何がすごいんすか?
ってめちゃめちゃ衝撃を受けたことを覚えている。
この本を読んでわかった。
それが世間の(刷り込もうとしている)価値観だったのだ。
そして、何を買ったか?
どんなモノを所有しているか?
それがその人のアイデンティティ、つまり「その人らしさ」を決めるのだと。
おそらく今の大学生や20代からすれば、
まったくのファンタジーみたいな世界だろうと思うけど、
そこへ官民挙げて突き進んだ時代が確かにあったのだ。
かくして、経済は延命した。
一家に一台だったテレビは、ひとり一台となり、
新機能がたくさんつきました!と宣伝されるコンポを買い替え、
「一人前になるための」家や車を買うために、ローンを組んだ。
でも、もう、そこに夢はない。
いや、もともとなかったんじゃないか。
「消費主体としての自分」が
アイデンティティを決めるなんて、
「シェアハウスしてます」
という大学生には、まったく理解できない価値観なのだろうと思う。
でも、そういう時代があったのだ。
そしてその時、労働するモチベーションが書き換えられた。
しかし、いま。
消費主体として、アイデンティティを構築することはかなり難しい。
現在の大学生が抱える「アイデンティティ・クライシス」や
就活の違和感の原因のひとつがここにあるだろうと思う。
「消費主体としてのあなたが、あなたの価値を決めるのだ。」
そんなメッセージ。
東京でバリバリ働いて、高い家賃を払って、オシャレなカフェでランチをして、
それをインスタにアップするような暮らし。
それ、本当にやりたいですか?
っていうことなのだと思う。
「にいがたイナカレッジ」に惹かれる大学生たちの感性。
そこにヒントがあるように僕は思う。

自己紹介で、ひとりの大学生が「シェアハウスしてます」って言ってて、
ああ、シェアハウスは住むものじゃなくて、するものなんだな、と。
(作りつつ住んでいるので「住む」と「つくる」両方やっているという意味なんだそう)
今日はそんなのにもつながる話を。
「就活の違和感」とか、「自分に自信がない」とか、「やりたいことがわからない」とかって、
結局「アイデンティティ・クライシス=(自分らしさ危機)」につながってくるなと思う。
自分とは何か?
自分らしさとは何か?
自分にはどんな価値があるのか?
その「自分」っていうのが違うんじゃないかっていうのが
ひとつのアプローチで。
もうひとつのアプローチ。
それは「アイデンティティ・クライシス」が
どのように生み出されてきたのか?ということ
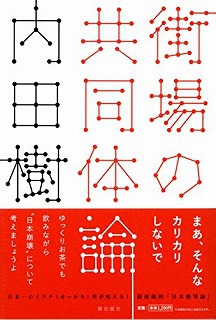
「街場の共同体論」(内田樹 潮出版社)
この本に的確に指摘されているなあと。
~~~以下メモ
経済成長のための最適解を求めた結果、最も合理的な政策は「家族解体」でした。消費活動を活性化するためには家族の絆がしっかりしていて、家族たちが連帯し、支えあっていては困る。だから、国策として家族解体が推し進められたのです。
どうして、経済成長のためには家族解体が必要だったのか。問題は消費単位です。「誰が」、あるいは「何が」消費活動を行うのか。それを考えてください。近代社会では久しく消費単位は家族でした。家族のそれぞれが労働によって、いくばくかの収入を「家計」に入れる。その使途についても家族全体の合意が必要でした。
自分の消費行動について他人から批判的なコメントをされることは、現代人にとって最も耐え難い苦痛のひとつなのです。現代人は、自分の消費行動に関するコメントを、自分の人格についてのコメントとして受け取るように教え込まれているからです。
「あなたが何ものであるかは、あなたがどのような商品を購入したかによって決せられる」そのような消費者哲学に基づいて、現代人のアイデンティティは構築されています。
どういう家に住んで、どういう服を着て、どういう車に乗って、どういう家具に囲まれて、どういうワインを飲んで、どういうレストランで食事をして、どういうリゾートでバカンスを過ごすか。そういう消費行動によって、「あなたが何ものであるか」は決定される。
だから、商品購入ができない人間は「何もの」でもありえないのだ。長い時間かけて現代人はそう教え込まれてきました。
「自分らしく」生きるためには、消費行動におけるフリーハンドを手に入れるしかない。何を買うのか自己決定できる環境で暮らすこと。その消費活動が「身の程」と引き比べて適切であるかどうかということについて、誰にも口を差し挟ませないこと。それがすべての日本人にとって喫緊の課題となりました。
バブル期以前まで、自分が「何もの」であるかは、消費行動によってではなく、労働行動によって示すものと僕たちは教えられてきました。「何を買うか」ではなく、「何を作り出すか」によって、アイデンティティは形成されていた。
自分が作り出したものの有用性や、質の高さや、オリジナリティについて他者から承認を得ることで、僕らは自らのアイデンティティを基礎づけてきた。
でも、80年代からの消費文化は、そのルールを変えてしまいました。それがこの時期の最大の社会的変化だったと思います。「労働」ではなく「消費」が、人間の第一次的な社会活動になったのです。
「何を作るか」ではなく、「何を買うか」を基準に、人間の値踏みをするようになった。その場合、消費の原資となる金をどのようにして手に入れたかは、原則的に不問に付されます。
この新しい貨幣観は、僕たちの労働観にも本質的な変化をもたらさずにはいませんでした。日本人に刷り込まれた新しい労働観というのは次のようなものでした。最も少ない努力で、最も効率よく、最も大量の貨幣を獲得できるのが、「よい労働」である。
労働の価値は、かつてはどのように有用なもの、価値あるものを作り出したかによって考量されました。バブル期以降はもうそうではありませんでした。その労働がどれほどの収入をもたらしたかによって、労働の価値は考量されることになった。そういうルールに変わったのです。
ですから、最もわずかな労働時間で巨額の収入をもたらすような労働形態が最も賢い働き方だということになる(例えば、金融商品の売買)。一方、額に汗して働き、使用価値の高い商品を生み出しても、高額の収入をもたらさない労働は社会的劣位に位置づけられました(例えば、農林水産業)。
そのようにして現代人の労働するモチベーションは、根元から傷つけられていった。
~~~以上メモ
1980年代以降の「消費文化」は、
アイデンティティをずらすことに成功した。
「生産者」としてではなく「消費者」として。
そして得たマインドが、
「最も少ない努力で、最も効率よく、最も大量の貨幣を獲得できるのが、「よい労働」である。」だった。
いや、これリアルにそうだなあと。
僕が20代のころに見た雑誌の連載で、
「わずか半年で株取引で1億円つくった」みたいな
大学生の連載があって、
えっ。
それ、何がすごいんすか?
ってめちゃめちゃ衝撃を受けたことを覚えている。
この本を読んでわかった。
それが世間の(刷り込もうとしている)価値観だったのだ。
そして、何を買ったか?
どんなモノを所有しているか?
それがその人のアイデンティティ、つまり「その人らしさ」を決めるのだと。
おそらく今の大学生や20代からすれば、
まったくのファンタジーみたいな世界だろうと思うけど、
そこへ官民挙げて突き進んだ時代が確かにあったのだ。
かくして、経済は延命した。
一家に一台だったテレビは、ひとり一台となり、
新機能がたくさんつきました!と宣伝されるコンポを買い替え、
「一人前になるための」家や車を買うために、ローンを組んだ。
でも、もう、そこに夢はない。
いや、もともとなかったんじゃないか。
「消費主体としての自分」が
アイデンティティを決めるなんて、
「シェアハウスしてます」
という大学生には、まったく理解できない価値観なのだろうと思う。
でも、そういう時代があったのだ。
そしてその時、労働するモチベーションが書き換えられた。
しかし、いま。
消費主体として、アイデンティティを構築することはかなり難しい。
現在の大学生が抱える「アイデンティティ・クライシス」や
就活の違和感の原因のひとつがここにあるだろうと思う。
「消費主体としてのあなたが、あなたの価値を決めるのだ。」
そんなメッセージ。
東京でバリバリ働いて、高い家賃を払って、オシャレなカフェでランチをして、
それをインスタにアップするような暮らし。
それ、本当にやりたいですか?
っていうことなのだと思う。
「にいがたイナカレッジ」に惹かれる大学生たちの感性。
そこにヒントがあるように僕は思う。
2019年04月04日
「学校」ってなんだっけ?

「すべての教育は洗脳である」(堀江貴文 光文社新書)を読み直し。
やっぱ、「学校」そのものをとらえなおす必要あるなあと。
「学校」ってなんだっけ?
みたいな問いから始めないといけないんじゃないかと。
~~~ここから引用
日本には、僕のような「我慢しない人」を軽蔑する文化がある。そして、「我慢強い人」を褒め称える文化がある。
どんなに不満があっても、どんなに理不尽な状況に置かれても、それを耐え忍ぶことを美徳とし、耐えしのいだ先にこそ「成功」が待っているかのような言説がまかり通っている。ほとんどマインドコントロールに近い不条理なこの呪いが、この国全体を覆っている。
その原因は何か?「学校」なのである。旧態依然とした学校教育の中で、日本人は洗脳されている。やりたいことを我慢し、自分にブレーキをかけ、自分の可能性に蓋をすることを推奨する恐ろしい洗脳、白昼堂々なされているのが今の学校なのだ。
教育はよく「投資」に例えられる。(中略)「学び」はそれぞれにとっての投資であるべきだと思う。投資とは、投資した側へのリターンが発生すること、すなわち投入した資本がそれ以上に大きな価値を社会に生み出すことをいう。
だが、今の学校教育は「投資」になっていない。いざという時に引き出すための「貯金」にとどまっているのだ。投資型の学びに我慢は不要。貯金の本質は我慢である。そして99%の我慢は、ただの思考停止にすぎない。
でも僕は、「高学歴の若者たち」がカルト宗教に洗脳されたことを、特に不思議とは思わなかった。僕の目に映る彼ら学校教育のエリートは、「洗脳されることに慣れた人たち」だった。もともと洗脳になれた人たちが信仰先を変えただけ。
僕は宗教にには何の興味もない。否定も肯定もしない。それによって幸せになれると思うのであれば、好きな神様を拝めばいいと思う。だけど、「常識」への信仰だけはおすすめしない。はっきり言って、幸せになれる確率が低すぎる。
残念ながら、普通に暮らしている限り、「常識」という教義の危険性に気づく機会は少ない。それは「常識」の洗脳が、国ぐるみで行われているからだ。国家は、全国に4万6000箇所もの「出先機関」を設け、この国で暮らす人たちすべてをその魔の手にかけている。その出先機関とは、「学校」だ。
学校の大きな役割は二つあった。一つは子どもの保護。そしてもう一つは、彼らを「望ましい工場労働者」へと育てあげることだ。
政府にとって、工場労働者の確保は死活問題だった。工場の生産性は、国家の軍事力と直結している。しかし、ただ単に人手があればいいというわけでもない。工場の生産性を上げるために必要なのは、基礎的な学力、忍耐力やコミュニケーション能力といった、複数の能力を備えた「人的資材」だった。
つまり学校はもともと、子どもという「原材料」を使って、「産業社会に適応した大人」を大量生産する「工場」の一つだったのである。
世界のどの国でも、学校の誕生・発展はナショナリズムの台頭と連動している。
問題の本質は、国家が人間の規格=「常識」という鋳型を作り、そこに人間を無理やり押し込めようとすることにある。その教育システムそのものの誤りに気づいていないから、今でも学校は恣意的な常識の洗脳機関なのだ。
~~~ここまで引用
「学校」とは、そもそもなんだったのか?
「学校」制度の目的とは?
そんな「そもそも」から考えていかないといけないと思う。
もちろん、これは、堀江さんのいう、
学校の負の側面を強調した文章になっているのだから、
学校の正の側面ももちろんあるだろうと思う。
(友人を得るとか、基礎的な学力がつく、とか)
しかし、そもそも「学校」ってなんだ?
「常識」ってなんだ?
みたいな問いに対して、
何か仮説を立てようとするには、
とてもいいヒント、ネタになるのではないかと思う。
僕がこの引用した中で一番好きなのは、ここだ。
「僕は宗教にには何の興味もない。否定も肯定もしない。それによって幸せになれると思うのであれば、好きな神様を拝めばいいと思う。だけど、「常識」への信仰だけはおすすめしない。はっきり言って、幸せになれる確率が低すぎる。」
「学校」は、あるいは「就活」というシステムは、
もしくは、「会社で働く」ということは、
「常識」への適応を要求する。
もちろんそれは、
世の中を生きていくために、必要なことだろうと思う。
しかし、「常識」を「信仰」してはならない。
本書にあるように、「学校」というシステムは、200年前に存在していないし、
「工業社会」とセットで生み出された仕組みだった。
「就活」について言えば、もっと短い期間でしかない。
その「常識」に適応する、ということ。
それは「適応」であって、正解ではないこと。
それを「信仰」することなく、考え続けていくことが大切なのだと思う。
2019年04月01日
学校外の「居場所」ではなく、「おでん」を持つこと

「日本再興戦略」(落合陽一 幻冬舎)
今日も読書日記。
この本から「わかりやすさ」と東洋思想について。
~~~ここから引用
幸せという概念は、明治時代以降の産物です。
西洋的な幸福観は押し付けられたものなのに、
今の日本人はメディアの基準に照らし合わせて、
「とにかく幸せでないといけない」と信じ込むように
なってしまいました。
何かを求めているけれども、
それが足りないという状態は、実は依存症です。
別に、自然でいればいいのに、
メディアが定義した幸せを探す日々の中で、
日本人はいつのまにか「幸せ依存症」になってしまったのです。
「愛」も明治以降に日本に入ってきた概念です。
日本人には、きずなは昔からありましたが、愛はありませんでした。
愛ときずなの違いとは、愛が熱情的な感情を指す言葉であるのに対して、
きずなはステート(状態)であるということです。
きずなは状態ですので、それが永遠に続くこともあります。
しかし、愛はあくまでも感情ですから熱したり冷めたりで総量が変わっていきます。
たとえば、日本人の伝統的な老夫婦は、「愛している」とは口で言わずに、
静かにたたずむイメージがあると思いますが、
あれはすごく日本的でジャパニーズです。
西洋の夫婦関係は、年老いてからも愛を語る美しさがありますが、
きずなそれ自体もまた美しい関係性です。
こうした幸せや愛という概念に限らず、明治時代に生まれた翻訳言葉が、
我々の変な価値観を規定しています。
福沢諭吉や西周をはじめとする知識人たちは明治期に、
西洋社会から輸入した概念の訳語をほとんどつくりました。
それはものすごい仕事であり、評価できることなのですが、
如何せん突貫工事でもあるので、時代に合わせて修正する必要がありました。
つまり、先人に学び、先人と対話し、我々の思考基盤のアップデートが
必要になるのは先人も想定した上で取り組んでいたのでしょう。
しかしながら、それを修正する前に、日本は第二次世界大戦の
敗戦国となり再びグランドデザインされてしまいました。
日本になじむ西洋との折衷概念が生まれる前に、
多くの言葉がふたたびリセットされたしまったのです。
言葉を考え直さないと、われわれは日本再興戦略を組むことができません。
このままでは言葉尻だけを追い続けてしまう。
「欧米」と言っているうちは、コミュニケーションは
できず何も見つけることはできないのです。
~~~ここまで引用
いやあ、テレビCMとか、トレンディードラマとか、ゼクシーとか、
広告屋さんが作った「幸せ」像にみんな向かっていった。
そうやって日本は消費を拡大し、経済成長していったのだなあと
それと同じことが、
たぶん、キャリアでも起こっている。
メディアとか、リクルートがいう、「幸せな就職」とか「ロールモデル」とか
「キャリアターゲット」とか「天職」とか。
そういう言葉に流されてはいないか?
その「言葉」に対する姿勢でも、
西洋と東洋は思想的にまったく違うのだと落合さんは指摘します。
~~~ここから引用
西洋的な思想は、言葉の定義が明確であり、わかりやすいという魅力がありますが、
わかりやすさばかりを求めてはいけません。
定義によるわかりやすさの対極にあるのが、
仏教や儒教などの東洋思想です。
身体知や訓練により行間を読む文化です。
東洋文化を理解する必要があります。
理解できないのは自分のせいだから、
修業しようという精神が求められるのです。
わかりにくいものを頑張って勉強することで理解していく
―それが東洋的な価値観なのです。
言外の意味を修業によって獲得する。
それは言外の意味が参照可能な西洋的文法に対して、
内在させようとする仏教的、東洋的文法だと思います。
一方、西洋の精神は、個人主義で
みなが理解する必要があると考えます。
もし内容が理解できなければ、
「わかりやすくインストラクションしないお前が悪い」という精神なのです。
読み手が自分で修業しろ、というのはとんでもないことで、
ジャンプなく読み手のところまで降りていかないといけません。
こうした点にも、東洋思想と西洋思想は立場上、大きな違いがあるのです。
~~~
「わかりやすさ」に本当に価値があるのか?
そもそも「わかりやすさ」が価値を持つのは、
西洋的価値観、思想なんじゃないか?
そんな問い。
まあ、だからと言って、
わかりにくくてもいいってことではないのですけど。
最後に教育について言及しているこの箇所から。
~~~ここから引用
根本的には、教育から変えないと、今の流れは変えられません。
今の近代社会を成り立たせるすべての公教育とはほぼ洗脳に近いものですが、
我々は中途半端に個人、自由、平等、人権といった
西洋的な理念を押し付けられた結果、
個人のビジョンがぼやけてしまいました。
今の教育は「やりがいややりたいことがない」といった
自己否定意識を持った歪んだ人間を生み出してしまいます。
要は、欲しいものをちゃんと選ぶとか、自発的に何か
行動する、ということを練習しないし、
それをガマンするように指導するのに、
好きなものを見つけることが重要だと
言い続けるのは大きな自己矛盾を生み出しうる欠陥であり、
自己選択に意味がなく、不安が募る社会にしてしまっているのです。
教育を変えて日本人の意識を変え、
地方自治を強化して、ローカルな問題を
自分たちで解決できるようにすること。
つまり、帰属意識と参加意識、
自分の選択が意味を持っている実感を、
それぞれの人々が感じ、
相互に依存することから、
日本再興は始まっていくのです。
~~~ここまで引用
公教育が起こしているダブルバインド(矛盾)を
的確に指摘しているなあと。
重要なのはたぶん最後の一節なのだろうなと。
帰属意識と参加意識、自分の選択が意味を持っている実感を
それぞれの人々が感じ、相互に依存すること。
それを感じられるような、
小さなプロジェクト。
あるいは、「場」。
影山さんの言う、「おでん」のような場。
http://hero.niiblo.jp/e489014.html
(3月15日:「おでん」のような「場」をつくり、「植物」を育てるように「事業」をつくる)
そういうのを作っていくこと。
たぶん中学・高校の時から
学校以外の場所に「おでん」を持つこと
そうそう。
「居場所」じゃなくて、「おでん」のような「場」を持つこと。

何か小さなプロジェクトが生まれる、
そこに小さな帰属意識と小さな参加意識が生まれるような、
そんな「場」を持つこと。
その「場」は、「場」から生み出されるプロジェクトは、
個人が特定されないような、
中途半端な「匿名性」を持っていること。
それは、「創造的脱力」(若新雄純 光文社新書)
で紹介されていた鯖江市「JK課」の取り組みのように、
「JK課が批判されても、私の学校の成績が下がるわけじゃない」
(参加高校生のコメント)
とか、福岡で出会った大学1年生の「インスタ講座」で
「インスタはもうひとつの人格を作り出す装置」
というような、
調べればだれがやっているのか分かるけど、
発言(表現)はプロジェクトとして、あるいはチームとして行う、
っていうのが、
日本人のメンタリティに向いているのかもしれない。
だからこそ、大学生たちは、「場」を持とうじゃないかと。
「おでん」のように相互に関係し合う「場」で
小さなプロジェクトを生んでいこうじゃないか。
「プロジェクト」は仮の自分だ。もうひとつの自分だ。
もちろん複数名でやっているから、自分そのものではないけれど。
その「中の人」として、何かを始めてみること。
これが、オルタナティブ就活への第1歩なのかもしれない。




