2016年10月31日
「夢」という言葉から夢が失われていく30年

「転換期を生きる君たちへ~中高生に伝えておきたいたいせつなこと」(内田樹編 晶文社)
3部作の最終巻。
今年の7月30日が初版。
週末の電車のバス移動の間に読み終わりました。
面白かった。
中高生にほんとに読んでほしい1冊。
ハックツ寄贈しようかな。
もっとも、そうそう!と唸ったのは、
小田嶋隆さんの「13歳のハードワーク」
村上龍さんが書いた「13歳のハローワーク」に
対するアンチテーゼ。
僕自身も若者と接しながら、
同じような疑問を抱いていたので、
胸に突き刺さることばかりでした。
まずは前段から。
~~~ここから一部引用
昨今、ものわかりのよさげな大人は、
誰もが異口同音に
「自分だけの夢に向かって努力しなさい」
といった調子のお話を子供に吹き込む決まりとなっているからだ。
50年前には、夢をもっている子供はむしろ少数派だった。
にもかかわらず、夢なんかなくても、
子供時代は楽しかった。当然だ。
子供は、「いま、ここ」にあるがままにある存在で、
その時々の一瞬一瞬を、その場その場の感情のままに生きている。
その、あるがままの子供たちは、
「将来の展望」や「未来への希望」を特段に必要としていない。
彼らの生活は、「大人になるための準備」として
運営されているのでもなければ、「
「夢への助走」として立案されたものでもない。
子供であるところの楽しさというのは、
元来、そこのところ(未来や過去と切り離されているところ)にある。
「夢」を持つことは、一見、
前向きで素晴らしい取り組みであるように見える。
しかしながら、注意深く検討してみると、
「夢」は「未来のために現在を犠牲にする」要求を含んでいる。
ということは、「夢を持ちなさい」という
一見素敵に響くアドバイスは、その実、
「今を楽しむ」という子供自身にとって最も大切な生き方を
真っ向から否定する命令
(具体的には「将来のために今の楽しみを我慢しなさい」ということ)
でもあるわけで、
若いころに自分で「夢」だと思っていたものが、
大人になった時点から振り返ってみると、
ただの「虚栄心」だったという例は珍しくない。
「夢」という単語が、ほぼ必ず「職業」に結びつく
概念として語られるようになったのは、
この30年ほどに定着した比較的新しい傾向だということだ。
「実現可能」だったりするものは、はなから「夢」と呼ばれなかった。
それが、いつの頃からか、
「夢」は、より現実的な「目標」じみたものに変質した。
そして、現実的になるとともに、
それは年頃の男女が、一人にひとつずつ
必ず持っていなければならない必携のアイテムとして
万人に強要されるようになっている。
21世紀にはいって十数年が経過した現在、
「夢」は、子供たちが「将来就きたい職業」
そのものを意味する極めて卑近な用語に着地している。
なんという夢のない話であることだろうか。
結局、この30年ほどのあいだに、
われわれは、より都市の若い子供たちに、
「実現可能な夢を早い段階で確定しておきましょう」
という感じのプレッシャーを与える教育をほどこしてきたわけだ。
ということはつまり、少なくとも平成にはいって以来の社会の変化は、
「夢」という言葉から夢が失われていく過程そのものだったということになる。
~~~ここまで一部引用
ちょっとこのまま「13歳のハローワーク」の
話に突入していくと文章量がたいへんなことになるので、
ここでいったん切ります。
たしかに、
昭和世代に小学校時代を過ごした僕としては、
(平成2年に中学校を卒業)
まだその「夢」の古きよき時代だった。
小学校のクラス文集で、「しょうらいのゆめ」
を書いたとき、
男子のあいだで「釣り」ブームに沸いていたとき、
「釣り名人」と書く男子が続出してた。
たしかにそれ、「職業」を想定していないな。
そんなもんだった。
この前段のポイントはココだ。
「夢なんかなくても、
子供時代は楽しかった。当然だ。
子供は、「いま、ここ」にあるがままにある存在で、
その時々の一瞬一瞬を、その場その場の感情のままに生きている。
その、あるがままの子供たちは、
「将来の展望」や「未来への希望」を特段に必要としていない。
彼らの生活は、「大人になるための準備」として
運営されているのでもなければ、「
「夢への助走」として立案されたものでもない。
子供であるところの楽しさというのは、
元来、そこのところ(未来や過去と切り離されているところ)にある。」
いま、ここ、この瞬間。
それを楽しむこと。
それは子供時代の特権であり、
子供であるところの楽しさ、であるからだ。
このあと、本文は
「13歳のハローワーク」に対する考察に突入していく。
詳しくは明日。
2016年10月28日
ラーハの時間

「コミュニティ難民のススメ」(アサダワタル 木楽舎)
この本のことを書くのも、
今日が最後になってしまうかもしれません。
なぜなら、読み終わってしまったから。
悲しいです。純粋に悲しいです。
読み終わるのが惜しい1冊、いいですね。
今日は最後の釈徹宗さんとの対談「コミュニティ難民の希望」より。
最後の最後まで面白いです。
シビれます。
~~~ここから一部引用
成熟期の社会では、
人と関わったり、世話したり/されたりしながら暮らす。
こういったスタイルは、社会がフェアじゃないと成り立ちません。
もっと厳しい競争社会では、人がいいようじゃ生きていけない(笑)
成熟社会はむしろフェアだから生きていけるし、
ある種の公共性を発揮することで、高い評価を得ることができる。
自分勝手な欲望を振り回すのではなく、分かち合う。
共感する人たちが集まる。まさに成熟社会です。
コミュニティ難民は、こういう状況だから出てきた人たちでしょう。
優れたアートは、人を宙吊りにします。
不安にもさせるし、日常を揺さぶってもくれるし、
今までの自分がちょっと崩れる。それがアートの力でしょう。
都市は地縁や血縁がなくても公平に扱ってくれるフェアな場所です。
もともと都市はかなり特殊な場所なのです。
企業そのものが都市化したんでしょうね。
都市の倫理観って何かっていうと、
「人に迷惑をかけない」というものなんです。
地縁・血縁が強いコミュニティというのは、
互いに迷惑をかけたり、かけられたりしながら
運営されていくんですよ。
そこでは「大目に見る」という態度が大事なんです。
これからの成熟社会のキーワードは「フェア」と「シェア」でしょう。
社会的公正性を担保しながら、分かち合っていく姿勢がカギになると思います。
仕事と遊びの関係性のグラデーションを大きくするんですよ。
仕事か遊びか、きっちり区別せよ、とのメッセージが蔓延していたわけです。
なぜなら、効率が大事だからです。
効率を優先すると、グラデーションは邪魔です。
ところが成熟社会では、グラデーションこそが大事なわけで、
公私混同するところでぐるぐる仕事が回ったり、経済が回ったりして、
それを楽しいと感じる価値観を育てるのが重要となってくる。
大部分の文化圏では、時間を二項対立で捉えているんです。
日本もそうなんです。
公的な時間と私的な時間、パブリックとプライベート、
仕事と遊びといった感じ。
ところがイスラムは第三の時間があります。
労働の時間=「ショグル」、遊びの時間=「ラアブ」、
さらにもう一つ「ラーハ」という時間があります。
これは日本語にはない概念なので、翻訳できません。
まさに時間のグラデーション部分。
では、この時間に何をしているか?
ダラダラしているんですよ。
とにかく、男性同士でも集まっておしゃべりする。
瞑想したり、神のことを思ったり、思索したりする。
彼らの価値観では、人生で一番大事なのは、「ラーハ」だそうです。
われわれは今まで一生懸命、欧米視点で
世界や人間を見るトレーニングを続けてきました。
でも少しイスラム文化を通して世界や人間を見ると、
また違った面が発達するんじゃないでしょうか。
~~~ここまで一部引用
なるほどね。
ラーハの時間。
グラデーションの時間。
仕事と遊びのあいだ。
計画と無計画のあいだ、ね。
そういう「あいだ」にこそ、あるんだよね、面白いものは。
いやあ、面白い本でした。
ラーハの時間を、
いろいろ共有していきたいなあと思いました。
2016年10月27日
「居場所」という「瞬間」がある
にいがたレポのマルヤマさんに、
ツルハシブックス閉店のインタビュー記事を書いてもらった。
http://niigata-repo.com/culture/post-9080/
来週までの営業とはなんだか信じられないのですが、
3日から5日は、私も店頭にいます。
そこで売りたいのはこちら。

「コミュニティ難民のススメ」(アサダワタル 木楽舎)
第6章 個、表現、居場所
の冒頭で、アサダさんはこのように書く。
自分にとって居場所とは、場所ではなく、
「今この瞬間」という「時間」そのものだった。
そしてそれは当然のように常に変化し、転がってゆくものだ。
そっか!
それか!って。
天職と同じだ、と。
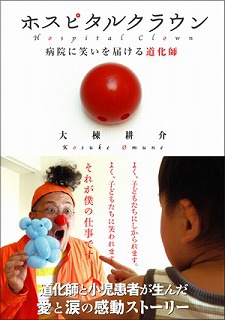
「ホスピタルクラウン」(大棟耕介 サンクチュアリ出版)
を読んだときに思った。
天職という職業があるのではなく、
天職だと思える「瞬間」があるだけなんだと。
ツルハシブックスだってそうだ。
そこにお金が介在するか否か、というのは
たいした問題じゃない。
高校生の居場所が瞬間的に誕生し、
そして、その場に居合わせたとき、
店員の役を演じ切れたとき、
それは、自分にとっての「居場所」でもあり、
そして「天職」であるのかもしれない。
だから。
もっともっと、瞬間を大切に、心をこめて、劇場化していこうと。
11月3日~5日
ツルハシブックス・ラスト3DAYS、始まります。
ツルハシブックス閉店のインタビュー記事を書いてもらった。
http://niigata-repo.com/culture/post-9080/
来週までの営業とはなんだか信じられないのですが、
3日から5日は、私も店頭にいます。
そこで売りたいのはこちら。

「コミュニティ難民のススメ」(アサダワタル 木楽舎)
第6章 個、表現、居場所
の冒頭で、アサダさんはこのように書く。
自分にとって居場所とは、場所ではなく、
「今この瞬間」という「時間」そのものだった。
そしてそれは当然のように常に変化し、転がってゆくものだ。
そっか!
それか!って。
天職と同じだ、と。
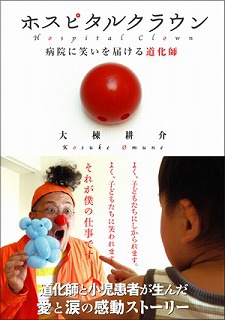
「ホスピタルクラウン」(大棟耕介 サンクチュアリ出版)
を読んだときに思った。
天職という職業があるのではなく、
天職だと思える「瞬間」があるだけなんだと。
ツルハシブックスだってそうだ。
そこにお金が介在するか否か、というのは
たいした問題じゃない。
高校生の居場所が瞬間的に誕生し、
そして、その場に居合わせたとき、
店員の役を演じ切れたとき、
それは、自分にとっての「居場所」でもあり、
そして「天職」であるのかもしれない。
だから。
もっともっと、瞬間を大切に、心をこめて、劇場化していこうと。
11月3日~5日
ツルハシブックス・ラスト3DAYS、始まります。
2016年10月26日
海面下の絶景

「コミュニティ難民のススメ」(アサダワタル 木楽舎)
連日お送りしてるこの1冊。
やっぱり今日もシビれました。
よくぞ、このタイミングで、この本を、という感じ。
甲府・春光堂書店さん、本当にありがとうございます。
~~~ここから一部引用
コンサートに行く人の日常は、
一体いつの時点から非日常へと切り替わっているのか。
当人がこの非日常な感覚を日常の中で意識的にコントロールできるのであれば、
目の前の現実を直接変えずとも、より豊かな人生を獲得できるのではないか。
日常/非日常の「/」の存在は、
そもそも固定しているものではなく、相対的なものだ。
この「/」の位置が編集によって決まるのであれば、
「日常」とは、「無意識に編んだ刺激のない編集結果」であり
「非日常」とは、「意識的/無意識的問わず、
その編まれた日常の意味を違う文脈に再編集した結果であると
言えるのではないだろうか。
「日常を再編集する」という行為の先には、
実は既存の専門性や常識で覆い隠されていた
新たな価値観の発掘、異なるコミュニティ同士の接続、
公私の編み直しなどを伴う可能性を存分に秘めているのだ。
ほとんどの人びとが現われの空間(人びとが行為と言論によって
互いに関係し合うところに創出される空間)に生きていない。
ハンナ・アーレント「人間の条件」
ある人は「何」という位相に関するかぎり、
他の人びとと交換可能である。
「ほとんどの人びと現われの空間の中に生きていない」のは、
私たちがほとんどの場合、互いを「何」として処遇するような
空間のなかに生きているからである。
表象の眼差しで見られるかぎり、
私は、他者の前に「現われる」ことはできない。
表象が支配的であるその程度に応じて「現われ」の
可能性は封じられるのである。
現われの可能性を高めるために、私たちがやるべきこと。
それは〈島〉の上に現れている一見してわかりやすい専門性を
便宜的に盛り込みながらも、一方で〈海中〉から
掬い上げてきたコンセプトまでもしっかりと「現」していくことではなかろうか。
「現われの空間」は、「誰」へのアテンションが、
「何」についての表象によって、完全には廃棄されていない
という条件のもとで生じる。
それは予期せぬことへの期待が存在するという意味で、
ある種の劇場的な空間である。
そこには、個々のパフォーマンス(言葉や行為)に
おける他者の現われに注目を寄せる「観客たち」が居合わせている。
そしてある時、〈小舟〉(筏)から身を放つことによって、
〈海面下〉では、〈島〉と〈島〉が緩やかにつながり合っている
という景色を発見してしまう。
ただでさえ不安定な漂流生活を送っているにもかかわらず、
されに身を挺して〈素潜り〉までしないといけない。
しかも、〈海中に潜りながらの表現〉は一見わかりにくいため、
「弱い現われ」しか伴わない。
いったい何をやっているのか。認識されるまでに時間がかかるし、
なかなか理解を得られないだろう。
心が折れてしまうかもしれない。
でも、〈海面下〉の世界には、
これまで見たことのない素晴らしき絶景が広がっている事実を
確かに知ってしまった今、もう後戻りはできないのだ。
こうして獲得した地平とともに、
自分の存在価値を徐々に受け入れ始める。
〈海中の表現〉は、やがてじわじわと〈島〉の日常を
足下から変えてゆく。
そう、「難民」だからこそ伝えることができる、
〈島〉と〈島〉との新たな関係性を〈海面上〉にあぶり出すのだ。
こうしてようやく
「個人の生産活動において、
特定の分野のコミュニティに重点的に属さず、
同時に表現手段も拡散させることで、
新たな社会との実践的な関わりを生み出す人々」
となることができるのである。
~~~ここまで一部引用
そう。
そうそう。
「海面下の絶景」を知ってしまったんだ。
表象化・言語化できないほどの絶景を見てしまったのだ。
これだ!
と思える美しい瞬間に立ち会ってしまったんだ。
それを海面上にどう見せていくか。
それが、
「作品」と呼べるような仕事につながっていくのかもしれない。
ツルハシブックスはやっぱり、本屋ではなかったし、
本屋業界のコミュニティにいるときの、
何とも言えない居心地の悪さは、
「コミュニティ難民」への萌芽だったのだろうと思う。
読めば読むほど、素敵な本だなあ。
2016年10月25日
「公私」の隙間を、自らの肩を脱臼させて、潜り抜ける

「コミュニティ難民のススメ」(アサダワタル 木楽舎)
朝の電車50分が楽しくなる1冊
もったいないので1章ずつ読みますね。
第4章 「公私を編み直す」
いいですね。
編み直すっていうのがいい。
公私混同とか公私混合とかっていうけど、
そうじゃなくて、もっと主体的に「編み直す」っていうのが
いいのだよなあと。
ここでの登場人物は、梅山晃佑さん。
大阪で、広く「働き方」を表現・サポートしている。
第4章にもシビれまくりました。
~~~ここから一部引用
彼は、世の中の就労支援のほとんどが、
自分を社会の常識へと合わす方向だけであることに違和感を表す。
無理して社会に合わせなくてもいい、
時には自分が生きやすい仕事のあり方を見つけるところから始める。
「アートやまちづくりの活動に関わったりする中で、
世の中には名前のない職業に就いている人がそれなりにいて、
しかもみんな何だか楽しそうに働いていることを知りました。
学校の授業では、そんな人たちの存在を誰も教えてはくれなかった。
だから、僕は、『何か既存の職業に就かないといけない』
と思い詰めて辛かったんだと。
みんながそうすればいいわけではないけど、
多くの人が働く民間企業が向いていないなら、NPOで働く選択肢があってもいい。
とにかく、もっといろんな働き方のバリエーションを社会に
可視化していく必要があると思うんです。」
そもそも「公私」という考え方自体がピンとこない
「よく、仕事の延長上でプライベートでもそういう活動をやっていると思われるんですけど、
『延長』ではなくて『並列』なんです。そもそもどこからがプライベートでどこからが仕事か
という感覚自体がないので、やっていることの一つひとつが、あくまでフラットにマッピング
されているんです。(中略)それが世間の基準でいえば、たまたま
『ここからが公で、ここから私』となっているだけなんだと思います。」
いま、仕事をしていてどこか生きづらさを抱えているのであれば、
社会に自分を合わすのではなく、自分の生きやすさをちゃんと見つめて、
そこから逆算して自分に合った働き方を考えていく。
このときにもはや「公私」という区分はあまり意味をなさないと思っているんです。
まるで壁と壁の細い隙間を、自らの肩を脱臼させて潜り抜けるような
彼の有りようは、公私という発想自体が、
そもそも社会に「合わせた」通念であることを気づかせてくれる。
「社会に合わせて仕事をするのではなく、
自分が生きやすいように、自分に仕事を合わせていく働き方」
のために、「自分の内なる声に耳を澄まし、その声を解放すること」
既存の就労支援のサービスというのは、
基本的に自分を社会に合わせるというアプローチなんです。
でも、本人と社会との相性が明らかに悪いのに、
なんで無理に社会に合わせて支援しないといけないのか。
「そういうもんだ」的な漠然とした常識に違和感を持ったり、
そこに生きづらさを感じたりする時に、その人の中で内なる声が生まれる。
その時に、それをちゃんと受け止めてあげる就労支援も絶対に
必要だと思うんです。
内なる声はよほど耳を澄ませないと聞こえてこない。
相談する人も、相談員も、みんな表に出てくる言葉に囚われてしまう。
求人情報の「どの部分」に引っかかってきたのかを
ときほぐしていく。
自分がどのように生きたいか、という問いが先にあって、
そこから逆算して働き方を考えていく。
僕がコミュニティ難民として紹介する人たちは、
やっていることがコロコロ変わりすぎていて、
一見、単なる「器用貧乏」や「根無し草」として
見なされる傾向がある。
しかし、表面に現れる職歴の前に、実は
「内なる声への応答の履歴」が存在する。
重要なのは、他者に対しても、自分自身に対しても、
この「生歴」とも言える存在の現れをつぶさに感じることだ。
私たちは人生の過程において、
どの時点でも完成形の存在ではない。
私たちの身体は常に新陳代謝を繰り返し、
私たちの思考は常に新しい情報を摂取しながら作動している。
しかし、自らの意志や指令を発意するためには、
それを限定的な時間と空間の中で表現しなければならない。
実際には流動的に生成変化し続ける思考を
断片的に切り取り、固定化を行う必要がある。
つまりプロセスの大部分が
捨象されたかたちでしか、私たちはお互いのことを知りえない。
人はお金だけじゃないいろいろな価値を稼いでいる。
それに対し意識的になることで生き方・働き方が変わるのでは?
「稼ぐ」にオフタイムはないのだ。
「いまこの瞬間も自分は動き何かを常に稼いでいる」という意識の問題なのだ。
この意識をもった状態で考えると、「仕事」や「生活」や「趣味」といった
区分の間にあるボーダーが、とても曖昧に感じられてくる。
~~~ここまで一部引用
またしても、「著作権大丈夫か?」くらいに引用してしまったので、
このブログを読んだ人は必ず購入してください。(笑)
第4章もすごいですね。
自分を社会に合わせるのが生きづらいとき、
自分の「内なる声」に耳を傾けて、
どう生きたいのか?を考える。
そして、「公私」を編み直しながら、
自分の生き方を決めていく。
言うなれば、
「しなやかな生き方」とは、
公私の壁と壁のわずかな隙間を、自らの肩を脱臼させて、潜り抜けるような、
そんな生き方なのかもしれない。
(↑この表現好きだなあ。)
僕自身が個人的に、いちばんうれしかったのは、
「僕がコミュニティ難民として紹介する人たちは、
やっていることがコロコロ変わりすぎていて、
一見、単なる「器用貧乏」や「根無し草」として
見なされる傾向がある。
しかし、表面に現れる職歴の前に、実は
「内なる声への応答の履歴」が存在する。
重要なのは、他者に対しても、自分自身に対しても、
この「生歴」とも言える存在の現れをつぶさに感じることだ。」
あ、俺のことや~、みたいな(笑)
「内なる声への応答の履歴」
なんだなと。
応答し過ぎたかもしれないな、と。(笑)
これからはもっとしなやかに、
壁と壁のあいだを自らの肩を脱臼させて、
潜り抜けていきますね。
2016年10月24日
まるでCDのコンピレーションアルバムのように

昨日は、川崎・武蔵新城の
「プロジェクト3号室」のキックオフでした。
高校生にとっての第3の部活動をつくる。
それが大学生や20代にとっての部活になる。
「受益者」になるだけではつまらない。
「投資」じゃないと面白くない。
自分にとっても、他者にとっても、地域にとっても。
そんな、10年後に開けるタイムカプセルのような「場」をつくる
いいかもしれないなあ。
素敵な話ができました。
翌日(つまり今日)、電車の中で読んだこの本。

「コミュニティ難民のススメ」(アサダワタル 木楽舎)
2016年下半期、最高にシビれた1冊になりました。
新刊書店であり続けたいと思うのは、
このような、「この本を売らなければ」と思える1冊に出会えたとき。
甲府の春光堂書店さん、本当にありがとうございます。
ツルハシブックス閉店の3DAYSでは、
この本を30冊くらい取り寄せて、売りまくろうと思っています。
サイン、書きます。僕のサインですが(笑)
「コミュニティ難民のススメ」です。
結論から言えば。(笑)
この本の定義によれば、
(詳しくは本書の32ページ)
個人の生産活動において、
特定の分野のコミュニティに重点的に属さず、
同時に表現手段も拡散させることで、新たな社会との
実践的な関わりを生み出す人々
のことだという。
つまり、1つのコミュニティの中の人になるのではなく、
いろんなコミュニティの狭間に生きたりする人のこと。
それは自分の感性の発動によって、
必然的に起こるのかもしれないと。
まだ、実は第3章までしか読んでないのだけど、
銀行員、建築士、宿屋の主人と、
越境する仕事や活動をしている人たちの事例と言葉にシビれまくります。
さて、今日は、さっき読んだばかりの
第3章の山中湖のほとりで「ホトリニテ」という宿をやっている
高村さんの話から。
~~~ここから一部引用
でも、ずっと関わってきた音楽を、
急に明日から「趣味」に切り替えるなんてことが、
本当にできるのだろうか?
物理的には、確かに音楽での収入はなくなり、
またそこに割いてきた時間も大幅に減るのかもしれない。
とはいえ、きっと目には見えない、
身体の奥底にある表現的感性は、
そんなに簡単に消えるものではない。
次に始める仕事の各要素に
これまで稼いできた表現的感性を
存分に埋め込み、まったく新しい表現=仕事
を確立している人たちも存在するのだ。
「うちは、素泊まりの宿にずっとこだわって来たんです。
なぜなら、ここで商売を完結するのではなく、
お客さんをこの地域のいろんなお店につないでいきたいから。
いかに山梨を楽しむかってことを伝えるのも話芸だし、
そして他のお店から帰ってきたお客さんのレスポンスをどう受け止め、
さらにこの地域の魅力を伝えることができるかも僕の芸のうち。
そういう意味では、地域のハブとしての機能を果たし続けることを意識してますね。」
「宿業」という職業像を変える。
「宿にこそ、冗談を」
「何が起きても、許せるよ」
僕の中では、面白い宿をつくっているというよりは、
未だ見ぬ、定義され得ない場をつくっている感じ。
そういう心持ちでないと、宿芸の極みには、辿り着けない。
宿主だって、まったく新しい価値や専門性を提示できる職業になれるはずでしょう。
僕はあくまで宿の経営者として世に出たいのではなく、
宿芸人としてのプロフェッショナルを追求していきたい。
ナオキが目指しているのは、音楽で言えば、
「いまこういうジャンルが出て来たらしいよ」というニュアンスよりは、
もはや「音楽なのかどうかもわからない何か」を目指す表現のあり方だ。
その感性を宿業という日常的な職種に置き換えれば、
自分の持つ専門性や、いまこの場で発生している
あらゆるコミュニケーションの一つひとつに対する
解像度をぐっと上げて(ズームイン)いきながら、
そこでピントに合わせて芸を埋め込み、
そして再俯瞰化(ズームアウト)して確認すれば、
「もはやそれは宿なのか!?」という状況を表す。
世間一般で言われる、芸がある、芸が細かいという言葉は、
表現活動を本気で通過してきた高村直喜にとっては、
とてつもなくリアリティを伴う言葉なのではないだろうか。
ラジオや地域サロンが「本業」とは言えないかもしれない。
しかし、こうしたアウトプットによってしか伝わらないことや、
繋がれない相手がいることは確かだ。
まるでCDのコンピレーションアルバムのように、
アート的なるまなざしを編集し、パッケージングすることは、
今、目の前にある日常や仕事に対する審美眼を
肥やすためのレッスンとして有効であったと実感している。
そう、あなたが今暮らすその生活や働く職場にだって、
あらかじめ何かしらの表現の種子が埋め込まれているのかもしれないのだから。
その種子を発見して誰かに伝えることは、
場合によっては、自分の価値観を理解してもらえない
戸惑いを助長してしまうかもしれない。
でも、その時に、その内的難民性を理解してくれる仲間たちが
津々浦々、多(他)分野に存在することを思い出してほしい。
そして、いつか必ず仲間たちとの出会いを
果たすときが来ると希望を持ちつつ、
どうかその気づきから生まれる新しい生き方・働き方を、
迷いながらも肯定してほしいと、心から思うのだ。
~~~ここまで一部引用
もうね、わーーーって叫びたい感じですよ。
よくぞこの本をこのタイミングで目の前に持ってきたなと。
ツルハシブックス閉店のメッセージとは、
一言でいえば、「コミュニティ難民のススメ」
なのかもしれない。
ツルハシブックスというコミュニティは解散し、
ひとりひとりは「コミュニティ難民」になる。
(本書で使われている意味合いとは違うけど)
でも、それは、
ひとりひとりにとって、
「生きる」の振り出しに戻ることではないだろうか。
「コミュニティ」は安心感をくれる。
しかし、そこにとどまっているだけではいけないのだ。
無数の第3の場所を、第3の部活動を、
自分の感性の発動に従って、つくっていくことだ。
そして、越境し、コラボレーションし、
CDのコンピレーションアルバムのような場を、空間を、時間を
つくっていくことだ。
これからつくられるコンピレーションアルバムに、
「ツルハシブックス」という曲が入っているかもしれないと、
祈りを込めて、11月3日~5日ラスト3DAYS、この本を売ります。
2016年10月23日
「なにモノかにならねばならない」という呪縛

「コミュニティ難民のススメ」(アサダワタル 木楽社)
甲府の春光堂書店で購入。
いい本あった。
旅先で出会う本って運命を抱えているような、
そんな気がする。
もう「はじめに」からシビれることばっかりだ。
子どもの頃、「将来の夢はなんですか?」
と聞かれることがとても苦手だった。
から始まる。
~~~ここから一部引用
もちろん夢を持つこと自体を、
あからさまに否定しようとは思っていない。
問題は、大人たちが子どもたちに対して、
求めてくる夢がイコール「なりたい職業」という、
暗黙の前提があることに違和感を抱いてきたのだ
その前提を子どもたちは無意識に受け取り、
周囲から浮いてしまわないように、
徐々に「スタンダードな夢の持ち方」を
心がけてしまうようになるのかもしれない。
例えば、作文で「野球選手になりたい」と書くことは夢とされても、
「ずっと好きな野球を続けていきたい」と書くことは夢として
認められにくいのだろうか。
あるいは「宇宙飛行士になりたい」は夢で、
「いつか宇宙船に乗ってそこで生活をしてみたい」だとどうだろう。
思うに、夢というのは、なりたい職業や仕事に関することに
限られるものでは決してないはずだ。
むしろ、こうなりたいではなく、こうありたいと
願うことも夢として受け入れられてもいいだろう。
もちろん僕自身も含めて、
子供の頃にそこまで突っ込んだ疑問を
言葉にできるわけではない。
でも、世間から認められる
「なにモノかにならねばならない」
(別に有名になるといった意味ではなく、既存の職業とかに)
という強迫観念を知らず知らずに刷り込まれ、
「こういう状態=コトでありたい」と願う
思考回路の芽が自然と摘まれてしまう状況に対して、
もっと芽を向けてもいいのではなかろうか。
(中略)
この本は、これまで自分が「なにモノ」でもなく、
「なにモノ」にもなれず、だからこそ「なにモノ」かに
ならないといけないという周囲からの要請に抗い続け、
フワフワした希望と葛藤の狭間を生き、働き、表現をしてきたことに対して、
答えを出すために書くものだ。
~~~ここまで引用
とこんな感じで始まる。
そうそう、そうそう!
みたいな。
僕がこの箇所を読んで思ったのは、
「なにモノかにならねばならない」っていう呪縛は
本当に大きいと思う。
何屋さんなのか?
本業は何か?
と僕も20代のときに問われ続けた。
5年前に「本屋」という肩書を手に入れたとき、うれしかった。
「内野で本屋さんをやっている」と
初めて既存のカテゴリーに入る、
他者に説明できる仕事ができた。
まあ、それも今はまた、手放すのだけど。
まつもと空き家プロジェクトの東さんと話していて、思ったのは、
いろんな地域活動をしていると、
「あの」活動をやっている誰かになるのだという。
でも、あたりまえだけど、
中身は変わってなくて、単なる一女子大生だったりする。
なにモノになってみて、初めて気づく、
なにモノでもないという感覚。
そして、ふたたびそれを演劇を演じるように手放し、
次の「なにモノ」をまたつくっていくこと。
これからの時代の生き方はそのようになっていくのではないか。
なにモノかであらねばならない、からの卒業。
それが人生の出発点になる。
2016年10月21日
直感知を積み重ねる

「日本の反知性主義」(内田樹編 晶文社)
引き続き、この本より。
「身体を通した直感知を 名越康文×内田樹」から。
~~~ここから引用
ものを学習していったり、
物事の論理性や関係性を発見したり、
現象の背後にある法則を発見したりというのは、
ただデータを積み重ねていってできるというものでもない。
「あ、わかった」と瞬間的に視界が開けるものじゃないですか。
知性の活性化・高度化って、
ものの考え方の構造そのものを作り変えて、
思考のシステムを再組織化することじゃないですか。
今すでにあるものを局所的に強化することとは全然違う。
今ある仕組みを手つかずにしておいて、
局所だけ量的に強化すれば、むしろシステムは硬直化する。
使いものにならなくなる。
「頭のよさ」って、結局は「頭がしなやか」ということなのに。
検索ってキーワードを知らないとできないじゃないですか。
だけど、僕らが今考えているような知というのは、
キーワードがなくても、何を自分は知ろうと思っているのかわからなくても、
突然「これだ」ってわかる。
それを知るためにこの本を読んでいたのだということが
読んでいくうちにわかる。読み始めた時には、
自分が何を求めてその本を手に取ったのかわからなかったのに、
読んでいるうちにわかる。
それが可能なのは、情報を入力するたびに、
一行読み進むたびに頭の中の仕組みを
どんどん組み換えているからですよね。
知性の運動というのは、
必ず集団的、共同体的に働くということが忘れられてるんじゃないかな。
単独の知性というのは存在しないんです。
知性は必ず他の知性との相互関係の中で活動する、
本質的に共同的、集合的なものだと僕は思うんです。
~~~ここまで引用
そうそう。
予測不可能な学びが楽しくて、
地域活動っていうのがあるのだと思うなあ。
そういう直感、直観を磨くこと。
ここに学びの本質があるように思います。
2016年10月20日
ガキの金メダル

「日本の反知性主義」(内田樹編 晶文社)
いやあ、面白い。
面白くて、一章ずつ読みたくなります。
毎日電車に乗れるって素晴らしい。
今日は小田嶋隆さんの
「いま日本で進行している階級的分断について」
頭のいい人ってどうしてこんなに
たとえ話が上手なんだろうって。
小田嶋さんは、
俗にいわれる「ヤンキー論」をバッサリ切り捨てる。
そして、優等生である「出来杉君」とそれ以外の「ヤンキー」
を題材に、このように言う。
~~~ここから引用
小中学校の時代に勉強ができたかどうかは、
後の人生に、決定的な影響を及ぼす。
出来杉君は優等生として高校、大学に進学し、
主としてホワイトカラーとして職に就く。
その間、出来杉君の人生観に大きな変動は無い。
彼らは、子供時代そのままの、
「人間の価値を決めるのは頭の良さだぞ」
という価値観を、牢固として抱いたまま大人になる。
ひるがえって、成績の良くなかった組の子供たちは、
思春期を迎えるや、そそくさと変身を果たす。
具体的には、自分を低く評価した「学校」なり、「世間」なり、
「体制」なりを否定する視点から、自他を再評価しにかかるのである。
彼らはある日、
「おい、百点なんてのはガキの金メダルだぞ」という衝撃的な事実に
突然、気づくのだ。
「この支配からの卒業」と尾崎豊は歌ったが、
学歴的諸価値から解放されたヤンキーの少年は、
その時点から、別の人間になる。
彼は、盗んだバイクで走り出すことはしないまでも、
ともあれそれまでとは別の足取りで、別の人生を歩み始める。
まずてはじめに、自分に特有な「価値」を模索する
作業をスタートする。
ある者は、クラス全員を笑わせることに狙いを絞り、
別の子供は腕っぷしで仲間を圧倒する作業に力点を置く。
どんなタイプのゴールを設定するにしても、
彼らが、ある段階で、偏差値競争から「降りた」ことは間違いない。
「学歴競争から降りる」ことについての見方は、
出来杉君とヤンキー層で、はっきりと違っている。
出来杉君は「脱落」と見なし、
ヤンキー層の多くは自分が敗北したとは考えない。
脱落したとも思わない。
「くだらねえから降りた」
「ダルいから勉強なんてやめたぜ」
「いい子ちゃんやってるのもいいかげんウザいからバイバイした」
というふうに、彼らは、自分が競争から降りたことを、肯定的にとらえている。
「ってか降りたっていうより別のステージに乗り換えたんだけどな。」
ぐらいな力加減だ。
この時点で「ヤンキー」の側の少年たちが獲得することになる
「非学歴的な価値観」を「学歴的な価値」の信奉者である
出来杉君たちが、
「ヤンキー美学」ないしは「ヤンキー主義」と呼んでいるというのが
ヤンキー論の実態なのだと私は考えている。
出来杉君の側から見れば、
「ヤンキー」は、なんだかいつも群れていて、
型にハマっていて、見え透いていて、個体識別のむずかしい、
単純で没個性なアタマの悪い人々ということになる。
じっさい、ヤンキー論の細部はほぼその種の記述で埋まっている。
が、「ヤンキー」の側から見た「出来杉君」は、
出来杉君から見たヤンキー以上に型にハマった、ガチガチのロボットだったりする。
なにしろ、小学校の時からものの見方が変わっていないのだからして。
~~~ここまで引用
いいですね、これ。
学歴信仰、競争幻想に憑りつかれてしまうと、
一生勝ち続けなければならない。
しかもそれは、単一の、他者からの評価によるものである。
それをいつかのタイミングで、
「次のステージ」に乗り換えること。
これが、人生においては必須だなあと思う。
そして、カッコよく見える大人には、
そのような「ステージを乗り換える瞬間」
があったのではないか。
それは別に学歴競争からドロップアウトしたからではなくて、
この先には、自らの幸せはない、と感じた瞬間、
次のステージを探す旅が始まり、
たどりついたのだろうと思う。
そんな旅のはじまりをつくる本屋でありたいなあと
強く思った。
素敵な一節をありがとう。
2016年10月19日
「リスペクト」なき国

「日本の反知性主義」(内田樹編 晶文社)
難しいっ。
けど面白いなあと。
知的好奇心をくすぐられる1冊。
今日は白井聡さんの「反知性主義、その世界的文脈と日本的特徴」より
~~~ここから一部引用
「日本社会は同調圧力が強い」といわれるが、
何に同調させられているのか?
その核心にあるのは、「敵対性の否認」にほかなるまい。
このことは、明治以降の近代化に始まり、
敗戦を契機とする民主化が行われても、
依然として日本国家が契約国家(社会契約に基づく国家)
になり切っていないことと関係している。
要するにこの国には「社会」がない。
社会においては本来、その構成員のあいだで
潜在的・顕在的に利害や価値観の敵対関係が
存在することが前提されなければならない。
しかし、日本人の標準的な社会観にはこの前提が存在しない。
そうでなければ、「社会」という言葉と「会社」という言葉が
事実上同義で使われるという著しい混乱が生じるはずがないのである。
(「社会人」とは実質的に「会社人」を意味する)
あるいは「権利」も同様である。
敵対する可能性をもった対等な者同士が
お互いに納得できる利害の公正な妥協点を
見つけるためにこの概念があるのだとすれば、
敵対性のない社会にはそもそもこの概念が必要がない。
ゆえに、社会内在的な敵対性を否定する
日本社会では「正当な権利」という概念が根本的に理解されておらず、
その結果、侵害された権利の回復を唱える人や団体が、
不当な特権を主張する輩だと認知される。
ここではすべての権利は「利権」にすぎない。
(中略)
「貴方のためなのよ」という母親が
しばしば子に対して発する言葉は、
支配の欲望を実現しつつ隠蔽するものであるが、
それは戦前戦中の思想検事の論理をぴたりとなぞっている。
そこでは温情と拷問は、いずれも、
思想犯の主体性を無化する、主体として思考することを
不可能にする手段としてコインの裏表をなしていたのであった。
~~~ここまで一部引用
なるほどなあ。
「孤独と不安のレッスン」や「空気と世間」の鴻上さんのいう
日本社会についての記述としてはうなるばかりだ。
社会システムとして、主体性が育たないように
しておきながら、
いまさら「主体性が大切だ」とか言っているんです、
我が国は。
ひとりひとりを個人として、リスペクトすること。
まずはそこから、ですかね。
2016年10月18日
「知性」はフライングする

「日本の反知性主義」(内田樹編 晶文社)
先週の「街場の憂国会議」につづいて。
冒頭の内田さんの
「反知性主義者たちの肖像」から、面白い。
「反知性主義」というのは、まさしく思考停止のことであり、
人類史上最悪の「反知性主義」とは、
フランス革命の原因はユダヤ人であるとした、
エデュアール・ドリュモンによるものだという。
まあ、それはおいといて。
興味深いのは、
「知性」と「時間」についての記述。
~~~ここから引用
私たちはその解法がわかっているものを
「問題」としては意識しない。
またその逆に、その解法がまったくわからないものを
「問題」としては意識しない。
私たちが「これが問題だ」と言うのは、
まだ解けていないが、
時間と手間をかければいずれ解けることが直感されているものだけである。
私たちの知性は、自分がまだ解いていない問題について、
「まったく解けない」のか「手間暇さえかければ解ける」のかを
先駆的に判断している。
私たちの知性はどこかで時間を少しだけ「フライング」することができる。
知性が発動するのはそういうときである。
まだわからないはずのことが先駆的・直感的にわかる。
私はそれが知性の発動の本質的様態だろうと思う。
(中略)
このような「対象へののめり込み」は、「ずばり一言で言えば」
というシンプルな説明を求める知的渇望とは似て非なるものである。
どちらもランダムな事象の背後に存在する数理的秩序を
希求している点では変わらない。
でも、一点だけ決定的に違うところがある。
それは、先駆的直観には時間が関与しているしていることである。
自分がある法則を先駆的に把持しているところはわかるけれど、
それをまだ言葉にできないときの身もだえするような
前のめりの構えにおいて、時間は重大なプレイヤーである。
(中略)
「私が見ているものの背後には美しい秩序、驚くほど単純な法則性が
存在するのではないか」という直観はある種の「ふるえ」のような感動を
人間にもたらす。
その「ふるえ」は、その秩序や法則を発見した「個人」が名声を得たり、
学的高位に列されたり、世俗的利益を得たりすることを期待しての「ふるえ」とは違う。
(中略)
ひとが「ふるえる」のは、自分が長い時間の流れにおいて、
「いるべきときに、いるべきところにいて、なすべきことをなしている」
という実感を得たときである。
「いるべき」ときも、「なすべき」わざも、単独では存在しない。
それは死者もまだ生まれぬ人たちをも含む無数の人々たちとの
時空を超えた協働という概念抜きには成立しない。
もう存在しないもの、まだ存在しないものたちとの協働関係という
イメージがありありと感知できた人間のうちにおいてのみ、
「私以外の誰によっても代替し得ない使命」という概念は受肉する。
~~~ここまで引用
うわあ!!
って叫びたくなるような一節でした。
そうそう、それ!!
コメタクとかってそれだわ。
たぶん、米屋と本屋、なんですよ。
でもそれはまだ説明ができない。
でも、自信というか確信というか
そういうのがあるよね。
あ、それを直感っていうのか。
まあ、そんな知性の発動をいていきたいなあと思いました。
この部分だけでも、この本を買う価値があると思います。
2016年10月17日
「株式会社」という生き物

「街場の憂国思想」(内田樹編 晶文社)
読み終わりました。
上田のNABOに続編が2つともあってすごいなあと思いました。
買っちゃいました。
前回のブログに続き、
http://hero.niiblo.jp/e482402.html
平川克美さんの
「オレ様化する権力者とアノニマスな消費者」より、
「株式会社」についての記述より抜粋
~~~ここから引用
たとえば、世界史的な歴史の発展段階で生まれてきた
株式会社というシステムは、成熟段階においては本質的には存在理由を失います。
なぜなら、経済成長せず、株価が上がらないとすれば、
誰も株に投資しなくなってしまい、株式会社というシステムの根本が崩れてしまうわけですから。
もちろんこれには本質的にはという留保が付きます。
グローバリズムが生まれてくる背景には、成熟国家における株式会社というものが、
国民国家ベースではもはや存続できないということがあります。
世界はまだら模様に発展段階の国家と、成熟段階の国家が存在しているので、
国境を取り払えばまだまだ株式会社が生き残る余地があるわけです。
株式会社は今後生存をかけて国民国家を打倒して
グローバル化した市場を作り出そうとすることになるでしょう。
しかし、人間が生きていくためのひとつの装置として
株式会社システムが生まれたのであって、
株式会社が生き残るためにわたしたちがあるわけではありません。
もうひとつ注目したいのは、
世界の市場化は、大量のアノニマスな(匿名の)消費者を
生み出すということです。
その結果、商品交換の場は、広く大きく、簡便なものになっていきます。
そこでは、消費者は売り手と面識もなく、会話も不要な、
顔のない貨幣運搬人に限りなく近づくしかありません。
コンビニエンスストアにおいて、対面している
売り手と買い手の関係はまさに、このアノニマスな消費者社会の
先駆的なかたちだったわけで、インターネット空間は、
市場のサイバー空間への拡大と消費者のアノニマス化に
拍車をかけたわけです。
(中略)
ここで、私が強調しておきたい、大切なことがあります。
それは、上記のような近代化、消費化のプロセスの中で、
生活者の思想というもの失われていったということです。
60年代、70年代に、近代化のプロセスの中で、
知識階級は欧米の思想を学習し、
普遍的な価値を作り出そうとしてきたわけですが、
知的な上昇過程に対置するように、生活の思想というものがありました。
それは、肥大化する観念に対置する暮しの思想であり、
大事よりも些事を積み重ねることを重視し、
ひとりひとりが日々の暮しのなかでの義務と責任を
果たすことのなかから強固な生活思想というものを作り出してきたわけです。
40年代後半に生まれ、50年代に広範な読者を獲得した
花森安治の「暮しの手帖」なども、こういった生活思想
を背景に生まれたものでした。
(中略)
生活思想とは、ひとりの人間で言えば、身体のようなもので、
身体性を失った思想はどこまでも観念の領域で肥大化することが可能です。
生活思想は、宗教やイデオロギーといった
観念的なものと異なって、世界の生活者を結びつけることになるのですが、
宗教やイデオロギーはむしろ差異を強調します。
~~~ここまで引用
なるほどな~。
株式会社は、発展途上段階にのみ有効な、あるいは機能するシステムなのであって、
国民国家が成熟段階に入ると、
「株式会社」そのものの延命のために、
発展途上の場所を探して、多国籍化、グローバル化せざるを得ない。
また、
金曜日に書いたように、
「株式会社」というシステムはひとりひとりの当事者意識を下げるように、
構造されているのと、
高度になればなるほど匿名性が増していき、
「消費者」は「貨幣運搬人」にかわっていく。
その危機感なのか、
本質的価値の追求は本能なのか、
「生活思想」が生み出され、それが「暮しの手帳」などにつながった。

15日、コメタク改装記念パーティー
もしかしたら、
コメタクってそういう意味なのかもしれないですね。
生活の思想。
そんなものをもういちど表現したいのかもしれません。
それは、本屋だけではできないのかもね。
2016年10月14日
「株式会社」という仮説

「街場の憂国会議」(内田樹編 晶文社)
2014年5月、
特定秘密保護法の成立を契機に出版された1冊。
いつも読むの遅くてすみません。
近くにいい本屋があれば。
って2014年5月はまだ現役の本屋だったか。
晶文社さん、ごめんなさい。
まずは内田さんの
「株式会社」化する国家について。
これ、面白いなあ。
某総理大臣や某市長が「株式会社」のように決断できる政治、
トップダウンな体制を目指しているのに対して、鋭く迫る。
まずは「株式会社」ってなに?
っていうところから。
これが意外とコワイ話。
~~~ここから一部引用
株式会社の原型は1602年の
オランダ東インド会社から始まる。
ほとんどが準国家組織であったが、
これが株式会社の原型とされるのは、
このとき歴史上初めて
「株主有限責任の法則」が確立したからである。
それまでの個人と個人の間では、
因習的に与えた損害に対する弁償は、
無限責任とされた。
いわゆる「目には目を、歯には歯を」である。
ところが株式会社では、
株主は、会社がどれほどの損害を出そうと、
どれほどの災厄を撒き散らそうと、
自分の出資分以上の責任を問われることがない。
このようなルールはそれまで人間社会には存在しなかった。
有限責任はいずれ支払い保証のない危険な信用を作り出し、
それが過剰取引や詐欺や賭博的投機を呼び込むのではないか、
そのような懸念は株式会社の黎明期からすでに多くの経済学者から
表明されていた。
しかし、産業革命とともに、
薄く広く多額の出資をかき集めなければならないという
資本の要請が生じ、それは株式会社という形態にみごとに適合した。
そのようにして、
詐欺と過剰な投機を抑制するために存在した
株式会社への法的規制が次々と廃止された結果、
株式会社は今日の隆盛を見るに至ったのである。
~~~
内田さんが、前提として確認したいことは二つだ。
1 株式会社は人類の歴史、経済史から見ても、
「ごく最近」になって登場してきたものであること。
そして、登場のとき「有限責任」という概念に強い違和感を
覚えた人たちがたくさんいたということ。
2 株式会社が一気に支配的な企業形態になったのは、
産業革命期に、「短期間に、巨額の資金を集める」
必要が生じたためである。
それまでは、「知っている人間」から「返済可能な額」の
出資を募っていたのが、「知らない人間」から
「破産しても返済できない額」の出資を募ることが
ビジネスのデフォルトになった。
だから株式会社という仕組みは、その成り立ちからして、
生身の人間の生活空間と生活時間の尺度となじまないのである。
なるほど。
そして、
奥村宏さんの言葉を借りて、
「有限責任とは、自らが負うべきリスクをほかの誰かに押しつけるもの」
なのだと。
このように出来上がった
「コスト外部化システム」が機能できたのは、
もちろん損失を「穢れ(けがれ)」として押し付けることができる
「外部」が存在したからである。
外部が存在する限り、コストの外部化は可能である。
かつては新世界が、続いて第三世界が、そして今は
地球の環境や資源が最後の「外部」となった。
それを蕩尽し尽くすまで株式会社は終わらない。
~~~ここまで一部引用
うんうん。たしかにそうだ。
そして内田さんは、
株式会社化する国家や、それを待望する人たちに対して警告する。
~~~ここからさらに引用
民主制というのは、「先のこと」を考えるための仕組みである。
人間の数だけ未来予測が違うから、あらゆる可能性を吟味する必要がある。
そして、もう論じることがない、といったときに、政策決定を行う。
その際に
「もしこの政策決定が間違っていても、それは議論に関わった
われわれ全員に多かれ少なかれ責任があり、それゆえ、
この失敗のもたらす災厄をそれぞれの割り前分だけ
引き受けなければならない」
と腹をくくるまで議論する。
民主制というのはそのための制度である。
もちろん、しばしば民主制は間違い、
不適切な統治者を選ぶ。
けれどその被害に対して、他責的になることは許されない。
民主制の成員たちは、
この災厄は「自分で招いたもの」だと
いうことを認めなければならない。
民主制はその点がすぐれている。
成功し続けるからではなく、やり直しが効くから
すぐれているのである。
かつての戦争で、大日本帝国は歴史的大敗を喫した。
けれどもその政策決定には、ほとんどの国民は関与できなかった。
国民の多くがその原因を「戦犯」に押し付け、
自らを被害者だと思った。
その大きな理由のひとつが
大日本帝国が民主制ではなかったからだ。
1945年まで日本が民主的な政体でなかったことの
最大の瑕疵は、非民主的な政体の下では、
政治的自由がなかったこととか、
言論の自由が抑圧されたことにあるのではない。
そうではなくて、
非民主的な政体が犯した政策上の失敗について
自分たちには責任がないと国民が思うことを
止められなかったことにある。
~~~ここまで引用
むむむ。
なるほど。
株式会社というのは、
ひとりひとりの「責任感」「当事者意識」を
無くしていく仕組みにそもそもなっているんだなあと。
そして、
国家の「株式会社」化とは、
戦争に突き進むことが危険なのではなくて、
(その可能性は増すのかもしれないが)
国民ひとりひとりが、
政策決定について、あるいは世の中についての
当事者意識を失うということを同時に意味しているのだろう。
400年の歴史でしかない、
「株式会社」の論理で、
国家が運営されていくことにも恐怖を感じるが、
何よりも、ひとりひとりが、
自らの生活を、人生を、人のせいにするような、
そんな世の中に生きたくはないな、と思った。
まだまだ読み進めます。
2016年10月12日
「直感」を信じる
「小商い」をやってみる。
これ、きっと大切。

1999年4月に新潟市西蒲区(旧巻町)でまきどき村を開始。
会員制度で「村づくり」を行うというもの。
※「DASH村」の放送スタートが2000年6月で、
「地図に名前を残す」などと、コンセプトがかぶっていた。
僕が農学部に進んだのは、
中学の時に見た大成建設の
テレビCM「地図に残る仕事」を
砂漠緑化で果たそうと思い、
鳥取大学農学部を志望したのが始まりだった。
その「地図に残る仕事」を
ふたたび思い出したのが「まきどき村」っていう
ネーミングだった。
当時原発問題がくすぶっていた
巻町議会(6月議会)でやり玉に上がり、
僕は8月に巻町に引っ越した。
一軒家で20,000円という民家を借り
水回りをちょっと工事して、
2000年1月には、
サンクチュアリ出版の書籍を扱う「本処くろすろうど」と
中学生高校生向けの私塾「寺子屋途輝(とき)」、
旅人達の宿泊施設「民宿まきどき」をスタート。
3つ合わせて、「朱鷺の波」(ときのなみ)だった。
東京・王子のカフェバー「狐の木」と
サンクチュアリ出版の影響が大きいな。(笑)
今風にカッコよく言えば、
「本屋と学習塾を併設したゲストハウス」
を立ち上げた。
うーん、早いね。先取りしてる。(笑)
まあ、売り上げとかもたいしたことなかったのだけど、
楽しくやっていたなあ。
「まきどき村」には県外からも僕の友達を
中心に遊びに来ていたから、そこそこ本も売れたので、
2000年11月に遊びに来たサンクチュアリ出版の鶴巻社長に
「営業やってみるか?」と言われて、
2001年2月からサンクチュアリ出版の地方営業をスタート。
といっても、新潟の本屋さんに空いた時間にコツコツ回って、
「この本が今の新潟に必要なんすよ!」ってシャウトするだけだった。(笑)
全然注文なんて取れないから、月給にして2万円とか3万円とか。
2000年に大学を卒業して、イベント企画会社に週3日だけ働くっていう
スタイルで社会人デビュー。
でも、そんな働き方が許されるはずもなく、先輩と合わずに7月に退職。
大学時代に学習塾のアルバイトのお金を
1円も使わずに貯めておいた200万円でなんとか暮らしてた。
2001年4月からは大学の先輩がやってる地ビール会社で
企画営業をやっていた。(こちらも週3日)
こちらはものすごく楽しかったのだけど、
ヒット商品の麻ビールとかを売っていたら、
忙しくなってきて、畑ができなくなりそうだったので、
12月に退職。
そして、その年明け、2002年1月。
会社を辞めて、超ヒマだった僕は、不登校の中学3年生、シンタロウに出会う。
まったくしゃべらなかった彼が、
だんだんと笑顔になっていく姿に、
「これはおかしい」
と思った。
だって、僕は27歳プータローだったから。
プータローが不登校の中学生を元気にするっておかしいだろ、って。
「ちょっと待てよ。」
直感した。
もしかしたら、そういう中学生高校生って世の中に
いっぱいいるんじゃないか。
いや、僕自身も、
そんな中学生高校生だったんじゃないか。
さびれた駅前商店街のたこ焼き屋のおばちゃんに
癒しの場を求めていたんじゃないか。
中学生高校生に「多様な地域の大人」を届ける。
をミッションとしたNPO法人虹のおとを設立。
ツルハシブックスへの旅は2002年から始まっていた。
つづく。
これ、きっと大切。

1999年4月に新潟市西蒲区(旧巻町)でまきどき村を開始。
会員制度で「村づくり」を行うというもの。
※「DASH村」の放送スタートが2000年6月で、
「地図に名前を残す」などと、コンセプトがかぶっていた。
僕が農学部に進んだのは、
中学の時に見た大成建設の
テレビCM「地図に残る仕事」を
砂漠緑化で果たそうと思い、
鳥取大学農学部を志望したのが始まりだった。
その「地図に残る仕事」を
ふたたび思い出したのが「まきどき村」っていう
ネーミングだった。
当時原発問題がくすぶっていた
巻町議会(6月議会)でやり玉に上がり、
僕は8月に巻町に引っ越した。
一軒家で20,000円という民家を借り
水回りをちょっと工事して、
2000年1月には、
サンクチュアリ出版の書籍を扱う「本処くろすろうど」と
中学生高校生向けの私塾「寺子屋途輝(とき)」、
旅人達の宿泊施設「民宿まきどき」をスタート。
3つ合わせて、「朱鷺の波」(ときのなみ)だった。
東京・王子のカフェバー「狐の木」と
サンクチュアリ出版の影響が大きいな。(笑)
今風にカッコよく言えば、
「本屋と学習塾を併設したゲストハウス」
を立ち上げた。
うーん、早いね。先取りしてる。(笑)
まあ、売り上げとかもたいしたことなかったのだけど、
楽しくやっていたなあ。
「まきどき村」には県外からも僕の友達を
中心に遊びに来ていたから、そこそこ本も売れたので、
2000年11月に遊びに来たサンクチュアリ出版の鶴巻社長に
「営業やってみるか?」と言われて、
2001年2月からサンクチュアリ出版の地方営業をスタート。
といっても、新潟の本屋さんに空いた時間にコツコツ回って、
「この本が今の新潟に必要なんすよ!」ってシャウトするだけだった。(笑)
全然注文なんて取れないから、月給にして2万円とか3万円とか。
2000年に大学を卒業して、イベント企画会社に週3日だけ働くっていう
スタイルで社会人デビュー。
でも、そんな働き方が許されるはずもなく、先輩と合わずに7月に退職。
大学時代に学習塾のアルバイトのお金を
1円も使わずに貯めておいた200万円でなんとか暮らしてた。
2001年4月からは大学の先輩がやってる地ビール会社で
企画営業をやっていた。(こちらも週3日)
こちらはものすごく楽しかったのだけど、
ヒット商品の麻ビールとかを売っていたら、
忙しくなってきて、畑ができなくなりそうだったので、
12月に退職。
そして、その年明け、2002年1月。
会社を辞めて、超ヒマだった僕は、不登校の中学3年生、シンタロウに出会う。
まったくしゃべらなかった彼が、
だんだんと笑顔になっていく姿に、
「これはおかしい」
と思った。
だって、僕は27歳プータローだったから。
プータローが不登校の中学生を元気にするっておかしいだろ、って。
「ちょっと待てよ。」
直感した。
もしかしたら、そういう中学生高校生って世の中に
いっぱいいるんじゃないか。
いや、僕自身も、
そんな中学生高校生だったんじゃないか。
さびれた駅前商店街のたこ焼き屋のおばちゃんに
癒しの場を求めていたんじゃないか。
中学生高校生に「多様な地域の大人」を届ける。
をミッションとしたNPO法人虹のおとを設立。
ツルハシブックスへの旅は2002年から始まっていた。
つづく。
2016年10月11日
「利潤」は差異からしか生まれない
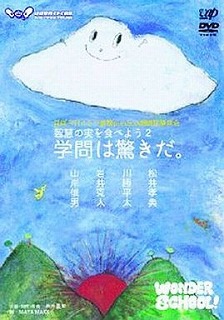
「智慧の実を食べよう 学問は驚きだ」(糸井重里 ぴあ)
冒頭の岩井克人さんの「会社の行方」。
いいですね。
これ本質的です。
会社はだれのものか?
ということでアメリカ型の株主中心のと
日本型の従業員中心の会社に言及し
もともと会社は二階建てだと主張。
そして、
産業資本主義からポスト産業資本主義へ。
ということで、
いま、何が起こっているのかを語ります。
まあ2004年の本なので。
ここで一番おもしろかったのは、
いろんな本で書いてあるのがこちらでも出ているということ。
~~~ここから一部引用
もともと、利潤は差異からしか生み出されません。
産業資本主義というのは、
「多数の労働者を使って、大量生産をおこなう
機械制工場システムにもとづく資本主義」のことです。
もちろん、単に工場があっても、
それだけでは、利潤は生まれません。
あたりまえですが、費用が収入より低くないといけないわけですが、
それは結局、労働者の賃金がその生産性よりうんと低ければいいわけです。
この「労働生産性と実質賃金率の差異」こそが、
産業資本主義の利潤のもとだったんです。
そして、そのような「差異性」を保証したのが、
農村における過剰な人口であったのです。
つまり、安い賃金でも働きたい労働者が、
農村から都市にどんどん流れ込むかぎり、
産業資本主義は成り立っていた。
これは発展途上国では、
現に存在している資本主義です。
しかし、先進資本主義国の中では、
産業資本主義の拡大がいつしか、
過剰人口の産業予備軍を使い切ってしまった。
その結果、「実質賃金率」が上がりはじめて、
「労働生産性」との差がなくなっていきました。
労賃が安かった時代では、
機械さえ持っていれば、
ほかの企業と同じことをやっていても、
必然的に、利益を生み出すことができたんです。
もはやそれでも差異性を生み出せない、
つまり利益が出ない。
だからポスト産業資本主義では、
「新しい差異を常に作っていかなければ、利潤は生まれない。」
そしてそれは、
「もはや機械ではなく、人間がもっとも価値を持つ社会である」ということです。
~~~ここまで一部引用
なるほど。
読めば読むほど、
産業資本主義は仮説に過ぎなかったんだなあと。
そしてその魔法はすでに解けたのだ。
だから、これからどう働くのか?
「差異性」を生み出す人材になること。
一方で、
その前にあった、人々が助け合える産業構造に
ふたたび戻していくこと。
この2つが大切になってくる。
たぶん、ツルハシブックスとコメタクの先にある未来は、
そんな形なのだろう。
2016年10月10日
ヒントは過去にある~Connecting the dots
アップル創業者のスティーブ・ジョブズの
スタンフォード大学卒業式での伝説のスピーチ。
「先を見て点をつなげることはできない。
できるのは過去を振り返って、点をつなげることだけだ。
だから将来、その点がつながることを信じなければならない。
直感や運命、人生、カルマ、何でもいいからそれを信じること。
点がつながって道となることを信じることで心に確信を持てる。
たとえ人と違う道を歩むことになっても、信じることだ」
大学を中退したことで、
潜り込んだカリグラフィーの授業。
当時はただ夢中でそれを学んでいただけ。
しかし、それがパソコンに「フォント」という概念を生み出した。
そう。
過去を振り返って、点と点をつなげる。
それは、「つながっているように見える」
だけかもしれない。
でも、多くの、活躍している人たちのインタビュー。
きっかけは?
と聞かれて答えるのは、ほとんどの場合、
「過去のリアル」だ。
「リアル」とは、
「感情が揺さぶられた経験」のこと。
病児保育分野で活躍するフローレンスの駒崎さんも、
自分のお母さんが電話で話していた相手が、
病気の子どもの面倒を見るために、何度か休んで、
会社を解雇されたという事実に心を揺さぶられたことから始まっている。
だから、進路に悩む大学生たちも、
過去の「心揺さぶられた経験」を思いだしていくことを
始めていくこと。
そして、大学時代も、多くの人に会い、
「心揺さぶられる経験」をすること。
感性を磨いて、
自分の心が揺さぶられる経験を多くすること。
これがキャリアドリフト時代の
進路選択の方法なのではないだろうか。
いつか、あなたもインタビューを受けて、
Connecting the dots
と答える日が来るのだ。
スタンフォード大学卒業式での伝説のスピーチ。
「先を見て点をつなげることはできない。
できるのは過去を振り返って、点をつなげることだけだ。
だから将来、その点がつながることを信じなければならない。
直感や運命、人生、カルマ、何でもいいからそれを信じること。
点がつながって道となることを信じることで心に確信を持てる。
たとえ人と違う道を歩むことになっても、信じることだ」
大学を中退したことで、
潜り込んだカリグラフィーの授業。
当時はただ夢中でそれを学んでいただけ。
しかし、それがパソコンに「フォント」という概念を生み出した。
そう。
過去を振り返って、点と点をつなげる。
それは、「つながっているように見える」
だけかもしれない。
でも、多くの、活躍している人たちのインタビュー。
きっかけは?
と聞かれて答えるのは、ほとんどの場合、
「過去のリアル」だ。
「リアル」とは、
「感情が揺さぶられた経験」のこと。
病児保育分野で活躍するフローレンスの駒崎さんも、
自分のお母さんが電話で話していた相手が、
病気の子どもの面倒を見るために、何度か休んで、
会社を解雇されたという事実に心を揺さぶられたことから始まっている。
だから、進路に悩む大学生たちも、
過去の「心揺さぶられた経験」を思いだしていくことを
始めていくこと。
そして、大学時代も、多くの人に会い、
「心揺さぶられる経験」をすること。
感性を磨いて、
自分の心が揺さぶられる経験を多くすること。
これがキャリアドリフト時代の
進路選択の方法なのではないだろうか。
いつか、あなたもインタビューを受けて、
Connecting the dots
と答える日が来るのだ。
2016年10月07日
「生きる」を体感する

「都市と地方をかきまぜる~食べる通信の奇跡」(高橋博之 光文社新書)
1次産業と都市生活者をつなぎ、
全国的な広がりを見せる「食べる通信」
の発祥であるNPO法人東北開墾の高橋さんの本。
「場づくり」志向の人は読んだほうがいいかも。
花巻出身の高橋さんはまるで、
現代の宮澤賢治のようだ。
印象に残ったキーワードは
「無常観」
「リアリティ」
「当事者意識」
といったところか。
この本は、時代の本質をとらえているなあと。
特にコトラーのマーケティング3.0を
AKB48を題材に、少ない文字数で端的に表現している。
~~~ここから一部引用
ただ物とお金を交換するのではなく、
人々はその物の背景にある価値観に「共感」したり、
その物の価値を高める物語づくりに「参加」したり
することを求めている。
これまでのアイドルは、
舞台裏を徹底的にベールに包んで、見せなかった。
見せるときは、
周到に演出されたフィクションとして提示していた。
ところがAKB48は、
このグループに加わった新人が
どのような動機で芸能界を目指しているのか。
どのように成長していくか、あるいは挫折しているか、
をドキュメンタリーで「リアル」にファンに見せる
そのうえで「総選挙」という
参加型のイベントを開催する。
つまりファンたちは、「投票」という行動を通して、
AKB48の物語に参加していく。
その臨場感と達成感、充実感こそが
AKB48というビジネスモデルの魅力になっている。
このことから考えると、
現代の日本でひとつのビジネスを成功させるためには、
ユーザーの「共感と参加」が得られるような仕組みを考えればいい、
ということになる。
そういう「回路」をつくることで、これまでにはなかった
共感と参加が生まれて、新しい価値のコミュニティが生まれる。
~~~ここまで引用
ふ~。
なるほど。
なんか、いいな。
これを読んで、
ツルハシブックスはいい線行っているんだけど、
なんか惜しい、そんな風に思う。
もう一歩なんだな、きっと。
高橋さんのビジョンには、
人を惹きつける魅力がある。
そのひとつが、
「二枚目の名刺」と「CSA=Community Supported Agriculture」だ
CSAはコミュニティに支えれられた農業のことで、
アメリカで広がりつつあるという。
「食べる通信」を通じて、
1次産業のサポーターとなり、
その上で、今度はコミュニティを維持する立場になり、
「二枚目の名刺」を手に入れる。
東日本大震災で多くの人が感じていたのは、
「無常観」ではないか、と高橋さんは言う。
すぐそこにある「死」と隣り合わせの「生」。
それを実感できるのが1次産業の現場であり、
実感を継続、きっかけを与えるのが「食べる通信」である。
「食べる通信」で、
生産者のリアルを知り、実際に現場に行くことで、
「食」というリアリティを知る。
そこで、人は「食」の当事者であることに気付く。
そして、農漁村の疲弊、都市と農村の隔たりに対して、
スーパーマーケットやコンビニエンスストアで買う生活をしている
自らも「共犯者」であることに気付く。
そして自分ができることは何かと考え、行動する。
そういう人が増えれば、問題解決に近づいていくだろう。
なるほど。
素敵だなあ。
「食べる通信」は
ここまで、物語の詰まったプロジェクトなのだ、と。
「生きる」を体感することから始まる、
ひとりひとりの未来が、世の中の未来になっていく。
ツルハシブックスやコメタクのこれからへ向けて、
ヒントの多い1冊でした。
2016年10月05日
作家は小説の後ろを追いかけている

「物語の役割」(小川洋子 ちくまプリマー新書)
「博士の愛した数式」の小川洋子さんが
「物語」について語った1冊。
おもしろいなあ。
小説を書きながら、こんなことを感じると言う。
~~~ここから引用
「こっちへいこう、こういうふうに世界を広げてゆこう」
という、物語自身が持っている力に導かれないと小説は書けないと思います。
(中略)
自分の思いを超えた、予想もしない何かに助けてもらえないと、
小説は書けません。
ですから私はときどき、
小説を書きながら、
書き手であるはずの自分自身が
いちばん後ろを追いかけているな、と感じます。
『博士の愛した数式」でも、
私よりも前に博士や家政婦さんやルート君がいる。
自分よりも前にすでに完全数や友愛数がある。
そういうすでにあるものの後を一所懸命追いかけていって、
振り返ったときに、自分の足跡が小説になっているという感じです。
(中略)
自分の思いを突き抜けて、
予想もしなかったところへ小説を運んでいってくれるのは、
自分以外の何かであるんじゃないか。
そうなると、小説家も数学者も同じだなと思うのです。
~~~ここまで引用
さらに、フランス人作家
フィリップ・ソレルスの講演から、引用しています。
~~~ここからさらに引用
「書くこと、文章に姿をあらわさせること、
それは特権的な知識を並べることではない。
それは人皆が知っていながら、
誰ひとり言えずにいることを発見しようとする試みだ」
まさにその通りです。
数学者が、偉大な何者かが隠した世界の秘密、
いろいろな数字のなかにこめられた、
すでにある秘密を探そうとするのと同じように、
作家も現実の中にすでにあるけれども、
言葉にされないために気づかれないでいる物語を見つけ出し、
鉱石を掘り起こすようにスコップで一所懸命掘り出して、
それに言葉を与えるのです。
~~~ここまで引用
なるほど。
数学者と小説家は似ているのか。
こういう、
「おいかけている」っていう感覚が大切なのかもしれない。
偉大な何か=サムシンググレイト
それは言葉にできない何かなのだけど、
それを追いかけているのだという感覚。
そうやって新しいものが生まれていくのかもしれない。
2016年10月04日
物語が生まれるまち

「脱・限界集落株式会社」(星野伸一 小学館)
いいですね。
素敵な読後感。
これを渋谷のど真ん中で
買ったっていうのがさらにいい。(笑)
なんか、小説なんだけど、話がリアル。
昔のジャスコとか、原発とか、
みんなこうやって誘致されたんだろうなあって。
そこに対抗していく
商店街の小さな店「コトカフェ」。
そうそう。
こんなお店になりたいなあと。
昨日のツイート
1
人が集まる場の形成について。
まずは主催者の魅力で人は集まる。
次に場が楽しいものでありつづけると、「好き」がその場に充満してくる。
「好き」を発信する人に会いたくて、行くようになる。
3段階目、「誰かに会えるから」行くようになる。このときに最初の主催者はもはや不要。
2
そして、「誰かに会えるから」となった瞬間に、
実はその場には、「好き」だけでなく、「偶然性」という魅力が加わっている。
この「偶然性」
をさらに高めるために、
「まちを歩く」というのが次のステージなのではないか、
あるいは、日替わりで店が替わる、市のようなものに
なっていくのではないか。
そして、「偶然性」が「好き」になり、
またそこに足を運ぶのではないか。
農業と商店街の関係性についても
考えさせられるとっても素敵な1冊です。
米屋本屋の次は、畑なんだろうな。
2016年10月03日
メディア化するお店の時代
トークイベント
「さよならの向こう側」3連発でのキーワード
・カフェという文化
・出版=パブリッシャー
・「食」というコミュニケーションツール
そこから導き出されるのは、
「商店街を巻き込んだ横のツルハシブックス」
「ツルハシブックスのメディア化」
サムライ、劇団員たちの
「編集員化」だろうと思う。
おそらく、これから、
お店はどんどんメディアになっていく。
参考:
メディアに期待するものは情報ではなくコミュニティとコミュニケーション
http://hero.niiblo.jp/e391242.html
(2014.3.29 20代の宿題)
メディアとしてのお店が示す世界観に賛同して、
そこに人が集まり、コミュニティを形成していく。
その参加の入り口が、
「購入」になっていく。
これを逆から言えば、
コミュニティ・プラットフォーム、
コミュニケーション・プラットフォームを
作りたければ、
世界観を発信するとともに、
入り口となるような小さな商品を売る「お店」
という形態を取ることが
必要なのではないだろうか。
届けようとしている人(顧客)が、
もし、積極的に新しいことに顔を突っ込んでいける人
でなければ、
(多くの中学生高校生大学生はそうであると思うが)
お店という形態を取り、
コミュニケーションの入り口を作らなければ、
接点をつくることができないのではないか。
そういう意味では、
本屋であること、古本屋であること、
米屋であること、雑貨屋であることは、
コミュニケーションの入り口として機能しているのだろう。
そんな入口を持ちながら、
メディアとしてお店を運営していくこと。
これがサムライや劇団員の
次のステージなのではないかな、と思う。
「さよならの向こう側」3連発でのキーワード
・カフェという文化
・出版=パブリッシャー
・「食」というコミュニケーションツール
そこから導き出されるのは、
「商店街を巻き込んだ横のツルハシブックス」
「ツルハシブックスのメディア化」
サムライ、劇団員たちの
「編集員化」だろうと思う。
おそらく、これから、
お店はどんどんメディアになっていく。
参考:
メディアに期待するものは情報ではなくコミュニティとコミュニケーション
http://hero.niiblo.jp/e391242.html
(2014.3.29 20代の宿題)
メディアとしてのお店が示す世界観に賛同して、
そこに人が集まり、コミュニティを形成していく。
その参加の入り口が、
「購入」になっていく。
これを逆から言えば、
コミュニティ・プラットフォーム、
コミュニケーション・プラットフォームを
作りたければ、
世界観を発信するとともに、
入り口となるような小さな商品を売る「お店」
という形態を取ることが
必要なのではないだろうか。
届けようとしている人(顧客)が、
もし、積極的に新しいことに顔を突っ込んでいける人
でなければ、
(多くの中学生高校生大学生はそうであると思うが)
お店という形態を取り、
コミュニケーションの入り口を作らなければ、
接点をつくることができないのではないか。
そういう意味では、
本屋であること、古本屋であること、
米屋であること、雑貨屋であることは、
コミュニケーションの入り口として機能しているのだろう。
そんな入口を持ちながら、
メディアとしてお店を運営していくこと。
これがサムライや劇団員の
次のステージなのではないかな、と思う。





