2022年03月17日
プロとアマチュアの共創プロジェクト
ルネサンス期の三大発明は「火薬」「羅針盤」「活版印刷」ということなのだけど。
近代社会(工業社会)の三大発明は、「未来」と「自分」と「自由」だと思うんですよね。その3つの発明を駆使して、工場労働者あるいは「サラリーマン」という存在を創出することに成功した。それが富国強兵な近代国家を成立させるため必要条件だったからですね。
2020年に始まった新型コロナウイルス下の世界からすでに2年以上が経過した。2年前の3月上旬には完全オンラインになった会議に上野のビジネスホテルから出席していた。
「未来」が失われた2年間、正確に言えば、直線的に進んでいく「未来」を失った2年間だと言えるだろう。まさにVUCAな時代そのものを体感したとも言える。
そんな中で生きていくためのキーワード。
・アマチュアリズム・・・とらわれずにやってみる
・ブリコラージュ・・・寄せ集めてつくり、修繕する
・共創(コ-クリエーション)・・・一緒に創造する
ちょうどABCになってますが。(講演とかに使える。笑)
いろんな人が教育を語る時に使っている「フラットな関係」とはそもそも何か?
この前の隠岐の国学習センターの澤さんの話を聞けば、それは場を共有し「問い」を生み出すことだし、未来をつくっていく方法はビジョンではなく「問い」そのものだと思う。
「共創」によるアイデンティティの構築(22.1.5)
http://hero.niiblo.jp/e492252.html
それは、僕の15年に渡るキーワードである「アイデンティティ」にも関わってくる。
「あなたは何のプロなのか?」
もしくは「あなたは何のプロになりたいのか?」
キャリアを考える大切な問いであると思う。
しかし。
その問いの前提を疑う。
・専業の時代(1人の人の「本業」は1つである)
・「プロ」(専門家)こそが価値を生み出す
それって、「未来」そのものが失われた今、まだ前提として正しいのだろうか?
プロを定義すると
「納期を守り、一定以上のクオリティで納品する人(会社)」と言えるだろう。
そこに金銭が発生する。
同時にプロ至上主義は、家庭や地域における非金銭的なことを仕事よりも下位に置くようになった。それは一部の進学校と呼ばれる学校での「(教科)学習」と地域活動の関係にも似ているのかもしれない。
でも、いま。「未来」そのものが失われた。「時間」という発明そのものが揺らいでいるのだとしたら。あるいは、プロセスエコノミーのように、人々がアウトプットのクオリティではなく、プロセスそのものに価値がある、と感じているとしたら。
アマチュアリズムとブリコラージュとコ・クリエーションの出番だ。
今までの常識をアンラーニングし、現在ある限られた資源を使って、様々な人たちと対話し共創していくことだ。
その移行期にある。
おそらくそれは学校も同じだ。
移行期に必要なこと。
それは「プロとアマチュアの共創」なのだろうと思う。
「未来」も「自分」もフィクションだった。「自由」も「未来」や「自分」を前提にした、尾崎豊風に言わせれば「仕組まれた自由」だった。
「場」を主語に、場に溶けだし、問いを生み出し、その問いへと向かっていくこと。
その共創のプロセスの中にこそ、学びがあり、「存在」があるのだと僕は思っています。
そんなリアルメディアとしての授業や課外活動が作れないかなあと。
近代社会(工業社会)の三大発明は、「未来」と「自分」と「自由」だと思うんですよね。その3つの発明を駆使して、工場労働者あるいは「サラリーマン」という存在を創出することに成功した。それが富国強兵な近代国家を成立させるため必要条件だったからですね。
2020年に始まった新型コロナウイルス下の世界からすでに2年以上が経過した。2年前の3月上旬には完全オンラインになった会議に上野のビジネスホテルから出席していた。
「未来」が失われた2年間、正確に言えば、直線的に進んでいく「未来」を失った2年間だと言えるだろう。まさにVUCAな時代そのものを体感したとも言える。
そんな中で生きていくためのキーワード。
・アマチュアリズム・・・とらわれずにやってみる
・ブリコラージュ・・・寄せ集めてつくり、修繕する
・共創(コ-クリエーション)・・・一緒に創造する
ちょうどABCになってますが。(講演とかに使える。笑)
いろんな人が教育を語る時に使っている「フラットな関係」とはそもそも何か?
この前の隠岐の国学習センターの澤さんの話を聞けば、それは場を共有し「問い」を生み出すことだし、未来をつくっていく方法はビジョンではなく「問い」そのものだと思う。
「共創」によるアイデンティティの構築(22.1.5)
http://hero.niiblo.jp/e492252.html
それは、僕の15年に渡るキーワードである「アイデンティティ」にも関わってくる。
「あなたは何のプロなのか?」
もしくは「あなたは何のプロになりたいのか?」
キャリアを考える大切な問いであると思う。
しかし。
その問いの前提を疑う。
・専業の時代(1人の人の「本業」は1つである)
・「プロ」(専門家)こそが価値を生み出す
それって、「未来」そのものが失われた今、まだ前提として正しいのだろうか?
プロを定義すると
「納期を守り、一定以上のクオリティで納品する人(会社)」と言えるだろう。
そこに金銭が発生する。
同時にプロ至上主義は、家庭や地域における非金銭的なことを仕事よりも下位に置くようになった。それは一部の進学校と呼ばれる学校での「(教科)学習」と地域活動の関係にも似ているのかもしれない。
でも、いま。「未来」そのものが失われた。「時間」という発明そのものが揺らいでいるのだとしたら。あるいは、プロセスエコノミーのように、人々がアウトプットのクオリティではなく、プロセスそのものに価値がある、と感じているとしたら。
アマチュアリズムとブリコラージュとコ・クリエーションの出番だ。
今までの常識をアンラーニングし、現在ある限られた資源を使って、様々な人たちと対話し共創していくことだ。
その移行期にある。
おそらくそれは学校も同じだ。
移行期に必要なこと。
それは「プロとアマチュアの共創」なのだろうと思う。
「未来」も「自分」もフィクションだった。「自由」も「未来」や「自分」を前提にした、尾崎豊風に言わせれば「仕組まれた自由」だった。
「場」を主語に、場に溶けだし、問いを生み出し、その問いへと向かっていくこと。
その共創のプロセスの中にこそ、学びがあり、「存在」があるのだと僕は思っています。
そんなリアルメディアとしての授業や課外活動が作れないかなあと。
2022年03月14日
「伴走」から「共鳴」へ

「手の倫理」(伊藤亜紗 講談社選書メチエ)
読み終わりました。
めちゃめちゃいい本でした。
タイムリーすぎる。
ヴィネスパさん幅さんありがとう。
最高の1冊でした。
今日も自分のためにメモします。
~~~
【記号的メディアと物理的メディア】
デジタル⇔アナログ
不連続⇔連続的
コード化⇔非コード化
非接触⇔接触・同期
書き言葉⇒話し言葉⇒手話⇒ジェスチャー⇒さわる/ふれる
【伝達モードと生成モード】
メッセージは発信者の中にある⇔メッセージがやりとりの中で生まれていく
一方向的⇔双方向的
役割分担が明瞭⇔役割分担が不明瞭
スピーチ⇒おしゃべり
さわる⇒ふれる
「伴走してあげる」とか「伴走してもらう」じゃない「一緒に走っている」という感覚。役割が曖昧になり、どちらかが能動でどちらかが受動かということの線引きができなくなるのです。言葉は共鳴に対する「切断」です。「二人で一つ」の共鳴を脱して、「自分でしっかり注意してね」と「個」のスイッチを入れることなのです。
共鳴の「伝わっていく」関係は、伝えるべき情報とそうでない情報の取捨選択ができないという意味で、文字通り「意のまま」の対極にあるやりとりの形態です。
「相手の体に入り込み合う」能動性すら消え、「あずけたことによって入ってくる」ものを分け隔てなく受け取っている。この筒抜けの直接性において、共鳴は生成モードの究極形態である、と言うことができます。
安心とは、「相手のせいで自分がひどい目にあう」可能性を意識しないこと、信頼は「相手のせいで自分がひどい目にあう」可能性を自覚したうえで、ひどい目にあわない方に賭ける、ということです。
ポイントは、信頼に含まれる「にもかかわらず」という逆説でしょう。社会的不確実性がある「にもかかわらず」信じる。この逆説を埋めるのが信頼なのです。
~~~
今回、一番感動したのは、ブラインドランナーと伴走者の話でした。
第5章「共鳴」
目の見えないランナーと目の見える伴走者は、ロープを通じてコミュニケーションしています。
そこには、伝わらなくても伝わってしまう何かがあると言います。
伴走者の視界に子どもが入り、危なくないなと思って何も言葉を発しなかったとしても、
ロープから伝わってしまい、「子ども?」と聞かれてしまうという。
それぐらい伝わってしまうし、いつのまにか一体となって走っているという。
そしてそれがすごく気持ちいいのだと。
それを著者は「共鳴」だと言います。
「伴走」ではなく「共鳴」か。これは響くなあ。
これって、高校生の探究的学びと地域の大人との関係にも、通じるし、
5年くらい前から言っていた「場のチカラ」とか、「場に溶ける」とか、
アイデンティティとかもこういう話だよね。
この前海士町の澤さんが言っていた「探究」「協働」から「共創」へ
ってきっとこういうことだろうと思うんだよね。
教育と探求社宮地さんの「探求のススメ」を思い出した。
一生残る問いを投げかけることができるか?(21.7.17)
http://hero.niiblo.jp/e491897.html
信じること、感じること、待つこと、一緒にいること。
たぶん、こういうことなんだろうな。
僕が「伴走者」ではなく「伴奏者」に言ってたのもきっとそういう感じ。
視覚や言語だけではなくて、もっと身体的に、「共鳴」なのだろうと。
そこにはまず、「委ねる」ことが大切なのだろうと。「安心」から「信頼」へシフトし、委ねること。
「越境」とは、そういうことなのかもしれませんね。予測不可能な未来を実感し、委ね、先へ進むこと。その超えた先に「共鳴」する何かに出会えるかもしれない。
「場」をつくる、っていうところの先にあるものは「共鳴」かもしれないと思いました。
阿賀黎明高校「地域学」発のクラウドファンディング、3日目です。
https://camp-fire.jp/projects/view/552815
「自分たちの居場所は自分たちで創る」阿賀黎明高校生と阿賀町の空き店舗活用PJ
2022年03月13日
リアルメディアに触れて自分の「輪郭」を確認する

「手の倫理」(伊藤亜紗 講談社選書メチエ)
最近のキーワードである「身体性」と「五感の解放」。
それにぴったりな本だなあと。
今日は第2章「触覚」から。
五感とは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚であるけど、そこにはヒエラルキーがあり、「視覚」が最上位にあります。これは、視覚がより精神的な感覚だととらえられたから。
触覚は、視覚や聴覚と比べると、「劣っている感覚」として位置づけられていたそうです。その理由は「距離のなさ」です。視覚や聴覚とそれ以外の3つの優劣は距離の問題で、視覚は人間の精神的な部分に、触覚は逆に動物的な部分に関わる感覚であると考えられてきました。もうひとつは「持続性」の問題です。触覚は時間的な感覚である。触覚は常に「部分の積み重ね」であり、「時間がかかる感覚」であるため、非効率的です。
そして、3つ目はポジティブな文脈で「対称性」というのが挙げられます。これが今日のテーマです。
~~~
つまり、私たちが自分の体にふれるとき、それは同時に「ふれられているのは私だ」という感覚をもたらします。私が私にふれるときは、私は私によって触れられてもいる。この感覚に特有の主体と客体の入れ替え可能性を、本論では触覚の「対称性」と呼びたいと思います。
注意しなければならないのは、私は主体でも客体でもありうるけれど、同時に主体でありかつ客体であることはできない、ということです。「仮に私の左手が右手に触れ、そしてふと、触わりつつあるある左手の作業を右手で捉えようとしても、身体の身体自身に対するこの反省は、きまって最後には失敗する。私が右手で左手を感ずるやいなや、それに比例して、私は左手で右手に触わることを止めてしまうからである。
興味深いのは、コンディヤックにとって、この対称性が「体をもった物理的な存在としての私の発見」という形で経験されていることです。私が、単なる精神ではなく、固有の空間を占める物体として世界に存在していること。このことは、裏を返せば、私が体として存在していることは、「発見」されなければならないほど、ときに曖昧になりうるものなのだ、ということを示しています。触覚は、そのような曖昧さのなかにある私に、明確な輪郭を与えてくれます。触覚は、「魂を自己の外へと脱出させる感覚」なのです。
私たちは、日々の生活のなかで自分の輪郭を見失い、不安にかられることがあります。そんなとき、ふと何かに包まれたり、何かを抱きしめたりすることで、精神的な安心を得たり、確かさの感覚を取り戻したりすることがあります。さわることでさわられ、そのことによって自分の存在を確認する。私たちが輪郭を見失ったとき、触覚の対称性が、確かな安らぎを与えてくれます。
触覚以外の五感に関しては、一般に「色を見る」「音を聞く」「臭いを嗅ぐ」「甘さを味わう」というように、対象をあらわす助詞として「を」を用います。ところが「ふれる」に関してだけ、「額にふれる」などと「に」が使われるのです。このように「に」が用いられるのは、「ふれる」が、その他の感覚とは違って、主体と客体を明確に分離せず、内部に入っていく感覚だからだ、と坂部恵はいいます。
~~~
「輪郭」とか、ってまさにキーワードでしたね。
「わたし」「しごと」という輪郭を溶かし、再構築する(22.1.11)
http://hero.niiblo.jp/e492262.html
オンラインな時代になり、人はますます、自分の「存在」を信じられなくなっていると感じる。
その「存在」を、「輪郭」を取り戻す、または再構築していく必要がある。
それには、具体的に、リアルメディアが必要なのではないか?
「流しのこたつ」のような。
「リアルメディア」という参加のデザイン(18.11.2)
http://hero.niiblo.jp/e488340.html
「ふれる」ことで、自分の輪郭を取り戻すこと。
昨日始まった、阿賀黎明高校の授業から生まれた空き店舗改装プロジェクトのクラウドファンディング

https://camp-fire.jp/projects/view/552815
「自分たちの居場所は自分たちで創る」阿賀黎明高校生と阿賀町の空き店舗活用PJ
この場所はきっと、高校生と町の人たちの「輪郭」を確認する場所になっていくと思います。
応援よろしくお願いします!
2022年03月10日
「地球の歩き方」的アプローチ
カーブドッチ・ヴィネスパが本屋になったらしいので
朝風呂に行ってきました。(午前7時オープン!)
https://vinespa.jp/





幅セレクトの本たちが、お風呂に入ってリラックスした感性に響いてきます。
これは最高の朝活スポットができちゃいましたね。
朝7時ヴィネスパ集合でミーティングしたいです。
モーニングは770円で食べられるようです。
六本木「文喫」の1650円だったら、
カーブドッチ・ヴィネスパの1770円の朝活がいいなあ。
平日の午前中に行ける人にはいい空間だなあと思いました。
それにしても、お風呂からの本、って考えている人やっぱいるんだなあと。
1時間くらい本棚を見ていて、購入したのはこの本でした。

「手の倫理」(伊藤亜紗 講談社選書メチエ)
「身体性」。
これは2020年春からの大きな僕のキーワードだったのだけど。
そんなキーワードにぴったりの1冊にお風呂後に出会える幸せ。
まず序章で、「さわる」と「ふれる」について、イントロダクションがあります。
~~~
「ふれる」が相互的であるのに対し、「さわる」は一方的である。
言い換えれば、「ふれる」は人間的なかかわり、「さわる」は物的なかかわり、ということになるのでしょう。
~~~
うーん、いいですね。
こういうこと、考えたいです。
そして第4章の予告がいい。
~~~
第4章はコミュニケーションについて。言葉や絵などさまざまなメディアを用いたコミュニケーションがある中で触覚的なコミュニケーションはどのような特徴をもつのか。一方的な「さわる」に対応する「伝達モード」のコミュニケーションと、双方向的な「ふれる」に対応する「生成モード」のコミュニケーションの違いに注目しながら論じます。
~~~
うわー、これです、これ、考えたかったことは。
というわけで、第4章まで到達するのを楽しみに、今日は第1章「倫理」より。
まずはフレーベル教育の話
~~~
興味深いのは、こうして石や木、物の性質を知っていくことが、フレーベルにおいては、「自分自身を知ること」へと折り返していく点です。ものの意外な性質が引き出されることと、自分の中の意外な性質が引き出されることは、フレーベルにとってはセットになった一つの出来事なのです。だからフレーベルは子供の発達において触覚的な経験が持つ力を重視したのでした。
~~~
これですね、触覚的な経験。五感の解放。
そういうことが必要なんだと思います。
そして、「道徳」と「倫理」の別について、哲学者・倫理学者の古田徹也の議論より
~~~
「道徳」:
・画一的な正しさ、善を指向する
・非難と強力に結びつく(「すべき」が「できる」を含意する)
・人々が生活の中で長い時間かけて定まっていった答えないし価値観が中心となる
・価値を生きること
「倫理」:
・すべきことや生き方全般を問題にする
・非難とは必ずしも結びつかない(「すべき」が必ずしも「できる」を含意しない)
・答えが定まっていない、現在進行形の重要な問題に対する検討も含まれる
・価値を生きるだけでなく、価値について考え抜くことも含まれる
「この場合にはこうしなさいと道徳的に説いたり指図すことは、一般的に言って、倫理の目的ではない。その真の目的は、考えるための道具を与え、考え方の可能性を広げることにある。」(アンソニー・ウエストン)
そもそも社会とは何なのか。
「帰属意識が危機に瀕している。しかし、この状況から目をそらすことなく、新たな結びつきに目を向けるために社会的なものに対して別の概念化を行う必要がある。」(ブルーノ・ラトゥール)
ラトゥールのアクターネットワーク理論(ANT)とガイド本的アプローチ:
・高みから俯瞰しないで、蟻のように地を這い、具体的な状況のなかを動きながら記述すること。従来の哲学の本のように、「社会」や「人間」や「存在」についての普遍的な理論を打ち立てるのではない。自分の本は、「地球の歩き方」のように(とはラトゥールは言っていませんが)具体的な状況を生きるための手がかりを提示するものだ、というのです。
多様性という言葉に安住することは、それ自体はまったく倫理的なふるまいではない。そうではなく、いかにして異なる考え方をつなぎ、違うものを同じ社会の構成員として組織していくか、そこにこそ倫理はあると言うのです。これに対し、「さわる/ふれる」ことは物理的な接触ですから、その接触面に必ず他者との交渉が生じます。
ただし、倫理は単に具体的な状況に埋没するものではない、という点に注意が必要です。状況の複雑さに分け入り、不確実な状況に創造的に向き合うことで、「善とは何か」「生命とは何か」といった普遍的な問いが問いなおされる。あるいは異なる複数の立場のあいだにも、実は共通の価値があることが見えてくる。倫理的な営みとはむしろ、具体的な状況と普遍的な価値のあいだを往復すること、そうすることで異なるさまざまな立場をつなげていくことであると言うことができます。
「目の前にいるこの人は、必ず自分には見えていない側面がある」という前提で人と接する必要があるということでしょう。それは配慮というよりむしろ敬意の問題です。」
~~~
いいですね。こういうの。
「探究的学びの伴走者であり、自らも探究者になる」ってこういうことだろうと思います。
リニア(直線的)な「未来」を失ったということは、「道徳」も機能しなくなるかもしれないということ。だからこそ、考え続けないといけない。状況に身を委ねないといけない。その上で、価値を感じ、他者を感じ、それを言語化し、倫理へと自分の中での一般化をしていくこと。
それは一生を通じて、行っていくことなのだろう。
「人生100年時代には、人は学び続けないといけない」という一般論ではなくて、目の前のリアルに「触れ」、ともに体感し、ともに考え、次のアクションを起こしていくこと。そんな「地球の歩き方」的アプローチでプロジェクトをつくっていきたい。
「阿賀で楽しむこれからの人生の歩き方」
そんなガイド本的なアプローチを、先輩高校生と共につくり、後輩につないでいくような、そんな取り組みがしたいです。
朝風呂に行ってきました。(午前7時オープン!)
https://vinespa.jp/





幅セレクトの本たちが、お風呂に入ってリラックスした感性に響いてきます。
これは最高の朝活スポットができちゃいましたね。
朝7時ヴィネスパ集合でミーティングしたいです。
モーニングは770円で食べられるようです。
六本木「文喫」の1650円だったら、
カーブドッチ・ヴィネスパの1770円の朝活がいいなあ。
平日の午前中に行ける人にはいい空間だなあと思いました。
それにしても、お風呂からの本、って考えている人やっぱいるんだなあと。
1時間くらい本棚を見ていて、購入したのはこの本でした。

「手の倫理」(伊藤亜紗 講談社選書メチエ)
「身体性」。
これは2020年春からの大きな僕のキーワードだったのだけど。
そんなキーワードにぴったりの1冊にお風呂後に出会える幸せ。
まず序章で、「さわる」と「ふれる」について、イントロダクションがあります。
~~~
「ふれる」が相互的であるのに対し、「さわる」は一方的である。
言い換えれば、「ふれる」は人間的なかかわり、「さわる」は物的なかかわり、ということになるのでしょう。
~~~
うーん、いいですね。
こういうこと、考えたいです。
そして第4章の予告がいい。
~~~
第4章はコミュニケーションについて。言葉や絵などさまざまなメディアを用いたコミュニケーションがある中で触覚的なコミュニケーションはどのような特徴をもつのか。一方的な「さわる」に対応する「伝達モード」のコミュニケーションと、双方向的な「ふれる」に対応する「生成モード」のコミュニケーションの違いに注目しながら論じます。
~~~
うわー、これです、これ、考えたかったことは。
というわけで、第4章まで到達するのを楽しみに、今日は第1章「倫理」より。
まずはフレーベル教育の話
~~~
興味深いのは、こうして石や木、物の性質を知っていくことが、フレーベルにおいては、「自分自身を知ること」へと折り返していく点です。ものの意外な性質が引き出されることと、自分の中の意外な性質が引き出されることは、フレーベルにとってはセットになった一つの出来事なのです。だからフレーベルは子供の発達において触覚的な経験が持つ力を重視したのでした。
~~~
これですね、触覚的な経験。五感の解放。
そういうことが必要なんだと思います。
そして、「道徳」と「倫理」の別について、哲学者・倫理学者の古田徹也の議論より
~~~
「道徳」:
・画一的な正しさ、善を指向する
・非難と強力に結びつく(「すべき」が「できる」を含意する)
・人々が生活の中で長い時間かけて定まっていった答えないし価値観が中心となる
・価値を生きること
「倫理」:
・すべきことや生き方全般を問題にする
・非難とは必ずしも結びつかない(「すべき」が必ずしも「できる」を含意しない)
・答えが定まっていない、現在進行形の重要な問題に対する検討も含まれる
・価値を生きるだけでなく、価値について考え抜くことも含まれる
「この場合にはこうしなさいと道徳的に説いたり指図すことは、一般的に言って、倫理の目的ではない。その真の目的は、考えるための道具を与え、考え方の可能性を広げることにある。」(アンソニー・ウエストン)
そもそも社会とは何なのか。
「帰属意識が危機に瀕している。しかし、この状況から目をそらすことなく、新たな結びつきに目を向けるために社会的なものに対して別の概念化を行う必要がある。」(ブルーノ・ラトゥール)
ラトゥールのアクターネットワーク理論(ANT)とガイド本的アプローチ:
・高みから俯瞰しないで、蟻のように地を這い、具体的な状況のなかを動きながら記述すること。従来の哲学の本のように、「社会」や「人間」や「存在」についての普遍的な理論を打ち立てるのではない。自分の本は、「地球の歩き方」のように(とはラトゥールは言っていませんが)具体的な状況を生きるための手がかりを提示するものだ、というのです。
多様性という言葉に安住することは、それ自体はまったく倫理的なふるまいではない。そうではなく、いかにして異なる考え方をつなぎ、違うものを同じ社会の構成員として組織していくか、そこにこそ倫理はあると言うのです。これに対し、「さわる/ふれる」ことは物理的な接触ですから、その接触面に必ず他者との交渉が生じます。
ただし、倫理は単に具体的な状況に埋没するものではない、という点に注意が必要です。状況の複雑さに分け入り、不確実な状況に創造的に向き合うことで、「善とは何か」「生命とは何か」といった普遍的な問いが問いなおされる。あるいは異なる複数の立場のあいだにも、実は共通の価値があることが見えてくる。倫理的な営みとはむしろ、具体的な状況と普遍的な価値のあいだを往復すること、そうすることで異なるさまざまな立場をつなげていくことであると言うことができます。
「目の前にいるこの人は、必ず自分には見えていない側面がある」という前提で人と接する必要があるということでしょう。それは配慮というよりむしろ敬意の問題です。」
~~~
いいですね。こういうの。
「探究的学びの伴走者であり、自らも探究者になる」ってこういうことだろうと思います。
リニア(直線的)な「未来」を失ったということは、「道徳」も機能しなくなるかもしれないということ。だからこそ、考え続けないといけない。状況に身を委ねないといけない。その上で、価値を感じ、他者を感じ、それを言語化し、倫理へと自分の中での一般化をしていくこと。
それは一生を通じて、行っていくことなのだろう。
「人生100年時代には、人は学び続けないといけない」という一般論ではなくて、目の前のリアルに「触れ」、ともに体感し、ともに考え、次のアクションを起こしていくこと。そんな「地球の歩き方」的アプローチでプロジェクトをつくっていきたい。
「阿賀で楽しむこれからの人生の歩き方」
そんなガイド本的なアプローチを、先輩高校生と共につくり、後輩につないでいくような、そんな取り組みがしたいです。
2022年03月09日
衝動とWHYの三角形
高校生のプロジェクトに「なぜか?」とたずねる時。
僕が聞きたいのは、まず「衝動の物語」であって、「合理的理由」や「社会的意義」、「数値的エビデンス」ではない。
いま、ワークシートを作り直しているのだけど、
「自分の好き」「仲間の好き」「他者・地域・社会の課題や資源」
というのを意識しながら活動している時に生まれる「衝動」。
とにかく「好き」でこれをしているとハッピーだ、とか、なぜ、こんなおかしなことになっているんだ?とかの憤り
ひとつひとつの物語の中にある衝動から描く未来をイメージすること。その未来も衝動なのだけど。
WHYと衝動の三角形をまずつくること。
そのWHYを補完するものとしての「社会的意義」や「数値的エビデンス」が必要になってくるんだ。
「衝動」を得る方法は、4つの出会い。
・自分との出会い(自分ってこんなやつだったんだ!)
・仲間との出会い(応援したい!)
・地域(社会)との出会い(この課題なんとかしたい!)
・お客との出会い(この人のために何かしたい!)
自分・仲間サイドと地域(社会)・お客サイドを組み合わせて、
なぜ(描く未来)と誰がどうなったらうれしいのか?というWHY(ビジョン)を描く。
そのWHYを補完するものとして「社会的意義」や「数値的エビデンス」を加えていく。
しかし、まずはそのWHYに向けてWHAT(何をするか?)を考え、HOW(どのようにするか?)に落とし込んでいく。
活動し再び4つの「衝動」に出会う。そしてサイクルが回っていく。
たぶんそういう感じ。
衝動を見つけるために観察が必要となり、観察を駆動するには好奇心が必要であり。
その衝動とWHYの三角形のことを、人は個性と呼ぶのだろうと思う。
そこにプロジェクトを立ち上げていくこと。仕事でも、趣味でも、ボランティアでも同じだ。
自分と他者のあいだに、プロジェクトができていて、そこに自分を差し出すこと。
これを繰り返し、いつの日か「衝動」と「呼びかけ」が一致するとき。
人は「天職」に出会うのだろう。
僕が聞きたいのは、まず「衝動の物語」であって、「合理的理由」や「社会的意義」、「数値的エビデンス」ではない。
いま、ワークシートを作り直しているのだけど、
「自分の好き」「仲間の好き」「他者・地域・社会の課題や資源」
というのを意識しながら活動している時に生まれる「衝動」。
とにかく「好き」でこれをしているとハッピーだ、とか、なぜ、こんなおかしなことになっているんだ?とかの憤り
ひとつひとつの物語の中にある衝動から描く未来をイメージすること。その未来も衝動なのだけど。
WHYと衝動の三角形をまずつくること。
そのWHYを補完するものとしての「社会的意義」や「数値的エビデンス」が必要になってくるんだ。
「衝動」を得る方法は、4つの出会い。
・自分との出会い(自分ってこんなやつだったんだ!)
・仲間との出会い(応援したい!)
・地域(社会)との出会い(この課題なんとかしたい!)
・お客との出会い(この人のために何かしたい!)
自分・仲間サイドと地域(社会)・お客サイドを組み合わせて、
なぜ(描く未来)と誰がどうなったらうれしいのか?というWHY(ビジョン)を描く。
そのWHYを補完するものとして「社会的意義」や「数値的エビデンス」を加えていく。
しかし、まずはそのWHYに向けてWHAT(何をするか?)を考え、HOW(どのようにするか?)に落とし込んでいく。
活動し再び4つの「衝動」に出会う。そしてサイクルが回っていく。
たぶんそういう感じ。
衝動を見つけるために観察が必要となり、観察を駆動するには好奇心が必要であり。
その衝動とWHYの三角形のことを、人は個性と呼ぶのだろうと思う。
そこにプロジェクトを立ち上げていくこと。仕事でも、趣味でも、ボランティアでも同じだ。
自分と他者のあいだに、プロジェクトができていて、そこに自分を差し出すこと。
これを繰り返し、いつの日か「衝動」と「呼びかけ」が一致するとき。
人は「天職」に出会うのだろう。
2022年03月08日
アイデンティティの脱中心化
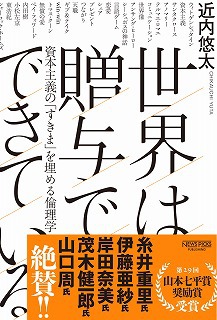
「世界は贈与でできている」(近内悠太 ニューズピックスパブリッシング)
読み終わりました。
ジワ―っと熱くなる読後感。
いいなあ、こういう本。
僕がいまなぜここにいるのか?
問い直される1冊。
美しい月を見て、「今日は月がキレイだね」と誰かに伝えたくなる自分。
それは自然からの一方的な贈与を、誰かに分け与えてたくなるからではないか。
メッセンジャー(手紙の運び手)であり、アンサング・ヒーロー(歌われざる英雄)である自分。
そんな存在として生きていきたいのではないか。
2015年に東京・練馬でスタートした「暗やみ本屋ハックツ」活動は、
本を通じた「贈与」の可能性という社会実験であるのかもしれない。
http://hero.niiblo.jp/e487092.html
(歌われざる英雄が詰まった本棚 18.3.7)
今日も少しだけ紹介します。
~~~
まずはマッキーの歌から。
「今君がこの雪に気づいてないから/誰より早く教えたい/心から思った」(槇原敬之「北風」)と感じたり、雪を見たら誰かに逢いたくなったり、思わず「雪がきれいだね」と言いたくなったりする。あるいは、月を見上げて愛の言葉を伝えたくなる。僕らに何かしらのアクションを迫り、しかもそのアクションは「他者とのつながり」へ向かっているという点において、それは生命力と言えるのではないでしょうか。
受け取った純粋な自然の贈与を、それをまだ受け取ることができていない誰かに向けて転送する、つまり、贈与を受け取った人はメッセンジャーになるということです。
手に入れた知識や知見そのものが贈与であることに気づき、そしてその知見から世界を眺めたとき、いかに世界が贈与に満ちているかを悟った人を、教養ある人と呼ぶのです。そしてその人はメッセンジャーとなり、他者へと何かを手渡す使命を帯びるのです。使命感という幸福を手に入れることができるのです。
なぜ僕らが「仕事のやりがい」を見失ったり、「生きる意味」「生まれたきた意味」を自問したりしてしまうのか。それが「交換」に根差したものだからです。
ギブ&テイク、ウィン-ウィン。残念ながらその中から「仕事のやりがい」「生きる意味」「生まれてきた意味」は出てきません。これらは贈与の宛て先から逆向きに返ってくるものだからです。それがメッセンジャーとなり、アンサング・ヒーローとなり、贈与の宛て先から逆向きに仕事のやりがいと生きる意味を与えられるための道なのです。
~~~
そうなんですよね。
昨日書いた、まずは贈与の受け手となる。
そしてそれをシェアしたいと思う。
生きる意味はそこから始まっていくのだと。
ここに、僕はこれからのライフスタイルの進む方向を感じる。
昨年6月に読んだ「学びの脱中心化」
http://hero.niiblo.jp/e491788.html
(二人称的アプローチとアイデンティティ)
学びと同じように、仕事とか働くことも中心がなくなっていくのではないか。
それはなぜか?
「交換主体」としてだけでは、人は生きられないからだ。
自分が存在する意味を感じられないからだ。
仕事と、副業と、プロボノと、ボランティアと、ファンと、その境目(輪郭)がだんだんと溶けていく。その境目(輪郭)を溶かし、さまざまな自分(特に贈与の受け手であり、渡し手である自分)を演じなければ、自分らしさという実感が得られないからだ。
それってサードプレイス論にも通じるのかもしれません。異なった価値観に支配された場で様々な自分を演じること。
リニア(直線的)な世界とノンリニア(非直線的)な世界では、アイデンティティのつくり方は違うのではないか。これまでの直線的に発展してきたリニアの世界では本業(仕事)がアイデンティティの中心だがノンリニアの世界では、仕事、副業、プロボノ、ボランティア、ファンの組み合わせの集合体がアイデンティティになる。
アイデンティティの脱中心化。
贈与の受け手であり、送り手である自分。
メッセンジャーでありアンサング・ヒーローを目指す自分。
それをこの自然豊かな町のベクトル感のある「実践の共同体」で体感、実践していくこと。
たぶん、そういう感じ。
2022年03月07日
届いていた手紙に気づくために、届いていた手紙を読むために
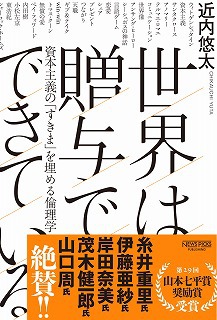
「世界は贈与でできている」(近内悠太 ニューズピックスパブリッシング)
2年ぶりの読み直し。
探究的な学びを駆動するものとは何か?
というテーマにおいて必要な気がしたので再読。
「贈与」を受けること。
「手紙」を受け取るために学ぶ(20.5.3)
http://hero.niiblo.jp/e490625.html
第4章「サンタクロースの正体」に、
時間軸に関することが書いてあったので、あらためて考察。
~~~ここから引用
サンタクロースは人ではありません。
見返りを求めない純粋贈与という非合理性を合理性へと回収するために要請される装置、昨日に与えられた名前であり、贈与の困難を切り抜ける方法だったのです。
サンタクロースの機能の本質がどこにあるかというと、「時間」です。名乗らないというのは時間を生み出すための装置なのです。
贈与は差出人に「届いてくれるといいな」という節度を要求するのです。贈与の呪いの正体は、その節度の無さ、祈りの不在だったのです。そしてその節度の無さとは、贈与は必ず届くという信念から生まれます。
贈与は届かないかもしれない。
贈与は本質的に偶然で、不合理なものだ―。
そう思えることが差出人に必要な資質なのです。
贈与は差出人にとっては、受け渡しが未来時制であり、受取人にとっては受け取りが過去時制になる。
贈与は未来にあると同時に過去にある。スローガン的に言いきればこのようになりますが、正確に言えば、ここでの正しい時制は未来完了時制と現在完了時制です。完了形とは、現在と未来あるいは現在と過去をつなぐ時制です。
「今-未来」「今-過去」が交錯するのが、贈与の本当の姿なのです。それに対し交換は無時間的、つまり、現在時制です。
贈与がどこから始まるかというと、第1章で見た通り、「受け取る」という地点からでした。僕らは受取人としてのポジションからゲームを始めるのです。
「過去そのもの」はもはや存在しません。だから、そこには想像力が要請されます。贈与は差出人に倫理を要求し、受取人に知性を要求する。そして、倫理と知性はどちらが先かと問われれば、それは知性です。つまり、受取人のポジションです。
なぜなら、過去の中に埋もれた贈与を受け取ることができた主体だけが、つまり、贈与に気づくことができた主体だけが、再び未来に向かって贈与を差し出すことができるからです。
この贈与は私のもとへ届かなかったかもしれない。
ということは、私がこれから行う贈与も他者へは届かないかもしれない。
贈与は差出人から見れば、たしかに「届かない手紙」かもしれません。ですが、受取人の視点に立つならば、贈与は「届いていた手紙」になるのではないでしょうか?それは、届いていたことに気づかなかった手紙、あるいは読むことができなかった手紙と言えます。
~~~
手紙、か。たぶん、そういうことなのだろうな、モチベーションの起点は。
手紙(贈与)を受け取ってしまったという自覚。次に渡さなければならない、という使命感。それをResponsibilityと呼ぶのかもしれません。
そして、実は「アイデンティティ」ってそこに生まれるのではないかなと。高校生や大学生が「地方」を目指すのは、直感的にそれを知っているからではないのか。
まず、贈与の受け手になる。そこからしか人生は始まらない。そう直感しているのではないか。
交換主体としての無時間モデルを生きていく自分には存在する価値がない(どこまでも交換可能である)、と。
キーワードは「時間軸」と「想像力」なのだろうと。
その手紙、確かに受け取った、と思うために、知性が必要だから、人は学ぶのだと思う。そして、その手紙を次につなぐためには行動が必要だから、人はプロジェクトに生きていくのだと思う。
起点は手紙(贈与)にあり、そのプロセスをゲーム化していくこと。大枠で言えば、そういうことが令和4年度のテーマになりそうです。
2022年03月05日
ゲームにはゲームを
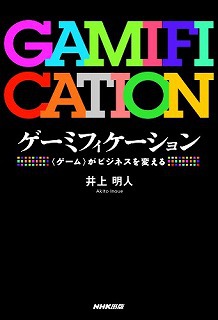
「ゲーミフィケーション」(井上明人 NHK出版)
読み終わりました。
「今時書店」さん、タイムリーな本をありがとうございました。
物語には、物語を
部活には、部活を
ゲームには、ゲームを
ですね。
同じ土俵で上書き保存していくことが大切かなあと。
昨日はプリマペンギーノさんグループの公営塾ネットワーク会議でした。
入試の対応の関係もあり、2日目午前だけの参加となってしまいましたが、
隠岐島前学習センターの澤さんの言葉にビビっときました。
「探究」ってなんですか?
「探究」の魅力を生徒に伝える50分の授業とは?
っていう根源的な問い。
正解のない問いであり、
HOWじゃなくてWHYを問いかける問い。
あの問いの瞬間、参加者がフラットになった。
探究の楽しさは、まさにそこにあるのではないか、って思った。
「場」による共創。「場」を主語にした共創。
「場」に巻き込まれ、一体化し、「問い」を生むこと。
「問い」の創造の前で人と人(高校生と地域の大人)はフラットになる。
それが偶然・予測不可能性のチカラだ。
もうひとつのエッセンスは、学校と方向性を合わせながら役割の違いを相互に理解し合いながら進めていくこと。そこには、アマチュアリズムとアンラーニングがキーワードになっていくと。
また、方向性を合わせていくためにも、対話のデザインが大事だ。初歩的な話だけど、隠岐島前のミーティングは、学校関係者もセンターのスタッフも、ハウスマスターもランダムに輪となって、話をしていた。きっとその積み重ねっていうのも大切なのだろうな。ひとまずウチも会議の席次をクジ引きにしようかな。
っという感じのまとめになりました。
~~~以下自分のためのメモ
グレーゾーンの可能性:「普通」の拡張⇒「関わり」の拡張
「カリキュラム」と「評価」を手放した場としての学習センター
★学校と方向性が同じであることと役割が違うことの明示
学習センターは半歩先をいくタグボート
一緒に問いをつくる⇒フラットになる。
「学び」と「幸せ」の両立:人間力を高めるプロジェクト
「関わり」の変化⇒使う言葉の変化:「連携・協働」⇒「共創」へ
何を残し、何を変えるのか?
「探究」を手放すフェーズに来ている。
チームになる=方向性を合わせ、役割を分担すること
学校の力学の把握:意思決定者、意思決定の仕組み
★手柄は全部学校に。
「これが探究なんですね」って言ってもらえる探究をつくる
探究=場を主語にした共創
授業をアンラーニングする
逆算せずにやってみることと積み上げること。
フェーズによって行き来する。
~~~
ってこんな感じ。シビれるなあ。
エッセンスをたくさんもらいました。
すぐに実践していきますね。
ということで、「ゲーミフィケーション」の話に戻ります。
12月に佐藤恒平さんのところで聞いた、
「ゲーム探究と演劇探究」って話。
まさにこれらのバランスだなあと。
中動態的な演劇アプローチと俯瞰してみるゲーム的アプローチの両方が必要なんだなあと。
で、これってゲームに似てるなあと。
今回の本で、いちばん刺さったのは、
たのしみの「順序」の話。(P162~)
~~~以下引用
コンピューターゲームのなかでたのしみの「順序」をつくるための手法として「アンロック」と「レベルデザイン」の2つがある。
1 アンロック
「アンロック」はかけられた鍵を一つずつ解錠していく」という意味だ。
アンロックが用いられると、最初にプレーヤーができることはほぼ一つしかない。「スーパーマリオブラザーズ」であればジャンプしかできない。だがしばらくプレイしていると「レベルアップしました」と言われ(アイテムを取り)、たとえば火を使うことができるようになる。さらにプレイを進めると空を飛べるようになったりする。
「教育」でも算数・数学などは段階的にステップアップしていくという意味では同じなのだが、致命的な違いは、教育では「義務」として次の課題が与えられるが、ゲームの「アンロック」は「あなたはレベルアップして強くなったので、こんな新しいことができるようになりました。といった「獲得」として、新たな技能が追加される。
新たにやらなければならない「義務」として提示されるか、新たにこれができる「獲得」として提示されるかにより、プレイヤーがたのしみを持てるかどうかは大きく変わってくるだろう。
これが最初から「たくさんのことができますよ」と言われたらどうだろうか。ほとんどの人は少ししか使いこなすことができないのではないだろうか。「アンロック」はかんたんに言えば、まず「これがたのしいですよ」と言われゲームが始まり、ゲームをプレイするなかでできることが少しずつ増えていく手法だ。
2 レベルデザイン
「レベルデザイン」はプレイヤーの自発性を損なわずに、ゲームの難易度を高めていく。そのため、「アンロック」よりもさらに高度な手法だと位置づけることもできるだろう。
「マリオなら、ひとつのネタがあったら必ずそれを覚える場所、実際遊ぶ場所、応用する場所、極める場所がある」(任天堂・宮本茂)
「覚え」「遊び」「応用し」「極める」というマリオをジャンプさせることを学ぶプロセスはプレイヤーに意識させることなく、マップのなかに周到に順序立てて配置されている。これこそが「レベルデザイン」という手法そのものだ。プレイヤーがゲームに対してより能動的にプレイしてゆくときの「上達の実感」や「適度な手応え」は、「レベルデザイン」という方法論によって実装されるのだ。
多くのコンピューターゲームでは、ゲームを遊ぶために必要な努力をなるべくしないように設計されている。マリオを遊ぶとき、ルールブックをわざわざ読み込む必要はない。また、マリオの動き方のパターンを何十種類も覚える必要はない。
~~~
うーむ。たのしみの順序、か。
こういうことですね、佐藤恒平さん。
自らが勝手にハマっていく「探究」は、きっとゲーム以上の「ゲーム」になっているのだろう。
自らがデザインした(あるいは結果的にデザインされた)ゲームの主人公となり、世の中を舞台に、次々に自分の才能を「解錠」し、気が付かないうちに、たくさんの技を「覚え」「遊び」「応用し」「極める」というプロセスを踏んでいるのだろうと。
令和4年度の僕のコミュニケーションデザインのテーマは「ゲーム」と「ゲーミフィケーション」になりそうです。
3月1日に話していた地域でつくる部活動的な動きに合わせて、いい視点をもらいました。
物語には物語を
部活には部活を
ゲームにはゲームを、ですね。
3年前くらいからずっと言っている「場」のチカラは中動態的な「演劇探究」で、今年のゲーミフィケーションは仕組み・構造を知り、俯瞰してデザインする「ゲーム探究」。
おそらくこの2つを行き来することが探究にとって重要なのだと思ってます。
地域と共につくる共創的な探究へと歩みを進めていきましょう。
2022年03月02日
内発的動機付けをつくるゲーミフィケーション

新潟市にある「今時書店」に行ってきました。
https://imadoki-shoten.com/
無人の古本屋さん。
選書のセンスが素晴らしくて、4冊購入しました。
その中の1冊。
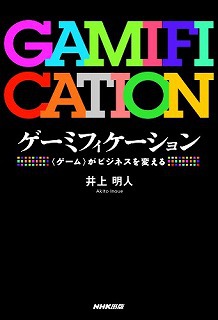
「ゲーミフィケーション」(井上明人 NHK出版)
山形朝日町の佐藤恒平さんと話してから気になっていたキーワード。
昨日は、阿賀黎明探究パートナーズの研修で、
来年度以降のビジョンについて話し合ったのだけど。
大きなテーマとして高校生の内発的動機付けっていうのがありまして、
「楽しそうな大人を見せていくっていうのが大切だよね」って話になっていたのですが。
(詳しくは現在まとめています)
今日はこの本から。
バラク・オバマ(第44代アメリカ大統領)現象っていうのは、
「ゲーミフィケーション」のチカラだったんだ、と改めて。
今日は、part2から「グリーンズ」にも取り上げられている
スターバックスの紙カップを減らすデザインである「カルマカップ」を。
https://greenz.jp/2011/02/01/karma_cup/
1 まず黒板を店頭に置く
2 マイカップを使った人がいたら黒板にチェックをしていく
3 その数が10人になったら10人目のキリ番となった人は飲み物が無料
4 さらに20人目のキリ番の人も無料に
5 30番目の人も無料に・・・という風に10人ごとに無料にしていく
~~~
なるほど~。
これがゲーミフィケーションか~。
毎回クジを引くような感覚でできる。
そして、ある意味、ギフト的でもある。
さらに「参加のデザイン」でもある。
こういう仕組みをつくること。
たぶん、それかもしれませんね。
「ビジョン」という物語を描き、
「物語」を機能させるために、
ゲーミフィケーションという仕掛けが必要なのではないかと。
「観光」と「教育」と「農業」や「林業」と。
「レジャー(旅)」と「ソーシャル(関係性)」と「ストーリー(物語)」と。
それらをつなぐ「ゲーム」をつくるゲーミフィケーションが必要なのだなあと。
令和4年の研究テーマはこれになりそうな気がしています。




