2018年11月30日
「プログラム」「プロジェクト」を外から見る
とある大学生の卒論の一環で、
イナカレッジ修了生へのインタビューをしています。
これがめちゃめちゃ面白いのです。
「イナカレッジとは何か?」
を考える上で、たくさんのヒントをもらっています。
「キャリアデザイン」とか、
「適職」思想とか、
「ロールモデル」とか、
もはや違和感だらけなんだな、って感想。
「やりたいことは何か?」っていう質問に対して、
職業名で答えることを強要されるキャリア教育って
ホントにおかしいなと思う。
「公務員」とか「研究職」
って手段であって、目的ではないでしょうって。
そうじゃなくて、
人生をいかに経営していくか?
顧客は誰で、提供する価値は何なのか?
どういうことを自分は大切にしていきたいのか?
そんな問いにあふれて、
自分なりの現時点での回答を探す、
それがイナカレッジなのかもしれないなあと思いました。
昨日、新潟大学の2人にインタビューをして、
イナカレッジで得たもの。
ひとりは「大切にしたいものを思い出させてくれた」
家族や身近な人たちを大切にしたいって
高校生まで思っていたのに、大学生になって、
目の前のことがいっぱいで、それを忘れていた。
イナカレッジの現場で、家族を大切にしている
人の話を聞いて、それを思い出させてもらった、と。
もうひとりは、「心の余裕が生まれた。」
バイト、サークルで忙しい日々から1か月離れて、
朝ごはん何にしよっか?って考えて、
自分たちが提供するものは何で、そこにどんな価値があるのか?
って問いかけられたこと、と。
だから、いまも3年生だけど、「就活」以外のことも考えられるようになったと。
「就職」は目的ではなくて、手段なんだと思えたこと。
なるほど。
2人にとって、イナカレッジというプログラムは
大きかったのだなあと実感。
そして、大学がやっているプログラムと、
イナカレッジの違いについて話が進んだ。
大学が行うプログラム・プロジェクトに3つほど
関わっているのだけど、そこでは役割が最初から想定されている。
たとえば、
「地域産品を発信する」「伝統文化を継承する」
など。
そのために、大学生ができることを考え、実践していく。
地域プログラム、地域プロジェクトはだいたいそのようになっている。
そうすると何が起こるか?
「発信する」というゴールが見えているから、
地域のフィールドをそのように切り取る。
彼女は、イナカレッジへの参加以降、
それを相対化(外から見る、メタ的に見る)することができるようになったのだという。
つまり、地域資源に出会ったときに、
違う活用方法があるのではないか?
と考えるようになった。
いや、そもそも、目的をもって地域を切り取る場合、
その目的に関わらない要素は「ノイズ」として、
地域資源とは認識されない。
たとえるならば、実験器具であるビーカーの中に、
大学生は素材として、あるいは触媒として放り込まれる。
その中での挙動は、あらかじめ期待されている。
もちろん、実験だから予想外のことは起こるのだけど、
それはプログラム・プロジェクト上は「ノイズ」になる。
しかし、そもそも、
その「ノイズ」にこそ価値はあるのではないか。
上野千鶴子さんが「情報生産者になる」(ちくま新書)

の中で、
「情報はノイズから生まれます。ノイズとは違和感、こだわり、疑問、ひっかかり・・・のことです。」
「情報とは、システムとシステムの境界に生まれます。複数のシステムの境界に立つ者が、いずれをもよりよく洞察することができるからです。」
参考:
「挑戦」するな、「実験」せよ(18.11.7)
http://hero.niiblo.jp/e488367.html
と言っているがまさにそれなんじゃないか。
つまり、ビーカーの外から見てみる。
「プログラム・プロジェクトはビーカーの中の話に過ぎない。」
と思えるかどうか。
それってなかなか難しいのかもしれない。
学校教育という巨大なビーカー(システム)の中で、
期待される挙動を演じて、それを演じることによって評価されてきた。
そのシステムを外から見る、
っていうのはなかなかできない。
「イナカレッジ」の1ヶ月は「暮らし」の中にある
暮らしというのは、ノイズだらけだ。
そして何より、プロジェクト自体を自分たちで再構築しなければならない。
7 どのようにやるか
6 なにをやるか
5 誰のためにやるか
4 なぜやるか
3 どこでやるか
2 いつやるか
1 誰とやるか
これがプロジェクトの7要素なのだけど、
特にこの中の4と5、なぜやるか、誰のためにやるかを
一緒にやるメンバーと、また地域の人たちと
話し合って、合意していかなければならない。
火曜日にインタビューした
長岡の大学生も、3人だからこそ、
地域の人たちのニーズだけではなく、
自分たちが感じた価値に向かって制作物を作れた。
と言っていたが、
まさにそのような問いがあるのだ。
つまり、
イナカレッジはビーカーそのものを自分で作ることができる、
ということだ。
それって、めちゃめちゃ大切なことなんじゃないのか。
与えられたビーカーの中で
期待されるような挙動をするのではなくて、
ビーカーを外から見て、
ああ、自分はそうやって作用しているんだなあと
俯瞰してみる。
そしてビーカーの外やビーカーとビーカーの
あいだにある素材を見つけ、次のビーカーをつくり、入れてみる。
それを繰り返してできていく何か。
残っていく何か。
それこそが地域にとっての、そして世の中にとっての
「価値」そのものなのではないか。
そしてそれを作っていく経験こそが、
価値が流動する時代に生きていくための
「生きる力」なのではないだろうか。
ひとまず3人のインタビューを終えて、
アウトプットしてみたくなったので書いてみました。
写真は、出雲崎海チーム(通称)の写真展の1コマ。

イナカレッジ修了生へのインタビューをしています。
これがめちゃめちゃ面白いのです。
「イナカレッジとは何か?」
を考える上で、たくさんのヒントをもらっています。
「キャリアデザイン」とか、
「適職」思想とか、
「ロールモデル」とか、
もはや違和感だらけなんだな、って感想。
「やりたいことは何か?」っていう質問に対して、
職業名で答えることを強要されるキャリア教育って
ホントにおかしいなと思う。
「公務員」とか「研究職」
って手段であって、目的ではないでしょうって。
そうじゃなくて、
人生をいかに経営していくか?
顧客は誰で、提供する価値は何なのか?
どういうことを自分は大切にしていきたいのか?
そんな問いにあふれて、
自分なりの現時点での回答を探す、
それがイナカレッジなのかもしれないなあと思いました。
昨日、新潟大学の2人にインタビューをして、
イナカレッジで得たもの。
ひとりは「大切にしたいものを思い出させてくれた」
家族や身近な人たちを大切にしたいって
高校生まで思っていたのに、大学生になって、
目の前のことがいっぱいで、それを忘れていた。
イナカレッジの現場で、家族を大切にしている
人の話を聞いて、それを思い出させてもらった、と。
もうひとりは、「心の余裕が生まれた。」
バイト、サークルで忙しい日々から1か月離れて、
朝ごはん何にしよっか?って考えて、
自分たちが提供するものは何で、そこにどんな価値があるのか?
って問いかけられたこと、と。
だから、いまも3年生だけど、「就活」以外のことも考えられるようになったと。
「就職」は目的ではなくて、手段なんだと思えたこと。
なるほど。
2人にとって、イナカレッジというプログラムは
大きかったのだなあと実感。
そして、大学がやっているプログラムと、
イナカレッジの違いについて話が進んだ。
大学が行うプログラム・プロジェクトに3つほど
関わっているのだけど、そこでは役割が最初から想定されている。
たとえば、
「地域産品を発信する」「伝統文化を継承する」
など。
そのために、大学生ができることを考え、実践していく。
地域プログラム、地域プロジェクトはだいたいそのようになっている。
そうすると何が起こるか?
「発信する」というゴールが見えているから、
地域のフィールドをそのように切り取る。
彼女は、イナカレッジへの参加以降、
それを相対化(外から見る、メタ的に見る)することができるようになったのだという。
つまり、地域資源に出会ったときに、
違う活用方法があるのではないか?
と考えるようになった。
いや、そもそも、目的をもって地域を切り取る場合、
その目的に関わらない要素は「ノイズ」として、
地域資源とは認識されない。
たとえるならば、実験器具であるビーカーの中に、
大学生は素材として、あるいは触媒として放り込まれる。
その中での挙動は、あらかじめ期待されている。
もちろん、実験だから予想外のことは起こるのだけど、
それはプログラム・プロジェクト上は「ノイズ」になる。
しかし、そもそも、
その「ノイズ」にこそ価値はあるのではないか。
上野千鶴子さんが「情報生産者になる」(ちくま新書)

の中で、
「情報はノイズから生まれます。ノイズとは違和感、こだわり、疑問、ひっかかり・・・のことです。」
「情報とは、システムとシステムの境界に生まれます。複数のシステムの境界に立つ者が、いずれをもよりよく洞察することができるからです。」
参考:
「挑戦」するな、「実験」せよ(18.11.7)
http://hero.niiblo.jp/e488367.html
と言っているがまさにそれなんじゃないか。
つまり、ビーカーの外から見てみる。
「プログラム・プロジェクトはビーカーの中の話に過ぎない。」
と思えるかどうか。
それってなかなか難しいのかもしれない。
学校教育という巨大なビーカー(システム)の中で、
期待される挙動を演じて、それを演じることによって評価されてきた。
そのシステムを外から見る、
っていうのはなかなかできない。
「イナカレッジ」の1ヶ月は「暮らし」の中にある
暮らしというのは、ノイズだらけだ。
そして何より、プロジェクト自体を自分たちで再構築しなければならない。
7 どのようにやるか
6 なにをやるか
5 誰のためにやるか
4 なぜやるか
3 どこでやるか
2 いつやるか
1 誰とやるか
これがプロジェクトの7要素なのだけど、
特にこの中の4と5、なぜやるか、誰のためにやるかを
一緒にやるメンバーと、また地域の人たちと
話し合って、合意していかなければならない。
火曜日にインタビューした
長岡の大学生も、3人だからこそ、
地域の人たちのニーズだけではなく、
自分たちが感じた価値に向かって制作物を作れた。
と言っていたが、
まさにそのような問いがあるのだ。
つまり、
イナカレッジはビーカーそのものを自分で作ることができる、
ということだ。
それって、めちゃめちゃ大切なことなんじゃないのか。
与えられたビーカーの中で
期待されるような挙動をするのではなくて、
ビーカーを外から見て、
ああ、自分はそうやって作用しているんだなあと
俯瞰してみる。
そしてビーカーの外やビーカーとビーカーの
あいだにある素材を見つけ、次のビーカーをつくり、入れてみる。
それを繰り返してできていく何か。
残っていく何か。
それこそが地域にとっての、そして世の中にとっての
「価値」そのものなのではないか。
そしてそれを作っていく経験こそが、
価値が流動する時代に生きていくための
「生きる力」なのではないだろうか。
ひとまず3人のインタビューを終えて、
アウトプットしてみたくなったので書いてみました。
写真は、出雲崎海チーム(通称)の写真展の1コマ。

2018年11月27日
みえない「歴史」

「日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか」(内山節 講談社現代新書)
いいですね。
こういうの、読みたかった。
古本屋さんバンザイ。
日本人がキツネを含む山の動物に
だまされまくっていた1965年以前と以降では
何が違うのか、を解読した本。
めちゃ面白かった。
すぐには言語化できないのだけど、
これって今に通じてるなあと。
なぜ、若者は田舎を目指すのか?
そして、リアルメディアを欲するのか?
つまり、「場」が必要なのか?
結論だけになるが、本書で内山さんは、
いわゆる日本の「村」で起こってきたこと、続いてきたことをベースに、
このように述べる。
~~~ここから引用
すべてのものを自分の村のなかでつくり変えながら生きていく。
そういう生き方をしていた人々にとっては、知性の継続、身体性の継続、生命性の継続が必要であった。
村人たちは自分たちの歴史のなかに、知性によってとらえられた歴史があり、身体によって受け継がれた歴史があり、生命によって引き継がれた歴史があることを感じながら暮らしてきたのである。
日本の伝統社会においては、個人とはこの3つの歴史の中に生まれた個体のことであり、いま述べた三つの歴史と切り離すことのできない
「私」であった。
といっても、次のことは忘れてはならないだろう。それは身体性の歴史や生命性の歴史は疑うことができない歴史であるが、知性の歴史は誤りをも生み出しかねない歴史だということである。
キツネにだまされたという物語を生み出しながら人々が暮らしていた社会とは、このような社会であった。そしてそれが壊れていくのが1965年頃だったのであろう。
高度経済成長の展開、合理的な社会の形成、進学率や情報のあり方の変化、都市の隆盛と村の衰弱。さまざまなことがこの時代におこり、この過程で村でも身体性の歴史や生命性の歴史は消耗していった。
歴史は結びつきのなかに存在している。
現在との結びつきによって再生されたものが歴史である。
現在の知性と結びついて再生された歴史。
現在の身体性と結びついて再生された歴史。
現在の生命性と結びついて再生された歴史。
1965年頃を境にして、身体性や生命性と結びついてとらえられてきた歴史が衰弱した。その結果、知性によってとらえられた歴史だけが
肥大化した。広大な歴史がみえない歴史になってしまった。
~~~ここまで引用
なるほど
「知性」「身体性」「生命性」ね。
これが1965年を境に「知性」偏重の時代となる。
そして、その「知性」によって描かれた歴史は果たして正しいのか?
という問いかけ。
ここにこの本の神髄があるように思う。
上の章より少し戻るけど紹介したい。
~~~ここから引用
かつて私たちは、人間たちの時代経過のなかに、ひとつの歴史が貫かれていると教わった。しかしいま考えてみると、この歴史観は「中央」あるいは「中心」の成立によって誕生したのではないかと思われる。
たとえば「古事記」「日本書紀」は、古代王朝という「中央」が成立することによって書かれた歴史である。そしてこの「中央」にとっては、「古事記」「日本書紀」は「正史」として機能する。
「国民の歴史」は、国民国家の形成と一対のものであった。「中央」史が国民の歴史に転ずるためには、歴史を共有した国民という擬制の誕生が必要であり、その国民が「中央」と結ばれた存在になることによって、中央史が国史、あるいは国民の歴史といsて機能するようになったのである。
そのとき歴史学は、客観的事実の中身をめぐって争った。「本当の歴史」を、それぞれの視点から書こうとした。しかし、統合された歴史が誕生したという、そのことの意味を問おうとはしなかった。
国民国家、すなわち人間を国民として一元的に統合していく国家は、国民の言語、国民の歴史、国民の文化、国民のスポーツといったさまざまなものを必要とした。求められたのは国民としての共有された世界である。
そのひとつが国民の歴史であり、私たちにとっては日本史である。そして、だからこそその歴史は人間の歴史として書かれた。
かつてさまざまに展開していた「村の歴史」はそのような歴史ではなかった。それは自然の人間が交錯するなかに展開する歴史であり、生者と死者が相互性をもって展開していく歴史であった。
なぜなら「村」とは生きている人間の社会のことではなく、伝統的には、自然と人間の世界のことであり、生の空間と死の空間が重なり合うなかに展開する世界のことだからである。
ところで「中央の歴史」としての「国民の歴史」が書かれるようになると、その「歴史」には共通するひとつの性格が付与された。現在を過去の発展したかたちで描く、という性格である。
それは簡単な方法で達成される。現在の価値基準で過去を描けばよいのである。たとえば現在の社会には経済力、経済の発展という価値基準がある。この基準にしたがって過去を描けば、過去は経済的に低位な社会であり、停滞した社会としてとらえられる。
だがこの精神の展開は、現在の価値基準からはとらえられないものを、みえないものにしていく作用を伴う。
キツネにだまされながら形成されてきた歴史も、過去の人々の微笑ましい物語にしかならないだろう。
~~~ここまで引用
うーむ。
とうなるしかない。
かつての「村」は、いや、人間の暮らしは、
「身体性」と「生命性」を伴っていた。
それが1965年頃を境に、
「知性」のみに偏重した暮らしへとシフトしたんだ。
大学生がなぜ、田舎を、地方を目指すのか。
「農業」や「リアルメディア」に心を惹かれるのか。
それは、「身体性」や「生命性」と伴った何か。
そこに何かがあると直観しているからではないか。
ベルクソンは1907年に言った。
「直観は精神そのものだ、ある意味で生命そのものだ。
知性は物質を生みだした過程にまねた過程が
そこに切りだしたものにすぎないのだ。
・・・知性からは決して直観に移れないであろう」
(創造的進化 1907)
なるほどなあ。
みえないもの。
そこに何かあるんじゃないか。
そういった感覚そのものがなくなっていった。
言語化、見える化ではなくて、言葉にできないもの、見えないもの。
身体性や生命性。
そういう感覚を、大学生や20代は必要としているのではないか。
それを求めてくる大学生に何ができるか?
どんな「場」を共有できるか。
イナカレッジをはじめ、地域で活動する団体は
おそらくそんなことが求められているのだ。

2018年11月26日
「ラボ」というゆるさと強さ
湯島・ソラでのミーティング。
http://solur.jp/

この場所をどんな場にしていこうか、っていう話。
1ヶ月半前、
10月4日に「NPO・NGO草莽の集い2018」
がこの場所であり、
10月5日に茨城大学で「iopラボのための場づくりラボ」
が開催された。
そのときのブログ。
http://hero.niiblo.jp/e488221.html
目的を持って始めないこと(18.10.6)
「暗やみ本屋ハックツ」活動に
20代や中高生が集まってくるのはなぜか?
という問い。
それに対して、
口をついて出た言葉が
前出のブログのタイトルでもある
・目的をもって始めないこと
・課題を解決しないこと
だった。
「つながるカレー」の加藤さんに出会い、
・「アマチュアリズム」には失敗は存在しない。
・「予測不可能性」こそがエンターテイメントの本質。
・「一期一会」を生み出し、感じてもらうことが場のチカラを高める。
ことを知った。
そしてそれは、
「挑戦」ではなくて、
「実験」なのだと最近分かった。
http://hero.niiblo.jp/e488367.html
挑戦するな実験せよ(18.11.7)
「挑戦」には「目的」「目標」があり、成功と失敗があるが、
「実験」には「目的」「目標」がなく、結果があるだけだ。
っていうこと。
で、
茨城大学・iopラボ2days
1日目の「場づくりラボ」では、少人数だったので、
つくりたい「場」の言語化が行われた。
2日目の「チームひきだし」報告会では、
企業の経営者多数、他大学の学生も交えて、
「場」のチカラのリアルを体感した。
ラボ、なんだって。
ラボに過ぎないんだって。
実験しているんだって。
そんなことを思いながら、
本屋に行くと、目の前に飛び込んでくる本があるから不思議だ。

「創造的脱力~かたい社会に変化をつくる、ゆるいコミュニケーション論」(若新雄純 光文社新書)
あの「鯖江市JK課」の若新さんの本。
過去に一度、ETIC.ギャザリングでお会いしたような。
このまえがきがまさにそのような
話が書いていて、
めちゃめちゃ共感したので抜粋します。
~~~ここから引用
そもそも、既得権にいる人たち全てをバランスよく納得させつつ、直面した問題を根本的に解決できるような都合のいい「差し替えプラン」など、あるはずがないのです。
経済学者のヨーゼフ・シュンペーターは、「創造的破壊」を唱えましたが、それは結果の話であって、現実には、その新しい活動や政策をつくりだすために既存のシステムや古い文化を正面対決で破壊しようとしても、なかなかうまくいきません。
古くなった社会システムが、ただの理論的な「システム」ならそれでいいかもしれません。しかし実際には、現実は生々しい「人間」の集合体です。
複雑な感情や思惑がうずまいていて、簡単には変化を受け入れてはくれないし、席を譲ってくれたりもしません。
僕は本当に変革が必要なのであれば、なんでも白黒つけようとする「勝負」や「答え探し」はもうやめた方がいいと思っています。
それよりも硬直化したシステムや複雑な人間関係を「ゆるめる」という脱力的なアプローチが大切なのです。
~~~ここまで引用
という前提で、
鯖江市のJK課の話へとつながっていく
▽▽▽ここからさらに引用
「JK課は、あくまで実験的なプロジェクトで、政策の本流じゃないですから」といった調子で、「ゆるいプラン」であることを強調しました。その結果多くの人が気軽に参加できる環境ができ、活動に広がりが生まれています。
「とりあえず楽しもう」「やりながらちょっとずつ良くしていけばいいじゃないか」という適度な脱力感が、「白か黒か」「成功か失敗か」という過度な緊張感を遠ざけ、すぐには結果の見えない実験的なプロジェクトに粘り強さをもたらしています。
「脱力」は「無力」ではありません。そして、それは「不真面目」でもありません。
「こういうのもあっていいんじゃないですか?」とか、「まずは実験してみよう」といって、本流ではないところで、周辺からアクションしてみる。既存のシステムや勢力を直接には攻撃してしまわない離れたところから、でも、ちゃんと見えるところから、それをやりたいという当事者たちが集まって、真面目に考え、小さくてもいいから、何かが変化するような振り切った実験を、真剣にやってみるのです。
失敗したならやり直せばいいし、もしうまくいったらなら、どんどん増やしたりひろげたりすればいい。
すると、そこに人や情報がどんどん流れてきて、いつかは本流にすり替わったりするかもしれません。
もちろん、新しい支流や一つの文化になるだけでもいい。これが僕の考える、「創造的破壊」ならぬ「創造的脱力」です。
△△△ここまでさらに引用
いいね、創造的脱力
さらに、その方法について
以下のようにイントロダクションしています。
↓↓↓ここからまた引用
目的やゴール、到達点が明確で、勝ち負けや白黒をはっきりさせたいプロジェクトやチームには、それにふさわしいまとめ方やまとめ役というのが必要なのだと思います。正しく状況を判断し、的確に情報を収集、分析し、権限を使って指示や命令をおこないながら、ときには破壊的な攻めにでることも必要なのでしょう。
一方で、すすんでみなければゴールがわからず、偶然の出来事や変化を受け入れながら学んでいくような実験的な取り組みにおいては、成果や正解を焦って求めすぎない脱力感と、そのプロセスを楽しめる柔軟性が必要です。
でも、ただ力を抜いてやわらかくしているだけでは、「まとまり」ができずバラバラになってしまいます。脱力しながらもうまくまとめていくためには、その場にいる一人ひとりの欲や好奇心、その場から得られる体験や感動をみんなで共有し、ときにはぶつかり合いながらもお互いを必要とするような、人間関係にみちあふれた「関わり合い」が必要です。
僕はこれを「ゆるいコミュニケーション」と呼んでいます。「ゆるい」というのは、「いい加減」ということではありません。
きっちりとは固定されていないのに、つながっている。
強制されているわけではないのに、参加している。
必要に迫られているわけでもないのに、欲している。
細かいことは決まっていないのに、全体としては成り立っている。
一見もろそうに見えて、実は「かたいつながり」以上の「ネバネバ感」があり、「まとまり」があるのです。
さらに「ゆるい」だけあって、平均からのズレや偏りを排除してしまわず、むしろその差や違いを吸収できる余白や「ゆらぎ」をもっています。つまり、「ゆるいコミュニケーション」は、一人ひとりの異なる価値観やライフスタイルをお互いに認め合い、それぞれの個性的なパーソナリティを引き出し合うことができる「成長の機会」なのです。
↑↑↑ここまでまだ引用
そうそう。
引用しまくってしまったけど、
なんか、これって「場のチカラ」のことじゃないかなと。
「ラボ」っていう場は、
そういうことを目指しているのではないかと。
「にいがたイナカレッジ」が生み出すプロジェクトも
そういう「ゆるいプロジェクト」なのではないか。
そしてそんな場を大学生たちは
切実に必要としているのではないか。
必要なのは、ラボ、なのではないか。
安心安全と偶然性のグラデーションの中にある
実験としての場。
場のチカラの構成要素である
・誰とやるか
・いつやるか
・どこでやるか
それを大切にしていくこと。
課題認識・目的・目標を共有して始めようとするから、
そこに参加する大学生は自分である必要がないと感じてしまうのではないか。
あなたとしかできない、この時しかできない、この場所でしかできない。
そういうプロジェクト、つまりラボに参加したいのではないか。
ラボ的なプロジェクトにおいて、
大学生は実験素材であり、
フィールド(地域、企業、プロジェクト)は実験器具である。
だから、募集の段階でも、
「このプロジェクトの目的・ゴール」や「得られる経験」
を明確にするのではなくて、
このプロジェクトのキーワードは、
「食」「本」「農業」「贈与経済」「コミュニケーション」です。
フィールドはこんな場所、住むところはこういう感じです。
あなた自身が持っている気になるキーワードと
なぜそれが気になるか?
を教えてください。
そうやって、
面談の段階でプロジェクトを組み上げていくような、
そういうラボを東京にも作っていくこと、なのかな
と思いました。
それはイナカレッジに限らず、
地域資源×都市の若者っていうキーワードの
プロジェクトにはすごい必要な場となるように思う。
半農半X研究所の塩見直紀さんが
「ひとり一研究所」の時代だと言っていたけど、
若者が地域で「実験」するための「場」をつくること。
それが僕なりの「学びあいの仕組みづくり」かもしれないなあと
思ってきました。
さて、年内に動きますよ~。
http://solur.jp/

この場所をどんな場にしていこうか、っていう話。
1ヶ月半前、
10月4日に「NPO・NGO草莽の集い2018」
がこの場所であり、
10月5日に茨城大学で「iopラボのための場づくりラボ」
が開催された。
そのときのブログ。
http://hero.niiblo.jp/e488221.html
目的を持って始めないこと(18.10.6)
「暗やみ本屋ハックツ」活動に
20代や中高生が集まってくるのはなぜか?
という問い。
それに対して、
口をついて出た言葉が
前出のブログのタイトルでもある
・目的をもって始めないこと
・課題を解決しないこと
だった。
「つながるカレー」の加藤さんに出会い、
・「アマチュアリズム」には失敗は存在しない。
・「予測不可能性」こそがエンターテイメントの本質。
・「一期一会」を生み出し、感じてもらうことが場のチカラを高める。
ことを知った。
そしてそれは、
「挑戦」ではなくて、
「実験」なのだと最近分かった。
http://hero.niiblo.jp/e488367.html
挑戦するな実験せよ(18.11.7)
「挑戦」には「目的」「目標」があり、成功と失敗があるが、
「実験」には「目的」「目標」がなく、結果があるだけだ。
っていうこと。
で、
茨城大学・iopラボ2days
1日目の「場づくりラボ」では、少人数だったので、
つくりたい「場」の言語化が行われた。
2日目の「チームひきだし」報告会では、
企業の経営者多数、他大学の学生も交えて、
「場」のチカラのリアルを体感した。
ラボ、なんだって。
ラボに過ぎないんだって。
実験しているんだって。
そんなことを思いながら、
本屋に行くと、目の前に飛び込んでくる本があるから不思議だ。

「創造的脱力~かたい社会に変化をつくる、ゆるいコミュニケーション論」(若新雄純 光文社新書)
あの「鯖江市JK課」の若新さんの本。
過去に一度、ETIC.ギャザリングでお会いしたような。
このまえがきがまさにそのような
話が書いていて、
めちゃめちゃ共感したので抜粋します。
~~~ここから引用
そもそも、既得権にいる人たち全てをバランスよく納得させつつ、直面した問題を根本的に解決できるような都合のいい「差し替えプラン」など、あるはずがないのです。
経済学者のヨーゼフ・シュンペーターは、「創造的破壊」を唱えましたが、それは結果の話であって、現実には、その新しい活動や政策をつくりだすために既存のシステムや古い文化を正面対決で破壊しようとしても、なかなかうまくいきません。
古くなった社会システムが、ただの理論的な「システム」ならそれでいいかもしれません。しかし実際には、現実は生々しい「人間」の集合体です。
複雑な感情や思惑がうずまいていて、簡単には変化を受け入れてはくれないし、席を譲ってくれたりもしません。
僕は本当に変革が必要なのであれば、なんでも白黒つけようとする「勝負」や「答え探し」はもうやめた方がいいと思っています。
それよりも硬直化したシステムや複雑な人間関係を「ゆるめる」という脱力的なアプローチが大切なのです。
~~~ここまで引用
という前提で、
鯖江市のJK課の話へとつながっていく
▽▽▽ここからさらに引用
「JK課は、あくまで実験的なプロジェクトで、政策の本流じゃないですから」といった調子で、「ゆるいプラン」であることを強調しました。その結果多くの人が気軽に参加できる環境ができ、活動に広がりが生まれています。
「とりあえず楽しもう」「やりながらちょっとずつ良くしていけばいいじゃないか」という適度な脱力感が、「白か黒か」「成功か失敗か」という過度な緊張感を遠ざけ、すぐには結果の見えない実験的なプロジェクトに粘り強さをもたらしています。
「脱力」は「無力」ではありません。そして、それは「不真面目」でもありません。
「こういうのもあっていいんじゃないですか?」とか、「まずは実験してみよう」といって、本流ではないところで、周辺からアクションしてみる。既存のシステムや勢力を直接には攻撃してしまわない離れたところから、でも、ちゃんと見えるところから、それをやりたいという当事者たちが集まって、真面目に考え、小さくてもいいから、何かが変化するような振り切った実験を、真剣にやってみるのです。
失敗したならやり直せばいいし、もしうまくいったらなら、どんどん増やしたりひろげたりすればいい。
すると、そこに人や情報がどんどん流れてきて、いつかは本流にすり替わったりするかもしれません。
もちろん、新しい支流や一つの文化になるだけでもいい。これが僕の考える、「創造的破壊」ならぬ「創造的脱力」です。
△△△ここまでさらに引用
いいね、創造的脱力
さらに、その方法について
以下のようにイントロダクションしています。
↓↓↓ここからまた引用
目的やゴール、到達点が明確で、勝ち負けや白黒をはっきりさせたいプロジェクトやチームには、それにふさわしいまとめ方やまとめ役というのが必要なのだと思います。正しく状況を判断し、的確に情報を収集、分析し、権限を使って指示や命令をおこないながら、ときには破壊的な攻めにでることも必要なのでしょう。
一方で、すすんでみなければゴールがわからず、偶然の出来事や変化を受け入れながら学んでいくような実験的な取り組みにおいては、成果や正解を焦って求めすぎない脱力感と、そのプロセスを楽しめる柔軟性が必要です。
でも、ただ力を抜いてやわらかくしているだけでは、「まとまり」ができずバラバラになってしまいます。脱力しながらもうまくまとめていくためには、その場にいる一人ひとりの欲や好奇心、その場から得られる体験や感動をみんなで共有し、ときにはぶつかり合いながらもお互いを必要とするような、人間関係にみちあふれた「関わり合い」が必要です。
僕はこれを「ゆるいコミュニケーション」と呼んでいます。「ゆるい」というのは、「いい加減」ということではありません。
きっちりとは固定されていないのに、つながっている。
強制されているわけではないのに、参加している。
必要に迫られているわけでもないのに、欲している。
細かいことは決まっていないのに、全体としては成り立っている。
一見もろそうに見えて、実は「かたいつながり」以上の「ネバネバ感」があり、「まとまり」があるのです。
さらに「ゆるい」だけあって、平均からのズレや偏りを排除してしまわず、むしろその差や違いを吸収できる余白や「ゆらぎ」をもっています。つまり、「ゆるいコミュニケーション」は、一人ひとりの異なる価値観やライフスタイルをお互いに認め合い、それぞれの個性的なパーソナリティを引き出し合うことができる「成長の機会」なのです。
↑↑↑ここまでまだ引用
そうそう。
引用しまくってしまったけど、
なんか、これって「場のチカラ」のことじゃないかなと。
「ラボ」っていう場は、
そういうことを目指しているのではないかと。
「にいがたイナカレッジ」が生み出すプロジェクトも
そういう「ゆるいプロジェクト」なのではないか。
そしてそんな場を大学生たちは
切実に必要としているのではないか。
必要なのは、ラボ、なのではないか。
安心安全と偶然性のグラデーションの中にある
実験としての場。
場のチカラの構成要素である
・誰とやるか
・いつやるか
・どこでやるか
それを大切にしていくこと。
課題認識・目的・目標を共有して始めようとするから、
そこに参加する大学生は自分である必要がないと感じてしまうのではないか。
あなたとしかできない、この時しかできない、この場所でしかできない。
そういうプロジェクト、つまりラボに参加したいのではないか。
ラボ的なプロジェクトにおいて、
大学生は実験素材であり、
フィールド(地域、企業、プロジェクト)は実験器具である。
だから、募集の段階でも、
「このプロジェクトの目的・ゴール」や「得られる経験」
を明確にするのではなくて、
このプロジェクトのキーワードは、
「食」「本」「農業」「贈与経済」「コミュニケーション」です。
フィールドはこんな場所、住むところはこういう感じです。
あなた自身が持っている気になるキーワードと
なぜそれが気になるか?
を教えてください。
そうやって、
面談の段階でプロジェクトを組み上げていくような、
そういうラボを東京にも作っていくこと、なのかな
と思いました。
それはイナカレッジに限らず、
地域資源×都市の若者っていうキーワードの
プロジェクトにはすごい必要な場となるように思う。
半農半X研究所の塩見直紀さんが
「ひとり一研究所」の時代だと言っていたけど、
若者が地域で「実験」するための「場」をつくること。
それが僕なりの「学びあいの仕組みづくり」かもしれないなあと
思ってきました。
さて、年内に動きますよ~。
2018年11月24日
対話の場をデザインする
昨日のつづき。
「就活」を学びあいに変える。
その第1歩は、「チームひきだし」のような、
「対話の場のデザイン」であると思う。
昨日、若松代表が書いていたけど、
「学びあい」は、フラットな関係性を必要としている。
お互いが学ぶ者という同志になること。
そこが必要だ。
そのフラットな関係性をつくるために、
「チューニング」をするのだ。
チューニングの要点は、
心を開き、「対話」の準備をすること。
「対話」の場に降りていくことをデザインすること。
そして
「対話」を始めること。
http://hero.niiblo.jp/e462090.html
(大学生は「場のチカラ」に貢献する 15.1.29)
http://hero.niiblo.jp/e462144.html
(未来は対話による会議から創られる 15.1.30)
http://hero.niiblo.jp/e462198.html
(ラボラトリーだという自覚 15.1.31)
キーワードからこのあたりを読み直す。
「対話」をデザインすることで、
フラットな関係性が生まれ、
そこから「学びあい」が起こり、
そこから新しいものが生まれる。
たぶん、「チームひきだしが目指すものはそういうことなのかもしれない。
ラボという場のデザインも同じだ。
この会社の魅力は何か?
っていうお題があることで、
学生同士に共通の問いが生まれた。
対話が始まった。
学生の意見を聞いて、採用活動を改めて見つめなおす。
そこから学生と採用担当者との対話が始まった。
まず、対話の場をデザインすること。
対話の場とフラットな関係性と学びあいを
ぐるぐるさせて、場のチカラを高めていくこと。
アウトプットはそういうところから生まれていくのだっていう仮説。
写真は
新潟→茨城ドライブのワンショット。

「就活」を学びあいに変える。
その第1歩は、「チームひきだし」のような、
「対話の場のデザイン」であると思う。
昨日、若松代表が書いていたけど、
「学びあい」は、フラットな関係性を必要としている。
お互いが学ぶ者という同志になること。
そこが必要だ。
そのフラットな関係性をつくるために、
「チューニング」をするのだ。
チューニングの要点は、
心を開き、「対話」の準備をすること。
「対話」の場に降りていくことをデザインすること。
そして
「対話」を始めること。
http://hero.niiblo.jp/e462090.html
(大学生は「場のチカラ」に貢献する 15.1.29)
http://hero.niiblo.jp/e462144.html
(未来は対話による会議から創られる 15.1.30)
http://hero.niiblo.jp/e462198.html
(ラボラトリーだという自覚 15.1.31)
キーワードからこのあたりを読み直す。
「対話」をデザインすることで、
フラットな関係性が生まれ、
そこから「学びあい」が起こり、
そこから新しいものが生まれる。
たぶん、「チームひきだしが目指すものはそういうことなのかもしれない。
ラボという場のデザインも同じだ。
この会社の魅力は何か?
っていうお題があることで、
学生同士に共通の問いが生まれた。
対話が始まった。
学生の意見を聞いて、採用活動を改めて見つめなおす。
そこから学生と採用担当者との対話が始まった。
まず、対話の場をデザインすること。
対話の場とフラットな関係性と学びあいを
ぐるぐるさせて、場のチカラを高めていくこと。
アウトプットはそういうところから生まれていくのだっていう仮説。
写真は
新潟→茨城ドライブのワンショット。

2018年11月23日
チームひきだしで就活を「学びあい」に変える
茨城大学「iopラボ」2DAYSでした。

21日はiopラボのための「場づくりラボ」

そして昨日、22日は「チームひきだし」報告会でした。

参加学生の発表のあと

受け入れ企業を含めた座談会

締めは「ヒキダシ、ヒキダシ」

会場閉鎖してからも会場外で盛り上がる。
なんというか、
ラボの可能性というか理想形というか
そういうのを見たような気がしました。
21日に話していたのが左脳的な(頭脳的な)ラボの価値だったとすると
昨日話していたのは、右脳的な(感覚的な)ラボの価値だったように思いました。
そして、「チームひきだし」というコンテンツの魅力。
このプロジェクトは「株式会社えぽっく」の若松さんと
この春から練ってきた企画で、
1週間のプログラム、4社に取材に行き、
経営者や社員と対話し、その後ワークショップを行い、
その会社の魅力や感じたことをアウトプットするというもの。
僕は2週目チームの
「株式会社ユーゴー」さんの会に
少しだけお邪魔したのだけど、とてもいい雰囲気で進んでいた。
昨日の報告会も
全員が自己紹介と出身地を語ったところから
すでに笑いが出ていたので、
とてもなごやかな雰囲気で進んだ。
なんか、あったかい場だった。
さて、
そんな「チームひきだし」報告会から
印象に残った発言と自分の気づき(つぶやき)をピックアップ。
~~~ここから
「見えないものを見ようとして望遠鏡を覗きこんだ。」
そんな感じ。チームひきだし 取材型インターンシップ。
大企業より中小企業のほうがチーム戦を戦っているような感じになるのかもね。
チームひきだしの受け入れ企業ってみんなそんな感じ。
「魅力を発見する」というお題がいいのかもね。
塗装とか農園とか介護とかって
自己分析を先にしていたら、まったく知り得ない業界。
☆ここから参加大学生のコメント
「どうせ働くなら「雰囲気のよい会社」を選びたい。」
「待ってるだけじゃなくて、自分から動くことが必要だと知った。」
「はたらくことに対するイメージが変わった」
「業種じゃなくて人との関係性で会社を決めたい」
~~~こんな感じ
「就職」とか「就活」への怖れっていうのは、
見たことがない、やったことがない
ことに対して怖れているだけなんじゃないか。
・社長は厳しい人なんじゃないか
・社長は「社長室」にいて指示を出すだけじゃなんじゃないか
・〇〇業界はブラックなんじゃないか
・IT企業ってネクラな人が集まっているんじゃないか
みたいな。
まるで幼い子どもが、
「悪いことばっかりしていると、怖い魔女がさらいにくるぞ」
みたいな脅しを本気でビビっている、みたいな感じなんじゃないかって思った。
ただ、知ればいい。
見てみればいい。
やってみればいい。
対話してみればいい。
それだけでだいぶ違うんだなあと思った。
さらに、座談会で、こんなシーンがあった。

参加学生の参加した感想
「8名でやれたのがよかった」
「1つのゴールに向かっているから仲良くなれた」
に対して、(株)ユーゴーの稲野辺さんが言った。
「それって会社も一緒ですよ」
そう。
それって会社も一緒なんだよね。
チーム戦を戦っているんだ。
そんな当たり前のことを改めて
思い出させてくれた。
会社でも、そういう「場」をつくるっていうこと。
そういうことが「はたらく」っていうことなんじゃないか。
稲野辺さんが今回のプログラムを通じて
得たものを次のように説明してくれた。
「再確認した」
大切にしたいもの、自分たちがどう感じられているのかを再確認した。
ココやっぱり面白いんだ!みたいな。
チームひきだしはそういう場を作った。
それはつまり、「学びあい」の場のデザインだったのかもしれない。
11月3日のしまね教育の日の島根県益田市のプレゼンで感じたこと
http://hero.niiblo.jp/e488353.html
「対話」から始まる「学びあい」(18.11.4)
学びあいの「場」っていうのは、
「就活」っていう舞台でも作れると思ったし、
そういう風にシフトしていく、いや、
シフトさせていくって思った。
自己分析して
向いている業種業界を知って、
そこから業界とか企業研究して、
エントリーして、面接受けて、、、
ってホントかよ?
って思った。
ひきだし参加学生が語った
「どうせ働くなら「雰囲気のよい会社」を選びたい。」
「業種じゃなくて人との関係性で会社を決めたい」
これのほうがよっぽどリアルなんじゃないかって思った。
ラストの感想の場面で、
参加学生のひとりが語ってくれた。
「貰いっぱなしで申し訳ないと思っていたけど、
経営者の人たちも学ぶところがあったと言ってくれたことがうれしかった」
そう。
たぶんそれ。
学びあいの「場」のデザイン。
それって、
「就活」にこそ必要なんじゃないか。
高いコストをかけて、新卒採用をする。
その「対話」から人事担当者は、会社は、何を学ぶか?
「就活」そのものを学びあいの「場」にしたい。
「チームひきだし」っていうプロジェクトは、そういう実験なのだと
僕は思っている。

21日はiopラボのための「場づくりラボ」

そして昨日、22日は「チームひきだし」報告会でした。

参加学生の発表のあと

受け入れ企業を含めた座談会

締めは「ヒキダシ、ヒキダシ」

会場閉鎖してからも会場外で盛り上がる。
なんというか、
ラボの可能性というか理想形というか
そういうのを見たような気がしました。
21日に話していたのが左脳的な(頭脳的な)ラボの価値だったとすると
昨日話していたのは、右脳的な(感覚的な)ラボの価値だったように思いました。
そして、「チームひきだし」というコンテンツの魅力。
このプロジェクトは「株式会社えぽっく」の若松さんと
この春から練ってきた企画で、
1週間のプログラム、4社に取材に行き、
経営者や社員と対話し、その後ワークショップを行い、
その会社の魅力や感じたことをアウトプットするというもの。
僕は2週目チームの
「株式会社ユーゴー」さんの会に
少しだけお邪魔したのだけど、とてもいい雰囲気で進んでいた。
昨日の報告会も
全員が自己紹介と出身地を語ったところから
すでに笑いが出ていたので、
とてもなごやかな雰囲気で進んだ。
なんか、あったかい場だった。
さて、
そんな「チームひきだし」報告会から
印象に残った発言と自分の気づき(つぶやき)をピックアップ。
~~~ここから
「見えないものを見ようとして望遠鏡を覗きこんだ。」
そんな感じ。チームひきだし 取材型インターンシップ。
大企業より中小企業のほうがチーム戦を戦っているような感じになるのかもね。
チームひきだしの受け入れ企業ってみんなそんな感じ。
「魅力を発見する」というお題がいいのかもね。
塗装とか農園とか介護とかって
自己分析を先にしていたら、まったく知り得ない業界。
☆ここから参加大学生のコメント
「どうせ働くなら「雰囲気のよい会社」を選びたい。」
「待ってるだけじゃなくて、自分から動くことが必要だと知った。」
「はたらくことに対するイメージが変わった」
「業種じゃなくて人との関係性で会社を決めたい」
~~~こんな感じ
「就職」とか「就活」への怖れっていうのは、
見たことがない、やったことがない
ことに対して怖れているだけなんじゃないか。
・社長は厳しい人なんじゃないか
・社長は「社長室」にいて指示を出すだけじゃなんじゃないか
・〇〇業界はブラックなんじゃないか
・IT企業ってネクラな人が集まっているんじゃないか
みたいな。
まるで幼い子どもが、
「悪いことばっかりしていると、怖い魔女がさらいにくるぞ」
みたいな脅しを本気でビビっている、みたいな感じなんじゃないかって思った。
ただ、知ればいい。
見てみればいい。
やってみればいい。
対話してみればいい。
それだけでだいぶ違うんだなあと思った。
さらに、座談会で、こんなシーンがあった。

参加学生の参加した感想
「8名でやれたのがよかった」
「1つのゴールに向かっているから仲良くなれた」
に対して、(株)ユーゴーの稲野辺さんが言った。
「それって会社も一緒ですよ」
そう。
それって会社も一緒なんだよね。
チーム戦を戦っているんだ。
そんな当たり前のことを改めて
思い出させてくれた。
会社でも、そういう「場」をつくるっていうこと。
そういうことが「はたらく」っていうことなんじゃないか。
稲野辺さんが今回のプログラムを通じて
得たものを次のように説明してくれた。
「再確認した」
大切にしたいもの、自分たちがどう感じられているのかを再確認した。
ココやっぱり面白いんだ!みたいな。
チームひきだしはそういう場を作った。
それはつまり、「学びあい」の場のデザインだったのかもしれない。
11月3日のしまね教育の日の島根県益田市のプレゼンで感じたこと
http://hero.niiblo.jp/e488353.html
「対話」から始まる「学びあい」(18.11.4)
学びあいの「場」っていうのは、
「就活」っていう舞台でも作れると思ったし、
そういう風にシフトしていく、いや、
シフトさせていくって思った。
自己分析して
向いている業種業界を知って、
そこから業界とか企業研究して、
エントリーして、面接受けて、、、
ってホントかよ?
って思った。
ひきだし参加学生が語った
「どうせ働くなら「雰囲気のよい会社」を選びたい。」
「業種じゃなくて人との関係性で会社を決めたい」
これのほうがよっぽどリアルなんじゃないかって思った。
ラストの感想の場面で、
参加学生のひとりが語ってくれた。
「貰いっぱなしで申し訳ないと思っていたけど、
経営者の人たちも学ぶところがあったと言ってくれたことがうれしかった」
そう。
たぶんそれ。
学びあいの「場」のデザイン。
それって、
「就活」にこそ必要なんじゃないか。
高いコストをかけて、新卒採用をする。
その「対話」から人事担当者は、会社は、何を学ぶか?
「就活」そのものを学びあいの「場」にしたい。
「チームひきだし」っていうプロジェクトは、そういう実験なのだと
僕は思っている。
2018年11月19日
アイデンティティとコミュニティ

「レイヤー化する世界~テクノロジーとの共犯関係が始まる」
(佐々木俊尚 NHK出版新書)
2012年4月10日のブログと同タイトル。
http://hero.niiblo.jp/e165439.html
同年7月7日にも
「アイデンティティの半分はコミュニティでできている」
http://hero.niiblo.jp/e182795.html
で書いていて、
そのあいだの5月11日にも
「生きる力とはアイデンティティを再構築する力」
http://hero.niiblo.jp/e171388.html
というタイトルで書いている。
2012年のテーマは「アイデンティティ」だった。
そこに帰ってきたのかもしれない。
「やりたいことがわからない」
「自分に自信がない」
「就職したいけど就活したくない」
この謎を解くには、
「アイデンティティ」というテーマに行き当たる。
冒頭の本は、2013年の本なのだけど、
ここには歴史的視座から、「場」についての興味深い考察がある。
中世から近代へ
帝国から国民国家へ
そして、国民国家というシステムの限界と
「場」による支配へ。
と乱暴に要約するとこういう感じになるのだけど。
昨日も書いたけど、
国民国家の神髄は、
「ウチとソトに分ける」
ということだという。
たしかに、
ヨーロッパと「そのソト」を分けて、植民地を作っていった。
国内と「そのソト」を分けて、戦争を仕掛けていった。
企業内と「そのソト」を分けて、競争を勝ち抜いていった。
「コミュニティ」っていうのはウチ(内側)のことだ。
実はそれと「アイデンティティ」は密接にかかわっている。
「ふるさと難民」という言葉がある。
東京出身でふるさとがない大学生が
地域に出て行って、そこを「第二のふるさと」にする。
それって
まさに「コミュニティによってアイデンティティを再構築」しているんじゃないか。
しかし。
根本的には、その手法は使えなくなる。
国民国家、資本主義という現在のシステムのベースにある
「ウチとソトに分ける」という
方法論自体がすでに限界に達しているからだ。
収奪すべきソトはもう存在しない。
だからこそ、ブラック企業の問題などが
起こっているのだ。
もう、ウチもソトも存在しない。
権力構造でも力関係でもなく、
テクノロジーという「場」に下から支配されている。
だから、所属すべきコミュニティを失い、
人はアイデンティティ不安を抱えているのではないか。
アイデンティティ不安。
それは自分という存在への不安だ。
だからこそ、
個人レベルでこそ、リアルな「場」を必要としているのだと
僕は思う。
それは「コミュニティ」というウチを作ることではないのでは、というのが
現時点での仮説である。
2018年11月17日
「アイデンティティ」とか「個性」とか
「やりたいことがわからない」
「自分に自信がない」
「就活したくない」
っていう大学生の根っこには、
「アイデンティティ」問題が横たわっているように思う。
「アイデンティティ」問題のキーワードとしては、
「個性」とか
「自分らしさ」とか
「貢献する」とか
そういう感じ。

「レイヤー化する世界~テクノロジーとの共犯関係が始まる」
(佐々木俊尚 NHK出版新書)
は、「近代」という時代と
「国民国家」というシステムを見渡す上で
非常に面白い1冊となっている。
~~~以下メモ
中世ヨーロッパでは、聖と俗が切り離されて存在していた。
印刷技術の発明が宗教改革を生んだ。
「よりどころ」としてのキリスト教が弱体化した。
聖の力の弱まりを俗の力によってカバーしようとした
「絶対王政」システムが生まれ、そして倒された。
「国民国家」システムの発明。
戦争に圧倒的に強いシステムだったため、世界を席巻した。
自分たちのよりどころは、神(宗教)でも古い大人(歴史)でもなく、
自分たち自身だと知った。
~~~以上メモ
国民国家の神髄は、「ウチとソトに分ける」
ということだと佐々木さんは言う。
そうやって、他国と戦争し、植民地をつくり、
自国を反映させる、ということだった。
これを「アイデンティティ」という側面から見てみる。
市民革命を成功させたフランスは、
その3年後のオーストリア・プロシア同盟との
戦争で敗走に次ぐ敗走を重ね、
自国内へ侵入させてしまったとき、義勇兵を募集する。
「祖国は危機にあり。祖国を救わんと考える義勇兵は応募せよ」
「フランス国民である」というアイデンティティ。
それが「よりどころ」となったと佐々木さんは言う。
おそらくはそれが、現代日本においても、
溶け出してしまっているのだろうと思う。
地域コミュニティ
や
会社コミュニティ
が弱体化し、
それに伴って、アイデンティティの
「よりどころ」を失っている。
しかもここにきて、
「国民国家」という概念そのものが
危機に瀕しているように思う。
アイデンティティ・クライシス
おそらくこれを解読しないことには、
「やりたいことはわからない」以下、
若者の課題の糸口は見えない。
「自分に自信がない」
「就活したくない」
っていう大学生の根っこには、
「アイデンティティ」問題が横たわっているように思う。
「アイデンティティ」問題のキーワードとしては、
「個性」とか
「自分らしさ」とか
「貢献する」とか
そういう感じ。

「レイヤー化する世界~テクノロジーとの共犯関係が始まる」
(佐々木俊尚 NHK出版新書)
は、「近代」という時代と
「国民国家」というシステムを見渡す上で
非常に面白い1冊となっている。
~~~以下メモ
中世ヨーロッパでは、聖と俗が切り離されて存在していた。
印刷技術の発明が宗教改革を生んだ。
「よりどころ」としてのキリスト教が弱体化した。
聖の力の弱まりを俗の力によってカバーしようとした
「絶対王政」システムが生まれ、そして倒された。
「国民国家」システムの発明。
戦争に圧倒的に強いシステムだったため、世界を席巻した。
自分たちのよりどころは、神(宗教)でも古い大人(歴史)でもなく、
自分たち自身だと知った。
~~~以上メモ
国民国家の神髄は、「ウチとソトに分ける」
ということだと佐々木さんは言う。
そうやって、他国と戦争し、植民地をつくり、
自国を反映させる、ということだった。
これを「アイデンティティ」という側面から見てみる。
市民革命を成功させたフランスは、
その3年後のオーストリア・プロシア同盟との
戦争で敗走に次ぐ敗走を重ね、
自国内へ侵入させてしまったとき、義勇兵を募集する。
「祖国は危機にあり。祖国を救わんと考える義勇兵は応募せよ」
「フランス国民である」というアイデンティティ。
それが「よりどころ」となったと佐々木さんは言う。
おそらくはそれが、現代日本においても、
溶け出してしまっているのだろうと思う。
地域コミュニティ
や
会社コミュニティ
が弱体化し、
それに伴って、アイデンティティの
「よりどころ」を失っている。
しかもここにきて、
「国民国家」という概念そのものが
危機に瀕しているように思う。
アイデンティティ・クライシス
おそらくこれを解読しないことには、
「やりたいことはわからない」以下、
若者の課題の糸口は見えない。
2018年11月12日
本を届ける、「一箱古本市」
松本・栞日の菊地さんが
やっている栞日古本市。
今月は18日にあるんですけどね。
そのガイドライン。
https://sioribi.jp/info/event_181118_02/
ココです。
栞日にとって、一箱古本市とは何か?
表現されているのが特にここ。
~~~ここから引用
【3】「一箱」古本市です。
当日の朝、〈古道具 燕〉で見繕った古い木箱を一箱ずつお渡しします。
木箱はどれもほぼ同じサイズですが、細かな寸法(幅・奥行き・深さ)はまちまちです。
当日、受付順に選んでいただきます。
途中、箱の中が少なくなってきたら、適宜補充していただいても構いませんが、お客さんにご覧いただく商品は、配布した箱の中に収めた本のみでお願いします。
また、当日ご持参いただく本の合計冊数も、ざっくり「箱2杯分」程度を、上限としてイメージしていただけると助かります。
理由は幾つかありますが…
限られた選択肢とスペースの中で、自分の本棚を表現して、その限られた書籍を通じて、目の前のお客さんと会話していただいた方が、結果的に、1冊1冊の取引の意味の濃度が高まって、本を手放した本人にとっても、本を受け取ったお客さんにとっても、もちろん本自身にとっても、幸せなのではないかなぁ、と考えているからです。
~~~ここまで引用
菊地さんは、
2011年6月のニイガタブックライト主催の
一箱古本市(ちなみに僕もツルハシブックスで出店していました)
に来ていたのだという。
その際、ブックディレクター幅さんの
「痕跡本」の棚を見て、
すでに菊地さんがついたときには、
棚は売れてスカスカになっていたんだという。
そして「補充はしないんですか?」
と聞いたら、「一箱古本市ですから」
と返答されたのだという。
そして、僕もなんとなく覚えているけど、
夜のトークイベントで、
同じような話をされていた。
「一箱古本市」って一箱だから面白いんじゃないか?
たしかそういう感じのコメントだったと思う。
僕もそのトークイベント会場にはいて、
なんとなく覚えている。
一箱であること。
それはたぶん。
菊地さんがこのラストに書いている、
「本を手放した本人にとっても、本を受け取ったお客さんにとっても、もちろん本自身にとっても、幸せなのではないかなぁ、と考えているからです。」
ここに尽きるのだろう。
本を売る。
自分の手元の本を売る、というのは
どういうことなのか。
そういえば、以前、大手中古書店チェーンで
働いている大学生が言っていた。
そこでは、本は完全に「モノ化」されているのだという。
一定の期間が経った本は108円コーナーに移動され、
またそこで一定期間が経った本は、
別の書店へ移送されるか、処分されるのだという。
それが本好きの彼女にとっては、
とても耐えられないのだという。
一方で、
伊那の土田さんが言っていた
「古本屋」っていうのは「本の一時預かり」のことだ。
誰かのためにこの本をキープしなきゃ、と思うから本を仕入れ、
誰かが買ってくれるのを待つ。
それがいつなのかわからないけど。
http://hero.niiblo.jp/e487816.html
(18.7.26 「本屋である」ということ)
本を届ける。
ってなんだっけ?
っていう強烈な問い。
菊地さんの姿勢。
僕自身も「暗やみ本屋ハックツ」
を再定義したいと思った。
菊地さんの言葉を借りれば、
「ハックツを再ハックツしたい」っていうことかな。

やっている栞日古本市。
今月は18日にあるんですけどね。
そのガイドライン。
https://sioribi.jp/info/event_181118_02/
ココです。
栞日にとって、一箱古本市とは何か?
表現されているのが特にここ。
~~~ここから引用
【3】「一箱」古本市です。
当日の朝、〈古道具 燕〉で見繕った古い木箱を一箱ずつお渡しします。
木箱はどれもほぼ同じサイズですが、細かな寸法(幅・奥行き・深さ)はまちまちです。
当日、受付順に選んでいただきます。
途中、箱の中が少なくなってきたら、適宜補充していただいても構いませんが、お客さんにご覧いただく商品は、配布した箱の中に収めた本のみでお願いします。
また、当日ご持参いただく本の合計冊数も、ざっくり「箱2杯分」程度を、上限としてイメージしていただけると助かります。
理由は幾つかありますが…
限られた選択肢とスペースの中で、自分の本棚を表現して、その限られた書籍を通じて、目の前のお客さんと会話していただいた方が、結果的に、1冊1冊の取引の意味の濃度が高まって、本を手放した本人にとっても、本を受け取ったお客さんにとっても、もちろん本自身にとっても、幸せなのではないかなぁ、と考えているからです。
~~~ここまで引用
菊地さんは、
2011年6月のニイガタブックライト主催の
一箱古本市(ちなみに僕もツルハシブックスで出店していました)
に来ていたのだという。
その際、ブックディレクター幅さんの
「痕跡本」の棚を見て、
すでに菊地さんがついたときには、
棚は売れてスカスカになっていたんだという。
そして「補充はしないんですか?」
と聞いたら、「一箱古本市ですから」
と返答されたのだという。
そして、僕もなんとなく覚えているけど、
夜のトークイベントで、
同じような話をされていた。
「一箱古本市」って一箱だから面白いんじゃないか?
たしかそういう感じのコメントだったと思う。
僕もそのトークイベント会場にはいて、
なんとなく覚えている。
一箱であること。
それはたぶん。
菊地さんがこのラストに書いている、
「本を手放した本人にとっても、本を受け取ったお客さんにとっても、もちろん本自身にとっても、幸せなのではないかなぁ、と考えているからです。」
ここに尽きるのだろう。
本を売る。
自分の手元の本を売る、というのは
どういうことなのか。
そういえば、以前、大手中古書店チェーンで
働いている大学生が言っていた。
そこでは、本は完全に「モノ化」されているのだという。
一定の期間が経った本は108円コーナーに移動され、
またそこで一定期間が経った本は、
別の書店へ移送されるか、処分されるのだという。
それが本好きの彼女にとっては、
とても耐えられないのだという。
一方で、
伊那の土田さんが言っていた
「古本屋」っていうのは「本の一時預かり」のことだ。
誰かのためにこの本をキープしなきゃ、と思うから本を仕入れ、
誰かが買ってくれるのを待つ。
それがいつなのかわからないけど。
http://hero.niiblo.jp/e487816.html
(18.7.26 「本屋である」ということ)
本を届ける。
ってなんだっけ?
っていう強烈な問い。
菊地さんの姿勢。
僕自身も「暗やみ本屋ハックツ」
を再定義したいと思った。
菊地さんの言葉を借りれば、
「ハックツを再ハックツしたい」っていうことかな。

2018年11月09日
いま、始めること
信州大学「地域ブランド実践ゼミ」
塩尻市‐信州大学包括連携協定
地域ブランド共同研究連携授業
の第7回授業に出てきました。

まずは山田さんから地域ベンチャー留学の説明。

今日のゲストは、「家族留学」など、
家族をキーワードに活躍する起業家、新居日南恵さん。
大学1年生の時に
「manma」をスタートした日南恵さんの
一言一言にスピードと臨場感があったなあ、と。
仕事の情報はこんなにたくさんあるのに
結婚の情報がない。
キャリアを考えるように、結婚を選択できるんじゃないか。
ということで立ち上げた。
当時19歳。
サービスは思いついたが、
始められる自信がない。
そんな彼女へのアドバイスが、
「いま(19歳で)始めなさい。」
だった。
「失敗しても大学生という肩書は消えないから
普通に就活すればいい。
もし10年続いたら、そのときは
ぜったいにあなたの右に並ぶものはいない。」
そして、もうひとつ、
自分はリーダー向きじゃなく
サポート向きだと思って尻込みしていると、
「やってないのに、なんでわかるの?
1年やって、失敗してから言えば?」
と言われた。
そしてやることを決め、
次に仲間を集めるフェーズ。
渋谷のカフェで3人で話して、
なんとなくmanmaという名前を決めた。
そして、一番おもしろかったのは、
彼女が「家族」というキーワードにいたった経緯。
彼女の大学1年生の時のキーワード。
「自己肯定」「スクールカウンセラー」「言葉の力」
など。
その中で「自己肯定」にフォーカスして、深めていった。
「自己肯定」
→
「ライフキャリアプランニング」
→
「家族のマネジメント」
というように掘り下げていったのだという。
そして、何より、行動してきた、ということ。
AorBで迷っていないこと。
「最後のメッセージ」
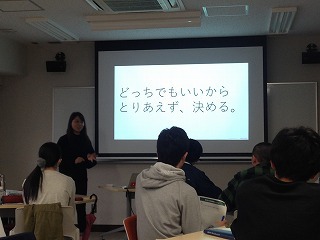
「どっちでもいいから、とりあえず決める」
彼女にとって怖いのは、「選んでいない状態」で進んでいくこと。
中途半端にやること。
途中でやめること。
「あれいけたかもな~」って思い続けること。
なるほど。
始めてみるっていうこと大事だ。
始められる人って、
「挑戦」じゃなく、「実験」だと思える人なのではないか。
失敗ではなくて、
結果が出るだけだと思える人なのではないかな。
キャロル・ドゥエック博士の
マインドセットの話にも通じる。
http://hero.niiblo.jp/e262963.html
(挑戦するのに自信は要らない2013.5.11)
自分の能力は変わらないという
固定的知能観と
やればやるほど自分は成長できるという
成長的知能観。
それは中学1年を境に、
どんどん固定的知能観へとシフトするのだという。
それは、「実験」することをやめてしまうから
ではないのか。
「挑戦」の呪縛にとらわれているからではないのか。
「実験」として始める。
そこなのかもしれない。
塩尻市‐信州大学包括連携協定
地域ブランド共同研究連携授業
の第7回授業に出てきました。

まずは山田さんから地域ベンチャー留学の説明。

今日のゲストは、「家族留学」など、
家族をキーワードに活躍する起業家、新居日南恵さん。
大学1年生の時に
「manma」をスタートした日南恵さんの
一言一言にスピードと臨場感があったなあ、と。
仕事の情報はこんなにたくさんあるのに
結婚の情報がない。
キャリアを考えるように、結婚を選択できるんじゃないか。
ということで立ち上げた。
当時19歳。
サービスは思いついたが、
始められる自信がない。
そんな彼女へのアドバイスが、
「いま(19歳で)始めなさい。」
だった。
「失敗しても大学生という肩書は消えないから
普通に就活すればいい。
もし10年続いたら、そのときは
ぜったいにあなたの右に並ぶものはいない。」
そして、もうひとつ、
自分はリーダー向きじゃなく
サポート向きだと思って尻込みしていると、
「やってないのに、なんでわかるの?
1年やって、失敗してから言えば?」
と言われた。
そしてやることを決め、
次に仲間を集めるフェーズ。
渋谷のカフェで3人で話して、
なんとなくmanmaという名前を決めた。
そして、一番おもしろかったのは、
彼女が「家族」というキーワードにいたった経緯。
彼女の大学1年生の時のキーワード。
「自己肯定」「スクールカウンセラー」「言葉の力」
など。
その中で「自己肯定」にフォーカスして、深めていった。
「自己肯定」
→
「ライフキャリアプランニング」
→
「家族のマネジメント」
というように掘り下げていったのだという。
そして、何より、行動してきた、ということ。
AorBで迷っていないこと。
「最後のメッセージ」
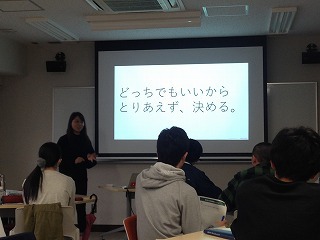
「どっちでもいいから、とりあえず決める」
彼女にとって怖いのは、「選んでいない状態」で進んでいくこと。
中途半端にやること。
途中でやめること。
「あれいけたかもな~」って思い続けること。
なるほど。
始めてみるっていうこと大事だ。
始められる人って、
「挑戦」じゃなく、「実験」だと思える人なのではないか。
失敗ではなくて、
結果が出るだけだと思える人なのではないかな。
キャロル・ドゥエック博士の
マインドセットの話にも通じる。
http://hero.niiblo.jp/e262963.html
(挑戦するのに自信は要らない2013.5.11)
自分の能力は変わらないという
固定的知能観と
やればやるほど自分は成長できるという
成長的知能観。
それは中学1年を境に、
どんどん固定的知能観へとシフトするのだという。
それは、「実験」することをやめてしまうから
ではないのか。
「挑戦」の呪縛にとらわれているからではないのか。
「実験」として始める。
そこなのかもしれない。
2018年11月07日
「挑戦」するな、「実験」せよ

「情報生産者になる」(上野千鶴子 ちくま新書)
鳥取・定有堂書店で購入。
まだまだ冒頭なのだけど、いい言葉入ってます。
わかりやすい。
「情報はノイズから生まれます。
ノイズとは違和感、こだわり、疑問、ひっかかり・・・のことです。」
「情報とは、システムとシステムの境界に生まれます。
複数のシステムの境界に立つ者が、いずれをもよりよく洞察することができるからです。」
なるほど。
たしかにそうかもしれないですね。
「違和感」をキャッチできるか、
キャッチした違和感を情報に変換できるか、
これがカギを握っていると思います。
僕が違和感を感じてきた言葉。
「挑戦」とか「目標」とか。
大学生の言葉でいえば、
「やりたいことがわからない」
「自分に自信がない」
かもしれない。
「自信」とは「やったことがあること」だと
たしか堀江さんが言っていたのだけど、
その理屈でいけば、
「やってみる」ことがとても大切なんだと思う。
「自分に自信がない」と言っている若者に対して、
いわゆる「スモールステップ理論」がある。
つまり、小さなチャレンジを繰り返して、
だんだんと大きなチャレンジをしていく、というもの。
しかし、この理論には重大な見落としがある。
本当に自信がない人は最初の小さなチャレンジのドミノが倒れないのだ。
だから、その人はいつまで立っても自信がつくことはない。
「やってみる」人を増やす。
これはたしか、2014年に「にいがた未来考房」の立ち上げの
時に使ったように思うが、
昨日、大学生からのツッコミを受けて見えてきたもの。
「チャレンジできない」ことを気にして、
「チャレンジしなきゃ」と思っている人は多いが、
実際にその人たちは何もはじめていない。
チャレンジする前に「トライ」があることを忘れてしまっている。
そうか。
実験か、と思った。
挑戦ではなく、実験をすること。
「挑戦」には「目的」「目標」があり、成功と失敗があるが、
「実験」には「目的」「目標」がなく、結果があるだけだ。
「挑戦」ではなく、「実験」
そしてその結果を出すのは、個人でもチームではなく、「場のチカラ」
であること。
だから、ふりかえりをするとき、
「予想しなかったよかったこと」も
「予想しなかった悪かったこと」も
結果にすぎない。
次からどうしようか。
そのための材料に過ぎない。
たぶんそういう思考でプロジェクトに参加していくこと。
予想できなかった「結果」を楽しむこと。
その先を、見てみたい。
やったことがないからやってみた。
やってみるの理由はそれだけでいい。
人は「やってみる」を繰り返すことで
生きていくのだ。
2018年11月05日
「関係人口」で「地方」と「若者」が学びあう

「関係人口をつくる」(田中輝美 木楽舎)
の輝美さんにお会いすることができました!
「関係人口は定住者増のための手段ではない」
うん。
たぶんこれ、かなりの自治体の人が誤解している気がします。
いきなり響きあったのは、出版物のリレーの話。
出版物は以下の駅伝を走っている。
0走者:題材者・テーマ
1走者:著者
2走者:編集者
3走者:営業
4走者:書店員(書店)
5走者:読者
輝美さんは、第1,2走者を、僕は第3,4走者を
走りたいということ。
「存在を誰かに伝えたい」(作り方の編集)っていうのと、
「メディアをつくりたい」(売り方の編集)っていうのとは違うんだっていうこと。
第3、第4走者を肌感覚を伴った「リアルメディア」に
したいんだなあと。
それは大きな気づきだった。
僕はどちらかというと、第3走者以下を読者に寄りながら
作っていきたいのだと。
「駅伝を走りたい」という意味では同じなのだけど、
その走るポジションが違うんだなあと。
そんなことを思いました。
ほかにも話していて様々な学びがあったのでメモ。
~~~ここからメモと自分の感じたこと(ツイートメモ)
若者に「好きなことは何か?」と
聞きすぎるのはきついのではないか?
中身が空っぽなのに「アウトプットしろ」って言われ続けるのはつらいと思う。
「君は何をやりたいのか?」という問いの暴力。
「やりたいこと」じゃなくて、過去に「心動いたこと」があって、
それを起点にプロジェクトをつくっていくほうが
当事者意識とモチベーションが高くなると思う。
その「心動いたこと」をつくるために、
学校外の「場」が存在しているような地域社会。
その場に参加する機会を提供するための本屋。
「地域再生」っていう大テーマに向かっている。
「教育改革」も「風の人」も「関係人口」もそのための手法。
「思考停止」こそが絶望。「考え続けること」でしか希望は生まれない。
「他者」と出会うと揺さぶられるが、「他人」を目の前にしても揺さぶられない。
都会では「他人」が多すぎて「他者」に出会えないので揺さぶられない、心が動かない。
「イナカレッジ」と「アイデンティティ」。このテーマは深めたい。
都市は「機能」に分化していて、田舎は未分化である。
田舎では「機能」としてではなく、ひとりの「存在」として承認される。
「関係人口」とは、
「地方」と「若者」が共に学びあう関係である。
「関係人口」⇒「課題解決」
「地方」と「若者」双方の課題を同時に解決する
「交流」⇒「定住」
↑
ココのプロセスに関係人口があるわけではなくて、
そのあいだの概念というだけ。
住む、住まないではなく、
地域(と都市部の若者)の課題を解決する手法として
「関係人口」があるのではないか。
「定住」に向かっていくのは人口減少時代には無理筋。
⇒他市町村との競争を激化させることに未来はあるのか?
「誇りの空洞化」をどうするか?
「地域を維持」することより、
ひとりひとりが「誇り」を持って死んでいくこと。
「大人のアドバイス」には
「なんでですか?」と問いかける。
⇒たいていがお金だったりくだらない理由でアドバイスしている。
~~~以上メモ
キーワードだらけ。
いろいろ気づいた。
「地方」と「若者」。
どちらかというと、「若者」視点から
この10年、自分は考えてきたのだなあと。
その上で、
「なぜ、本屋なのか?」
という問い。
そうそう。
本屋は手段であって、目的ではないからね。
現時点で整理すると、
エンターテイメントの本質は「予測不可能性」で、
「予測不可能性」がもっとも得られるのは学ぶこと本を読むことで、
「学びあいのデザイン」と「学びの機会提供」をして、
日々を考え続けるエンターテイメント化すること。
その「学び」のフロンティアが「地域課題」であり、
「学び」のパートナーが「地域住民」と「関係人口」(都市住民)となる。
またその根っこには、
若者自身の「アイデンティティ」の課題があり、
「ふるさと難民」などはそこにあたる。
「アイデンティティ」の課題を解決するには、
「未分化」な地方に身を置いて、存在承認の機会を得ること、
「場のチカラ」を感じることと、
「チューニング」によって、思ったことを言えるデザインをし、
場に自分を溶かしていくこと。
そして場のチカラでアウトプットするという繰り返しをすること。
そうやって、「アイデンティティ」そのものを
相対化、他者化していくことが可能なのではないかと感じた。
輝美さんに言われた宿題。
「それを一言でいうと何なのか?」
次回、お会いする時まで、出しておきます。
素敵な時間をありがとうございました!



宍道湖の夕日がこの後朱鷺色に変わって、
初めて蛍を見たとき以来の感動を経験しました。
島根・松江、住みたい。
2018年11月04日
「対話」から始まる「学びあい」
しまね教育の日フォーラム。
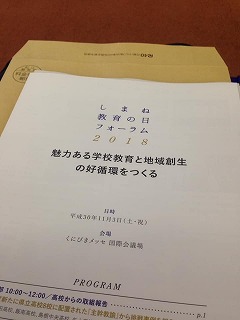

霧がすごい松江・くにびきメッセで聞いてきました。
一番すごかったのは、
益田市の取り組み。


「益田版カタリ場」と「新・職業体験」。
この2つの取り組みにはトリハダが立ちました。
~~~以下メモ
島根県益田市:「人が育つまち」
「益田版カタリ場」
事前アンケート:約半数の中高生が気軽に話をする大人が1人もいない。
約半数の中・高生が益田には「魅力的な大人がいない」と思っている。
⇒ロールモデルとの出会い不足。
人との繋がりが希薄化しつつある時代だからこそ、対話を軸に、人を繋ぐ
働き方のロールモデルから、生き方、在り方のロールモデルへ。
「ワークキャリア」教育から「ライフキャリア」教育へ。
ライフキャリア教育で、未来をつくる。
学校と家庭任せではなく、地域住民全体の力で。
中学生×地域の担い手
公民館との連携でその地区の大人と子どもの対話の場をつくる。
中学生×産業の担い手
新・産業体験
体験中心から、対話重視の職場体験へ。「やりがい」や「想い」に触れる
高校生×働く大人でカタリ場⇒高校生×小学生へ
最後は自分が語り手になる。
結果、約8割の中高生が益田には魅力的な大人がいる、と思うように。
益田出身の大学生が益田で活動するように。
職場体験で行った公民館へ、次は大学生として。
母校でのカタリ場を企画・地域の大人との出会い直し。
「益田版カタリ場」:地域の大人と子どもが本音の対話で繋がる。
これまでのキャリア教育:一方的な講演スタイル
カタリ場:双方向
「評価しない大人」に出会うこと。
中学校カタリ場は公民館連携で、高校カタリ場は企業連携で。
「新・職場体験」:対象は中学生
1 求人票の発行・ポリシー・大切にしていることが記載されている
2 中学生へ面接(市役所職員による)
3 事業所研修会:ねらいとノウハウ共有
4 体験⇒対話:価値観・生き様を聞く
大切なのは教育を支える風土を醸成すること。
「新・職場体験」の結果、その会社に入りたいといって実業系の高校に入学した人が3名出た。
生き抜いていく力を地域の人と一緒につくっていくこと。
事業所研修会で地域の人同士がつながる。
「求人票」のデザイン
A5サイズの枠だけがあり、PRしたいこと、大切にしたいこと、ポリシーなどがあればお書きください。
これって、受け入れ事業所に対する壮大な問い。
そして、「求人票」そのものが地域の人から子どもたちへの「手紙」であり、「メディア」そのものになっている。
「ふりかえり」のデザイン。
事業所を自分の言葉で紹介するレポート(写真付き)と自分の感想を書く。
⇒礼状の代わりに出す。
たしかに、型どおりの礼状もらうよりよっぽどうれしいな。
「対話」を促すデザイン
・名刺をつくる
・質問を考えていく
・忙しくても昼食時等には対話をしてほしいと頼む。
「対話ができた」と思った子の意識が変わっていく。
~~~ここまでメモ。
他にも「高校魅力化」についての話もあったのだけど、
ひとまずは一番シビれた益田市のことを。
「自己を探求するとはいったいなんだろうか?」
「学びあいってなんだ?」
「地域の大人が参画する学びとは?」
ツルハシブックスや暗やみ本屋ハックツが言っていた
「第3の大人」のコンセプトを思い出した。
それは「評価しない」大人。
教えてくれるのではなく、あり方が伝わってくるような大人。
そして、何より、
「共に学ぼう」と思っている大人。
ヒーローズファーム時代に中村くんと実現しようと構想していた
経営者と学生が共に学ぶモデルを思い出した。
圧巻だったのは、
「新・職業体験」のデザイン。
特に求人票そのものだけでメディアになっているところ。
思いを出発点に人と出会うこと。
高校魅力化も、職場体験そのものも、
ツールに過ぎないんだっていうこと。
問いを共有し、「ともに学びあう」っていうこと
それをデザインしていくことなのだろうと思った。
僕が「本屋」で実現しようとしている世界観が
益田市ではすでに動き出しつつあった。
心地よい敗北感。
そして同時に、
僕は地域側にそんなプラットフォームをつくろうと思った。
その舞台はもちろん本屋さんだ。
「カタリ場」や「新・職業体験」のようなプログラムで
出会った大人たちにまた出会える場。
偶然、居合わせる場。
何かがうっかり始まってしまうような場。
そんな「場としての本屋」をつくりたいという思いを強くしました。
素敵な機会をありがとうございました。

松江の夜景がとてもキレイでした。
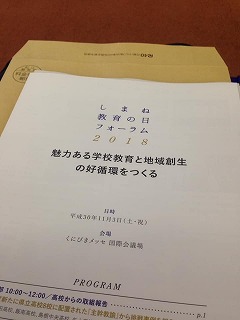

霧がすごい松江・くにびきメッセで聞いてきました。
一番すごかったのは、
益田市の取り組み。


「益田版カタリ場」と「新・職業体験」。
この2つの取り組みにはトリハダが立ちました。
~~~以下メモ
島根県益田市:「人が育つまち」
「益田版カタリ場」
事前アンケート:約半数の中高生が気軽に話をする大人が1人もいない。
約半数の中・高生が益田には「魅力的な大人がいない」と思っている。
⇒ロールモデルとの出会い不足。
人との繋がりが希薄化しつつある時代だからこそ、対話を軸に、人を繋ぐ
働き方のロールモデルから、生き方、在り方のロールモデルへ。
「ワークキャリア」教育から「ライフキャリア」教育へ。
ライフキャリア教育で、未来をつくる。
学校と家庭任せではなく、地域住民全体の力で。
中学生×地域の担い手
公民館との連携でその地区の大人と子どもの対話の場をつくる。
中学生×産業の担い手
新・産業体験
体験中心から、対話重視の職場体験へ。「やりがい」や「想い」に触れる
高校生×働く大人でカタリ場⇒高校生×小学生へ
最後は自分が語り手になる。
結果、約8割の中高生が益田には魅力的な大人がいる、と思うように。
益田出身の大学生が益田で活動するように。
職場体験で行った公民館へ、次は大学生として。
母校でのカタリ場を企画・地域の大人との出会い直し。
「益田版カタリ場」:地域の大人と子どもが本音の対話で繋がる。
これまでのキャリア教育:一方的な講演スタイル
カタリ場:双方向
「評価しない大人」に出会うこと。
中学校カタリ場は公民館連携で、高校カタリ場は企業連携で。
「新・職場体験」:対象は中学生
1 求人票の発行・ポリシー・大切にしていることが記載されている
2 中学生へ面接(市役所職員による)
3 事業所研修会:ねらいとノウハウ共有
4 体験⇒対話:価値観・生き様を聞く
大切なのは教育を支える風土を醸成すること。
「新・職場体験」の結果、その会社に入りたいといって実業系の高校に入学した人が3名出た。
生き抜いていく力を地域の人と一緒につくっていくこと。
事業所研修会で地域の人同士がつながる。
「求人票」のデザイン
A5サイズの枠だけがあり、PRしたいこと、大切にしたいこと、ポリシーなどがあればお書きください。
これって、受け入れ事業所に対する壮大な問い。
そして、「求人票」そのものが地域の人から子どもたちへの「手紙」であり、「メディア」そのものになっている。
「ふりかえり」のデザイン。
事業所を自分の言葉で紹介するレポート(写真付き)と自分の感想を書く。
⇒礼状の代わりに出す。
たしかに、型どおりの礼状もらうよりよっぽどうれしいな。
「対話」を促すデザイン
・名刺をつくる
・質問を考えていく
・忙しくても昼食時等には対話をしてほしいと頼む。
「対話ができた」と思った子の意識が変わっていく。
~~~ここまでメモ。
他にも「高校魅力化」についての話もあったのだけど、
ひとまずは一番シビれた益田市のことを。
「自己を探求するとはいったいなんだろうか?」
「学びあいってなんだ?」
「地域の大人が参画する学びとは?」
ツルハシブックスや暗やみ本屋ハックツが言っていた
「第3の大人」のコンセプトを思い出した。
それは「評価しない」大人。
教えてくれるのではなく、あり方が伝わってくるような大人。
そして、何より、
「共に学ぼう」と思っている大人。
ヒーローズファーム時代に中村くんと実現しようと構想していた
経営者と学生が共に学ぶモデルを思い出した。
圧巻だったのは、
「新・職業体験」のデザイン。
特に求人票そのものだけでメディアになっているところ。
思いを出発点に人と出会うこと。
高校魅力化も、職場体験そのものも、
ツールに過ぎないんだっていうこと。
問いを共有し、「ともに学びあう」っていうこと
それをデザインしていくことなのだろうと思った。
僕が「本屋」で実現しようとしている世界観が
益田市ではすでに動き出しつつあった。
心地よい敗北感。
そして同時に、
僕は地域側にそんなプラットフォームをつくろうと思った。
その舞台はもちろん本屋さんだ。
「カタリ場」や「新・職業体験」のようなプログラムで
出会った大人たちにまた出会える場。
偶然、居合わせる場。
何かがうっかり始まってしまうような場。
そんな「場としての本屋」をつくりたいという思いを強くしました。
素敵な機会をありがとうございました。

松江の夜景がとてもキレイでした。
2018年11月02日
「リアルメディア」という参加のデザイン
奥井希さんの「流しのこたつ」に初参戦した。

駅ではこんな感じにコンパクト

最初は2人

隣で歌を歌っているおねーさんいます。

東京から1週間前に転勤してきた柳原くんが寄ってくれました

ブルガリア人御一行様も参戦。
いやあ、あれが「流しのこたつ」か~。
昨日集まった人たちは
東京で屋台をやっている吉池くんと
(はじめ、「屋台をやっている」ってどういうことだ?って思った)
舟型の屋台をつくった伏見の港デザイン研究所の林さん。
https://ameblo.jp/fns716/entry-12382242736.html
↑これが伏見マール。やばい。熱い。
こたつとか屋台とかって「リアルメディア」なんだって。
紙メディア
ウェブメディア
ときて、次は里山十帖の岩佐さんのように
「リアルメディア」なんだなと。
あと、吉池くんは、
なんとびっくり僕も敬愛する橘川幸夫さんの「デメ研」
にいるのだという。
橘川さんと言えば、
「参加型メディア」の草分け。
僕は「インターネットは儲からない」の頃からの
橘川さんのファンなのだけど、まさかこんなところでつながるとは。
紙メディア、ウェブメディア、そしてリアルメディアが
循環していることがポイントだと実践者はいう。
流しのこたつは
プライベートとパブリックのあいだの「場」
だと奥井さんは言った。
吉池さんは
屋台をやることで、君も(リアル)メディアをつくれよ、っていうメッセージを
伝えたいって言ってた。
僕が思ったのは、
「リアルメディア」は「参加のデザイン」でもあるなと。
参加型メディアっていうのは
インターネット以降、言われつづけているのだけど、
紙やウェブだと、
発信者と受信者(受け手)は
相互に関係しあっているとはいえ、
分かれている。
そこにきて、
今回のこたつや屋台のようなリアルメディアは、
その「場」を分け合っているという意味において、
発信者と受信者の区別はない。
誰もが発信者であり、同時に受信者になっている。
つまり、もっとも境界があいまいになっている。
たぶんそれなんだ、って。
境界をあいまいにすること。
それが余白をつくり、参加の余地が生まれる。
http://hero.niiblo.jp/e488318.html
「余白」とは、境界をあいまいにして「委ねる」こと
(2018.10.29)
で書いたように、
肌感覚をもったリアルメディアだからこそ、
「参加のデザイン」が可能になるのかもしれない。

駅ではこんな感じにコンパクト

最初は2人

隣で歌を歌っているおねーさんいます。

東京から1週間前に転勤してきた柳原くんが寄ってくれました

ブルガリア人御一行様も参戦。
いやあ、あれが「流しのこたつ」か~。
昨日集まった人たちは
東京で屋台をやっている吉池くんと
(はじめ、「屋台をやっている」ってどういうことだ?って思った)
舟型の屋台をつくった伏見の港デザイン研究所の林さん。
https://ameblo.jp/fns716/entry-12382242736.html
↑これが伏見マール。やばい。熱い。
こたつとか屋台とかって「リアルメディア」なんだって。
紙メディア
ウェブメディア
ときて、次は里山十帖の岩佐さんのように
「リアルメディア」なんだなと。
あと、吉池くんは、
なんとびっくり僕も敬愛する橘川幸夫さんの「デメ研」
にいるのだという。
橘川さんと言えば、
「参加型メディア」の草分け。
僕は「インターネットは儲からない」の頃からの
橘川さんのファンなのだけど、まさかこんなところでつながるとは。
紙メディア、ウェブメディア、そしてリアルメディアが
循環していることがポイントだと実践者はいう。
流しのこたつは
プライベートとパブリックのあいだの「場」
だと奥井さんは言った。
吉池さんは
屋台をやることで、君も(リアル)メディアをつくれよ、っていうメッセージを
伝えたいって言ってた。
僕が思ったのは、
「リアルメディア」は「参加のデザイン」でもあるなと。
参加型メディアっていうのは
インターネット以降、言われつづけているのだけど、
紙やウェブだと、
発信者と受信者(受け手)は
相互に関係しあっているとはいえ、
分かれている。
そこにきて、
今回のこたつや屋台のようなリアルメディアは、
その「場」を分け合っているという意味において、
発信者と受信者の区別はない。
誰もが発信者であり、同時に受信者になっている。
つまり、もっとも境界があいまいになっている。
たぶんそれなんだ、って。
境界をあいまいにすること。
それが余白をつくり、参加の余地が生まれる。
http://hero.niiblo.jp/e488318.html
「余白」とは、境界をあいまいにして「委ねる」こと
(2018.10.29)
で書いたように、
肌感覚をもったリアルメディアだからこそ、
「参加のデザイン」が可能になるのかもしれない。




