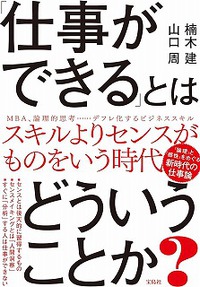2024年06月04日
「正しさ」という暴力

『インフォーマル・パブリック・ライフ』(飯田美樹 ミラツク)
第二部まで読み終わりました。
第四章から第六章のイギリス郊外の誕生の話は、
歴史的背景が詳しく書かれていてドキドキします。
以下メモ
~~~
十九世紀の産業革命が進むにつれ、分離・役割分担は拍車をかけて進んでいった。分離したのは大抵の場合、力があり、そこから離れることにした側が嫌悪感をもっていたからである。
ロンドンは産業革命が進むにつれて田舎や外国から都市へと流れ来る人の数は日増しに多くなり、人口増加に伴う問題も手がつけられなくなっていく。賭博、強盗、売春も日常茶飯事となった。そんなロンドンの様子に嫌気が差したロンドンのブルジョワたちは、郊外の住宅に理想のイメージを抱くようになっていく。
郊外の一軒家で利発な子どもたちに囲まれて、優雅にお茶を楽しみ、精神的に豊かな暮らしを送る。それがイギリスのブルジョワたちが描いた夢だった。
~~~
分離・分断の端緒はここにあったと著者は説明する。そして、フランスでも郊外は開発されたが、カトリック色の強いフランスにおいては、ブルジョワたちは都市の楽しみを諦めることができなかった。
カギを握るのは「福音主義」と「プロテスタンティズム」である。
~~~
中世のカトリック教会は、人間の性質はアダムの罪によって堕落したが、もともと善を求めており、また人間の意志は善を求める自由をもっている、というような人間の尊厳や人間の意志の自由やまた人間の努力が有効であることを強調した。
カトリックにおける神は、イエス・キリストのように分け隔てなく人々を愛し赦してくれる、あたたかい存在だった。罪を犯しても赦してもらえるからこそ、告解という仕組みや、ルターが非難した免罪符が誕生したともいえるだろう。
また、カトリックにおいて聖書だけでなく教会とそこで執り行われる伝統的儀式もかなりの重要性をもっていた。
~~~
腐敗したカトリックに対抗して生まれたプロテスタントは、聖書に記載されていない教会の儀式や伝統などは根拠がないとして否定した。プロテスタントでは、神の言葉が書かれた聖書に直接向き合う信徒という、神と人との一対一の直接的な構図が重要だった。
ここで重要なのは、これまでの「神と人間の間に教会というクッションがある構図」から「絶対的な権力をもつ神と小さな個人」というダイレクトな構図に変わったことである。
マルティン・ルターやジャン・カルヴァンが語る神の姿は、同じキリスト教かと疑いたくなるほどに厳しい、専制君主的な恐ろしさをもっている。
フロムは言う「ルッターはひとびとを教会の権威から解放したが、一方では、ひとびとをさらに専制的な権威に服従させた。すなわち神にである。神はその救済のための本質的条件として、人間の完全な服従と、自我の滅亡とを要求した。」(『自由からの逃走』)
「神のように絶対的な理想と無力な個人」という構図こそが、近代の資本主義社会の発展や二十世紀の郊外に残された人々の魅力感を理解するための鍵になる。
~~~
「宗教改革」っていいことだと思ってました。「改革」だからね。実際はなんて恐ろしいことなのでしょうか。
この前提を知っていることは、現在の社会の構造を理解する上でとても重要なことだと思った。
さらに恐ろしいのはカルヴァンの「予定説」。
「偉大なる神は、ある選ばれた人だけを永遠の生命に予定した。他の人々は永遠の死滅に予定されている。これは人の信仰によるものではなく、変えることのできない運命として神が事前に決定したものである。」というものだ。
フロムは言う
「予定説は個人の無力と無意味の感情を表現し、強めている。人間の意志と努力とが価値がないということを、これだけ強く表現したものはない。人間の運命についての決定権は、人間みずからの手からは完全にうばわれ、この決定を変化させるために、人間のなしうることはなに一つとして存在していない」
「個人がみずからの行為で、その運命を変えることができるというのではなく、努力することができるということそれ自体が、救われた人間に属する一つの証拠なのである。さらにカルヴァニズムが発展すると、道徳的生活とたえまない努力の意味とを強調することが重要になり、とくにそのような努力の結果として、世俗的な成功が救済の一つのしるしであるという考えが重要になってくる」
~~~
あーこわい。
「努力したから成功した=神に選ばれた」がいつのまにか、「成功したのは努力したからで、成功しないのは努力が足りないからだ=神に選ばれていない」に変わってしまった。
それを後押ししたのが「福音主義」であると著者は説く。背景は産業革命によるブルジョワの誕生である。
プロテスタントの教えの通りによく働き、豊かになった者たちを待っていたのは、キリスト教の宗教観にあった「金持ちは天国にいけない」というものだった。信仰心の強い者のなかには、富を築いたことを重荷に感じ、自分を罪深く感じてアイデンティティ・クライシスに陥る者もいた。
これを「事業によって獲得した資金を自分や家族の快楽のためではなく、事業の発展のために再投資するのであれば問題は解決する。それは天職の遂行であり、世界をよりよくすることに一層貢献するため、良心の呵責は生じない。」つまり、事業の成功を収めることは、神に選ばれた証であるという発想の大転換により当時の支配階級や多くのブルジョワたちの指示を得ていったのである。
そんなタイミングで、ロンドン南西部「クラッパム」で「初期郊外」が誕生した。そこに集ったものは「クラッパム派」と呼ばれた福音主義者で、地上に神の国を創ろうと様々な慈善事業やキャンペーンを手がけていた。
福音主義の家庭にとって、最大の敵は都市での玉石混淆の娯楽だった。
真のキリスト教徒として目覚めた両親が神が非難した世界から手を切ったとしても、世界は誘惑に満ちており、子どもたちがその誘惑を避けるのは難しい。誘惑に勝ち、悪い影響を受けないようにする手っ取り早い方法は、誘惑がありそうな場所に行かないことである。
その誘惑を断ち切るためには、物理的に遠く離れた場所に居続けるというのが一番効果的な方法なのだ。郊外に引っ越せば、都市の娯楽とは全く別の穏やかな家庭生活と、自然と調和のとれた美しい生活が手に入る。
ロバート・フィッシュマンは言う。
「都市と福音主義的家庭の理想とのこの矛盾が、郊外の理念となって核となる、都市と市民の住宅の前例のない分離に対する最終的な原動力となった。都市はただゴミゴミし、汚く、不健康なだけではない。都市はモラル違反だったのだ。救済の成功は、家庭という女性の神聖な世界と子どもたちを、大都会という神を冒瀆したような場所から切り離すことにかかっていた」
こうして「郊外」は「都市」から分離された。
そしてそのことにより、郊外に移り住んだブルジョワと、都市に住み続けるしか選択肢がない労働者は大きく分断された。
「郊外」が始まったのが、経済的理由だけでなく宗教的理由が非常に大きかった、いや根本的な原動力はそこにあったのだ、と実感させられた。
そして、それこそが「分離」「分断」の始まりだったのだと。
「(宗教的)正しさ」によって、「郊外」は誕生した。それによってブルジョワと労働者は、ますます分断された。
それをさかのぼると、「宗教改革」(と学校で習った)ことの残酷さが見えてくる。
格差の増大はもちろん、それだけでなく「アイデンティティ・クライシス」についても。
産業革命によって世の中が劇的に変わっていく中で、自らの「存在」の価値を信じられなくなったこと。カトリックからプロテスタントへの大きな流れの中にあったこと。お金持ちになることへの苦悩。スラム街を見て、目の前の格差に心痛めること。
その不安から救ってくれたのが「福音主義」という「正しさ」であった。
ブルジョワは郊外へと引っ越し、家庭を守りながら仕事へと邁進した。
そして何が起こったか。
都市生活から切り離され、たしかに危険なことや誘惑から解放された。
それと同時に何かを失ったのだ。
その「何か」は、ひとりひとりの「アイデンティティ」に関わることだった。
「正しさ」という暴力に、今もなお、僕たちはさらされているのだ、と感じた。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。