2023年11月12日
「問い」を生み出すレイヤーライフ
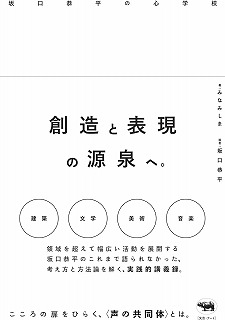
『坂口恭平の心学校』(みなみしま 晶文社)
第1章 建築
を読んでいたら、無性に復習したくなった10年前の本を再読。
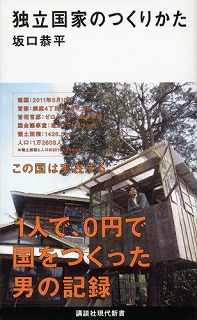
『独立国家のつくり方』(坂口恭平 講談社現代新書)
これ、大学生にもっともおススメしたい新書です。
たぶん某大手古本チェーン店で110円で買えるので探してみてください。
僕はこの本の「放課後社会」というキーワードにビビっと来て、その日以来、そんな場づくりを心掛けているのですけども。
参考:自由とはタテの世界を行き来すること(13.1.19)
http://hero.niiblo.jp/e229119.html
問いが詰まりまくってます。
今日はこの本の根幹をなす「レイヤーライフ」について。
P31 思考が空間を生み出す より
~~~
これまで、人間はこの一つの地球という空間の中で領土を拡げようと試みてきた。あらゆる戦争、いがみ合いの原因はここにある。日本という国の中でも、お金を獲得して自らの土地を増やす、所有を増やすという行為がすべての経済活動、生活のもとにあった。しかし、路上生活者たちは違った。
僕がいた建築の世界もそうだ。私的所有することができた土地を、建築物で囲っていく。そうすることが空間をつくり上げることだとしていた。しかし、それは本当なのか。僕はそうは思わない。なぜなら、どんなに壁をつくって自らの領土に建築物をつくったとしても、空間は増えないからだ。むしろ減る。
それに対して、路上生活者たちの空間の捉え方は違った。もともと自分の土地というような私的所有を断念せざるをえない状況で生きているので、実際に買うことができない。そこで、彼らは自分たちのレイヤーをつくることにしたのだ。日本に住むみんなが当たり前と思い込んでしまっている「匿名化」した社会システムと別のレイヤーを。
建築では空間を生み出せないけど、思考では生み出すことができる。
レイヤーライフが創造にも転化することを教えてくれたのは、鈴木さんの家の玄関だった。この玄関はドアを閉め、ブルーシートを閉じて、沸かしたお湯をプラスチックのケースに入れるとお風呂になる。さらにドアを開くと、裏側には包丁が入っており、台所に早変わり。玄関のどこに自分が立つかによって、一つの空間の用途が変幻する。
つまり、レイヤーを使うことによって、空間がどんどん増えていくのである。これまでの建築の「一つの空間をどうやって壁で埋めていくか」という考え方とはまったく正反対の方法だ。壁など必要ない。人間には見えない空間を次々とつくり出す能力がもともと備わっているのだ。
僕が言うレイヤーとは新しい技術ではない。それは太古からの力だ。
~~~
昔の家でいうところの縁側とか、土間とか、そういう感じの場所、立ち位置や構成員によって変化する場所、なのかもしれませんね。
さらにP41には
~~~
何かを変えようとする行動は、もうすでに自分が匿名化されたレイヤーに取り込まれていることを意味する。そうではなく、既存のモノに含まれている多層なレイヤーを認識し、拡げるのだ。チェンジじゃなくてエクスバンド。それがレイヤー革命だ。
~~~
いや、まさにこれなんですよ。
それが「放課後社会」というキーワードにたどりついた当時の僕のレイヤーに対する認識。
高校生や大学生にとって、本当に大切なのは、「やりたいことが見るかる」ではなくて、「一生かけても答えを出したい問い」が見つかることなのだろうと思う。
!「驚く」ことと?「疑問を持つ」ことを出発点にして、自分の中の共感と違和感に気づいていく。そこから問いを生み出していくこと。
それをもっとも生み出しやすいのは「越境」なのだと思うけど、その「越境」とは、物理的な距離の遠さというよりも、坂口さんの言う、「レイヤーを変えて観る」ということなのかもしれない。
たとえば旅人の目線(視点)から自分の町を見てみること。
そんなレイヤーライフの方法のひとつが「放課後社会」から見る、ということになるのかもしれない。
P123 匿名で交易はできない より
~~~
学校社会から放課後社会へはジャンプできない。学校社会は人間が集まって暮らすには必要な要素である。それに対して、放課後社会は完全に個人の領域だからだ。でも、放課後社会どうしはジャンプすることができる。これが僕の考える交易だ。学校社会上では交易することができない。交易は匿名下では不可能なのである。
今の状況を見ていると、どうにかして学校社会自体をぶっつぶして新しい社会を形成しようと試みている人が多いように感じる。しかし、それは不可能なことだ。なぜなら学校社会は個人の領域ではないからである。それは無意識だから。他人の見る夢なんて改変できっこない。
学校社会は変わらない。変えられるのは放課後社会とのバランスだけだ。
学校社会は消せないけど、認識を変化させることはできる。それが「考える」という行為。学校社会が無数の中のひとつのレイヤーであり、唯一の無意識領域のレイヤーであることがわかれば、もっとうまくバランスが取れる。そのためには自分の放課後社会の風景を拡げる必要がある。
~~~
いやー。これ伝わりますかね。
「放課後社会:おのおのにとって違う社会の在り方」から世界を見つめてみること。
あるいは放課後社会を形成している一人のオーナーとして、違う放課後社会オーナーと、「交易」すること。
それこそがいわゆる「越境」であり、「対話」の意味なのではないか、と。
そこから!や?と共感や違和感をキャッチして、問いが生まれてくる。
まずはこの「放課後社会」っていう概念をいかに伝えていけるか(できれば図解したい)
そんなことを考えていきたいな、と。
「自由」とはタテの世界、つまりレイヤーライフを行き来し、いくつかのレイヤーのオーナーになること。
そこから「探究」的な人生が始まっていく。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。









