2023年10月08日
「学ぶ」と「遊ぶ」を再び融合させること
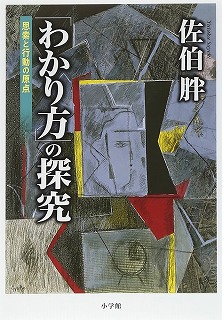
『「わかり方」の探究』(佐伯胖 小学館)
本日2記事目。いよいよメインです。
先日の「遊び」と「学び」はいつ分かれたのか?
http://hero.niiblo.jp/e493256.html
に続いての、待望のこの箇所です。
~~~P198「遊ぶ」ということの意味より
まずは遊びの定義
「その活動がなんらかの別の目的を達成するための手段ではなく、それ自体が目的であるとしか言いようのない、自発的な活動」
~~~
まずその定義からしてすごいな、と。それ自体が目的であること。それが遊び。
「ストレス解消」とか「明日からの英気を養う」目的にやるとかじゃないんですよ。
その定義からすれば、もはや購入して享受するだけの「遊び」は本来の意味で「遊び」とは言えないのだろうな。そこから出発した方がいいな、と。
「本気で遊ぶ」そんな大人の背中を見せていくこと。地域愛ってそういうところから始まるのではないかと。
~~~
「活動の目的」とか「自発性」などは、厳密に言えば、当人しか分からないことだから、やはり「遊んでいるか、否か」は当人しか分からないはずのことである。
「遊び」が「活動形態」のカテゴリーになり、「レジャー産業」という産業による商業活動にゆだねられるようになった。私たちはそういう売り物になった「遊び」をオカネを払って「買う」ようになってしまった。
さらに大人の世界では、「遊び」といえば、「仕事」の対立語であり、「仕事に疲れたから」、「仕事から逃れるために」遊ぶ。
そこでは「遊ばせてくれる」ことを期待し、「楽しませてくれるハズ」の世界に身を預ける。遊び本来の「無目的性」や「自発性」はどこかに飛んでしまい、「仕事を忘れるタメ」、いろいろなことを「シテクレル」ことを期待し、そのためにオカネを払って「遊ぶ」のである。
子どもの世界では、遊ぶことと学ぶことはほとんど区別がない。遊びの中で学んでいるのだし、学びは遊び心をともなって生じている。
これが大人の世界になると、全然話が違ってくる。遊びというのは、ヒマつぶしであり、ただ楽しむことだけのためにやることで、そこで何かを「学ぼう」などという気は起こらない。
一方、学ぶ(これを大人は「勉強する」というのだが)ときは、遊んではいられない。我慢して、努力して、一歩一歩、何らかの知識や技術を「向上」させていくのである。
しかし、大人でも、実は子どものように、遊んでいるのだか学んでいるのだか分からないという場合もある。科学者が研究に没頭しているときとか、画家が夢中で絵を描いているとき、というような場合である。「結果的には」それでお金をかせいでいるのだが、当人にとってはオカネが目的ではない。
ものごとの探究がおもしろくて、「やめられない」だけの話である。
~~~
ほんとそれだ。では、いつから「遊び」と「学び」や「仕事」は分かれてしまったのか。著者はいつのまにか「勉強」=「学び」-「遊び」時代が到来してしまったのだと言う。
「能力」という信仰(23.10.5)
http://hero.niiblo.jp/e493261.html
にも書いたけど、まさに「能力」なるモノを高めるために「勉強」するように強いられるのである。そしていつの間にか「遊び」と「学び」や「仕事」は切り離されてしまった。
~~~以下引用
わたしたちが「学校」という奇妙なところを作って、そこ(学校)では、学ぶ(勉強する)ことを主たる目的とし、そればかりだと疲れてしまうので、休み時間というものを合間にいれて、その休み時間には遊んでもよい、というきまりをつくってしまったことに端を発している。
それ以来、学ぶ(勉強する)ときは遊ばないし、遊ぶときは勉強から解放される、ということで、遊びと学びは真っ二つにわかれてしまった。
そればかりではない。大人の世界には、「仕事」というものが入ってきて、「外から」与えられた課題、要求される作業を達成することで、その代償としてオカネをもらい、生計を立てることになり、それこそ「遊んでいられない」事態になってしまった。
~~~
なんてことだ!「学校」という箱はなんのためにあったのか。「学び」と「遊び」を分離し、「勉強」、「学力(能力)」というフィクションを作り上げたのだった。
それはたぶん「仕事」と「余暇」を分ける発想にも似ている。そしてその両方が資本主義社会に絡めとられ、仕事以外の時間に「消費する」レジャーをさせられている。
さらに、本書では「評価」についても言及されている
~~~P212「評価」というバケモノ
「評価」というのは、「評価スル側」が「評価サレル側」に向けて行うものである。そこにはあきらかに「権力関係」がある。「評価スル側」は「評価」によって、「評価サレル側」を支配し、相手を「変える」のである。「評価サレル側」は評価内容、評価基準に「あわせて」、学習活動を組織し、そこに無関係ないしは直接関係しないことはムダなこととして排除される。
「ハゲミ」というのは、外からの枠組みや基準とは無関係に、「わき起こってくる」ものであり、「発見」されるものである、。ただそれが自分の「よさ」の自覚であり、自分で進んでいる方向の適正さの自覚である。
ものごとをじっくり鑑賞する(appreciateする)ことを広げることである。ものごとのおもしろさ、不可思議さ、大切さ、そして「ありがたさ」をじっくり味わうことである。(英語のappreciationには「感謝」の意味も含まれる)
レイチェルカーソンの言う「センスオブワンダー」もアプリシエーションの一つである。世界の不可思議さ、見事さ、美しさなどに「驚愕する」感覚である。
~~~
ホント、それ。「評価」によって、スル側とサレル側に分断されている。分断を超えて、「ともにつくる」ために、アプリシエーションを実践していかなければならない。
「生きてるぜ」っていう実感が足りないと、多くの若者が思っている。僕はその根源に、「学び」と「遊び」の分離があり、それによって「創造」から遠ざかっているからなのではないかと思う。
ジミー大西さんの発言が、ヒントをくれる。
~~~
たまたま「遊びごころ」で描いた絵を、故・岡本太郎氏に文字通り「アプリーシエイト」(絶賛)されたことがきっかけで世界的な画家になったジミー大西が、次のように語っていた。
「エジソンは、99パーセントの努力と1パーセントのヒラメキやというたけど、あれ、まちがってますね。99パーセントの遊びと1パーセントのヒラメキですわ。ヒラメキが1パーセントというのはホンマやけど、努力が99パーセントいうのはウソや。99パーセント遊びでないと、1パーセントのヒラメキも出ませんわ」
この1パーセントのひらめきを、「遊び」のなかから発掘し、コトアゲし、みんなでそれを喜び合う、つまり、アプリーシエ―ションの実践の共同体が、今日、私たちのまわりにどれだけあるのだろう。
バケモノとなった「評価」におびえ、笑いを失い、真からの怒りもなく、シラケきった勉強で「能力」だけを追い求めている世界には「遊び」もないし、そこから生まれるヒラメキもない。
~~~
僕たちはもっと遊ばなければいけない。本気で遊ぶ、大人の姿を見せること。
本気で遊びながら、振り返って結果的に学んでいた、みたいな活動をしていくこと。
「学ぶ」と「遊ぶ」を再び融合し、「ともにつくる」を実践し続けなければならない。
そんな実践を重ねているうちに、この町と、小さな共同体と、ひとりひとりの未来がつくられていく。
2023年10月08日
「課題解決」というわかりやすさの罠
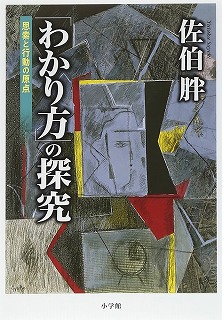
『「わかり方」の探究』(佐伯胖 小学館)
「冒険の書」からの読書サーフィン。衝撃の1冊となりました。
まずは、第1章4 「考える」ということはどういうことか
P47のおやつをかいにいきました問題の解説がすごい。
~~~
おやつをかいにいきました。
あめだまを、5つかうと まだ20円のこっていました。
そこで、あめだまを、ぜんぶで7つかうことにしました。
すると4円しかのこりません。
あめだまは1こいくらですか?
~~~
この問題は小学校6年生でも正答率が1割程度という「むずかしい問題」である。
ところが同じ問題を小学校2年生を対象にして83%の正答率を得ている。
「2個で16円」だというところまでわかった子どもを含めると94%になる。
(ちなみに小学校2年生段階ではまだ「割り算」を習っていない。)
どんな魔法をつかったのか?
実は3つの段階に分けて考えさせていくにすぎない
1 問題文を読んで解かせる:正答できた子ども:35人中1人
2 買う人になって考えさせる(子どもたちにキミならどうする?と問う):35人中9人が正答
3 売る人になって考えさせる(売る人と買う人に分かれ、お店屋さんごっこをする):35人中19人(計29人)が正答
~~~
このことから展開して、著者は「文化と思考」の観点から次のように説明する
1 生きた知恵や技能というものは、そもそもそれを活用する現実生活の実践と結びついたものであり、文化的実践と無縁の「形式的」な思考は、本来は身につかないはずのものだ、ということである。それにもかかわらず、「知能テスト」で高得点をとれる子どもというのは、文化的実践と切り離した、「人工的」な世界での操作活動にたまたま習熟しており、「頭を切り替えて」しまうスキルを身につけているのではないか、という考え方もできる。これは思考の「領域固有性」の問題として注目されてきた。
2 「発達段階」というものに対する盲信への警告である。思考は「具体から抽象へ」と発達するというが、人は本当に「抽象的に」思考できるのか。本当に「形式」に従って思考しているのか。私たちは「形式」的思考を教えるのではなく、「具体」的思考を「形式」で代用して考えるようにしむけているにすぎない。
「文化の中で意義を確かめられる活動や操作と結びつく」ためには、どういう授業の進め方があるか。
1 エピソード化:ものごとの背景となる具体的なエピソード、物語、経験談を話す
2 多元機能化:こういうことのために有効だとか、これはこういう状況でこういう機能を果たしているということを様々な観点から見る。
3 モデル化:アナロジーや比喩、隠喩による理解の促進
教材を意義づけること。子どもの世界、子どもの生活の中で、自然に活用している知恵と技能と、どの程度の連続的な関連を結びつけることができるか、という点にもっと注目してほしい。
これ、本当にリアルだな、と。
国語や算数が、現実に即していなかったら、それをやる意味がわからない。
それをただ覚えるっていうのは、どんなゲームなのだろうか。
いや、子どもが興味があって、鉄道の路線名を全部覚えるだったらいいのだけど。
小学校6年生が解けない問題を2年生が解ける実践はそんなことを教えてくれる。
この後の「信じる」とはどういうことか についての図が、現在の「教科における探究」や「アンラーニングできない組織」への違和感とマッチしていたので図をお借りする。
(わかり方の探究 P69より)
学校においては、Ⅱの「課題解決」ばかり取り組んでいるのではないか。その前にⅢの「方略選択」があり、もっと言えばⅣの「自己、視点」がある。そして、それより上のⅠには「展開」がある。ところがⅡの訓練ばかりをしていると、子どもたちはⅠやⅢ、Ⅳのレベルでの吟味をしなくなっていくのではないか。
そして「教科探究」を含めて「探究」と呼ばれるものは、このⅠ~Ⅳのレベルで考える、ということなのではないのか。アンラーニングできないおじさんたちは、「仕事」とは目に見えるⅡ「課題解決」のことだと思っているからではないのか。
大人こそ、「探究」が必要なんだよね。
ということで、次につづきます。




