2019年11月16日
アートとデザインのあいだ
長岡で大正大学浦崎先生の講演があるので電車で移動。
電車内読書はこの本。
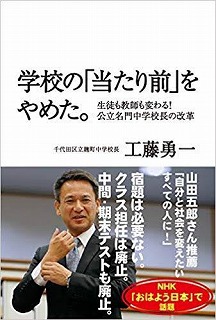
学校の「当たり前」をやめた。(工藤勇一 時事通信社)
すごい。
改革がすごいというより、問いを立てる力というか、
常識を疑う力がすごい。
以下、ビビっときた語録
学校という存在自体も手段の一つにすぎず、目的ではありません。
「関心・意欲・態度」は、目に見えない尺度だけに、評価するのが難しいものです。
そのため、宿題の提出量や授業中の挙手回数などをカウントし、それを評価に活用していることは珍しくありません。
そもそも学力をある時点で切り取って評価することに、意味があるのでしょうか。
担任制はなんのためにあるのか?
これまでの学校教育では、「規律」や「団結」が尊ばれ、私自身も、チームが一丸となって何か達成するといったストーリーに感動してきました。
人が社会で生きていくスタイルそのものがアクティブラーニングだからです。
社会でよりよく生きていけるようにするという目的に対し、寺子屋が最適な手段だった
~~~
と、こんな感じ。「そもそも、何のためにあるのか?」
ってすごい根本的な思想だけど。
からの大正大学浦崎先生の講義「地元回帰の人材育成」。

講義のあとのアリバイ作り写真。(笑)
講義に興奮して赤くなってます。
いや、ホントに行ってよかったなと。
事例として出てきた飯野高校。
生徒たちが主体的にガンガンと地域で活動していて、
先生たちは新聞を見てそれを知る、みたいな。
「観光列車を走らせたい」って思ったら
本当に実現させてしまう先輩を見て、後輩は奮起する、みたいな。
恋愛のように、夢中になる地域での活動。
たしかに、部活や遊び、恋愛を超えるワクワクは
地域で作れると僕も思う。
~~~以下メモ
なぜ「地域で探究」なのか?
社会に出たときに求められる力:よりよい提案・アイデア・プランを生み出す力
=仮説:AをするとBという結果が出るはずだ
仮説が正しければ結果を出せるが、仮説が間違っていれば結果は出せない。
⇒より正しい仮説を生み出す力」が必要
1 思いつきレベルの提案:実効性なし
2 妥当性がある提案:仮説(前提条件)の吟味を行う⇒実効性あり
情報収集・整理分析・まとめ・表現
3 実践して仮説を検証:解決プランの実践⇒解決プランの修正
⇒現場(地域)での実践が必要
これからの新卒採用
・社会人基礎力と学歴(偏差値)は相関しない(高校卒業時までに決まる)
・社会人基礎力は出身高校による差が大きい
・社会人基礎力を育成する力の高い高校の卒業者を採用したほうがいい
地域が稼ぐ力/地域で稼ぐ力
→仮説形成能力がつく:地域が検証の現場になる
地元企業が採用したい若者像
→地域と豊かに関わってきた高校生が有望
・元気で提案力がある
・人柄や能力を熟知している
・幅広い年齢層と関われる
地元に回帰する可能性
→大人との一体感がカギ
採用の視点が激変する可能性
→高校に焦点、地域連携に誠実なほど有利
Society5.0
狩猟→農業→工業→情報→AI
人間には容易だがAIには困難なこと
1 現場で「感じる」こと
2 問いを立てること
3 意味を味わうこと
→探究(自問自答)によって
・課題発見(問い)には、現場(地域)で感じることが必要
・感性には個性→探究テーマは高い個別性
習得すべき知識量も以前よりさらに増加
→「与えた知識しか頭に入らない」:指示待ち人間を量産
→「放っておいても自ら吸収する力」が必要:探究する態度・能力の育成
Society5.0
人間にしかできないこと「探究」
Society4.0
「知識」は瞬時に賞味期限切れになる
・「知恵を生み出す」力が必要
・「三人寄れば文殊の知恵」
・「徹底的に個性を伸ばす」ことが必要
「対話」の重要性(三人寄れば文殊の知恵)
主体的・対話的で深い学び
お互い思い切りとがっているほうがよいものがでる。
若者が帰属意識を持つ集団・場所
1 親近感・一体感をもてる人がいる
2 自分をそこで表現できた
3 自分がそこで成長できた
若者は自分に無関心な地域には戻ってこない。
信頼を寄せる大人から誘われれば喜んで参加し、一緒に挑戦し、表現・成長できる。
Society5.0時代の教育
一人ひとりの感性・興味関心に応じた探究。
公正に「個別最適化」された学びが必要。
「個別最適化」された学び:問いに当事者性がある
地域課題解決(地域素材×探究能力)
その真ん中にふるさと教育(担い手育成)をつくっていく。
1 何を理解しているか、何ができるか
2 理解していること・できることをどう使うか
3 どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか
高校生が地域の多様な大人とともに、地域の課題発見・解決にあたる
⇒関わり合いを通して、大人も地域も揃って変容する。
行政プロセスと学校のプロセス:
「教授」から「探究」へ。
「教授」:一方向、正解を持っている
・対話性が乏しく全体最適案・深い理解ができない
・委員(生徒)の当事者性や創造性は高まらない
⇒
「探究」:委員(生徒)からの問いを誘発する
・自分たちで考える
・対話性が高く、納得感の高い解に至る
・委員(生徒)の当事者性や創造性が高まる。
~~~以上メモ
「地域の課題解決」と「問いの当事者性」の真ん中に
探究をつくっていくこと。
ここは非常にその通りだと思った。
僕は少し表現が違う。
アートとデザインのあいだ。
「課題解決」って、むずかしいし、マイナスをプラスにするようなエネルギーが必要
だから「デザイン」なんだ。
縦割り社会で予算が削られていたら、
課題をそれぞれ単独で解決することはさらに難しい。
「まちの保育園」で、高齢の方が幼児の見守りをする、など。
課題と課題を組み合わせると、一方の課題は一方に対して資源だったりする。
そういうことだ。
もうひとつは「アート」、自分の当事者性のある課題、テーマ。
「表現したいこと」に出会うこと。
それには、地域が必要。
「お客に出会うこと」が必要なのだと思う。
「この人のために頑張りたい」と思える何か。
デザインは社会を出発点にして、アートは主観を出発点にしている。
そのあいだ。そこに探究テーマをもってくること。
なんか、見えてきたよ、なんとなく。
電車内読書はこの本。
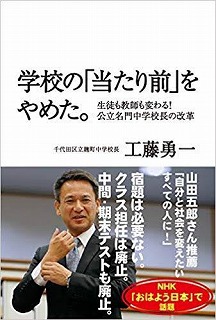
学校の「当たり前」をやめた。(工藤勇一 時事通信社)
すごい。
改革がすごいというより、問いを立てる力というか、
常識を疑う力がすごい。
以下、ビビっときた語録
学校という存在自体も手段の一つにすぎず、目的ではありません。
「関心・意欲・態度」は、目に見えない尺度だけに、評価するのが難しいものです。
そのため、宿題の提出量や授業中の挙手回数などをカウントし、それを評価に活用していることは珍しくありません。
そもそも学力をある時点で切り取って評価することに、意味があるのでしょうか。
担任制はなんのためにあるのか?
これまでの学校教育では、「規律」や「団結」が尊ばれ、私自身も、チームが一丸となって何か達成するといったストーリーに感動してきました。
人が社会で生きていくスタイルそのものがアクティブラーニングだからです。
社会でよりよく生きていけるようにするという目的に対し、寺子屋が最適な手段だった
~~~
と、こんな感じ。「そもそも、何のためにあるのか?」
ってすごい根本的な思想だけど。
からの大正大学浦崎先生の講義「地元回帰の人材育成」。

講義のあとのアリバイ作り写真。(笑)
講義に興奮して赤くなってます。
いや、ホントに行ってよかったなと。
事例として出てきた飯野高校。
生徒たちが主体的にガンガンと地域で活動していて、
先生たちは新聞を見てそれを知る、みたいな。
「観光列車を走らせたい」って思ったら
本当に実現させてしまう先輩を見て、後輩は奮起する、みたいな。
恋愛のように、夢中になる地域での活動。
たしかに、部活や遊び、恋愛を超えるワクワクは
地域で作れると僕も思う。
~~~以下メモ
なぜ「地域で探究」なのか?
社会に出たときに求められる力:よりよい提案・アイデア・プランを生み出す力
=仮説:AをするとBという結果が出るはずだ
仮説が正しければ結果を出せるが、仮説が間違っていれば結果は出せない。
⇒より正しい仮説を生み出す力」が必要
1 思いつきレベルの提案:実効性なし
2 妥当性がある提案:仮説(前提条件)の吟味を行う⇒実効性あり
情報収集・整理分析・まとめ・表現
3 実践して仮説を検証:解決プランの実践⇒解決プランの修正
⇒現場(地域)での実践が必要
これからの新卒採用
・社会人基礎力と学歴(偏差値)は相関しない(高校卒業時までに決まる)
・社会人基礎力は出身高校による差が大きい
・社会人基礎力を育成する力の高い高校の卒業者を採用したほうがいい
地域が稼ぐ力/地域で稼ぐ力
→仮説形成能力がつく:地域が検証の現場になる
地元企業が採用したい若者像
→地域と豊かに関わってきた高校生が有望
・元気で提案力がある
・人柄や能力を熟知している
・幅広い年齢層と関われる
地元に回帰する可能性
→大人との一体感がカギ
採用の視点が激変する可能性
→高校に焦点、地域連携に誠実なほど有利
Society5.0
狩猟→農業→工業→情報→AI
人間には容易だがAIには困難なこと
1 現場で「感じる」こと
2 問いを立てること
3 意味を味わうこと
→探究(自問自答)によって
・課題発見(問い)には、現場(地域)で感じることが必要
・感性には個性→探究テーマは高い個別性
習得すべき知識量も以前よりさらに増加
→「与えた知識しか頭に入らない」:指示待ち人間を量産
→「放っておいても自ら吸収する力」が必要:探究する態度・能力の育成
Society5.0
人間にしかできないこと「探究」
Society4.0
「知識」は瞬時に賞味期限切れになる
・「知恵を生み出す」力が必要
・「三人寄れば文殊の知恵」
・「徹底的に個性を伸ばす」ことが必要
「対話」の重要性(三人寄れば文殊の知恵)
主体的・対話的で深い学び
お互い思い切りとがっているほうがよいものがでる。
若者が帰属意識を持つ集団・場所
1 親近感・一体感をもてる人がいる
2 自分をそこで表現できた
3 自分がそこで成長できた
若者は自分に無関心な地域には戻ってこない。
信頼を寄せる大人から誘われれば喜んで参加し、一緒に挑戦し、表現・成長できる。
Society5.0時代の教育
一人ひとりの感性・興味関心に応じた探究。
公正に「個別最適化」された学びが必要。
「個別最適化」された学び:問いに当事者性がある
地域課題解決(地域素材×探究能力)
その真ん中にふるさと教育(担い手育成)をつくっていく。
1 何を理解しているか、何ができるか
2 理解していること・できることをどう使うか
3 どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか
高校生が地域の多様な大人とともに、地域の課題発見・解決にあたる
⇒関わり合いを通して、大人も地域も揃って変容する。
行政プロセスと学校のプロセス:
「教授」から「探究」へ。
「教授」:一方向、正解を持っている
・対話性が乏しく全体最適案・深い理解ができない
・委員(生徒)の当事者性や創造性は高まらない
⇒
「探究」:委員(生徒)からの問いを誘発する
・自分たちで考える
・対話性が高く、納得感の高い解に至る
・委員(生徒)の当事者性や創造性が高まる。
~~~以上メモ
「地域の課題解決」と「問いの当事者性」の真ん中に
探究をつくっていくこと。
ここは非常にその通りだと思った。
僕は少し表現が違う。
アートとデザインのあいだ。
「課題解決」って、むずかしいし、マイナスをプラスにするようなエネルギーが必要
だから「デザイン」なんだ。
縦割り社会で予算が削られていたら、
課題をそれぞれ単独で解決することはさらに難しい。
「まちの保育園」で、高齢の方が幼児の見守りをする、など。
課題と課題を組み合わせると、一方の課題は一方に対して資源だったりする。
そういうことだ。
もうひとつは「アート」、自分の当事者性のある課題、テーマ。
「表現したいこと」に出会うこと。
それには、地域が必要。
「お客に出会うこと」が必要なのだと思う。
「この人のために頑張りたい」と思える何か。
デザインは社会を出発点にして、アートは主観を出発点にしている。
そのあいだ。そこに探究テーマをもってくること。
なんか、見えてきたよ、なんとなく。




