2024年03月23日
「自分とは何か?」に応えてくれる活動
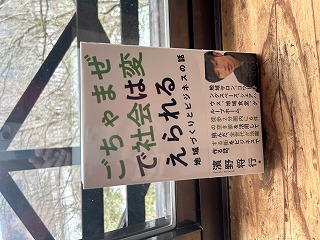
『ごちゃまぜで社会は変えられる』(濱野将行 クリエイツかもがわ)
読みました。シビれました。こんなすごい人いるんだなあって。
さっそく本書に出てくるユースサポーターズネットワークの岩井さんに連絡して、5月くらいに行きます、って言いました。
舞台は栃木県大田原市。
濱野さんが代表を務める一般社団法人えんがおは、「誰もが人とのつながりを感じられる社会」を目指して、高齢者の孤立問題を中心とした地域課題・社会課題に向き合っています。
えんがおHP
https://www.engawa-smile.org/
徒歩2分圏内の6軒の空き家を活用し、10の事業を展開しています。
もともと濱野さんは作業療法士を志す大学生でした、それが大学1年次3月東日本大震災で大きく動き出しました。高齢者の生活支援事業から始まり、いまではさまざまな事業を展開しています。
そんな濱野さんの本からの抜粋を
~~~
「生活のお手伝いをする」という「手段」を用いて、人とのつながりが希薄な高齢者の生活に「つながり」と「会話」をつくる。それが僕たちの生活支援事業です。
地域サロンの運営で大切なのは、「役割をつくる」です。お茶飲み場が居場所になるわけではないんです。人にとって居場所とは「役割」です。
介護予防=運動+役割なんです。
~~~
なるほどな~。役割をつくること。
畑をやり続けるっていうのもある意味「役割」だよなあと。
つづいて「関係人口の増やし方」
~~~
関係人口の増やし方は主に2つです。
1つめ「相談」のくせをつけること。2つ目「発信」。
課題解決の力と「人を巻き込む力」の両方が必要です。
他人に対しては結果を求めなくていいけど、何かを変えたければ、自分に対しては結果主義になること。
「結果」とは、テレビに出ることやSNSのフォロワーが増えることではなく「誰が幸せになったのか」です。
「人を幸せにした事実や想い」が「発信されて」生まれるものが「信用」だと思っています
どんな人が来たのか、どんなことで困っていたのか、自分たちの活動の結果、どう喜んでくれたのか。それを発信してください。
それを第三者がみて初めて「へー。いいことしてんじゃん」となるわけです。
目の前の人を喜ばせることが、何より大切です。順番で言えば間違いなく、1番は「人を幸せにした事実を積み重ねる」ことです。だけど、これからの時代、それとセットで「発信して信用を貯める」ことも大切なんです。
~~~
まさに、まさに。「発信」することは大切で、さらに「発信」すべきは、活動そのものではなく、「その活動によって誰がどのように幸せになったのか」ということなのです。
いや、まさに本質
さらに、濱野さんたちがひたすらやってきたこと
~~~
・目の前のニーズを拾う。それが自分たちのもつ性質と合っているかを確認してできそうならやる。
・やるときはなるべく多くの人を巻き込む、つくる段階から巻き込む
・壁にぶつかって凹む
・とにかく相談する
・その活動で誰が喜ぶかを明確化して、発信する。
~~~
いいですね。シンプル。
つづいて、関わりやすさを示す「余白力」について
~~~
チーム運営において、もっとも大切なことは「メンバーのもっている強みを最大限に活かすこと」だと考えています。そのためにリーダーは「不完全」でいたほうがいいと考えています。
「意図的」に、自分の弱みをそのまま開放することで、「自然に発生する」余白。そこに人が集まる。
他者が入る余白があれば、一時的に混乱しても、リーダーである人の想像を超えた形で、チームは進化していきます。この「想像を超えた」もポイントです。予測できない変化(進化)が起きるチームです。
~~~
いいですね。
リーダー像。
さらに、この本のハイライトはP200からの若者の巻き込み方。
これは、授業の設計においてもまったくその通りなので、写経します。
1 活動の「体験価値」を高める
2 余白をつくる
3 存在を受け入れる(名前を呼ぶ、個人の物語を捉える・強みを見つけて言語化するなど)
4 信じる。活動に来ている時点で、もう最強。信じる。任せる。
5 放置する。失敗できる環境こそが価値。間違っていても正さない。失敗してもらう。常に、付かず離れずの距離で見ている。失敗して自分で気づき、学ぶ。その過程を見守る。相談には乗る。
6 本人の変化を本人より先に捉えて、言語化して手渡す。
7 参加者(学生)よりも自分が楽しむ。
8 活動の社会的意味を伝える。なぜ、その活動がなければいけないのか。それに対してどんな解決策を提示しているのか。
9 環境のせいにする時は声をかける(気づけるような問いを投げる)。自分で気づけないスパイラルに入っているのであれば、嫌われてもいいからそれを伝える。
10 10個もなかった。だめなところを見せる。2と被った
~~~
10。笑
すごいなあ、濱野さん。
文章からにじみ出る人間性。
そして、その前に書いてあることになるのですが、僕の研究領域であるアイデンティティ問題についての言及メモ
~~~
家族以外にも「自分の存在を心配してくれる人がいる」という感覚が、そういう日々の声かけで、潜在意識の中に刷り込まれていくのではないでしょうか。その小さな積み重ねで「自分はここにいていいんだ」と、言語化できない、心の深いところで感じていくのだと思うんです。
誰かに心配されているとか、気にかけられている、みたいな体験の積み重ねが、数年後の自分自身への「自信」につながるのではないかと考えているのです。
彼が変わったわけではなく、「もともとできる」ことが、いろいろなものに抑圧されて、それを「発揮できなくなって」いたんです。
それが、世代を超えた交流で認められたり、受け入れられたりして、徐々に発揮できるようになっただけなんです。自分らしさが戻ったんですね。この場合もえんがおがやったのは、もともと素敵な彼を受け入れて信じることだけでした。
今も昔も、「今時のワカモノ」自体は変わっていなくて、みんな超ステキですよ。優しいんです。彼らを取り巻き育てる「環境」が変わっているんですね。そうして自分を「発揮」しにくくなっているのだと思います。
~~~
いや、ホント、その通りだなあと思います。
「存在の承認」という出発点をどうデザインするか。
そこに若者との活動はかかっていると僕も思います。
介護予防は、運動+居場所(役割)だと濱野さんは言う。
その「役割」を感じられなくなった。
若者は本当は若いだけで価値があるのだ。
価値があるから、声をかけてくれるのだ。
話をするだけで元気もらえるからね。
「仕事でアイデンティティを形成せよ」とキャリア教育は言う。
でも、それができる人は一部の優秀な人だ。
その優秀な人だって、「経済社会」というフィクションの中における「役割」を果たしているに過ぎない。
「自分とは何か?」
その問いに応えてくれる活動を必要としている。
それは「生きる」に直結しているから。
それは若者であっても高齢者であっても私たちオジサンにとっても同じだ。
自分は、どんな共同体で、どんな役割を果たせるだろうか。どんな役を演じられるだろうか。
そんな根源的な問いを皆、かかえていて、
一般社団法人えんがおと濱野さんは、その問いに応え続けているのだと強く思った。
2024年03月23日
演劇のような本屋、劇団のような会社、劇場のようなまち
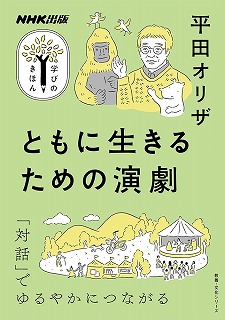
『ともに生きるための演劇』(平田オリザ NHK出版 学びのきほん)
ひさしぶりのオリザ節にシビれていました。
まずはひたすらメモを
~~~
「ある共同体に強い運命が降りかかったとき、共同体の一人ひとりから価値観の表出が始まる。そこに対話が生まれ、ドラマが生まれる」
私たちは、相手によってさまざまな態度をとり、「演じ分ける」ことができるのです。相手や場面によって、そして自分の社会的役割によって演じ分けることが、人間を人間たらしめる重要な能力なのです。人間にとって、身振り手振りや言葉によって人に何かを伝えること、演じ分けることは、共同体での生活を円滑にするためのごく自然の発達であり、これが芸術や演劇の萌芽だと私は考えています。
「演劇」は、「哲学」だけではすり合わせることのできない、異なる「感性」のすり合わせだと私は考えています。
イギリスが植民地を失っていく過程でイギリスの地方都市が急速に多国籍化し、人口の二、三割が外国から来た人にらなりました。そのため、他文化への理解や多様性理解が急速に必要となったのです。富国強兵、臥薪嘗胆、戦後復興、高度経済成長などの国家目標が掲げられ、その目標に向かって生きていけば、たいていの人が幸せになれると信じていた時代、そのような社会では、異なる価値観を理解することも、そのために必要な対話の言葉も必要ありませんでした。
~~~
まずは演劇とは何か?
人間を人間たらしめているもの、それは「演じ分ける」ことだとオリザさんは言います。
そして演劇とは、感性をすり合わせることなのだと説明します。
そしてまた「1つの目標に向かって皆が生きていける時代・社会」では、それは不要だったのだと説明します。
先日の只見高校の
「この授業を通して、自分が、只見町が、世の中が、〇〇になったらうれしい」
という問いは、まさに感性、あるいはベクトル感のチューニングだったのだろうと思います。
次に面白かったのは「かわいい」について
~~~
日本語には、対等なほめ言葉が少ないとよく言われます。日本語には、ほめ言葉にも上下の関係がどうしても入り込んでくる。たとえば、上司から部下への「よくやった」「がんばったな」、親から子への「いい子だね」「上手だね」という声かけには評価の成分が含まれています逆に部下から上司に対しては、「すごいですね」「さすがですね」など過度に持ち上げるようなほめ言葉が多い。
そこに汎用性のあるほめ言葉として登場したのが「かわいい」でした。中年のおじさんたちは、「今の若い子はなんでも『かわいい』で済ませる」とよく言っていましたが、ボキャブラリーが少ないのは、私たちおじさんのほうなのです。対等なほめ言葉がない日本語の欠落を、「かわいい」はずいぶん補ってきたことになります。このように、対等な関係性で使える言葉を、私たちはこれからも作っていかなければなりません。
長年硬直していたジェンダーや職場における関係性がいま、動き始めているのに、そこに言葉が追いついていないという状況があちこちで生まれています。これから私たちは、対等な関係を作りながら、対話の言葉を作っていかなければなりません。
~~~
若い人が言う、「かわいい」は、フラットなほめ言葉として、他の言葉が適切でないから、使われている、とオリザさんは言います。
なるほどな、と。
フラットなコミュニケーションを求めているんだよな、って。
直線的な人生を生きていないから。
その場その場で出会った人たちとフラットにつくりたいものがあるからね。
最後に演劇・劇団というチームについて
~~~
実は、演劇に限らず、「共同体の中で最も弱い人をどう活かすか」ということが、全体のパフォーマンスを上げる秘訣なのです。
黒澤明の『七人の侍』でも若くて弱い侍が登場するように、集団のドラマでは必ずその中に弱い人が含まれています。その人が力を発揮できるようにすることがとても重要なのだと、子どもたちは台本を作り、配役を決めながら気づくことができます。
その子の弱さを責めたり、克服させるのではなく、「弱さを活かす方法」を演劇の形式を借りて考えるのです。「この作品をいいものにしよう」という思いを全員が持っているという前提でしか劇団は成り立ちません。「俺はこんなに働いているのに、なんであいつはあんなにサボってるんだ」という疑念を誰かひとりでも抱き始めたら、劇団は崩壊します。
一つの作品に向かって、自分も、相手も、できる範囲の最大限の努力を払っているという合意がないと、演劇はできない。そのような前提は、本来、社会のどんな共同体にも必要です。「誰もが最適の努力をして今を生きている」という前提に立てば、エンパシー、想像力は生まれてくるはずです。
こうしたエンパシーを持ち、社会にも広めてゆくには、できるだけ多くの他者、異なる価値観を持つ他者と出会う体験を繰り返すことが必要です。そして、異なる他者と出会うことで、何か新しいことを生み出す喜びを繰り返し経験することです。その光明は、地方にあり、演劇にあると私は考えています。
「どんな人を育てたいですか?」と訊かれて「楽しく共同体を作れる人」と答えました。ここにどんなに多様な価値観が集まったとしても、それぞれの価値観を認めあいながら、対話をあきらめず、問題を解決して、楽しく共同体を作っていける自立した一人ひとりを育てたい。
~~~
「共同体の中で最も弱い人をどう活かすか」
「一つの作品に向かって、自分も、相手も、できる範囲の最大限の努力を払っているという合意がないと、演劇はできない。」
「異なる他者と出会うことで、何か新しいことを生み出す喜びを繰り返し経験することです。」
「楽しく共同体を作れる人」
いやあ、どれも金言すぎます。
しかもその光明が地方にあり、演劇にあるというのです。
まさに、地方の田舎町にこそ、「どんなに多様な価値観が集まったとしても、それぞれの価値観を認めあいながら、対話をあきらめず、問題を解決していく、楽しく共同体を作っていける自立した一人ひとり」になる機会がたくさん詰まってますもんね。それは「地域みらい留学」でも同じかも。
2014年1月、ツルハシブックスとは何なのか?を考えていた時、秋田のスターバックスで降りてきた「It's a theater」(劇場だ!)という言葉。心の中で叫んでいた。
あの言葉をふたたび思い出す。
僕がこの場所で実現したいのは、
演劇のような本屋
劇団のような会社
劇場のようなまち
なのかもしれない。




