2013年11月05日
大学時代の宿題は、消費者マインドから卒業すること
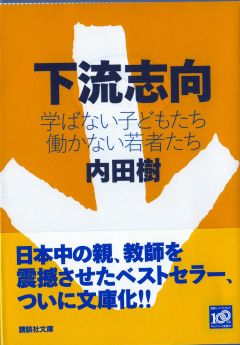
何年か前、
「下流志向~学ばない子どもたち、働かない若者たち」(内田樹 講談社文庫)
を読んで、
内田樹さんの
「教育がお買いものになったときから、子どもは学ばなくなった」
というのが非常に強いインパクトを受けた。
「なんのために学ぶのか?」
という質問に対する僕の答えは、
「学べば分かる」
つまり。
現時点で学んでいない状況の中で、
学んだ後のメリットや自分の変化を分かる必要がない。
ということだ。
これは、学校等における、
「まず、目標を立ててから学び始めよう」
というのと、根っこが異なっているから、相容れない。
しかし。
これはどっちが正しいか?
というようなものではなくて、
両方が真実だろうと思う。
目標を立てて進んでいく学びと
目標とは無関係に結果として学べるものを
振り返って学びに落とし込んでいく。
その両方が世の中では必要なのだと思う。
そして、この本。

「大人のいない国」(内田樹 鷲田清一 文春文庫)
移動時間に読む。
同じ理論なんだけど、
ふたりの対談から引き出される言葉も
力があるなあと。
~~~ここから引用(一部省略)
内田氏談
今の日本における「未成年者」は、
現実の年齢や社会的立場とは無関係に
「労働し、生産することではなく、消費を本務とする人」
というふうに定義できると思うんです。
労働を通じて何をつくり出すかではなく、
どんな服を着て、どんな家に住み、どんな車に乗って、
どんなレストランで食事をするか・・・
といった消費活動を通じてしか自己表現できないと思っている。
鷲田氏談
消費者であるということは、
裏返すと僕らの生活空間自体がサーヴィスで充満しているということです。
ものを食べるにしても、勉強するにしても、もめ事を解決するにしても、
病気やケガを治すにしても、その手段はみんな「サーヴィス」というかたちで提供される。
生きること自体が
どういうサーヴィスを選んで買うか、ということになっている。
内田氏談
消費によってしか自己表現ができないと信じているからこそこういうメンタリティが生まれるんです。
彼らやあらゆるものを「商品」としてとらえようとしますから、あらゆるものについて「費用対効果」を吟味する。
でも、このマインドは「学び」を動機づけることができない。
「学び」というのは、、
自分がこれから学ぶものの意味や価値がまだわからない。、
だから「学び」を通じて、自分が学んだことの意味と価値を事後的に知る、
という時間の順逆が逆転したかたちの営みだからです。
消費者マインド にはこれが理解できない。
自分がこれから買おうとする商品の価値や有用性を知らないで、
商品を買うという消費者は存在しませんから。
~~~ここまで引用
いやあ。
コワイ。
その通りではないかなあと思う。
まあ、でも、これは、
個人ひとりひとりが悪いとか、
教育が悪いとか、そういう悪者探しではなくて、
僕自身は、
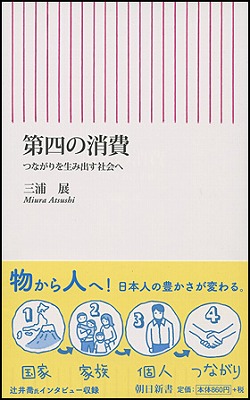
「第四の消費」(三浦展 朝日新書)
にあるように、
テレビや車、家電製品を売り続けることが
絶対の正義だった時代に、
世の中の要請として
「消費によって自己表現・自己実現せよ」
と世の中が一丸となって、キャンペーンしたことが
原因なのだと思う。
一方で
工業社会の絶対の正義として、
「効率化・合理化」「費用対効果の最大化」
は常に求められてきたのだから、
学校というか、世の中の教育空間が、
消費者マインドを持って、
「消費によって世の中に貢献できる人間」
を大量に生み出したことは、当時としては仕方のなかったことだと思う。
しかしながら。
モノはいいかげん行き渡り、
工業社会からサービス業社会へと移行し、
「付加価値を最大化する」ことが求められ、
そのためには、「自ら考え、行動すること」が
何よりも必要だと言われる世の中になっているのだから、
人生のできるだけ早く、
この「消費者マインド」を脱し、
「価値を生み出す主体」となることを経験していくことが必要になるだろう。
大学時代は、そのラストチャンスなのだと思う。
3日に集まった「起業家留学」の卒業生たちは、
みな口々に「当事者意識」、「起業家精神」、「振り返りの重要性」
を語った。
あらためて思う。
大学時代の宿題は、消費者マインドから卒業することだ。
「何のために?」と問うだけで行動しないのではなく、
とりあえず面白そうだから、成長できそうだからやってみよう、
とチャレンジを始めることだ。
その後、チャレンジを振り返ることだ。
何を学んだのか?と問い直すことだ。
その繰り返しが消費による自己表現ではなく、
価値を生み出す主体となることによって自己表現する人となる近道だ。
可能なら、小学生・中学生・高校生のうちに
段階的にそのようなプログラムを商店街あたりで
やれたら素晴らしいのだが、
まずは大学生にそのような機会を提供していくことが
ヒーローズファームの使命なのだと感じた。
ヒーローとは、「価値を生み出す主体」のこと。
自ら考え、行動すること。
行動を振り返り、「何が価値だったか?」と問うこと。
この機会を地域社会で、あらゆる手法で提供することが必要だと
僕は信じています。
自動車運転免許+キャリア基礎力
「働き方研究所」
現在、大学生募集中です。
免許を持っていない人、
「消費者マインド」を脱ぎ去るチャンスです。


Posted by ニシダタクジ at 08:06│Comments(0)
│学び
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。










