2021年12月23日
感じて、楽しむ
趣味はなんですか?と聞かれたら
「各駅停車の中での3冊並行読書」かもしれません。
昨日の3冊は

くらしのアナキズム 松村圭一郎 ミシマ社
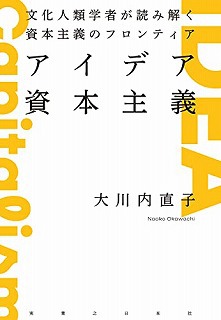
アイデア資本主義 大川内直子 実業之日本社

学校の役割ってなんだろう 中澤渉 ちくまプリマー新書
いい3冊を選びましたね。
本質的な問いを投げかけてくる3冊でした。
いちばんアツかったのは「くらしのアナキズム」の
~~~
21世紀のアナキストは政府の転覆を謀る必要はない。自助をかかげ、自粛にたよる政府のもとで、ぼくらは現にアナキストとして生きている。
~~~
ですかね。「国家」とは何か?という根源的な問いを突き付けられる。
そして「アイデア資本主義」からは「時間のフロンティア」という概念をもらいました。
これもすごかった。
かつて「未来」というのは存在しなかったのだ。
いわゆる狩猟採集の「その日暮らし」には未来は存在しない。
農業を始めてから初めて、1年単位で計算できるようになった。
そしてそれは人々の幸せのためではなく、支配者が効率的に支配するためだ。
そもそも「やりたいことは何か?」という問いは「自分」と「未来」という二重のフィクションを信じた者にだけ発することができる問いだ。その両方がフィクションに過ぎないのだとしたら。自分も未来も本当は存在しないとしたら、そんなことを考えてもいい気がする。
さらに、「学校の役割ってなんだろう」からは、そもそも「学校」なるものが何か?と
問いかけてくる。
~~~
近代に入り、効率性や合理性を追求して生まれた組織を、社会学では官僚制組織とよびます。官僚制組織は合理的に構成されていて、組織目標を達成するために各部署で役割分担をしているわけです。ですから行うべき職務は計画的に定められ、ルール化され、それを実行していかなければなりません。
~~~
なるほど。
「効率性」と「合理性」、これが近代であり、近代に発祥した「学校」もそれに倣っているよね。
そして、もうひとつ、機能している学校の教員の関係=協働関係のポイント5つ。
1 自発性に委ねられている
2 行われている実戦に強制性や義務性がない
3 実践が発展志向である
4 同僚間でのコミュニケーションに制限を設けない
5 実践の成果はいつどのように出るかは明らかではないという不透明性があり、そのことを教員たちも理解している
これ「マイプロ」とかでも同じですよね。
つまり、学び続ける教員っていうのと。
これら3つの本から、「これから」が見えてくるような気がする。
先日、オンライン対話でもらったキーワードは「人はみな違っているということ。一方で人はみな同じであるということ」だった。
たぶんこれが対話する意味なのだろうし、創造力の源であると同時に、安心感なのだろう。
それをもっとも簡単に体感できるのは、異文化コミュニケーションであるという。
「国際交流」とはそのためにあるのだ、と。
たぶん、それだ。いちばん大切なこと。同じであることを強制されないこと。
違いこそが価値だ、とまでは言い切らないけど、創造のタネになる。
20日に発表会をしたえぽっく「取材インターンひきだし」の時のハイライト
「違和感の表明」に近い。
きっと言葉にすれば
対ヒトとしては、「違い」を感じて、楽しむこと
対自然としては、「季節」を感じて、楽しむこと
対社会としては、「場」を感じて、楽しむこと
そうやって、人は、自分の「存在」を感じて、楽しむことができるのかもしれない。
そういう「体感」が必要なんだ。

宮沢賢治先生がなぜ、教師を辞め、羅須地人協会をつくり、自ら畑に立ったのか。
「存在」のために、そういう「体感」が必要だったんじゃないか。
おお朋だちよ いっしょに正しい力を併せ
われらのすべての田園とわれらのすべての生活を
一つの巨きな第四次元の芸術に創りあげようでないか
まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう
われらの前途は輝きながら嶮峻である
嶮峻のその度ごとに四次芸術は巨大と深さとを加へる
詩人は苦痛をも享楽する
永久の未完成これ完成である
(農民芸術概論綱要より)
賢治先生の「第四次元の芸術」という問いに、僕たちはまだ応えられていない。
農民芸術概論綱要が書かれた1926年からもうすぐ100年が経つ。
その問いを果たしに、またここから始めようと思う。
「各駅停車の中での3冊並行読書」かもしれません。
昨日の3冊は

くらしのアナキズム 松村圭一郎 ミシマ社
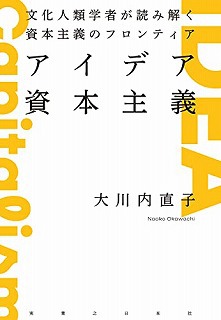
アイデア資本主義 大川内直子 実業之日本社

学校の役割ってなんだろう 中澤渉 ちくまプリマー新書
いい3冊を選びましたね。
本質的な問いを投げかけてくる3冊でした。
いちばんアツかったのは「くらしのアナキズム」の
~~~
21世紀のアナキストは政府の転覆を謀る必要はない。自助をかかげ、自粛にたよる政府のもとで、ぼくらは現にアナキストとして生きている。
~~~
ですかね。「国家」とは何か?という根源的な問いを突き付けられる。
そして「アイデア資本主義」からは「時間のフロンティア」という概念をもらいました。
これもすごかった。
かつて「未来」というのは存在しなかったのだ。
いわゆる狩猟採集の「その日暮らし」には未来は存在しない。
農業を始めてから初めて、1年単位で計算できるようになった。
そしてそれは人々の幸せのためではなく、支配者が効率的に支配するためだ。
そもそも「やりたいことは何か?」という問いは「自分」と「未来」という二重のフィクションを信じた者にだけ発することができる問いだ。その両方がフィクションに過ぎないのだとしたら。自分も未来も本当は存在しないとしたら、そんなことを考えてもいい気がする。
さらに、「学校の役割ってなんだろう」からは、そもそも「学校」なるものが何か?と
問いかけてくる。
~~~
近代に入り、効率性や合理性を追求して生まれた組織を、社会学では官僚制組織とよびます。官僚制組織は合理的に構成されていて、組織目標を達成するために各部署で役割分担をしているわけです。ですから行うべき職務は計画的に定められ、ルール化され、それを実行していかなければなりません。
~~~
なるほど。
「効率性」と「合理性」、これが近代であり、近代に発祥した「学校」もそれに倣っているよね。
そして、もうひとつ、機能している学校の教員の関係=協働関係のポイント5つ。
1 自発性に委ねられている
2 行われている実戦に強制性や義務性がない
3 実践が発展志向である
4 同僚間でのコミュニケーションに制限を設けない
5 実践の成果はいつどのように出るかは明らかではないという不透明性があり、そのことを教員たちも理解している
これ「マイプロ」とかでも同じですよね。
つまり、学び続ける教員っていうのと。
これら3つの本から、「これから」が見えてくるような気がする。
先日、オンライン対話でもらったキーワードは「人はみな違っているということ。一方で人はみな同じであるということ」だった。
たぶんこれが対話する意味なのだろうし、創造力の源であると同時に、安心感なのだろう。
それをもっとも簡単に体感できるのは、異文化コミュニケーションであるという。
「国際交流」とはそのためにあるのだ、と。
たぶん、それだ。いちばん大切なこと。同じであることを強制されないこと。
違いこそが価値だ、とまでは言い切らないけど、創造のタネになる。
20日に発表会をしたえぽっく「取材インターンひきだし」の時のハイライト
「違和感の表明」に近い。
きっと言葉にすれば
対ヒトとしては、「違い」を感じて、楽しむこと
対自然としては、「季節」を感じて、楽しむこと
対社会としては、「場」を感じて、楽しむこと
そうやって、人は、自分の「存在」を感じて、楽しむことができるのかもしれない。
そういう「体感」が必要なんだ。

宮沢賢治先生がなぜ、教師を辞め、羅須地人協会をつくり、自ら畑に立ったのか。
「存在」のために、そういう「体感」が必要だったんじゃないか。
おお朋だちよ いっしょに正しい力を併せ
われらのすべての田園とわれらのすべての生活を
一つの巨きな第四次元の芸術に創りあげようでないか
まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう
われらの前途は輝きながら嶮峻である
嶮峻のその度ごとに四次芸術は巨大と深さとを加へる
詩人は苦痛をも享楽する
永久の未完成これ完成である
(農民芸術概論綱要より)
賢治先生の「第四次元の芸術」という問いに、僕たちはまだ応えられていない。
農民芸術概論綱要が書かれた1926年からもうすぐ100年が経つ。
その問いを果たしに、またここから始めようと思う。




