2020年10月17日
ウチに天才はいない。だがウチが最強だ。
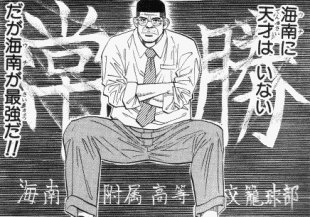
「海南(ウチ)に天才はいない。だが海南(ウチ)が最強だ」
スラムダンク、高頭監督の名台詞を思い出した、
第4回の探究学習コミュニティの勉強会。
講師は、福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校の
学校支援統括コーディネーターの長谷川勇紀さん。
もう、絶句するくらい、すごかったなあ。
何度もお話は聞いているのだけど、
いま探究学習やマイプロジェクトを設計する状況になると
ふたば未来の実践のすごさがよく分かる。
そもそもマイプロって何?からスタート
~~~ここから勉強会メモ
岩手県大槌町の高校生が東日本大震災で被災した町で何かしたいという思いを
NPOカタリバがマイプロジェクトという手法を通じて2012年から始まった放課後活動
「高校生の被災したまちへの想い」×「マイプロジェクト」手法(SFC井上研究室2006年~)×カタリバ「コラボスクール大槌臨学舎」
=復興木碑プロジェクト、笑顔photoプロジェクト
マイプロジェクトの考え方:
高校生自らが「やりたい」と思えるテーマを設定し、リアルな社会と接する実践を繰り返すことで、
高校生が意欲と創造性を育む学びを得る。
「主体的な問い」×「実社会での実践」×「意欲と創造性を育む学び」
マイプロジェクトでの学び:
参画度の高いテーマで「主体性」を育み、実践の中で「協働性」を発揮し、それらを繰り返す中での問いの更新を通して「探究性」を養うことを重視する。
主体性(参画のはしご)・・・ロジャー・ハート:
参画の段階のより上段を目指すために、主体性を持てるテーマを発見する。課題と自分の繋がりが強ければ強いほど、取り組みは真剣になり、学びが深くなる。
協働性:
調べて終わりにせず、課題解決に向けた実践を行うことで、実社会における他者との協働を経験する。
探究性:
主体的な問い⇔実践
実践を繰り返す中で、問いを更新する。途中で問いが変わることを厭わない。
マイプロジェクトの進め方
1 プランニング・・・プロジェクトをつくる
自分を知る(興味関心・価値観を知る)、課題の設定、情報の収集、整理・分析
2 アクション・・・プロジェクトを実行する
行動(実践を試みる)
3 リフレクション・・・プロジェクトを振り返る
まとめ、考えの更新(振り返り)
「自分の関心をベースにプロジェクトを作る」⇒「実践と振り返りを繰り返し、学びを深める」
2012~2014年度:プログラム開発期
岩手県大槌町で高校生マイプロジェクト誕生
プランニング合宿を開催
2015~2017年度:放課後展開期
東北初のプランニング合宿
2018~2020年度:総探融合期
高校でマイプロ型の探究学習の実践が始まる
~~~
総合的な探究の時間とマイプロジェクトの共通点
従来の総合的な学習の時間では、「課題」と「自己」は別々であった。
自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見解決していく
総合的な探究の時間は、マイプロジェクトの考え方と一致している。
主体性と実践を重視するとは?
・学びが大きい分、従来よりコストがかかる
・その覚悟と実践での工夫が必要
主体的⇔受動的 仮説検証・実践(アクション)⇔仮説提案
2017:大船渡高校船野さんのマイプロ
ふるさとの水にチャレンジの衝撃
主体的な問い⇔実践の繰り返しによって問いの更新が起こっていた。
年間の授業の流れモデル
1 自分を見つめよう
2 北極星を見つけよう
3 問いを出そう⇒調査してみよう⇒結果を整理・分析しよう(夏休み)
4 調査結果を発表してみよう
5 北極星に向けたアクションを決めよう⇒アクションしてみよう⇒振り返ろう(8~2月)
6 学びを発表してみよう
プロジェクト事例
テーマ設定の理由
課題の発見(夏季アクション)
具体的な課題と解決方法(仮説提示)
解決アクション
活動からの学び
高校3年間を通した総合的な探究の時間
地域をフィールドに、地域の課題を題材に、その解決の過程を通して、汎用的なスキルを身につけたり、自分自身の生き方あり方に繋げていく、地域課題解決型プロジェクト学習
1年次:複雑な地域課題を多面的に理解する(ふるさと創造学 2単位)
2年次:地域課題解決の探究と実践(未来創造探究 3単位)
3年次:探究成果発表と自らの進路実現
探究のプロセスに対応した「生徒の学びの姿勢」
テーマの設定⇒調査のための実践⇒振り返り⇒解決のための実践⇒発表⇒振り返り
学びの準備
⇒「守」:受容的な姿勢(問題状況の把握と課題設定、現状や事実を正確に知る)
⇒「破」:生成的な姿勢(現状を他の事例や考え方と繋げる、課題解決の仮説を立て、プロジェクトを実践する)
⇒「離」:持続的にプロジェクトに取り組む姿勢(プロジェクトの実践を振り返りフィードバックをかける、実践の課題から次なる独自の実践を創造する、実践の連鎖)
生徒の学びの姿勢と教員の関わり方
「学びの準備」⇔「モチベーター(探究心に火を灯す)
探究に対する学びの意欲を高める⇒意欲に火を灯すコミュニケーション、外部イベントへの参加
「守:受容的な姿勢」⇔インストラクター(現状を正しく捉えさせる)
正確に物事を知り探究の基礎を作る⇒知識のレクチャー、調査研究(書籍、WEB、インタビューなど)
「破:生成的な姿勢」⇔「ファシリテーター(問いを立てて引き出す)」
柔軟に他の問題と繋げたり想像力を働かせる⇒問いを通してテーマを深化させる、生徒自身が本当に取り組みたい実践を引き出す
「離:持続的に取り組む姿勢」⇔メンター(応援・勇気づけをする)
リスクを恐れずチャレンジし、実践を連鎖させる⇒実践への勇気づけ、実践後の振り返り(リフレクション)
この4つのパターンに生徒、プロジェクトの現状を把握する
意欲高め⇔低め(上下)
課題設定のセンス良⇔いまひとつ(右左)
で右上:メンター、左上:インストラクター、右下:ファシリテーター、左下:モチベーター
的なかかわりをする。
左下方向では、教材指定、グループで調べ学習、動画で発表や個別面談をして丁寧にテーマ設定をするが
右上方向ではアクションの計画サポートと振り返りに重点を置く
探究テーマを決める視点
地域・社会の理解を深める(地域・社会から解決を求められる課題(NEED)が明らかになる
自分について理解する(自分の取り組みたいこと(WILL)自分ができること(CAN)が見つかる
その真ん中に探究テーマをつくれるかどうか。
そのプロセスにおいての「ヒューマンライブラリー」(カタリバ型講義&対話)などの活用
成長をどう測るか?
半年に1度ルーブリックで資質・能力について自己評価する。
2期生アンケート
入社試験や入学試験に活用したか?→62%
社会とどう関わっていきたいかを見出すことに繋がったか→80%
自分の価値観を考えることに繋がったか?→87%
「探究学習」が進路選択やキャリア形成に影響を与える
「未来創造探究の全体像」
1 建学の精神・理念:新しい生き方・新しい社会の建設
2 教育目標:変革者たれ
3 資質・能力:自立・協働・創造
4 ルーブリック:知識・技能・人格・メタ認知
5 カリキュラム:未来創造探究・各教科学習
6 教員体制:企画研究開発部・6つのゼミ・教科チーム
7 各ゼミ計画:授業設計
8 教材:全体教材・各ゼミ教材
9 指導法:生徒への関わり方
10 外部活用:地域・講師・カタリバ・課外活動
「教員体制」
1 探究カリキュラム企画開発の校務分掌を設定
(教務部、進路指導部とも密に連携・協働)
2 教科担当横断の全教員体制で探究活動を指導
(毎週水曜日5・6限目に、1~3年生のそれぞれの授業が行われる)
3 教員間で悩みを共有し解決策を考えていく
(各学年で月1で全員参加会議を設定。生徒の伴走のあり方などを議論)
~~~ここまでメモ
圧倒された。
声が出ない。
すごすぎるわ、ふたば未来。
ポイントは、前日の浦崎先生の話でも出てきたけど
仮説・検証プロセスの楽しさをいつ知るか?というところ。
ふたば未来の場合は、1年生の夏休みの「調査」において
仮説検証プロセスを回しているということ。
まずはそういうような「探究プロセス」の面白さを知るということ
なのかもしれない。
質疑応答で、
探究的な学びの成功とはどこにあるのか?という問いかけがあり、
それに応える形で、
マイプロ2.0→船野さんの登場により、マイプロの評価基準に「探究性」が加わったこと
つまり、「実践による問いの更新」の重要性が加わったこと、
さらに言えば、マイプロ3.0は実際の「課題解決」なのだろうと。
しかし「課題解決」そのものを評価するのかどうか?は難しいところだと。
僕はそれを聞いて、
「北極星」とは、終わらない問いの方向性なのではないか?
その北極星に出会うことだ、と。
その北極星は、ミッションであり、ビジョンであり、好奇心の源であり、
そういう方向・方角のこと。
実践の中にある「違和感⇔問い」の積み重ねの中で、北極星は生まれてくる。
「北極星」に出会えたら、
あとは問いが無限に出てくる。終わらない問いの連鎖が起こる。
そうやって、問いの更新と自己変容、つまり自己の更新のサイクルが回る。
長谷川さんの言葉を借りれば、
マイプロはどこまでいってもキャリア学習で、
自分が自分であるために変容していくプロセスのことだと。
だから、いわゆる「マイ感」が必要なのだと。
ラストに、
「組織としてどうマイプロ・探究的学びを根付かせていくのか?」に対して、
「先生が全員関わる探究でないと、文化にはならない」と言っていた。
ふたば未来は、先生みんなでやってる、と。
長谷川さんはラストに言った。
「ふたば未来にはスゴイ先生いないじゃないですか。」
たしかにそうだ。
大船渡に梨子田先生あり、とか
飯野には梅北先生あり、とか
佐渡中等に宮崎先生あり、とか
じゃなくて、組織全体でやっているんだと。
だから「文化」になっていくんだ、って。
かっけー。
かっけーなと。
組織のチカラ、そして、地域を含めた場のチカラが探究的学びをつくっているんだ。
もちろん、ふたば未来の実践メソッドというか仕組みは、ものすごかったし、
真似できるところがたくさんあるなと思った。
でも、ふたば未来が本当にすごいのは、「学びの環境(場)」に働きかけている、ということ。
「文化」を作り始めている、ということ。
わが町でも必要なのは、きっとそういう実践なのだろうなと。
コーディネーターってそういうことか、と思った。
僕も数年後に言ってみたい。
「ウチにはスゴイ先生もスゴイ地域の人もスゴイ生徒もいない。だがウチが最強だ」と。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |









