2020年05月14日
杉林を育てるのではなく、雑木林を見守る。
5月13日付新潟日報の
県央・下越版に「オンライン黎明学舎」の様子が掲載されました。

そして昨日午後は、阿賀黎明探究パートナーズのオンライン勉強会で
先生方とパートナーズの皆さんがオンライン上ですが、顔合わせました。
「話をする時間がもっと欲しい」との声が多数あり、
来週からは事前に資料を見てもらう「反転授業」パターンを検討します。

そして今朝、月刊先端教育のオンライン教育特集を読みました。
日本教育工学会が3月31日に発表した
「学校と家庭をつなぐオンライン学習実践ガイド」。
https://www.jset.gr.jp/sig/pre_online_learning_guide_sig04.pdf
まず同期型(リアルタイムでつなぐ)と
非同期型(時間を合わせずに学校と家庭のあいだでやりとりする)
の2つに分けた上で、オンライン教育の4つの方法を示す。
1 リアルタイム授業配信
会議ツール等を使ったネットでの授業実施
2 録画授業動画の配信
授業の講義場面を録画したビデオを、学習者が各自で視聴して学習する
3 ドリル形式アプリ
学習に使えるドリル形式のアプリを活用したオンライン学習
4 オンラインでの共同制作
学習者たちが一緒に何かをつくる共同制作をオンラインで実施する
なるほど。
ほかにも、たくさんの実践例などからのメモを以下に。
~~~ここからメモ
オンライン教育の最大の魅力は、自分に合った「師匠」と出会うチャンスが世界に広がることです。
同じ形ではなく、同じ価値を追求すること。
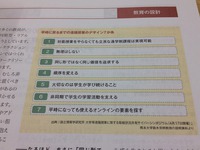
オンラインは自律性を身に付けるチャンス
壇上の賢者から寄り添う案内人へ
最大の課題はモチベーション維持。
録画版に向いているのは、英文法などのインプットが多い知識伝達型の授業です。
質問がリアルタイムでできる双方向型でなければできない授業は何か?という問い。
「ちゃんとやる」っていうことに対するハードルが下がっている。
大学であれば、聞いているほうがフォローすることもできる。
ICTが持つ3つの機能
1 個別で学ぶこと(Adaptive)
2 気付きの機会があること(assistive)
3 協働すること(Active)
多くの人は、「学習指導要領が変われば、教育が変わる」と思っていますが、それは大きな間違いです。現場の授業を実施質的に規定しているのは学習指導要領ではなく、アナログ環境下で構築された各教科の教科教育の指導法なのです。
子どもたちは毎日、ランドセルを背負って、「過去」にタイムスリップしているようなものです。
料理をしてみるという最小単位のPBL。確かに、料理って小さな、でも壮大な、自由度の高い、プロジェクトだなあ。
~~~ここまでメモ
思ったことは、
「何を学ぶか?」から「どのように学ぶか?」
そして「誰と、いつ、どこで学ぶか?」が大切になってくるということ。
そして、その前に「なぜ学ぶか?」と「誰のために学ぶか?」を考えるとき。
場のチカラとか、プロジェクトとかの話だなあと。
プロジェクトベースドラーニングってそういうことかもしれない。
さらに、特別企画「GIGAスクール構想の実現と教育改革」のページでの一言
「新しい学びの場における教師の役割は、いわば雑木林の成長を見守る里山の住人です。今までの教育は、一律に整えられた綺麗な杉林を作ることでしたが、これからの学びの集団は雑木林であるべきです。雑木林といっても、荒れた林ではありません。一つひとつの木の状態を見て手入れをするように、全体を見守りながらも一人ひとりの個性を伸ばしていくのです。個性は他者とぶつかり合うことで磨かれていきます。子どもたち同士の関わり合い、そして教師との関わり合いという豊かな関係性を構築していくことが大切です。」
いやあ、これですね。これからの森づくり。
「学びの土壌」の上にある、「学びの生態系」って
そういうところにあるのかもしれませんね。
かつて、杉林を育てる理由があった。
しかし、社会や時代のほうが変わってしまい、
杉をつくっても売れなくなってしまった。
いまや、森の中で自分の木を育て、それを自分自身で売り込まないといけない。
そしてそれは、木単体で売るのではなくて、ほかの木や生き物との組み合わせで売る、
あるいは、森を観光資源にした観光ビジネスや生き物を教育コンテンツにした教育ビジネスを売っていかないといけないのだ。
学びの雑木林づくり。
先生はその見守り人(ファシリテーター)に。
地域の人は、雑木の中の1つや動物に、
あるいは太陽や風という役割を担っていくことかもしれない。
県央・下越版に「オンライン黎明学舎」の様子が掲載されました。

そして昨日午後は、阿賀黎明探究パートナーズのオンライン勉強会で
先生方とパートナーズの皆さんがオンライン上ですが、顔合わせました。
「話をする時間がもっと欲しい」との声が多数あり、
来週からは事前に資料を見てもらう「反転授業」パターンを検討します。

そして今朝、月刊先端教育のオンライン教育特集を読みました。
日本教育工学会が3月31日に発表した
「学校と家庭をつなぐオンライン学習実践ガイド」。
https://www.jset.gr.jp/sig/pre_online_learning_guide_sig04.pdf
まず同期型(リアルタイムでつなぐ)と
非同期型(時間を合わせずに学校と家庭のあいだでやりとりする)
の2つに分けた上で、オンライン教育の4つの方法を示す。
1 リアルタイム授業配信
会議ツール等を使ったネットでの授業実施
2 録画授業動画の配信
授業の講義場面を録画したビデオを、学習者が各自で視聴して学習する
3 ドリル形式アプリ
学習に使えるドリル形式のアプリを活用したオンライン学習
4 オンラインでの共同制作
学習者たちが一緒に何かをつくる共同制作をオンラインで実施する
なるほど。
ほかにも、たくさんの実践例などからのメモを以下に。
~~~ここからメモ
オンライン教育の最大の魅力は、自分に合った「師匠」と出会うチャンスが世界に広がることです。
同じ形ではなく、同じ価値を追求すること。
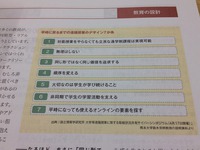
オンラインは自律性を身に付けるチャンス
壇上の賢者から寄り添う案内人へ
最大の課題はモチベーション維持。
録画版に向いているのは、英文法などのインプットが多い知識伝達型の授業です。
質問がリアルタイムでできる双方向型でなければできない授業は何か?という問い。
「ちゃんとやる」っていうことに対するハードルが下がっている。
大学であれば、聞いているほうがフォローすることもできる。
ICTが持つ3つの機能
1 個別で学ぶこと(Adaptive)
2 気付きの機会があること(assistive)
3 協働すること(Active)
多くの人は、「学習指導要領が変われば、教育が変わる」と思っていますが、それは大きな間違いです。現場の授業を実施質的に規定しているのは学習指導要領ではなく、アナログ環境下で構築された各教科の教科教育の指導法なのです。
子どもたちは毎日、ランドセルを背負って、「過去」にタイムスリップしているようなものです。
料理をしてみるという最小単位のPBL。確かに、料理って小さな、でも壮大な、自由度の高い、プロジェクトだなあ。
~~~ここまでメモ
思ったことは、
「何を学ぶか?」から「どのように学ぶか?」
そして「誰と、いつ、どこで学ぶか?」が大切になってくるということ。
そして、その前に「なぜ学ぶか?」と「誰のために学ぶか?」を考えるとき。
場のチカラとか、プロジェクトとかの話だなあと。
プロジェクトベースドラーニングってそういうことかもしれない。
さらに、特別企画「GIGAスクール構想の実現と教育改革」のページでの一言
「新しい学びの場における教師の役割は、いわば雑木林の成長を見守る里山の住人です。今までの教育は、一律に整えられた綺麗な杉林を作ることでしたが、これからの学びの集団は雑木林であるべきです。雑木林といっても、荒れた林ではありません。一つひとつの木の状態を見て手入れをするように、全体を見守りながらも一人ひとりの個性を伸ばしていくのです。個性は他者とぶつかり合うことで磨かれていきます。子どもたち同士の関わり合い、そして教師との関わり合いという豊かな関係性を構築していくことが大切です。」
いやあ、これですね。これからの森づくり。
「学びの土壌」の上にある、「学びの生態系」って
そういうところにあるのかもしれませんね。
かつて、杉林を育てる理由があった。
しかし、社会や時代のほうが変わってしまい、
杉をつくっても売れなくなってしまった。
いまや、森の中で自分の木を育て、それを自分自身で売り込まないといけない。
そしてそれは、木単体で売るのではなくて、ほかの木や生き物との組み合わせで売る、
あるいは、森を観光資源にした観光ビジネスや生き物を教育コンテンツにした教育ビジネスを売っていかないといけないのだ。
学びの雑木林づくり。
先生はその見守り人(ファシリテーター)に。
地域の人は、雑木の中の1つや動物に、
あるいは太陽や風という役割を担っていくことかもしれない。




