2015年04月23日
学びの場のデザイン
「学びたい」と思うのは、
人間の根源的欲求である。
と僕は思っている。
他の動物と比較して、
巨大な頭脳の持ってしまったヒトという種は、
「学ばなければ生きられない」
宿命を負っているといってもいいのかもしれない。
大学時代に、
「いかに楽をして単位を取得するか?」
という思考を持った人は多いだろう。
先輩に単位を取りやすい授業を聞いたり、
誰かに代返(代わりに返事をすること)を頼んだり、
テスト前にノートをコピーさせてもらったり。
「要領よく単位を取る」ほうが
「毎日授業を一番前の席で聞いてノートをカリカリ取る」
よりもスマートなような気がしてしまう。
しかも、専門科目に直結していないような
文系であれば理科系科目とか
理系であれば歴史系科目とか、であればなおさらだ。
「ラクをして単位を取る」ことを
内田樹氏は、「教育がお買いものと同じになった」と言う。
※参考「大学時代の宿題は消費者マインドから卒業すること」
http://hero.niiblo.jp/e296335.html
消費者マインド。
それは、いかにコストをかけずに価値あるものを手に入れるか?
という価値観が重要視される。
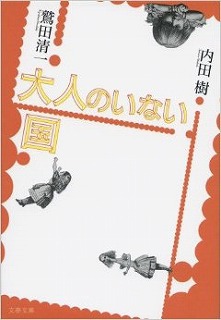
「大人のいない国」(内田樹 鷲田清一 文春文庫)
の中に、内田氏のこんな発言がある。
~~~ここから引用
消費によってしか自己表現ができないと信じているからこそこういうメンタリティが生まれるんです。
彼らやあらゆるものを「商品」としてとらえようとしますから、あらゆるものについて「費用対効果」を吟味する。
でも、このマインドは「学び」を動機づけることができない。
「学び」というのは、、
自分がこれから学ぶものの意味や価値がまだわからない。、
だから「学び」を通じて、自分が学んだことの意味と価値を事後的に知る、
という時間の順逆が逆転したかたちの営みだからです。
消費者マインドにはこれが理解できない。
自分がこれから買おうとする商品の価値や有用性を知らないで、
商品を買うという消費者は存在しませんから。
~~~ここまで引用
これが、消費者マインドの怖さだ。
「なんのためにこれを学ぶのか?」
「これを学んで自分にどんなメリットがあるのか?」
を先に考えるとすると、
大学生をたとえにすれば、大学入学時点の段階で、
「自分には有用である」か「有用ではないので単位だけ取れればいい」
という判断をしていることになる。
それはもはや、
「学ぶ人(=学生)」ではなく、「教育サーヴィスを買っている消費者」
となっていることを意味する。
「学びたい。」
その根源的欲求を、育めるような学びの場を
つくっていくことが大切だ。
そこには、
対象者が必要なのかもしれない。
対象地域が必要なのかもしれない。
自分のためではなく、誰かの笑顔が見たいから、学ぶ。
そんな学びのスタートを作ることで、
自分にとってのテーマが見つかるのかもしれない。
「本」や「地域」や「地域の大人」は
そんな学びのスタートのヒントをくれるのかをしれない。
そんな「学びの場」と「学びのきっかけ」をつくっていきたい。
人間の根源的欲求である。
と僕は思っている。
他の動物と比較して、
巨大な頭脳の持ってしまったヒトという種は、
「学ばなければ生きられない」
宿命を負っているといってもいいのかもしれない。
大学時代に、
「いかに楽をして単位を取得するか?」
という思考を持った人は多いだろう。
先輩に単位を取りやすい授業を聞いたり、
誰かに代返(代わりに返事をすること)を頼んだり、
テスト前にノートをコピーさせてもらったり。
「要領よく単位を取る」ほうが
「毎日授業を一番前の席で聞いてノートをカリカリ取る」
よりもスマートなような気がしてしまう。
しかも、専門科目に直結していないような
文系であれば理科系科目とか
理系であれば歴史系科目とか、であればなおさらだ。
「ラクをして単位を取る」ことを
内田樹氏は、「教育がお買いものと同じになった」と言う。
※参考「大学時代の宿題は消費者マインドから卒業すること」
http://hero.niiblo.jp/e296335.html
消費者マインド。
それは、いかにコストをかけずに価値あるものを手に入れるか?
という価値観が重要視される。
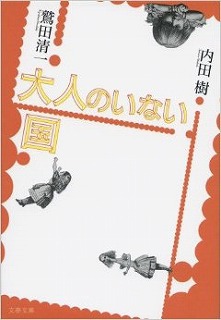
「大人のいない国」(内田樹 鷲田清一 文春文庫)
の中に、内田氏のこんな発言がある。
~~~ここから引用
消費によってしか自己表現ができないと信じているからこそこういうメンタリティが生まれるんです。
彼らやあらゆるものを「商品」としてとらえようとしますから、あらゆるものについて「費用対効果」を吟味する。
でも、このマインドは「学び」を動機づけることができない。
「学び」というのは、、
自分がこれから学ぶものの意味や価値がまだわからない。、
だから「学び」を通じて、自分が学んだことの意味と価値を事後的に知る、
という時間の順逆が逆転したかたちの営みだからです。
消費者マインドにはこれが理解できない。
自分がこれから買おうとする商品の価値や有用性を知らないで、
商品を買うという消費者は存在しませんから。
~~~ここまで引用
これが、消費者マインドの怖さだ。
「なんのためにこれを学ぶのか?」
「これを学んで自分にどんなメリットがあるのか?」
を先に考えるとすると、
大学生をたとえにすれば、大学入学時点の段階で、
「自分には有用である」か「有用ではないので単位だけ取れればいい」
という判断をしていることになる。
それはもはや、
「学ぶ人(=学生)」ではなく、「教育サーヴィスを買っている消費者」
となっていることを意味する。
「学びたい。」
その根源的欲求を、育めるような学びの場を
つくっていくことが大切だ。
そこには、
対象者が必要なのかもしれない。
対象地域が必要なのかもしれない。
自分のためではなく、誰かの笑顔が見たいから、学ぶ。
そんな学びのスタートを作ることで、
自分にとってのテーマが見つかるのかもしれない。
「本」や「地域」や「地域の大人」は
そんな学びのスタートのヒントをくれるのかをしれない。
そんな「学びの場」と「学びのきっかけ」をつくっていきたい。
Posted by ニシダタクジ at 07:44│Comments(0)
│日記
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |









