2019年11月01日
伽藍を捨ててバザールに向かえ
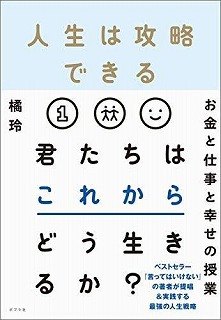
「人生は攻略できる~君たちはこれからどう生きるか?」(橘玲 ポプラ社)
橘さんの本の面白さは、いかにも自己啓発っぽいタイトルなのに、
本人はこの世から自己啓発書を消滅させたいと思っていること。
僕が最初にファンになったのは、
「残酷な世界を生き延びるたったひとつの方法」(幻冬舎文庫)を読んだとき。
http://hero.niiblo.jp/e485390.html
参考:政治空間と貨幣空間のあいだ(17.7.20)
これでもかっていうくらい、エビデンスをもとに、
あなたは変われない、「やればできる」なんて嘘だ
っていうのを説いてくる。もはや絶望しかない。
まあ、この本はラストにめちゃめちゃ救いがあるのだけどね。
それは読んでからのお楽しみ。
今回の「人生は攻略できる」は
中学生でも読めるように平易な文章で書かれている。
学校図書館に入れるべき1冊。
さて。
今回もエッセンスのメモを書き起こします。
~~~ここから引用
好きなことの見つけ方
1 キャラに合った自分らしい生き方をする
2 トライ&エラーを繰り返す
知性とビッグファイブ
「知性」「経験への開放性」「堅実性」「外向性」「同調性」「安定性」
「圧倒的な努力」ができるのは好きなことだけ。
「やればできる」ではなく「やってもできない」を前提として人生ゲームの攻略法を考えるべきだ。
最初から「好き」がわかっていて、夢に向かって一直線に進んでいける幸運なひとを除けば、「好きを仕事にする」方法はたぶんひとつしかない。それはトライ&エラーだ。その時に大事なのは「会社」ではなく「仕事」を選ぶことだ。
君が知らなくても、君のスピリチュアルは知っているから。
ジョブズが「探し続けてください」というのは、「天職」が見つかるまで何度も転職しろとか、「運命の相手」が見つかるまで恋人を取り替えろということではない。「スピリチュアルが拒絶するもので妥協するな」ということだ。
トライ&エラーをしていくうちに、君のスピリチュアルが「好きなこと」を(偶然に)見つけてくれる。そうなれば、あとはそれに全力投球するだけだ。
会社は社員が幸福になるためのただの道具だ。
大事なのは「きらきら」のキャリアをつくることではなく、相手が納得する魅力的な「物語」を持つことだ。
だったらなぜ、これほどまでみんなが不動産を所有したがるのか?いちばんの理由は、農耕社会では土地を所有していないと生き延びられなかったからだろう。
「土地を失うことは死ぬことだ」というルールで何千年もやっていると、「土地なんかなくてもなんの不都合もない」という新しい時代に対応できなくて、使い古しの神話にしがみついてしまうのだ。
ウマい話は、君のところにはぜったいこない。ほんとうにウマい話なら、自分で投資するに決まっているから。だから、ウマい話はすべて無視すればいいのだ。
~~~ここまで引用
リアルだ。
やっぱリアル。そして言語化能力がすごい。
その通りすぎる。
そして本書は、働くこと、働き方についての核心に迫っていく。
~~~ここから引用
働き方には大きく3つある。クリエイター、スペシャリスト、バックオフィスだ。
拡張可能な仕事と拡張できない仕事。
将来の夢や、やりたいことを職業名で答えさせるっていうのは、スペシャリストの養成っていうメッセージになっている、ってことかな。
それではクリエイターは生まれないのかも。
「共感力」が必要とされる仕事はロボットに置き換えられにくい。
仕事と会社が一体化しているのはバックオフィスだけだから。
それに対してスペシャリストは、自分の専門が職業だと思っている。
「伽藍」と「バザール」。
「バザール」の攻略戦略は、「失敗を恐れずに、ライバルに差をつけるような大胆なことに挑戦して、一発当てる」だ。
「伽藍」の攻略戦略は、「失敗するようなリスクを取らず、目立つことは一切しない」だ。
だから、伽藍を捨ててバザールに向かわないといけないし、スペシャリストを目指さないといけない。
シリコンバレーでは大失敗すると投資家から高く評価されて、より大きなチャンスがめぐってきたりする。なぜなら、能力のない人間には大きな失敗などできないから。
伽藍とバザールではゲームのルールが正反対なのだ。ネガティブゲームを抜け出し、ポジティブゲームに徹せよ。そういう風に言われないとさ、単に失敗を恐れずにチャレンジしろって言われてもチャレンジできないけど、バザールに向かうのだから新しいことやってみろって言われたほうが納得するよね。
~~~
働き方の3分類もうなったけど、
やっぱり一番は伽藍とバザールの話だ。
インターネットは伽藍の壁を破壊しつつある。
「伽藍(がらん)」とは、寺院にある門のように、外界と遮断する壁の内部のことだ。
かつて会社は、そして地方は、さらには地域社会は、伽藍の中にあった。
そこでのゲームのルールは、橘さんのいうように「ネガティブゲーム」だ。
「失敗をするようなリスクを取らず、目立つことは一切しないこと」
失敗すれば、不義理をすれば、そのネガティブな評判は一生ついてまわる。
その壁は、破壊されたのだ。
あるいは、破壊されつつあるのだ。
世界はバザールに向かっている。
バザールとはオープンな市場だ。
誰かが珍しい良いものを売れば、それが評判を生んで儲かっていく。
粗悪品は評判によって淘汰されていく。
よいものはよいフィードバックがなされ、評判資本が増える。
たぶん、そんな社会へと変化しつつあるんだ。
そんなときに、「高校」と「地域」っていう文脈では、何をすればいいのか?
バザールな社会を生きていくことになる高校生にとっての価値はいったい何なのか?
自ら題材に出会い、探究し、自分なりの価値を見つけていくこと。
それだろう。
「百姓3.0」は自ら価値を決められる人、そして価値を生み出せる人をつくるっていうコンセプトだ。
その価値に共感してくれる人が
世界という大きなバザールにいるのかもしれない。
そこに届けるための方法を考えること。
それを「探究」できる場。
昨日、友人と話していて、
「高校生」が「地域」で「探究」に対する、
高校生自身が感じる「違和感」について話をしていた。
で、タイムリーな10月30日のこれ。
https://news.yahoo.co.jp/byline/endotsukasa/20191030-00148864/
まちづくりは「クソダセェからやりたくない」とのこと
リアルだなあ、と。
「高校生」が「地域」で「探究」もこれに陥りやすいのではないかなあと。
「高校生」が「地域」で「探究」。
その時の題材は「地域課題」であることが多い。
あるいは地域課題をベースに「SDGs」まで考えちゃったりしてるかもしれない。
それ、つまんねーなって。
何がつまらないのか。
「ベクトル」が一緒なんだ。
「地域の課題解決」みたいなベクトルが。
しかも、それを一元化された価値で評価されてしまう。
(それが「ルーブリック」評価だとしても一元化されていることには変わらない)
わー、それつまんねえなって。
学校っていう「伽藍」の中で踊らされているのに関しては
これまでとなんら変わらないじゃないかと。
そんなときに出てきたコンセプト
(株)グランドレベルの田中さんの「補助線」の話
https://blog.kitchhike.com/makanai-interview-tanakamotoko/
素人力を引き出す「補助線」っていうキーワード。
そう、それ!
そこにあるのかもしれない。
大切なことは「地域の課題解決」なんかじゃなくて、高校生ひとりひとりのスピリチュアルが「これだよ!」って思える題材に出会えること。
課題解決は目的ではなく結果だし、単なる機会にすぎない。
それを「伴走」ではなく、「伴奏」するようなかかわり。
それが田中さんのいう補助線をひく、ということなのかもしれない。
高校生に伝えたいこと。
与えられても与えられていなくても「機会」の中で自らの「違和感」をキャッチし、
それを深めていく中で「これだ!」って思える題材に出会い、
好奇心を原動力に深めていくことによって、「価値」に出会うこと。
思えば、僕は、大学時代にそんな探究をしていた。
地球環境問題の深刻さにかかわらず、エコバックを持ちましょうなどという
小手先の対策しかしていない現実に大きな違和感があった。
個人が幸せになるってどういうことなのか?そんな問いがあった。
たまたま僕は「畑で野菜を育てる」っていうところに深く感動し、
それを手段に環境問題へアプローチしてみようと思った。
現在も毎週日曜日朝、畑作業のあと朝ごはんを食べる活動
「まきどき村」の始まりはそんな「探究」から始まっていた。
その場所は、僕にとって「ふるさと」になった。
いまでもそこに足を踏み入れるとホッとする。
バザールを生きていく高校生へ
地域課題をこちらで設定するのではなく、
「機会」をともに味わいながら、補助線を引き、
さまざまなベクトルに探究が始まっていくような、
そんな活動をしていくこと。
そんな現場を僕は見てみたい。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。









