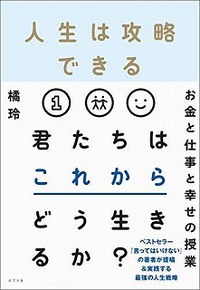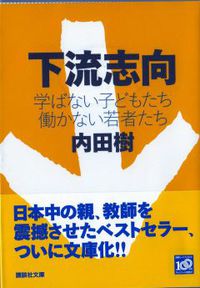2014年10月30日
本屋という機会提供装置
「教育の改善」とは、
目標を立てて、
手法を考え、
その達成度を測り、
手法を評価し、内容を改善する。
「目標」そして「評価」
と切り離せない関係にある。
これがあまりにも進むと、
学ぶ環境にとって、
あまりよくないことが起こる。
人文学部や美術科に
進学しようとすると、
「そんな学問を学んでも就職できない。」
という謎の指摘が生まれる。
たしかに、文学や美術が
現代経済社会において、
短期間のうちに評価される(=お金を生み出す)
ことはほとんどない。
しかし。そもそも。
大学進学は「学びたいことを学びたい」
からするのであって、
就職をにらんでするものでは決してないはずだ。
「機会を提供する」ことと「機会を得る」
ということに価値があると認識することがすごく大切だと思う。
クランボルツ博士の「計画された偶発性理論によれば、
「機会」の積み重ねによって、人は天職にたどり着くのだという。
だからこそ、本屋の出番だと思う。
本屋には
「機会」が詰まっている。
本との出会い、人との出会い。
それは偶然であり、貴重な機会である。
機会提供に徹していくということ。
それが、本屋に与えられた宿命なのだと思う。
目標を立てて、
手法を考え、
その達成度を測り、
手法を評価し、内容を改善する。
「目標」そして「評価」
と切り離せない関係にある。
これがあまりにも進むと、
学ぶ環境にとって、
あまりよくないことが起こる。
人文学部や美術科に
進学しようとすると、
「そんな学問を学んでも就職できない。」
という謎の指摘が生まれる。
たしかに、文学や美術が
現代経済社会において、
短期間のうちに評価される(=お金を生み出す)
ことはほとんどない。
しかし。そもそも。
大学進学は「学びたいことを学びたい」
からするのであって、
就職をにらんでするものでは決してないはずだ。
「機会を提供する」ことと「機会を得る」
ということに価値があると認識することがすごく大切だと思う。
クランボルツ博士の「計画された偶発性理論によれば、
「機会」の積み重ねによって、人は天職にたどり着くのだという。
だからこそ、本屋の出番だと思う。
本屋には
「機会」が詰まっている。
本との出会い、人との出会い。
それは偶然であり、貴重な機会である。
機会提供に徹していくということ。
それが、本屋に与えられた宿命なのだと思う。
Posted by ニシダタクジ at 07:42│Comments(0)
│思い
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。