2017年05月23日
「心を開く」をデザインする
http://hero.niiblo.jp/e484552.html
「心を開く」から始まる。
(17.4.20)
http://hero.niiblo.jp/e484560.html
本屋というプロセス・デザイン
(17.4.21)
のつづき。
結果論なのだけど、
僕がやってきたことは、
「心を開く」をデザインする。
だったのかもしれない、という仮説
そういう意味でのポートフォリオは
1 まきどき村の人生最高の朝ごはん。
1999年~現在。
毎週日曜日朝6時集合。
早すぎる。
まきどき村1年目の1999年8月1日。
神奈川県から来たお客さんに
竹炭焼きをするための竹割りをやってもらうため、
猛暑だったので朝7時集合したのが始まり。
あとは朝市が7時から近所でやっていたため、
そこの試食の漬物を食べるために、
そこでご飯を食べる、という活動が始まった。

現在でも
1 旧庄屋佐藤家に6時集合
2 畑作業
3 買い出し
4 朝食づくり
5 朝ごはん
でおおむね朝9時半には解散している。
ここのポイントは
・朝6時集合で化粧とかする暇がない。
・農作業とか囲炉裏の煙の匂いがつくので、いい服では来れない。
・農作業や朝食づくりなど、作業を共にするので、仲良くなる。
・一緒に食べる。
・地域のじいちゃんや歴史などがあって、話のネタがある。
うん。
こうやって書くと、なかなかできないデザインだなあと。
2 粟島での大学生向けプログラム
2012年~2014年
大学のプログラムや島開きの手伝い、カフェの工事など、
粟島で行った大学生向けのプログラム。

ここでのポイントは、なんといっても
1 船に乗り、離島に渡る
というところ。
ここには心を開くプロセスがあると思う。
そして人口300人の島、粟島では、
特にオフシーズンに行くと、村ですれ違う人がみな、話しかけてくる。
民宿に2泊しようものなら、
「今日はどうするんだ?」と聞かれて、
場合によっては車を貸してやる、って言われる。
民宿の代金にレンタカー代も入ってる。(笑)
そして2日目には
「ただいま~」と言って帰っていくのだろう。
自然、そして人。
本当の意味での「開放」がここにある。
「自分が好きになれない」
っていう悩みを抱える大学生や20代の人には
粟島に2泊することをおすすめしたい。
ご相談ください。
3 ツルハシブックス
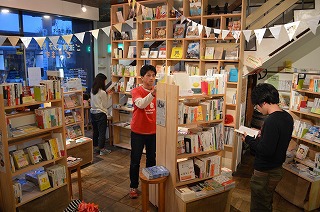
2011年~2016年:新潟市西区内野駅前にあった本屋
ツルハシブックスでは、
「偶然」を演出することによって、
「心を開く」を実現してきたのではないか。
1 入店した瞬間に「こんにちは」と声をかける。
2 店内の説明をする。
3 お菓子を食べてもらう。
お菓子を食べてもらう際に
「差し入れでもらったんですけど」
とすすめるのがポイントだ。
差し入れでもらったのだけど、
甘いものが苦手で食べきれない。
とか言うと、たいていの場合は食べてくれる。
あとは、
「差し入れの来る本屋さん」であるという
いいイメージが湧く。
そこで出会う「偶然」が、
次のアクションへの背中を押す。
4 暗やみ本屋ハックツ
もともとは「地下古本コーナーHAKKUTSU」という名前で、
新潟市のツルハシブックスにあったのだけど、
今は、東京練馬区・上石神井と、大阪旭区・千林で行っている。
10代限定の暗やみで行っている古本屋さん。

こちらも10代の若者にとっては、
・暗やみであることで非日常感がある。
・寄贈者のメッセージを感じ取ることが求められる。
・ハックツし終わった後に話ができる、または自分もスタッフになれる。
また、こちらは寄贈する大人にとっても、
・10代に本を贈る読書会では、自分の10代のころの
エピソードを語ることになり、自己開示が起こる。
5 大学生×若手社会人の紙芝居プレゼンによるコミュニケーション力講座

「カタリバ」をモデルにした大学生のキャリア教育モデル。
社会人が紙芝居をつくり、
それをもとに、学生とコミュニケーションする。
その後、学生自身が自分の紙芝居を作成、プレゼンする。
紙芝居というツールが、距離を縮め、心を開くことになる。
番外 ミーティングファシリテーション
・アイスブレイクで「最近会ったよかったこと」
終わるときに「今日の感想」をいう
を繰り返すことで、気持ちを出す練習をする。
フルネームで名前をいうことがポイント。出身もあったらよい
・カタルタ:予想外のことを言うことができるツール
・1度は休憩を入れる。休憩の際はトイレに行く。
心を開く。
オープンマインドをつくる。
そこから始まるのだろうな。
以上の活動をしてきて、なんとなく見えてきた、
若者の心を開く方法。
・船に乗って離島に渡る。
・一緒につくって食べる。
・「偶然」をプロデュースする。
そして何より、僕が大切だと思うのは、
・いい加減な大人に出会う。
ことなのではないかな、と思う。
多様な、っていうよりは、
「ああ、そんなんでいいんだ。」
っていう安心感を与えてくれるような大人に出会うこと。
そうやって、心が開いていく。
そういう意味でも、僕は、その仕事、
向いているような気がします。
新しい肩書き、できました。
「オープン・マインド・デザイナー」
のニシダタクジです。
いや、あやしい。
あやしすぎる。
ココロヒラキストとかにしときますか。笑。
「心を開く」から始まる。
(17.4.20)
http://hero.niiblo.jp/e484560.html
本屋というプロセス・デザイン
(17.4.21)
のつづき。
結果論なのだけど、
僕がやってきたことは、
「心を開く」をデザインする。
だったのかもしれない、という仮説
そういう意味でのポートフォリオは
1 まきどき村の人生最高の朝ごはん。
1999年~現在。
毎週日曜日朝6時集合。
早すぎる。
まきどき村1年目の1999年8月1日。
神奈川県から来たお客さんに
竹炭焼きをするための竹割りをやってもらうため、
猛暑だったので朝7時集合したのが始まり。
あとは朝市が7時から近所でやっていたため、
そこの試食の漬物を食べるために、
そこでご飯を食べる、という活動が始まった。

現在でも
1 旧庄屋佐藤家に6時集合
2 畑作業
3 買い出し
4 朝食づくり
5 朝ごはん
でおおむね朝9時半には解散している。
ここのポイントは
・朝6時集合で化粧とかする暇がない。
・農作業とか囲炉裏の煙の匂いがつくので、いい服では来れない。
・農作業や朝食づくりなど、作業を共にするので、仲良くなる。
・一緒に食べる。
・地域のじいちゃんや歴史などがあって、話のネタがある。
うん。
こうやって書くと、なかなかできないデザインだなあと。
2 粟島での大学生向けプログラム
2012年~2014年
大学のプログラムや島開きの手伝い、カフェの工事など、
粟島で行った大学生向けのプログラム。

ここでのポイントは、なんといっても
1 船に乗り、離島に渡る
というところ。
ここには心を開くプロセスがあると思う。
そして人口300人の島、粟島では、
特にオフシーズンに行くと、村ですれ違う人がみな、話しかけてくる。
民宿に2泊しようものなら、
「今日はどうするんだ?」と聞かれて、
場合によっては車を貸してやる、って言われる。
民宿の代金にレンタカー代も入ってる。(笑)
そして2日目には
「ただいま~」と言って帰っていくのだろう。
自然、そして人。
本当の意味での「開放」がここにある。
「自分が好きになれない」
っていう悩みを抱える大学生や20代の人には
粟島に2泊することをおすすめしたい。
ご相談ください。
3 ツルハシブックス
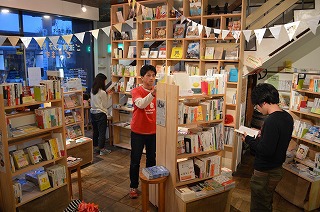
2011年~2016年:新潟市西区内野駅前にあった本屋
ツルハシブックスでは、
「偶然」を演出することによって、
「心を開く」を実現してきたのではないか。
1 入店した瞬間に「こんにちは」と声をかける。
2 店内の説明をする。
3 お菓子を食べてもらう。
お菓子を食べてもらう際に
「差し入れでもらったんですけど」
とすすめるのがポイントだ。
差し入れでもらったのだけど、
甘いものが苦手で食べきれない。
とか言うと、たいていの場合は食べてくれる。
あとは、
「差し入れの来る本屋さん」であるという
いいイメージが湧く。
そこで出会う「偶然」が、
次のアクションへの背中を押す。
4 暗やみ本屋ハックツ
もともとは「地下古本コーナーHAKKUTSU」という名前で、
新潟市のツルハシブックスにあったのだけど、
今は、東京練馬区・上石神井と、大阪旭区・千林で行っている。
10代限定の暗やみで行っている古本屋さん。

こちらも10代の若者にとっては、
・暗やみであることで非日常感がある。
・寄贈者のメッセージを感じ取ることが求められる。
・ハックツし終わった後に話ができる、または自分もスタッフになれる。
また、こちらは寄贈する大人にとっても、
・10代に本を贈る読書会では、自分の10代のころの
エピソードを語ることになり、自己開示が起こる。
5 大学生×若手社会人の紙芝居プレゼンによるコミュニケーション力講座

「カタリバ」をモデルにした大学生のキャリア教育モデル。
社会人が紙芝居をつくり、
それをもとに、学生とコミュニケーションする。
その後、学生自身が自分の紙芝居を作成、プレゼンする。
紙芝居というツールが、距離を縮め、心を開くことになる。
番外 ミーティングファシリテーション
・アイスブレイクで「最近会ったよかったこと」
終わるときに「今日の感想」をいう
を繰り返すことで、気持ちを出す練習をする。
フルネームで名前をいうことがポイント。出身もあったらよい
・カタルタ:予想外のことを言うことができるツール
・1度は休憩を入れる。休憩の際はトイレに行く。
心を開く。
オープンマインドをつくる。
そこから始まるのだろうな。
以上の活動をしてきて、なんとなく見えてきた、
若者の心を開く方法。
・船に乗って離島に渡る。
・一緒につくって食べる。
・「偶然」をプロデュースする。
そして何より、僕が大切だと思うのは、
・いい加減な大人に出会う。
ことなのではないかな、と思う。
多様な、っていうよりは、
「ああ、そんなんでいいんだ。」
っていう安心感を与えてくれるような大人に出会うこと。
そうやって、心が開いていく。
そういう意味でも、僕は、その仕事、
向いているような気がします。
新しい肩書き、できました。
「オープン・マインド・デザイナー」
のニシダタクジです。
いや、あやしい。
あやしすぎる。
ココロヒラキストとかにしときますか。笑。
Posted by ニシダタクジ at 05:46│Comments(0)
│アイデア
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。










