2018年03月15日
これからの「地域メディア」をつくる
川崎市・武蔵新城駅前の「新城劇場」が
「shinjo gekijo」にリニューアル中。
地元産野菜を使ったクレープとジェラートの「Revegee」、
本屋の後をつぐ「よりみちブックス」、
大学生4人で立ち上げた「出会えるラジオ、まるラジ」
の3つが1つの建物を分け合うようになる。
(6月オープン予定で進行中)
そんな中で、
まるラジがクラウドファンディングに挑戦中。
https://camp-fire.jp/updates/view/48907
未来に悩む若者のために、フリーペーパー『まるラジおとな図鑑』を作りたい!
たぶん、この場所が
これからの地域メディアの実験場になっていくのだろうと思う。
http://hero.niiblo.jp/e486304.html
メディアの力とは予言の自己実現能力のこと(17.11.17)
http://hero.niiblo.jp/e486326.html
本屋というメディアをつくる(17.11.20)
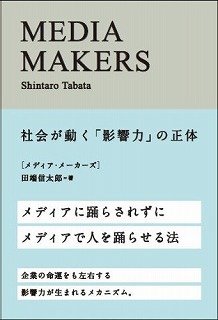
ふたたび、「MEDIA MAKERS」から引用するけど、
~~~以下引用
何かを伝えたい、という発信者の思いがあるときに、
それを伝達する「媒体・媒質」となるものこそが
語源本来の意味でのメディアの定義。
メディアとは、そこに情報の送り手と受け手の
二者が存在し、その間を仲介し、両者間において、
コミュニケーションを成立させることを目的とするものである。
Media型:送信者1 VS 受信者N ヤフーニュース等
Tool型:送信者N VS 受信者1 G-mail等
Community型:送信者N VS 受信者N フェイスブック等
メディアの影響力の本質
メディアで語られる=生きた証が記憶されるということ
メディアの価値「予言の自己実現能力」
これまでは、さまざまなビジネス上の
生態系をもとに産業の垣根ができていたわけですが、
クラウドのインフラ上では、あらゆる境界線が溶けてなくなりつつあります。
そんな状況では、メディア企業と事業会社や広告主の境界線も消滅しつつあります。
さらに、プロとアマチュアの境界線も、
例えば、大学と書店とコンサルティング会社とビジネス・カンファレンス業と、
専門出版社の境目すら消えつつあるわけです。
知識を売る、という意味では、大学も書店も、
コンサルティング会社も全てフラットに同一平面上に並ぶわけです。
そして、徹底的にアンバンドリングが進んだ後には、
これまでとは違ったメディア環境が広がり、
アンバンドルされたものがまた別の視点から
パッケージングされ、リワイヤリングされているのではないでしょうか?
その際の主役となるプレイヤーは誰でしょうか?
私の仮説では、それは個人です。
雑誌がオーケストラなら、メルマガはロックバンド。
~~~ここまで引用
そうそう。
境界線が溶けてなくなっている現在において、
主役となるプレイヤーは、「個人」であって、
その「個人」には大学生もなりうるということ。
「何かを伝えたい、という発信者の思いがあるときに、
それを伝達する「媒体・媒質」となるものこそが
語源本来の意味でのメディアの定義。
メディアとは、そこに情報の送り手と受け手の
二者が存在し、その間を仲介し、両者間において、
コミュニケーションを成立させることを目的とするものである。」
最近、新刊書店をやっぱりやりたいなあと思うのは、
メディアの力が予言の自己実現能力だとすれば、
新刊書店っていうのは、
まさにそういう場だし、
僕がヴィレッジヴァンガード郡山アティ店で感じたのは
まさにそれだった。
http://hero.niiblo.jp/e337058.html
「本屋という双方向メディアの可能性」(14.1.17)
大学生が地域メディアのプレイヤーになる。
たぶん、まるラジはそういう実験なのだろうと思います。
「shinjo gekijo」にリニューアル中。
地元産野菜を使ったクレープとジェラートの「Revegee」、
本屋の後をつぐ「よりみちブックス」、
大学生4人で立ち上げた「出会えるラジオ、まるラジ」
の3つが1つの建物を分け合うようになる。
(6月オープン予定で進行中)
そんな中で、
まるラジがクラウドファンディングに挑戦中。
https://camp-fire.jp/updates/view/48907
未来に悩む若者のために、フリーペーパー『まるラジおとな図鑑』を作りたい!
たぶん、この場所が
これからの地域メディアの実験場になっていくのだろうと思う。
http://hero.niiblo.jp/e486304.html
メディアの力とは予言の自己実現能力のこと(17.11.17)
http://hero.niiblo.jp/e486326.html
本屋というメディアをつくる(17.11.20)
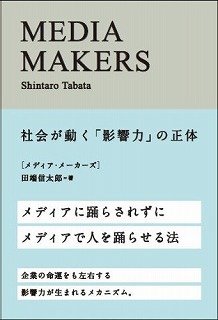
ふたたび、「MEDIA MAKERS」から引用するけど、
~~~以下引用
何かを伝えたい、という発信者の思いがあるときに、
それを伝達する「媒体・媒質」となるものこそが
語源本来の意味でのメディアの定義。
メディアとは、そこに情報の送り手と受け手の
二者が存在し、その間を仲介し、両者間において、
コミュニケーションを成立させることを目的とするものである。
Media型:送信者1 VS 受信者N ヤフーニュース等
Tool型:送信者N VS 受信者1 G-mail等
Community型:送信者N VS 受信者N フェイスブック等
メディアの影響力の本質
メディアで語られる=生きた証が記憶されるということ
メディアの価値「予言の自己実現能力」
これまでは、さまざまなビジネス上の
生態系をもとに産業の垣根ができていたわけですが、
クラウドのインフラ上では、あらゆる境界線が溶けてなくなりつつあります。
そんな状況では、メディア企業と事業会社や広告主の境界線も消滅しつつあります。
さらに、プロとアマチュアの境界線も、
例えば、大学と書店とコンサルティング会社とビジネス・カンファレンス業と、
専門出版社の境目すら消えつつあるわけです。
知識を売る、という意味では、大学も書店も、
コンサルティング会社も全てフラットに同一平面上に並ぶわけです。
そして、徹底的にアンバンドリングが進んだ後には、
これまでとは違ったメディア環境が広がり、
アンバンドルされたものがまた別の視点から
パッケージングされ、リワイヤリングされているのではないでしょうか?
その際の主役となるプレイヤーは誰でしょうか?
私の仮説では、それは個人です。
雑誌がオーケストラなら、メルマガはロックバンド。
~~~ここまで引用
そうそう。
境界線が溶けてなくなっている現在において、
主役となるプレイヤーは、「個人」であって、
その「個人」には大学生もなりうるということ。
「何かを伝えたい、という発信者の思いがあるときに、
それを伝達する「媒体・媒質」となるものこそが
語源本来の意味でのメディアの定義。
メディアとは、そこに情報の送り手と受け手の
二者が存在し、その間を仲介し、両者間において、
コミュニケーションを成立させることを目的とするものである。」
最近、新刊書店をやっぱりやりたいなあと思うのは、
メディアの力が予言の自己実現能力だとすれば、
新刊書店っていうのは、
まさにそういう場だし、
僕がヴィレッジヴァンガード郡山アティ店で感じたのは
まさにそれだった。
http://hero.niiblo.jp/e337058.html
「本屋という双方向メディアの可能性」(14.1.17)
大学生が地域メディアのプレイヤーになる。
たぶん、まるラジはそういう実験なのだろうと思います。




