2014年11月18日
書店は本を売っているから、ダメなのだ
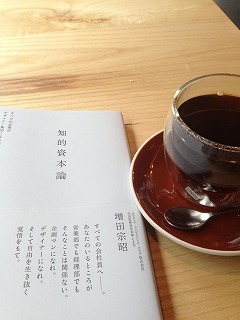
「知的資本論」(増田宗昭 CCCメディアハウス)
三たびこの本が登場。
いやあ、いいですね。
「僕たちはこれから何をつくっていくのだろう」以来の衝撃。
CCC(ツタヤ本部)のビジネスのやり方はともかく、
思想としてはめちゃめちゃ共感するなあと。
ということで、
おとといの続き。
~~~ここから一部引用
プラットフォームがあふれているサードステージに
おいては、人々は「提案」を求めている。
そして本や雑誌というのは、
その一冊一冊がまだに提案のカタマリとも
いうべき存在なのだ。
それが売れないというのは、売り方のほうに問題があるのではないか。
それを考えるうちに増田さんがたどり着いた答え
「書店は本を売っているからダメなのだ。」
顧客にとって価値があるのは、
本という物体ではなく、そこに盛り込まれている提案のほうなのだ。
そう、売るべきはその本に書かれている提案だ。
それなのに、そうした点に無自覚なまま、
本そのものを売ろうとするから、
書店の危機などといわれる事態を招いてしまっているのではなかろうか?
ジャンル分けされた書店の売り場は、
顧客のためを第一に考えて構成されたものではないのだ。
雑誌、単行本、文庫本などといった分類はあくまで流通側からのもの。
そうした分類をそのまま売り場に持ち込んでしまうのは、
顧客ニーズを顧みていないからだと思わずにはいられない。
CCCが運営する「代官山蔦屋書店」では、
「提案内容による分類で書店空間を再構築した」
旅、食・料理、デザイン・アートなど、
などでゾーニングされ、
単行本、文庫本、雑誌の枠を飛び越えて配置されている。
~~~ここまで一部引用。
「なーんだ、そんなことか。」と思われたかもしれない。
それは例えば、千駄木の「往来堂書店」で行われてきた
「文脈棚」のようなもの。
それを大規模にやっているのが代官山蔦屋書店だ。
後追いで、それをマネして、
書店員ではなく、コンシェルジュと呼ぶなどしているが、
実際はものすごい単純なことなのかもしれない。
しかしそれを徹底してやり、
圧倒的にお客さんの支持を得ている。
これは事実である。
そしてこれは、
書店、本屋だけの話ではまったくない。
すべての小売業が向き合うべきテーマである。
顧客は、「モノ」を必要としてない。
生活を豊かにする「提案」を必要としている。
その「提案」に心動かされたとき、
その「共感」は「モノを買う」という行為によって、
表現されるのだ。
これは本屋に限らず、
米屋もお菓子屋も魚屋も洋服屋も、
もっと言えば家電量販店も(CCCは家電業界に踏み込むらしい)
みんなが問うべき問いである。
自分たちはどんなライフスタイルを提案するのか?
そんな問いから小売店は出発しなければならない。
ツルハシブックス、まだまだですね。
ライバルは代官山蔦屋書店です。(笑)




